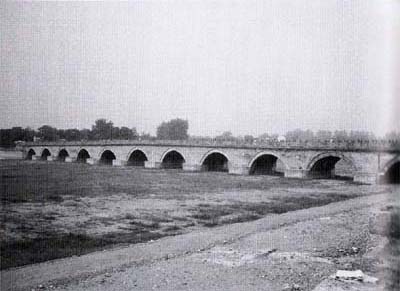|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章
|
六章 草泊(ツアボア)村のお宅で考えたこと
1 意味不明の金は不要 top
「先ほどはご苦労さまでした。
駅から港へと足を延ばしてもらったわけですが、あれから半世紀以上も過ぎていますよね。
もちろん様子も変わっていたとは思いますが……」
ホテルに戻って、会議室での劉さん父子を前にして、夜の部の懇談となった。夕食前のひとときである。
お茶の一杯から、私はおもむろに切り出したのだが、今度は現在とかかわることでの感想に、ピントをしぼりたかった。
「といいましても、少しハードではと気になるのですが、あのう、お疲れではないですか」
「いやいや……」
劉さんは、長い右手を振って、なんのなんのといった感じで笑った。
「畑仕事できたえてきたから、まだまだ大丈夫だ」
「北海道でも頑張り抜いたんですものね」 |

青島革命烈士記念館
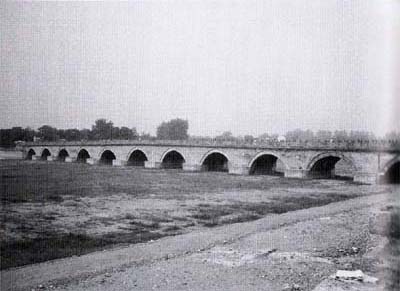
北京郊外盧溝橋
|
「全くだよ。しかし、やっぱり思い出すんだ。
昔のことを。駅も、港も。いろいろとこみ上げてくるものがある。
そうして、わしは日本に引っぱられていったちゅうのに、日本政府はまだそれを認めておらん。
ふふっ、こりゃ一体どういうことなんだ」
呆れたような苦笑だったが、その目はもう笑っていなかった。
「しかしだね」
と、続けていうことには、「わしは生きているかぎり、このことを代々伝えていく。
過去の歴史を認めない政府が、どうして日本人を代表できるのか、わしにはわからん。とても理解できないんだよ」
「そのことに関連してですけれど、岸信介という日本人を、ご存知ですね」
「キシ? そりゃ何者だね」
「劉さんが引っぱられた時の日本は、東條内閣の時代でして、岸信介はあの戦争を推進した閣僚の一人です。
いうなれば強制連行担当大臣だったわけですが、劉さんが発見された時には総理でした」
「ああ……」
と、うなずいて、にが虫をかみつぶしたような顔になり、
「それなら知っている。強制連行を否定したんだろ、国会で」
「ええ、どう思いますか」
「うむ、それで、忘れられないことがある。日本政府からということで、代理人がやってきた。
一〇万円を用意してな。わしは、何度も聞いたんだ。(語調激しく)その金は一体どこから出たのか。
キシちゅう総理からか、政府からか、とね。それにはかまわずに受取ってくれっていうんだな。
わしは断わった。いらん、と。意味不明の金なんだ」
「なるほど」
「それで、ことをうやむやにしようったって、そうはいかん!」
|

青島から草泊村の自宅へ向かうバスの中で説明する劉さん
2 戦争の傷は癒えず top
「我不要、と。ほかに、劉さん、何かおっしゃいましたか」
「あん時は、なにしろ、一三年間も苦労してきたばかりだったからな。 政府の言い逃れには、ハラの虫が治まらん。
わしはそんなことも口にしたと覚えてるが、うん、思い出すだにハラが立つ」
「日本のことわざにあります。ただより高いものはない、と。後になってから高いものにつくということです。
高くつくものを受取らずによかったと思います。
岸首相をはじめ、日本政府の態度には、まだハラの虫が治まらないってわけですね」 |

劉連仁さん親子。右が煥新さん
|
「そう、そう」
劉さんは、大きくうなずいて、きっとした表情のままで続けた。
「日本政府が何といおうと、わしはこうして生きておる。何よりの証明じゃないか、わしの存在が」
「はい……」
「それだけじゃない。事実関係もいろんな書類で残っている。ちゃあんとな。それも証拠になる。
何も好きでことを荒立てるんじゃなくて、あったことをあったというだけの話なんだ」
「これはね、ただ単に、親父個人の問題じゃないんですよ」
と、横から声をはさんだのは、煥新さんだった。
父親の様子をうかがいながら、身を乗出したのである。
「私たちの村では、九人が亡くなりました。小さな村ですがね。
つまり、強制連行されたままで、帰ってこなかったということ。
その人たちの子供が、相談にくるんですよ、私のところに。
本当に自分の親が亡くなったのかどうか、事実を知りたいとね。
直接に訪ねてきた人だけでも、二〇〇人以上もいるんですよ、これまでに」
「草泊村って、いうんですよね。人口はどのくらいですか」
「今でも六〇〇人ほどですから、当時はしれたものです」
「そのうち九人も? そんなにいるんですか」
私は、うーんと、嘆息せざるを得ない。戦争の傷は、決して癒(いや)されてはいないのだと思う。
戦争犯罪は、被害者にとっての終りはないということだろう。煥新さんは、しみじみとした感じで言葉をついだ。
「私は、おやじが連れ去られて、四〇日後に生まれました。
もの心つくにつれて、母親や祖父母が、いつもいつも嘆いているのを聞いてきましたよ。
私たちは何にも悪いことなんかしていない。
それなのに、どうしてこんな目に遭わなくちゃいけないのか、と。
日本はなんで、こんな目に遭わせるのか、と」
「………」
「大黒柱を失った一冢の苦労といったら、そりゃ大変なものでした。
しかし、母も家族たちも、おやじがきっとどこかに生きていると、信じてきました。
信じてはきたけれど、祖父はすぐに死んだ。
祖母も、おやじが無事でいるという知らせが届く少し前に、亡くなりました。
その痛みは、私たちが受継がなきゃいけないのです」
私は、黙ってうなずいた。この父にしてこの子ありというか、劉さんにとっては、実に頼もしい息子である。
この息子がいてくれたおかげで、どんなに救われたことだろう。
それにしても、日本人の一人として、いささか耳の痛い 3 日の丸・君が代について top
「わが家は、おやじが無事に帰ってきたからよかったけれど、痛みのある家が、まだまだ無数にあるということなんですよ」 と、煥新さんは、こちらの心中を察してか、ふくよかなほおを少しゆるめた。
「だから、みんなで手を取合って、日本政府への謝罪と賠償要求に取りくんでいる。 民間のネットワークづくりです。もちろんメインは父ですけど、私もね」
「あのう、中国政府の対応は、どうなんでしょうか」
私は、再び取材者に戻った。
「ええ、前よりも明快になってきました。
公的な支持ではないけれど、一切拒んだりはしません。
いずれはもっとよくなるとみています」と、煥新さん。
「なるほど。こうしてうかがってきますと、劉さん一人の裁判でないことが、よくわかってきました。
判決も近いのですが、さて、どんなふうに出ることか……」
「そりゃね」と、しばらく息子の発言にまかせていた劉さんが、私の問いに向き直った。
「決して楽観はできないと思う。なにしろ日本政府はあったこともあったといわないんだから、簡単じゃない。
ところが、わしは八六歳だ。もうこの先そう長くはない」
「いえ、まだまだですよ」
「そうはいってもだ。ただ、わしには四代もの家族がいる。明日は家にもくるはずだが、四代目は生まれて六ヵ月だ。
孫たちに伝えて、スジを通したいんだよ。
日本は法治国家なんだから、法の裁きで、過去の過ちをきちんと認めよ、と」言葉に、返す言葉もなかった。
「その日本でですが、といっても、私どもの国ですから、責任の一端を感じるんですけれど、最後の質問です。
ごく最近の国会の動きです新ガイドライン法という“戦争法”やら、日の丸・君が代を国旗国歌になど、駆け込み乗車じゃないけれど、バタバタと決まってしまいました。
日の丸・君が代といったら、劉さんにも特別な思い出があるでしょう」
「うむ。これはわしの個人的な意見だがね。軍国主義の現われではないのか。
過去の亡霊が復活するというか、その恐れありで、この先の平和が気にかかる」
「平和が、どこまで続くか、心配だということですか」
「そう。でも、平和を願う人たちのほうが、ずっと多いんだし、わしも戦争に反対しつづけるよ。
あなたも多くの本を書いてきたけれど、わしはね、いつも近くの者に、自分の体験を話してるんだ。
戦争で、大勢の人が犠牲になったんだから。それも、ごくごく普通の庶民がね。日本も中国もだ。
愛する者を亡くして、悲しまない人はいないと思う」
劉さんは、そこで一息入れて背筋を立て直し、しわがれた声に力をこめた。
「裁判の結果が思いに反しても、わしの子や孫たちは闘い続ける。ずっとずっと……、わしにかわってね。
それはね、中国と日本の平和と友好のためなんだから」
4 青島市から草泊村へ top
翌日は、またまた快晴だった。
一夜が明けたわけだが、昨日の余韻がまだ胸に残っている。インタビューはうまくいったと思う。
しかし今日はお宅訪問をかねて、劉さん父子をお送りしなければならない。朝八時、車でホテル出発だ。
青島市内より、北西約一〇〇キロの高密県を目指す。
昔は諸城県といったのだが、そのなかの井洵鎮草泊村は、高密市内からまた西に入って三〇キロ。
かなりの距離だが、車は日本の高速よりも広い車道を、びゅんびゅんと飛ばした。
カーレースもどきのスピードで、これまた前方を見ているだに両足がすくむ。
かといって、横を見れば、市内を抜けたとたんに巨大なゴミ捨て場があって、ガスだかホコリだか、上空が灰色にかすんでいる。
一昔前の中国なら、こんなにゴミが出ることはなかっただろうから、やはり物質文明のツケではないのか。
そういえば、昨夜、ホテルの窓から建設中のビルの鉄骨に、点々と明かりが見えた。
夕食時だったので、ガイドの張さんにあれは何かと聞いたら、工事人夫たちがそれぞれのフロアで、自炊をしているのだという。
彼らはビル完成時まで、作業現場で寝泊りするのだというのに驚いた。 |

青島から草泊村へ
|
朝になってみると、超高層の鉄骨に蟻のようにうごめく彼らは、ヘルメットもかぶっていなかった。
前も横も冷汗ものばかりかと思ったが、郊外に出た車は、たちまちにして田園地帯に分け入った。
さすがは穀倉地帯だけあって、地平線まで続く畑また畑だ。
大豆、トウモロコシ、コーリャン、綿などで、ようやくのこと人心地つく思いである。
劉さん父子は、前の座席に並んで座っている。
昨夜はよく眠れたとのことだったが、やや過密のスケジュールで、疲れも残っているだろうから、車中で声をかけるのは遠慮した。
しかし、私たちは、劉さんらが、数珠つなぎにされて移送されてきた道を、逆に進んでいるわけである。
汽車の窓からの風景は、どんなふうに見えたことだろう。
あの日あの時、劉さんは朝食前に家を出たところで、傀儡兵に捕まったのだ。
妻はそれと気づいて、途中まで追いかけたものの、身重だったので、どうすることもできなかった。
お腹の子は七ヶ月目になっていた。
だが、それは不幸中のしあわせだったのではないのかと思う。
夫が消えた後、妻はすぐに出産し、その子を育てることに追われ、ただただ目の色を変えねばならなかった。
働き手の「大黒柱」を奪われた貧農一家は、食うや食わずで、それこそ路頭に迷う日々だったからである。
もしも、彼女がひとり身だったら、どうなっただろう。
二三歳の若妻が、生死不明の夫を、ずっと待ち続けられる条件は薄い。
「日本鬼子」に拉致されて、一三年間も消息がなければ、まず望みはないと考えるのが妥当である。
戦争中のことだが、召集されていった夫の戦死公報が届いて、残された妻が再婚するという例は、ごく一般的だった。
ところが、死んだはずの夫が復員してきた悲劇を、私は知っている。中国でも、例外ではなかっただろう。
それなのに、劉さんには、いとしい妻のほかに、まだ顔を見たこともない息子が待っていたのだ。
めったにない快挙で、その邂逅(かいこう=めぐりあわせ)を思うだに胸が熱くなる。
これから会う妻の趙玉蘭さんは、どんな人なのだろうか。
|

草泊村の劉さんの自宅近くで

村を案内する劉さん
|
5 趙玉蘭(チャオユイラン)さんに会う
top
幼い時の煥新さんは、二つの名を持っていた。
「盼」(バン)と「尋」(ジュン)だ。
盼は、父が帰ってくるのを待つという意味であり、尋はその父がどこにいようとも探し出すという意味で、祖母がつけてくれたものだった。
しかし、食うや食わずの生活苦は、人民中国になっても解消されなかった。
ペンペン草の生えるような荒地同様の耕作地に、肥料も機械もなく、収穫は極端に少なかった。
母も子も朝から晩まで泥まみれで働かねばならなかったから、彼が小学校に入ったのは一二歳の時だったという。
生還した父親と初対面した煥新さんは、小学校に上がってまだ一年ちょっとだった。
しかし、その後生活は徐々に改善されて、息子もけんめいに学んだのだろう。今は高密市井淘綿油工場の工会(労働組合)主席になっている。
主席にもいろいろあるが、組合長といったところか。
毛主席に似た押し出しからして、多くの組合員の信頼を得ていることだろう。
などと思いをめぐらしているうち、車はいつのまにか、素朴な農村地帶に入っていた。でこぼこ道である。
このあたりは、映画「紅いコーリャン」のロケ地だったと、煥新さんがいう。
もう一〇年ほど前に見た映画だったが、野性的なエネルギーいっぱいの、衝撃的な作品だった。
嫁入りの娘を乗せた寵(かご)が、身の丈(たけ)ほどもあるコーリャン畑の道を行くシーンが思い出されて、現実の風景と重なってしまう。
道の彼方から、大きなワラの山が、ユサユサと揺れながらきて、通り過ぎた。
一台の自転車に、あんなにも積めるものかと驚く。ワラの山ごと歩いてくる人もいる。
その後から、ポンコツのトラクターがやってきた。気のいい男たちが何人か乗っていて、笑顔で手を振ってくれた。
やっと、草泊村についたらしい。
空地に車をとめて、あとは赤土の道を歩いていくことになる。
先に立つ劉さんは、煥新さんとともに歩幅も大きくスタスタと歩き、その後を鶏やガチョウが、群をなしてついていく。
道の両側に点在する家は、みな平屋で、路上に牛や馬がつないである。
ひしゃげたような家ばかりで、昔なじみの肥料の匂いがしてきた。
まだ下水がないらしく、道の端がぬかっている。中国の都会は開発ばやりだが、農村部の生活は貧しく、戦時中と大差ないのではあるまいか。
|

近所の人々が笑顔で見ていた

煥新さんにうながされて趙玉蘭さんが私たちを出迎えた
劉さんの家は、道の角地にあって、赤レンガ塀で囲まれていた。
レンガは日本のように単調ではないので、なかなかの風情だが、外塀に開いた一ヵ所だけの窓は、ガラスでなくて一枚板だった。
風通しのためか、板が斜めに上げてある。
入口は道に面したところにあって、色とりどりの張り紙がしてあった。
|

趙王蘭さん

劉連仁さん一家と
|
すぐ目につく大きめの赤いシールには、「福」の一字が踊っていた。
先になかに入った煥新さんが、知らせたのだろう。母屋のある中庭から、白髪で赤ら顔の女性が、大きな身体を揺すりながらやってきた。
陽焼けした顔をほころばせて、太い両手を差しのべてきた。
それが、趙玉蘭さんだった。
ああ、この人がそうなのか、と私は胸が熱くなった。
|

遠まきに見守る近所の人々
|

トラクターは立派な交通手段
|
6 曾孫は生後六ヵ月で top
さあ、どうぞどうぞということで、入口をくぐる。
とたんに、母屋から出てきた家族一同にどっと囲まれてしまった。
劉さんが、妻に続いて、一人ずつを紹介してくれた。
まず煥新さんの奥さんと、その長男夫妻と、またその子である。
つまり、孫にあたる劉利(りゅうり)さんは二九歳、その妻は范秀美(はんしゅび)さんで、抱いている子は生後六ヵ月目の劉敬(りゅうけい)ちゃんだ。
劉老にとっては、それこそ四代目の曾孫ということになる。
みんな明るい。初対面のような気がしない。 |

ひ孫と遊ぶ劉さん
|
わしが死んでも、代々の家族で闘うといった昨夜の言葉が思い出されたが、四代目はぶくぶくとよく太って、無心にあどけない女の子である。
ほかに、劉さんが生還してから生まれた長女の劉萍(りゅうひょう)さんとその子がいるのだが、今日は都合があってということだった。
塀に囲まれた敷地は、小ぢんまりとしたもので、一〇〇平方メートルくらいか。
ナツメの木と古井戸の先が、やはり平屋造りの母屋になっている。
「さあさあ、なかで休んでくれ。長旅で大変だっただろ」
と、劉さんが、メモをとる私の肩をたたく。
「でも、わりと早く着きましたよ。三時間もかかりませんでしたものね」
「いやいや、あんたたちは、はるかな海の彼方からやってきたんだ。大変なことだよ」
その海の彼方まで引っぱられた劉さんは、どんなに大変だったかといいかけたが、王蘭さんが手を取らんばかりで、とにかくお茶を一杯いただくことにした。
母屋は二K。入った先のキッチンの左右に小部屋があって、オンドル式のベッドにテレビがある。
「この家はね、昔からのものじゃない。元の家はもう少し先にあって、二〇年ほど前に建ててもらったんだよ」
と、劉さんは相好をくずしていう。
「え? 建ててもらった?」
「そう、省からね。えらい目にあったんで、プレゼントというわけだ」
「へえっ、それはそれは!」
「ただし、電気がきたのは一〇年ほど前で、水道もないんだ。今はね、わしらだけが住んでいる」
子供たち孫たちは、四キロほど離れたところにいるということだが、きっと、ここよりかは市街地に近く、便のいいところなのだろう。
中国も日本も、過疎地には高齢者だけが取残される。
若夫婦が、赤子をあやしながら、横にきた。
彼の職業を聞いてみると、自動車のセールスマンなのだそうだ。
大都会ならいざ知らず、地方で成り立つのかと聞いてみたら、景気はよくないと苦笑する。
生活協同組合に働いていた彼女も、いまは子育て中なので、時々、ここまで小麦などもらいにくるという話だった。
7 反ファシズム闘士として top
|

家の裏では馬が干草をはんでいた
|

飲料水はポンプ式井戸
|
その小麦は、誰が収穫したのか。念のため、ちょっと聞いてみた。
すると、劉老あてに国から無償で支給されるのだという。
「反ファシズム闘士で、“抗日老英雄”になってるんですよ、おやじは。さんざん苦労したことでの特別待遇ですよ」
「へえっ、そうなんですか。ちょっと、くわしく教えてください」
私はまたメモ帳を広げた。
煥新さんの説明によると、抗日老英雄扱いとなった劉さんには、国(厚生省)から耕作地が無償提供されたほか、年に小麦五〇〇キロが支給される。
さらに電気代は無料、医療費も年に一五〇〇元(一元は約一五円)まで無料だという。
テレビやベッドは、息子が働いて買ってくれたものだが、家は省からのもらいもので、生涯年金もつく。
年間一三〇〇元で、月に換算すれば日本円で一五〇〇円ほどでしがないが、それでも農民一般としては高いほうだ。
健康管理もかねて畑仕事をしているので、自給自足だから、余った小麦など孫たちがもらいにくるのだろう。
「ふーん、そりゃいいなあ。家付き畑付きで食付きってわけなんですね」
私は、声をはずませたが、とたんに何となくうしろめたい思いにがられた。
本当は日本政府がすべきことを、かわって中国側が償い、ぬくもりのある手を差しのべているのではないのか、と。
とはいっても、日中間の外交問題にまでおよんだ劉さんの場合は、明らかに「特別」なのだった。
この大地の続くところから、強制連行された四万万人までには、到底、手が届かない。
いわんや、もの言えぬ白骨となって帰還した約七〇〇〇人の遺族たちは、どこでどんな生活をしているのだろうか。考えるだに胸がふさがる。
劉さんは、人生でもっとも充実期の一三年間を奪われたが、その夫が生きて帰ってくる時、妻のひそかな心配事は、
「白毛男になってくるのでは……」ということだったそうだ。
中国には、誰もが知る白毛女の現代歌劇がある。
昔、貧農の娘が城主の迫害を逃れて山中の洞穴にこもり、三年のうちに白髪となったが、解放車に救出され、村も解放されたという内容だ。
自由になった娘は、とたんに黒髪に戻って、めでたしとなる。
その娘より一〇年も多く雪穴に隠れていたのなら、妻の不安もうなずけよう。
が、夫はいくらかはげ上かってはいたが、角刈り頭は、黒々としていた。
しかし、今は後頭部までつるりと上がってしまった夫に対して、妻の頭髪は、さらしたように白く、それこそ白毛女である。
七八歳という年齢からすれば、別に不思議はないけれど、私には何とも痛ましく、それだけ余分な苦労をしてきたのだと思える。
子供らが独立したあとの夫婦は水入らずの、やっと穏やかな生活になった感じだが、しかし、残り時間はもう少ない。
夫とちがって、肉付きのよい玉蘭さんは、歩くのも少し不自由そうだった。
これまでの苦難を思えば、ともに一日でも長生きしてもらって、日本の裁判による公正な判決を見届けてほしいもの。
|

劉さんの家に集まった近所の人たち
|

劉さんの孫嫁
|
8 日本人の一人として top
カマド付きキッチンと、二間しかないお宅は、テレビに扇風機、ベッドが目につくぐらいで、やけにがらんとしている。
家具調度品らしいものが極端に少ないせいだが、そこで私は、ふと思い出したものだ。
「そういえば……」
と切り出したのは、忘れぬうちにカメラに収めておきたい品々のことである。
「劉さん、あのう、北海道で過ごされた時のサバイバル(生活術)道具というか、スコップの先とか、鍋、鉄瓶など、ほら、いろんな道具をお持ち帰りになりましたよね」
「あれは、もうないんだ。文革(文化大革命)でね、みんなどこかへいってしまったよ」
と、虚しく両手を広げてみせる。
「え? そうなんですか。そりゃ、残念だなあ」
「みんな、ひどい目にあった。まあ、わしはそれほどでもなかったが……」
文化大革命の嵐は、六〇年代後半から全中国を荒し回ったが、劉さんは多くを語ろうとしなかった。
何か後味のよくないことでもあるのか。それにしても惜しい。
劉さんの戦争体験を伝えるには、貴重な物的資料だったはずなのに。……
「でも、当時のことなど、お子さんお孫さんたちには、語り継いでいるんですか」
と、重ねて聞いてみた。
「うむ。捕まった時と、帰ってきた時とを、わしの記念日にしている。
みんな集まってくるんでね、まあ、できるだけしゃべっているんだよ」
「小麦などもらいにくるお孫さんは、まだ二〇代ですよね。話しても、なかなかぴんとこないでしょうね」
「ぴんとくるようになったら、困るんだよ」
赤ん坊を抱いた劉さんは、盛んに好々爺ぶりを発揮しながら笑った。赤子はお尻丸出しだった。
おとなしい子で、人見知りもせずに、きょとんとしている。
いつのまにか、私たちは、近所の皆さんたちに囲まれていた。
子供もいれば老人も、若い衆もいて、みな興味あり気である。
子供たちは夏休み中なのだろうが、平日の午前中に、なぜ若い人たちがのんびりしているのかがわからない。
そういえば、みんな腕時計なしで、よくよく見れば劉さん一家もそうなのだった。
世間に追われる生活ではないのだろう。
かわりに物質的な豊かさとは縁遠く、上半身裸の男や子供もいれば、裸足の子もいる。
ふと、その視線が気になった。
彼らは、日本人である私たちを、どう見ているのだろうか?
私は、思わず足もとを振り返らざるを得ない。
若き日の農夫だった劉さんを、この地から日本にまで拉致した責任は、一体誰が負うのか、と。
国際法に反する強制連行の閣議決定をしたのは、紛れもなく日本政府だった。
しかし、現地での陰惨な「労工狩り」作戦は、一部に傀儡軍が手先になったものの、日の丸の旗をかざした日本兵によって行われている。
さらに国内での奴隷並みの強制労働は、これに企業が加担したものだった。
その企業=昭和鉱業は今はもう存在しない。
従って主たる責任は日本政府が負うべきだが、直接にかかわった日本人一人ひとりも、戦争犯罪に手を下したといえる。
被害者たちの傷がまだ癒されていない以上、その戦争犯罪に時効はないのだ。
しかし、戦後半世紀余が過ぎた今となっては、無関係だという人がもはや絶対多数だろう。無関係なら、オレは知らないまでいいのかどうかである。
この問題に、「我関セズ」では、臭いものに蓋をしようという勢力の思う壺にはまってしまうし、歴史そのものも継承できず、日本と中国との真の友好は望むべくもない。
さらに後に続く世代が国際社会に生きる以上、アジアや世界から孤立していくだろうことも、気にかかる。
他民族をないがしろにすれば、自らの人権も危うくなると思わざるを得ない。
いまや「日本人の誇り」だけをうんぬんする説が声高だが、人間として人類としての心構えが大事で、私は劉さんら中国人戦争被害者の人権回復に関心を持ち、いささかなりと心を寄せたいと思う。
それは、とりもなおさず私たち自身の人間らしく生きる権利と社会正義、ならびに国際的信頼を構築する課題とも、一つに結び合うだろう。
「はるばるとわが家まできてくれて、本当にうれしい。これからの旅の一路平安を祈ります。
またお会いできる日を楽しみに、再見!」
劉さんは最後にそういい、家族そろっていつまでも手を振り続けたが、遠ざかる車のなかで、私の胸は様々な思いに溢(あふ)れた。
top
****************************************
|