|
****************************************
Home 概要 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ
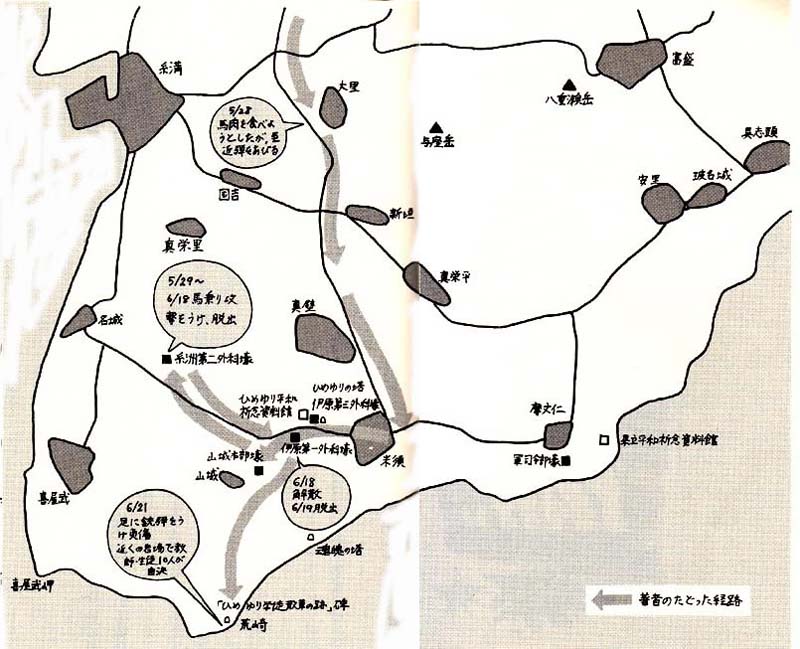 |
1 南風原(はえばる)からの脱出
top
「一両日中に移動するからその準備をするように」という指令が出されました。
独歩(どっぽ=歩ける)患者はそれぞれ、衛生兵や看護婦をつけて送り出されました。
しかし、横たわっている何百という重傷者については、どうすることもできません。
「移動のことは一言ももらしてはいけない。患者に気づかれないようにせよ」とのことで、壕内作業はなおもつづけられました。
しかし、不気味な沈黙はかえって患者の敏感な神経をいらだたせているようでした。
「学生さん、移動するんじゃないですか。ぼくたちを捨てていくんじゃないだろうね」
「さあ、私たちにははっきりしたことはわからないのですが」
息づまるような雰囲気のなかで、私たちは顔を見合わせるだけでした。
五月二六日、いよいよ移動の命令が下りました。
朝から壕内はごたごたと準備に忙しく、みんな深刻な表情で身のまわりを整えていました。
一週間ほど前からかぜ気味(ぎみ)で休んでいたのが、また二、三日来不眠症にかかって困っていた私は、軍医の注意で朝八時に睡眠剤を飮んで横になっていました。
「比嘉(ひが=筆者)さん、比嘉さん」
とゆり起こされて目を開くと、もうみんなはリュックサックを背負い、靴のひもを結んだりしていました。
まだ覚めきらない目をこすりながらとび起き、配給された乾パンや缶詰、衛生材料などをリュックサックに詰めていると、内田先生が回ってきて、
「なんだ、いまごろそんなことをやっているのか。もう出発だというのに」としかられました。
友だちに手伝ってもらってやっと準備が整い、寝台から下り立とうとしたら靴がありません。
暗やみのなかで、あたりを探しまわっても見つかりません。
あの長い道のりを裸足でと思うと、気が気ではありません。
私は二〇壕の泥だらけの通路を行ったり来たりしてなにか履(は)けそうなものはないかと、血眼(ちまなこ)になって探しまわりました。
とそのとき、二段式寝台の上の段のかます(穀類を入れるむしろでつくった袋)のカーテンが開いて、
「だれだ、さっきからそこを歩き回っているのは」
「はい、比嘉であります。靴がなくなって、探しているのです」
「それはたいへんだ。よし、これをおまえにやろう」
仲本軍医は真新しい軍靴(ぐんか)を私に渡しました。
「少し大きいかもしらんが、裸足よりはいい」
「軍医殿ありがとうございます。私は古いのでいいのですが」
「いや、おれはいま履いているのがある。それにおれはここへ残ることになるかもしらんからな。気をつけて行けよ」
「ありがとうございます。助かります」
地獄で仏とは、まさしくこのことだと思いました。
しかし、仲本軍医がここへ残るということは、どういうことなのだろうか。
患者を担架で運び終えるまでということか。いったい何日ぐらいかかるのだろう。死を覚悟しているのでは。
いろんな思いが頭のなかをかけまわりましたが、私は軍医になにも言えませんでした。
やがて、本部、第一外科もすでに出発したとの知らせに、第二外科の生徒も壕の入口のほうへ出ていきました。
「出発用意!」の声で、私も後について歩きだしたのですが、薬が十分に覚めきらないためか、ふらふらしました。
友だちも心配して気づかってくれましたが、さいわいなことに治療班と手術班は治療器具の整理のためにしばらく残ることになったので、いっしょに残ることになりました。
私は内心ほっとしました。
先生方やみんなに遅れることは不安なことではありましたが、いますぐみんなといっしょに駆けだす自信はとてもありませんでした。
壕の入口ではしばらく騒音が聞こえていましたが、七時すぎ、急に静かになり、先発隊の脱出が完了したようでした。
不気味な静けさのなかで、ガチャガチャと治療器具の触れあう音がいっそう不安をかりたてていました。
治療器具の整理を終え、荷物を整えた私たちも、九時近くになっていよいよ一九壕の入口へ出ていきました。
しょぼしょぼと降る雨のなかに照明弾がひっきりなしに上がっていました。
「それっ、いまだ、前進」の掛け声を合図に二、三歩壕の外へ出たかと思うと、また真昼のような照明で後退します。
なんどかそれをくりかえしていましたが、やがて、目(さがん)、川崎、高山軍医たちが真っ先に飛び出しました。
看護婦や私たちもそのあとにつづきました。
「もどるな、前進、前進」と言いながら、すべる坂道をかけのぼりました。
ちょうど丘の頂にさしかかったとき、またもや三、四発の照明弾が打ち上げられ、みんなは泥のなかに顔を埋め、しっかりと地面に伏しました。
光が少しうすれたとみると、「前進!」先頭の軍医の声でバタバタとかけだします。
弾が落ちてあいた穴にころがりこんだり、土手からころげ落ちたりしながらやっと本部の壕へ着きましたが、本部壕はすでにもぬけのからでした。
ふと気がつくと、いっしょに出たはずの田場(たば)さん、岸本さん、中里さんや川崎軍医らの一行が見えません。
しばらく待ってもいっこうに姿を見せないので、本部へ寄らずにまっすぐ目的地へ向かったのだろうということになり、私たちの一行も出発することにしました。
「どうしたのかしら」
許田さんと私は友の身を案じながらも、とり残されてはいけないので、やはり軍医らのあとを追いました。
まわり道するのももどかしく、畑を横断して本道へ出ると、南へ逃げていく兵やトラックが、ひっきりなしにつづいていました。
2 南部撤退 top
遠く近く炸裂する砲弾の音に、何度も溝にかくれながら、頭を低くして進んでいくと、山川(やまかわ)というところを少し過ぎたところで、どこから流れこんだ人の群れなのだろうか、兵、避難民、トラック、荷馬車、と道いっぱいの雑踏になりました。
人びとの足は速く、ともすると私は連れに遅れがちになりました。
背負ったリュックサックをゆすりあげゆすりあげ、友や軍医の姿を見失うまいと、まばたきもせず追っていきましたが、疲れきった目はなかば視力を失いかけていました。
「許田さん!」、友の名を呼ぼうとしましたが声が出ません。
いつのまにか連れの姿は完全に視野から消えてしまっていました。
ふらふらとなる心のなかから、「そうだ、道のまんなかに倒れてはみんなに踏みつけられてしまう。
端に寄らなくては」と力をふりしぼって、雑踏のなかを横切って道の端へ移っていきました。
睡魔におそわれたかのような心地よさに、しばしわれを忘れた一瞬「こらっ、しっかりしろ」と大声でどなられ、はっとしました。 |

山川の三叉路――右へ入ると南風原(はえばる)、手前が東風平方面
|
気がつくと、うしろから知らない兵の手で支えられていました。
「こらっ」二度どなられ、ほおをたたかれて、はじめてはっきりと意識をとりもどしました。
やがて、兵の呼ぶ声に引きかえしてくれた、許田さんと仲本軍医に助けられて、なおも進んでいきました。
一〇メートルも前を行く目大尉らがぶりかえっては、「おーい、だいじょうぶか」と声をかけてくれます。
「おーい、だいじょうぶだ」と仲本軍医も声を返します。
あえぎあえぎ行く私たちの一行と、大尉らの一行との間隔はしだいに長くなり、「おーい、おーい」の声もだんだん遠ざかっていきました。
「すみません」、泣きだしたいくらいの焦燥(しょうそう)にかられながらも、私の歩みはいっこうにはかどりませんでした。
「そんなに心配せんでもいいよ。真壁(まかべ)への道は私がいちばん詳しいのだから、遅れたって心配はない」
親切な軍医はゆっくり歩くように言ってくれましたが、私は困難な呼吸にあえぎながらも早められるだけ足を早めました。
あれほどの人の群れもどこへ行ってしまったのか、いつしか道ゆく人はまばらになっていました。
照明弾もほとんど上がらなくなり、着弾の音もなくなっていました。
やっとのことで道ばたに休んで待っていた大尉らの一行に追いつくことができ、私たちはほっとしました。
「ここまで来ればだいじょうぶだよ。とにかく夜の明けないうちにどこか壕を探さねばなるまい」
しばらく休んで、一行はまた出発しました。
すっかり元気をとりもどした私は、こんどはみんなに遅れないように、前になって歩きました。
民家の近くへ来ると、ところどころ着弾があったらしく、家々がまっ赤な炎を上げて燃えています。
もう空はしらじらと明けはじめ、道ゆく人は足を早め、あるいは壕を探して入ったりしています。
ババーン
耳もつぶれるばかりの発砲音がしました。すぐ近くに日本軍の野砲陣地があるようでした。
「まあ、撃たなければいいのに。いまに返礼の一斉射撃が来るわ」
私たちは小走りにその陣地の近くを通り過ぎました。
「看護婦さん、看護婦さんじゃありませんか。包帯がずれて歩けないのです。巻きかえてもらえんですか」
見れば、足を引きずりながら歩いていく負傷兵です。
泥にまみれた包帯はとても巻きかえられるものではありません。
そのまま上にあげて止めるだけの処置しかできませんでした。
尻をついて泥のなかをいざってゆく兵、戦友や看護婦に支えられてかろうじて歩を運ぶ兵など、負傷者の姿はなんといってもみじめでした。
まもなく夜も明けようというので、交渉して付近の修理部隊の壕に入れてもらうことになりました。
本道から少し畑のなかの小道を行くとちょっとした林があり、そのなかに壕があったように覚えています。壕に入っていくとなかは大広場になっており、一隅に戸板がしかれて兵たちが串(くし)ざしのように寝ていました。
私たちは思い思いに休憩をとることになりました。
私は、兵たちが寝ている戸板のすきまを見つけて、割りこんでなんとか横になることができました。
疲れがどっと出たようで、前後不覚になってほんとうに気持ちよい睡眠をとることができました。
「学生さん、学生さん」と足をひっぱられて目をさますと、知らない兵が飯ごうのふたにスープを入れて持っています。
「鶏のスープだよ。元気がでるから飮みなさい」
「ありがとうございます」
この一両日なにも口にしてない私にとって、なんとも言えない、生きかえるような、そのまま血液になっていくような味わいでした。
どうして見も知らぬ私を起こしてまで、鶏をつかまえてきてつくった貴重なスープを分けてくれたのだろう。
ひょっとして、昨夜倒れかかった私をうしろから支えてくれた兵ではなかったのか。
名も告げずに去っていった親切な兵の心づくしで、ほんとうに不思議なほど元気がわいてきました。
壕の人たちに礼をのべて出立したのは正午近くでした。
相変わらずの小雨で、野も山もぼうっと白く煙り、飛行機も朝からまったく見えません。
空襲も艦砲射撃もないなんて、まるでうそのような気がします。
道ばたのさとうきび畑に入って、二、三本折り、久しぶりに甘い汁をすすりました。
ほんとうに何日ぶりだろう。小声で歌さえ口ずさみながら歩きました。
ある部落へさしかかると、被害のない民家が並んでいます。不思議に懐かしさがわいてきます。
人さえ住んでいるようすです。
「危なくないのですか」
そばに立っている家主(やぬし)らしい人に聞くと、
「いいえ、こちらはたいしたことはないんです。それでも昼のうちは壕へ行っていますがね」
との話です。
「沖縄にもまだこんな平和な土地が残っていたのね」
なにかしら熱い涙がにじんできました。
その人の注意で、私たちは回り道でも安全なほうへ行くことにしました。
先に行った生徒の一行は近道を行ったとの話に、危険なことはなかったろうかと案じながら先を急ぎました。
|

高嶺の坂から見おろした糸満の海
|

高射砲隊の壕のあった松林
|
糸満の海を右手に見おろしながら行くと、さすがに艦砲射撃が来ました。
近くに壕を探し、日が暮れるのを待ってから出かけようと、あちらこちらそれらしいところをのぞいてまわりますが、どの壕もいっぱいで入れてもらえません。
付近の人の世話で、松林のなかに高射砲隊の空いた壕を見つけて、そこに泊ることになりました。
その壕にいた兵隊はみんな切りこみに出ていったとのことでした。
入口には砲弾の箱が重ねられ、片隅の天井には弾痕(だんこん)らしい大きな穴があいていました。
チョンチョンとたれる水滴を避けながら、一夜を明かしました。
翌日もまた艦砲射撃がつづいて、出るに出られません。壕のなかにくすぶっていると、
「師範の生徒がいますか」
聞きおぼえのある声が入口でしました。
「はい、おりますよ」 私は夢中で出ていきました。
「あっ、少尉殿」 それは細見少尉でした。
天久(あめく)の作業以来、識名(しきな)の作業でも五ヵ月のあいだ、私たちの作業監督の任にあたっていた高射砲隊の小隊長でした。
「おお、みなさんご無事でしたか。ついそこで、師範の生徒がいると聞いたものだから。
とんだ目にあいましたね。部隊もみな散り散りになって切りこみに出たんですよ」
「まあ、よくご無事で」
「では時間がないので失礼。お元気でがんばってください。あちらへ行ったらみなさんによろしく伝えてください」
小走りに去って行くうしろ姿に、数力月前には見られなかった憔悴(しょうすい)の影がうかがわれました。
「みなさんの手で築いた陣地は百発百中ですから、心配ご無用」
との頼もしい言葉に元気百倍して築いたあの陣地ははたしてどうなったろう。
識名の作業場で作業の手を休めては、文学好きの少尉の話に耳を傾けたり、墓石を背に会食したりした懐かしい思い出が、走馬灯のように浮かんできました。
当時、部下の兵に対して寛容であるというので、生徒の好意を一身に集めていた少尉でした。
「どうぞご無事で」
祈るような気持ちで、松林に消えてゆくうしろ姿をいつまでも見送ったのでした。
ようやく昼すぎに壕を出ました。
道路の反対側の林のなかを歩いていると、松の枝に馬の片脚がかけられています。
先にここを通っていった兵たちが、砲弾にあたった馬をほふって食べ、残った足を、あとから来る人たちの目につくようにと、枝にかけておいたのでしょう。
ちょうどそこにいあわせた兵が、今夕は馬肉のごちそうだと言って、許田さんと私は飯炊きを割りあてられました。
道路わきの畑のなかに、石を三つ並べてかまどをつくり、枯れ枝をあつめて火を燃やしはじめました。
たそがれどきで、飛行機も飛ばず、艦砲も鳴りをひそめていました。
コトコトコトとごはんのたぎる音を聞き、おいしそうな匂いをかぎながら、二人はぼんやりと糸満の海をながめていました。
ヒューッ、バン! 至近弾です。
思わず伏せて難をのがれましたが、あたり一面に土煙がもうもうと上がっています。
みんな不思議に無事です。不発弾だったのです。
こぼれた釜のごはんをかまどのなかに投げ入れて、火を消しました。
もちろん、もう少しで口に入るはずだった、おいしいごはんも馬肉のごちそうもだめになってしまいました。
二発目が危ないというので、すぐにそこを出発しました。もうあたりはうす暗くなっていました。
目的地にいつ着くというあてもなく、ただ前を歩いている人たちの後につづいて黙々と歩きました。
ふと人声やざわめきが聞こえたので、歩みを止めました。
道路わきの木立のなかをのぞくと、大きな自然壕があり、なかには兵や一般人などがおおぜい入っているようでした。
中央あたりに池のような水まであって、繩(なわ)でまわりを囲ってあるようでした。
足場がわるく、それに滑るようだったので、私たちはなかには入りませんでした。
ちょうどそのとき、ボンボンボンという発射音とともに、中空に照明弾らしいのが一〇発くらい、暗号のようにきちんと並んで上がりました。
「なんだろう」、わるい予感がして、私たちはそこに泊らず先へ歩きました。
極度の不安と疲れで、ただ無意識に足を運んでいて、どこをどう通ったのかほとんど覚えていません。
3 山城壕から糸洲壕へ top
|

山城(やましろ)本部壕
|

糸洲(いとす)第二外科壕と筆者――入口はふさがれている
|
南風原を出て三日目の明けがた、やっと石部隊(第六二師団)が入っている山城(やましろ)の壕に着きました。
すでにあちこちから集まってきた人びとでいっぱいでした。
案じていた田場さん、岸本さんたちも無事に着いていて、私たちの来るのを待っていました。
四月以来まったく会ったことのない友だちどうし、たがいに再会を喜び、過ぎし日のことどもを語りあいました。
本部の壕から担架で運ばれてきた山城芳子さんと石川清さんを見つけたときは、なんにも言えず、ただ手を取りあって涙にくれるだけでした。
第二外科では生徒の犠牲者は一人も出なかったので、負傷した友を目のあたりにするのははじめてでした。
「山城さん、つらかったでしょう。元気を出してね」と言えば、
「ありがとう。あなたこそ、どうもなかったの。気をつけてね」
と自分の傷も忘れて気づかう友情に、また新たな涙がせきあげてきました。
「石川さんは」
「あの人弱っているのよ。担架から二度もふるい落とされたのですって。途中でまた肩をやられたらしいの」
不運な友は、幅のせまい木箱の上に力なく横たわっていました。
「石川さん」胸のせまる思いで冷たい手をとると、
「比嘉さん?」とかすかにほほ笑みました。
「しっかりしてね。もう少しのしんぼうよ」
「ええ、ありがとう」
一ヵ月半前まであんなに元気だった友の声とも思えないほどかすかな声でした。
第一外科、第二外科はすでに割りあての壕へ出発した後だったので、私たちはすぐに出発しなければいけません。
うしろ髪をひかれる思いで、糸洲(いとす)の壕へ向かいました。
糸洲までもう遠くはないと聞いても、二、三日来歩きつづけているので、足どりは重く、なかなか進みません。
空襲もなく艦砲の音も聞こえませんが、途中に砲弾で破壊された民家がぽつぽつとあるのを見ると、ここもやはり戦場なんだと、怖(こわ)い気持になりました。
小一時間ほど歩いてやっと、みんなが待っている糸洲の部落に着きました。
先に行っていた第二外科の人たちが、民家の縁側や庭先、門のあたりに腰をおろしていました。
予科二年生の照屋キクさんの家だということでした。
広い屋敷に瓦ぶきの、堂々たる農家でした。
よく拭(ふ)きこまれだ槇(まき)の柱や床が懐かしく思われました。
私たちは、久しぶりに靴を脱いで床の上にからだを横たえました。
こんなことができるなんて、まるで夢のようでした。
照屋さんの両親は、私たちのためにさつま芋をふかしてくれたり、ぜんざいを炊いてくれたり、娘の学友だということでほんとうに親切にしてくれました。
糸洲に来て三、四日のあいたはまったく楽土でした。
艦砲の響きもときおり遠くのほうで聞こえるだけで、空襲もたいしたことはありませんでした。
それでも日中は民家にいるのは危険なので、糸洲の部落の裏側につらなる雑木林の丘にそれぞれ安全な場所をもとめて散っていました。
夕方になって、宿泊所の民家へ引きあげてくると、私たちは髪や着物を洗い、久しぶりに自分の身を整えることができました。
しかし、安穏の日もそう長くはつづきませんでした。
そろそろグラマン機が飛びはじめ、艦砲も近くへ着弾するようになりました。
気のつよい人たちはなおも床の上を恋しがって、夜になると民家へ帰っていきましたが、ほとんどの人は壕に泊るようになっていました。
糸洲第二外科壕は、照屋家から二〇メートルくらい後方の雑木林のなかに「コ」の字型に掘られた壕でした。
入口のほうはかがんで入り、反対側には銃眼があると聞きましたが、私は入口近くにいて奥はまったく知りませんでした。
六月四日の夜、友に誘われて民家へ行って泊りましたが、なにかしら身の危険を感じて、夜中から仲里順子さんと二人で壕へ引きかえしました。
はからずもその夜、民家に艦砲が命中して、女学生と看護婦の二人が即死、数名の負傷者を出したのでした。
4 中村少尉の死 top
糸洲へ来て一週間くらいたったころでした。
「中村少尉殿がやられました」
担架をかついで二、三人の兵がよろよろと照屋家へかけこんできました。
聞きつけて走りよった私たちは、担架のまわりに集まりました。
「第二外科が糸洲だと聞いて探してきたのです。お願いします」
兵はいまにも泣きだしそうな表情で訴えます。
思えば四月の中旬、切りこみに出かけるということで、中村少尉が森少尉といっしょに生徒壕を訪ねてきたとき、「ばんざい三唱をしよう」とだれかが言いたしたのを、「よしてくれよ。死にに行くというのに、ばんざい三唱でもないだろう」とつぶやいた少尉の悲痛な表情がまざまざと思い出されます。
慶応大学を出たばかりで、ちょうど私たちぐらいの妹が一人いると話していました。
北国の人らしく、血色のよい端麗(たんれい)な容姿の人でした。
しかしいま私たちの前に投げ出された姿は、軍服は泥にまみれ、「うんうん」とひきつるような顔は土色で、まったく血の気もなく、
「少尉殿、少尉殿」
と桐原婦長が声をかけゆすぶっても、眼をとじたまま、
「うう……、いたた……」
とうめき苦しむ痛々しい姿に、みんな涙の目をそむけました。
やがて軍医の治療がすんで、いくらか痛みもしずまったらしく、静かに眠りに入った少尉は、つきそいの兵たちに担がれて近くの民家へ移されました。
それから二日目だったでしょうか、夕方壕を出た私たちは、「中村少尉をお見舞いしなくては」と話しながら行くと、急ぎ足で来る友と行きあいました。
「少尉殿、とうとう亡くなられたのですって」
「最後まで『師範の女学生は来ないか、まだ来ないか』と待ちかねて。せめてもう少し早く来てくれたらよかった」とつきそいの兵が話していたとのことです。
それを聞いて暗然となりました。
昼じゅう、危険を恐れ、無断外出で非難されることを恐れて、壕のなかにいたために、生きた少尉の顔を二度と見ることができなくなってしまったのです。
取返しのつかないことをしたと、ざんきにたえない思いでした。
「せめて一茎の草花でも墓前にそなえよう」と話していましたが、ついにつきそいの兵に会う機会もなく、埋葬の地も知らないままになってしまいました。
異郷の地で、このように人知れず葬られた人びとがどれほどあったことでしょう。
やがて、ここでも完全な壕生活がはじまりました。
壕といっても南風原の壕のような坑木の入ったりっぱなものではなく、直撃弾にでも見舞われたらひとたまりもないと思われる小さな穴でした。
それに民家へ出る人もなく、約六十人の第二外科全員が入ったので、入口近くの生徒席はいつも外へあふれ出る状態でした。
夕方になると私たちは、近くの民家にいる二、三の負傷兵を治療してまわっていましたが、そのうちに衛生材料も少なくなったので、ほかの部隊の人の治療をしてはいけないと、軍医に止められました。
しかし、「お願いします」と頼んでくる患者をむげに断ることはできませんでした。
夜になると、衛生材料の隠されているというところを聞いては、看護婦たちといっしょにそれを取りにいきました。
民家の垣根のそばや庭に、息絶えてすでに死臭のただよう死体がそのままになっています。
そのなかで、軒下に積まれた包帯やガーゼを手あたりしだいリュックサックにつめこんでくるのでしたが、ときおり、ねっとりと血の着いたガーゼなどに触れてぎょっとすることもありました。
いよいよ攻撃もはげしくなってくると、民家にいた負傷兵たちもそれぞれ壕を探して出ていったので、私たちは治療にまわる必要もなくなりました。
毎夜輪番で行く本部連絡以外には、もう生徒の仕事はほとんどなくなりました。
一時、食糧事情がわるいということで、各自で工面(くめん)することになり、四人または五人単位で班が編成され、夜な夜な付近の芋畑へ出かけるようになりました。
一晩じゅうあさりつづけて、やっと一食分の芋を掘り出すことができた班はまだいいほうでした。
ほかの班が、細いけれどもいくつかの芋を炊いて分けあっているころ、まだ照明弾や艦砲におびえながらむなしい努力をつづけている班もありました。
こうしたなかでとうとう、高江洲(たかえす)美代さんが砲弾の破片を背中に受けて負傷したのです。
この危険な仕事も結局五日目ごろにはとりやめになり、私たちはほっとしました。
5 艦砲射撃で死者が top
班が編成されたころから、私たち治療班の田場其枝(たばそのえ)、岸本ヒサ、仲里順子と私の四人は、みんなのいる壕から五メートルほど離れた、銃眼のある小さな壕に入っていました。
衛生兵が二、三人と軍属のおばさんが三、四人に私たちのあわせて十数人でした。
「く」の字型をした穴で、角になっているところに銃眼があり、そこからは山城、喜屋武(きやん)一帯の丘がながめられました。
すぐ前方の糸満への一本道の県道を、荷物を持った住民たちが群れをなして駆けぬけていく姿も見えました。
五月下旬からなだれこんできた軍隊に壕をうばわれ、隠れ場所を失った住民たちが西へ西へと避難していくのでした。
ときおり飛行機が低空を飛び、人の群れを襲うかのように見えましたが、列はつぎからつぎへとつづいていました。
そんなある晩、久しぶりに食糧運搬作業がありました。
「今日はほんとうによかったね、一人だって犠牲者が出なかったもの。よくまあ全員無事で帰れたわね」
帰ってきたばかりの友は口々にそう言って喜びあいました。それは月の澄んだ晩でした。
「ああ、暑い暑い。からだでも拭いてこようかしら」
ふと田場さんが言いました。
ちょうど衛生兵が二、三人、近くの井戸端から手ぬぐいをしぼりながら上がってきたところでした。
「よしなさいよ、いつ艦砲が飛んでくるかもしれないのに」
と私たちは止めましたが、ほんとうにむせかえるような六月の暑さでした。
「あの危険のなかを無事に抜けきていながら、こんなところでやられるなんて、まったくつまらないことよ。ねえ、なかへ入りましょうよ」
仲里さんはしきりになかへ入りたがっていました。
しかし、あたりは静かで、願っても艦砲など飛んでこようとは思えませんでした。
「暑くてやりきれないわ。だいじょうぶよ」
私たちはたおものんきな笑い声をたてて話しあっていました。
「あなた一人で入っていらっしゃいよ。私たちもう少し涼んでいたいわ」
そう言っても、仲里さんはなかなかききません。
私たちはとうとう負けて、壕のなかヘ入ることにしました。
「この人がこわいって言いますから、お先に」
外に残った衛生兵や軍属の人たちにこんな冗談を言いながら、なかへ入りました。
なかといっても、わずかに二、三メートルくらい下のほうへ斜めになっている穴でした。
なかには、軍属のおばさんが二人に、兵長、ほかに衛生兵が二、三人人っているばかりでした。
私たち四人は、少し横に曲がったところの土の上に草を敷いて、土壁によりかかり、重なるようにして横になりました。
それから七、八分経つたでしょうか。
突然、耳もつぶれるばかりの破裂音とともに、はげしい振動が起こりました。
天井の上がパラパラと落ちてきます。はっとして私たちは一度にとびおきました。
「かなり近かったようだが」
兵長はそう言って横になったようでした。
「おや、話し声が聞えないぞ。やられたかな」
しばらくたっても、壕の入口からはなんの音も聞こえません。
「一の壕に退避したかな」
「いや、そんな時間はなかったはずだ。直前まで話し声が聞こえてたもの」
兵長らはしきりに案じていましたがやがて、
「しかたがない。いつまでも出てやがるから」
そう言ってまた横になりました。私たちは抱きあったまま、おそろしさに身ぶるいしました。
「ああ、もう少し遅れたら、私たちもいっしょだったんだわ」
口には出せませんが、同じ思いで四人はかたく手をとりあったまま身動きもしませんでした。
あたりはしんしんとして、前よりいっそう静かにふけていきました。
そしてついに、翌朝まで着弾の音は聞こえませんでした。
「おい、出てきて木の枝をかぶせてくれよ」
という声に、私たちは銃眼からはって出ました。
まだすっかり明けきらない海の向こうには、うすぼんやりと米軍艦のマストらしいものが見えます。
衛生兵はシャベルで土を掘りながら、「まったくひどいよ」と話しています。
私たちはおそるおそる入口のほうへ行ってみました。
「あっ」
私たちは、二の句がつげませんでした。
衛生兵が両足を持って引きずってくる死体には、首もなければ両腕ともありません。
残った胴体は一糸まとわず、それどころか肉さえちぎりとられて、助骨(ろっこつ)がむきだしになっているのです。
腕がとび、足がちぎれ、四肢散乱(ししさんらん)のありさまはあまりに残酷でした。
兵三人と軍属の女性一人の四人がやられたのです。
とうとう頭は一つも探しだすことができませんでした。
入口の土壁には、血しぶきと肉片がくっついていて、いくら削り捨ててもその死臭は消えませんでした。
その後、治療班の四人は一の壕にもどりました。
6 馬乗り攻撃を受ける top
日一日と切迫する危険のまっただなかにおかれ、このころでは昼はもちろん夜といえども、壕の外に出ることはまったく危険きわまりないことでした。
早朝と夕方にきまって撃ちだされる迫撃砲が、しだいに身近にせまってくることがわかるのです。
そのなかで、「今日も無事だった」と、一日ながらえた生命を、私たちは心からいとしく思いました。
死は時間の問題と思いながらも、やはり一日一日と生きのびるうれしさは禁じえませんでした。
しかし、最後のときは意外に早くきました。
六月一八日午後二時ごろ、銃眼にいた生徒が、
「壕の上で英語の会話が聞こえる」と知らせてきました。
馬乗り攻撃(壕の上に敵兵が陣どること)を受けたのです。
突然おそいかかる身の危険に、私たちは一瞬声が出なくなりました。
壕の人口にあふれていた人たちも、無言のうちに奥へ奥へとつめかけてきました。
幅一・五メートル、長さが延べ二〇メートルくらいの曲がった穴に、私たちだけでも四十数人、それに軍医、衛生兵、看護婦らを合わせておよそ六〇人がぎっしりとおさまっているのです。
身動きもできない穴のなかで、咳(せき)一つもらさぬようにと息をこらし、むせかえるような暑さに大つぶの汗が頭から足先へとたらたらと流れていきます。
顔の見分けもつかぬくらい暗い壕のなかで、恐怖のために、ほとんど硬直したかと思われるほどの重苦しい沈黙が、何時間か過ぎていきました。
「ああ……、うう……」
ふと、嘆息と倦怠(けんたい)とをいっしょにしたような声が、一隅におこりました。
「しっ……」
とたしなめる人もいますが、それをきっかけに、
「はあ……」
「やりきれないわ」
という嘆息の声があちらこちらにおこりました。
そしてふたたび壕の入口へあふれ出ていく人もあらわれました。
ババンー
突然、けたたましい音が聞こえました。
まわりはまたもとの静けさにかえりましたが、入口のほうが少しざわついているようです。
「治療班のかた、来てください。宮城美智子さんがやられました」
と言う声が聞こえます。
「ああ、とうとう犠牲者を出してしまったのか」
人びとはふたたび奥へとつめかけてきました。
通路もふさがっているので、治療器具を手渡しで送って、入口のほうで手当をしてもらうことにしました。
しらじらとした沈黙のなかに、「う……うん」と、通路に寝かされた宮城さんのうめき声がいっそう痛ましく聞こえてきます。
「かわいそうに」と口々に言いながらも、身動き一つかなわないほど重なるようにすわっているので、どうすることもできません。
先にようすを見に出た一等兵の話では、二人の米兵が銃をかまえてうしろ向きに座っていて、手榴弾(しゅりゅうだん)でも投げてやりたいほどの近さだが、もしうまくいかないときには、こちら六十数人の生命が危ないので軽はずみな行動はできなかったとのことでした。
「今夜のうちにここを出なければいけないだろう」
だれが言うとなく、そんなことをささやきあって、私たちは手荷物を整理しはじめました。
着替えをほんの一、二枚救急カバンにおしこんで、文字どおり最小限の持ちものでした。
7 伊原第一外科壕へ top
やがて、主任軍医の目大尉から「日が暮れたらただちに壕から脱出すべし」との達しがあり、ガーゼニ反と海軍用のビスケット二枚が全員に配給されました。
「どこまでもいっしょにね」
と私たちはかたく約束しあって、日の暮れるのを待っていました。
「生徒から先に出るように」とのことで、私たちは入口の擬装棚の下へ出ていきました。
日はとっぷり暮れて、すでに照明弾が打ち上げられていました。
「敵兵の姿が見えなくなったから、出るのはいまだ」
斥候(せっこう)に出ていた一等兵の声で、私たちはいよいよ出発待機の姿勢で入口へ向かって順に並びました。
「足音が聞こえてはいけないから、かならず一人ずつ、五メートルの間隔をおいて出ること。
部落の道へ出るまでは、畑の溝にそってはって行くこと。
行く先は各自にまかせるから、第一外科、第三外科いずれへでも行きたいところへ行くように」との注意がありました。
照明弾が散ったあとはまっ暗やみです。
すでに敵の入りこんでいるこのあたりを、行く先もきめず、しかも単身投げ出されることはあまりに心細いことでした。
「どうなろうとも、この壕にとどまることをゆるしてくれたら」
こんな気持ちにさえなりましたが、負傷者の高江洲さんと宮城さんのほかは許されるはずもありませんでした。
つぎつぎと打ち上げられる照明弾の光で、部落への道は真昼のように照らしだされました。
出てはしりごみ、出てはしりごみしているあいたに、はやくも一〇時近くなっていました。
「なにをぐすぐずしているのだ。おまえたちが出ていかないと、この壕は明朝までに全滅なんだよ」
追いたてるような冷たい声に、私たちの頬(ほお)にはくやし涙があふれてきました。
「先頭のほう出てちょうだい。どうなってもかまわないわ」
私たちは一瞬おそろしさを忘れて、脱出を開始しました。
私は岸本さんと手を取りあって、ちょうど照明弾のうすれたところを小走りに走って出ました。
さいわいに、木かげのある曲り角まで一気に行くことができました。
そこで、先に待っていた二、三の友と後から来た田場さんだちと六、七人になったので、いくらか心強くなり、「どうせやられるならいっしょだわ」などと言いあいながら、畑のなかの一本道を急ぎました。
ババン、ボボン。照明弾はひっきりなしに上がっては消え、消えてはまた上がりました。
二人、三人と手をつないだまま畑の溝にへばりつき、なるべく低いほうへところがりこみます。
一走りに二、三メートル進むだけで、伏せている時間のほうがはるかに長いのです。
やっとつぎの部落へさしかかると、道の両側に高い木が茂っていたので、照明弾に照らされながら歩きつづけました。
ある三叉路(さんさろ)へくると、そこは砲弾のためにすっかり穴だらけになっていて、付近にはモンペ姿の女性や、子供をおぶったままの人たちが倒れて息絶えています。
「まっすぐだったかしら」
「左のような気もするわ」
暗いなかを一、二度通ったことのあるだけの私たちは、はっきり道を覚えていませんでした。
道の十字路にはほとんど定期的に着弾するので、立ち止まって考えることはひじょうに危険でした。
一〇メートルくらい走っていっては、「ここじゃない」と引きかえし、こんどは左へ走ります。
突然、あまり近くないところで着弾の音がしたと思うと、ヒューヒュルヒュル、ヒューヒュルヒュルと不気味なうなりをたてて、なにかが近くせまってきます。
破片が落ちてくる音です。
一〇秒も土手にへばりついていると、ヒュール、ガチャッと二メートルくらい離れた岩に当たる音がしました。
ほっとして歩きだすと、こんどは照明弾が三、四発も同時に上がりました。
ちょうど一〇〇ルクスの電灯の明るさです。
思わず伏せると、なにかやわらかい塊(かたまり)の上のような感じがします。
と同時に、プーンと鼻をつく死臭に「あっ」と叫んでとびのきました。
光にすかしてみると、のどに血を浴びた死体でした。
光のうすれるのを待って、がぱっとはね起き、急いでそこを離れました。
しばらく行くと、片側のくぼ地にふと灯火が細くもれています。
「壕だわ」、私たちは喜びと安堵(あんど)に声をはずませました。
「もしもし、このへんに女学生の壕をご存じありませんか」
「さあ、知りませんね」
私たちはがっかりして道にしゃがみこみました。
とたんに、バババンーと着弾の音がしました。
「あぶない」と叫んで木立のなかに身を寄せると、パチパチ、ガサガサと木立の奥で破片の落ちる気配がしました。
「そんなところにいるとあぶないですよ」と言われ、しかたなくまた走りました。
切割りの道を通りかかると、両側の岩や土塊がくずれていて、その上にも下にも数人の死体が折り重なっています。
たまらない臭気に、私たちは急いでそこを通り過ぎました。
坂道を少し下ると、また右側のほうに灯火が見えます。
かすかな望みをいだいて、私たちは灯火のほうへ走りよりました。
穴のなかをすかして見ると、ここにも兵隊が右往左往しています。
「もしもし、女学生の壕がこのへんにないでしょうか」
「さあ、知らんですな」
そっ気ない返事に、私たちはもう立ち上がる元気さえなくなってしまいました。
「今晩だけ泊めていただけませんか」
「ああ、いいですよ。ぼくたちはこれから出かけますから」
「えっ、どうして」
「ここももうあぶなくなりましたからね。しかし明日の朝まではだいじょうぶでしょう」
「ああ」
私たちはため息とともに土の上に座りこんでしまいました。
だれ一人、口をきこうとする人はいません。もうなにを考えるのもおっくうでした。
しばらくして、上の道で人声がします。細い女の人の声です。私たちは、はっとしてふりかえりました。
「もしもし、女学生ではありませんか」と聞くと、
「ええ、第一外科です」と言います。
「まあ、よかった、よかった」
私たちは涙の出るほど喜びました。
「兵隊さん、おじゃましました」とのあいさつもそこそこに、上の道へ走り上がりました。
|

伊原第一外科壕
|
 伊伊原第一外科壕の遺骨収集 伊伊原第一外科壕の遺骨収集
|
聞けば、波平(なみひら)の第一外科壕もくずれて、いま伊原(いはら)の壕へと出てきたところだというのです。
喜びはずんだ心もつかのま、ふたたび不安と恐怖の念に私たちの胸はしびれるほど痛くなりましたが、
「だいじょうぶよ。伊原の壕はすぐ近いんだから」とはげまされ、さっき通った道をまた引きかえしました。
たしかな道案内ができたので、いくらか心強くなり、友の荷物を手伝ったりしながら道を急ぎました。
民家の近くを通りかかったとき、四メートルほどうしろに艦砲が着弾しました。
私たちは一目散に走りだしました。と、また着弾。
こんどはすぐそばの民家に命中して、目の前は一瞬火の海になりました。
気がついて無事だとわかると、私たちはとびおきて走りつづけました。
艦砲は一定の間隔をおいて私たちを追ってきます。まったく絶体絶命です。
方角を考える暇もなく、足の向くままに走りつづけていくと、行く手に屏風(びょうぶ)のような岩が立ちふさがっています。
そこで道が消えてしまっているのです。
「まわれ右!」
先頭の声に、私たちは引きかえしました。
岩から五メートルくらい退いたとき、砲弾はみごとに岩に命中しました。そして、破片が乱れとんだのです。
「こんどはだいじょうぶ。たしかにこの道たった」
佐和田(さわだ)さんの声で、私たちは本道からはずれた小道を小走りに行きました。
「ああ、ここよ。やっときたわ」
の声に、一同はほっとしてかけよりました。
暗やみで入口はわかりませんが、たしかに奥のほうでざわめきが聞こえています。
手さぐりで奥のほうへと入っていきました。
じめじめした暗い通路をなんどもすべりながら下りていくと、照屋先生、大城(おおしろ)先生の声が聞こえてきました。
「先生、お久しゅうございます」
「よう、元気だったか。さあ、ずっと奥へ入りなさい」
照屋先生の変わらない明るい声でした。
一段一段下りていくと、そこは大広場で、光の届いているだけでも一〇〇人くらいを収容できる広さでした。
「まあ、こんなりっぱな自然壕」
私たちはすっかり安堵(あんど)して腰をおろしました。
ちょうどそこでは、仲宗根(なかそね)先生が整列した生徒たちを前に、なにか熱心に話しているところでした。
思えば何十日ぶりだろう、おおぜいの友がこうしていっしょに整列して師の言葉に耳を傾けているのです。
その光景に私は思わず涙があふれました。
私は、どうにかして先生の話を聞きとろうと努めましたが、あたりの雑音に消されてなに一つ聞くことはできませんでした。 そのうちに、極度の緊張と不安からきた疲労が、睡魔(すいま)となっておそってきました。
どのくらいの時間がたったのでしょうか。名前を呼びあう騒音で、目を覚ましました。
ふと気がつくと、人びとはぞろぞろと出口のほうへつづいています。
仲栄真(なかえま)先生に引率された一高女の生徒が、隊を組んで私の目の前を上っていきます。
「みんなどこへ行くんでしょう」
軽い胸さわぎがして、そばの人にたずねました。
「もうそろそろ夜が明けるので、いまのうちに各自壕をさがして出ていくんでしょう」
「まあ、どうして? こんなりっぱな壕から出て、はたしてもっと安全なところがあるのかしら」
「まあ、のんきな人。あなたはなにも知らないのよ。
昨夜、学徒動員が解散になって、みんな自由行動ってことになったのよ。
この壕もあぶないから、各自で安全な場所を探していくようにって。
仲宗根先生がお話なさったのは、そのことだったんじゃありませんか」
「え? 解散?」
まったく青天のへきれきでした。
「そう」
私は深いため息とともに、つめたい悪寒(おかん)を背筋に感じました。
top
**************************************** |
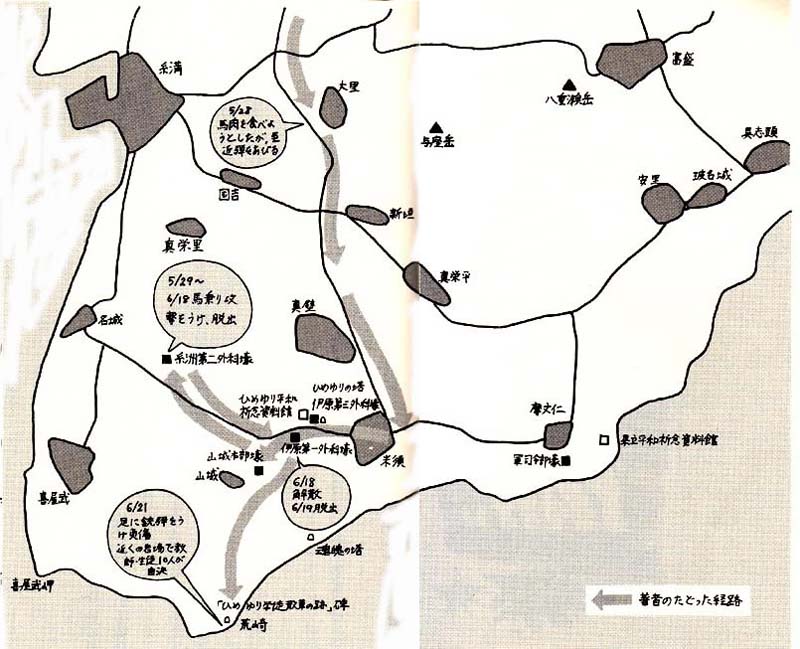






 伊伊原第一外科壕の遺骨収集
伊伊原第一外科壕の遺骨収集