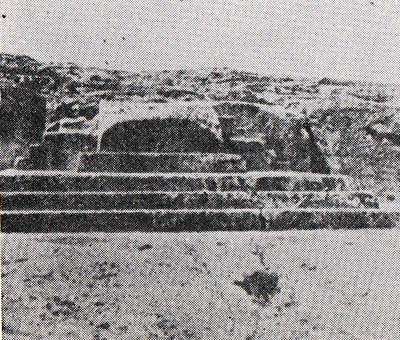|
****************************************
IIndex 概要
釈迦
孔子 ソクラテス
キリスト
マホメット
1 知識ほど良い物はない top
ソクラテスは、クレイニアスという青年を相手にして、つぎのように語っている。
「クレイニアス君、我々人間は、すべて幸福を欲するだろうか。
それとも、欲しない者もいるだろうか。」
「幸福を願い求めない人はいないでしょう。」
「では、我々はどうすれば幸福になれるのであろうか。まず、良い物がたくさんなければなるまい。」
「そうだと思います。」
「さあそこで、我々のもっているどのようなものが、良い物であるといえるのだろうか。ともかく、金持ちであることをよいと思わない者はなかろう。」
「誰でも、そう思うにちがいありません。」
「また、健康であること、美しくあること、家柄の良いこと、権力、名誉などのあることも、良いことだと思うだろうし
「それを良くないと思う人は、おそらくいないでしょう。」
「わしは、まだほかにも良いことはたくさんあると思う。思慮深いこと、正義、勇敢などだ。これらも善とするべきではないだろうか。」
「もちろん、そうするべきです。」
「そこで君に聞きたいのだが、このような良い物が備わってさえいれば、私たちは幸福になれるのだろうか。
たとえば、食べ物がかりにたくさんあっても、それを私たちが食べない場合、または、飲み物があっても飲まない場合などでも、私たちは何かの点て利益をうけることがあるだろうか。」
「まず、ないと思います。」
「それでは、お金や権力や、そのほかの良い物をもっていても、それらを使わないときはどうだろう。」
「いくら良い物を多くもっていても、使わなければ、何にもならないと思います。」
「そうすると、幸福になろうとする人は、ただそのような良い物をもっているだけではなく、それらを使わなければならないということになるわけだ。」 |

ソクラテスの像
|
「確かに、おっしゃるとおりです。」
「しかし君、それだけで人間は幸福になれるだろうか。良い物をたくさんもっていて、それを使うというだけで………。」
「私は幸福になれると思います。」
「人がそれを不正に使ってもか。」
「いいえ、正しく使えばです。」
「そこをハッキリさせておかないといけないのだ。
不正に用いるくらいなら、何もしないでいるほうが、はるかによいのだから。」
「それは、もちろんそうです。」
「そこで聞きたいのだが、良い物を正しく用いるにあたって、一番必要なのはなんだろう。
私は知識だと思うのだが、君はどう思うか。
たとえば大工が仕事をし材木を使う場合には、大工に材木を正しく使わせるのは、大工の建築の知識である。
私たちが今までに話してきた富や健康や権力を用いるのにも、知識がなければ正しく用いられないと思うが、どうだろう。」
「おっしゃるとおりだと思います。」
「そうすると、知識はどのようなものをもち、どのような行ないをする場合にも、人々に幸福をあたえ、まわり合わせを良くするといえるのではないか。」
「確かに、そういえると思います。」
「また、反対に、知識を欠いているならば、どんなに良い物をもっていても、何の役にもたたないわけだ。
つまり、クレイニアス君、私たちが最初に善であるといったものは、無知な者や悪人が用いれば、かえって悪い結果をもたらすものとなり、知識のある人が用いれば、いっそうよい結果を生むものになるのだから。」
「ごもっともです。」
「だから、結論としては、知識ほど良い物はなく、無知ほど悪い物はないということになるわけだ。」
ソクラテスによれば、金銭や名誉や権力はかならずしも人間を幸福にするものではなく、それが幸福に役立ちうるためには、知識を必要とするということになるのである。
さて、それでは人間を幸福にするのには、何についての、どのような知識が必要なのであろうか。
ソクラテスの教えを受けたアルキビアデスという人は、
「ソクラテスは平凡な事ばかりをいっているようにみえるが、よく考えてみると、彼の言葉のなかには、およそすぐれた人間になろうとする者が、考えるにふさわしいようなことは、大部分、いや、むしろ全部がふくまれていることがわかる。」
といっている。
確かに、ソクラテスは平凡なことしかいわない。
クレイニアスという青年との問答においても、彼のいっていることは、まことに当然の事ばかりである。
しかし、考えさせられる。彼と話をする者は、ほとんど一人の例外もなく、
――そういえば、そうだな………――と、あらためて考えさせられてしまう。
そして、よく考えてみると、大切な問題をうっかり見のがしていたことに気づく。
おそらく皆さんのうちにも、ここにあげた問答を読んで、
――そういえば、そうだな………――と思った人がたくさんいるに違いない。
人間は誰でも幸福を願い求めている。しかし、
「幸福になるためには、何についての、どのような知識が必要なのか。」
などと質問されたならば、大抵の人が満足には答えられないであろう。
私たちには、わかっているつもりでいながら、実際にはわかっていないことがたくさんあるのだ。
ところが、ソクラテスという人は、一見まことに平凡な話し合いを通じて、それをハッキリと気づかせてくれるのである。
しかも、彼が気づかせてくれることは、私たちが生きていくうえに大切なことばかりだといえる。
彼の波瀾の生涯をたどりながら、私たちの人生の重大問題をひろいあげて、徹底的に考えてみようではないか。
2 デリオンの戦い top
地中海のまんなかには、長ぐつの形をしたイタリア半島がつきでている。
そのすぐ右側には、骸骨の手のような形の大きな半島か南北にのびている。
これがギリシア半島で、アテネ市はこの半島の東側の先端に近いところにある。
ソクラテスは、このアテネ市に紀元前四七〇年(一説には四六九年ともいわれる)に生まれた。
その頃のアテネは、世界第一の海軍力をもち、交通と商業の発展によって、政治的にも経済的にも、ギリシア全土の一大中心地をなしていた。
その面積からいっても、ギリシアの都市国家(都市でありながら国家的性格をそなえているもの、今のシンガポールやバチカン)のなかで一番大きく、日本の佐賀県ぐらいの広さがあった。
ソクラテスの誕生に関してはおもしろい話は何もない。
父親は石像の彫刻師で、母親はお産の手伝いが大変にじょうずだったというだけのことで、彼の劇的な死に方にくらべてみると、全く平凡な生まれ方をしている。
竜が雨を降らせたとか、大きな星が急に輝きはじめたとかいうような奇跡は、一つも伝えられていないのである。
幼少時代の記録も全くのこされていない。
しかし、青年期以後の資料や記録から考えると、彼はその当時の教育を、充分に受けられるだけの家庭に育ったと思われるのである。
その頃の学校教育は、日本の場合とほぼ同じようで、七才からはじまった。
しかし、日本の小学校とは違って、授業の主な課目は体操と音楽しかなかった。
読み書きや歴史などは、音楽の時間に詩文をとおして教えられた。
体操は主として五種(跳躍、競走、円盤投げ、槍投げ、すもう)にわかれ、男の子たちはこれらの運動によって体を鍛えるとともに、勇気と忍耐力を養ったのである。
ソクラテスが、生まれながらにすぐれた素質をもっていたとしても、彼はほかの子供たち以上に真剣に心身を鍛えたに違いない。
大人になってからの戦揚における彼の目ざましい働きぶりはおそらく、学校時代のきびしいトレーニングと無関係ではないと思う。
ソクラテスは生涯の間に四度戦争に参加したが、紀元前四二四年(四十七才)のデリオンの戦いにおいては、勇気と忍耐力の手本を示すような大活躍をした。 |

ギリシアの地図

今日のアテネ
|
アテネ軍の守る砦が猛火につつまれて、全軍総くずれとなって敗走しつつあるとき、追いせまる敵兵をランランたる目でにらみつけながら、ゆうゆうとしりぞいていく二人の勇士がいた。
アテネ軍の指揮官、アルキビアデスが馬上からふと見ると、ソクラテスと彼の親友ラケスである。
三方に敵をひかえて、ソクラテスはびくともしない。一歩、一歩と落ち着いて退却していく。
白刃をふりかざす者も、槍をかまえる者も、この男にはうちこむすきが見いだせないのだ。
左右をわれさきに友軍が敗走していく。敵兵がそれに追いすがる。
見る間に死体が山ときずかれていく。鼻をつく血なまぐさい臭い、悲痛な叫び声、すさまじい乱戦だ。
そのまっただなかにいながら、ソクラテスの周囲にだけは無気味な静けさがある。
味方といえばラケス一人しかいない。
しかし、ソクラテスの敵兵を射るような眼光、その堂々たるからだ全体に満ちあふれる勇気が、むらがる敵兵を近寄らせないのだ。
とっさにソクラテスの危機を見てとったアルキビアデスは、
「力を落とすなっ!」と大声でさけぶと同時に馬首をめぐらせた。
アルキビアデスは自分が一軍の指揮官であることもわすれて、逃げ去っていく味方の命を守るために、ソクラテスとともに敢然として敵兵に剣をかまえた。
ときおりパッと燃えあがる砦の火が、三人の勇士の姿を夕ぐれの戦場のなかに赤々と照らしだす。
冷たい冬の空にたちこめるモーモーたる煙、やがて沈もうとする夕陽までが血の色をしている。
左右をかためる二人の味方と一緒に、ソクラテスはルイルイと横たわる死体をふみわけ、一歩、また一歩と後退していく。
そのたびごとに、敵兵の白刃が風になびくススキのように、いっせいに動く。
しかし、斬りこんではこない。うかつに斬りこむならば、たちまち手ごわい反撃に合わねばなるまい。
これが敗軍の兵なのか。勝ちいくさに気負いたつ敵兵を圧倒してしまっているではないか………。
やがて、吹きすさぶ風が、はるかに見える砦の火をひときわ赤く燃えあがらせたとき、ソクラテスは退却の足をはやめた。
友軍の大半が後退し終わったのを見きわめたからである。
戦いがひらかれてから十五日めに、デリオンの砦は完全に敵の手に渡ってしまった。
アテネ軍の被害はまことに甚大であった。
一千名にのぼる戦死者、捕えられた者二百余名、そのほか数えきれないほどの負傷者、生残った者は、命からがら船で本国へ逃げ帰るというしまつであった。
この惨憺(さんたん)たる敗戦のさいのソクラテスについて、アルキビアデスとラケスはつぎのように語っている。
「デリオンからの退却のとき、すべての将兵がソクラテスと同じ態度をとったならば、わが軍はけっしてあのような大敗はしなかったであろう。
ソクラテスは戦いのまっただなかにいながらも、落ち着いて敵と味方の情勢を注意深く見守っていた。
そして自分の身の危険をかえりみず、味方の安全を保つために、追ってくる敵を勇敢にさえぎりつづけたのである。
死を恐れないその堂々とした態度には、敵兵も全く手を出すことができなかった。
私たちが全滅をまぬがれたのは、一にソクラテスのおかげであるといえよう。」
この話は、ソクラテスの生来の素質と学校時代に養った勇気と忍耐力とを、あますところなく物語っているといえる。
彼は出陣するたびごとにめざましい働きを示した。
しかし、ソクラテスは軍人だったわけではない。
それでは何者だったのかというと、一口で説明するのはまことにむずかしい。
当時のアテネ市民の間でさえも、ソクラテスについては意見や評判がマチマチで、大いにほめる者もいれば、盛んに悪口をいう者もいたのである。
約二千四百年前のアテネ人たちにとっては、ソクラテスという人物は一つの大きな謎にひとしかったのだ。
しかし、今日の私たちにとっては、それは解くことのできない謎ではない。
ソクラテスは、釈迦やイエスなどと同じく、自分自身では何も書き残さなかったが、彼の弟子や友人などの書いた忠実な記録を手がかりとして、私たちはソクラテスの真実の姿に近づいていかれるのである。
3 私は自然科学には適さない
top
当時のアテネでは、男子はおよそ十六才になると学校へいくことをやめる。
そしてその二年後には同族組合の者たちによって検査を受け、青年団員となって市民としての待遇を受けるようになる。
このときには神にいけにえを捧げ、共同の食事をしてそのお祝いをすることになっている。
そして二十才になれば、法律上のすべての権利を行使できるようになる。
この点だけは現在の日本の場合と全くひとしい。
ソクラテスも中流以上の家庭の子弟と同じように、このような過程をへて成長していったにちがいない。
そして、勉強や体育のあいまにはギリシアのすぐれた悲劇やオリンピアの祭典に、青春の胸をときめかせたことであろう。
今日のオリンピック大会はスポーツ競技だけにかぎられているが、その当時は体育大会と芸術祭をかねたものであった。
拳闘、すもう、槍投げ、跳躍、競走などの競技とともに、詩の発表、劇、音楽のコンクールなどが行なわれていたのである。
この祭典は紀元前七七六年にはじまって、紀元三九四年になるまでの千年以上の間、四年めごとに行なわれていた。
そして、ソクラテスの若いころがもっとも盛んだったのである。
たとえ都市国家のあいだで戦争が行なわれていても、祭典のある年には「神の休戦」として約一か月のあいだ戦闘を中止し、こぞってこの祭りに参加したほどであった。
ギリシア全土をあげてのこの祭典は当時のギリシア民族の信仰と伝統の発展のために、欠くことのできない大行事だったのである。
ソクラテスが二十四、五才になった頃には、アテネは東地中海の制海権を一手におさめ、ますます栄えていた。
理想的な民主政治(といっても戦争で得た捕虜を奴隷として使っていたのだが)のもとで商工業が非常に発達し、貿易と植民が盛んに行なわれていたのである。
この繁栄の地アテネを目ざして、アジア、アフリカ、ヨーロッパの各地から、言葉も信仰も服装もちがう人々が続々とつめかけてきた。
ソクラテスは、それらの外国人に深い関心をもった。彼らと貿易をすることがアテネの富を増大させたからではない。
彼らが未知の国の人であり、思いもよらぬ知識をもっていたからである。
彼らの話はしばしばソクラテスを驚歎させた。
そして、彼の生まれながらの探究心を火のように燃えあがらせた。
とりわけ、青年ソクラテスの心を奥底からゆり動かしたのは、エーゲ海の対岸にあるミレトスや南イタリアなどから訪れてきた有名な学者たちであった。
ソクラテスは、これらの人々を一人ひとり訊ねまわり、彼らの話す自然科学的な理論や批判的な心のの考え方を熱心に学んだ。
しかし、「世界は何から成りたっているのか」「万物の根源は何か」「世界は平らか、それとも丸いか」などの問題について研究を進めているうちに、ソクラテスは、呆然(ぼうぜん)としてしまった。
いろいろな学説が、それぞれ著しく矛盾していることを知ったからである。
もっともおどろかされたのは、地球の形について、東西の学説が全く一致していなかったことである。
つまり、東方の学者たちは地球は平らなものであると主張し、西方の学者たちは丸いと説いていたのである。
これらの矛盾する学説に接して、ソクラテスの迷いは深まり、疑問はふえる一方であった。
やがてソクラテスは、
――それぞれ説を異にする学者たちのうちで、誰か一人が正しいとすれば、ほかの学者はみな間違っているということになる――と思うようになり、
――どうしても納得できる学説が見い出せないところをみると、私はこの方面の研究には向いていないのだ――という結論に達して、数年来の研究を中止してしまった。
これは、彼がおよそ二十七、八才ごろのことと思われる。
ちょうどこの頃、アテネ市およびその周辺の諸国に、自ら「ソフィスト(賢い人、知者を意味するギリシア語)」と名乗る一群の学者たちが現れてきた。
彼らは自分でソフィストと袮するだけあって、大変に博識であり、そのうえ、自由自在に言葉をあやつるコツを心得ていた。
ひとつその実例をあげてみょう。
これはあるソフィストと一人の少年との問答である。
言葉の魔術にひっかからないように、特別に気をつけながら読んでいただきたい。
「ものを学ぶのは、賢い人か、それとも愚かな人か。」
「賢い人です。」
「それでは聞くが、学ぶときには、人は学ぶことを知っていて学ぶのだろうか。」
「いいえ、知らないから学ぶのです。」
「では、ものを知らない人は賢い人か。」
「賢い人とはいえません。」
「賢くない人は、つまり、愚かな者だということになるだろう。」
「そうなります。」
「そうなれば、ものを学ぶのは賢い人ではなくて、愚かな者であるということになってしまうではないか………。
君の最初の答えは間違っていたわけだ。」
「わかりました。ものを学ぶのは、確かに愚かな者です。」
「しかし、先生のいうことをよく学ぶのは、賢い子だろうか。それとも、愚かな子だろうか。」
「賢い子です。」
「では、ものを学ぶのは賢い子で、愚かな子ではないということになるわけだ。
そうだとすると、君のいまの答えも正しくなかったことになるではないか。」
どこに誤魔化しがあるか、おわかりになったろうか?
わからなかったら、もう一度読みなおして、よく考えてみていただきたい、
これはほんの一例にすぎない。ソフィストたちは、
「どんな問題をたされても答えることができる。」
と自慢してあらゆる問題に口をさしはさみ、立て板に水を流すようにまくしたてたのである。
彼らはアテネを中心にいろいろな国をめぐり歩き、一時はいたるところで大歓迎を受けた。
特にアテネでの人気はたいしたものであった。一体どんなわけで、彼らは人気をえたのであろうか。
4 「四つの理想」より以上に
top
当時のアテネでは、市民は誰でも議会に列席する資格をあたえられており、能力のある者はどんな地位につくこともできた。
家柄や職業に関係なく、大臣にでも長官にでもなることができたのである。
万事が多数決によるのだから、大勢の人を納得させるような話の仕方ができさえすれば、立身出世は望みしだいだったのだ。
皆さんも、日本の選挙や国会の議論などでよくごぞんじであろう。
社会や政治の問題にはいろいるな考え方や意見があって、どれが本当に正しいのか、なかなかわからないものである。
そういうときには、意見が正しいかどうかということよりも、とかく、話のうまい人のところに賛成の票が集まってしまう。 この点については、アテネでも全く同じだったわけである。
ところで、ソフィストたちは、
「公の場所での、もっともすぐれた話し方。」
「どうすれば、有能な市民となって出世することができるか。」
というようなことを、月謝さえはらえば、教えてくれたのだから、出世を望む人々にとってはまことに便利な存在であった。
彼らは自然科学者たちとは違って、日常生活に縁のないことや、役にも為(ため)にもならないようなことは全く問題にしなかった。
これは彼らが物事を相対的にしか考えなかったからにほかならない。
たとえば、あるソフィストは、
「真理は、絶対に正しいものが一つだけあるのではなく、各人に正しいと思われることが各人の真理である。」
といっている。
つまり、何事もそれぞれの人の考え方しだいだというわけである。
自分が正しいと思ったことは、ほかの人が何といおうと正しい、というのだから、きわめて乱暴な考え方だといえよう。 こういう考え方にたいして、ソクラテスは深い疑問をもった。 |
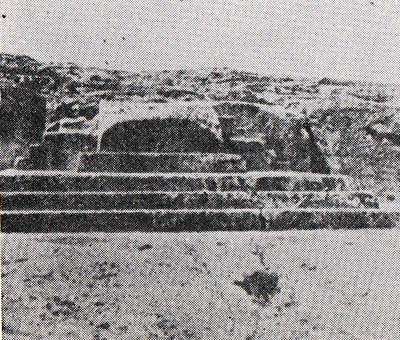 |
|
民主政治の象徴、
演説壇の遺跡(上)と、
投票具(右)。 |
 |
――はたして、人間の心や社会のなかには、ソフィストたちのいうように、相対的なものしかないのであろうか。
党派の違いや金銭上の利害にかかわりなく、誰もがうなずけるような真理はないのであろうか。
いや、あるはずだ。
人生は、考え方や言い方しだいで、どうにでもなるようなものであっていいはずがない。
個人のかってな意志や考えのままに生きるのが、どうして正しいといえよう。
すべての人がみとめることのできる善、誰もがかならずさけねばならない悪、それがなんであるかを研究しよう。
正義にせよ、幸福にせよ、私たちが人間として生きているかぎり、あらためて考えてみなければならない問題は山ほどもある。
人間はまず、人間自身のことを知らねばならないのだ。
私たちの精神をよくし、人生をいきがいのあるものにするのにはどうすればよいか。
それを見ざわめよう――
ソクラテスはこう考えて、人間の研究と正面から取り組んだ。
今まで天上に向いていた探究心が、百八十度の転回をして地上にふり向けられたわけである。
ところがソクラテスのこういう気持ちは当時のアテネ人には全く理解できなかった。
何故かというと、アテネ人の人生の理想は、
一、健康であること、
二、顔や姿の美しいこと、
三、悪いことをしないで金持ちになること、
四、よい友人を持って、いつまでも若々しい気持ちを失わないこと、の四つにつきていたからである。
彼らは、このほかに求めるべき真理や理想があるとは思っていなかったのだ。
ここにあげた四つの理想は、今日の私たちの人生にもそのまま通用する、いずれも願わしいものばかりである。 |

スポーツをたのしむ若者たち。紀元前6世紀の浮き彫り。
|
しかし、これだけそろっていれば、ほかのものは何も必要ではないだろうか。ことによると皆さんのうちにも、
――それだけそろえば、もう何もいうことはない――
と思うような人がいるかもしれない。そう思う人がたくさんいるとしても、少しも不思議ではない。
確かに、それだけでもすばらしいことなのだから、
ソクラテスにとっても、美や健康、良友や金銭などは、いずれも望ましいものであった。
その点では『彼と私たちとの違いはない。ただし、彼にはこの四つの理想より以上に、強くはげしく求めるものがあった。 それは、「人間はいかに生きるべきか。」にたいする正しい解答であった。
彼はこの解答を何よりも熱烈に、真剣に求めるようになったのである。
「私は、真理でないことを語るときには、おまえのいっていることは間違っていると、ハッキリ教えてもらいたい。
教えてもらえるときには、私は本当にありかたいと思う。
何故かというと、教えてもらう場合は、教える場合よりも、はるかに為になるからである。
ちょうどそれは他人の病気を治すより、自分の病気を治してもらうほうが利益が多いのと同じことだ。」という。
この言葉だけからでも想像できるように、ソクラテスは常に公正で謙虚な態度で、研究を進めていった。
彼にとっては、まじめに人生を考える人はすべて、彼のなかまであり、大切な協力者だったのである。
ソクラテスはしばしば市場や体育場のような、人のだくさん集まる場所へでかけていって、大勢の青年たちと熱心に問答をした。
また、ときには一人静かに川のふちや、オリーブの木陰にたたずんで、深卜思索にふけることもあった。
その真剣な態度はしだいに青年たちの好感をよびあつめ、やがて、彼らから非常に慕われ、尊敬されるようになった。
5 産婆術(さんばじゅつ) top
アテネの青年たちのソフィストへのあこがれや人気が、だんだんとソクラテスへの尊敬に変わりはじめた頃、ソクラテスはヒポクラテスという青年と、つぎのような話をしている。
「ヒポクラテス君、君はソフィストのところへいって、高い金をはらってまで講義を聞きたがっているようだが、君は一体、何になるつもりでそうするのかね。
たとえば君が有名な医者のところへいって、授業料をはらおうとしているとする。
誰かが君に、『何になろうとしてそうするのか』とたずねたら、君は何と答えるだろう………。」
「医者になるつもりだ。と答えるでしょう。」
「ではもしも、フィディアス(ギリシア第一の彫刻家)のところにいって授業料をはらおうとしているとすれば、どうかね。」
「彫刻家になろうとしてにきまっています。」
「では、君がソフィストのところにいくのは?」
「ソフィストになるため、ということになります。」
ヒポクラテスはこう答えて、顔を赤くした。自分の返答に自信がもてなかったのである。
「しかし君は、本心からソフィストになりたいと思っているわけではないだろう。」
「そうです、そういうつもりはありません。」
「君は、ソフィストから教養としての知識を学ぼうとしているのではないか。
かって国文の先生や、竪琴の先生について学んだ時と同じように、何もその道の専門家になるつもりではあるまい。」
「確かにそのとおりです。」
「しかし、君はソフィストとは何者なのか知っているのかね。」
「それは学識のある人のことです。」
「では何についての学識のある人かね。」
「雄弁な人間をつくることについて、だと思います。」
「君の答えはまだ充分ではない。ソフィストは何について雄弁な人間をつくる学者なのかね。」
「もちろん、ソフィスト自身が知っていることについてですよ。」
「そりゃあそうさ、ところで、ソフィストは何について知っているのだろうか。」
「どうも、これ以上は答えられません。わからなくなってしまいました。」
「ヒポクラテス君、君は、自分の魂をどんな危険にさらそうとしているのかわからないのか。
君は健康上のことについてならば、自分でいろいろと考えもしようし、また、しかるべき人にも相談するだろう。
ところが、君の幸福や不幸の基礎となるほど大切な魂を、ソフィストなどにまかせるべきかどうかを、よく考えてもいないし、誰にも相談してもいないようだ。
何の学者だかわかってもいない者に、君はきみ自身をまかせようというのか。」
「お話をうかがって、どうも軽はずみだったように思われます。」
「ヒポクラテス君、私にはソフィストというものは、魂を育てる商品の卸売人か、小売人としか思えないのだ。」
「どうも、おっしゃることがよくわかりません。魂を育てる商品とはどんなものなのでしょうか。」
「むろん、知識だよ。
ところがだ、ソフィストはからだの栄養品を扱う商人のように、自分の商品をむやみにほめて、私たちをだますようなことがないだろうか。
彼らは知識を諸国へもち歩いて売っているが、それが人間の魂に有益であるかとうかを、本当に知っているだろうか。
まして買うほうの君もそれを知らないのだから、まことに心細い話だ。
知識を買うのは、食料品などを買うのより、はるかに危険が大きい。
有害な知識は君を不幸にしたり、悪い人間にしてしまうからだ。」
ソクラテスのこういう話の仕方、つまり、質問をして答えさせ、さらにその答えにまた質問をして、しだいに人々の心のなかに自発的に努力する気持ちをよび起こしていく方法、この方法はのちに「産婆術」として広く知られるようになった。
なぜこの方法を「産婆術」というのかについて、ソクラテスは、みずからつぎのように語っている。
「知恵を自分で産むことは私にはできないのだ。
多くの人たちは、ソクラテスは他人に質問するだけで、自分は何もいわない。
これは知恵がないからだ、といって私を非難している。
まことにそのとおりなのである。
確かに私自身は少しも賢くないので、私のなかからは、知恵といえるようなものは全く生まれてこない。
しかし私と交際していると、初めはまことに愚かにみえる者でも、自分でも、また他人がみてもおどろくほどの進歩をする。
しかも、それらは私から教えられることがあったためではない。
彼らはみな自分自身で、多くの見事なものを見いだし、産み出したのである。」
つまり、ソクラテスは、人が知恵や徳を産みだすのを、わきにいて手助けするだけだというのである。
それではなぜ、ソクラテスにはそういうことができたのであろうか。
何も知らないという彼にも、一つだけ知っていることがあったからである。
一体、それは何か。いよいよこのへんから、ソクラテスという人物の核心にせまっていくことになる。
6 アポロン神のお告げ top
ソクラテスが三十七、八才になった頃には、彼を尊敬する青年が大変に多くなった。
自然科学者の説く純粋な理論に満足できない者、あまりにも出世本位なソフィストの教えに感心できない者、また、伝統的な宗教の信仰だけでは心の安まらない者、それらの青年たちが、ソクラテスのもとに続々と集まってきたのである。
しかし、むかしながらの権威と習價にあまんじている者や、地位とか名誉ばかりをほしかっているような者からは、ソクラテスの考えていることは全く理解されなかった。
目さきの仕事や娯楽に追われて、毎日をいそがしく明け暮らしている大半のアテネ人からみれば、ソクラテスという男は、何の役にもたたない変わり者にすぎなかった。
「一体、あの男はどういうつもりなのだろう。
よくも毎日あきもせず、つまらんことを長々と話し合ったり、考えたりしていられるものだ。」
「あの男はちっとも働かないで、若者としゃべってばかりいるが、あれじゃあ、貧乏になるのも無理はないわい。」
「人間は、金がもうかって楽しがっていられれば、それでいいじゃあないか。あいつはきっと頭がおかしいんだろう。」
ソクラテスを尊敬する青年たちは、一般の人々のこういう無理解を、非常に残念がった。
なかでも、カイレフォンという青年は、ソクラテスを熱烈に尊敬していたので、的はずれのうわさ話や評判には我慢ができなくなってしまった。
ついに彼は、いろいろな悪評を一挙につぶしてしまおうとして、アテネ市からはるばるカスタリア渓谷の奥の、デルフィの神殿まででかけていった。
当時のギリシア人の間には、国家的、国民的な重要問題をきめるときには、デルフィにまつられているアポロン神の神意をうかがう習慣があったのである。
アポロン神とは予言、音楽、詩などをつかさどる神で、ギリシア人にとっては、あらゆる知性と文化の代表者であり、律法、道徳、哲学の保護者でもあった。
カイレフォンはうやうやしく神殿にぬかづいて、
「私の先生、ソクラテスよりも賢い人が、この世のなかにいるでしょうか。」とたずねた。
アポロン神につかえる巫女は、カイレフォンの願いを聞くと、いつものように、神殿の奥深くに置かねている大きな椅子の上に座った。
あたり一面の地下からは、モーモーと湯気(硫黄からでる煙ではあるまいか)がたちのぼっている。 |

デリフィ神殿のアポロン神(中央)
|
この湯気を吸っているうちに巫女は意識を失ってしまう。
その、無意識のうちに語られることばが、神聖な神のお告げであるとされていたのである。
今日の私たちの常識で考えれば、これはまことに不合理な話だが、バカバカしいといって笑いとばしてしまうわけにもいかない。
二十世紀の現代でも、これと同じようなことが、世界のいたるところで行なわれ、重んじられているからである。
日本でもこの種の神託(神のお告げ)は、いろいろな宗教のなかで、いまなお盛んに行なわれている。
皆さんにも、おみくじをひいた経験がありはしないだろうか。
あれは紙に書かれた神のお告げにほかならない。
いや、正確にいえば、神のお告げが書かれている神聖な紙であると称して、一枚十円ぐらいで売られているものである。
科学の世に生きる現代人でさえも、そのようなものにまで頼りたくなることがあるのだから、紀元前五世紀のギリシア人が、いざというときに神託にすがりついたのは無理もないといえよう。
やがて意識を失った巫女(みこ)の口をとおして、おごそかにアポロン神のお告げがあたえられた。
「ソクラテスのように賢い人物は一人もいない。」
これを聞いてカイレフォンはとびあがるほどよろこんだ。
――やはり、ぼくの尊敬する先生は世界で一番賢いんだ。
日頃、先生の悪口ばかりいっていた人々にも、これからは文句をいわせないぞ。
ともかく、先生のかしこさはアポロン神が保証してくれたんだ。何とありかたいことか。
先生もさぞかし喜んでくれるだろう――
一九六六年四月、私はデルフィのが削を訪れたときにはじめて、カイレフォンがここで、その昔どんなに喜んだかを、クッキリと心に描くことができた。
神殿へ通じる広い石段の脇には、カスタリア渓谷の清流がゆるやかに流れている。水はすんで氷のように冷たい、
北側には岩山の絶壁がそそり立ち、南側には緑の野がはるかに展開する。
神殿のなごりをとどめる数本の石の柱は太く、がっしりとしていて、しかも気高く美しい。
石の肌は昔ながらに白く、青い天空に映えて、歴史の流れを無言のうちに語りかけてくる。
その清らかな雰囲気は、訪れる人に神を感じさせずにはおかない。
――ここで、カイレフォンは神託をうけて感動したのだ――
私は彼の感動を、心からなっとくすることができた。
その帰り途、私は車のなかで、カイレフォンが胸をはずませて歩いていく姿を想像した。
アテネへの道は遠い。山また山がゆくてをさえぎる。
自動車でさえも四時間もかかる道のりなのだ。
しかし、彼は山をこえ谷を渡って、まっしぐらに歩みつづけたにちがいない。
うれしい神託が、疲れも空腹もわすれさせてくれたことだろう。
アテネに着くとすぐ、カイレフォンはたソクラテスを訪れてこの報告をした。
――どんなに喜んでくださるか………―― と思ったのに、意外!
ソクラテスはニコリともしなかった。
「私はここ数年来、人間の研究に全力をあげている。
しかし残念ながら、まだ何もわかっていない。
一体、アポロン神はどういうつもりで、私のような無知な人間を賢者だといったのであろう。
アポロン神は、闇をやぶって光をもたらす日の神さまだ。
そのお告げに誤まりがあろうとは思われないが、しかし、私などよりも賢い人は、いくらでもいるはずだ。
私を誰かとお間違えになったのではあるまいか。」
ソクラテスは深しおどろきの色を浮かべながら、低い声でこのようにつぶやいただけだったのである。
もう一度いうが、これはソクラテスが三十七、八才のときのことであり、デリオンの戦いはこの神託よりも約十年も後のことなのである。
7 神への挑戦 top
デルフィの神託は、当時のギリシア人のおいたではもっとも権威のあるものであった。
ソクラテス自身も、アポロン神を深くうやまい尊んでいた。
しかし、カイレフォンによって伝えられた神託だけは、どうしても信じられなかった。
なぜならば、ソクラテスには自分の愚かさが心の底からわかっていたし、自分を賢い人間だなどとは夢にも思えなかったからである。
――この神託の本当の意味はどこにあるのだろうか――
ソクラテスはしばらくの間、深い疑いをいだいて考えつづけていたが、やがて、賢者として広く名前の知られている人々を、一人一人たずねてまわる決心をした。
自分よりも賢い人を見つけることによって、この神託が間違いであることを証明してみようと思ったのである。
これは確かに神をうやまわない行為であり、敬神の念が厚い日頃のソクラテスにはふさわしくないことであった。
しかし、彼は何よりもまず理性の人であった。
たとえアポロン神のお告げであっても、理性的にうなずけることでなければ受取れなかったのである。
弟子たちが喜び勇むなかにあって、一人ソクラテスは、人間の理性の力によって神に挑戦する決心をかためた。
そして、
「見よ、この人こそ、私よりも賢いではないか。」
といえる日のくることを確信して、彼は賢人、知者といわれる人々を訪問しはじめた。 |

デルフィ神殿跡
|
皆さんは、「これはおかしな話だな」と思わないだろうか。
というのは、人間は誰でも、自分を実際よりも賢く思わせたがる傾向をもっているからである。
皆さんも、自分の愚かさはなるべく隠そうとするであろう。
より賢く、より美しく見られたいと願うのは、私たち人間の本能であるともいえる。
ところが、ソクラテスはわざわざ他の人の家まででかけていって、自分の愚かさを証明しようというのである。
よほどのバカか気違いでもなければ、やりそうもないことではないか。
ともかく、常識ではちょっと考えられないことである。
しかし、常識を逆立ちさせるところにこそ、ソクラテスの本領があったのである。
彼はまず、有名な政治家を訪れた。
そして、青年たちと話をするときと同じような調子で、彼独得の問答をはじめた。
「人生を正しく生きるのには、どうすればよいでしょうか。」
「正直であればよい、嘘をつかぬことだ。」
「では、戦争のときに敵につかまった場合でも、聞かれれば、味方のようすを正直に話すべきでしょうか。」
最初は自信をもって答えた政治家も、たちまち返答につまってしまった。
「善とは何で、悪とは何でしょうか。」
「いろいろあるが、まず、健康が善で、病気が悪であることは確かだ。」
「しかし、病気のために、偶然にも沈没する船に乗らないですんだ者にとっては、病気は善で、乗ったために死んだ者にとっては、健康は悪にたりはしないでしょうか。」
どんなに話題をかえても、結果は同じことであった。
ソクラテスがこういう調子でそれからそれへと問い返していくと、相手はどの問題についても、しまいには、
「自分にはわからない。」といわざるをえなくなってしまった。
ソクラテスは、その政治家のもとを立ち去りながら、ひとり静かに考えた。
――あの人は多くの人々から賢人だと思われている。そして、自分でもそうだと思いこんでいる。
が、実際はそうではないのだ。あの人も私と同じように、善や美については何も知らない。
にもかかわらず、彼はそれを知っていると信じていた。しかし、私は最初から知っているとは思っていない。
知らないという点では、確かに二人とも同じだが、私は知らないということだけは知っているという点で、あの人よりもすぐれているといえるのではないだろうか――
意外な結果を見いたして、ソクラテスはおどろいてしまったのである。
多くの人々から賢い、偉いと思われている政治家が、人間として知っていなければならないことを知らないとは、一体どうしたわけであろう。
善とは何かというような大切なことを知らないで、どうして国を正しく治めることができよう。
思いがけないことである。
しかも、これほど恐ろしいことはない。
なぜならば、彼らはその無知の手に握る権力によって、やがては国家を滅亡させ、国民のすべてを不幸のどん底におとしいれる恐れがあるからである。
このことは、現代の日本の政治家たちについても同じくいえる。
皆さんもやがて選挙権をえたならば、よほど慎重に各自の一票を投じなければならない。
善悪のけじめもつかないような人間に政治をまかせるならば、日本の国はどうなってしまうかわからないのだ。
ソクラテスは、期待に反して政治家の無知にガッカリしてしまった。
深いいきどおりさえも感じた。
しかし、彼は気をとりなおして、いっそう賢明の噂の高い大政治家を訪問した。
そして、「今度こそは………」と、大きな期待をもって問答をはじめた。
しかし、結果は全く同じことであった。
この頃のことについて、ソクラテスはのちに、みずからつぎのように語っている。
「その後も私は、次々といろいろな人を訪問した。
私は少しも遠慮しないで、善、幸福、徳などのような、人間として知っていなければならない問題について、ドンドン問答を進めた。
しかし意外なことに、誰一人として、私の質問に充分な答弁のできる者はいなかった。
『無知』という点では、私と彼らとは少しも違わなかったのである。
ただし、私は自分の無知をよく知っているという点て、彼らとは全く違っていた。
この間に、私は多くの敵をつくった。と同時に、賢者であると評判されるようにもなった。
結果からみれば、世間で尊敬されている人々をやりこめるために、歩きまわったようなことになってしまったのである。」
このようにして、ソクラテスはようやく神託の意味をさとることができた。
「なんじら人間のうちでは、ソクラテスのように自分の無知をよく知っている者こそ、最高の賢者なのである。」
と、神託を解釈して、はじめて納得したのである。
8 使命を見いだす top
私は、ソクラテスの「産婆術」について述べたときに、
「それではなぜ、ソクラテスにはそういうことができたのであろうか。
何も知らないというかれにも、一つだけ知っていることがあったからである。」と書いた。
それが何であるか、すでに読者の皆さんにはおわかりいただけたことであろう。
彼は、人生の重要問題について、自分が無知であるということ、それだけはよく知っていたのである。
奇妙な言い方になるが、彼は知らないということだけはハッキリと知っていたのである。
――よしっ、私はこれからはこの点について、人々の無知を大いに追求していこう。
アポロン神が私のような者にありかたいお告げをくださったのは、世の人々の無知を自覚させるためであるに違いない。
「人格を高め、人生を正しく生き、幸福をえるためにはどうすればよいか。」
この問題に人々の関心をひきよせ、その無知を自覚させるところに、私の使命があるのだ。
人間であるかぎり、この問題をいいかげんにしておくことはできないはずであるのに、多くの人々はほとんど関心をもっていない。
しかも、困ったことには、大抵の人が、実際には何もわかっていないのに、よくわかっているとかってに思いこんでしまっている。
私の使命はこの思い違いをきびしく指摘して、彼らをみずからの無知に目ざめさせるところにあるのだ――
ついにソクラテスは、生涯をかけて生きる道を見いたしたのである。
ここにいたるまでにはかれの誕生からかぞえて、約四十年の歳月が流れている。
孔子は「三十にして立つ」といった。
釈迦も人生に確信をもつまでには三十五年もかかっている。
生きる道(生きがい)を見つけるのは、それほどむずかしいことなのである。
世の中には、何となく生きて、何となく死んでしまう人がどれほどたくさんいることか。
ウカウカしていると、すぐに人生の終着駅に着いてしまう。
まことに光陰(月日のこと)は矢のごとくに速い。
皆さんもいまのうちから、自分の生きる道、つまり、いざ死ぬまぎわになっても悔やむことのない生き方を、真剣に追求していただきたい。
さて、神託の意味を知ってからのソクラテスはほとんど毎日のように、市場や体育場などへでかけていって、青年たちを相手にして使命の遂行にはげむようになった。
「君は大政治家になるうとするからにはきっといろいろと考えていることがあるだろう。
まず、どういうことをやろうと思っているのか。それを聞かせてもらいたいものだ。」
この質問に、相手の青年が考えこんでしまったので、ソクラテスはつけくわえていった。
「君は政治家になって、国家をいまより豊かにしようとするのではないのかね。」
「そうです、そうするつもりです。」
「国家を豊かにするためには、国家の収入をふやさねばならんと思うが………。」
「ぼくもそう思っています。」
「ではいってみたまえ。いま、国家は何から収入をえているか。そして、総額どのくらい収入があるか。
君はそのくらいのことは研究しているだろう。
しかも、どれかそのなかで、すくなすぎるものがあれば、増額すべきであると考えているであろう。」
「しかし、まだ………。」
と、その青年はまごつきながらいった。
「まだ、そんなことまでは研究していないんです。」
「よろしい、それでは、国家の支出をいってみたまえ。君は、無駄があれば、はぶこうと考えているに違いない。」
「正直のところ、それも考えておりません。そういうひまがなかったんです。」
しどろもどろになった青年を、ソクラテスがたしなめるように、
「それでは、国家の富をますことはあとまわしにしよう。
収入も支出も研究していないのでは、とても話にならんのだから………。」
というと、その青年はいいことを思いついたというような顔つきをして、
「ですが、ソクラテスさん。敵からうばって国を富ませることもできると思います。」
「なるほど、しかしそれは、こっちが敵よりも強いときにかぎる。
弱い場合には、持っているものまでなくしてしまうのだから。」
「それはおっしゃるとおりです。」
「したがって、国の政治をとる者は自分の国の兵力と敵国の兵力とを知っていなくてはならない。」
「お説のとおりです。」
「それではまず最初にわが国の陸軍と海軍の兵力を、わしに話してみたまえ。
そして、つぎに敵の兵力をいってみたまえ。」
「しかし、そんなことは、そう簡単に口ではいえません。」
「よろしい、それではもしも書きとめてあるなら、それを持ってきなさい。」
「実は、べつに書きとめてもいないのです。」
青年はすっかり恥じ入ってしまった。
ソクラテスはいつもこのように問答を進めることによって、青年たちのうちに、
「自分では知っているようなつもりでいながら、実際には何も知らないのだ。」
という自覚をよびさましていったのである。
しかし、私たちはどんなに努力しても、あらゆることをすべて知るというわけにはいかない。
また、その必要もないであろう。それでは、何について知ることが一番大切なのであろうか。
逆にしえば、何について無知であることが、一番いけないのであろうか。
9 無知の知 top
|

ソクラテスによって学問への情熱をよびさまされた
プラトン(右)とその著書。
|

プラトンの教えをうけたアリストテレス(左)とその著書。
|
ソクラテスがエウテュデモスという弟子とかわしたつぎの問答には、一番大切なことが明らかに示されている。
「君は今までにデルフィヘいったことがあるか。」
「ええ、二度いったことがあります。」
「では君は、あの神殿に彫りこんである『汝自身を知れ』という言葉を見ているだろう。」
「はい、見ました。」
「君はあの文句には何の注意もはらわなかったか。
それとも、心にとめて、自分が何者であるかをあらためて考えてみたか。」
「いいえ、全く考えてみませんでした。自分のことはよく知っているからです。
自分のことさえわかっていないとしたら、ほかのことなどわかるわけがないでしょう。」
「それでは聞くが、君は自分の名前だけを知っている人間が、自分を知る者と思うか。
それとも、たとえば馬を買う人が、おとなしい馬か、暴れ馬か、力が強いか弱いか、駆けるのが速いか遅いか、そのほか、馬の用途から考えてどんなことに適するかなどをすべて調べてみるまでは、買おうとする馬を知ったとは思わないように、自分についてはどんな人間で、何をすればうまくできるかをよく知っている人が、自分を知る者だと思うか。」
「私は今まで、自分についてそんなふうに深く考えたことがありませんでした。
自分を知るということは、確かに、名前だけでなく、性格や能力までも充分に知っていることだと思います。
いまご意見をうかがって、私がそういう意味では自分をよく知ってはいないということが、ハッキリとわかりました。」
「それでは、君は今日から自分を知る努力をさっそくはじめなければいけない。
自分を知ることぐらい大切なことはないのだ。
何故かといえば、自分を知る人々には、自分の益となるものが何であるかがわかり、自分にできることとできないこととを見分けることができる。
そして、自分のよく知っていることを実行し、必要とするものを手に入れて豊かに暮らし、知らないことはさけて過失をおかさず、しまいには、功なり名とげて、多くの人々の尊敬をうけるようになるからである。
これに反して、自分をよく知らない者は、何をしても失敗し、損をしたり、こらしめをうけたりするばかりでなく、やがては誰からもバカにされ、不名誉な一生を送るようになるからだ。
国家にしても、みずからの力を知らず、自分よりも強大な国と戦うものは、滅びたり、自由を奪われたりしてしまう。
それは、君も実際に見てよく知っているだろう。」
「はい、知っています。しかし、自分を知ることがどんなに大切かということは、いま、はじめて本当によくわかりました。」
確かに、自分をよく知っていれば、もっているだけの力をうまく配分して、それらを最高度に発揮できるはずである。
また、自分の弱点を自分の長所でおぎなっていけば、バランスのとれた生き方ができるし、その結果、幸福をえることもできるであろう。
これに反して、自分の性格も能力もろくに知らない者は、何をしてよいかわからないばかりか、何をやってもうまくいくはずがない。
しかも困ったことには、その心のすきにつけこんで、卑怯、怠慢、無分別、不節制などの悪節が続々と生じてくる。
そういう悪徳にうずもれている人間が、どうして幸福になれようか。
ソクラテスによれば、幸福になるためにはまず自分を知らねばならないのである。
私はこのソクラテス伝のはじめのほうで、
「幸福になるためには、何についての、どのような知識が必要なのか。」
という問題を提出したが、必要なのは自分についての知識にほかならない。
さてそれでは、自分についての知識とはどのような性質をもつ知識なのであろうか。
この知識は、何かほかの知識とは全くちがう。
たとえば、自分がどう考えても怠け者だということがハッキリわかった場合には、誰でも怠け者ではなくなろうと真剣に努力するであろう。
もしも真剣な努力をしない人がいるとすれば、その人には怠け者であるということがよくわかっていないのだ。
つまり、自分についての知識には自分をより良くしようとする努力が、かならずともなうのである。
その努力が真剣なものになればなるほど、自分の良くない点がますます明らかにわかるようになり、謙虚な態度で向上、進歩を求めるようになる。
したがって、自分についての知識には、けっして理屈だけにはとどまらないという特徴があるといえよう。
ソクラテスは、このような知識を「無知の知」といっている。彼によれば、自分を知るということは、自分の無知を知って、かぎりなく努力することだったのである。
ところで、ソクラテスは自分の無知をよく知っていたがゆえに、知を、何よりも愛した。
「ソクラテスとは何者であるか。」
という質問にたいしては、彼は知を愛する人つまり「愛知者」であったと答えるよりほかはない。
この愛知者を意味する「フィロソフィー」というギリシア語は、日本では特別に「哲学者」と訳されて、明治時代以来、広く用いられるようになったのである。
10 誤解と反感 top
ソクラテスは哲学者ではあったが、青白くて、気むずかしい学者タイプの人間ではなかった。
彼は社交性か豊かで、誰とでも楽しく交際し、酒も飲めば、ご馳走も喜んで食べた。
演劇のコンクールや体育祭にも、はりきってでかけていくという広い趣味の持ち主であった。
つまり、「よく学び、よく遊ぶ」という幅の広い人間だったのである。
ある男が、あいさつを無視されたといって腹をたてているとき、ソクラテスは笑いながら、
「何も、そんなに怒ることはない。君はからだの悪い人間に出会っても、べつに腹をたてないだろう。
それなのに、心のできが悪い人間に出会ったからといって、憤慨するのはおかしいではないか………。」
と、明るい口調でいって聞かせたという。
ソクラテスの心はアテネの大気のように、いつも清くすみ、さわやかな光に満ちあふれていたのである。
このアテネの冬は短く、北方から寒い風が吹きよせてくことがあっても、たいしてきびしくはない。
雨はまれにしか降らず、夏の暑さはすずしい海の風がほどよくやわらげてくれる。
その程の良さが、彼の人柄や生活に、そのまま現れていた。
「自制心に欠けるような人間は、もっとも無知な動物と少しも違わない。
もっとも大切なことに心をそそがず、あらゆる手段を用いて愉快なことばかりをしようとしている人間が、どうして立派な人間になれるはずがあろう。
そういう人間は何よりも快楽を求めながら、その快楽さえも、えることができない。」
この言葉のとおり、ソクラテスみずからも、きびしく自制し節制することによって、常に「ほどよい生活」に心がけていた。
そして彼によれば、節制による「ほどよい生活」こそが、「無知の知」から自然に生じてくる真の幸福だったのである。
ソクラテスのこういう人格、思想、生活態度は、しだいに広く知れわたり、遠く海外からも、彼の名声をしたってアテネを訪れてくる者が次々とでてきた。
しかし、そのような人ばかりがいたわけではない。
思いあがった頑固な政治家や、ていさいだけを気にする上流階級の人々は、ソクラテスを徹底的に憎み嫌った。彼らにしてみれば、自分の無知を指摘されたのがおもしろくなかったのである。
また、ソクラスがアテネの政治を遠慮なく批判するのも大いに気にくわなかったのである。
たとえば、ソクラテスは役人をクジ引きできめる当時のアテネの習慣について、つぎのようなきびしい批判をしている。
「国の役人をクジ引きできめるくらい、愚かなことはない。
国政をあずかる者を選ぶのは大工や笛吹きを選ぶのとはわけがちがう。
大工や笛吹きならば、たとえへたくそな者を選んだところでたいした害はない。
それでも、クジでこれらの者をきめる人は一人もいないのに、役人だけはクジ引にするとは何ということだ。
もしも悪い人聞か役人になってしまったならば、その害は大工や笛吹きの場合とはくらべものにならないではないか。」
ソクラテスとしては無知を指摘する場合と同じく、本当のことをそのままいっているにすぎない。
しかし、皆さんにも苦い経験があると思うが、本当のことをあまりハッキリいうと、とかく誤解をうけやすいものである。
かえって遠まわしにいったほうが、理解してもらえる場合が多い。
だからといって、私たちは自分の意見をいつも遠まわしにばかりいっているわけにもいかない。
この点については、皆さんの一人一人に、あらためてよく考えてもらわなければならぬ。
ソクラテスにたいする誤解や反感の原因は、無知の指摘や政治へのきびしい批判だけにあったのではない。
彼が青年時代に親しくつきあっていた人々の間から、大変に卑怯な裏切り者と悪い政治家がでたことも、強い反感をよぶ主な原因の一つとなった。
「あの二人が裏切り者や悪い政治家になったのは、若いときに、ソクラテスの思想の影響をうけたからだ。」
「そのとおりだ。彼の問答は青年を悪い方向へ導いて、だらくさせてしまうのだ。」
「あんな危険な男はいなレモ、あいつは、我々をやりこめて喜んでいるだけではない。
このアテネ市の民主主義政治をぶっつぶそうとしているんだ。」
人の噂ほど恐ろしいものはないが、ソクラテスという人は、良いにつけ悪いにつけ、噂の的にされるような目立つ人物だったのである。
ソクラテスには目をギョロギョロさせる癖があり、鼻の孔がとても大きく、ひどいししっ鼻であった。
そのうえ、歩きぶりが、もったいぶった水禽(みずどり)のように愛嬌があったので、どこにいてもすぐに人目をひいた。
しかも、彼が使命として心がけた「無知の知」の追求は、彼の外見以上に人々の注目をよび集めた。
|

アテネ市民の公共生活の中心だったアゴラの遺跡。
中央がアクロポリスの丘。
|

アクロポリスの丘のパルテノン。ここで古代ギリシア哲学が栄えた。

丘の斜面につくられた野外劇場。
ギリシアでは昔からこうした野外劇場で、喜劇や悲劇が演じられた。
|
――ソクラテスみたいな男を主人公にして、皮肉な喜劇をつくってみたい――
ギリシアの有名な喜劇作家、アリストファネスが、こんなふうに思ったのも無理はない。
彼はふとそう思っただけではなく、実際にソクラテス的な人物を劇中の主人公にして、「雲」という喜劇をつくった。
そして「雲」は、デリオンの戦いの翌年(紀元前四百二年、ソクラテス四十八才)に、アクロポリスの丘のふもとにある野外劇場で上演されたのである。
劇中のソクラテスは、自然科学者とソフィストとをまぜあわせてつくられた人物であった。 確かに、実際のソクラテスも自然科学の知識を持ち、しかも問答の進め方には一見、ソフィストに似ているところがあった。
その点を作者は利用して、喜劇の舞台上に、
「アテネの伝統的な神々を信じないで、金銭や名声ばかりにとらわれて、いいかげんなことしかいわないソクラテス」
を演出したのである。
演出されたソクラテスと実際のソクラテスとの間には、大きな違いがあったが、単にうわべを見ただけでは、大変によく似ていた。
よく似ていたために、多くの観客は舞台上の人物から、まるで本物を見ているような印象をうけてしまった。
その印象が、ソクラテスに関する噂を、ますます悪くさせてしまったのである。 |
11 脱獄のすすめと死 top
こうして、まるで雪だるまが坂道をころがるように、誤解が誤解をうみ、反感が反感をよんで、ソクラテスの評判は悪くなる一方であった。
やがて紀元前三九九年、
「ソクラテスは青年をだらくさせ、国家の信仰する神々を信じない危険人物である。」
という理由をつけられて、アテネの法廷に告訴されてしまった。
まさに無実の罪である。
ソクラテスは五百人の陪審員を前にして一三時間に渡って堂々と意見をのべた。
「アテネ市民諸君、少々おかしなたとえかもしれないが、わが国アテネは気品はあるが居眠りばかりしているのろまな軍馬であり、私はその軍馬の目をさますために、神によって軍馬のからだにくっつけられたアブのようなものである。
だからこそ私は、一日じゅう、いたるところで、眠っている諸君の精神を問答の針でつきさし、真理に目ざめさせることをけっしてやめないのだ。
今までに、私の針でさされたことのある人々は、ウトウトしていた者が急にゆり起こされたときのように、しばしば怒ってしまった。
しかし、これは腹をたてるべきことだろうか。
諸君は腹だちまぎれにアブをピシャリとたたくようなつもりで、告訴状にもとづいて私を死刑にしてしまうかもしれない。
しかし、もしも私を死刑にしたならば、神が諸君のことを心配して第二の私をお送りにならないかぎり、諸君は一生、眠りつづけるようになってしまうだろう。
諸君、諸君は知力や武力において、もっともすぐれたアテネの市民でありながら、どうして、金銭や名声ばかりを求めようとするのか。
どうして、自分の心をみがき、真理をめざそうとしないのか………。」 |
ソクラテスがもしも憐れみを求めたならば、あるいは死刑をまぬがれることができたかもしれない。
もともと無実の罪なのだ。しかし、彼は一歩もゆずろうとはしなかった。
断固として、正しいと思うことを主張した。その結果、
「有罪票数二八〇、無罪票数二二〇。」
ついに六〇票の差で、何の罪もないのに、彼は死刑に処せられることになってしまったのである。
こうして、ソクラテスが獄屋に投じられ、いよいよ明日は死刑にされるという日の早朝、クリトンという親友がひそかに獄屋を訪れてきた。
「脱獄のチャンスができたのだ。手はずはすっかり整えた。さあ、ここから逃げてくれ。」
クリトンはたとえ自分の命を投げだしても、この偉大な友人を死なせたくはなかったのである。
しかし、ソクラテスは逃げだそうとはしなかった。 |

ソクラテスの最期(J.L.デヴィッド筆)
|
「クリトン君、私は君の友情を本当にうれしく思う。
しかし、脱獄の計画だけはすぐにとりやめてもらいたい。
もうこうなったら、一切を運命の手にまかせようではないか。
尊いこと、善いことというのは生きながらえるということとは全くべつの問題なのだ。
自分がどんな人間であるかをぬきにして、ただ自分の生命を保ち、どれほどかの時間でも生きるなどということは男子の問題にすべきことではない。
人間は誰でもいつかはかならず死ぬのだ。
だから、我々が常に考えなければならないのは、死をまぬがれようとすることではなく、生きられるだけの時間を、どうしたらもっとも良く生きられるかということだ。
私は今日まで、できるかぎりよい人間になるうと最善をつくしてきた。
自分の一生涯を、ただ正義を行ない不正を避けることのみについやしてきたのだ。
残された時間は短いが、私はこのまま自分の一生を貫きとおすべきだと思う。」 |
ソクラテスは脱獄のすすめには少しも心を動かさず、この翌日、落着きはらって死んでいった。
アクロポリスの丘のそばには、ソクラテスがとじこめられ、そして死刑に処せられたという獄屋が今日もなお残っている。
入口が鉄の柵で閉じられているので、中には入れなかったが、外から見たかぎりでは、まことに小さな暗い洞穴である。
彼の肉体はその洞穴のなかで消えてしまったのだ。
その生涯はわずかに七十一年間にすぎない。
しかし、彼の精神と思想とはヨーロッパの人々の心を支え、さらには、広く「人類の良心」として、今日もなお生きつづけているのである。
top
**************************************** |