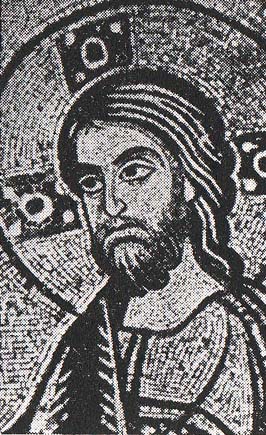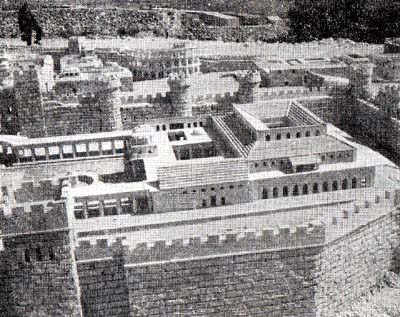|
****************************************
IIndex 概要
釈迦
孔子
ソクラテス キリスト
マホメット
1 どうすればよいのか top
私は一九六五年の十二月から翌年の四月まで、約四か月にわたってイスラエルに留学した。
イスラエルでは今日でも、ユダヤ教の安息日がしっかりと守られていて、毎週金曜日の日没(およそ午後四時)以後は誰も仕事をしない。
おどろくべきことに、郵便も配達されないし、バスまでがとまってしまう。
タバコはもちろん、パンを買うことさえもできない。外国からきた旅行者のうちには、そういうきまりを知らないために、あわてふためく人がすくながらずいる。
私も最初のうちは安息日をうっかり忘れて、タバコは買えず、バスには乗れずで、大変に困ったことが何回もあった。
この安息日について、イエス・キリストはつぎのように語っている。
「ユダヤ教では週に一日、安息日なるものをつくって、この日に休息しない者は石で打ち殺せと規定している。
それを神のいましめであるとして尊んでいるが、それではその日に誰かが井戸へでも落ちたらどうするのだ。
見殺しにせよとでもいうのだろうか。
安息日などというものは、人のために設けられたものであって、人が安息日のために設けられているのではない。
よいことをするのには安息日であろうとなかろうと、少しもためらうべきではないのだ。」 |
イエスが生きていた頃には、二十世紀の今日よりも、安息日はいっそう厳しく守られていた。
その当時にこんなことを堂々といえば、たとえそれがどんなに筋のとおった主張であるにもせよ、いざこざの起きないはずがない。
「英雄、故郷にいれられず」――すぐれた人物でも、生まれ故郷ではあまり認めてもらえない――という諺(ことわざ)があるが、イエス・キリストもこの諺の英雄と同じく、彼は最期には死刑にされてしまったのである。 |
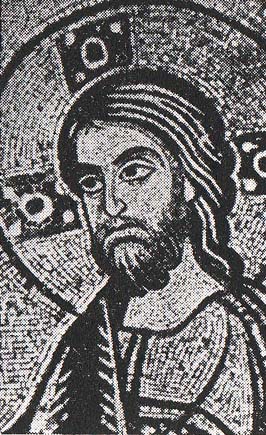
描かれたキリスト
|
イエスは単に安息日の厳守に反対しただけではない。
当時のユダヤ教の不合理な規律や風習をドンドンうちやぶった。
内容のない形式などは一切問題にしなかった。その点だけを特に取りあげて、
「イエスという男は、世の人々をあおりたてて、暴動を起こそうとする。危険な反逆者だ。」
などと騒ぎたてる者がたくさんいたが、はたして、彼は本当に危険な人物だったのであろうか。
いや、それよりもまず、彼は「神の子」だったのか、それとも「人の子」だったのか、昔の偉大な人物の生涯はほとんど例外なく、多少なりとも謎につつまれてはいるが、イエスの生涯ほど謎だらけのものはない。
まず第一に、彼については実際に存在したかどうかが問題になる。
「実際には存在しなかった」と主張する学者や思想家が、意外にたくさんいるのである。
クリスチャンとして名高いアルバート・シュヴァイツァーさえも、自分の著作のなかで、
「イエスが歴史的に存在したということを証明しようとして、大いに努力してみたが、どうしてもうまくいかなかった。」
と述べている。皆さんにとっては、これは思いもよらない話であろう。もしもこの本を読んでいる人々のうちにクリスチャンがいれば、
「イエスさまの生涯がフィクション(つくり話)だなんて、そんなバカな話があるものか。」
と、断然、憤慨するに違いない。しかし、
「その頃のユダヤには、神さまに人間を犠牲としてささげるお祭りがあった。
犠牲にされる人間は王さまの仮装をし、ロバに乗ってエルサレムに入城し、人民のかっさいを受け、最後には十字架につけられる。
『福音書』に述べられているイエスの最後のようすと少しもちがわない。
これを偶然の一致といえるであろうか。
イエスの一生は、このお祭りを種子(たね)にして、でっちあげられたものに相違ない。」
「イエスの誕生以前にも、メシア(世を救う者)といわれる者が、世の人々の罪をあがなうために、十字架上で何人も死んでいる。
ユダヤ人にとっては十字架は救いのシンボルであり、メシアの十字架上の死はけっしてめずらしいものではなかった。」
このような説を唱える人たちは
「だから、イエスという人物が実際にいたかどうかは疑わしい。」
「だから、イエスなどという人物は絶対にいなかったのだ。」
などと主張してゆずらない。
確かに、イエスの生涯にはわからない点が多い。
『福音書』は彼の生涯を伝える重要な資料ではあるが、これは彼の存在を最初から少しも疑わないクリスチャンによって書かれたものである。
信仰上の書物としてはこのうえなく貴重なものではあっても、歴史の本としては百パーセント信用するというわけにはいかない。
第二の問題として、かりにイエスが実際に存在したとしても、『福音書』には彼の十二才のときのできごとを最後として、その後は三十才にいたるまで、何も書かれていない。
一体この十八年の間、イエスは何をしていたのであろうか。
資料も記録も一つもないので、この間のことは世界じゅうの誰にもわからない。
それではどうすればよいのか。
私はイエスの伝記を書くにあたって、考えれば考えるほどこまってしまった。
嘘は書きたくない。しかし、信頼できる資料や記録はまことにとぼしいのだ。
にもかかわらず、イエスは私の心を強くひきつける。
『福音書』のうちからおどりでてきて、私の心のなかにとびこんでくる。
そしていきいきと躍動し、私を教え導いてくれる。
いろいろな学者や思想家のいうとおり、『福音書』に説かれている彼の生涯のストーリーはことによると、すべてたんなる伝説、神話にすぎないのかもしれぬ。
しかし、そこには力強い精神が、美しい感情が、そして不屈の意志が、見事にえがきだされている。
私は『福音書』のうちに、明らかに一つのすぐれた人格を読みとることができるのだ。
私としては、私に読みとることができたかぎりの人格を、そのまま書くほかはあるまい、
2 赤ん坊をみな殺しにしろ!
top
伝えられるところによると、イエスはナザレの大工、ヨセフを父とし、その妻マリアを母として、いまからおよそ二千年前、紀元前四年(前七年という説もある)十二月二十五目に生まれた。
場所はベツレヘムの馬小屋で、屋根からは星の光がもれ、わらくずがかすかに光って見えたという。
この誕生の直後に、大事件が起った。
ある日、荒々しい兵士の一隊がベツレヘムにのりこんでくると、すぐに手わけをして、生まれたばかりの赤ん坊をさがし始めた。
「おまえの家に赤ん坊はいないか。」
と大声で怒鳴り歩き、いることがわかると、ドカドカと入っていって、ひとつきに突き殺したのである。
赤ん坊たちは、その騒ぎにおびえて火がついたように泣く。
その泣き声がたちまち剣を呼び、死をまねいた。
両親はさけんだ。怒った。
剣をふりかざす兵士の腕にとりすがった。
『どうして、そんなむごいことを………。やめてください、お願いです。お願いです。」
「どうしてだと………。そんなことを俺たちが知るものか。手をはなせっ!
俺たちはヘロデ王の命令にしたがっているだけだ。」
「いいえ、はなしません。王さまからどんな命令がでたというのです。」 |

ベツレヘムの赤ん坊を殺せと命じるへロデ王。 13世紀の絵。
|
「二才以下の男の子を皆殺しにせよという命令が出たんだ。
さあ、はなせっ! はなさぬと、おまえも一緒に突き殺すぞっ!」
兵土たちは腕にしがみついてくる母親を力まかせにふりとばして、泣きさけんでいる赤ん坊を次々と突き殺していく。
彼らは体じゅうに血をあびながら、しつこく赤ん坊を探しまわる。まるで地獄の鬼のようだ。
血のにおいがあたり一面にただよう。
一瞬のうちにベツレヘムの平和は無残にふみにじられてしまった。
しかし、執念深い兵土たちも、一組の夫婦が、生まれたばかりの赤ん坊をしっかりとだきしめて、ひそかにこの町から逃げだしていったのには気がつかなかった。
やがて、兵土たちは血のしたたる剣を夕日にギラつかせながら、足音高くひきあげていったという。
さて、たとえこの話がたんなる伝説にすぎないとしても、どんなわけで、ヘロデという王さまは、こんなにむごいことを兵士たちにさせたのだろう――
と、首をかしげざるをえない。
理由をハッキリたしかめてみなければ、皆さんとしても胸がおさまるまい。
悲しみの底にしずむ町の人々は、たまたまとおりかかったヒツジ飼いのお爺さんに、そのわけを聞いてみた。
「わしの聞いたところによると………。」
そういって、お爺さんはこわれた石の塀の上に腰をおろし、つぎのように語り始めた。
つい先日のことだ。東の国からきた三人の博士たちが、エルサレムをおとずれてへロデ王に、
「私たちは、三つの大きな星がこの国の上空でかさなり合って、ひときわ明るく輝いているのを見ました。
これはユダヤに新しい王が誕生した証拠に違いありません。その方はどこにおられるのでしょうか。
おがませていただきたいと思います。」
と申しあげた。思いもよらない話を聞いて、へロデ王はたいそう不安を感じたらしい。
――赤ん坊のうちに殺してしまわなければ、わしの王位があぶない――
と思ったのだろう。王はさっそく家来たちを呼び集めて、いろいろと問いただした。
そして、「新しい王となる者は、ベツレヘムに生まれる」という預言があることがわかったので、ヘロデ王は本心をかくして、三人の博士にやさしい口調でたのんだ。
「その幼児のことをくわしく調べて、見つかったらわしに知らせてくれ。わしもおがみにいくから。」
こういわれて、博士たちは星の光に導かれてベッレヘムヘいった。
すると、どうだろう。
見すぼらしい馬小屋のなかに、人間の子供とはとても思えないほど気高い赤ん坊がいたのだ。
――この子こそ、新しい王になるかたに違いない。ヘロデ王に報告すれば、きっと殺されてしまう。
この子は神の子に違いない――
ひとめ見て、そう思ったので、博土たちはひれふしておがみ、たくさんの贈り物をしたので、ヘロデ王のところへはもどらないで、黙って自分の国へ帰ってしまった。
これを聞いて、王は真赤になっておこった。
「ようしっ、それではベッレヘムにいる赤ん坊をみな殺しにしてしまおう。
そうすれば、やがては王となるかもしれぬ赤ん坊も、一緒にこの世から消えてしまうことになる。
さあ、いまからすぐベッレヘムへいけ。そして、一人残らず赤ん坊を殺してしまえ。」
こんな乱暴な命令が出されたために、このベッレヘムの赤ん坊たちは、とんでもないめに合わされたのだ。
この話をどう受取るかは全く皆さんの考えにまかせるほかはない。
信じるもよし、信じなくともよしなのだ。
ともかく私としては、『福合書』に伝えられている話をそれからそれへとたどりながら、一人の偉大な人物のすぐれた生涯を、私なりに描きだしていくことにする。
3 仕事場のある洞穴を見て
top
地図をよく見ていただきたい。ナザレとベツレヘムとは遠くはなれている。
二千年前には、この間にべんりな交通饑関は何もなかった。
当時の人は荷物をヒツジの背に乗せて、歩いて旅をしていたのである。
ところで、ナザレで暮らしていたイエスの両親が、どうしてはるばるベッレヘムまででかけていったのであろうか。
この点について『ルカによる福音書』には
その頃、全世界の人口調査をせよとの勅令が、皇帝アウグストからでた。 これは、クレニオがシリアの総督であった時に行なわれた最初の人口調査であった。
人々はみな登録をするために、それぞれ自分の町へ帰っていった。(第二章一節〜三節) |
と書いてある。
ローマ帝国の支配下にあった当時のユダヤ人たちは、この命令にしたがって、それぞれ、いわば本籍地へ登録をしにいかなければならなかったのである。
このことから、イエスが馬小屋で生まれたという話にも、おのずから筋道がつく。 |

イスラエルの地図
|
いろいろな地方から、大勢のユダヤ人か一度に戻ってくれば、当然、旅館は満員になってしまう。
イエスの両親はどの旅館からもことわられて、馬小屋の隅にでも身をおくより仕方がなかったに違いない。
『ルカによる福音書』には、つぎのように伝えられている。
| 彼らがベツレヘムに滞在している間にマリアは月が満ちて初子を産み、布にくるんで、飼葉おけの中に寝せた。客間には彼らのいる余地がなかったからである。(第二章六節) |
つぎに、イエスの誕生に関して問題になるのは星が輝卜たという話『フタイによる福音書』第二章の二節と九節)である。このベッレヘムの星についてはドイツの有名な天文学者ケプラー(一五七一〜一六三〇年)が、
「西暦前七年には、木星、土星、金星などの会食があった。」
と述べている。また、学者のうちには、
「それは、バレー慧星のような星ではなかったろうか。」
と想像する人がいる。
こんなふうに、星がひときわ明るく輝いたという話にも、それ相応の根拠を見いだせないことはないのである。
イエスの誕生についてはこのほかにもいろいろな話が伝えられているが、理屈をこねるのはこのくらいにしておいて、「それからどうしたのか」をたどってみよう。
兵士たちの厳重な警戒の目をのがれて、危なくベッレヘムを逃げだした一組の夫婦は赤ん坊とともに、ぶじにエジプトにたどりつくことができた。
いうまでもなく、この赤ん坊こそがイエスだったのだから、殺されたほかの赤ん坊たちは、ダンプカーにはねとばされたようなものである。
エジプトに着いたイエスは両親のやさしい愛偕にいだかれてスクスクと育っていった。
やがて何年かたったのち、ヘロデ王が死んだという噂が伝わってきたので、この三人は喜び勇んでナザレに戻ってきた。
ナザレは、緑の山と色とりどりの花にかこまれた小さな町である。
オリーブやイチジクの森、アネモネやシクラメンのさく花畑、大きな岩の間からこんこんとわきでる清い泉、ナザレの自然はまるでこの世の楽園のように美しい。
日本の小豆島にもオリーブは豊かにしげっているが、ナザレのオリーブとはとてもくらべものにならない。
緑のこさが違う。幹の太さが違う。一人ではかかえきれないほど大きいのだ。
その枝は広くひろがって、ここちよい影をつくる。
おそらく、少年イエスもこの木蔭にたたずんで、もの思いにふけったことなどがあったに違いない。
私はイスラエルを旅して、ナザレの自然の美しさに目を見張った。
しかし、何よりもおどろかされたのは、イエスが育つたといわれる住居の跡をおとずれたときのことである。
それは今日もなお昔なからに保存されているのだ。
二千年という長い年月を経ながらも、崩れもしなければ、こわれてもいない。
なぜか、地下につくられた洞穴住居だからである。
私はその洞穴に案内されたとき、ユダヤ人の案内人がいうことを、とてもそのまま信じる気持ちにはなれなかった。
「本当にイエスはこんなところで育てられたのですか。」
「そうです。
二千年前のユダヤ人で、このあたりに住んでいた者は、いわば穴居族(穴のなかで暮らす人種)だったのです。」
「どうして、穴のなかなどに住んでいたのですか。」
「地下の穴のなかは冬は暖かいし、夏はすずしいからですよ。
この穴のなかには井戸もあったし、あかりとりは今でもついています。」 |

イエスの住居跡といわれている洞穴住居
|
「そうすると、イエスの父のヨセフは、家を建てる大工ではなかったわけですね。」
「ヨセフは、家のなかの机や椅子をつくる人だったのです。
家具の職人であったというべきでしょう。この穴のなかには、彼の仕事場もつくられていますよ。」
そういって、案内人は仕事場の跡を指さして教えてくれた。
入口から地下に通じる岩の階段はとても狭いが、中はゆったりとしていて、思いもよらないほど広いのである。
この洞穴の上には、いまは豪華、壮大な教会が建てられていて、この世界的名所は教会によって大切に管理されている。
私はここをおとずれるまではイエスの一族が穴居族だったとは夢にも思わなかった。
おそらくは皆さんにとっても、これは全く意外な話であるに違いない。
私はいろいろな疑いの念をどうしても消しきれなかったので、同行していたユダヤ人の友だちにこっそりささやいた。
「昔のユダヤ人が、ナザレではこんな洞穴のなかで暮らしていたのだとしても、これがイエス一家の住居だったということが、どうしてわかるのか、何かハッキリした証拠でもあるのか。」
この質問にたいして、彼は茶目っ気たっぷりに片目をつぶりながら、私の耳元に口をよせて、
「証拠などがあるものか、昔からそう伝えられているだけの話さ。
イエスの生涯は雲につつまれているんだ。誰にだって、ぼんやりとしか見えはしない。
きみだけがハッキリ見ようとしたって、それは無理というものさ。」
と答えたのである。こんな会話を案内人に聞かれたら、怒鳴りつけられたかもしれない。
4 鉛筆はなぜ転がるか top
そのユダヤ人のいうとおり、イエスの生涯、特にその幼少時代はすっかり雲につつまれているために、私たちとしては、当時の歴史的情況を手がかりとして想像するよりほかはない。
その頃の子供たらは、自分でおよその判断や行動ができるようになると、町にあるユダヤ人の会堂にいって、『トーラー』(『旧約聖書』のはじめの五巻)を教えられた。
つまり会堂は当時の子供たちにとっては、いまの小学校のようなものだったのである。
数学や理科の授業はなかったが、『卜ーラー』の暗誦がうまくできないと、子供たちはむちでなぐりつけられたという。
イエスも子供時代には、一度や二度はそのむちでたたかれたことがあったかもしれない。
かれの家はけっして金持ちではなかったから、彼は勉強のあいまにはオリーブの油をしぼったり、かんなくずをかたづけるなど、両親の仕事の手伝いもしたことだろう。
ときには、広々とした野原にでて、ヒツジの群れや雲や山に見とれていたこともきっとあったに違いない。
やがて、イエスは十二才になった。
ユダヤの少年たちは、十二才になって、ヘブライ語の『トーラー』が読めるようになり、律法(掟=おきて)にしたがうことを学ぶようになると、エルサレムの神殿の奉仕に参加することが許された。
『ルカによる福音書』には、
イエスの両親は、過越(すぎこし)の祭りには毎年エルサレムヘのぼっていた。
イエスが十二才になった時も、慣例にしたがって祭りのために上京した。(第二章四一節〜四二節) |
と書いてある。
「過越(すぎこし)の祭り」とは迫害されていたユダヤ人がエジプトを脱出したのを記念する祭りである。
イエスは両親につれられて、ニズレル平原のでこぼこ道を、神の都エルサレムへ向かうことになったわけである。
アジア、ヨーロッパ、アフリカの三大陸がもっとも接近しているこのあたりは、旅する者の目をハッと見はらせるほど美しい。
サマリアの山々はゆるやかに起伏して、すんだ青空にくっきりと浮かぶ。
緑の野には、ヒツジの群れがのどかに、軽やかに歩む。
道ばたには黄や紅(くれない)の花が一面にさきみだれて、旅人の心をふと夢の世界へさそう。
イエスの一家は、同じくエルサレム参りをする大勢のユダヤ人とともに、『詩篇』を合唱しながら神の都への道をたのしく歩んだ。
やがて幾日かの後、彼らは天空に清らかにそびえるあこがれの神殿に詣でた。
壮大な大理石の冷たい光は神の威厳を物語り、豪華な黄金の輝きは神の豊かさを感じさせた。
イエスは、小さな胸をどんなに高鳴らせたことだろう。
ユラユラと香の煙が立ちのぼる、白い衣を着た祭司のお祈りの声が、銀の笛の音にまじっておごそかに聞こえてくる。
祭壇では子ヒツジの血が流され、やがて、ジリジリと焼かれる。
巡礼者たちはみな頭をさげて祈っていたが、イエスだけは焼かれているヒツジを見つめていた。
―― 一体、あのヒツジは何を表わしているのだろう。誰かの身がわりに焼かれているのかしら………―― |

聖殿内の12才のイエス
|
三日たち、四日たつうちに、イエスの疑問はしだいに深く大きくなり、一週間にわたるお祭りが終る頃には、どうしても質問をしないではいられなくなってしまった。
「ラビ(先生という意味)、なぜ神殿ではヒツジを焼くのですか。」
エルサレムには、神の律法を教える先生がたくさんいたのである。
「ヒツジを焼くのは、神さまの命令だからだ。」
「それでは、なぜヒツジの肉をあたえて、人々からお金をとるのですか。それも神さまの命令なのですか。」
「………」
ラビたちが答えにまよっている間に、イエスはドンドンつぎの質問に移っていった。
「ラビ、神さまはなぜ、アブラハム(ユダヤ人の祖先)に自分の子供を殺して神に捧げよといったのですか。」
「それは、神さまがアブラハムの信仰をためしてみょうと思ったからだ。」
「神さまは、アブラハムが自分の子を殺すのを、黙って見ていたのですかご
「いや、おまえの心はもうよくわかったから、やめなさいといって中止させたのだ。」
「そんなにやさしい神さまが、なぜヒツジを焼き殺すのをやめさせないのでしょうか。
かわいそうだとは思わないのでし’ようか。」
イエスの質問はそれからそれへとはてしなくつづいた。
『ルカによる福音書』には、彼のその質問ぶりについて、
| 聞く人々はみな、イエスの賢さやその答えに驚歎していた。(第二章四七節) |
と書いてあるが、私は驚歎するほどのことではないと思う。
たいていの子供は、急速に成長しつつある時には「なぜ」、「どうして」を連発する。
その質問が単純であればあるほど、先生や両親は答えがたい。たとえば、
「鉛筆はどうして転がるの………。」
という質問に、はたして何人の大人が正しく、わかりやすく答えることができるであろうか。
鉛筆が転がったり、りんごが木から落ちたりするのは、大人にとっては当然のことである。
しかし、子供にとってはしばしば不思議きわまりない。
子供らしさとは人生に不思議を見いだすところにあるといえるのだ。
そして「なぜ」「どうして」と真剣に問い進んでいくことによって、子供は素直に成長しかぎりなく向上していく。
大人っぽい子供とは、「なぜ」、「どうして」をもたない子供であり、子供っぽい大人とは、「なぜ」、「どうして」をもちつづける大人である。
私は皆さんに、イエスのような、子供らしい子供であってほしいと思う。
そして、その子供らしさをいつまでももちつづけて、かぎりなく前進しつづける人間になっていただきたいと願う。
5 神への扉に近づく top
まえにも述べたとおり、この十二才のときの出来事をさかいとして、イエスは四つの『福音書』から全く姿を消してしまう。
やがてヨハネの洗礼を受けるために、ヨルダン川のほとりに現れたときは、彼はすでに三十才になっていた。
しかも、からだも心も立派に成長して、特別すぐれた人物になっていたのである。
この二十年に近い年月を、イエスがどのようにすごしたかについては皆さんにも大いに想像をたくましくしていただきたい。
イエスの家庭には、両親のほかに弟が四人、妹が二人いたようだから、生活はけっして楽ではなかったろう。
父親はまもなく死んでしまったのだから、長男たるイエスは家族を養うために、さんたんたる苦労をしたに違いない。
しかし、年月がたつにつれて、彼は生活の悩み以上に大きな悩みをもつにいたったと思う。
というのは、その頃、ユダヤ人の住んでいた地中海沿岸の地域一帯は、ローマ帝国の植民地にされていたために、ユダヤ人たちは奴隷のような扱いを受けていたからである。 |
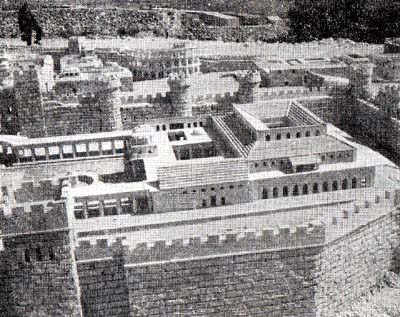
エルサレムの神殿の模型
|
「我々はまるで税金をはらうために生きているようなものだ。」
「そうだ、子供が生まれても税金、道をとおっても税金、これでは全くやりきれん。」
「しかも、ローマ人は、我々をラクダか馬みたいに追いまわす。
我々ユダヤ民族の守り神、ヤウェーは、いつになったら救ってくださるのか。」
「救ってくださるどころか、ヤウェーのまつってあるエルサレムの神殿の金までが、ローマ人にかすめとられているというではないか。」
「『聖書(旧約)』には、我々ユダヤ人は、ヤウェーから特に選びだされた尊い民族だと書いてある。
それなのに、どうしてこんなに不幸なめにばかりあわされるのだろう。」
「ヤウェー神が、ダビデのようなすばらしい王をもう一度この世に送ってくだされば、我々はみんな幸福になれるのだがなあ………。」
ユダヤ人の間には、このような不平不満のつぶやきや神の救いを求める声がみちあふれていた。
「偉大な救い主にでてきてもらって、ローマ人を一人のこらず追いはらってしまいたい。」
というのが、彼らの一致した願望だったのである。
小さな地主やヒツジ飼いのうちには、税金がはらいきれなくなって、山のなかに逃げこんでしまう者もたくさんいた。
また、彼らのうちには、ローマからきているピラトという総督や、皇帝の命令でこの地方の王となったヘロデ王の一族を、殺してしまおうと思っている者さえもいた。
イエスの誕生から青少年時代にかけては、ユダヤ人のそういう気持ちが二度ほど爆発して、ローマ軍との間に血の雨を降らせたことがあった。
しかしで不幸にして、二度とも武力でねじふせられてしまったのである。それでも、
「何とかして、ローマの支配をはねのけて独立しよう。
我々ユダヤ人こそは、神に選ばれた民族であり、この世でもっともすぐれた人種なのだ。」
という誇り高い気持ちは少しもおとろえなかった。
イエスもユダヤ民族の一人だったのだから、このような周囲の事情と無関係であったはずがない。
彼は洞穴のなかの仕事場で、毎日、机や椅子をつくりながらも、
――こんなことではいけない。
ユダヤ人が、いや、人間のすべてが、もっともっと幸福に生きられるようにならねばならぬ。
そのためには、どうすればいいのだろう………――
と、何かにつけて考えたり、悩んだりしたことであろう。
しかし、イエスには七人の家族を養うだけでも、なみたいていのことではなかった。
ユダヤ民族の独立運動などに参加すれば、家族がたちまち飢えてしまうのだ。
――私は自分の家族のために働かなければならない。
だからといって、ユダヤ人の不幸を見すごしているわけにもいかない。
この世の中をもっと住みよくするために、私はできるだけのことをしてみたい。
しかし、家族のために働いてばかりいれば、社会のためには働けなくなってしまう。
自分も自分の家族も幸福になると同時に、世の中の人がすべて幸福になるような道はないものだろうか………――
こんな悩みが、青春時代のイエスの心のなかでは、いつも激しくゆれ動いていたに違いない。
こういう場合、皆さんならばどうするであろうか。
――自分の家が貧乏で困っているのに、他人のことなどにかまっていられるのか。
ウカウカしていれば、飢え死にしてしまうじゃないか――
と思うのが普通だろう。
だがしかし、それでいいものだろうか。
たとえば映画館のなかで火事が起きたとする。
誰もが自分の身の安全だけを考えて、われさきに逃げだそうとすれば、危険はかえって大きくなってしまう。
――早く逃げださなければ死んでしまうんだ。他人のことなどにかまっていられるものか――
と思うのは当然だが、皮肉なことに、そんなふうにしか思えない人ほど混乱をかきたて、危険や不幸を自分の身に呼びよせてしまうものだ。
ここに人生の大問題がある。
こういう場合に、他人を先にして自分をあとにするところに、宗教への入口があり、神への扉がある。
イエスは考えたり悩んだりしたすえに、しだいにその扉へ近づいていった。
それが彼の生まれながらの運命だったのかもしれない。
6 「われこそ、神の子!」
top
イエスが神への扉に近づきはじめた頃、ヨルダン川のほとりにヨハネというすぐれた預言者(よげんしゃ)が現れた。
彼はラクダの毛で織った布切れを身にまとい、腰には皮の帯をしめ、草の根やイナゴなどを食べながら、
「悔いあらためよ、神の国が近づいた。まもなくメシア(救い主)が現れてくださる。」
と、毎日毎日、声をからしてさけんでいた。
そばをとおりかかった人々は、彼のまわりに集まって話に耳を傾けた。 |

ヨルダン川

洗礼の図の古い壁画。洗礼によって信者は神の子となる
とされるので、洗礼を受ける者は子供の姿で描かれていた。
|
「皆さん、荒野に道を開いて、神のためにその道を平らにしなさい。 そうすれば、神はかならず皆さんのいるところにきてくださるのです。
斧はすでに木の根元におかれているのです。
よい実を結ばない木はことごとく伐られて、火のなかに投げこまれてしまうのです。
皆さん、いますぐ悔いあらためて、正しい人になってください。 利己主義は捨てなければいけません。
着物を二枚持っている人は、一枚を貧しい人にわけてやりなさい。 また、食べ物をたくさん持っている人は、持たない人にわけてやるがよい。」 |
ヨハネの叫びは、しだいに多くの人々の心のうちに大きな感動をよび起こした。
ヨハネの噂がそれからそれへと伝わるにつれて、貴族、学者、兵士、農夫、漁師などが、続々とヨルダン川のほとりにつめかけてきた。
「悔いあらためよ、神の国は近づいた。」
力強く荒野にこだまするこの声に胸をうたれて、人々は十人、二十人と、これまでの自分中心の生活を悔いあらため、ヨルダン川の水でヨハネの「バプテスマ(洗礼)」を受けるようになった。
「バプテスマ」とは「水にひたす」ということで、これには清めの意味がふくまれている。
つまり、「水にひたす」ことによって、過去の間違いや罪を洗い流し、人間を新しく生まれ変らせるという儀式なのである。
ヨハネはヨルダン川でこれをさかんに行なったので、「バプテスマのヨハネ」といわれるようになった。
「ヨハネこそは我々が待ち望んでいたメシアではあるまいか。」
そんな噂が、ナザレに住むイエスの耳にも伝わってきたとき、彼の心にはかたい決意がいなずまのようにひらめいた。 |
――私もバプテスマを受けよう。そして、生まれ変った人間となって、世の多くの不幸な人々のために全力をつくそう。
自分や自分の家族の幸福を願う気持ち、それは、誰もみな同じなのだ。
その気持ちをのりこえなければ、この世の中は、いつまでたってもよくなりはしない。
まず、私がのりこえてみよう。それはつらく苦しいことには違いないが、私にはできる。
きっとできる。不幸な人々のために、私は一切を捨てよう。私自身をも捨ててしまおう――
イエスは、長年にわたる迷いの糸をいさぎよくたちきり、不動の覚悟をかためて、ヨルダン川のほとりにヨハネをおとずれた、
大勢の人をかきおけて、背の高いイエスが長卜髪を風になびかせながら近づいてきたとき、ヨハネはただちにそのするどい目の光を見てとった。
唇(くちびる)はうすく赤い、眉間(みけん)にはたてじわがぐっと刻みこまれている。
ヨハネは、たとえようもなし迫力を感じた。
――これこそ私が待ちに待った人物だ――と思った。
「あなたは、私のバプテスマなどを受ける必要はない。私はあなたの靴のひもをとくにもあたいしない男だ。」
「いや、私は世のすべての不幸な人々を救うために、あなたのバプテスマを必要としているのです。
ぜひ、受けさせてください。」
やがて、イエスの希望でバステスマがはじめられた。
清らかなヨルダンの水が、イエスのきょうまでの生活を、そして彼の人間的な欲望のすべてを、静かにゆるやかに洗い流していく。
その流れにのって、ヨハネの言葉がおもおもしく響く。
「あなたこそ、我々のメシアです。
私はこのヨルダンの水でバプテスマを行なっていますが、あなたは神の御霊(みたま)によって、人々の心を清らかにし、世の中を明るくする神の子であるにちがいない。」
ヨハネに励まされて、イエスの心には満々たる自信がわいてきた。
たとえようもない勇気が、体じゅうにみちあふれてきた。
――私は神の子となるのだ。そして、不幸な人々のために、神への道を歩むのだ――
イエスはただ一人、焼けた砂地を一歩、一歩、重くふみしめながら、誰もいない砂漠のまんなかへ入っていった。
太陽はジリジリと照りつける、一滴の水もない。しかし、彼は少しも恐れずに歩きつづけた。
誰もいないところで、全くの一人きりになって、自分というものと思うぞんぶんに闘ってみたかったのだ。
すこしでも自分をあまやかす気持ちがあっては、とても神の子にはなりえない。
神の子として生きぬくためには、自分を徹底的に捨てなければならぬ。
十日、十五日、二十日とたつうちに、肉体はいよいよおとろえていった。 三十日をすぎると、歩くことはもちろん、手を動かすことさえつらくなった。
しかも、昼には恐ろしいハゲタカが頭の上を飛びまわり、夜には気味の悪い獣(けだもの)の声が耳に響いてくる。 ときには、ふと、いたたまれない気持ちになることもあった。
――私のような弱い人間に、世の人々を不幸から救いだすちからがあるのだろうか………――
また、はてしない迷いの念が急にわいてきて、思わず、
「私は神の子になれるのであろうか。」と叫んでしまうこともあった。
しかし、イエスは逃げだそうとはしなかった。
ただ一人で、自分の弱さと正面から闘った。
飲まず食わずの毎日、迷いと疑いの身をげずるような苦しみの連続、その四十一日めの暁に、
「われこそ、神の子!」
と、イエスは火のような叫び声をあげた。 彼の心のうちにひそむ弱さは人類にたいするるかぎりない愛情によって、あとかたもなく吹き飛ばされてしまったのである。
ついに彼は、一切の自分本位の欲望にうち勝ち、神への道を歩む神の子として、生まれ変ることができたのである。 |

イエスは洗礼を受けたあと、断食をして心の迷いや欲望の誘惑と闘かった。ヨルダンの平地から数百メートルの高さの伝説の「誘惑の山」。
|
7 神への信仰と人への愛情こそ
top
私たち人間の心の底には、他人をすこしぐらい犠牲にしても、自分だけはよくなりたいという気持ちがひそんでいる。
そんな気持ちを全くもたない人がいるとしたら、それは人間の子ではなく神の子だといってもいいのではあるまいか。
そして、もしも人間がすべて神の子になれれば、人間の世の中は神の国になりうる。
もちろん、この世に神の国を実現するのはきわめてむずかしい。人間自身の力ではとてもできないだろう。
――しかし、神の力を借りれば、けっしてできないことではない―― と、イエスはかたく信じて、希望に燃えてナザレに戻ってきた。 |

イエスが最初に宣教活動を行なったといわれるガリラヤ湖畔に建つ教会 |
「皆さん、神の国はすぐ真近にあります。
この世のできごとなどにとらわれないで、心をつくし、精神をつくし、思いをつくし、力をつくして父なる神を愛しなさい。 悪者にも手向かってはいけません。
右の頬を打たれたならば、左の頬も打たせてやりなさい。 下着をうばおうとする者には、上着もあたえてやることです。」 |
|
はじめてイエスの話を聞いた人々は、
――冗談じゃない。右の頬を打たれたら、相手の頬を打ち返すべきだ。
下着をうばおうとする者に、上着まであたえてやるなんて、とんでもない話だ――
と思った。無理もない。
イエスの話のなかでは常識が全くびっくり返されてしまっていたのだ。
だからといって、彼はけっしてデタラメをいっているのではなかった。
「天の父は悪者の上にも太陽をのぼらせ、恩を知らぬ者にも慈愛をそそいでくれます。
この神の大きさのまえには、人間のさだめた善悪などがなんの役にたちましょう。
人をさばいてはいけません。すべてを許してやるのです。
そうして、あなたがたを憎み、呪いはずかしめる者さえも、大いなる慈悲の心で愛してあげなさい。
あなた方の心のうちに、愛情が泉のようにわきあふれてくるとき、神の国がこの地上に実現するのです。
皆さん、生きがいのある人生を生きようと思ったら、全力をあげて神を求めてください。
求める者にはかならずあたえられます。皆さんは『聖書(旧約)』を信じているでしょう。
『聖書』のなかに述べられている預言(よげん)は、いまこそ私によって、そして皆さんによって、正しく実行されなければなりません。 さあ、まず第一に、愛の生活をはじめましょう。
愛によって、私たちは神の子として生まれ変ることができるのです。」 |
イエスのこういう話は、貧しい人や不幸な人の間に、しだいに力強く食いこんでいった。
「イエスさまこそは我々が久しく待ち望んでいたメシアだ!」
「我々ユダヤ民族の独立も、遠いことではないぞ。」
彼らは、のどのかわいている者が水を飲むように、イエスの福音を次々と心に迎え入れるようになった。
しかし、貴族や祭司やパリサイ派の人々は、イエスの話などには少しも耳を傾けなかった。
パリサイ派とは、昔ながらの宗教の一律法を何よりも重んじ、それをすべてのユダヤ人に厳しく守らせようとする人々のことである。彼らは、
――ユダヤ人がローマ人に支配されて、みじめな生活をさせられているのは、律法を守らなかったための神罰なのだ――
と考えるほどこり固まっていたので、律法よりも愛や信仰を重んじるイエスにたいしてはとりわけ強い反感をもったのである。
ある日のこと、イエスが弟子たちと一緒に取税人の家にまねかれて、楽しく食事をしていたとき、これを見たパリサイ人は憤然としてくってかかってきた。
「あなた方はなぜ取税人なんかと一緒に食事をするのだ。
ユダヤ教では、そのような職業の者と交際することは、かたく禁じられている。神の掟を知らないのですか。」
その当時、取税人はユダヤ人の誰からも毒ヘビのようにきらわれていた。
同じくユダヤ人でありながら、ローマ帝国の手先となって、情け容赦もなく税金を取りたてて歩く役なのだから、確かに誰からも好かれるはずがない。
マタイという収税人はそんな職業につくづく嫌気がさして、イエスの話に耳を傾けていたのである。
イエスは、がなりたてるパリサイ人のほうにゆっくりと顔を向けて、静かな口調で答えた。
「健康な人には医者の必要はないが、病人にはどうしても医者が必要です。
それと同じように、正しい人はともかくとして、悪い人々罪をおかした人には私の救いの手がなくてはなりません。
あなた方は、律法を守る人だけを正しい人だと思っているようですが、それは大間違いではないでしょうか。
世の人々からひどい悪口をいわれている人のうちにも、正しい人はいるのです。
神の子となる美しい心をもった人がいるのです。」
イエスはつねに、社会の吹きだまりに生きる人々の味方であった。
彼にとっては、何の役にもたたない規則や、職業のいやしさなどは、少しも問題にならなかった。
神にたいする信仰、人類にたいする愛情、これがイエスのすべてだったのである。
しかも、彼の説く神は、ユダヤ人のためだけの神ではなく、全人類のための神であった。
ユダヤ教においては神は民族の独占物であり、「神の国」とは、ユダヤ民族が地上を支配することを意味したが、イエスはその「神の国」をせまい民族意識と形式的信仰から解放しようとしたのである。
8 やさしく、そして、厳しく
top
イエスは、罪を悔いあらためた人には、どこまでもやさしく親切であった。
ある時、悪いことをしたのに気づいて苦しんでいる人に、彼はつぎのような話をしてやったという。
ある人に二人の息子があった。その弟のほうが、
「お父さん、私にわけてくれることになっている財産を、どうかいまのうちにください。」
としきりにせがむので、その父親は財産を半分わけてやった。
すると、息子はその財産をそっくり持って遠い国へいき、したい放題のことをして、たちまちのうちに、一文なしになってしまった。
ところがちょうどその時に飢饉になり、彼は飢え死にしそうになったので、その国の金持ちに泣きついて、豚の番人にしてもらった。
しかし、給料が安いために、ご飯を充分に食べることができない。
そこで、彼は豚に食べさせるイナゴマメを食べようとしたが、どうしても具合よくのどをとおらない。
彼はすき腹をかかえて、すっかり考えこんでしまった。
――父の家では、雇い人にさえも食べきれないほどの食べ物があたえられている。
それなのに、私はここで飢え死にしそうになっている。私はとんでもない間違いをしてしまったのだ。
これからすぐ、父のところへ戻ろう。そしておわびをして、心を入替て暮らすことにしよう。
たとえ元通り息子として扱ってはくれなくとも、せめて雇い人の仲間には加えてくれるに違いない――
彼は自分のあやまちを深く深く反省し、すっかり心を入替て故郷へ向かって出発した。
やがて、この息子が乞食のような姿になって、生まれ故郷の家の前まで戻ってきたとき、父親は息をはずませて走り寄ってきた。
やせ細った息子をしっかりとだきしめて、
「おお、よく帰ってきてくれた。何………おまえが悪かったと………。
それに気がついてくれさえすれば、わしには何もいうことはない。早く家のなかにはいれ。
遠慮することはないぞ。おまえの家ではないか。まず、着物を着かえたらどうだ。
いや、風呂にはいるのが先だ。わしはおまえが死んだとばかり思っておった。
生きて帰ってきてくれて、こんなにうれしいことはないぞ。」
怒るどころか、父親は涙を流して喜び、大騒ぎをしてお祝いをしてくれた。
まもなく、兄が畑から帰ってきてみると、家のなかが大変にそうそうしい。
不思議に思って、どうしたわげかと召使にたずねた。
「あなたの弟さんがヒョッコリ帰ってきたので、ご主人さまが喜んで、お祝いをしているのです。」
これを聞いて、兄はカッとなった。顔色をかえて父親のところへいき、猛然と文句をいい始めた。
「お父さん、私は毎日、一生懸命に畑で働いております。あなたのいいつけにそむいたこともありません。
それなのに、あなたは私のためには、今日のようなすばらしいごちそうをつくってくれたことは一度もありません。
一体、どうして、弟ばかりをかわいがるのですか。
弟はしたいほうだいのことをして、せっかくもらった財産を無駄に使いつくしてしまったんですよ。」
そういわれて、父親はちょっと困ったような顔をしたが、すぐ気をとりなおして、噛(か)んでふくめるようにやさしく説き聞かせた。
「そんなに怒るものではない。おまえはあの子の兄ではないか。おまえはいつもわしと一緒にいる。
わしのものはみな、おまえのものなのだ。おまえにはわしの気持ちがよくわかっているはずではないか。
自分の過(あやま)ちに気がついて、深く後悔しながら帰ってきた弟を見て、おまえもわしとともに喜べないものだろうか。
わしはこんなにうれしいことはないと思う。」
父親の言葉はまるで清らかな流れのように、兄の胸のなかにしみとおっていった。
神はこの父親にひとしい。罪をおかした者が、その罪に気づくのを待っていてくださるのだ。
心をあらためさえすれば、神はいつでも喜んで許してくれる。
だから、けっしてやけになったり、いこじになったりしてはいけない。
神の愛を信じて、そのふところにとびこんでいけば、神はやさしく迎えてくれるのである。 |
それでは神はいつもやさしいのかというと、イエスは、
「心のねじけている者にたいしては神はこの上なく厳しい。」
といって、つぎのような話をしている。
ある王が、家来に大金を貸したことがあった。約束の日がさてもその金を返さないので、
「おまえの持っているものをざんぶ売りはらっても、すぐ返さなくてはいかん。」と命令した。
するとその家来は
「どうか、もうしばらくお待ちください。近日中にはかならずお返しいたします。」
とひれふして頼むので、王は哀れに思って、待ってやることにした。
ところが、この家来は王のところに呼びだされた帰り道で、わずかな金を貸したことのある友だちに出会った。
すると、「おれが貸した金を、いますぐ返せ。」といいはって、友だちがどんなに頭をさげて「待ってくれ」と頼んでも、少しも聞いてやろうとはしないで、とうとう牢屋にたたきこんでしまった。
これを見たほかの家来たちは、そのやりかたがあまりひどいのに黙っていられなくなり、一切を王に報告した。
王は大変に怒って、その家来をすぐに呼びだし、
「おまえは何というなさけ知らずだ、わしはおまえの願いを聞き入れてやったではないか………。
わしがおまえを哀れんだように、なぜ、おまえも友だちのいうことを聞いてやらないのか。」
と、激しく叱り付け、借金を返すまで、彼を牢屋に投げ入れてしまったということである。
あなた方は、このような虫のいい残酷なことを、けっしてしてはならない。
自分の罪は何度でも許してもらいながら、他人の同じ罪を平気でとがめだてするような人は、とても神の国にははいれない。
神のやさしい愛のうちには、いつも正義がふくまれているのである。
その厳しさを忘れてはならない。 |
イエスの説く神は、悔いあらためた者や、素直な心の持ち主にとってはやさしい愛の泉のように思えたが、反省心のない者や形式にばかりこだわっているような者にとっては、砂漠の太陽のごとくに厳しいものだったのである。
9 パリサイ人の悪だくみ
top
イエスは十二人の弟子(十二使徒)をもっていたといわれる。
おそらくこれは、ユダヤ民族が十二の種族からたっていたので、それにちなんで十二人ということにされたのであろう。
私は、イエスには、もっとたくさんの弟子かいたに違いないと思うが、その数はともかくとして、最初に弟子となったヘテロがある時、
「イエスさま、誰かが私にたいして罪をおかしたならば、私はいくたび許すべきでしょうか。七度まででしょうか。」
とたずねたことがある。これにたいして、
「いや、私は七度までとはいわない。七度を七十倍するまで許せという。」
イエスはこう答えているが、そのイエスもパリサイ人だけは許すことができなかった。
彼らはいつも神をわがもの顔にして威張りちらし、ほかの人の悪口ばかりいっていたからである。
つぎのイエスの話から、彼らがどんなに思いあがった人間であったかを知ることができる。
二人の者が神殿へお祈りをしにでかけた。一人はパリサイ人で、一人は取調人であった。
パリサイ人は神殿の中まで入っていって、
「神よ、私はほかの人のように悪いことはしません。
また、取調人のような人間でないことを感謝します。
私は毎週かかさず二度断食をして、所得の十分の一はかならず納めております。」
と、堂々と祈りをささげたが、取調人は神殿のそばにも近寄らず、
「神さま、私を哀れんでください。」と、深く嘆きながら祈っただけであった。
あなた方は、この二人の人間のうち、どちらが神から正しい人間とされると思うであろうか。
いうまでもなく、それは取調人である。
神からみれば、自分で自分を偉いと思いこんでいるような人間には、何の価値もないのである。
自分の欠点を知り、自分のいたらなさを自覚している人こそ、本当に正しい、そして尊い人間なのである。
神とは完全なものであり、人間とは不完全なものである。
人間であるかぎりは、誰にでもかならず過(あやま)ちや欠点があるものだ。
それに気づいてかぎりない努力をするところに、人間の真の「人間らしさ」があるのだといえよう。
そういう人でなければ、ほかの人にたいして、やさしい思いやりをもつことなどは、とてもできはしない。
イエスは人間のいたらなさをシミジミと知りつくしていたので、彼の心はいつでも、そのやさしい思いやりに満ちあふれていたのである。
ある日のこと、パリサイ人たちは、一人の女を力ずくでつれてきて、イエスのまえにひきすえ、
「この女はいちばん重い罪をおかしているところをつかまった。 モーゼの教えによると、石でぶち殺さなければならないのだが、そのまえにぜひあなたの考えを聞きたい。」
といって、まわりじゅうからつめよってきた。
彼らにとっては、この女の事件は、イエスをやりこめるための、絶好の手段であった。
というのはローマの法律下にあったその頃のユダヤ人には、死罪を決定する権利があたえられていなかったからである。
したがって、もしもイエスが「殺せ」といえば、法律違反者として彼を訴えることができたし、「殺すな」といえば、ユダヤ民族の伝統的宗教の掟(おきて)にそむく者として、やはり訴えることができたのである。
形式や伝統を何よりも重んじるパリサイ人にとっては形式よりも内容を、そして伝統よりも創造を尊ぶイエスは、世の中の秩序をみだす危険な反逆者にほかならなかった。
何とかしてしくじらせて、牢屋にでもたたきこんでしまいたかったのである。 |

イエスの生誕を記念して建てられたベツレヘムの教会
|
彼らの悪だくみを知ってか知らずか、イエスは黙ったまま身をこごませ、地面に指で何かを書きはじめた。
いつもはすぐに答えるイエスが、いつまでも口を開かないので、彼らは意地悪くせきたてた、
「どうしたのだ………。こんなことに返答ができないのか。」
「グズグズしないで、ハッキリした返事を聞かせてもらいたいものだ。」
まわりには、続々と人が集まってきた。ガヤガヤと騒ぎたてる。
なかには、「さっさと殺してしまえ」と叫ぶ者もいる。
その無責任な叫び声はたちまち次から次へと伝わりはじめた。
パリサイ人たちは心のなかでニヤリと笑って、針を突きさすように問いただした。
「さあ、早くあなたの意見を聞かせてほしい、みんなは『殺せ殺せ』といって、あんなに騒ぎたてている。
あなたはどう思うのか。」
イエスはゆっくりと体を起こした。
彼はうれいをふくんだまなざしで、騒ぎたてている人々を見まわしながら、ただ一言、
「あなた方のうちで、今までに何も罪をおかしたことのない人だけが、この女に石をぶつける資格がある。」
と厳しくこういいはなって、再びかがみこんで、何かを地面に書きはじめた。
イエスのいう罪とは、法律に反する罪ではなく、心の罪である。心のなかでは誰でも罪をおかす。
悪い考えを心のなかに浮かべたことのない人は、この世の中に一人もいないだろう。
すでに石を手に持っていた人がソーッと、その石を足元に置いてしまった。
もしも石を投げようものなら、「なんて、あつかましい奴だ」と思われるにきまっている。
大勢の人の見ている前ではとても投げるわけにはいかない。
集まっていた人々は、一人去り、二人去りして、しまいにはパリサイ人たちも、コソコソと姿を消してしまった。
イエスの深い人間愛のまえには、彼らの悪だくみも、何の役にもたたなかったのである。
10 隣人愛 top
イエスはガリラヤ、サマリア、ユダヤといろいろな地方をめぐり歩きながら、神について語り、いかに生きるべきかを説いた。
「空の鳥を見るがよい。撒(ま)くことも、刈ることもせず、倉に取入れることもしない。
それなのにあなた方の天の父は彼を養っていてくださる。
あなた方は彼らよりも、はるかにすぐれた者ではないか。
あなた方のうち、誰か思いわずらったからとて、自分の寿命をわずかでものばすことができようか。
また、なぜ、着物のことで思いわずらうのか。
野の花がどうして育っているか、考えて見るがよい。
働きもせず、紡ぎもしない。
しかし、あなた方にいうが、栄華をきわめたときのソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。」
こんなふうにいわれてみれば、まことにそのとおりなのだが、私たちはついうっかりして、生命や体よりも飲食物や着物のほうを重んじてしまう。
つまり、イエスは私たちが日ごろ見のがしてしまっている真理を、詩情ゆたかに取りあげて、人間の生きるべき筋道をハッキリと示してくれたのである。
いわば、彼は「神に酔う詩人」であったのだ。
このような美しい言葉で語られるイエスの教えは、しだいに多くの人々の心をひきつけ、信者の間からは、
――イエスさまを王にして、ユダヤ民族の独立国家をつくりたい――
と願うような者さえもでてきた。
しかし、イエスの評判かよくなればなるほど、パリサイ人は彼をいよいよ激しく憎んで、何かにつけて、いやがらせや妨害をするようになった。
その頃、パリサイ人は約六千人もおり、社会的に一つの強い勢力をなしていたので、イエスにとってはまことにやっかいな存在であった。
しかも、イエスのことをよく思わなかったのは、パリサイ人だけだったのではない。
ユダヤ教の祭司や財産のあるユダヤ人の貴族たちも、
――イエスという男は、貧乏人どもを集めて、社会をひっくり返そうとしているのではなかろうか。
早く何とかしまつをしてしまわないと、我々の地位や財率があぶない――
などと、イエスにたいしておよそ見当はずれの考えをもっていたのである。
しかし、彼らがどう思おうと、イエスはただひたすら神への道を歩みつづけていた。
彼がガリラヤからヨルダン川をわたり、神の都エルサレムへ向かって旅をしていたときのことである。
途中で出会った教法師(ユダヤ教の掟を教える人)が、イエスにつぎのような質問をした。
「モーゼからあたえられた掟のうちでは、どれがいちばん大切でしょうか。」
「私は、『あなたの心をつくし、精神をつくし、思いをつくしてあなたの神を愛しなさい』という掟と、『自分自身と同じように隣人を愛しなさい』という、この二つの掟(おきて)が、いちばん大切なものだと思います。」
「その『隣人』とは、具体的にはどんな人のことをいうのでしょうか。」
この質問に答えて、イエスは「善良なサマリア人の話」をしてやった。
一人のユダヤ人がエルサレムからエリコヘいく途中で、強盗におそわれた。
強盗はたちまち彼に一撃をあびせ、持ちものはいうまでもなく、着ているものまではぎとって、風のようにどこかへ逃げ去ってしまった。
血にそまってたおれたユダヤ人は深い傷を受けて身動き一つできなかった。
うめき声をあげながら、まるで捨てられた石のように、道ばたに転がっていたのである。
そこへ一人の祭司がとおりかかった。
しかし、彼は「さわらぬ神にたたりなし」とでも考えたのか、わざと横を向いて、知らん顔でとおりすぎてしまった。
日ごろ神殿のなかで神につかえて暮らしている身でありながら、自分の都合しか考えなかったのである。
それからしばらくすると、やはり神について説くことによって生活しているレビ人(びと)がとおりがかった。
彼も、死にかけている旅人を見るとあわてて目をそらし、気がつかないふりをしていきすぎてしまった。
さて、その後にとおりかかったのは、ユダヤ人からいつも除(の)け者にされ、仇のように憎まれているサマリア国の人であった。
彼は血みどろになってたおれているユダヤ人を見ると、日ごろ仲の悪いことなどはすっかり忘れてしまった。
やさしく抱き起こして傷の手当てをしてやったばかりか、自分の馬にのせて旅館までつれていき、夜どおし世話をしてやった。
そのうえ、翌朝出発するときには、旅館の主人にお金をあずけて、
「どうか、私にかわって、この人のめんどうをみてやってください。医者への払いや何かで、もしもお金がたりないようでしたら、私が帰りに寄ってかならず払いますから、くれぐれもよろしくお願いします。」
そういい残して旅立っていったということである。
あなたはどう思う………。この三人のうちで、だれが傷ついたユダヤ人の隣人であろうか。 |
隣人とは、このサマリア人のように、縁もゆかりもない者にたいして、いやそれどころか、怨(うら)みや憎しみをもつ者にたいしてさえも、愛情をそそぐ人をいうのである。
イエスはまさに、世界じゅうの人々の隣人であった。
彼の愛情は泉のように自然にわきあふれて、人種や国家のちがいには全くかかわりなく、人間の不幸や悩み、迷いや苦しみの暗い谷間に、明るく清く流れこんでいったのである。
彼の心は、人類の言葉かりを思って、ほかのことを思うひまのないほどすみきっていた。
それだけに、心のおじけた者やにごった者にたいしては、彼はだれよりもきびしかった。
世の中の不正や悪を、けっして見のがすことができなかったのである。
11 生ける神殿と永遠の十字架
top
貧しい人や不幸な人々の間で人気が高まるにつれて、イエスはひそかに死を覚悟するようになった。
パリサイ人、祭司、貴族などの反感が、ますます激しくなってきたからである。
しかし、彼は少しも恐れなかった。みずから、
「地上に平和を投げあたえるために、私がきたのだと思ってはいけない。
私は平和をあたえるためにきたのではない。刃をあたえるためにきたのだ。」
と語っているとおり、争いのさけがたいことは、最初からわかっていたのである。
神への道を清く正しく歩もうとする人や、真理のために献身する人々は、不幸な人や愚かな人を導いて、暗い世の中を明るくしようとする。
悪い社会をよりよい社会へと前進させようとする。
ところが、いつの時代でも、どこの国でも、大多数の権力者、上層階級、金持ちなどはそれを歓迎しない。
彼らは明るい世の中よりも暗い社会を好み、前進よりも今までどおりの状態のほうを望む。
なぜならば、彼らにとっては、今まで通の方が都合がいいからだ。
せっかく手に入っている地位や財産を死んでも手離したくないからだ。
これでは争いのさけられるはずがない。
こんなわけで、イエスの身辺にしだいに死の影がせまってきた頃、彼は群衆の歓呼の声に迎えられながら、敵の本陣ともいうべきエルサレムにのりこんだ。
「ホザナ、ホザナ、(バンザイというような意味)、ダビデ(父ヨセフの祖先)の子!」
「ホザナ、ホザナ、ユダヤの王!」
人々の熱狂ぶりはたとえようもないほどであった。
彼らはさきを争って、イエスのゆくてに、シュロの葉や自分の着ていた上着をしきつめて敬意をあらわした。
このありさまを見て、パリサイ人や祭司たちが苦々しく思ったことはいうまでもない。
「イエスよ。これらの人々を静かにさせてもらいたい。ここは神聖な都なのだ。」
「黙らせよ、というのですか。」
「そうだ。祭司からもご注意があった。」
「それではあなた方が黙らせるがよい。しかし、この人たちを黙らせても、石が叫ぶことだろう。」
イエスは振り向きもしないでこういって、神殿の内部へ進んでいった。
神殿の廊下には牛やヒツジなどがつながれており、売り物のハトを入れた篭がおいてあったり、両替屋が店をならべていたりした。 |

イエス受難の地エルサレム。
中央長方形は昔の神殿の地域。
|
毎年、過越(すぎこし)の祭りには、いろいろな国の人がそれぞれのお金を持ってエルサレムに集まってくるので、ここの両替屋は大繁昌していた。
神殿のまわりには各種の動物がひしめいていたが、それらはいずれも神へのお供え物にするためのものであった。
これを見たイエスは、ただちに縄をよってむちをつくり、家畜を追い払い、ハトを空にはなしてやり、両替屋の台を力まかせにひっくり返して、大声でさけんだ。
「これらのものをここより取り去れ。わが父の家を商売の場所にしてはならぬ!」
人々は腰をぬかすほどおどろいた。イエスの弟子たちでさえ、びっくりして立ちすくんでしまった。
人々のうちには、あわてて逃げだす者もいたが、イエスにくってかかってくる者もいた。
「あなたは何の資格があって、そんなことをいうのです?」
「こんなことをするからには、するだけのわけがあってのことでしょう。一体、どういうわけなのですか。」
これらの不平や質問に答えて、イエスは断固とした口調で語った。
「この神殿をこわしてしまいなさい。私は三日間で、新しい、生げる神殿を起こしてごらんにいれよう。」
「この神殿は四十六年もかかって建てたものです。三日ぐらいで建てなおせるはずはありません。」
「私は、この神殿よりもはるかに大切なものについて話しているのだ。
私のいう生ける神殿とは全人類がお互いに心の底から愛しあうようになったときの全世界を意味するのだ。」
多くの人々にはイエスの言葉を理解することができなかった。
彼らは、ヤウェー神のまつってある神殿よりも尊いものはないと信じていたからである。
しかし、イエスにとっては、人々の愛に満ちた正しい心こそ神の住み家であり、どんな立派な建物にもまさる神の殿堂であり、神の国だったのである。
しかし、エルサレムの神殿が何よりも尊ばれ、ユダヤ教の掟が何よりも重んじられている時代に、こんなことをしたり、こんなことをいったりすれば、当然、
「ユダヤ人でありながら、ユダヤの宗教をないがしろにするけしがらん男だ。死刑にするべきである。」
ということになる、
さて、この結果どうなったかは、すでに読者の皆さんもよくご存知のところであろう。
イエスは捕えられて法廷にひきだされた、
「おまえは神殿をこわせ、といったそうだが、それは本当か。」
「そのとおりである。」
「おまえは『神の子』だといっているそうだが、それも本当か。」
「いかにも、私は『神の子』である。そして『キリスト(救い主という意味)』である。」
この答えを聞いて、大祭司をはじめパリサイ人たちは「しめた」とばかりに怒鳴りはじめた。
「何という罰あたりだ。神をけがす今の言葉だけでも、おまえは充分に死刑にあたいする。もう何も聞く必要はない。」
彼らは口々にわめきたてながら、唾(つば)をはきかげたり、なぐりつけたりしたのち、ローマから派遣されてきている総督ピラトのところへ、イエスを手荒くひきたてていった。
「私たちは、この男をあなたさまに死刑にしていただこうと思ってつれてまいりました。
私どもユダヤ人には人の命をうばうことは許されておりません。どうか、よろしくお願いいたします。」
「なぜ、この男を死刑にせねばならぬのか、そのわけを聞かせてもらおう。」
ピラトがこういうと、彼らはいかにも憎々しげに、
「この男は自分を神の子だというばかりか、キリストだとさえいうのです。」
「メシアだとか、ユダヤ人の王だとかいい、ローマ政府に謀反(むほん)をくわだてております。」
「このままほうっておいたならば、ますます国民を迷わし、しまいにはどんなに悪いことをするかもしれません。」
それこそ口からでまかせに、考えられるかぎりの悪口をいいはじめた。
しばらくの間、彼らのいうことを黙って聞いていたピラトはおしのように沈黙をつづけるイエスに向かって、
「おまえは、確かにユダヤ人の王なのか。」とたずねた。
「そうです。しかし、私の求める王国はこの世にあるものではなく、人々の心のなかにあるものなのです。」 |

ピラトの審問。上段中央がピラト。
|
イエスはただ一言、このように答えただけで、その後は何を聞かれても、一言も返事をしなかった。
むちでたたかれても、足げにされても、イエスはくちびるをかたくとじて、巌(いわお)のように毅然としていた。
その態度があまりに立派なので、ピラトは何とかして助けてやりたいと思った。
「わしには、この男に罪があるとは思えない。許してやろうではないか。」
といったが、祭司やパリサイ人がどうしても承知しなかった。
ものすごい勢いでいっせいに騒ぎたてるので、ついにやむをえずく死刑を行なわせることになってしまったのである。
こうして、イエスは三十三才の若さで、十字架上に無残な死をとげた。
しかし、「神の子」イエスは、たちまち人々の心のなかによみがえった。
彼の愛の教えは弟子たちに受継がれて、しだいに人々の心のうちにしみこんでいった。
もちろん、ひどい迫害や圧迫もうけた。
しかし、イエスの説いた神は、一ユダヤ民族のためだけの神ではなく、全人類に幸福を約束する神であった。
幸福を願う点では国や民族の違いはない。
その教えは、ヨーロッパの人々からも、アジアの人々からも、東の空にのぼらんとする太陽のようにあおぎ見られた。
今も昔も、人間は愛に飢えている。暖かい愛情を願い求めない人はいない。
イエスの教えは、人間の誰もがもっている心のすきまに、暖かい風を送りこんで、この世に生きる悩みや迷いを、やさしくいやしてやったのだ。
その愛の風はときにはやさしく、ときには厳しく、全世界に吹きおよんで、今日では九億におよぶ人々の心をやさしくあたため、また、厳しくはげましている。
私たちは、一人のイエス・キリストのなかに、砂漠で育ったユダヤ民族のあらあらしい厳しさと、地中海沿岸の温和な気候にめぐまれて暮らしている人々のやさしさとを、同時に見いだすことができる。
彼は自分自身を犠牲として神にささげ、みずからの血を、人類救済の約束のしるしとした。
その精神と教えは、『聖書』のうちに見事に伝えられて、人類の生きるべき永遠の道しるべとなっている。
イエスが死んで以来、早くも二千年の年月が流れた。
しかし、今日もなお、彼は私たちの心のなかに広くよみがえって、うまずたゆまず、神の国の建設につとめているのである。
top
**************************************** |