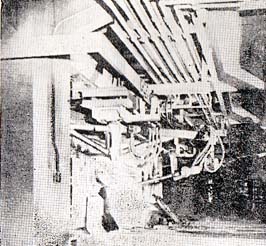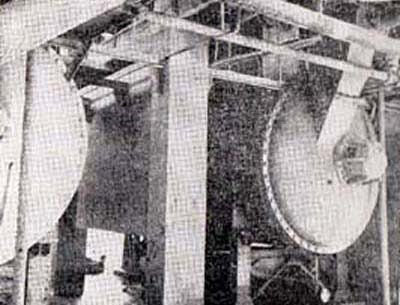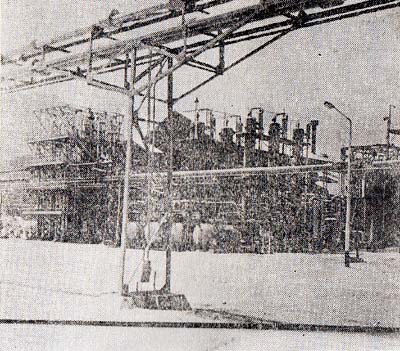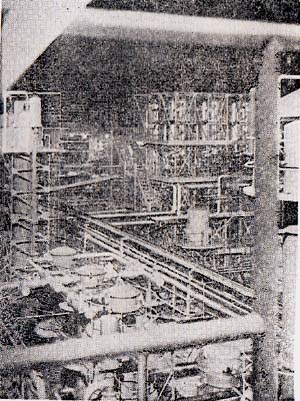|
****************************************
Index 産業革命 家庭製品 建設材料 石油工業 プラスチック 半導体
Ⅴ プラスチック
十二章 新しい材料プラスチック 《セルロイドとベークライト》
top
プラスチック、セルロイド、ベークライト
1 はじめに
第二次大戦が終ったとき、これほどプラスチックが広まるとは、だれが考えたろう。
いまでは金属のかわりになるものから、玩具や金魚や、佃煮をいれる袋まで作られている。
しかし、プラスチック――練物をかためて作ったもの――のおこりは古い。
昔フイルムや玩具や文房具やかざり玉に使われたセルロイドと、いまでも電球のソケットなどに使われているベークライトが、プラスチックの先祖である。
また、ビニールやポリエチレンなども、作られたのは戦争前のことだった。
ただそれが、戦争向けに使われていたので、私たちの目にふれなかっただけだったのだ。
私たちはよくこのことを考えてみないといけない。
なぜなら、発明した化学者は、きっと心の中では、産業や生活をゆたかにするために作りだそうと努力したにちがいないのだから、また、いろいろなプラスチックが、突然発明されたのではないことに注意してほしい。
次にお話するセルロイドやアセテートを作る原料は、火薬や紙を作る原料セルロース(繊維素)なしには発明されなかったろう。
ベークライトや合成ゴムは、石炭タールの研究から始った合成化学の知識や工業なしにはなかったろう。
また、ビニールやアセテートは、アセチレン工業なしにはできなかっただろうし、それを作るには、特別な高圧技術を使うアンモニア合成工業がなくてはならなかった。
プラスチックの歴史は、もとになる大事な化学工業の発達の歴史でもある。
2 償金一万ドル top
西部から十年ぶりにかえってきたハイアット青年は、ニューヨーク市アルバニーの町かどで見た貼紙がどうしても忘れられなかった。
象牙の代用品を考えだした者には一万ドルの賞金をさしあげます。
フェラン・コランダー商会 |
ときは一八六三年、南北戦争が終った東部アメリカの話である。
その頃のアメリカの上流階級では、「玉突き」が大流行。
ところが玉突きの玉は高価な象牙でできていた。
玉突き会社であるコランダー商会は、何とかこの代用品はないものかと、血眼になっていたのだった。
「よし、一つ応募するか。」
ハイアット青年の本職は印刷工なのだが、なかなかの天分でもういくつかの発明をやったことがあったので、夢中になってこの研究にうちこんだ。
「なにを材料にしたらよいだろうか?」
ハイアットは、いろいろな材料をためしてみた。粉々にした木くず、ふやかしたボロきれ、パルプを膠(にかわ)、澱粉、シェラック(ワニスの原料)、水絆創膏(コロジオン)などをつなぎにしてこねてみた。
木くずと膠を混ぜた物でチェスの駒なども作ってみた。しかし、どれもうまくいかない。
三年がすぎた。夜も休日もなかった。
ついにハイアットは、紙くずとシェラックとコロジオンとで玉突きの玉を作ってしまった。
一万ドルにはほどとおかったが、賞金を手にいれたハイアットは、どうも自分の作ったものに満足できなかった。
コロジオンでかためたものは、乾くと縮んでしまうのである。
「コロジオンが乾いても縮まない方法はないものか?」
実はすでに数年前、イギリスでパークスという技師が、うまい方法を見つけていたことなど、ハイアットは知る由もなかった。
3 パークシンという新物質 top
つまりコロジオンは、硝酸繊維素(ニトロセルロース)をエーテルとアルコールに溶かしたネバネバした液体で、乾くとうすい皮ができるので、水絆創膏としていまでも使われている。
が、もともと硝酸繊維素は爆薬である。硝化綿といわれるように、これは綿と硫酸と硝酸の混合液につけて作られる。
この硝化綿を作ったドイツの化学者シェーンバインから、イギリスのパークス技師は、硝酸繊維素の見本を送ってもらったのである。一八四五年頃のことだろうか。
冶金学者でゴム製造技師のパークスは、大変先見の明のある人で、硝酸繊維素からコロジオンを作り、それを金属の形にいれ、アルコールとエーテルを蒸発させれば、思いどおりの形ができ、しかも安くて強い物質が作れることをしると、コロジオンのすばらしい未来にすぐ気がついた。
パークスはコロジオンのエーテルとアルコールを蒸発させ乾かしたあとにのこる、かたい弾力性のある物質を「パークシン」と名づけた。彼はこれで花を作ったり、いれものを作って一八六二年の万国博覧会に出品した。
しかし、パークシンには一つ具合のわるいことがあった。
それはコロジオンをかわかすと、もとの形より縮んでしまうことだった。
パータスはそれを防ぐために樟脳(しょうのう)を使うことを考えついた。
このためパークシンぱずっと品質のよいものになった。
パークスはいまのセルロイドを作ったのである。
彼は会社を作ってパークシンを売り出したが、残念なことにこの会社は二、三年でつぶれてしまった。
4 役にたったぬり薬、カンフルチンキ
top
そんなことは知らないハイアットは、パークスが突き当ったのと同じ問題で苦しんだ。
コロジオン中の硝酸繊維素かよく溶かす薬品をまぜればいいことまでわかった。
「何がいいだろう」――ハイアットは思いつくままに片っ端からためしてみた。
あるときハイアットは、薬棚にあったぬり薬カンフルチンキを混ぜてみた。なかなか具合がよかった。
カンフルチンキは「樟脳」をアルコールに溶かしたもの、この「樟脳」がすばらしい働きをしたのだ。
一八七〇年(明治三年)のことである。
ついに研究を完成した。こうしてできたものは、熱をかけるとどんな形にもでき、普通の温度では象牙のようにかたく弾力のあるものだった。
ハイアットは弟のイサヤと協力して、これに「セルロイド」と名をつけてアルバニーに会社を作った。
会社で初めて売り出しだのは義歯だった。セルロイドはそれからいろいろな用途に使われ、世界中に拡がっていった。
写真のフイルムなどにもずいぶん使われた。
5 「あづま玉」のかんざし top
さて、 日本のセルロイドはどうだろうか?
明治十八年、東京の鼈甲(べっこう)・珊瑚(さんご)商「かずさや」の店先は大変なにぎわいである。 売りだしたばかりの「あづま玉」のかんざしが評判であった。
「なにしろ、本物の珊瑚そっくりの玉でしょう。それに安いのです。 このかんざしの玉など、珊瑚にみられない色合いですもの。」
実は、このかんざしの玉は、セルロイドだったのである。 三井物産会社がドイツから輸入したもので、輸入したセルロイド板を「鼈甲」作りの職人がけずって、かんざしの玉にみがきあげたものだった。 その職人の一人、向島の小蝶六三郎も、自分のみがいた「あづま玉」の売れゆきがいいのに気をよくしていた。
ところが明治二十二年夏すぎ、いままで「あづま玉」を取り扱っていたほかの店先に、それとそっくりの「あさひ玉」なるものが現れた。 |

セルロイド製のかんざしを売り出して賑わう「かずさ屋」
|
びっくりした「かずさや」が調べてみておどろいた。仕入先は小蝶だという。
数ヵ月まえに仕事熱心の小蝶は、近くの東京職工学校に知合いの松井先生を訪ねて、セルロイドの性質を教わりにいった。
すると、セルロイドは九〇度ぐらしに熱すると軟らかになり、型で押せば、楽に形ができることを知った(熱可塑性という)。
「それなら、苦労してセルロイドを削ることなんかない。熱して形にとるほうがよほどはやい。」
そこで小蝶は、セルロイドのけずりくずをあつめ、かためて玉にする機械を作り上げ、できた玉を「あさひ玉」と名付けて売出したのだった。
6 日本最初のセルロイド工場 top
「今度は自分でセルロイドを作ってやろう。」
小蝶はつづいて、こう決心し、明治二十三年、向島に昇光社というセルロイド工場をたてた。
しかし、薬品の調合、製造の機械、何から何まで胡蝶が考え出さねばならない。
紡績会社からボロをもらって硫酸と硝酸で硝酸繊維素からくるのだが、どんな割合、どんな時間つけておいていいかわからない。
それにできた硝酸繊維素を蒸気で熱して乾かすという危険なことをやっていた。いつ爆発するかわからない。
小蝶は、硝酸繊維素を乾かした残りの蒸気で風呂をわかして従業員や家族にはいってもらっていた。
これがいけなかった。
明治二十三年六月十四日午後三地頃、小蝶の家族がその浴室にいたとき、となりの硝酸繊維素の乾燥室が爆発した。
そして、奥さんはじめ家族の人たちが瀕死の重傷をおった。
それから一ヵ月たったとき、また爆発して工員二人が重傷をおった。
このかなしみに心かかわらず小蝶は努力したが、できるセルロイドはとうてい輸入品にはかなわない。
ついに、日本最初のセルロイド工場は、明治二十五年十一月に解散した。
小蝶はその後、細々とくらしていたが、明治四十一年四月二日夜自殺してしまった。
一方ちょうどこの年、日本は近代的セルロイド工場施設に着手しはじめていたのである。
セルロイドの原料として、かくことのできない樟脳は、日清戦争後日本の領土になった台湾の特産品で、諸外国に輸出していた。
その頃台湾の樟脳技師の松田茂太郎は、
「樟脳を輸出する日本人が、セルロイドを輸入していたのではいけない。ぜひ日本にも、セルロイドの工場を作ろう。」
と考えた。
松田の努力のすえ、当時の資本家鈴木直吉たちは、外国の技師をまねいて、兵庫県網干(あぼし)に、日本セルロイド人造絹糸会社を作った。
同じころ、大阪の堺にも堺セルロイド会社が作られた。
日本人技師たちは、夜もねむらずに研究して、とうとう日本人だけで立派な品物を作りだすことができた。
その後日本のセルこイドはどんどん発展をつづけ、世界でも指折りのセルロイド生産国になった。
7 ベークライトの話 《特別読物6》
top
科学を産業に役だてよう
「これからは電気工業の時代です。
私たちのいままでの研究を、この電気工業に役だてなければなりません。」
ドイツの電気工業を視察してかえったばかりのベークランドは、ニューヨークのハドソン川に面した真新しい実験室に、助手たちを集めて、こう話した。
一九○○年のこと、ベルギー生まれのベークランドはこのとき三十七歳であった。
ドイツではすでに、苛性ソーダを電気分解によって作る工業などがさかんになっていた。
アメリカでも十年ほど前から、ナイアガラに水力発電所かできて、そのあたりにたくさんの電気化学工業会社ができていた。
ベークランドがまず目をつけたのは、電解ソーダを作るときに必要な容器(電解槽)の改良であった。
この改良はすぐ成功して、新しい電気化学会社がそのために作られた。
ところがそのとき、ベークランドの頭には、もうつぎの研究ができあかっていた。
「今度は、良質の電気絶縁材を作ることだ。」
なるほど、これから電気はますます利用され、しだいに高圧電気が必要になる。
だから、いままでのような天然の絶縁材(シェラックなど)では電気漏れがしてしまうだろう。
助手たちの休むひまはなかった。さて、どんな材料が絶縁によいだろうか。 |

ベルギー生まれの
ベークランド(1863~1944)は、
アメリカでベークライトを発明した。
|
前の失敗をよく調べてすすむ
いろいろ調べているうちにベークランドは、二十八年前の一八七二年に、ドイツの大化学者バイヤーが、二つの化学薬品をまぜでシュラックという絶縁材料に似たものを作った、ということを知った。
バイヤーは、フェノールとホルマリンをまぜ、それに少量の酸を入れてこの物質を作ったのだが、これはシュラックとちがって熱にもつよく、薬品にもとけないじょうぶなものだった。
そのためにかえって、加工もできず、塗料にもするわけにもいかず、とうとうバイヤーはこの研究をやめてしまうのだった。
「よく調べていけば、フェノールとホルマリンから新しい絶縁材ができるかもしれないぞ!」
ベークーランドは、バイヤーやそのほかの人たちの失敗をよく調べることにした。フェノールとホルマリンとが、一体どんなふうにむすびつくのか、それをしらなければならなかった。
それには、二つの薬品が、ゆっくりとむすびつくような工夫をしなくてはならない。
バイヤーは酸を加えたために、そのむすびつきかたが早くなりすぎたのではないだろうか?
では、酸のかわりにアルカリを加えたらどうだろう?
そこで、ベークランドは、アンモニアをすこしいれて、二つの薬品を結びつけてみた。
すると、できた物質はかたまらず、薬品にとけやすいではないか。
そしてうまいことに、これを熱しなから圧力をかけると、はじめて硬い熱にも薬品にも強い物質になるのだ(熱硬化性)。
しかもこの物質は、すぐれた絶縁材でもあったのだ。
だから、熱と圧力を加えないうちに薬品で溶かして形にいれ、次に熱と圧力を加えれば、どんな形の絶縁材でもできる。
ベークランドはこの物質に自分の名にちなんでベークライトというよび名をつけた。
ベークランドは、前の失敗をよく調べ、ベークライトの熱硬化性という特別な性質を見つけて、これに成功したのだった。
ベークライトの宣伝におおわらわ
一九○九年にベークライトの発明が公表されると、新しい電気の絶縁物を探していた電気技術者たちの間で大評判になった。
けれども当時の工業家たちは、この海の物とも山の物ともわからぬベークライトを利用することは大変な冒険だと考えた。 もし失敗したら大損だと、おいそれとベークライトをむかえようとはしなかった。
それにベークライトを作るためにいままでとはちがった新しい機械をそろえなければならなかった。
ベークランドは、何度も講演会をひらいて説明し、自らベークライトの使い道を研究して、人々に根気よくそれを教えたのだった。
この努力が実をむすんで、アメリカのウェスチング電気会社や、ブーントンゴム会社がベークライトを取上げ、一九一〇年には、ベークランドの手でゼネラルベークライト会社が誕生した。
高峰博士が一役
日本の科字者高峰譲吉博士にアメリ力でベークランド博士としたしいあいだがらだった。
日本の三共会社は高峰博士の発見したタカジアスターゼを日本で初めて売り出した会社だが、薬品業を中心にする一方、高峰博士がアメリカからもちかえる新しい発見や事業に手をそめていた。
ベークライトもその一つであった。
一九一四年、三共会社は技師をアメリカに送ってベークライト工場で実際の勉強をさせ、日本最初のベークライト工場を東京品川に作った。
ベークランド博士も三度ほど日本をおとずれて、工場を指導したのだが、本格的な生産が始ってまもなく、第一次世界大戦が始って、原料の輸入がとまってしまった。
当時の日本は、まだ原料のフェノールやホルマリンを合成する工業がそだっていなかったので、生産は思うようにあがらず、そのうえ、工場が火災にあったり、震災にあったりして、大正のすえに本格的生産にはいるまでは苦闘の連続であった。
高宮兄弟の作ったベークライト
ところが大正の末頃、大阪地方にすぐれたベークライ卜製のたばこパイプが広く出まわっていた。
産地は大阪府河内郡長瀬村であるという。
実はこのパイプこそ、大阪府東成郡猪飼町の高宮兄弟が自分たちの力だけで作り上げた、日本のベークライトだったのである。
兄の高宮謙二は薬剤師で、ふとしたことから、フェノールとホルマリンとをむすびつけると、琥珀(こはく)ににたベークライトができることをしり、すでに大正四年四月頃から、ちょうどベークランドがやったような苦心をしたのだった。
いろいろな薬品もまぜてみた。熱の加減もかえてみた。
しかし、できるものは、赤色で不透明で、とても売り物にはならなかった。
二年のあいだ苦心がつづいた後、大正六年春ごろになって、やっとかなりよいものができた。
この研究のあとを、弟の高宮孝二がうけついだ。孝二は骨製のパイプを作っていたので、技術者でもなく、大変苦労した。
しかし、謙二の研究助手をしていた人が、うっかりして製造の秘密をもらしてしまった。
秘密はもれて大阪各地に伝わった。
そのために、高宮たちのパイプができたときには、同じような製品がでまわって、結局損をしてしまった。
日本では、ベークライトは、電気工業だけでなく、人絹を作る紡績機械の部品としておおきな役目をはたし、長いことベークライトはプラスチックの王座をしめていた。
十三章 外国にたよらず独力で 《アセテートとビニール》
アセチレンから作るプラスチック
top
1 はじめに
いまでも縁日といえば、アセチレンの青白い光と匂いと煙を思い出す。 あの灯りのもとになるアセチレンガスは大切な工業原料である。
このアセチレンは、カーバイドという黒いかたまりに水をそそいでえられるガスである。
ところでカーバイドは、コークスと石灰石とを電気炉にいれて作る。 たくさんの電気がいるが、日本では特に電気が豊富だったので、明治の末から作られていた。
初めは、カーバイドから石灰窒素肥料を作り、そこから硫安を作っていた大正末から昭和の初めにかけて、硫安がアンモニア合成(空中の窒素と水素から合成)から作られるようになったので、カーバイドの使い道がなくなってきた。 |
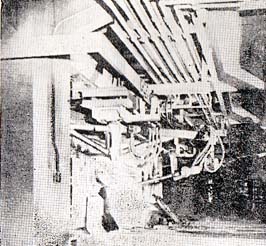
カーバイドをつくる電気炉
|
つまりアセチレンを何とか利用して、そこからいろいろなものを作りださないわけにはいかなくなった。
昭和七年(一九三二年)、九州・水俣にある日本窒素肥料会社でも、こういう問題にぶつかって、そこの研究員たちは、何とか、アセチレンを原料にしたものを作るように、命令された。
まず、アセチレンから酢酸(酢)が作られた。
これはもとは木材を蒸し焼きにしてでてくる液から取り出されていたのだった。
すぐさまこれが酢酸繊維素にされて、神谷博士のアセテートの発明になった。
一方、中村技師は、アセチレンからビニールを作った。
ここではこの二人の日本人の努力についてお話しよう。
2 ついに糸巻きは回り始めた top
その朝、しきりに神社の前で心をしずめようとしているのは、日本窒素肥料会社の水俣工場でアセテートを研究している神谷卓郎だ。
研究はもう三年もつづいていた。
「今度こそうまく行くように。」
アセテートの糸を作るには、綿の実からとった毛と酢酸(食用の酢の原料)とから酢酸繊維素(アセテートフレーク)を作り、このフレークをアセトンに溶かした液を小さな孔(ノズル)から噴き出させ、かたまったところを糸にして巻き取るのである。
が、この最後の糸巻きの段階つまり紡糸(ぼうし)試験がなかなかむずかしかった。
何回も失敗し、どうしても糸にできなかったのだ。」
そして、「今日こそは」というのである。
研究室の一同がじっと見守る前で、フレークが噴き出してきた。手製の糸巻きの筒がまわり始めた。
すると、まかれた糸がはっきりわかるようにと、黒い紙をはった糸巻きの筒の上に、一筋、二筋と透明な糸がまきついていくではないか! 絹のように光る糸だ。
よろこびの溜息をもらす一同のまえに約一〇グラムのきれいな糸ができあがった。
昭和八年(一九三三年)十一月のことである。
3 初めはフィルムや飛行機の塗料に
top
アセテートのもとである酢酸繊維素をはじめて作ったのは、ドイツの化学者シェツツェンペルガーで、一八六五年である。
その後一八九四年に、ビスコースの発明者クロスとビバンとブリップスが酢酸繊維素から人造絹糸(つまりアセテート)を作ることに成功した。
しかし、アセテートの糸を作る工業は発達しなかった。
酢酸繊維素は、まず、もえないフイルムの原料となり、硝酸繊維素を原料にしたこれまでの燃えやすいセルロイド製のフイルムにかわって使われた。
そこに第一次大戦が始った。
燃えない性質をもつ酢酸繊維素は、飛行機の翼にぬる塗料として大変具合がいいのだった。
さあ急に酢酸繊維素の役割が重大になってきた。
工場がたくさん作られ、酢酸繊維素を安くたくさん作る方法が研究されるようになった。
4 アセチレン工業がうしろだて
top
酢酸繊維素の原料の酢酸やアセトンは、これまでは木材を乾溜して作っていたのだが、それではとても間に合わなくなった。
これをアセチレンから合成することが考えられた。
アセチレンはカーバイトから作る。カーバイトは石灰石とコークスと大量の電気があればできる。
原料はみな豊富だ。このため、第一次大戦中には、アセチレンをもとにした合成化学工業がどんどん発達した。
そこへ大戦がおこった(一九一八年)。酢酸繊維素は余っていた。
そこでイギリスのセラニーズ会社などがこれをもとにしてアセテートの糸を作りだした。
そして一九二五年(大正十四年)頃にはアセテート人絹はビスコース人絹とならぶ大工業に成長した。
5 アセテート作りを独力でやろう
top
しかし、当時の日本では、まだアセテート人絹工業はもちろん、アセチレン合成工業もまだ、生まれていなかった。 アセチレンのもとになるカーバイトは、主に石灰窒素肥料に使われていた。
神谷の会社の日本窒素肥料会社でも、カーバイトは肥料の原料になっていたが、大正十二年からはアンモニア合成法という新しい方法が肥料を作るようになったので、カーバイドが余ってしまった。
そこで会社はこのカーバイドをもとにしてアセチレンを作り、アセチレン合成工業をおこそうとしていた。
アセテート人絹を作ることも早くから考えられていた。
しかし原料のアセトンを合成する研究がまだ完成していなかった。 (酢酸の合成は昭和三年、アセトンの合成は昭和十一年に完成した。)
そして昭和六年、いよいよ神谷たちはアセテートの研究にとりかかった。 |
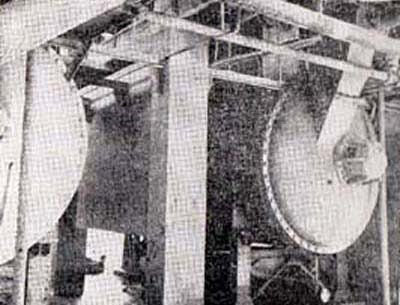
アセチレンガス発生器
|
当時外国のアセテートの作り方は、厳重な秘密にまもられていて、日本では何もかも独力で研究をすすめるほかなかった。
入社したての神谷はまず脱脂綿で酢酸繊維素(フレーク)を作り、それをアセトンに溶かす実験を始めた。
初めは何度繰返しても、アセトンに溶けるフレークができなかった。
「フレークがアセトンに溶けると本に書いてあるのは嘘ではないか。」
と思うほどだった。それでも根気よく実験をつづけた。
一年もたつうちにはアセトンに溶けるよいフレークが作れるようになった。
そこでいよいよ脱脂綿を綿の毛にかえて、本式にフレークを作り、昭和八年、やっと待望の糸ができたのだった。
6 残念! 外国でも同じやりかたをしている!
top
神谷たちの苦心して考案した紡糸法は、乾式紡糸法といって、アセトンに溶かしたフレークを真空中噴き出して糸にする方法であった。
当時、日本ではビスコース人絹に使われる湿式紡糸の技術はほとんど完成されていたが、乾式紡糸の技術はまだ開拓されていなかったので、神谷たちは非常に苦心したのだった。
紡糸試験に成功した昭和八年、外国のアセテートの作り方を詳しく書いた本が出版された。
むさぼるようにこれを読みとおした神谷はがっかりしてしまった。
「や、そっくりだ! 私が三年間苦心してきた糸の作り方と同じじゃないか。
研究を三年遅らせれば、こんな苦労せずにすんだものを……」
しかし、これは独力でやった研究が世界の水準と同じだったということでもある。これはほこりにしていい。
「よし、外国と競争だ!」
神谷たちはふるいたった。
そしてつぎの年にはフレークを作る試験工場がでぎ、糸を作る機械の研究もすすめられて、昭和十二年にはすこしばかりだが、アセテートの糸が売り出された。
しかしこの年には日華事変がはじまり、糸作りどころではなくなってしまった。
酢酸の臭気に悩まされながら品質を改良した工場のフレークは、飛行機の塗料や電線をおおう絶縁材料に向けられてしまい、日本のアセテートの研究はここでばったりとぎれてしまった。
こうして戦争が終ったときは、日本のアセテートはとても遅れてしまった。
7 ビニールの話 《特別読物7》
top
見たこともないビニールの研究
昭和十二年、日華事変の始った年の十一月のこと、九州の日本窒素肥料会社水俣工場では、大学を出たばかりの技師中村基与士が、会社のビニール製造命令をうけて若々しい情熱をもやした。
この会社は、もともと硫安肥料を作る会社で、カーバイドからアセチレンを作り、アセチレンから石灰窒素肥料、それから硫安肥料を作るという遠回しの製法をとっていたが、今度アンモニア合成法(第七巻『化学』を見てください)ができて、こんなまわり道をする必要がなくなった。
そのため、カーバイドつまりアセチレンが余ってきた。
会社は何としてもアセチレンを原料にした新しい工業をおこさればならなくなった。
その一つとして酢酸繊維素やこのビニールを作ることが考えられたのだ。
ビニールはアセチレンと塩酸から作られる。理屈は簡単だし、実験室ではもうズッと以前に作られた化合物だ。
しかし、実際にこれを作ろうとなると、そう簡単ではない。
いまでこそどこの家にもビニールはあるが、その頃は、これからそれを作ろうという中村さんが、それがどんな物なのか見たことがなかった。
何から何まで自分で考えださなければならなかった。
難題次々におこる
いくつかの実験をしてみると、工場でビニールを作る方法としては、まずアセチレンと塩酸から塩化ビニールを作り、次に触媒(反応をすすめるもの)を使って、塩化ビニールを重合(一つの化合物の二個以上の分子が結合して幾倍かの分子量をもつほかの化合物を作ること)させ、ビニールにする方法がよさそうだった。
こうしていよいよ本格的に実験にとりかかったのだが、新しいことばかりで、難題が次から次へとおこってきた。
まず、原料の塩酸ガスだ。これは水に溶けやすく湿りやすい。そこで乾かしでおくのがひと苦労だった。
また塩酸ガスは、金属を腐らせやすいので、実験に使う器具がすぐいたんでしまうのだ。
また塩化ビニールは零下一四度という低温で気体になってしまう。
こういう困難さを一つ一つ解決して塩化ビニールが作られるようになると、つぎは塩化ビニールを重合する方法を考えねばならない。
まず触媒をえらびだす仕事だ。つづいていい重合法をみつけることである。これらは根気のいる仕事だった。
考えられるかぎりの種類の触媒と重合法を片っ端しからためしたのだった。 |
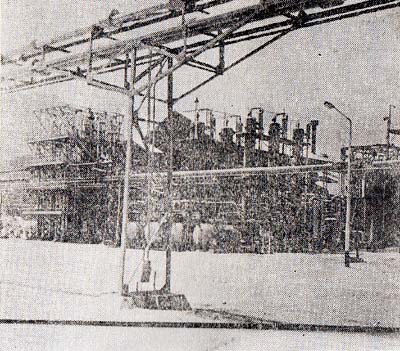
塩化ビニール製造設備の一部
|
とうとう硫酸アルミを触媒に、その頃新発明された合成洗剤「エキセリン」を入れた重合法(乳化重合法)で成功した。
缶詰の酒を傾けながら
研究もすすんできた昭和十四年水俣の中村のところへ、東洋製缶会社の山本行常が訪ねてきた。
「どうです、このおみやげは?」
山本のさしだしたのは、めずらしい「酒の缶詰」だった。 この年の三月頃、山本はアメリカでビールの缶詰ができたという話をきいた。
製缶会社の山本は、さっそく取り寄せたところこの缶の内側にぬってある塗料が、どうやらアメリカのビニール(「ビニライト」)らしい。
アメリカでは昭和五年頃ビニールができていたことをしっていた山本は、「これで清酒の缶詰を作ったら」と思いついた。
山本は母校の京都大学の研究室で、実物をもとにして、ビニールを作り上げた。
が、ビニールを大量生産するには、どうしても水俣工場のような原料の豊かなところでなくてはならない。
そこで酒の缶詰を見本に、ビニールの製造をすすめに中村のところへやってきたのだ。
中村は山本のおみやげの酒の缶詰をあけながら、はじめてビニールの実物を見たのだ。
中村の作ったビニールには「ニポリット」という名がつけられた。
山本が訪ねてきた昭和十四年には、もうビニールは試験工場ですこしずつ作られていた。
昭和十六年からは本格的な工場が運転を始めたが、すぐ戦争が始ったため、ビニールの用途は軍用ばかりだった。
紫外線に強いビニールを雨合羽にぬって南方におくったり、電線や電池のおおい、など……。 |
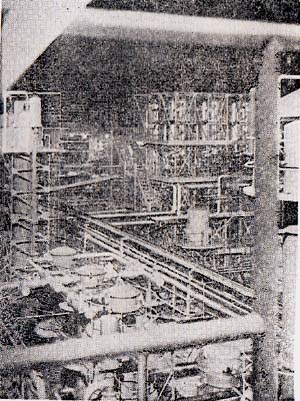
塩化ビニール製造設備
|
top
**************************************** |