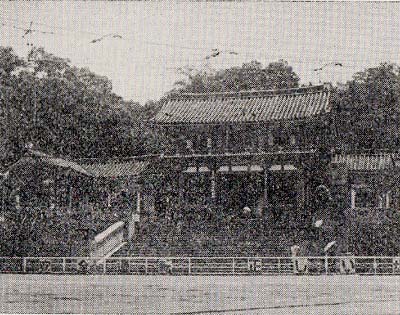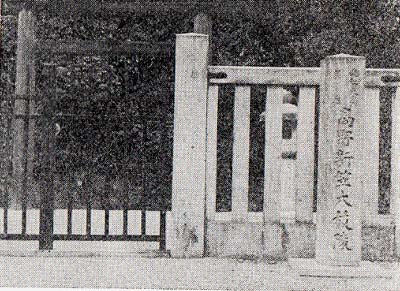|
****************************************
概要 大和 和泉 河内 摂津 山城 武蔵
五章 山城(京都)
1 高麗寺(こまでら)から八坂(やさか)へ top
高麗寺跡
山背(やましろ)・山代(やましろ)とも書かれた山城国は今の京都府であるが、全府下ということになると、北方の丹波(たんば)、丹後(たんご)国までふくまれることになる。
この丹波、丹後も古代朝鮮文化遺跡の濃厚なところであるが、さきの摂津と同じように、こちらもそこまでみることはできないので、京都市内となっているところと、南山城の一部だけみておくことにしたい。
奈良県寄りの南山城に相楽郡山城町があるが、この山城町は一九五六年に、上狛(かみごま)町・高麗(こま)村・棚倉(たなくら)村が合併したものである。
上狛の狛が高麗とともに、古代朝鮮の高句麗(こうくり)をさしたものであることはいうまでもなく、かってのこの地は大狛郷(おおこまごう)となっていたところであった。
いまも山城町には上狛(かみこま)、下狛(しもこま)があるが、この上狛に住む中津川保一氏は一九三四年、自宅近くにあったひとつの寺院跡を発見した。
それが、いまは国指定史跡となっている高麗寺(こまでら)跡である。
そしてこれが最初に発掘調査されたのは一九三八年のことで、結果、そこに「史蹟 高麗寺跡」とした石碑がたてられた。とともに出土品なども整理され、山城町教育委員会編『史蹟 高麗寺跡』をみると、それはこうなっている。 |

京都府山城町の高麗寺跡
|
塔跡 十二・八メートル平方の瓦積基壇を有し、中央に心礎(しんそ)を原位置にとどめている。
心礎は表面に円柱孔を、右側に横口の舎利孔(しゃりこう)をもち、全国唯一の形式をとどめている。
金堂跡 塔跡の西八メートルに南北十三・三メートル、東百十七メートルの瓦積基壇をもった金堂跡がある。
講堂跡 金堂跡北側に水田をへだてて講堂跡があり、二箇の礎石を残している。
出土品 飛鳥時代の鐙瓦(あぶみがわら)、奈良・平安初期の宇瓦(うがわら)、鴟尾(しび)等多数の古瓦・破瓦・金具・釘・化粧石等が発見され、京都国立博物館・山城町役場に保存されている。 |
ところで、どういうことでか、それだけ史跡として貴重だということからであろうが、この高麗寺跡は最近、今度は五ヵ年計画でさらに再発掘されることになった。
一九八四年一一月一七日付の京都新聞をみると、「山城町の高麗寺跡/講堂・回廊を確認/寺域示す築地跡も/白鳳期伽藍配置と一致」という見出しのもとに、そのことがこう報じられている。
| 京都府内で最古の寺跡とみられる相楽(そうらく)郡山城町上狛の国の史跡「高麗寺(こまでら)」跡で発掘調査していた同町教委は、十六日までに白鳳時代創建の講堂、回廊や寺域を示す築地跡の一部を確認した。 |
蟹満寺(かにまんじ)
記事は長いのでまえがきだけ引いたが、「このことから寺域の一辺は約一〇八メートル四方で、現在の同寺史跡指定地(約四二〇〇平方メートル)の倍規模と推定される」とあるのをみると、そこにあった高麗寺はこれまで考えられていたより、はるかに大規模な寺院だったようである。
そして、同記事は終りに「注」としてこういうことを書きそえている。
「高麗寺跡 南山城に居住した高句麗系の渡来氏族が創建したと推定される古代の寺院跡。『日本霊異記(りょういき)』などにその名が出ている」
そのとおりで、この高麗寺を氏寺としていた高句麗系渡来の高麗氏族はそこからさらに発展して北上し、京都市内となっている山城の東山山麓に八坂塔で知られている八坂寺や八坂神社を祭った。
そのことについてはあとでみるとして、高麗寺から木津川沿いの国道二四号線を京都市内に向かって北上すると、綺田(かばた)というところに「蟹の恩返し」ということで有名な蟹満寺(かにまんじ)がある。
蟹満寺には国宝となっている美麗な自鳳仏があって、これはもと高麗寺にあったものではないかといわれている。
が、それはどちらにせよ、松本清張・樋口清之氏の『京都の旅』に蟹満寺のことがこう書かれている。
この付近は、古くから帰化人の開拓したところであった。
その帰化人は農地開拓とともに、染色技術のすぐれたのを持っていた。
そのすぐれた織物がカムハタ(綺)であった。いまでもこの村落を綺田と書いてカバタと読んでいる。
カムハタから変わってきた名である。
この寺(蟹満寺)も古い時代には、紙幡(かみはた)寺と書いたこともある。
また村の名も蟹幡郷(かにはたごう)と書いたときもある。
それがカムハタ=カンハタ=カニマタ(カバタ)=カニマ=カニマンと転化して、紙幡寺から蟹満寺に字と読みが変わったのではないかと思う。
そして、今度は、字から蟹がいっぱい出て恩返しをする話になり、そこへ観音信仰が便乗したのではないか、という推定か成り立つ。
そうでないと、蟹満寺というような、音訓を混ぜた不自然な寺名などの起こることが理解できない。 |
養蚕(ようさん)をする韓人(からひと)
蟹満寺(かにまんじ)のあるそこからさらに京都市へ向かって北上すると、木津川の西岸は綴喜(つつき)郡田辺(たなべ)町となる。
「筒木(つつき)の韓人(からひと)」が住んでいたところで、綴喜郡の綴喜というのもその「筒木」からきたものであった。
ここには『古事記』に語られている、なかなかおもしろいものがたりがある。
倉野憲司校注の『古事記』仁徳段(にんとくだん)によってみると、それはこういうふうである。
仁徳帝が八田若郎女(やたのわきいらつめ)とねんごろになったのを嫉妬(ねた)んだ大后(おおきさき)の石之比売(いわのひめ)は、出先からそのまま帰らずじまいとなってしまう。
そして石之比売は、「つぎねふや 山代河(古代の木津川は山代河、または輪韓(わから)川ともいった)を 宮上り 我が上れば あをによし 奈良を過ぎ 小楯(おだて) 倭(やまと)を過ぎ 我が見が欲し国は 葛城高宮(かつらぎのたかのみや) 吾家のあたりとうたひたまひき。
かく歌ひて還りたまひて、暫(しま)し筒木の韓人(からひと)、名は奴理能美(ぬりのみ)の家に入りましき」となるのであるが、筒木とはこの筒木のことで、つつ(筒)は古代朝鮮語のツツウ、岳(おか)ということであり、き(木)はキ(城)ということであった。
つまり「岳の城」、すなわち古代朝鮮式山城のことで、韓人(からひと)の奴理能美はここにそういう山城を構えて住んでいたのである。
一方、八田若郎女とねんごろになったものの、大后の石之比売もけっして嫌いだったわけではなかったらしい仁徳帝は、鳥山という名の舎人(とねり)を使いにたてて、
「山代に い及(し)け鳥山 い及けい及け 吾が愛妻に い及き遇(あ)はむかも」
といった歌を、何度も送ったりする。
つまり、早く帰って欲しいというわけであったが、いつの世も同じことで、それで困ったのは、間に立だされた奴理能美(ぬりのみ)たちのほうだった。
そこでこのくだりは、こういうふうに結末がつけられている。
「ここに口子臣(くちこのおみ)、またその妹口比売(くちひめ)、また奴理能美の三人議(はか)りて、天皇に奏(まお)さしめて云(い)ひしく、
『大后(おおみさき)の幸(い)でましし所以(ゆえ)は、奴理能美が養(か)へる虫、一度は匐(は)う虫になり、一度は鼓(つつみ)になり、一度は飛ぶ鳥になりて、三色に変る奇しき虫あり。この虫を看行(みそな)はしに入りまししこそ。
更に異心(ことごころ)なし』といひき。
かく奏す時に、天皇詔(の)りたまひしく、
『然らば吾も奇異(あや)しと思ふ。故(かれ)、見に行かむと欲(おも)ふ』とのりたまひて、大宮より上り幸(い)でまして、奴理能美の家に入りましし時、その奴理能美、己(おの)が養へる三色の虫を大后に……」というしだいとなる。 |
ようするに、仁徳帝はそうして大后の石之比売(いわのひめ)を迎えにくることになったもので、『古事記』の筆者もなかなかしゃれた書き方をしたものであった。
しかし、まだそれで仁徳帝の浮気はやんだわけではなかったが、それはともかくとして、以上の筒木の奴理能美との関係をみてわかることは、そこに「奴理能美が養へる虫」、すなわち養蚕という事実が出ているということである。
つまり筒木、『日本書紀』には「筒城(つつき)」となっているその山城を構えていた韓人(からひと)たちは、そこで養蚕をもしていたのである。
これが日本における養蚕(ようさん)のはじめだったかどうかはわからないけれども、田辺町の多々羅(たたら)というところに、いま、「日本最初の外国養蚕飼育旧跡」という石碑がたっており、また、のち継体帝がここの筒城谷に一時、宮居をさだめたということで、そこに「筒城宮址」という大きな石碑もたっている。
八坂神社
さて、相楽(そうらく)郡山城町の上狛(かみこま)から木津川に沿って北上し、京都市内の東山山麓に八坂寺(法観寺ともいう)や八坂神社を祭った高麗氏族であるが、このことではあるいはもしかすると、「あの祇園祭で有名な八坂神社を――」と思われる人があるかもしれない。
しかしそのことについては、いま祟戔鳴尊(すさのおうのみこと)を祭神としている『八坂神社由緒略記』にもこう書かれている。 |
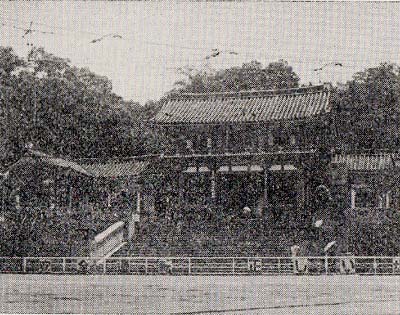
八坂神社
|
八坂神社は祇園(ぎおん)さんの名で親しまれ、信仰されている。
八坂神社の創立については諸説があるが、斉明天皇二年。
高麗より来朝せる副使の伊利之使主(いりのおみ)か新羅国牛頭山(しらぎのくにごずさん)にます祟戔鳴尊(すさのおのみこと)を八坂郷に祀り、八坂造(やさかのみやっこ)の姓を賜わったのに始まるとの説は、日本書記に素戔鳴尊が御子五十猛神(みこいたけるのかみ)と共に新羅(しらぎ)国に降(くだ)り曽尸繁梨(そしもり)に居(お)られたとの伝、また新撰姓氏録に八坂造(やさかのみやっこ)は狛国人(こまのくにびと)万留川麻乃意利佐(まるかわまのいりさ)の子孫なりとの記録と考え合せて、ほぼ妥当な創立とみてよい。 |
それからまた、いまもある八坂塔(やさこのとう)で知られている八坂寺(法観寺)との関連については、林屋辰三郎氏の『京都』(岩波新書)にこうある。
洛西の広隆寺(こうりゅうじ)と並ぶものに東山の法観寺がある。
町とともに生きるとでも言いたいこんにちの寺のたたずまいも、二つの寺はよく似ている。
この寺も崇峻(すしゅん)天皇二年(五八九)聖徳太子の発願とつたえられるが、この寺地の八坂郷の地を占拠していた高麗(こま)の調使(ちょうし)伊利佐(いりさ)の後裔の創立するところである。
高麗の帰化氏族は相楽(そうらく)郡の上狛(かみこま)・下狛(しもこま)の地を根拠として高麗寺を創建し、氏族の拠点としていたが、八坂造の名でよばれたこの地の氏族は、ここの祇園社(ぎおんしゃ=八坂神社)の前身ともなるべき神社をまつり、この八坂寺を建てた。 |
「高麗より来朝せる副使の伊利之使主(いりのおみ)」とか、「高麗の調使伊利佐」などというのはあとからの付会(ふかい)で、八坂神社と八坂寺とは、相楽郡の上狛・下狛から北上した高麗氏族が、「八坂造の名でよばれたこの地の氏族」となって建てたものであったにちがいない。
したがって、日本三大祭のひとつとして有名な「祇園祭」も、もとは高麗(こま)氏族の祖神を祭ったその八坂神社の祭祀から始まったものだったのである。
このように、京都市となっている山城の東は高句麗系渡来の高麗氏族が繁栄した地であったが、それにたいして洛西、すなわち西の地は新羅・加耶系渡来の秦氏族がおおいに繁栄し、ついには奈良・平城京にあった都までこちら山城に引き寄せて、ここを平安京としたのであった。
朝鮮語ではソウルということである京都という名称も、それから始まったことはいうまでもないであろう。
2 京都における秦氏 top
平野神社
ここで、本稿はじめの「大和・奈良の発見」の項に引かれた『大和めぐり』の一文を思いだしてもらいたい。
それの終りのほうは、こういうふうになっていたはずである。
これら帰化人は奈良朝末期になっても、高市郡の人口の八割ないし九割を占めていたという。
そのころ大和の葛城(かつらぎ)地方にいた奏氏のひきいる移住民は、のちに山城国に住んで財力をたくわえ、それによって長岡、または平安京の遷都が行なわれたのであった。 |
八世紀末、桓武(かんむ)帝時代のことで、平安京の遷都には奏氏族の持つ財力のみでなく、彼らの政治力もおおいに働いたことはいうまでもないであろうが、それよりさきにまず、その平安京遷都(せんと)によって生じたひとつの神社をみておくことにしたい。
京都市北区平野宮本町の平野神社で、この神社のことは、赤松俊秀・山本四郎氏の『京都府の歴史』にも出ていてこうある。
北野天満宮の北につらなる平野神社は、平安遷都の前年に大和国から移された。
祭神の今木(いまき)の神は“今来(いまき)”すなわち新来の帰化人の意を寓(ぐう)したといわれ、奈良の高市(たけち)郡は今来郡ともいわれ、帰化人漢(あや)氏の根拠地であった。 |
大和のそこにあった「今来神」が平安遷都とともに京都へ移されたわけであったが、平野神社は平野造り、または春日比翼(かすがひよく)造りともいわれる四つの本殿がそれぞれみな、国の重要文化財となっていることでも有名である。 |

平安京遷都でできた平野神社
|
今度久しぶりに同神社をたずねてみると、まえに来たときはなかった『平野神社由緒略記』ができていて、それにはかなりくわしくこう書かれている。
祭神
今木神(いまきかみ、第一殿)
久度神(くどかみ、第二殿)
古開神(ふるあきかみ、第三殿)
比売神(ひめかみ、第四殿)
由緒(ゆいしょ)
延暦十二年十月十四日鎮祭。桓武(かんむ)天鳬の平安遷都に際し、御生母高野新笠(たかののにいがさ)を中心とする当時の大陸文化をもたらしてきた人たちが、この新しい街づくりに新進の技術を駆使して貢献した功績は大きく、又完成後は、その外護(げご)となった事等に対して天皇の御親祭をみたものである。
今木神(いまこのかみ)は、当時の和(やまと)氏の遠祖である百済の聖明王である。
久度神(くどのかみ)は竈神(かまどがみ)とされ、古開神(ふるあきのかみ)は聖明王(せいめいおう)の遠祖枕流王(ちんるおう)、肖古王(しょうこおう)と伝えられ、比売神(ひめがみ)は高野新笠(たかのにいがさ)であるとされている。
延喜式の名神(みょうじん)大社。平安中期以降は、二十二社中の五位とし、京都では賀茂・石清水・松尾につぐものとして、明治四年官幣(かんぺい)大社。平野郷の氏神と仰がれている。 |
古代日本最大の氏族
桓武(かんむ)帝の「御生母(ごせいぼ)高野新笠」とは、百済系渡来人の和氏族から出た者であった。
京都市右京区大枝町沓掛(くつかけ)には高野新笠陵があって、いまも宮内庁によって管理されている。
しかし、この『平野神社由緒略記』には、「桓武天皇の平安遷都に際し、御生母高野新笠を中心とする当時の大陸文化をもたらしてきた人たちが、この新しい街づくりに新進の技術を駆使して」うんぬんとあるけれども、それは彼ら新来(しんらい)の今来人(いまきびと)が集住していた大和でのことであって、こちら山城でのことではなかった。
これからみるように、平野神社もここにある、京都西部のそれはほとんどみな新羅・加耶系渡来人集団の秦氏族によるものであった。 |
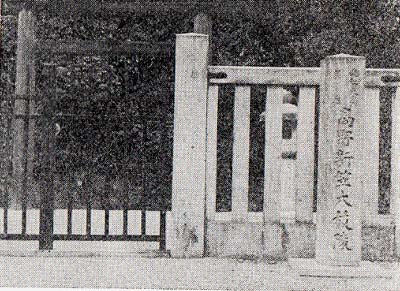
高野新笠陵
|
大体、大和にあった今来神(いまきのかみ)の平野神社がこちらに移されたことからして、秦氏族によってなされた「平安遷都に際し」てだっ
たのである。
私は全一二巻を予定している『日本の中の朝鮮文化』(いま八巻まで刊行)のため日本全国を歩きまわっているが、それでわかったことのひとつは、秦氏族は九州、四国、中国地方はもとより、全国いたるところに分布していた古代日本最大の氏族であった、ということである。
大和の今来として知られた漢(あや)氏も大きな氏族で、和(やまと)氏と同じようにそれから出た坂上氏(坂上田村麻呂が有名)の『坂上系図』をみると、「時に阿智王(あちおう)、奏して今来郡を建つ。
後に改めて高市郡(たけちにこおり)と号す。
しかるに人衆巨多(じんしゅうきょた)にして居地隘狭(きょちあいきょう)なり。
更に諸国に分置す。摂津・参河(みかわ)・近江・播磨・阿波等の漢人村主(あやひとのすぐり)これなり」とあるけれども、秦氏族はもっと巨大であった。
たとえば、いまは九州・福岡県となっている豊前国〔一部は大分県)における七〇二年にあたる大宝二年の戸籍台帳によると、そこの人口の八五パーセント以上が秦氏とその係累とによって占められている。
そして彼らは、豊前のそこに宇佐八幡神宮を祭って氏神としていた。
八幡神宮・八幡神社の八幡は、いまでははちまんといわれているけれども、もとはヤ・ハタ、すなわち「多くの泰」ということで、八幡神宮、八幡神社とはその「多くの秦の神宮、神社」ということにほかならなかった。
大野鍵太郎氏の「鍛冶(かじ)の神と秦氏集団」にも、そのことがこう書かれている。
豊前国(びぜんのくに)八幡神とは、いわゆる宇佐八幡宮である。
八幡神はヤハタの神である。ヤは多いという意味をもつ集合体を表現する言葉である。
ハタは秦族の族称を示すものであって、秦族が共通して信仰する神、すなわち秦族のすべてが信仰する神である。
泰族は明らかなように、古代大陸から渡来した氏族である。いわば秦氏の総氏神である。 |
秦氏のはたした役割
それからさらにまた、安本美典氏の「邪馬台国(やまたいこく)」をみると、「宇佐八幡神宮は、全国四万六百三十八の八幡宮の総本社である。
平安時代から、伊勢神宮とならぶ『二所宗廟(そうびょう)』(皇室の祖先を祭った建物)としてあがめられている」とある。
「四万六百三十八の八幡宮」とはおどろくべき数であるが、近年では、その秦氏族についての研究もすすみ、「天皇家も秦氏から出ている」とする小島信一氏の『天皇系図』や、安藤輝国氏の『邪馬台国は秦族に征服された』といった著書も出ている。
しかしそれはおいて、古代史上、秦氏族がもっとも有名なものとしてあらわれるのは、山城・京都におけるそれであった。
なにしろ、それまでは奈良にあった都を山城に引き寄せたのであるから当然であるが、平野邦雄氏の「秦氏の研究」をみると、その秦氏族のことがこう書かれている。
わが古代文明史上において秦氏の果した役割は極めて大きく、他の如何なる氏族にも劣らないといえよう。
秦氏は殖産的氏族とよばれるにふさわしく、厖大な構成員をかかえていた。……
私の手許の資料では、延暦にいたるまでに人名の明らかなもののみで一、一四七名を数え、このほか改姓記事、例えば秦等一、二〇〇余姻(よえん)に伊美吉姓(いみきのかばね)を賜い、秦忌寸(はたのいみき)等一一九人に奈良忌寸・朝原忌寸を、秦勝(はたのすぐり)等五二人に秦原公(はたはらのきみ)を賜うなどの記事をみると、そこに現われる人数もまた他氏族にみられないほど多きに上るのであるから、秦氏の勢力はまことに隠然たるものがあったというはかない。
|
ここにいう「秦等一、二〇〇余姻」とは、一二〇〇余戸ということである。
古代の当時は大家族制の時代であるから、その数はどれほどであったか、想像してみるよりほかない。
太秦(うずまさ)の広隆寺(こうりゅうじ)
山城・京都における秦氏族の根拠地のひとつは、いまは京都市右京区となっている太秦(うずまさ)であった。
そのことについては、山本四郎氏の『京都府の歴史散歩』(下)にもこうある。
「太秦は渡来人秦氏の本拠地だ。秦氏は新羅系と考えられ、“ハタ”は朝鮮語の海を意味する」と。
その朝鮮語の「ハタ」がもとは波多ともいった秦氏の氏族名になったというのであるが、そして太秦には、日本国宝第一号の宝冠弥勒(ほうかんみろく)ともいわれる有名な弥勒菩薩(みろくぼさつ)半跏思惟(はんかしい)像を本尊とする広隆寺がある。
秦氏族の氏寺だったもので、そこにある半跏像については、仏教史家である田村開澄氏の『半跏像の道』にこう書かれている。 |

秦氏の氏寺である広隆寺にある弥勒菩薩。
|
百済または新羅から半跏像(はんかぞう)が日本に伝えられたが、注目されるのは、日本では半跏像が聖徳太子信仰と結びついたことである。 聖徳太子は隋との新しい外交路線を開いたが、また従来の対新羅強硬路線をしりぞけ、友好政策をうち出した。 この外交方針を支持し推進したのは、太子側近の秦氏や難波吉士(なにわのきし)氏であり、いずれも新羅系渡来氏族であった。
六二二年(推古三〇)聖徳太子が亡くなったが、その年の七月に新羅の真平王(しんぺいおう)は、仏像一具(ひとそろえ)と金塔(きんとう)・舎利(しゃり)などを日本に送ってきた。
太子の追善のためであったが、仏像は太秦の広隆寺に安置され、また金塔・舎利などは難波の四天王寺に納入された。 広隆寺の宝冠弥勒(ほうかんみろく)は、このときの仏像にあたると考えられる。 |
なおまた、美術史家である水澤澄夫氏の『広隆寺』にもこう書かれている。
仏教関係で言えば、漢氏の百済系に対して秦氏は新羅系だった。
それは飛鳥寺の大仏、法隆寺の金堂の本尊をはじめ、法輪寺の木彫虚空像菩薩立像などの諸仏像に漢氏系統の鞍止利およびその系列の仏工の手になる百済様式が多くみられるのに比べて、広隆寺の弥勒像が新羅様式であることだけから言っても肯けるところである。 |
太秦(うずまさ)には秦氏族の氏寺だったその広隆寺だけではなく、ここには「蚕養(さんよう)機織(はたおり)管弦楽舞之祖神」という秦酒君(はたのさかぎみ)を祭神とする大酒(おおさけ)神社や、「蚕の社(かいこのやしろ)」ともよばれる木嶋(きじま)神社などがあるが、これは彼らの氏神となっていたものであった。
それからまた、いまは「太秦映画村」となっているところに、全長約三〇メートルの前方後円の蛇塚(へびづか)古墳があるが、これは秦河勝(はたのかわかつ)の墳墓とされているものである。大和・飛鳥の石舞台古墳につぐものというその横穴石室は、近くの保津川から運んだものとみられる巨岩でおおわれている。
|

巨岩でおおわ礼た蛇塚古墳。
|
最も高い生産力をもった氏族
保津川といえば、それの下流は景勝地として知られている嵐山(あらしやま)である。
保津川の急流はそこにいたって大堰(おおい)川となり、そして桂川となっているが、ここにいう「大堰」とは秦氏族の治水技術から生じたもので、それが古代の当時、どういう意義をもったものだったかについては、林屋辰三郎氏の『京都』(岩波親書)にこうある。
彼らはまず湿潤なこの地域の土地改良からはじめた。それはそこを流れる桂川に大堰(おおい)をつくって水量を調節し、開拓と灌漑に利用したことである。
現代日本にも、発電のためのダムつくりが一つのブームとなっている。その目的や規獏には大きなちがいがあるが、さしあたりダムつくりの元祖といえば、このあたりであろうか。それは秦氏がその種族六類を率い催して造るところで、天下に比肩(ひけん)するものなしと称せられたという。
確かにそれは古代人にとっては驚異的な技術であった。
彼ら帰化人はこうした水利工事に、特にすぐれた才腕(さいわん)をもっていたようで、……桂川の大堰は、その後この川が大堰川の名でよばれたように、ながく葛野(かどの)地方の繁栄を約束するものであったと思われる。
その工事の箇所はもとより定かでないが、保津川の急湍(きゅうたん)が盆地に流出する咽喉(いんこう)を扼(やく)して、ほぼこんにちの嵐峡(らんきょう)千鳥ヶ淵のあたりを利用してつくられたものであろう。
その工事は決して容易なものではなかったにちがいないが、そのことによって下流の開発、灌漑の利便ははかり知れないものであったろう。 |
ちょっと長くなるけれども、林屋氏のそれをもう少しみると、さらに続けてこうのべられている。
|
こうして秦氏はここに大規模な開墾を計画して、その活動の根拠としたのであった。
彼らがこのような農業技術ばかりでなく、養蚕(ようさん)と絹織(きぬおり)をもってあらわれたことは、太秦(うずまさ)の起源伝説によって、これまた周知のことがらである。……
彼らは庸調(ようちょう)として、絹縑(きぬかとり)を朝廷に充(み)ち積むほどに献(けん)ずるようになった。
その賞として秦酒君(はたのさかぎみ)は、太秦の姓(かばね)を賜ったというのである。
従って地名(太秦)もまたその姓名に由来するのである。
こうしてみると太秦は、古代日本において最も高い生産力をもった地域であり、そこに定住した秦氏は最も大きな殖産的氏族であったといわねばならない。
そして、秦氏の来住がこの盆地を一挙に歴史の舞台におし上げたともいえるのである。 |
「この盆地」とは京都盆地ということであるが、そのように、桂川流域を開発して肥沃な農耕地とした秦氏族は、いまは京都市西京区嵐山宮(あらしやまみや)町となっている桂川畔のそこに、松尾大社を氏神として祭った。
しかも、それだけではない。京都市南方の伏見区深草にあって、全国にひろがった稲荷神社の総本社となっている伏見稲荷大社も、彼ら秦氏族の氏神となっていたものであった。
3 神宮・神社と古墳 top
渡来人(とらいじん)がもってきた風習
これも全国に一三〇〇余の分社がある松尾大社は、「日本第一酒造神(しゅぞうじん)」として有名なもので、境内にはいっも全国の酒造業者から寄進された酒樽がうず高く積まれている。
今度たずねたとき求めた新しい由緒書(ゆいしょがき)の『松尾大社』をみると、「桂(かつら)川両岸を農耕地」とした秦(はた)氏族の活動につづいて、「酒造神」としてのそれが、なかなかおもしろい書き方でこうなっている。
さて、(そうして)農業が進むと次第に他の諸産業が興って来て、絹織物なども盛んに作られるようになったのです。
酒は当時産業とはなっていなかったのですが、秦一族の特技とされたことは、秦氏に酒という字の付いた人が多かったことからも推察できるのでありまして、室町末期以後、当社が日本第一酒造神と仰がれ給う由来はここにあります。 |
なるほど、そういわれてみると秦酒君(はたのさかぎみ)、秦酒田万(はたのさかたま)など、確かにそうである。
農業や他の諸産業が進むとともに酒造もまた産業となったこと、それもよくわかるような気がする。
それにくらべると、こちら伏見「深草(ふかくさ)の里」を根拠地としていた秦氏族が祭った稲荷大社は、その「稲荷(いなり)」という名称からして「稲生(いねな)り」ということからきたといわれるように、はじめは農業一筋のそれであったようである。
まず、高柳光寿・竹内理三編『日本史辞典』「稲荷神社」の項をみると、その創建のことがこうある。
「七一一(和銅四)、秦中家忌寸(けたのなかえのいみき)の祖が祭りはじめたと伝える。代々秦(はた)氏が神官として奉仕」
ついで、『伏見稲荷大社略記』によってみると、それがこう書かれている。
稲荷大神は、もともと五穀(ごこく)をはじめとするすべての食物・蚕桑(さんそう)のことをつかさどる神として信仰されていたが、平安期にいたって、当社が東寺(とうじ)の鎮守(ちんじゅ)とされてよりは朝野の尊崇(そんすう)をあつめ、社運隆盛(りゅうせい)とともに、その信仰も一段とひろく伝播していった。
さらに中世から近世にかけて工業が興り商業が盛んになると、神格も従来の農業神から殖産興業神・商業神・屋敷神へと拡大し、農村だけではなく広く大名・町家の随所に勧請(かんじょう)・奉祀(ほうし)されるようになった。
現在では稲荷神社の数は約四万余を数え、わが国神社十一万余社の、ほぼ三分の一を占めるが、これに個人の邸内祠(ていないし)等を加えれば殆んど無数に近い。 |
「個人の邸内祠等」は別としても、これまたおどろくべき数といわなくてはならない。
「これまた」といったのは、同じ新羅・加耶(かや)系渡来人集団の秦(はた)氏族が祭ったものとしてさきにみた、宇佐八幡神宮を総本社とする八幡神宮・八幡神社が四万六〇〇余だったからである。
すると、どういうことになるか。
秦氏族がその氏神として祭った神宮・神社だけでも、稲荷神社の四万余を加えると、じつに八万余となるのである。
そのうえさらに、これも新羅系渡来人が祭ったもので、これまた全国にひろく分布している白山(はくさん)神社や白髪(しらひげ)神社などを加えると、その数はおそらく一〇万以上となるにちがいない。
そのうえさらにまた、高句麗系の高麗神社や狛(こま)神社、百済系の平野神社や韓(から)神社(これは宮中に新羅系一社とともに、二社祭られている)などとみてくれば、それはほとんどもうきりがないはずである。
このことはようするに、彼らが古代朝鮮から渡来したときに、そのような神宮・神社を祭る風習をも伴ってきたということにほかならなかったのである。
日本における神宮・神社はどういうものであったか
つまり、そのような神宮・神社を祭る風習は古代朝鮮に始まったものだということであるが、それよりさきに、日本における神宮・神社とは本来どういうものであったか、ということをみておかなくてはならない。
これも私かどうだったなどというより、「神の国」といわれる出雲(島根県)の古い『岐久村(きくそん)誌』「神社の起源」に適切なことが書かれているので、それによってみることにしたい。
氏神と氏子
神道でいう「カミ」は字義的には「上」であるが、実質的には祖霊である。
他の宗教でいうような、ある抽象化された理念ではなく、現実に吾々と血のつながった祖先の魂(たましい)であるという点に大きな特色があった。
故にそうした神をまつる神社は古来原則として氏神(うじがみ)であり、これに奉仕する人は、その神の子孫であるか、しからずとも子孫であるという自覚の上に立つものであった。
つまり、神社と氏子(うじこ)との関係は本来、祖先と子孫の関係で一貫していたのである。 |
それからまた、別のところ(「神社行政」)では、「即ち神社は独立した状態で発生し、各社相互間はもとより、初めは国家とのつながりも無かった」とも書かれているが、まさにそのとおりではなかったかと私も思う。
私は私なりに神宮・神社をみて歩いて考えたうえでのことであるが、その「祖先」がそうして祭られることで、何々の尊(みこと=命)などともいわれる「祖神」となったのである。
古代朝鮮の歴史書である『三国史記』によって新羅の「祭祀(さいし)」をみると、新羅第一代王は赫居世(かくきょせ)という者であった。
これを朝鮮語でよむと赫居世(ヒヨクコセ)で、赫とは名であり、居世とは「様」というほどの尊称であることを覚えておいてもらいたいが、その赫居世が亡くなって、「祖神廟」ができたのは西暦六年のことであった。
いまからすると一九七九年前ということになるが、この祖神廟が四八七年に「神宮(シングン)」となった。
五世紀後半のこれが朝鮮、日本をつうじてみられる神宮ということの初見であるが、そうして日本に「神宮(じんぐう)」ができるのは、約一〇〇年後の六世紀後半になってからであった。
前川明久氏の「伊勢神宮と新羅の祭祀制」によると、「神宮の称号の起源は新羅の神宮に由来している」として、そのことがこう書かれている。
「伊勢神祠(しんし)に神宮の称号が付せられ、伊勢神宮として成立したのは六世紀後半、いいかえれば敏達(びたつ)朝か用明(ようめい)朝のはじめにかけてであろう」
|
古墳と神社・神宮は一体であった
それで神宮の由来はわかったが、では、たんに社(やしろ)ともいう神社はどういうことからであったか。
神社の「社」は、さきにみた赫居世(ヒヨクコセ)の「居世(コセ)」という尊称からきたもので、社は、もと「社(こそ)」といったものであった。
以前、村社(むらこそ)というオリンピックの選手がいたのを覚えている人もあるかと思うが、そのことは、江戸時代の考証学者である判信友(ばんのぶとも)が「神社を古曽(こそ)と云事(いうこと)」として、大阪の阿麻美許曽(あまみこそ)神社や比売許曽(ひめこそ)神社などたくさんの神社を例にあげ、「比売許曽は下照姫(赤留比売(あかるひめ)と同じ)の社にて、姫社(ひめこそ)の義也(なり)」(『神明帳考証』)といっていることからもわかる。
居世(こせ)=古曽(こそ)が「様」というぼどの尊称であったということは、これも伴信友のあげていることであるが、『今昔物語』第二四巻一五話に「文古曽(ふみこそ)」という言葉が出ている。
この古曽は文に尊称をつけていったばあいで、したがって、何々の神社とは本来、何々の神様(社=やしろ)ということだったのである。
ところで、神宮が祖神廟から始まったように、神宮・神社は祖先(神)を葬った古墳と密接な関係があった。
ここで、さきの「王仁(わに)と古市(ふるいち)古墳群」の項に引かれた羽曳野市教育委員会編『歴史の散歩道』にある「誉田(こんだ)八幡宮」のことを思いだしてもらいたいが、それにこうあったはずである。
誉田八幡官は応神陵(古墳)の後円部のすぐ南側にあり、広大な境内を保有する府社である。
この神社は五七一年に欽明(きんめい)天皇が応神陵の後円部の頂上に設けられた祖廟形式(朝鮮の風習の名残り)の小社であった。
ところが平安中期の永承六年(一〇五一)二月、後冷泉(ごれいぜい)天皇の命によって南一町の現在地に移され、このときから東面の社殿となり……。 |
また、同『歴史の散歩道』の「応神天皇陵」には、「誉田八幡宮は創建当初は朝鮮・新羅の神廟(しんびょう)形式をまねて、後円部の頂上に設けられていた」ともある。
このように、古墳と神宮・神社とが密接なものであったことについては、民俗学者の谷川健一氏もこう書いている。
私は日本各地の神社をたずねあるくことを近来の仕事の一つとしているが、そこで気の付くことは、神社の境内に古墳が多いという事実である。
神社は聖(せい)であり墓地は穢(わい)であるという聖穢(せいわい)の観念にわざわいされて、神社の中に墓地があるのをかくしたがる神主(かんぬし)や禰宜(ねぎ)もあり、なかなかその実情に触れたがらない。
だが、こうした観念自体が仏教の渡来普及以後のことであって、それ以前には死者と生者を隔離する聖穢(せいわい)の観念があったわけではない。
一族の祖先や土地の豪族の埋葬地を礼拝するのは当然のことで、後代の神道家が忌避するようなものでは全くない。
神社の起源が古墳であるというのは、何も私の発見ではない。すでに江戸時代以来、多くの学者が指摘しているところである。 |
ここにいわれていることは、たとえば、さきにみた松尾大社にみられることでもある。
松尾大社背後の松尾山や周辺にも秦氏族の古墳がたくさんあって、一〇年ほどまえまでの旧『松尾神社略記』には、そのことがこうあったものである。
「松尾山の頂上部に五基、摂社月読(せっしゃつきよみ)神社の上方に十一基あり、また別に神社前の田畑にあったが、今は宅地となって姿を消した。
これらは、この地が秦氏による古代文化の中心地であったことを物語るものである」と。
だが、今度行ったとき求めた新しい『松尾大社』は二十数ページもある小冊子となっている略記にもかかわらず、それら古墳のことは、今度は略記のうえからも「姿を消し」てしまっている。
古墳のことはどこにもない。
このようになって、本来は一体の関係にあった古墳と神宮・神社との間が、だんだんと引き離されてきた。
神宮・神社のもとは、そこにある古墳の「拝所(はいしょ)」のようなものだったが、後世になるにしたがって、そのことはもうすっかり忘れられたようなものとなったのである。
top
**************************************** |