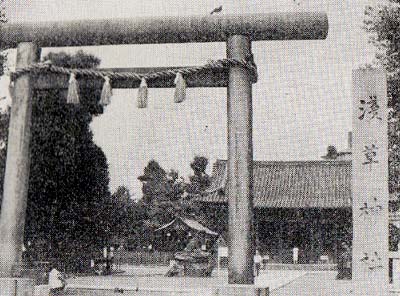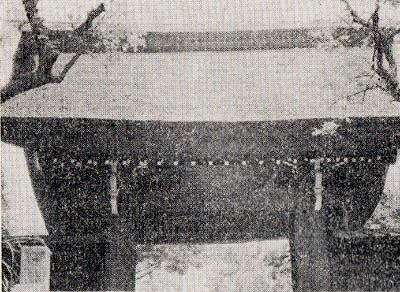|
****************************************
概要 大和 和泉 河内 摂津 山城 武蔵
六章 武蔵(東京・埼玉)と周辺
1 常陸(ひたち)の虎塚古墳ほか
top
武蔵はどのような地域であったか
本稿ははじめ、大体半々くらいのかたちで関西編・関東編としたかったのであるが、しかしずいぷんと省略したにもかかわらず、関西でもいわゆる五畿内(大和・摂津・河内・和泉・山城)だけで予定紙数の三分の二以上となってしまった。
それであとは、こちらも新羅・加耶(かや)系や百済系渡来人集団の集住地であった近江(滋賀県)などをみることで、つまり、関西の主要部分だけでおわろうかとも考えた。
が、やはり、今日の畿内・首都がそことなっている武蔵をのぞくわけにはゆかない。
そういうわけで、今度は山城の京都から一足飛びに武蔵の東京ほかとなった。かっての武蔵国は正確にいうといまの東京都・埼玉県から神奈川県の川崎市、横浜市までをふくむ広大な地域を占めていたものであった。
そこは、どういうところであったか。まず、東京都歴史研究会編『東京都の歴史散歩』(上)をみると、こう書かれているのが目につく。
『日本書記』には、六八五(天武天皇一三)年と七六〇(淳仁天皇天平宝字四)年の間に六回、渡来してきた百済・新羅・高句麗の僧俗男女多数を、武蔵国におく記事がある。
とくに七一六年には高麗郡を、また七五八年には新羅郡が新設される。
もともと武蔵国造の笠原直使主(かさはらのあたいのおみ)の名は、多分に渡来系の人物のにおいが濃いが、浅草寺の縁起にでてくる土師直中知(はじのあたいなかとも)・桧前浜成(ひのくまのはまなり)・同竹成(たけなり)の名も同様だ。
桧前(ひのくま)は大和の桧隈(ひのくま)で、阿知使主(あちのおみ)の子孫漢直(あやのあたい)の本貫地(ほんがんち)であり、土師(はじ)は、河内の羽曳野(はびきの)をその本拠とする百済系の人々が称した氏だった。
浅草寺についで古い深大寺(じんだいじ)は、高句麗系の人々の開発になるとされている狛江郷にあり、その開基と伝えられる僧満功(まんくう)は、渡来人系と考えられている。
まさに律令時代にはいったころの東京都は、朝鮮半島系開拓者の天地だったらしい。
七七〇(宝亀元)年には、武蔵守(むさしのかみ)に高麗福信(こまふくしん)が任命されている。 |
いまは東京都狛江(こまえ)市、調布市、三鷹市、武蔵野市などとなっている武蔵の狛江郷(こまえごう)は、『日本書記』の記事以前、すでに五〇〇年代の六世紀はじめには高句麗系渡来人の集住地となっていたことが明らかになっているが、しかし、武蔵におけるそれらはあとのことにして、先に、その周辺のほうを紙数のゆるすかぎり、ざっとみておくことにしたい。
虎塚(とらづか)壁画古墳
武蔵の周辺となると、その東北方は常陸(ひたち=茨城県)、上野(こうづけ=栃木県)、下野(しもつけ=群馬県)となるが、常陸は、ここもさきにみた秦氏族の広がっていたところで、那珂(なか)郡に幡田(はた)郷、茨城郡、新治(にいはり)郡にはそれぞれ大幡多郷(おおはたごう)があった。
常陸国全体としては、百済王遠宝(えんぽう)、阿部狛(高麗)臣秋麻呂(あべこまのおみあきまろ)といった百済系、高句麗系人の国司もいたが、一九七三年に、いまは勝旧市となっている那珂郡幡田郷で、新羅・加耶(かや)系渡来の秦氏族のそれであった虎塚壁画古墳が発見された。
この発見は当時の新聞を大きくにぎわし、考古学者はじめ、多くの人々の目をみはらせたものである。
私もそのうちの一人だったが、のち、私は友人たちとともにその虎塚壁画古墳をたずねたときのことをあるところに書いているので、この古墳のことはそれによってみてもらいたいと思う。 |

茨城県勝田市の虎塚壁画古墳。
|
――勝田市についてみると、市史編さん事務局の平野伸生氏、教育委員会社会教育主事の鴨志田篤二氏らが待っていてくれて、平野さんはまず、「勝田市史資料絵はがき」第三集の『虎塚古墳』や、勝田市教育委員会編『甲斐武田氏の発祥の地をたずねて』などをくれた。もちろんいうまでもないことであるが、以上は二つとも、関東地方をあつかった私の『日本の中の朝鮮文化』(1)(一九七〇年刊)が出たのちになって発見されたものであった。
私たちは、できたばかりの市商工会館のレストランで昼食をすますと、平野さんたちが用意してくれたクルマで、さっそく虎塚壁画古墳めざして出発した。
関東平野特有の小丘陵の多いところで、今度発見された彩色石室の虎塚壁画古墳は、灌木におおわれたそんな丘陵のひとつの台地上にあった。
あたりは小史跡公園といったものとなっていたけれども、古墳自体は厳重な保存装置がほどこされている。
私たちは、とくに鴨志田さんが鍵を使って扉を開けてくれたので、石室内にまではいってみることができた。
奥壁中央の蛇目文(じゃのめもん)はじめ、そこに描かれた彩色文様はどれもあざやかで、それが千数百年前のものとはとても思えないぼどたった。
私たちはみな、目をみはるような思いでそれをみたものだった。
『勝田市史資料絵はがき』第三集「虎塚古墳」のなかにある(虎塚古墳の概要)をみると、それはこういうものとなっている。
虎塚古墳は常磐線勝田駅の東方約四・六キロ、湊線中根駅の北々東〇・九キロに位置し、茨城県勝田市東中根指渋(さししぶ)三四九四番地にある前方後円墳である。
中丸川の支流にのぞんだ谷に面する南側の台地上に立地し、全長五五メートル、後円部径三〇メートル、高さ五・七メートル、前方部幅三一メートル、高さ一・五メートルで前方部を西に向けている。
古墳の周囲には幅五メートル前後の周堀がめぐり、とくに北側に痕跡がよくのこっている。
昭和四八年夏、勝田市史編さんの事業として第一次調査が行われ、後円部の南側に小形の横穴式石室を発見した。
石室前面には幅一メートル、長さ約四メートルの墓道がつづき周堀へ接続していた。軟質の凝灰岩を用いた石室は長さ一メートルの短い羨道(せんどう)と長さ三・〇七メートル、幅一・四メートル、高さ一・五メートルを測る玄室(げんしつ、遺骸埋葬の場所)からなる。
玄室入口には酸化鉄を原料とした赤色顔抖で描いた連続三角文がある。
玄室の奥壁と東西両側壁は凝灰岩の大きな板石を用い、壁の前面に白色粘土を塗り、その上に幾何学文と武器・武具・馬具・装身具などが赤く描いてあった。
奥壁には三角文・環状文のほか鉾・槍・大刀の武器と靱(ゆき)・鞆(とも)・冑(ちゅう)などの武具がみられた。
東壁には三角文・渦文(かもん)のほか、靱・楯・首飾り・鐙(あぶみ)状のものなどがあり、西壁には三角文と円文・舟あるいは馬具らしき図文が発見された。
三枚の天井板は赤く彩色され、七枚の床石上には白色粘土を塗りこめ、上面を彩色している。
一体の遺骸には黒漆塗(くろうるしぬり)大刀・刀子(とうす)・鉄鏃(てつぞく)を副葬していた。
虎塚古墳は七世紀中頃、この地に勢力を占めていた豪族の墳墓(ふんぼ)であり、彩色壁画古墳として東国の古墳の中で特異な位置を占めている。
これらの壁画は悪霊から死者の身を護る意味をこめて描いたものであろう。
昭和四八年一二月に国の史跡指定をうけた。 |
幡田郷(はたごう)
飛鳥の高松塚壁画古墳ほどではないとしても、東国としては飛鳥のそれに匹敵するほど意義深い古墳の発見であったわけであるが、さて、では、このような彩色壁画古墳を築造した「この地に勢力を占めていた豪族」とは一体どういうものたちだったのであろうか。
そのことについては、『勝田(かつた)市史』別編(1)『虎塚(とらづか)壁画古墳』中にある志田淳一氏執筆の「古代史における虎塚古墳の問題点(3)」「秦氏との関連/虎塚古墳と幡田郷」にくわしい。
つまり、虎塚壁画古墳が発見された常陸のそこは、斎藤忠氏の「わが国における帰化人文化の痕跡」にある「那珂郡 幡田郷」だったところであった。志田氏の「秦氏との関連/虎塚古墳と幡田郷」にその関連がこう書かれている。
幡田郷は幡多郷(はたごう、三河国渥美郡)、幡多郷(遠江国長下郡)、幡陀郷(紀伊国安諦(あんたい)郡)、波多郷(肥後国天草郡)などとも書き、渡来人秦氏の後裔(こうえい)や、秦氏と関係ある一族が居住していたようである。
ところで、最近の研究によれば、朱(しゅ)や丹(に)をもって、各種の物品を赤く染める赤染(あかぞめ)の呪術(じゅじゅつ)は、新羅、加耶系の呪術で、赤染氏によってなされていた。
その赤染氏は秦氏と同族、または同一の生活集団を形成していた氏族で、新羅系の帰化人だといわれている。
のちに赤染氏や秦氏のかかには、画師として活躍する者が少なくない。 |
甲斐の武田氏はどこから出たか
なお私たちは、虎塚壁画古墳近くにある「十五郎穴横穴(じゅうごろうあなよこあな)郡」といわれるたくさんの横穴古墳をみてから、ついで今度は勝田市武田の湫尾(ぬまお)神社にいたった。
これも丘陵台地上にあるあまり大きくない神社だったが、その前には(甲斐武田氏発祥の地)とした標柱がたっており、また、「名将信玄を出した/甲斐武田氏発祥の地」とした勝田市教育委員会による説明板もだったりしている。
どちらも最近になってたてられたもので、その間のことについては、“風林火山”の子孫/ルーツ訪問の旅/勝田市の武田郷へ二十七人/歴史のロマンを求めて」とした一九八一年九月二八日付の朝日新聞・茨城版の記事をみたほうが早い。
こう書かれている。 |

武田信玄発祥の地、湫尾(ぬまお)神社
|
風林火山の旗で知られる戦国時代の勇将、武田信玄の祖先(の地)は常陸国武田郷である、とする新説に基づき、二十七日、山梨県から武田家家臣の子孫ら二十七人が勝田市武田の“甲斐武田氏発祥の地”を訪れ、地元住民と歴史のロマンを求めて交歓した。
ルーツ巡りの発端は、茨城キリスト教大学の志田淳一教授(五一)=古代史=が打ち出した新説。
(志田氏は)勝田市史編さんを引き受けていた五十二年、初期の佐竹氏をめぐってと題する論文を発表し、「武田氏は常陸の国を支配した佐竹氏とともに 源義光(新羅三郎、八幡太郎義家の弟)が祖先で、義光の三男義清が那珂川北岸の武田郷に住み、武田冠者(かじゃ)義清と名乗った。
のちに義清は子の清光とともに常陸を追われ、甲斐に移り、甲斐武田氏に続いた」とする新説を展開した。
これを聞いた山梨県から昨年十二月、研究者十五人が現地を訪れて調査、あっさり新説を認めた。
山梨ではこれまで、義清の孫信義が元服した韮崎(ならさき)市を武田氏発祥の地としていたが、どこから移って来たかは解明されていなかった。
甲斐(かい)への配流について、志田説は、京都の公家の日記を根拠に「十二世紀の初めの武田郷周辺は勢力争いが激しく、拡張をあせる新参の義清、清光父子に行きすぎの行為があって告発された」と説明している。 |
記事はまだつづいているが、甲斐の武田氏が源義光(みなもとよしみつ)から出たものであることは、これまでもはっきりしていたことであった。
それがこの記事のような経過によってであるということは、義光が「常陸介(ひたちのすけ)」になっていたことがあるということからもうなずけるが、ところで、その源義光はどうして新羅三郎義光であったかということである。
「甲斐武田氏、常陸佐竹氏の祖である源義光は、近江園城寺(おうみおんじょうじ)の新羅明神の神前で元服したので新羅三郎と呼ばれる」(勝田教育委員会編『甲斐武田氏発祥の地をたずねて』)というのか、一般的な通説となっている。
「三郎」とよばれたのはかれが源頼義の三男だったからだとすると、では、その彼はどうして、近江(滋賀県)の大津市にいまもある園城寺(三井寺)の新羅明神(新羅善神堂)の神前で元服したのであろうか。
もう紙数がないので簡略にするが、そのことに解答をあたえてくれるのが、遠江(とうとうみ=静岡県)の浜松市江之島に、近江の新羅明神を勧請して新羅大明神をまつった小笠原源太夫基長の自筆「新羅大明神祀記」である。
源太夫もまた源氏一門から出たもので、その「――祀記」によると、近江の新羅明神は自分たち源氏の「祖神であるから」ということがはっきりと書かれている。
すなわち、佐々木源氏ともいわれる近江におこった源氏は、新羅系渡来人から出たものだったのである。
そうしてみると、さきにみた新羅・加耶系の渡来人である秦氏による虎塚壁画古墳といい、常陸佐竹氏、甲斐武田氏など、これは皆それから出たもので、常陸国だった茨城県の古代・中世は、百済王遠宝(えんぼう)、阿部狛(あべのこま、高麗)臣秋麻呂(おみあきまろ)といった百済系、高句麗系の国司もいたが、那珂(なか)郡幡田郷(はたごう)ほか新治(にいはり)郡や茨城郡などにも大幡郷(おおはたごう)があったことからみて、新羅・加耶系渡来人またはその子孫が中心であったようである。
2 下野(しもつけ)・上野(こうづけ)から相模(さがみ)へ
top
新羅系渡来人の活躍
常陸(ひたち)の茨城には、あるいは常陸の茨城にも、秦(はた)氏族の集住地であった京都に「蚕養機織(ようさんはたおり)管弦楽舞之祖神」という秦酒君(はたのさかぎみ)を祭る大酒(おおさけ)神社や、「蚕の社(かいのやしろ)」があったのと同じようなものがある。
筑波郡筑波町の蚕影(こかげ)神社や初酉(はつとり=服部=機織)神社がそれで、さらにまた、斎藤忠氏の「わが国における帰化人文化の痕跡」をみると、行方(なめかわ)郡玉造(たまつくり)町に朝鮮渡来の冠帽(かんぼう)や垂飾(たれかざり)付耳飾などが出土した三昧塚(さんまいづか)古墳がある。
しかしながら、さきを急がなくてはならぬのでそれらはおき、常陸の西方となっている下野(しもつけ=栃木県)に目をやると、もとは寒川郡だった小山(おやま)市に間々田(ままだ)というところがある。
間々田が古代朝鮮からの渡来人と関係あるところとは想像もできないであろうが、今井啓一氏の『帰化人の研究』によると、この間々田はもと真楽(しらぎ=新羅)郷であったものが真木郷(まきごう)となり、そして真木、間々田となったものだという。
それと関係あることと思うが、小山市喜沢(きざわ)の古墳から大和の石上(いそのかみ)神宮にあるのと同じ古代朝鮮製の七支刀(しちしとう)が出土していて、そのことが一九七一年一月二七日付の毎日新聞にこう報じられていた。
「古墳からナゾの出土/朝鮮製の七支刀/“どうして東日本に”/日本で二つ目/学界の課題に」と。
どうして東日本からもそれが出土したかということは、その七支刀(しちしとう)を祭祀用、または権威のシンボルとして持っていたものが古代朝鮮からそこへも渡来していたからにほかならない。
それからまた、那須郡湯津上(ゆづがみ)村の笠石(かさいし)神社には、新羅系渡来人のものだということがはっきりしている「那須国造碑(すわのくにのみやっこのひ)」がある。
那須国造だった那須直韋堤(なすのあたいいで)を顕彰したもので、「永昌元年」(六八九)と、当時新羅が使用していた中国・唐の年号が用いられているのがおもしろい。
大町雅美(おおまちまさみ)氏ほかの『栃木県の歴史』には、そのことがこう書かれている。
この碑が新羅の帰化人によって建立されたことは明らかである。「永昌(えいしょう)」とは唐の則天武后(そくてんぶこう)のときの年号であり、しかも中国風の墓誌形式をとっていることによって実証される。
唐の年号を用いたのは、新羅が唐の冊封(さくほう)を奉(ほう)じたがらである。
『日本書記』持統天皇元年(六八七)の条に、新羅人(しらぎびと)が下野(しもつけ)に居住した記事があることは、この間の経緯をよく物語っている。 |
実際からみて、「冊封を奉じた」とはちょっといいすぎであるが、それにしても、古代の当時、遠い日本列島のここ下野にいた彼らが、新羅で使用されていた年号をそのまま用いていたとは、考えてみればふしぎのような気がしないでもない。
それはそれとして、この那須国造抻は宮城県多賀城市の多賀城碑、上野(群馬県)吉井町の多胡碑とともに日本三古碑のひとつとして国宝となっているものであるが、そのうちの多胡碑がこれまた、新羅系渡来人によるものであることがはっきりしているものなのである。
群馬県の大古墳の真実
そこで、下野(しもつけ)から西どなりの上野(こうづけ)となったが、上野の群馬県は古墳の多いところで、斎藤忠氏の「わが国における帰化人文化の痕跡」にある大古墳のそれだけみても、次のようなものがあげられている。
=の下は、朝鮮渡来のものとみられる出土品である。
△勢多(せた)郡城南村 前二子山(まえふたこやま)古墳=四神装飾付有台長頸壺(ゆうだいちょうけいこ)
△伊勢崎市今(いま) 古城(こじょう)古墳=冠帽(かんぼう)
△佐波郡玉村町 二子山古墳=冠帽
△高崎市 乗附(のりつけ)古墳=冠帽
△高崎市 観音山古墳=垂飾(たれかざり)付耳飾 |
もちろん、これだけが全部ではなく、ほかにもまた宝塔山(ほうとうざん)古墳、蛇穴山(じゃけつやま)古墳などたくさんあるが、群馬大学教授(考古学)だった尾崎喜左雄氏の「上野における韓来(かんらい)文化」をみると、その古墳文化のことがこうある。
群馬県では四世紀末乃至五世紀初め頃から大古墳が造られ、この傾向は六世紀にもあるが、その終り頃から七世紀前半にかけては巨石使用の大石室が営まれ、再び大古墳が築造されている。更に七世紀の終りから八世紀初頭にかけて、大古墳とは言えないが、精巧な古墳が築かれているのである。
この文化的な発展は自生とは言えない。
その当初は大和或は河内の古墳文化を受容したものであろうし、爾後(じご)も大陸から継受されたものを逸早(いちはや)く受容したのであろう。
けれども、はたして文化のみの単なる受容であったと見るわけにはいかない。 |
そして尾崎氏は、六世紀の大和朝廷成立以前に、九州から来たものによる「河内王朝」があったとし、そのときに来た朝鮮渡来人の「蝦夷地東国(えぞちとうごく)」への進出、上野(こうづけ)への「投入」があったらうとして、さらにこうのべている。
それ以後の投入も考えられようが、郡の設置に際して、甘楽(かんら)郡が早くから存在したことは、「から」の地方の始源(しげん)をかなり古くに置くべきであろうと考えるからである。
群馬県の大古墳の創始も、この辺に真実が含まれてはいないだろうか。 |
「郡の設置に際して」とは、たとえば「上野国(こうづけのくに)甘楽郡」といった国・郡設置のことで、そのとき早くも甘楽郡が存在したということは、この地方が以前すでに(から)というところだったからである。
したがって、「群馬県の大古墳の創始も、この辺に真実が……」というのである。
甘楽(かんら)郡とはいまの藤岡市、富岡市、吉井町などのことであるが、この甘楽は甘羅(から)、甘良(から)とも書かれたもので、それ以前は「から」、すなわち「韓(加羅)=から」となっていたところであった。
ここは古く、七世紀半ばの「大化の改新」以後といわれる国・郡設置以前から新羅系渡来人の集住地だったのである。
吉井町神保(じんぽ)にはいまも、もとは韓(から)だった
辛級(からしな)神社がある。 |

群馬県の古来の渡来人を祀る辛級(からしな)神社
|
多胡碑(たごのひ)
さきの那須国造碑(なすのくにのみやつこのひ)とともに日本三古碑のひとつとなっている多胡碑があるのも吉井(よしい)町で、ようするに多胡碑というのは、「弁官符(べんかんふ)に上野国(こうづけのくに)片岡(かたおか)郡、緑野(みどの)郡、甘良(から)郡のうちの三百戸を郡となし、羊に給いて多胡郡となす」と碑文(ひぶん)にあるように、七一一年の和銅四年に多胡郡が新設されたことの建郡記念碑である。
そして従来、ここにいう「羊」とはなにかということについていろいろな議論があったが、尾崎喜左雄氏の『多胡碑』をみると、碑のある吉井にいた新羅人のこととともに、その「羊」のことがこう書かれている。
天平神護(てんびょうじんご)二年(七六六)といえば奈良時代の中頃であるが、上野国にいる新羅人子午足(しごたり)等百九十三人に、吉井連(よしいのむらじ)という姓(かばね)があたえられた。
新羅人は出身地をしめしたもので、帰化人である。子午足は名であって、したがって氏(うじ)も姓もなく、吉井連という姓をあたえられたのである。
二百人近い新羅人に一度に賜姓(しせい)されたのであり、このような多人数への一度の賜姓は他に例がない。
子午足はその筆頭であるので、帰化人としての一大勢力家であったにちがいない。
それなのに、それまで氏も姓もなかった。
このように、帰化人に出身地と名だけ記されている例が、『日本書記』には多い。……
新羅人(しらぎびと)子午足(しごたり)は、前に述べたように、吉井連(よしいのむらじ)の賜姓(しせい)のあるまでは、氏も姓もなかったが、百九十三人の同族を擁する吉井在住の豪族であった。
だから、おなじ吉井に所在する多胡碑(たごのひ)の羊は、やはり氏も姓ももたない豪族で、郡司に擬(ぎ)せられた者とみられ、羊、子午足、羊子三(ようしさん)は順次関係ある人物のように思えるので、おそらく羊は帰化人であろう。 |
いまの吉井町の吉井ということも、新羅系渡来人の「吉井連」というそれからきたものだったのであるが、その吉井連という姓は、筆頭の子午足のみでなく、「子午足等百九十三人」全部にあたえられたということに注目したい。
これらはそれぞれみな、大家族制時代の戸主だったであろうから、朝鮮語でいうその食口(シツク=人口)は大変なものであったにちがいない。
寒川(さむかわ)神社
上野(こうづけ)ははかにもまだみたいところはたくさんあるが、しかしもう、武蔵西方の相模(さがみ=神奈川県)のほうへまわらなくてはならない。 相模ということになると、まず、相模国一の宮とかっている寒川神社である。
この神社については、私にひとつの思い出がある。というのは、一九七〇年に『日本の中の朝鮮文化』(1)をだした直後のこと、私は山形県寒河江(さがえ)市に住むある郷土史研究家から、「寒河江市の寒河というのは古代朝鮮語からきた言葉と聞いているが、するとこれはどういう意味なのだろうか」という問い合わせの手紙をもらった。
しかし、私としてははじめて聞くことだったので、「わからない」とそう返事をするよりはかなかった。
そしてそのことは忘れていたが、しかしなんとなく気になっていたものらしく、その後、一九七五年に出た丹羽基二氏の『地名』を手にしたとき、寒河江の「さが」「さむかわ」の項を引いてみたところ、それが次のようになっているではないか。 |

相模の寒川神社
|
さむかわ 寒川。朝鮮語のサガ(わたしの家、社などの意)からくる。朝鮮渡来人の集落があった。
寒川はもとは寒河で当て字。 |
私は、「ああ、そうだったのか」と思い、ついでまた、「さがみ」というところを引いてみると、それはこうなっている。
さがみ 相模、相摸。相武にも当てる。朝鮮語のサガ(寒河)からきている。朝鮮人の居所。
相模には朝鮮渡来人の集落があった。寒川神社はその氏神。 |
私はいよいよ、「ああ、そうだったのか」と思わないではいられなかった。
私は相模もひとまわりして、すでに本(『日本の中の朝鮮文化』(1))にまでしていたにもかかわらず、そこにそんな神社があったとは全く知らなかったのである。
私は、山形県寒河江(さがえ)市の郷土史研究家にそのことを知らせたかどうか、それはもう忘れているが、後日、高座(こうざ)郡寒川(さむかわ)町にある寒川神社をたずねてみて、さらにまたおどろいた。
一の鳥居からの参道を歩くだけでも、かなりの時開かかかった。
社務所で求めた『相州一の宮/寒川神社誌』をみると、「現境内は一万四千二百八十五坪余りである。
因みに古の神領は現今の藤沢・茅ヶ崎・寒川・海老名の三市一町に及ぶ広大なものであった」とあり、祭神は「寒川比古命(ひこのみこと)、寒川比女命(ひめのみこと)」となっていて、その「由緒」はこうである。
関八州鎮護(ちんご)の神として、古くからこの地方の名祠(めいし)としてあがめられている。
即ち総国風土記によると、約千百年前、雄略(ゆうりゃく)天皇の御代(みよ)に弊帛(へいはく)を奉納せられたとあるので、当時すでに関東地方における著名な神社として遠近に知られていたことが明らかであり、従って創建の極めて古いことと、往古から朝野の崇敬(そうけい)殊に厚いことが知られる。 |
高麗若光(こまじゃっこう)とは
この「由緒」どおりだとすると、寒川神社が祭られるようになったのは、中郡大磯町高麗にある高来(たかく、高麗)神社よりもはるか以前ということになる。
そして、寒川神社を氏神としていたのは古代朝鮮のどこから来たものか、具体的なことはわかっていないが、高来(たかく)神社のほうはそれがかなりはっきりしている。
神奈川県林業指導所のリーフレット『高麗山(こまやま)』にも、「東海道線平塚駅から大磯にむかう右手に、こんもりとした山が見えます。この山を高麗山といいます」として、そのことがこう書かれている。
高麗という地名のおこり
奈良時代に高麗若光(こまじゃっこう)一族が海路この地に移住してきました。
彼等は花水(はなみず)、相模(さがみ)両川の下流原野の開拓を行いながら、大陸の先進文化をひろめました。
その後、高麗人は霊亀二年(七一六)に武蔵国(埼玉県)に移ったといわれます。
現在でも高麗寺、高麗山、唐(から)ヶ浜、唐ヶ原などの地名がのこっており、その当時がしのばれます。
高来神社(高麗神社)
うっそうと樹木のおい繁った高麗山南面の山麓に高来神社、高麗神社、権現さんなどの名で呼ばれている由緒ある神社があります。……
奈良時代に本地垂迹説(ほんちすいじゃくせつ)が唱えられるようになると神仏を一つに考え、神社の境内にお寺を建てるようになりました。
高麗神社の境内にも養老年間に法相宗(ほうそうしゅう)の僧が千手観音像を本地仏として鶏足山雲上院(けいそくさんうんじょうじ)高麗寺を創建し、高来神社の別当(べっとう)としました。……
しかし、明治維新になると、神仏分離という時代の潮流がここにも押しよせ、建物は破壊され、歴史を誇る高麗寺も廃寺(はいじ)となり、ただ神社のみが高来神社として、今ものこっています。
高来神社の祭典は一月七日の七草祭、四月十八日の春祭、七月十八日の夏祭と年三回あります。 |
ここにいう「高麗若光一族」とは、あとでみる武蔵・狛江郷の高句麗系渡来人とはまた異なり、六六八年に高句麗がほろびたことからやって来た集団であった。
そしてそれからはここ大磯の高麗山麓に高麗(こま)神社を祭っていたのであるが、それが一八九七年の明治三〇年に高来(たかく)神社となったのである。
いまも高麗山頂には高麗神社の奥宮があって、その「高麗山のごときは、山腹に蜂の巣のように横穴がほられ、県下でも有数の横穴古墳郡をなしている」(読売新聞社横浜支局編『神奈川の歴史』(上))。
古墳はほかにも楊谷寺(ようこくじ)横穴古墳郡や清水谷(しみずだに)横穴古墳郡などがあるが、つまりそのように彼らは、そこで何世代にもわたって生と死とをくりかえしていたのである。
したがって、「その後、高麗人(こまびと)は霊亀二年(七一六)に武蔵国(埼玉県)に移ったといわれます」とあるけれども、それはこれからみる新設の武蔵国高麗郡の大領(郡長)となった高句麗の王族であった高麗若光ほか一部で、けっしてその全部ではなかった。
そればかりか、中野敬次郎氏の「箱根山の開発と高麗文化」にみられるように、彼らのうちの一部は大磯から西へも広がって行った。
そして、箱根の駒(こま=高麗)岳山頂に高麗神社の分社である駒形権現、すなわちいま芦ノ湖畔にある箱根神社の奥宮である駒形神社を祭り、さらにまたそこから駿河(静岡)の伊豆へ広がっては、そこに伊豆山(いずさん)神社を祭っている。
3 奥武蔵から浅草へ top
武蔵野は朝鮮人の移住地であった
さて、そこでいよいよ、「武蔵野は往古、朝鮮人の移住地であった。
これは武蔵野に限らず、関東一般概ね然りであったが、武蔵野は特に然りだ」(徳富蘇峰「平凡の景色」)という武蔵となった。
このような武蔵については、「常陸(ひたち)の虎塚(とらづか)古墳ほか」項のはじめに引いた『東京都の歴史散歩』(上)のそれを思いだしてもらいたいが、さらにまた、地元、埼玉大学の教授である原島礼二氏の「関東地方の渡来文化」にもそのことがこうある。
関東地方の渡来文化を語るには、まず何よりも武蔵国の場合をとりあげなければならない。
埼玉・東京・神奈川県にまたがる武蔵国には、早くから屯倉(みやけ)の管理者として新羅系の渡来氏族である吉士(きし)集団が移住してきた。
しかもそれから一世紀近くたってから、七世紀後半におきだ高句麗・百済の滅亡にともない、高句麗人と新羅人の大集団がこの国の北半、埼玉県の飯能(はんのう)市・日高町や志木(しき)市付近一帯に移住している。……
埼玉県の西北端にある本庄(ほんじょう)や児玉(こだま)町は、群馬県が利根川や神流川をへだててその北に接している。
このあたりは古代武蔵の北限で児玉郡とよばれていた。
八高(はちこう)線だけが通っている児玉町の周辺は今日では過疎に近いが、かっての児玉郡は北武蔵でもっとも人口密度の高い地方たった。
一九三一年に刊行された『埼玉県史』の第二巻には平安時代の郡別の郷配置図がある。
一つの郷の人口は七〇〇人から一二〇〇人ほどだが、およその人口は大差がないから、郷のこみいった郡ほど人口密度が高いと考えてよいだろう。
埼玉県ではそうした意味で、児玉郡と大里(おおさと)郡がもっとも人口密度が高かったというわけである。
ところがこの児玉・大里地方、すなわち古代の児玉・加美(かみ)・那珂(なか)・榛沢(はんざわ)・幡羅(はたら)・大里郡と男衾(おぶすま)郡の北半部には、渡来人の古い波が顕著に及んでいることを見逃せない。
まず神流(かんな)川の東岸にある加美(かみ)郡には今城青八坂(いまきあおやさか)神社という社名を共有する(延喜)式内社(しきないしゃ)が三座もあった。
今城はいうまでもなく今来(いまき)で、今来の渡来文化がこの地に及んでいた一証になる。
七世紀後半になって移住したあの大集団ではなく、それより早く移住してこの郡内で有力な地位を占(し)めた渡来人のグループだろう。
七世紀後半の大集団が住みついた新羅・高朧の二郡に式内社が全くない事実から、かえってそうみることができる。
また幡羅(はたら)郡には秦(はた)氏とつながる上秦郷(かみはたごう)や下秦郷があり、秦氏の力がそこに及んでいた。 |
武蔵の地名のおこり
ここにいう「吉士(きし)集団」のことについては、さきの摂津「難波吉士と四天王寺」の項でちょっとみているが、それから、またも山城の京都や、常陸の茨城でみたと同じ秦(はた)氏である。
じつをいうと、私はそれをはぶいてきたが、さきにみた相模にも秦野(はたの)市があって、いまここで中村和伯氏の『神奈川県の歴史』をみると、さきのそれとちょっと重複するけれども、そのことがこういうふうに書かれている。
東海道線大磯駅から東ヘ一キロのところに高来(たかく)神社があるが、そこは『倭名抄(わみょうしょう)』の“高来郷(たかくごう)”であり、海をわたってきた高麗人が唐ヶ原(もろこしがはら)をひらいてつくった集落である。
そこから金氏が花水(はなみず)川をさかのぼってひらいたのが金田(かねだ)や金目(かなめ)であり、秦氏が開拓したのが秦野(はたの)盆地である。
東へすすんだ秦氏が八幡の地名をのこし、相模川をわたって広大な相模野を開拓して高句麗(こうくり)とよむ高倉(または、たかくら)の郡名となった。
箱根も朝鮮語の箱、バコニからきたものである。 |
なお、いまここに引かれた『倭名抄』には、武蔵では播羅郡(はたらぐん)ばかりでなく、男衾(おぶすま)郡にも幡郷(はたごう)や幡々郷(はたはたごう)がみられるが、それはおいて、幡羅郡(のち大里郡に併合)に古くから秦氏族などが渡来していたことは、幡羅郡がのちにそうなる大里郡だった熊谷市上中条の古墳から、古い朝鮮製の高坏(たかつき)型の器台が出土していることからもわかる。
一九七九年一〇月四日付の読売新聞・埼玉版をみると、「熊谷の鎧塚(よろいづか)古墳/珍しい器台が出土/五世紀中期の朝鮮製か」という見出しのもとに、そのことがこうある。
熊谷市上中条にある中条遺跡郡の鎧(よろい)塚古墳からこのほど五世紀中頃のものとみられる高坏型(たかつきがた)器台が出土した。
大きさは直径四十センチ、灰色をしており、紋様(もんよう)、成形技法などから、関係者は朝鮮で焼かれたものと推定している。
こうした器台(きだい)は関東地方では、まだ確認されておらず、考古学研究の重要な資料となるものとみられる。 |
記事はまだつづいているが、新聞にはその器台の写真も出ていて、私のような素人(しろうと)がみても、それが新羅・加耶(かや)あたりから直行した硬質土器(こうしつどき)であることがすぐにわかった。
まだ武蔵国というものも成立していなかった五世紀中頃、すでにそういう土器を持ったものたちが北武蔵に来ていたのである。
武蔵国といえば、大体、この「武蔵」という言葉からして、鳥居龍蔵氏の『武蔵野及其周囲』によると、朝鮮語のモシ・シ(麻の種子)からきたものとして、こうのべられている。
「私は要するにムサシの地名はもと朝鮮語と同じく、モシシの苧(からむし)種子の意味であって、最初、武蔵の一ヵ所の小部分にこの苧を植えた所の名で、これが次第に武蔵の地名となったものと思う」と。
そのモシ(麻=あさ)のことを日本では苧麻(ちょま)、または苧(からむし)といっているが、しかしこのからむし(苧)ということも、「加羅(カラ、韓)モシ」、すなわち(韓むし)ということにほかならないのである。
この苧は武蔵野一帯、いたるところで栽培され、古代では『万葉集』にも出ている多摩川あたりのそれが有名だったが(調布という地名もそれからきた)、いまでは福島県会津の「からむし織」などが知られている。
銅の発見
それから、さきに引いた原島氏のそれに、「七世紀後半の大集団が住みついた新羅・高麗二郡」というのがあったが、それについてはあとでみるとして、ここでは北武蔵のほうをみたついでに、信濃(長野県)などと境を接している西北武蔵のほうもちょっとみておくことにしたい。
とすると秩父(ちちぶ)市となるが、ここの黒谷に「和銅遺跡」とした碑があって、そこの山々で銅が発見されたことを記念している。
近くの山麓には銅塊も神体のひとつとなっている聖(ひじり)神社もあるが、七〇八年の慶雲(けいうん)五年に、ここで銅鉱を発見したのは、新羅系欧来人の金上元(こんじょうげん)らであった。
それでただちにこの年から年号が(和州)となり、日本史上に有名な「和銅開珎(かいちん)」も鋳造されることになったのである。
『続日本紀』和銅元年条をみると、そこで発見された銅のことを、「天地の神の顕(あらわ)し奉(たてまつ)れる瑞(しるし)の宝」とし、年号を和銅としたことで「大赦」まで行っている。
そしてそれまで無位だった発見者の金上元には従五位下(じゅごいげ)をさずけたり、ということにもなっている。
古代の当時、秩父でその銅が発見されたということは、それほどに文化史的大事件だったのである。
のち七四九年、陸奥守だった百済王敬福(きょうふく)による金の発見も大きな文化史的事件だったが、金上元(こんじょうげん)らによる銅の発見はそれより半世紀ほど早かったことで、その意義はいっそう大きかったのである。 |

秩父市黒谷にある「和銅遺蹟」の碑。
|
秩父には知知人彦命(ちちおひこのみこと)を祭神とする秩父神社があって、毎年一二月三日に行われる「夜祭り」が有名であるが、そういう祭りということになると、先に、『東京都の歴史散歩』でみた「浅草寺縁起にでてくる土師直中知(はじのあたいなかとも)・桧前浜成(ひのくまのはまなり)・同竹成(たけなり)」を祭る「浅草・三社祭り」は江戸時代からすでに有名なものであった。
浅草神社
普通は浅草観音といわれる浅草寺「縁起」とは、大和(奈良県)飛鳥の漢(あや)氏がのちそれとなる桧前忌寸(ひのくまのいみき)一族からでた桧前浜成・竹成(武成とも書かれる)兄弟と土師直中知(真仲知とも)が小観音怺を海からひろいあげて祭ったのが浅草寺のはじめだというはなしである。
が、「海からひろいあげて」というのは、こういう「縁起」によくみられる付会で、それはやはり、鳥居龍蔵氏の『武蔵野及其周囲』にこうあるのがただしいのではないかと思う。
| 漢人(あやひと)は古くから関東に移住して居ったが、本国に居った時も又日本に移住後も、仏教を信仰して、小さい持仏を持っていたが、かかる小仏像が帰化人によって祀られたのが此の寺の基で、それが膨張して今日の浅草寺を成したのではあるまいか。 |
野田宇太郎氏の「浅草観音」にも同じようなことが書かれているが、しかしそれはどちらにせよ、そういうことで、桧前浜成(ひのくまのはまなり)ら三人を神として祭ったのが、浅草寺本堂裏手にある浅草神社である。
浜成(はまなり)ら三者を祭ったところから三社権現ともいわれ、毎年五月に行われるその祭りが浅草・三社祭りなのである。
その祭りは、深川の八幡祭り、神田明神祭りとともに「江戸三大祭リ」のひとつとなっていたもので、今日でも盛大なものとなってつづけられている。
毎年、新聞にも写真入りで出るが、たとえば今年、一九八五年五月一七日付の毎日新聞をみると、「きょうから三社祭り/祭り一色、燃える浅草っ子」という見出しのもとに、三日間にわたって行われるその祭りのことがこう報じられている。 |
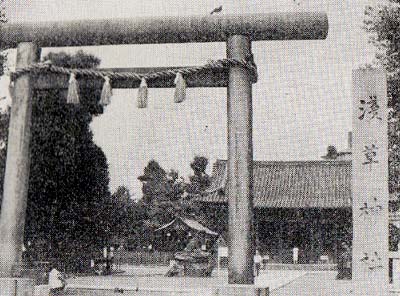
浅草神社
|
例年二百万人余の人出でにぎわう浅草・三社祭りが十七日、幕を開ける。浅草かいわいはすでに祭リばやしが流れ、祭りムードがいっぱい。……
十六日は、浅草神社が拝殿で用意した神輿(みこし)先導のおんべ(御幣=ごへい)百十三本のおはらいと神輿(みこし)の御魂(みたま)入れの儀式に氏子の四十四町会長が集合、のりとなどの神事を約一時間で終え、各町会の神酒所(みきしょ)におんべを持ち帰り、本番待ち。
神社境内は約千軒の露店が並び早くも商売スタート。
十七日は、浅草芸者の見番(けんばん)「東京浅草組合」から名物の大行列が繰り出す。
芸者さんが手古舞(てこまい)の衣裳で花を添え、……このほか都内各区のトビ職、氏子(うじこ)総代、おはやし連も参加し、総勢千人近い行列となる。
十八日は、四十四町会から百十三基の「町内神輿(みこし)」が繰り出す。
十九日は祭りのハイライト、宮神輿(みやみこし)三基の宮出し、宮入りが行われ、各町内を練る。 |
「例年二百万人余の人出」とはおどろくべきもので、鳥取県を例にとると、その総人口の三倍以上である。
今年はちょうど、この稿を書いているときだったので、念のため私もその三社祭りへ行ってみた。
どこも人、人、人の列でよく歩くこともできず、汗をたらたら流しながら、神社近くまでたどりつくのがやっとだった。
若い娘さんたちがねじり鉢巻き姿で、屈強の男たちにまじって神輿をかついでいるのもおもしろかったが、一方で私は、びっしり詰(つ)まった人々にもまれながら、この人々のうち、浅草神社の神として祭られている三者(三社)が三者とも、古代朝鮮からの渡来人であることを知っているのは何人いるだろうか、とそんなことを思ったりしたものだった。
なお、そんな神社は浅草神社だけではない。近くの隅田川にかかった白髪橋(しらひげばし)をわたると向島だが、そこに新羅明神の白髪神社があって、稲村坦元・豊島寛彰氏の『東京の史跡と文化財』にこうある。
| 社伝に天暦(てんれき)五年(九五一)に近江国滋賀郡打下(うつげ)から勧請祭祀(かんじょうさいし)したといわれ、近江の本社は比良(ひら)明神と称して、祭神は猿田彦命(さるたひこのみこと)であるが、元来は海を渡って来た朝鮮の神戸武蔵にも上代朝鮮帰化人が来住したので、それらによって祭られたものと思われる。 |
4 高麗(こま)郡と狛江(こまえ)郷
top
高麗郷
奥武蔵の埼玉からいつのまにか、東京の浅草まで来てしまった。
それでというわけではないが、今度はその東京・山手線の池袋駅や新宿駅から出ている私鉄に乗る、ということで、あれこれをみることにしたい。
まず、池袋であるが、池袋からは西武電鉄の池袋線と東武電鉄の東上(とうじょう)線とが出ているがその東武東上線に乗って二〇分ほど行くと、埼玉県の志木(しき)となる。
「七世紀後半の大集団が住みついた新羅・高麗二郡」(原島礼二「関東地方の渡来文化」)のうちの新羅郡となっていたところであった。
新羅郡はのち新座(にいざ)郡となり、さらに北足立郡となりして、いまは志木(しき)市、新座市などとなっている。
三上吉之助氏の「志木の町名の移り変りその他について」にこうある。
「新羅文化の移入により、新座郡には志木郷、志楽木(しらき)郷(今の白子)、新座郷(今の新倉)、余戸(あまりど=今の野火止、片山)など新羅に影響された地名が多い」
「志楽木郷(今の白子)とは新羅ということであり、白子も、都がもとは宮処(みやこ)であったようにこれも新羅の斯羅処(しらこ)、すなわち新羅人の居処ということだったのである。
ここには一九四三年ごろまで白子村(しらこ)、新倉(にいくら)村があったが、それがいまでは和光(わこう)市となっている。
大体このように、新羅郡は「大集団が住みついた」にもかかわらず、いまではその地名などに、少しばかりの痕跡をのこしているだけである。
|

高麗神社
|

西武池袋線高麗駅前にある将軍塚。
|
それにくらべ、高句麗(こうくり)系のそれが住みついた高麗(こま)郡のほうは、いまも高麗神社などいろいろなものを、はっきりとした形でのこしている。
そこで今度は池袋から、西武池袋線に乗ることにする。
すると約一時間で、これもハンナラ(韓国=ハンナラ)という朝鮮語からそれとなったという埼玉県の飯能(はんのう)となるが、そこから秩父行に乗りかえた二駅先は高麗(こま)駅となる。 |
最近はここも東京のベッドタウンということで宅地化か進んでいるが、しかし、ここまでくるとまだまだ、林や森など武蔵野のおもかげがかなり色こく残っている。
高麗駅からはそういう風景を目にしながら、高麗川をわたって三〇分ほど歩くと、高麗神社や高麗山勝楽寺(しょうらくじ)の聖天院(しょうてんいん)などがある高麗郷である。
いまは入間(いるま)郡日高(ひだか)町となっているが、もとは高麗郡高麗村だったところで、さきにみた新羅郡ができたのは七五八年であったが、高麗郡ができたのはそれよりずっと早い七一六年のことであった。
『続日本紀』霊亀二年五月条に、そのことがこうある。
| 駿河、甲斐、相模、上総(かみふさ)、下総(しもふさ)、常陸(ひたち)、下野(しもつけ)の高麗人千七百九十九人を以て武蔵国に遷(うつ)し始めて高麗郡を置く。 |
高麗家から分家した人々
ここにいう「高麗人」とはもちろん高句麗から渡来したそれであるが、しかしこれは河内(大阪東部)などでみてきた古い高句麗系渡来人とは異なり、相模(神奈川県)でみたのと同じく、六六八年に高句麗がほろびてから渡来したものたちであった。
彼らははじめ駿河(静岡県)、甲斐(山梨県)などに分散していたものだった。
それが駿河など各地で、先着あるいは土着のものたちとのあいだで悶着をおこしていたところから、秩父山地に近い武蔵野の一角に彼ら一七九九人がうつされて、そこが高麗郡となったのである。
そして相模の大磯にいた高句麗王族の高麗若光(こまじゃっこう)が、その郡の大領(だいりょう=郡長)となったのであった。
高麗若光は高句麗の王族であっただけではなく、人々を統率するのにすぐれた能力を持った人物だったらしく、相模にいたころの七〇三年の大宝三年に従五位下(じゅごいげ)に叙(じょ)され、「王」という姓(かばね)をあたえられでいる。
コシキ(王)とは王を意味する古代朝鮮語である。
この高麗王若光(じゃっこう)と猿田彦(さるたひこ)とを祭ったのが高麗神社であるが、代々の宮司(ぐうじ)は王若光(じゃっこう)の血脈を伝える高麗家で、それがいまでは第五九代目となっている。
そして高麗家には、失火などのことがあったにもかかわらず、なおまだ「高麗王大刀(たち)」といわれるものなどいろいろな「宝物」が伝わっているが、なかでも貴重なのは、千数百年にわたる『高麗氏系図』である。
二十八代永純(えいじゅん)の壮時(そうじ)、高麗家は古今を通じての最大不幸に遭遇した。
それは後深草(ごふかくさ)天皇の正元元年の十一月に失火して、故国より持ち来れる貴重な宝物古記録等の大部分か灰塵に帰したことである。
高麗氏の古系図もこの時焼失したので、一族老臣始め、高麗の百苗(ひゃくびょう)が集まり、諸家の日記を取調べて編成したのが、現在、高麗家に伝わる系図一巻である。(高麗明津編『高麗神社高麗郷』) |
こういうしだいで、いまの『高麗氏系図』はこのとき再編成されたものであるが、しかしそのことで我々は別にまた、貴重なある事実を知ることになった。
というのは、このとき系図再編のために集まった「高麗の百苗」、すなわちそれまでに分かれ出た高麗氏の主要な分家が、その再編系図に記録されることになったからである。
それによると、再編のために集まったのは、宗家(そうけ)の高麗氏ほか次の諸氏であった。
| 高麗、高麗井(こまい)、駒井、井上、新(あらた)、神田、新井、丘登(おかのぼり)、岡登、岡上、本所、和田、吉川、大野、加藤、福泉(ふくいずみ)、小谷野(こやの)、阿部、金子、中山、武藤、芝木(しばき)。 |
「後深草天皇の正元元年」は一二五九年であるから、その時点で高麗家からは、これだけの分家が分かれ出ていたのである。
日本に渡来した氏族は、このようにその姓(名字=みょうじ)を変えたりしているので、宗家(そうけ)からは一体どれだけのものが分かれ出ているかよくわからぬのが普通であるが、その意味でも、『高麗氏系図』の記録は貴重なものとなっているのである。
重層している渡来人
ところで、高麗家の場合はそういう記録があるからわかるが、ではほかの、それで高麗郡ができた「千七百九十九人の高麗人」の場合はどうかというと、それは記録がないので全くわからない、というよりほかないのである。
しかし高麗氏のそのような増加ぶりからみて、これはもう無数といっていいのではないかと思われる。
なお、記録のある高麗氏についてもう少しみると、それから分かれ出て国鉄八高線の金子(かねこ)を根拠地としていた金子氏族なども、それなりに繁栄してあちこちに広がっているが、高麗氏族自身もまた相当な広がりをみせている。
湯山学氏の「高麗氏と三沢十騎衆」と副題された「戦国時代の高幡三郷(たかはたさんごう)」をみると、高幡不動堂における座次(ざじ)のなかに高麗山城守、高沢平次左術門、高説近江守といった名がずらりとならんでいる。
そういうことから湯山氏は、いまは東京都日野市となっている室町時代の高幡三郷を、高麗氏一族が「領有していたと推定できる」としている。
高幡三郷は、新宿から出ている京王線高幡不動のあたりであるが、金子氏族などはそこをさらに飛びこえて、同じ京王線沿線の東京都調布市まで広がっている。
その金子氏族のことはあとにして、韭塚一三郎(にらづかいちさぶろう)氏の「武蔵野における朝鮮文化」によると、いま武蔵には高麗神社の分社が一三〇余社ある。
そしてあるところでは大宮神社、広瀬(ひろせ)神社、白髪(しらひげ)神社となったりしているが、これにどうして新羅明神の白髪神社がまじっているかというと、それは先住の新羅系渡来人が白髪神社を祭っていたあとに、高麗神社が祭られたからである。
高麗神社が高麗王若光(じゃっこう)とともに猿田彦(さるたひこ)を併祭(へいさい)しているのはそのためで、これはがれら渡来人が重層したことを物語るものであるが、そのような重層はここばかりではない。
これからたずねる、いまは東京都狛江(こまえ)市となっている狛江郷でも、それがみられるのである。
狛江郷
さて、そこで今度は新宿駅である。ここから出ている小田急線に乗ると、二〇分ほどで狛江(こまえ)市の狛江につくが、京王線に乗ると、これまた二〇分ほどで調布市のつつじヶ丘につく。
東京都立植物園や、重要文化財の白凰仏(はくほうぶつ)があることで知られている深大寺(じんだいじ)へはここからバスで一五分ほどであるが、ところで、この「つつじヶ丘」はもと「金子(かねこ)」となっていたところで、いまもバス停留所などに金子という地名が残っている。
そして西つつじヶ丘に厳島(いつくしま)神社があるが、そこの石碑に、「当社は神代(深大=じんだい)村金子の鎮守にして、……思うに当地は往昔(おうせき)金子氏移住の所なれば」うんぬんとあるように、これはそこへ広がってきた金子氏族の氏神だったものであった。
広がってきた金子氏族とは、もちろん、さきにみた高麗家から分かれ出たそれであるこというまでもない。
一方、その調布市つつじヶ丘のとなりとなっている狛江(こまえ)市のほうに目を向けると、かっての狛江郷の中心だったといわれるここは、非常に古墳の多いところで、江戸時代末期までは「狛江百塚」といわれたものだった。
それについては、手元にある新聞の切リぬきをみたほうが早い。一九七五年二月五目付の読売新開・武蔵野版によると、「兜塚古墳(狛江)都の史跡に/六世紀中期の原形保存/周辺も買収、公園に」という見出しのもとにこうある。
狛江市和泉(いずみ)にある兜塚(かぶとづか)古墳が、近く(東京)都の「史跡」に指摘される。
狛江には約百六十の古墳跡があったことが確認されているが、調査、保存が行われないま宅地化が進み、ほとんどが破壊されてしまった。
たった一つかろうじて原形をとどめているのが、六世紀中頃のものとみられているこの兜塚古墳。
それも取り壊される寸前に市が所有者から一億五百万円で買い取ったので“命拾い”、今度ようやく保護の手が差しのべられることになった。
都教委の調べによると、兜塚(狛江市和泉七四九)は、高さ四メートル、直径三十メートル、約千二百平方メートルの円墳。
いまでは原形がなくなってしまったが、約五百メートル南西の亀塚(前方後円墳)が、かっての発掘調査で、朝鮮半島からの帰化人集団の六世紀中頃のものと推定されており、兜塚も同系列集団の古墳とみられるという。 |

東京都狛江市の兜塚古墳
|
|
狛江郷の高句麗系渡来人
ここにいう亀塚古墳が発掘調査されたのは一九五〇年代に入ってからであったが、ここからは高句麗よりの神人歌舞画像鏡(しんじんかぶがぞうきょう)や、金銅飾板(こんどうかざりいた)などが出土している。
いまその跡には、狛江市教育委貝会による「狛江亀塚」とした石碑がたっていて、「蓋(けだ)し古墳は西暦六世紀頃この地に在住せし豪族の墳墓(ふんぼ)にして、狛江郷の発祥に至大(しだい)の関係あるものなるべし」とある。
そういうことから、狛(高麗=高句麗)江という地名もおこったのであったが、なお、朝日新聞社三多摩支局編『三多摩風土記』の「亀塚古墳」をみると、こういうことが書かれている。
この狛江郷は、現在の調布市、三鷹市、武蔵野市、川崎市などの一部をふくむかなり広い地域で、狛江市がその中心地だったという。……
高句麗系の帰化人がいつごろから狛江付近に住みついたか、という点で、亀塚古墳は一つの手がかりを与えてくれた。
築造されたのが六世紀前半ということになっているから、それよりも前、五世紀の後半から六世紀初め頃、という計算になる。
その後、朝鮮半島では高句麗が戦争に敗れ、多数の高句麗人が日本に亡命、帰化したが、そのころ狛江郷の帰化人は二世、三世の時代になっていたと考えられる。 |
高句麗が「戦争に敗れて」ほろんだのは、七世紀後半の六六八年のことであった。
したがって、それがほろびたのちに渡来した集団により、さきにみた高麗郡ができたのは七一六年であるから、こちら狛江郷との差は約二百年であった、ということになる。
そして、その高麗郡の高麗家から分かれ出た金子氏族が狛江郷にまで広がってくるまでには、さらにまた相当の時間がたっていたはずである。
それであるから、そのあいだ狛江郷にいた高句麗系渡来人はもう「二世、三世」どころか、すっかり土着化したものとなっていたにちがいない。
もとから狛江郷にいたそれを先来の「土着者」とすれば、あとからそこへ広がって来た金子氏族は後来の「よそもの」ということになるであろう。
その先来の土着者と後来のよそものとの接点となったのが、調布市深大寺町にある深大寺である。
日本人とは何か
「一般に寺伝縁起の類にはマユツバものが多いのであるが、これにはかなりの真実性がありそうに思える」と甲野勇氏の『武蔵野を掘る』に書かれている『深大寺縁起』によると、それはこういうふうになっている。
むかし、狛江郷柏野(かしわの)の里といわれたここに、温井右近(ぬくいうこん)・虎女(とらじょ)という長者の夫婦が住んでいた。
その夫婦の間に生まれていた一人娘が、いつのまにか「よそもの」の福満という青年と愛し合うようになった。
近隣にうわさが立ち、右近夫婦は娘をしかってとめたけれども、娘は聞き入れない。
そこで右近夫婦は怒って、湖のなかにあった小島に小屋をつくり、娘をそこへ閉じこめてしまった。
深大寺のある小盆地は湧水が多く、いまも池があって、かってのそれは湖のようなものとなっていたようであるが、そのことを知った青年福満の悲しみは深く、小島の娘に逢いに行こうにも、船もなければ筏もない。
福満は水神・深沙(じんじゃ)大王に祈り、この湖を何とか渡れるようにしてくれれば、あなたを湖水の主として、また、村の鎮守として末永く崇(あが)め祀りますと誓いを立てた。
すると、一匹の大亀が水中からあらわれ出て、彼を湖のなかの島へと運んでくれた。
もちろん、福満は娘に逢うことができたばかりか、そのことにおどろいた右近夫婦も、彼ら二人が結ばれるのを許した。
やがてこの若夫婦のあいだからは、一人の男児が生まれた。
男児は生まれながらにして天資聡明、長じて奈良の都に上り、大乗法相の仏教を学んだ。
そして彼は帰って、ここに深大寺を創建した。
この彼がすなわち深大寺の開山(創建者)となっている満功上人(まんくうしょうにん)であり、その開山は七三三年の天平五年だったというのである。 |
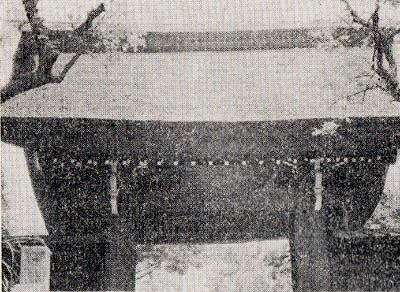
福満の子が奈良の都で仏教を学んで、満功上人となって
開山したと伝えられる武蔵野の深大寺
|
水中から大亀があらわれてたすけるなどというのは、もとよりそのまま信じることはできないが、それをのぞけば、甲野勇氏の『武蔵野を掘る』にあるように、なるほど「かなりの真実性がありそうに思える」はなしである。
甲野氏は、さらにつづけて書いている。
奈良時代創建というのは、金銅仏の存在や、近所にわずかながら布目ガワラが出ることでも裏づけられるし、よそ者との恋物語も帰化人が移住しているのだから、頭から否定することもできない。
おそらくこの寺は、奈良時代に狛江郷に住む帰化人によって建立され、水源の守りとされたものではないだろうか。
この豊かな泉は、狛江の水田をうるおす、大切な水源の一つだったからである。
水の守りに深沙大王というエキソチックな水の神をまねいたのも、日本人らしからぬ感覚である。 |
ここにいう「日本人」とはなにか、ということが問題となるであろう。
なぜかといえば、これによると、いわゆる「帰化人」、私のいう渡来人は先来も後来もすべて「よそもの」で、それとは別に多数の「日本人」がいたかのようである。
しかし、これまでみてきたことで明らかなように、そういうことはないはずである。
というより、古代朝鮮からのいわゆる帰化人、渡来人が現代でいう日本人にほかならないのである。
第一、千数百年前の古代には、その風土での歴史の積み重ねによって形成される民族としての日本人はまだなかったのである。
top
**************************************** |