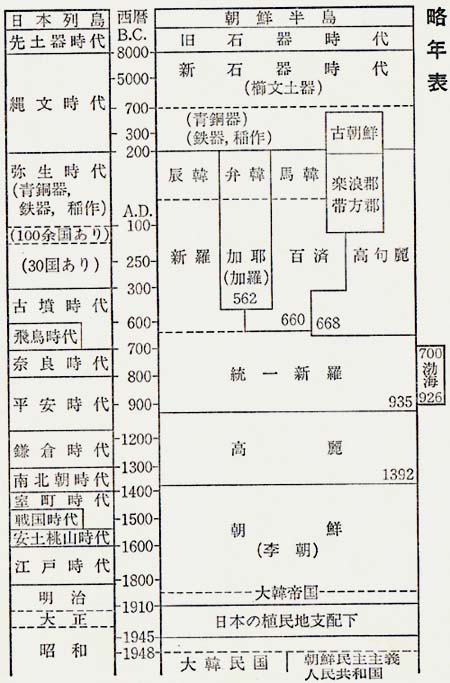|
****************************************
Home 地球と生物の謎 人間の誕生 日本誕生 古代の日本と朝鮮
古代の日本と朝鮮
(金達寿(キム・タルス)著 ちくま少年図書館94 筑摩書房 1985年刊)
あとがき――近江の渡来人
別ページ
一章 大和(奈良)
二章 和泉(大阪南部)
三章 河内(大阪東部)
四章 摂津(大阪西部)
五章 山城(京都)
六章 武蔵(東京・埼玉)と周辺 |
日本人はどこから来たのだろうか
古代、日本と朝鮮はどんな関係にあったのだろう。
大挙して朝鮮からやってきた人々は、日本の歴史をどのようにつくりかえていったのか。
奈良の小路に故郷朝鮮を発見して以来、全国各地の古代の遺跡を精力的にたずね歩き、文献や地名、神社などを手がかりに、日本の古代史の謎をときあかそうと試みる刺激に満ちた物語。
著者略歴
1919年朝鮮、慶尚南道に生まれる。1930年日本に渡り、働きながら独学。1941年日大芸術家卒業。神奈川新聞、京城日報記者、『民主朝鮮』編集者をへて、作家生活にはいる。
『金達寿小説全集』『日本の中の朝鮮文化』など、多数の著書がある。 |

|

あとがき――近江の渡来人 1985年 top
私の古代史関係の仕事としては、これまでに、全一二冊を予定している『日本の中の朝鮮文化』という古代遺跡紀行シリーズを八冊だし、それとともに雑誌などに書いたものをまとめた文集を五、六冊だしているが、『古代の日本と朝鮮』とした本書のような、全部を書きおろしで一冊とするのはこれがはじめてである。
私か筑摩書房編集部の土器屋泰子さんに「ちくま少年図書館」としての本書を書きおろす約束をしたのは、たしか八、九年前ではなかったかと思う。
ずいぶん長い年月がかかったものであるが、しかし、それで大変よかったということもある。
というのは、その八、九年のあいだに各地で新たに発見された追跡ばかりか、専門研究者たちによる最新の知見をも、これにはとり入れることができたからである。
そのことは本書の随所に引用されている、何年何月何日付という新聞記事などをみてもよくわかると思う。
本書の対象となったのは、古代はそこが日本の中心地であった関西のいわゆる五畿内(きない)と、それから関東の「武蔵(東京・埼玉と周辺)である。
畿内とは、「王城付近の地。……我国では京都近い国々、即ち山城(やましろ)・大和(やまと)・河内(かわち)・和泉(いずみ)・摂津(せっつ)の五個国。五畿内」と岩波版の『広辞苑(こうじえん)』にある。
しかし、これにはどういうわけか、近江国(滋賀県)がくわえられていない、というより、はずされているということがある。
近江は「京都に近い国々」のひとつであるどころか、すぐとなりの国なのである。
そればかりか、近江は「王城付近の地」というより、「王城」そのものの地でもあったのである。
天智帝が六六七年から六七二年までの間、ここに(近江朝)をおいたことは広く知られているとおりである。
しかも、それだけではない。 |
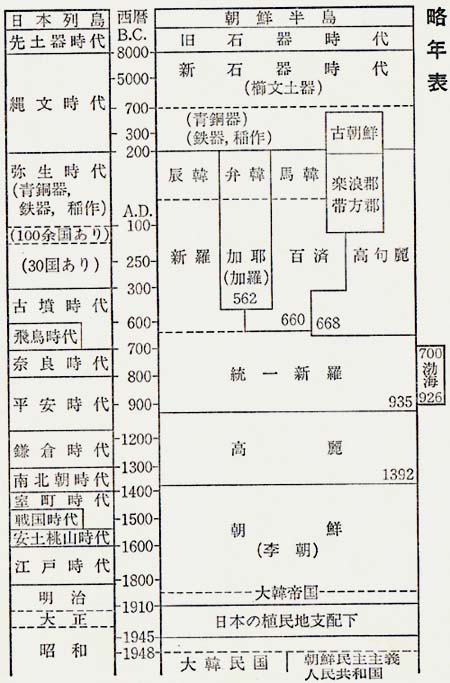 |
『日本史探訪』『別巻古代編』(二)に林屋辰三郎氏の「近江王朝」があって、そのことか林屋氏はこういうふうにのべている。
結局、アメノヒボコ(天日槍・天之日矛)の伝説は、弥生(やよい)時代の日本に、大陸から最新の農業技術と優秀な金属器文明と、新しい呪具(じゅぐ)の信仰を伴って渡来してきた人たちがあったこと、その場合に、いわゆる日本海ルートを経て裏日本から畿内(きない)へというコースがかなり重要な舞台であったらしいことを示していると思います。
それから、大事なことは、アメノヒボコの系譜が、最後にオキナガタラシヒメ(息長帯比売)、すなわち神功皇后(じんぐうこうごう)に至っているということですね。
つまりこの伝承全体が、息長(おきなが)氏に結びつけられている点は、これからお話しする「近江王朝」と大いに関係してくるのです。……
息長氏は大体琵琶湖の東岸、和邇(わに)氏は琵琶湖の西岸に勢力を張っていた。
私はこの二つの豪族は共に渡来人から出たものだと思います。おそらく弥生時代のある時期に、日本海ルートで裏日本に上睦し、琵琶湖の両岸にそれぞれ展開した渡来人の集団でしょう。
そして林屋氏は、
「いま、大津市坂本穴太(あのう)町に高穴穂(たかあなほ)神社がある。
ここが高穴穂宮(たかあなほみや)跡と伝えられる揚所である。
景行(けいこう)天皇のあと、成務(せいむ)天皇と仲哀(ちゅうあい)天皇もここに都を置いた」 |
として、日本に最初の王朝ができたのは、近江であったというのである。
つまり、近江の地は天智帝の近江朝ばかりでなく、それ以前にも、景行・成務・仲哀帝による王朝、すなわち「王城」があったところというわけであるが、しかし、にもかかわらず、近江はいわゆる畿内からははずされているのである。
こういうところにも古代日本史の「隠くされた」一面があるのではないかと思われるが、それはともかく、いまみた林屋辰郎氏の述べていることからもわかるように、この近江もまた、本文でみた大和(奈良県)などと同じく、古代朝鮮からきた欧来人の集住地であった。
たとえば近江州の大津京や、高穴穂宮跡だという高穴穂神社のある大津市の穴太(あのう)である。
ここでは近年も遺跡の発掘調査がつづいていて、一九八二年一一月一二日付の京都新聞をみると、
「日本最古の切妻/大壁造り住居跡/大津・穴太遺跡で発見/一三〇〇年前、帰化人集落/大津京遷都解明の糸口」 という大見出しのもとに、そのことがこう報じられている。
大津市の穴太(あのう)遺跡の発掘調査を進めている滋賀県教育委員会は十一日までに、わが国で初めてという約千三百年前の切妻大壁造り住居遺構を発見した。
同教委は、この遺構がわが国では例のない特異な構造を持っていることから、朝鮮半島からの渡来人集団が営んだ集落跡とみており、彼らが大きな役割を果たした天智天皇の大津京(六六七〜七二)遷都のナゾを解く手がかりとなるものと期待している。
遺構が見つかったのは、大津市下坂本(しもさかもと)と唐崎(からさき)にまたがる穴太地区。
国鉄湖西線唐崎駅から北へ約八〇〇メートルの地点。十八棟以上の掘立柱建物にまじって切妻大壁造り住居一棟が見つかった。
同遺構は一辺約八メートル、幅約一メートル、深さ三十〜五十センチの溝で囲まれ、溝の中に直径約十二センチの間柱が三十〜五十メートル間隔で立てられている。……
遺構群は、いずれも七世紀初めから後半の飛鳥〜白鳳期に建てられたものだが、この時代、寺院以外の民家に土壁が用いられた例はなく、遺構を復原すれば、その形が和歌山市六十谷(むそたに)遺跡から出土した朝鮮半島南部の系譜をひく土器・家形瓲(はぞう=水か酒を入れた祭祀(さいし)用具)によく似ていると推定されるため、朝鮮半島の影響を強く受けた建物だとしている。……
今回、発見された遺構群は、上層部から検出されたものだが、年代的には五十年程度の差しかなく、礎石建物や切妻大壁造り住居などからみて、同教委では同集落が渡来人集団が営んだ集落とみて間違いないとしている。
これまで、穴太(あのう)、錦織(にしごり)など大津近郊の山すそで見つかった約六百基の横穴式石室墳(せきしつふん)の被葬者が、その構造や副葬品から朝鮮半島南部からの渡来氏族と考えられていた。
今回の発見で、初めてそうした人たちの居住集落が明らかにされたわけで、当時の彼らの生活ぶりをうかがう貴重な手がかりといえる。
さらに、渡来人を重用(ちょうよう)した天智天皇が、なぜ大津に都を移したのか、ナゾに包まれた大津京解明の糸口になる期待もかけられている。 |
近江朝の大津京ばかりではなく、高穴穂宮(たかあなほのみや)のあった穴太(あのう)でそういう遺跡が発見されたということが重要なので引いたが、地名だけではなくのちには人名(姓)ともなる穴太(あのう)とは、古代中部朝鮮にあった加耶(かや、加羅・加那ともいう)諸国中の一国である安那(あな、安耶・安羅ともいう)からきたものであった。
もちろん、高穴穂宮というのも「穴太宮(あのうのみや)」ということで、この場合の「高」は美称にほかならないのである。
近江には草津市穴(あな、もと穴村)というところがあるが、これはなにもそこに大きな穴ぼこがあったから、というわけからのものではなく、これも安耶(あや)・安羅(あら)ともいった安那(あな)からきたものであった。
草津市穴のそこにはいま天日槍(あめのひばこ)を祭神とする安羅神社があって、ほかにも付近に小安羅神社となっているのが二社ある。
穴太(あのう)、穴と同じ阿那(あな)、吾名(あな)などとなっていたところは、新羅(しらぎ)・加耶(かや)系渡来人集団の象徴となっている天日槍にかかかる遺跡とともに、ほかにも近江にはたくさんある。
「ここに槍日槍、莵道河(うじがわ)より沂(さかのぼ)りて北の方、近江国の吾名(あな)の邑(むら)に入りて暫(しまし)住み、……この故に、近江国の鏡谷(かがみのはざま)の陶人(すえびと)は天日槍の従人(つかいびと)なり」(『日本書紀』垂仁(すいじん)三年条)とあるその吾名からきたもので、いま蒲生(がもう)郡竜王(りゅうおう)町鏡にも天日槍を祭神とする鏡神社がある。
それらの遺跡については、私も『日本の中の朝鮮文化』(3)「近江・大和」でみているが一九八四年に出た石原進・丸山竜平氏の古代近江の朝鮮にもかなりくわしく書かれている。
とくにこの『古代近江の朝鮮』には巻末に、『続日本紀』『新撰姓氏録(しんせんしょうじろく)』などの古文献に出ている「古代近江朝鮮関連人名一覧」があって、これによると本文でもみている新羅(しらぎ)・加耶(かや)系渡来人の秦(はた)氏だけでも、依智秦今吉(えちはたいまきち)はじめ三二三氏となっており、穴太(あのう)氏が穴太村主(あのうすぐり)など一六氏となっている。
ほかにまた百済・安耶系の大友氏が大友漢人若子売(おおともあやひとわくごめ)はじめ二九氏となっているが、これらはいずれも大家族制となっていた古代のことであるから、全体としての食口(人口)はどれほどであったか、それはもう知りようがないのである。
それにまた、林屋辰三郎氏のいう「『近江王朝』と大いに関係して」いる息長(おきなが)氏、和邇(わに)氏などの豪族をくわえるとなおさら、ということになるであろう。
ところが、また、それだけではないのである。
これまでみたのは、どちらも六世紀以前に渡来していたとみられる新羅・加耶系または百済・安耶系の渡来人であるが、そこへさらにまた七世紀後半からということがはっきりしている、百済系のそれが重層してくるのである。
すなわち、六六〇年に百済がほろびたとき、斉明、天智帝のいわゆる大和朝廷からは三万余の「百済救援軍」が送りだされて「白村江(はくすきのえ)の敗戦」とかっているが、それにともなって百済からはまたたくさんの人々がやって来たのであった。
なかには当時四歳だった『万葉集』の歌人、山上憶良(やまのうえのおくら)などもくわわっていた(中西進『山上憶良』)が、そのたくさんの人々がどういうふうに近江に定着したがということを『日本書紀』天智段によってみると、それはこういうふうである。
「四年の春」「二月」「この月、百済国の官位(くらい)の階級(しな)を勘校(かむが)う。
よりて佐平福信(さへいふくしん)の功(いたわり)を以(も)て、鬼室集斯(きしつしゅうし)に小錦下(しょうきんげ)を授く。(その本位(もとのくらい)は達率(たつそつ))
また、百済の百姓(たみ)男女四百余人を以て近江国の神前郡(かみざきのこおり)に居(お)く」
「五年」「この冬」「百済の男女二千余人を以て、東国に居らしむ。
すべて緇素(しそ)を択(えら)ばず(僧、俗の区別なく)。
癸亥(みずのとい、天智二年)より起(はじ)めて三歳(みとせ)に至るまで、並びに官食(おおやけのいい)を賜う(三年にわたって官食を給した)」
「八年十二月」「また、佐平余自信(さへいよじしん)、佐平鬼室集斯(さへいきしつしゅうし)等、男女七百余人を以て、近江蒲生郡(がもうのこおり)に遷(うつ)り居らしむ」 |
天智四年は六六五年であるが、ざっとこれだけみても大変な数である。
大体、日本の総人口五〇〇万ほどであった当時、三万余もの百済救援軍を送りだしたということからしてそうであるが、百済の男女三千余人のうち二千余人にはとくに「三年にわたって官食を給した」というのだから、百済と天智朝との関係がどういうものであったか、容易に推しはかれるというものであろう。
しかもまた、それだけではない。
六六七年の天智六年に、天智朝は都を近江にうつしているが、それから四年後の『日本書紀』天智十年条をみると、この年の正月に、「大友皇子(おおとものみこ)を以て太政大臣」とし、蘇我赤兄臣(そがのあかえのおみ)を以て左大臣となし、中臣金連(なかとみのかねのむらじ)を以て右大臣となす」といった内閣改造と論功行賞のようなことが行われていて、つづけてこう書かれている。
この月に、大錦下(だいきんげ)を以て、佐平余自信、沙宅紹明(きたくじょうみょう、法官大輔)に授く。
小錦下(しょうきんげ)を以て鬼室集斯(きしつしゅうし、学職頭)に授く。
大山下(だいさんげ)を以て達率谷那册首(たちそつこくなしんしゆ、兵法に閑えり)、木素貴子(もくそきし、兵法に閑えり)、憶礼福留(おくらいふくる、兵法に閑えり)、答本春初(とうほんしゅんそ、兵法に閑えり)、本日比子(ほんにつひし)、賛波羅(さんはら)、金羅金須(こんらこんしゆ、薬を解れり)、鬼室集信(きしつしゅうしん、薬を解れり)に授く。
小山上(しょうせんじょう)を以て達率徳頂上(たちそちとくちょうじょう、薬を解れり)、吉大尚(きちだいしょう、薬を解れり)、許率母(こそつも、五経に明かなり)、角福牟(かくふくむ、陰陽に閖えり)に授く。
小山下(しょうせんげ)を以て余(あだし)の達率等五十余人に授く。
童謡(わざうた)に云う。
橘(たちばな)は 己(おの)が枝枝 生(な)れれども 玉に貫(ぬ)く時 同じ緒(お)に貫(ぬ)く。
(橘の実はそれぞれ異なった枝に生っているが、それを玉として緒にとおすときは同じ一つの緒にとおす)。 |
これによると、少なくともあとの「この月に」以下のものは、ほとんどみなすべて百済から来た高官たちである。
しかもさきの天智四年条にみえていた鬼室集斯(きしつしゅうし)などは、このときは早くも「学職頭(ふみつかさのかみ)」となっている。
もとは百済の将軍で、こちらに来てからは、新羅と唐の追撃にそなえて筑紫の大野城など、朝鮮式山城をつくったりした憶礼福留(おくらいふくる)や答本春初(とうほんしゅんそ)ら、それからのちには大博士となる許率母なども大きな存在だが、当時の学職頭といえば、これは今日の文部大臣兼国立大学総長のようなものなのである。
それまでは百済第十六等官位第二位の達率という高官であった鬼室集斯が、その国百済がぼろびると、今度はこちら日本にやって来て天智朝の学職頭となり、小錦下(しょうきんげ)という竹位か授けられているということ、これは一体どういうことだったのであろうか。
ようするに、「橘(たちばな)は……」の童謡にもうたわれているように、もとは一体的なものであったということにほかならないのである。
さきにもいったように、本書の対象となったのは、関西のいわゆる五畿内と関東の武蔵ほか、それにこの「あとがき」でみた近江の一部であるが、それでとくにここでことわっておかなくてからないのは、これまでにみた古代朝鮮との密接な関係は、この五畿内などばかりではなく、日本全国どこも皆、ほとんど同じだということである。
対象となったところだけでも、まだ行ってみたかったところや、書きたりないところがたくさんあるが、ともかくこうして本書が成ったのは、前記の土器屋泰子さんはじめ、筑紫書房編集部のみなさんのおかげである。
とくに直接担当の土器屋さんの強いしごきがなかったとしたら、私はまだ本書を書いていなかったにちがいない。
ここにしるして、感謝の意を表したい。
top
****************************************
|