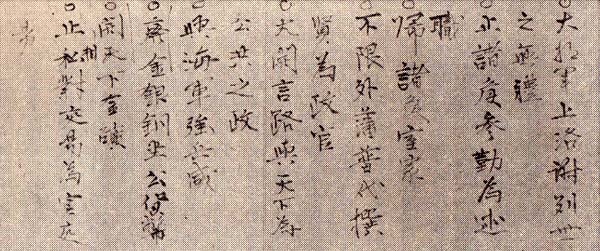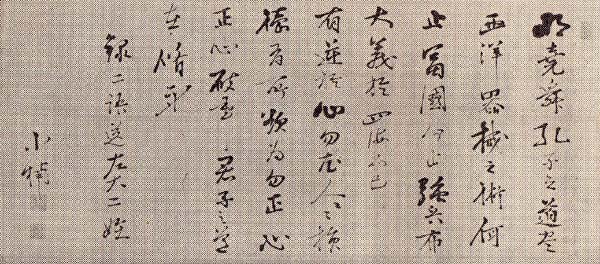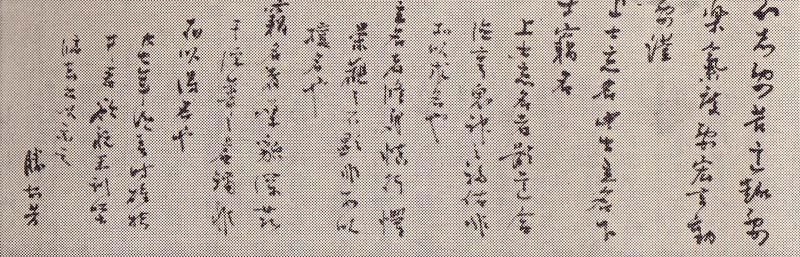|
****************************************
Index 井伊直弼 徳川斉昭 佐久間象山 吉田松陰 武市瑞山 横井小南
横井小南 松浦 玲著
1 肥後熊本での日々
1.1 覚られがたい人
1.2 酒飲み
1.3 実学党
1.4 諸国遊歴
1.5 沼山津
2 政治の舞台へ
2.1 招かれて越前へ
2.2 民衆の利益が根本
2.3 小楠の「富国論」
2.4 幕府の顧問となる
2.5 参勤交代制の改革
2.6 外交路線をめぐって |
3 失意の日々
3.1 士道忘却事件
3.2 小楠不在の政局
3.3 挙藩上京実現せず
3.4 肥後へ帰る
3.5 士籍を失う
3.6 小楠とその家族
4 実らざる理想
4.1 小楠の大理想
4.2 思想と現実
参考図書
横井小南略年譜 |
松浦 玲(まつうられい) 歴史家。
1931年(昭和六) 広島県に生まれる。
京都大学中退(放学処分)、
立命館入学、大学院修了。
著書 『勝海舟』『暗殺』
『日本人にとって天皇とは何であったか』
『勝海舟と幕末明治』ほか。 |
1 肥後(ひご)熊本での日々
top
1.1 覚(さと)られがたい人
不思議な人物である。いや、不運な人というべきか。
肥後熊本生まれの熊本育ち、兄死去のあとを継いで、れっきとした肥後熊本藩細川家の家臣でありながら、ついにその肥後藩では一度も役につかない。つかせてもらえない。
昔は人生五十年といった、その五十歳まで、直接政治に携わることはまったくなかった。
ところが五十を過ぎてから、越前福井藩へ招かれた。
それも藩主の賓師(ひんし)として藩の政治全体を指導するためである。越前福井藩松平家は、親藩家門である。
徳川将軍家の親戚として、御三家(ごさんけ)に次ぐ家柄であった。
そうして、いろんないきさつのすえだが、小楠(しょうなん)を最初に招いたときの藩主だった松平慶永(よしなが=春嶽)は、幕府の政事総裁職という大老に相当する地位につき、小楠はその顧問となる。
出身藩ではなにも仕事をさせてもらえなかった男が、幕府の政治を指導することになったのだ。
それなのに、わずか半年で小楠は失脚してしまう。
それも、政治方針などとはまったく関係のない、つまらぬできごとによってである。
そうして、中央政界から身を引くだけではすまず、出身藩つまり肥後藩の士籍を削られてしまった。
武士の身分を失ったのである。
幕末の、彼の見識と手腕がもっとも必要とされた時期に、熊本郊外の沼山津(ぬやまづ=熊本市秋津町)に逼塞(ひっそく)して暮らさねばならなかった。
やっと明治新政府ができて、その参与(さんよ)つまり国務大臣に登用されると、たちまち京都で暗殺されて終わる。
思うままに腕をふるったという感じは、とうとう最後までない。 |

横井小楠銅像 熊本市沼山津
|
だが、それにもかかわらず、同時代のある系列の人々の間では、小楠(しょうなん)の評価はめっぽう高い。
たとえば勝海舟は、次のようにほめる。
「おれは、今までに天下で恐ろしいものを二人見た。
それは横井小楠(よこいしょうなん)と西郷南洲(さいごうなんしゅう)とだ。
横井は西洋の国も沢山は知らず、おれが教へてゃったくらいだが、その思想の高調子な事は、おれなどは、とても梯子(はしご)を掛けても、及ばぬと思ったことがしばしばあったヨ。
おれはひそかに思ったのサ。
横井は自分に仕事をする人ではないけれども、もし横井の言を用いる人が世の中にあったら、それこそ由々しき大事だと思ったのサ」
海舟には、先輩・同輩・後輩に対する人物評がたくさんあるけれども、横井小楠と西郷隆盛のふたりだけは、いつも別格である。
つねに賛辞を惜しまない。
ところで、この『氷川清話(ひかわせいわ)』の海舟のことばを追っていくと、
「横井の思想を、西郷の手で行なはれたら、もはやそれまでだと心配して居たに、果して西郷は出て来たワイ」と結ばれている。
「もはやそれまでだと心配して居たに」とは、幕府サイドの人間としての危惧(きぐ)である。
横井の思想と西郷の行動が結びついたら、幕府は倒れるほかはない、というのだ。
そうして「果して西郷は出て来たワイ」とは、つまり明治維新である。海舟からみると、明治維新は、「横井の思想」を「西郷の手で」行なったものなのだ。
西郷が明治維新をやったことはだれでも知っている。
しかし、それが小楠の思想だということになると、いったいどのくらいの人がわかっているのだろうか。
ほとんど理解されてはいまい。
海舟もまた、「とても尋常の物尺では分らない人物だ」「覚られ難い人物サ」等々と強調する。
「長州派はほとんど小楠の功をみとめず」という発言もある。
維新の中心勢力だった長州人にさえ、小楠の偉さはわかっていなかったと、海舟は言うのだ。
なるほど覚(さと)られがたい人物ではないか。
もっとも、この海舟のことばには、長州人だからわからないのだという響きもあるのだが。
1.2 酒飲み
小楠(しょうなん)が、出身藩の肥後藩とうまくいかなくなったのは、酒のうえの失敗からだという。
数え年で三十二歳になったときのことである。
それまでの小楠は、むしろ順調だった。
肥後藩士横井時直(よこいときなお)の次男に生まれ、普通なら武士の家の次男・三男は厄介者なのだが、勉強がよくできるので、藩校時習館(じしゅうかん)の秀才コースを進んで、父や兄と別に給料をもらえる見通しができていた。
二十九歳のときには、居寮長といって、学生代表で同時に教師の卵みたいな地位についている。
そうして、三十一歳になった天保十年(1839)には、勉強の総仕上げとして、江戸遊学を命じられた。
江戸時代の学問の総本山、林大学頭(はやしだいがくのかみ)の門にはいってハクをつけてこいというのである。
もどれば正規の教師にしてもらえること、まずまちがいない。こういうように、地方の藩校を卒業して江戸へ遊学する最大の目的は、人に会うことである。 |

時習館跡 藩主細川重賢が宝暦5年に創設。
藩士の子弟は8歳から修学した。熊本市
|
このときの大学頭(だいがくのかみ)は林述斎(はやしじゅっさい)というのだが、この人は行政家タイプで幕府の仕事に忙しく、学校のほうは佐藤一斎(さとういっさい)がとりしきっていた。
だから小楠も、まずこの人に会って入門の手続きをする。
「官学」の実質的代表が佐藤一斎(さとういっさい)であるのに対して、「私学」の代表は、目黒の羽沢村に私塾を開いていた松崎慊堂(まつざきこうどう)である。
だから小楠は、つづいて慊堂を訪ね、さきに入門手続きをとった一斎と比較してみる。
質問するといくらでも答えてくれて、どうもこっちのほうが力がありそうだというのが、小楠の診断である。
自分と同じように、地方の各藩から遊学してきている学者や学者の卵とも交際する。
旗本で学問のある人物ともつきあう。
このころ、幕府の勘定吟味役(かんじょうぎんみやく)だった川路聖謨(かわじとしあきら)らが、よくできると評判で、それではとすぐに会いに行く。
それと、このころ江戸で人気のあったのは、水戸藩の藤田東湖(ふじたとうこ)だった。
水戸藩は、他藩にさきがけていわゆる天保の藩政改革をやっており、東湖はその理論的支柱である。
実地の行政にも携わったけれども、藩主徳川斉昭(なりあき)の側近として江戸にいることが多く、地方から出てくる若者は、争って訪問したようだ。
小楠も東湖に魅せられている。水戸学(みとがく)という独特の学問と政治とが結びついているところが、たまらない魅力で、江戸で話を聞くだけではがまんできず、水戸まで出かけて、改革の成果を目で確かめたいと切望する。
東湖も、どうぞ見学にいらっしゃい、と言ったようだ。
ところが、このあたりで事件が発生する。
東湖は、この天保十年の暮れに、自分の周辺に集まっている諸藩有志を招いて、忘年会を開いた。
小楠もよばれた。
おそらくその席か、帰り道かで、小楠は酒を飲みすぎて他藩のものと喧嘩し、肥後藩江戸留守居(るすい)の判断では、とても江戸へ置いておけないということになったのである。
年が明けて天保十一年の二月、小楠は帰国を申し渡される。
ことの真相は、なにを調べてみても、はっきりしない。小楠が生来の酒飲みで、飲むと議論が鋭くなりすぎて口論に及ぶ傾向があったのは事実だが、それと、遊学中のものを帰国させるという処罰とは、どうみてもつりあわない。
現に国許(くにもと)の藩庁からは、「前途有望な秀才をそんなつまらぬことで挫折させてはいけない、喧嘩して報復される危険があるのなら、本人もかねて希望しているように、東北への旅行に出してほとぼりをさませばいいではないか」と言ってくる。
だれがみても、こっちのほうが筋が通っている。
ところが江戸留守居は、この国許からの指示が届くまえに、小楠を出発させてしまっており、「あの酒グセはとてもなおる見込みはないと思って、もう帰らせました」と弁解している。
江戸留守居(るすい)の立場からみて、よほどぐあいの悪い、小楠を置いておけない理由があったのだろう。
私怨(しえん)がからんでいたのかもしれない。
どんなつまらない理由でも、藩費留学中のものが帰国させられてきたのでは、国許(くにもと)の役所としても放ってはおけない。
正規の処分を加えねばならない。小楠は、七十日間逼塞(ひっそく)という罰をこうなり、そのうえ、時習館(じしゅうかん)の居寮長から江戸留学というコースのさきに予想される、藩での将来の地位を失ってしまった。
家督はすでに天保二年に兄の時明(ときあき)が継いでおり、小楠は、その兄の「厄介(やっかい)」になるほかはない。
この事件の真相は、さきに書いたように不明のままなのだが、表向きの理由は酒である。
そこで小楠が、これに懲りて酒をやめたかというと、全然やめないのだからうれしい。
もっとも、兄の厄介(やっかい)時代は、好きかってに飲むわけにもいかず、神棚(かみだな)にあげてあるお神酒(みき)を盗んで飲むなど、苦労をしたようだが、のちに塾を開いて独立の収入ができると、おおっぴらに飲む。
兄が死んで家督を継げば、ますますおおっぴらに飲む。
越前に招かれて高給をもらえばいっそう遠慮なく飲み、失脚して不遇の時代にも、時勢を憂えてやはり飲む。
こればかりは終生やめられなかった。
味にも、なかなかうるさい。
ごひいきの銘柄は「丹醸(たんじょう)」で、この名前を読みこんだ漢詩まである。
1.3 実学党
これまで書いてきたところからも察せられるように、小楠(しょうなん)は、儒学者である。
徳川(江戸)時代の武家社会は、儒教を正規の学問として採用し、藩校も儒教が中心である。
むろん、中央の昌平黌(しょうへいこう)もそうだ。
ところで、儒学者には、現実政治に積極的にかかわっていこうとするタイプと、政治には関係せず、もっぱら古典の訓詁(くんこ)註釈(ちゅうしゃく)を専門とするタイプとがある。
どちらがよいかといえば、前者すなわち政治にかかわっていくほうがほんとうである。
儒学とは元来、政治をするもののための学問なのだ。
原始儒教、つまり孔子(こうし)や孟子(もうし)の教えがそうだし、徳川時代の日本で支配的だった朱子学(しゅしがく)や陽明学(ようめいがく)もやはりそうである。
中国の宋(そう)の時代の朱子も、明(みん)の時代の王陽明(おうようめい)も、学者であると同時に政治家で、政治家としてさんざん苦労をしている。
その学問はひと口で言って、理想的な政治を行なって、天下万民を幸福にするための学問なのである。
しかし、その政治的理想をすべての儒学者に期待することはむずかしい。
中国においても日本においても、何万人何千人といる儒学者の大部分は、孔子(こうし)や朱子(しゅし)のテキストを解釈するのが精一杯で、それについて道徳的な、お説教をするだけで終わってしまうのだ。
それでりっぱに学者先生として通用する。
だが小楠は、儒学で政治をしようと考えている数少ないひとりだった。
日本でいえば、徳川時代の初期に、備前岡山藩池田家に仕えた熊沢蕃山(くまざわばんざん)のような人物を模範とする。
蕃山は陽明学者(ようめいがくしゃ)で、小楠が属している朱子学(しゅしがく)とは学派が違うのだが、その違いよりも、本当に政治をした先輩儒学者だという点を小楠は重視する。
そういう小楠の学問態度がはっきり固まってきたのは、酒の失敗で藩との関係が悪くなってからである。
皮肉なものだ。うまくいかないものだ。
遊学途中で帰国させられ、藩校時習館での地位も失ってしまった小楠は、兄の家の居候として肩身の狭い思いをしながら、あらためて学問に励んだ。
幸いに同志があって、長岡監物(ながおかけんもつ)・下津休也(しもつきゅうや)・荻昌国(おぎまさくに)・元甲水孚(もとだなが)らと研究討論を重ねることができた。
学問と政治の実際とを結びつけて論じるところから、このグループが“実学党”とよばれるようになる。
反対派は、時習館中心の“学校党”である。
実学党の研究会とは別に、小楠個人の塾も、同じ時期にはじめられた。 |

熊沢蕃山
|
こちらは、兄の家の一室を使わせてもらったり、敷地内に一部屋を新築してもらったりである。
武士はあまり弟子入りしてこず、芦北(あしきた)郡の徳富一敬(とくとみいっけい)とか益城(ましき)郡の矢島源助(やじまげんすけ)ら、惣庄屋(そうじょうや)クラスの豪農の子弟が多い。
徳富一敬は、のちに徳富蘇峰(そほう)・蘆花(ろか)兄弟(どちらも明治の著名ジャーナリスト)の父親になる人である。
矢島源助は、矢島楫子(かじこ)という明治の有名なクリスチャンや、蘆花の作品にある「竹崎順子」の兄さんだ。
こういう豪農層を弟子にもったことも、やはり小楠の学風に影響してくる。
それに彼らは、そこらの普通の武士よりも豊かだから、塾経営も楽になってくるわけだ。
1.4 諸国遊歴
こうやって、江戸遊学中に前途を挫折(ざせつ)させられてから十一年め、嘉永四年(1851)には、こんどは自費で諸国を見て歩こうと思い立つほどの余裕を得た。
アメリカのペリーやロシアのプチャーチンがやってくる二年まえである。
ただしこのたびは、江戸へは行かない。
山陽道から大阪・和歌山・京都、東海道を伊勢から名古屋、それに北陸路を金沢まで行っている。
途中、通過する諸藩の政治ぶりを観察し、儒学者と会って意見を交わす。
246
新しい勉強でもあり、同時に、自分の勉強がどのくらいのところまできているのかのテストでもある。
このとき小楠は、はじめて越前福井を訪れ、通算二十五日もの長期滞在をした。越前藩はどうも小楠とウマが合うらしく、藩をあげての大歓迎で、有志が毎晩小楠のもとに集まっては討論会を楽しんだ。
ことに、小楠が行なった『大学』冒頭の「明明徳、新民、止至善」のいわゆる三綱領の講義は、参会者に非常な感銘を与えたらしい。
これが、七年後の正式招聘(しょうへい)に結びつくのである。
招聘前にも、越前藩は、学校の建設方針などを、わざわざ熊本の小楠のところまで諮問してくるようになる。
1.5 沼山津(ぬやまづ)
こうして高く評価してくれる藩が現われ、また、柳川藩など近隣の藩からの入門者も出てきて、肥後実学党首領横井小楠の名は、ようやく高まったのだが、肝心の肥後藩との関係は、あいかわらずかんばしくない。
越前など諸国を遊歴してから三年後の安政元年(1854)には、兄の時明(ときあき)が死んで小楠(しょうなん)が家督を相続するのだが、兄と違って、藩の役人の口はかかってこない。
翌安政二年には、いろんな事情がからんでのことだろうが、熊本城下の家を引き払って東へ八キロほども離れた農村の沼山津(ぬやまづ)にひきこもるしまつなのだ。
むろん、正規の藩士が城下を離れるのは異例中の異例で、許可がいるのだが、藩庁があっさり認めているところをみると、こんな男に用はないと思っていたのだろう。
しかし、沼山津は、よいところである。
東に阿蘇(あそ)、西に島原(しまばら)湾の向こうに雲仙(うんぜん)、村の集落の南側を木山川が流れて、その向こうに田園が広がる。
小楠は、その木山川沿いの土地と建物を買い求めて、四時軒と名づけた。
四季さまざまに変化する景色がたまらなく美しいところからきた命名である。
ここで塾を開き、収入があったときには増築もしたので、建物には消長があるのだが、現在でも、最盛時に玄関と客間だった部分が残っており、家の裏に回って木山川のほとりに立って見渡すながめは、小楠在世のころとほとんど変わらない。
小楠は、この川やさらに南を流れる赤井川で魚をとり、近くの山々では鳥をとった。
狩猟は、酒と同じく彼の一生の趣味で、ことに網打ちには独特のくふうがあったらしい。 |

四時軒 藩政から遠ざけられた小楠は熊本城下を離れ、
沼山津に居を構えた。
|
小楠がそんなことをしているうちに、いや、じつは、小楠が沼山津にひっこむよりもまえに、浦賀(うらが)にはペリーが、長崎にはロシアのプチャーチンがやってきて、日本は大騒ぎになっていた。
肥後藩だって、幕府から海岸防御の割り当てがあったりして、けっこう忙しくなっているのだが、小楠は使ってもらえない。
まえに江戸遊学のとき知り合いになった川路聖謨(かわじとしあきら)が、このときは勘定奉行になっており、プチャーチンとの交渉掛(がかり)として長崎へ来るというので、小楠(しょうなん)は『夷虜応接大意(いりょおうせつたいい)』という文章を書いて川路の参考に供しようとするのだが、これも、どの程度の効果をもったのか不明である。
ただ、この『夷虜応接大意』のなかに、早くも小楠の外交についての基本態度、「有道の国とは交わり、無道の国とは絶つ」が現われているのは、注目しておかねばなるまい。
小楠は、これを書いた嘉永(かえい)六年(1853)には、まだ鎖国論者の色が濃く、翌年ぐらいから、少しずつ開国論に転じていくのだが、相手国の「道義」をはかり、それによって応待を考えるという態度は、終始変わらない。
2 政治の舞台へ top
2.1 招かれて越前へ
越前(えちぜん)藩から横井小楠(よこいしようなん)を招きたいとの正式打診があったのは、安政(あんせい)四年(1857)である。
藩主松平慶永(よしなが=春嶽)の意をうけて村田氏寿(むらたうじひさ)が熊本まで足を運んだ。
帰りに長崎に立ち寄ったが、このときオランダ人教師から海軍教育をうけていた勝海舟に会い、小楠の人物を吹聴した。海舟が小楠に注目するのは、これからのことらしい。
村田の交渉をうけて、小楠本人は、すぐに承知した。越前藩で腕をふるえれば本望である。
だが、問題は肥後藩だった。冷遇されているとはいえ、れっきとした藩士なのだから、了解をとらずに出向くわけにはいかない。はたして承認するかどうか。
やはり肥後藩は難色を示した。自分のところでも使わないほどの役立たずの男を、他藩へ借すわけにはいかないというのである。
他球団に移ってとたんにめざましく働かれたら、いろんな意味でみっともないと思うのは、いまのプロ野球だが、肥後藩は必ずしもそう思ったわけではない。
ほんとうにダメな男なのだと、決めてしまっている感じが強い。人間評価のむずかしさであろうか。
それともよほど肌が合わないのか。
小楠も、よりによっておかしなところへ生まれたものだ。
それでも、最後には、松平春嶽(しゅんがく)から細川斉護(なりもり)へあてて、つまり殿様から殿様へ直接に、二度も申し入れるという越前藩の熱心さに、肥後藩もついに妥協する。
「お貸ししましょう」と言う。
そんなにいらないのなら、貸すのではなくて、移籍させてしまえばよさそうなものだが、そこまでの話は、どちらからも出ていない。
むろん先例もない。 |

福井城跡 福#30万石の本拠で、石塁と水濠が残る。
|
このとき、無理にでも移籍していれば、あとでの小楠の運命は、ずいぶん変わってくるのだが。
小楠が、沼山津に家族を残したまま、単身福井へ赴任するのは、安政五年である。
ハリスとの日米修好通商条約調印の年、将軍の跡継ぎに紀州藩主の慶福(よしとみ=のちの徳川家茂=いえもち)が決まった年、そうして安政の大獄(たいごく)の年だった。
招いてくれた松平春嶽(しゅんがく)は、一連の政争で大老井伊直弼(いいなおすけ)ににらまれ、隠居させられた。
江戸の屋敷で謹慎しなければならないので、小楠に会いに福井へ帰ってくることもできない。
側近の俊秀で小楠とも旧知の橋本左内(はしもとさない)は、大獄で死刑になった。
しかし小楠は、非運の越前藩家臣団を励まして、よく藩政の維持につとめた。
儒学の講義だけでなくて、財政政策のめんどうをみるところが、小楠の、ただの学者ではないところである。
越前藩の財政家として、のちに明治維新政権成立期の中央財政を担当する由利公正(ゆりきみまさ)がいるが、この由利公正(もとの名を三岡(みつおか)八郎)を育てたのが、横井小楠なのだ。 |

橋本左内 由利公正(三岡八郎)
|
2.2 民衆の利益が根本
小楠の指導で三岡八郎(みつおか)がやった財政政策は、ひと口で言うと、殖産興業・藩営貿易である。
そのかぎりでは、徳川時代中期から幕末にかけて多くの藩が実施した藩営専売と大差ないようにみえる。
しかし、諸藩の藩営専売が、生産・流通過程で生じる利益の全部を藩庁に集めることに最大のねらいをおいていたのに対して、小楠の発想は、まず民百姓に徹底的にもうけさせるというところに特徴があった。
藩の世話で民百姓にものすごく金がはいれば、藩財政など自然に立ち直るというのである。
では、民に利を得させるにはどうするか。
領民が、これまで他領からはいってくる商人に買いたたかれていたのよりも高い値段で産物を買い上げる。
また、じょうずにつくって売れば、もっともうかるような商品の生産を計画指導する。
もちろんこの場合、生産を奨励し、生産者が満足する値段で買い上げた物産の、大量売りさばきが保障されねばならないのだが、小楠と三岡八郎は、それを外国貿易に求めた。
長崎へ持っていって売ろうというのである。長崎は、鎖国時代からつづいているオランダ貿易だけでなく、安政五年(1858)の日米修好通商条約、およびそれにつづくイギリス・フランス・ロシアなどとの通商条約によって、世界万国に向けて開かれた開港貿易地になろうとしている。
小楠は、他家へ養子にいっていた弟が死んだので、安政五年の暮れに、いったん熊本へ帰るのだが、そのとき、三岡(みつおか)を伴った。道々宿ごとに三岡を相手に学を講じながらの旅である。
三岡(みつおか)は、翌安政六年、沼山津(ぬやまづ)の小楠の家に二ヵ月滞在したあと、長崎に向かった。
長崎の唐物(からもの)商小曾根乾堂(こそねけんどう)なる人物の協力で、一町歩(一ヘクタール)ほどの土地を購入して越前藩蔵屋敷を建て、オランダ商館を相手に、越前産の生糸・醤油(しょうゆ)などの売買契約を結ぶ。
これで、販売のほうはだいじょうぶである。あとは、生産がスムーズにいくかどうかだ。
帰国した三岡は、再度赴任した小楠の激励と援助をうけながら、領内をわらじばきで回って、有力な農民や商人に協力を求めた。
販売契約を結んできた商品を増産するために、新しく藩札五万両を発行して生産者に貸し付け、また、買い上げは藩庁ではとても無理なので、福井や府中(武生=たけふ)などの商人の力を借りて物産総会所を設ける。
できるだけ農工商人の自主性に任せ、藩は介入しない方式である。
これは、非常な成功をおさめた。初年度、つまり安政六年に長崎のオランダ商館に売った生糸が二十五万ドル、これを日本金に換えると約百万両で、これを何十匹という馬に積んで運ぶと、九州地方の大評判になったという。
その翌年、つまり万延元年(1860)は、生糸と醤油で合計六十万ドルというから、換算すると二百万両をこえ、さらにその翌年の文久元年(1861)には、日本国内向け取引も含めて、物産総会所から領外に輸出した総額は三百万両に達した。
藩札はたちまち正金に引き換えられたし、また、たまった金貨の重さで倉庫の床が落ちたとも伝えられる。
2.3 小楠の「富国論」
小楠が万延元年(1860)に著わした『国是三論(こくぜさんろん)』の第一番めの「富国論」は、この経験を理論化したものである。
この「国」というのは、日本国のことではなくて、越前国などの国、つまりは藩のことなのだが、小楠は、一藩の政治をうまくやれる力量があってはじめて、日本全体の政治もできるのだという考え方で、これを書いている。
この越前藩の実験は、日本全体に拡大適用できると主張しているのだ。
まず一藩の政治を実際に成功させてみてから、というのが、小楠の強い姿勢だったと思われる。
越前藩に招かれることが決まる前後、つまり安政(あんせい)の大獄(たいごく)前に松平春嶽(まつだいらしゅんがく)や橋本左内(はしもとさない)が中央政界で、幕府政治の改革を目ざして活躍しているころ、小楠は、春嶽や左内の動き方に危惧(きぐ)の念を表明している。
そんなことよりも、越前藩一藩に模範的な政治を行なってみせるのが先決だというのである。
その忠告は間に合わず、春嶽は隠居させられ、左内は刑死した。
しかし、まず一藩に正義をという小楠の方針は、大獄が荒れ狂っているさなかの越前藩で、みごとに実現された。
三岡八郎(みつおかはちろう)という人材を発見・育成したことをも含めて、小楠の学問と手腕のすばらしさは、もう疑いようがあるまい。
これだけの人物を、肥後(ひご)藩では使いもせずに五十歳を過ぎるまで埋もれさせ、越前(えちぜん)藩は、他藩士を招くという異例のことをあえてやって、これだけの実績をあげさせる。
人を使うことのむずかしさであり、また人の運命のわからなさであろうか。
さて、すでに、藩で成功した以上は、小楠の次の目標は、それを日本全体に適用することでなければならない。
そうして、その機会は、『国是三論(こくぜさんろん)』を書いた翌々年の文久(ぶんきゅう)二年(1862)にやってきた。
いや、厳密には、やってきかけた、というべきかもしれない。
2.4 幕府の顧問となる
横井小楠は、毎年のように福井と熊本を往復している。最初の年の安政五年(1858)に弟が死んで熊本へもどったことは、さきにも書いた。翌安政六年には、母の病気で急行するのだが、間に合わず、死に目に会えなかった。
翌万延元年(1860)は帰らなかったけれども、その次の文久元年(1860)には、これは越前藩に招かれてからはじめて、きちんと長期の休暇をもらってもどっている。
その長期の休暇をもらうまえ、小楠は一度、福井から江戸まで往復している。
江戸藩邸の松平春嶽が、「どうしても会いたい」と言ってよこしたのだ。
井伊大老のために自由を奪われていた春嶽だが、万延元年の例の桜田門外の変で井伊が斬られたあとは、幕府の警戒もゆるみ、かなりわがままがきくようになっていた。
江戸へ行った小楠は、春嶽みずから立って座蒲団をすすめるというほど丁重に扱われた。学問の師でしかも藩政の恩人だとして、礼が尽くされたのである。
二十年前に肥後(ひご)藩留守居(るすい)の命で追放された江戸、そこで、自藩の藩主よりも格の高い人物からそのように待遇されて、どういう感慨をもっただろうか。
この文久元年あたりが、小楠個人にとっては、いちばん幸福な時間が流れたように思える。
政治に役だたせる学問を目ざした彼の「実学」に、てごたえがあったのだ。
しかし、この文久元年末には、暗い影もさしている。
江戸から福井を経て熊本へもどった小楠は、休暇を楽しんで銃猟に出た帰り、沼山津(ぬやまづ)の家の近くの藩主の放鷹地(ほうようち)で一般には禁猟区となっているところで、うっかり発砲した。 獲物をねらってではなくて、こめたまま残っている玉を、いつもやるように帰り道に空へ向かって放つただけらしいのだが、小役人にみとがめられて問題になった。
越前では藩主専用猟場で何度も狩猟をしてきた小楠には、心外だったろうが、いかんせんここは自分が生まれた肥後である。
進退伺いを出し、増築中の沼山津の家の工事を中止するという騒ぎとなった。
さすがに肥後藩も、越前藩と契約中の人物をこんなつまらぬ理由では処分しかねたのだが、その結論を出すまでずいぶんてまどり、しかも、違反は違反だとして、一種の前科扱いになった。
越前藩では前藩主がてずから座蒲団をすすめてくれる小楠も、肥後藩では、二十年前の酒失逼塞(ひっそく)七十日に加えてこれで前科二犯である。
それでも、なんとかこの問題がかたづいて、文久(ぷんきゅう)二年六月、小楠(しょうなん)は、また福井へ向かった。
招聘(しょうへい)されてから四度め、そのまえの遊歴を加えれば、五度めの越前行きである。
もう、通いなれた道だ。
ところが、こんどは福井まで到着できない。
おそらくは西近江路を通って、敦賀(つるが)の手前の疋田(ひきた)まで来ると、江戸の春嶽から早馬で、江戸へ直行するようにとの指示が届いた。
ここからだと、琵琶湖側へもどるほうが江戸へ近い。
小楠は、すぐにそうした。どの道を通ったかわからないけれども、距離からいえば、塩津街道を抜けて湖東に出るのがいちばん短いようだ。
しかし、どうしてまた松平春嶽は、そんなにあわてて小楠をよんだのか。
じつにこのとき、春嶽には、幕府の政事総裁職に就任する問題がおこっており、小楠の助言を必要としたのである。
文久二年は、政局が大きく動いた年である。
年頭に、老中安藤信正(あんどうのぶまさ)暗殺未遂事件があって、幕府の権威はまたまた大きく揺らぎ、そこをみて、薩摩藩主の父で藩の実権を握っている島津久光(しまづひさみつ)が、兵を率いてまず京都へ行き、幕政改革を命じる勅書を出させ、これを勅使の大原重徳(おおはらしげとみ)に持たせ、自分は勅使の護衛というかっこうで江戸へ乗り込んできた。
その要求のひとつが、幕府最高幹部の刷新で、具体的には、まえに改革派の将軍候補になったこともある一橋慶喜(よしのぶ)を将軍後見職に、そうして松平春嶽を大老にせよというのである。
「大老」には、老中以下の幕府首脳部も、越前藩の家臣も、ともに反対した。
理由は対照的で、老中たちは春嶽にそんな実権をもたせたくないのだが、越前藩のほうでは、譜代(ふだい)大名がつとめることに決まっている大老に、それより格の高い家門の春嶽をつかせるわけにはいかぬというものだ。
すったもんだのすえ、「政事総裁職」という名前が考え出されて、なんとかおさまったのだが、どの程度の実力と責任を伴うものにするかは、いっこうにはっきりしない。
春嶽の側からいえば、自分の意見がどのくらい貫けるのか、はなはだ心もとない。
こういうわけで、小楠が急ぎに急いで七月六日、江戸の越前藩邸へ着いてみると、春嶽は、総裁職就任を保留したまま、病気と称してひきこもっている。
小楠は、就任をすすめた。これは、春嶽にとっても小楠にとっても、願ってもないチャンスではないか。
「わたくしがお助けしますから、ぜひおやりなさいませ」と、小楠は強く押し切った。
隠居とはいえ春嶽はまだ三十五歳。五十四歳の小楠が万事頼りである。
2.5 参勤交代(さんきんこうたい)制の改革
|
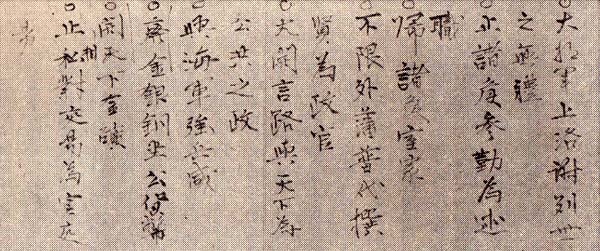
小楠の書付 春嶽のブレインとして活躍時のメモで、参勤交代制の廃止などが記されている。横井家蔵。
|
幕府政事総裁職のブレインとなった小楠が、まずてがけたのは、参勤交代制(さんきんこうたいせい)の廃止である。
これは、徳川幕府の「私」政権的性格を、「公」政権に切り替えようとする野心的な試みだった。
参勤交代の趣旨は、諸大名が徳川将軍に忠誠を誓いに来るところにある。
一年在国して次の一年は在江戸。
妻は人質としてずっと江戸に住まわせねばならない。
江戸での経費が大変なうえに、往復の費用がばかにならない。
すべて、大名が徳川の天下に反抗できないように、また反抗する力を蓄えることもできないようにとの見地から、組み立てられたものである。
政治をよくしようとの観点は、少しもない。
要するに徳川氏の私事なのである。徳川氏の私利私益のための制度にすぎない。
しかし、徳川政権は、二百数十年をこの原理でやってきた。
それをひっくり返そうというのだから、抵抗は大きい。小楠――春嶽の提案もはじめは相手にされず、春嶽はまた病気と称してひきこもりのストライキ、もっぱら小楠が老中(ろうじゅう)や側衆(そばしゅう=老中待遇の将軍補佐役)・大目付(おおめつけ)などのところを根回しに歩いた。
小楠にとって幸いなことに、幕府では、一年あまりまえから、軍制改革の検討を進めていた。
ペリーやプチャーチンがやってきて、旧来の軍制ではヨーロッパの圧力に対抗できないことが明瞭になったので、立て直しをはかろうというのである。
ここでも幕府は、発想の転換を強いられた。
大名たち、特に外様(とざま)大名に、徳川氏に対抗する力をもたせないよう統制していたのでは、その大名たちの外敵に対する防御力も必然的に弱い。
そのジレンマに悩んで改革構想は難航しているのだが、参勤交代がむだな出費であり、それをつづけているかぎり、海防体制を強めよといくら命令しても、あまりききめがないことは、幕府にもわかってきている。
小楠の言うような「公」と「私」の議論を幕府首脳部がどこまで受け入れたのか、はなはだあやしいところもあるのだが、ともかく、参勤交代の事実上の廃止は実現した。
文久二年(1862)閏八月二十二日、幕府は参勤交代の大幅緩和を決めた。
これまでの一年おきの出府を三年に一回と改め、滞府期間を三ヵ月に短縮する。
また、妻子は帰国してかまわないことになった。
三代将軍家光のときにこの制度が確立して以来、最初の、幕府政治の根本原理にかかわる大変革だった。
この改革を推進した小楠の手腕を見込んだ幕府内部に、小楠を旗本にとりたてようとの説が出たことがある。
肥後藩士で越前から出ている政事総裁職の顧問という半端な立場にしておくのは、もったいないというのだ。
正規の幕臣にして腕をふるわせたほうがいい。
小楠も、かなり心が動いたらしい。ことに、幕府側か譲歩して、肥後藩から幕府が借り受ける形にしてもよいとまで言い出したときには、それまでも断わるのはむずかしいと考えて、その意を肥後藩の重役に伝えている。
そこまで進みながら、結局は実現していないところをみると、やはり肥後藩が承知しなかったのだろうか。
出身藩からの拘束は、うんざりするほど強かった。
2.6 外交路線をめぐって
さて、参勤交代(さんきんこうたい)制の改革で、幕府政治転換の第一着手に成功した春嶽と小楠のコンビが、次に直面したのが、京都朝廷からの攘夷(じょうい)要求である。
さきに島津久光が勅使大原重徳を連れて東下したあと、京都は、長州系および土佐系の尊攘(そんじょう)激派に占拠され、こんどは土佐勤王党の武市瑞山(たけちずいざん)が演出して、攘夷督促の勅使を送り出す。
正使が三条実美(さんじょうさねとみ)、副使が姉小路公知(あねがこうじきんとも)。
この勅使が来るとの予告をうけて、幕府は困惑した。
幕府は、そのときの日本政府として、アメリカやイギリスと和親条約を結び通商条約を結んでいるのだ。
攘(う)ち払うことなど、できはしない。
しかし幕府には、朝廷の要求を拒絶できない弱味がある。幕府は、最初の開国のときからずっと、朝廷に対しては、「そのうち攘夷をいたしますから」と約束しつづけてきているのだ。
ことに孝明天皇の妹和宮を将軍家茂の夫人にもらいうけたときには、攘夷が交換条件になっていて、幕府は、それまでにもしていた約束をあらためて強く確認させられた。
だから、朝廷が催促してくると、幕府は弱い。
そのうえいまは、一橋慶喜将軍後見職、松平春嶽政事総裁職と、朝廷が指名した人物がトップにいるのだ。
しかし、だれがトップにいようと、攘夷などできはしない。これまで、できるはずのない空約束をしてきたのがよくなかったのである。
このとき小楠がたてた策が、「破約攘夷(はやくじょうい)論」あるいは「破約必戦論」などとよばれているものである。必要なら、いったんヨーロッパ諸国との条約を破棄しようというのだ。
幕府は、国内向けにはそのうち攘夷するなどとごまかしながら、自分だけの都合でかってに条約を結んだ。
これは幕府の失政である。だから、いまあらためて全国の公論によって、開国するか鎖国にもどすか決めようというのだ。 |

徳川慶喜
最後の将軍として活躍した。
|

松平春嶽
元老井伊直弼の安政の大獄で
越前藩主の地位から失脚したが、
直弼が桜田門外の変に倒れて、
元老に相当する政事総裁職に
復帰した。
|
もし全国の公論が鎖国と決まれば、条約を破棄しなければならない。
一方的に破棄を通告すれば、先方が怒って戦争になるかもしれない。その覚悟でいこうというわけで、「破約必戦」なのである。
このときの小楠は、越前藩での貿易指導やその成果を理論化した『国是三論』でわかるように、積極的開港論者・貿易推進派である。
しかし小楠は、その政策を実施するよりも、幕府の私政を精算して公論による政治に切り替えるほうを重視した。
公論の場で小楠はむろん、開港論を主張するつもりだが、通らなければしかたがない。
公論に従おう。
そのほうが、幕府がかってにやっているよりはずっとよい。
小楠のこの考え方には、幕府の軍艦奉行並になっていた、やはり開国派の勝海舟も賛成だった。
また、攘夷派の中心勢力長州藩の周布政之助や、桂小五郎(のちの木戸孝允)らも同意した。
やってみなければわからないけれども、幕府が独占している全情報を公開してオープンな討議にかければ、頑固な攘夷派も説得されて、全国一致の開国方針がまとまったかもしれない。
小楠にも、その自信があったのだろう。
例によって小楠が根回しに動き、表では春嶽がやはり例によってひきこもりストライキで脅したりしたので、老中たちは、しぶしぶながら、この「破約必戦論」に同意した。
しかし、最後まで反対したのは、なんと将軍後見職の一橋慶喜(よしのぶ)である。
慶喜の反対論は、いちおうもっともらしい理屈になっている。
通商条約は、締結のときのいきさつはどうであれ、政府と政府の間に結ばれた正規の条約である。
こちらから一方的に破棄すれば、こちらの不正義になってしまう。
たとえ戦争に勝っても、不義の名を負いつづけねばなるまい。
ここは、条約を守りとおさねばならない。
それも、事情のわからぬ諸侯を集めて手間のかかる議論をする必要はなく、自分が京都へ行って開港論で天皇や公卿を説き伏せ、攘夷論の拠点をつぶしてしまおうというのである。
小楠はこれにひっかかった。
慶喜がそこまで言い、そこまでやろうとするのなら、そのほうがずっとよいからと、自説をひっこめてしまう。
ところが慶喜は、京都側を説き伏せることをやらなかった。
いよいよ攘夷督促の勅使が江戸城へ乗り込んでくると、攘夷奉承(ほうしょう)つまり「おおせのとおり攘夷いたしましょう」と返事をする方針に切り替えてしまう。
このときの朝廷と幕府の力関係では、「攘夷ができないのなら征夷大将軍の称号をとりあげるぞ」と言い出される危険性があったので、朝廷を怒らせない作戦をとったのだ。
幕府が攘夷奉承と言ってしまったのでは、小楠の「破約必戦論」をもう一度もちだすこともむずかしい。
小楠の構想する全国的公論は、その討論の場で幕府代表が開港政策を主張するのでなければ意味はないのだ。
そうやって、開港政策が承認されれば、もっとも理想的である。
しかし、その幕府が攘夷奉承では、議論にもなんにもならない。
こうして、小楠の案は、文久二年(1862)の時点では、完全にタイミングをはずされてしまった。
はずしたのは慶喜である。慶喜にそこまでの計算があったのではなかろうが、結果的にはそうなった。
そこで小楠は、次のチャンスを、文久三年初頭の京都に求めようとした。
年末から年始にかけて、将軍や後見職をはじめ、幕府の幹部が大挙上京する予定になっており、土佐の山内容堂(豊信=とよのぶ)のような諸藩の実力者も集まる。
尊攘激派はまえからがんばっているし、むろん京都だから、天皇も公卿もいる。
小楠は、一度つぶされている天下公論の場を、この京都に設営しようともくろんだ。
事前に絵を書いておくことはむずかしいが、将軍以下が京都へ乗り込めば、それだけでも京都のふんい気が変わるので、うまくきっかけをつかめば、案外成功するかもしれない。
ただし、そのためには小楠も京都に行っておらねばならない。
これは、政事総裁職のプレインをつとめている小楠にしかできないのだ。
むろん小楠は、春嶽の供をして行くつもりである。
3 失意の日々 top
3.1 士道忘却事件
ところが小楠は、京都に行けなくなった。江戸にもおれない。身の置きどころがなくなったのである。
文久二年(1862)の暮れもおしつまった十二月十九日、小楠は、肥後藩江戸詰の吉田平之助の妾宅(しょうたく)を訪ね、用談のあとで酒になった。
同じく肥後藩士の都築(つづき)四郎も席に連なっていた。
夜がふけて、なおにぎやかにやっている二階の座敷へ突然、刺客(しかく)が斬(き)りこむ。覆面の男ふたりである。
小楠は逃げた。
刀ははずして床の間に置いてあり、小楠は床からいちばん遠く、梯子段に近いところにいたので、立ち上がると、さきに飛び込んできたひとりをやりすごして階段をかけおり、段の途中で、あとのひとりとうまくすれちがって表へ飛び出す。
そうして、十町(約一・一キロ)ばかり離れた越前藩邸へ駆けつけ、窓の外から呼んで差し替えの刀を取り、門人や越前藩士十人ほどを引き連れて現場にもどってみると、もう刺客の姿はなく、吉田と都築が倒れているだけだった。
ふたりとも、床の間の刀を取れないまま格闘、重傷を負ったのである。
小楠の行動に対して、肥後藩士の間から猛烈な非難があがった。
武士にあるまじき卑怯(ひきよう)なふるまいだという。
小楠は逃げたのではなくて刀を取りに走ったのだとの弁護も成立するし、また、ああいう状況なら逃げてもかまわぬとも思える。
逃げるべきだ、とさえ言える。
しかし、そういう考え方を、肥後藩ではまったくしなかった。
士道忘却一点ばりである。
犯人を搜すことなどそっちのけで、小楠の処分ばかり問題にしている。
肥後藩邸ではすぐに、小楠を越前藩邸から引き取って国許へ送還することに決めた。
途中で斬ってしまえという声もある。
越前藩では非常に心配した。肥後藩から申し入れどおりに小楠を返したら、生命の保障もないのだ。
事実、だいじょうぶだろうかとの打診に、受け合いかねると返事してくる。
越前藩では、返すのを断わった。しかし、これだけ大問題になっては、江戸へ置いてはおけない。
京都へ行かせるのも無理である。こっそり福井へ送って、ほとぼりのさめるのを待つことにした。
小楠は、極秘裡に江戸を出発、無事に福井へ着きはしたが、政策転換のきっかけを文久三年初めの京都でつかもうという計画は、これで完全につぶれた。
3.2 小楠不在の政局
実際、小楠の行かない京都は、ひどいことになった。
将軍後見職の一橋慶喜は、天皇に面会して、攘夷の政策と引き替えに、政務をこれまでどおり幕府に任せるとの委任状を手に入れる。
開港論で朝廷を説き伏せると言い切った、昨年の慶喜と別人のようである。
春嶽は怒った。小楠がそばにいないためキメのこまかい作戦のたたない春嶽は、開港論が通らなければ幕府は政権を返上しようという単純明解な説を唱えて孤立し、十四代将軍家茂に将軍職を辞任するようすすめたが相手にされず、そこへ慶喜のこの行動で、頭にきてしまった。
政事総裁職の辞表を出し、承認も得ないままかってに退京、福井へ帰ってしまう。
このあと、将軍家茂(いえもち)は、完全に朝廷の捕虜である。
攘夷を何月何日からはじめますと、はっきり答えるまで、江戸へ帰らせてもらえない。
一度などは、帰ると公表して、行列の一部を先発させたのに、天皇によびつけられて足どめをくった。
結局、四月二十日になって、五月十日から攘夷いたしますと、期限を切らされてしまう。
京都は、攘夷一色となった。
ことに長州藩は喜び、五月十日になると、自領の関門海峡下関側からほんとうに外国船を砲撃しはじめる。
3.3 挙藩上京実現せず
このころ、京都では、越前藩について、妙な噂がたった。
さきに攘夷の方針が気に入らないで退京した松平春嶽が、越前一藩の全兵力を率いて京都へなぐりこみをかけてくるというのである。
武力で威圧して国論を開国・開港に変えようとしているのだという。
この噂で、京の尊攘派は、越前藩を非常に憎んだ。
七月二十六日には、越前藩が上京したときに旅館とする東山の高台寺に火をつけるなど、妨害やいやがらせをしている。
確かに越前藩には、挙藩上京の計画があった。
しかしそれは、京での噂のような、尊攘派を武力でおさえるためのものではない。
攘夷といってやみくもに外国船を撃っていたのでは、日本は滅びてしまうから、在日中の諸外国外交官を京都へよび、朝廷は関白以下、幕府は将軍以下の要人が出席して談判を開こうというのだ。
そこで日本側の現在の方針を説明し、先方の意見もきき、そのうえで、開国か鎖国か、和か戦かを決めればいい。
そのことを将軍と朝廷とに進言したい。ところが、越前藩は開国一本槍だと思われてしまっているために、これは決死の覚悟でやらねばならない。
小人数で行ったのでは、尊攘派に全滅させられてしまう。
だから、精兵四千人を出動させようというのだ。
この計画を立案したのは、江戸の事件以来、福井にひっこんでいる小楠だった。
越前藩の力だけでは不足だからと、近くでは加賀藩前田家・小浜藩酒井家など、遠くは薩摩藩にまで使者を送って協力を求めた。
小楠のつもりでは、この機会に、幕府政治をさらに根本的に改革したい。
将軍にはこれまでかってな政治をやっていた幕府高官の首を切る力があるまいから、官吏の任免を朝廷が行ない、全国の諸侯やその藩士から有能なものを採用すれば、「日本国中の共和一致」の政治ができるだろうというのだ。
このプランは、越前藩内でもすんなりとまとまったわけではない。
一藩の存在を賭ける危険な案だから、当然反対派があり、その説得にてまがかかる。
それに、京都へ押し出すタイミングがむずかしい。京都側が上述したような予断と偏見をもっているので、よほど気をつけないと、逆効果が大きい。
そこで、京都へ情報入手掛を出して、刻々の状況を報告させているのだが、その情報掛がこのプランに消極的だったりすると、うまく機をつかめない。
小楠も、「いまこそ」という判断をつけかねている。
そうこうしているうちに、将軍家茂が江戸へ帰ったとの知らせがはいる。
小楠の策は、将軍が京都にいることを前提にしているので、いっぺんに情勢が不利になる。
藩論は、紛糾のあげく、計画中止と決まり、つづいて、小楠の構想に積極的に賛成した家臣たちが処罰された。
3.4 肥後へ帰る
ここにいたって、小楠は、熊本へ帰ろうと決意する。自分の意見が通らなくなった越前藩にいつまでもおれない。
だいたい、いま自分が福井にいるのは、前年暮れの江戸の事件のほとぼりをさますためで、いずれは肥後藩の命令どおりに帰藩して処分をうけねばならないのだ。
帰路は船と決めた。福井の北にある三国(みくに)港を、八月十二日に出帆している。
このときには、小楠反対派の越前藩士に襲われる危険があったので、城下をこっそり抜けだしたようだ。
船は西へ回って、十九日に長崎へ着く。
小楠が海上にいた八月十八日に京都ではクーデター(八月十八日の政変=禁門の変)がおこり、会津と薩摩の兵力によって長州系尊攘派が追い出されるのだが、それは、越前とも、また、これから帰る肥後とも、関係ない。
熊本へ帰れば、処罰が待っている。 |

沼山津の田園風景
小楠は失意の日々をこの木山川での釣りなどで慰めた。熊本市
|
徳富蘇峰(とくとみそほう)の依頼で横井小楠(よこいしょうなん)の伝記と史料集をまとめた山崎正董(やまざきまさただ)は、小楠を出迎えた門弟たちの間に、先生に腹を切らせる計画があった、ということを伝えている。
小楠の罪は重ければ死刑、軽くても士籍剥奪(はくだつ)をまぬがれない。
先生がそんな目にあえば、先生の家に傷がつくだけでなく、門弟の自分たちも、世間に顔むけができない。
それよりも、出迎えたとき、熊本城下にはいるまえに適当な場所へ導いて、その場で切腹するようすすめようというのだ。
弟子たちは、さすがの小楠も、こんどは悄然(しょうぜん)と帰ってくるだろうと思ったのに、郊外の山伏塚(やまびしづか)に出迎えると、意外に元気で、あいさつもそこそこに、小躍りして先頭に立って歩きはじめる。
弟子たちが機先を制せられて、「お前言え、いやお前言え」と譲り合っている間に、小楠はさっさと城下にはいってしまった。弟子たちは、腹を切らせそこなった。
この話は、門人のひとり嘉悦氏房(かえつうじふさ)がある人に語り、山崎は、そのある人から聞いたのだという。
間接的な証言だけれども、いかにもありそうな光景にちがいない。
3.5 士籍を失う
十月になって、小楠の罪は決定した。
松平春嶽と越前藩当主の茂昭(もちあき)をはじめ、各方面から肥後藩にあてて厳罰にしないようにとの働きかけもあって、予想されたなかではもっとも軽いところに落ち着いたが、それでも、士籍および知行の没収である。
小楠は、武士身分も、武士としての収入も、失ってしまった。
一平民として、沼山津(ぬやまづ)に閑居するしかない。
これから、明治新政府に登用されて上京するまでの五年間、小楠は、苦しかった。
国内情勢は、禁門の変から二度にわたる長州征伐、そして第二回征長戦の幕府軍敗北、大政奉還、王政復古クーデターと、大きく揺れ動くのだが、それはみな、小楠抜きで進む。
彼には、なにもできないのである。
酒を飲んで憂さばらしをするほかはないのだが、収入がとだえて、それも自由にならない。
この時期の小楠の面倒をいちばんよくみたのは、沼山津の、四時軒から木山川沿いに少しさかのばったところに居を構えた「西の弥冨(やどみ)家」の弥冨千左衛門(せんざえもん)である。
この近辺で指折りの豪農だ。
小楠はどうも、毎晩のように、この弥冨(やどみ)家へ飲みに行ったらしい。
川伝いに行って、川を背にした庭にはいり、此接、座敷の雨戸をたたく。
夜、座敷の外で音がすると「それ先生だ」ということになったようだ。門や玄関と反対側の小楠専用通路である。
座敷へ上がると酒になる。ときには夜を徹して飲み、明け方に帰ることもあった。
酒を飲みに行っただけではない。借金もずいぶんした。担保には刀をいれている。
どうして刀なのか。小楠は、奇妙なことに、刀に趣味があった。 |

弥冨家の屋敷
豪農弥冨于左衛門は不遇時代の小楠を保護した。熊本市沼山津
|
第一が酒、第二が刀である。越前に招かれて、ふところがあたたかだった時期には、古刀をずいぶん集めた。
その刀が、弥冨家に残っている。弥冨千左衛門としては特に担保をほしいと思ったわけではないが、小楠のほうで気がすまなかったらしい。
3.6 小楠とその家族
そういう借金をしても養わねばならなかった小楠の家族のことを、少し書いておこう。
父母はもういない。しかし、母はもうひとりいた。兄が死んでそのあとを継いだので、亡兄が義父、したがって、兄嫁は自動的に義母となる。
兄の子どもが三人いて、本来なら甥と姪だが、これも自動的に義弟・義妹、しかもそのうちのひとり、兄の長男の左平太には、自分のあとを継がせることにしていたので、同時に養子でもあるややこしさだ。
このうち、姪のいつ子は、万延元年(1860)に嫁に行った。
小楠自身の結婚は遅い。次男だからやむをえないのだが、嘉永六年(1853)四十五歳のときである。その最初の妻は、男の子を生んだけれども育たないで死に、つづいて妻も死んでしまった。
そこで安政三年(1856)、小楠は、もっとも古い門人のひとりである矢島源助(やじまげんすけ)の妹の“つせ”をめとった。ただしこのときは、小楠は兄のあとを継いで百五十石の武士、矢島は豪農とはいえ農民身分だから、正規の手続きは省略したままである。この“つせ”に、男の子が生まれ、次いで女の子ができる。
文久三年(1863)、士籍を剥奪(はくだつ)されたときには、男児は七歳、女児は二歳。これに女中の寿加を加えて、合計七人、これを食わせねばならない。
ことに心を痛めたのは、甥で養子とした左平太(さへいた)や、その弟の太平(たへい)のことである。
|

横井小楠夫人“つせ”
|
小楠は、兄から受け継いで甥(おい)に渡すべき家を、つぶしてしまったのだ。
小楠は、その償いの意味もこめて、この甥たちに、できるだけの教育をつけようとする。苦しいなかを勝海舟(かつかいしゅう)の神戸の海軍操練所(かいぐんそうれんじょ)に入れ、さらには、無理に無理を重ねながらつてを求めて、甥をアメリカへ留学させるのである。慶応二年(1866)のことだ。 |
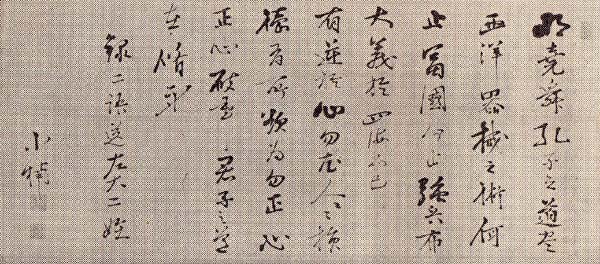
小楠が甥に与えた送辞 アメリカに留学する甥に「西洋器械の術」の習得を説いている。横井家蔵。
|
4 実らざる理想 top
4.1 小楠の大理想
ところで、甥(おい)たちを送り出すときの、小楠のことばがある。
堯舜(ぎょうしゅん)孔子(こうし)の道を明らかにし
西洋器械の術を尽さば
何ぞ富国に止まらん
何ぞ強兵に止まらん
大義を四海に布(し)かんのみ |
これは、よく佐久間象山の有名な「東洋の道徳、西洋の芸」に対比される。
小楠(しょうなん)が「堯舜孔子の道」と言い、象山(しょうざん)が「東洋の道徳」と言っているのは、ともに、儒学のことだ。
いっぽうに儒学、いっぼうに西洋の技術、その両方をマスターしなければならない。
そこからさきは、象山と小楠では少し違うのだが、象山はさておき、小楠のほうをつづければ、富国とか強兵というような一国レベルの問題にとどまらず、大義を四海に布(し)くという、全世界レベルのテーマに到達するとなっている。
どうしてそうなるのか。そこには、小楠独特のヨーロッパ文明批判があるのだ。
まえにも書いたように、小楠は儒学者である。
終生、儒学者であって、儒学的理想に基づいて政治をやろうとした。洋学をやったことはない。
しかし、洋学あるいは洋学に基づく西洋の政治には、非常な関心をもっていた。
耳学問や翻訳書で、できるだけ情報を集め、評価をくだしている。
その評価は、現状ではヨーロッパ諸国の政治のほうが、日本や清朝中国の政治よりも優れているというものだった。
判断の基準は、民衆が幸福かどうかである。ヨーロッパ諸国のほうが経済活動が盛んで、社会福祉も行き届いており、民が豊かのようだから、文句なしに向こうが優れている。
儒教の理想どおりの政治をやっていない日本や中国よりも、ヨーロッパ諸国のほうが、むしろ儒教の理想に近い。
ことに小楠が感心したのは、アメリカの初代大統領ワシントンである。
政治がりっぱだっただけでなく、その子孫がなんの権利ももっていないところがすばらしい。
日本の徳川氏やまた諸藩藩主のように、代々子孫がうまく権力をもちつづけるようにという観点から政治をやっているのとは、大違いである。
ワシントンこそ、儒教で模範とする中国大古の聖王、堯(ぎょう)や舜(しゅん)のような人ではなかろうかと、小楠は考える。 堯や舜のようだとは、儒学者の呈しうる最大級の賛辞である。
それに対して、日本の徳川氏のこれまでやってきたことは、あれは政治ではないのだとまで、小楠は言い切る。
ヨーロッパやアメリカの政治を、それほどにも評価する小楠だが、しかし彼は、百点満点を与えているのではない。
悪いところがあると指摘する。
いちばんけしからんのは、相互に戦争をすること、それに他地域、ことにアジアを侵略し植民地にしていることである。
ヨーロッパの国民が豊かなことと、アジアを侵略し植民地にしていたことには内的連関があるのだが、小楠もそこまで踏み込んではいない。
しかし、アジア侵略やヨーロッパ相互の戦争はよくないことであり、小楠に言わせれば、それは彼らが儒学の本当の精神を知らないからである。
国内の民衆を幸福にしている点では、儒学の教えに非常に近いのだが、根本のところで儒学の精神がわかっていないから、侵略や戦争を根絶できない。
だから日本は、開国して国際社会に列していくに際して、儒学の教えの本質をきわめ、欧米諸国の戦争侵略をやめさせねばならない。
それが、彼のいう「堯舜(ぎょうしゅん)孔子(こうし)の道を明らかにし」である。
儒教思想がそんなに“たいそう”なものか、いまの読者は不審に思うだろう。
しかし、そのときのヨーロッパ近代やその思想が、戦争と侵略を随伴していたことは、まぎれもない事実である。
ペリーにしても、浦賀(うらが)にやってきたときには、ずいぶん無礼な態度で、小楠は、そういう無道な国と交際する必要はないと論じたものだ。
そういう、戦争や侵略を随伴しているヨーロッパ近代やその思想と対抗するには、どうすればいいのか。
相手が強いからというので、ただ相手のまねをしたのでは、同じ侵略国家になってしまうだけのことだ。
それを拒否し否定し去る原理を、他に求めねばなるまい。
もしアジア側にあれば、申し分ない。
儒学がそれだというのが小楠の立場である。
ただし、この儒学のすばらしさは、忘れ去られて久しい。
それは、日本や清朝中国の無惨さに、よく現われている。
しかし小楠は、不遇時代の勉強で、忘れ去られていた儒学のすばらしさを再発見した。
それが彼の「実学」である。
彼はそれを招かれた越前藩で使ってみて成功した。
次いで幕府の顧問としてやりかけて、まったくつまらぬことで失脚して果たさなかったけれども、彼は、自分が再発見した儒学に自信をもっている。
西洋諸国も、そのすばらしさが半分くらいはわかっており、それが「西洋器械の術」として結実している。
あれはもともと儒学思想中にあったものが、中国で忘れられ、ヨーロッパで発展したのだ。
それは、そのまま学びとればいい。
そのうえで、西洋でも理解されず発展もしなかった儒学思想の精髄――それを小楠は「仁(じん)」の一字でとらえているのだが――を明らかにすれば、日本は、日本一国の富国や強兵にとどまらず、西洋の侵略や戦争を批判して大義を世界に布(し)くことができるのだ。
そう確信している小楠は、しかし、肥後藩の罪人として、士籍を剥奪(はくだつ)されたまま、沼山津(ぬやまづ)を動けない。
動けないままに思想がますます純熟してきていることは、後輩の井上毅(いのうえこわし=のち帝国憲法起草者)が訪れて話を書きとめた『沼山対話』や、また、やはり後輩の元田永孚(もとだながざね=のちの明治天皇の侍講)が筆録した『沼山閑話』などでうかがえるのだが、せっかくのその思想は、だれも使ってくれない。
わずかに松平春嶽や勝海舟が、おりにふれて意見を求めてくる程度だが、その春嶽や海舟にしてからが、政治全体の動きのなかでは傍流に押しやられていて、影響は小さい。
4.2 思想と現実
政治の表舞台で正面衝突していたのは、幕府側も、反幕府側も、小楠の思想とは比較的縁の遠い勢力である。
幕府側では、徳川宗家を継いで十五代将軍となったもとの一橋慶喜と、それに連なる幕権派、つまり批判的な諸藩を押しつぶして幕府中心の統一国家をつくろうと構想するグループ。
慶喜の立場が小楠や春嶽と違うことはまえにも少しふれた。
慶喜の幕府に正面から刃向かっているのは長州である。
この長州に対して、小楠はかねてから危惧(きぐ)をもっている。
長州の攘夷論には、排外主義の色が強く、たとえば小楠が、ヨーロッパの外交官も同じテーブルにつかせて会議しようともくろんでいたときに、長州は、条約を結んでいる相手国の船をいきなり撃ちはじめた。
これは正義でない。
その長州は、単純な攘夷主義を捨てたあとは、裏返しの侵略主義的膨張主義に転じたとの印象を小楠に与える。
ヨーロッパの悪いところばかりまねようとしており、しかもそれを、日本の神道の独善主義で補強して、神聖の道を世界に推し広めようとか、地球上を横行しようとか主張している。
小楠は、神道に反対で、非常に狭くかってな理論だと思っており、また、長州流の地球横行とは単に勢力を張るだけのことで、必ず後日の災害を招くにちがいないと断定する。
小楠からみれば、幕府も長州も、ともに危険千万なのだ。幕府はもうすぐ倒れるからいいけれども、長州は勝ち残るから厄介だ。そうして、長い目でみれば、小楠の長州に対する危惧(きぐ)は、あたったといわねばなるまい。
しかしともかく、現実の事態は、長州が幕府を倒す方向に進んだ。
ただし、単独では倒せない。まず薩摩藩が協力し、越前藩や尾張藩など、中立的諸藩を強引にひきつけて、慶応三年(1867)の暮れ、京都で新政府が成立する。
大政奉還コースに対する王政復古クーデターコースの勝利である。
この経過に、小楠はなにも関係していない。
しかし、おそらく新政府に加わった越前藩の推薦によってであろうが、小楠に上京するよう呼び出しがかかり、小楠も行こうと思った。
ともかく、新しい政治の場ができており、自分の抱負を実現する条件がわずかでもあるかもしれない。
ただし、こんども肥後(ひご)藩が反対した。
自分のところで処罰して、士籍まで削ってしまった人間を、頭ごしに新政府に登用されたのでは、藩の面目は丸つぶれである。しかし、新政府も譲らなかった。とうとう藩が折れ、士籍をもとにもどし、上京を承認した。
|
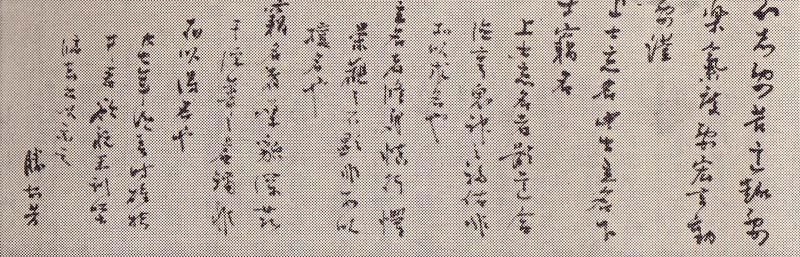
勝海舟か小楠の甥に与えた送辞 海舟塾を巣立ってアメリカへ留学するときに書き送ったもの。横井家蔵。
|
明治元年(1868)四月に船で大阪に着くとすぐに参与(さんよ)に任命され、次いで京都にはいると制度局判事。
閏(うるう)四月二十一日の官制改革で諸藩からの徴士(ちょうし=藩から朝廷に召された官吏)が大量に整理されたときにも、小楠は参与で残っているから、非常に期待されていたことはわかる。
というよりも、この年は、鳥羽伏見の戦いにはじまった内戦がまだつづいているために、小楠のもっている大理想と、現実の新政府との矛盾が、まだ表面化しなかったのだろう。
越前藩など中立系諸藩の発言力が大きい間は、小楠の地位は重く、長州や薩摩も小楠を粗末には扱えない。
いや薩摩には「小楠の思想を、西郷の手で行なわれたら」という冒頭で紹介した海舟のことばでも知られるように、小楠の考え方との親近度が認められた。
西郷が下野するまでの新政府には、いろんな可能性が混ざりあっていたりだ。
だが、小楠(しょうなん)は、結局なにもできなかった。
ひとつには病気のせいもある。上京前から「痳疾(りんしつ)」に悩まされていたのだが、京都へ来るといっそうひどく、高熱を発し、出血もあり、一時は危篤状態に陥っている。
医学者でもある山崎正董(やまざきまさただ)は、「痳疾」とは腎臓(じんぞう)と膀胱(ぼうこう)の結核ではなかったかと推測する。それが回復しないまま、明治二年正月五日、小楠は斬(き)られた。
不自由な身体のまま、京都御所内の太政官(だじょうかん)から駕籠(かご)でもどってくるところを、寺町丸太町下ルで襲われたのである。
駕籠を出て小刀で防戦したが、及ばなかった。六十一歳。
新政府のいわゆる「開明政策」が小楠のせいだと思った攘夷(じょうい)派生き残りのしわざである。
最後まで「覚(さと)られがたい」人であったのだ。 |

小楠殉難の地 明治2年1月5日、小楠は京都御所
を駕籠で出たところを、暗殺された。京都市上京区。
|
参考図書 top
山崎正董『横井小楠伝』日新書院(昭和十七年)
坂田大『横井小楠の思想』九州時報社(昭和二十七年)
坂田大『小楠と天道革命論』坂田情報社(昭和三十八年)
佐々木憲徳『横井小楠評伝』文化新報社(昭和四十一年)
圭室諦成『横井小楠』吉川弘文館(昭和四十二年)
松浦玲編『日本の名著』「佐久間象山・横井小楠」中央公論社(昭和四十五年)
横井小楠略年譜 top
文化六年(1809)
天保四年(1833)
天保八年(1837)
天保十年(1839)
天保十一年(1840)
天保十四年(1843)
嘉永四年(1851)
嘉永五年(1852)
嘉永六年(1853)
嘉永七年(1854)
安政二年(1855)
安政三年(1856)
安政五年(1858)
安政六年(1859)
万延元年(1860)
文久二年(1862)
文久三年(1863)
慶応三年(1867)
明治元年(1868)
明治二年(1869) |
一歳
二十五歳
二十九歳
三十一歳
三十二歳
三十五歳
四十三歳
四十四歳
四十五歳
四十六歳
四十七歳
四十八歳
五十歳
五十一歳
五十二歳
五十四歳
五十五歳
五十九歳
六十歳
六十一歳 |
肥後(ひご=熊本)藩士横井太平(よこいたへい)の次男として誕生。幼名は又雄(またお)。通称平四郎。小楠(しょうなん)は号。
藩校時習館(じしゅうかん)の居寮生に選ばれ、菁莪斎(さいがさい)に寄宿する。
時習館の居寮長となる。
藩費で江戸に遊学し、藤田東湖(ふじたとうこ)らと交わる。
二月、酒後の過失により帰国を命じられる。帰国後、実学(じつがく)党(改革派)を形成。
実学党の綱領として「時務策」を草し、藩政改革に乗り出す。
二月、諸国遊歴の旅に出る。二十四藩を巡歴し、八月、帰国。
『学校問答書(もんどうしょ)』を著わして、学政一致・経世済民(けいせいさいみん)の理想を述べ、実学を提唱する。
肥後藩士小川吉十郎の娘ひさと結婚。
兄時明(ときあき)の病死により、横井家の家督を継ぐ。
実学党の上士層と分裂し、下士・豪農層の立場に拠る。積極的な開国論を唱えはじめる。
妻ひさの死により、郷士矢島忠左衛門の娘つせと再婚。
越前(えちぜん=福井)藩主松平春嶽(しゅんがく)に迎えられて、藩校明道館(めいどうかん)で講義する。
再度福井に赴き、越前藩政を指導。
三度福井に赴き、藩政指導の成果を総括して『国是三論(こくぜさんろん)』を著わす。
幕政改革で政事総裁職に就任した春嶽の懇請により出府。幕政改革につとめる。十二月、士道忘却事件おこる。
越前藩の政変のため帰国し、前年末の事件により知行・士籍を剥奪(はくだつ)される。
肥後沼山津(ぬやまづ)の蟄居地(ちっきょち)より、越前藩に「国是十二条」を呈する。
京都の新政権の要望により上洛。徴士(ちょうし)・参与として新政府に出仕する。
正月、御所からの帰途、京都寺町(てらまち)の路上で刺客に襲われて横死。 |
top
****************************************
|