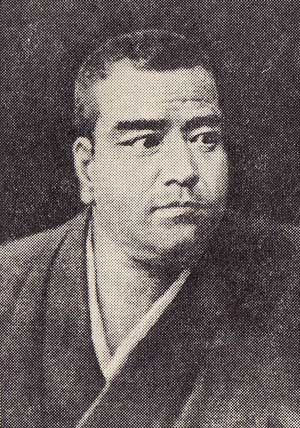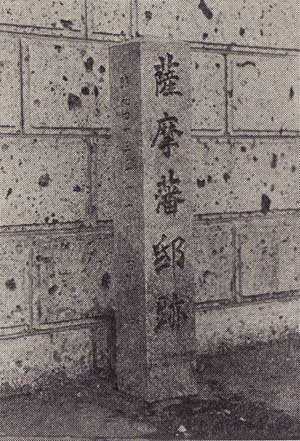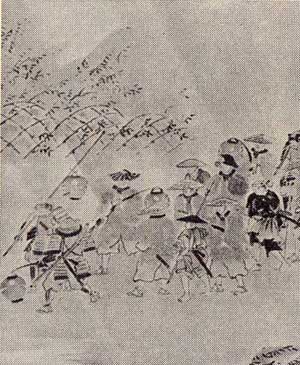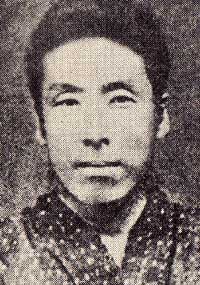|
****************************************
Index 岩倉具視 大村益次郎 西郷隆盛 木戸孝允 大久保利通 福沢諭吉
西郷隆盛 戸川幸夫著
1 世に出るまで
1.1 下級武士の伜
1.2 斉彬に従って江戸へ
1.3 国事に奔走
1.4 大島へ流される
1.5 二度めの流罪
1.6 久光の公武合体論
1.7 西郷の出番くる
2 維新劇の晴れ舞台――江戸開城
2.1 禁門の変
2.2 海舟とはじめて会う |
2.3 西郷、開眼する
2.4 長州再征と薩摩の態度
2.5 英仏の策動
2.6 隆盛の戦争挑発策
2.7 いよいよ武力討幕
2.8 海舟の述懐
2.9 西郷の一言
3 征韓論と西郷の敗北
3.1 新政府と西郷
3.2 征韓、是か非か
3.3 西南戦争 |
戸川幸夫(とがわゆきお)作家。
一九二一年(明治四十五)佐賀県に生まれる。山形高校卒業。
『高安犬物語』で第三十二回直木賞を受賞。
著書『乃木と東郷』
『戸川幸夫動物文学全集』他。
西郷隆盛略年表 |
1 世に出るまで top
1.1 下級武士の伜(せがれ)
西郷隆盛は文政十年(1827)の十二月七日、鹿児島城下の加治屋(かじや)町で平士小姓組頭(こしょうくみがしら)吉兵衛の長男として生まれた。
西郷家は家格が低いので知行は少なく、そのうえ隆盛の下に三男三女があったので、家計はひどく苦しかったらしい。
しかし、父の吉兵衛は清貧に安んずる剛直精励の典型的な薩摩藩士であり、妻の満佐子も夫と歩調を合わせる女性だったので、家は貧しいが、夫婦とも子どもたちの教育には熱心だった。
この時代の鹿児島藩士の家庭は、ひとり西郷家だけでなく、一般的に子弟の教育にはひどく力をいれていた。
ことにこの加治屋町というところは、七十軒あまりの下級武士ばかりが集まった屋敷町であったが、気位が高く、子どもたちに負けじ魂を叩き込んだとみえて、この町内からは西郷のほかに、大久保利通・大山巌(いわお)・村田新八(むらたしんぱち)・東郷平八郎(とうごうへいはちろう)・黒木為槙(くろきためもと)といった大人物が輩出している。
こんな町はほかにはみられない。
隆盛は幼名を小吉(こきち)といい、十六、七歳ごろから吉之介(きちのすけ)と称した。
父の死後は代々の慣習に従って吉兵衛(きちべい)を名のったが、のちに吉之助と改め、名を隆盛と名のり、号を南洲(なんしゅう)とつけた。
また一時、遠島に処せられていたときなどはいろいろの変名を用いているが、本編ではわずらわし方を避けるために隆盛の名で通すことにする。
隆盛の次の弟は吉次郎といって、隆盛が国事に奔走するようになってからは、兄をたすけて家事のことから弟妹の養育いっさいをひきうけ、後顧の憂いのないようにした。 |
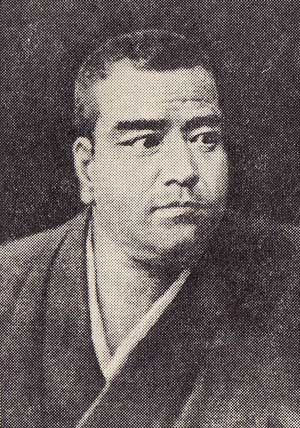
西郷隆盛像
|
隆盛の陰の人として、隆盛もこの弟にはひどく感謝していたが、惜しいことに戊辰(ぼしん)戦争のとき越後口で戦死している。
その下の弟信吾がのちの侯爵・海軍大将・陸軍中将の従道(つぐみち)である。
末弟の小兵衛(こべえ)は西南戦争で戦死、妹たちはそれぞれ同藩の士に嫁いでいる。
長男の隆盛は早くから親をたすけ貧乏世帯をきりもりし、弟妹たちを養育してゆくために、借金をして知行地(ちぎょうち)を買い入れたり、いろいろと苦労して過ごした。そうしたことが、彼に親分的性質を培(つちか)い、経済観念を発達させたといえる。
そしていつまでも人の下にはおらぬぞ、との負けじ魂をいっそう成長させたとみていいだろう。
ところで明治維新に活躍した藩は(明治維新には限らないが、特に明治維新では)藩士の子弟教育に熱心だった藩であったことは注目すべき点であろう。
倒幕派でも佐幕派でも、そういった藩はめざましい活躍をしている。
薩摩の島津、長州の毛利、佐賀の鍋島、土佐の山内、それに会津の松平など皆しかりで、青少年の学校教育・家庭教育がいかにその国の人材をつくりあげてゆくかを如実に示している。
薩摩藩では藩士の子弟たちを訓育するのに有名な郷中教育というのを施した。
簡単に述べると、まず青少年を稚児(ちご)と二才(にせ)とに分け(稚児(ちご)は六、七歳から十二、三歳までで、十四、五歳から二十三、四歳までを二才(にせ)といった)、各郷中で厳しい青少年教育をした。
それぞれ稚児頭・二才頭というのがいて教育のことを処理する。教育の目標は忠孝仁義・質実剛健の精神を養うことで、文武の練磨、長幼の礼を守ることなどを厳格に教え、不良や怠惰なものは仲間うちで制裁を加えるという徹底したものだった。
稚児(ちご)は毎日午前と午後に武道の稽古をさせられ、また相撲や合戦遊びなどをさせられ、夜は日を決めて二才などの指導で、『大学』『論語』などを学ばせられる。
二才(にせ)となると午前中は藩校造士館(ぞうしかん)に通って学問を学び、午後は武道の稽古をしたり、後輩の指導にあたる。勇壮なる戦記を読んだり、肝だめしをしたりという教育だった。
隆盛もこういった教育のなかで育った。
特に薩摩藩が力を注いだのは薩摩藩に対する忠君愛国主義であった。
心理学者の説によると、人の後天的な性格形成は四、五歳ぐらいまでの幼児期間にうける周囲からの影響によることがもっとも強く、それにつづく少年期から青年期にかけての教育が大部分を決定するという。
西郷隆盛を手きびしく批判するものは、「西郷は薩摩あって日本あるを知らず、したがって維新の功臣は明治の賊臣となり果てた」と言っているが、それは酷であるとしても、隆盛ほど郷土愛に強く、郷土臭を身につけていた日本の偉人はいないようだ。
そのために、彼はとどのつまり身を滅ぼすような結果を招来したが、それは薩摩藩の下級武士の伜(せがれ)として生まれ、藩の徹底的な教育をうけ、成長期に家庭や周囲から「偉くなれ、君国(この場合は薩摩をさす)に役立つものになれ」と教えこまれたことからきていると思う。
1.2 斉彬(なりあきら)に従って江戸へ
隆盛は十八歳のときに郡方(こおりかた)書役助(かきやくじょ)となり、のち書役に転じ、二十七歳までつとめた。
これは農政関係の事務を扱う役目だった。
薩摩藩の政治は農民を奴隷視し、農民には冷酷だったといわれているが、隆盛は自家の生活が苦しくて芋を主食としていた境遇が、農民の生活と共通するところがあったのと、役目がら、農民に親しんだので同情的で理解があった。
こういったところが、鹿児島の農民階級から彼が支持された点であった。
だが、藩とても無理無体に農民をいためつけていたわけではなく、文政から天保にかけて薩摩藩の財政は極度に悪化していたからであった。
文政十年(1827)に側用人(そばようにん)調所広郷(ずしょひろさと)が起用されて財政改革を行なうようになってからややもちなおし、さらに調所(ずしょ)は琉球の中国貿易を利用し、幕府からゆるされている制限以上の密貿易をやったり、奄美大島・徳之島・喜界ヶ島の砂糖で莫大な利益をあげた。
調所は嘉永元年(1848)の暮れに、密貿易のことが露見しそうになったので責を負って自殺したが、調所の財政改革によって薩摩藩は近代的軍備をととのえることができた。
さらにその軍備を土台として藩兵を近代的軍隊に育てあげたのが島津斉彬らであった。
斉彬(なりあきら)はオランダ語を学び、洋学をおさめ、世界的視野をもって藩を近代化した名君である。
彼は物理・化学は経済の基礎となるものであるとし、鎖国を捨て、広く外国と交わり、産業をおこし、軍備を充実させなければならぬと家臣たちに説いた。
洋式築城書によって沿岸各地に砲台を設けたり、火器の改良に心を砕いた。
のちのことだが斉彬の後継者忠義(ただよし)も、文久三年(1863)の薩英戦争で敗れてからは、鋳砲を行なわしめたり、新式砲を購入したり、洋式の軍事教育を導入、また天文・地理・数学・測量・航海・器械・造船・物理・分析・医学などの学問を藩士たちに学ばせた。
慶応元年(1865)には十九名の藩士を英国に留学させたりもしている。
この留学生のなかには寺島宗則(むねのり)・五代友厚(ごだいともあつ)・森有礼(もりありのり)などもまじっていた。
嘉永六年(1853)ペルリが来日すると、外威に対する準備のできていなかった幕藩体制はゆらいだ。
そのため、かねがね中央進出をねらっていた薩摩藩にチャンスは早くも訪れた。
それは下積みの藩士であった隆盛を浮き上がらせるチャンスでもあった。
安政元年(1854)三月、斉彬は薩摩藩主に就任してはじめての出府をした。
このとき隆盛は中小姓として随行することになった。
なぜ彼が登用されたかというと、しばしば藩庁に意見書などを提出していたのを、下級藩士のなかから有為な士を拾いだそうと目を配っていた斉彬が見つけたのである。
隆盛はこの出府の前年、両親を失っている。両親在世中に彼は同藩の伊集院兼寛(いじゅういんかねひろ)の妹と結婚していた。
隆盛はこの新妻を残して江戸に出た。参勤交代のあった当時としてはこれは当然なことだが、まもなく離婚している。
夫と父母のいない西郷家に、未婚の小姑たちと暮らすのは辛かったのかもしれない。
離縁の話は伊集院家のほうから出たということである。
江戸に出てまもなく隆盛は庭方役(にわかたやく)を拝命した。
これは非公式な斉彬の密事を取り扱う秘書のような役目だった。
そして隆盛に与えられた仕事は水戸家との連絡係だった。
その関係で彼は、小石川の水戸藩邸で勤王家として知られている藤田東湖(ふじたとうこ)に会った。
隆盛は東湖(とうこ)に心酔し、しばしば彼を訪れている。
隆盛の任務は、尊王攘夷の中心である水戸邸に集まってくる各藩の名士と交わり、その人たちの口から洩れる天下の形勢を藩主斉彬に報告することであった。
これは重要な役目だった。だが、隆盛は、
「東湖先生をお訪ねするとまるで清水のなかに浴したように、心中一点の曇りも消えて清浄となり、帰路を忘れてしまう」と語っているように、役目をはなれて東湖(とうこ)の談話に耳を傾けていたらしい。
だから、彼が東湖から強く感化されたことはまちがいない。
後年の隆盛は茫洋(ぼうよう)としていかにも大人物らしい風貌(ふうぼう)だが、このころの彼は青年らしい一本気で行動的なところが多分にみられた。
彼は安政二年に藩の権臣を除かんと同志と暗躍し、これを斉彬にいましめられている。
しかし、隆盛が藩の主要な人物として活発に動きだしたのはこのころからといえる。
安政四年の春、斉彬は帰国したので、隆盛もそれに従った。
1.3 国事に奔走
その後、将軍継嗣問題が重大化してきたので、斉彬(なりあきら)は十月に隆盛を徒目付(かちめつけ)に起用して、密命をふくめて出府させた。
これは一橋慶喜を擁立して将軍世子の降下に尽力することであったが、紀州派の暗躍や関白(かんぱく)九条尚忠(ひさただ)の反対にあってうまくゆかず、翌年五月になると紀州派の巨頭である彦根藩主井伊直弼(いいなおすけ)が大老に就任したことで形勢は一変。
直弼の独断で条約・継嗣問題は斉彬の望まぬ方向に突っ走った。
そこで隆盛はいったん帰藩していたが、六月、斉彬(なりあきら)の命によってまたも大坂(このころは坂の宇をあてた)に向かった。
このとき隆盛三十二歳。大坂に着いた隆盛は吉井友実(よしいともみ)らとともに京坂の間を往来して、勤王僧の月照(げっしょう)や梁川星巌(やながわせいがん)・頼三樹三郎(らいみきさぶろう)らと連絡して情勢をさぐっていたが、七月下旬になって斉彬が死去したとの報を知らされ、隆盛は呆然(ぼうぜん)となった。
このときの隆盛の驚愕(きょうがく)落胆ぶりは、彼がすべてをなげうってただちに帰国し、殉死しようとしたことでわかる。
自分をよく理解し、引き立て、使ってくれた主君の死に、彼の目の前はまっ暗になっていたのだろう。
しかし月照に慰諭(いゆ=なだめる)されて翻意し、斉彬の志をついで国事に奔走することを誓った。
斉彬は死の直前に腹違いの弟久光(ひさみつ)を枕もとに呼び、久光の長男忠義(ただよし)を自分の継嗣とすること、
久光は新藩主をたすけて朝権伸張・幕政改革・公武一体のために力を尽くすことを遺言した。
ところがこのとき忠義はまだ十九歳であったから、父久光のロボット的な藩主となり、斉彬の死後、藩の政治は久光の思う通りに動くようになるのである。
隆盛はこのことを予見していた。
かつては久光一派の陰謀を排除しようとして反久光活動をした自分が、久光の代となってはいままで通りであるわけがない、と悲観したことも事実であったろう。
しかし、国事に尽くすことを心に誓った彼は、藩主交代によるさまざまな藩の変革には強いて目を向けぬようにした。
彼は同藩の日下部伊三次(くさかべいぞうじ)らが行なっている水戸藩への勅諚(ちょくじょう)降下による一橋慶喜擁立運動に挺身した。
彼は近衛忠煕から託された密書をもって水戸・尾張両藩に使いしたりしたが、両藩には密勅に応じられない事情があったので、密書は手渡さずにもどった。
八月七日、朝議は幕府と水戸藩に勅諚(ちょくじょう)を下すことになった。
それは条約の無断調印および水戸・尾張両家謹慎の処置について幕府を詰問するとともに、外患の折から、内憂を除けと戒告し、そのためには大老・老中・三家・列藩一同は力を合わせ、群議を尽くして公武合体の精神にそって行動すべしと命ずるものであった。
そして水戸藩に対し、この勅諚に添えて、この趣旨を列藩一同に伝え、協議を尽くして国家の安泰に努力せよ、と告げた。 このことは幕府には寝耳に水で、大ショックだったので、態度を硬化させた。井伊大老は、これこそ水戸藩を中心とする陰謀だとみて、いわゆる安政の大獄を開始した。
勤王の志士たちが相次いで投獄され、斬られたのである。
このころ隆盛は江戸の薩摩藩邸にいたが、事態容易ならずと、八月下旬に急ぎ上洛した。
彼の考えは同志とともに江戸と京都で義兵を挙げ、井伊大老はじめ幕府の主だったところを除こうというのだった。
彼は前薩摩藩主島津斉興(なりおき=斉彬・久光の父)が大坂に滞在していたので、これを説き藩兵を大坂にとどめることの許可を得た。
そのことをさっそく江戸の同志に知らせ、老中間部詮勝(まなべあきかつ)が条約調印釈明のために上京するのを待ち、間部と所司代(しょしだい)酒井忠義を討ち、彦根城を占領するから、これに呼応して江戸でも義兵を挙げてほしいと求めている。
だが、ことは隆盛の思うようには運ばなかった。
幕府の志士弾圧はますます激しさを加え、隆盛らの暗躍を知って、彼の身辺にも危険が迫ってきた。
こうなっては薩摩藩兵を大坂にながくとどめておくことができない。
挙兵の夢は破れ、隆盛は、同様に身の危ない月照とともに十月二十四日の夜、ひそかに便船で鹿児島に帰った。 |
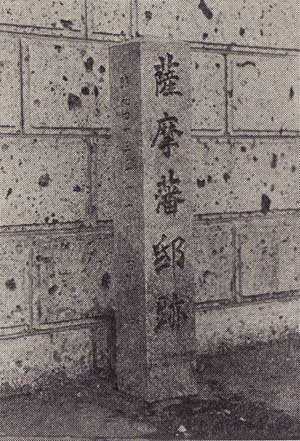
京都の薩摩藩邸跡 現在の同志社大学構内。
|
1.4 大島へ流される
郷里鹿児島なら守ってくれるであろうという隆盛の心だのみも裏目に出た。
斉彬の没後は保守派が勢力を盛り返していたので、幕府から指名手配されている月照(げっしょう)をかくまうどころか、捕えようとする気配さえあった。
もはや月照を救うことはできないとみた隆盛は、友誼(ゆうぎ)のために月照とともに自殺しようと考えた。
そして十一月十五日夜半、彼は月照・平野国臣(くにおみ)らと薩摩湾に舟を出し、大崎ヶ鼻の沖で、月照と相擁して投身した。
隆盛が自決を考えたのはこのときが二度めで、彼としては斉彬の時分と、いまとあまりにも違ってしまった藩の空気に嫌気がさし、将来の望みもないということと、月照をここまで引っ張ってきて、藩の態度が冷たいからと突っ放すこともできず、友人への責任からいっしょに死のうとしたのであろう。
平野国臣は隆盛の心境はまったく知らなかった。
びっくりした彼はすぐに舟をもどして、ふたりを救い上げた。
隆盛は介抱を加えると息を吹き返したが、月照のほうは絶命していた。
藩では隆盛の処置に苦慮した。幕府にはばかりがあるので処罰しなければならぬが、隆盛は斉彬の密命をうけてやっていたことで、多少のやり過ぎはあったとしても藩として罰するほどのことはない。
しかも藩内には隆盛に同情し、味方する空気も強い。
そこで表面は水死したことにして、隆盛に菊池源吾と変名させ、しばらくの間奄美(あまみ)大島に潜伏させることにした。
こうして隆盛は、安政六年(1859)一月十一日、大島の龍郷(りゅうきょう)村に送られた。
いちおうは遠島の罪人ということになっているが、藩の同情的な指令が届いているので島役人も隆盛を大切にして、自由に生活させた。
ここで島人佐栄志(さえし)の娘あいがな(のちに愛子と称す)と同棲し、菊次郎(のちの京都市長)・菊子(のちの大山誠之助夫人)をもうけた。
隆盛は龍郷村に足かけ三年生活したが、ここでの生活で彼は島民たちの奴隷的な生活を見てひどく同情し、しばしば藩庁に対し島民の生活を向上させてくれるよう上申している。
したがって隆盛の島での人気は非常によかった。
万延元年(1860)三月三日、水戸浪士たちによって決行された桜田門外での井伊大老暗殺は、世間を驚愕させたが、薩摩藩に与えた影響も大きかった。
小松帯刀(こまつたてわき)・堀仲左衛門(ほりちゅうざえもん)・中山尚之介(ひさのすけ)・大久保利通(としみち)らの革新派は、この事件を契機として保守派を駆逐することに成功して、久光の知遇を得た。
久光は利口な男だったから、はやくも時流の動きを明察した。
そこで兄斉彬(なりあきら)の遺言に従って公武合体の推進を思い立った。
それにはまず藩内の統一をはかる必要があったので、いままでの首脳部の更迭を断行し、革新派を登用した。
久光はこのように変わり身のはやい人物であった。
藩内体制をととのえると、久光は堀仲左衛門を江戸に、中山尚之介を京に、さらに大久保利通も京に派遣し、みずからも兵千名を率いて上京し、朝権の回復と幕政の改革の進言をすることにした。
そこで隆盛が必要となってきた。
文久元年(1861)十二月、隆盛は召還の命をうけて三年ぶりに鹿児島にもどってきたが、このとき彼は大島三右衛門と名のっていた。
1.5 二度めの流罪
久光の出府に先立って、隆盛は先行し、下関で久光の到着を待つことを命じられた。
そこで隆盛は文久二年(1862)三月二十二日に下関に到着してみると平野国臣が待ちうけていて、京坂にて義兵を挙げる相談をもちかけた。
隆盛は、自分の進言を久光が取り上げないことで不満をもっていたので、平野のことばに従い主命に背いて即日上京、京都伏見などを泳ぎまわり、尊王攘夷の実現に努力した。
三月二十八日になって下関に着いた久光は、隆盛が無断で上京したことを知って激怒した。
ようやく藩論を統一した久光にとっては、隆盛の独断的な分派行動はゆるせなかった。
大久保利通は、親友の身を心配して大坂に急行、隆盛に会ってその真意をただし、主君にとりなすためにすぐ引き返したが、もうそのときには隆盛の処罰は決定していた。
文久二年六月、隆盛はこんどは大島よりもさらに遠い徳之島の岡前に流された。
前のときは藩のなかにも同情があり、処置は寛大だったが、こんどは主命に背いたというので島役人の監視も厳重なら、扱いもひどかった。
隆盛もこれでは、もう二度と世の中には出られないと諦(あきら)め、ふてくされた様子である。
彼が島から友人に出した書簡に、それが見られる。曰(いわ)く――
「私にも大島へまかりあり候節は今日今日と相待ち居り候ゆえ肝癪(かんしゃく)もおこり、一日が苦にこれあり候ところ、このたびは徳之島より二度出で申さずとあきらめ候ところ、何の苦もこれなく、安心ものに御座候」
「とてもわれわれ位にて、おぎない立て候世上にてこれなく候間、ばからしき忠義だてはとりやめ申し候」 |
この書状から見ると久光に対して反抗的にさえなっている。
こういった彼の態度は久光のほうにも反映したとみえ、久光の憎しみはさらに激しく、八月下旬には徳之島から重罪人だけを流す沖永良部(おきのえらぶ)島に送られ和泊村の牢屋に入れられた。
「着島の上は囲に召込み、昼夜をあけざるよう番人両名をつけおくべきこと」
との達しが島役人になされていたから、監視は厳重をきわめた。
隆盛のこのころの唯一の楽しみは読書だったというから、読書によって彼は内面的なものを育てたにちがいない。
彼がこの島で書いた『与人役大体』『間切横目大体』『社倉趣意書』などの著述は、民政に関する優れたものだといわれている。
1.6 久光の公武合体論
ところで隆盛が沖永良部島に流方れている間、日本の政局はどのように変化していたであろうか?
文久二年(1862)島津久光は勅使大原重徳(しげとみ)を擁して江戸に下り、幕閣の改造を進言して、ある程度成功させた。
しかしこれは、あくまで藩主としての立場からの公武合体論の実現であった。
それだけに若い公卿たちや勤王の志士たちは不服で、彼らは長土二藩を背景として、下級武士としての彼らが考える尊王攘夷論を推進させた。
その結果、十月に勅使として三条実美(さねとみ)、副使として姉小路公知(あねがこうじきんとも)が江戸に下り、攘夷決行の日どり、方策などの決定を幕府に伝えた。
文久三年三月、久光は再び京に上った。
そのころの京都は志士たちの活躍で、下士的な尊王攘夷論が燃えさかっていた。
三条実美ら急進的な少壮公卿は長州藩その他の志士と結び、朝廷を動かそうとしていた。
久光はこのありさまを見て、近衛邸に中川宮・関白鷹司輔煕(たかつかさすけひろ)・徳川慶喜・山内豊信(とよしげ)らを招き、攘夷の決議は軽率であると非難した。
久光は朝廷が幕府を軽視して、浮浪藩士の暴論を信用するのは誤りであるから、まず暴論にくみする三条たち少壮公卿を退け、志士と称する浮浪藩士を厳重に取り締まり、中川宮・近衛忠煕公らを回復させ、国政は将軍にまかせ、在京の無用の大名や藩士らは帰国させ、公卿がみだりに浮浪藩士たちと会うのを禁止すべきである、と説いた。 |

島津久光像
|
ところが、このことはとこから洩れたのか、久光は尊攘過激派連中から激しい攻撃を加えられだしたので、早々に帰藩した。
その後の京都は尊攘過激派の公卿や長州藩の天下となった。
天皇はその勢力に押されて、四月十一日には攘夷祈願のために石清水(いわしみず)行幸、二十日には五月十日をもって攘夷決行の期日とするとの布告を出した。
そこで長州藩は五月十日、下関を通過する米船を砲撃して気勢をあげた。
それから十日後、尊攘派の公卿で三条実美(さねとみ)の片腕ともいわれた国事参政の姉小路公知(あねがこうじきんとも)が路上で暗殺された。
現場に落ちていた刀が薩摩藩士のものだということで、暗殺を命じたのは薩摩藩だとの疑いがかり、薩摩藩は乾(いぬい)御門守護の役を免じられ、藩士の九門出入りが差し止められた。
凋落(ちょうらく)した薩摩藩は巻き返しの機をねらっていた。
尊攘派志士たちの運動が単に攘夷だけでなく、幕府打倒・王政復古へと流れてゆく陰で、薩摩藩士たちはひそかに中川宮・近衛父子らとはかり、会津藩と手を結び、長州勢力の転覆を計画していた。
そこへ八月十三日の大和行幸・攘夷親征の詔(みことのり)が出た。
間髪を入れず、十八日の未明に中川宮が参内し、前関白近衛忠煕(ただひろ)父子・右大臣二条斉敬(なるゆき)・内大臣徳大寺公純(きんずみ)・京都守護職松平容保(かたもり)・所司代稲葉正邦(まさくに)らを召集し、薩摩藩兵と会津藩兵とが御所の諸門をかためた。
そしてさらに因幡(いんば)・備前(びぜん)・阿波(あわ)その他在京諸大名に兵を率いて参朝せよとの命が下され、尊攘派の公卿と長州藩は完全に閉め出された。
このクーデターで薩摩藩は宿敵長州藩とそれにくみする尊攘派勢力を一掃し、政局の主導権を握ることができたのである。
京を追放された長州藩は十九日、三条実美ら七人の尊攘派公卿を守って西下の途についた。
そのあと長州藩は嘆訴のため家老の根来上総(ねごろかずさ)を上京させたが、入京することさえゆるされずに帰藩、長州
の薩摩に対する憤激は炎のように燃え上がった。 |
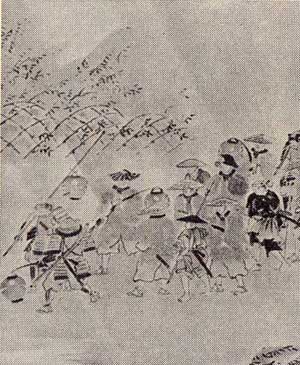
七卿都落ちの図 文久3年8月18日の政変で、
三条実美ら激派公家は長州に落ちた。
|
1.7 西郷の出番くる
島津久光の考えは、対立する朝廷と幕府の間に入って、公武合体という大義名分の旗印を掲げて両者をうまく融合させ、薩摩の覇権を確立しようというのであったが、時の流れは久光の構想を過去のものとして押し流していった。
下級武士たちの間で醸成された尊王攘夷論は日に日に勢力を盛り上げ、久光の言うような生ぬるい公武合体論などは通用しなくなりつつあった。
彼の公武合体思想は下からの突き上げで散々に叩かれた。
そうなると機を見るに敏感な久光は、これ以上公武合体論に固執することは薩摩藩にとって不利であり、時流に乗り遅れるおそれがあると悟った。
薩摩藩が天下の覇権を握るためには面目などにこだわらず、いままでの行きがかりを捨て、いっさいを御破算にして政策の大転換をしなければならないと考えた。
そう決心すると久光ははやい。
ただちに藩首脳部の入れ替えを断行した。
八月十八日の禁門の変に功績のあった藩士たちを藩政の主流からはずすと、尊攘論に同調したために沖永良部島に流罪に処していた隆盛を呼び返して起用し、一日もすみやかに藩を下級武士的尊攘論路線に乗せ替える努力をはじめた。
面目よりも実利であるとする久光の行動は、天下に号令しようとする打算に徹したものではあっても賞められてよい。
隆盛を起用することを久光に説いたのは伊地知正治(いちじまさはる)であった。
久光は隆盛に対しては、まだ好ましからざる感情のしこりを残していたが、すべて打算の上で行動する彼は、伊地知の説得をいれた。
赦免の使者に立ったのは隆盛の実弟の従道(つぐみち)だった。
こうして隆盛は二月二十八日鹿児島にもどってきた。
そして彼はただちに上京し、軍賦役を仰せつけられた。
隆盛このとき数え年の三十八歳で、事実上の薩摩藩代表者になったのである。
2 維新劇の晴れ舞台――江戸開城 top
2.1 禁門の変
しかし、そうはいっても、久光も隆盛もただちに長州藩志士たちが唱えているような下級武士的尊攘論に頭を切り替えたのではない。
人間の思想は、いくら打算の上に立つたからといってもそう飛躍するものではないからである。
久光は幕府に対し、長州藩主毛利敬親(もうりたかちか)父子を大坂に召喚し、詰問すべきことを強硬に主張した。
幕府ももっともだとして、長州藩に七卿を連れて行ったこと、幕使を殺害したり、薩摩の傭船長崎丸を砲撃したことをあげ、長州藩支族の吉川経幹(きっかわつねもと)および末家・家老が上坂して釈明することを命じたが、長州藩はその命に従わず、かえって過激なる藩士が京都に潜入して暗殺や放火などで市中を騒がし、政変にもってゆこうとした。
元治元年(1864)六月五日、例の新選組による池田屋事件が発生した。
このことはいっそう長州の態度を硬化させ、長州藩は福原越後(ふくはらえちご)・国司信濃(くにししなの)・益田右衛門介(ますだうえもんのすけ)の三家老に兵を与えて上京させた。
これは幕府の詰問に答えるという態度ではなく、逆に幕府の責任を問うというものといえた。
そこで幕府は、六月二十四日、これを打ち払うために薩摩藩に出兵を命じたが、隆盛は久光を説いてこの命令を拒否している。
つまり、隆盛は、その以前から桐野利秋(きりのとしあき)を長州に送りこんで情報をさぐらせていて、いまの状態では出兵すべきでないと判断したのだった。
隆盛の言い分け、斉彬の遺志である禁闕(きんけつ=朝廷)守護を第一にすべきで、それ以上のことに手を出してはいけない、というのだった。
彼はこんどの争いは会津と長州の私闘であるとみた。
そこで会津藩とともに出兵することは、長州の恨みを買うことになるからとるべき策ではない、とした。
ここに隆盛と久光との間に考え方のギャップがあった。
しかし、長州とは戦うべからずとしていた隆盛も、強引に京都に入ろうとする長州軍とこれを入れさせまいとする幕府側とが激突し、いわゆる禁門の変が勃発するに及んでは、禁闕(きんけつ)守護のたてまえから長州軍と交戦せざるをえなかった。
隆盛が陣頭に立って、戦闘を指揮したのはこの戦いがはじめてで、このときの薩摩軍の奮戦ぶりはめざましいものがあった。
この戦闘で隆盛は足に弾丸をうけて負傷をしている。 |
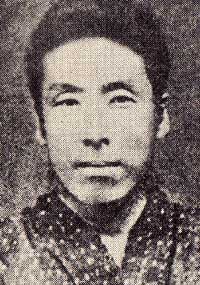
桐野利秋
|
禁門の変の結果、八手口にわたって民家四万三千戸が焼かれ、戦闘は二昼夜つづいた。
長州側は久坂玄瑞・真木和泉(まきいずみ)・入江九一(いりえきゅういち)ら多くの志士を失って敗退した。
そしてその余波は六角堂(ろっかくどう)の獄舎に国事犯として捕えられていた平野国臣(くにおみ)以下三十七名に及び、いっせいに斬首された。
隆盛はこのころは大島吉之助と名のっていたが、十月二日側役に昇進したので、西郷吉之助隆盛と名のることになった。
2.2 海舟とはじめて会う
隆盛が勝海舟とはじめて会ったのは、その直前の九月十五日のことで、場所は神戸海軍練習所においてであった。
隆盛が国際的な視野をもって、日本の進路を見る目を開かされたのは海舟との会見によってであった、といわれているが、事実のようだ。
それまでの隆盛は視野が狭かった。
前後五年余にわたる島での牢居生活の直後なので、新時代に処すべき確固たる理念は急には生じなかったであろうが、もともと隆盛という人物は、広く四方を見回すということのない男のようである。
彼によき助言者や忠告者がいるときは、すばらしい働きをしたが、それがなくなると晩年のように過ちを犯してしまうのだろう。
禁門の変で、尊攘派であり、ライバルであった長州藩勢力を京都から追放し、政局の主導権を握った薩摩藩としては、年来の望みがかなったことで満足した。
いっぽう幕府は、尊攘派に壊滅的打撃を与えるため、そして幕府の権威を内外に誇示するために長州征伐の許可を奏請し、七月二十三日に朝命を下してもらった。
禁裏守衛総督の一橋慶喜は、その旨を諸藩に伝え、西国二十藩に出兵の命を下したが、肝心の幕府は長州征討を本気では考えていなかった。
征伐するぞと声を高くして叫べば、長州は恐れ入って足もとに這(は)いつくばるものと考え、つまりハッタリをかけたのであった。
したがって長州征討の措置は緩慢で、征討の命が下って三ヵ月たってようやく大坂城で征長の軍議を開き、総攻撃の日を十一月十八日と決めるといったありさまだった。
このころ隆盛が在藩の親友大久保利通に出した手紙によると、兵力をもって長州を下し、長州が降を乞うたなら、東国あたりに、わずかの領土を与えて国替えを命じたがよい。
さもないと長州という奴は、先々もまた乱をおこしかねないからだ――と言っている。
戦った以上は相手を徹底的に叩きつけておかないと安心がならないから、潰しておこうというのが隆盛の考えであった。
彼の薩摩中心主義の考え方の現われである。
そして、この考えは彼の本来の下級武士的尊攘主義よりも、久光の考えていた公武合体論に近づいているとみていい。
つまり、このころの隆盛の理念は一定しておらず、周囲の状況によって揺れ動いていたようだ。
こういったときに彼が海舟に会ったことは幸いであった。
そのきっかけは福井藩の同志堤正誼(つつみまさよし)が隆盛を訪ねてきて、
「神戸の海軍操練所に勝安房(かつあわ)という仁がいる。
幕臣だが徳川譜代の臣ではなく、親父の小吉は御家人だ。
だから身分は低いがこの勝はできた奴で、蘭学を学び、海軍伝習生に交わり、教授方頭取として遣米使節とともに咸臨丸でアメリカに行った。
文久二年軍艦奉行並となり、操練所を開いたが、さかんに諸藩の志士たちとも交わるので、幕府からは睨まれているという噂だ。
この男なかなかの人物らしい。
そこでわれわれで彼を訪ね、将軍上洛のことを頼んでみようではないか……。
さもないと将軍は朝命を軽んじていると非難されるやもしれんのだ」と誘った。 |
よかろうというので隆盛は九月十五日堤とともに勝に会見した。
このとき勝は正直に、
幕府の腐敗がその極に達し、再建は不可能であること、
山積みしているいろいろな問題、特に諸外国の脅威を退け、日本の独立を守るには、雄藩が力を合わせてことにあたる以外に道のないこと、
幕府はもはやそれだけの力がないことなどを話した。 |
隆盛は、幕臣である勝の口から、幕府の実情を聞かされてびっくりすると同時に、なぜ征長の軍がいつまでももたもたしていたのか、その理由を納得することができた。
隆盛は勝からいろいろと教えられた。勝は言った。
「外国人たちは幕吏をばかにしているから、幕吏の談判ではとても話をまとめることはできない。
そこで この際、明賢の諸侯が四、五人も力を合わせ、同盟し、異国軍艦を打ち破るだけの兵備をもったうえで、横浜や長崎の港を開放し、筋を立てて談判し、条約を結ばれたならば、日本の恥にならないようになり、外国人はかえって条理に服し、その結果、天下の大勢も決定するでしょうよ」 |

勝 海舟
|
2.3 西郷、開眼する
隆盛は、勝の見識に心から感服してしまった。彼はこのときのことを、次のように書いている。
「勝氏へはじめて面会つかまつり候処、じつにおどろき入り候人物にて、最初は打ちたたくくばりにてさし越し候処、とんと頭を下げ申し候。
どれだけか智略のあるやら知れぬあんばいに見うけ申し候。
まず英雄肌あいの人にて、佐久間(象山)より事のでき候儀は一そうも越え候わん。
学問と見識においては佐久間抜群のことに御座候えども、現事にのぞみ候てはこの勝先生と、ひどくほれ申し候」 |
隆盛は勝の意見を聞いて公武合体論ではだめだ、どうしても武力討幕をし、雄藩連合によって国の政治を行なわなければならぬと覚悟した。
そこで長州征討の無意味であることを悟った。
時勢の推移を的確にとらえる叡知に弱く、国際的な視野も狭かった隆盛は、勝によって開眼されたといっていい。
このあとの隆盛の一連の行動には、勝の意見が随所に生きて現われているからである。
勝との会見により、長州を叩くことだけでは問題は解決することにならぬことを知った隆盛は、強硬論をすてて、最少の犠牲でこの問題を処理しようと考えた。
そこで彼は総督徳川慶勝(よしかつ=尾張)に、長州支藩である岩国の藩主吉川経幹(きっかわつねもと)を説得する役を自分に仰せつけてほしいと願い出た。
隆盛は十一月三日、岩国に行き吉川に会って恭順をすすめた。
長州藩ではこのとき俗論党が勢力を得ていて藩論が恭順に決していたので、隆盛の説得は成功した。
その月の二十三日、総督徳川慶勝は動員を下令した諸藩に長州藩処分の意見を聞いた。
あくまで開城さすべしと強硬意見を吐く藩もあったが、隆盛は、なるべく処分を寛大にして藩主父子の退隠、削封程度にしておくがよろしいでしょうと答えた。
総督は隆盛の意見をいれて、毛利父子に伏罪書を差し出させること、三条実美ら長州藩でかくまっている五人の公卿を他藩に移すこと、山口城を破却することでゆるすことにした。
これに反対する諸藩をなだめる役では隆盛は非常な働きをしている。
しかし、幕府はあくまで長州征討をして大いに威勢を回復しようと考えていたので、再征のことを朝廷に言上、将軍家茂は慶応元年(1865)五月大坂城に入った。
幕府老中らは、将軍が本営を大坂に進めたと聞いただけで長州藩は無条件降伏を申し出るにちがいないと考えていたが、こんどはそうはいかなかった。
長州藩では高杉晋作らの反幕勢力が台頭して、俗論党を追い、財政・軍政の改革を行なって対幕戦の準備の強化につとめていたから、幕府の思惑ははずれた。
しかも薩摩藩はじめ多くの藩が長州再征には反対で出兵を拒否したから、幕府はますます苦しい立場に追い込まれた。
2.4 長州再征と薩摩の態度
隆盛はこれより一ヵ月前、幕府の長州再征が決したことを耳にすると鹿児島に帰り、藩論を出兵拒否にまとめて、上京していた。
彼は小松帯刀(こまつたてわき)に将軍が無理押しに発足するようすだが、このことは幕威を張るどころか、天下動乱の因をなすこととなり、徳川氏衰亡がこれではじまるだろう、ということを手紙で書き送っている。
もうこのときの隆盛は、はっきりと倒幕に踏み切っており、ただそのチャンスだけを待っていた。
長州藩の桂小五郎(木戸孝允)は、薩摩が倒幕戦列に加わったことをこの時期で見抜いていた。
それなのに、うかつにも幕府は、まだ薩摩は幕府の系列にあるものとみて出兵を求め、三度督促している。
もちろん薩摩はこれを拒否した。幕府はおどろくと同時に、薩摩の態度が他藩に影響を及ぼすであろうことをおそれて、勝海舟に大久保や西郷を説得するよう頼んだ。
しかし勝は出兵拒否をした薩摩の態度こそ正当であると進言している。
幕府の面目(めんもく)まるつぶれといったところである。
さて有力な諸藩の反対を押し切って、幕府は長州再征の戦闘を開始したが、うまくゆくはずがない。
幕府側はいずれも戦意なく、各方面で次々と敗れた。
足並みが揃わないうえに、武器の面においても、訓練においても幕府側ははるかに長州勢に及ばなかったからだ。
長州再征戦は、むしろ幕府軍の弱体ぶりをさらけ出し、倒幕も夢でないことを天下に知らせたようなものであった。
このときにあたり、土佐藩士坂本龍馬は、禁門の変以来敵視しあっている薩摩と長州の間を奔走して、両者を結びつけることに成功した。
衰えたとはいえ徳川家を倒すにはこの二大雄藩の協力が絶対条件だったからで、薩摩藩の代表は西郷隆盛・小松帯刀、長州藩は桂小五郎、これらの英傑が存在していたので、薩長の連合は慶応二年(1866)一月二十一日成立した。 |

坂本竜馬像
|
その年の七月、将軍家茂(いえもち)が死去した。
狼狽した幕府は慶喜を名代として戦陣に立てたが、戦意を失っていた幕軍が活気づくはずもなかった。
そこで軍艦奉行縢海舟を軍使として広島に送り、休戦の談判をさせ、うやむやのうちに長州再征の幕を下ろした。
2.5 英仏の策動
ところで、ここで見落としてならないのは、陰で策動する外国勢力の動きである。
ことにイギリスとフランスがもっとも露骨を極めた。
そして両国は相反目し、表面には現われない戦いをつづけていた。
すなわち、フランスが徳川幕府を支持して力を貸せば、イギリスは倒幕派の雄藩である薩長両藩を応援した。
その目的とするところはいうまでもなく、将来の日本を支配するであろう指導層にとり入って、独占的利益を得ようとするものであった。
フランス公使のロッシュは幕府外国奉行の小栗上野介に接近し、幕府をたすけてその権力を保持させようと努力し、必要とあらば大砲・軍艦などを提供するから早急に薩長を討つことを進言していた。
小栗はこれに同意したが将軍慶喜は勝の進言をとって、フランスのこの申し出は断わった。
しかし、兵制や調練などではフランスの兵式をとり入れた。
いっぼう、イギリス公使パークスはもう幕府は日本を代表する政権ではなく、将来日本を動かすものは薩長であるとみてあらゆる援助を申し出ていた。
慶応二年(1866)六月、イギリス公使パークスと東洋艦隊提督キューパーは薩摩藩を訪れた。
このとき応待の長として親交をはかったのが隆盛で、その歓待は至れり尽くせりだったという。
このときパークスは隆盛に、
「王政復古となった場合、われわれは公卿衆を相手として談判することになりますか?」と開港その他のことで質問した。隆盛は、
「いや、朝廷より五、六藩の諸侯に命ぜられ、それらの藩が合議によって交渉にあたることになりましょう。
その際、万国共通の条約をもって結び、信義の交わりをし、そのときこそすべてがととのうようになりましょう」と答えている。
つまり天皇親政を表面に押し立てておいて、幕府にとってかわった雄藩連合によって日本を統治してゆこうという構想を、隆盛はこのとき確固たるものとして考えていたのである。 |

パークス
|
この構想はのちに薩長を中心とした明治新政府の誕生として実現したわけだ。
その年の九月、隆盛は大目付に任ぜられた。これは家老に次ぐ重役職である。
こんな話がある。
その年の十二月九日に、隆盛は兵庫でイギリスの通訳官サトウに会った。
サトウはパークスの片腕として暗躍していた。
サトウは隆盛に、長州藩一国すら討てないような幕府が、どうして天下諸藩に号令をかけられるものか、もはや幕府は日本を代表する政権ではない。
今日、天下の実権を握るものは薩摩藩である、としきりにおだてあげ、隆盛に軍資金や武器を貸与してもいい、ということをほのめかした。
サトウとしては隆盛がイギリスの援助を頼むだろうと思っていた。
ところが隆盛は、気づかぬふうで、
「これまでいろいろと手を尽くし申したが、かえって幕府に疑われるばかりゆえ、ここ二、三年は静かに傍観するつもりでごわす」ととぼけ、やんわりと相手の申し入れを断わっている。
もしこのとき、慶喜にしろ、隆盛にしろ、外国の力を借りてでも相手を倒そうと考えたら、相手も黙っておらず、外国の兵力を借りたであろうから、事実上の英仏の争乱となって、日本はめちゃめちゃにされ、当時の中国のように外国の植民地化していたかもしれない。
慶喜(その陰に海舟がいた)や隆盛の叡知が、この危局をうまく乗り切ったといえよう。
2.6 隆盛の戦争挑発策
さて紙数の関係で先を急ごう。慶応二年(1866)十二月、朝廷内における親幕派の中心であった孝明(こうめい)天皇が崩御され、慶応三年一月、明治天皇が践祚(せんそ)された。
五月、隆盛は大久保と薩摩・越前・土佐・宇和島会談をはかり成功、六月、長州藩と討幕を約す。
十月、大久保らと芸長薩による王政維新を策し、討幕の密勅を得る。
しかし、このとき坂本龍馬・後藤象二郎らの働きで将軍慶喜は大政を奉還した。
それでも、薩長二藩の出兵計画は着々と進み、島津忠義(ただよし)がまず隆盛らを従え、三千の藩兵を率いて十一月二十三日、京に入ると長芸の藩兵もそれぞれ到着した。
十二月九日、隆盛はクーデターを断行し、薩摩・尾張・土佐・安芸(あき=広島)の藩兵で宮門をかためてしまった。
こうしたなかで、王政復古の号令が発布された。
そして二月九日夜開かれた小御所会議で、岩倉具視の提案により、慶喜に官位辞退、所領返納を命ずることに決定した。
大政は奉還したといっても、なお徳川家は強大な兵力・財力を握っている。
これを完全に叩き潰さなければ、真の王政復古はありえないというのが、隆盛の考えだった。
徳川慶喜は大政奉還後はひたすら恭順している。
これでは叩くわけにはゆかない。
そこでなんとかして徳川を憤らせ、向こうから刃向かうようにして、それを理由に武力討伐をしようと隆盛たちは計画した。
小御所会議において土佐・越前・尾張・安芸四藩の反対を押し切って、慶喜に官位辞退、所領返納といった幕府としては受諾できない過酷な命令を下すことを決定したのは、そのことを計算にいれた隆盛の戦争挑発の布石だった。
当然幕臣たちは憤激した。急を聞いて江戸から続々とかけつけてくる。
これは薩摩藩が幕府にとってかわらんとする陰謀であるから、この際、薩摩藩と雌雄(しゆう)を決すべしという主戦論が大勢を占めた。
そのうえで列藩衆議の名によって改革を奏請すべきであるというのである。
その結果、採正退奸の表が慶喜から奏上された。
その要旨というのは、
「大政を奉還したのは政令の一途に出ることを願う気持ちからいたしたのであり、朝廷において列藩の意見を徴し、不朽の基本を立てられるようにとの考えから建白したのである。
しかるに在京諸侯にはなんの諮問さえなく、一両藩の戒厳の下に大変革が行なわれ、しかもなんの理由もなく孝明天皇遺託の摂政をやめ、皇族・公卿を退け、これにかえるに謹慎中の公卿を起用し、陪臣の輩が玉座近くを占めて、天下の乱れの因をつくらんとしている。
願わくは天下列藩の衆議をつくし、正をとり奸を退け万世不易の国是を定められるべきである」 |
というのであった。
奸(かん)とは、いうまでもなく隆盛たち薩摩勢力をさすものである。
大目付戸川安愛は十八日の夜、これを岩倉具視に提出した。
朝廷ではこのため二十三、四両日会議を開いて、慶喜の辞官、納地の件を再検討し、将軍職を辞した慶喜には朝廷辞官の例にならって前内大臣とすること。御政務用度の分、領地のうちより調査し、天下公論をもって確定することを沙汰して、慶喜の面目が立つようにしたので、辞官、納地の開題は朝廷と旧幕府の間で妥協が成立する形となった。
これでは隆盛が計画した戦争挑発は失敗である。
そこで隆盛が次の手段としたのは江戸市中の騒乱であった。
隆盛は京都を武力で圧服すると同時に、江戸も武力抗争に巻き込もうと計画し、前々から腹心の藩士伊弁田尚平(いむらしょうへい)・益満休之助(ますみつきゅうのすけ)に密命を与えて江戸に派遣、権田直助(ごんだなおすけ)ら五百余の浪人を集めて、江戸を攪乱(かくらん)した。
権田らは薩摩邸に濳み、夜闇にまぎれて江戸市中に出て御用金集めと称して豪商を襲って金を奪い、屯所に放火したり、市中取り締まりの庄内藩邸に銃撃を加えたりし、市民の不安を高めた。
いわゆる御用盗事件である。十二月二十三日には江戸城二の丸が炎焼した。
これも御用盗一味の仕業だという噂が立った。
幕府は江戸薩摩藩邸にかけ合ったが、もちろん白(しら)をきるばかりで、とうとうたまりかねて十二月二十五日、三田の薩邸を焼き打ちした。
2.7 いよいよ武力討幕
これこそ隆盛の待っていたことだった。獲物は罠(わな)にかかった、と彼は喜んだ。
薩摩藩邸焼き打ちの報が大坂城の旧幕府首脳部に届いたとき、彼らはいまこそ薩摩を討つべきときだとして、慶喜に奸賊を除くために兵を率いて上京することを迫り、慶喜もその請をいれて幕軍を北上させた。
隆盛は武力によってのみ政局の打開はできると考えていた。
小御所会議で土佐の藩主山内容堂が反対して意見がまとまらないとき、薩摩の岩下佐次右衛門が岩倉に言われて、警備についていた隆盛のところに、どうしたものかと相談にゆくと、
「口舌ではらちがあき申さん。要は……」と、短刀で刺す手まねをしたと伝えられている。
山内容堂がいつまでも反対しているのなら、刺し殺してでも、言い分を通せ、と言ったのだが、隆盛にはこういった激しい性格がある。
目的のためには手段を選ばずで、力ずくで押し通そうとして、ほかに平和的な手段が残されていないかを考え直す余裕がない。
それは、彼が征韓論に敗れたあとにとった武力によって、相手を屈伏させようという態度にも現われており、勝海舟が言っているように「西郷はああいうときにはじつに工夫のない男だった」ということになろう。
しかし、とにかく、このときは隆盛の目算通りに事は運び、彼の勝利となった。
慶応四年(1868)一月の鳥羽伏見の戦いで、幕軍は敗北し、王政復古までは態度をきめかねていた大坂商人もみんな幕府との縁を切って官軍一辺倒になり、イギリス公使パークスの斡旋で、諸外国も局外中立を宣言するなど、隆盛にとってすべてが好転した。
隆盛は大総督府参謀となり、徳川氏の本拠江戸を攻撃するための諸軍を率いて征途につき、三月五日駿府に着き陣を布いた。
さて、これからいよいよ無血江戸開城の檜舞台の幕が開くことになる。
官軍は東海道・東山道・北陸道から江戸に迫り、先鋒部隊は品川に達し、江戸の人心は動揺し、上野・武蔵を中心に方々で百姓一揆が発生していた。
このときの思い出を、のちに勝海舟は書いているが、隆盛のことをひどく感心してたたえている。
隆盛が海舟を尊敬したのと同様で、この尊敬し合ったふたりがいたから江戸の無血開城は成ったのである。
これは衆知のことだが、ところでこの陰でパークスが隆盛に、降伏している相手を武力討伐するという法はない、それは公法にもとるものであり、そのような官軍なら、イギリスは今後いっさいの協力をしないだけでなく、列国と同盟して徳川家をたすけるだろう。
むろん、横浜の病院も医者も、医薬もいっさい貸さないと強く意見したこともあずかっている、と言われている。 |

西郷隆盛着用の陸軍大将軍服
明治百年記念館蔵。
|
2.8 海舟の述懐
勝海舟はその著『氷川清話』のなかでこう述べている。
「おれは今までに天下で恐ろしいものをふたり見た。
それは横井小楠(よこいしょうなん)と西郷南洲(さいごうなんしゅう)とだ。(中略)
西郷の意見や議論はむしろおれの方が優る程だったけれども、所謂天下の大事を負担するものは果して西郷ではあるまいかと、また窃(ひそか)に恐れたよ。(中略)
136
横井の思想を西郷の手で行われたらもはやそれ迄だと心配して居たに、果して西郷は出て来たワイ。(中略)
坂本龍馬がかつておれに、先生しばしば西郷の人物を物せられるから拙者も行って会って来るにより、添書をくれといったから、早速書いてやったが、その後、坂本が薩摩から帰って言うには、成程西郷という奴はわからぬ奴だ。
少しく叩けば少しく響き、大きく叩けば大きく響く。
もし馬鹿なら大きな馬鹿で、利口なら大きな利口だろうといったが、坂本もなかなか鑑識のある奴だよ。
西郷に及ぶことの出来ないのは、その大胆識と大誠意とにあるのだ。
おれの一言を信じて、たったひとりで江戸城に乗り込む。
おれだって事に処して多少の権謀を用いないこともないが、ただこの西郷の至誠はおれをして相嘆くに忍びざらしめた。
この時に際して、小籌(しょうちゅう=小謀)浅略(せんりゃく)を事とするのは却ってこの人の為に腸(はら)を見すかざれるばかりだと思って、おれも至誠を以て之に応じたから、江戸城受渡しもあの通り、立談の間に済んだのさ。
西郷は今いう通り実に漠然たる男だったが、大久保は之に反して実に截然(せつぜん=はっきり)として居たよ。
官軍が江戸城に入ってから市中の取締りが甚だ面倒になってきた。
これは幕府は倒れたが、新政がまだ布かれないから、ちょうど無政府の姿になったのさ。
然るに大量なる西郷は意外にも、実に意外にも、この難局をおれの肩に投げかけておいて行ってしまった。
どうか宜しくお頼み申します。
後の処置は勝さんが何とかなさるだろうと言って江戸を去ってしまった。
この漠然たる『だろう』にはおれも閉口した。実に閉口したよ。
これが大久保なら、これはかく、あれはかくとそれぞれ談判して置くだろうに、さりとは余りに漠然ではないか。
しかし考えてみると西郷と大久保との優劣はここにあるのだよ。
西郷の天分が極め高い所以(ゆえん)は実にここにあるのだよ。
西郷はどうも人に解らないところがあったよ。
大きな人間ほどそんなもので……小さい奴ならどんなにしたって直ぐ肚(はら)の底まで見えてしまうが、大きい奴になるとそうでない喃(のう)。(中略)
維新当時の模様をも少し細かに言うと、官軍が品川までおし寄せてきて今にも江戸城に攻め入ろうという際に、西郷はおれが出した僅か一本の手紙で芝田町の薩摩屋敷までノソノソ談判にやってくるとは、なかなか今の人では出来ないことだ。
あのときの談判は実に骨だったよ。官軍に西郷が居なければ話はとてもまとまらなかっただろうよ。
その時分の形勢といえば品川からは西郷などが来る。
板橋からは伊地知(いじち)などが来る。
また江戸の市中では今にも官軍が乗り込むといって大騒ぎさ。
しかしおれは他の官軍には頓着せず、ただ西郷ひとりを眼においた。(中略)
山岡鉄太郎が静岡へ行って西郷に会うというから、おれは一通の手紙をことづけて西郷へ送った。
山岡という男は、名前ばかりは予(かね)て聞いていたが、会ったのはこの時が初めてだった。
それも大久保一翁(いちおう)などが、山岡はおれを殺す考えだから用心せよといって、一寸も会わせなかったのだが……。
しかし、この時の面会は、そののち十数年間莫逆(ばくげき=意気投合)の交りを結ぶ本となった。
さて山岡にことづけた手紙で、まずおれの精神を西郷へ通じておいて、それから彼が品川に来るのを待って、更に手紙をやって、今日の場合、決して“兄弟牆(かき)に鬩(せめ)ぐ”(兄弟げんか)べきでないことを論じた所が、向うから会いたいといって来た。(中略)」
2.9 西郷の一言
「当日(三月十三日)おれは羽織袴で馬に乗って従者をひとりつれたばかりで(田町の)薩摩屋敷へ出かけた。
まず一室に案内されて暫(しばら)く待っていると、西郷は庭の方から古洋服に薩摩風の引き切り下駄をはいて、例の熊次郎という忠僕を従え、平気な顔で出てきて、これは実に遅刻しまして失礼、と挨拶しながら座敷に通った。
その様子は少しも一大事を前に控えたものとは思われなかった。
さていよいよ談判となると西郷はおれの言うことをいちいち信用してくれ、その間に一点の疑問も挟(はさ)まなかった。
『いろいろ難しい議論もありましょうが、私が一身にかけてお引受けします』
西郷のこの一言で江戸百万の生霊もその生命と財産とを保つことが出来、また徳川氏もその滅亡を免れたのだ。
もしこれが他の者だったら、いや貴様の言う事は自家撞着(どうちゃく)だとか、言行不一致だとか、沢山の凶徒があの通り処々に屯集(とんしゅう)しているのに恭順の実はどこにあるかとか、いろいろ喧(やかま)しく責め立てるに違いない。
万一そうなると、談判はたちまち破烈だ。
しかし、西郷はそんな野暮は言わない。
その大局を達観して、しかも果断に富んでいたにはおれも感心した。
このときの談判がまだ始まらない前から、桐野(きりの)などという豪傑連中が大勢で次の間へきて窃(ひそか)に様子を覗(うかが)っている。
薩摩屋敷の近傍へは官軍の兵隊がひしひしと詰めかけている。
その有様は実に殺気陰々としてもの凄いほどだった。 |

西郷隆盛着用の陣羽織、明治百年記念館蔵。
|
然るに西郷は泰然として、あたりの光景も目に入らないもののように、談判を仕終えてから、おれを門外まで見送った。
おれが門を出ると、近傍の街々に屯集していた兵隊はどっと一時に押し寄せてきたが、おれが西郷に送られて立っているのを見て、一同恭しく捧銃の敬礼を行った。
おれは自分の胸を指して兵隊に向い、いずれ今明日中にはなんとか決着致すべし、決定次第にて、或は足下等の矛先にかかって死ぬることもあろうから、よくよくこの胸を見覚えておかれよ、と言いすてて西郷に暇乞いして帰った。
このときおれが殊に感心したのは、西郷はおれに対して幕臣の重臣たるだけの敬礼を失わず、談判の時にも始終、座を正して手を膝の上にのせ、少しも戦勝の威光でもって敗軍の将を軽蔑するというような風が見えなかったことだ」 |
芝田町の薩邸での西郷・勝の会見は三月十三、十四の両刪にわたって行なわれ、その結果江戸城総攻撃は中止された。
そして二十日、京都の朝議は慶喜その他のものの処分を寛大にすることに決定した。
武力討幕をもっとも強硬に主張していたのは隆盛であったのだから、彼が寛大に扱おうと言い出せば、朝議としては異議はなかったのである。
そこで四月四日、勅使橋本実梁(さねむね)・柳原前光(さきみつ)は江戸城に入り、慶喜の恭順謹慎の実を認めたので、徳川の家名の存続をゆるし、慶喜の死罪一等を減じて水戸において謹慎すること、江戸城を明け渡すことを命じた。
四月十一日、慶喜は朝命に従って江戸城を開城し、水戸に謹慎した。
3 征韓論と西郷の敗北 top
3.1 新政府と西郷
明治維新にまで政局を導いた隆盛の殊勲はたしかに、志士のなかでピカ一のものであり、この時代は彼のもっとも得意な時代といっていい。
しかし、できあがった維新政府は、隆盛の期待とは反対に公卿(くぎょう)・諸侯を中心として組織したものだった。
維新最高の功労者である薩摩藩と隆盛を中心に組織さるべき新政府なのに、かえって諸藩は隆盛と薩摩藩とを引きずり下ろそうとしていると憤慨した。
隆盛は、兵を率いてさっさと鹿児島に帰った。
このときの隆盛には、自分が出なくてだれが新政府を動かせるのだという考えがあった。
だからこんな新政府では日本の行く手を再び誤る、どうしても薩摩藩を中心にした新政府をつくらねばならぬと考え、第二の維新を断行しようと決心した。
その手はじめとして、隆盛はまず薩摩藩の体制を実力主義につくり直すことを考えた。
つまり、門閥の弊風を打破して、下級武士といえども力のあるものをどしどし高位に登用する藩制に改革すべきことを藩庁に要求した。 |

西郷隆盛愛用の硯と毛筆 鹿児島市立美術館藏。
|
隆盛は帰国するとすぐに凱旋(がいせん)将士に対して他藩よりははるかに大きい行賞をしていたので、彼の人気は高かった。
これらの凱旋将士が隆盛を支持した。
久光としては下級武士中心の改革案には不満であったが、隆盛は押し切った。
この結果、薩摩は隆盛の思うままになり、西郷王国と化した観さえあった。
明治三年(1870)、藩制の改革を終え、その軍隊の洋式化に努力した結果、薩摩藩は中央政府に対抗できる一独立国家のようになっていた。
そうしておいて隆盛は、この恐るべき軍隊を率いて上京し、いまにもクーデターを行なうような揚言(ようげん=言いふらす)をはじめた。
武力によって、なにごとも押し通そうとする隆盛の本質の現われである。
驚愕(きょうがく)した明治政府は辞を低くして隆盛を迎えることにして、第二の維新戦争を回避した。
隆盛は機嫌をなおして上京し、参議に就任、木戸孝允と協力して廃藩置県の実現に努力した。
いちおう、隆盛をなだめるために明治政府としてはやむをえず卑屈な態度をとったものの、内心憤懣に耐えないことは事実で、木戸孝允は時の大蔵大丞(だいじょう)井上馨(かおる)宛の手紙に、
「西隅(鹿児島)の一条は実になげくべし。
かくのごとき体制ゆえ始終上の方も、おおくこれ(隆盛のこと)へ気がねの気味これあり、万端かの(隆盛の)流儀におちいらず候ては御発行も難しく……
強弱衆寡(しゅうか=人数の多い少ない)によりて処置いたし候様にては国家の大典なにを以て相立て候や。
愚人といえども解しやすきところに御座候ところ、堂々たる先生顔に(隆盛のこと)ことごとくかくのごときことを申し出て候ては、じつに慨嘆にたえず候」 |
と、隆盛が時勢をわきまえず、暴力をもって自分の言い分を押し通そうとする態度を憤慨している。
維新の完成までは大久保も木戸も隆盛の親友であり、よき協力者であった。
だかもともと隆盛と木戸・大久保とは政治路線を異にするものであるから、うまく合致するはずはなかった。
隆盛の憤慨をうまくなだめることでクーデターの矛先をかわし、同時に隆盛を中央政府に引きつけておいて、政府の軍事力を強化しようという考えから、木戸と大久保は相談して隆盛を参議に迎えたのであった。
木戸・大久保の策にうまく乗せられた隆盛は、それだけ単純だったともいえるわけで、やがては墓穴を掘る運命へと追い込まれてゆくのである。
隆盛はおだてられて廃藩置県の実現には夢中になった。
親分肌の彼は祭り上げられ、頼まれると人情にとらわれ、信念の線から多少はずれてもそれをやろうと努力するタイプであった。
人は言う――思想をもたぬ政治家の悲劇である、と。
隆盛は大人物であり、大英傑ではあったが、政治家ではなかった。
策謀はよく行なったが、それとて第一級のものではなかった。
彼は至誠の人だが、政略家ではない。
その人が政治の世界に入っていったことがまちがいだったといえる。
3.2 征韓、是か非か
さて、問題の征韓論に話を移そう。明治元年(1868)三月、新政府は江戸時代の先例に従って韓国との修好交渉をすることにして対馬(つしま)藩に命じて、王政復古のことを伝え、今後もいままでどおり友好国交をつづけたい旨の書状を手渡させた。
ところが韓国側は書状に皇室、政権帰一、奉勅などの文字があり、旧例故格に反するからうけとれぬと突き返してきた。
そこで明治二年、所管を外務省に移して交渉したが埒があかない。
業を煮やした木戸は対韓強硬論を主張した。
このことは韓国にも反映し、交渉はこじれ、明治六年になると韓国内に反日運動がおこり、釜山にあった日本の出先機関草梁館(そうりょうかん)への食糧供給を断ち、日本商品の輸入を禁止し、国交断絶をほのめかしたりした。
なぜ韓国がそのような排日政策をとったかというと、日本の修好要求のうらには欧米諸国があり、中国同様に侵略の手を伸ばそうとしているのだ、とみたからであった。
政府は六月に第一回の閣議を開いて、どのように対処すべきかを論議した。
参議板垣退助は、居留民保護のためにただちに釜山に兵を送り、そのうえで修好条約の締結に努力すべきである、と主張した。
これに対して隆盛は反対し、
「いまただちに出兵すれば韓国は侵略のためと思うであろうから、まず使節を送ってわが真意を伝え、しかもなお韓国の態度が改まら ぬときは出兵すべきである」
と述べ、その使節にはぜひ自分をやらせてもらいたいと言った。
こういうと隆盛の主張はいかにももっともで、武力で押し通そうという隆盛らしがらぬ正論のように聞こえるが、隆盛の真意は和親ではなく侵略だった。
まず遣韓使節を送って、それで相手が聞き入れないときは出兵すべし、というのは名分を正すということで、これならば諸外国も納得するだろうと考えたのである。
自分をその使節にしてくれと言ったのは、韓国側か怒って自分を殺すにちがいない。
使節を暴殺したとあれば出兵の理由は十分に成り立つ。
自分が犠牲になって原因をつくり、韓国侵略の兵をおこさせようというのが隆盛のねらいだった。
その年の八月十七日に、隆盛が板垣にだした手紙にそれが読みとれる。
そのなかで彼は、自分が使いして韓国の非を厳しく責めたら、彼は必ず使節である自分を暴殺するであろうから、そのときこそ大義名分の上に立って出兵し韓国を占領すればよい、と言っている。
徳川氏を武力討伐するために、京都や江戸で使い古した手を、またここでも使おうというのである。
その八月十七日の閣議は、隆盛を遣韓大使として派遣することに内定した。
しかしそのときは、不平等条約を改正するために、右大臣岩倉具視を首班とする特命全権大使の一行(木戸・大久保・伊藤博文・山口尚芳はか随員四十八名)が欧米に旅行中で留守なので、岩倉大使の帰朝を待って正式決定をすることにした。
言い分を通した隆盛が喜んだことはいうまでもない。
ところが九月十三日、帰朝した岩倉たちはこの内定にびっくりしてしまった。
欧米を視察してきて、日本の国力が欧米諸外国とあまりにもかけ離れていることを痛感してきた彼らは、この際まず内治に全力を尽くして国力を充実すべきだと一致して考えてもどってきただけに、国力のことも考えないで出兵を前提とするような遣韓使節などはとんでもないことだった。
「征韓是か非か」について激論は一ヵ月余にわたってつづけられ、結局、隆盛は敗れた。
十月二十四日、隆盛は、同じ征韓論派の副島種臣・板垣退助・江藤新平らとともに辞表を提出して野に下った。
3.3 西南戦争
隆盛らの征韓派の主張が正しいか、岩倉らの言い分が正しかったか、ということはおくとして、陸軍卿の山県有朋も海軍大輔の勝海舟もともに「いまは戦える状態ではない」と言っているところからみても、隆盛の主張は精密な計算によって発言されたものでなく、今日流にいえばフィーリングだけの強硬論といえる。
子分の桐野利秋らの突き上げがあって、そうせざるをえなかったとしてもあまりにもひどい暴論であった。
隆盛は胆のすわった、大度量・大至誠の人で、転換期の日本を引っ張ってゆく力と叡知を備えていて、比類のない人物だった。
しかし、そのころの彼には、彼をたすけてくれる優れた同僚やよき先輩がいた。
島津斉彬・勝海舟・大久保利通・藤田東湖など彼によき助言を与え、彼が道を誤らぬようにした。
また隆盛自身も謙虚にそれをうけた。
ところが、どんな人物でも功成り、名遂げてみると、自惚れが出てくるものだが、隆盛もそうで、よき助言者から離れ、子分たちだけを近寄せた。
これらの子分たちが薩摩藩士族としての狹い視野しか持ち合わせていないことも不幸だった。
隆盛は辞表を提出すると、しばらく東京郊外の小梅村にいたが、十一月鹿児島に帰った。
鹿児島に帰った隆盛は、桐野利秋や鹿児島県令の大山綱良らを幕僚とし、隆盛に従って帰郷した軍人や士族の子弟を集めて私学校と称する反乱軍を組織した。
彼の頭にはまたもやクーデターの構想が浮かんでいたのである。
いっぽう、政府は時を稼いで、反乱を鎮圧できるだけの軍隊をつくりあげていた。 |

私学校跡に残る西南戦争時の弾痕 鹿児島市城山町
|
そこで西郷党の鎮圧にとりかかった。隆盛とその一党はこれに抗して上京、クーデターを断行して西郷首班内閣をつくろうとした。
こうして明治十年の西南戦争は勃発した。
しかし、西郷軍の旧式戦術と兵備は政府軍の敵ではなかった。
もっともおもしろかったのは隆盛たちの誇り高い士族軍隊が、彼らが軽蔑しきっていた百姓兵たちの銃口にかかって、バタバタとうち破られたことであった。
勝海舟は隆盛戦死の報を聞いて、
「とうとう不平党のために死んだか……。
あんな不平党を散らすぐらいわけのないことだが、西郷はああいうときには知恵のない男だった」
と語ったという。しかし、勝には隆盛は終生忘れられぬ友であったとみえ、『氷川清話』に、
「西郷も自分の仕事が成就せぬということはちゃんと知っていたのだ。(中略)
賢くないとはいうものの勤王論ぐらいは西郷も知っている。
だから(西南)戦争中は自分では一度も号令はかけなかったというではないか。(中略)
しかしあれはどの人物を弟子のために情死させたのは惜しいものだ。
桐野とか村田とかいう弟子がいなかったらあんな事はあるまいに。(中略)
とにかく西郷の人物を知るには西郷ぐらいな人物でなくてはいけない。
俗物には到底わからない。あれは政治家やお役人ではなくて一個の高士だ……」
とたたえている。 |
参考図書 top
伊藤痴遊『西郷南洲』平凡社(昭和十五年)
田中惣五郎『西郷隆盛』吉川弘文館(昭和三十三年)
田岡典夫『南洲西郷隆盛』講談社(昭和三十三年)
圭室諦成『西南戦争』至一文堂(昭和三十三年)
圭室諦成『西郷隆盛』岩波書店(昭和三十五年)
木村毅『西郷南洲』雪華社(昭和四十一年)
勝海舟『氷川清話』’新人物往来社(昭和四十三年)
平岡正明『西郷隆盛における永久革命』新人物往来社(昭和四十八年)
米沢藤良『西郷隆盛と私学校』新人物往来社(昭和四十八年)
西郷隆盛略年譜 top
文政十年(1827)
弘化元年(1844)
安政元年(1854)
安政五年(1858)
文久元年(1861)
文久二年(1862)
元治元年(1864)
慶応元年(1865)
慶応二年(1866)
慶応三年(1867)
明治元年(1868)
明治二年(1896)
明治三年(1870)
明治四年(1871)
明治五年(1872)
明治六年(1873)
明治七年(1874)
明治十年(1877)
明治二二年(1889) |
一歳
十八歳
二十八歳
三十二歳
三十五歳
三十六歳
三十八歳
三十九歳
四十歳
四十一歳
四十二歳
四十三歳
四十四歳
四十五歳
四十六歳
四十七歳
四十八歳
五十一歳
|
鹿児島城下に、小姓組頭(こしょうくみがしら)西郷吉兵衛の長男として生まれる。幼名小吉(こきち)。通称吉之助。号南洲(なんしゅう)。
郡方(こおりかた)書役助(かきやくすけ)となる。のち書役に進む。
藩主島津斉彬(なりあきら)に登用され、その出府に従う。在府中斉彬の腹心として活躍し、藤田東湖(ふじたとうこ)・橋本左内(はしもとさない)らと交友。
斉彬没す。安政の大獄を逃れ、僧月照(げっしょう)と薩摩の海に投身するが西郷のみ蘇生(そせい)。藩命により大島に流刑。
島津久光、国事周旋を決意し、西郷の赦免召還の命下る。
帰藩。久光の先発として下関に出向し、ついで無断で上阪の罪により、徳之島、さらに沖永良部(おきのえらぶ)島に流刑。
ゆるされて帰藩。上京し、藩兵を率いて禁門の変に長州勢を撃退。勝海舟と会見。征長総督の命をうけて長州藩と折衝する。
幕府の長州再征に対し、薩摩藩の藩論を出兵拒否に決定させる。
坂本龍馬の周旋に応じ、薩長連合を成立。
在京。薩摩・越前・土佐・宇和島の四侯合同を周旋。つづいて討幕運動の主力となる。王政復古後、参与となる。
征東大総督府参謀として東下。江戸にて勝海舟と会見し、江戸城を無血接収。北越(ほくえつ)戦争に出陣。
薩摩藩の藩制改革により参政に就任し、諸郷常備隊を編成する。新政府の上京要請を辞退。
参政を辞して藩政顧問、ついで鹿児島藩大参事となる。
上京して参議に就任。廃藩置県の実現に尽力する。
陸軍元帥(げんすい)・近衛都督に任じられる。
陸軍大将に任じられる。征韓論に敗れて下野し、鹿児島に帰る。
鹿児島に私学校を設立し、士族子弟の軍事教育にあたる。
挙兵上京の途につき、九州各地で政府軍と交戦、敗れて城山に戦没す(西南戦争)。
罪をゆるされ、正三位を追贈される。 |
top
****************************************
|