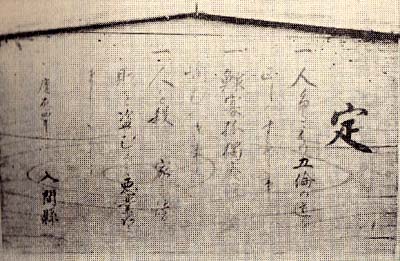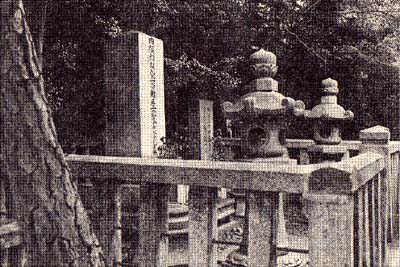|
****************************************
Index 岩倉具視 大村益次郎 西郷隆盛 木戸孝允 大久保利通 福沢諭吉
木戸孝允 大江志乃夫著
1 桂小五郎と木戸孝允
1.1 あるエピソード
1.2 平衡感覚
1.3 長州藩の外交官
1.4 薩長同盟外交の木戸
2 桂小五郎の生い立ち
2.1 吉田松陰との出会い
2.2 小五郎の江戸遊学
2.3 軍事技術者へ
2.4 松陰と小五郎 |
3 政治的実践へ
3.1 戊午の年
3.2 奉勅攘夷
3.3 流血の自己批判
3.4 割拠論
4 桂小五郎から木戸孝允へ
4.1 潜伏行
4.2 芸妓幾松
4.3 薩長同盟
4.4 討幕 |
5 開明派官僚の総帥
5.1 権力者の変革論
5.2 木戸・西郷・板垣
5.3 中央集権国家論
5.4 木戸派官僚群
5.5 木戸と大久保
5.6 同床異夢
5.7 洋行と死
木戸孝允略年表 |
大江志乃夫(おおえしのぶ)東京教育大学助教授。
一九二八年(昭和三)大分県に生まれる。名古屋大学経済学部卒業。
著書『明治国家の成立』『日本の産業革命』『近代日本とアジア』『木戸孝允』他。 |
1 桂小五郎と木戸孝允 top
1.1 あるエピソード
スクラップしておかなかったので、いつのなに新聞にだれが書いたのか、はっきりした記憶がない。
芝居の観客に対するサービスについて書いた文章であった。
地方まわりの 剣劇の一座の話であった。
例によって、幕末の京都は鴨河原の夜、坂本龍馬が新選組に襲われ、危機一髪の瞬間、突如として助太刀が現われ、坂本は危機を脱する。
助太刀に礼を述べ、名前を尋ね、長州の桂小五郎という名のりを聞いた坂本の次のせりふはこうであった。
「さては、のちの木戸孝允公でござったか」
観客サービスの解説のせりふである。
それほどに、日本の民衆のなかにあるイメージとしての幕末の志士桂小五郎と、維新の三傑のひとり木戸孝允とは、食い違った人物像を形づくっている。
わたくしは、かつて『木戸孝允』という新書(「中公新書」)を一冊書いたが、じつは明治維新までの木戸を中心に書いたので、本の題名を桂小五郎にしたいという主張をしたのであるが、採用してもらえなかった。
幕末の桂小五郎から、明治の木戸孝允へ、それはたんに氏名を変えたにすぎないのか、あるいは氏名の変化が彼自身の転身のひとつのあらわれであったのか。
もっとも、桂小五郎という名にもふたつのイメージが重なりあっている。
ひとつは、江戸の剣客斎藤弥九郎の道場練兵館の塾頭をつとめた青年剣客、暗殺剣の乱れかう京の鴨河原に変装して潜伏しながら、美妓幾松(のちの孝允夫人)と演じたラブ・ロマンスの主人公のイメージ。
いまひとつは、家格の高い武士の家を継ぎ、松下村塾の大先輩として重きをなし、若くして長州藩を代表する青年外交官として活躍した秀才官僚のイメージ。 |

木戸孝允像
|
1.2 平衡感覚
木戸孝允のイメージとなると、ちょっと違う。
しかし、ここでも異なったイメージの二重写しがある。
ひとつは、きわめて平衡感覚に富み、理性的な政治家木戸というイメージである。
もうひとつは、やや鬱症状(うつしょうじょう)的な感情の起伏のはげしい人間木戸のイメージである。
このふたつを総合した場合、井上清氏が名づけた「日和見主義的政治家」というイメージが成立するのであろうが、木戸の場合、日和見主義というにはちょっと問題があるように思われる。
むしろ、みずからを故意に日和見的な位置にたたせるように意識的に演出し、結局は平衡の重心にある自分の政治的比重を大きくするという、きわめて政治的平衡感覚に富んだ行動をとっていると考えるほうが適切であろう。
維新以後、中央政府を去っていた木戸が、中央政府に復帰するにあたって、つねに中央政府内の政治的諸潮流のなかで、政治的平衡の重心に自分が位置するよう、細心の注意をはらっている。
第一回めは、明治四年(1871)六月に、西郷隆盛と連立内閣を組織するまでのことである。
当時、国内でもっとも強大な兵力を擁する西郷を中央政府に迎えるにあたって、西郷の対極に位置し、これまた土佐藩の軍事力を支配する板垣退助を説いて上京させ、みずから平衡の重心に位置することに成功した。
第二回めは、明治八年のいわゆる大阪会議の結果、内閣に復帰するときのことである。
すでに中央政府の実権を一手に握った大久保利通は、鹿児島に事実上の独立王国を建設して中央政府に対峙する西郷党を孤立化させるため、長州派の長老木戸の協力をとりつけようとした。
木戸は、事実上の大久保独裁政権内部で自分を政治的平衡の重心とするために、これまた、大久保の対極にあり、愛国社を率いて、民選議院の設立を要求している板垣の入閣を条件としたのであった。
いずれの場合にも、結局は木戸の政治的立場の強化と、木戸の政治的主張の実現をたすけるために使われた板垣の立場からみれば、板垣と連合しながら、つねに板垣と西郷、または大久保との平衡線上を綱渡りする日和見主義者にみえたにちがいない。
しかし、木戸はこうした平衡線上を巧みに歩こうとしたのではなく、みずから思い定めた道に平衡線を一致させるために、さまざまの政治的力関係をみずからの意志でつくりだしていったのであった。
1.3 長州藩の外交官
このような政治的平衡感覚を、木戸は、じつは、幕末の桂小五郎時代に、長州藩の外交官として活動した時期に身につけたと考えることができよう。
桂が、長州藩の外交に重きをなしはじめたのは、安政六年(1859)、二十七歳にして、江戸の藩邸の有備館(ゆうびかん)用掛(ようがかり)となったときからであり、さらに、文久二年(1862)に、機密に参与すべき藩命をうけ、学習院用掛という京都における諸藩の政略外交の場に出て、長州藩の少壮外交官としての地位はますます大きなもめとなった。
ところで、桂が長州藩の少壮外交官として京洛の巷(ちまた)に活動したのは、じつは、奉勅攘夷の藩論を掲げて国論のリーダーシップをとった時期から、文久三年八月十八日のクーデターによって、一挙にリーダーシップを失い、六十余州の敵意のうちに防長二州が孤立し、元治元年(1864)に蛤御門(はまぐりごもん)の敗戦で、ついに京都を逃れ潜伏しなければならなくなった二年余の歳月であった。
この二年余のうち、後半の一年間に、藩の武力の背景もなく、孤立したまま、情勢を転換させ、国論の回復をめざして、その信ずる政治戦略である「正藩合一(せいはんごういつ)」の実現を目的としてめまぐるしい外交を展開した。
この体験が、桂に鋭敏な政治的平衡感覚を身につけさせたのであろうか。
これを境に、桂の行動様式は変化を示している。(慶応元年(1865)九月、藩命によって木戸貫治(かんじ)と改めている)
有名なエピソードとして、薩長同盟の締結をめぐる京都薩摩藩邸での話がある。
斡旋者である坂本龍馬が木戸より十一日あとに京都藩邸に着いたとき、肝心の同盟の話はまったくされていず、あきれた坂本に対して木戸は、現在の長州藩の立場上、自分のほうから話を切り出すわけにはいかない、と説明したという。
力の劣位を政治的対等にまでもっていくために、みずからが政治的平衡の重心にたつ条件ができるまで待つという、「待ち」の外交であり、こうした姿勢は桂小五郎時代にはみることができない。
1.4 薩長同盟外交の木戸
坂本龍馬は、この木戸の説明には納得しなかったであろうし、むしろ、いまさら藩の面目などにこだわる木戸の考え方に驚いたと思われる。
しかし、それよりも同盟の実現を先決とする坂本は、西郷を説き、西郷はあっさりと坂本の提案をいれ、薩摩藩から長州藩に同盟を提案した形で、幕末最大の政治情勢の転換である薩長同盟を実現した。
このときの三人の動きを、かつてのわたくしは次のように評した。
この過程に、はしなくも、木戸・坂本・西郷の性格がよく示されている。
なにごとにも筋を通さねばおさまらない木戸、そこに、理性人としての性格が、悪くすれば、筋を貫くために大局の判断を誤りかねないという特有の欠陥をも伴うという弱点をさらけだした。
そして、このことが、じつは、維新後の新政府部内において、もっとも筋の通ったイデオローグとしての立場に光彩を発揮しながら、現実の政治の動きのなかで泥にまみれることのできない、木戸のスッキリしない進退の変転となって現われる、と。
坂本と西郷の評価については省略するが、少なくとも薩長同盟をめぐる木戸の動きについてのこの手きびしい評価は、いくらか修正すべきであると、現在では考えている。
ここで木戸ががんばったのは筋を通すためというより、外交の技術としての駆け引きとしての「待ち」ではなかったか。
そして、坂本と西郷という組み合わせが生み出す平衡の上にたって、はじめて四境皆敵の孤立のもとで劣位の政治的立場にある長州藩が薩摩藩との対等の同盟者としての地位を獲得できると、木戸は考えたのであろう。
明治六年(1873)、岩倉具視大使一行の欧米巡遊中に、西郷を首班とする留守内閣が征韓論を決定したとき、岩倉大使一行に先だって、木戸は急ぎ帰国した。
しかし、けっして、孤立して性急な動きを示そうとはしなかった。
薩長同盟交渉のときの西郷と木戸の関係、西郷に対する木戸の態度と似ている。
しかし、このときは、薩長同盟交渉のときの坂本のような人物は存在しなかったし、存在する余地もなかった。
木戸の政治的平衡感覚はバランスを失って、ついに「脳病」を発したのであった。
2 桂小五郎の生い立ち top
2.1 吉田松陰との出会い
小五郎は、毛利氏三十七万石の城下町萩に生まれた。
天保四年(1833)六月二十六日である。
父は和田昌景(わだまさかげ)、藩医として二十石取りの身分であったが、正規の武士ではなく、富裕であった。
小五郎は昌景の後妻の子で、長男ではあったが、昌景五十四歳のときの子であり、昌景はすでに先妻との間の畋に養嗣子を迎えていたので、小五郎は和田家を継ぐ必要はなかった。
和田家の隣家は。桂という百五十石取りの武士の家であった。
当主の孝古は六十二歳で、嗣子がなく、病気となった。
家を断絶させないためには、生前に養嗣子を決めなければならない。
隣家の和田家は、藩祖毛利元就の七男天野元政の血統につながる家柄であるとされ、桂家もまた毛利氏の祖先である大江広元の十世の孫にはじまるとされていた。 |

木戸孝允の生家跡 孝允はここに20年間居住した。萩市呉服町。
|
家柄もつりあいがとれていたところから、八歳の小五郎が桂家を継ぐことになった。
末期(まつご)養子は減禄(げんろく)という成規によって、少年桂小五郎は九十石取りの武家の当主となった。
そしてまもなく養母も亡くなったところから、生家の和田家で成長することになった。
家格の高い武家の当主でありながら、富裕で比較的自由な知識人の家庭に育つという恵まれた環境のなかで、小五郎は、やや病弱の身を、藩士として要求される文武の教育をうけたが、良家の子弟らしく、特に抜きん出た秀才ぶりを発揮したようでもなく、特筆すべき少年時代のエピソードも残されていない。
この平穏な小五郎の人生の転機となうたのが、吉田松陰との出会いであった。
弘化四年(1847)、十八歳で山鹿(やまが)流兵学師範として独立した吉田松陰は、嘉永二年(1849)三月、御手当御用掛を命ぜられ、六月下旬から須佐(すさ)・大津(おおつ)・豊浦(とよら)・赤間(あかま)ヶ関などの海岸を巡視し、十月には門人を率いて、羽賀(はが)台で演習を行なった。
小五郎が松陰に入門したのは、この十月であった。
松陰二十歳、小五郎十七歳であった。
しかし、このときの松陰は、藩の兵学師範としての松陰であって、まだのちの松下村塾の松陰ではなかった。
門人も、藩の重臣である益田弾正(ますだぜんじょう)以下、多数あり、小五郎もそのひとりにすぎなかった。
にもかかわらず、のちに、小五郎が松門の大先輩として重きをなした起点として、この出会いは重要な意味をもった。 |

吉田松陰像
|
2.2 小五郎の江戸遊学
嘉永五年(1852)九月、江戸練兵館(れんぺいかん)を主宰する斎藤弥九郎の嗣子新太郎が萩にやってきた。
これを機会に、藩は藩士五人を剣術修行のため官費で江戸に派遣したが、選にもれた小五郎は、私費で三年の江戸遊学をゆるされた。
萩では恵まれた環境のために鷹揚(おうよう)でありすぎたのか、特に頭角を現わすこともなかった小五郎は、江戸という広い世界に出てみて、にわかに気力充実したのであろうか。
翌年には、早くも江戸三大道場といわれた斎藤弥九郎道場の塾頭となった。
ちょうど、郷里では幼少時代を「泣虫龍馬」とよばれた坂本龍馬も江戸に出て、予葉周作の弟・千葉定吉の道場でめきめきと腕を上げつつあった。
そのころの江戸は、徳川将軍家の秩序正しい城下町から、新しい時代の予感をひめた青雲の志が渦(うず)巻く混沌(こんとん)をはらんだ日本の中心都市へと変貌しつつあった。
有名な剣術道場や学者の家塾は、時代を担おうとする志や野心に満ちた青年たちが、直臣(じきしん)・陪臣(ばいしん)の差、藩の壁、藩士・郷士(ごうし)・豪農などの出身身分の壁をこえて交流する場となっていた。
西国の雄藩の出身で、しかもれっきとした身分の小五郎が、斎藤道場の塾頭であるということの重みは、はかりしれないほど大きい。
長州に桂小五郎ありとの声は、青雲の志に満ちた諸藩の青年武士たちの間に広まった。
しかし、小五郎、そして龍馬の人生にとって重大であったのは、じつに、嘉永六年、「癸丑(きちゅう)」という年を、この日本の中心都市江戸で迎えたことであった。
幕末・維新に関するさまざまの文書に、「癸丑以来」という語が頻々と使われているが、この年こそ、アメリカの東洋水域艦隊司令長官ペリーの率いる四隻の黒船が来航して日本の開国をせまった年であった。
それは、幕末の政治的激動の第一歩となり、日本の民族的めざめの出発点となったからである。
松陰もまた、癸丑(きちゅう)の衝撃を江戸で迎えた。
嘉永三年、平戸から長崎を遊歴した松陰は、日本をめぐるきびしい国際情勢にめざめた。
そして翌年、藩主に従って江戸に出た松陰は、安積艮斎(あさかごんさい)に儒学を学び、家学である兵学という技術学のわくを踏み越えて政治哲学の分野に突き進むとともに、技術学の分野では佐久間象山(さくまぞうざん)に洋学を学んだ。
生粋の武士であり、それも藩の兵学師範という家学の伝統のなかで生きてきた松陰が、日本的視野にたって、日本の危機に対処する政治と軍事を考えるという立場にたつための、命がけの飛躍がはじまった。
まず藩に無断で東北旅行に出て亡命の罪に問われ、士籍を奪われ、世禄を失い、兵学師範の肩書きもなくした。
しかし、藩も松陰を惜しんで、十ヵ年諸国遊学ということでその人生は再び開けた。
こうして、松陰が再度江戸に出たのは、ペリー来航の十日前、松陰は斎藤道場に小五郎を訪ねた。
2.3 軍事技術者へ
癸丑(きちゅう)の衝撃は、松陰に第二の命がけの飛躍を決意させた。
きびしい国禁を破っての海外渡航の決意である。
しかし、小五郎の場合は、衝撃への反応は違った。
師の斎藤弥九郎に頼んで伊豆(静岡県)韮山(にらやま)代官江川太郎左衛門の従者となり、のちには門弟となり、洋式軍事技術の習得にあった。
この段階では、小五郎にはまだ政治へのめざめはみられない。
ただ、現実の防衛体制という軍事技術の側面から考えたとき、武士軍隊だけでは力不足であるので農兵取り立てを主張している。
江川の影響であろう。
小五郎が農兵の組織を主張したとき、そこには旧来の封建支配のわくをはみ出した、新しい政策的あるいは政治的思考が作用した。
農民に軍事的負担をかけるならば、その分だけ年貢負担を減ずるなどの反対給付が必要という政策的主張がそのひとつである。
しかし、より重要なのは、農民こそが、「数代にわたって土着のものでございますから、父母の地を賊夷に侵略されたとなれば、上からのお諭しによってはどのようにもふるいたつものと存じます」という、政治的思考である。
この考え方が、のちの長州藩奇兵隊の組織や、明治徴兵軍隊創設の思想へとつながっていくのである。
小五郡の軍事技術者への志向は、さらにロシアの使節プチャーチンの率いる軍艦ディアナ号が下田沖で大地震にあい、津波で破壊されたため、幕府が代替の洋式スクーナー型船を建造したとき、洋式造船技術を習得する努力となって示された。
下田奉行与力(よりき)の中島三郎助(さぶろうすけ)は、蘭学を学び、火技に長じ、軍艦操縦法をマスターしていた。
小五郎は中島に寄食し、二畳半ほどの塩物の納屋に住み込んで教えをうけるとともに、派遣されてきたふたりの船大工に技術を習得させた。
このスクーナー船が完成したのち、さらにその操縦法を視察して、藩にスクーナー船建造のことを建言した。
安政三年(1856)十二月に進水した丙辰丸(へいしんまる)は、この建言に基づいて建造された。
中島は、のちに幕府の軍艦頭取となり、榎本武揚らとともに五稜郭(ごりょうかく)にたてこもって戦死した。
五稜郭軍の首脳が、オランダ留学六年の榎本をはじめ、緒方洪庵塾を経て江川太郎左衛門に学んだ大鳥圭介、開明的な幕吏の永井尚志(ながいなおむね)、それに中島ら、むしろ開明的で有能な先進的技術者集団であったことは興味深い。
2.4 松陰と小五郎
海外密航を決意した松陰はプチャーチンのロシア艦が長崎に来航したと聞いて、長崎に向けて旅だった。
出発に先だって小五郎に会いたいとの手紙を書いたが、藩命で羽田・大 森の地理調査に出向いた小五郎は、松陰の期待に反して、ついに品川からの旅だちに姿を現わさなかった。
長崎でロシア艦をとらえることができなかった松陰は、翌年のペリー再来航にあたって、ついに米艦乗り込みを決行したが、幕府との外交関係を重くみるアメリカ側は、松陰を陸に送り返した。
松陰の命がけの第二の飛躍は失敗し、松陰は投獄、幽囚の身となり、師の佐久間象山も投獄された。
小五郎は、松陰の決意と計画を知っており、のち妹婿となる来原良蔵と、米艦乗り込み用の小舟を手配しようとしたり、失敗後の松陰救出のための金策や人脈を考えたりしてみた形跡がある。
しかし、やがてあきらめ、また軍事技術の勉強にもどった。
造船・海軍の勉強の次は、手塚律三の又新塾で蘭学、さらに又新塾の先輩神田孝平に歩兵調練を学ぶという冷静な知的好奇心ぶりを発揮する。 |

ロシア使節プチャーチン
東洋文庫蔵。
|
松陰の密航への行動は、ペリーの『日本遠征記』に、「知識をもとめるために国法を破り、死をかえりみないふたりの教育ある日本人」(ひとりは松陰の従者金子重輔=かねこじゅうすけ)と、その知的情熱に感激の賛辞を書き残させた。
小五郎の知的欲求のあらわれ方は、松陰と対照的である。
獄中の松陰に宛てた小五郎の手紙は、ほとんどが軍事技術に関する内容のものであり、しかもはつらつとしている。
ひたすらに技術を学ぶことの希望に満ちているかのようである。
一通だけ、藩の政変についての感想を述べているが、楽天的なものである。
松陰と小五郎の違いは、小五郎が相伝の武士の出身ではなく、技術者である医家の出身であることにもよるであろう。
幕末の英才橋本左内をはじめ、長州藩にも、小五郎・久坂玄瑞・村田藏六(大村益次郎)と、医家出身の活動家は多い。
相伝の武士と違って、比較的に自由で合理的な知的環境のもとに育ち、そしてなによりも実地の技術が大きくものをいう世界に人となっただけに、軍事や政治についても、同じような発想をもって臨むことができたのであろう。
現に、小五郎の生家和田家は、小五郎の祖父・実父・義兄と、三代にわたって養子相続である。
血統の相伝ではなく、技術の相伝として成立していた家系の子が、技術者的理性の持ち主として成長したのは当然といってよいであろう。
相伝の武士の子である松陰が、武士の閉じ込められた世界からの飛躍を敢行するには、哲学の革命が必要であった。
技術者的理性の持ち主である小五郎は、それを必要としなかったが、行動的理性人として、哲学なき革命にのめり込む可能性が大きかった。
3 政治的実践へ top
3.1 戊午(ぼご)の年
安政五年(1858)八月、小五郎は、長かった遊学時代を終わり、はじめて役についた。大検使役に任ぜられて江戸桜田邸の番手を命ぜられたのである。
二十六歳であった。
おりしも、アメリカ領事ハリスとの間に、日米条約交渉がつづ・けられており、対外的危機感の高まりのなかで、将軍継嗣問題が、国内領主階級を二分する大政争へと発展しつつあった。
危機の幕閣を支えてきた柱であった老中阿部正弘が前年に死んだあと、幕政を徳川譜代大名が排他的に独占する幕閣の専制のもとに維持しつづけるか、有力な親藩・家門・外様の雄藩主の幕政関与をゆるすか、が政争の基本テーマとなった。
保守的な譜代や大奥のホープが井伊直弼(いいなおすけ)であり、そのシンボルが紀州藩の徳川慶福(よしとみ)であった。
雄藩主や対米交渉の第一線にたつ開明的幕吏のホープは、家門の松平慶永(よしなが=春嶽)であり、シンボルは水戸の徳川斉昭(なりあき)の子で御三卿(田安・一橋・清水の三家をいう)のひとつである一橋家に入った慶喜(よしのぶ)であった。
この、幕府創立以来の大政争に、松平慶永の謀臣として、縦横の活躍をしていたのが、小五郎より一歳年下の、同じ医家出身の橋本左内(さない)であった。
結果は、井伊の大老就任、そして電撃的な条約調印と継嗣決定、反対派に対する大弾圧の開始という、情勢の急転を示す。本来は、条約反対の立場にある井伊が、外交権もまた、将軍すなわち幕閣の専権に属するとの主張を貫徹するため、あえて無勅許調印に踏み切った、思いきった作戦の勝利とも思われた。
十一月、小五郎は帰藩の途につく。獄から解放された吉田松陰は、松下村塾(しょうかそんじゅく)を開いていた。
久坂玄瑞・高杉晋作ら俊秀の青年が松陰のもとに集まっていた。
家柄の高杉を除けば、医者や軽輩の子たちであった。
この時期の松陰は単純な攘夷論者ではない。
みずから海外渡航を企てたように、原則的な開国論者であり、
「一国に居ついたままなのと、天下に跋渉(ばっしょう=歩き回る)するのとでは、人の知愚労逸は、狭い日本でもかけ離れています。
まして、世界ではどうでしょうか」と、知識を世界にもとめて発展することを主張していた。
しかし、松陰は、井伊大老の専権政治がはじまり、老中間部詮勝(まなべあきかつ)が京都に乗り込んで在京の志士狩りをはじめ、安政の大獄の口火を切るや、老中間部襲撃を計画する。
在江戸の門下、高杉や久坂が師を案じて手紙でいさめると、松陰は、「僕は忠義をするつもり、諸友は功業をなすつもり」と、これに従わない。
小五郎が萩に着いたのは、ちょうどこのときであった。
七年ぶりの再会の機会ではあったが、ここでも機先を制して、松陰は、「僕は世の笑いもの、わざわざのお尋ねは必ず無用に存じます」と書き送った。
しかし、小五郎は松陰に会って説いた。
松陰はもとより聞こうとしない。松陰は下獄した。
獄中から、ことばはげしく小五郎に決起をせまった。
そして、安政六年五月、幕命によって江戸に護送され、十月二十七日、小塚原の刑場に斬られた。
十一日、江戸詰めとなって着府した小五郎は、松陰を埋葬した。
安政五年戊午の年にはじまる大獄を画期として、政治情勢は激動しはじめる。
政治的な力と力の対決が、むきだしの暴力的激発となって現われはじめた。
松陰亡きあと、松門の大先輩として、しかも江戸藩邸の要職にあって、小五郎の言動は重きをなしはじめた。
ときに、小五郎は二十七歳。
3.2 奉勅攘夷(ほうちょくじょうい)
万延元年(1860)三月三日、水戸浪士らが白昼の桜田門外に井伊大老の首級(しるし)をあげ、幕閣の権威は泥にまみれた。
久世広周(くぜひろちか)・安藤信正の二閣老を中心とする幕閣は、朝廷の権威をかりて幕府の権威を回復しようとし、公武合体の政策を追求しはじめた。
皇妹和宮(かずのみや)の十四代将軍家茂(いえもち=旧名慶福)への降嫁が、その中心柱であった。
本来、公武の武とは、幕府が無二の武門の棟梁であることを前提としている。
ところが、癸丑(きちゅう)以来、この前提は崩れはじめ、幕閣専制に反対する雄藩は、公すなわち朝廷の周辺に結集しはじめた。
この武門の分裂を力の政策でおさえつけ、朝廷の公と雄藩の武の結びつきを断ち切ろうとしたのが戊午(ぼご)の大獄(たいごく)であった。
しかし、井伊の惨死がこの政策の挫折(ざせつ)を告げて以来、久世・安藤政権は、公=朝廷を、武=幕府にとりこんで、幕府以外の求心力の存在を消滅させようと試みたのであった。
公武合体の実現をはばむ政治的な障害は、井伊の条約無勅許調印による開国と、これに対する公=朝廷の側の深い怒りであった。
この難問を解決するための論理を考えついたのが、長州藩の重職長井雅楽(うた)であった。
長井の論理は単純であり、要するに、朝廷が既成事実を認めたうえで、現実に即した命令を幕府に下せば当然幕府は朝命に服するので、朝威も高まり、国内の平和も回復するであろう、というのであった。
これは、全面的な権力追随・現実肯定、すなわち幕府擁護の理論であった。
幕閣は、長井のこの「航海遠略説」にとびつき、長州藩の政治的比重は強まった。
小五郎は、いち早く、長井の「航海遠略説」に基づく公武周旋策に疑問をなげかけ、批判した。
できないことを要求するのはやめようと主張するならば、なぜ、幕府にできることをやれと要求しないのか、戊午の大獄で処罰された諸侯や幕吏を解放し、幕府の腐敗を正せという要求をしないで、一方的に既成事実の追認を説くのは、いたずらに腐敗した不正義の政権を擁護するだけではないかと。
こうして、小五郎や久坂らは、長井の追い落としと藩論の転換をめざして、活動を開始した。
安藤老中が坂下門外に襲われ、生命は助かったものの、傷癒えての再勤が轟々(ごうごう)たる不人気のうちに、ついに幕閣を退くにいたったとき、長井の主張を藩論とする長州藩の政治的命脈をおびやかす台風の目が西から東へと、ふくれあがりつつ移動してきた。
勅使を奉じての薩摩藩の島津久光(ひさみつ)の東下である。
客観情勢の変化には目もくれず、亡兄斉彬(なりあきら)の遺志の継承者を自負する久光は、公的には無官の身でありながら、藩主忠義(ただよし)の実父として、藩兵を率いて入京し、久光の兵力に期待をかけた尊攘激派の一団を伏見の寺田屋に襲って上意討ちとした。 |

幕末のころの木戸孝允(桂小五郎)
|
斬殺を免れた薩摩藩士のなかには、のちの大山巌(いわお)・篠原国幹(くにもと)・西郷従道(つぐみち)らがいたし、長州藩からの参加予定者のなかには、久坂をはじめ、前原一誠(いっせい)・品川弥次郎・山県有朋らがいたという。
久光が奉じた勅命は、
一、将軍上洛(じょうらく)のこと。
二、沿海五ヵ国の大藩を五大老として国政に参与させること。
三、一橋慶喜(よしのぶ)を将軍後見職に、松平慶永(よしなが)を大老に任ずること。 |
の三項であった。
第一項は小五郎の建策、第二項は廷論に基づき、第三項は久光の主張であったという。
結局、久光は、江戸で自分の主張である第三項を実現(慶永の職名は政事総裁職)し、帰洛の途次、神奈川の生麦で行列の先頭を馬上で横切ったイギリス人を斬殺した。
久光の出府と入れ違いに江戸を去った長州藩主一行は、京都からの迎えの小五郎らと中津川に会し、三日間の密議のすえ、長井の「航海遠略説」に基づく公武周旋の藩論を捨て、奉勅攘夷の路線に転換した。
リーダーシップをとったのは小五郎であった。
しかし、小五郎自身、しばしば行を共にした親友であり、妹婿でもある来原良蔵(くりはらりょうぞう)――長井を支持していた――の引責自殺という人生の苦悩を経なければならなかった。
3.3 流血の自己批判
公武周旋・航海遠略から奉勅攘夷へ、この長州藩論の百八十度の転換は、長州藩内ではひとつの政変であったが、諸藩、特に、幕府サイドの長州に対し、朝廷サイドからの公武合体を推進しつつあった薩摩藩のはげしい不信を招いた。
以後、勝海舟が西郷隆盛の視野を広げてその政治路線の修正をさせ、坂本龍馬が薩長同盟という形でこれを具体化するまで、幕末の政治路線をめぐる対抗関係は、薩長抗争を基軸に展開するのである。
小五郎は、藩論転換の立役者であっただけに、薩摩藩の信頼を回復するための説得外交に奔走する。
しかし、誠意と説得では、政治の問題は解決しない。
要は、行動による表現である。
来原良蔵の割腹自殺は、そのひとつの表現であった。
久坂は、藩論の転換がまやかしでないことを明らかにするために長井を死に追いつめ、攘夷論が口先だけのものでないことをみずからの良心のあかしとするため、品川御殿山(ごてんやま)に新築中のイギリス公使館に焼き打ちをかけた。
上海(シャンハイ)に渡航して、太平天国革命圧殺にイギリス軍などが公然と介入している状態を見聞し、現地の中国人に、鎖国や禁書は国を衰微させる、と書き残して帰国した高杉でさえ、みずから「狂挙」と称しつつ、この焼き打ち行に身を投じていった。
まさに、血をもってする自己批判であった。
藩論のリーダーである小五郎らは、みずからの主張の対決の相手を、幕府政事総裁職松平慶永の政治参謀である横井小楠(よこいしょうなん)にもとめた。
この幕末日本のもっとも卓越した実践的政治思想家横井小楠は、その政治的識見のスケールの大きさ、視野の広さ、読みの深さ、展望の遠大さ、その・いずれにおいても小五郎らの及ぶところではなかった。
幕末・維新期に輩出した政治的人物の群像のなかで、体系的な哲学と明確な理想をもち、しかもそれを現実の政治政策論にまで展開し、実践に移すことのできたただひとりの人物であったといえよう。
両者の対決は、横井の開国論が戦略論であり、小五郎らの攘夷論が戦術論であることを確認しあい、基本的には一致することを了解しあった。
文久二年(1862)九月二十一日であった。
その直後、上京の途についた小五郎は、熱田で土佐の山内豊範(やまのうちとよのり)一行と会って、江戸で得た情報を提供したが、従来の一橋ひとりがしっかりしていて、越前は因循論、土佐は越前の一派という世評がじつは逆であることを土佐藩士に伝えた。
他方では、翌年五月、勝海舟の使者として越前に赴いた坂本龍馬は、幕臣大久保忠寛(ただひろ)から松平慶永宛の手紙を託された。
その手紙のなかに、破約攘夷を主張する「暴論家」たちについて、
「自分の家庭がおさまらないからといって、他人と喧嘩したら家庭がおさまるようになるだろうというのでは、天の道理に反し、後世の笑い草になるであろう。しかし、ほかに下からの変革の・方法もないのであながち無理とはいえない」
と記してあった。
変革の戦術論としての破約攘夷論の意味を認めたのであった。
勝の使者坂本が越前に運んだ手紙であることに重大な意味があった。
そこには、横井・勝・大久保・坂本を結んだ路線をみることができるからである。
3.4 割拠論
再び江戸にもどった小五郎を、長州藩のその後に重大な影響をもたらした事件が待っていた。
小五郎らが推進する政治路線の代表としていただいた藩政の重鎮周布政之助(すふまさのすけ)が土佐藩との間に決定的な感情の疎隔を生じ、長州藩の公的代表の地位を去らねばならなかった事件である。
周布が山内容堂(豊信)の前で、また土佐藩士の前で、二度にわたって、公然と容堂をののしったのである。。
当時、長井を失脚させた長州藩と、参政吉田東洋を暗殺した土佐藩と、尊攘派が政敵を倒して藩政権を握っていたのは、この二藩だけであった。
その土佐藩との対立は、尊攘派が支配する雄藩を結合してゆく方向で外交方針をたて、推進していた小五郎には、かなりの衝撃を与えたようである。
しかし、小五郎は機敏に、次の方針をたてた。
それは、いずれはやってくるであろう長州藩の政治的孤立という事態を想定して、孤立に耐えぬき、他日の「勤王の決戦」に対応できるだけの藩の力量を蓄積しようという、防長二州割拠の主張であった。
周布を帰国させて、割拠体制づくりの改革のリーダーとし、高杉らを改革の先頭にたてよう、この案が採用されなければ、周布も高杉も小五郎も、いったん脱藩同盟しようとまで、固い決意を示した手紙を、おそらくは松島剛三宛に、小五郎は書いた。
そして、この方針が、周布・小五郎・高杉を一貫する政治方針として貫徹していたからこそ、文久三年(1863)八月十八日の反尊攘クーデターにもかかわらず、長州藩尊攘派は瓦解せずにすんだのであった。
文久三年三月四日、かねてからの小五郎の主張が実現して、将軍家茂(いえもち)が入洛(じゅらく)した。
すでに、長州の久坂、土佐の武市半平太(たけちはんぺいた)・平井収二郎(しゅうじろう)ら、それに諸藩の志士が京都に蝟集(いしゅう=群がり集る)し、全国的横断組織を形づくっていた。
長州と土佐以外では、藩という政治的背景をもっていない活動家たちが、全国的な規模での政治勢力としてみずからを組織化した点で、画期的であった。
しかし、彼らは藩の権威にかわる朝廷の権威を絶対的なものと信じ、よりどころとしていた。
武市でさえ、朝廷の権威の絶対性のゆえに、朝廷の権威に服する土佐藩が自分たちを裏切るはずはないと、信じきっていた。
ここに土佐藩尊攘派の政治的もろさがあった。
もともと、周布の容堂罵倒そのものが、朝廷の権威にやむをえず服したのであって、本質的には反尊攘派であることを見抜いでのことであったといえよう。
しかし、小五郎らは、かつてみずから行なった長井追い落としの体験から、朝廷の権威などいつひっくり返るかもしれないことを知っていた。
みずから藩政権を保持し、自分たちの政治路線を実現してゆくのは、藩を上から動かすための朝廷への政治工作によるものではなく、藩内における実力以外にないと考えたのであった。
こうして、割拠論が形成され、八月十八日のクーデターに敗れた長州藩は、割拠体制づくりへと進んでいく。
4 桂小五郎から木戸孝允へ top
4.1 潜伏行
|

孝明天皇の賀茂神社行幸 文久3年、天皇は攘夷祈願のため賀茂神社に行幸した。東大史料編纂所蔵。
|
文久三年(1863)三月十一日、天皇は将軍供奉(ぐぶ=お供)のもとに上賀茂(かみかも)・下鴨(しもかも)両社に行幸して攘夷祈願、三月十四日、幕府は攘夷期日布告、しかし、長州藩の破約攘夷論の実現はここまでが限度であった。
政治的反動の波はヒタヒタと寄せ、白い波頭を見せはじめた。
最大のヤマ場、四月十一日に石清水社頭で天皇みずから将軍に攘夷の節刀を授ける計画は、肩すかしをされ、攘夷の手だてを講ずるためと称して江戸にもどった。
一橋慶喜は攘夷実行不可能と辞表を出した。
そして、老中小笠原長行(ながみち)の卒兵上京を機会に、尊攘派にとっては最大の人質であった将軍家茂は京都を脱出した。
松平慶永は、横井の主張に基づいて、公然と公約を踏みにじった幕府の政治的責任を追及して政権返上を主張し、無断退京して、幕府から逼塞(ひっそく)を命ぜられた。
越前藩論は沸騰し、一国の政治的姿勢を正すために藩の命運をかけて挙藩上京を主張した横井は、藩の安全を望む穏和派に敗れて失脚した。
越前藩の挙藩上京の実現のために、小五郎や坂本は必死の努力をした。そして挫折した。
土佐藩では、すでに尊攘派に対する弾圧がはじまっていた。
こうして、八月十八日、薩摩・会津二藩による反尊攘クーデターが成功し、長州藩は京都における政治的な地位を失った。
百八十度転換した政治路線が、「真実の朕(ちん)の存意」として公布された。
だが、それは、勝海舟が「真に乱世の姿勢、朝威幕威、ともに地に落ちた」と評したように、力と力の激突だけがいっさいを決する時代の到来を告げるものであった。
忠実に攘夷を実行して外国船を破撃し、しかも国内で孤立した長州藩は危地に陥った。
藩内反尊攘派が、この機に乗じて藩政権奪取に動いた。
だが、この反動を挫折させたのは、奇兵隊総督の高杉晋作らであった。
外敵に抗することを目的に、幕藩的な身分秩序のわくをこえて創設された奇兵隊は、藩の機構と秩序をよりどころとする反尊攘派の影響力が及ばない「聖域」であり、しかも藩内最精鋭の軍事力として、尊攘派の切り札であった。
藩内反動への反撃に成功した尊攘派は、しかし、分裂した。
勢いをかって、一挙に京洛の軍事的制圧を実現し、中央政局における藩の地位を回復しようと主張する進発派と、周布・小五郎・高杉らの割拠派である。
進発派が、いぜんとして、八月十八日のクーデター以来の尊攘派の伝統を継承しているのに対し、割拠派はもはや、信頼に値しない「叡慮」を手に入れることなどは無視して、「二州一致、容易に動揺しないことを示せば」おのずから「正議」への道は開けると考えたのであった。
しかし、小玉郎は、高杉の反対を押しきって京都に潜行し、長州藩の外交的立場の回復に努力する。
進発論に沸き立つ藩論を鎮静するには、京都における長州藩の立場を少しでもよくする以外にないと考えたからである。
正面から進発反対論をぶっつけた高杉は、力尽きて、無断東上、脱藩の罪に問われて投獄された。
周布もまた、酔余、抜刀して獄に赴き、高杉の軽率をなじって逼塞(ひっそく)の身となった。
新選組の池田屋襲撃は、長州藩進発派を激昂させ、元治元年(1864)七月、いわゆる蛤御門(はまぐりごもん)の戦闘となり、長州藩は敗北し、「朝敵」の名のもとに、軍事的にも孤立した。
小五郎は、潜伏行を開始する。
4.2 芸妓幾松
小五郎は、蛤御門の戦闘に先だつ四月、京都留守居を命ぜられている。
前年八月のクーデターで中央政局における地位を失ったとはいえ、幕府と戦争状態に入ったわけではなく、したがって長州藩の駐京都外交代表部は存置されていた。
そこの公式代表に任ぜられたとなると、いちおうの外交特権的な権利を保持することになる。
いわば、孤立した長州藩で、京都において公然と合法的政治活動ができるという貴重な立場にあった
池田屋事件のとき、小五郎が要領よく動いて難を免れたこと、蛤御門の戦闘開始後も長州藩部隊と合流する機会がありながら合流しなかったことなど、小五郎の行動についての疑問は、この外交官として公式に登録された京都留守居であるという地位を抜きにしては解くことができない。
法の保護外におかれた潜伏者である志士たちの池田屋の会合に、公式の外交官である小五郎が深入りすることはできないし、まして開戦時の外交官には戦闘員とは違った任務があった。
しかし、長州藩敗戦後の京都では、もはや長州藩外交代表部の存置も、外交特権も認められなかった。
藩邸員たちは藩邸に火をかけて京都を退去したが、小五郎だけは単身帰京して潜伏した。
戦時戒厳下の敵地に、幕府の公敵筆頭ともいうべき小五郎が、まったく藩からの連絡も断って潜行したのであるから、危険この上もなかった。
小五郎の潜伏行を知っていたのは、長州藩御用商人の今井太郎右衛門であり、今井と小五郎の連絡をとったのは芸妓幾松(いくまつ)であった。
幾松が今井家から夜ひそかに二条大橋下に潜む小五郎に握り飯を運んだというエピソードはこのときのことである。
捕吏に包囲された坂本龍馬に浴室から飛び出して裸のままに危急を告げた寺田屋のお龍の話とともに、幕末政争史をいろどるもっともあでやかなロマンスである。このとき、小五郎三十二歳、幾松二十二歳。
しかし、このロマンスは五日間で終わり、戦後の京都の情勢を見きわめた小五部は、但馬(たじま=兵庫県)出石(いずし)に脱出し、広江孝助と称して小店の商人に身を変じた。
京に残した幾松の身を案じた小五郎は、幾松を対馬(つしま=長崎県)に落とし、対馬藩の同志にその身の安全を託した。
そして、龍馬とお龍の間とは逆に、小五郎と幾松のロマンスは、幸福なことに実を結んだ。
木戸孝允夫人松子となり、両人とも病没年齢こそ偕老(かいろう)の域に達しなかったが、同穴のちぎりを実現したのであった。
出石潜伏中、長州藩中にだれひとりとして小五郎の所在を知るものはなかった。 |

木戸孝允夫人松子像(幾松)
|
いわゆる第一次征長後に長州藩が恭順を誓ったとき、幕府から個人名をあげて追及をうけたのは、小五郎と高杉のふたりであった。
しかし、小五郎は所在不明、高杉はいち早く藩外へ亡命していた。
恭順の代償として、多くの生命が絶たれた。
周布をも含めた、いわゆる「五大夫十一烈士」とよばれる人たちの生命である。
そして、第一次征長と藩の恭順、四ヵ国連合艦隊の下関攻撃と講和による攘夷方針の最終放棄、亡命中の高杉の帰藩と武力反乱による藩政奪還、こうして「武装恭順」という名の、かねてから小五郎が主張していた割拠体制が確立した。
だが、小五郎の所在は知れない。
幾松=松子を通じて小五郎の所在がわかったのは慶応元年(1865)二月、小五郎が帰藩したのは四月であった。
4.3 薩長同盟
帰藩したものの、長州藩はなお「朝敵」であり、小五郎は幕府の追及をうける身であった。
桂小五郎は、藩命によって木戸貫治(きどかんじ)と名を改めた。
小五郎潜伏中の日本における最大の政治的事件は、勝海舟と西郷隆盛の出会いであった、といってもよいかもしれない。
勝によって、大局的な政治的視野を開かれた西郷は、もはや幕府が救いがたいことを悟らされ、割拠体制をとった雄藩の連合の力こそが日本の将来を決定することを教えられた。
とすれば、当の西郷が総督参謀となって討とうとしている長州藩こそ、じつは連合すべき相手ではないか。
しかも、割拠体制下に「正藩合一」を追求する長州藩にとっても、こうなれば、まさに不倶戴天(ふぐたいてん)の「薩賊」こそ、合一すべき相手ということになる。
「横井の思想を、西郷の手で行なわれたらもはやそれまでだ」と考えていた勝自身が、横井の思想を西郷に吹き込んだ。
横井・勝・坂本とつらなる思想の縦軸を中軸として、西郷の薩摩と木戸の長州との政治的同盟の横軸が形づくられたとき、まさに勝のいうとおり、幕府の運命は「もはやそれまで」となるのである。
こうして、高杉が実現した割拠体制を基礎として、木戸は薩長同盟を実現した。
幕府打倒の政治的前提は成立した。
しかし、厳密にいえば、もうひとつの条件が必要であった。
幕府を軍事的に圧倒する条件の整備と、整備された軍事力の運用にあたる軍事指導者の出現である。
そして、木戸のそもそもの政治的生涯の出発点は、そのような軍事的指導者への道であった。
みずから最新の軍事技術をマスターし、強力な軍事力を建設し、すぐれた軍事的指導者として活動することを夢見た青年小五郎の人生を、政治家木戸への方向に向け替えさせたのは、師の吉田松陰を刑死させた戊午(ぼご)の大獄(安政の大獄)を画期とする政治情勢の激動と、松門の大先輩としてひときわ重きをなした彼自身の地位や家格にある。
その木戸が自分にかわる軍事的指導者として、しかも木戸自身の努力をもってしてはとてもそこまでは到達できないだけの力をそなえた軍事的天才を発見したのが、村田蔵六(むらたぞうろく)すなわち大村益次郎(ますじろう)であった。
木戸と大村の出会いは、安政六年(1859)夏のことであったが、同じ医家の出身とはいえ、城下を離れた農村の医師の出身にすぎなかった大村が長州藩の軍事的指導者に登用されるには、その軍事的才能を見抜くだけの素養を身につけていた木戸との親交によるところが大きい。
出石(いずし)から帰藩した木戸は、大村を長州藩の兵制改革の中心的指導者に任じた。
大村は、封建軍隊とは違った、奇兵隊をはじめとする諸隊の兵卒の自発性と最新の輸入小銃をよりどころとし、ヨーロッパの近代戦法である散兵戦術を採用することを可能にした。
せまりくる第二次征長、長州藩側からの四境戦争で、対幕決戦の作戦計画をたてた大村は、みずから石州口軍の参謀として戦闘の指揮をとり、実戦における用兵家としても天才的な手腕を発揮したのであった。
4.4 討幕
薩長同盟を政治的な力とし、四境戦争に軍事的勝利をおさめた長州藩は、公然と討幕に踏み切る。
しかし、慶応三年(1867)四月、木戸は、無二の盟友高杉を失った。
進発論に断固として反対し、藩内でも孤立し、投獄・亡命、あるいは潜伏と苦難ののち、軍事的割拠体制と政治的対薩同盟を実現し、四境戦争に勝利をおさめるまで、木戸と高杉は長州藩の軌跡を決した不可欠の両輪であった。
薩摩における大久保利通と西郷のように、その高杉の病没は、ひとつの時代の終幕を告げるものであった。
そして、この時代の転換は、木戸に新しい位置づけを与えた。
同士的集団として組織されてきた大村や松門の軽輩出身者たちを、新しく、新国家建設を担う開明的官僚群として組織する任務が課せられたのである。
しかし、なお形式的には「朝敵」である長州藩の木戸に、京都の政治的檜舞台への花道が開かれるには、王政復古クーデターを必要とした。
討幕の密勅に対して、将軍慶喜の政権返上という虚々実々の政治的駆け引きのなかで、王政復古クーデターは、綿密にしくまれた二重クーデターであった。
西郷と木戸との間の軍事的密謀を基礎に、大久保と岩倉具視との間の政治的密謀として計画された。
クーデターは、まず旧幕府と旧幕寄りの諸藩に対しての、土佐・芸州・尾州・越前のいわば政権返上路線を推進する雄藩までをもまきこんだクーデターとしての王政復古として実現された。
しかも、このクーデターは、土・芸・尾・越の政権返上路線を軍事的に制圧して、武力討幕の道を開く雄藩連合内部における薩・長のクーデターという性格をももった。
だが、現実の武力討幕に転化するには、もうひとつの謀略、旧幕府とそれに従う諸藩に対する軍事的挑発を必要とした。
この謀略の主役が西郷であった。
こうして、慶応四年一月三日、鳥羽伏見戦争の火ぶたが切られ、旧幕軍は敗走した。
木戸が新政府の太政官に出て徴士(ちょうし=藩出身の宮廷官僚)となり、新国家の官僚政治家としての第一歩を踏み出したのは一月二十五日のことであった。
5 開明派官僚の総帥 top
5.1 権力者の変革論
成立した明治新政府は、戊辰戦争の解決と取り組まなければならなかった。
もともと、広大な領地と強力な軍事力、有能な吏僚群を擁する幕府から、直轄領も直轄軍事力も、すぐれた人材ももたない朝廷への権力の平和的移行などという構想は、実質的な幕府温存策でしかなく、だから、新国家の建設には武力討幕が必須とされたのであった。
しかし、変革のために必要とされた内乱であっても、どの程度の内乱が必要であったかが問題であった。
ある意味では、内乱の程度が変革の程度を決定するといえた。
しかし、内乱が深まれば、内乱は民衆反乱に転化して新政府のコントロールがきかなくなるおそれがあり、しかもこうした混乱に乗じて、イギリス・フランスなどの諸列強が軍事的介入を行なう危険があった。
木戸は、新政府首脳のなかでは、討幕戦争の徹底的遂行論者であった。
「御一新にあたって確固とした基礎をすえるには、戦争より良法はない」「関東の戦争はじつに大政一新の最良法」などと主張している。
いわば、内戦を通じて幕藩制の解体を促進しようとする考え方であった。
しかし、内戦の遂行を通じて幕藩制の解体を推し進めれば進めるほど、大量の失業武士=浪人が生ずる。
これが封建領主間の戦闘であれば、勝者が自分の家臣団を強化するために召し抱えることもできるが、封建制解体の内戦であってみれば、そうはいかない。
「いずれにしても国内のことであるから、内に浪人がたくさんあっては、つねに政治にとってははなはだ邪魔ものである」、木戸はこう考えこむ。
この邪魔ものをどう処理するか。
さらに、もうひとつ悩みがあった。
内戦の徹底的遂行といっても、新政府は直轄軍事力をもたない。
その軍事力は、薩摩藩の軍隊であり、長州藩の軍隊であった。
だから、幕藩制解体戦争の成功は、特定の藩の軍事力したがって政治的発言権の強大化につながり、必ずしも新政府の権力の強化につながらない。
もっとも、薩摩藩にしても長州藩にしても、藩主を頂点とし、家格や身分の秩序に基づいて組織されていた古い藩制は崩れ、もっぱら戊辰(ぼしん)戦争を戦った軍事的指導者層が藩の実権を握るにいたった。
この勝ち誇った、しかも新政府の統制外にある諸藩の軍隊をどうするか、である。
失業武士の処理と、横暴な討幕軍の処理と、両方を一挙に解決するために、木戸が考えついたのが征韓論であった。
木戸の征韓論主張のはじめは、明治元年(1868)十二月、東北の戦塵がやっとおさまったばかりのときであった。
5.2 木戸・西郷・板垣
戊辰戦争が終わったあと、藩地に凱旋した各藩の軍隊に対して、新政府はまったく統制力をもたなかった。
しかも、諸藩とて、藩の統制のもとに戦ったのではなく、新政府の指揮下に戦った軍隊に対して、藩としての統制力は発揮できなかった。
統制力を発揮できたのは、各藩軍を率いて各地を転戦した武将たち、薩摩では西郷隆盛、土佐では板垣退助であった。
長州では大村益次郎か山県有朋ということになるのであろうが、そうはなっていない。
戊辰戦争後、大村は木戸の軍事幕僚的地位にあって新国家の軍制のことに任じ、山県は外遊した。
木戸は、軍事と政治のきびしい分離を主張していた。
軍事力の統率者が政権を支配することを極度に警戒していた。
だから、長州藩では、西郷や板垣のような軍事的指導者から藩政の実権の掌握者になるというようなことは生じなかった。
さればといって、文官である木戸が藩政に独裁的権限をふるうというわけでもなかった。
むしろ木戸を中心に結集した一群の集団が、やや未熟な官僚集団を形づくって、戊辰後の藩政をリードしたと考えてよいであろう。
これらの集団の頂点にある存在として、木戸は長州藩の象徴的存在であった。
戊辰戦争を終えて帰藩した西郷は、その率いる軍事力を背景として、一挙に藩政を改革し、旧来の藩制や機構を打破して軍事政権をつくり上げてしまった。
それは、形のうえでは島津藩であったが、実質的には西郷王国であった。
王国は廃藩後もつづき、西南戦争にいたるまで、中央政府は鹿児島県政に介入できず、形式上の県令は島津久光に近い大山綱良(つなよし)、実質的な支配勢力は西郷直系の私学校党ということになるのである。
会津攻略戦で卓越した武将としての手腕を発揮した板垣もまた、その声望を土佐藩の改革に向けた。
土佐藩軍事力もまた、薩摩藩と同じように、割拠的軍事体制を築き上げる方向に進みつつあった。
谷干城(たにかんじょう)や片岡健吉を指導者とし、藩軍務局を中心とし、土佐藩のみならず四国地方全体を結集した軍事的割拠体制を形づくるべく、四国会議=金陵会議を成立させた。
驚いた中央政府は、四国会議の解散を命ずるとともに、板垣と後藤象二郎が帰藩して藩政改革にあたった。
明治三年のことであった。
会津攻略戦の経験から、武士独裁の藩体制が軍事的にいかにもろいものであるかを痛感した板垣は、軍事独裁政権を築いた西郷とは逆に、むしろ長州藩奇兵隊の発想に近い形の、農工商をも含みこんだ藩体制をつくり出そうとした。
士族中心ではあるが、四民平等を唱え、藩議院制を創設するなどの改革が行なわれた。
改革をそのような方向に向けさせたのは、薩摩藩と違って、土佐における農民一揆の力の大きさであった。
板垣自身、戊辰戦争の軍隊指揮官として、東山道を関東平野に進出したとき、広大な関東の野をおおい尽くした世直し一揆の波のなかに孤立し、補給も途絶し、進退きわまった経験をもっていたのであった。
長州藩は、薩摩や土佐と違って、戦後の大きな課題を、肥大した藩軍事力の整理であると考えた。
しかも、整理の対象とされたのは、幕末・戊辰の動乱にもっとも活躍した諸隊であった。
非常の場合に民衆の自発性を軍事的に組織し、不用になれば使い捨てにするという、のちの帝国軍隊の思想がここにはじめて顔を出したのであった。
この軍事力整理に不満の諸隊士の反乱を、木戸はみずから陣頭にたって武力で鎮圧し、長州藩体制を確固としたものにしたのであった。
その点では、なお封建的な軍事的割拠体制を追いつづける薩摩の西郷、民衆のエネルギーをくみ上げて国家の力量に転化させるための政治体制の実現をめざす土佐の板垣に対し、強力な中央集権国家の形成とこれを運営する官僚体制の創出を急ぐ長州の木戸と、三藩三様の改革のなかに、それぞれの追求する政治目標を見出すことができる。
5.3 中央集権国家論
成立した明治新政府が最初に掲げた綱領ともいうことができる五箇条の誓文の冒頭が、「広く会議を興し」となっており、越前の由利公正、土佐の福岡孝弟らの「列侯会議を興し」という原案に木戸が手を加えたことは知られている。
まだ直轄領も直轄軍事力もない新政府が、いわば雄藩連合の上にその政権の基礎を置こうとした公議政体論に対し、木戸は早くも集権国家の構想を対置し、貫徹したのであった。
この箇条がけっして民主主義的な国家構想を示したものでないことは、翌日に公布された民衆向けの「五榜(ごぼう)の掲示」では、民衆の強訴(ごうそ)・徒党・逃散(ちょうさん)の禁を掲げている。
現在でいえば、団体交渉権・団結権・争議権の禁止である。
木戸のこの集権国家構想は、しかし、制度的にも機能的にも整備され、よくコントロールされたものでなければならないと考えられていた。 |
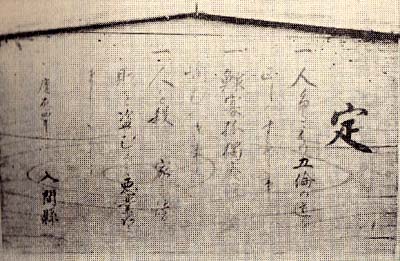
五榜の高札
五箇条の誓文の翌日に、民衆に向けて太政官より公示された。
|
つまり、制度としては立憲制、機能としては集権的専制という構想である。
こうした構想が出てきたのは、木戸の考えた国家目標が、「万邦対峙(ばんぼうたいじ)」つまり早く日本を欧米諸列強とはりあえる地位に引き上げることにある、という一点にしぽられていたからにほかならない。
木戸に限らず、新政府に出仕後まもなく暗殺されてしまった横井小楠を除いては、この「万邦対峙」以上の国家目標をもった人物が新国家建設の中心的な担い手のなかにいなかったことは、明治新国家の悲劇であった。
同時に、そのゆえに、哲学のない国家目標を政治構想として展開するためのリーダーシップをとらなければならなかった、維新後の木戸の悲劇があった。
木戸は、新政府にあって、いち早く、廃藩の前提として版籍奉還(はんせきほうかん)を主張し、実現し、集権国家への第一歩を基礎づけたが、他方では、「政治の邪魔もの」処理の当面の策である征韓論(せいかんろん)の実現と、政治構想展開のための洋行の実現との二兎を追い、動揺しつづける。
そして、そのいずれに対しても、最大の「邪魔もの」として木戸の前にたちはだかったのが、薩摩藩の割拠体制であった。
明治三年(1870)七月二十七日、薩摩の士族横山正太郎(森有礼の兄)が征韓論に反対し、集議院の門前で抗議自殺するに及んで、政府は狼狽(ろうばい)した。
木戸は、征韓論を断念した。
そして、その年の秋、西郷が兵力を率いて上京し、クーデターを敢行するとの噂が木戸をおびやかしはじめた。
5.4 木戸派官僚群
木戸の集権国家構想において、その機構を支える中心は、一群の官僚の集団であった。
幕末、すでに洋行の経験をもつ長州藩出身の後輩、井上馨(かおる)や伊藤博文もその中心人物ではあったが、木戸を総帥とするこれら開明的官僚群の結集の中核となったのは、奇妙なことに、長州出身でもなければ、洋行の経験もなく、幕末の動乱にもこれという足跡をとどめていない肥前(佐賀県)出身の大隈重信であった。
この一群の集会所となった大隈邸は、「築地の梁山泊(りょうざんぱく)」とよばれた。
彼らは、巨大な国内行政官省である大蔵省と民部省の要職を兼ね、その団結の固さとすぐれた行政能力の発揮によって、あたかも政府そのものであるかのような観を示していた。
明治三年(1870)六月当時、大隈は大蔵大輔兼民部大輔、伊藤は大蔵少輔兼民部少輔と、両省の次官を兼ね、井上は造幣頭兼大蔵大丞兼民部大丞で、大蔵省外局長官と両省の局長を兼務していた。
当時の内閣は、右大臣三条実美、大納言徳大寺実則・岩倉具視、参議副島種臣(肥前)・広沢真臣(長州)・佐々木高行(土佐)・斎藤利行(土佐)・木戸孝允(長州)・大久保利通(薩摩)の顔ぶれであった。
政争の発端は、木戸が大隈の参議昇任を提案したことにはじまった。
国内行政官省に絶大な影響力をもつ大隈を入閣させた場合、政府はもはや完全な木戸派官僚群の独占する政府となる。
大久保・副島・佐々木・広沢の四参議は、木戸に内密で三条・岩倉・徳大寺と会し、大隈を参議に任命するならば四人そろって辞職すると、強請した。
佐々木は、木戸の意図を
「長州人は木戸はじめ大隈の肩をもつ景況である。これはつまるところ薩摩を忌み憎むことから出ている」
と推定し、日記に記している。
いわば集権的国家体制の確立を急ぐ木戸派官僚群と、これに対立して軍事的割拠体制をとる西郷の薩摩の、ぬきさしならぬ激突を恐れての大久保らの強硬な反対であったといえる。
さすがに、木戸は、この政争における自分の判断の誤りを悔いている。
事前に佐々木の了解はとりつけてあったし、土佐を味方とし、広沢ともども閣議の多数を制することができるとの読みは、完全に狂ったのであった。
特に、広沢の裏切りは木戸にはこたえた。
木戸は伊藤に宛てた手紙のなかで、
「殊にまた驚嘆したのは広沢がこのたびの一件に大いに荷担したこと」
「わたくしにはなはだ遺憾至極であるのは、広沢の一条もあってただ顔を赤らめるほかなく」と書いている。
この事件の半年後、参議広沢は殺害され、犯人はついにわからずじまいとなるが、事件の背後に木戸の名がささやかれたのは、このときの木戸の屈辱感の深さのゆえであろう。
しかし、広沢暗殺の背景木戸説は、実際にはほとんど成立の余地がない。
木戸は敗北し、大蔵省と民部省は分離された。
しかし、この敗北の教訓は、一年後の、西郷との対決にあたって、巧みに生かされた。
5.5 木戸と大久保
この政争は、薩南に寓居する西郷と、行政府を制する木戸との対立が、内閣対蔵・民の形で現われたものであった。
蔵・民分離の発令が七月十日、横山正太郎諌死事件が七月二十七日、木戸の政治的敗北がつづいた。
木戸は出勤をやめ、かつ洋行のことを強く願った。
しかし、木戸の下野洋行が「恐らく是より有議達材の士、離散せんとす」るきっかけとなることを恐れた三条は、木戸が意をひるがえすことを説き、岩倉もまた木戸の説得にあたった。
木戸派官僚群の有能さゆえに、その内閣への進出をはばんだものの、この官僚群を失っては、政府はなすすべをもたなくなる。
こうして、蔵・民分離ののち、木戸の内閣復帰をもとめて、大隈の参議昇任という妥協が成立した。
しかし、木戸はなお出勤しない。、
横浜にあった木戸の腰を上げさせたのは、三条からの一通の飛報であった。
それには、薩藩のことについて大久保から内談の事件があり、ぜひ足下とも至急談合したい、とあった。
事件の具体的内容は不明であるが、木戸の帰京をうながした林友幸の手紙には、時機を失すればどんな変事になるかもしれない、とあるところから考えると、これ以後の木戸の書いたものにしばしばほのめかされている、西郷の率兵上京・クーデター説であろう。
木戸が真に対決すべき本命が姿を現わした。
それまで、すねた感じの木戸は人が変わったように動きはじめた。
薩摩に宥和的であるためにことごとく木戸と対立した大久保も、もはや腰をすえたようである。
十月十三日、木戸と大久保は会し、意志統一をはかった。
一般に木戸の日記と大久保の日記を比べると、大久保の日記は無味乾燥なまでに簡潔で事務的であり、これに対して木戸の日記は感情の起伏をむきだしに、蜿々と書きつらねることが多く、両者の性格の相違を示している。
ところが、この日ばかりは、両者が入れ替わったかと思われるほどで、木戸は「心事を語り前途を論ず」とのみ書き、大久保は長々と自己の「心事」を書きつらねている。
木戸の決然たる態度が示されている。そして、木戸と大久保の同盟が成立した。
5.6 同床異夢
事態解決の道はひとつしかなかった。
西郷を中央政府にとりこむことであった。
しかし、それを実現する条件は西郷らの要求をある程度いれることであった。
そのひとつは、まだ解決がついていない政府の直轄軍事力をどういう形で編成するかであった。
木戸派の徴兵軍隊論の前には、精強を誇る薩摩の士族軍隊を率いる西郷がたちはだかっていた。
この、薩摩の士族軍隊を中核として政府直轄軍事力を創設する、それは、木戸の西郷に対する大きな譲歩であった。
しかし、木戸はぬけめがなかった。
ひとつは、板垣と板垣の率いる土佐の軍事力を、この構想のなかに引き込み、政治的・軍事的に巧みな力のバランスをとることに成功したことである。
もうひとつは、おそらくは、中央軍を士族軍隊で固める代償として、地方軍すなわち鎮台を徴兵軍隊で編成する方針を西郷に容認させたのではないかと思われる。
西郷にしてみれば、どうせ烏合の衆の地方雑軍などどうでもよかったのではないか。現に西郷が征韓を主張したとき、鎮台兵を統轄する陸軍卿山県有朋はつんぽ桟敷に置かれたままであった。
こうして、勅使岩倉を奉じて大久保は鹿児島に赴いて西郷の上京を説得し、大久保・西郷は山口で木戸と合流し、三人同道して高知に赴いて板垣の協力と上京を説いた。
明治四年(1871)二月十三日、薩長土三藩の兵を献じて親兵とし、ここに中央直轄の軍事力が成立した。
しかし、西郷と木戸の連立という同床異夢の内閣が成立したのは、六月二十五日のことであった。
西郷の入閣は、かねてからの憎悪の的であった大隈らの追い落としをひとつの目的としていた。
大隈は参議を免ぜられて、大蔵大輔に左遷され、大蔵卿に新任した大久保の下僚とされた。
西郷は国許に対して、「このたびは俗吏も余程落胆いたし、濡鼠(ぬれねずみ)の如くなってしまった」と勝ち誇った手紙を書き、逆に伊藤博文は、この不当な人事に対する痛憤と絶望の手紙を井上馨に送った。
これほどまでにして、木戸が実現しようとした当面の政治的目標はなんであったか。
それは、廃藩の一事であった。
これさえ実現すれば、集権的国家体制の実現は非常に大きな前進を示す。
しかし、その実現には、諸藩の反対をゆるさぬ強力な軍事力を必要とする。
上京前には廃藩に消極的であった西郷も、上京してみて廃藩が不可避であることを悟った。
もはや十年も藩は維持できず、この運命は人力の及ばないことを知った、といういかにも西郷らしい悟り方であった。
七月十四日、廃藩置県(はいはんちけん)断行、そしてこのとき木戸はあざやかな手をうった。
このうえは、薩長土肥が団結して中央政府を固める必要があるという理由で、西郷と木戸に加えて、土佐の板垣と肥前の大隈を参議に任命するという主張を通したのであった。
大隈の失脚わずか二十日間で復職という、逆転の離れ技(わざ)であった。
5.7 洋行と死
廃藩置県後、木戸は大久保とともに、岩倉大使一行の欧米巡遊に、副使として参加する。
欧米の近代国家の機構と制度を学んだ若い官僚たちは、ぞくぞくと育ちつつあった。
すでに一群の集団、大隈を中心とするいわゆる「築地の梁山泊(りょうざんぱく)」の域をはるかにこえはじめたこれらの官僚群を統率する政治家としては、大久保も木戸も、その識見の限界に達していた。
一大飛躍なしには、集権国家体制を整備し確立するためのリーダーシップを保持できない。
このことがふたりを長期の外遊に駆り立てた理由であった。
しかし、外遊中に、大久保と木戸の地位は逆転する。
冷徹な、非情なまでの実務家である大久保は、官僚を統卒する官僚としての能力をたちまち身につけ、発揮しはじめた。
その器であるとは言いがたかったが、なまじ新国家のイデオローグとしての役割を演じつづけなければならなかった木戸は、実務的官僚群から孤立しはじめた。
洋行中、木戸の子飼いであった伊藤の心は、木戸から大久保へと動いていった。
病気が木戸を気弱にしたこともあって、帰国後の木戸には、もはや廃藩前の木戸の精彩はない。
征韓論破裂後、再び薩摩の軍事的割拠体制のなかに西郷が閉じこもったあと、中央政府は実質的には大久保の独裁政権と化した。
かつて、木戸を頭首と仰いだ開明派官僚の大隈や伊藤は、大久保の手足となって活動した。
中央政局の脇役の地位に退いた木戸は、いまや確立した集権政府と徴兵軍隊を擁した大久保と、薩摩士族軍隊の驕兵を率いる西郷との死闘のさなか、死の病床にあった。
明治十年(1877)五月二十六日、木戸は京都で病死した。
「西郷、もう大抵にせんか」と叫んだという。
西郷の死に先だつこと四ヵ月、大久保の死に先だつこと一年たらず。
年四十五歳、いわゆる維新の三傑のなかで、もっとも早く、もっとも若く、しかし、ただひとりだけ畳の上で死んだ。 |
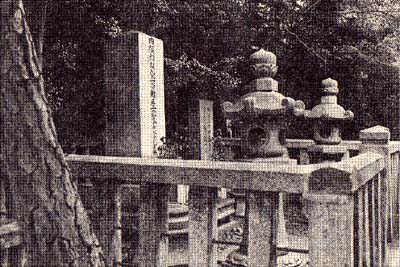
木戸孝允の墓 京都市霊山。
|
参考図書
大江志乃夫『木戸孝允』中央公論社(昭和四十八年)
大久保利謙編『明治政府・その実力者たち』新人物往来社(昭和四十一年)
冨成博『木戸孝允』三一書房(昭和四十七年)
木戸孝允略年譜 top
天保四年(1833)
天保十一年(1840)
嘉永二年(1849)
嘉永五年(1852)
嘉永六年(1853)
安政五年(1858)
万延元年(1860)
文久二年(1862)
文久三年(1863)
元治元年(1864)
慶応元年(1865)
慶応二年(1866)
慶応三年(1867)
明治元年(1868)
明治二年(1869)
明治四年(1871)
明治七年(1874)
明治八年(1875)
明治十年(1877) |
一歳
八歳
十七歳
二十歳
二十一歳
二十六歳
二十八歳
三十歳
三十一歳
三十二歳
三十三歳
三十四歳
三十五歳
三十六歳
三十七歳
三十九歳
四十二歳
四十三歳
四十五歳 |
萩城下に藩医和田昌景の子として誕生。通称小五郎。号松菊。
隣家の藩士桂孝古(家禄九十石)の養子となる。
吉田松陰の門に入る。
江戸に遊学。斎藤弥九郎の剣術道場に学び、のちその塾頭となる。
江川太郎左衛門に洋式兵学を学び、海岸測量に従事する。
安政の大獄。千住小塚原の吉田松陰の刑死体を引き取る。薩摩・越前・水戸などの尊攘派志士と交わる。
帰国し、有備館館長となる。竹島開拓を大村益次郎と幕府に建議。
上洛。周布政之助とともに長井雅楽の航海遠略説を廃し、尊王攘夷の藩論を確立。
勝海舟と面談。八月十八日の政変後帰国して武装上京論をおさえる。すぐ上京し、洛中に潜伏して尊攘派再起の暗躍をつづける。その間芸妓幾松(のちの松子夫人)の庇護をうける。
京都留守居となる。池田屋事件に危うく難をのがれる。禁門の変後但馬出石に潜伏。
正義派、藩権力を握り、帰国。下関にて中岡慎太郎・坂本龍馬と相次いで会見。木戸貫治と改名。
長州藩を代表して大久保利通・西郷隆盛と会見し、薩長連合成立。準一郎と改名する。
山口にて大久保利通と密議し、討幕挙兵の細目につき六ヵ条を協約。
王政復古後太政官徴士となり、総裁局顧問、ついで外国事務掛兼任となる。「五箇条の誓文」を完槁。
版籍奉還を主張し推進する。支那朝鮮巡遣使節を任命(翌年中止)される。長州藩諸隊の反乱を鎮圧する。
参議となり、西郷隆盛らとともに廃藩置県を断行。全権‐副使として欧米に派遣される。
征台の役に反対して下野。
大阪会議後参議に復し、地方官会議長となる。
西郷の西南戦争反乱を憤りつつ病没。 |
top
****************************************
|