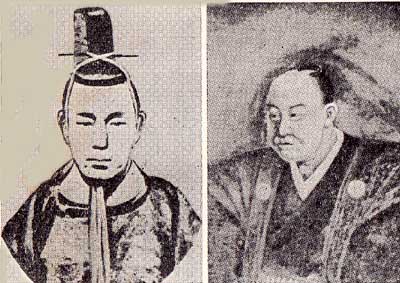|
****************************************
Index 1
2 3 4
5 6
3 土佐勤王党
1 土佐に帰る top
「徳兵衛、しばらくであったな。」
竜馬がふらっと、日本橋の徳兵衛の店をたずねたのは、安政元年の五月の初めでした。
徳兵衛は竜馬が江戸にのぼる途中で知りあった商人で、紙問屋をいとたんでいました。
「これは坂本さま、ようこそおいでくださいました。サア、どうぞおあがりください。
しばらくお見えにならないので、心配しておったところですよ。一段と、腕をあげられたそうですね。」
徳兵衛は奥の部屋に、竜馬を通して、おせじぬきにいいました。
桶町の千葉道場では重太郎におとらない腕だと、もっぱらの噂でした。
「黒船騒ぎのたびに品川沖の警備にかり出されておったので、思ったように道場へもかよえず、上達もままならん。
江戸に来て一年、もう土佐に帰る期限が来てしまったし、竜馬はその挨拶に徳兵衛の店に立ち寄ったのです。
竜馬が藩庁からもらった剣術修業の期限は、ひとまず一年でした。
「期限ぎれとはもったいのうございますね。
中目録免許はすでにいただかれて、残るは大目録皆伝のみでございましょう。
その日も遠くないとか、巷(ちまた)ではいっておりますが………。」
徳兵衛は竜馬の噂を聞くたびに、嬉しくてなりません。
北辰一刀流の最高位までもう一息の竜馬に立ちよってもらえるだけでも、鼻が高いのです。
江戸の剣士のなかでもしだいにその名をあげている竜馬に、道中の道連れになってもらったことは徳兵衛の自慢の種でした。
「また出直してくるさ。」
「しばしのお別れですね、今夜はゆっくりと、天下の動きなど語り聞かせてください。お酒など用意いたしましょう。」
「いや、わしは天下の事には疎(うと)いたちで、とても語ることなどできんが、武市半平太のいうとおり、ロシア、エゲレスも和親条約を結んだ。オランダもこれまでの顔にものをいわせて、新しい条約を願い出ている。」
竜馬がおもむろにしゃべり始めたときでした。
いきなり、グラグラッと、家を付き上げるように地震が襲ってきました。
「これはいかん!」
竜馬は顔色をかえました。揺れは中々おさまりません。
さいわい徳兵衛の家では怪我人こそありませんでしたが、紙の束がくずれたり、屋根瓦がおちたりで、大変な騒ぎでした。
竜馬は藩邸に駆け戻りました。
「まっこと地震ばやりじゃ――。」
太平の 世を大変に ゆりかえし 上もゆらゆら 下もゆらゆら
狂歌のすきな江戸に、また新しい歌がはやりました。
“上”とは外国におびやかされ、開国か攘夷かの決心をせまられている幕府の事をさしています。
道場の貞吉先生や重太郎と再会を誓って、竜馬は黒船騒ぎ、地震騒ぎのつづくあわただしい江戸をはなれ、東海道を西へむかいました。大坂から船を乗りついで高知に帰ったのは六月の事でした。
「善じいちゃん帰ったぞ。」
竜馬は屋敷の木戸をなおしていた善吉じいさんに声をかけました。
善吉じいさんは一瞬、キョトンとしていましたが、
「ああっ、坊ちゃん!」
とっぴょうしもない声をあげて、ほこりまみれの竜馬の袴(はかま)にしがみついてきました。
「ようこそ、ご無事で………。」
善吉じいさんは嬉しさのあまり、ポロポロと涙をこぼしました。
竜馬が帰ったとの知らせに、屋敷中が蜂の巣をつついたような騒ぎになりました。
町にも、竜馬帰るの知らせがひろがりました。
善吉じいさんが、日根野道場やら親戚筋にこの知らせをふれ歩きました。
竜馬は父の八平と、兄の権平に、「ただいま江戸より戻りました。」しっかりと挨拶をしました。
(見違えるほどたくましくなった。とてもあの“よばあたれ”の泣き虫とは思われん――、)
八平も権平も目をほそめました。
夕方になると、日根野弁治をはじめ道場の仲間や近所の人たちが、坂本屋敷におしかけてきました。
「まちかねていたぞ。黒船の騒ぎはどうじゃった?」
「剣はどこまで進んだ? そろそろ皆伝ではないのか。」
日根野道場で竜馬と親しかった今村昇治郎もやってきました。
昇治郎は竜馬の話す江戸の様子に、ひとみを輝かせました。
「土佐はどうだ?」竜馬は藩政の事をたずねました。
「吉田東洋がにぎっちょる。」
「ほう。東洋が………。」
吉田東洋(元吉)は豊信の前の藩主、豊熈(とよてる)の代に郡奉行や船奉行を務めたことのある人物で、豊熈の死とともに、いったん職を退いていました。
東洋は剣にも、学問にもすぐれていて、とりわけ読書力はきわだっていました。
礼儀をおもんじるため、融通のきかないところもありましたが、藩にとっては大切な人材でした。
「幕府から届いたアメリカの国書の漢訳文を受取った藩には、これを読みこなす者がおらなかった。
読めなくては、藩の意見ものべられん。そこで再び、東洋が登用されたわけじゃ。」
吉田東洋は藩政の改革に手をつけていました。
新しい産業をおこし、藩の財政をたてなおして、大砲や船を備えようとしていました。
土佐にも激しい時代の波がおしよせていました。
あくる朝、早々とおきた竜馬は、乙女の嫁いでいる香美郡の山北に向いました。
山北までの二十キロの道のりも、乙女姉さんに会えるのですから、苦になりません。
「姉さん。」
「まあ、竜馬! いつ高知へ。」
88
乙女は洗濯物をほす手を休めて、おどりあがりました。
たすきをかけて掃除や洗濯をする乙女姉さんの姿は、かいがいしい奥様ぶりが板についていました。
「ゆっくりしていきなさい、あわてて江戸に帰らなくてもいいでしょう。」
「やあ、竜馬さん。」
乙女の夫、岡上新輔も飛出してきました。
オランダの医学をおさめた岡上新輔はその考え方も進歩的でした。
竜馬が黒船の騒ぎや幕府のぐらついた態度をいきどおると、
「竜馬さんは攘夷に凝(こ)り固まっておるな。」
笑いながらいいました。
「あたりまえです。夷狄に馬鹿にされて、我慢できますか。」
「だが、日本は眠りすぎた。すべてに遅れをとっている。これからは進んで外国のよいところを学びとる必要がある。」
新輔は開国だといいました。
「医術一つとってみても、外国では麻酔をつかって、大がかりな手術も可能だが、日本では大方が漢方のせんじ薬にたよっている始末。
竜馬さん。外国の事情に明るい人物が、この高知にいるが、あってみるつもりはないかね?」
「そのような人がおりますか?」
竜馬には初耳でした。
「おるとも、竜馬さんとまんざら縁のない人ではないな。」
「というと、親戚ですか。」
「いや、竜の絵をかくのがとくいな絵かきだ。狩野派の画家で、河田小竜(かわだ・しょうりゅう)という人だよ。」
竜馬は絵ごころなどまるでない剣術にだけの青年でしたから、画家の名には興味がありませんでした。
けれど、竜の絵を好んでかくといわれて、つい心が動きました。
「うん、たずねてみるか………。」
「中浜万次郎は知っているだろう?・」
「会ったことはないが、江川太郎左衛門に引取られていると聞いています。
黒船との交渉に、通訳としてつかってもらえなかったのはおしい………
それが小竜とかいう絵かきと、何かつながっているのですか?」
竜馬は怪訝(けげん)そうにいいました。
「万次郎から海外事情をのこらずに聞いて、本を表わした。
『漂巽紀略(ひょうそんきりゃく)』という、すぐれた本だから、竜馬さんも読まれるといい。」
「本を読むのは苦手じゃ………、おりをみて、河田小竜をたずねます。」
竜馬は小竜の名を心にとどめておきました。
本町筋の屋敷に帰った竜馬は毎日おしかけてくる客の応待にてんてこまいでした。
「江戸はどんな様子で?」
「黒船は今度、どのような難題をふっかげて来ましょうか?」
「京都のお公卿さまたちは幕府にこの危機をあずけっぱなしで、どうなさるおつもりですか、教えていただきたく、はるばる伺いました。」
初めての客もたくさんありました。
それも高知まで二日も三日もかけて竜馬をたずねてくるのですから、むげに追いかえすことはできません。
武士ばかりか、庄屋のせがれや、饅頭屋の長次郎といった変わり種も、竜馬をおとずれてきました。
竜馬の人気はしぜん高くなっていきました。
2 絵師小竜(しょうりゅう)
top
竜馬が播磨凰橋の東に住打河田小竜をたずねたのは山北の乙女のところから帰ってまもなくの事でした。
「ごめんください。」
「はい、どなたでしょうか?」
取次にあらわれたのは竜馬の屋敷に江戸の様子を聞きにきた若者のひとり、饅頭屋の長次郎でした。
「オッ、これは驚いた。おんし、絵をならっちょるのか?」
「いいえ、河田先生は西洋の事にくわしい方ですから、弟子にしてもらっているのです。」
長次郎は学問ずきの青年でした。
「わしも河田先生の弟子にして欲しいと、伝えてくれないか?
毎日はかよえないが、ときどき西洋の事や、鹿児島城下の工場の事など教えてもらいたいのだ。」
「ちょっとお待ちを………。」
長次郎は小竜のいる画室に入っていきました。
小竜は藩でおかかえになっている絵師でしたが、万次郎の漂流記を本にまとめたほどですから、文章力はゆたかでした。
日本は開国して、外国の文明を取入れるべきだという意見の持主です。
前の年から土佐藩は軍制を改め、洋式の軍備を採用したり一般から民兵を募集したり、海防の備えを固めようとしました。
大砲をつくる鋳砲場もこしらえて、試作が始りました。
ところがいざ、砲弾をこめてためし射ちすると、砲身にヒビびが入ったり、砲身が破れ飛んで死者がでる始末で、中々実用にはなりません。
92
藩ではこまって、薩摩藩に技術を教えてもらうことになりました。
島津斉彬(しまづ・なりあきら)の薩摩藩では、いち早く反射炉を築いて大砲の生産をする一方、ガラスや造船や機械の工場をつくるなど、産業が発展していました。
小竜は藩のいいつけで、御筒(おづつ)奉行や砲術指南役らと、鹿児島におもむいて、その進んだ技術や機械の仕組みを、つぶさに見てきました。
小竜は画家としての目で、正確なスケッチをとってきました。
やがて長次郎は面目なさそうに出てきていいました。
「先生は剣術屋には用がないといっています。」
これを聞いて、竜馬はカッとしました。
剣術使いを剣術屋と小馬鹿にされたのでは、黙って引っ込むことはできません。
「ごめん!」
竜馬はさっさと画室にあがりこみました。
「先生のほうでは用がなくとも、私の方に用があるのです。」
「仕事の邪魔をしては困る。」
小竜は絵筆をとっているところでした。
気むずかしい顔をした小柄な老人でしたが、目は竜馬を射すくめていました。
「これは失礼しました。しかし、先生も失礼な方だ。私が懸命に励んでいる剣道をさげすまれる。」
「剣など役にはたたんよ。」
小竜老人は、張りのある声でいいました。
自信にみちあふれた声でした。
「そんなことはありません。」
「ある! 剣の力で黒船を追いかえすことができたかな?
のう坂本さん、あんたは江戸から父上八平どのにあてた手紙に、夷狄の首を打ちおとしてやると書いたそうだが、黒船にちかづくことさえできなかったではないか。」
「うーん………。」
これには竜馬も、さすがに唸(うな)ってしまいました。
「剣は自分を磨きあげる訓練にすぎんよ。剣の力で国を護ろなどとは了見違いもはなはだしい。
坂本さんは黒船を見て、何と思われた?」
「欲しい、日本にも黒船が欲しいと思いました。黒船があり大砲があれば、アメリカやエゲレスやロシアに脅し上げられることはなく、対等に付き合えるわけです。」
竜馬は思ったままにいいました。 |

竜馬は小竜に会いに行ったが、剣を馬鹿にされたので怒った。しかし
小竜から黒船に剣では役にたたなかった事を指摘され、すぐ納得した。
|
「その黒船を手に入れる方法がある。」
小竜老人の目は、さっきよりもやさしくなっていました。
「どうすれば手にはいります?」
「買うのだよ。」
小竜老人はあっさりと答えました。
「藩にも幕府にも、黒船を買う金などありませんよ。先生、まじめに話してくれないとこまります。」
「わしはまじめにいっているつもりだよ。産業をさかんにして、外国から物をなるべく買わんようにする。
日本が必要とする物を国内の産業で作り出して、生産のあまりを逆に外国へ売りつける。これが理想だよ。
産業をおこし、商業をさかんにすれば、国のふところがうるおうだろう。それには船がいる。
アメリカやエゲレスの産業がさかんなのは、工業と物を運ぶ仕組みとがうまくできているからだ。
鉄道が町と村をむすび、貨物船が港から港へ物資を運ぶ。」
河田小竜(かわだ・しょうりゅう)は輸送と貿易の重要性をときました。
「最初の船はどうして手に入れるのです?」
「オランダ辺りにたのめば、貸してくれないこともないし、ボロ船ならば土佐藩でも買えるだろう。
やれ開国だ、攘夷だといっている間にも、外国船は次々にやって来る。
そんな内輪もめをしているうちに、日本は外国にのっとられてしまうよ。
国の力を強めるのは産業と輸出であって、けっして大砲をこしらえることではない。」
小竜老人はジュンジュンと語りました。
西洋の機械文明の発達ぶりは日進月歩の勢いでした。
ゆたかな産業から生みだされた製品の市場を求めて、西洋の国々は東の海に進出して来たのです。
竜馬の心は、激しくゆさぶられました。
(じっとしていられないぞ。)と思いました。
「幕臣の勝麟太郎とかいう男も、先生と同じような事を、いっておるそうです。
開国して貿易を盛んにし国を富ませよと、幕臣のくせに幕府を外国に売り渡そうとする悪い奴と思っていましたが、間違った意見ではないようですね。」
「間違っているのは攘夷一辺倒の坂本さんたちの頭の方さ、勝さんはえらい人だ。
あの人は五十年も先の日本の姿を見通している。自分の信念にしたがって、まっすぐに歩んでおられる。」
竜馬は小竜老人の話に、すっかり引込まれてしまいました。
とりわけ、西洋の蒸汽船を買い入れて、物資や人を東西にはこんで利益をあげると同時に、日本人の水夫に航海術をのみこませて、日本の将来をひらこうという小竜の意見に、目を覚まされる思いがしました。
(剣道はしょせん、天下を動かすにはたりない。
これからはもっと志を大きくして、国のゆくすえにつくさなければ………、)
竜馬の心の中に、土佐にとじこもっていてはならない。
天下国家のために働かなければならないという考えが、夏空の雲のようにひろがってきました。
竜馬はそれからもしばしば、河田小竜にあって、外国の政治の仕組みや歴史を教えられました。
竜馬は思ったより長く高知に足をとめてしまいました。
江戸からはいつまでたってもかえらない竜馬の身をあんじて、千葉重太郎が手紙をよこしました。
高知にもどって一年がたちました。
このころから、父の八平の健康がすぐれなくなって、ふせっていることが多くなりました。
竜馬は父の病が心配で、江戸に戻る決心がつきません。
「竜馬、わしの事はかまわぬ。権平やおまえの姉たちがいてくれるのだから、江戸にいって修業にはげめ。」
八平はいいましたが、秋が深まりゆくほどに病は悪くなっていき、竜馬たちの懸命な看病や祈りもむなしく、息をひきとってしまいました。
安政二年もおしつまった、十二月四日の事でした。
八平は五十四歳で、この世の人では亡くなってしまったのです。
竜馬は思いきり泣きました。けれど、明日からはもう二度と泣くまいと思いました。
「竜馬、家は私が切りまわしていく。おまえは江戸で剣術の最後の仕上げをしてから、高知に帰って来てくれないか。
ご城下に道場をひらいて、末永く暮らすとよかろう。」
兄の権平はそういってくれました。
「それは修業をおえてからのも、考えます。
しかし天下がもしも、私を必要とするならば、道場の先生に修まる事を捨てて、天下のために働こうと思います。」
竜馬はきっぱりと答えました。
「なるほど、感心な心がけだ。国事を忘れるなといっていた父も、竜馬のいまの言葉に安心なされたことであろう。
しっかりやってくれ。」
「ありがとう。兄さん。」
竜馬が父をなくした悲しみをかなぐり捨てて、再び江戸に向って旅だったのは安政三年(一八五六)八月下旬の事でした。
3 剣術試合 top
「竜さん、よく帰ってきてくれた。竜さんのいない道場は、まるで火のない火鉢のようなもので、妙にさみしかった。
明日からまた、道場も活気づく。」
千葉重太郎は三年ぶりに竜馬をむかえて、ほっとしました。
実は幕府が武士をきたえるために、講武所をこしらえて、重太郎を指南役の一人に指名してきました。
「それは、おめでとう。」
「いや、俺が講武所にいってしまえば、道場の門弟たちが、思うように稽古できない。俺の留守に竜さん、あんたが教えてくれないか。」
「よし、頑張ってみよう。だが公儀が講武所をたてるとは、驚いたものだ。」
竜馬が江戸をはなれている間に、幕府の人材も変ってきていました。
『西洋かぶれ』の佐倉藩主、堀田正睦が老中首座になって、攘夷派の徳川斉昭と対立していました。
斉昭のちえぶくろであった水戸学の中心人物藤田東湖が、去年江戸をおそった大地震のとき、母親を救おうとして、たおれてきた家におしつぶされるという不幸があってから、斉昭の力はおとろえていました。
東湖の考えにささえられていた斉昭の人気はしだいにおちこんでいました。
斉昭の権力が強まっていたときには攘夷を唱えていた大名たちの中に、しだいに外国との戦争は避けたいということなかれ主義が広まってきました。
「開国や、通商条約をみとめるのも、時のながれで仕方のないことだ。」
江戸城の溜間づめの大名たちの間に、こうした声が生まれてきました。
溜間づめの大名の中心人物、彦根藩主井伊直弼は堀田正睦とむすんで、斉昭を圧迫していきました。
「竜さん、七月にハリスが下田におしかけてきたのを知っているかい?)
「噂には聞いたが、アメリカの領事の事だ。通商のきまりを結ぼうというのだろう。」
「気軽な事をいうなあ、これは大事だよ、竜さん。斉昭公は巌(がん)として攘夷だ。
しきりに京都の朝廷につかいを出して、天皇が攘夷の勅令をくだすようにねがっているそうだよ。
ところが堀田正睦や井伊直弼は攘夷は無理だ。開国に踏み切ろうという腹づもりでいる。
ふたつの勢力がぶつかりあっているところに、ハリスの登場、ひともんちゃくおきそうな雲ゆきだよ。」
「重太郎さん、わしはご政道(政治)に関してはまだまだあきめくらじゃ。
それに、郷士のぶんざいだから、何の口出しもできん、しばらくは剣術にはげもうと思う。」
竜馬はあくる日から、桶町千葉の道場で、激しい稽古を始めました。
稽古に明け暮れているうちに、安政四年(一八五七)となりました。竜馬は二十三歳になっていました。
年があけてまもなく、竜馬は大きな褒美をさずかりました。
北辰一刀流の最高位である、大目録皆伝の資格をもらったのです。そしてさらに、塾頭にあげられました。
竜馬はこの嬉しい知らせを、ただちに国元の兄や乙女に、手紙で伝えました。
乙女のとびあがる姿が、目にうかぶようです。
竜馬は門弟たちの祝福をあびても、おごりたかぶることなく、稽古の先頭になってわざを磨いていきました。
そんなある日、道場に日本橋の徳兵衛が現れました。
「坂本さま、このたびはおめでとうございます。しかし、水臭いじゃありませんか。
土佐からもどったことも、免許皆伝になられたことも教えてくださらんのですからね。」
「すまん、この半年のあいだ剣のほか、なにも考えておらなかったのだ。
それに、皆伝をとったとわざわざお前のところに知らせにいくなど、てれくさくてな。」
竜馬は頭をかきかき、いいわけをしました。
「桶町千葉の塾頭とあれば、江戸の剣客のなかでも一流中の一流、よくぞ頑張られました。
つまらんものですが、お祝いのしるしです。普段にはいてください。」
徳兵衛は袴(はかま)をつくってきてくれました。
「やあ、これはすまん、ちょうど欲しいと思っていたのだ。さっそくにつかわせてもらうよ。」
竜馬は徳兵衛の好意弋すなおに受けとりました。
やがて夏もすぎて、さわやかな秋空が目にしみるようなある日、講武所での指南をおえた重太郎が、息をはずませてかけこんでくると、
「竜さん、耳よりな話だよ。」
といいました。
「なにごとです?」
「この秋、諸流の剣術試合がひらかれる。しかも竜さんの土佐の殿さま山内侯がもよおされるそうだ。
めったにない大試合だけに、わが道場の名誉にかけても勝ちたい。」
重太郎はかなり意気ごんでいました。
「その試合なら知っちょる。数日まえ、武市半平太から聞いた。」
「桃井道場の塾頭からか、なぜ教えてくれなかった?」
重太郎はうらみがましくいいました。
[あんたが出るべき試合だときめていたからじゃ。
北辰一刀流の千葉道場からは千葉を名乗る者が出場しないとおかしな具合になる。」
竜馬は本当にそう思っていたのです。
「いや、実力では竜さんにかなわん。」
「では、二人で立ち合いをしてきめましょう。十本勝負で。」
「それがいい。」
門弟たちがかたずをのんで見護るうちに、竜馬と重太郎は激しく打ちあいました。竜馬は最初の二本をとられました。
桶町干葉を自分が代表するのは、おこがましいのではないかという遠慮が、竹刀をにぶらせていましたが、竜馬はそれが間違っていることに気がつくと、もうぜんとおどりかかりました。
本当に強い者が出場して、北辰一刀流の名誉を護るべきだと思ったからです。
重太郎が四本、竜馬が五本とったところで、桶町千葉の代表はきまりました。
「竜さん、たのんだよ。」
「豊信公も、ものずきなかたじゃ。」
竜馬は重太郎の手をにぎりしめていいました。
土佐藩主山内豊信が、江戸にひしめく諸流の剣士を一堂に集めて試合させようと思いついた裏には、攘夷に備えて武士の魂(たましい)を奮い立たせるという、もくろみがあっだからでしょう。
土佐藩邸に江戸でゆびおりの剣客たちがそろったのは十月三日の事でした。
道場の正面に重臣をしたがえて、山内豊信がすわりました。竜馬はそっと顔をあげて、自分の殿さまをながめました。
『容堂は身の丈高く、少しあばた顔で歯が悪く、早口でしやべる癖があった。
彼は確かに体の具合が悪いようだったが、これは全く大酒のせいだったと思う………、』
幕末にイギリス人通訳として活躍したアーネスト・サトーは、『一外交官の見た明治維新』という回想記のなかで、豊信の印象をそう書いています。
自分から『鯨海酔侯(げいかいすいこう)』、よっぱらい大名という号をつけているくらい、大変な酒飲みであったことは事実でした。
竜馬が豊信を見かけたのはあとにもさきにも このときだけでした。
身分からいって、竜馬が藩主にお目どおりを許されることはありえなかったのです。
「構えて! 勝負三本! はじめ!」
竜馬の相手は神道無念流の斎藤弥九郎の門下で、島田駒之助といいました。
一本め、相討ち、二本め、竜馬、三本め、竜馬、
「それまで。」
審判の声があっても、竜馬のすさまじい突きわざをくらった島田駒之助は、しばらく起上れませんでした。 |

土佐藩主山内豊信の前で諸流の剣士を一堂に集めての
試合があり、北辰一刀流の代表として竜馬は出席した。
この中には見事な太刀さばきの長州の桂小五郎もいた。
|
「あの男、強いな、どこの藩の者かの?」
豊信は重臣の一人にたずねました。
「わが藩士です。坂本竜馬、本町筋の郷士のせがれにて北辰一刀流の皆伝にございます。」
「郷士か………、おしい男だ。」
つぎの試合がはじまると、豊信はたちまち竜馬の名を忘れてしまいました。
竜馬は席に戻ると、熱心に試合を見護りました。
江戸の一流の剣士が腕におぼえの流儀を競うのですから、またとないいい試合があいつづきました。
竜馬は、土佐藩士の福富健次を三本とも軽く打ちやぶった男の剣のさえに目をうばわれました。
「武市さん、あの男は?」
竜馬はこの日の試合の世話係である半平太にたずねました。
「桂小五郎、斎藤弥九郎道場の塾頭だよ。おんしが島田駒之助に勝ったとき、にらんでおったぞ。同門がたおされたのだからな。」
「ほう。練兵館の塾頭では強いはずじゃ………。」
挂小五郎は長州の生まれでした。竜馬より二つ年上で、松下村塾の吉田松陰に教えをうけた秀才です。
剣にも詩にもすぐれていて、藩の軍制を洋式軍隊につくりかえようとするはりきり屋でした。
のちの木戸孝允(きど・たかよし)、その人です。
その後、竜馬は桂と道場どうしの試合などで、いくたびか顔をあわせるうちに、すっかり親しくなりました。
桂や、同藩の武市、それに最近国元からやって来た中岡慎太郎(なかおか・しんたろう)とふれあうことによって、竜馬はしだいに『天下国家』の動きに関心をよせるようになりました。
開国か攘夷か、佐幕か勤王か、将軍の後継をだれにするか、問題は幕府を苦しい立場においこんでいました。
いままでどおり、徳川幕府を護っていこうという佐幕派、
足なみのそろわなくなってきた諸藩のおさえに、京都の天皇をひっぱりだし、天皇の号令によって攘夷を行おうとする尊王攘夷派。
幕府をたおし、朝廷による統一国家をつくろうとする尊王倒幕派――、それぞれの勢力がまんじどもえに入り乱れています。
(おれには学問がないから、むずかしいことはわからんが、半平太のいう尊王攘夷は正しい。
しかしその考えを実行するにはどうすればいいんじゃ。時代は渦を巻いて流ている。渦にのみこまれてはいかん。
流れをしっかり見きわめて、行動せねば――、)
竜馬は武市半平太についていこうと思いました。
他藩の桂小五郎とも力をあわせて、新しい時代をつくる手助けがしたいと考えるのでした。
時代が自分を必要とするまでは剣を磨こうと、竜馬はひたすらにはげみました。
4 大獄の嵐 top
年があげて安政五年(一八五八)、竜馬は江戸で二十四歳の春をむかえました。
「重太郎さん、今年の秋には土佐に帰らねばなりません。藩からいただいている遊学の許しは九月で切れてしまうのだ。」
竜馬は道場の初稽古のあとでいいました。
「少し、のばしてはもらえないのかね。国元で道場をひらくのも悪くないが、国事のために働こうという気があるなら、何といっても江戸だよ。それに竜さんがいなくなると、道場が気合いぬけしてさみしくなる。」
予葉重太郎は本音をいいました。
「藩のおきては窮屈なもんじゃ。期限までに帰らねば、脱藩の罪人にされる。」
「だからそこのところを、兄の権平どのにとりなしてもらって、延期というわけにいかないかなあ。」
「わしのように藩のためにならん者にかわって、国元から優秀な若い者が出てきて、藩の長屋もいっぱいじゃ。
わしは土佐にひっこむ、ひっこんでから、何をするか考える。おくればせながら、学問でもやろうかのう。
学問がないと、肩身がせまいだけでなく、国家の動きもよく見えん。」
竜馬は冗談めかしていいましたが、まんざら出まかせではありませんでした。
「では江戸で最後の修業の年、心のこりのない稽古をつんでいかれるといい。」
「江戸と土佐はおよそ二十五日の道のりがあるが、急ぎなら十二日、日本にも黒船ができれば四日かそこいらでいける。
天下がわしを必要とするときになったら、いつでも出てくる。」
「“天下国家”が、口癖になってきたね。竜さん、天下はあんたを必要とするさ。きっとまた江戸へくるよ。」
「わしのようなぼんくらが、天下のためになれるかなあ。」
「なれるとも、竜さんは不思議と人の心をつかむわざを備えている。剣だけに生きる人じゃない。」
重太郎は竜馬の人柄を見ぬいていました。
物事にこだわらず、天真らんまん、いつとはなしに人を引き付けてしまう、おおらかな天分が、竜馬には備わっています。
「重さんはいつから易者になったのだ。ハッハハハ………。」
竜馬はほがらかに笑いました。
その年の春の事です。
「彦根の藩主、井伊掃部頭(直弼=なおすけ)どのが、大老になったぞ。」
土佐藩邸の若者たちは肩をいからせて、わいわいと騒ぎました。
大老は老中を代表する者として、大きな権力をあたえられます。
「井伊家は三十五万石、徳川家にむかしからしたがっている大名だ。家柄に不足はない。だが、斉昭公とは対立している。したがって、水戸藩はもちろんの事、越前、薩摩、土佐を圧迫してくるにちがいない。」
若者たちに説いているのは武市半平太でした。
井伊直弼が大老になった裏には将軍家定の後継問題がからんでいました。
ペリーが最初に来航した嘉永六年になくなった将軍家慶は水戸の徳川斉昭の子、慶喜(よしのぶ)を十四代の将軍にしようと思い、とりあえず一橋家の養子にしておきました。
越前の松平慶永、薩摩の島津斉彬、土佐の山内豊信らは一橋派の先頭に立っていました。
一方には紀伊家の徳川慶福(よしとみ)を十四代将軍にしたいとねがう南紀派があって、にらみあっていました。
慶福は十二歳の少年でした。
慶喜は二十一歳、一橋派の勢力に護られて、慶喜が十四代将軍につく可能性は十分ありました。
まきかえしをはかる南紀派は十三代将軍家定にとりいって、慶福をぜひ後継にして欲しいといいました。
家定は慶喜を嫌っていました。
幕政にいちいち口をはさむ斉昭の子供を十四代にしたら、斉昭はますます威張ると思ったのです。 |
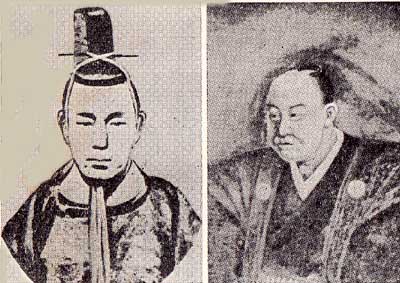
一橋慶喜(左)と井伊直弼(右)
|
そこで一橋派をおさえるため、井伊直弼を大老にしました。
しかし、力のおとろえている幕府は将軍の世継ぎを幕府独断できめられず、朝廷にはからねばなりません。
一橋派は越前松平慶永の家臣である橋本左内を薩摩の西郷吉之助(隆盛)と協力して朝廷に働きかけていました。
また一橋派である老中の堀田正睦は、ハリスが求めている通商条約の事で、京都の孝明天皇にお願いにいったさい、
『家定さまは政治をまとめることもできず、病気も悪くなる一方でございますから、一橋家の慶喜さまに実際の政治をとってもらい、越前の松平慶永どのを大老になされて、有力な大名と力をあわせて、この難局を乗切ろうと考えます。』
といいました。
大の外国嫌いの孝明天皇は通商条約調印に反対してから、将軍の世継ぎについてはかしこくて人望のある者をえらびなさいといっただけで、慶喜の名をあげずじまいでした。
南紀派が公卿の実力者の九条関白に、手をまわしてあったためです。
「老中が朝廷にいっている留守に、南紀派は家定さまをすっかりだきこんで、井伊掃部頭を大老につかせる工作をしたのだ。
大老の掃部頭は紀州慶福公をたてて、一橋派を幕府から追いはらおうとしてくることだろう。」
武市半平太ははらだたしそうにいいました。半平太の予言は、おそろしいまでに現実となってあらわれてきました。
一橋派のしめ出しがはじまったのです。さっそく、大目付の土岐頼旨(とき・よりむね)や勘定奉行の川路聖謨(かわじ・としあきら)が格下げされ、老中堀田正睦(ほった・まさよし)の地位もあぶなくなってきました。
「ハリスはだいぶ、しびれを切らせているようだ。将軍家をあいてにしていたのでは、いつまでたっても通商できない。将軍よりもえらい天皇があるのなら、自分から京都にいって、天皇に会い条約をむすぶといい出して、掃部頭どのをあわてさせているそうだ。」
竜馬が半平太からそう聞かされたのは五月のおわりごろでした。
「それはおもしろい。ハリスが直接、朝廷と条約をむすべば、徳川のご威光はまるつぶれだ。
大老がオロオロする様が見えるようじゃ。武市さんは江戸でいまはやりの、“世の中、井伊づくし”というざれ歌を知っちょるか?」
「………外国交易せぬが井伊、西洋さっぱりとめるが井伊、叡慮(天皇の考え)もちっとは立てるが井伊、という歌だな、
江戸の人たちの気持ちがよくあらわれている歌だ。しかし、掃部頭はハリスの求めに応ずるしかない。ハリスは七月二十五日まで調印できない場合は力づくでも、といってきている。」
「攘夷の考えにかたまっている朝廷が、調印をみとめはしないと思うが、大老は説得の自信があるのだろうか?」
竜馬がいうと、
「おそらくあるまい。」
半平太はため息をつきました。
「ではどうする?」
「方法はたった一つ、朝廷の許しをえずに幕府の手で調印してしまうことだ。幕府の権威を保つにはそれしかないだろう。」
「開国するというのか? 朝廷をないがしろにして、攘夷の声に耳をふさいで、幕府がかってに、この国を夷狄に売りわたそうというのか?」
竜馬運ぶしをにぎりしめて、激しい口調でいいました。
尊王攘夷という、国民のおおかたの意見を無視して、井伊直弼は日米修好通商条約の調印を決意していました。
それが、日本を護るもっともいい策だと思ったからです。
六月十九日、アメリカ船ポーハタン号の艦上で、幕府の代表が調印しました。
下田、箱館のほか、神奈川、長崎、新潟、兵庫の港をひらき、江戸と大坂に市場をもうけることや、裁判権の事など、アメリカ側に都合のいい条約でしたが、調印はすでに断れないところにきていました。
「とんでもないめくら調印じやないか、アメリカの商人は日本の役人に口出しされずに、自由に交易ができるなんて、もっとはらのたつのは裁判のとりきめだよ。
日本人に害をあたえた異人は異国でさばかれる。筋からいえば日本の奉行所がさばくべきじゃないか。」
千葉重太郎も息まいて、竜馬に条約がいかに不平等であるかをうったえました。竜馬もくやしさでいっぱいでした。
この条約調印には攘夷派ばかりか、開国論者からもごうごうと非難の声があがりました。
「条約をむすぶにしても、掃部頭が天皇に拝して、納得いただいてからするべきだ。
朝廷をかろんじているご公儀の一人芝居ではないか。」
竜馬のいきどおりも、大変なものでした。しかし、竜馬や半平太や重太郎たちが、いくらいきどおっても、しょせんは仕方がありません。
ところが、徳川斉昭ともなると、ご三家の実力者ですから、だまってはいません。
条約調印から五日め、斉昭は尾張の徳川慶勝(よしかつ)や、むすこの徳川慶篤(よしあつ)をつれて、江戸城へ乗込んでいきました。
井伊直弼が紀州の慶福をつぎの将軍にきめて、慶喜をかえりみないうらみもあって、斉昭は激しく直弼にくってかかりました。
のちに“水戸の烈公”といわれた斉昭だけに、直弼は手厳しくせめられて、うけこたえにたじたじでした。
そこに、越前の一橋派の大もの、松平慶永もあらわれて、斉昭とともに、直弼につめよりました。
『お話はわかりました。天皇にはつかいを出して、いきさつを納得してもらいます。
天皇にそむいたことになるかどうかはその結果しだいでしょう。
ところで斉昭どの、いかに大藩の大名諸侯とはいえ、登城の日が定められている事を、お忘れではありますまい。
急ぎの登城も、まえもって知らせをいただかないといけません。』
おいつめられた直弼は、にわかに四人をにらみかえしました。
斉昭や慶永が直弼から、みだりに登城した事を理由に、謹慎や隠居を命ぜられたのは七月五日の事でした。
よく七月六日、十三代将軍家定がなくなって、とりこんでいる江戸城に、朝廷の命令が届きました。
『朝廷の許しもなく通商条約を結んだことについて、ご三家の者か大老が、天皇にお目どおりして、くわしく説明せよ。』
命令に対して、幕府の返事はそっけなく、天皇をはじめ公卿たちは怒りました。
天皇はこれは自分に力がないからだと思い、退位したいといったほどでした。
朝廷をかろんじている幕府をこらしめよ、という公卿たちの声は、かねてから幕府を倒して朝廷に政治を返そうと運動していた“倒幕尊王論”の人たちの動きに、火をつけました。
尊王、攘夷の『志士』たちは京都に集って、意見をたたかわし、運動をもりあげていきました。
梁川星巌(やながわ・せいがん)、梅田雲浜(うめだ・うんぴん)、頼三樹三郎(らい・みきさぶろう)、池内大学(いけうち・だいがく)たちは 『一橋慶喜さまを将軍にたて、井伊大老を辞めさせなければ、幕府の朝廷に対する態度はあらたまらない。』
として、水戸藩や薩摩藩屋敷に同志を求めて来ました。
越前の藩士橋本左内(はしもと・さない)や、薩摩の日下部伊三次(くさかべ・いさじ)も、いまこそ慶喜を将軍にし、朝廷を大切にする大名たちが国を治めていけるよう、はたらいていました。
大老井伊直弼(いい・なおすけ)が、このような志士たちの行動に目をつむっているはずがありません。
『反幕府の志士たちをとらえよ。』
大老は自分の手足になっている長野主膳に命じました。京都町奉行にも志士の動きを調べるようにいいました。 |

尊王攘夷の志士たちが、京都に集まり騒ぎ出した。
|
「竜馬、掃部頭がついに本性をあらわしてきたぞ。若狭の藩士で、志士の中心人物の一人、梅田雲浜がとらえられた。
江戸送りにされて投獄のうえ、死罪か遠島ということになろう。志士弾圧の手始めとみていい。
志士の動きを封じて、さらには一橋派の公卿や大名をとりつぶしにかかるにちがいない。
城中にはすでに、掃部頭をおさえられる大名はいないからな、弾圧の手をますます厳しくしてくる――。」
沈痛なおももちで、武市半平太がいったのは九月初めの事でした。
竜馬が土佐に帰らなければならない日が、せまってきています。
竜馬は桂小五郎のところや、日本橋の徳兵衛に挨拶にまわったり、旅じたくを整えたり、忙しく日を送っていました。
「竜馬、江戸にとどまらんか、期限をのばしてもらうよう。わしが働きかける。」
半平太は弾圧の魔の手が、土佐藩にもかならずのびてくると思っていました。藩公山内豊信は、一橋派です。
井伊大老が見のがすはずがありません。最悪の場合は土佐藩のとりつぶしという事態もありうるのです。
半平太は藩が一大危機にさらされているときだけに、竜馬を土佐にやってしまいたくありませんでした。
「いや、わしは土佐で剣をみがく、学問も少しはやらんといかん、江戸の事は武市さんにまかせる。
諸生たちから“武市先生”としたわれているおんしではないか。
若い者を間違った方向につっ走らせんように、導いていってくれ。」
竜馬は半平太に頼みました。土佐へ帰る気持ちは変りません。
『安政の大獄』が嵐となって荒れ始めた風雲前夜、竜馬は江戸をはなれました。九月も半ばすぎの事でした。
東海道をくだりながら、めぼしい道場で他流試合をして、北辰一刀流免許皆伝の腕前をひろうし、道中の費用をひねり出そうと、竜馬はのんきな無銭旅行をくわだてました。
5
立ちあがる下士(かし)たち top
江戸から二度目の帰国をした竜馬の人気は、たちまちご城下に高まりました。
「今度は江戸の三大流儀の一つ、北辰一刀流免許皆伝をもってもどったそうじゃ、土佐で大流儀の皆伝をもっているのは鏡心明智流の武市瑞山(ずいざん=半平太)とならんで、坂本竜馬が二人め、あの本町筋の泣き虫がのう………。」
「坂本家も鼻が高かろう。」
「うちの子も、竜馬さんか瑞山先生のようにしたいもんじゃ。」
竜馬が帰国すると、武市瑞山もほどなく土佐にもどり、私塾をひらいて、学問や剣道を教え始めました。
郷士や、足軽といった下士の若者たちは瑞山の人物と剣と学問にひかれて、ぞくぞくと集ってきました。
「竜馬、武市さんに負けずに、道場をひらけ、費用はこしらえてある。」
江戸から帰ってきてから、毎日のんびりしている竜馬に、兄の権平がいいました。
「道場の先生にはなろうと思えばいつでもなれますが、若いときにしかできないものがあります、学問です。」
「竜馬が、学問?」
ププッと、権平はふき出してしまいました。少年のころ楠山塾から見はなされたほど、学問には才のない竜馬が、まじめな顔でいうのですから、つい笑ってしまいました。
「兄さんは笑われるが、学問を知らんと、自分の考えを人にはっきりと伝えることができません。
天下を見定めることもできません。」
竜馬のまなざしは真剣でした。
竜馬は日根野道場で、門弟に稽古をつける合間に、河田小竜のところで西洋談義を聞いたり、武市の『瑞山塾』に顔を出したり、蘭学を教えている塾をたずねるようになりました。
「竜馬が本を読んでおるそうだ。その読み方が、何ともかわっているらしい。
武市ばなしに“坂本竜馬、本を逆さに論語読む”とからかわれるくらいじゃ。
それがいま、武市瑞山に勧められて、“資治通鑑(しじつかん)”を読んでいるというぞ。」
噂は高知の城下にひろがっていました。
“資治通鑑は三百巻にちかい、中国の歴史の本です。
かなりの学問をつまなければ、読みこなせる本ではありません。
「竜馬がどんな読み方をしているものやら、我々ものぞいて、ひやかしてやろう。」
ある日、今村昇治郎が友だちと一緒に坂本屋敷にやってきました。竜馬はキチンと膝を折って、書見の最中でした。
「竜馬、せいがでるのう。わしらにも聞かせてくれんか?」
「これは昇治郎、わしの読み方を笑いにきたのだな。わしはわしの読み方で読んでいる。こんなふうに。」
竜馬はつかえながらも、漢文を読んでいきました。全く自己流の読み方でした。
昇治郎たちはたまりかねて、笑い出しました。すると竜馬はいいました。
「意味はわかっちょる!」
そして昇治郎たちをまえにおいて、資治通鑑の解釈をとき始めました。
それは本の内容を的確にとらえた立派な答えでした。
「えらいぞ、竜馬。先日、蘭学塾の先生をへこましたという噂も、嘘ではないな。」
昇治郎たちは感心してしまいました。
「あれは誤訳を誤訳といったまでじゃ。」
竜馬は先日、蘭学塾で法律のテキストの講義をうけました。
ところが先生の訳は日ごろ竜馬が小竜老人から聞いている西洋の法律の筋からはずれています。
どうも違っているようだと竜馬にいわれて、先生はシブシブ原文を読みなおして、誤りに気がつくと、竜馬にいいました。
「蘭語を知らない君に、よく訳の間違いがわかったものだ。」
竜馬は頭をかくだけでしたが、学問の面倒な約束ごとよりも、肝心な本質をズバリとつかみとる事の方が大切だと思っていました。
年があけて安政六年、大獄の嵐は激しく吹きつのっていました。
江戸や京都で、橋本左内や日下部伊三次、吉田松陰などがとらえられ、首をはねられてしまいました。
土佐藩主山内豊信が、隠居を命ぜられたのは前の年の十月でした。
大老井伊直弼は、豊信が京都の公卿とむすんでいたことや、洋式武器の買い入れを幕府に要求したことに怒って、処分したのです。
土佐藩主は豊範に受継がれました。
実際に土佐の藩政をとっている吉田東洋は豊信が隠居したのをよいことに、尊王攘夷派の家来をやめさせ、幕府の方針に従う佐幕開国をめざすようになりました。
その土佐に、大老井伊掃部頭直弼が、江戸城桜田門外で、水戸の浪士の手によって暗殺されたという知らせが入ったのは万延元年(一八六〇)三月の事でした。
「世の中がひっくりかえる!」
竜馬の体中の血が騒ぎました。
幕府の権力者である大老が、数人の浪士に暗殺されたのですから、幕府の権威はガタガタです。
竜馬が武市の瑞山塾にかけつけると、半平太は馬にむちをあてて、江戸に向うところでした。
「竜馬、わしたち下士が働かねばならぬ時代がくるぞ。
わしは江戸に走って、薩摩や長州と土佐の三藩を連合し、天皇をいただいて幕府をきりくずすつもりだ。
帰国したら、土佐七郡の郷士浪人、足軽たちをまとめて党をつくり、藩政をかえねばならん。竜馬、留守をたのむぞ!」
ピシッとひとむちあてた馬上の武市瑞山は土ほこりを竜馬にあびせて、江戸をめざしました。
竜馬は瑞山塾で若い書生たちの面倒をみるようになり、いつのまにか“坂本先生”としたわれていました。
あげて文久元年(一八六一)の春の事です。
高知に、上士が酔った勢いで下士を斬り、下士の弟が『兄のかたき!』と上士を討つ、大事件がおきました。
上士の名は山田広衛、またの名を鬼(おに)山田といわれる一刀流の達人でした。
山田が、城の花見酒に酔って下城する途中、くらがりの橋の上で郷士とすれちがい、よろめいて郷士にぶつかりそうになりました。二人は喧嘩になりました。
「軽格のくせに無礼な奴!」
「酔って人にあたりながら、上士であるのをいいことにわびをせぬか!」
郷土の中平忠一郎は気の強い男でした。軽格とののしられては我慢できません。二人は刀のさやをはらいました。
酔ってはいても鬼(おに)山田は、一刀流を千葉周作の道場でおさめた強者(つわもの)です。
バッサリと忠一郎を斬ってしまいました。
この知らせを聞いた忠一郎の弟、池田寅之進は、鬼山田と戦って、兄の仇をはたしました。
寅之進は竜馬と、日根野道場で一緒に稽古した仲でした。 |

激しい世の中の動きに、武市は竜馬に留守を頼んで、
江戸に駆け付けていった。
その間に土佐では上士(上格)が下士を切り殺す事件が起こり、
竜馬は下士のグループのリーダーに祭り上げられた。
|
「上格の侍たちが、池田寅之進を襲うというぞ。俺たち下士は寅之進を見ごろしにはできない。坂本さん、あんたが下士の大将になってくれ。」
軽格の青年のなかでも年かさの池内蔵太(いけ・くらた)や今村昇治郎や、瑞山塾の若者たちが、声をそろえていいました。
「よし、引受けた。」 竜馬は下士の代表として、この池田事件を解決しようと思いました。
そして上士と下士の垣根をとりはらって、土佐藩をよくしたいと考えました。
けれど、二百年もにらみあってきた両者です。
簡単に解決しそうにはありません。竜馬が思案しているとき、
「池田寅之進が切腹したぞ!」
瑞山塾の門弟の一人が、坂本屋敷に知らせてきました。
「寅之進、早まった、下士に迷惑がおよぶと考えての切腹だろうが、おんしが死んでは戦いにならんのだぞ。」
竜馬はぎゅっと、くちびるをかみしめました。
124
「寅之進、おんしの犠牲にされたいのも、けっして無駄にはせぬぞ。下士はいまこそ力をあわせて、立ちあがる。」
竜馬はかたく誓いました。
池田寅之進の切腹は下士の者すべてをいきどおらせ、下士を結束させる口火となりました。
おりしも八月、江戸で桂小五郎や、同じく長州の久坂玄瑞、高杉晋作らとともに『勤王倒幕』をはかっていた武市瑞山が、土佐に帰って来ました。
「薩摩、長州、土佐の西国三藩で幕府をたおすことにした。しかし土佐には吉田東洋が佐幕(さばく)の構えをかえぬ。
わしらの力で、土佐藩をつくりかえねば、幕府はたおせぬ。みんな、力をあわせよう。
土佐勤王党をつくり、東洋を説きふせ、新しい時代をわしたちのものにしよう。」
瑞山塾にかけつけた門弟たちに、武市半平太は熱っぽく語りかけました。
郷士以下、下士の者たち百九十二名が、土佐勤王党の盟約書に名をつらねました。
坂本竜馬、中岡慎太郎、大石弥太郎………、
盟主は武市瑞山(半平太)、これだけの組織になると、下士の集りとはいえ、藩庁もうかつには手がだせません。
「武市さんを助けて、俺は働くぞ。幕府を倒して、新しい日本をつくるために、俺は俺の方法を考えて働く。」
竜馬は土佐勤王党の盟約書に、血判をおしながら、倒幕の決心をかためました。
top
****************************************
|