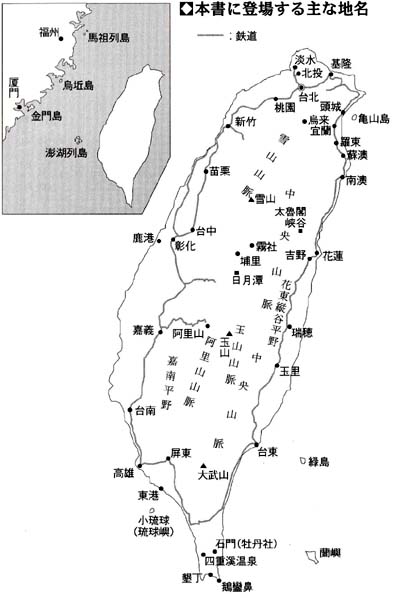|
****************************************
HOME 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章
三章 台湾北部
1 淡水――夕陽の美しい港町 top
どこよりも美しい夕陽が眺められる港町。淡水はこういった言葉で紹介されることが多い。
水量豊かな淡水河のほとりに町が開け、対岸には観音山がゆったりとした姿を横たえている。
川面に沈んでいく夕陽はたしかに美しく、赤く染まった空を前に語り合う若者たちが毎日のように集まってくる。
淡水は台北の外港として発達した町である。交易港としての機能がなくなった現在も、町は港を中心に開けている。
山並みが河岸に迫っているため、市街地は川に沿って細長く伸びているのが特色だ。
ここは古くから庶民に愛された行楽地であった。
北東一五キロほどの場所にある白沙湾は日本統治時代は「鎌倉海水浴場」と呼ばれ、遠浅で波が穏やかなことで知られていた。
そして、淡水河の対岸にある観音山は、青空に浮きたった山容が美しい。
ここは終戦まで「淡水富士」という名で親しまれていた。
さらに、町のはずれには当時は非常に珍しかったゴルフリンクもあった。
この町が最初に歴史の舞台に出たのは一六二六年。スペイン人がフィリピンから北上し、台湾北部に着いた時にさかのぼる。
スペイン人は基隆に近い社寮島(現・和平島)にサンサルバドル城を築き、後に淡水へ入った。
この時に造営されたのがサンドミンゴ城で、現在、紅毛城がある場所である。
スペイン人はここを拠点として、中国大陸の南部、そして日本との交易を試みた。
この時、淡水は最初の繁栄を迎えることになるが、間もなく、台湾南部に拠点を築いていたオランダ人によってスペイン勢力は駆逐されてしまう。
そのオランダ勢力も、鄭(てい)氏政権によって台湾を追われた。淡水が次に繁栄を迎えるのは、清国統治時代に入ってからだった。
一九世紀に入る頃には、原野が広がっていた台湾北部も開拓が進み、徐々に台北が町として発展するようになった。
そして、淡水は北部一帯のゲートとして賑わいを見せるようになる。
なお、当時は淡水という地名ではなく、「滬尾」(ホーポェト)と呼ばれていた。
淡水が港町として本格的な発展を遂げるきっかけとなったのは、一八五八年に清国が英仏と結んだ天津条約であった。
これによって淡水は台湾北部に開かれた最初の港となり、廈門(アモイ)や福州といった中国大陸との交易で栄えた。
また、当時はイギリスが台湾北部産の茶葉を熱心に購入しており、淡水はその積み出し港として賑わった。
しかし、この繁栄も長くは続かなかった。
日本統治時代に入った頃から深刻だった土砂の堆積で淡水の港湾機能は低下し、後発の基隆に商港の機能を譲ることとなったのである。
昭和時代には、すでに交易港として淡水の名が記されることは少なく、景勝地としての知名度の方が高くなっていた。
現在、港は完全に廃れ、わずかに対岸への渡し舟が残るばかりとなっている。
2 持主が転々と代わった英国領事館 top
港町だけあって、淡水は古くから西洋人との関わりを持っていた。
そして、台湾でいち早く外国文化が定着した町でもあった。
キリスト教の布教も北部においてはかなり早期に始まっており、今も教会や洋館が残る。
そんな背景もあって、淡水にはどことなく異国情緒が漂っている。 紅毛城は淡水へやってきた観光客が必ず訪れる場所である。
淡水駅から「老街」と呼ばれる古い町並みを抜け、しばらく進んだところに入口がある。
敷地内は緑が多く、その中に美しい洋館が見える。
ここは淡水河を見おろせる小高い丘の上にあり、眺めが素晴らしい。館内には歴史資料の展示があり、特に日本統治時代以前についての紹介が詳しい。 |

紅毛城と呼ばれるこの建物は古蹟とされ、
館内には歴史資料が展示されている。
|
また、隣接して旧イギリス領事館(領事邸)がある。ここには当時の暮らしぶりを再現した部屋などもあって興味深い。
紅毛城はスペイン人によって築かれたサンドミンゴ城を起源とするが、スペインがオランダに駆逐された後、その所有者は転々と代わっている。
開港後は英国領事館として使用され、清国政府から永久租借された。
これは日本統治時代に入っても受け継がれたが、一九四一(昭和一六)年、日英開戦によって英国領事が撤退すると、台湾総督府の所有となった。
そして、終戦後は再び英国政府に租借される。
さらに、イギリスが北京政府と国交を結び、中華民国政府と断交した後は、オーストラリア領事に管理が委託された。
さらにオーストラリアとの断交後は、アメリカが管理者となっている。
こういった経緯を経て、台湾政府の所有となったのは一九八〇年になってからであった。
3 今もなお人々に敬愛される宣教師 top
淡水の歴史を語る上で欠かせない人物として、ジョージ・レスリー・マッケイ(マカイ)の名を挙げておこう。
マッケイはカナダ出身の宣教師で、二八歳で英国長老教会の伝道師となり、一八七二年に淡水へやってきた。
そして、ホーロー語を学び、現地の風俗・習慣を身につけ、人々の信望を集めていった。一八九一年には淡水教堂を設立している。
マッケイは牧師としてだけでなく、医師としての顔も持っていた。
布教活動と同時に近代医学の普及にも努力し、一八七九年には台湾で初めての西洋医院である「滬尾偕医館(マッケイ医館)」を設立している。
さらに、マッケイは台湾で最も早く西洋式の教育を導入した人物でもある。
マッケイが開いた神学校は、一九一四(大正三)年に私立淡水中学(現淡紅中学)となった。
この学校は校舎が独特で、西洋ビザンチン様式と中国風寺院建築のデザインを融合させた八角楼と呼ばれる建物がある。
なお、現在の真理大学構内にある牛津学堂(オックスフォード・カレッジ)はマッケイ自身の設計によるという。
さらに、当時は珍しかった写真機を持ち込み、台湾各地の風俗文化を記録したのも功績の一つに数えられよう。
現在、淡水の繁華街である中正路と新生路の交差点にはマッケイの像が建てられている。
台湾で外国人の銅像が建つことは珍しく、この町とマッケイの深い関わりが感じられる。 |

マッケイ博士の像。淡水の町とマッケイは
切っても切れない結びつきとなっている。
市街地にはマッケイの像が
シンボルとして建てられている。
|
最後に、淡水でぜひ体験してほしい乗り物を挙げておこう。対岸の八里との間を結ぶ渡し舟だ。
わずか一〇分あまりの舟旅だが、観音山の美しい山容が楽しめるだけでなく、ベッドタウンとして発展する淡水の町並みも眺められる。
もちろん、夕焼けや夜景も美しい。淡水河は台湾では指折りの大河川で、河口付近での川幅は一キロを超える。
この渡し舟は今も住民の大切な交通機関である。
時にはニワトリや魚介類を運ぶ行商人などもいて、生活臭が感じられる。
河岸には遊歩道や公園も整備され、海鮮料理レストランなどもある。
4 烏来(うらい)――温泉郷として栄える山間の村
top
烏来は古くから日本人に親しまれてきた観光地である。台北からはMRT新店線とバスを乗り継
いで一時間あまり。日帰りが可能で、気軽に訪れることのできる温泉郷として人気がある。
「ウライ」とはアタヤル(タイヤル)族の言葉で「自然に沸いた熱湯」を意味し、温泉が湧き出る場所であれば、どこでも「ウライ」と呼ばれる(例えば桃園県にも「小烏来」を名乗る土地がある)。
ここも川原に湧いた露天の浴場かおり、随所から湯気が上がっている。
冬場や早朝、雨上がりには、立ちこめる湯けむりが見事な眺めとなる。
なお、アタヤル(タイヤル)の人々は、自然に沸騰する奇妙な水を毒水ととらえていたが、ある日、傷ついた鹿が温泉で傷を癒しているのを見て、温泉浴の効を知ったという言い伝えが残っている。
日本人がこの温泉を知ったのは、一八九六(明治二九)年のことだった。
烏来のゲートとなる屈尺という集落に駐在所が設けられた際、当時は「蕃務官吏」と呼ばれた山地勤務の警察官が出湯の存在を人々に教えられたという。
この時は、簡単な浴槽が設けられただけだったが、一九一〇(明治四三)年に烏来駐在所が設けられた際には、本格的な浴場設備が整えられた。
湯は無色透明で無臭の弱アルカリ性炭酸泉。カルシウムやナトリウムを多量に含有しており、胃腸病や関節炎、神経痛などに効能を持つという。
温度は六〇度前後で、内用すれば、消化不良や慢性腸カタルなどにも卓効があるという。
ここ数年、台湾は全土的な温泉ブームとなっている。その影響もあって、烏来も改めて注目を集めるようになっている。 |

古くから温泉で知られてきた烏来。
ここ数年、台湾でも温泉浴が
人気を集めている。
|
本格的なスパ設備を整えたリゾートホテルや「日本式」を謳った露天風呂をもつ浴場も増え、アタヤル(タイヤル)族の経営する民宿などもオープンしている。
これらの中には先住民の伝統料理や山菜料理を味わえるところもある。
5 高砂(たかさご)義勇隊の慰霊碑
top
烏来には日本統治時代に「高砂族」と呼ばれた先住民の戦没者慰霊碑がある。烏来を訪ねた際には、ぜひとも足を運んでみたい場所である。
高砂義勇隊は太平洋戦争中に日本軍として戦った先住民兵土たちのことである。密林におけるゲリラ戦に強く、兵士としては世界最強と評されるほどの戦闘能力を誇っていた。
一九四二(昭和一七)年、第一回高砂義勇隊が募集された(当時の名称は「高砂挺身報国隊」)。
以後、南方戦線に向けて合計七回の高砂義勇隊が派遣されている。
彼らの多くは口々に「お国のため」と言って戦地へ向かっていった。言うまでもないが、「お国」とは日本を示している。
終戦までの先住民従軍者数は六〇〇〇以上と言われるが、正確な数字は示されていない。 |

高砂義勇隊英霊碑。
高砂義勇隊は「日本人」として南方の島々に送られた。
しかし、終戦後の彼らは等しく不遇であった。(写真は移設前の様子)
|
ただ、戦死者が三〇〇〇人に及んでいることはほぼ確実だという。
終戦時、台湾の先住民総人口が一五万人程度であったことを考えると、この数字に凄惨さを感じずにはいられない。
さらに、激戦地へ送り込まれ、前線に立だされながらも、その身分はあくまでも軍夫・軍属であり、後方支援を任務としていた。
つまり、正規の軍人とは扱われなかったのだ。彼らは「義勇」の人員であり、軍人の地位は与えられなかったのである。
高砂義勇隊の正確な人数が示せないのもこれが理由の一つとなっている。
日本の敗戦で戦争が終結すると、彼らは生まれ故郷である台湾へ戻された。
しかし、そこはすでに日本領の台湾ではなく、蒋介石率いる国民党政府が新たな統治者として君臨していた。
復員兵土たちは、日本が台湾を放棄した時点で日本人ではなくなり、自動的に中国(中華民国)人にされてしまったのだ。
当然ながら、「敵国兵士」であった彼らへの風当たりは厳しいものがあった。
そればかりでなく、終戦後、一貫して行われてきた国民党政権の偏向教育の下、彼らはそれまでの半生を否定され、日陰で生きていかざるを得ないという状況を強いられたのである。
慰霊碑は一九九二年一一月に除幕式が行われている。
戒厳令の時代が終り、言論の自由が認められるのを待ってからの建立だった。
それまでは、戦没した「日本軍兵士」の英霊が台湾の地で祀られることはなく、日本政府もこういった事情を知っていながら放置してきた。
石碑には当時総統職にあった李登輝による「霊安故郷」の文字が刻まれている。
高砂義勇隊の出征時、台湾総督・長谷川清は隊旗を授けたと言われ、それにちなんで石碑の脇には日章旗も掲げられている。
除幕式には元高砂義勇隊兵士や、日本からの戦友が数多く参列したという。しかし、そこに若者の姿は少なかった。
アタヤル(タイヤル)族に限らないが、先住民の若者たちはこういった歴史にきわめて無関心である。
国民党政権時代の偏向教育についてはこれまでも触れてきたが、学校教育で中国(中華民国)人であることを教え込まれれば、自ずと彼らは「日本人」であった祖父母の世代を否定するようになる。
そして、年長者への敬意が失われれば、伝統文化を継承する意識も薄れていく。
この石碑は、アタヤル(タイヤル)族内における価値観と人生観の世代差が浮き彫りになった現場でもあるのだ。
そんなことを考えてみると、この石碑は、戦場で空しく散っていった同胞たちへの思いだけでなく、失われつつある伝統文化と部族精神を後世に伝えようとする老人たちの願いが込められているように思えてならない。
現在、この石碑を訪れる人が多いとは言えない。
日本政府は長らく彼らへの補償問題を放置し、時には一方的な決定を押しつけた。
処遇をめぐっては、日本人として従軍していながら、日本人兵士とは明らかに差があり、不公平であるとして解決は見ていない。
かって徹底した皇民化教育の下、若者たちは血書をしてまで高砂義勇隊の入隊を争ったという。
私も先住民の村々を訪ねた際、こういった話を耳にしたのは一度や二度ではない。
そして、生きて戻った兵士たちは、今もなお、高砂義勇隊に選ばれたことを誇りに思い、心身に深い傷を抱きながら、孤独な老後を過ごしているのである。
なお、この慰霊碑に土地を提供していた観光事業者は事業の不振から倒産し、今後石碑をどうするかが問題となっていた。
しかし、日本をはじめ各方面から多額の寄付が集められ、近くに移設されることが決まっている。
6 基隆(きいるん)――「雨港」と呼ばれた台湾の玄関
top
基隆は北部最大の港湾都市である。長らく台湾の玄関となっていた町で、日本統治時代は内地と呼ばれた日本本土との間に「内台航路」という連絡船が就航していた。
当時ここは、台湾を訪れる人々がその第一歩を踏んだ場所であり、敗戦で台湾から引き揚げることとなった人々にとっては、台湾最後の地となった。
戦前、台湾と関わりを持った日本人が、必ずや何らかの思い入れを抱いた町である。
基隆は別名を「雨港」という。この一帯は海上より吹きつける季節風のため、冬場になると決まって天候が崩れる。
この町は港湾以外の三方を山にはばまれているため、海洋で発生した水蒸気はこの山並みに遮られて雲となり、降雨をもたらす。
基隆と台北は距離にしてわずかに二八キロだが、基隆で雨が降っていても、台北は晴天ということが少なくない。
雨の基隆駅を出た列車が一〇分ちせず、ただトンネルを抜けるだけで青空を見るということもあるのだ。 |

「全台湾の門戸」と称された基隆。道路は港湾に並行するか、
垂直に交わるように整備されたという。
|
台湾の人々は基隆へ向かう仲間に向かって、「財布を忘れても傘は忘れるな」と声をかけるという。
実際、毎年一〇月を過ぎて北東の風が吹き始めると、三月頃までは毎日のように雨降りとなる。
そして、付けられた名前が「雨港」だった。
この呼称については、この時期に基隆を訪れてみれば、誰もが納得できるだろう。
基隆郊外に位置する暖暖測候所の記録では、年間二〇〇日の降雨は珍しくなく、大正時代には一年で三〇〇日も雨が降ったことがあったという。
また、降雨の時期は海上も大きく荒れることになる。長らく、降雨期に基隆へ着岸するのは困難であると言われてきた。
日本統治時代に入り、築港工事が施されるまでは、船体の小さい漁船は港内の航行もままならなかったという。
7 港都――基隆の歴史 top
「基隆」という地名の由来は興味深い。
この一帯は漢人住民がやってくる以前、ケタガラン族が集落を作って群居してい たという。
そこに明国末期、漢人住民が台湾南部から土地を求めて北上してきた。
そして先住の人々との間に幾多の葛藤を経ながら、この地に定住していった。
この町が転機を迎えたのは、一六二六年のことであった。
フィリピンのルソン島を拠点としていたスペイン人が現れたのである。
スペインは台湾南部に拠点を得たオランダに対抗し、台湾の東海岸を北上してこの地にやってきた。
そして、現在は和平島と呼ばれている社寮島に要塞を築き、これをサンサルバドル城と名付けた。
小さな漁村は一躍、外国勢力の拠点へと変ったのである。
しかし、キリスト教の布教にも人々の馴化にも失敗したスペインは、わずか一六年で台湾から撤退し、オランダも鄭成功によって駆逐された。
その後、一八世紀に入った頃から漢人住民の移住が急増した。中南部の平野部は開墾し尽くされ、新天地を求めて北上してきたのである。
一八五八年の天津(てんちん)条約では基隆の開港が決まった。
まずは安平(あんぴん)と淡水の二港が開かれ、ここは副港として打狗(ターカウ、現高雄)と共に税関が置かれた。
正式な開港は一八六三年である。一八六九年にはそれまでの「鶏籠」(ケーラン)という表記が「基隆」と改められた(現在も「基隆」は、ホーロー語では「ケーラン」と発音される)。
なお、「基隆」は「基地隆昌」という言葉にちなんだものである。この時点で、すでに軍事色の強い町であった。
「基隆」の表記が、日本語で何と読まれていたかというのも興味深い。当時からここは「きいるん」と呼ばれていた。
戦前の台湾の地名は、「蕃地」と呼ばれた先住民の居住地域以外は、漢字表記を日本語の音読みに従って読んでいた。
ここはその例外として、安平(あんぴん)と共によく知られている。
基隆は国際貿易港としての名称が「KEELUNG」で、清国統治時代からすでにこの名が定着していたので、それに従って日本語でも「きいるん」とされたのだ。
また、安平は歴史ある港町で、古くから日本との関わりがあったため、現地で使用されていた「あんぴん」の発音が継承された。
さて、基隆と日本は古くは倭寇(わこう)の時代より接点があったと言われるが、統治者としての日本は、一八九五(明治二八)年六月二日に初代台湾総督の樺山資紀が、基隆沖で清国全権委員の李経芳(りけいほう)と台湾授受の会見を行っている。
調印式は横浜丸の船上で行われ、以後、台湾は日本の統治下に入った。
日本統治時代の基隆は興隆の一途をたどった。基隆湾は天然の良港だったが、計画された港湾規模は大きく、築港工事も大がかりなものとなった。
ちょうど、台北の外港だった淡水が土砂の堆積で港湾機能を失いかけていた時期である。本格的な築港工事は一八九九(明治三二)年に始まった。
完成を急ぐため、工事は昼夜をわかたず進められたという。
そして、港湾の完成を待たずに軍港となり、その後、終戦まで付近一帯が要塞地区とされた。
そんな背景もあって、決して開かれた町ではなかったが、その活気は常に特筆されていた。
各地に向けて定期連絡船が就航し、港付近は終日人影が絶えなかったと言われている。
築港工事は当然ながら技師と多くの作業員が必要となる。総督府は日本から技術者を呼び寄せ、労働者として各地から台湾人を集めた。
一九三〇(昭和五)年末の統計によると、基隆の人口は八万七四〇〇人。そのうちの約二万人を日本人が占めていた。
つまり、全人口の二割以上を日本人が占めていたのである。
なお、常時五〇〇〇人近い外国人がいたのも港町ならではのものだろう。
その大半は日本国籍を得られなかった福州系中国人(福州人)で、主に港湾労働者として基隆に住んでいた人々だった。
基隆の町並みは築港工事と並行して整備された。
その美しさは台湾随一とも言われ、さらに一九〇七(明治四〇)年の都市計画で、整然とした道路配置が確固たるものとなった。
この時には、主要道路に沿った家屋のほとんどが、赤煉瓦建築で統一されたという。美しい建物が並ぶ商店街は基隆の自慢となっていた。
しかし、この美しさは終戦後には保たれなかった。すべての道路は自動車で埋め尽くされ、家屋が路地の隙間を埋めるように建ち並んでいった。元々、基隆は三方が山でふさがれているため、市街地は狭い。そこに無計画な開発が進められたため、住環境は極度に悪化し、交通渋滞がひどくなった。今やどこへ行っても排気ガスにまみれる町になり果ててしまった。
終戦までは「全台湾の門戸」と称されていた港も、以前ほどの賑わいはなくなっている。それでも、港町ならではの風情は残っており、個性的な町であることは確かである。最近は観光客を相手にした港湾巡りのフェリーも就航し、観光都市への脱皮を模索している。

廟の門前市から発達した基隆の廟口夜市。
港町らしく海鮮を扱う屋台が多いのが特色だ。
8 観光コースでない基隆を歩く top
町歩きの拠点となる基隆駅は、日本が台湾を領有する以前からすでに設けられていた。清国統治時代の末期、劉銘伝(りゅうめいでん)の時代に台湾最初の鉄道が敷設され、ここはその起点だったのだ。
現在の駅舎は、台湾ならどこでも見かけられそうな普通の建物だが、かっては台湾を代表する美しい駅舎に挙げられていた。
そのたたずまいは絵葉書にもなっていたほどである。 |

基隆駅前の蒋介石像。
雨の町として知られる基隆では、駅前の
蒋介石像も雨合羽を羽織っている。ここには
かって初代総督・樺山資紀の銅像があった。 |
残念ながら、老朽化を理由にこの駅舎は建て直されてしまい、その面影を感じ取ることはできない。
また駅前には蒋介石の銅像が立っている。終戦まで、ここには初代台湾総督・樺山資紀の像が立っていた。
現在も台座は日本統治時代のものが使われている。なお、この蒋介石像は、雨の町らしく、レインコートを羽織っている。
駅舎を背にして左手には基隆市営バスの乗り場があり、市内各所へ向けてバスが発着している。
この乗り場の建物にも注目したい。駅からは建物の背部が見えるだけなので、バス乗り場を越えて、港の側に回ってみよう。建物の正面はこちら側である。
ここは陽明海運という会社の事務所になっているが、かっては日本郵船の基隆出張所であった。
さらに、その隣の海關大楼という建物も見ておきたい。ここは基隆税関合同庁舎として造営された建物である。
船が基隆港に着くと、乗客はここで手続きを済ませて駅へと向かった。終戦時に台湾から引揚げた日本人は約四〇万人と言われる。
その多くがこの港から台湾を去っていった。そんな人々の記憶の中に、この建物はどのような印象を残しているのだろうか。
基隆港は台湾の門戸として重要な役割を担っていた。
突貫工事で整備が進められたという港湾設備は、大正時代を迎える頃にはすでに東西六五五メートル、南北一〇九一メートルの規模で、大型船舶の航行にもほとんど問題が起こらなかったという。
ちなみに当時、三〇〇〇トン級の汽船なら三五隻が停泊できたと言われている。
その後も、拡張工事は続けられ、機能性の高い港として知られていくこととなった。
基隆駅の脇には倉庫が並び、基隆税関の前を第一号岸壁として、北に第一八岸壁まで設けられていた。
その距離は四キロにも及び、貨物の引込線が基隆駅との間を結んでいた。
また、基隆駅付近は終戦まで明治町と呼ばれていたが、岸壁に沿って、大正町、昭和町と市街地が伸びていった跡が見える。
まさに港と共に発展した町であった。
なお、この町には廟口夜市という名の常設のナイトマーケットがある。
基隆駅から繁華街を抜けて一〇分ほどなので、ぜひとも訪れてみたい。
基隆の町並みは雑然としているが、それもこの町の個性と考えれば、趣が湧いてくるように感じられるはずだ。
ぎっしりと並んだ建物の間に、突如大きな廟が現れたりするので散策は楽しい。
9 宜蘭(ぎらん)――宜蘭と蘭陽平原の歴史
top

蘭陽平野のシンボルとも言うべき亀山島。
洋上に浮かぶその姿は確かに亀のようである。
長らく軍事管制下に置かれてきたが、
現在は夏場のみ入域が可能となっている。 |

頭囲橋。頭城は古い街並みが残る地方都市。
日本統治時代に架けられた橋が今も使用されている。
(写真の圍は囲の旧字体) |
台湾の北東部、蘭陽平原は蘭陽渓によって形成された沖積平野である。
土地が肥沃で、気候も温暖なことから、日本統治時代に積極的な農地開発が進められた。
現在は台湾を代表する穀倉地帯に数えられている。
蘭陽平原は、かって「鴫瑪蘭(カマラン、蛤仔灘とも)」と呼ばれていた。
これは先住のクヴァラン(カマラン)族に漢字を当てたものである。
クヴァラン族の人々は清国統治時代に漢人住民の移入で圧迫を受け、東海岸を南下するようにこの地を去っていった。
現在、この一帯で彼らの姿を見かけることはほとんどない。
蘭陽平原の開拓者としては、呉沙の名を挙げておかなければならない。
台湾の北東部に開拓の千が入ったのは、一八世紀も末にかかった頃である。
呉沙は福建省の漳州(しょうしゅう)出身の人物で、台湾へ渡ってしばらくは基隆付近に暮らしていたという。
その後、北部海岸を南下し、この地へやってきた。
開拓は一七九六年から始められ、先住の人々との間に小競り合いを繰返しながら、この地は切り拓かれていく。
その際、開墾した土地に外部の者が侵入しないよう、周囲に柵を設けた。
そのため、蘭陽平原には「頭囲」(とうい)「壮囲」といった地名が多く見られる。
宜蘭へ向かう手前には頭城という町があるが、ここもかっては「頭囲」を名乗り、現在もその名を冠した橋が残っている。
宜蘭は台湾東北部最大の都市である。
蘭陽平原の中心部に位置し、台北からは列車に揺られて約二時間の距離である。
清国統治時代は四方を城壁に囲まれていたが、これは日本統治時代に撤去されている。
地図を開けば、「舊(=旧)城路」という道路が市の中心部を円状に囲んでいる。ここがかっての城壁跡である。
日本人は城壁を撤去した後に濠を設け、石材を水道の整備に転用した。
城壁の跡地に濠を造ったのは、後述する新竹と同様である。
しかし、宜蘭の濠は埋立てられて道路となっているため、その痕跡を確認することはできない。
宜蘭に限らず蘭陽平原にある羅東(らとう)や蘇澳(すおう)といった町は、大正時代に入ってから急速な発展をみている。
穀倉地帯としての蘭陽平原は古くから知られていたが、日本統治時代に入ると、治水工事や品種改良が積極的に進められ、より大きな収穫を得るようになった。
そして、一九一九(大正八)年には台北・基隆と蘇澳を結ぶ鉄道が開通する。
平原ということもあり、道路網は比較的早期に整えられていたが、鉄道の開通で流通はより盛んになった。
さらに、木材や石材などの積出しには蘇澳の港が利用できる。
とりわけ、物資の輸送については理想的な環境だった。
さらに、蘇澳に発達したセメント工業も注目しておきたい。
一九三九(昭和一四)年に創業した台湾化成会社の工場は台湾屈指の規模で知られ、現在も台湾水泥公司蘇澳工場として操業を続けている。
そのほか、アルミニウム工業や製紙業なども昭和一〇年代に入ってから発達した。
これらはいずれも空襲の被害を免れなかったが、終戦後は比較的早期に回復し、地域経済を支える存在となった。
農業のイメージが強い蘭陽地方だが、基本的なインフラは日本統治時代にすでに整備され、さらに勤勉な人々の気性もあって、投資環境の良さで注目される土地となっている。
10 宜蘭公園に残る石碑 top
宜蘭の駅に降り立ったらまずは駅前通りを進んで市内最大の緑地となっている中山(ちゅうざん)公園を目指してみよう。
ここは終戦まで宜蘭公園を名乗っていた。開園は一九〇九(明治四二)年。
終戦後は孫文にちなんで「中山公園」と改められた。
公園自体は台湾ではよく見られる雰囲気で、亜熱帯性の植物が深く生い茂っている。
木陰には老人が憩い、中国将棋や雑談を楽しむ人たちで賑わっている。
そんな中を進んでいくと、突き当たりに大きな石碑が見えてくる。
この石碑は「獻馘碑」(けんかくひ)と呼ばれている。
台座だけでも見上げるほどの高さで、縦一二七センチ、横一一六センチとかなりの大きさだ。
碑文によれば、この石碑は公園が開かれたのと同じく、一九〇九(明治四二)年に建立されている。
この石碑は宜蘭のみならず、蘭陽平原、そして、台湾東部一帯を日本が制圧していった過程を物語る遺構である。
日本統治時代に入った頃、宜蘭はすでに都市機能を有しており、羅東(らとう)も物資の集散地として賑わっていた。
しかし、清国が治めていたのは蘇澳までの平地に限られていた。
山岳部にはアタヤル(タイヤル)族の人々が住んでおり、蘇澳よりも南には「南澳(なんおう)蕃」、蘭陽渓の上流には「渓頭(けいとう)蕃」と呼ばれる人々がいた。
いずれも勇猛なことで知られ、「出草」(しゅっそう=首狩り)の風習をもっていた。
漢人住民は先住民を恐れ、両者の間にはほとんど接触がなかったという。
勇猛なアタヤルに支配の手を伸ばしたのは総督府だった。 |

獻馘碑。総督府は先住民勢力を
鎮圧した際、帰順の証拠として守護神である
髑髏(どくろ)を供出させた。獻馘碑は
それらを安置した場所に建てられた。
|
地の利を得ない日本軍は、当初は大苦戦を強いられたが、圧倒的な武力で、徐々に形勢を逆転させていった。
当時、日本は先住民勢力を制圧した際、帰順の証拠として、銃器と、彼らが祀っている髑髏(どくろ)を供出させていた。
それはこの地でも実施され、百数十個という髑髏がこの場所に集められたという。
この石碑はその収蔵を記念して建てられたものであった。
日本統治時代はもちろんだが、現在でも、出草は「迷信による陋習(ろうしゅう)」、もしくは「怨念に起因する残虐行為」と考えられることが多い。
しかし多くの場合、出草は単なる復讐や仇討ちなどといった単純な動機ではなく生活と密接な関わりをもつ風習であった。
もちろん、その意味合いは部族によって異なるが、たとえば蘭陽渓上流の集落に住むアタヤル(タイヤル)族の長老は、どんな時に出草するのかという私の問いに、以下のような状況を挙げていた。
・解決しない論争の決着を付けたい時
・自らにかかった嫌疑を晴らしたい時
・冤罪をすすぎたい時
・凶事を未然に防ぎたい時
・少年が壮年の仲間入りをする時
・自らの武勇を示し、自己を誇りたい時
なお、首を取る対象は、異部族であれば戦士でなくてもよかった。
場合によっては、集落さえ異なればよいというケースもあり、「同族意識」が育まれるのを拒んできた。
なお、出草が成功するか否かは、すべて神霊の意思によるものとされていた。
出草後は、そのたびに祭事が催され、霊を慰める。
そして、取ってきた首を自らの集落の絶対的な守護神として、手厚く首棚に安置する。
帰順式で髑髏を差し出すことのためらいがいかなるものであったのか、それは想像に難くない。
総督府は出草を全面的に禁止し、同時に日本語教育を徹底させた。
これによって、異部族間のコミュニケーションが可能となり、出草は根絶されていった。
これを日本の功績だとする声は、現地においても頻繁に耳にすることである。
しかし一方で、この石碑のように日本がこの地で行った強硬な行政を伝える遺構も存在している。
なお、献馘碑の向かいには忠霊塔がある。これも日本統治時代に建てられた石碑で、一九三六(昭和一一)年八月に建てられた。
この石碑は終戦後、横倒しにされていたが、現在は郷土史蹟として扱われ、宜蘭県政府によって再び起こされている。
11 「西郷堤防」――治水工事の記念碑
top
台湾の河川はいずれも高峻な山々を水源としており、日頃の流水は少ないが、山間部に降雨があれば、それが谷間に集まって、一気に流れて激流と化す。
当然、氾濫が多く、人々はそれに苦しめられてきた。
そのため、台湾では流水が少なくても河川敷をたっぷり確保して堤防を設ける。これは洪水を防ぐための知恵なのだ。
蘭陽平原は肥沃だが、たび重なる水害と降雨期以外の水利の悪さのため、大規模な開墾は難しかった。
この土地を開拓した呉沙が英雄視されるのも、治水を意識した開拓を進めたからだという。
日本統治時代に入ってからも、そういった状況は変わらず、町と農耕地を守るための治水工事が早くから計画されていた。
宜蘭の町はずれを流れる宜蘭河の堤防上に、古い石碑が建っている。 |

宜蘭の町を護り続ける「西郷堤防」。
石碑は現在、郷土史蹟に指定されている。
|
高さは台座を含めると二ノートルに近いのでかなり目立つ。
この石碑は「西郷廳憲(ちょうけん)徳政碑」という。
一八九七(明治三〇)年五月から約五年間、宜蘭支庁長に任ぜられていた西郷菊次郎を記念した石碑である。
西郷菊次郎は西郷隆盛が奄美大島に流された際、島の女性、愛加那との間にもうけた子供である。
二四歳で外務省に勤務し、米国への留学を果たす。そして、下関条約が締結された一八九五(明治二八)年、台湾総督府の参事官心得を命ぜられ、初代総督・樺山資紀と共に、横浜丸で渡台している。
彼は牡丹社事件(五章16、参照)の西郷従道(つぐみち)の甥でもある。
西郷が宜蘭在任中に最も力を入れたのが治水工事であった。宜蘭は地域の中枢として発展していたが、宜蘭河の氾濫に民衆は常に悩まされていた。
そこで、西郷は治水工事に尽力し、水害を根絶させたのである。
石碑は現在、中山橋と呼ばれる橋梁の脇に残っている。碑文は漢文で西郷菊次郎の徳政について記されている。
それによれば、この治水工事には三万九〇〇〇円の巨費が投じられたという。
一六六〇メートルの河床が固められ、堤防が設けられた。工事は一年半に及び、動員された人員はのべ七四万人に及んだという。
そして、治水工事が竣工すると、確かに水害はなくなり、民衆有志によって石碑の建立が発起された。
なお、この堤防は「西郷堤防」、もしくは「西郷堤」と呼ばれていたという。
しかし、終戦後は、この石碑も報われない運命を歩むこととなった。
一九四九年、国民党政府と共に外省人と呼ばれる人々が大挙台湾へ渡ってきた。
その際、住む場所のない下級兵土たちは、日本人の引揚げで管理者がいなくなった神社や公園などにバラックを建てて住みついた。
この堤防も例外ではなかった。これは不法占拠であり、家屋もすべて違法建築だった。
しかし、国民党政権下では、長らく黙認されてきた。石碑はこういった家屋に埋もれ、忘れられていたのである。
その後、堤防上のバラックが取壊された際、ほぼ無傷の状態でこの石碑が見つかった。
バラックに埋もれていたために、風雨に哂されることがなかったのである。
保存状態はかえって良く、二〇〇一年六月には宜蘭県より古蹟の指定を受けた。
現在、石碑は場所を少し移されているが、郷土史蹟として手厚く保存されている。
延々と続く長い堤防は、今も宜蘭の町を守り続けている。

南方澳の漁港は接岸条件としては東海岸随一と言われる。
漁獲高も有数の規模を誇る。
12 蘇澳(すおう)――台湾有数の良港を抱く町
top
蘇澳は台湾有数の港湾都市である。特に東海岸では、台東県の成功と並んで二大漁港と称される存在だ。
蘭陽平原で収穫された物産の積出港としてもその名を馳せてきた。
なお、蘇澳の日本語での読みは本来なら「そおう」となるが、領台当初に「すおう」と誤読され、これが定着していた。
終戦まで公的にも使用されていたので、本書でもこれに従っている。 |

蘇澳冷泉。常温のままでも効能があ
るという冷泉。現在は公園として整
備されている。 5月から10月までは
特に多くの行楽客でにぎわう。 |
蘇澳の市街地は駅周辺と港のある南方澳に分かれている。
現在は鉄道駅を中心に町が開けているが、南方澳まではバスで一〇分ほどなので、ぜひこちらも訪れたい。
漁港のすぐ脇には市場があり、水揚げされたばかりの海の幸をその場で調理してもらい、味わうことができる。
この町の名物としては、冷泉の存在を挙げておきたい。冷泉は常温のままで温泉と同じ効能があるという奇泉である。
無色透明の炭酸泉で、飲用も可能だ。胃病や結石のほか、糖尿病にも効果があるという。
なお、冷泉は豊富な地下水脈があること、そして、石灰岩の厚い地層があることが条件とされる。
冷泉は日本統治時代の初期、竹中信景という人物が、七星山の麓に湧くこの泉の存在を耳にし、興味をもったのが起源であるという。
その前から、気泡を含んだ不思議な泉の存在は知られていたが、人々は水棲動物が全く見られないこの泉に近付くことはなかったという。
その後、冷泉には療養効果があることが判明し、徐々に脚光を浴びていく。
しかし、冷泉の名が全土的に広まるきっかけとなったのは、実は冷泉浴ではなく、「ラムネ」であった。
炭酸を含む湧水を用いた清涼飲料水が人気を博したのである。現在、ラムネ工場はなくなってしまったが、冷泉を用いたラムネは今も人々に知られており、この地の名物となっている。
なお、「ラムネ」という単語は、台湾では日本語のままで通用する語彙の一つとして知られている。
蘇澳の歴史をたどってみよう。
先住民の人々をのぞくと、蘭陽平原を最初に開拓したのは、呉沙をはじめとする漢人の開拓民たちであった。
しかし、それよりも前に、この地に住みついていた人々がいたこともわかっている。
一六世紀中葉、倭寇と思われる集団がこの一帯を拠点としていたのである。
日本統治時代の文献にも、台湾東北部に「日本人」がいたと記されていることは多い。
しかし、彼らは水と食糧の補給基地としていただけで、ここに定住することはなかったようである。
そして、倭寇の衰退と共に消え去っていった。次に現れたのはスペイン人であった。
当時の蘇澳は小さな漁村に過ぎなかったが、スペイン人はこの地に「サンロレンソ」という名を付け、中継地とした。
しかし、スペイン人がこの地に絡んだ時代は短く、現在、蘇墺にスペインとの歴史的関わりを伝える史蹟は見られない。
その後、漢人住民が開拓にやってくる。
「蘇澳」という地名は、蘇十尾という人物が四四人の部下を引き連れて、この地を開拓したことにちなんでいる。
なお、「澳」とは入江を意味する言葉である。
|

フランス艦隊を迎撃した砲台。日本統治時代には
隣接して金刀比羅神社が鎮座していた。
港と海原を見おろせる景勝地でもあった。
|

南天宮。航海の安全を祈願するため、
台湾の港町には必ず媽祖廟がある。
ここ南天宮は翡翠や純金製の媽祖像があることで知られている。
|
一八八四年には清仏戦争にともなって、蘇澳はフランス軍の侵攻に遭っている。
これを受け、港が見おろせる高台に砲台が築かれた。
日木統治時代に入ると、この場所には港と航海を鎮護する社として金刀比羅(ことひら)神社が設けられた。
しかし、現在は砲台も神社もわずかにその痕跡を残すばかりである。
蘇澳に港が開かれたのは一八九七(明治三〇)年のことだった。日本が台湾を領有してから二年後のことである。
当時、すでに蘇澳は漁港の機能を持っていたが、その施設は極めて小規模なものだったという。 周囲を海で囲まれた台湾だが、意外にも水産業の歴史は浅い。
これは漢人住民が基本的に農業を糧とし、漁業への関心が低かったことが理由とされる。
台湾土着の先住民ではアミ族やタオ族が漁労を知っていたが、いずれも原始的な手法による零細漁業に過ぎなかった。
台湾に水産業を持ち込み、発展させたのは日本人であった。
一九一〇(明治四三)年、総督府内に水産係が置かれ、主に漁法の研究が進められた。
この時、最も重視されたのは鰹節製造と養殖業だったという。
この一石は、その後も順調に成長し、台湾における水産業の中核をなしていく。
特に台湾南部で発展した養殖業は地域を支える基幹産業となり、屏東県や台南県では現在も養魚池を頻繁に目にする。
日本統治時代、港湾都市として知られたのは北の基隆と南の高雄であった。
しかし、一九一九(大正八)年に宜蘭線が開通すると、その終着駅となった蘇澳も後発の港として注目を集めていく。
そしてそれまでは陸の孤島と言われていた花蓮港(現・花蓮)へ向かう定期航路が就航し、乗継客でも賑わうようになった。
一九二一(大正一〇)年には港湾施設の拡張工事も施された。
さらに一九三一(昭和六)年には、歩行道路としてのみ機能していた臨海道路の拡張工事が終り、花蓮港との間に自動車による陸上交通も開かれた。
大正期、蘭陽平原に灌漑設備が整備されると、瞬く間に耕地は広がった。
稲作はもちろん、サトウキビの栽培も始められた。
そして、収穫された農作物は蘇澳の港から搬出されていった。
阿里山や八仙山と並ぶヒノキの産地となっていた太平山の木材も、森林鉄道で羅東へ運ばれ、蘇澳へと持ち込まれた。
さらに昭和時代に入ってからは、背後に控える山岳地帯から大理石や雲母、そして石灰石が豊富に産出されるようになる。
現在も、蘇襖から花蓮方面に鉄道で南下していくと、駅ごとに石灰石の採掘場やセメント工場を目にすることができる。
大戦後は、高雄港の急成長と日本統治時代に起工した花蓮港が完成したことを受け、蘇襖港の重要性は以前ほどではなくなった。
それでも、南方澳は漁港として以前と変らぬ賑わいを見せており、港町ならではの風情が漂っている。
13 沖縄と密接な関係を持った町 top
琉球弧(南西諸島)の最西端となる与那国(よなぐに)島から台湾までの距離は一一一キロ、与那国島から石垣島までは一一七キロである。
つまり、与那国から見れば、石垣島よりも台湾の方が距離は近い。
海霧の関係もあって、与那国の小さな島影を台湾から眺めることはできないが、与那国からなら、天候次第で台湾の山並みが見えるという。
古くから、遭難した琉球船が台湾島に漂着することはしばしばあったようだが、与那国と台湾の歴史上の交流は、台湾が日本の統治下に入ってからとなる。
これは沖縄と台湾の交流の始まりでもあった。
台湾が日本の統治下に入ると、沖縄から多くの人々が台湾に渡っていった。
巡査や教員、鰹節工場や建設現場での労働者など職種は多岐にわたるが、沖縄よりも社会規模が大きく、インフラ整備の進んでいた台湾は、就業機会も多く魅力的だった。
大正時代を迎える頃には約一〇〇〇人の沖縄人が台湾に定住していたと言われ、一九三五(昭和一○)年頃には、一万人を超えていたという。
一九二九(昭和四)年頃には、味噌や醤油といった食料品のほか、生活物資も台湾から与那国に持ち込まれており、与那国をはじめとする島々は、台湾の経済圏に組み込まれていた。
また、石垣島を中心とする八重山諸島からは多くの女性が女中奉公で台湾に渡っていた。
さらに一九三一(昭和六)年頃には、台湾から沖縄に多くの移民が渡っており(移民そのものは昭和初年から始まっている)、パイナップル栽培などに従事した。
さらに、沖縄に戦火が迫ってきた一九四四(昭和一九)年には、宮古と八重山を中心に、一万四〇〇〇人近くの沖縄県民が台湾に疎開している。
終戦を迎え、国民党政府は日本人が台湾に留まることを許可しなかったが、沖縄県民については希望者にこれを認めている。
終戦後、台湾に残った沖縄県民は三万人あまりいたという。
中華民国の立場としては、沖縄(琉球)は元々中国政権に帰属するという考えを持っており、これを自らのコントロール下に置きたいという意図があった。
日本人引揚者は「日僑」、沖縄県民は「琉僑」と言い分けたりもした。
もちろん、沖縄出身者が台湾で築いた資産は日本人と同様に没収され、困窮を味わうこととなったが、一部の人々は基隆の社寮島(現・和平島)に集まり、沖縄の中華民国帰属や独立を目指す動きを画策したこともあったという。
現在、台湾と沖縄との間には、さまざまな形で交流がある。
このところ、台湾から沖縄へは年間一〇万人から一二万人の観光客が訪れている。
一方、沖縄にとっても台湾は近くて大きなマーケットだ。
また、台湾で中国語を学ぶ沖縄の留学生は多く、沖縄県民だけが利用できる奨学金も用意されている。
現在のところ、蘇澳と与那国、八重山方面に直接の航路はなく、輸送機関はない。
しかし、蘇澳鎮(「鎮」は台湾の行政単位で市・町に相当)は石垣市と姉妹都市の関係を結んでおり、与那国町は花蓮市の姉妹都市となっている。
14 南澳(なんおう)――日本語が生きる村を訪ねる
top
南墺は蘇澳から南に一五キロほどの町である。
住民の多くはアタヤル(タイヤル)族の人々で、人口は六〇〇〇に満たない。
一平方キロあたりの人口密度はわずか八人という少なさである。
この町に限らず、先住民の住む村々を訪ねてみて、まず驚かされるのが、老年世代の人々が話す日本語の美しさであろう。
その流暢さには、誰しもが驚嘆を禁じ得ないはずだ。
そのレベルは外国語として習得したものではなく、あくまでも日常言語であり、当然ながら母語のレベルである。
私はこれまで、先住民に伝わる神話や伝承を取材するために、数々の集落を訪ねてきたが、そういった調査も時には日本語だけで事足りてしまうことがある。
コミュニケーションというレベルであれば、戦後生まれの人であっても、上の世代の影響を受け、日本語を操れることが珍しくない。
中でも、宜蘭県南部に住む人々は日本語が通用する確率が高い。
蘇澳から花蓮方面へ向かって鉄道に揺られると、東澳、蘇澳、武塔といくつかの集落を過ぎる。
これらの村では、日本統治時代とは縁の薄そうな若者たちでさえ、日常の会話に日本語が混じることがある。
私も南澳駅のホームで子供をあやす母親が日本の子守歌を唄っているのを聞いて驚いたことがある。
老人たちは決まって「全部、子供時代に習った日本語です。みんな忘れてしまいました」と謙遜する。
しかし、山地における日本語の定着度にはやはり驚かされる。
日本は台湾の隅々まで学校を設け、日本語の教育を実施したが、こういった村々を訪ねると、当時の教育がいかに徹底していたかを感じずにはいられない。 |

武塔(ブター)村には「愛国乙女サヨン遭難之地」の石碑がある。
召集された警察官の荷物を運び、激流に呑まれた少女の石碑である(移設前の様子)。
|
そして、終戦以降、日本との接点を失ってからも、日本語が台湾の地で独自の発達をみたことも注目しておきたい。
日本統治時代を迎えるまでは存在していなかった「兵隊」や「警察」といった言葉や桁数の大きい数字は、現地語にその概念がなかったため、日本語が直接入り込んで定着しているほか、明らかに終戦後に持ち込まれた「タクシー」や「動物園」といった言葉は、日本語が外来語として取り込まれている。
さらに、「台東県(日本統治時代の台湾に県はない)」や「台湾大学(終戦までは台北帝大)」といった単語は、日本統治時代には存在していなかったが、中国語の表記をそのまま日木語で読むことで、彼らの言葉となっている。
これらは一例にすぎないが、日本語が彼らにとって、いかに身近な存在であるかは理解できる。
しかし、日本人が行った教育が部族の言葉を奪ったという一面も見逃してはならない。
戦前の教育は彼らの生活様式を変えただけでなく、言語面についても変容を強いた。
さらに終戦後は国民党政権に日本の教育施設が受継がれたため、今度は徹底した北京語教育が実施されることとなった。
つまり、戦前と戦後、部族の言葉は為政者たちの教育によって、二度も奪われたのである。
現在、台湾土着の文化を尊重する政策が実施され、先住民各部族の母語教育にも相当な力がかけられている。
アタヤル(タイヤル)族についてもその例に漏れないが、村によっては、母語を常用レベルまで普及させるのは手遅れという事態も見られる。
もちろん、すべての若者が部族の言葉を話せないわけではないし、全く話せないという若者が多いわけでもない。
しかし、年々部族の言葉が廃れていることは事実で、その状況はきわめて深刻である。
最後に、山地の村々で見かける不思議な光景を紹介しておこう。
彼らの集落を訪れると、都市部と同様ほとんどの家に大きな衛星放送のアンテナが付いている。
門扉を閉めていない家が多いので、意図せずとも部屋の中が見えてしまう。
その際、老人がプロレスを見ていることがあるのだ。
台湾のケーブルテレビは世界でも指折りの普及率を誇り、各家庭でチャンネルが一〇〇近くあることは珍しくない。
中にはプロレスや格闘技を専門とするチャンネルも存在し、終日放送されている。
そして、こういった村では特にプロレスが娯楽番組として定着しているのである。
また、NHKに関しても、思わぬ視聴者が台湾に大勢いる。
これは山地に限らないが、大相撲とのど自慢は台湾でも人気が高く、その時間に合わせて帰宅するという老人もいるほどである。
のど自慢に関しては、政治的な制約と障害もあって実現は難しいというが、台湾での収録実現に向けて熱心な署名運動が展開されている。
15 桃園――今も残る日本時代の神社の遺跡
top
桃園は台北から鉄道で三〇分あまりの距離にあり、人口は約三四万。台北と新竹の中間に位置している。
古くは清国統治時代から交易都市として発達してきた町で、桃園県の県庁所在地となっている。
桃園という地名は清国統治時代にさかのぼる。南部より漢人住民による開拓の手が入った際、薛啓隆という人物が街路樹として桃を植樹したことにちなんで「桃仔園」という地名が誕生した。
その後、日本領有後の一九〇五(明治二八)年七月の地名改正で「桃園」と改められた。
市内に観光物件と言えるものはない。旅行者の姿を見かけることもほとんどないが、台北に近く、交通も便利なので、最近は日系企業の工場進出が目立っている。
市内には、日本人ビジネスマンを相手とした日本食レストランやナイトクラブなども見かけるようになっている。
また、桃園県や台北県、新竹県の工場には、フィリピンやタイ、インドネシアなどからやってきた外籍労働者が多い。
週末になると、桃園駅前は仲間を求めて集まる彼らで埋め尽くされる。
台湾は失業率の上昇や産業・技術の中国流出など、経済についての諸問題が後を絶たないが、ここはそういった現実の一部が垣間見られる町である。
この町にもかって神社が存在した。この旧桃園神社は現在、台湾で唯一、往時の姿を保った神社の遺跡である。
虎頭山という公園の山腹にあり、観光名所ではないが、最近は台湾史に興味をもつ日本人旅行者が訪れることも多くなっているという。
桃園神社は一九三八(昭和一三)年に創建され、九月二三日に鎮座式が挙行されている。
その後、毎年一一月三日が例祭日とされた。
祭神には台湾の守護神とされた北白川宮能久(よしひさ)親王をはじめ、大国魂命(おおくにたまのみこと)、大己貴命(おおなむちのみこと)、少彦名命(すくなひこなのみこと)、豊受大神(とようけのおおかみ)、そして、明治天皇が祀られた。
なお、終戦直前の一九四五(昭和二〇)年四月一二日には県社に列格されている。
この神社が創建された当時、台湾では人々の日本への同化を狙った皇民化運動が展開されていた。
神社もその一環として各地に設けられた。当時、戦争に勝利するために、一人でも多くの「日本臣民」を作り上げることが急務だった。 そして、総督府は信仰を通じて愛国烈士を育てようと試みた。 |

台湾には200を超える神社が存在していたが、
現在、本殿が残るのは桃園神社だけとなっている。
現在は忠烈祠として中華民国軍兵士の英霊を祀っている。
|
つまりこの時代に設けられた神社は、等しく戦時体制下における戦争協力者の養成という意味合いを含んでいたのである。
長い石段を上りきると、正面に大きな鳥居が見える。
上部が撤去されていて、完全な形ではないが、鳥居であることは誰の目にも明らかだ。
そして、参道の両脇には石灯籠が並ぶ。
さらに進んでいくと、左手には手水(ちょうず)舎が残り、右手には社務所が当時の姿を保っている。
手水舎には手水鉢も残っており、木造平屋の社務所は忠烈祠の管理所となっており、管理人の住居を兼ねている。
さらに、神馬像を見ながら石段を上っていくと、拝殿と本殿がある。
この敷地を取り巻いている雰囲気は、まさに神社そのものである。
16 中華民国の忠烈祠へと変った桃園神社
top
終戦を迎え、桃園神社は国民党政府に接収された。そして、忠烈祠へと転用される。
本殿には抗日戦争で命を落とした中華民国軍兵士の英霊と、「中華民族」の英雄とされる鄭成功らが祀られるようになった。
ここで忘れてはならないのは、きわめて特殊な一部のケースを除いて、終戦前の台湾人が中国軍人の立場で日本と戦った事実はないということである。
つまり、中華民国兵士として日本軍と戦った軍人を祀る忠烈祠と台湾人との関係は、きわめて薄いのである。
戦前、日本は台湾の人々に神社の参拝を強いたが、それと同様に、忠烈祠も外来の統治者が台湾の人々に参拝を強要し、愛国心の修養を押しつけた現場なのである。
こうした忠烈祠は終戦後、政府の手で台湾各地に設けられた。しかし、それらを訪れてみると、忠烈祠に対する地域住民の無関心さに驚かされる。
実際に足を運んでみると、辺りは静まりかえり、人の気配も感じられないことも多い。
もしくは、緑豊かな「憩いの場」と認識され、家族連れやカップルなどが散策を楽しむ場所となっているかもしれない。
いずれにしてもその様子は、忠烈祠と台湾の人々の間の「距離」を物語っている。
17 桃園神社はなぜ残されたのか top
では、なぜ、桃園神社の施設が現在まで往時の姿を保ってきたのか。 先にも述べたように、日本による統治の象徴とも言える神社は、終戦と同時に敵性資産として国民党政府に接収された。
桃園神社は一九四六年に忠烈祠に改められている。
当時は施設を改築する余裕はなかったので、神社の施設はそのまま使用された。
これによって、外観は神社のままで、祭神だけが中華民国軍兵士の英霊に代わるという奇妙な事態となった。 一九八五年には一度、忠烈祠の新社殿造営が計画された。
神社は木造であり、老朽化が進んでいるというのがその理由であった。
しかし、この計画には建築家や文化財保存団体が反対する動きをとった。 |

旧桃園神社の拝殿内には日本統治時代の賽銭箱まで残っている。
神苑には神馬像や手水舎、社務所なども残っている。
|
中でも、建築関係者はその学術的価値を強調し、熱心な保存運動を展開したという。
かって全島に二〇〇以上あった神社は、国民党政府の反日政策ですべて撤去されてしまった。
しかし、このままでは過去を感情的に否定するあまり、歴史そのものを失ってしまう。
国民党政権下、日本統治時代の半世紀は徹底的に否定されてきたが、郷土の歴史を直視するために、こういった遺構は敢えて残しておくべきだという主張が展開されたのである。
結局、行政側との話合いの末、神社とそれに付随する家屋群は、「古蹟」として保存されることとなった。
神社建築を知る戦前生まれの建築士たちが、修復工事にあたった。一年間で総費用は八〇〇万元(邦貨三二〇〇万円程度)を費やしたという。
台湾で唯一残った日本統治時代の神社。ここは、郷土の歴史を客観的にとらえようとする姿勢から残された「遺構」である。
確かに、神社は植民地統治下に設けられた「負」の遺産であろう。
しかし、それを「生きた教材」として活用していこうとする姿勢が、いま台湾では主流となっている。
これは台湾意識(本土意識)の高揚と、言論の自由を得た時代の産物であり、民主化の下、変貌を遂げる台湾の胎動でもあるのだ。
18 新竹(しんちく)――活気みなぎる産業都市
top
新竹は台湾北西部の中枢となっている産業都市である。
人口は約四〇万。台北から特急・自強号で一時間あまりの距離である。
町の歴史は古いが、ここ一〇年ほどで大きく発達した新興都市でもあり、産業面における台湾の強さを感じさせる町でもある。 郊外にはlC産業とコンピュータの周辺機器の生産で知られるサイエンスパークを抱き、外国人エンジニアの姿も目立つ。
その発展ぶりは「台湾のシリコンバレー」とも称されるほどで、大学や研究機関が集まっていることも特色とされる。
この町は強風の吹く町として知られてきた。特に冬場に吹きつける季節風は強く、清国統治時代の新竹は「風城」とも呼ばれていた。
さらに、冬場から春先は山岳部から冷風が吹き下ろすため、意外なまでに冷え込みが厳しい。 |

新竹の夜景。ハイテク産業のメッカとして知られる
新竹市には外資系企業も多く集まっている。
迎曦門(げいぎもん)前の広場はギャラリーとして使用されている。
|
この風は次高(つぎたか)山の名にちなんで、「次高おろし」と呼ばれていた。
次高山は標高三八八六メートルで、終戦まで、新高(にいたか)山に次ぐ日本第二の高峰であった。
命名は皇太子時代の昭和天皇による(現在は雪山(シュエサン)と呼ばれている)。
この風は、新竹特産のビーフン(米粉)にも影響を与えている。山から吹き下ろす風と海から吹き付ける風を当てることで、ビーフンに独特の歯ごたえが出てくるのだ。
なお、新竹と並んでビーフンの産地とされる南投県の埔里(ほり)も、中央山脈から吹き下ろす冷風で知られている。
新竹地方は台湾北部において、最も早く開拓が始まった土地である。その歴史は三〇〇年ほど昔にさかのぼる。
当初、ここに住んでいたのは平埔族のタオカス族であったという。オランダ人が編纂した地図には、「竹塹」(テッツァム)という集落がこの辺りに存在している。
一帯は草原が広がる沃野となっていたため、漢人住民の入植と同時に、開墾が急速に進んでいった。
鄭氏政権が崩壊し、台湾が清国の版図に入ってからは、中国大陸南部から移民が大量に流入してきた。
人口が急速に増加する中で、先住の人々は山間部へ駆逐されるか、漢人と混血していくかのいずれかとなった。
鄭氏政権の末期、この地で漢人とタオカス族の争いがあり、敗れたタオカス族が竹東と南庄方面へ追いやられ、これが後にサイシャット族を形成するようになったという言い伝えも存在している(これについては確証がなく、当時、平地に居住していたサイシャット族が山地へ退転したという説が有力である)。
いずれにしても、漢人との接触を経て、タオカス族は部族としてのアイデンティティを失っていった。
日本統治時代に入り、一九〇一(明治三四)年に新竹庁が置かれると、ここは台湾北部における行政の中心となった。
その後、市区改正が施行され、都市計画によって町並みは一新された。新竹庁は新竹州に改められ、神社、専売局、地方法院、少年刑務所などが置かれた。
そして、新竹は名実ともに台湾北西部の中枢となっていった。
一九三〇(昭和五)年には宜蘭や嘉義と共に市制が施行され、新竹市となっている。
一九三四(昭和九)年末に編まれた統計では、当時の人口は五万四〇〇〇あまりとなっている。
そのうち、日本人は約六〇〇〇人を占めていたという。
終戦後の新竹は、国民党政府と共に中国大陸を追われてきた外省人が多く住む町となった。
市内各所に「谷村」と呼ばれる外省人集落が形成され、その数は現在も四六を数えている。
新竹は日本統治時代に軍の飛行場が設けられていた関係で、終戦後も空軍関係者が多く住みついた。
現在、新竹市は総人口の約四分の一が外省籍であると言われ、統一派勢力の根強い地盤となっている。
なお、市内には台湾で唯一の谷村の暮らしと文化を紹介する博物館がある。
19 観光コースでない新竹を歩く top

新竹の玄関として機能する駅舎。
戦前のターミナル建築の風格を今もまとっている。 |

新竹市政府。日本統治時代に新竹州庁舎だった建物が
現在も使用されている。 |
台北から新竹へはバスを利用するのが便利だが、往路にはぜひ鉄道を利用したい。
それはこの町の表玄関である新竹駅に降り立つことができるからだ。
創設以来、町の顔として機能してきた老駅舎である。
この駅舎は一九一三(大正二)年一二月三一日に竣工したものである。
それ以来、基隆駅や台中駅と並んで、台湾を代表する駅舎建築に数えられてきた。
建物としては大きくないが、駅前へ出て振返ってみれば、その壮麗さが伝わってくるはずだ。
ドイツ風ネオバロック様式の建物は、直線で構成された屋根のラインが印象的で、優美な中にも厳(いか)つい表情を持ち合わせている。
この駅舎の設計者は松ヶ崎萬長(つむなが)である。
松ヶ崎は一八七一年に弱冠一三歳で遣欧使節団のメンバーとしてドイツに渡り、ベルリン工科大学で建築を学んだ人物である。
日本で最初にドイツ建築を紹介したことでも知られ、日本建築学会の創設にも関わっている。
彼は一九〇七(明治四〇)年に台湾総督府鉄道部の嘱託技師として台湾へ渡ってきた。
在職中は基隆駅や台北鉄道ホテルの設計に携わり、そのほか、いくつかの駅舎建築を手がけている。
駅前通りとなっている中正路を進んでいくと、突きあたりに迎曦門(げいぎもん)がある。
大きなロータリーの中央に城楼がどっしりとした構えを見せている。新竹もかって城壁に囲まれた町であった。
城壁は一八二七年から二年間にわたる工事を経て完成したという。
当初は四つの城楼が設けられていたが、これらは日本統治時代の都市計画で、東門(迎曦門)を除いて撤去されてしまった。
一九〇一一(明治三五)年に東門から南門の間が取り壊されたのを皮切りに、城壁も次々と撤去されていった。
当時、台湾は治安の維持と衛生事情の改善が優先されていた。
城壁を撤去する際に取出された石材は、兵営の造営と上下水道の整備に使用されたという。
迎曦門付近の城壁の跡には濠が設けられた。この濠は緑地として整備され、公園のようだったという。
残念ながら、終戦後、無秩序な開発によってその眺めは過去のものとなっていたが、ここ数年間で改めて整備された。
現在は市民の憩いの場と変り、「親水公園」と呼ばれて親しまれている。
迎曦門のロータリーから中正路をさらに進んでいくと、新竹市政府(市役所)がある。
ここは日本統治時代の新竹州庁舎である。この建物は一九二六(大正一五=昭和元)年から使用されている。
二階建てで「コ」の字型をしているのは、陽あたりと風通しを考慮した結果だったという。
正面に立ってみると、赤煉瓦の落ち着いた色合いが印象的だが、屋根の部分には黒瓦が用いられ、さりげなく東洋的な雰囲気が混じっている。
荘厳な雰囲気を強調するのは、日本統治時代に一貫してみられる官庁建築の特徴であった。
新竹市政府の前には警察署と消防署が中山路を挟んで対峙している。この一帯は日本統治時代は表町と呼ばれていた。
消防署は現在、消防博物館となっており、内部の参観が可能だ。
また、市政府の後方には、戦時中に竹東方面で開発が期待された天然ガスの研究所も置かれていた。
この建物は現在、新竹市衛生局として使用されている。
なお、新竹市政府の正面を走る中山路を進んでいくと、城陛廟(じょうこうびょう)がある。
ここは一七四八年に創建された古刹で、新竹で最も賑やかな廟として知られている。
敷地内には味自慢の屋台が並んでいるので、新竹の名物であるビーフンや槓丸湯(コンワンタン、すり身団子のスープ。一般的には「貢丸湯」と表記するが、新竹では「槓」の字が用いられることが多い)をぜひとも賞味したい。
新竹は台南や基隆、彰化などと同様、大型レストランは少ないが、小さな屋台で食べる軽食がとても美味しい町である。
廟内には歌仔戲(コーアーヒー、台湾オペラ)の常設ステージもあるので、そこで観劇もできる。
台湾の伝統芸能にも、機会があれば触れてみたいものである。 |

城隍廟の敷地内には歌仔戲(台湾オペラ)の常設ステージがある。
|
top
****************************************
|