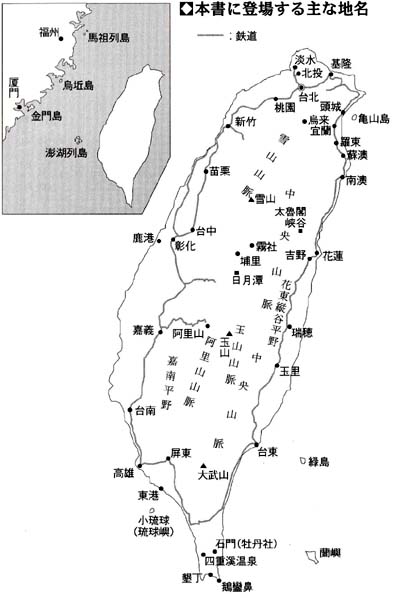|
****************************************
HOME 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章
六章 台湾東部
1 花蓮(かれん)――人口の四割を日本人が占めた新興都市
top
花蓮は台湾東部の中枢である。
市域人口は一一万を切るが、隣接する吉安郷を含めた都市圈としては、台東を上回って東部最大の都市となる。
太魯閣(タロコ)峡谷観光の起点でもあり、ガイドブックなどでは必ず紹介される町となっている。
花蓮は台湾で最も若い都市である。この町が開かれたのは明治の末期からで、清国時代の漢人住民の入植もかなり遅れて始まっている。
それは、台湾南部からの移民が台湾の南端を経由して台東に着き、そこから北上して花蓮付近に到達したことに起因している。
ちなみに、この一帯に漢人住民が入植したのは一八七八年頃だったという。
日本統治時代、この町の名は花蓮港(かれんこう)であった。
ここには「港」という文字が含まれているが、以前から港湾が存在していたわけではない。
現在は日本統治時代に起工した築港工事によって(完工したのは戦後)、港の規模は台湾でも指折りのものとなっているが、元々は港湾都市ではなく、当時の地名がすでに「港」の字を含んでいた。
荒野が広がる無人地帯だったというこの地には、北部アミ(南勢アミ)族と呼ばれる集団が住んでいた。
彼らは小さな集落を作って暮らし、狩猟と採集を糧としていたという。
簡単な農耕も知っていたようだが、降雨量の季節差が大きく、川の水も石灰分を含んでいるため、本格的な農業を行うことは難しかった。
日本の統治が始まった当初、台湾東部は全体が台東庁に属していたが、一九〇九(明治四二)年になって花蓮港庁が置かれた。
当時、花蓮北方の山岳部にはタロコ族の人々が住んでいた。
一方、北部アミ族も集落ごとに連合し、これに対抗していた。
アミ族は基本的には出草(しゅっそう、首狩り)の習慣がなく、現在は「歌と踊りの民」という優雅なイメージが定着している。
しかし、武勇を尊ぶ精神性は他部族に決してひけを取らない。中でも北部アミ族が勇敢なことは広く知られていた。
この人々が歩むこととなった運命は、後述の吉野移民村の項で触れたいと思う。
花蓮は日本統治時代に入ってから本格的な開発が始まった町である。
住民構成についても興味深い数字が残っている。
日本統治時代、この町の住民の約四割は日本人で占められていた。
これは当時としては異例の数字である。
一九三五(昭和一〇)年末の人口統計では、総人口一万六四八一人に対して、日本人は六五一五人となっている。
終戦を迎えるまで、台湾でここまで日本人の比率が高かった町は見られなかった。
そういった事情もあって、現在、花蓮市内を散策していると、いたるところで日本式の木造家屋を見かける。
中でも旧花蓮駅付近や中山路一帯、また、かっては神社であった忠烈祠付近などに多く見られる。
こういったエリアでは路地に漂う雰囲気そのものが、どことなく日本的である。
最近は、こういった木造家屋の趣が注目され、喫茶店やレストラン、パブなどとして利用されるケースが見られるようになっている。 |

日本統治時代は港の有無を問わずに「花蓮港」を名乗っていた花蓮。
日本式の木造家屋が多く残る。
中には喫茶店などとして生まれ変るケースもある。
|
2 太魯閣(タロコ)峡谷――時代に翻弄された部族と台湾最大の景勝地
top

日本統治時代の山岳道路を整備した緑水歩道。
下に見えるのが戦後に開通した東西横貫公路だ。
ここは台湾を代表する景勝地である。
毎日、旅行者を満載した大型バスが花蓮からこの地をめざしてやってくる。
二〇〇三年七月には蘇澳(すおう)−花蓮間の鉄道が電化工事を済ませ、台北を早朝に出発すれば、日帰りも可能となった。
この大峡谷は大理石の岩盤が立霧(たつきり)渓という河川の浸食を受けてできたものである。 両側には切り立った断崖が迫り、巨大な一枚岩に圧倒される。 |

太魯閣(タロコ)は大理石の岩盤が
浸食されてできた大峡谷。
台湾を代表する景勝地となっている。 |
この付近は硬質の岩盤で形成されており、その谷間を「東西横貫公路」が走る。
これは花蓮県と台中県を結ぶ全長一九三キロの山岳道路である。
この一帯の地質は複雑をきわめている。
異なる岩性地層が複雑に絡み合っており、各種鉱物が豊富に埋蔵されていた。
大理石や片麻岩のほか、工業原料となる石灰石、白雲母、長石、石英、さらに金や銅、鉄なども確認されていた。
蘇澳と花蓮を結ぶ臨海道路も、こういった鉱産資源の採掘が敷設の目的に含まれていた。
太魯閣峡谷の入口までは花蓮からバスで三〇分ほどの距離である。
太魯閣国家公園入口のゲートを過ぎると、すでに前方には高峻な山々が迫り、息を呑むような景観が広がっている。
かっては険しさで知られたこの道路だが、現在はトンネルの整備と道路の拡張工事が進み、一部を除いて快適な旅が約束されている。
その分、車窓からの景観は楽しめなくなってしまったが、旧道は遊歩道として開放されているので、のんびりと散策が楽しめる。
ゲートから三キロほど進んだところには長春祠がある。
岩盤の割れ目から水が噴き出し、滝のようになった上に祠(ほこら)が設けられている。
ここには東西横貫公路の建設で殉職した二一二人の工員が祀られている。
工事は中華民国の退役軍人が動員され、道路は一九六〇年五月九日に開通している。
工事の際、台中県側では食料不足を解消するため、沿道の河岸段丘や山の斜面を無計画に切り開いて農場にし、道路の完成後、工事関係者に土地を分け与えてしまった。
これが果物や野菜を栽培する農園として貸し出され、表土流失などの環境破壊を招いた。
一九九九年の台湾中部大震災でも大規模な土砂崩れに見舞われたのは記憶に新しい。
なお、この峡谷で最初に設けられた道路は日本統治時代につくられた軍用道路で、この工事では二三八名の犠牲者を出している。
峡谷のハイライトとなるのは、燕子口(イエンツコウ)と錐麓(フェイルー)大断崖、そして九曲洞(チョウチュイトン)の辺りだ。
燕子口は向かいの断崖までがわずかに一六メートルあまり。岩肌にあいた無数の穴はイワツバメの巣となっており、この地名の由来となっている。
錐麓大断崖は道路工事の際に、最大の難所とされた場所である。対岸に迫る岩盤は、筆舌に尽くせない迫力だ。
この辺りの最高地点は一六六六メートルもあり、昼間でも太陽が差し込みにくいので薄暗い。
かっては、ここを通行する車両は終日点灯を義務づけられていた。
九曲洞は曲折したトンネルが続く区間である。
カーブが連続し、剥き出しの岩肌が迫る。ここも旧道が遊歩道となっている。
道路の真上にせり出した崖や素掘りのトンネルなど、スリル満点の峡谷歩きが楽しめる。
太魯閣観光の終点となるのは天祥(ティエンシャン)だ。
ここは河岸段丘上に開けた集落で、かっては「タピド」と呼ばれていた。
しかし、終戦後、南宋の忠臣・文天祥にちなんだ現在の地名に改められてしまった。
天祥は古道散策や文山温泉などへの拠点となっており、ここを起点とした遊歩道がいくつか整備されている。
宿泊施設も整っているので、ぜひ一泊して早朝の散策を楽しみたい。
教会などにも宿泊設備が備わっており、投宿が可能だ。
緑水歩道はぜひ訪ねておきたいところだ。ここは日本統治時代に設けられた古道の一部で、現在は観光用の遊歩道となっている。
全長二キロほどだが、戦前の道路はほとんどが廃道となっているので、往時の山岳道路の雰囲気に触れられる機会は多くない。
歩道は緑水地質景観展示館の脇にある石段から始まる。
途中、断崖を大きく回り込むところがあり、その先には日本統治時代に建てられた弔霊碑が残っている。 これはタロコ族との戦闘で命を落とした兵士のために日本人が建てたものである。
廃道となった後、長らく草むらの中に遺棄されていたが、最近、太魯閣国家公園の手で案内板が整備された。
天祥から二キロほど進んだ地点にある文山温泉は、野趣溢れる出湯だ。ここは大理石の岩盤から湯が噴出している。
日本統治時代に駐屯していた部隊によって発見され、隊長の深水武平次の名にちなんで「深水(ふかみ)温泉」と呼ばれた。
温泉までは泰山トンネル脇にある石段を降りていく。
温泉は三つの湯舟に分かれており、温度はそれぞれ異なる。
泉質は弱アルカリ性炭酸泉で、特に皮膚病に効果があるという。なお、泉源は一番奥の洞窟内にある。 |

大理石の岩盤から湧出る文山温泉は
延々と続く石段と吊橋を渡ってアクセスする。
現地では「トブラ」と呼ばれていた。
すぐ脇を大沙渓が流れる。
|
3 タロコ族――日本統治に激しく抵抗した人々
top
この峡谷一帯に住んでいたタロコ族の人々についても触れておこう。
太魯閣峡谷という名称もこの部族の名にちなんでいる。
タロコ族はこれまでアタヤル(タイヤル)族に分類されることが多かったが、現在は台湾で一二番目の先住民部族として政府の認定を受けている。
なお、彼ら自身は「トゥルク」を自称している。
タロコ族が元々居住していた土地は、南投県の高原地帯であった。
しかし、人口の増加によって耕地が不足し、太魯閣峡谷方面に移住するようになったと伝えられている。
人々は奇莱(きらい)主山北峰(海抜三六〇五メートル)を越えて、この地へやってきたのである。
日本統治時代、彼らは日本人による統治を甘受せず、両者の閧で激しい戦闘が繰返された。
地形的に険しい土地だけあって、制圧を試みた日本側も相当な被害を出している。 |

教会で歌うタロコ族の女性たち。
礼拝時に日本語が混じることは少なくない。
|
一九一〇(明治四三)年、総督府は「五ヵ年理蕃計画」を発表している。
「理蕃」(りばん)とは「蕃人を治める」という意味で、先住民の各部族を総督府のコントロール下に置くことを意味する。中でも北部に住むアタヤル(タイヤル)族と中南部のブヌン族に対しては、抵抗運動が激しかったため、徹底的な弾圧が加えられた。
制圧された集落では銃器が押収され、総督府への忠誠を誓わされた。
アタヤル(タイヤル)族に対しては合計二八回の軍事攻略が行われている。
中でも一九一四(大正三)年五月三一日の「太魯閣蕃征伐軍事行動」は最も規模が大きかった。
太魯閣地区に関しては、一八九七(明治三〇)年に攻略が企てられたが、死傷者多数ということで失敗に終っている。
これを受け、軍警約三〇〇〇名が動員されることとなった。それでも日本側は苦戦を強いられ、三ヵ月にわたって攻防が続いた。
制圧後については、太魯閣峡谷に住む人々の勢力を削ぐことに重点が置かれた。まず、警備機関を置き、交通網と連絡網を整備した。
太魯閣峡谷一帯だけでも四二の警察官駐在所が置かれたという。さらに移住政策が実行された。
一九一八(大正七)年から一九三七(昭和二一)年までの間に二度にわたって移住は実施されている。
前半は誘導を軸とした方針であった。山を下りる者に対しては新集落を建設し、山地道路に沿った場所に移住させる。
これらの新集落は山岳部内にあったため「山間集落」と呼ばれた。
そして、後半は霧社事件(一七二頁以下)を契機としており、山間集落を強制的に平地へ移させた。
一九三七(昭和一二)年までに移転作業は完了したが、これによって、太魯閣峡谷内におけるタロコ族の集落は、わずかに三村を残すのみとなってしまった。
終戦後も移住政策は続き、さらに就労機会の少なさもあって、若者を中心に平地や都市部への移住が進んだ。
例外なく過疎化が進み、集落そのものが消滅の危機にさらされることも珍しくなかったという。
移住先となったのは花蓮県内の山麓部で、多くの場合、移住前の集落名を現在も名乗っている。
移住先では周囲に暮らす異部族との間に言語の問題が生じており、今も、老年世代を中心に、日本語がコミュニケーション言語として機能していることが少なくない。
4 日本から渡っていった開拓移民の村
top
台湾東部には日本人による開拓移民村が設けられていた。これは台湾東部の歴史を語る上で欠かせない存在である。
移民村は開墾や産業開発を目的に入植した日本本土からの移住者集落で、正式には「内地人移民村」と呼ばれていた。
台湾の東部、特に花蓮一帯に多く見られたものである。
本来、移民村は大きく二種類に分かれ、日本本土から移住してきた内地人移民村と、台湾西部からやってきた漢人系住民による本島人移民村があった。
内地人移民村は、吉野(よしの)村と豊田(とよだ)村、林田(はやしだ)村が知られている。
本島人移民村は台東県下に多く、その数は一〇以上に及んでいた。
台湾東部に移民村が設けられた理由はいくつかあるが、この地が人口希薄地域であり、未開発であったこと、そして住民の大半が先住民の人々であり、縄張り意識こそ強いものの、土地所有の観念が薄かったことが挙げられる。
さらに、台湾の地に日本人を定住させることで、より一層の日本化を推進することが目的に含まれていた。
台湾東部は花蓮と台東付近に平野があるほか、中央山脈と海岸山脈の間に細長く縦谷平野が存在する。
いずれも乾燥した土地で、降雨期以外は水を得にくい。また、河川は降雨のあるたびに氾濫を起す。
しかも、上流地域が粘板岩質であるために水は白濁していて、農耕には適さない。移民たちは、こういった土地を開墾しなければならなかった。
また、当時は「蕃害」と呼ばれていた先住民による襲撃事件が頻繁に起っていた。
先住民と警察との葛藤は続き、双方に大きな損害を出していたので、移民村の経営もまずは治安の維持に重点が置かれた。 |

旧豊田神社の敷地には
「開村三十周年記念」の石碑が残っている。
終戦後、一度は倒されたが、
最近になって立て直された。
第一八代台湾総督の長谷川清
(海軍大将)が揮毫した石碑である。
|
警察による強権支配で各機関を整備し、同時に先住民を撫育(ぶいく)する。
そして、農耕技術や生活規範を教え込んで、開墾を進めていく。
こういった方法で台湾東部の開発は進んでいった。
日本では想像もできない自然の猛威を前にして、移民村の運営は困難をきわめた。
その土地で苦労を重ね、開発に当たった人々の話を聞いていると、その労苦は確かに計り知れないものがある。
しかし、自然環境を克服し、移民事業を成功させることが、総督府にとっては格好の宣伝材料となっていた一面も見逃してはならないだろう。
5 「吉野村」を訪ねる top
内地人移民村の例として旧吉野村を訪ねてみよう。
ここは官営移民村として最も長い歴史を誇っていた。
一九一〇(明治四三)年に第一回目の入植が行われ、その大多数が徳島県吉野川流域の出身者だったことから、村名が「吉野」と定められた。
現在は「吉安」(チーアン」)と改められている。
元々、この土地にはアミ族の人々が住んでいた。
しかし、この土地を訪れても、アミ族の人々を見かけることは多くない。
現在、吉安郷の人口は七万八〇〇〇あまりだが、このうち先住民は一五%を占めるに過ぎない。
住民の多くは日本人が引揚げた後にやってきた客家人で占められている。
ここは元々「チカソワン」と呼ばれていた土地である。
この地名は清国統治時代の文献には「七脚川」という表記で登場する。 |

旧林田移民村に残る、かってての派出所。
台湾東部ではこれに準じる派出所建築が各地で見られた。
旧林田村には現在、客家人が多く住んでいる。
|
見渡すかぎりの原野が広がり、わずかな灌木が草原に点在するだけの寂しい土地だった。
他地域と同様、水利に問題があるため農業は難しく、もっぱら小動物の狩猟が行われていたという。
この一帯に住んでいた人々は、現在の分類に従えばアミ族に分類される(注)。
(注)アミ族内の分類については、北部(南勢)アミ、海岸アミ、秀姑巒(しゅうこらん)アミ、卑南(ひなん)アミ、恒春アミの五集団にわけられる。
言語についてはおおむね共通性があり、同族意識はあるものの、現地における認識としては差異がある。
また、北部アミの一部は「サキラヤ」を自称し、政府に部族としての認定を請願している。
しかし、厳密には「北部アミ族」、もしくは「南勢アミ族」と呼ばれ、自称は「パンツァー」である(同じアミ族でも東南部や海岸沿いの人々の自称は「アミス」)。
中でもチャカン(寿豊)渓以北の人々は、日本に対しての抵抗が激しく、武力衝突が頻発していた。
特に北部アミ族とタロコ族の人々が連合して日本を攻撃した七脚川事件の際には、日本はこれを徹底鎮圧し、その勢力を削ぐために、集落ごとの移住を強いて勢力を分散させた。
この方法は、先に述べたタロコ族の場合と似ており、花蓮地方の二大勢力は日本の軍警との戦闘をへて消滅させられてしまった。
そして、主のいなくなった土地に日本人の入植が始まった。
当初はマラリアをはじめとする疾病に悩まされ、暴風雨や洪水といった自然災害も絶えなかった。
期待された政府主導の開墾事業も遅れた。
そこで、第二期以降の移民は、地質や気候に類似点が多いということで、九州地方からの入植が盛んとなった。
ここに限らず各地の移民村には九州出身者が多かったが、その理由にはこのような事情が挙げられるのである。
6 戦後の移民村と客家人 top
終戦を迎えると、移民村の様相は激変した。国民党政府は日本人が台湾に留まることを許さず、その場所には新竹や苗栗方面から客家住民が移住してきた。
しかもこれは集団移住だったため、自ずと客家人の比率が高くなった。
現在、こういった旧移民村を訪ねると、かなりの確率で客家語を耳にするのはそのためである。
具体的には、吉安(チーアン、旧吉野)、豊田、鳳林(ほうりん)、林田などは客家系住民の占める割合が大きく、瑞穂なども市街地では客家人が大半を占めている。
花蓮県としても、客家の生活習慣を郷土文化としてアピールすることが多くなっている。
産業の面でも、大きな変化を迎えることとなった。製糖事業が衰退したことで、稲作と並ぶ主要産業だったサトウキビの栽培は大幅に減った。
終戦までは寿(現・寿豊)やカレワンなどに製糖工場があった。
しかし、空襲を受けたまま復活しなかったものを含め、ほとんどが閉鎖に追い込まれていった。
最後に光復(コワンフィー)糖厰(旧鹽水港(えんすいこう)製糖株式会社上大和(かみやまと)糖業所)が二〇〇二年度で操業を終え、台湾東部の製糖工場はすべて閉鎖された。
稲作については日本統治時代の水利事業が終戦後にも受継がれ、栽培環境は良好と言われている。
それでも、現在はかってのような勢いはない。
駅売り弁当で知られる池上(いけがみ)をはじめ、富里(とみさと)や関山(かんざん)など、米どころと称される土地は多いが、むしろ、農閑期の水田を利用して栽培される菜の花の方が、地元では注目されているというのが現実だ。
現在、こういった地域を支えているのは、タバコやビンロウといった嗜好品や、カボチャ、トマトなどの野菜である。
これにフルーツの栽培を加えると、台湾東部の農業の大まかな姿が見えてくる。
つまり、いずれも換金性の高い商品作物で、市場価格の変動も少なく、政府の保護もある。こういった作物を主軸に置いていることから、台湾東部の農業は比較的安定していると言われている。 |

「煙楼」と呼ばれるタバコの乾燥小屋。
タバコの栽培も台湾東部の経済を支えてきた。
(花連県瑞穂郷で)
|
7 台東(たいとう)――先住民が多く住む町
top
台東は花東縦谷平野の南端部に位置している。町を取囲むように卑南平野が広がり、穀倉地帯となっている。
市内はゆったりとした道幅の道路が碁盤の目状に走っており、整然とした雰囲気が漂う。
現在、人口は一一万あまりで、そのうちの一万七〇〇〇人を先住民が占める。
台湾では稀に見る先住民の多い都市だが、それでも年々漢人系住民の比率が高くなっている。
この町を訪れてみると、路地の隅々まで活気が満ちあふれていることに気付く。
現在、台東市は台東県の人口の半数を占めており、かなり広範な地域の中枢となっている。
そのために自ずと人が集まって賑やかになるが、商活動が展開される日中と、夜間との隔たりは大きい。
また、自家用車やオートバイの保有率が高い町としても知られる。
この土地には、古くはアミ族(卑南アミ)とプユマ族が混じって暮らしていた。 |

台東空港。先住民が多く住む台東の空港では、
構内放送にアミ語が入る。
このほか台東駅や花蓮駅でもアミ語の放送を耳にすることができる。
|
台東は清国統治時代の文献では「寶桑」(ボーソン)という表記で登場するが、これはプユマ族の集落であったと推測され、現在も台東には通称「北町」(きたまち)と呼ばれるプユマ族ばかりが住む地区がある。
アミ族は寶桑に隣接するように住み、その居住地域は「ファランガオ(ヴァランガオ)」と呼ばれていた。
これは日本統治時代に「馬蘭」と表記されるようになり、現在にいたっている。
漢人住民の移住は清国統治時代の一八五五年頃に始まっている。
当時、台湾南部の平野はすでに開墾され尽くされており、新天地を求めた人々が南端部を回ってこの地にやってきたのだ。
そして、卑南平野から縦谷平野を北上するように、開墾を進めていった。
この地域は降雨が季節によって偏るため、日本統治時代に入ってからは、用水路の整備が積極的に進められた。
これらは主にアミ族の人々の賦役によって完成し、今も使用されている。
また、昭和時代に入ってからは、サトウキビの栽培も盛んとなり、馬蘭には製糖工場が設けられた。
台東が都市として整備されたのは、一九一九(大正八)年一月一五日に台東街が置かれた時からである。
新興の町らしく、すべてが計画的に造営された。
同年八月には未曾有の暴風雨に遭い、既存の家屋のほとんどが壊滅するという事態となったが、これを機に、都市計両は強力に推し進められていった。
現在の街路配置の大半は、日本統治時代に整備されたものである。
また台東は、第二次大戦後に中国大陸からやってきた外省人が他都市に比べて少なかったことも特筆される。
国民党政権が台湾へ逃れてきた際、上級官吏たちは日本人が住んでいた家屋に住み、下級兵土たちは、日本人の引揚げによって管理者のいなくなった公園や神社、学校などの敷地にバラックを建てて住みついた。
これによって各都市はひどく混乱したが、台東に限ってはそういったケースが少なかった。
つまり、日本統治時代に造られた町並みが終戦後も残ることとなったのである。
町全体がどことなく日本の地方都市のような雰囲気に包まれているのには、こういった理由があるのだ。
終戦後は漢人系住民の人口が急増したが、それでも町に先住民の人々を見かけることは多い。
夜市などでは、人々が持ち寄ったアクセサリー類や工芸品なども売られている。
また、最近の文化復興ブームを受け、アミ族やプユマ族の伝統料理が味わえるレストランもオープンしている。
台東には観光スポットと呼べるような景勝地は多くない。
しかし、町を包み込む雰囲気は開放感に満ちており、他の都市に比べて空間的な広がりが感じられる。
現在、旧台東駅の敷地が「鉄道芸術村」を名乗る芸術空間として整備されているほか、旧台東神社の神苑は鯉魚山と呼ばれ、眺めが素晴らしい。
また、正気路にはフルーツばかりを専門に扱った露天市場がある。
鉄道駅と市街地が離れており、やや不便は否めないものの、台湾の中でも異色と言われるその町並みを散策してみたいところである。
8 緑島――「監獄と人権」の島 top
台東の東南約二九キロの洋上に浮かぶ緑島(リュイタオ)は、一周二二キロという小さな島である。
日本統治時代は「火焼島」(かしょうとう)と呼ばれていたが、これはかってこの島の最高地点に火を焚いて、付近を航行する漁船の目じるしとしていたことにちなんでいる。
「緑島」と改められたのは一九四九年のことであった。
現在、この島の人口は三二〇〇あまり。漢人住民が住み、ほぼすべてがホーロー(河洛)人である。
かっては、次に述べる蘭嶼と同様、この島にも先住民の人々が暮らしていたと言われるが、現在その姿を見ることはできない。
これは漢人住民に滅ぼされてしまったという説や疫病の蔓延で絶滅したという説があるが正式な解明はされていない。 |

緑島。周囲20キロほどの孤島だが、地勢は険しく絶景が続く。
かっては政治犯収容所があり、多くの知識人がここに送り込まれた。
|
また、台湾東部に住むアミ族のほか、いくつかの先住民の部族が自らの起源としている「サナサイ(スナサイ)」という島嶼は、この緑島を指しているという説があり、海岸アミ族には祖先が火種をこの島の頂部からとってきたという言い伝えも残っている。
これは火焼島の名前の由来にも関わっていそうな伝説で、興味が尽きない。
この島は火山島で、島全体が火山岩とサンゴ石灰岩で形成されている。
面積は小さいものの、東海岸を中心に起伏に富んだ地形となっており、スケールの大きい風景が楽しめる。
また、海底から湧出する珍しい温泉もあり、観光スポットとなっている。
この温泉は硫黄泉で、温度は海水が混じるために五三〜九三度と幅があり、満潮時には水没する。
終戦までは「旭(あさひ)温泉」と呼ばれていたが、後に「朝日(ザオズー)温泉」と表記が変えられた。
ただし、最近は観光開発が進んで、昔ながらの素朴な風情は失われている。
住民は漁業従事者が多く、全人口の八五%を占める。
長らく原始的な零細漁業で、自給自足の域を出ていなかったが、日本統治時代に鰹節の工場が設けられたことによって事情は大きく変った。
大正時代に入ると鰹節の生産はますます盛んとなり、沖縄からの移民も多く働くようになった。
また、最近は副業として花鹿(はなしか)を飼育している家が増えている。
この鹿は中国語では「梅花鹿」(メイホワルー)と呼ばれ、かっては台湾本島にも数多く棲息していたという。
しかし、オランダ統治時代以降の乱獲がたたり、ほぼ絶滅してしまった。
オランダは台湾で鹿皮を得、それを日本へ輸出していた。台湾産の鹿皮は防水性が優れていたこともあって、武士たちが競ってこれを求めたという。
一時、オランダは税の代わりに鹿皮を献上させていた。
これによって、台湾本島では花鹿を見ることはできなくなってしまったが、離島であるこの島にはその鹿が残ったのだ。
緑島の名は台湾の人々にとって、ある種、特別な響きをもっているという。
ここにはかって、政治犯・思想犯を収容した監獄があった。
白色テロの時代、多くの人が反政府活動や独立運動の嫌疑をかけられて、ここに収容されていたのである。
現在は緑島人権紀年園区というテーマ公園が設立され、当時の様子についての展示がある。ここもまた、台湾の戦後史を考える上で、ぜひ足を運んでおきたい場所である。
現在、この島は一島すべてが緑高郷という行政区分となっている。
離島ということで、若者の流出を止めることは難しい。
現在は観光を活性化の軸にすえ、開発が進められている。
それでも、海底温泉以外の観光資源に乏しいこの島で、行楽客を呼び巣めることは容易ではない。
そこで、最近は「監獄の島」というイメージを逆に利用して、「監獄」や「人権」をキーワードとした売店や喫茶店などが登場するようになっている。
9 蘭嶼(ランユイ)――太平洋に浮かぶ海洋民族の島
top
蘭嶼は緑島の南方に位置している。台東から八二キロの沖合にあり、面積は緑島の三倍程度である。
緑島以上に地勢は険しく、海岸線のほぼ全てが岩場となっている。
島を一周するように三八キロの環島道路が走っているが、その途上では無数の奇岩が眺められる。
島の人口は三六〇〇人あまりで、その九割近くをタオ(タウ・ヤミ)族が占めている。彼らは台湾で唯一の海洋民族である。
集落としては、椰油(ヤユー)、漁人(イラタイ)、紅頭(イモルッ)、朗島(イララライ)、東清(イリヌミルッ)、野銀(イワギヌ)の六つがあるがいずれも就業機会が少なく青年人口の流出は深刻だ。
なお、ここに記した現地語による集落名は、それぞれの集落によって発音が多少異なる。
この島は日本統治時代「紅頭嶼」(こうとうしょ)と呼ばれていた。 そしてここに住む人々は「Ponso no Tauo(人の島)」とこの島を呼んでいたという。 |

蘭嶼の風景。
島を一周する道路はあるものの、バスは朝夕に走っているだけなので
車を手配するかレンタルバイクで回らなければならない。
|
「蘭嶼」という呼称は、一九四七年の国際花卉(かき)展でこの島の胡蝶蘭が特選されたことにちなんでおり、一九四九年から正式に使用されている。
ここは全島のほとんどが山岳地帯で占められており、平野らしきものは少ない。
海岸線は屹立した岩石に阻まれ、荒涼とした風景が延々と続く。ただし、年間を通じて安定した雨量があるので、森林は発達している。
また、小さいながらも渓流があり、谷間を利用してタロイモが栽培されている。
住民の多くは農業と漁業に従事し、自給自足を基本とした生活が成り立っている。
また、漁業に関しては毎年四月前後に行われるトビウオ漁が広く知られている。
この島には日本統治時代、多くの研究者が訪れていた。
この島の住人タオ族については、長らく「ヤミ族」という呼称が使用されてきたが、これは一八九七(明治三〇)年に、文化人類学者・鳥居龍蔵によって名付けられたものであるという。
「ヤミ」とは彼らの言語で「我々」を意味する「yaman」が転訛したもの、そして「タオ」とは「人間」を意味する言葉である。
10 自然と融合した暮らしを送る人々 top
タオ族は台湾の先住民の中でも際立って個性的な文化を誇っている。
彼らはおよそ八〇〇年前に、フィリピン北部の島から渡ってきたと推定されている。
先住民の他部族と同様、オーストロネシア系の言語を話すが、台湾島の東南部に住むアミ族やプユマ族、パイワン族などとの間に言語の共通性はほとんど見られない。
しかし、フィリピン北部のイバダン族とは通訳を要さずに会話ができる。
イバダン族とは骨格的にも酷似しており、外見では区別ができないほどであるという。
彼らの風俗習慣はこれまでにも数多く紹介されてきた。老人は現在でも半裸でいることがあり、半地下式の伝統家屋に住んでいる。
こういった生活様式は中年以下の世代ではかなり廃れており、集落によっては絶えているが、正装は今でも男子はふんどしで、女子は膝上までの草木の繊維で織った短い布をまとう。
また、他部族との接触を持たなかったこともあり、出草(首狩り)の慣習は見られない。
家屋については、政府がコンクリート造りの簡易住宅を建て、そこに住むことを推奨してきたが、強風を避けることが考慮された半地下式の伝統家屋は快適なようで、なかなか定着しなかったという。
信仰面においても、独特の考え方を持っている。
絶海の孤島であったこの島には、外敵の侵攻や交流がなく、彼らの募らしは常に自然との調和の中にあった。
したがって、自然との相互依存の発想が徹底している。何かものを生み出す際には、大地の恵みに頼り、それを享受しながら暮らしていく。
また、「アニト」と呼ばれる死者の霊を極度に恐れ、それから身を守ることが最も重要なこととされる。
また、無数の禁忌が存在する。
祭事にはブタやヤギを供える。ブタはこの島の固有種である。
また、日本人に接触するまでは飲酒の習慣が存在していなかったというのも興味深い。
しかもタバコに関しては、タバコが山間に自生しているにもかかわらず、喫煙の習慣はなかったという。
ちなみに、これらは現在も日本語で「サケ」「タバコ」と表現されている。
食習慣も興味深い。タオ族の人々が主食としているのはイモ類で、これを茹でて食べる。
サトイモやサツマイモも食べるが、多くの場合はタロイモである。
各所から湧出する小川の周りには、美しい段々畑が幾何学的な図案となって広がっている。
イモは必要な分だけを収穫し、茎は再び挿しておく。
彼らの伝統文化では、土地はすべて集落の共同管理下にあり、個人所有は認められなかった。
なお、イモ作りは女性の仕事であり、トビウオ漁が男性の仕事であるのと同様、男性が触れることはタブーとされている。
トビウオ漁は、宗教的にも社会的にも重要なものとされている。
トビウオは現地では「イヴァンヴァン」と呼ばれ、天の恵みと考えられている。
毎年四月から六月にかけての漁期には多くの祭事と禁忌がある。
この時期は全島をあげて漁労に没頭する。男たちは共同生活を送り、女たちは漁から戻る男たちを待つ。
老人や子供たちにもそれぞれの分担がある。
トビウオ漁は彼らにとって、儀礼の対象であり、同時に集団活動の基礎にもなっている。
そのため、暦もトビウオ漁や祭事を意識したタオ族独自のものが存在している。 |

タタラ船。トビウオ漁はタオ族にとって最大の行事。
タタラと呼ばれる木彫りの船を用い、男子だけで行われる。
|
top
****************************************
|