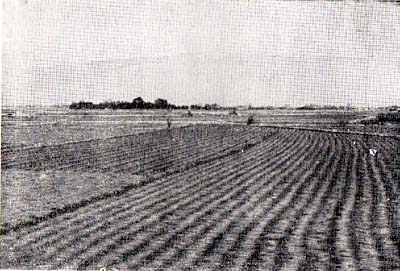|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章
五 黒馬(あお)よいななけ
1 足利平をわたる風
top
年があけて一三三三年元弘三年の春でした。
渡良瀬川の岸の川柳が、川風にふきあげられ、ちかちかと光って裏葉をひるがえしています。
足利平の田のあぜのハンノキの花はもうちって、日ましに若葉をしげらせています。
夜は蛙(かえる)の声が夕立のようにきこえてきました。
足利高氏は二十九歳になりました。
春のさかりをむかえたのに、あいかわらず高氏には気分のすぐれない日がつづきます。
今年になってかぜをひいて、こじらせたこともありますが、それだけではないようです。
朝おきると、すぐ仏間にはいって、父の貞氏や、先祖の位牌にむかって、お経をよみますが、そのあとは、居間にはいって寝ることが日課のようになってしまいました。
今日も昼すぎになって、母屋からつぼ庭におりてきた高氏は、そのままなにもいわずに、広い屋形の庭の東にある鏝阿寺(ばんなじ)にむかって歩きだしました。 |
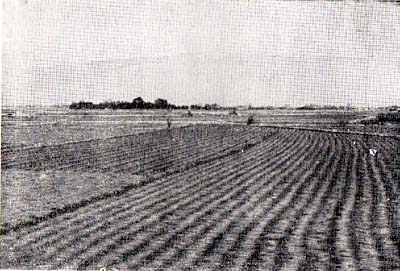
いまも変わらぬ足利平
|
家来が二、三人、あわててそのあとを追いましたが、高氏はふりむこうともしません。
そんな高氏の後姿を、妻の登子(たかこ)が心配そうに見つめていると、後から弟の直義(ただよし)が声をかけました。
「いったい、兄上はどういうおつもりなのでしょう。
本当に、からだが悪いのなら、鎌倉あたりから医者をよんで………。」
「はい、………そのことでしたら、私も、なんどか申しあげたのです。
鎌倉の兄(守時)も心配して、昨日も文で、容体をたずねてきました。」
直義と登子は心配そうに、またしばらく話しあいました。
しかし、同じ心配でも、二人の心配の中味はちがいました。
夫の病気は、ずいぷんと神経をなやましているものらしく、不機嫌であったり、わけもなく、登子をしかりつけたりもするのです。
だから登子は、
「ひょっとすると、私は夫に愛されていないのかもしれない………。」
ふと、こんな不安さえ感じるのでした。
でも、弟直義の心配はちがいます。
笠置が落ち、後醍醐天皇が隠岐島へ流され、いったんは、おさまったはずの京なのに、今年になって、にわかにそうぞうしくなってきました。
河内の楠木党は、昨年こもった赤坂城などとは問題にならないほど、まもりのかたい城を金剛山のふもと一帯にいくつもきずいたそうです。
そればかりでなく楠木党は、今年になると、みやこちかくにまで兵をすすめ、六波羅軍をたびたび打ちやぶったと、京からの使者は伝えてきました。
この楠木党の旗上げにこたえるかのように、播磨(兵庫県)では赤松則村、伊予(愛媛県)では土居氏、得能(とくのう)氏が旗あげをして、幕府方である守護の軍をやぶりました。
後醍醐天皇が隠岐島をぬけでたという知らせもはいりました。
それで数日まえ、鎌倉幕府では高氏に、西国出陣の命令をくだしてきたのです。
しかし高氏は病気を理由に、出陣を断わりました。
幕府の命令を断わったことで、“兄は天皇方につくつもりかもしれない………。”と直義は内心、思いました。
しかし、そのあとの高氏の動きをみると、まだ、迷いつづけているとしか思えないのです。
兄の態度をみて、直義はただいらいらするばかりです。
鎌倉方につくか、それともいっそ、幕府をたおす軍をあげるか………。
足利家はいま一族一門の、栄えるか、おとろえるかのわかれ道に立っているのです。
それなのに、兄の高氏は、病気をいいことに、仏間にはいって経をよんだり、寺へ座禅をくみに出かけたり………で、いっこうに頼りになりません。
☆ ☆
その日、直義は、夜になっても自分の屋形には帰らず、兄をまちうけていました。
昼すぎから、座禅をくんでいた高氏は、夕方ちかくに、母屋に戻ってきました。
ちょうど、登子のいないのを見はからって、直義は居間にいきました。
「兄上、みかどにお味方もうして幕府を倒し、源氏再興の悲願をはたすときはいまですぞ。」
直義、まわわりにするどく目をくばりながらいいました。
「直義、あせってどうなるものでもない。」
めんどうくさそうに高氏はいいました。
「では、鎌倉の命令で、ふたたぶ西国の楠木一族を討ちにいかれるのですか。」
直義がいうと、高氏は首をふりました。
「ではいったい、どうなさるつもりですか。」
直義は、じれたように床板をたたいていいました。
「わしは病気じゃ。」
高氏はめんどうくさそうにいって、
「それゆえ鎌倉へは、西国出陣はかなわぬとお断わりしたはずだ。」
「やれやれ、腰の重い兄上ですな。しかし、幕府はだまっていますまい。また出陣命令をいってきますぞ。」
「いってきたら、またそのときじゃ。人間、あしたのことはだれもわがらぬ。あせるな直義、とにかくわしは病人じゃ。」
しまいには、こういって口を閉ざしてしまいます。
こんな病人とも神経衰弱ともつかない高氏の生活がしばらくつづきました。
ときおり、足利にちかい村々の名ある武士たちが、屋形をたずねてきます。
「いまこそ、源氏の宗家足利どのが、平氏である北条幕府をたおすとき………。」
「隣国の新田どのは、宣旨をうけて、ひそかに武士を集め、鎌倉をせめるしたくをしているとか………。」
この客たちは、高氏が倒幕に立ちあがることを、それとなくすすめる武士たちです。
しかし、高氏があわないので、直義や執事の高師直(こうのもろなお)に、こんなことをいきまいては、帰っていきます。
☆ ☆
その日、高氏は四歳になった長男の千寿丸をひざにのせ、いかにも、いとおしくてたまらないというように頭をなでていました。
「思えば、この千寿もふびんよのう。」高氏は、一人ごとのようにいいました。
「なぜでございますか。」
妻の登子が不審そうにたずね、思わずはっと、まゆをひそめました。
夫高氏のひとみが、わずかにうるんでいます。涙ぐんででもいるのでしょうか。
高氏はうるんで赤くなった目を、妻にのぞかれないように、ふせながらいいました。
「千寿も足利家の惣領(そうりょう)、やがてこのわしのように、一族一門の上にたって苦しまねばならぬのかと思うと、ふびんでならぬ。」
「どうして、そんなお心弱いことを申されますか。」
登子は、このところほおもこけて、口ばかりぎょろつく夫のやつれた顔を見て、はげますようにいいました。
「そなた………。」と、高氏が、今度は妻にいいました。
「北条一門に生まれたそなた。
わしが、みかどにお味方もうして、鎌倉をせめたならば、さぞ、わしをうらみに思うであろうな。」
「いいえ。」登子は、きっぱりと首をふりました。
「私が鎌倉の家を出るとき、兄は私にいいました。今日よりは足利のみあって、北条家などはなきものと思えと。」
「なるほど………あの守時どのならいいそうなことよ。」
高氏は、いっそうゆううつそうな顔になりました。
みかどの命をうけて、鎌倉と戦えば、執権職にある妻の兄北条守時は、敵の総大将ということになります。
☆ ☆
ところがその晩、また鎌倉から早馬の使者が屋形につきました。その使者の口上をきいたとき、とうとう高氏も、決断しないではいられなくなりました。
「病気中なので、西国出陣は遠慮させてほしい。」
という高氏の断わりが、いったんは妻の兄、執権北条守時によって認められました。
ところが、北条高時は、「ぜったいに出陣せよ。」と命じたのです。
高時は、執権をやめ出家し、「相模入道どの」といわれるいまも、執権守時をしのぐ勢いをもっていたのです。
高時のあたまごなしの命令は、高氏を激しい怒りにかりたてました。
そしてその怒りが、とうとう高氏に、あるひとつの決断をくださせたのです。
高氏は、その夜のうちに、直義と、高師直をよびました。
直義も、ほおをふるわせるばかりに怒っています。
「このまえの西国出陣は、父上の喪中でした。今度は、兄上の病気を知りながらの出陣命令です。兄上!」
「わかってる、そのさきはいうな。おそらく、おまえの考えていることと、私の考えていることは同じはずだ。
それだからこそ、こうして夜中にもかかわらず、よんだのではないか。」
高氏がこういうと、直義はにっこりしました。まゆとまゆがせまって、するどいまなざしの直義の顔が、大きくほころびました。
☆ ☆
つぎの朝早く、下野(しもつけ)の武士団にむかって、高氏の出陣命令がくだされました。
日ごろから高氏の人柄をしたう武上たちは、まるでこの日を待っていたように、続々と、
足利屋形にあつまりました。広い屋形の庭も、よろい武者たちの金具ずれの音、馬のいななきでに
ぎわしく、二つ引両(ひきりょう)の旗さしものは、屋形の空を雲のようにおおいました。
高氏は一族の細川和氏、上杉重能(しげよし)の二人をよびました。
「そなたたちは、あす足利をたって、三河へいけ、私がゆくまでに、充分、西国のよう
すをしらべておくのだ、ま气場合によっては船上山へいってもらうかもしれん。」
それをきいて、二人は、思わず「あっ!」とさけびました。
船上山には、隠岐島を脱出し、土地の豪族である名和長年の兵にょってまもられる後醍醐天皇の仮宮があるはずです。
二人は、今度の西国出陣は足利家にとって、どんな運命をもたらすものか、また自分たち使者のはたす役割が、どれだけ重いものか、を感じないではいられませんでした。
高氏は、妻の登子や千寿丸にも旅のしたくをいいつけました。
ところが、昼すぎ、またまた鎌倉の使者、かかけつけてきたのです。
「このたびの西国出陣、まことにごくろうである。
ついては、足利屋形も無人となろうから、妻の登子どのと、惣領の千寿丸どのは鎌倉へ住まわせるように――。」
という高時の言葉を伝えました。
つまり、妻と子を人質としてあずかるということなのです。
高氏は、思わずくちびるをかみました。
高氏は、四歳の千寿丸のあたまをなでました。
「武士の子に生まれたのは、そなたの宿命じゃ。武士の子はいつでも死ぬ覚悟が必要なのじゃ。」
もちろん、そんな理屈が手寿丸にわかるわけはありません。直義が兄をなぐさめるように、
「鎌倉にいけば、北条守時どのがおられます。姉上や千寿丸どのに、けっして悪くに振舞われないでしょう。」
しかし、登子は首をふりました。
「いいえ、私の覚悟はできております。どうぞ足利家が末長くお栄えになるよう、心おきなく、お振舞いくださいませ。」
高氏も、大きくいきをはいていいました。
「死ぬは一定(いちじょう)………いずれ、早い遅いはあっても、あの世では再び、妻としてわが子としてのちぎりを結ぼうぞ………。」
高氏は登子と手寿丸を、ひと足さきに鎌倉へ旅だたせることにしました。
千寿丸が出発するまえの夜、高氏はじゅずを片手に仏間にはいり、人の立ち入りを禁じました。
明方ちかく、やっと仏間から出てきた高氏は、手に一枚の墨絵をつかんでいます。
高氏は妻の登子に、それをさしだしてにっこりわらいました。
「千寿丸のぶじを祈って一筆かいたぞ。」
登子がうけとって見ますと、日ごろ、夫が信仰している地蔵菩薩の絵です。
筆の勢いが、強からず弱からず、顔には深い慈悲の相をそなえ、どこか子ぼんのうな高氏の面影に、にかようものがありました。 |
 |
「もし、さだめつたなく、命はてることがあろうとも、この地蔵にみちびかれれば極楽往生疑いなしと思い、つねに千寿丸のそばにおくのじゃぞ。」
高氏は、しずかなまたぎしでいいました。
☆ ☆
東の空が白み、妻とわが子にわかれをつげるときがきました。
「若ぎみ、奥方さまのごぶじは、それがしの命にかえても………。」
とちかう紀(き)五左衛門が、三百の兵をひきいて屋形の門を出ました。
これがあるいは最後のわかれとなるかもしれないと思うと、高氏の胸はいたみました。
そんな高氏のもとに直義がやってきました。
「兄上……… このたびの出陣の祝いに、この直義、引き出物をさしあげとうござる。」
直義は、きびしい顔のなかにも、かすかに笑みをうかべています。
「引出物だと。」
「とにかく、庭におりてください。」
なにごとかと、思って高氏が渡殿(わたりどの)に立つと庭さきの松に、金覆輪(こんぷくりん)の鞍をおいた一頭の馬が、つながれてあります。
「おう! ………これは見事よ。」
高氏は、黒うるしをぬったようにつややかな黒馬を見て、思わずうなりました。
「兄上はいつか、八朔(はっさく)の引出物に、見事なあし毛をくだされた。
私は、あのときのうれしさをわすれることができません。
この馬は、日ごろ、目をかけていた、那須の馬飼いが『あっぱれ、坂東一の名馬』と、鼻たかだかに、私に売りにきたのです。
これは源家嫡流の兄上にさしあげます。」
「そうか………うれしいぞ直義。」
まるで油をつけてみがいたようにつやのある黒い毛なみが、日の光をてりかえして、こいみどりがかかった色に光ります。胴がくびれ、まゆや腰の肉づきのゆたかさ、また圧のつけねは力づよく立っています。
妻や子とわかれ、黒馬にまたがった高氏は、いままでの心の迷いをはらって、顔色もみちがえるように生きいきとしてきました。
☆ ☆
一三三三年元弘三年三月二十二日(いまの五月)、高氏は弟直義、執事高師直ほか、吉良、上杉、今川、仁木、荒川など一族三十二人、下野の武士団、兵士もふくめて二千ちかくの軍勢をひきつれ、渡良瀬川をわたり、関東平野を南にくだっていきました。
この日の高氏のいでたちは、むらさき裾濃(すそご)の大よろいを着て、源氏重代のこがねづくりの太刀をはき、立見ぼしの上から、白ぎぬのはちまきをしめました。
馬はもちろん、黒馬(あお)の三歳駒です。
屋形のイチョウは、いっぱいの若々しい緑葉でおおわれ、高氏兄弟の出陣を見送りました。
渡良瀬川堤のサクラは、すっかりちってしまいましたが、赤い山ツツジがあちらにひとむれ、こちらにひとむれと、草原の緑にはえ、足利平は今がいちばん美しいときでした。
生きて再び、この足利を見ることがあろうか………ふと思う高氏の胸の中に、あの月見の丘のほとりの、石の地蔵さまがうかびました。
地蔵さまの顔は、少年の日、母と話をきいた、みやこ北山の疎石禅師の顔とかさなりました。
すべてこの世のことは、はかなごと………といった禅師の言葉が、耳によみがえります。
天下がこの足利のものになるもよし、武運つたなくやぶれほろびるもよし………と、覚悟をきめた高氏のくちびるのあたりに、不敵な笑みがうかびます。
そんな高氏を、直義をはじめ一門の武士からか、たのもしげに見あげました。
鎌倉につくと、名越(なごえ)高家が、一千の兵士をそろえて待っていました。
もちろん、高氏の決意など知るよしもありません。
三月二十七日、足利、名越あわせて二千の兵は、鎌倉をたちました。
しかし足利方の二つ引両の旗は、三本からかさの名越の旗さしものを圧倒するように見えました。 |
 |
三河の矢作(やはぎ)につくと、先発隊の上杉重能(しげよし)と細川和氏が待っていました。
西国のありとあらゆる情報を集めていた二人は、主人の到着するのももどかしそうに、話しはじめました。
千早城の楠木党をせめる幕府軍は、あいかわらずの苦戦で、城はまだまだ落ちそうにないとのこと、さらには、長い戦いに疲れた兵士の間で、すごろくやでばくちに明け暮れするものがふえてきたこと、内輪もめから同士討ちをするものまで出てきたことなどが、やつぎばやに報告されました。
2 篠村(しのむら)八幡にひるがえった白旗
top
上杉重能(しげよし)と、細川和氏(かずうじ)の報告をきいた高氏は、幕府軍の武士たちが、もうすっかり戦う気のないのを知りました。
播磨で旗上げした赤松則村(のりむら)も、いよいよさかんです。
そのため、六波羅によばれて、みやこへやってくる幕府軍が、神戸のあたりでさえぎられてしまっています。
また、四国の水軍、土居二郎、得能(とくのう)弥三郎も、長門(山口県)の探題を攻めて、北条時直(ときなお)を討ちとったということです。
高氏は、足利を出発するとき、ひそかにいだいた野望を、ついに決行することにしました。
高氏は、再び上杉重能(しげよし)と細川和氏をよびよせました。
高氏から、なにやら命令をうけると、その夜、二人は、名越勢に知られないように、三河をたち早馬で西へ西へとむかいました。
高氏は、あせる名越高家をしりめに、なお兵を集めるといって、数日をここですごしました。
高氏の声におうじて、三河武士が、続々と集ってきます。
☆ ☆
月があらたまった四月十三日、足利勢は、近江の鏡宿につきました。
すると、早くも、伯耆の船上山を往復してきた上杉重能と細川和氏が待っていました。
「との、みかどのご命令をいただきました。ぞ。」
上杉重能が、ふところから、錦の小ぶくろにおさめた、幕府追討の命令書をさしだしました。
高氏は直義とともに口をすすぎ、からだを清め、天皇みずからがしるされた、幕府を討てとの命令書をおしいただきました。
それとも知らぬ六波羅探題では、武勇関東一をほこる足利勢の到着に大喜びでした。
さっそく、軍評定か行われました。
とりあえず京の南にせまっている赤松則村の軍勢を討つこと、つぎに足利、名越(なごえ)の二手に別れて北の山陰道、南の山陽道を船上山へむかうということになりました。
四月二十七日。先発隊の名越高家の子の者か、まず久我縄手で、赤松隊と正面からぶつかりました。
ところがこの戦いで、大将の名越(なごえ)高家は、赤松党一の弓の名手、佐用範家(さよのりいえ)のひく弓でみけんを射ぬかれ、即死してしまいました。
大将を失ってあわてた名越勢は、総崩れとなりました。
☆ ☆
そのころ、足利高氏はみやこの北、丹波の国、篠村(しのむら)八幡の社殿で、弟直義ほか、一族の武士を集めていました。
高氏はそこで用意の白紙をひろげ、みずから矢立てをとって、さらさらと筆をはしらせました。
この八幡神社におさめる願文です。
「………みかどのご命令をうけて兵をあげるわが足利軍の武運をおまもりください………。」
と、見事な筆蹟で書かれた願文を、高氏は声高くよみあげました。
ついに、討幕の宣言をしたのです。
願文をおさめると、そなえた神酒(みき)をくみかわしました。
ここ丹波篠村は、高氏、直義の母、上杉清子の実家があったところで、足利領になっています。
二人が、母とおさない日をすごした故郷でした。
高氏と直義は、源氏の守護神として、しばしば参詣した八幡神社の境内で、きょう、北条幕府討伐、源氏再興の旗上げをする感激で、ほおをかがやかせていました。
「直義! 旗をあげい!」
「こころえました。」 |

篠村(しのむら)八幡宮
|
かねて用意していたふとい竹づつのなかから、源氏の白旗をとり出しました。
直義は社殿の前の一本の大きなヤナギの枝に、その白旗を掲げさせました。
源氏の白旗は、ふかい緑の木立のなかで、ひときわ美しく風にはためきました。
高氏は、後醍醐天皇のご命令をよみあげ、全軍の兵士に九鎌倉討伐のいくさをすることを告げました。
「えい、えい、おお」
三千の兵、出陣のときの声は、丹波の空にこだまして、十キロとはへだたらない、みやこの、六波羅の空にまでとどいたかと思うほどです。
高氏はつづいて、一族のなかからえりすぐりの武士を十数人えらびました。
高氏は、小さなうすい布きれを何まいも用意させると、今度は細筆で密書をしたためました。
「伯耆(ほうき)船上山(せんじょうざん)より勅命をこうむりそうろうあいだ、参(さん)じそうろう。
合力(ごうりき=味方)せしめ給いそうらわば本意(ほんい)にそうろう。
恐々謹言、四月二十九日 高氏」
としたためた布きれを、ある武土は、太刀のさやのおくにつめました。またある武士は、衣のすそにぬいつけました。
力をあわせて、天皇のため幕府をたおそうという密書でした。
密書をひめた武士たちは、かわるがわる、高氏のさかずきをうけると、東へ西へ、南へ北へとちっていきます。
東は常陸(茨城県)の結城氏、西は薩摩(鹿児島県)の島津氏にまで密使がつかわされました。
篠村(しのむら)八幡を本陣にして、夜もかがり火をたき、なおも高氏は兵を集めました。
このあたりの武士団は足利と縁がふかく、ここでも、続々と兵が集ってきました。
☆ ☆
高氏が幕府にそむいて、みやこを攻めようとしているときいて、六波羅探題のおどろきは、ひととおりではありませんでした。
六波羅顯題は、北と南にわかれていました。
北の北条仲時、南の北条時益は、ただちに六波羅に城のように柵をめぐらし、一部の軍勢を大宮二条のあたりにすすめ、高氏方をむかえ討つことにしました。
五月七日、高氏は、嵯峨野のあたりから、じりじりと市内にせまっていきました。
太陽がすっかりのぼりきったころ、六波羅軍と高氏軍は、お互いの顔が見られるほどに近づきました。
両方の陣から弓のはまれ高い武士が出てきて、たがいに相手の陣にむかって矢を射こみました。
矢じりにあなをあけた、上矢(うわや)のかぶらは、「びゅるびゅる」とうなりをあげて空をきりました。
いくさはじめの挨拶です。
上矢のかぶらが鳴りおわらぬうち、両軍、「わーっ」とときの声をあげて、たがいの陣にむかいました。
足利一門のため、また妻子のため、どちらにつくべきか、悩みつづけてきた高氏は、いままでの重苦しい日々をふきとばすように、みずから、源氏重代の大太刀をぬきはなちました。
あるじの勇む心を知ったかのように、馬は黒く光る鼻づらを空にむけ、声高くいななき、たくましい両の足で、二度、三度、大地をけると、風のように敵陣にむかって走りだしました。
大将軍を先にやってはならぬとばかり、足利勢は高氏をかこむようにしながら、しゃにむに六波羅勢につっこんでいきました。
そのあとをひとかたまりとなった歩兵が追っていきます。
敵もまた、騎兵集団を先頭にして攻めてきました。
いま、みやこ大路に、騎兵集団と騎兵集団が、黒いふたつのつむじ風のように、真正面からぶつかりあったのです。 |
 |
集団と集団とは、互いに相手方のうしろをおそおうとします。
それで両軍は、まるで回転する駒のようにぐるぐるまわります。
ときおり空高く、かぶと武者が、まるで空中にとびあがるようにしてのけぞり、また首すじから血をふきあげたかぶと武者か、まりのようにふりとばされ、あるじのいなくなった馬が、前あしで大きな輪をかきあげます。
少しずつ足利勢の勢いがまさっていくとみえ、ぐるぐるまわっている六波罹勢の馬のあしなみが乱れはじめたようです。
ある馬はさお立ちになり、ある馬はあとずさり、またある馬は、横にそれてにげようとしたため、お互いにぶつかりあい、ぶつかっては、いっそうおびえて、混乱が大きくなっていくようでした。
しかし、敵もさるもの、くずれかけてはまた立ちどまり、懸命に戦います。
高氏は、味方さえ、とめら且段いほんの勢いで、太刀をふるいます。
よろいのそでには、数本のおれた矢がささっています。
ともすれば、味方の先頭に出てしまって、相手方の目標になりがちな高氏を、直義(ただよし)、高師直(もろなお)が、必死になってかこみ、その手綱をひいて、うしろへさげようとしました。
さかだった黒いまゆの下から、ふたつの目がらんらんとかがやいて、あの足利屋形の仏間で経をよみ、人間のはかなさをなげき、また千寿丸いとしさに涙ぐんだ高氏の面影は全くありません。
この御大将の戦いぶりに、部下の将兵もまたいっそういさみたちました。
と、六波羅方の騎馬集団から、三騎ばかり、かけぬけ出て、真一文字に高氏めがかけてつっこんできました。
あわてて高氏をまもろうとする騎馬武者たちが、次々になざたおされていきます。
それでも、敵の二騎はようやくしとめました。
だが、のこった一騎は、ついに高氏の前におどりでて、大太刀をふりおろしました。
高氏は、かろうじて身をよじってかわしましたが、敵はすばやく二の太刀をふりあげました。
さすがの高氏もあぶなく見えたとき、馬のまま高氏の前をかけぬけた武生がありました。設楽(しだら)五郎でした。
敵のふりおろした人太刀は、高氏を体ごとさえぎった五郎の左肩さきをきりさきました。
よほどの力とみえて、よろいの金具ごと、太刀は五郎の肩にくいこみました。
しかし、五郎はひるまず、敵にしがみつき、敵の腰にあったよろいどおしを引きぬいて、相手の腹にさしこみました。
さすがの敵も落馬して、そこを味方がどっとかけより、たちまち首をうちおとしました。
「との………。」
血しぶきをあげた五郎が、高氏をふりかえりました。
「あっぱれぞ、設楽五郎。」
五郎は、十数年まえ、借金のために失った先机伝来の土地を、高氏のはからいで、取戻してもらった恩義に、むくいることができたとばかり、にっこりわらいました。
「五郎、うしろへさがってきずの手当てをせい。」
高師直が大声でいいました。しかし、五郎は首をふると、ぶかでの身のまま馬首を敵方にむけ、そのままつっこんでいきました。
もう太刀をぬく力もないのでしょうか。
かろうじて、馬の首にしがみつくようにして敵陣にはいり、たちまち見えなくなりました。
「それ、設楽をむだ死にさせるな!」
とばかり、なおも足利勢は敵陣にきりこみます。
すなけむりはまいあがり、矢は雨のようにふりそそがれ、もう、敵も味方も区別がつかないほど、いり乱れた戦いとなりました。
しかし、夕方ちかくなると、さしも激しい抵抗をした六波羅がたも、じりじりとひく気配をみせてきました。
すると、九条のあたりからも火の手示あがりました。播磨からよせてきた赤松則村の軍勢でした。
突然、後醍醐天皇がわに寝がえった足利勢によって、とうとう六波羅軍は、市中から追われ、にわかづくりの六波羅とりでにこもってしまいました。
足利、赤松の連合軍は、六波羅をとりかこみ、その日は暮れました。
その夜、高氏の陣に、赤松則村が挨拶にきました。昼の勝ちいくさを祝って簡単な酒、さかなが出ました。
「このたびの赤松どののはたらき、ばつぐんでござる。」
高氏は、ます則村にこういったあと、六波羅のかこみを一部とくように、といいました。
「それはまた、なにゆえに………。」
赤松則村も弟直義も、けげんそうな顔でいいました。
「ぬけ道がなければ、かえって敵は死にものぐるいで戦うであろう。
そうなれば、味方のうけるきずも多くなるはず。」
「なるほど………。」
「それに、いくさの決着のついたいま無用の殺生はやめたい。
まして、敵とはもうせ、われらと同じ鎌倉武士じゃ。」
高氏はそういって、屋形からはこんできた大さかずきに、なみなみと酒をつがせました。
☆ ☆
六波羅がほろび、捕えられた光厳天皇は位からおろされたという知らせをきいたもう一人のみかど、後醍醐天皇は、名和長年の兵にまもられてみやこへむかいました。
またそのころ、足利と同じ源 義家を祖とする新川義貞も、北関東の赤城山のふもとで、たくさんの武士団を集めていました。
あつまった武士団をひきいた新田義貞は、これをはばむ上野の守護代の兵をやぶり、利根川をこえ、武蔵の国にすすんできました。
五月十五日、鎌倉幕府は、北条高時の弟、泰家をむけました。
しかし、多摩川、分倍河原(ぶばいがわら)でこれをやぶった新田勢は、つなみのように鎌倉にせまっていきました。
新田勢が鎌倉にせまっている、ときいた高氏の家来、紀(き)五左衛門は、奥方登子(たかこ)と千寿丸(せんじゅまる)を、ひそかに、鎌倉大蔵谷から脱出させました。
鎌倉をぬけ出した五左衛門は、上総(千葉県)の武上団を集めました。
数百騎があつまると、五左衛門は、その先頭に千寿丸をたてました。四歳の千寿丸をこしにのせた足利軍は、二つ引両の足利の旗をなびかせ、新田勢やそのほかの関東の武士団とともに、北条氏の鎌倉幕府にせめこみました。
せめるも、まもるも関東武者とあって、戦いは火のでるようなはげしさでした。
五月二十八日。新田義貞は、鎌倉ぜめの近道として、稲村が崎をえらびました。
海の引き潮どきを知っていた新田義貞は、砂浜づたいに一気に鎌倉へせめいりました。
そして極楽寺坂で北条氏とはげしく戦ったすえ、これをうちやぶりました。
いよいよ、栄えた鎌倉幕府にも最後のときがきました。
北条高時や、足利登子の兄であり、さいごの執権でもあった北条守時。その他一族は、先祖の墓のある東勝寺にはいって自殺しました。
心おきなく戦って血にそまった北条一門は、あるいは切腹し、あるいは父子兄弟さしちがえて死にました。
百五十年に渡った鎌倉幕府は、こうしてほろびたのです。
top
**************************************** |