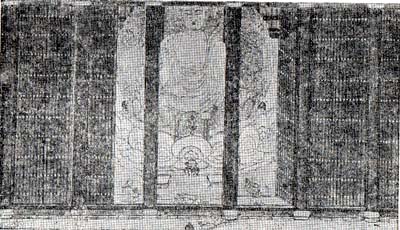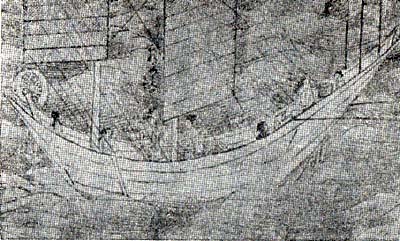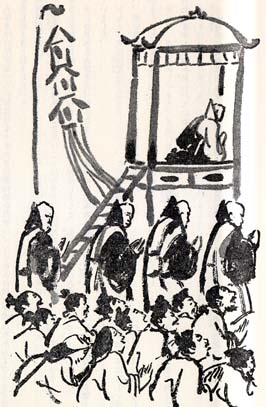|
****************************************
Index 1
2 3 4
5 6
7
3 燃え落ちた大仏
1 支えの土山(つちやま)
top
元明天皇によってひらかれた平城京は、七代七十年にわたって、天平文化の中心となってさかえましたが、やがて延暦三年(七八四年)、桓武天皇によって、都は京都の長岡へ移されました。
のちに都は京都市中に移され、明治にいたるまで千年余り王城の地として栄えました。
その反対に、奈良はみるみるうちにさびれていきました。
平城宮のあった地域から皇室、役所、それに貴族たちが、平安京といわれる京都にそっくり移ったわけで、もはや町なかを歩く人はありません。
農民たちも水のとぼしいこの町をすて、水のゆたかなところへ移り、また神社や寺などの残っているところへ引っ越すなど、ついには平城宮のあとは、全くの荒れ野原になってしまいました。
『万葉集』にも、あれはてた昔の都をうたった歌がいくつも残されていますが、一二〇〇年をへた今でも、ここに華やかな大都市があったとは信じられないほど、草ぼうぼうの原っぱです。 |

その後、都は京都の平安京となり、平城京(奈良市)は寂れていった
|
一方、東大寺は平安時代に書かれた『大鏡』という歴史物語をみると、
「世の中に手斧(ておの)の音のするところは、東大寺とこの宮(その頃の実力者、藤原実頼の屋敷)とこそはべるなれ。」
と書かれているように、大寺院だけに、毎日修理、増築などの大工が盛んに仕事をしていたことがわかります。
ところで大仏は建てられてから、三、四十年ほどたつうちに、仏体の尻、背中あたりから、しだいにひびがはいり、倒れる心配がでてきました。
そこで大仏のうしろに仏後山(ぶつごやま)という土山を築いて大仏を支えることにしました。
大仏が建てられてから七十八年めの天長四年(八二七年)四月のことです。
この仏後山は平安時代の僧、鳥羽僧正覚猷(かくゆう)が描いたといわれる『信貴山縁起絵巻』という絵巻物のなかに、おぼろげながらみることができます。
大仏の光背のうしろに白く描かれているのがその土山で、またここに描かれた大仏像は、創建当時のものを伝えるただ一つのものとして、まことに貴重です。 |
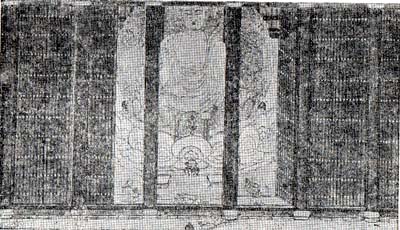
『信貴山縁起絵巻』に描かれた大仏
|
なお、仏後山が築かれるまえから、大仏の頭がかしいでいたといわれていますが、これはそのままにしておかれたようです。
ところが、それから二十八年たった斉衡二年(八五五年)四月の十、十一日の地震によって、いよいよ首が危なくなり、ついに、五月二十三日の地震で転げ落ちてしまいました。
大仏の頭部が落ちた第一回めです。
このため六年ほどかかって仏頭の修理がほどこされ、貞観三年(八六一年)三月十四日、再び仏頭は取付けられました。
この日の開眼のため、開眼導師は篭にのってロクロ(滑車)で引き上げられ、目に点を入いれたということです。
天平の開眼後、百十年めにあたります。
それ以後は、特に大きな変化がないうちに、やがて平安時代もおわりに近づいていました。
すでに、都は奈良から京都へ移って、はや四百年がすぎさっていました。
2 源平の戦い top
その頃、政治を治めていた貴族の藤原氏にかわって、武士の平清盛を中心とした平氏一族が政治をとっていました。
清盛は皇室や藤原氏の内輪もめがもととなっておこった保元、平治の二つの戦いで、同じ武士の源氏一族を倒し、天下を平氏一族でおさえていたのでした。
「平氏でなければ人ではない。」
そんなおごりたかぶった平氏に、源氏一族や藤原氏の貴族たちが心良く思うぱずがありません。
「平氏をうて、清盛をたおせ。」
ついに源氏の一族の源頼政は後白河法皇の第二皇子以仁王(ももひとおう)をおしたてて、京都で兵をあげました。
つづいて、信濃(長野県)、伊豆(静岡県)、近江(滋賀県)でも、次々と源氏は平氏に戦いをいどみました。
戦いのじょうずな清盛はすばやく兵を送って源氏の軍勢をけちらしましたが、そのなかで、もっとも恐れたのは、近江の園城寺(三井寺)や延暦寺、奈良の興福寺や東大寺などの寺にいる僧兵のことでした。
僧兵というのは、その頃、自分の寺の広い領地を自分の力で守るために、槍、刀、なぎなたなどで武装をしている僧のことです。
寺によっては二千人から二万人近い僧兵がいたといわれ、武士でさえも、てこずるほどの強い力をそなえていました。
ところが、その近江の園城寺の戦いでやぶれ、奈良へにげる途中殺されたのが以仁王や頼政などでした。
ことに奈良には古くから藤原氏の保護をうけ、また氏寺としても力をもつ興福寺があり、僧兵たちははげしく平氏打倒に燃え上がっていました。
「おのれ、おもいあがった坊主どもめ。いまこそ平氏の力をみせてやるわ。」
かねてから僧兵たちを苦々しくおもっていた清盛は、自分の息子の平重衡(しげひら)を総大将に、兵四万を奈良へ送りました。
暮れもおしせまった治承四年(一一八〇年)十二月二十五日のことです。
清盛の作戦は近江の園城寺、延暦寺がやぶれたいま、奈良に力をもつ興福寺、東大寺を倒すには絶好のチャンスとみたのです。
これをむかえうつ奈良側の僧兵たちは、少年から老人までかりだしておよそ七千人。東大寺の北方の奈良坂、般若寺の道路に堀をほり、矢をはねかえす楯(たて)をならべ、さかもぎという棘のある木の枝を逆さにしたものを、垣根に取付けるなど、平氏の大軍団にそなえました。 |

源平の戦いでは興福寺は平家に、
東大寺は源氏に味方した。
|
一方、重衡軍は奈良側の木津川の陣地を一気におとした勢いで、奈良坂をせめたてましたが、なかなかおとせません。
僧兵たちの守りは固く、一日たち、二日たち、ついに三日めになりました。
「ええい、これしきの陣地をやぶれずに何とする。平家の恥ぞ。進めや進めえ。」
総大将の重衡は二十四歳の若者だけに、もう我慢がなりません。
その晩、大軍をひきいると、しゃにむに奈良坂の般若寺の陣地をつきやぶり、奈良市内に突入しました。 |

般若寺
|

般若寺は東大寺の北にある
|
3 奈良焼き打ち top
あいにくと月のないまっ暗な夜で、東大寺の大仏殿の大屋根さえ、やみにしずんで敵地のようすは全くわかりません。
どこに僧兵たちがひそんでいるのか、危険このうえもありません。
「火じゃ、火じゃ、火をつけい!」
重衡は大声で命令しました。
あかりのかわりに、民家に火をつけるのは、その頃の戦場のならいです。
すぐさま近くの家に火がつけられたとたん、おりからの強い北風にのって、みるみるうちに火の手は広がっていきました。
「な、何と、火がでたぞ。」
「平家らめ、火をつけおったぞ。」
赤々と夜空をこがし、もえくるう火柱。風にのり、うずをまいて走る炎。
ゴウゴウ……。バシバシバシ。
火は風をよび、風は炎を運び、般若寺からあおられた火はまたたくまに、近くの東大寺の周りを煙と火の海にしてしまいました。
「それっ、坊主どもめを逃がすな。たたっ斬れい。」
「おのれ、平家め。地獄へうせろ。」
槍をかまえ、刀をふりかざし、追いつめる平氏の大軍勢。
多勢に無勢ながら、ふみとどまってなぎなたをふるう僧兵。
そのなかを家を焼かれ、逃げまどう老人や女、子供。
「盧舎那仏、守りたまえ。」
「大仏さまあ。おたすけえ……。」
死にものぐるいで東大寺の境内へ逃げのびた人々は、大仏殿の中へ我がちに逃げ込みました。 大仏こそ平和、平安を守る仏であり、平氏のやいばも、火の手もおしかえす力があるはずです。
広い大仏殿の土間や二階に、こうした震えおののく老人、女、子供が二千人ちかく、びっしりと小さくなっていました。
その大仏殿に火が移ったからたまりません。
はやくも大仏殿から火柱があがり、やがて、大音響をあげて崩れ落ちました。
瞬間、うずまく火の海のなかから、真赤に焼けた巨大な大仏が全身をあらわしました。
目元からも鼻からも炎をふきだし、口は耳物からさけ、おおらかな顔はすさまじい怒りにかわっていました。
なおも、はげしくもえくるう火の海のなかで、大仏の首は宙とんで焼けおち、両手は炎にねじられて崩れ落ちました。
大仏自身の体もまた熱気にとけ、焼けただれ、みにくい巨大な銅のかたまりにかわっていきました。 |

源平合戦でついに大仏殿も焼け落ちた
|
と同時に、大仏殿ににげかくれていた二千人をこえる子供、女、老人たちも、大仏とともに焼け死んでしまいました。
何といういたましいことでしょう。ゆるしがたいことでしょう。
この晩、平氏の軍勢によって戦死した僧兵、やき殺された女、子供ら約五千人、焼けだされたお堂、仏像は、東大寺だけでなく興福寺までおよび、その被害は目をそむけるほどのむごだらしさ、すさまじさでした。
天平の昔、大仏が建立されてから四二九年めにあたる治承四年(一一八〇年)十二月二十八日夜のことです。
このことは、その頃の人々をどんなにおどろかせ、深い悲しみにおいやったか、当時朝廷につかえていた藤原兼実は、日記にこのように記しています。
「……天をあおいでは泣き、地に伏しては泣く。涙をぬぐいつつ心を痛めるばかりで、言葉ではこの苦しみをいいつくせない。文字に書いても何の役にもたたない。」と、嘆き悲しみつつ、
「……なおなお大仏が再び造立されるのは、いつの世であろうか。」と、せつせつたる悩みをつづっています。
また、のちの鎌倉時代になって、『平家物語』という平氏一族のことを書いた物語がでましたが、ここでも次のように書かれています。
「……聖武帝のご文章に『東大寺が盛んになれば、日本も盛んになる。東大寺が衰えれば、日本も衰えよう。』と、おっしやっている。されば、東大寺の炎上によって、天下はみだれ、衰えること、疑うことはできない。」
と、どんなに東大寺の炎上が日本をゆさぶる大事件であったかを、物語のなかでといています。 |
事実、天皇みずから仏の教えを守り、皇族、貴族、武士、商人、農民にいたるまで、仏を信じているその頃の日本では、寺院、仏像を焼くことは、何というおそろしい罪でしょう。
「仏を恐れぬ大悪人よ。平氏一族は仏の敵じゃ。」
大悪人であり、仏の敵とは平重衡です。
そしてまた、その父であり平氏一族のかしらである清盛の罪であり、清盛らにつながる平氏一族の罪でもありました。
平氏をそしる声は、やがて日本中に野火のように広がっていきました。
「いまこそ、仏の敵、平氏を倒すときだ。」
平氏と戦い、そのたびに負け戦をつづけている源氏一族にとって、この事件は平氏を叩きふせるまたとないチャンスです。
おりもおり、年があけた治承五年(一一八一年)二月、平氏一族のかしら、平清盛はにわかに熱病のために死にました。
「それみたことか。仏の罰があたったのじゃ。平家はもう終りよ。」
ひややかな人々の声のように、この頃からしだいに平氏の勢いは衰えをみせ、かわって東国に力をもつ源氏が伸びていくようになりました。
|

平清盛――大仏殿を焼き払ったことで、
世論は平家から源氏に変っていった
|
4 老僧の重源(ちょうげん)
top
こうした源平の戦いが日本各地でつづけられているさなか、「東大寺の大仏をまず、再建せよ。」という命令が、後白河法皇から、朝廷につかえている藤原行隆(ゆきたか)にくだりました。
造東大寺長官という、昔、佐伯今毛人がつとめた建設の総責任者の役目です。
その年の六月二十六日のことです。
つづいて、同じ年の八月、年号がかわった養和元年(一一八一年)八月、京都の醍醐寺の住職である俊乗坊重源(しゅんじょうぼう・ちょうげん)が行隆の下について、勧進をつとめることとなりました。
勧進というのは、昔、行基が大仏などの建立のために、人々から寄付をもとめて歩いたように、信者にすすめて金品の寄付をさせることをいうのです。
重源は浄土宗という仏教の二派をひらいた法然(ほうねん)という僧の弟子で、そのとき六十一歳の老人でしたが、勧進をつとめるについて、こんな話があります。
その年の春、東大寺の大仏の焼け跡をみにいって、余りのひどさにおどろくよりも、ただただ嘆き悲しむばかりでした。 |

大仏殿再建を命じた後白河法皇
|
けれど、涙をながしていても大仏も寺も再興はできません。そこで、
「私が勧進(かんじん=寄付を募る)の中心となって、もう一度、大仏や寺をたててみせよう。」
重源はそう決心をすると、このことを知合いの行隆(ゆきたか)にうちあけました。
やがて行隆が長官にえらばれたとき、重源はすすんで勧進の役を申し出た――といわれています。
このような重源だけにさっそく都へでむくと、後白河法皇からの銀の香炉を初めに、皇族、貴族たちからも銅製品の水瓶、鏡など、数々の資材の寄付をうけました。
また、三度も宋(中国)へいったことのある重源は、その頃の宋の新しい乗物である、あとおし式の一輪車をつくらせ、それに乗って日本各地を勧進してまわりました。
人々はめずらしい乗り物に目を見張りながら、熱心に大仏の再建を説く重源の言葉に、すすんでもっている物を差出しました。 |

一輪車に乗って勧進する重源(富岡鉄斎画、明治時代)
|
重源のこの働きは、天平の昔、行基が人々によびかけたあの言葉と同じです。
信仰をともにする者が、自分のもっている物を出しあって仏のためにつくすこと――あの《知識(ちしき)》が四百年をへた平安時代の末にも生きていたのです。
こうして全国の人々の差出した資材は、やがて牛車や人の背によって、奈良へ奈良へと運ばれていきました。
奈良の町はあの天平の頃のように、日ましに銅や木炭の山々がふえていきました。
もちろん、一人一人の寄付は貴いものでありながら、大仏再建の資材としては、まだまだ足りません。
そのため後白河法皇らは、周防(山口県の東部)、備前(岡山県の南部)の二ヵ国から取立てる税などを、大仏建立につかえるようにはからいました。
また鎌倉にいる源氏一族の頭(かしら)源頼朝は、平氏との激しい戦いの最中でしたがすすんで資材を送ったり、役夫のせわをしたりしました。
こうした重源の老人とはおもえぬたくましさ、大仏再興への激しい気がまえによって、いよいよ資金、資材が集まってきました。
一方、勧進と一緒に、鋳造の作業は鋳物師たちによって進められていました。
5 大仏の修理 top
ところで、重衡(しげひら)によって焼きおとされた大仏は、どれほどの損傷をうけていたのでしょうか。
『平家物語』をはじめ、その頃のいくつかの本にいろいろと書かれていながら、実ははっきりしたことがわかってはいません。
これは、著者たちが人からのまたぎきをもとに書いたためといわれています。
そこで、なにが焼け落ちたかを、修理した記録からみれば本当の破損の個所がわかってくるはずです。
これを表にしてみましょう。
養和元年(一一八一年)十月 六日
寿永二年(一一八三年)二月
同 二月十一日
同 四月十九日
同 五月十九日
寿永二年(一一八三年)五月二十八日
|
螺髪の鋳造にかかる。(焼けたあくる年)
大仏の首の土の原型ができあがる。
大仏の右手の鋳造がおわる。
仏頭の鋳造にかかる。
目、鼻の部分ができあがる。
仏頭の鋳造がおわる。このあとで、左手、胴体の順序で鋳造がおこなわれて、寿永三年(一一八四年)夏、鋳造の全部がおわる。 |
これが修理された主なもので、土台にあたる銅座の蓮弁については何も記録がありません。
なお、大仏のうしろに仏後山(ぶつごやま)という土の山があることは記しましたが、この土山のおかげで、大仏の腰、背中の部分が焼けずに助かったことは、なによりの幸運でした。
こうした記録からみると、このときの焼損の修理はいがいに小規模ですんだと思われます。
西大由(にしたいゆう)先生らのことは前にも記しましたが、先生らはその論文のなかで、
「源平時代の兵火による被害のていどは不明確であるが、このときの修理は首や手のほかは、それほどの大規模なものとはいえないかもしれない」と、記されています。
このことは、のちに江戸時代になって、二度めに焼けた大仏の修理がおこなわれましたが、そのときに使われた銅の量とくらべると、鎌倉時代の量の方がかなり少ないことがわかります。
また、鋳造の場所は大仏のうしろの仏後山を利用し、その上に大きな炉を三つ築いて、十四回の鋳造ののち完成したということです。 |

大仏の修理されたとおもわれる部分
大仏の倒れるのを防ぐ仏後山のおかげで、
大仏の焼損の被害は比較的軽かった。
|
6 宋の鋳物師、陳和卿(ちんわけい)
top
次に、鋳造にあたった技術者たちをあげてみましょう。
宋国の鋳物師 七人
大工 陳和卿(ちんわけい)
陳仏寿(ちんふつじゅ) ほか五人
日本の鋳物師 十四人
大工 草部是助(くさかべこれすけ)
草部助延(くさかべすけのぶ)
小工 是末(これすけ)ほか十一人
この役がらは天平時代の仕事にあわせると、宋の陳和卿は大仏師の国中君麻呂にあたり、総監督の技術者です。
日本の鋳物師の大工は天平時代の大鋳師にあたり、鋳造の主任技術者といえましょう。 |
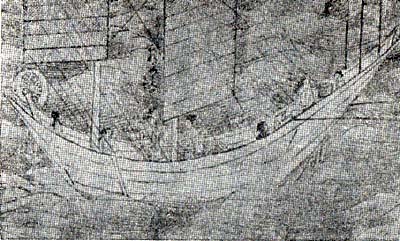
日宋貿易
|
ところで、総監督の陳和卿はどういう経歴の人であるか、くわしいことはわかっていません。
和卿は弟たちと宋から日本へ何かの商売にきていて、帰国するため長崎で船をまっているとき、東大寺の勧進の重源(ちょうげん)に見い出されたといわれています。
和卿は鋳造のほか、建築の技術にもくわしく、鋳造がおわったあとも、重源と大仏殿の建築についています。
また、のちに海を渡る船をつくったともいわれ、造船の技術もこころえていたようです。
このようなことから、鋳造、建築などの技術面をまかせられる専門家をさがしていた重源にとって、和卿はえがたい技術者であったのでしょう。
ことに重源は宋へは三度もいき、新しい時代の仏像、建築をみてきているので、何かと都合がよかったのでしょう。
こうして陳和卿を中心に鋳造がはじめられましたが、どういうわけか和卿は日本人の鋳物師との仕事を嫌い、その仲もよくありません。
和卿という人はかなり変った人で、これよりずっとあとのことですが、こんな話があります。
平家を倒し、鎌倉に幕府をひらいた源頼朝が大仏の参拝にきたときです。
「大仏を再建した陳和卿とやらに、あってみたいものだ。」
将軍頼朝は重源にこのことをつたえ、和卿をよびだそうとしました。
ところが、和卿は首をふり、
「会いとうはない。将軍頼朝は平家をはじめ、弟の義経や、多くの人を殺した罪ぶかい公人というではないか。
そんなお人は、こっちからごめんだ。」と、断わってしまいました。
その頃の頼朝といえば、天皇をしのぐ日本一の実力者です。
その頼朝を悪くいったり、いいつけにそむいたりすれば、たちまち捕えられ、殺されてしまっても文句はいえません。
ところが、断わられた方の頼朝はすこしもおこらず、
「おもしろい奴め。」と、反対にたくさんの褒美(ほうび)をよこしました。
けれど、和卿(わけい)はその褒美さえもつっかえし、わずかに兜(かぶと)と、鞍(くら)だけをもらいましたが、
「兜は鋳(い)なおしてくぎにお使いくだされ、鞍は何かとお役にたつであろう。」
と、東大寺に納めてしまいました。
このように、和卿(わけい)は自分の考えを強くおしだす人で、仕事のうえでも、何かといざこざをおこしたようでした。
このため、重源(ちょうげん)は日本人の鋳物師と和卿たちとの間にはさまれ苦労したことが、その頃の本に残されているほどです。
しかし、それはともかくとして、鋳造、修理がおわって、顔の部分だけの塗金がはじめられました。
大仏に魂をむかえる開眼の供養をいそぐためです。
もうこの頃、平氏の勢いはすっかり衰え、天下は源氏にかわっていました。
なかでも、奈良を焼き打ちした平重衡は、一の谷(神戸市)の合戦で源氏にやぶれ、生けどりにされ、頼朝のいる鎌倉におくられていました。
「大仏を焼きつぶした重衡めを、われらにおわたしくだされ。
仏の敵をこらしめれば、仏に申し訳がありませぬ。」
東大寺の僧兵たちは頼朝にたのみ、重衡の身がらを奈良へおくってもらいました。
もちろん、奈良へおくられた以上、重衡はなぶり殺しの運命にあいます。
けれどさすがにむごい殺しかたはさけられ、武士の手によって木津川の川原で斬り殺されました。
重衡は仏像を前に高らかに念仏を唱えつつ、首をうたれたということです。
大仏を焼いてから三年め、重衡が二十七歳の文治元年(一一八五年)六月二十三日のことです。
重衡の死体は胴体はそのまま川原にすてられ、首は奈良坂にさらされましたが、重衡の妻は悲しみにたえられず、重源に特別にたのんで首をもらいうけ、胴体とあわせてねんごろに葬ったということです。
重衡が首をうたれ、その首をあらったという首あらいの井戸は、木津市の木津川のそばの重衡団地という住宅団地の片隅に、今も残っています。 |

平重衡(たいらのしでひら)の墓
大仏殿を焼いた重衡は、鎌倉から奈良に
おくられ、木津川の川原で斬り殺された
|
7 大雨の開眼会 top
重衡の死から二ヵ月ほどたって、いよいよ大仏開眼がおこなわれることになりました。
文治元年(一一八五年)八月二十七日のことです。
大仏の塗金はまだ頭部が終っただけでしたし、大仏殿をはじめ建物は全く手がついていない状態でした。
けれど開眼をいそぐ後白河法皇の気持には、戦乱がおさまってきたとはいえ、一日もはやく大仏によって、平安がくるようにという祈りがこめられていたのです。
この日、法皇はみずから高い足場の上にのぼって、筆をとって大仏の目に墨で点を描きました。
法皇が使った筆と墨、その筆についた長い綱は、天平の昔菩提僧正が使ったものを、正倉院から取り出してきたものです。
ところが、そのときです。
「オーッ、オーッ」 式場の周りで今日のこの日をみようとつめかけていた大勢の人が、大声で叫びながら門をやぶって雪崩こんできたのです。
「ひかえろ。ひかえろ。」
式場を守っている武士、僧たちがどなりつけ、おしかえそうとしますが、雪崩こむ人たちの勢いにはかないません。
「開眼のお綱を……。」
「あれらにもお綱をひかせたまえ。」
人々は叫びながら、法皇のもった大きな筆についた長い、たくさんの綱に下の方からとびつき、握りしめようとしました。
「オーッ、オーッ」 天平の昔には考えられぬことがおこったのです。
大仏再興につくした町民、農民、作業につく人夫たち一人一人が、自分らもまた法皇らと同じように、仏の恵みにあずかろうとしているのです。
ひしめきあう人々を、みんなより高い席についてみおろしていた重源の目には、いつしか涙が光っていました。
おもえば大仏再建をこころざしてから、この日で満五年になります。
その間、源平による激しい戦い、家を追われ、食べるものもないみじめな国民のくらし、そのなかでよくぞ大仏の再建がはたせたものだと、苦しみよりも大仏のめぐみに、ただただありがたく思うばかりだったのです。
やがて騒ぎがしずまり、またおごそかな読経に移り、そのあとから菩薩の舞、迦陵頻迦(かりょうびんが)の舞いといったにぎやかな舞がまわれているときでした。
曇り空であった空から、とうとう雨がふりだし、まもなく大雨となりました。
大仏殿がまだ建てられないときだけに、法皇をはじめ、皇族、貴族、僧、源頼朝の代理の武士たち、それに式場になだれこんできた大勢の人々は全身ずぶぬれになりながら、再建大仏の開眼を祝ったのでした。 |
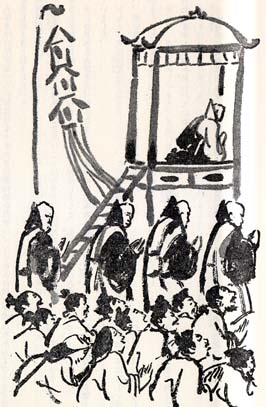
開眼式には民衆も雪崩込んできて、
法皇、僧侶と共に仏の恵みに授かろうとした
|
ところで、和卿が中心になってつくった大仏について、その頃の人の意見がいろいろとわかれています。
ある人は大変ほめそやしていますが、反対に、ある人はこういっています。
「昔のおおらかなお顔とくらべると、このたびのお顔は、大変見劣りがする。」
おそらくこれは天平時代の彫刻の様式と、陳和卿(ちんわけい)のもっている宋の彫刻の様式との違いからきたものと思われます。
けれど和卿がつくった大仏の顔はその後、また戦争のために焼けてしまったので、今となってはその優劣をきめるすべがありません。
8 大仏殿の再建 top
こうして大仏開眼はめでたく終ったものの、東大寺の再建という仕事全体からみると、まだまだ仕事は残っています。
これからは、主に大仏殿の建立です。
重源は(ちょうげん)、和卿(わけい)や、番匠(ばんしょう=大工)の物部為重(もののべためしげ)、桜島国宗(くにむね)などをひきいて、周防(山口県)の山中へ入って用材をえらび、切りだしにあたりました。
東西八十六メートル、南北五十メートル、屋根の高さ四十六メートルという天平時代そのままのものを建てるだけに、柱も長さ三十メートル、直径〇・七メートルといった、途方もない大きな物が百何十本もいるのです。
「柱一本に米一石のほうびをだすぞ。」
重源はきこりたちにそういってよびかけましたが、さて、そうした柱がみつかっても、節(ふし)や枝がおおかったり、中がウツロになっていたり、使えるものは三十本のうち、せいぜい一、二本という始末でした。
これでは周防(すほう=山口県)だけではまにあわないので、特に頼朝にたのんで、隣の長門(ながと=山口県)、また、備中(びちゅう=岡山県)、伊賀(いが=三重県)の国々の山林の木も用材につかえるようにはからってもらいました。 |

木材を運んだルート
|
こうしてようやくみつけて切りだした木を川へ運び、海へ流し、陸上では百頭ほどの牛にひかせて運ぶのです。
周防、長門、備中などからでは、瀬戸内海をとおり、尼崎(兵庫県)へいき、さらに木津川をさかのぼって、木津から奈良へ送るのです。
平地でも長さ三十メートル、直径〇・七メートルの棟木(むなぎ)はなかなか運べるものではありません。
それを人の入らない山奥から運びだすには、まず谷をうずめ、岩をくだき、橋をかけ、木を切りはらって道をつけなければ、とうてい運びだすことはできません。
ことに、天平時代は朝廷の力が強く、国家の事業として思うようにできましたが、鎌倉時代は天皇家よりも武士のほうが力のある時代です。
そのため、重源は何度も地方をおさえている豪族の武士たちの妨げにあいながら、およそ十年、ねばり強く用材を切りだし、運びだしていきました。
重源のこうした苦労に、こんな伝説があります。
山から大木を出すことに人夫たちが疲れはてて動けないでいると、重源はそばにあった大石を餅のようにちぎって、数千万にして投げました。
人夫たちはそれを食べたところたちまち元気を取戻し、大木をふもとまで運びだすことができました。
また、大木を切りだしたものの、道をつけることもできず、困っていると、にわかに大蛇が現れて山をくずし、川を海へつけてくれたので、ようやく大木を海まで運ぶことができました。
伝説とはいえ、その頃七十歳をこえた老僧の重源が、どんなに骨身をけずるおもいで働いていたか、頭のさがる話ではありませんか。
やがて、大仏開眼後十年めの建久六年(一一九五年)はじめ、重源らの努力によって、見事、大仏殿は完成しました。
この頃、大仏鋳造の足場ともなった仏後山(ぶつごやま)は取り去られていました。
その年の三月十二日、大仏殿の完成をいわう落慶供養という式が大仏殿でおこなわれました。
この日、後鳥羽天皇のほか、特に鎌倉からはるばる幕府の将軍、源頼朝が、夫人や家来たちを大勢したがえて参列しました。
「仏の敵、平氏が焼いた大仏や東大寺を源氏がたてなおしたのだ。
源氏のひきいる鎌倉幕府こそ、仏につかえ、国民とともにある政府だ。」
平氏にかわって天下をとった源氏の総大将頼朝の参列の心には、幕府をあらためて認めさせる政治的な考えがあったようです。
この儀式のあと、只々み仏のためにだけつくして十四年、その間、大仏、大仏殿再建をはたした重源に大和尚位(たいかしょうい)という僧として最高の位が授けられました。 |

大仏殿の完成をいわう落慶供養に
鎌倉から来て参列した源頼朝
|
なお東大寺の再建の仕事をみると、初めに大仏、第二に大仏殿、第三に境内のお堂その他です。
そこで重源は三度その再建につくし、中門、回廊、南大門などの付属の建物を天竺式(てんじくしき)という宋の芸術様式でたてました。
大仏殿もその天竺式です。
また、この時代、南大門の金剛力士像の仁王像を、力をあわせて彫刻した運慶、快慶をはじめ、奈良仏師とよばれる大仏師たちは、重源のさしずによって、建物や仏像の復興に力をつくしました。 |

南大門(宋風の天竺式で建て物)
|
こうして重源が六十一歳のときから二十二年間、八十三歳にいたるその日まで、ただひたすらに東大寺再建につくした努力は、ついにみのる日がきました。
建仁三年(一二〇三年)十一月三十日、東大寺のすべての建物、仏像、大仏は再興され、東大寺総供養がおこなわれたのです。
重源はこの日を見届けると、やがてその三年後の建永元年(一二〇六年)六月四日、しずかにその貴い八十六年の一生をおえました。
東大寺復興に一身をささげた俊乗坊(しゅんじょうぼう)重源は、大仏殿から三月堂にむかう道の片脇の俊乗堂とよばれるお堂にまつられています。
そのお堂には重源の肖像の彫刻があって、キッと唇をひきしめ、志したことはかならずやりとげてみせるという強い気持を、そこに表わしています。
その彫刻は重源のしたしい彫刻家の快慶(かいけい)の作ではないかといわれています。 |

東大寺を再建した重源(ちょうげん)
|
9 鎌倉の大仏 top
なお、この頃から四十年ほどたった鎌倉時代の中頃、鎌倉にも大仏が建てられました。
この大仏は奈良の大仏のおよそ十分の七、高さ三丈七尺(十一・三メートル)で、いまは金銅仏ですが、建立のときは木造であったということです。
浄土宗の高徳院の本尊で、奈良の慮舎那仏の像とちがって、阿弥陀如来の像です。
寺の言い伝えによれば、奈良の大仏を参拝した頼朝とその夫人が、鎌倉にも大仏を建立したいと考え、計画したといわれています。
頼朝夫妻が亡くなったあとは、頼朝につかえていた稲多野局(いなだのつぼね)という老女が、二人の志をついで建立したということです。
top
**************************************** |