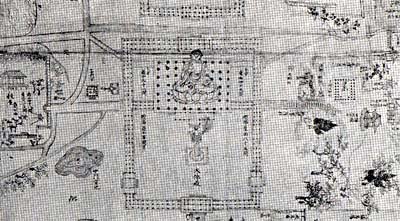|
****************************************
Index 1
2 3
4 5 6
7
5 大仏事始(ことはじめ)
1 小僧の公慶(こうけい)
top
家康によって築かれた徳川幕府は、やがて日本じゅうをしっかりとおさえ、ゆるぎない強大な政府になっていきました。
この頃、東大寺はほかの大寺院と同じように、幕府の監督をうけ、特に朝廷に近づいてはならないこと、僧が武器をもってはならないことなど、固くいましめられていました。
東大寺については、聖武天皇が建立された考えにしたがって、国家のための寺として、国家への祈りが第一とさだめられました。
普通の寺の場合、檀家(だんか)といってその寺や僧の経営、生活を支える信者がいますが、東大寺は国家の寺ということから、檀家信者は一人もありません。
そのかわり、幕府からあてがわれた領地からの米、その他の年貢で経費をまかなうことになりました。
また、古くから関係のある周防(山口県)には毛利氏が大名となっているので、周防にある領地は毛利氏に守ってもらうことになりました。
けれどこれらの領地や年貢などは、盛んであった奈良、鎌倉時代にくらべるとグンとへって、地方の小さな大名の収入にもおよばないほどでした。
しかしこれがその頃の幕府の寺院に対する監督のやりかたであり、東大寺もまたそれに従わなければならなかったのです。
ところで、こうしたきりつめたとぼしい財政のなかで、はたして大仏殿は再建できるのでしょうか。
いつまで大仏は、雨ざらしのままの露座(ろざ=屋根がない)でいなければならないのでしょうか。
戦乱の時代は遠くはなれ、家康が幕府を開いてはやくも八十年、将軍はもう五代めを迎えているではありませんか。
「おいたわしいことじゃ。大仏さまは傾(かし)いでおられるぞ。」
奈良をたずねる人々は露座の大仏をあおぎながら、いいあわせたように顔をくもらせました。
だれの目にも大仏の巨体が心もち傾いているようにみえるのです。 |
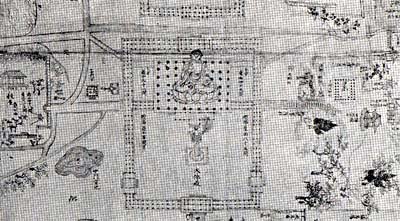
露座(ろざ)の大仏古地図(東大寺寺中寺外総絵図)
|
むりもありません。永禄十年(一五六七年)に焼けていらい、百年余り、不完全な仏体のまま、雨ざらしになっていたため、仏体のなかの支えの木材も腐ってきたのです。
そのうえ、火をあびて台座もこわれているので、十六メートルの巨体がいっそう傾いているようにみえるのでしょう。
その頃、そうした参拝の人の嘆きや大仏の余りにもいたましい姿に、いつも心を悩ませている小僧がいました。
十三歳のとき、丹後(京都府)から、僧になるためにやってきている東大寺の式部卿公慶(こうけい)でした。
でも、小僧の公慶になにができるのでしょう。
忙しい勤めのひまをぬすんで、大仏のまわりを掃き清め、心から大仏の再建を祈るより道がないのです。
けれど五年、十年とたつうちに、公慶は大仏の姿が不様でも傾いでみえても、余り気にならなくなりました。
毎日毎日みなれているせいでしょうか、それとも公慶が悪い遊びでも覚えたからでしょうか。
ところが、ある晩のことです。
公慶はつかいの帰りすっかり遅くなって、東大寺の南大門をくぐったころは、とっくに真夜中をすぎていました。
あいにくと夕方からの大雨がぶりやまず、道をいそいでいるうちに、公慶はおもわずハッとして立ち止まりました。
すぐ目のまえに、黒山のような大仏がたちはだかっていて、ザンザンと滝のような大雨に全身をうたれているのです。
頭から肩、胴、ひざ、手――たたきつける大雨に、じっとたえている大仏の何と痛々しいこと、哀れなこと。
「ああ、恐れおおいこと。」
公慶はべったりと大仏のまえにひれふしました。
ぬかるみも、滝のような雨も、公慶の頭にはありません。
いまのいままで、大仏をこのように不様(ぶざま)なかっこうで、雨ざらしにしたまま放っておいたとは、何と罪の深いことであろう。
これが、大仏を本尊とあがめる東大寺の僧のすることといえようか。
公慶ははずかしさ、申し訳なさで、いたたまれないほど苦しくなりました。
「大仏をおなおししなければならぬ。大仏殿をもう一度たてなければならぬ。それが私の務めだ。」
公慶ははっきりとそのことを大仏に誓い、自分自身にいいきかせました。
こうして公慶はこのときから大仏の修理、大仏殿の再建に乗り出しましたが、また、こういう言い伝えも残っています。
やはりある真夜中、公慶が遊びからの帰り、月光にてらされ夜露にぬれ、風にふかれる露座の大仏をあおぎ、
「ああ、これではならぬ。」と、ハッとしたおもいで遊びほうけていた行ないを恥じ、大仏の修理という大事業を決心したというのです。 |

雨に打たれている大仏の姿を見て
公慶は大仏の大修理を決心した
|
2 銅をかついで top
公慶はその晩をさかいに熱心に仏の教えに励むようになり、やがて東大寺で一、二といわれる僧にまでなりました。
そして、三十五歳のときの貞亨元年(一六八四年)、つづいて、二年の二回、奈良から江戸(東京)へでて、幕府に大仏再建の願いをうったえました。
奈良、鎌倉の両時代、行基や重源が命をかけて大仏再興につくした勧進を、公慶もまた願ったのです。
その頃、幕府は五代将軍綱吉の時代でしたが、公慶の願いはきき届けられ、いよいよ、念願の大仏再建の勧進がはじめられました。
貞亨三年(一六八六年)十一月九日のことで、この日を人々は、大仏再建の「大仏事始」とよびました。
「事始」というのは、仕事にとりかかるという意味です。公慶の勧進は奈良から大阪、京都と、まもって歩きましたが、はやくも大阪の商人、北国屋治右ェ門(ほっこくやじろえもん)が、瓜形の銅のかたまり九百斤(約六〇七キログラム)の寄付を申し出ました。
九百斤といえば瓜形で約三千個ほどです。
「はて、これだけの銅をどのようにして奈良まで運ぼうか。船にするか、車につむか。」
余りにも多い銅のかたまりに、公慶にしたがう人たちも、運ぶ方法に困ってしまいました。
すべて、人の寄付にたよっている以上、運び賃まではたのめません。
「おう、それなら、よいことをおもいついた。銅のかたまりは山にしてこの道ばたへ積んできなされ。
なに、とられるものか。かまわん、かまわん。」
公慶は心配する人々をしりめに、木の立て札をもってこさせると、そこに「大仏殿用の銅」と筆で書き、銅の山のそばに立てておきました。
すると、それをみた人や、旅人たちは、
「おお、ちょうど、奈良へいく用がある。ついでに大仏さまの御用ができるとはありがたい。
なむあみだぶつ、なむあみだぶつ。」と喜んで、一つずつ、銅のかたまりを奈良へ運んでいきました。
こうして、三千個の銅のかたまりは、とられるどころか、何と七日めに、全部東大寺へ届けられたということです。
さて、勧進と同時に、大仏の修理、大仏殿の再建の作業や準備もはじめられていました。
これらの鋳物師、大工ら技術者の総監督に、京都にすむ後藤玄順があたりました。
玄順は永禄年間、山田道安をたすけて大仏の顔を銅板でつくったという後藤吉正の子孫で、公慶をうやまっていた建築家であるといわれています。
この玄順のさしずをうけて、鋳造にあたった人たちは、
鋳物師 鍋屋町 かまや 広瀬弥左衛門国重
同 広瀬弥次郎兵衛正次 |
たちでその下に弟子十五人、人夫十人がつきました。
この弥左衛門たちによって、大仏の古い頭部は取り除かれ、新しい頭部が鋳造され、また首から胸にかけてかなり人がかりな鋳かけがおこなわれました。
さらに台座の蓮弁がこわれたり、失われたりしていたのを十八枚もつくりなおし、数をそろえました。
もちろんこのときに、露座の間にくちはてた体内の支えの木組みを新しく取換えましたし、蓮弁の下の台座の石もすっかり組見直しました。
こうして大仏事始の貞亨三年(一六八六年)から次々と修理がすすめられ、五年後の元禄四年(一六九一年)初めには、ほぼ修理がおわりました。
この頃書かれた『大仏再建記』という本に、修理に使われた材料、人数が次のように記されています。
唐金(青銅のこと) 六万
五七五四貫 (24万6582キログラム)
炭 二万 八〇五六俵
鋳物師工数 四万 二〇六人
日雇人夫 三万 八五八二人 |
これらの大仏修理に使われた材料、人夫たちの費用はその頃の金額で、一万一一七両もかかり、いまの金額になおすと、約一億円になると、まえにあげた荒木宏氏の本に記されています。
やがて、大仏の修理がすべておわり、あくる年の元禄五年(一六九二年)三月八日、いよいよ、大仏開眼の供養の儀式がおこなわれました。
この日まだ、大仏殿ができていたいため、大仏の上に大きな板ぶきの屋根をかまえ、蓮弁の上の台に花などを供え、そのまえに開眼をする導師の席をつくりました。
導師は東大寺の別当済深法親王があたり、特に正倉院にしまってある聖武天皇、後白河法皇のときに使った開眼の大筆で、黒々と大仏の両眼に墨をいれました。
導師のそばでじっとみあげている公慶の感激は、いかばかりであったでしょう。
この日のために、東山天皇は勅使をおくり、また幕府から奈良町奉行も参列し、さらに興福寺をはじめ、奈良、京都の寺々からも僧たちが一万二〇〇〇人もくわわり、おごそかで華やかな開眼供養をいとなんだのでした。
まさに、永禄の炎上以来、一二五年ぶりの大仏開眼です。
この盛んな開眼供養はその日から三十日間、釈迦が誕生したゆかりの日、四月八日までつづき、その間、約二十一万人の人が、京都から大阪からあるいは江戸から、続々と参拝にやってきました。
そのため奈良の案内人は一人あたり百両という途方もない大金をかせいだともいかれ、また大阪から奈良へぬける街道の一つの生駒山の暗(くらがり)峠は毎日毎日、人の行列でにぎわったということです。
いまならさしずめオリンピックか、万国博覧会のような大変な人出だったと思われます。
3 三度めの大仏殿 top
念願の大仏の修理再建ができて、公慶はほっとしたのでしょうか、それとも五年にわたる苦労が、体にこたえたのでしょうか、まだ四十五歳という働き盛りなのに、明日をもしれぬ重病にかかりました。
大仏はできても、大仏殿はこれからです。まだまだ、しなければならない仕事は残っています。
公慶は動けない自分をこのときほどもどかしく、くやしく思ったことはありません。
けれど幸いにも、体はもとどおりになおり、今度はいままでの遅れを取り返すように、懸命に大仏殿建立のために勧進につくしました。
幸せなことに公慶のこの働きは、将軍綱吉があらためて見直し、すすんで幕府が便宜をはかってくれることになりました。
将軍自身も建設資金の寄付をし、また、全国の大名にそれぞれ身分におうじて寄付をさせました。
おかげで十万両という多額の資金が集められ、仕事もぐんとやりやすくなりました。 ところが、それほどの建設資金をもってしても、どうにもならないのは大仏殿を支える虹梁(こうりょう)です。
虹梁というのは、柱と柱の間にわたす梁(はり)のことで、苦心に苦心をかさね、ようやく日向(宮崎県)の山中で、それにふさわしい松二本を見つけました。
長さ十三間(約二三・七メートル)もある巨材だけに、山中から海まで運びだすのに五ヵ月、そこから木津まで船で運び、木津から奈良まで車で数千人の人が懸命に引いて、ようやく運びこんだということです。
この虹梁(こうりょう)さがしが意外に手間どり、大仏殿の建設がほぼできあがったのは、開眼後七年たった宝永二
年(一七〇五年)四月のことでした。
もうあと一息です。
公慶は八、九分どおりできあがった報告とお礼をかねて、また、江戸へでて幕府を訪ねました。
けれど何ということでしょうか江戸へついてまもなく病気にかかり、日頃の疲れのためそれをはねかえす力もなく、七月十二日五十八歳で亡くなりました。
赤痢のような伝染病であったといわれています。
けれどあとしばらくすれば、百有余年ぶりに大仏殿が完成するというのに、その落成を見ずに亡くなったとは、どんなに心残りであったでしょう。
公慶の残したその志は、三人のでし、公盛(こうせい)、公俊(こうしゅん)、庸訓(ようくん)にしっかりと受継がれ、力をあわせて建設をすすめました。
やがて宝永六年(一七〇九年)三月二十一日大仏殿は見事に完成しました。
永禄の炎上以来、実に一四三年めに、雨ざらしのままの大仏にようやくそれをおさめる金堂、大仏殿ができたのです。
この大仏殿は三度めのものですが、まえの二回、奈良、鎌倉時代のものとくらべて高さだけは元のままですが、間口は三分の一ほど小さくなっており、形も長方形から正方形とあらたまりました。 |

大仏殿再建につくした東大寺の僧公慶

大仏殿を支える虹梁の松二本を
宮崎県の日向から奈良まで運んだ
|
大きさは、今も昔も世界最大の木造建築物です。
こうしていま、私たちが仰(あお)ぎみる大仏と大仏殿は、元禄の昔、公慶が一生をかけて再建したものなのです。
公慶は生前、勧進のために、勧進所という赤い門のある寺を開いていましたが、今もそのなかの公慶堂には、公慶の木像がまつられ、その働きをたたえています。
top
**************************************** |