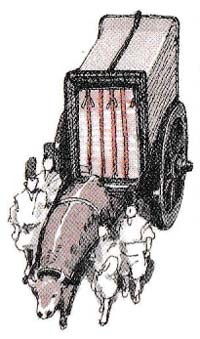|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 付録
一章 武士の時代の幕あき
1 さむらいという武士 top
「さむらい」という言葉を聞くと、だれもが、よろいかぶとに身をかため、腰に刀をさした強そうな昔の武士の姿を思いうかべる。
いまでも、「あの人はさむらいだなあ。」などということがある。
そのとき、わたしたちはどのような人のことを考えているのだろう。
きっと、何事も自分の力でことをはこび、他人やまわりのことを気にしないで自分を信じ、勇ましくなしとげる人のことを思いうかべているにちがいない。
さむらいという言葉は、立派な人、偉い人のことをいう言葉になっていることが多い。
「さむらい」という言葉はずいぶん大昔からつかわれているが、もとは「さぶらう(侍う)」という言葉からできたものだ。
「さぶらう」というのは、主人のそばにつきしたがうという意味である。
いまからおよそ千三百年昔に、中国の政治のしくみを取入れて、大宝律令
* という法律が定められた。
* 大宝律令
律令というのは、奈良・平安時代の国の基本になる法律。
律は、犯罪について定めた、いまの刑法にあたり、令は、その他の法律にあたる。大宝律令は、七〇一(大宝一)年に制定された。
そのなかに「侍人」(さぶらいびと)という制度があって、おもい病気にかかっている者や八十歳をこえた人には、この侍人が一人つきそって、身のまわりのせわをすることがきめられていた。 |
 |
九十歳以上は二人、百歳以上は五人とも定められていたという。
こういう福祉制度 *
が、じっさいにどれほど実施されたかはわからないけれど、「さむらい」というのは、そういう看護人のことをさす時代もあったのである。
* 福祉制度 めぐまれない人々を重点に、みんなが、できるだけ満足のいく生活をおくれるようにするための社会のしくみ。
では、いまわたしたちがいう「武士」というさむらいは、いつごろあらわれたのであろうか。
いまから千年ほど昔のことになる。その頃都のあった京都の町が、一番栄えた時代である。
|

藤原氏の祖、中臣の鎌足
とくに、奈良・平安時代に
大きな力をふるった一族。
大化の改新で手柄をたてた中臣鎌足が、天皇から藤原という名字を
たまわったことにはじまる。
|

十二ひとえ はかま
十二ひとえは、平安時代、朝廷につかえた女性の正式の服装。
きものを何枚もかさねて着て、そでぐちやえりが、
何重にも見えるもの。はかまを下にはいた。
|
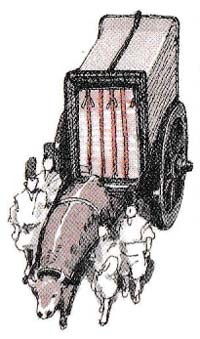
牛車
牛がひく、屋根がついたのりもの。
身分の高い人がのる。
|
天皇のそばで、政府の役人として高い位についていた藤原氏をはじめ、力のあった貴族たちはみな、たくさんの財産をたくわえて、ぜいたくなくらしをしていた。
毎日の生活には長たらしい儀式が多く、歌あそび
*
がはやり、夜ごと夜ごと宴会がつづくといったありさまだった。
* 歌あそび ここで歌というのは、和歌のこと。貴族が左右二組にわかれ、和歌を一首ずつくみあわせて、どちらがすぐれているかをきそう、歌あわせというあそびなどがおこなわれていた。 |
貴族の婦人たちは、幅のひろくて長いはかまの上に「十二ひとえ」などという、たくさんの絹のきものを着かさねて、かざりたてた牛車
* にのり、都の大路をゆきかっていた。
しかし、一歩、都をはなれると、人々はみな苦しい生活をしていた。
食べ物がなくてゆきだおれになる者も多かったし、しかたなく盗賊になって物持ちの家をおそう者など、自分の土地をはなれていく者が多かった。
その昔定められた「律令」という法律では、土地は国の所有と定められ、国司、郡司などという地方官にまもられて、人々に平等にわけあたえられていた。
しかし、都の貴族たちが政治をわすれて、その日その日を楽しくあそびくらしているうちに、人々をまもらなければならないはずの国司や郡司が、政府の目のとどかないのをよいことにして、弱い農民の土地を取上げたり、政府のゆるしもなく新しい土地を開墾したりして、かってに自分の土地をひろげていった。
もちろん税もろくに納めない。
こんなありさまを、都の貴族が知らないはずはない。
しかし貴族たちは、それをとりしまるどころか、反対に自分たちもこれにならって、各地に自分の領地をふやしはじめた。
都でぜいたくなくらしをするためには、たくさんのお金や物が必要だったのである。
これでは、もとから地方に住みついている者もじっとしていられなくなった。
いつ政府や、力のある地方役人からおどかされて、自分たちの土地を取上げられるかわからない。
こつこつと自分の土地をたがやしながらも、一方では自分の土地をまもるために、力の強い者を集めて敵をふせぐことを専門にする人間をやしなうようになった。 |

国司の屋敷(「石山寺縁起絵巻」)
国司、郡司(こくし、ぐんじ)
このころ日本は、いくつかの国とよばれる地域にわけられ、
そのなかが、さらにいくつかの郡にわけられていた。
国司は、国をおさめるように命じられた中央の役人で、
郡司は、郡をおさめるよう命じられた地方の豪族。
|
こうして、貴族や、力のある豪族がひろめていった所有地のことを「荘園」というのである。
そして、その荘園をまもるためにやしなわれた人々が、やがて武士といわれるようになっていくのである。
国からわけてもらった土地で生活している農民のなかには、自分の土地をまもるだけの力もなく、苦しい生活にたえられなくなって、荘園の中ににげこみ、百姓をやめて荘園の用心棒になる者が多くなった。
荘園の武力はだんだん強くなり、荘園の領土は用心棒の親分、つまり武士の大将となって、その地方に強い勢力をもつようになった。
こういう武士の大将が国の方々にできた。なかでも関東地方に強い武士が多かったようである。
それは、関東地方にはよい馬の産地がたくさんあったからだといわれている。
こうして各地にできた武士のなかで、とくに力のあったのが、天皇の血すじをひくという源氏と平氏であった。
武士のかたまりが国の方々にできると、たがいにその勢力をひろげようとするから、あらそいがおこる。
しかし、都にいる政府の役人たちは、地方に争いがおこっても、もうそれをしずめるだけの力がなくなっていた。
なにかことがおこるたびに、政府は源氏や平氏にたのんで、その争いをしずめさせるようになった。
争いをしずめるといっても、そこで裁判が行われるわけではない。
いくさをして相手を攻めほろぼすか、降参させてしまうのである。つまり戦争である。
戦争に勝って都にのぼり、政府に報告すると、ほうびがもらえる。
しかし、そのほうびは、せいぜい都の下っぱ役人に取上げられるくらいのものであった。
|

白河法皇
一〇五三〜一一二九年。一〇七二年に、二十歳で天皇になる。
一〇八六年に位をゆずって上皇になると、より強大な権力を手にした。
一〇九六年に出家して法皇となった。
源氏の大将に源義家(よしいえ)という武士がいた。
八幡太郎といわれる有名な大将だが、二度にわたって陸奥(むつ、東北)の国を平定するために戦った。
「前九年の役」「後三年の役」とよばれる戦いであるが、文字どおり長い戦いであった。 |

源義家を祀る石清水八幡宮
源義家(みなもとのよしいえ)、一〇三八〜一一〇八年ごろ。京都府の石清水八幡宮で大人になる儀式をしたので、八幡太郎とも名乗った。
武術にすぐれ、馬の上から弓を射ることをもつとも得意とした。
学問もこのんだ。
|
しかも都を遠くはなれたところでの苦しい戦いであったが、ようやく勝つことができた。
義家の勢力が強大になったため、白河法皇は義家に御殿に昇ることをゆるした。
これは「昇殿」(しょうでん)といって、たいへん名誉なことだった。
昇殿をゆるされた人は「殿上人」(てんじょうびと)とよばれた。
武士で殿上人になっだのは、この義家がはじめてのことだった。
武士が殿上人になることは都の貴族たちにとって大きな問題であった。
その頃右大臣の位にあった中御門(なかみかど)藤原宗忠(むねただ)という人が書きのこした『中有記』(ちゅうゆき)という日記に、こんなことが書いてある。
「義家は天下第一の武勇の士である。だが、今度それが昇殿をゆるされたというのはいかがなものだろう。
我々からみれば、それは感心できるものではない。しかし、いまはなにもいうまい。」 |
いくさに強いことはじゅうぶんみとめているのだが、だからといってあまりおもくもちいられ、都で大きな顔をされてはたまらないということだろう。
「しかし、いまはなにもいうまい。」というのは、なにかをおそれていることがわかる。
おそれるといえば、その頃都ではやった歌に、こんなのがあった。
| 「鷲(わし)のすむ深山(みやま)には なべて(すべて)の鳥はすむものか 同じ源氏ともうせども 八幡太郎はおそろしや」 |
深い山奥には鷲がすんでいるから、ふつうの鳥はすめないのだ。
それと同じように、八幡太郎のように強い男が都にいては、とても一緒にはいられないというのである。
その頃の都の人々の気持ちを、じつにうまくあらわした歌である。
いや都の人々の気持ちというより、都の人々が、武士をおそれている貴族たちをからかった歌といったほうがよいかもしれない。
武士は強い、そしてこわい。でも、その武士に働いてもらわなければ、都の貴族たちはもう自分の命や財産、そして地方にある領地だってまもることができなくなっていた。
「さぶらう」者は、いつしか武士になっていたのである。
しかしまだその武士は、貴族の用心棒であり、番犬でしかなかった。
2 源氏は東、平氏は西に top
武士として都でまっさきに重くもちいられたのは源氏だった。
しかし、義家が死んでからの源氏は、いきおいがきゅうに衰えはじめた。
それは源氏の一族のあいたで内輪もめが多かったからである。
そのあいだに、おくれをとっていた平氏がめきめきとその勢力をのばしはじめた。
それは、平忠盛(ただもり)という平氏の大将が、鳥羽上皇の命令をうけて瀬戸内海の海賊をたいらげて、手柄をたてたころからであった。
そのほうびに忠盛は源氏の大将よりも高い位をもらうことになった。
忠盛は瀬戸内海の海賊征伐に成功し手柄、瀬戸内海を往来する船をほとんど支配することになった。
船は当時の最大の輸送機関であった。一そうの船は、一頭の馬よりはるかにたくさんの荷物を運ぶことができる。
忠盛はただいくさに強いばかりでなく、船を支配することによって商取引をおこない、莫大な利益をあげた。
その取引は、国内だけではなく、中国との取引もあった。
そうして手にいれたお金やめずらしい品物を、忠盛はせっせと宮中へのおくりものにした。
そして貴族にしたしまれ、貴族の仲間いりができるまでになった。
貴族の仲間いりをするためには、いろいろ教養も身につけなければならない。忠盛にはそういう才能もあった。
ある年、忠盛が備前(びぜん、岡山県南東部)の国から都へ帰ってきて上皇の御所にうかがった。
上皇は忠盛を見ると、
「明石の浦やいかに。」とたずねられた。すると忠盛はすぐに、
| 「ありあけの 月も明石の 浦風に 波ばかりこそ よると見えしか」 |
と、歌をよんで答えた。上皇はすっかり感心して、この美しい和歌を『金葉(きんよう)和歌集』という歌集にいれたほどである。
* 明石の浦 兵庫県明石市の南部の海岸。かつては白い砂浜と松の緑が美しかったが、いまは防潮堤や水族館などができて、昔の面影はうすれている。
「ありあけの月も明石の……」
「ありあけ」は、陰暦(いんれき、この頃、日本でつかわれていた、月のうごきをもとにした暦)の二十日すぎに、月が空にかかったままで夜が明けること。歌の意味は、「夜明けの月があかるい明石の浜辺には、潮風がふき、波がおだやかによせてくるのが見えるだけだ。」というもの |

かつての明石の浦
|
この頃になると、日本じゅうのほとんどの豪族たちは、なんらかの形で平氏か源氏と主従の関係を結ぶようになった。
そして、瀬戸内海を支配した平氏は西に、馬に強い源氏は関東に、その見えない勢力が大きくわかれていった。
それはもはや、政府の力ではどうすることもできないものになっていた。
国でつくった律令という法律や制度もまったく形だけのものになってしまった。
貴族の用心棒であった武士の力以外に、国の政治をうごかせる力は、もうなにもなくなっていたということである。
これからお話をする源頼朝という人は、そういう時代に、源氏のあととりとして生まれた人であった。
3 頼朝の誕生 top
源頼朝が生まれたのは、一一四七(久安三)年という年であった。
父は、武士のなかで最初に昇殿をゆるされた、あの八幡太郎義家から数えて四代めにあたる源氏の大将 源義朝であった。
母は熱田神宮の大宮司藤原季範(すえのり)のむすめであった。(いまも名古屋市熱田区にある熱田神宮である。)
この大宮司の家は上代からつづくという、古い家柄であった。
しかし、頼朝が、この大宮司の家で生まれたかどうかはわからない。
母親は「由良御前」(ゆらごぜん)とよばれていたというから、都にでて誰か貴族の屋敷にでもつかえていたのかもしれない。
父の義朝はその頃下野守という役人であったが、下野(しもつけ、栃木県)の国に赴任していたわけではない。
ほとんど都にとどまって、はやく高い位について平氏をおさえ、都の大大将(おおだいしょう)になろうとしていたのである。
そんな二人がむすばれて頼朝を生んだのだから、頼朝はあるいは京都で生まれたのかもしれない。
頼朝には、義平(よしひら)、朝長(ともなが)という兄があった。頼朝は義朝の三番めの子どもであった。
義門(よしかど)、希義(まれよし)、範頼(のりより)、そして今若(いまわか)、乙若(おとわか)、牛若(うしわか)と`、男だけでも九人の兄弟があった。 |

熱田神宮 三種の神器という、
天皇の位のしるしとして代々うけつがれる宝物のうち、
草薙剣(くさなぎのつるぎ)を一番の神とし、
天照大神(あまてらすおおみかみ)、
素戔嗚尊(すさのうのみこと)などを祀っている。
|
牛若というのは、後に源氏の九番めの男であるから「源九郎(げんくろう)義経」と名のった、あの義経(よしつね)である。
ただ、今若、乙若、牛若の三人をのぞいて、六人の兄弟はみな母親がちがっている。
それは、いまからはとても考えられないふしぎなことだが、当時はごくふつうにそういうことがあったらしい。
武士の家では、一人でも男子が多いということは、それだけ血のつながる武士がふえるということであったのだろう。
頼朝が生まれると、三男であるのに、源氏のあととりに代々つたえられるという「源田の産衣」(げんたのうぶぎぬ)というよろいと、「ひげ切りの太刀(たち)」という刀が頼朝にあたえられた。
それは、「おまえこそ源氏のあととりだぞ。」というしるしである。
それは、兄弟のなかで頼朝の母の血すじが一番よかったからだという。
* 「源太の産衣」 八幡太郎義家(よしいえ)が二歳のときにつくられたというよろい。源太は義家の子どものときの名。
* 「ひげ切りの太刀」義家が、前九年の役のときに、奥州(陸奥の国)の鍛冶屋につくらせた、大きな刀。千人の首と、そのあごひげまできつたといわれる。
4 保元(ほうげん)の乱
top
頼朝が十歳のとき、都でいくさがおこった。
武士の力がだんだん強くなってきたころ、都の貴族のあいだでは、内輪の争いがたえなかった。
都の貴族のなかで一番身分の高いのは藤原家だったが、その藤原家の本家に忠通(ただみち)、頼長(よりなが)という兄弟がいた。
* 忠通、頼長兄弟 藤原忠通(1097〜1164年)は、崇徳天皇のあとおしで、一一二九年に関白となった。23歳年下の頼長(1120〜1156年)は、1125年に兄忠通の養子となった。
その二人が内輪喧嘩をはじめた。同時に皇室のなかでも争いがおこった。
国の中心である皇室のなかで争いがおこることなど、いまからはとても考えられないことだが、それには深いわけがあった。
その頃、院政ということが行われていた。
元々は、藤原氏のいきおいが強くなって、摂政、関白などという高い位について、かってな政治をするようになったので、これをおさえようとした天皇が、その位を退いてからも、上皇(じょうこう)や法皇(ほうおう)というものになって、なお政治の実権をにぎるようになった。(法皇というのは僧侶になった上皇のことである。)
* 摂政、関白 摂政は、天皇が幼かったり、女性のときに、かわって政治をおこなう職。関白は、成人後の天皇のしごとをたすける職。平安時代以後、いずれも藤原氏がほとんどひとりじめした。
そのため、天皇が亡くならなくても、天皇の位をゆずるということが普通になった。
そして、上皇や法皇は天皇の上にたって、なお政治を行うようになった。
しかし、政治のしくみからいえば、中心はなんといっても天皇であるから、天皇からいろいろ命令がでることももちろんである。
こうなると、朝廷にもしぜんに二つの力ができてくる。
つぎの天皇をだれにするかということなどがもとになって、宮中でも内輪もめがはじまった。
この内輪もめが藤原家の内輪もめと一緒になって、大きな争いになっていった。
もうこうなると、勝ち負けをはっきりさせるほかはなくなった。
勝ち負けをきめるといっても、武力をもたない皇室や貴族のたよりは源氏や平氏の武士だった。
武力によって政治の決着をつけようというのである。
しかし、武力によって政治が左右されることになれば、たとえ自分の目的がなしとげられたとしても、そのあとがどういうことになるか、その頃の貴族たちは考えてもみなかったのだろうか。
いがみあう二つの力を大きくわけて、鳥羽(とば)法皇派と崇徳(すとく)上皇派とすると、鳥羽法皇は崇徳上皇の父親にあたる。
鳥羽派についた藤原忠通(ただみち)は、頼長(よりなが)の兄である。
同じく鳥羽派についた源氏の義朝は、崇徳派についた為義(ためよし)の子であり、為朝(ためとも)の兄である。
また、鳥羽派の平氏清盛(へいしきよもり)は、崇徳派についた平忠正(ただまさ)の甥(おい)であった。
* 平氏清盛 平清盛(1118〜1181年)のこと。前述の明石の浦の歌を詠んだ忠盛の長男。1153年に父忠盛が死んで、たくさんの遺産をもらい、平氏の大将となった。
皇室も、藤原家も、源氏も、平氏も、みな親子兄弟どうしの戦いだった。
一一五六(保元一)年七月、鳥羽法皇が亡くなると、崇徳上皇と法皇の対立は、崇徳上皇と後白河天皇との対立となった。
天皇は上皇の弟である。
そして鳥羽法皇の死がきっかけとなって、この戦いは京都の町の真ん中でおこった。
こんなみにくい戦争は、長い日本の歴史のうえでも、これが一度だけである。
戦いは長くはつづかなかったが、鳥羽法皇派(後白河天皇派)の勝利におわった。
政治のあらそいをこのように武力で解決したということは、武士が政治に勝ったということである。
もうこれからの世の中は、武力によってきまることになっていくのである。 |

鳥羽法皇(1103〜1156年)も
崇徳上皇(1119〜1164年)も、
五歳で天皇になっている。
1141年、鳥羽上皇が法皇に、
崇徳天皇が上皇になった。
|
これまで、貴族につかえ、貴族の用心棒としてつかわれていた武士が、日本の最高の政治を左右するまでにのしあがってきたということである。
保元一年という年におこった戦いなので、この戦いは「保元(ほうげん)の乱」とよばれている。
まだ十歳にしかならない源頼朝は、この戦いには参加しなかったが、長いあいだ日本を支配してきた貴族の力はだんだんおとろえて、世は武士の時代となっていくのである。
そして、その時代は、明治維新まで七百年以上もつづくのである。
top
**************************************** |