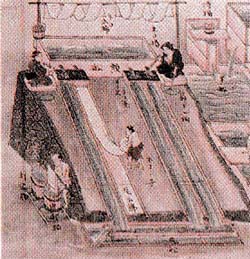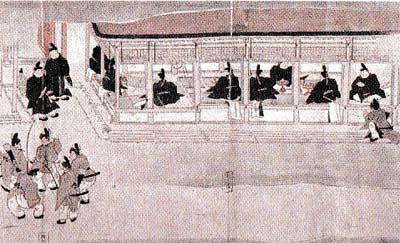|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 付録
六章 悲しい栄光
1 都を去る義経 top
鎌倉にいれられなかった義経を、ひそかに京都で待っていたのは、叔父の行家であった。
以仁王の令旨を持って諸国をまわった、あの行家である。頼朝が旗あげをしたときには、紀州や尾張、美濃で自分も平氏と戦った。
そして頼朝を頼って鎌倉にもいったが、頼朝は行家を御家人としてしか受入れなかった。
それで木曾義仲のところへいって、一緒に京都に攻めのぼったが、義仲が法皇にそむきはじめたので、しばらくゆくえをくらましていた。
そして、都に近い河内や和泉で、ひそかに武士をあつめ、ようすをうかがっていたのである。
行家(ゆきいえ)には、そもそも諸国の源氏をふるいたたせ、平氏をうちたおすことができたのは、自分が危険をおかしてよびかけたからだという気持ちがあった。
それなのに、甥である頼朝は、すべてを自分の手柄にしようとしている。
行家は、鎌倉からむなしく帰ってきた義経をたずねて、いうのだった。
「腰越での話は聞いている。頼朝のそなたへのしうち、とても許せるものではない。
都はみなそなたの味方だ。法皇も、公卿方も、そなたの帰りを待っておられる。」
行家のそんな言葉は、義経の心をうごかした。
しかし、義経と行家が都でひそかにあっていることは、すぐに鎌倉につたわった。
頼朝は義経を京都に追い返しておきながら、京都に帰った義経がどのような行動をとるか、ずっと見守っていたのである。
京都には、頼朝のはなったスパイがいっぱいいる。
朝廷のうごきでもなんでも、都のできごとは鎌倉につつぬけであった。
義経が行家とくんで鎌倉にそむこうとしていることがわかると、頼朝は梶原景季
*
を京都につかわし、義経に、行家を討てと命じた。
義経が行家を討つようなことはしないだろうと、頼朝にはわかっていての命令であった。
義経は使者の景季にあうことを断った。景季が鎌倉に帰っ
て、このことを報告すると、頼朝は今度は土佐房(とさのぼう)昌俊(しょうしゅん)という者に、八十人ばかりの家来をつけて京都にむかわせた。
昌俊はもと頼朝の父義朝につかえる武士だったが、義朝が死んだとき出家して僧になった。
その後も頼朝につかえ、頼朝から信頼されている家人の一人であった。昌俊は京都の町をよく知っている。
昌俊のうけた命令は、はっきりと、義経を暗殺せよということであった。
昌俊(しょうしゅん)の一行は、熊野の神社に参詣するというふれこみで、義経の住んでいる六条室町
* の館のすぐそばにとまった。
* 六条室町 平安京の六条大路と室町小路がまじわるあたりで、いまの東本願寺の近くにあたる。 |
梶原景季(かじわらかげすえ)
1162〜1200年。梶原景時の長男。
若いときから弓がうまく、頼朝の寝室をまもる役についた。木曾義仲を追討する宇治川の合戦で、佐々木高綱と先陣をあらそった話は有名。

宇治川の先陣争い(『平家物語絵巻』) |
そして、義経の動向をさぐってから、夜討ちをかけた。
しかし、義経もこのあやしげな一行に用心していたので、ひそかに待ちかまえていて、逆に昌俊たちをうちやぶった。
昌俊は鞍馬山ににげたがつかまって、翌日六条河原できられた。
しかし頼朝は、弟である義経をどうしてこんなにまでして、追いつめなければならないのだろうか。
義経が壇ノ浦に平氏をほろぼしてからというもの、頼朝は義経をおこらせ、自分にそむかせようそむかせようとしているとしか思えない。
頼朝は義経を利用して、後白河法皇の出方を待っていたのである。
日本じゅうを支配する鎌倉政権を樹立するという大きな目的のためには、弟一人の命など、どうでもよかったのである。
しかも頼朝は、直接法皇を攻めようとはけっしてしなかった。朝廷にそむくことは、国賊になることである。
あくまでも、朝廷の命令によって国を支配することを考えていた。
一方、法皇もまた、頼朝に輪をかけた陰謀家であった。
義仲が都に攻めのぼったとき、同じ源氏の一族である頼朝に義仲を討たせたように、ひそかに義経、行家たちを頼朝と対立させることによって、鎌倉の力をおさえることを考えていた。
ちょうどそこへ、義経がとびこんできたのである。
「このままでは、頼朝に殺される。朝廷に願い出て、頼朝追討の宣旨をいただこうではないか。」
行家もまた義経をけしかけた。
土佐房昌俊におそわれた翌日、義経は意劃床凵で、法皇に頼朝追討の宣旨を願い出た。
一一八五(文治一)年十月十八日、義経と行家に頼朝追討の宣旨がくだされた。
義経と行家は宣旨をもらうとすぐに、都に近い国々に使いを走らせて兵をつのった。
ところが、それにこたえて集まる武士は、ごくわずかしかなかった。とても鎌倉の軍と戦える兵力ではなかった。
一方、頼朝追討の宣旨のことは、はやくも五日後の十月二十三日に鎌倉につたわった。
頼朝は、鎌倉にいる御家人のすべてをひきつれて、みずからも出陣することをきめ、同時に東海、東山、北陸道の武士たちにも、出陣を命じた。
二十五日にまず先発隊を京都にむかわせ、二十九日には頼朝みずから土肥実平(どひさねひら)、千葉介常胤(ちばのしけつねだね)以下の大軍をひきいて鎌倉を出発し、十一月一日には駿河の黄瀬川まですすんだ。ここに一時とどまって、京都からの情報を待つことにした。
頼朝が大軍をひきいて都に攻めのぼるという情報がつたわると、京都は上へ下への大さわぎとなった。町の人々も荷物を持って逃げ出した。
一番あわてたのは、法皇であった。頼朝追討の宣旨をだしてしまったことを後悔したが、どうすることもできない。
しかし義経は、いますぐ頼朝と決戦しようとは思わなかった。
いったん西国にのがれて力をためるしかないと考え、法皇に、
「義経を九州の地頭に、行家を四国の地頭に任じていただきたい。」と申し出た。
法皇は、すぐにこれをゆるした。義経たちが京都にいるかぎり、都は戦場になってしまう。
義経たちが西国へのがれてくれることは、ありかたかったにちがいない。
そのかわり、義経が都を去ると、もうだれも都をまもる者はいない。頼朝のいいなりになるしかないのである。
十一月三日、義経と行家は、わずか二百騎の兵をつれてしずかに京都をはなれた。朝廷の公卿たちも、ひとまずほっとした。
義経の一行は大物の浦から四国、九州にわたろうとして船にのったが、突然の暴風雨のために船が転覆し、かろうじて岸に流れついたが、ここで部下のほとんどは望みを失って、義経のもとから去ってしまった。
義経は和泉の浦に流れついたが、その時そばにいたのは、伊豆有綱(いずありつな)、堀弥太郎(ほりやたろう)、武蔵坊弁慶(むさしぼうべんけい)、そして義経をしたう静御前(しずかごぜん)のたった四人だけだった。
主従五人は、そこから大和の吉野のほうにのがれて消息をたった。 |
大物(だいもつ)の浦
大物は、いまの兵庫県尼崎市。
このころ以後、京都と瀬戸内海を最短距離でむすぶ港として栄えるが、大阪が発展するとおとろえた。
いまはたくさんの工場があつまる工業地域。浦は海岸や小さな湾(入江)のこと。

いまの尼崎市
|
武蔵坊弁慶(むさしぼうべんけい)
?〜1189年。子どものころ鬼若といい、僧となるために比叡山にはいったが、もっぱら武術の稽古ばかりしていたという。
義経の最期のときには、弁慶は全身に失を射られながら、立ったままいきたえたという。

歌舞伎「勧進帳」の弁慶 |
2 「守護」(しゅご)と「地頭」(じとう)
top
義経らが京都をはなれると、いれかわるように、十一月五日、鎌倉の先発隊がはいってきた。
つづいて北条時政が一千騎の兵をともなって京都にはいった。
頼朝は、義経、行家が京都をはなれたことを知ると、黄瀬川から鎌倉にひきあげた。
京都は完全に頼朝軍によって占領されてしまった。法皇をまもる武士はもうだれもいない。
法皇は、あわてて頼朝のところへ使者をおくって、
「義経、行家にくだした宣旨は、けっして法皇の本心ではなく、義経らに劃要されたの窓やむなくくだしたものである。
まことに義経、行家という人間は、まるで人をまどわし、仏の道にさからう、天狗のような男たちである。」
とつたえた。
同時に、義経にあたえた官職をみなとりあげたうえ、「義経、行家を追討せよ。」という宣旨をくだした。
「昨日は、義経に頼朝を討て。今日は、その頼朝に義経を討てとは、いったい朝廷はなにをしているのだ。」
公卿たちも、町の人々も、法皇の無節操ぶりをなげくのだった。頼朝におくった使者の返事には、
「義経、行家のことを天狗とおおせですが、日本第一の大天狗が、どこかにおいでになるのではありませぬか……。」
としるして、頼朝はきびしく法皇をせめた。
一千騎の兵とともに、頼朝の代官として京都にはいった北条時政は、次々と頼朝の要求を法皇につきつけた。
法皇は、頼朝追討の宣旨をくだしてしまった大きな弱みをにぎられているうえに、たのみとする武力がなにひとつなかったので、頼朝の要求は、すべてのまずにはいられなかった。
頼朝がまず要求したのは、朝廷のなかで、頼朝に反対する公卿たちを、すべて解任することであった。
そうして朝廷が頼朝の思うとおりになるようにしてから、ゆくえがわからなくなった義経、行家をさがしだすことを名目に、日本全国に「守護」と「地頭」をおくことを認めさせた。
守護(しゅご)というのは、はじめは総追捕使(そうついぶし)とよばれた一種の地方長官で、鎌倉に謀反をおこす者や殺人犯をとりしまり、また、京都の警護にあたる大番役を監督する役人である。
地頭(じとう)は、国ごとにおかれ、国内の税をとりたて、土地を管理し、警察権ももつ役人である。
いったん戦いになると、守護は武士を動員する軍司令官になるし、地頭は兵糧米をとりたてる強い権限をもつことになる。
頼朝は信頼のおける有力な御家人を守護、地頭の役に任命した。
全国に守護、地頭をおくということは、つまり全国の軍事、警察、徴税、国土管理という、国の政府が行うべき仕事が、すべて鎌倉にまかされたということである。
伊豆に流された罪人であった頼朝は、旗あげから五年間で、実質的に全国を支配する大将になったのである。
のちに幕府とよばれるようになる、頼朝による鎌倉の政権は、実際には、この時にできあがっていた。
3 静の舞 top
義経たちを捕えるために総追捕使(守護)が設置されたけれども、大和の吉野方面に姿を消したままの義経のゆくえは、いぜん不明のままだった。
年があけて一一八六(文治二)年の三月になって、義経につきしたがっていた静御前(しずかごぜん)が捕えられた。
静はすぐに京都におくられ、北条時政のきびしい尋問をうけたが、吉野の山でわかれた義経は、山伏姿で大峰山のほうにむかったこと以外、なにもわからなかった。
静自身にもわからないことだった。捕えられた静は、やがて鎌倉におくられた。
静(しず)は京都では有名な白拍子(しらびょうし)とよばれる舞姫だった。
吉野で義経とわかれたときは、まだ雪がふっていたが、鎌倉はもうさくらのさかりだった。
花を見るにつけても、静は義経のことが思いだされて悲しかった。 |
大峰山
奈良県南部にある山。長い年月にわたって、雨水などでけずられた絶壁が多く、「油こぼし」「ありのとわかり」などと名づけられた難所がある。
修験道の道場で、女性ははいることができなかったが、いまは一部にはいれるようになった。

山上の修験者 吉野山から大峰山をのぞむ |
そんな静に、頼朝は、鶴岡八幡宮で舞をまってみよと命じた。
頼朝も、うわさに聞く静の舞を一度見たいものだと思っていたのだ。
しかし静は、夫を捕えようとしている頼朝の前で舞などまいたくなかったので、断った。
けれども静をあわれむ人たちは、頼朝の機嫌をそこねることをおそれて静にいうのだった。
「そなたの舞が、鎌倉どののお気にめしたら、義経どのもゆるされるかもしれないのですぞ。」
「とののためなら……。」
静はそう思って、舞うことにした。
八幡宮の舞殿には、頼朝や妻の政子をはじめ、御家人たちがずらりとならんでいた。
つづみは工藤祐経 * (すねつね)が、銅拍子は畠山重忠(しげただ)がつとめた。 |
舞殿 器楽の合奏にあわせて、舞をまつたりするための舞台になる建物。

鶴岡八幡宮のいまの舞殿 |
つづみ 木製の胴の両はしに革をはり、手で打って音をだす、日本の楽器

つづみの練習 |
* 工藤祐経(すけつね)?〜1193年。はじめは平重盛につかえでいた。京都にいる間に、伊東祐親に伊東(いまの静岡県伊東市のあたり)の領地をうばわれたため、おこつた祐経は、祐親にきずをおわせ、子の祐泰をきりころした。
吉野山 みねの白雪ふみかけて
いりにし人の あとぞ恋しき
しずやしず しずのおだまき くりかえし
昔をいまに なすよしもがな |
静の姿の美しさと、その舞の美しさに、みなうっとりして、舞がおわっても、あたりはしずまりかえっていた。
ところがその時、頼朝はっと立ちあがると、いまにも静につかみかかろうとするようないきおいで、
「いまなんとうたった。この頼朝の前でむばん人九郎をしたう歌をうたうとは……。」
とおこった。
もしこの時、妻の政子が、「との……。」といって、頼朝をとめなかったら、頼朝は本当にその場で静をきってしまいそうな剣幕であった。
「おしずまりください。静が九郎どのをしたうのは、まことの女の姿でございます。 私はいま、殿が石橋山に兵をあげられた日のことを思いだしておりました。
伊豆山権現に隠れて、どれほど殿のことを思いつづけて、殿のたよりをお待ちしたことでしょう。
静とて、同じでございましょう。ゆくえのわからぬ夫をしたってこそ、女というものでございます。
静の舞は、その悲しみを心のうちに深くひめた女の美しさをまったものではございませぬか。おほめになってこそ、鎌倉殿らしゅうございます。」 |
これを聞いて、頼朝もようやくいかりをおさめたようであった。
静はこの時、義経の子供をみごもっていた。
しかし、やがて生まれたその子が男子であったので、頼朝の命令で殺された。
静はゆるされて京都に帰ると尼になったが、その翌年、とうとう義経に二度とあえずに亡くなった。 |
吉野山 みねの白雪……
吉野山のみねにふりつもった雪を足でかき杓けるようにして、山奥へはいっていった人(義経)のことが、とても恋しい。靜は、むかしをいまにすることができればなあと、くりかえし思っております、というような意味。
「しずのおだまき」のしずは、青や赤などのしまを織りだした布。
静の意味もふくめている。
おだまきは、しず用麻糸を、中をからにして、球になるようにまいたもの。
 |
4 義経の最期 top
多武峰(とうのみね)
奈良県桜井市の南部の丘陵地帯。
標高六百十九メートルの破裂山に、十三重の塔で有名な、藤原鎌足をまつる談山神社がある。ここは、さくらともみじの名所でもある。
 |
法隆寺
奈良県斑鳩町にある、聖徳太子が建立したとつたえられる寺。現在のこつている木造建築では、世界最古のものといわれる。
 |
平泉
岩手県の南西部。藤原氏の栄えたあとをいまにのこす、中尊寺や毛越寺(もうつじ)などがある。
芭蕉は毛越寺で、「夏草やつわものどもが(兵士たちの)夢の跡」の句をよんだ。
 |
一一八六(文治二)年五月、行家は和泉の国のかくれ家を発見され、捕えられてきられた。
しかし、義経のゆくえは、依然つかめなかった。
吉野から多武峰(とうのみね、奈良県桜井市)にはいったといううわさが流れたかと思うと、京都にいるといううわさが流れたり、奈良の法隆寺や京都の仁和寺にいるというので、北条時政の軍が捜査したが、むだだった。
比叡山の延暦寺、奈良の興福寺などにかくまわれているらしいということがわかったこともあるが、そうした大きな寺には、たくさんの僧兵がまもりをかためていて、直接ふみこんで捜査することはできなかった。
いったん朝廷にもうしいれ、許可をとってからでなければ捜査ができなかった。
そんな手つづきをとっている間に、義経はいちはやく姿をくらますのである。
こうしてにげかくれできるということは、それだけ義経をたすけ保護する者がいるということである。
そのうちに、法皇の御所や、頼朝に反感をもっている公卿の屋敷にもかくまわれているらしいということがわかった。
この年の十一月、頼朝はついに法皇に使いをだした。
「都には、義経に同情してかくまう者がいるらしく、これまでのような手ぬるい捜査では、とても捕えることができないので、二万か三万の兵を動員して、寺も屋敷もすみずみまで捜索させるつもりである。
そうなれば、思わぬいくさもおこりかねない。
そのまえに、朝廷のほうで、義経をめしとる方法でもあれば、うけたまわりたい。」
これは、朝廷にかかわる者が義経をかくまったり、にげるのを助けたりしていることがわかったうえで、法皇におどしをかけたのである。
ここまで追いこまれると、いくら同情者がいても、義経はもはや都の近くにひそむことはできなくなった。
義経が奥州平泉(ひらいずみ)の藤原秀衡(ひでひら)の元にいるらしいということがわかったのは、一一八七(文治三)年二月の頃だった。
「やはり、そうであったか。」と、頼朝は喜んだ。予想していたことが的中したからではない。
頼朝の支配がおよばないところは、奥州だけだった。いつかは、奥州の藤原氏を討たなければならないのだった。
しかし、これまでその機会がなかったのだ。
機会がなかったどころではない。義仲を討つときも、平氏を討つときも、そして、義経と行家が京都で兵をあげたときにも、もしや背後から鎌倉を攻められないかと、奥州の藤原氏のことを心配していたのであった。
頼朝がこれまでほとんど鎌倉をはなれなかった理由の一つも、奥州のことが気になってしかたがなかったからである。
藤原秀衡(ひでひら)は、源氏と平氏が戦いをくりかえしているあいだも、じっと奥州で、どちらに味方するでもなく見守っていた、不気味な存在であった。
奥州には、砂金 * と馬とうるし *
が豊富にあった。いずれも、いくさに必要なものである。
それを都にはこんで売っては、力と富をたくわえていた。
都の人々は、秀衡のことをいつしか「北の王者」といっておそれていた。
そこへ義経がにげこんだのは、頼朝にとって、とても都合のよいことだった。
奥州に兵をすすめる絶好の口実ができたのである。
しかし用心ぶかい頼朝は、すぐに軍勢をむけるようなことはしなかった。
まず義経が本当に平泉にいるかどうかを確かめるために、使いをだした。 |
* 砂金
金がふくまれた岩石が、雨風の力などによって、こまかくくだけ、川の底などにつもったもの。
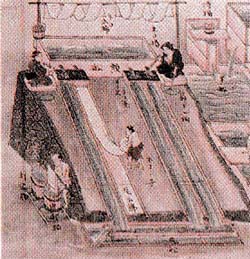
砂金から金を選別するようす |
* うるし うるしの木の樹液からつくった塗料。
木製のはこやおわんなど、さまざまなものに、中国や日本で古くからつかわれている。

うるしをぬった箱 |
平泉の中尊寺の金色堂
中尊寺は、平泉にある天台宗の東北地方の大本山。
一一〇五年に藤原清衡によって建立され、栄えた。
しかし、藤原氏の滅亡でおとろえて、いまは清衡・基衡・秀衡の藤原氏三代の霊をまつる、
うすい金をはりめぐらした金色堂などがのこっているだけである。

金色堂
その使いというのも、義経のことにはすこしもふれず、奈良東大寺の大仏を修理したいので、砂金三万両をおさめてもらえないかという手紙を持たせ、秀衡の鎌倉にたいする気持をさぐった。
秀衡は、これを断った。
使いの者は、おとなしく鎌倉に帰ってきたが、義経が立派な館に住み、かなり大勢の家来にとりかこまれているようすを、ちゃんとさぐりだして頼朝に報告した。
頼朝は、義経が平泉にいることを確かめると、また使いをだしていった。 |
 |
「弟の九郎が、朝廷のおたずね者になって、ゆくえをくらましている。昔、そちらにお世話になっていたので、あるいはまた、そなたを頼って、そちらに隠れているのではないかと思う。 もしそうだったら、すぐ鎌倉におくりかえしてほしい。」
秀衡はこの手紙を読むと、負けずに返事を書いた。
「もし、そのような者が領内に現れたら、すぐに捕えてさしだそう。」
秀衡はこんな返事をしておいて、いくさの準備をすすめているようすであった。
「平泉には、続々と兵や馬が集められて、町全体がなにやらさわがしゅうございました。
それに、桜川(北上川)のほとりには、いつでも船で軍勢をうごかせるように、しきりに船着き場をつくり、近くに倉のようなものも建築中でした。」
使いの者は、見てきたことを報告した。
ここまで確かめておいて、頼朝は法皇に奥州討伐の宣旨を願い出た。
ところがその頃、秀衡はきゅうにおもい病気にかかっていた。
秀衡には、国衡(くにひら)、泰衡(やすひら)、忠衡(ただひら)、高衡(たかひら)、通衡(みちひら)、頼衡(よりひら)という六人の息子があった。
秀衡は、息子たちをまくらもとによびよせて、いったという。
「わしが死んだら、鎌倉からおまえたちのところに、これまでよりきびしく九郎どのをさしだせといってくるにちがいない。
その時には、もう返事をすることはない。かたっぱしからきってすてるのだ。
あるいはすぐに、軍勢をむけてくるかもしれぬ。その時は、九郎どのを大将にして、兄弟力をあわせて戦うのだ。
けっしてやぶれることはない。」
秀衡のなきがらは、中尊寺の金色堂におさめられた。遺言にしたがって、泰衡(やすひら)があとをついだ。
それからしばらくは何事もなく、兄弟たちは、秀衡の遺言をまもって義経を中心にまもりをかためているかにみえた。
ところが、秀衡の死が鎌倉につたわると、頼朝はきびしく泰衡を問いつめた。
頼朝のだす使者は、すべて朝廷をとおして、法皇の宣旨としておくられていた。
「なぜ、義経をいつまでもかくまっておくのだ。義経の首を鎌倉におくれば、泰衡には常陸の国をあたえる。
もし、なお朝廷の命にそむくならば、ただちに官軍をさしつかわす。」
朝廷の命令によってうごくことになれば、頼朝の軍隊はもうすべて官軍である。
頼朝は、まず泰衡と義経の間をさくことを考えたのであった。すると泰衡から返事がきた。
「義経は、父がひそかにかくまっておりましたので、自分はすこしも知りませんでした。最近そのことがわかったので、討ちとるつもりです。」
これは、義経にはもちろん、兄弟たちにも内密の返事であった。
泰衡はまず、兄弟のなかで義経と仲のよい弟の忠衡(ただひら)と頼衡(よりひら)を不意におそって殺してから、五百騎ばかりの兵で、義経の住む衣川
* (ころもがわ)の館も不意におそった。
義経は、わずかな家来とともに戦ったが、勝ちめのないことをさとると、持仏堂
* にはいって自決した。
* 持仏堂 信仰する仏像や位牌(祖先にたいし死んだあとであたえられた名前を書いた札)をおさめておく建物。
この時義経は、三十一歳だった。
義経の首は、泰衡の弟高衡(たかひら)のひきいる二十騎ばかりの兵にまもられて鎌倉にとどけられた。
鎌倉の人々は、そのさびしい行列が、義経の首をはこぶ行列であることを知ると、みな涙をながしてむかえたという。 |
* 衣川 岩手県南西部からながれだし、中尊寺の近くで北上川と合流する川、またその流域あたりの地名。
前九年の役、後三年の役は、このあたりで戦われた。

北上川にながれこむ衣川 |
5 奥州征伐 top
平泉では、泰衡が高衡の帰りを待っていた。常陸の国をあたえるという、頼朝からの知らせをもって帰るはずである。
ところが頼朝は、泰衡をほめるどころか、義経を長い間かくまっていた罪人であるときめつけた。
頼朝にとって、いまとなっては、もう義経はどうでもよかった。
奥州に長い間勢力をもっていた藤原一族をほろぼし、天下を自分の支配下におさめることしか考えていなかった。
高衡がもち帰った返事は、頼朝みずから大軍をひきいて、奥州征伐にむかうというものだった。
泰衡は、あわてて鎌倉に手紙をおくった。
「私は鎌倉どののおおせにしたがって、九郎どのを討ちとったのです。それを、いまとなって罪人とは……。
なにゆえ奥州に軍勢をむけられるのでありましょうか。」
頼朝はもちろん、そんな泰衡のなきごとには耳をかさなかった。
鎌倉には、ぞくぞくと武士が集まっていた。それは関東の武士ばかりでなく、京都に近い国々や西国からかけつける武士もいた。
頼朝は、自分の支配する全国によびかけて、奥州征伐の軍勢をそろえようとしていた。
しかも、かつてほとんど陣頭に立って指揮をしなかった頼朝が、今度はみずから出陣し指揮をとるというのである。
頼朝にしてみれば、全国支配という鎌倉政権の総しあげを、みずからの手でなしとげたかったのだろう。
頼朝は、義経の死を確認すると、すぐ法皇に泰衡追討の宣旨を要求していた。
ところが、法皇は、
「義経がいなくなった以上、平泉をなぜ征伐しなければならないのだ。一体なんのための宣旨なのか。」
と、なかなか宣旨をくださなかった。
しかし頼朝は、いまさら計画を中止するつもりは毛頭なかった。
「いったい法皇は、なにをぐずぐずしておられるのだ。」
頼朝は思わず御家人に不満をもらした。すると、大庭景能という義朝以来の御家人が。
「いくさのさいちゅうには、将軍の命令があればよいのであって、いちいち天子のご命令をきくものではありませぬ。
朝廷へは、すでに征伐のことは通告してあるので、その許可を必要とはいたしませぬ。」
と、きっぱりといいきった。
頼朝はそれにしたがって、七月十九日、二十八万四千という大軍を三手にわけて、鎌倉を出発した。頼朝は中央軍を指揮し、北上した。
泰衡は、頼朝がつくよりさきに、平泉に火をはなって逃げ出したが、家来に殺されて、あわれな最期をとげた。
頼朝が平泉についたときは、北の王者といわれた藤原四代の黄金の都はすでに灰になっていた。
6 大姫(おおひめ)の悲しみと頼朝の死
top
奥州を平定して、頼朝の支配がほぼ全国におよぶようになったとき、頼朝ははじめて都にのぼる決心をした。
伊豆に旗あげをしてから、ちょうど十年の歳月がたっていた。
一一九〇(建久一)年十月三日、頼朝はよりすぐりの千騎の武士を従えて鎌倉を出発し、途中、尾張の野間の荘(のまのしょう)で父義朝の墓にまいり、また母の出身地である熱田神宮にもゆっくりと参詣して、十一月七日京都にはいった。
十四歳のとき、池禅尼に助けられ、さびしく都をあとにしてから三十年、頼朝は一度も都の上をふんでいなかった。どれほど感慨ぶかいことだったろう。
頼朝は、立烏帽子(たちえぼし)に濃紺の水干(すいかん)ばかまという正装で、うるしのように黒い馬にまたがり、前後に千騎の武士を従えて、堂々と都にはいった。
はじめて目の前にする頼朝を、都の人々はなかばおそれ、なかばめずらしがって見物したという。
頼朝は三十日あまり京都に滞在し、これまで使者をとおしてのやりとりしかしていなかった法皇や貴族たちともはじめてあった。 |
尾張野間 いまの愛知県知多半島の美浜町の西側。古くから漁業がさかん。
江戸時代には、大型の荷船のつく港として栄えた。義朝の墓は大御堂(おおみどう)寺にある。
長田忠致にころされたとき、「せめて木の太刀でもあつたなら。」とくやんだといわれることから、
墓にはたくさんの木太刀がそなえられる。

大御堂(おおみどう)寺 |
かつて頼朝が「日本第一の大天狗」とののしった法皇とは、二人きりの長い会談があった。
そこでどんな話合いがあったのかは知ることができないが、法皇は、頼朝に権大納言、右近衛大将(うこんえのたいしょう)という官職をあたえた。
右近衛大将というのは、朝廷につかえる武士にとっては、最高の職であった。頼朝はいったんそれを拝命したが、十二月にはこの二つの職を辞任してしまった。
自分はただ朝廷につかえる侍大将ではなく、全国を支配する武士の総大将であることを、法皇に、そして天下に知らせるためだったにちがいない。
このことから察しても、法皇と頼朝の会談では、かなりきびしいやりとりや、かけひきがあったにちがいない。
頼朝はかねてから、武士の総大将にふさわしい「征夷(せいい)大将軍」に任じられることをのぞんでいたのだが、この時、その職はついにあたえられなかった。
頼朝が征夷大将軍に任じられたのは、法皇が亡くなって四か月後の一一九二(建久三)年七月のことだった。
そうしてようやく頼朝は、名実ともに武士の総大将になることができた。 |
権大納言、右近衛大将
権は、定員のほかに、特別に仮に任命したことをしめず語。
大納言は、左大臣、右大臣につぐ役職。両大臣と相談して政治の仕事をし、天皇に考えをのべたり、天皇の言葉をほかの人々につたえたりする。
右近衛大将は、右近衛府という、朝廷のまもりや行事を
仕事にする役所の長官。従三位にあたる。
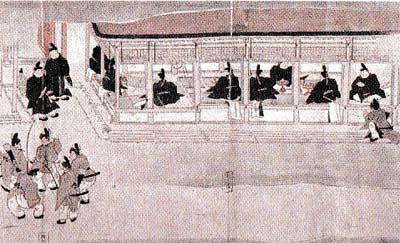
朝廷の行事における右近衛府(うこんえふ)の役人 |
一一九五(建久六)年二月、頼朝は再び都にのぼった。
今度は妻の政子、長男の頼家、長女の大姫ら、家族そろっての上京であった。
その目的は、奈良東大寺の再建供養に参列することと、京都、奈良、摂津の寺や神社に参詣することであった。
この旅は、一見だれの目にも、功なり名をとげた人間のたのしい家族旅行であるかにみえただろう。
しかし、家族の幸、不幸というものは、外の者にはわからない。征夷大将軍ともなった頼朝夫婦にも、他人にはさらすことのできないふかい悩みがあった。
それは、長女大姫のことであった。
木曾義仲が旗あげをしたさい、人質としてその子義高を鎌倉におくり、義仲が都にのぼって義経・範頼の軍と戦ってやぶれたとき、人質の義高が、頼朝の命によってきられたことはすでにのべた。
しかし、そのようすを、ここでもうすこしくわしくのべなければならない。
それは一一八四(元暦一)年の春のことだった。
まだ十一歳の義高がきられるらしいとわかったとき、義高のせわをしていた下女が、それを聞いて、あまりのあわれさに、そのことをそっと義高に告げた。
そして女の姿をさせ、音がしないようにひづめを綿でつつんだ馬を用意して、
「いっときもはやく鎌倉をでて、すこしでも遠くへ、おにげになるのですよ。」
といいふくめて、夜明けまえに義高をにがしたのだった。
義高がいないことに頼朝が気づいたのは、その日の夜になってからのことだった。
頼朝はすぐに家来をよびあつめ、義高のゆくえをさがさせた。
すると、五日めに、武蔵の国の入間川のほとりでみつかった。
みつけた家来は、頼朝の命令にしたがって、その場で義高を殺した。
十一歳の義高は、たった一人でどこをめざしてにげようとしていたのだろう。
義高が殺されたことは、大姫には秘密にされていたのだが、毎日のように一緒にあそんでいた大姫に、かくしとおすことはできなかった。
義高の死を知った大姫は、悲しみのあまり水ものまなくなった。大姫はその時まだ七つだった。
幼かっただけに、その心の傷は深く、大きかったのかもしれない。
二か月たち、三か月たっても、義高のことを思いだすと、突然、 「義高さま、義高さま、私の義高さまはどこにいるの……。」
といって、屋敷の中をなきながらかけまわるのだった。 |
入間川 秩父山地からながれだして、埼玉県を東にむかい、荒川に合流する川。
鎌倉街道の道すじにあたる。
江戸時代のころは、江戸の市中まで通じる、大事な船の交通路だった。
 |
父親の頼朝にとって、そんな声を耳にすることは、まことに苦しいことだった。
頼朝は義高の追善供養をしたり、みずからも読経し、また各地の寺院へ祈願したり、大姫の心をなぐさめるために、あらゆる手段をつくした。
しかし、大姫の心はいやされなかった。いやされるどころか、幼い日の悲しい別離の思い出は、大姫の一生を病気の日々にしてしまった。
十年たったのちも、大姫の心のなかから、義高の面影をぬぐいさることはできなかった。
一一九四(建久五)年、頼朝が二度めの上京をするまえの年のことである。このころ、ようやく大姫の病気は快方にむかったように思われた。
ちょうどその頃、頼朝の妹むこで、京都守護職についていた一条能保
* (よしやす)の子の高能(たかよし)という青年が、鎌倉にやってきた。年は十九歳の貴族である。大姫も十七になっていた。
* 一条能保 1147〜1197年。藤原一族だが、京都の一条に住んだので一条と名のる。妻は、源義朝のむすめで、後鳥羽天皇の乳母をつとめた。
京都守護職には、一一八六年に北条時政にかわってついた。
結婚させれば大姫の心機一転もはかれるかと考えた頼朝と政子は、高能との結婚話をすすめようとした。
すると大姫は、一言にのもとにこれを断った。
「私の夫は、義高さま以外にはありません。どうしても再婚しろとおおせでしたら、私は深いふちに身をなげて死んでしまいます。」 大姫は、そういってきかないのである。
頼朝も、そして政子もこれにはほとほと困ってしまった。
そんなとき、思いがけない話が京都からまいこんだ。
「大姫さまを、後鳥羽天皇のお后(きさき)になされてはいかがでしょう。」というのである。
それは、朝廷につかえる貴族から人をとおして、間接にもたらされた話だった。
後鳥羽天皇も、この時十五歳だった。年からいっても、不釣合ではない。
それに、天下を支配する大将軍のむすめが天皇の后になる……。
頼朝には、それはまことにふさわしいことに思えた。
「天皇なら、大姫もまさか嫌とはいうまい。」
頼朝の言葉に、政子も賛成した。
「大姫が后(きさき)になる。そして皇子を産み、その皇子がやがて天皇の位につく。
そうすれば、朝廷にどれほど大きな勢力をもつことができるだろう。」
頼朝の希望は、かぎりなくひろがった。そして、家族そろっての京都への旅になったのであった。
しかし、これはかつて平清盛がしてきたことと、全くかわりがないことである。しかも、この話には、落し穴があった。
後白河法皇が亡くなってからの朝廷では、貴族たちの間ではげしい勢力あらそいがつづいていた。
頼朝の力を利用して有利に立とうとする貴族もいれば、頼朝の力をおさえて、朝廷のなかで自分の力を強めようとする者もいた。
その泥沼のような朝廷の権力あらそいのなかに、頼朝はみずからふみこんでいくことになってしまった。
今をときめく征夷大将軍のたった一つの泣き所をつかんで、朝廷から頼朝の力を除こうとする者のしくんだわなであった。
大姫のことを成功させるかにみせかけて、頼朝から引出せるもの(朝廷にたいする頼朝の譲歩)を引出していたのである。
頼朝一家は、京都に四か月近くも滞在して、むなしく鎌倉に帰った。
頼朝は、なおも大姫を天皇の后(きさき)にすることをあきらめなかったが、大姫は再び病気がおもくなって一一九七(建久八)年七月、二十歳で死んだ。
その頃になって、ようやく頼朝は、朝廷のようすがすっかり鎌倉幕府にとって不利な様相になってきたことに気づいた。
そして、大軍をひきいて、もう一度都にのぼることをひそかに計画していたが、一一九八(建久九)年十二月二十七日、まるで何者かにのろわれたかのように落馬して、それがもとで、翌正月十三日に亡くなった。
五十三歳であった。
頼朝の死は、あまりにもあっけなかったが、頼朝のなしとげた仕事は、日本の歴史に大きく残された。
頼朝がなしとげた仕事とは、一体なんだったのだろう。
はじめて、富士川に平氏の大軍と戦ってそれをやぶったとき、頼朝はそのまま都にまで攻めのぼるつもりであったが、御家人たちにとめられて断念した。
この時はまだ、関東の武士たちが自分になにをもとめているのか、頼朝にはよくわかっていなかった。
関東の武士がもとめていたのは、都にのぼることではなかった。
自分たちの土地をまもってほしいということであった。
武士たちはみな、農民を使い、何代もかかって荘園を開拓してきた地主だった。
そのことに気がついたとき、頼朝は武士たちの願いを一つにまとめ、鎌倉に武士たちの力を集結する仕事にとりかかった。
それは、貴族の用心棒でしかなかった武士たちの地位を高め、武士たちによる、武士たちのための、武士たちの政府をつくることであった。
様々な立場にあり、様々な希望をもった武士たちの力を一つにまとめるということは、それはむずかしい仕事であった。
そこには、かならずは乱す力もあり、邪魔をする力もでてくる。
頼朝はそれらの力を、用心ぶかく、事前につみとらなければならなかった。
頼朝が、弟や多くの御家人を次々に殺さなければならなかったのは、そのためだった。
まだ十一歳の木曾義仲の子義高を殺し、生まれたばかりの静御前の赤ん坊ですら、男であったばかりに殺されなければならなかったのだ。
こうして多くの犠牲をはらいながらも、十年の歳月をかけてきずきあげたのが、武士による独自の政府、つまり鎌倉幕府であった。
(おわり) top
****************************************
|