|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章
五 新しい国
1 肩すかし top
|
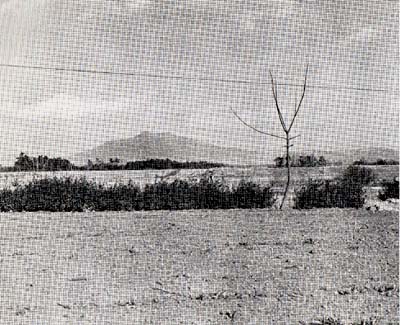
筑波山をはるかにのぞむ。
|
 |
ふた月ほどたって、将門はついに“とむらい合戦”のいくさをあげました。
下総の領内の百姓たちすべてが、鍬(くわ)をすてて刀をとったのです。
田畑をあらされ、肉親をころされた農民は、将門の気持ちと同じでした。
「常陸の良兼(よしかね)は畜生だ! きゃつを生かしておいては眠ることもできない………。」
「そうだ。こうなりゃ命のとりかえっこだわ。将門のとののあとにつづこう!」
東の君の父、平真樹(たいらのまたて)もまた、老いの身をひっさげてかけつけました。
娘と孫のあだを討とうというのです。
十月九日、あかつきとともに、将門と真樹の軍勢千八百余人が良兼のこもる筑波山のふもと、羽鳥へとむかいました。 |
豊田は焼け野原です。
からすの群が大軍におどろいてぱッとまいたち、あけがたの空から将門軍を見おくっていました。
人が死に人家が焼けて、喜ぶものはからすばかりです。
人間の世をあざわらうかのように、からすは騒ぎたてていました。
“火雷天神”としるした旗を朝風になびかせて、将門軍が羽鳥にはいったとき、すでに良兼のやかたはからっぽでした。
「火をはなて!」
文屋好立の命令で、羽鳥は火の海となりました。火が風をよび、風は火をよびます。
ものみの兵の知らせが将門のもとにはせかけてきました。
「将門のとの、良兼の軍は弓袋山(ゆぶくろやま=筑波山の東の湯袋峠)にこもったようすです。」
さらに、ものみを出してさぐらせると、敵は弓袋山の南の谷の森のなかにかくれていました。
「真壁から谷へさそいこもうという策でしょうな………。」
多治経明は考えぶかげにいいました。
「南へ大まわりして小幡(おばた)へ陣をしきましょうか?」
将門はうなずきました。
秋雨が降りはじめて、いつやむともしれません。
しかし雨であろうと風であろうとたたかいをやめるわけにはいかないのです。
小幡へつくと、すぐに将門は包囲陣をかまえ、とりいれのすんだ稲たばを、ぬかるみ一帯にしきつめて陣をはりました。
「もったいないことだ。むざむざ米のなる木を………。」
だれの胸にもその考えがうかびます。しかし、とりあえず、いま目前の敵をたおすことが、土地をまもり収穫をまもることなのです。
将門たちは敵のでかたを待ちました。ところが敵軍は山から一歩もでてきません。
しびれをきらした将門は、経明らと相談して“戦書”を送り届けることにしました。
「将門、兵をひきいて小幡にいたる。
一戦して雌雄(しゆう)を決せん(たたかって勝ち負けをはっきりしよう)。」
という内容の手紙でした。
使いには文屋好立がたちました。小半刻(やく一時間)ほどしてかえってきた好立に、
「戦書はだれが受けとったぞ?」と将門がききますと、
「良兼のとのじきじきに手渡しました。受けて立とうとご返事です。」
なるほど。しばらくすると山の中から敵軍があらわれ、たてをならべて陣をしきはじめました。
もう夕やみがせまって、たいまつの火があちらこちらで燃されはじめました。
「夜軍か………。いや、夜があけるのを待ってせめ入ろう………。」
夜が白みはじめると同時に、将門軍はドッとときの声をあげて敵陣にせまりました。
ところが敵陣からはなんの反応もありません。
「なにか、しかけがあるのではないか?」
すこし心配そうに真樹が将門に問いかけました。
将門はだまって一騎で敵陣へかけてゆきました。真樹があとをおいます。
陣の中は犬の子いっぴきいません。まるでからっぽでした。
「なんというやつらだ! 敵に背を見せてのがれさるとは………。」
真樹はあきれ顔につぶやきました。
「勝ちめのないたたかいには手だしをせぬというわけか………。」
将門は、思わぬ肩すかしをくって、ふりあげたこぶしのやりばがないといったように苦笑いをしました。
「ひきあげだ。三郎、全軍をととのえよ。」
「ちえっ!」
三郎は大地にツバをはいて、ひとしきりののしったあと、全軍をよび集めにかけてゆきました。
「よいか、よっく聞いてくれ、われらはたたかわずして勝った。
これからひきあげとするが、ひきあげ先は豊田の鎌輪ではない………。」
意外な言葉に、集ったともからたちは耳をすまして、将門のつぎの言葉を待ちました。
「………いつまた東方から、この将門の敵たちが、おそってくるかもしれぬのだ。
鎌輪は平坦で地の利がわるい。
これよりもさらに西南に石井(いわい)に営所をきずこうと思う。どうだみんな………。」
一同は目をかがやかせて聞きいりました。
「石井なら、良兼のすむ羽鳥からは、桜川、子飼川、毛野川と、大小とりまぜて三本の川をこえねばせめられない。
石井は未開の荒野だが、沼地が多く山もあり、牧(まき)にてきしたところが、家人(けにん)はいうにおよばず、奴婢一人にいたるまで土地を分けよう!」
一同はどっとどよめき、喜びあう声があがりました。
「石井へゆけ!」
「ひきあげだ!」
「おらたちの国をつくるだ!」
「石井へ!」
「石井へ!」 |

将門のやかた跡をつたえる「石井(いわい)」の旧碑(茨城県岩井市)。
|
とちゅう豊田へたちより、夫や子を待つ家族もろとも、翌日中には石井の地に仮小屋の建設がはじまりました。
たしかに石井は将門のいうとおり、たたかいの地の利としてもよく、また利根川、毛野川による水上交通のかなめにもあたって多くの利点がありました。
しかし将門が安全と考えても、叔父良兼の目から見たらどうなのか、その日のくるまで、将門をはじめ一同には思いもよらぬ考えでした。
叔父良兼は、こうした将門がいよいよじゃまでならず、こうなれば意地でもどう策略をめぐらしても、将門を殺さなくては枕を高く眠ることができません。
良兼はにえたぎるようなにくしみの目で、一人考えにしずんでいました………。
2 馬商人 top
筑波おろしがふいて寒い日がつづきますが、今日も石井のあたりは、材木や石を運ぶ人々でにぎわっています。
将門のやかたをはじめ、そのまわりの農夫たちの家が、次々と建てられてゆきました。
しかし将門は、胸にポッコリと大きな穴か相手、むなしい風がふきぬけてゆくような思いでした。
つれそう東の君と子供をうしなった事実は、忘れようとしても忘れる事ができません。
三郎がしきりに、
「兄者! 忘れたのではあるまいな、東の君や豊太は叔父貴に殺されたのだぞ!」
と、いっこうにたたかう気のない将門を、なんとか立ち上がらせようと、口からあわをふくばかりにつめよるのでしたが、将門はまったくとりあおうとしません。
すべてがむなしく、灰色につつまれてしまったようです。
そんななかで、かいがいしく身のまわりのせわをやく桔梗の姿が、将門のすさんだ心をなごませてくれました。
「との! ここにおられましたか?」
近づいてきたのは五郎丸でした。
うしろにだれやら赤ぐろい顔の男が一人、白い歯を光らせてついてきていました。
五郎丸はそっちをちょっと見かえって、
「この男が不意に訪ねてきて、とのにひきあわせろといってききません。
古い友だちの、はかまだれという名前の男ですが。
はかまだれはぺこりと頭をさげて、
「五郎丸とわしとは、昔の泥棒なかまで………。」
言いかけて、五郎丸にそでをひかれて口をとざしましたが、我慢しきれなくなったように笑いだしました。
将門も笑いだしました。
「なるほど、その泥棒仲間のはかまだれが、わしになんの用事じゃ?」
「されば、将門のとのに馬を買ってもらいにうかがいました。」
「なに、馬? よい馬で安ければ買うが、馬はこの地のほうが名産じゃ。」
「ところが、名馬ぞろいなので、ごらんになればひとめでおわかりかと思うが、めったな値段では手ばなせませぬ。」
「ところが、との………。」
五郎丸がくちばしを入れました。
「………この男、いまでは、“しゅうばの党”とかいう馬泥棒たのです。」
「なに、しゅうばの党?」
「はい………。」
将門はまじまじと、はかまだれの顔をながめました。
さすがにはかまだれも、てれくさいような顔つきです。
「ですから、との、こいつの持って来た馬は、みんなもとはタダなのです。
思いきって安く買ってももとではないのですから………。」
「おい、おい。」
はかまだれは弱りきったように五郎丸をとめました。
「おぬし、本当に、“しゅうばの党”の者か?」
「はい。とのは、“しゅうばの党”をごぞんじで?」
「名前は聞いている。ではきくが、おぬしはどこからやってきた?」
「武蔵国。足立郡からで………。」
「では、武蔵武芝のとののところからか?」
「はい。さようで………。将門のとのは、武芝のとのをごぞんじでございますか?」
「いや、まだあったことはないが、評判は聞いている。立派な郡司じゃそうな………。」
はかまだれは、にたにたと笑みくずれて、まるで自分の兄でもほめられたような顔つきで、
「立派だのなんのって、武芝のとのは旧家であるばかりでなく、代々郡司や判官代という職にあって、民百姓を子供のように思ってくださる。
そのうえ、貢ぎや税も期日どおりにちゃんとおさめるというお人だ。
俺たちだって、この武芝のとのの前にゃ頭があがらないのじゃ………。」
「すると武芝のとのも、なにかおまえたちのやっている“しゅうばの党”にかかわりあるとでも申すのか?」
「とんでもねえ、武芝のとのにはいろいろ迷惑をかけたり、お目こぼしはいただいているが、かかわりなんてとんでもねえ………。」
「わしも武蔵武芝のとののうわさを聞いて見習うべきだと思っているほどだ。いつか、あうおりもあろうが………。一
「とにかく馬をごろうじませ、駿馬ぞろいでございます。」
馬のことになると将門も夢中になるたちです。
将門は馬を見に、広庭のほうにまわりました。
二人がそのあとを追おうとしたとき、はかまだれはギクッとしたふうに足をとめ、五郎丸にそのままのかたちで、きゅうに声をおとして話しかけました。
「五郎丸。俺のうしろのほうで炭を馬からおろしている若者がおろう? あれはだれじゃ。」
五郎丸がふりかえりますと、それは子春丸でした。
「子春丸じゃが………。」
「子音丸? ぶむ、………五郎丸。きゃつには気をつけよ。」
「なぜ?」
「石田の貞盛のやかたで会った。」
「ええッ? まさか………。」
五郎丸はおどろきましたが、すぐに人ちがいだろうと思いなおし、きゅうにおかしくなって笑いだしました。
「ははははは、はかまだれ、おぬし、貞盛のやかたへも馬を売りにいったのか?」
「あたりまえじゃ。馬商人は馬の買い手のあるところへはとこへでもゆくわ。
俺のいうのは冗談ではないぞ、きゃつ、あやしげなやつじゃ………。」
「まさか、あやしいのはおぬしのほうだ。」
五郎丸はとりあおうとせず、将門のあとを追いました。
広庭につながれた七、八頭の馬を見て、将門はひとめで気にいったようすで、上機嫌です。
「これ、桔梗。この客人に絹十疋をだしてやるように手くばりぜい。」
桔梗(ききょう)はぬりごめ(倉)のほうへ走ってゆきました。
「なるほど、おぬしの言葉にまちがいはない。いずれもたいした駿馬じゃ。
そのお礼におぬしにもめずらしいものを見せてやろう。
子春丸! 子春丸はおらぬか!」
将門の声を聞いて、子春丸が姿をあらわしました。
「この人を鵠戸沼(くぐいどぬま)へ案内せい………‥」
石井の南のほうに、そのころ大きな製鉄所がつくられていました。
ごく原始的なやりかたの製鉄ではありましたが、大きな炉をきずき、木炭をつかって、すき、くわなどの農具や、自分たちのつかう武器をつくっていたのです。
これも将門の発案でした。
砂鉄は鹿島あたりからたくさんに運びこみ、また木炭は、筑波山のふもとから、子春丸が買い集めてきていました。
大勢の人々が、この寒空にはだかになってあせをながしてたち働しています。
タタラ(大きなふいご)をふむもの、炉をきずくもの、それらを見て、はかまだれは舌をまいておどろきました。
「………一体この熱気はなんだろう? よその国には見られない、この国の熱気は?
………それにしてもやはりあの将門というお人はただものではないようだ。」
えい、おう!
えい、おうI
タタラをふむ職人のかけ声が、夕やみのなかに、いつまでもひびいていました。 |
 |
3 うらぎり top
それからひと月たつかたたぬある晩のことでした。
羽鳥の良兼のやかたは、喜びの声にわきあがりました。
やかたを焼きはらわれ、怒りに怒った良兼は、あることないこととりまぜて、将門を都にうったえ出ました。
その罪状には、
一つ、石田、羽鳥などのやかたをはじめ、多くの民家を焼きはらったこと、
一つ、ひそかに武器をつくり、公に謀反するきざしが見えることなどなど、
将門がこの訴状を読んだら、さだめしたくさんの言い分があるだろうと思われるような事ばかりが書きつらねてあったのです。
そしてきょう、その訴状にたいする官符(公の命令書)がもたらされたのでした。
“将門、討つべし”
良兼のやかたが、喜びにわきかえったのもむりはありません。
この官符さえあれば、将門は公にそむいた逆賊となり、朝敵となるのです。`
「いや、これでこそ積年のうらみもはれるというものじゃ。」
良兼は自分のやったことも忘れて、ほくほく顔です。
「良兼のとの。」
「なんじゃ?こ
「石田の貞盛のとのが見えましたが。」
「よいよい、これへとおれと申せ。」
「あいや、かってながら庭先へまわりました。ついに官符がくだったげに聞きましたが………。」
そういってはいってきたのは貞盛でした。
「叔父者に手みやげがござりまする。これ、その者をこちらへひきずり出せ………。」
見ればくらがりから一人の若者が、手を背中にしばられて出てきました。
「なにものじゃ?」
ふしんそうにきく良兼に、貞盛はつめたい笑いで答えて、しとねの上にすわりました。
「顔をあげい。千春丸!」
びくっとしたように若者は顔をあげました。まぎれもない子春丸です。
「よいか、子春丸。ムチがほしくばムチをやろう。
ほうびがほしくばほうびをやる。どちらがよい?」
子春丸は血ばしった目つきで貞盛の顔を見あげました。
「や、約束がちがう! おれをなんでしばったのじゃ?」
「すなおに答えたら、約束どおり黄金も絹もとらそう。なわ目もといてやろう。」
「だから、俺は全部しゃべったではないか!」
貞盛は叔父の良兼をふりかえって笑いました。
「ははははは、叔父上、こやつは将門の走りづかいをつとめる子春丸というものです。」
「なに、将門の?」
「はい。将門が鉄をきたえるために、この辺りへ炭の買い出しによこしていたのを、うまくえさをまいて飼い慣らしました。
これよ、千春丸のなわをといてやれ。」
庭先にたっていた郎党が、てばやくなわをときました。
「おまえのほしいものは、これか?」
しびれた腕をなでている子春丸の目の前に砂金のふくろがなげられました。
千春丸が一生かかってもためることのできないほどの、ずっしりした重みです。
子春丸は、あわてて砂金ぶくろをふところへねじこみました。
「………それとも。このムチがよいか?」
貞盛のつめたい声音に、千春丸は震えあがって、
「い、いえ、も、申しあげます。な、なにもかも、申しあげいでなんといたしましょう………。
そのかわり郎党にお取立ください。」
千春丸の目の前に、将門のやかたの絵図面がひろげられました。
………武器のおき場所。将門の眠る場所、馬にのったまま出入りできる門など、攻撃のツボのすべてが、その夜のうちに良兼の絵図面にしるされてゆきました。 。
十二月十四日、夜。八十余騎の武士が、羽鳥を出発しました。
まっすぐ南へ行かかずに、鳥羽の淡海の北をまわって、結城のほうへむかいました。
結城の南に矢畑というところがあります。
その矢畑にある結城寺で眠りについていた五郎丸は、時ならぬ馬のひづめの音にはねおきました。
馬はまっすぐこっちへやってきます。
五郎丸は身じたくをととのえ、馬にのって街道ぞいの闇のなかで待ちました。
今夜ここにいたのも将門の指図があったためです。
「敵が大軍をもって攻めるときは、川をわたってこよう。
しかし夜討ちをかけるときは、結城へまわって北から攻めるにちがいない………。」
結城寺には毎晩だれかがか当番でつめていたのでしたが、五郎丸の当番のときにまさか夜討ちがあろうとは、思いもよりませんでした。
五郎丸にはまだ信じきれません。
五郎丸はいきをひそめて、あやしい馬の一行が近づくのを待っていました。
やはりそうでした。大きなかぶとをかぶり、弓を張った武者たちです。
八十余騎が目のまえをとおりすぎたかすぎぬかのうち、五郎丸は馬を走らせて、敵のすぐうしろからついてゆきました。
こうなると命がけです。星かげの中を、仲間のふりをしてついてゆきました。
これが月夜ででもあったら………そう思うと五郎丸のワキの下にはひやあせが出ます。
敵の一団はかも橋をこえてゆきました。
そこで五郎丸はかも橋から左へ道をとり、ムチを鳴らして、石井へまっすぐひた走りに走りつづけます。
このほうがはるかに近道なのです。
馬のはく息が、夜目にも白く見えました。
「走れ! いきあるかぎり。足のつづくかぎり………。」
五郎丸も懸命です。やかたの近くまでくると五郎丸は、
「との、との! 一大事じゃ。開門! 開門!」
門のあけられるのを待つ間ももどかしく、五郎丸はおどりあがって泡をふく馬にのったまま、
「との! とのはいずれに? 敵がきましたぞ! 数はおよそ八十騎!」
やかたのなかに灯がともされ、やがて大きな将門のかげぼうしが、ゆらぎながら近づきました。
「五郎丸か、ごくろうだった。兵を集めい! あけがたが近い。いそげ!」
やかたの中は、きゅうの知らせで大騒ぎになりました。
「桔梗! 桔梗をよべ!」
「はい。これにおります。」
「そなたは女どもを安全なところへ落とせ。よいか、たのんだぞよ。」
将門は、目のまえの武器を手にした郎党たちを見ました。わずか十人しかいません。
「よし、よっく聞け。味方の数はすくない。だが、敵も八十数騎じゃ。
それに十数里の夜道をいそいできている。
わしらには一所懸命の勇猛心がある。けっしてひるみは見せまいぞ!」
「そうじゃ。とのと一緒に死にますべい!」
だれかがこたえました。
「敵にうしろは見せませぬわ。敵の矢が背中に当っていたか、前に当っていたか、死んだあとで調べてもらいますべい。」
一同どっと笑いくずれました。そのとき、
「きました!」と矢倉の上からものみが叫びました。
もう夜が白んで、卯(う)の刻(午前六時)になっています。
将門は馬にひらりとまたがり、大刀をふりあげ、
「つづけ!」と北の出口から敵軍のまっただなかへ切りこんでゆきました。
不意をおそうつもりできた良兼は、門が突然ひらいて将門かおどり出てきたため、かえってびっくりしました。
陣形をととのえるひまさえありません。
大将のあわてぶりは、そのまま部下へも伝わります。
いったんくずれた陣は、将門らの手で無二無三(むにむさん)においたてられてゆきました。
「罪のない妻子まで殺した鬼め!」
そう心にさけぶ将門のほうが、かえって鬼ではないかと思われるほど、まなこをつりあげ、こめかみに青いすじをはしらせ歯がみをして、ものすごい形相です。
良兼はかなわぬと見ると、簡単に馬の首をひるがえして羽鳥をさして逃げかえりました。
あとからの調べでは、敵は八十余人のうち、半分の四十余人が討ちとられていました。
はっきり負けだとわかっても、良兼のくやしさにかわりはありません。
それいらい高い熱をだして寝こんでしまいました。
子春丸の裏切りは評判になり、あくる年の正月、かくれてしたところを見つけられて、その場ですぐに首を切られました。
4 千曲川のたたかい top
貞盛はこの知らせを聞いてがっかりしました。
いえ、がっかりどころではないのです。
まごまごしていると貞盛自身のいのちさえあぶないものです。
国司のがわに立ち、良兼までもおどらせたことで、貞盛にたいする土地のものの評判はますます悪くなるばかりでした。
「………ええい! こんな常陸の片田舎にくすぶっていられるか!」
そう思うといよいよ都の空かこいしく思われてなりません。
「よし、ままよ。この上はみずから都へ出て、公にうったえるまでじゃ………。」
病のとこにふしている良兼を見すてて、わずか四十騎ばかりの家来をひきつれ、碓氷峠をこえて東山道から都をさして旅だちました。
碓氷峠にはまだ雪がのこっている二月のなかばのことです。
そんなある日、石井(いわい)の将門のもとへ、佐野に住む豪族。
田原藤太秀郷からいそぎの使いがやってきました。
「なんだろう………?」といぶかりながら使いの若武者に会ってみました。
「主人田原藤太。いまだ将門のとのにおあいする機会もなく失礼いたしております。」
「いや、それはおたがいじゃ。で、いそぎのお使いと聞いたが?」
「は、貞盛のとののことでお耳に入れたい事がござりまして………。」
「なに? 貞盛の?」
若武者は声をおとして、佐野の領内を西へいそぐ四十騎ばかりの武者があったこと、それがどうやら貞盛の主従らしいことをつげました。
「………かようなわけで、この件、ちょっと石井の将門のとののお耳に入れてまいれとの、主人のいいつけでござります。」
「………ふむ、いや、かたじけない。将門、このご恩は忘れませぬ。
田原のとのへ、どうかくれぐれもお礼を申しあげてくだされい。」
使いの若武者にみやげなどを持たせ、丁重に送りかえすと、将門は三郎をよびにやり、いそいで身じたくをはじめました。
「兄者! 本当か?」
「本当らしい。田原藤太どのの知らせじゃ。」
「それは聞いた。きゃつを都へやっては、また何を告げ口するか知れたものではない。
しこたま金銀をつかって、めめしくほえづらかいて、何をうったえることやら………。
ぶち殺してしまえ。」
「いや、貞盛はまだおもてだっては一度も俺たちに喧嘩をしかけてはいぬぞよ。」
「そ、そんな。兄者は、妻や子を殺されてまで、まだそんなことをいうのか?」
「殺すな、生かして捕えるのじゃ………。」
文屋好立が、用意のできたことを知らせにきました。
三郎は、兄将門の言葉が気にいらなかったせいか、むやみに大声をだし、馬にまであたりちらしています。
五郎丸は、こんなときの三郎にはあまり近よらないようにしています。
近づいてなにか声をかけようものなら、やつあたりのエサにされる恐れがあるからです。
将門の一行は百余騎。ひた走りにかけて雪の碓氷峠をこえました。
ものみの知らせで、貞盛勢が小諸のあたりにいることを知り、さきまわりした将門は、上田にちかい国分寺のあたりへ鶴がつばさをひろげた形で陣形をとり、しずかに貞盛勢を待ちました。
西風がふきすさんで、腹の底にこたえる寒さです。
「いい風だ、兄者。矢が風にのるぞよ。」
「貞盛は殺すな。」
「わかった。だが戦場のことじゃ。流れ矢のことまでは知らぬぞ!」
やがて貞盛勢四十騎が姿をあらわしました。
まさか将門らがここで待ちうけていようとは知らず、がやがやと話しごえが聞こえます。
五郎丸は
「貞盛に味方するつもりはないが、いまここで貞盛にいくさをしかけるのも気のどくのようだ………。
将門のとのは貞盛を殺すなといわれる気持ちもわがらぬでもない。」 と思いました。
「待てい!」
大音声とともに将門はただ一騎、敵から姿の見えるところへ、おどりでました。
貞盛勢は、はッと息をのんで、何事かと見まもっています。
「常平太貞盛(じょうへいたさだもり)はいずれにおわす。小次郎将門が話をしたい!」
つぎの瞬間、敵勢は混乱して逃げまどいはじめました。
なかには勇気のあるつわものがいて、将門めがけて矢をはなってくる者もありました。
「つづげ!」と文屋好立がさけんで刀をふりあげ、敵中へおどりこんでゆきました。
貞盛は思いもかけぬ将門の出現にきもをつぶしました。
馬の方向がどっちをむいているかさえわからぬまま、ムチをふるって一目散に逃げました。
左に右にかぶら矢がうなりをたててとんできます。
「きたなし! 逃げるか!」
将門の声を聞いたようにおぼえましたが、貞盛はふりむこうともしませんでした。
たたかいはたちまちはっきりしてしまいました。
貞盛勢は三十騎ほどがうちとられ、あとは貞盛ともども、どこへかくれたのか姿も見えません。
味方のうちでは文屋好立が胸に矢を射こまれて深手をおいましたが、幸い命はとりとめました。
「どうだ? 大丈夫か?」
幕をはりめぐらした陣屋のうちをのぞいた三郎が、そっと将門に訪ねます。
「いいようだ、だがだいぶ深手じゃった。しばらくこのままにしておこう………。」
「兄者、話がある。」
「あん?」
将門は三郎のいいたい事がわかっているのですが、ちょっととぼけて、しぶしぶ幕のそとへ出てきました。
パチパチはぜるかがり火に手をかざして、
「なんだ、あらたまって話とは?」
「貞盛は逃げた、にがしたのは兄者だ!」 |
 |
「何をいうか。」
「兄者は卑怯だ!」
「なんだと、はっきりいえ、はっきり。」
「はっきりいっている。兄者は卑怯だ!
おぬしには貞盛を討つ気など、さらさらなかった。
そうだろう?」
「そんなことはない。ただわしは貞盛を殺すな、生けどりにせよといった。それだけのことよ。」
「兄者の仏心(ほとけごころ)、仏づらがしゃくにさわる。長い間のあだがたきどうしではないか。
ここにいたって、待てしばしはないはずじゃ。
貞盛を殺してなにがわるい。
天にも地にもはじるところはないぞ。」
「待て、三郎。よいか、俺にはいま、あのいとこの貞盛が、従者をうしない食糧もなく、ただ一騎、この雪の于曲川ぞいに逃げてゆく姿が目にうかぶのだ。」
「そういう兄者なのだ! 俺にはわかっていた。」
「まあ、聞け!」
「いや、聞かぬ。兄者、あとでくやむまいぞ!」
三郎はいいすてて自分の陣屋のほうへ去ってゆきました。
空に、星がいてついたようにかがやいています。
「………この国の星はとくに大きいのだろうか?」
天をあおいで、将門はふとそんなことをぼんやり考えていました。
top
**************************************** |