|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 当時の日本地図
二 みやこの二つの顔
1 新しい女帝 top
かえってみると、小さな家は、すっかり手ぜまになっていました。
なにしろ、長男の憶人(おくひと)は背のたかい立派な少年でしたし、春日(はるひ)は母親よりもずっと大きくなっていました。
憶良は、一番びっくりしたのは、ちっちゃな赤ちゃんだった憶男(おくお)の成長ぶりです。
そんなふうたので、小さな家は、ますます小さく見えるのです。
けれども、手ぜまになっているのは、憶良の家だけではないようです。
藤原のみやこが、せまくなってしまっているということでした。
憶良は、日本へ帰ってきてはじめにきかされたのは そのことでした。
見まわしてみても、けっして、そのようには見えないのですが、もっと便利のよい広々としたところへみやこを移したほうがよいと、高い位の人たちは考えているのです。 |
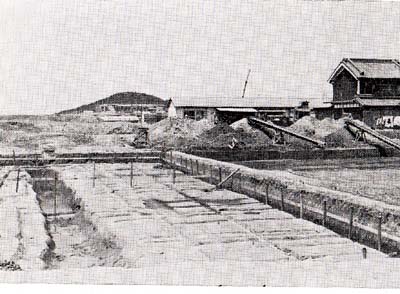
発掘作業のすすむ藤原宮あと
|
なるほど、六年前よりは人口もふえていましたし、家の数も多くなっています。
けれども まだ城内のあちこちには空地もあり、宮城だって、なにもかもがすっかり出来上ってはいないのです。
これ以上、長安をまねして、大きくする必要があるのでしょうか。
城内の北にあって築地の塀にかこまれた朝堂院は広場のような大路を中心に、十二もの役所の建物が軒をならべ、そのおく深く回廊のかなたにいちだん高く大極殿があります。
屋根はつばさをひろげた大鳥のように空を区切っています。
宮城の中にある建物は、天皇のすまいのほかは、すべて堂々とした唐ようで、瓦も木材も、えらびぬかれ、つくりあげられたものでした。
これらはもちろん、憶良が出発する大宝元年よりもまえ、なくなられた女帝の御代にすでにできあがっていたのです。
でも、手いれがゆきとどいていて、六年たった今、見ても、すこしも古びたようすはありません。
瓦の青、壁の白、朱いろの柱………目もまばゆいばかりの美しさです。
宮城の外、みやこのまちは朱雀大路で左右にわけられ、碁盤の目のように大路が走っていました。
大路に面して建っているのは、身分の高い人たちの住まいで、広々とした敷地に瓦ぶきや、板ぶきの立派な家がならんでいます。
長い塀に囲まれたそんな屋敷のならぶ大路を一歩わきにはいると、敷地もせまくなり建っている家も粗末になります。
すべて、身分にしたがってあたえられるので、敷地や場所もきまってしまうのです。
憶良の家も大路からずいぶんはなれたところにありました。
みやこへ帰り着いたつぎの朝、まずしい憶良の家には似つかわしくない、上等の身なりをした人が、訪ねてきました。
長屋王(ながやのきみ)からのお使いです。
長屋王の屋敷は朱雀大路に面して、宮城とは、すぐ近いところにありました。
案内されるままについてゆくと、広く美しい庭をとおり、はなれのような小さな亭につきました。
もう長屋王と粟田真人が、憶良のくるのをまっていました。
長屋王は高い身分の皇族でしたが、うちとけたようすで、憶良に漢の学問について、たずねたいことが山ほどあるといいました。
「何もかも日本は、まだ出発点にいるのだ。唐のことをいろいろ知らなければならない。
真人どのからきみのことをきいて、ぜひ、会いたくなったので、今日きてもらった。
これからは、日をきめて勉強会をしていこうと考えている。すこしも、遠慮はいらない。たのんだよ。」 |
ありがたい言葉でした。憶良は、ふかくおじぎをしました。
「ちょうどよいときに帰ってものだよ、憶良くん。
もう、きいたかもしれないが、みやこをうつすという案は、この二月に会議にでてね。」
真人(まひと)は上品な手つきで、ひげをなでました。長屋王(ながやのきみ)がいいました。
「ここは、土地がせまいうえに、交通のべんもわるいからな。」
「交通のべんが………。」
憶良は、思わずまゆをひそめました。長屋王は、
「そうだ。というのも、宮城やそのほか、まだ建物もできあがっていない。
そのうえ、二十年もすると、建てかえねばならないものもでてくる。
手入れもしなければならない。それなのに、よい木材か年ごとに、手にはいらなくなってきているのだ。」
と、説明しました。
飛鳥には長年にわたって宮城がありました。
宮城は大王や、天皇がかわるたびに場堺かうつされるのがならわしです。
そして、それに使う木材は吉野の山からきり出されるのです。
今までに大変な量の木がすでに、きりだされていました。
「もう宮城にふさわしい木材は、だんだん奥地にはいらなければ、手にいれることができないのだ。
そうなれば切りだすために、人手が三倍心四倍もいる。
そこで、藤原のみやこには近江の山からも木材をはこんできた。
これからも、まだまだ必要だ。しかし、いずれにしても人手がいるのだが、働き手が不足している………。
そこで思いきってみやこをうつすことにきめたのだ。唐ではどうなのだろう。」
長屋王がたずねました。
「出発点にいる日本は、唐とくらべるわけにはいかないと思います。
それに、国の広さも人口もちがいます。
みやこをうつすとなれば、またはじめからやりなおししなければならないし、働き手は、ますます不足するのではありませんか。」
憶良は思ったとおりに、こたえました。
「だから、木材もまだゆたかにある、近江へも便利な土地へ移るのだ。
たとえば、平城山(ならやま)の南にひろがる平野のようなところへ………。」
長屋王(ながやのきみ)は、椅子にゆったりと、もたれました。
「あんなに、北へ………ですか。山背の国との国ざかいではありませんか。」
憶良はびっくりしました。
「そう。近江の湖から、木津川まで、すべてのものを川がはこんでくれます。」
と、真人がほほえみました。
「そのうえ、あのあたりの土地は藤原氏のもちものだ。よろこんでさしだすと、不比等がいっているしな。」
そんなことを、長屋王は、なんでもないようににいいました。
それから、四日めの六月十五日、大変なことがおこりました。
若い文武天皇が病気でなくなったのです。位について十年あまり、二十五歳でした。
あとつぎの首皇子(おびとのみこ)は八歳で、皇太子もきまっていません。
「また、天皇の位をめぐって、血て血をあらう、おそろしい争いがおこるのではないか。」
藤原のみやこは、不安な暗い空気につつまれました。
朝廷は、三日間まつりごとをやすみ、一か月喪にふくすよう命令しました。
悲しみの一か月がすぎると、なくなった若い文武(もんむ)天皇の母、阿閇皇女(あべのひめみこ)が天皇の位につきました。 さきの女帝持統天皇が 孫の軽(かる)皇子が大きくなるまでの間、天皇の位をついだように、新しい女帝も、孫の皇子が大きくなるまでの間をつなぐために、位をついだのです。
元明(げんめい)天皇です。この皇女(ひめみこ)は、持統(じとう)天皇の妹でした。
「なら山の南へ、みやこをうつす話はどうなるのだろう。」
秋とはいっても、まだ夏のような日差しがきえない七月十七日、大極殿でおこなわれた即位式のあと、道麻呂は憶良にたずねました。
高い位の人たちと、交わりのある憶良はだれよりもよく、いろいろなことを知っていたからです。
「さあ、やっぱり、移ることになるでしょうね。天皇さまがかわっても朝廷の方針はかわりませんよ。」
憶良は、ゆううつそうにいいました。
「そうだろうな。
しかし、みやこのにぎわいは、みせかけのものだということを、高い位の人たちは、どう考えているのかね。
唐へいっているあいだにも、暮らしむきは、どんどん悪くなっている。
ほしいものは何でも手にははいるが、市へいっても取替る籾(もみ)や布(ぬの)は、うんとださなければならんのだ。
それもこれも、つぎからつぎへと、とだえることのない工事のせいなのに………。
即位のおいおいに、罪人を許したって、そんなことがなにになる。」
と、道麻呂は、すこし、おこっていいました。
「そうなのですよ。去年は疫病がずいぶん、はやったようですしね。
東国が長雨で、さむい夏なら、西国はひでり、そして虫の害でしょう。
こう天候に左右され、飢饉にみまわれていたのでは、租税をがす農民たちの暮らしも、なりたちませんからね。
かといって、租税や労役をなくせば、日本はなりたたないのですから、困ったものです。」
憶良は、大極殿のまばゆいばかりの白い壁に目をやりました。
この壁をぬったのは、百済からわたってきた職人でしょう。
けれども、土地をならしたり、柱を立てるための礎石をすえたり、遠い近江から木材をはこんだりしたのは、労役にひっぱってこられた地方の農民たちです。
あせとあぶらにまみれて、材木をひっぱっている労役の人たちのかけ声が、宮城のあちらこちらからひびいてくるように、憶良には思えました。
「そんな話、もういいじゃありませんか。」
横から、阿麻留が口をはさみました。
「憶良くんは、この律令をつくるのを手つだった人です。
その人が、いまごろ、負担がおもすぎるなどといっては、農民たちがこまりますよ。
公地公民(こうちこうみん)、農民に口分田(くぶんでん)をあたえるかわりに、きまっただけの租税をだせといったって、よろこぶものは朝廷と、ゆたかな人たちだけです。
労役や租税のとりたてがきびしすぎて、自分たちのすみ家も食べ物も、着るものもないのが、農民のいまの姿です。
それでも租税で、池をほったり水路をつくったり洪水をふせいでくれるのならともかく、ちっともいいことはないのです。
道をつくるからと狩りだされても、その道は租税や貢ぎ物をはこぶ道で、人々の暮らしとはなんのかかわりあいもない道なのです。
“いざ子供、早く式場へ、青みどろの沼へ………。”私は、早く宴会場へいきたいものだ。
なぜならおなかの虫がぐうぐうないてとまらない………。」
と、大きな声でわらうと、式場のほうへ歩きだしました。
「青みどろの沼とは なんのことだ。」
道麻呂がふしぎそうに憶良にたずねました。憶良は、わらって答えました。
「私たち役人の服の色が、位によって濃い薄いはあっても、全部緑色にきめられているから、役人が集っている式場のことを、青みどりの色にたとえていったのでしょう。
憶良には、阿麻留という人物がどうにも、わかりませんでした。
とてもいいことをいうかとおもえば、きゅうに、とんでもなく口が悪くなったり、役所の仕事はなまけてばかりいるのに、ちっともにくめないのです。
大極殿や朝堂院に、色とりどりののぼりがはためき、楽の音がひびいても、かなしみのはれない即位式でした。
普通なら華やかに、はでやかにとりおこなわれるはずの式典なのです。祝いの会も、ごく内輪にということでした。
新しく天皇がきまると、今度は、
「ほんとに、みやこは移るのだろうか。もし移るとすれば、それはいつだろう。」
人々はひそひそと不安そうに、顔をよせあいました。
せっかく、すみなれたこの藤原の地をはなれるのは、なごりおしいことです。
けれども、それにもまして、暮らし行きのことが心配だったからです。
いっぽう、朝廷では、みやこを一日も早くうつそうと、計画をすすめていました。
とにかくそれには、まず正式に会議にかけて決定しなければなりません。
憶良はみやこをうつす準備の仕事に、毎日おいまくられることになりました。
やがて、若い文武天皇のもがり(仮に遺体をまつる)の期間もすぎて、十一月十二日、飛鳥の岡で火葬にされました。
それはさむい日で、粉雪がちらちら、まっていました。
火葬は、若い天皇のおばあさんにあたる先の女帝(持統)のときからはじめられ、いまでは皇族の人たちの間でも、用いられるようになっていました。
けれども岡の上から遺体を焼く煙を見て、泣かないものはありませんでした。
なんという、悲しいわかれでしょう。火葬がなかったころには、こんな煙を見ることはなかったのです。
塚をきずいて、そのままほうむったのですから。
とはいっても、これが天皇家の信じる仏教のならわしなのです。
それから八日め、遺骨は、飛鳥檜隈(あすかひのくま)にきずかれた安古(あこ)の山陵にほうむられました。
それは、お爺さん『お婆さん(天武、持統)がねむっている大内山陵のすこし南です。
藤原のみやこがつくられる少し前にきずかれたこの大内山陵は、みやこの朱雀門のほとんど真南に位置しています。
そして、山陵とみやこのちょうど中間あたりに菖蒲池(しょうぶいけ)の陵(みささぎ)もありました。
このあたり、起伏する岡のふもとにまた中腹に、大きな前方後円の大塚や、円形の塚がいくつもあります。
いまは亡き文武天皇は、きっとさびしくないことでしょう。
文武天皇の死、そしてあのはれがましい宮廷の大歌人柿本人麻呂の死と、慶雲(けいうん)四年はかなしく、くれてゆきました。
けれども新しい年は、おもいもかけない、うれしい知らせとともにやってきました。
正月十二日、武蔵の国秩父郡から銅が献上されたのです。銅がほりだされたのは、日本ではじめてのことです。
もちろん、東国へすみついた百済人たちが、なしとげたことでした。
元明女帝はよろこびをあらわすために、すぐさま年号を和銅とあらため、天下にこのことを知らせました。
二月には、鋳銭司(ちゅうせんじ)という役所がおかれ、銅銭をつくる準備にかかりました。
その昔、唐から唐銭を輸入してつかったこともありましたが、うまく流通しなかったので、すぐにとりやめになりました。
まだ貨幣をつかいこなすだけの力が、人々にはなかったからです。
残念なことに、いまも昔どおり、籾や布が貨幣のかわりにつかわれていました。これからはどうでしょうか。
銅がほりだされて、朝廷はよろこびにわき、みやこの人々も、今年はきっと、よいことがおこりそうだと、うきたっていました。
そんなある日、阿麻留が憶良のつくえの前へやってきました。
阿麻留はやっぱり新しいみやこの準備をする役についていて、憶良と同じ役所の建物の中にいるのです。
「おや、こんなよい天気に、まだ仕事をしているのですか。すこし、外をぶらついてみませんか。
まちでは、子供たちが『銅がでて、どうなるの』なんて、ざれ歌をうたっていますよ。
ほんとにどうなるのですかね。私には、川の水が酒になってくれるほうが、ありがたいようなものです。」
憶良はすずりをかたづけると、阿麻留について、外へでました。
ほんとによく晴れています。
「目の前に、春がきてますね。」阿麻留(あまる)が、大きく息をすいこみました。
2 秘密の集まり top
阿麻留はどこまでゆく気なのか、どんどん歩いていきました。羅城門をでてから、もうだいぶたちます。
門を一歩でると枯れた株の残っている田んぼ道です。
春のけはいが感じられるといっても、野をふきぬける風は身をきるようなつめたさで、西風をまともにうけて憶良は息ぐるしいくらいです。
それなのに、阿麻留は、ふとった体をすこしも苦にしないで、すたすたゆくのでした。
役所で見ている阿麻留とは、まるで人がちがっているようです。
歩くにつれて葛城の山がだんだん大きくなり、とうとう当麻(たいま)の里にまできてしまいました。
「どこまでゆくのですか。」たまりかねて、憶良はたずねました。
ゆくさきもきかずについてきたことを、さっきから後悔していたのです。
「ゆくさきもおしえずに、すみませんでした。
しかし、竹の内峠まで、などといったらあなたは、たぶん、きてくれなかったでしょう。
どうしても、あなたにあってほしい人たちがいるのです。峠の途中なのですが、きてくれますね。」
阿麻留は、まじめな顔でいいました。
「ここまできたのです。いまさら引返すわけにはいかないでしょう。」
憶良は、目の前にそびえる山なみを見て、いいました。この山あいをぬける道が竹の内街道なのです。
阿麻留はにっこりわらうと、先にたって歩きだしました。
山道にかかってからは、強い風もさえぎられて、すこしはらくになりましたが、今度はうねうねの、のぼり道です。
歩きつけない憶良は、すっかりくたびれてしまいました。それから、どのくらいのぼったでしょう。
「ちょっと、けわしくなりますよ。」
阿麻留は、街道をそれて、あるかないかの細い枝道にはいっていきました。
枝道は、きこりがつかう道のようで、とてもけわしくて、ともすれば憶良は、ころびそうになりました。
やせてひょろ長い体を二つにおるようにして、ぜいぜいいいながら、それでも阿麻留についてゆくと、
「さあ、ここです。」阿麻留がやっといいました。
それはまるで、人目をはばかるように木々の間にかくれて、建っていました。
小屋は小さいものでしたが、頑丈そうなつくりでした。
阿麻留は、入口の板戸を、とんとんと叩きました。
「阿麻留だ。お客さまをおつれした。」
すると、板戸が相手、一人の僧があらわれました。そして、だまって、二人を家の中へとおしました。
ちゃんとゆかもしいてある、立派なものです。
中はまっくらで、小さなあかりが一つ、ぽっと、うかんでいました。
どこからか、香のかおりも、ただよってきます。
「憶良どの。お疲れになったでしょう。さあおすおりください。」
なれたようすで阿麻留は、どっかりゆかにすわりました。 いわれるままに憶良は阿麻留の横に、こしをおろしました。
「阿麻留どの。一体、ここは………。」
憶良は、あたりをすかして見ました。どうやら四、五人の人がいるようでした。すると、こだまみたいに、
「ここは、道場です。」
と、わかい男の声が かえってきました。
「道場………。」
耳なれない言葉に、憶良が思わず、問いかえしました。すぐに、べつの声が、
「そうです。行基さまがおつくりになった道場です。」と、こたえました。
憶良は阿麻留のほうを見て、問いつめるような口調でいいました。
「阿麻留くん。これは、どういうことなのです。こんな秘密めいたことは、きらいです。 なんのために、私を、こんなところへつれてきたのです。」 |
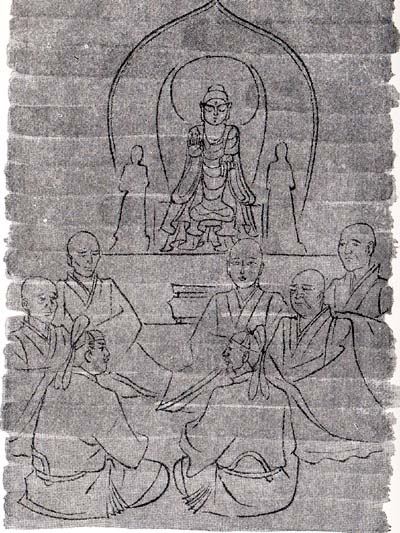 |
「とにかく、この人たちの話をきいてやってください。」
阿麻留はただ、それだけいって口をつぐみました。
そのころになると、憶良も小屋の中のうすぐらさに、ようやく目もなれてきました。
あかりにゆらめくように、仏の像が金色にかがやき、像をかこむように、すわっている人の数は五人でした。
女の人も一人います。そして、みんな頭をそり、僧の衣(ころも)を着ていました。
「私どもは、行基(ぎょうき)さまの弟子です。」
女の人がいいました。その声は、憶良のむすめの春日(はるひ)と同じくらいの年頃でしょうか。
「行基さまは仏になりかわって、私どもを救ってくださるありがたい坊さまなのです。」
「なぜ、こんな山の中にこもっているのか。」
憶良はたずねました。今度は年とった僧が、ちょっとひざをすすめて、
「それはひそかに、僧にしていただいたからです。私たちはこの道場にこもって、修行しています。」
「ひそかにだと………。これは驚いた。それは、おきてにそむくことだぞ………。」
憶良がいうと、としとった僧の延明(えんめい)は、
「わかっています。朝廷のさだめた寺でしか、僧になることはできません。
行基さまもまえは薬師寺におられましたが、いまは寺を出て諸国をさまよい、僧になりたいものの得度(とくど)してくださっているのでございます。」
得度とは、出家するための儀式のことです。
「行基さまは罪をおかしても、人々を仏の道にみちびいてくださっているのです。
私どもは、仏さまにすがるよりほかに、生きる道はないのです。」
と、わかい戒光尼(かいこうに)の目が、きらっとひかりました。
「私は、百済からわたってきたものです。朝廷の奴(やっこ=どれい)だったものもいます。
皇族や、朝廷の高官、豪族などの奴だったものもいます。また、百済人の豪族もいます。職人もです。
藤原のみやこができたのも、私たち朝鮮からわたってきた者のもっている、高い技術があったからですわ。
それなのに………。」
かわって、永長がいいました。中年の渡来人です。
「飛鳥にある代々の天皇の宮殿をつくったのも、また私たちの技術です。
それだげではありません。私たちのもっている土木技術は、大きな陵(みささぎ)をきずきました。
しかし、宮殿をつくることなんか、陵をきずくことを思えばたいしたことではないのです。
それが先の天智天皇の御代(みよ)に、葬式を簡単にするようにという命令がだされてからは、土木工事の技術者の多くが、職をうしないました。
行基さまは、それらのものをすくうために、池をほり水路をつくるような仕事を、こしらえてくださっているのです。
それはまた農民たちのためにもなることなのです。」
憶良は、うなずきました。
「百済人の豪族も、そんな行基さまを応援して、この道場を建ててくれました。
こんな道場は、河内や和泉にも、二つ、三つありますが、これからはもっと、もっと、ふえてゆくでしょう。
行基さまは、仏の教えをひらめ、一人でも多くの人をすくおうとしておられるのです。
なぜならこの日本は、飢え死にしそうな人が山ほどいて、救いの手がさしのべられるのをまっているのです。
私はずっと昔、子供のころ、飛鳥の宮城の工事へかりだされてそのままゆくえ不明になった父をさがしているうち、有間皇子さまにめぐりあい、かわいがられていたズクというものです。
長い間、東国でさまよい、苦しみやつらいことを、いやというほどあじわいました。
人々の暮らしぶりの、裏も表もみてきました。
年老いて紀の国にまいもどり、行基さまにお目にかかったのです。」
と、年よりの僧延明は香をくべながら、いいました。戒光尼は、目に涙をうかべています。
「あんまり、つらくて、仏さまのお力にすがりたいと思っても、普通ではなかなか、坊さんになることはできません。
朝廷がきびしいおきてをつくっているからですわ。
朝廷の建てた薬師寺では、とても人をすくうことはできないと、寺をすてて世の中へ出られた行基さまは、人々を得度する資格は失ってしまわれました。
けれども、そのようなおきてにかまわず、罰をおそれず、信心ぶかいものを得度してくださるのです。」
「得度して坊さんになれば、貢ぎ物をさしださなくてもよくなります。労役にかりだされることもありません。」
ひどい東国なまりの仁高(にんこう)は どもりながらいいだしました。
「私は、常陸の国の農民です。おととしの秋『租』の稲たばをせおって故郷をでました。」
その話は聞くのもつらいものがたりでした。
仁高は五人の仲間ときめられた日、里人たちからあつめた租をせおって、里長(さとおさ)につれられ、郡衙(ぐんが=郡の役所)へゆきました。
郡衙にはもう、あちこちの里からやってきた農民たちがきています。
郡衙にあつまった農民たちは、つれだって国衙(こくが=国府にあるその国の役所)へゆきますと、そこにはそれぞれの郡(こおり)からやってきた農民たちがきていました。
みんなみやこへ『祖』の稲たばをもっていく人たちです。食糧の干飯(ほしい)をもち、野宿しながらゆくのです。
途中で逃げださないように、兵士が見はりについています。
みやこまで三十日間、さむい風にふきさらされ、おもい荷物におしつぶされそうになりながらの、長い旅でした。
「私は、あんまり体が丈夫ではありません。
故郷をでて五日もすると、荷物がせおえないほど体が弱ってしまいました。
みんなもよく救けてくれましたけれど、自分の荷物だけでせいいっぱいなのです。」
その話をきいているうちに、憶良の目にありありと、雪のまじる風の中をすすんでゆく仁高たちの姿が、うかんできました。
馬にのった数人の兵士たちに、早く早くとせめたてられている人たち………。
馬で荷をはこんでいる人たちがいるなかで、馬のない仁高は前のめりになり、いまにもたおれそうです。
山道はだんだんけわしくなり、仁高はとうとうたおれました。
『仁高、仁高、しっかりしろ、みやこはもう近いのだぞ。』
仲間が声をかぎりにはげまし、仁高を救けおこそうとしています。憶良が、そこまで考えたとき、仁高は、
「兵士たちは親切に、救けてくれました。彼らも、私たちと同じ農民なのです。
いやおうなしに、おきてにしたがって国衙の兵士にされているだけたのですから、そして私は、やっと『租』をみやこのお役所におさめることができたのです。」
と、いいましたので、憶良はわれにかえりました。仁高はつづけました。
「けれども体がすっかり弱ってしまい、帰り道でおもい病気にかかり、今度こそたおれてしまいました。
そこへこの永長さまがとおりかがられたのです。仏さまのお導きというほかはありません。
おかけで体もよくなり、行基(ぎょうき)さまにもおめにかかることができて、僧にしていただきました。
もう、苦しみからのがれられたのです。
春になったら、こっそり故郷へかえり、行基さまのことを、みんなにつたえようと、思っています。」
「私は、労役につれてこられた肥前の国の農民なのです。
でも、あまりのきびしい労働にたまりかねて、逃げ出しました。
もちろん、つかまらなくても故郷へかえれば、重い罰です。
でも、私は、逃げたい一心でもう夢中だったのです。
あちらこちらとさまよっているとき、悪い奴にだまされて、すんでのところで深草の寺の奴にされるところを、幸運にも行基さまに救けられたのです。
労役につれてこられたものたちは、日に何人となく逃げ出しているということです。
逃げてもゆくところはないのに………。寺や豪族の奴になるか、のたれ死ぬのが、私どものゆくすえです。
でも、逃げます。そうしないではいられないのです。」
と、うったえるようにいう久延は、たくましい青年でした。としおいた僧の延明が
「飛鳥にある代々の天皇の宮殿、藤原のみやこ、みんな国の民のはたらきでできたものです。
朝廷のお役人の給料も国の民がつくりだしたものです。国の民は、朝廷から口分田をいただいています。
租税をさしだすことでお返しするのに、文句をいっているのではありません。ただあまりに、ひどすぎるのです。」
と、再び口をひらきました。憶良もこれには、うなずかないではいられませんでした。
香具山でゆきだおれている人をみてうたった柿本人麻呂の歌が、憶良の胸にせまってきます。
あれは、労役から逃げ出して、飢え死にした人だったのでしょうか。
それとも仁高(にんこう)のように、租税をおさめにきて、ゆきだおれたのでしょうか。
あるいは租税をおさめることもできず、一家をあげて故郷を逃げ出したものの、とうとうのたれ死んだのでしょうか。
そのとき阿麻留(あまる)が、いいました。
「憶良どの。律令制かゆきわたり日本が栄えようとすればするほど、こんな人たちがふえてゆくのはふしぎなことです。
農民たちが飢え死にするようなめにあっていて、どうして日本が栄えることができるでしょう。
行基は仏のおしえで、農民たちをすくおうと考えました。
朝廷の建てた寺の僧侶で、そんなことを考えるものは一人もいない、行基は立派な僧侶です。
さて、ぼつぼつかえるとしましょうか。羅城門がしまれば、家にかえれませんからね。」
外にでると日は山のかげにかげっていて、またいちだんと寒さがきびしくなっていました。
「もうこんな時間になっていたのか。」憶良はびっくりしました。
「長い間ひきとめて、お許しくださいよ、憶良どの。
しかし、私はどうしても、きいていただきたかったのです。彼らの声を………。
なぜといわれれば、それは、あなたに、詩人だから………とこたえるより、ほかはないでしょうな。
本当にありがとう。心から感謝します。」
阿麻留が、ていねいに頭をさげました。
「いや、阿麻留どの。おやまらなければならないのは、私のほうです。
私は、どうやら、あなたを誤解していたようです。」
「いや、わたしなどは虫けらです。行基(ぎょうき)こそ立派です。
なにごとにもめげず、自分をすててつきすすむあの勇気には頭がさがりますよ。」
阿麻留はがさがさと下草をふみながら、もう山をおりはじめていました。
3 泥棒市 top
二月十五日、元明女帝はみやこをうつすことについての、みことのりをくだしました。
朝廷の会議で決定したのです。場所はやはり、なら山の南にひろがるあの湿原でした。
『自分は徳のうすい身だのに、天の命じるままに天皇の位をついだ。
その任務の重いことを思うばかりで、みやこをうつすということにまで、思いをめぐらせているゆとりはなかったのだが、貴族や大臣の考えをいれて………。』
みことのりは、そのような言葉ではじまっていました。
みことのりがくだった日、祝いの会がひらかれ、憶良のような低い身分の役人までまねかれました。
けれども数々のごちそうを前に憶良は、なぜか気がはれませんでした。
それにいつも、きっと宴会ではとなりの席にいる阿麻留の姿が見えないのも気になりました。
宴会が終ると、憶良は、
「これを、家にもってかえっておくように、私は、ゆくところがあるので………。」
と、召使いの波止里に、朝廷からのくださりものを渡しました。
憶良は、阿麻留の家をたずねてみようと考えたのでした。
というのも、阿麻留はあのつぎの日からもう六日も、届けなしに役所をやすんでいたからです。
けれど大阿麻留の家にはだれもいませんでした。近くの人にたずねてみましたが、
「さあ………。」と、首をかしげるばかりです。
「阿麻留さまが唐からお帰りになっても、家族のかたや子供さんは、一度もみやこへはいらっしゃいません。
故郷におもどりになったままのようです。
阿麻留さまもほとんど、この家には、住んでいられなかったようですよ。」
憶良は、教えてくれた近所の人にお礼をいうと、歩きはじめました。
どこからか、梅の花のかおりがただよってきます。このかおりは、白梅でしょうか。
「長安では、いま、花のさかりだろうな。」憶良はつぶやきました。
みやこで近ごろ、庭木に流行しかけている梅の木も、唐からもたらされたものなのでした。
「八年も九年もつきあいながら、私は阿麻留どののことを、すこしも知らなかったようだ。
あの人は、唐でもいつものんだくれてばかりいたし、私も勉強に忙しかったから、それほど気にもかけていなかった。
一体、なにを考え、なにをしようとしているのだろう。」
憶良の足はいつか、羅城門のほうへむかっていました。
竹の内峠のちかくの、あの道場へいってみようと考えたのでした。
門のところまできたとき、
「あ、憶良さま………。」
役所の部下が青い顔をして、門をはいってきました。
「根麻呂くん。どうしたのだ。そのかっこうは………。」
だぶだぶの麻の服を着て、足もはだしです。
「そうだった。ゆうべ、きみの家へ泥棒がはいったという届けがきていたね。」
憶良はいいました。
けさ、役所のつくえの上にのっていた、根麻呂からの欠勤届けの木ふだのことを、思いだしたのです。
それには、『泥棒に、制服を盗まれたので、市へさがしにゆくから、一日、休ませてほしい。』と書いてあったのでした。
「あとで、家へいって、ようすをたずねようと思っていたのだが 盗まれたものは、見つかったのかね。」
と、憶良がたずねると、根麻呂は、半べそをかいて、こっくりうなずきました。
「はい、軽の市へゆけば、たいていのものは、見つかると人にきいたので、朝くらいうちから出かけたのです。」
「じゃ、よかったではないか。」
憶良がいいました。
「冠(かんむり)、沓(くつ)、制服(せいふく)、それから、妻のよそゆきの服と、布、かや、盗まれたものは、みんな、ありました。でも、買いもどせないのですよ。私がもっていった、布や籾だけでは………。」
根麻呂は、背中にせおっている品物を、ちょっと憶良に見せました。
「妻の親や、親戚、それに友だちの所から借り集めて、やっとこれだけのものをつくったのです。
あした、お役所で、給料の前がりをさせてもらおうと、いま、考えながらかえってきたところです。
なにしろ、物の値段がものすごく上っていますので。」
「そうか、もう一度、市へいってみないか。制服がなければ、役所にはでられないだろう。
私も、ついていってあげるから………。」
 |
そんなわけで、憶良は、竹の内峠とは反対の方角、三輪山のふもとにある軽の市までゆくことになりました。
軽の市は、昔からさかえているので有名なところでした。
もう、午をだいぶすぎていましたか市の通りは、ゆきかうもの売りや、大勢の買物客でにぎわっています。
どの店にも木ふだをつけた品物が山のようにつみあげられ、人いきれや食べものや、そのほか雑多なもののにおいがいりまじり、うきうきした感じでした。
憶良と根麻呂は、ほこりっぽい人ごみをかきわけるようにして、目当ての店へやってきました。
「あれ、あそこにあるでしょうし
根麻呂は小声でいいました。なるほど、つぼや食器、ざる、布なんかが、ごっちゃにならべてあるがらくたにまじって、青緑色の制服がおいてあります。
「あの服は、どのくらいかな。」
憶良がたずねると、店の主人がでてきました。
「とても高くて買いもどせないそうだが………。これがなくては、役所にでられないのだ。なんとかならないものか。」
「なんとかしろですって、たったこれだけの布と籾とで、ですか。
冠(かんむり)、沓(くつ)、帯(おび)と、ひとぞろい、みんなそろっているのですよ。
それに、絹の女ものの服やかや………。
とんでもありませんや、大損します。わしらだって、これで商売しているのですからね。」
憶良の制服を見て、下っぱと見たのでしょう。店の主人は、ばかにしたようにいいました。
「大損といったって、これは盗まれたものなんだぞ。」
根麻呂が まっかになってどなりました。
「おかしなことをいわないでください。ちゃんとわしどもは、籾と布で買いとったのですからね。
このうえ、いいがかりをつけるのなら市(いち)の司(つかさ)さまにきてもらいます。」
「まあ、まちなさい。私は役所の帰りで、なにももっていない。
この、すずりでなんとかしてもらえないだろうか。」
憶良は、ふところから、小さな石のすずりをだしました。
「憶良さま、な、なにをなさるのです。それはいけません。唐からもちかえられた、そんな大切なものを………。」
根麻呂は、あわてておしとどめましたが、店内主人は、すずりをすばやく手にもってしまいました。
「持ち歩きのできる小さなつくりだが、上等の石だときいている………。」
すずりは、こまかく竜をほりこんだ高価なもので、憶良自慢の品なのでした。
主人は手のひらの中にすずりをおいて、
「まあ、それほど、おっしゃるならよいでしょう。損なのですが………女ものの服もかやもおもちなさい。」
と、しぶしぶみたいにいったので、根麻呂はいそいで品物をかきあつめました。
「もしもし、お役人さまがた。布と籾もおいていってくださいよ。とんでもないお人たちだ。
こんな小さなすずりだけのつもりでいたのですか。この物の高いときに………。」
根麻呂は、もうかんかんに腹をたてて、主人につかみかかろうとしました。
「憶良さまの大切なすずりにむかって、なんということをいうのだ。ゆるさないぞ。」
「まあ、いいじゃないか。盗まれたものが、戻ってきたのだから、」
憶良は、あわてて根麻呂の服のそでをひっぱりました。
「なんてやつだ。憶良さま、すみません。」
市(いち)をではずれると、根麻呂はぽろぼろ涙をこぼしました。
「いいんだよ。根麻呂くん。あのすずりは、なければないですませられるけれど、きみは服が必要なんだよ。
それより泥棒ににいられないように気をつけることだね。」
憶良はいいました。
さっきの店の店先には、盗まれたものだとすぐわかるような靴の片一方とか、着ふるしの肩布とか、はんぱな品物が、いっぱいころがっていました。
近ごろ、泥棒がはやっているに、ちがいないのです。
二人は、夕陽にかかって、あるいていきました。
二上、葛城の山が晴れた空に、はりついたようにはっきり見えています。
その山なみのつづき、北へむかって信貴山、生駒山と連なっています。
「今度のみやこは、ずいぶん北へうつってしまうのですわ。飛鳥をはなれたくありませんのに。」
根麻呂がいいました。
「そうだね。けれども今日、女帝さまはみことのりで、天や地の相をうらなって、その相にかなったところをみやことさだめて、はじめて国の基(もとい)もさだまり、永遠になるのだとおっしゃっている。
またみやこは役人たちや民のためにあるので、天皇一人のためにあるのではないのだから、それが国の利益になるのなら、遠くであってもみやこは移さなければならない、とも………。」
と、憶良がいいました。
「それが、唐のある中華(ちゅうか)の国に昔から伝わっている考えかたなのですね。
それで、なら山の南の地は、うまくうらないにあてはまるのですか。」
根麻呂がたずねました。
「そのようだな。東西南北をまもる神々、つまり青竜(せいりゅう)、白虎(びゃっこ)、朱雀(すざく)、玄武(げんぶ)が正しい位置にあってみやこをまもるのだが、なら山の南の地はまさにぴったり、そのとおりの位置にあるのだ。」
憶良は答えました。
「私は武蔵の生まれです。先祖は小さいながらも昔は豪族でした。
父が稲たばをたくさん朝廷にさしあげましたので、外正八位下とひくくはありますが、位をいただくことができました。
そして私も学問所にやってもらい、こうして朝廷の役人になることができました。
何年かつとめて、正七位くらいにはなってかえるようにと父にいわれていますが、いつのことになりますか。
そんなことより、早く故郷へかえりたいと思いますよ。
友だちが、兵士にされて去年、租をおさめる人をおくって、みやこへきました。
あの時は楽しったです。二人で酒をのんで………。」
「武蔵はとおい国だ。草原がどこまでもつづいて、夕陽がひどく大きく見えるというではないか。」
憶良がいいました。このあいだ竹の内峠のあの道場でであった久延のことをふと思い出したのです。
久延もたしか武蔵の生まれだといっていました。
根麻呂はなつかしくてたまらないように、
「なにもかも、大和とは、まるでちがいます。
私の家は、国府(東京都府中市)のある郡のはずれの丘陵にあります。
朝や夕方には、それは美しい不二(ふじ=富士)の山が見えますし、秩父の山々もまぢかに見えるのですよ。
多摩川の流れは清らかで………魚が手づかみにできるくらいです。それはよいところです。
みやこの人は、言葉もうまく通じあわない、田舎者とばかにしますけれど………。」
憶良はうなずきながら、いいました。
「このみやこには、さまざまな人間が集っている。きみよりもずっと遠くの国からだってきている。
常陸や上総………陸奥のあたりなどは、片道四十日もかからねば、みやこへはこられない。
南の薩摩からは三十四日………。
きみは役人になるためにやってきている幸せ者なのだよ。
そんな人はわずかなもので、みやこへくるほとんどの人は、貢ぎ物を届けたり、労役や兵役のためにやってくるのだからね。」
「はい、友人の兵士も、そういいました。
彼がいなければ、そのぶん家では、妻や両親がはたらかなければならないので、それが気にかかっているのです。
武蔵は大和とちがって気候が荒々しく、冬は強い風がふき、川も沼もこおってしまいます。
でも、防人(さきもり)にされなかっただけましだ、ともいっていましたが………。」
「そうだな。防人になると筑紫までゆかねばならないのだからな。筑紫も遠いところだ。
夏は暑く、海はあらい。防人たちは、いつ東国へ帰れるかわからないままなれない土地で、せめてくるかどうかもわからない敵にそなえて、むなしい日をおくっているのだ。」
「ああ、憶良さまは、防人たちにあったことが、おありなのですね。筑紫で………。
東山道へはゆかれましたか。ずいぶん雪がふかいそうですね。」
「想像もできないほどだと、きいている。そんなことからも、みやこへ、人々はやってくるのだ。
東から西から、北から南から………。
きびしい気候、洪水、虫の害、飢饉(ききん)にめげず米をつくり、布をおり、海にもぐって魚をとり、山にはいって木をきりだし、みやこへはこんでくる………。大変なことだ。」
憶良は、つぶやきました。根麻呂は、
「女帝さまは、新しいみやこづくりにとりかかるのは、秋の取入がおわってからと、おっしゃっています。
でも、人々の苦しみなんか、本当には、わかってはいらっしゃいませんよ。
兵士の友人は、心をわけあう親友ですが、私に、こんなことをいうのですよ。
『おまえは、なんといったって、昔の豪族の家柄で、親父は郡司(ぐんじ=郡の役人)だ。
貢ぎ物をとりたてにまわるがわの人間たちの、農民の苦しみがわかってたまるものか。』と………。」
と、さみしそうでした。それから、思い出したように、
「阿麻留(あまる)さまはどうなさったのですか。ずっと、お顔が見えませんが………。
あの方はああ見えて、なかなか、いいところがあるのですね。
一か月ほどまえ、役所の井戸さらえがありましたね。
あの時、気分の悪くなった職人がいて、それを頭(かしら)がしかりつけていました。
そこへとおりがかった阿麻留さまは、薬を渡して、頭(かしら)に『休ませてやるように』と、たのまれたそうです。
私も水あたりをしたとき、薬をいただきました。
給食がかりの女たちにもたいそうな人気ですよ。わけへだてなく、おもいやりがおありなのですね。」
憶良は、根麻呂のおしゃべりを聞きながら、
――私はなんて、うかつな人間だったのだろう。
給食がかりの女にまでしたわれているのに、道場へつれてゆかれるまで、阿麻留どのの本当の姿に気がつかなかったのだから………。
一体、私は給食がかりの女たちと口をきいたことがあるだろうか………。
そういえば、阿麻留どのをたずねて、道場へいこうとしていたのだったな。
憶良の目はいつか、葛城山と二上山のさかいになっているあたりをみつめていました。
そこが竹の内峠で、峠の手前すこし左によったところに、あの道場はあるのです。
4 暑い夏 top
みやこが移るときまってから、朝廷の動きがきゅうにあわただしくなりました。
三月には、大臣はじめ役人たちの大移動か発表され、藤原不比等(ふびと)が右大臣になり、粟田真人(あわたのまひと)は大宰の帥(そち=長官)になりました。
唐から一緒に帰って副使の許勢祖父(こせのむらじ)は播磨守(はりまのかみ)、大位鴨吉備麻呂(かものきびまろ)は下総守(しもふさのかみ)です。憶良は従(じゅ)七位。
五月、まず記念の銀貨がつくられ、八月には銀貨とそっくりの銅銭ができあがりました。
唐のものにくらべると、できばえは上々とはいえませんが『和銅開珎』という文字がうきだしているところなど、なかなかたいしたものです。
けれども、長雨で麦の穂がくさったという報告があちこちから届きました。
今年も疫病が心配されることです。
九月にはいると、元明女帝が平城(なら)のみやこの敷地を見にゆくことになりました。
平城とかいて、“なら”と読ませることになっているのです。
十四日の早朝、女帝の行列はみやこの西のはずれをはしる下(しも)つ道をまっすぐ北へすすんでいきました。
さわやかな秋日和が約束されるような、つめたいすんだ空気のなかを憶良も道麻呂も行列のおともをしたのでした。
下つ道は新しく整備されていました。
この大路のつきあたるところが平城のみやこの羅城門(らじょうもん)となり、朱雀大路(すざくおうじ)をへて大極殿(だいごくでん)へとつながるはずでした。
平城の予定地は南北に長くひろがる大和の盆地の北のはずれで、そこは両側から山なみがせりだして、盆地をとじるかっこうになっていました。
休みながらの行列はつぎの日、予定地の西、生駒山のふもとにひろがる丘陵のあたり、菅原寺(すがわらでら)にとまりました。
「憶良どの。このあたりが大極殿になりますかね。」
道麻呂が、すこし小高くなっているあたりで足をとめました。
「たぶんそうでしょう。ここしか大極殿にふさわしいところはありませんよ。」
その日、菅原寺へゆく女帝とわかれて、憶良たちは予定地にやってきたのです。
「ひろいものですね。」
はじめてきた憶良は、その敷地のひろさに、まずびっくりしました。
南の方、遠くに大和三山が貝がらをふせたように見えています。
「これでも、長安の四分の一の大きさにしようとすれば、山をけずらなければならない。」
道麻呂がいいました。もう、新しいみやこの計画図はできているのです。
「あれが和珥(わに)氏の先祖の大塚ですか。」
今度は、北の方を見て、憶良がいいました。小山のような大塚が、見えています。
「いま、日本史の編纂を手伝っているので、わかったのですが、和珥(わに)氏はずいぶん古い家柄で、大和の大王たちに、きさきをたてまつっているのですね。
あの大塚は昔の勢力をよくものがたっていますよ。
それにしても、古くから住みついた土地をよく手ばなしてくれたものです。」
「代替地をもらっても移りたくはなかっただろうが、まあ、時の流れにはさからえない。
和珥氏もあきらめているのだろう。
藤原右大臣さまが、このあたりの土地をさし出されたこともあるしな。
あれ、あそこが春日山だよ。あれも右大臣家の土地だ。
朝廷の離宮も近くにあって、この旅の帰りには女帝さまもお寄りになるときいている………。」
と、道麻呂はいいました。
元明女帝は、新しいみやこの一部にめし上げられる二つの郡(こおり)の民に、貢ぎ物をへらすと約束されて、二十八日、藤原のみやこへもどりました。
もどるとすぐ、三十日に造平城京司(ぞうへいじょうきょうし)という役所をつくり、長官ほか大匠(おおたくみ=技師長)をきめて、そこことを発表しました。
伊勢神宮に造営の報告など、さまざまの手つづきをすませるともう十二月になっていました。
十二月五日、やっと地鎮祭(ちしんさい)を行うと、いよいよ本格的に工亊がはじまりました。
「それはそうと、これほど忙しいというのに、阿麻留くんは、一体どうしてしまったのだろう。
届けもでていないし、全く困った人だ。」
そんなある日、道麻呂が憶良にたずねました。
「役所に来なくなってかれこれ一年になります………。どうしたのでしょう。
なんの便りもありません。家にもいってみたのですが、あき家になっていましたし………。」
忙しさにとりまぎれて、あのあと道場にも、とうとう出かけずじまいだったのです。
それに憶良は、道麻呂にもあの道場のことは秘密にしていたのです。
すると道麻呂は、ほこりにまみれた大きなさかずきをだしました。
「これは、阿麻留くんのものではないかね。さっき書類だなのすみにころがっているのを見つけたのだが………。」
さかずきには『お酒は恋人』と大きな字でらくがきがしてあります。
「そうです。湯のみがわりに、いつもつかっていたものです。私が、あずかっておきましょう。」
さかずきを手にして、憶良はすこし悲しくなりました。
あけて和銅二年、正月からみやこをあげて、いや、日本の国じゅうをあげて、平城のみやこづくりにつきすすみました。
そんなときなのに、正月の月に『和銅開作』をまねて、早くも偽金がでまわりました。
三月には、陸奥、越後のえみしがはんらんをおこしかけているという知らせがはいり、討伐軍がおくられました。
けれどもそれとはかかわりなく、遠国、中国、近国から宮城づくり、みやこづくりのために農民が労役者として、ぞくぞくとおくりこまれてきました。
遠国、中国、近国は、みやこまでやってくるのにかかる日数でわけられているのです。
そして労役にくるものは、二十二歳から六十歳までの健康な男子ときめられていました。
十月から三月までは農閑期とされて五十日の労役、四月から九月までは農繁期になっていて三十日間、どちらにしても農民が家をあけることは、農業にとって大変な痛手になることは間違いありませんが、大宝律令でこのようにきめられているのです。
新しいみやこづくりの計画がすすむにつれて、憶良の忙しさも増していきました。
あんまり忙しくて、今年はひでりで、せっかく植えた稲がそだたないことや、月とともにふえていく工事現場から逃げだす労役にきた人たちのうわさにも耳を傾けているひまさえないくらいでした。
再びはじめられる国史編纂については、いろいろ調べることもありますし、長屋王の勉強会にも出席しなければなりません。
気がつくといつのまにか、夏もすぎ秋がきて、十月になっているしまつでした。
そんなある日、
「さっき、きいたのだが、逃げだす労役者をかくまって、自分の家の農地で働かせているものに、厳しい罰がくわえられることになったらしい。
逃げる者もふえるばかりだし、それにつれてかくまう者も多くなる。いずれにしても、困った問題だ。」
帰りしたくをしながら、憶良は根麻呂に話かけると、根麻呂は、にこにこして、
「憶良さま。いま、ここへ友人がきているのですよ。
用事をいいつかったとかで、役所へきたついでに、私を訪ねてくれたのです。
会ってやっていただけないでしょうか。」
根麻呂の友だちの青年は、役所わきの井戸のそばに立っていました。
二十四、五のがっしりした体付きでしたが、たいぶ疲れているようです。
「憶良さま、この真夜(まや)は、私のおさな友だちで、平城のみやこの造営にきているのです。」
真夜はぺこんとおじぎをしました。
「真夜も兵士の内麻呂も、小さい頃からの友だちです。みんな、いいやつです。
でも、私の父をえらく恨んでいるのですよ。なんとか、いってやってください。」 |
 |
根麻呂は、冗談めかしてわらいながらいいました。憶良は、
「きみがここへきているのは根麻呂くんのお父さんがえらんだせいではない。
労役や、兵士になることは、みんな律令できめられているのだ。農民の義務なんだよ。
きみたちが働いてくれなくて、どうして、みやこをつくることができるだろう。
で、あと何日、働かねばならないのかな。」
とたずねました。
「はい、十七日すぎましたから、あと十三日残っています。
でも帰りには十五日くらいかかりますから、家につくのは、ずっとさきです。
それでは、田のあとしまつをしないうちに雪になってしまいます。」
真夜は、わかりにくい東の言葉でいいました。根麻呂は、つけくわえるように、
「真夜の家には、弟が一人、あとはお母さんと妻と子供が二人います。
冬じたくをととのえるために、力仕事がいっぱいあるのに、弟一人ではとても手がまわらない、どうするだろうか………
と心配で、夜もねかれないのです。
それに、工事は朝から暗くなるまで休みなしで………。」
「土運びをしています。食事は一日に玄米八合に塩一勺、配給してくださいますが、でも、故郷とは気候も水もちがうので、おなかをこわしたまま、よくなりません。」
憶良は、うなずきました。
「お給料は、銭だとききました。それに、かえりの食糧はきちんとくださるのでしょうか。」
真夜は不安そうに、おどおどとたずねました。
「食糧は、もちろん心配することはない。
給料も、銭はすこしで、布や籾のほうが多いのだよ………。
それより、根麻呂くん。医者にみてもらうように、手つづきをとってあげなさい。
道麻呂さまにいえば、ちゃんとしてくださるはずだ。では、真夜くん。元気を出して頑張りたまえよ。」
そして憶良は、その場をさったのでした。
それから、一か月ほどして、根麻呂が青い顔で憶良にいいました。
「真夜(まや)が逃げたんです。あの日、護衛についてきていた兵士の内麻呂と二人で………。
真夜のかわりのものをつれて武蔵からやってきた兵士が、さっき知らせにきたのです。父にいいつかって。」
「逃げたって………。きみ、逃げても故郷へかえれば罰せられるのだぞ。
かくまったものまでむちうちの刑に処せられるのだぞ。」
憶良は真夜の顔を思いうかべました。まっくろに日やけした顔、白いきれいな歯なみ………。
「どこへいってしまったのだろう………。ばかなやつらだ。ああ、憶良さま、どうしたものでしょう。
どこかのお寺か。ゆたかな家の奴にでもなっているのでしょうか。
さがすといっても………。かわいそうなことをしたなあ。」
「まあ、まて、根麻呂くん。いまさら、きみがあわててみたところで、どうにもならないことだ。
無責任みたいだが、ぶじを祈るよりほか、方法はあるまい、」
憶良は、二人とも、あのような道場の人たちに救われてくれればよいのだが………、と、考えないでは、いられませんでした。
「きみ、行基という僧侶のことを知っているかね。」
憶良がたずねました。根麻呂は、ぼんやりと、首を横にふりました。
「さあ、元気をだしたまえ。そして、今度の休日には、新しく武蔵からきたものを連れてていって、力づけてやりなさい。 それがきみにできるたった一つのことなのだよ。」
その言葉に、根麻呂は悲しそうに、うなずきました。
top
**************************************** |