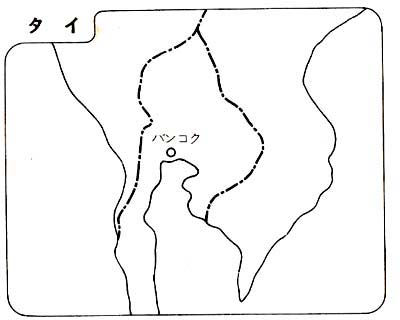|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章
第四章 揺れ動く政情
|
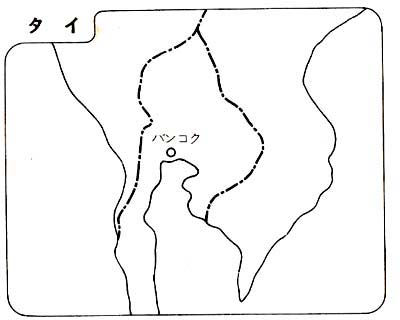
東南アジアの国々で完全な民主主義政体をとっている国は一つもない。
どの国でも国民の言論は制限され、監獄には政治犯がつながれ、政府は強大な権限を持っている。
そのことのゆえに、東南アジアの政治を未熟であるとして批難し軽蔑するのはたやすい。
しかし、東南アジアにそのような政治を余儀なくさせている背景を見逃してはならない。
財閥解体と農地解放を掲げ、そのために権力の集中をはかるフィリピン、マルコス政権の背後には、四〇〇年にわたる植民地時代に培われた大財閥への富の偏在と、大地主に収奪された極貧の農民たちがいる。
マレーシアの国内には、植民地からの独立をがち取るために戦った共産ゲリラが、そのまま反政府勢力となって潜伏している。
また、多人種間の対立という火種もある。 |

現在はミンダナオ島の東側にあるダバオが島の中心都市

|
インドシナ紛争の余波を極度に警戒しているタイは、一方で南部イスラム教徒ゲリラの独立要求にも大きな軍事力をさかなければならない。
東南アジアのなかで最も安定的に国を維持しているシンガポールでさえ、政府は強大な権力を持ち、完全な言論の自由は許されていない。
勿論、だからといって東南アジアでは、独裁が最も秀れた政治形態だというのではない。
しばしば独裁は汚職を生み、同族政治という弊害を生ずる。
フィリピンのマルコス政権やインドネシアのスハルト政権はそのよい例である。
この章では、西欧型民主主義だけでは律しきれない東南アジアの複雑な政治、社会状況と、独裁政治が腐敗した時に生ずる弊害を、実例によって紹介したい。
1 国反乱の地――フィリピン・ミンダナオ―― top
花の土地
“歌と詩に満ち溢れた、東洋の空の下に移植されたスペインの都市”
これは、名大統領といわれたキリノが、サンボアンガについて述べた言葉である。
|

サンボアンガ市中心部、スペイン人がつくった街。
|

イスラム、スペイン、アフリカの三様式が混合した市庁舎
|
|
現在はミンダナオ島の東南にあるダバオが島の中心都市 |
フィリピン、ミンダナオの西南端サンボアンガは、確かに、時に起こる銃撃戦やバイジャックさえなければ、フィリピンで最も美しく、最も魅力的な南海の楽園といってよいかもしれない。
人口二〇万、スル海に面したサンボアンガ市の中心部には、サンボアンガの北、ダピタンに流され、その後処刑された独立の父、ホセ・リサールの像が建ち、像の周りには、“愛情”“正義”“芸術”といった、リサールが生存中、身をもって示した価値が、スペイン語で彫られている。
その国民の英雄の像と向かい合って市庁舎がある。
一九〇七年、アメリカの統治時代、ミンダナオ全体を統治する軍政府の庁舎として建てられたものである。
全体の建て方はアメリカ風だが、屋根とバルコニーはスペイン風でバルコニーを支える木彫の支えはイスラム風と、三つの建築様式が混然と混り合っている。
その建築様式に、ミンダナオが置かれた複雑な歴史が象徴的に表れている。
街のなかにはカトリックの教会やマリア像が多い。
墓石の碑文にもスペイン語がみられ、この地方で日常使われている方言チャバカノに到っては、七〇パーセントがスペイン語である。
サンボアンガはスル諸島の北の端に位置しており、先住民は島伝いに船でやって来たらしい。
まず、マレー系の人たちが渡来し、色とりどりの匂い皀かな花が咲いているのを見て、この地を定住の地とし、シャンハンガンと名づけた。
シャイハンガンとは“花の土地”という意味である。
その後、南のスル諸島から、精悍な海賊として恐れられていたバジャウ族やサマル族が、ピンタと呼ばれる木造の小船を漕いでやって来た。
台風地帯の外に位置し天候の安定しているスル海は、サンゴ礁が多く、紺碧というよりもコパルト色に近い。
海を生活の根拠とするイスラム教徒たちは、眩しいほどに白く輝く浜辺に高床式の家を建てて住みついた。
スペインの統治
そのイスラム教徒の楽園が戦乱の地になったそもそものキッカケは、一五六五年のレガスピーの遠征にさかのぼる。
最初に、この地に足を踏み入れたスペイン人、フランシスコ・コンペは「ミンダナオとホロの歴史」という本のなかで、この一帯を極東と東南アジア、さらに南西の海への出入口と書いている。
スペインは、フィリピンを東洋へのカトリック伝道の拠点とし、同時にポルトガルの香料貿易独占に割り込む基地にしようと図ったのであった。
イスラム教徒に対するスペインの統治は苛酷で徹底したものであったらしい。
彼らはこの地域に住むイスラム教徒を一括してモロ族と呼び、厳しく貢税、夫役、強制供出を課した。
また、キリスト教に改宗させるために、聖俗の制度もつくった。
それでも改宗しないイスラム教徒は、力で南へ追いやられた。
一時マニラ周辺にまで及んだイスラム教徒の勢力は、こうしてスペイン統治時代に、完全にミンダナオ南部とスル諸島に封じ込められてしまった。
しかし、抑圧されたイスラム教徒たちは、かえって強い抵抗を示し、しばしば反乱の火の手を上げるようになる。
サンボアンガの町を東へ出外れた辺りに、イスラム教徒撃退の前進基地としてつくられた要塞がある。
一六三六年、スペインの神父メルチョール・デ・ペラによって建造されたもので、ピラール砦と呼ばれている。
ヨーロッパ列強の激しい植民地争奪戦のなかで、一六四六年にオランダの砲撃を、一七九八年にはイギリスの侵略を見事に撃退したこの砦も、ついにイスラム教徒を完全に制圧することはできなかった。
サンボアンガ港
砦から見下ろすサンボアンガ港には、香港やオーストラリアからやって来た外国船や、色とりどりのマストを立て、太い竹を船体の両脇にさし渡した、ビサヤからやってきた漁船が停泊しており、その間を、ビンタと呼ばれる手漕ぎの船が動き回っている。
スル諸島沿いに、インドネシアや東マレーシアへ行き来する玄関口にあたるサンボアンガ港は、フィリピンきっての漁港であり、椰子油の積出し港であり、麻の集散地でもある。
とりわけ水産資源は豊かで、魚は年間二万トンを越す水揚げがある。
スル海、パシラン海峡それにモロ湾の一帯は、魚の他、天然真珠。黒珊瑚、さらに装飾用の貝も獲れる水産物の宝庫なのだ。
港に隣接する魚市場には、早朝四時ごろから帆かけ船や手漕ぎのビンタが魚を満載して集まってくる。
獲れた魚を種類構わず売りにやってくる漁民は、ほとんど皆イスラム教徒で、岸壁の上で買い上げる仲買人はクリスチャンである。
時に買叩かれたイスラム教徒の漁民と、クリスチャンの仲買人の間でいさかいが起こることも珍しくない。
魚の仲買だけでなく、街の商業の中枢はクリスチャンと華僑が握っており、スル海経由でインドネシアやマレーシアの商品を運んでくるのはイスラム教徒である。
その多くは税関を通らない密輸品で、酒、煙草からシンガポール製の傘まで、市場のなかで堂々と売られている。
市場は一種の無法地帯で、貧乏なイスラム教徒は、観光客をみるとオパールや黒珊瑚を売りつけにくる。
だがそのほとんどは贋物で、本物そっくりにみえるオパールはコーラのビンの底でつくったものである。
クリスチャンのガイドや運転手は、勿論そのことをよく知っているが、報復をおそれて口をつぐんでいる。
そのイスラム教徒を威圧するように、岸壁には南西ミンダナオ地区司令部所属の軍艦が横づけされ、砲口を市場にピタリと合わせている。
アヤラ農場・キリスト教徒入植地
市街地から西北へ、南西ミンダナオ地区指令部の前を通り抜けて二〇キロほどいった辺りに、見渡す限り広がる農園がある。
キリスト教徒の入植地アヤラ農場である。
六〇〇家族、三、〇〇〇人が住み、米、トウモロコシ、野菜、砂糖キビなどを栽培している。
三五歳になるエボルも、父親の時代にビサヤからやって来た。
政府から二ヘクタールの土地を借りうけ、一年に二度陸稲をつくっている。
年間の収入は五、〇〇〇ベソ(二〇万円)から一万ペソ(四〇万円)のあいだ。
耕作面積としてはこの辺りで一番小さいほうだが、土地の借用料が安いことと、家族が夫婦の他に子供二人だけという少人数であることもあって、生活は楽なほうだという。 |

アヤラ農場――水牛を使って脱穀するエボル家。
|
一九〇〇年代のはじめ、スペイン領からアメリカの統治に変わった当時のサンボアンガの人口は、僅か一三万人に過ぎず、スペインの根強い布教活動にも拘らず、ほとんどがイスラム教徒であった。
それが、アメリカが支配するようになってルソン島やビサヤ地方からキリスト教徒の入植が進められ、そのために総人口はみるみる膨れあがり、イスラム教徒とキリスト教徒の比率は一挙に逆転した。
現在、サンボアンガの人口は一六〇万人をこえ、イスラム教徒とクリスチャンの比率は二三対七六七ある。
エボルの両親も、こうした入植政策の一環としてやって来たのだった。
しかし、アメリカ植民政府のとったキリスト教徒の移民政策は、イスラム教徒の先住権を全く認めないものであった。
イスラム教徒たちの土地は、法的には国有地とされ、次々に入植者に貸し与えられた。
また、僅かにイスラム教徒の耕作地として残された土地も、夜のうちに境界線が引きなおされ、イスラム教徒は日々土地を失っていったという。
その土地争いが改宗を押しつけられたイスラム教徒の怒りに火をつけた。彼らは武器をとり、山にこもり、ゲリラ戦を展開するようになる。
「座して破滅を待つよりも、反撃するほうがアラーの御心に適う」というのである。
フィリピンが独立した後も、彼らの政府に対する不信感は変わらず、やがてイスラム教徒圈の独立を唱えるようになった。
こうしたイスラム教徒の言い分を、しかしキリスト教徒は一言のもとにしりぞける。
「イスラム教徒はただ先に住んでいただけであり、元々農耕などはしていなかった。
生来怠け者の彼らは、気が向いた時だけ魚を獲り、金がなくなれば海賊に早変わりする。
とりたてて産業のないサンボアンガを発展させ、人々の暮らしを向上させてきたのは我々キリスト教徒なのだ」
確かにキリスト教徒の言い分にも一理はある。
イスラム教徒の多くは海で生活しており、農耕もせいぜい焼畑程度であった。
土地を丹念に耕し、収量を増大させたのは、キリスト教徒の努力に負うところが多い。
エボルたちは、ここに入植してからバエアンと呼ばれる相互援助組織をつくり、協力して耕作を進めている。
しばしば集会が開かれ、一軒の家から代表一人が出席し、お互いのなかから選んだ議長の下で耕作法や肥料の施し方などを議論し合う。
時には県の役人を呼んで勉強することもある。
ミンダナオでも最高の灌漑施設を持つこの辺りは、米だけは一年に二度、七月と一月に収穫できるが、野菜は全部よそから買っている。
肥料がじりじりと値上がりしているので、何とかして野菜をつくり、二〇パーセントの収入増を図りたいというのが、アヤラ農場の当面する最大の課題である。
そのアヤラ農場も、政府軍とイスラム教徒ゲリラの戦闘激化の影響を強くうけはじめている。
戦闘で家を焼かれた難民が、この農場にも流れ込んできており、エボルの家にも逃げてきた親戚二人が、家事の手伝いをしながら住みついている。
彼らのイスラム教徒に対する憎しみは驚くほどで、「良いイスラム教徒は死んだイスラム教徒だけだ」と言いきる人さえいる。
日曜日の朝六時、この日ばかりは畑仕事の手を休んで、着飾った人々が農場のなかにある教会にやって来る。
スペインは、血縁中心の小社会、パランガイを構成していた人々を、“教会の鐘のきこえる”範囲に集め、プエブロと呼ぶ単位をつくった。
アヤラ農場の人たちも全員熱心なクリスチャンで、教会の牧師はスペイン人である。
敬けんな祈りを捧げた後、男たちは安息日を町外れの闘鶏場で過ごす。エボルも闘鶏場通いを欠かしたことがない。
闘鶏場は、真ん中のリンクを囲んでスリ鉢のように観覧席が設げられており、入口には「サンボアンガスポーツセンター」と書いた看板が掲げられている。
その闘鶏場が朝早くから人で一杯だ。
フィリピンの闘鶏は日本のそれに比べてはるかに残酷である。
訓練された鶏の足には研ぎすまされたナイフがしばりつけられており、片方の鶏が血を吐いて死ぬまで闘いがつづけられる。
血統のよい熟達した鶏は飛び違った時、一閃で相手の動脈を切り、勝負は一瞬でついてしまう。
しかし技量が伯仲している場合には飛び違い切り合い、しかしそれが致命傷にはならず、勝負がつかぬまま両者ともに動けなくなってしまうことがある。
しかし、それでも立会人は喧嘩をけしかけ、一方が眼を閉じこと切れるまで闘いを止めることは許されない。
フィリピン人の賭博好きは世界でも有名で、マニラ辺りではハイアライ、ビンゴと事欠かないが、サンボアンガでは闘鶏が唯一の大衆賭博である。
僅かな日銭でも稼ぐのが大変なこの土地で、人々はなけなしの金が無くなるまで賭けるのをやめようとしない。
鶏もアメリカや南米から血統書付の、一羽数十万円もするのを買って飼育している人もいる。
陽気で楽天的だが激しい気性を持っているという点では、ラテン系人種の影響をうけてきたキリスト教徒もアラーを信じるイスラム教徒も変わりがない。
サンボアンガには「言葉で傷つけられるよりはナイフで傷つけられるほうがましだ」という諺があるぐらいだ。
タロクサンガイ・イスラム教徒の村
アヤラ農場と街を挟んで反対側、ピラール砦の銃砲が砲口を向けている東側には、イスラム教徒たちの住む村々がある。
市の中心部に近い村は比較的平穏だが、遠く離れるにつれて小ゼリ合いが多くなり、サンボアンガ・デル・スルといわれる東部では激しい戦闘が繰り返されている。
東部に通ずる道には政府軍の検問所が置かれ、バスや車は、積荷に到るまで厳しくチェックされている。
その検問所から東へおよそ三〇キロ行った所にイスラム教徒の村タロクサンガイがある。
サンタクルス島とパシラン島に向かい合う、半農半漁の村である。
キリスト教徒は検問所から先へは行きだからないから、タロクサンガイに入るためには、村長にも顔の効くイスラム教徒の運転手を探さればならない。
そのタロクサンガイに入った我々は、銃を持った目つきの鋭い男たちにいきなりとり囲まれた。
運転手にきくと政府の者かと疑っているらしい。
「日本のテレビの者だ」というと、今度は物珍しそうな顔に変ったが、「危ないから早く村長の家へ行け」という。
軍隊かと思ったら、これが自警団であった。
フィリピンでは、一九七二年、マルコス大統領が戒厳令を布いてから、武器の所持は固く禁じられている。
銃砲の不法所持は、死刑または無期懲役という極刑が課される重罪である。
それが、イスラム教徒の村だけは自警団の存在が許され、武器の所持が容認されている。
村長サワニ・アサリは、まだ三十代半ばの痩ぎすのインテリであった。
スル諸島の州都ホロ島の出身で、かって中学校の校長をしていたという。
一九七四年の大反乱の時に家を焼かれ、十二人の家族が着のみ着のまま、このタロクサンガイに逃げてきたのであった。
アサリの父親はサルタン(土侯)の血を引いており、母親は二代前がアラブの人である。
いわば名門の出で、島ではダトー(イスラム教徒の世俗的称号。いわばイスラム世界の貴族)を称していた。
アサリの妻テレシタもアラブの血をうけた彫りの深い美人である。
イスラム教徒の社会では、アラビアの血をひいている人は、神アラーに近い人として尊敬されている。
アサリ夫妻が見知らぬ土地に住みついて間もなく村長になれたのも、こうした血筋が大きな力になっていたのに違いない。
アサリの話によると、村には村長の他に六人の村議会議員がいるが、東部の戦闘が激しくなるのにつれて、難民が続々と村に入り込み、今では村長の影響力もほとんどなくなってしまったという。
誰が政府側なのか、誰がゲリラに通じているのかさっぱり分からず、お互いに疑心暗鬼なのだ。
盗みや喧嘩は日常茶飯事である。
この日の朝も男二人が女のとり合いで争い、一人が相手の口に銃口を突っ込み殺して逃げたという。
はっきりした殺人事件なのに警察はこわがってやってこない。結局自分の身は自分で守るしかないらしい。
アサリの家にも用心棒が四、五人ごろごろしている。海に出たいというと、早速三人の護衛をつけてくれた。
海は抜けるように青く、あちらの村こちらの村から、スル諸島特有の色どり豊かな帆をかけたビンタが漁場めがけて走ってゆく。
海から見たタロクサンガイは眠っているようにのどかで、海に張り出した家並みの向こうで村のモスクのドームが金色に輝いている。
対岸のサンタクルス島は起伏もなく、大きな木もない偏平な島で、海岸は輝くような祖い白砂で、珊瑚礁の間を熱帯魚が泳いでいるのが透けて見える。
この楽園のような島で、新婚旅行中の日本人女性関陽子が誘拐されている。
末広丸がバイジャックされたのも、スル四号の乗組員や南洋真珠の潜水夫が連れ去られたのもすべてこの近くである。 |

海賊の横行する海、タロクサンガイ沖合い。
取材班には、自動小銃を持った護衛がついた。
|
誘拐され九日本人が監禁されていたバシラン島はサンタクルス島のさらに裏側にある。
この辺りは最高の漁場で、帆をかけた船があちらに数隻、こちらに数隻とかたまって漁をしている。
「もっと近くで撮影したい」と言うと、一度は一〇〇メートルほどの距離まで近寄ってくれたが、すぐ向きを変えて全速力で逃げ出した。
「村が違うから危い」というのだ。
この辺りでは漁場の取り合いから銃撃戦になることは珍し卜ことではない。
しかし、さらに「少しでも……」と頼むと、船は一度タロクサンガイに引き返して、今度はピカピカの自動小銃を抱えた迷彩服の男を連れてきた。
何者かきいてみたが、押し黙ったまま返事もしない。
漁場に近づいてみると、一見静かに網でも投げているのかと思っていたのが、実はダイナマイト漁なのであった。
屈強な男が水中眼鏡をかけて水中にもぐり、魚がいるとみるとダイナマイトを仕掛ける。
勿論、ダイナマイト漁はフィリピンでも禁じられている。
しかし、ここではダイナマイトと武器がインドネシアとマレーシアからの密貿易の目玉商品なのだ。
そのタロクサンガイでミスコンテストのパレードを見た。
近隣の四つの村からそれぞれ一人ずつの代表を選び、そのなかから女王を一人決めるというのだった。
タロクサンガイのミスは村長サワニ・アサリの四女コラソンで、まだ一四歳である。
しかし身体はもう立派に大人で。顔立ちも母親に似て彫りの深い美人だ。
会場の中学校の周りは、太鼓を叩き笛を吹く速成の楽隊がぐるぐる回っており、両親につきそわれた四人のミスたちは、いずれも華やかなロングドレスを着て、いささか緊張気味である。
しかしこのコンテスト、審査員が票を投ずるのではなく、順位はすでに決っていた。
中学校再建の寄付を募り、納めた金額の多い順に順番が決められるのであった。
サワニ・アサリの娘コラソンは三位と発表された。
この辺りでは、男性が、結婚する相手の両親に多額の金品を引出物として贈るしきたりがある。
金のない男は気に入った娘を迎えられないばかりか、一生結婚できないことすらある。
言い換えれば、一軒の家にとって女の子は貴重な財産であり、女の子をたくさんもっていればいるほど多額の金品を受取ることができるわけだ。
アサリの家は男の子は一人だけ。あとの九人は皆女の子である。
すでに上の三人はかたづいており、その度にアサリ家は豊かになっていった。 |

ミス・タロクサソガイとなったアサリの娘コラソン
|
しかしそれだけにしっとやねたみを買うことも多くなるわけで、公共の物への寄付は、いわば身を守る手段なのである。
今政府が何よりも強く寄付を募っているのは、難民収容所の建設資金である。
すでに赤十字、社会福祉省、それに軍が協力して難民復帰プロジェクトをつくり、サンボアンガ周辺にもいくつかの難民村がつくられたが、とても、それだけで足りるわけがない。
自分で仮小屋を建てて住んでいる者や、ジプシーのように村々を転々と渡り歩いている者まで含めると、難民の総数は百万を越すだろうとみられている。
治安は悪くなる一方で、金持ちで政府に協力的なアサリの命は風前の灯だという人さえいる。
マルコス大統領も難民問題には頭を痛めており、
「これだけの数の難民に衣食を与えるのは不可能だ。早く故郷に帰って欲しい」
と呼びかけているが、あえて戦火のなかに帰りたがる人がいようはずもなく、難民は増える一方である。
その難民の過半数は、激戦地、バシラン島やホロ島からの避難民である。
ゲリラの聖地・ホロ島
全市が焼野原になったスル諸島の州都ホロは、ホロ民族解放戦線の拠点であり、また思想上の聖地でもある。
解放戦線の掲げるスローガンは、イスラム教圏の独立要求である。
つまりミンダナオ南部とスル諸島は、歴史的にも文化的にも、さらに生活圏という点からも、フィリピンの他の土地とは異質であり、むしろ、インドネシアのカリマンタンや、マレーシアのサバ・サラワクに近いというのである。
そこから、カリマンタン、サバ、サラワクに、スル諸島とミンダナオ南部を含む独立国家構想が生まれてくる。
そのホロ民族解放戦線の思想上のリーダー、元フィリピン人学教授のヌル・ミズワリはスル諸島の出身である。
またホロ島の反乱軍のリーダーは、サルタンの血をひく、前ホロ市長の長男である。
そのホロ島取材は、正規の手続きをとる限り、まず不可能といってよい。
ホロ島の帰趨(きすう)は、ミンダナオのイスラム教徒の反乱全体に決定的といってよい影響を持つだけに、島への出入りは軍が厳しく制限しているからだ。
その厳戒のホロ島に私たちは都合三回潜入を試みた。
最初ホロ島に入った一九七五年ごろは、焼打ち後、間もないこともあって、島への出入りは極度に厳しく、航空券を手に入れることすら至難の業であった。
軍指令部の許可証なしに外国人に切符を売ることは固く禁じられていたのだ。
しかも、軍指令部が外国の特派員にホロ島取材の許可証を出すことなぞ、あり得ないことである。
しかし、この最初の難関はフィリピン人になり済ますことで、意外に簡単に通過することができた。
幸いというべきか、フィリピン人に間違われるのが不思議でないほどに色が黒いことと、同行した運転手のチャバカノと我々のダンマリ戦術が見事に効を奏したのであった。
航空会社のカウンターは、拍子抜けするほどにすんなりと切符を売ってくれた。
しかし思わぬ成功に、これで八分通りうまくいったと思ったのが間違いだった。
ホロ島への一番機は早朝六時である。
早いほど警戒が手薄だろうと踏んだ我々は、まだ暗いうちに起きて空港へいそいだ。
夜明け前の空港は電灯もつかず静まり返っている。
闇のなかで、時々金属の触れ合う音と靴音がするのは、見回りの兵士に違いない。
空港にはいつも一個小隊ほどの政府軍兵士が駐留しているのだ。
しばらく待つうちに、カウンターに電灯がつき、ぼつぼつとやって来た乗客が手続きを始めた。
乗客は全部で二〇人ほどだろうか。
その後に並んで航空券を搭乗券に換え、民間人の女性に手荷物を見せた後待合室に入る。
このままゆけばうまくいきそうだと思っていたところへ、若い兵士が眠そうな目をこすりこすり現れた。
搭乗前にもう一度荷物を改めるというのである。不吉な予感がしたが、ここまできたら何喰わぬ顔で並ぶしかない。
次々に義務的に荷物を改めていた兵士の目が、カメラを見つけ九時キラリと光った。
「どこから来た?」
「マニラだ」
「何国人かときいているんだ」
「日本人だよ」
「ではだめだ」
「何かだめなんだ」
「飛行機には乗れないよ」
「そんな馬鹿な。搭乗券があるんだよ」
「どうして手に入れたんだ」
「町の航空会社で買ったのさ」
「では、ソメラ少佐の特別許可証があるのか?」
「そんなものはない」
「それではだめだ。帰れ」
「冗談じゃない。ほれこの通り情報省からもらったプレスカードを持っている。
これはどこで取材してもよいという、あなたの国の政府がオーソライズしたものなんだぜ」
「とにかくだめだ。ソメラ少佐のサインがない限り絶対だめだ」
相手はテコでも動かない。業を煮やして、いちかばちかハッタリをかませてみた。
「書付こそ持っていないが、ソメラ少佐にはすでに会って取材の許可を貰っている。
我々の搭乗を拒否して、あとでソメラ少佐に叱られても知らないよ」
その一言は効いた。
ソメラ少佐とは、南西ミンダナオ地区指令部のキレ者の情報将校で、民間人に対しては絶対と言ってよい権力を持っている。
しかし結果的にこれは失敗であった。当惑した兵士は寝ていた上官を起こしに行ってしまったのである。
やがて連れていかれたのは四畳半ほどの薄暗い部屋。机を挾んで正面に痩せた小柄な男が下着にサロンを巻いたまま座っている。
その顔を見て、まずかったと瞬間的に思った。
狐のような細い目に残忍な光がみなぎっている。その上、寝起きの不快感が全身を被い、会うなり、
「拘留されたいのか?」と、上目づかいに浴びせかけてきた。
どこの出身か知らぬが、語尾の上がる妙なアクセントをしている。
「夜が明げるまでここで待っていろ。オフィスが開けばお前たちの嘘はすぐ。バレルさ」
背筋がぞっとする。こうなればもう逃げの一手しかない。
ソメラ少佐に会ったのは事実だが、ホロ島の取材まで許可されたわけではないからだ。
「いやそれには及ばない。切符も簡単に手に入ったし、手続上問題はないと思っていたんだ。
それをあなたの部下にいきなり駄目だといわれて思わずかっとなって……。
いやお手数をかけて申し訳なかった。ソメラ少佐にはいずれ頼みにゆく」
長居は無用と部屋を出かかった我々の背に狐のような下士官は鋭く言った。
「切符を売った航空会社の社員は、今日中にクビにする」
数日後、破壊されたコレラ研究所の視察団の一行として、結局、焼打ち以後外人記者としてははじめて入島を果たすのだが、飛行機のなかでも大勢の兵士が目を光らせており、またホロ島の飛行場でも身分を調べられ、改めて規制の厳しさが一筋縄ではないことを知った。
焼打ちの跡
反乱一年後のホロ島はいささかの復興の跡もなく、焼打ち直後の姿をそのまま残していた。
ホロは海に面した人口五万人ほどの小さな町で、後は三方を山で囲まれている。
政府軍が抑えているのは市の中心部だけで、解放戦線は山にひそみ市を威圧している。
市民の多くは海の上に張り出した水上家屋に住んでいた。
その水上家屋は完全に焼き払われ、黒く焦げた杭だけが海面に林立している。
モスクのドームもキリスト教会も破壊され、コンクリートの柱には弾痕が生々しく残っている。
事件の日、つまり一九七四年の二月七日から八日にかけて、ホロ島に停泊していたマグロ船に同乗していた、日比合弁漁業会社の伊藤光俊社長は、当夜の模様をこう証言している。
「七日、ホロ島に着いた時、いつになく街が静まり返っていました。 |

焼打ち後のホロ島――残っているのは水上家屋を支えていた杭だけ。
満潮時には海水の下に没する。
|
道をゆく人も、車も少ないので不思議に思いきいてみますと、この日、戒厳令に基づく武器狩りが行われるというのです。
ホロ島民の九〇パーセントはイスラム教徒で、解放戦線を心情的に支持している人が多いことは知っていましたから、彼らが果たして、おとなしく武器を渡すだろうかと、不気味な予感がしました。
政府に不信感を持っている彼らにしてみれば、武器を取り上げられた上で一方的に屈服させられるのではないか、という疑惑をもったとしても不思議はないのですから。
私の予感を裏づけるように、夕方になると何人かのイスラム教徒の船員が、親や親戚を連れてやってきて、一晩だけ泊めてくれと頼むのです。
果たして、夜半過ぎに銃声が起き、やがて艦砲射撃も含め激しい銃撃戦が数時間もつづきました。
火の手が上がったのは、銃撃戦が終ってしばらくした早朝のことでした。
炎はたちまち全市を被い尽してしまいました。
その後、軍の要請で難民を何回かサンボアンガまで運びましたが、港には死体が鮪のようにゴロゴロ並んでいました」
ちなみに伊藤社長は、その後しばらくマグロ漁と買付に精力を注いでいたが、イスラム教徒に網を盗まれたり詐欸まがいの被害に会ったりして、ついに事業から手を引き、今は日本で予備校を経営している。
では、火は誰が放ったのか?
ホロ市内できいた話を総合すると、よそから来た政府軍が放った疑いが濃厚である。
保健所長、市役所の役人、看護婦など、政府軍兵士が火を放ち物を略奪して卜るのを目撃したと証言する人は多い。
しかも、その証人の半数以上はキリスト教徒であった。
日本の援助によって建てられたコレラセンターも破壊され、目ぼしいものはあらかた略奪されていた。
冷凍庫、温度計、顕微鏡はわかるとして、薬は中身が捨てられカンだけ持ち去られている。
なんと、カンは水浴に必要なのだそうだ。
反乱に際していくつかのドラマがあった。サワニ・アサリをはじめ、多くの難民がサンボアンガに逃れたのもこの時である。
しかし、進退に一番悩んだのは市長であったろう。
この時の市長アブバカールはマルコス大統領に協力することを誓い、解放戦線側からは裏切者としてうらみを買っていた。
しかし、今回の反乱の張本人はわが息子である。
市長は軍が怒りのあまり、親の市長にも危害を加えるのではないかと恐れた。
迷いに迷った揚句、彼は長男がいる山へ走った。しかし解放戦線に身を投ずる気にはどうしてもなれない。
しばらく山にとどまった後、軍艦がホロの港にきたことを知った彼は、山を下り海軍に身を預けた。
陸軍よりは海軍のほうが紳士的だと思ったのだと、彼は後で話している。
海軍は市長をマニラに運んだ。そしてマルコス大統領は投降した市長を利用した。
獄に投ずる代わりに大統領官邸に招じ入れ肩を抱き、その姿をテレビや新聞を通して報道させたのである。
「解放戦線に関係のある者でも、投降する者は暖かく迎え入れる。政府はあなた方を受け入れる用意がある」
ということをPRしたのであった。
それほどまでにマルコス大統領は、ミンダナオのイスラム教徒の反乱に手を焼いていた。
莫大な軍事費を投じてもゲリラをせん滅できない。
大体、戦意の上から言っても、解放戦線の兵士一人を殺すために、政府軍兵士二〇人が必要だというのである。
しかし、何よりもマルコス大統領を窮地に追い込んだのは、アラブ産油国の出方であった。
解放戦線に、同じイスラム教徒として連帯感を抱く彼らは、マルコスがミンダナオのイスラム教徒を弾圧するなら、石油の輸出を止めると脅したのである。
そもそも、モロ民族解放戦線の背後には、リビアの元首カダフィーと、サバ州の州首席大臣ムスタファがいるといわれていた。
リビアは金と武器を送り込み、サバ州は武器を提供するだけでなく、ゲリラの訓練基地になっているというのである。
こうしたイスラム教圈の支持をさらに拡大するため、解放戦線は毎年、イスラム教国の会議に代表を送り、マルコス大統領の非道ぶりを訴えている。
ルソン島の共産ゲリラが壊滅した現在、ミンダナオ問題はマルコス大統領の最大の足枷となっている。
力による弾圧の一方で、マルコス大統領は様々の宥和政策を講じた。
宥和策
激しいシャワーがあがったばかりのある朝、イスラム教徒の村タロクサンガイに二人の政府軍将校がやって来た。
軍帽の代わりにターバンを巻いた二人は、いずれもイスラム教徒の中尉である。
訪問の目的は軍のイメージを和らげ、政府軍に協力を要請することであった。
年配のサリド中尉が村の人に配っている紙にはこう書かれていた。
「残念なことだが、最近恐怖にかられた政府軍兵士が酒を飲んで発砲したり、金に困って庶民から金品を強奪するという事件が頻々と起きている。
そしてこうした政府軍兵士の非行を訴え取り締まりを願う手紙が毎日山のように寄せられている。
なかには軍指令部は、こうした非行を見て見ぬふりをしていると不信の念を示している人もある。
しかし軍当局は、このような不届きな兵士は即刻逮捕し、敝しい処罰でのぞむ積りでいる。
政府軍の努力を認め、諸君も軍の任務遂行に是非協力して欲しい」 |
文章の最後には、参謀総長、ロメオ・エスピノとあった。政府と軍当局は庶民の味方であることを示すPRである。
この文章を説明した後、中尉はモスクに入り、村人と一緒にメッカに向かって祈りを奉げた。
イスラム教徒の説得には同じイスラム教徒の軍人をあたらせる……。
そこに、この争いが単なる宗教戦争でない一面をのぞかせる反面、政府の必死の想いを読みとることができる。
軍だけではない。イスラム教徒の子供をマニラのキリスト教徒の家に寄宿させたり、イスラム教の学校とキリスト教の学校の親善体育大会を開いたり、イスラム教徒の子弟に優先的に奨学金を与えたり、およそ考えつくあらゆる宥和策を講じた。
しかし、こうした懸命の努力も決定的な解決策になっているとは言い難い。
キリスト教徒からは、イスラム教徒を不当に優遇し過ぎるという不満が上がっている。
「我々キリスト教徒が人を殺せば、まず終身刑は間違いないのに、イスラム教徒は人を殺してもすぐ釈放される」とか、
「何故彼らだけ武器の所持を放置しているのか? すぐにでも取り上げるべきだ」というのである。
一方イスラム教徒は、「政府はマニラを始め、キリスト教徒の住む大都会ばかり優先的に開発してきた。
長い間にミンダナオは大きく取り残されてしまった。
その責任は政府にある。生活に困っている我々の面倒をもっとみるべきだ」と反論する。
マルコス大統領にとって、最後の頼みの綱はイスラム教国、それもモロ民族解放戦線の後ろ盾リビアに和解への仲介を頼むことだけであった。
停戦後のホロ島
一九七七年、マルコス大統領はリビアで開かれた解放戦線との話し合いにイメルダ大統領夫人を派遣し、カダフィー議長の斡旋で、イスラム教徒に自治権を与えることを条件に、ようやく一時停戦に漕ぎつけた。
会議の代表ヌル・ミズワリは解放戦線に停戦の指令を発し、やがてイスラム教国の監視団が続々とミンダナオに入った。
我々が再びホロ島に入ったのはこの時期である。
国防省に文書で取材許可を出し、エンリレ国防大臣の名で公式に“ノー”の返事が届く前に、我々はサンボアンガに飛び、実力者ソメラ中佐(この時彼は一階級進級していた)と直接交渉をしていた。
「今度の停戦は、世界の関心を集めており、マルコス大統領も内外の記者に向かって、ホロを見てくれと言っている」
説得が効いたというよりは、顔なじみになっていたことと、多少の土産を渡したことが効いたのかもしれない。
また、当時はまだ混乱していて、国防省の正式な態度がミンダナオまで伝わっていなかったことも幸いした。
「この日本テレビチームに、掩護とできるだけの便宜を与えるように」
ソメラ中佐の記したお墨付をもって、我々はまたも日本人記者としては停戦後はじめてホロに入ることができたのだった。
ホロ島はこの前訪れた時と大きく様子が変わっていた。
焼け跡にはバラックが建ち、政府が安い料金で貸している難民住宅もあった。
山岳地帯からは政府軍の戦車が轟音(ごうおん)をたてて引き揚げてくる。
それと入れ替るように、市街地にいた解放戦線兵士の家族や、一時避難していた山地の住民が、乗合いバスにぶら下がるようにして山奥に帰ってゆく。
山のなかでは、もう帰った人々が木を切り、家を建て始めている。
政府軍は兵士を集めて停戦の心構えを説いている。停戦の効果はじわじわと浸透しつつあるようにみえた。
我々が入島した翌日、政府軍のゲリラ地区での医療奉仕が行われた。
停戦後も、山奥に集結し武装を解かない解放戦線に対する宥和策であったが、さすがにはじめてのゲリラ地区入りだけに政府軍兵士の緊張はひと通りではない。
早朝、武装兵士を乗せた数十台のトラックが先行し、山道の両側に散開配備された。
その武装兵士の掩護のなかを、医療班が、さらに前後を六台のジープとトラックに乗った兵士に護られて、ゆっくりと山に入ってゆく。
両側の椰子の木は、激しい銃撃戦ですべての葉を吹き飛ばされている。
解放戦線シンパの案内で、予定されていた広場に机を並べ看板を立て、拡声器で音楽を流す。三〇分もだったろうか、相談班、内科、歯科と分かれて待機していた広場に、一人、二人と解放戦線の兵士が姿を現し始めた。
いずれも長髪にハチマキをし、迷彩服を着ている。腰に蛮刀を下げ、なかには肩に自動小銃を担いでいる者もある。
一様に鋭い目つきをしているが、態度は悠然としていて、むしろ下手にでてご気嫌をとっているのは政府軍のほうだ。
なかには旧知の間柄なのか、手をとり肩を叩いている者もいる。 |

停戦後のホロ島ゲリラ地帯。
道路沿いの木の葉は、銃火で吹き飛ばされている。
|
「停戦をどう思う?」と解放戦線の兵士にきいてみた。
近くてみると兵士の多くはまだ一七、八歳としか見えず、あどけない顔をしている。
「一時停戦はあくまでも一時停戦だ。これが永久平和につながるかどうかは、政府の態度にかかっている」
そう言えと指導されているのだろうか。返事は一様で素気ない。少なくとも喜んでいる様子は全く見られない。
一方政府軍の将校たちは強い恐怖と嫌悪感におそわれているようであった。
それでも地元出身のイスラム教徒の将校は何とか仲直りしたいという表情が滲み出ていたし、人のよいイスラム教徒の大尉などは、自分の小遣で買った煙草を解放戦線の兵士に配って回っていた。
しかし、ルソン島やピサヤからやって来たキリスト教徒の将校は恐怖で顔がこわばっており、また若いビサヤ出身の軍医少佐に到っては、
「奴らは信用できない。何をされるかわからない。触るのも嫌だ」とジープから一歩も外に出ようとしなかった。
この恐怖は、一年後現実のものとなる。
勿論、この時はまさか。あの人のよいイスラム教徒の大尉や恐怖で震えていた若いキリスト教徒の少佐が雨のような銃弾を浴びて死ぬことになろうとは思ってもいなかったのだが……。
険しい和平への道
和平への道はなかなか進展しなかった。
解放戦線側か一刻も早い自治権の確立を要求したのに対して、政府側は住民投票をその前提として譲らなかったのである。
すでに述べたように、スル諸島とバシラン島を除いて、ミンダナオ南部はイスラム教徒よりキリスト教徒のほうがはるかに多い。
住民投票にかければ、イスラム教徒に自治権を与える案など多数を得られるはずはない。
その上、軍隊、警察をどうするか、徴税権は……というような自治権の中身についての合意もなかなか進まなかった。
それだけではない。イスラム教徒反乱軍の内部がいくつかに割れていることも交渉の進展を難しくしていた。
何とか政府と和解しようとする穏健派の他に、停戦を受け入れたヌル・ミズワリに抵抗を示す過激派もいる。
しかも底辺には思想など全く関係なく、もう盗賊やならず者とかわからない者がたくさんいる。
日が経つのにつれて、市民の乗っているバスが襲撃されたり街の建物が爆破されるという事件が相次いで起こるようになった。
そして、一九七八年の一〇月、解放戦線に話し合いを求められて山を訪れたバウチスタ将軍以下三五人の政府軍の将兵が、解放戦線の銃弾を雨のように浴びて殺されるという、最悪の事態が発生した。
一年前解放戦線兵士の前で脅え切っていた若いキリスト教徒の軍医も、解放戦線の兵隊に煙草を配っていたイスラム教徒の大尉も、一瞬のうちに生命を奪われてしまった。
政府軍は犯人掃討を口実として、大規模な報復攻撃に出た。
司令官ロムロ・エスパルドン少将は
「これはだまし討ちであり、計画的な人量虐殺だ。徹底的に掃討する」と宣言、一方、解放戦線の代表ハチミール・ハッサンは、
「今回の事件は政府軍の挑発によるものだ。今や政府軍による皆殺しが行われてしる」とイスラム教国に訴えた。
お互いの不信感は増幅する一方で、事態は停戦以前に戻ったかのようである。
サバからの武器の流入が止った気配もない。
ようやく和平へのキッカケが掴めたかにみえた一時停戦も、憎しみと血でつづられたミンダナオの歴史を塗り変えることにつながりそうにない。
背負わされた十字架
さようあまた、南○海に溶け込むように太陽が沈む。
そして、昨日も、今日も、そして明日もまた、同じように沈んでゆく太陽めがけて、スルの海を漕ぎ出してゆくモロ族の漁民たち。
この一見平和で静かな景色の背後で、深い憎しみがたぎり、多くの巓が流されている。
スペインからの独立を求めて闘ったフィリピンの英雄ホセ・リサールは、処刑の直前こう歌っている。
東の海の真珠なる国よ。
ああ奪いとられた楽園の国よ!
あなたの為に、よろこんで私はこの哀しい生涯を奉げます。
野を山をどよもす叫喚。
激突のなかで、いくたりの若い命が捧げられたことでしょう。
たじろぎもせず、かえりみもせず。
ああ、母のいます家と国とが叫ぶとき
この命 何の惜しみがありましょう。 |
民族の独立を叫んだホセ・リサールを国民の英雄として賛えるフィリピンが、今、国家の一部をしめるモロ族の独立を何とかして抑えようとして苦悩している。
一六世紀の半ば、まだ国としての統一体が形成していないうちに植民地にされ、そのまま国家の境界が定まったフィリピンの、それは長くて深い植民地統治の矛盾のほとばしりと言ってよいだろう。
2 サバの専制君主 top
サンダカン
マレーシア・サバ州、サンダカン。
サバがマレーシアの一州であることを知らない人でも、北ボルネオのサンダカンを知っている日本人は多い。
カラユキさんのはしりとして、この地に住みついた女傑木下くにが小説や映画で紹介されたからである。
その木下くにの墓は、港を見下ろす丘の上に、大地を揺るがす帝王蝉のウナリに耳を傾けるようにして建っている。
明治から大正にかけて、サンダカンと日本とを結びつけたのは娘子軍と呼ばれたカラユキさんであった。
今、日本とサンダカンを結びつけているのは木材である。
木下くにの墓が見下ろす港には、長い筏を曵いたタグボートがものうくエンジンの音を響かせて貯木場に向かってゆく。
貯木場につながれた木材は、商社の駐在員に等級を決められ、五、〇〇〇トンから六、〇〇〇トンの船に積み込まれて毎日のように出港してゆく。
木材の行く先は日本である。
木材はサバ州にとってかけがえのない資源で、輸出総額の七九パーセントをしめている。
森林のほとんどは州政府のもので、業者は政府から伐採の権利を買わねばならない。
森林伐採の権利金は州政府の歳入二七〇億円の六〇パーセントをしめている。
その巨額の金を意のままにしていたのが、サバの専制君主といわれたトゥン・ムスタファである。
木材の宝庫
果てしなく広がる森林。北海道よりやや小さい土地のほとんどは、ラワンなどの南洋材で被いつくされている。
この資源豊かな土地はボルネオと呼ばれ、長い間ブルネイのサルタンの領土であった。
後、フィリピン・スル請島のサルタンがこれを譲りうけ、やがて大航海時代になって、イギリスの北ボルネオ会社がスルのサルタンから北ボルネオの大部分を買いとっている。
第二次世界大戦の間、日本軍に占領されていたボルネオは、戦後イギリスの直轄植民地となったが、一九六三年、マレーシアが独立した時その一州となった。
しかし、地理的にも文化的にも全く西マレーシアと異なるサバは、軍事、警察を除いて財政、教育、移民など多くの点て大幅な自由、自治が認められている。
特に森林は大切な州財産であるだけに、州の憲法は、はっきりと西マレーシア連邦政府の介入を排し、
「森林は州が専管するものである。
サバは地方自治に関し、連邦の方針に従うことを強制されない」とはっきりと規定している。
こうして得た自治権を活用し、私腹を肥やし、専横の限りをつくしだのが、トゥン・ムスタファである。
カダザン族
標高四、一〇一メートル、キナバル山は東南アジア随一の高さを誇っている。
そのキナバル山を中心にしたサバの中央部に住んでいる人々の大半は、サバ州の最大多数民族、カダザンと呼ばれる農耕民族である。
学術的にはデウスンと呼ばれ、およそ一五〇〇年前、中国南部やペトナムからやってきた種族といわれている。
性格は温和で色はさほど黒くない。
黒っぽい服を着て菅笠を被った姿は、ベトナムやラオスの山岳民族に似ている。
いずれ劣らぬ働き者で、米は年に二度収穫をする。
典型的なカダザンの村トゥアランに住むミロスは六人の子持ち。 二ヘクタールの田を持ち、一頭一〇万円はする水牛を三頭飼っている。
下の子供三人は義務教育の小学校通いだが、費用は全部政府持ちで無料。
上の三人は小学校を終えるとすぐ農業の手伝いをしている。
家は木と籐、竹を使った高床式の建物で、広いベランダの他に三部屋ある。
ミロスは親の代からのキリスト教徒だが、教会には時々行く程度で、むしろキナバル山を霊山として信仰している。
ミロス家の墓は、家から五〇〇メートルほど離れた小高い丘の上にあり、石でつくった十字架の両側に水牛の角とひづめをかけた木の柱が建っている。
カダザンの人たちは、一家で人が死ぬと牛や豚を殺し、その血を家の周りに撒き、角やひづめを墓にかかげるという奇妙な習慣を持っている。
こうすることによって悪霊が動物に移り、死んだ人にとりつかないと信じているのである。
ミロスだけでなく、カダザンの多くはキリスト教徒であるが、同時に積霊崇拝が根強く残っており、死後、魂が天に昇ることを信じて疑わない。 |

キナバル山とイスラム寺院。サバ州の帝王ムスタファは
全州各地に次々とこのようなモスクを建てていった。

カダザンの農耕風景
|
ミロスの唯一の道楽は椰子酒である。
夕方農作業が終ると椰子の木によじ登り、枝の切口にとりつけた竹筒に溜った椰子酒をとってくる。
時には村の人々が集まって宴会をすることもある。
こういう時は、招ばれた人はすべて出席しなければならず、また出された料理は全部食べなければならない。
全員が出席し、同じ物を食べることによって、お互いに敵意がない仲間どうしてあることを確認する古い習慣の名残りである。
同じ座にいることは闇討ちをしないことを意味し、同じ物を食べることは毒殺しないという証しなのだ。
こうした習慣は、カダザンがその温和な性質のゆえに、その時々の強者に利用され、また、迫害されてきた歴史と無関係ではない。
奴隷制度が残っていた時代は、カダザンはしばしば、ブルネイやフィリピンのスル諸島に売られたという記録も残っており、時の権力におもねって仲間を売った者もいたらしい。
日本軍がサバを占領した時も、バジャウ族は激しく抵抗したが、カダザンは日本軍に協力している。
“見よ東海の空明けて……”
酒が入るとミロスは得意気に歌う。ミロスの父親は日本軍に雇われ、当時小学生だったミロスは学校でこの歌を習った。
一九六七年。独立後初の直接選挙が行われた時、統一原住民カダザン組織は、非イスラム教徒であるために立候補者の割当数を制限され、最大多数民族であるにも拘らず第一党になれなかった。
以来、バジャウの帝王・トゥン・ムスタファの辣腕に、あるいは懐柔されあるいぱ弾圧され、組織は徹底的に分断された。
バジャウ族
カダザンが内陸に住む農耕民族なら、パジャウは海沿いに住む海洋民族である。
バジャウがサバに定住するようになったのは、わずか二○○年前のことだという。
かって彼らは、フィリピンのスル海を根城とする海のジプシーであった。
船の上で暮らし、一か所に定住することなく動き回り、しばしば通りかかる船を襲う海賊となった。
現在、船の乗っとりや日本人の誘拐をしたりしているフョリピン・ミンダナオのイスラム教徒、モロ族と元は同根である。
サバに住みついたバジャウのうち、東海岸に定着したものは主として漁業で生計を立てているが、西海岸ではカダザンを追い払い農耕を始めたものも多い。
人によると、これら陸に上がったバジャウを、陸バジャウと呼んで区別する人もいるが、いずれも色が黒く、精悍な目つきをし、熱烈なイスラム信者である。 |

バジャウ族の水上村
|
バジャウの男は、相手がイスラム教徒でさえあれば、どこからでも妻をめとる。
インドネシア、フィリピン、西マレーシアと、あちこちに血縁をもっている者が多く、国境を無視して動き回る。
そのため、はっきりした人口が掴み難く、州政府の統計でもカダザン二八パーセント、中国系二二パーセントと、人口をはっきり数字で出しているのに、バジャウはその他原住民として一括りにされている。
おそらくその人口は、カダザンと中国人の中間であろう。
バジャウの人口を掴み難くしているもう一つの要因はフィリピンからの流民である。
彼らはバジャウの予備軍であったり、時には完全にバジャウと交り合って住んでおり、区別することができない。
スル諸島と目と鼻の先にあるサバの東部、セントポルナに住むモハメッド・ユソフも、つい二年前までスル諸島のタウイタウイに住んでいた。
フィリピン政府軍とイスラム教徒ゲリラとの戦闘が激化した一九七四年、ユソフは七人の子供と家財道具一切を船に乗せてセントポルナまでやってきた。
ユソフばかりではない。
難民のほとんどは、バシラン、ホロ、タウイタウイなどスル諸島の激戦地の人がほとんどで、一人頭およそ四、〇〇〇円を払って小型ランチに相乗りしてやってくる。
人口七五万人のサバ州に、一時は二五万人の難民が住んでいたこともあり、停戦が成立した後の今でも、一〇万人を越す難民が居座っている。
難民がサバ州に逃れてくる理由の一つは、資源の豊かなサバでは労働力が不足気味で、労賃が高いことが挙げられる。
漁業をしていたユソフの収入は、フィリピンでは一日三〇〇円ほどにしかならなかったが、今は工事現場で働いて一、〇〇〇円にはなる。
ユソフの友人のなかには徹夜の漁に雇われて、一晩に二、○○○円貰う人さえいるという。
しかし、難民がこれほどまでに続々とサバにやってくる最大の理由は、ムスタファの存在である。
サバ州の首席大臣でありパジャウの頭領でもあるムスタファは、パスポートもビザも持たないこれらの島々からの難民を黙って受け入れた。
黙って受け入れたばかりか、職を斡旋し、時に一軒二六〇万円もする家を建て、それを無料で提供したりさえした。
ムスタファの名前は難民を通して、フィリピン・スル諸島にまで鳴り響き、サバの帝王とか、バジャウの父親とまで呼ばれるようになった。
サバ州の帝王、トゥン・ムスタファ
トゥン・ダツー・ムスタファ・ヒン・ダツー・ハルン、この舌をかみそうに長い名前を持つサバの帝王の生まれは謎につつまれている。
サバ州の北端クダに生家と袮する家があるが、実はスル諸島タウイタウイの出身だという説が強い。
赤貧の家に生まれた彼は、幼くしてイギリス人のハウスボーイになり、そのズバ抜けた才覚と実行力でみるみるうちに頭角を現していった。
日本軍がサバを占領した時、バジャウの兵士を率いてこれと戦い、抗日戦の勇士として名をはせている。
戦後バジャウの頭領として政界に進出、サバ統一国民党の総裁になり、以来権謀術数を駆使して州首席と州首席大臣とを歴任、サバの政治・経済をほしいままにした。
ロンドンの郊外、テムズ川のほとりに、六ホールのゴルフコースと農場つき七五ヘクタールの別荘地を買い、アメリカ、香港、イギリスに数人の妻妾を抱えるというプレイボーイぶり。
かねてからサバ州の分離独立を唱え、フィリピンのイスラム教徒ゲリラを公然と支持し、フィリピンのマルコス大統領やマレーシアのラザク首相の神経を逆(さか)なでして平然としていた。
大臣も議会も意のままにならないものはなく、議会はまだ首席大臣在任中のムスタファの恩給を決め、退任後も終身、運転手つきの自家用車、庭師、ボディガード、召使いを使える法律を決めてしまった。 |

サバ州の帝王、トゥン・ムスタファ
|
ムスタファの専横ぶりはとどまるところを知らず、一九七三年には、信仰の自由を保障している州憲法を改訂して、イスラム教をサバ州の宗教と規定し、州都コタキナバルに州立の大寺院を建立した。
地方の町にも豪華なモスクを次々に建て、就職、森林伐採権、税金など、様々の面でイスラム教徒を優遇した。
キリスト教徒や仏教徒はアメとムチで次々に改宗させられ、一九七四年、州政府は、イスラム教徒の数は全人口の五三パーセントに達したと発表している。
これほどまでにムスタファの専横を許した背景には、最大多数民族カダザンの温和な性質の他に、他の民族の無関心と体制順応とがあった。
ムルト族
サバ州の大地のほとんどを被いつくすうっ蒼たる大森林のなかには、カダザンより古くから北ボルネオに住みついているムルトと呼ばれる狩猟民族がいる。
元来彼らは山の中を移り住み、弓矢と吹き矢で鳥や動物を殺して暮らしていたが、次第にその数が少なくなり、最近では州政府に保護されるようにたった。
我々が訪れたムルトの村は、サバの西北部にある商都ケニンガウから南西の山奥に入っだアンシップという集落である。
キナバル山麓からケニンガウに通ずる道路は、第二次世界大戦の時日本軍によってつくられた道で、舗装こそしてないが、曲がりくねった悪路の多いサバでは珍しく、三〇キロにわたって見事に一直線の道がつづいている。
戦後、敗れ九日本軍はこの道を通ってケニンガウに集結し、ここで武装解除されている。 |

ムルト族の酋長ティソクロール(左から2人目)と一家。左端は筆者。
後方の建物は大家族用のロングハウス。
|
ケニンガウから二時間ほど、ゴムやココヤシの林を過ぎ、さらに灌木の生い綮った道をゆくと突然林が開けて、今にも崩れ落ちそうな竹づくりの高床式の家が現れた。
物珍しそうに窓からのぞく老人の皮膚は、一面に青い刺青をほどこしている。
一〇軒余りある家並みの、なかでも大きな家屋に、酋長ティンクロールが住んでいた。
家は一種の長屋で、中央は居間と客間を兼わた大広間になっている。
その大広間に、一〇人ほどの男と五、六人の女がいて、女は赤ん坊に乳をやったり昼寝をしており、男たちは一抱えもある素焼の壺を抱き寄せ、竹の筒を吸っている。
タパイと呼ばれる米からつくった一種のドブロクである。
広間の両脇には小部屋と台所があり、小部屋には夫婦者が住み、独身者は広間で寝起きしている。
酋長の部屋は一番奥まった所にあり、この部屋だけは次の間つきで、銃や吹き矢が飾ってある。
次の間や台所ではティンクロールの何人かの妻たちが野菜を切ったり縫い物をしたりしている。
とにかく大変な人家族で、一軒の家に平均五、六世帯。四〇人内外の人が同居している。
高床式の家の床は竹が渡してあるだけで風通しがよく、ゴミはすき間から下へ落してしまえばそれで終りという、大層便利なつくりだ。
祭りの日や祝い事のある日には、近所の人々が着飾ってやってきて踊りを踊る。
踊りはドラの音に合わせたゆっくりしたリズムの単調なものだが、男たちがタパイを好きなように、女たちは踊りが大好きである。
ムルトもカダザンと同じように、一種の精霊信仰をもっており、よい魂は天に昇り、悪い魂は地上をさまよって害を及ぼすと信じている。
踊りの多くは悪霊を追い払い、幸せを祈るものである。
昼間から酒の匂いをぷんぷんさせているティンクロールに、政治に関心はないかときいてみる。
「俺たちは昔から鳥や獣を獲ることにだげ熱中してきた。女は焼畑で米をつくり、仕事が終ると酒を飲んだ。
それがどうだ。最近ではトラックやブルドーザしが山に入り、道はつくる、木は切り倒す。
獣たちは奥へ奥へと逃げて数は少なくなるし、焼畑だって十分につくれない。
最近では若い者は猟をしないでゴム園で働いて労賃を稼いでいる。馴れない畑を耕しているものもいる。
でもしかたがないよ。それが時代なんだ。政府は俺たちを保護してやると言っている。
何が良くて何が悪いのか、そんなことがわかるものか」と、あとは昔を懐かしんでぐちをこぼすばかり。
案内人の話でも、最近は昼間から酒びたりの老人が多いという。
本来、ムルトとは森の大という意味で、狩猟に使う道具は吹き矢であった。長さ三メートルはあろうという木の筒に、長さ五センチほどの矢をつめる。
矢は、木の枝を削ってつくったいわば太いつま揚子のようなもので、根元に、筒の内径に見合う太さの柔かい木が差し込まれている。
矢の先には植物から採った猛毒が塗ってあり、鹿ぐらいの動物ならものの五分で死んでしまう。
しかし最近は、実際の猟には鉄砲を使うことが多く、吹き矢を使う人はめったにいなくなってしまった。
以前はおよそ二五メートル離れた所から直径五センチほどの的を狙って外すものは一人もいなかったというが、今の若いものは直径三〇センチもある的に当てるのがやっとだという。
そういって嘆く年老いたかっての名手たちも、私たちがつくった的に向かって吹き矢を演じてもらうと、手が震え息が切れ、矢が的にとどかないことさえあった。
ムスタファは、勢いをなくしたムルトを政治的に利用した。
今でも山野を馳けめぐる生き方を好み、未開の森林の奥地を転々としているムルトは別として、生きる道を失いつつあるムルトを種族保存のためとして、都市周辺に移住させた。
政治などに関心を持ったこともない彼らは、政府の言うままに票を投じ、あるいは票を渡した。
ムスタファにとってムルトはそのまま、意のままになる白紙委任状だったのである。
中国系住民
サバにおける中国人の歴史はカダザンやバジャウよりも古く、しかも人口は二二パーセントと、三番めの多数民族である。
それにも拘らず、シンガポールを除く東南アジアのどの国でもそうであるように、あらゆる点て最下順位の優先権しか与えられていない。
西マレーシアでいうブミプトラとはマレー人優先政策のことだが、サバでは、中国系の人を除くすべての民族の優先を意味している。
例えば、森林の伐採は中国系の人にだけは与えられていない。
しかし中国人は金のない木材業者に資金を融通し、そのかわりに収益の何割かを得たり、あるいは輸送や輸出をうけもったりして、実質的に経済の中枢を握っている。
したがって、時の権力とは絶対に喧嘩することなく、むしろそれにつけ入ることによって生存を計ろうとする傾向か強い。
サバ中華総商会の陳玉発会頭は、放送に出さないならと断った上で、
「ムスタファの専横ぶりには時に、忍耐もここまでと思うこともある。
しかし我々は絶対勝てるという勝算なしに闘うことはしない。しかし何時か時は必ずくるはずだ。
それまでは耐え忍ぶ、それが華僑の生き方だ」と声をひそめて語ってくれた。
中華総商会は、ムスタファに多額の献金をすることによって同胞の安全と権益を守ってきたのであり、それがムスタファを支える有力な資金源でもあった。
帝王、失墜
不動と思われたムスタファにも、ついに最期の時がきた。
直接の引き金になったのは、ロンドンの別荘やメッカに通うために自家用のジェット機二檐を買い込んだことである。
マレーシアでは中央の連邦政府首相さえ特別機を持っていない。州の首席大臣が私用ジェット機を、それも公費で買ったことは確かに大事件に違いなかった。
しかし、この事件をキッカケにムスタファを引きずり下ろしたのは、何と言っても中央政府の力である。
時の首相ラザクは、かねてからサバ州の分離独立を狙うムスタファの野望に鉄槌を下す機会を狙っていた。
また、ムスタファがフィリピンのイスラム教徒ゲリラを支援していることも、ASEAN(東南アジア諸国連合)の統一を願うラザクにしてみれば、苦々しい限りであった。
自家用ジェット機の購入は、機会を狙っていた中央政府にまたとない口実を与えることになった。
一九七五年七月、それとも知らずムスタファがロンドン郊外の別荘で羽を仲ばしている最中、与党の一部指導者は、ラザクの後押しでムスタファの汚職を糾弾、脱党して新党をつくった。
仰天して帰国したムスタファを迎えたのは、一五、〇〇〇人の政府軍であった。
連邦政府は、反乱に備えるという名目で、大量の軍隊をサバに送り、ムスタファ辞任へ強い圧力をかけたのであった。
こうして、三か月後ムスタファはついに首席大臣の地位を追われた。
ムスタファが最後の巻き返しを狙った翌七六年の総選挙も、中央政府が送った大量の軍隊と警官隊の監視のなかで行われ、統一サバ国民組織はあっさり過半数を割ってしまった。
この日の夜、長い間抑圧されてきたカダザンの人々は喜びで一晩中、踊りつづけたという。
専制君主の座はこうして崩れた。
しかしこの場合、専制君主は一州の統治者であり、それを倒すために大きな力となったのは、軍隊と警察を握る中央政府の力であったことを忘れてはならない。
一国の統治者が専制君主となった時、それを倒すのは時にクーデターを待つしかない。
しかも、完全な民主主義のない東南アジアでは、実力のある統治者が専制君主になることはけっして珍しいことではない。
3 民政崩壊――タイのクーデター top
亡命の大立物、タノム
シンガポールの目抜通り、オーチャード道路沿いにタイ国大使館がある。
鉄柵に囲まれた宏壮な敷地の中央に白亜の建物が建ち、その両翼に、木陰に隠れるように、これも白い二階建ての家が並んでいる。
向かって左側の建物は大使公邸であり、右側の建物はナンバー二の一等晝記官の住居である。
二年余り前からその大使公邸の一室に一人の男が住みついていた。
身の丈一メートル八〇もあろうか、剃髪し、眉は太く鼻が大きい、ほとんど外出することはなく、ひたすら読経と読書三昧に眈っているこの容貌怪異の男こそ、一〇年もの間、独裁政権の座にあった、タイの元首相タノム・キチカッチョン元帥であった。
一九七三年一〇月、恒久憲法の制定を要求した知識人が逮捕された事に端を発した学生のデモは、軍の弾圧にも屈せずに市街戦にまでエスカレートし、ついに何人かの命と引き換えに、さしもの強力を誇っていたタノム政権を退陣に追い込んだ。
「タイに民主主義」、それはタイ史上はじめてであるというだけでなく、東南アジアに実現した最初の民主主義と言ってもよかったろう。
以来、軍部独裁政権の巨魁タノム陸軍大将元帥は、シンガポールで亡命生活を送りながら横目で祖国タイの動きを睨んできた。
新憲法公布、総選挙による政権と、何もかもが初々しく輝かしい将来を思わぜる門出をした新生タイも、しかし、国民の興奮がさめると同時に急速に多くの障害が現れた。
総選挙ではどの党も過半数が得られず、出てきた政治家は年老いた既成の政治家ばかり、インドシナ諸国と友好を保つために払った代償、米軍撤退は、軍部の反発を招いただけでなく、巨額のドルを失った結果、タイ全土に失業と不況をもたらすことになった。
そればかりではない。自らの力に自信を得た学生たちは事あるごとにデモやストを繰り返し、学費値上げ反対から知事の罷免までも力で押し通そうとし、国民の学生に対する批判は急速に高まっていった。
こうしてヅ学生と結ぶ弱体内閣に対する嫌気が国全体に広がるのを待っていたように、一九七六年八月、タノムの片腕であったプラパート元副首相が秘かに帰国、国内は混乱の渦に巻き込まれた。
時機到来。タノム・キチカッチョンは、この朧を逃さず、三年近いシンガポール生活に終止符を打って、僧侶姿で祖国タイに向かった。
入国の口実は、父親の病気見舞であった。
惨劇
タノム帰国の報に、タイはたちまち大混乱に陥った。
「独裁者の入国を許すな」「即時国外に追放せよ」学生は連日のようにデモを繰り返す。
一方右翼と軍部はタノム歓迎を打ち出し、タノム受入れを政府に迫った。
両者の要求の板ばさみに合ったセニ・プラモート首相の態度は煮えきらず、九月二三日、ついに決断を下せないまま総辞職してしまった。
その二日後、タノム追放のビラを貼っていた二人の学生が、ノコン河沿いのナコンパトム県で虐殺され、絞首刑姿で見つかるという事件が発生した。
このころ共産ゲリラに悩むラオスやカンボジア国境沿いの地方では、ビレッジスカウトと呼ばれる反共組織が次々に誕生していた。
いわば反共右翼集団である。犯行はこのビレッジスカウトによってなされたとみる見方が一般的である。
それにも拘らず、警察は事件解明に積極的な姿勢を示さず、犯人は捕まらない。
タノム追放を望んで無期限ストライキに入っていた名門、タマサート大学の学生は事件の処理に憤激し、事件を再現する寸劇を演じ犯人の早期逮捕を訴えた。
この時、木に吊される役を演じた学生の顔がワチュラロンコン皇太子に似ていたということから、あの「血の水曜日」と呼ばれる大虐殺事件に発展した。
「皇太子を木に吊したのと同じだ。警察が何もしないのなら、我々が代わって天誅を下す」
かねてから左翼学生せん滅の機会を狙っていた行動右翼は、皇室侮辱の大義名分の下に、雪崩れを打って構内に突入、構内は目を被う惨劇の場となった。
射殺されたり撲殺されたりした学生の死体が木に吊され、油をかけられて焼かれた。 |

逮捕されキャンパスに寝かされた学生たち。(WWP提供)
|
それは手を合わせにこやかに頬笑みかけるこの国の人の日常の姿からは、およそ想像もつかない凄じいものであった。
クーデター
死者四二人、重軽傷一八〇人、逮捕者三、〇〇〇人……。
しかし事態はこれだけで終らなかった。騷動か治まったころ、首相官邸のなかでは駑くべき事態が進行していた。
事態を収拾する能力のないセニ首相に代わって軍が政権を掌握しようとしていたのである。軍部によるクーデターであった。
全権を奪った軍は、直ちにサガット・チャロユー国防大臣を議長とする「国家改革評議会」を組織し戒厳令を布告した。
“タイでクーデター”“タマサート大学で生まれた民主主義はタマサート大学で死んだ”外電はあっという間に世界をかけめぐった。
夜一〇時、テレビに姿を現したサガット議長は国民にこう訴えた。
「一部グループが共産主義を振りかざし、王制と国家と宗教を侵そうとした。
我々は国家の安全を守るために立ち上がらざるを得なかった。これは軍の義務である」
そしてこの夜のうちに、憲法停止、国会閉鎖、政党結社の禁止、新聞出版の禁止など、次々に一連の布告を発表した。
こうして東南アジアではじめてとまで言われた民主主義政治は僅か三年で幕を閉じてしまった。
東南アジアに民主主義は育たないのか? このクーデターを国民はどう受けとめているのだろうか?
一夜明けたバンコク
一夜明けたバンコックは、今にも降り出しそうな雲が低く垂れ込めており、前日激しい闘いが繰り広げられたタマサート大学は、警察の手で捜索が行われていた。
なかにまだ潜伏している学生かいるらしいという噂も流れ、銃を手にしたものものしい検索である。
大学の周りは黒山のような人だかりで、誰もかも押し黙ったまま立ち去ろうとしない。
無表情で見物している群衆にマイクを向けてみる。
「今度の事態をどう思いますか?」
――眼鏡をかけた若い女性
「学生たちは好き勝手な要求ばかりして困りものだったわ」
――背の高い二五歳ぐらいの男
「学生たちの心情も、ある部分は理解できないでもないが、要求はエスカレートして、どこまでゆくのかわがらなかった。
死んだ人には気の毒だが、軍のとった措置は仕方ないと思う」
――中年の男
「治安も悪くなり世の中に秩序がなくなってきた。これも学生たちが無制限に自由を要求したからだ。
これで世の中もよくなるだろう」
銃口や周りの目を意識しているのか、あるいは全く本心なのか、返事を拒む人はあっても、軍や右翼を批判する人は一人もいない。
逮捕された学生およそ三、〇〇〇人は、警察に収容し切れず、市内の公共施設に分散して収容されていた。
市中央部のパヤタイ消防署にも逮捕者の名前が掲示され、息子や兄弟の安否を気づかう人たちが詰めかけていた。
軍政府はラジオを通じて、逮捕されたと思われる学生をもつ身内は、もよりの警察か消防署に来るよう呼びかけ、身元が確認できた学生の保釈手続きを始めた。
ただし保釈金は、一般学生で四五万円の現金か九〇万円相当の土地。リーダーに到っては一五〇万円出さなければならない。
警察官の初任給が一万円そこそこというこの国では途方もない金額である。
兄妹で学生運動に参加し、兄が逮捕されたと言う女の学生は、絶望的な表情でこう話していた。
「兄が留置されている場所だけは確認されました。
両親はとても心配しているけれど、家が貧しくてとてもあんな人金をやりくりすることはできません。
結局手を拱(こまぬ)いて様子をみているしかありません」
国民の反応
クーデターから二日経った朝。
早くも夜間外出禁止令が解かれ、バンコク市内は全く元の平静に昃った。
托鉢に回る僧侶の姿も普段と何の変わりもない。
目抜き通りに面したパトゥナム市場。
バンコクに住む人々の胃袋を賄うこの大きな市場にも、主婦たちが何事もなかったように群がっている。
野菜も肉も豊富で売り惜しみをする人もいなければ買い溜めする人もない。
一体、二日前のクーデターは何だったのか?
「クーデターのことを知ってますか?」
――魚屋の主人
「ラジオでやってたね」
「何か変わりましたか?」
「物の量も同じ、値段も同じ。何も変わっていませんよ」
――サングラスをかけた若い女性買物客
「デモもなくなってせいせいするわ。野菜なんか値段が安くなったような気がするけど……気のせいかしら」
一方バンコク市の経済の実権を握る中国人街、ヤワラ地区。
ここには両替商や銀行、さらに金の売り買いをする金行があり、毎日巨大なお金が動いている。
それだけに時局には敏感で、日本の株式相場のように金の値段は微妙に国民の心を反映する。
そのヤワラ地区で、何と金の値段は多少ではあったが下がっていた。
市民はクーデターに政情の安定を感じとっているのだろうか。
少なくとも市民が金の買い占めに走っていないことだけは確かだ。
農村はどうか。
タイは周りの国々に比べると、いわば国土すべてが穀倉地帯といってもよいほどで、バンコクを一歩出外れると見渡す限り青々とした田圃である。
米はタイ経済を支える大黒柱なのだ。
この年は、東北地方は旱魃に泣いたが、その他の地域はいつにない豊作だとあって、農民は取り入れを前に政変よりも天候のほうが気になるようであった。
しかし、それにしてもあまりにのんびりしている。
農作業の合間に、あぜ道で竹筒に入れた米を蒸した弁当を食べている家族にマイクを向けてみる。
「クーデターを知っていますか?」
「さあて、きいたことないね」
「首相が変わったんですよ。民政から軍政に変わったんですけどね」
「ああ、首相が変わったとかってのは誰かが言っていた。でも、誰がどう変ったのか、そのへんは全く知らないよ」
この農夫はまだよいほうだった。その後きいて回った農家の人たち、とりわけ女性は、政変のことを全く知らない。
あまりの無知と無関心に改めてタイという国の不可思議さを思いながら村の役場に行ってみた。
応対に出てきた中年の職員はさすがにクーデターのことを知っていた。
「何で知っだのですか?」
「ラジオできいたんです」
「政府から何らかの通達などはないのですか?」
「さあ、そんな事はきいていませんね」
「で、政変の結果良くなったと思いますか? それとも悪くなったと……?」
「それは良くなりましたよ」
「何かが変わっだのですか?」
「何も変わっちゃいませんよ」
「では何で良くなったと思うんです?」
「皆が良くなったって言っていますからね」
タノム
バンコク市内にある王室ゆかりの寺、バッヴォン寺。
三年前、そして今度とタイを揺がす大きな政変のキッカケとなったタノム元首相は、この寺で僧侶としての修業を積んでいた。
学生がタノム元首相の爆殺を画策しているという噂も流れ、寺の入口とタノムが寝起さしている僧坊の前には警察が厳重な警備を固めている。
八時ちょうど、鳴り響く鐘の音を背に渦中の人タノムは本堂で読経を上げるために僧坊を出て来た。
数人の僧侶が周りをとり囲むようにして足早に歩いてくる。
「あなたの帰国がきっかけで、多くの血が流されたことをご存じですね?」
突然マイクを突きつけられて、周囲の人たちはとっさにタノムをとり囲み防御の姿勢を示す。
タノム自身は一言も発せず、本堂に姿を消してしまった。
寺側の説明によると、タノムは仏一途の生活を送っており、政界復帰の意図はきっぱりと否定しているという。
しかし、タノムが宿泊している僧坊の庭には、テントが張られテーブルが置かれ、いかめしい軍服を着た将校たちがたむろしており、きらびやかな肩章をつけた軍枢要の人たちが慌ただしく出入りしている。
それにしても、もう、どの新聞もタノムの追放を叫ぶものはなく、街の噂でさえ、
「タノムはタイとタイ国民を心から愛している」という話がきかれこそすれ、タノムの悪口はきかれなくなってしまった。
革命記念日
クーデター一週間後の一〇月一三日、三年前学生たちが政権を奪取した、いわゆる“革命記念日”の前夜、政府は突然二度めの夜間外出禁止令を出した。
政府はその理由を明らかにしなかったが、右翼は、左翼学生が革命記念日に一斉蜂起しようとしているという情報を掴んだとして、臨戦体制に入っていた。
そして同じ日の午後、今度はクーデターの当事者、クリアンサク事務局長がはじめて記者団の前に姿を現した。
長い会見のなかでクリアンサク事務局長が一貫して示した新政権の姿勢は、
「タイに完全な民主主義は早過ぎる」ということであり、
「今後は国王を頂点とする政府の指導の下で民主主義への道を進む」とはっきりと表明した。
翌一〇月一四日、緊張した雰囲気に包まれながらもバンコク市内は何事もなく一日が過ぎた。
かって学生が大群衆を前に演説した舞台、憲法記念塔では何の記念巣会も開かれず、反政府演説も行われなかった。
学生と軍隊とが激しい市街戦を繰り広げたラジャダムナン通りにある学生会館は、右翼の襲撃によって破壊されたまま廃屋になっている。
三年前、「タイの歴史ではじめてO民主主義が生まれた」とまで言われ、拍手をもって国民に迎えられた学生たちは、今どこに行ってしまったのか。
「学生たちが変ったのではない。三年前の政変は決起であっても革命ではなかった。
タイ社会の構造は何一つ変わっていなかったのだ」と書くマスコミ人もいた。
いずれにせよ、もういつ建つのかその可能性さえなくなってしまった革命記念碑の台座は、国民と学生との間が冷えびえとした関係になってしまったことを象徴的に物語っていた。
ラジャダムナン通りのすぐ裏に、スントンタマタン寺という、コンクリートづくりの大きな寺がある。
この寺にひっそりと詣でる数人の人たちがいた。
三年前の市街戦で死んだ犠牲者たちの遺族であった。
そのうちの一人、ホテルの会計係をしているソムコン・チャプラヤは一九歳と一八歳の二人の息子を一度になくしていた。
英語学校の生徒だったプラセアとプラサンの兄弟は、国旗を持ちデモの先頭に立って抗議している時、機関銃で一瞬のうちになぎ倒されてしまったという。
その後、妻は落胆のあまり病床についてしまい、末の息子は兄たちの霊を慰めるため頭を剃り、仏門に入ってしまった。
銀行に勤めている長女だけを頼りに生きているソムコンは、今度の政変については口を固く閉したまま一言も話してくれなかったが、
「民主主義を求めて銃弾にたおれた子供の気持は今も全面的に支持する」ときっぱりと言い切った。
東南アジアの選択
クーデター後の日曜日、タマサート大学前の名物のサンデーマーケットでは国王の写真が飛ぶように売れていた。
三年前の政変の時、プミボン国王は学生の指導者に会い、彼らの勇気をほめ賛えたと言われる。
今度のクーデターでは、ワチュラロンコン皇太子が、逆に右翼を激励した。
そして、そのいずれの時も、皇室の態度は国民に喝采をもって受け入れられた。
「この国の人たちは、自分の身の周りさえよければ。あとは何でもよいのだ」という人もいる。
また「自分で決めるより、人に決めてもらってそれに従うほうが好きなのだ」という人もいる。
しかし、人々の底抜けに明るい表情や、飛ぶように売れている国王の写真を見ると、今度のクーデターは、彼ら自身が選んだしかるべき道だと考えざるを得ない。
日本をはじめ外国の新聞は、“タイの自由は死んだ”と叫び、“アジアに民主主義は育たないのか”と書きたてている。
しかし、東南アジアには西欧民主主義が定着している先進国とは違う、東南アジアなりの選択があることだけは忘れてはならないだろう。
top
**************************************** |