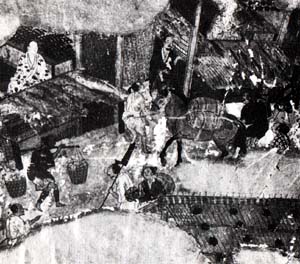|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 図解コーナー
一 さまよう少年日吉丸
新しい父に反抗した日吉丸は、何をやっても失敗ばかりだ。
しかし亡き父とのおおきくなったら侍になる、との約束は忘れない。
大きな夢を抱いて、少年は旅にでる。
1 三人の武将 top
「日本の歴史を、なるべく簡単に教えてください」
そういわれても、どうしてもふれないわけにはいかない三人の人物が、いまから四五〇年ほど前にそろって生まれた。
一五三四年生まれの織田信長――。
一五三七年生まれの豊臣秀吉――。
一五四二年生まれの徳川家康――。
この三人である。
その頃の日本は、室町時代とよばれて、京都の室町にあった幕府か国を治めていた時代である。
幕府の長の将軍には、最初にその幕府をひらいた足利尊氏の子孫が代々なっていた。
ところで、信長、秀吉、家康が生まれるころになると、幕府はすっかり力が衰えて、日本全国を一つにまとめて治めることができなくなっていた。
そのため、各地に力のつよい武将 * が興(おこ)って、
「われこそ、幕府にかわって全国を統一してみせるぞ」といって争った。
* 各地に力のつよい武将 西国には大内氏、尼子氏、毛利氏らがおり、東国には武田氏、上杉氏、北条氏、今川氏らがいて、それぞれ勢力をきそっていた。
世のなかは、戦国時代のまっさかりである。
信長、秀吉、家康も、その争いにくわわったすぐれた武将であり、政治家なのである。
この三人は生まれた年だけでなく、生まれたところもちかい。
信長と秀吉は尾張の国(愛知県西部)に生まれ、家康はそのとなりの三河の国(愛知県東部)に生まれた。
愛知県の人は、さぞかし鼻が高いことだろう。
同じころ、近いところに生まれて、そろってすぐれた武将・政治家になった三人だが、しかし秀吉には初めから他の二人とはっきりちがった点がある。
それは、信長と家康がもともと名のしられた武将の家に生まれたのにたいして、秀吉が名もない貧しい農民の家に生まれたということである。
そのため秀吉には、子供のころのことでわからないことが多い。 実をいうと、その生年月日もはっきりしていなかったのである。
秀吉のことを記した古い本には、
「秀吉は、天文五年(一五三六年)一月一日に生まれた」
と書いてあるものが多い。新しい本にも、そう書いてあるものがある。
しかし、その後の学者たちの研究で、
「秀吉が生まれたのは、天文六年(一五三七年)二月六日ではないか?」 といわれるようになり、最近では、この説のほうが有力になっているのである。 |

農民の子、日吉丸 のちには天下を支配した秀吉も、
もとは普通のガキ大将にすぎなかった。
|
|

三人の武将 「織田がつき、羽柴がこねし天下もち、
すわりしままに食うは徳川」 という、
三人の天下とりのようすをうたった歌を絵でしめしたもの。
|

左=綴織(つづれおり)鳥獣文陣羽織
秀吉がこのみそうな華麗なもようだ。高台寺蔵
右下=芦穂蒔絵鞍(あしほまきほくら)
秀吉がつかったもの。東京国立博物館蔵
右上=真珠団扇(うちわ)型軍配
秀吉がつかっていものといわれる。徳川黎明会蔵
|
2 わからない幼名 top
信長は、幼名を吉法師といっていた。家康は、竹千代といっていた。
しかしこの二人の幼名を知らなくても、秀吉の幼名が日吉丸だったということを知っている人はたくさんいるだろう。
そのくらい、日吉丸という秀吉の幼名は、多くの人々に親しまれている。
この日吉丸という立派な名は、秀吉が一月一日というめでたい日(吉日)に生まれたためにつけられたともいわれている。
「となると、秀吉が一月一日生まれでないとわかったのだから、その日吉丸という名もあやふやになってしまうじゃないの?」
実際、そのとおりである。
日吉丸というのは、秀吉がのちに立派になってから本のなかでつけられた名前で、実際の秀吉は、二十五才ぐらいになって木下藤吉郎と名のるときまで、なんという名前だったかも知られていないのである。
「名前がわからないのなら、どんな子だったかもわからないのじゃないの?」
それも、そのとおりで、のちにかかれた日吉丸の話はどこまでが真実なのかよくわからないといわれている。
しかし古い本の作者も、まるで根も葉もないつくり話ばかりをかいたわけではない。秀吉のことを調べていきながら、
「秀吉ほどの人なら、このぐらいのことはしただろう」と、調べた話をつい大げさに書いてしまうことが多かったのである。
よい人物ならよいほうへ、悪い人物なら悪いほうへと、まるでふくらし粉でも使ったように誇張して書かれるのは、秀吉の場合にかぎらない。
それになにより、主人公が名なしでは話がしにくい。
そこで作者も、秀吉に日吉丸という立派な幼名をつけたのだろう。
ここでも、そういうことを頭におきながら、日吉丸の話からはじめることにしよう。
「どこからが、ふくらませた部分かなあ?」
そんなことを考えながら、秀吉の少年時代を楽しんで読んでもかまわないのである。
3 日吉丸誕生 top
東海道線、名古屋駅――。
駅をおりると、その西側が名古屋市中村区になっている。
駅から二キロほどはなれたところに、中村町があり、中村公園がある。
のちに豊臣秀吉になった日吉丸は、この中村公園のあたりで生まれた。
その頃は、尾張の国愛知郡中村というところだった。
中村公園には、現在でも「豊公(ほうこう)誕生之地」という石碑がたっていて、そのことをものがたっている。
日吉丸が生まれたのは、前にも述べたように、一五三七年二月六日
* である。
* 2月6日 秀吉の祐筆(ゆうひつ=書記、秘書の役めをする人)であった大村由己(ゆうこ)は、秀吉が関白になった翌月に『関白任官記』をかき、そのなかでうまれた月日を2月6日としている。
父は弥右衛門、母は“なか”といった。
“とも”という、一人の姉がいた。いくつ上だったかは、わかっていない。
弥右衛門は、もと、織川信秀に仕えていた武士であった。
武士といっても、一番身分の低い足軽(足でかけまわる歩兵)である。
織田信秀は、信長の父である。 |

秀吉誕生の地の碑
名古屋市の中村公園に石碑がたっている。
|
その頃日本の各地は、幕府の任命する守護によって治められていた。
しかし、守護の多くは京都にいたままで、実際の現地の仕事は、守護代(しゅごだい)とよばれる守護の代理人があたっていた。
信秀は、尾張の国(愛知県西部)の守護代であった。
ところが、幕府の衰えとともに守護の力も衰えたので、信秀はいつのまにか尾張の国を自分の領地にしていた。
弥右衛門は、この信秀のもとで鉄砲足軽だったという説がある。しかしそれは、間違いだろう。
「以後(15)、予算(43)がかかる鉄砲伝来」
そういう年号早覚え言葉がしめすように、日本に鉄砲がつたわったのは一五四三年
* である。
* 1543年 この年の8月、ポルトガル船が九州の種子島に漂着し、領主の種子島時堯(たねがしまときたか)に、鉄砲のつくりかたと火薬の調合のしかたを教えた。そのため、この年を鉄砲伝来の年とする。
ところか、日吉丸の生まれだのは一五三七年で、それより前だから、その頃弥右衛門が鉄砲足軽だったはずはないのだ。 |

日吉丸となかまたちの像 名古屋市中村公園内
|
日吉丸の話には、ふくらし粉をきかせたものだけでなく、ときにはこういうあやまりもある。用心が必要だ。
おそらく弥右衛門は、鉄砲ではなく、槍や刀をふりまわして走りまわっていた普通の足軽だったにちがいない。
あるとき、弥右衛門はいくさに出て負傷した。
そのため二度といくさに出られなくなり、しかたなく中村で農民になっていた。
その頃生まれたのが、日吉丸だったのである。
4 少年の日の約束 top
弥右衛門は、いくさに出られないくらいだから、農業のほうも満足にできなかった。そのため、家は貧しかった。
寝具(しんぐ)がなく、むしろを使っていたといわれている。
でも、ともや日吉丸はなんとか育った。
弥右衛門は、日吉丸が少し大きくなると、よく語ってきかせた。
「日吉、チャン(父)はな、これ、でももとは織田信秀さまに仕える侍だったんだ」
「フーン」
「あるとき、いくさに出てな、こっ、このとおり、足をやられてしまったんだ」
「フーン」
「足さえやられなかったらな、チャンだって、いまごろは大将になっていたかもしれねえ」
弥右衛門は、足をさすっていかにもくやしそうである。日吉丸は、子供ごころにも同情するようにその顔をみつめる。
日吉丸は、栄養がたりないのか、からだが小さい。
顔も、ほっぺたがこけている。目のくぼみも、ひろくてふかい。
そのくせ、目の王は大きくてクリクリしている。なんだか、ちょっとサルに似ている。
*
* サルに似ている 秀吉の顔が、サルにそっくりだということは、『甫庵(ほあん)太閤記』や『絵本太閤記』などの江戸時代の古い本にもかかれている。概要のページのほそおもての顔も、どこかサルに似てみえる。注=筆者はこの二つの本をもとにしてこの本を書いている。
「日吉、おまえ、大きくなったら何になるんだ」
「まだ、わからないよ、チャン」
「ウーム、それは残念」
弥右衛門(やえもん)は、ますますくやしそうである。
何度も話をきくうちに日吉丸は弥右衛門が自分のくやしさを晴らすために、日吉丸を武士にしたがっていることに気づいた。
そこで、それからは日吉丸もこたえた。
「チャン、おいらも大きくなったら、侍になる」
弥右衛門は、よろこんだ。
「ウーン、そうか、よしよし」
弥右衛門は、ますます武士やいくさの話を日吉丸に語ってきかせた。
日吉丸は聞きながら、だんだんと胸がおどりだすようになるのを感じた。
日吉丸が七つのとき、弥右衛門が死んだ。母のなかは、ともと日吉丸をかかえて困った。
その頃、やはり織田信秀に仕えたことのある竹阿弥(ちくあみ)という人がいた。
同朋衆 * (どうほうしゅう)といって、雑用係のようなことをしていたが、しかし病気にかかったことがあって、もう武士をやめていた。
* 同朋衆 戦塲へでる武士とはちがって、能や鼓、茶道などの芸能にすぐれた者で、主君のそば近くに仕え、身のまわりのせわを何でもこなした。
母のなかはやがてその竹阿弥と再婚した。
といっても、なかが竹阿弥のところへいったのではなく、逆に竹阿弥がなかのところへ移ってきたのである。
竹阿弥が、日吉丸の新しい父になった。
5 お寺にあずけられる top
日吉丸は、新しい父竹阿弥に反抗した。
死んだ父の弥右衛門がまだ心のなかに生きていて、日吉丸には、竹阿弥がその父をおしのけて家に入りこんできたように、おもえたのである。
日吉丸が反抗するため、竹阿弥も日吉丸を嫌った。
「かわいげのない子供だ」
そういって、ときには日吉丸をなぐった。
母のなかが、二人の板ばさみになって、いつもオロオロしていた。
“なか”はこまって、日吉丸を光明寺という寺にあずけることにした。
寺にあずければ、一家は平和になるうえに、ひとり分の食べ物が助かる。
それに、日吉丸が手習いやお経を覚えて、ゆくゆくは立派な僧になるかもしれない。
そうなってくれれば、一石二鳥(一つのことをして二つの得がある)どころか、一石三島、一石四鳥だ。
「ホホウ、こりゃ、ちょっぴりサルに似ているが、目がクリクリして利口そうな子じゃわい」
光明寺の和尚も、日吉丸をみこんであずかることにした。
なるほど、和尚のみこんだとおりだった。
手習いをさせてみると、日吉丸は、ほかの小僧とちがって何でもすはやく頭のなかにいれてしまう。
和尚は、おどろくとともに、内心よろこんだ。
ところが、あとがいけない。お経になると、日吉丸は少しも覚えられないのである。
はじめから、覚える気が全くないのである。
「これ、日吉、なぜお経を覚えないのか?」
「おいら、坊さんになりたくないんだ」
「坊主にならずに、なにになるんだ?」
「おいら、お侍になるんだ」
「侍に? どうして侍になるんだ?」
「おいら、チャン(父)がまだ生きているとき、チャンと約束したんだ。
お侍になるって。チャン、うれしそうだったよ」
ひとみがキラキラしている。どうやら、本気のようである。
6 お寺で失敗 top
やがて日吉丸は、近所の腕白(わんぱく)な子供たちを集めて遊びはじめた。
いつも、竹や棒きれをふりまわして、いくさごっこをしている。和尚がいくらしかっても、やめない。
あるとき、和尚が寺に帰ってくると、日吉丸がいなかった。
ちかくの原っぱで、ワァーワァーという子供たちの声がきこえる。
「またやっているな。しょうがない」
和尚は舌うちしながら、本堂に入った。
すると、須弥壇 * (しゃみだん=仏像をおく台)の前においてある大きな太鼓がなかった。
* 須弥壇 本尊となる仏さまをまつる祭壇で、寺でいちばんおもんじられる場所。仏教では、世界の中心にそびえる山を須弥山といい、須弥壇はこの山をかたどったものという。
両手にもって、ジャランジャランとならす、麦わら帽子のような鐘もなかった。
和尚が本尊さまの前でうちふるう、白くて長い毛のついた払子(ほっす)もなかった。
「まさか、日吉のやつ……」
和尚は、あわてて原っぱへいってみた。すると、その「まさか」の光景がそこにみられた。
日吉丸が、ジャランジャランの鐘を甲(かぶと)のようにかぶると、手に払子(ほっす)をもって大将のようにたっている。
その横で、ドンドンと太鼓がなっている。
太鼓の前では、棒の刀と竹の槍とをもった二人の子が、たがいにみあって一騎うちだ。
「コッ、コラ――!」和尚が、おもわずどなった。
そのとたん、つきだされていた子供の槍が太鼓にあたって、皮がビリリッと破れた。
子供たちがクモの子をちらすようににげてしまい、日吉丸一人があとに残された。
和尚は、日吉丸の手から払子をうばいとると、その頭を鐘の甲(かぶと)の上からジャランジャランとたたいた。
日吉丸は、その日のうちに家に帰された。
帰ると、母のなかが小竹 *
という子をうんでいた。
* 小竹 のちの秀長(ひでなが)である。秀長は武将としてもすぐれ、人びとの信頼もあつく、兄の秀吉の片腕として活躍した。秀吉の兄弟は、姉、弟、妹の4人だった。 |

いくさごっこ 日吉丸は、お寺に
入っても毎日いくさごっこだ。
|
小竹はかわいかったが、しかし日吉丸は、母に小竹をうませた竹阿弥がますます嫌いになってきた。
その仕返しのように、竹阿弥のほうも日吉丸を嫌った。
「日吉や、おまえにも困ったもんだねえ。どうして、お寺でおとなしくしていてくれなかったのだい?」
なかは、日吉丸をみながら嘆いた。
「だって、おいら侍になるって、死んだチャン(父)と約束したんだ」
「侍になるっていったって、どうせ農民のせがれじゃ。
チャンと同じで足軽(身分の低い歩兵)ぐらいにしかなれっこないじゃないか」
日吉丸は目をクリクリさせて考えている。
「だからね、今度は何かほかのものになるっていう約束でも、しておくれよ」
日吉丸は、いまさらそんな約束はできないという顔つきでだまりこんでいる。 |

家に帰される お寺で失敗した日吉丸は、
スゴスゴと家に帰った。
|
7 商人でも失敗 top
なかは日吉丸を商人にしたいと思った。
そこで今度は、ある布屋にたのんで日吉丸を使ってもらうことにした。
「いいね、日吉、今度は辛抱するんだよ」
店までおくってきて、なかがいった。
「うん」 日吉丸は、神妙な顔でこたえた。
武士になるのぞみはすてていなかった。ただもう少し大きくなってからでないと、武士にはなれない。
それまで家にいると、二度めの父と喧嘩ばかりするから、おっかあがかわいそうだ。*
* おっかあがかわいそうだ 日吉丸は、二度めの父の竹阿弥(ちくあみ)になつこうとしなかった。母のなかは竹阿弥への気がねと、日吉丸をかわいいとおもう気持ちの板ばさみになってくるしんでいた。
だから、それまでは我慢しようと思ったのである。
新しい生活かはじまった。日吉丸は、毎日、掃除、水くみ、まきわり、使い走りなどをさせられた。 |
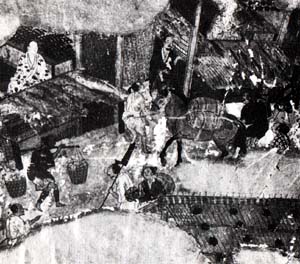
にぎわう町なみ 「京洛月次風俗扇流図屏風」より。
光円寺蔵
|
嫌ではなかった。どんな仕事でも、一生懸命にやれば、けっこうだのしかった。
でも、どうしても我慢できないことが、一つあった。
「サル――、サル――」
みんなに、そういわれることである。
日吉丸はよくはたらくので、店の主人にかわいがられた。
すると、かわいがられればかわいがられるほど、他の奉公人がそれをねたんで、うさばらしをするのである。
「おい、サル――、サル――」
日吉丸は、自分の顔を水面にうつしてとっくりながめた。
なるほど、目が大きいくせにひっこみ、ほおもこけていて、ちょっぴりサルに似ている。
そ の目をカッとみひらき、口を真横にひきさいて、「キーッ、キーッ」とないてみると、ますます似てくる。
日吉丸は、あわい悲しみを胸に覚えた。
あるときまた、他の奉公人が日吉丸をからかった。
「サル――、サル――」
そのとたん、日吉丸はカッとなってわれを忘れた。
「なにをつ、こいつめ!」
手にもっていた桶の水をザブンと相手の顔にかけると、そのままうしろもみずに布屋をとびだした。
もう二度と店にもどる気はなかった。
「家に帰ると、おっ母がこまるだろうな」
そうおもうと、家に帰る気もなかった。日吉丸は、足のむくままにブラブラ歩いた。*
* ブラブラ歩いた 寺をとびだしてから侍になるまで、日吉丸は、38軒の店ではたらいたとされている。米屋、八百屋、みそ屋、刀とぎ屋などで、全部ながつづきしなかった。
なかは、日吉丸がいつまでも帰ってこないので、今度はおとなしくはたらいているとばかり考えていた。
そこで布屋にあいに出かけた。
「なにっ、日吉っ? ああ、あのサルか――。あのサルめっ、とんでもないやつ、で……」
なかは、さんざん油をしぼられた(おこられた)。
ひらあやまりをして店を出ると、村々をたずねて日吉丸をさがしまわった。
ある村の茶わん屋にいるらしいといううわさを耳にした。でもその茶わん屋にいってみると、主人にいわれた。
「あのサルめっ、二か月前にわしの顔に茶わんをぶつけて……」
三軒めが、針屋である。その針屋でも……、。
なかはあきらめると、かなしい心をいだきながら、トボトボと家に帰った。
8 侍へのゆめ top
日吉丸がひょっこり家にもどってきたのは、十四か十五になったころである。
世の荒波にもまれてきたらしく、背もたかく、みるからにたくましい少年に成長した。
もっとも、顔はまだサルに似ていたが……。
なかは小竹のあとに、朝日 * (あさひ)という女の子もうんでいた。その朝日も、もう大きくなっていた。
* 朝日 日吉丸のたった一人の妹。1543年ごろのうまれで、日吉丸より6才年下。日吉丸が秀吉と名のり、しだいに出世していくにしたがって、朝日の運命も大きくかわっていく。
「おっかあ、おいら、どうしてもあきんど(商人)にはなれなかったよ。
だから、やっぱり、死んだチャンと約束したように、侍になろうとおもっているんだ。
おいら、そのことをいいたくて、家に帰ってきたんだ」
日吉丸が、なかにそう語った。
「日吉、おっかあは、おまえにはもう何もいわない。これからは、おまえ一人の考えで、おまえ一人の道をいくがよい」
なかはそうこたえると、押入のなかをゴソゴソとかきまわして何かを取り出した。
みると、銭(ぜに)である。
永楽銭(えいらくせん)といって、まん中に四角いあなのあいた銅銭(どうせん)である。
それが、一〇〇枚以上も丈夫な麻ひもにとおされて、輪になっている。
永楽銭は中国の明でつくられた銅貨である。
日本では十世紀の中頃以後、正式な貨幣がつくられていないので、中国から輸入
* したものを使っていたのだ。
* 中国から輸入 日本では、708年に「和同開珎」(わどうかいちん)という貨幣を発行したのを最初に、12種類の貨幣が発行された。しかし、平安時代の末ごろから、しだいに輪入銭にかわっていった。
なかがつづけた。
「日吉、これはね、おまえの死んだチャン(父)が、まだ生きているあいだにコツコツとためた銭だよ。 おっかあは、これをいつかはおまえにやろうとおもって、どんなに困ったときでもつかわないでしまっていたのだよ。
さあ、これを、これからのおまえのために役だてるがよい」 |

永楽銭 中国の明の銅銭で、
日本でもつかわれていた。
|
日吉丸は、ズッシリと思いその永楽銭の束をもらった。
「おっかあ、ありがとう」
なんだか、目がしらがあつくなって困った。
9 あれが信長さまか! top
日吉丸は、永楽銭の麻ひもを首にかけてふところにしまった。
背中には、姉のともがつくってくれた握り飯をつつんで背負った。
「じゃあ、おっかあ、いってくるよ。今度は、侍になるまで帰らないからな」
なかとともが、それをみおくった。小竹と朝日も、一緒にみおくった。
日吉丸は、すぐちかくの那古野(なごや=名古屋市)へむかった。
死んだ父弥右衛門が仕えていた織田信秀の城がある。
どうせ武士になるなら、父の仕えていたその信秀の家来になろうと考えていた。
ところが、いってみると、大変なさわぎになっていた。
その信秀が死んでしまって、まもなく葬式がおこなわれるというのである。
「信秀さまのあとつぎは、信長さまじゃな」
「だが、その信長さまは大バカ者ときている。気の毒だが、織田家ももうおしまいよ」
そういううわさが、日吉丸の耳に入った。奇妙に胸がさわいた。
日吉丸は自分も、葬式がおこなわれる万松寺 * (ばんしょうじ)という寺にいってみることにした。
* 万松寺 現在は、名古屋市中区大須3丁目にあり、父信秀の葬式がおこなわれたのは、1551年3月6日のこと。信秀は、はやり病がもとで、42才の若さで死んだ。
万松寺は、それこそ何万本というマツにかこまれた大きな寺だった。
白と黒の幕をはりめぐらして、何千人という織田家の家来がつめかけている。
おもおもしいお経の声もきこえる。
日吉丸は、ちかくの畑道に腰をおろして、ボンヤリと寺のほうをみていた。
突然、馬のひづめの音がひびいたかとおもうと、四、五人の若者たちが馬にまたがって日吉丸の前をとおった。
先頭の若者は乱れた髪の毛をひもで結び、ふんどしをした上に短い着物だけをきて、太刀(たち)を腰にさしている。
まるで、野武士か山賊だ。
野武士の若者は、万松寺につくと、織田家の武士たちをおしのけて中に入った。
日吉丸は、みていてあっけにとられた。
しばらくすると、若者は万松寺から出てきて、また日吉丸の前をとおった。
「ワッハッハ、ワッハッハ……」
愉快そうに高笑いをしている。日吉丸は、ふたたびあっけにとられた。
織田信秀の葬式がおわった。すると、いろいろなうわさがまた日吉丸の耳に入った。
「信長さまは、野武士のようなかっこう *
で、父上のお葬式にのりつけてきたそうじゃ」
* 野武士のようなかっこう 髪はうしろでたばね、きものはすねまるだしのうすよごれたもの、あらなわで腰をしばっで刀をさし、しかもはだしだったという。
「仏前にパッと香(こう)を投げつけて、さも愉快そうに高笑いされたとか」
「信長さまは、やっぱりバカか気違いよ。アーア、織田家も本当におしまいじゃな」
日吉丸は、馬にまたがった若者の姿を思い出しながら、胆(きも)をつぶすほどびっくりしていた。
「あれが、信長さまだったのか」
同時に、織田家に仕えたいという気持ちが、水をかけられた火のようにすっかりきえていた。
「それなら、どこへ仕えようか?」
しぜんに、今川義元(いまがわよしもと)という名がおもいうかんだ。
今川義元は駿河・遠江の国(ともに静岡県)をもつ守護大名で、いつのまにか三河の国(愛知県東部)までせめとって自分の領地にしていた。
織田家が信長のものとなれば、その織田家をつぶすのもわけはないだろう。
日吉丸の心はきまった。
日吉丸は、永楽銭をだしてたくさん針を買うと、それを村々に売りながら東にむかった。
10 蜂須賀小六(はちすかころく)との出あい
top
ある晩、日吉丸は矢作川 * (やはぎがわ)の橋の上でむしろをかぶってねていた。
* 矢作川 愛知県のほば中央を流れ知多湾にそそいでいる。矢作橋がかけられたのは。この話より50年ほどあとというから、橋の上の二人の出あいは本当のことではないようだ。
数人の野武士が、槍をつきながらとおった。
槍が、日吉丸のからだにさわった。日吉丸は、ガバッとはねおきた。
「まっ、まてっ!」
「なんだ、小僧かねていたのか。どうした、小僧?」
「いま、槍でおいらをついたろう。あやまれ」
「ホホゥ、なかなか元気な小僧だ。おまえ、名前はなんという?」
「名前をきくなら、自分のほうから名のれっ」
「そうか。わしは、蜂須賀小六という野武士のかしらだ。さあ、おまえは……?」 |

蜂須賀小六との出あい 日吉丸は、ものおじしないばかりか、
大いばりでいいかえすありさまだ。
|
「おいらは、尾張の国(愛知県)中村生まれの日吉丸だ」
「ホホー、名前だけで名字はないのか?」
「まだない。侍になったら、つける」
「ホホー、武士になりたいのか?」
「あたりまえだ。それより、さあ、あやまれ」
手下の野武士たちが、さわぎはじめた。
「おかしら、こんな小僧、川の中へたたきこんでやりましょう」
小六は、手をのばしてそれをおさえた。
「これ、日吉丸とやら、おまえなかなかみどころがある。
武士になりたいなら、いっそ、このわしの家来にならないか?」
「あやまるなら、なってやってもよい」
「おお、あやまる、あやまる。『日吉丸どの、さきほどはすまなかった』これでよいか?」
日吉丸はむしろをたたむと、大いばりで小六の家来になってやることにした。
現在では、この矢作川の話もつくり話だといわれている。
その後の調べで、その頃の矢作川には橋がかかっていなかったため、つくり話だということがわかるのである。
しかし川は、橋がなければ、渡し船でわたる。
日吉丸も、あるいはその船の中にねていて蜂須賀小六とあったのかもしれない。
この話もそういうふうに解釈して、あじわうほうがよいだろう。
古い物語の作者 *
も、日吉丸の威勢のよかったところをしらせたくて、この話をかいたのだから――。
* 古い物語の作者 蜂須賀小六との出あいのエピソードは、秀吉物語の有名な話。江戸時代のおわりごろ、岡田玉山のさし絵で出版された「絵本太閤記」に出ている。
11 日吉丸の知恵 top
日吉丸は、小六の屋敷へいっても威勢がよかった。そのため、小六にかわいがられた。
あるとき小六は、床の間の刀かけにかけた立派な刀を日吉丸にみせて、わらった。
「どうじゃ、日吉、おまえも武士になったのなら、立派な刀がほしいじゃろう?」
「はい、ほしいです」
「よし、それでは三日三晩のうちに、わしに気づかれないようにあの刀をとってみろ。そしたら、おまえにやる」
「あ、ありがとうございます」
「礼などいっても、まだやっておらぬぞ」
「いえ、もうもらったも同じことです」
「アハハ、とれるものか」
それから三日間、小六は、床の間のそばで刀をみまもっていることにした。
夜になると、庭で立ち木のゆれるのがわかった。日吉丸がかくれて、すきをうかがっているのにちがいなかった。
二日間が、ぶじにすぎた。
三日めの晩、雨がふった。庭に、今度は、みの笠が雨にうたれる音がきこえた。小六はわらった。
「日吉のやつ、まだいるな。知恵があるようでも
*、やはり子供じゃわい」
* 知恵があるようでも… 威勢がよくて頭の回転がはやいといわれている日吉丸を、小六がためしたくなってしくんだ、という話。小六と日吉丸の知恵くらべであった。
みの笠の音は、明方になってもきこえた。
小六は、あきれかえった。
「あいつ、ねむってしまったのかもしれないぞ」
小六は縁側にいって雨戸をひらいた。
立ち木のそばに、白っぽくみの笠がうかんでいたが、日吉丸の姿はみえなかった。
小六は、下駄をはいていってみた。みの笠が木の枝にのっていて、日吉丸の姿はやっぱりなかった。
「しっ、しまった!」
小六はあわてて、座敷にとんで帰った。
「おかしら、ありがとうございました」
日吉丸が刀を手にして、ニンマリ笑っていた。 |

知恵をつかって小六をやりこめた日吉丸 「絵本太閤記」より
|
12 松下嘉兵衛との別れ top
日吉丸はしばらくして、小六のところから出ていくことにした。
野武士は、泥棒や強盗のようなこともしていた。
小六も、そうだった。
「これでは、自分の将来ののぞみにあわない」
日吉丸は、そうおもったのである。
また一人で、東のほうにむかって歩いた。今度は、小六からもらった刀をさしていた。
遠江の国(静岡県西部)に入った。今川家のもともとの領地である。日吉丸の胸がはずんだ。
ある川の土手でやすんでいると、身なりの立派な武士が、数人の家来をつれてとおりかかった。
武士は、目についた日吉丸をしばらくみていたが、やがてツカツカとちかづいてきた。
この武士も、一目で、日吉丸をすぐれた才能の持ち主とみぬいたのである。
武士は、今川義元の重臣(おもい役目の家来)の松下嘉兵衛
* (まつしかかへい)だった。
* 松下嘉兵衛 今川義元の家来で遠江(静岡県西部)地方の豪族。武術の腕がたち、今川家でもその名がたかかった。日吉丸は、約3年間仕えて尾張(愛知県西部)へもどった。
嘉兵衛は、その場で日吉丸を家来にやとった。
嘉兵衛は、日吉丸を草履とりに使った。
草履とりは、主人が外出するとき草履をそろえたり、走り使いをしたりする一番下っぱの役で、とても武士とはいえない。
しかし日吉丸は、いっしんにその草履とりの仕事にはげんだ。それをみて、嘉兵衛はうなずいた。
「日吉は、やはり私のおもっていたとおりの男じゃ」
それからは、日吉丸をドンドン取り立て、二、三年後には納戸役
* (なんどやく)までやらせた。
* 納戸役 納戸とは、もともと衣服や日常つかう道具、家具などをおく部屋のことだったが、ひろく室内の物置をさすようになった。納戸役は主人のお金、衣服、家具などをあつかう役。
一家の会計をあずかる大事な役である。
すると、ふるくからの家来たちが、それをねたんだ。
「サル――、サル――」
そういって日吉丸をののしる。
そればかりか、みんなでたくらんで、日吉丸の身に直接の危害までくわえはじめた。
嘉兵衛は、心配のあまり日吉丸をよびよせた。
「日吉、私がおまえをかわいがったことは、かえっておまえのためにならなかったようじゃな。
なんだか、申しわけないような気がする。
そこで相談じゃが、この際私のところをやめてはどうじゃ?
そのほうが、おまえのためになる。このままでは、おまえの身があぶない」
嘉兵衛は、ふところから路銀(ろぎん=旅費)をだして、日吉丸にあたえた。
「それにしても、おまえには才能がありすぎる。それで、人にねたまれる。
これからは、必要のないときには、なるべくその才能をかくすようにしたらどうじゃな?」
日吉丸は、ポロポロと涙を流した。 |

松下嘉兵衛との別れ
日吉丸の目になみだが……。
|
top
****************************************
|