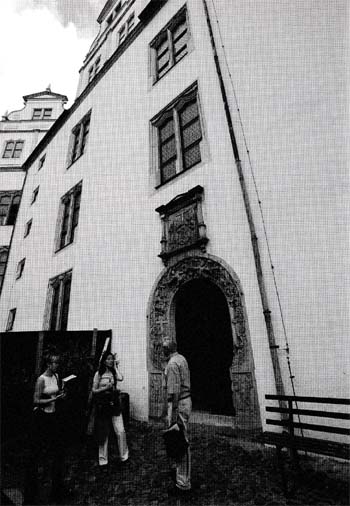|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章
五章 不戦と友好の町トルガウ
◆ライラックの花 それは、まさに信じがたい光景だった。
エルベ川の近くまで来ると、いたるところ咲き乱れるライラックの花。
陣地戦に継ぐ陣地戦で、出口のまるで見えなかった長い長い暗闇のあとに、生きることの感動で、最高に胸がときめいた瞬間だった。
(『Yanks treffen Rote』収録のポロウスキーの手記、樽屋文絝訳より)
|

ドルガウ市庁舎と露店マーケット
|

ウルリケさん家族とシェジナー氏(中央)
|
1 ウルリケ嬢とシェジナー氏 top
トルガウに着いた。とにかく、小さな町である。
エルベ川の岸にそびえ立つメルヘンチックな古城を基点にして、西に開けた市街地は、おそらく一キロ四方あまり。
車で走れば、すぐに突き抜けてしまう感じ。
まずは、市の西北に面したホテルセントラルへ。
名前こそ一人前だが、いかにも場末の頑丈そうな木賃宿的ホテルで、入口の木製ドアを開けて入ると、すぐ鼻先にフロントがあって、壁に骨董品のようなルームキーがいくつかぶらさかっている。
その右横がレストラン。といってもミニ食堂で、出迎えのお二方に会う。
少し日本語のできるライプチヒ大学三年生のウルリケ・エルメル嬢と、その恩師で、戦争中のことにくわしい元英語教師のヘルペルト・シェジナー氏だ。
ウルリケさんとは初めてではない。三ヵ月ほど前に、東京・赤坂のドイツ政府観光局で会っている。
トルガウについて問い合わせたのがきっかけで、特にそれらしいものはないけれど、ちょうど現地からの実習生がきているので、良かったら紹介するとのことだった。
願ってもない話で、まもなく帰国する彼女に、トルガウで「エルベの誓い」についての資料やら案内をぜひと頼んだのだ。
「こんにちは!」
と日本語で挨拶した彼女は、再会のせいか、にこやかな白い歯並みだった。
ややボーイッシュな断髪だが、季節が夏に変っていたせいか、見事なプロポーションである。
白髪でおだやかな表情のシェナジー氏は、ウルリケ嬢にいわせると、趣味みたいに「エルベの誓い」にのめり込んでいる方だそうだ。
そのことで海外からツーリストがくるたびに、案内したり解説したりしているという。
「でも、日本からの客人は非常に珍しい。これが二回目ですよ。一回目は一〇年以上前になるが、日本のテレビ局の取材でした」
「そんなにも前ですか。関心のある日本人がきたのは……」
「だから、テレビ局の人に聞いたのです。取材の目的をね。そしたらクイズ番組だという」
「クイズ? なるほど」
「そう、世紀のハイライトとかいってね。ここで何があったんでしょうってわけですかな。
そりやいいアイデアだといってやりましたがね。はっははは……」
と、にこそかに笑う。庶民的な人柄に加えて、教え子の紹介ということもあるのだろう、会ったとたんから、初対面という感じがしなかった。
「日本のテレビは、クイズばやりでしてね。なんでもかんでも、はい、ここでクエスチョンですというわけです。
広く浅くいこうといわんばかりに、右へならえですよ」
といいながら、私はふと気になったものだった。
ドイツ人にとっての「エルベの誓い」は、つまり敵兵同士が合流したことになるわけで、さてどんな感じになるのかなあと。
少なくとも、日本人の私が考えるほどには、客観的になれないはずである。
そのことは、もう少し先へいってから、聞く機会があるかもしれないと思う。
「もしお疲れでなければ……」
と、ジェンナー氏は切り出した。
「先に、ちょっと現場を案内するとしましょうか。なに、歩いてもたいしたことはありません。
観光客もこない小さな町ですが、歴史はやたらと古くて、それなりの味というか風情があると思いますよ」 |

左からシェナジナー氏、ウルリケさんと著者
|
|
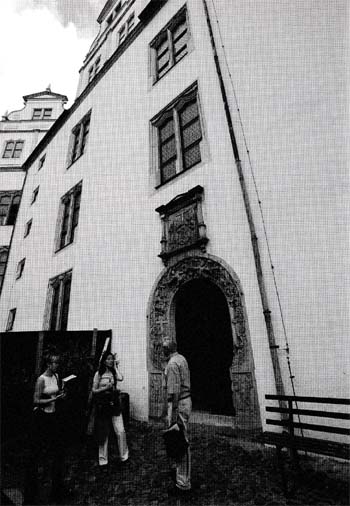
プロテスタントの最初の教会
|

マルチン・ルターの妻カタリーナの眠る教会
|
2 中世の面影を残す町 top
トルガウは、人口二万人ほどのミニ都市だが、私の第二印象は、中世のたたずまいを残したのどかな、そして静かな町並みだった。
高層ビルは皆無で、三階建てくらいの集合住宅が並ぶ。
白、クリーム、グレーとその壁の色は様々だが、屋根は三角形に尖っていて、大抵、赤か薄茶だ。
その色合いがよく調和されていた。
ベランダに添えられた花々も、通行人の目を楽しませてくれる。
大は小を兼ねるというが、都市に限っては決してそんなことはない。小さければ小さいなりに、古ければ古いなりの良さがあるのだと思う。
道を歩いていて、何となくゆっくりした感じになるのは、歩道橋とか電柱がないせいもある。
かわりに古風なカンテラが一定間隔で並んでいて、こまかな敷石の道だった。
コンクリートを流しこんだだけの道路とちがって、町造りには大変な手間ひまがかかったにちがいない。
お二人の説明によれば、トルガウは約一〇〇〇年の歴史があるが、コロンブスが新大陸を発見した一五世紀末あたりから、町らしくなってきたという。
ザクセン王国でもっとも大きく、近代的なハルテンフェルス城がエルベ河畔に建設されてからは、社会的文化的中心地の城郭都市として栄えた。
当時の人口は三〇〇〇人ほどだったが、城ができて倍以上にふくれ上がった。
城では議会や競技大合、花火大会も開かれ、皇帝の結婚式には人口と同じ三〇〇〇人もの客が集まったという。
城の完成に先だって、その隣接地に最初のプロテスタント教会ができたが、同教会は、宗教改革の先駆者マルチン・ルターによって奉献されたもの。
時のローマ・カトリック教会に対して、その世俗化と堕落ぶりを批判し、不退転で闘い拔いたルターの役割は大きい。
破門され追放されても、幽閉中に新約聖書のドイツ詰訳を成しとげている。
ルターは元修道女カタリーナと結婚したが、彼女が眠るセント・マリーズ教会が、エルベ川に出る道の途中にあった。
現在のトルガウは、二八〇もの個性ある建築物によって、中世の面影を代表する国際記念建築都市に指定されているのだという。
「しかし、壁崩壊からは状況が変わりました。若い人が出ていってしまうんですな、西へ西へと。
これぞという企業もなく、旅行者もこない町では、人口は減るばかり。今は二万人を切っていると思いますよ。
自由の代価は、決して小さくはないというわけです」
歩きながら、ジェンナー氏が含みがちの声でいった。教え子も黙ってうなずく。そうか、やっぱり……と私は思う。
伝統のある落ち着いた町並みに何かが足りないと気になっていたが、それは活力とか若さといえるものかもしれなかった。
3 出会いのモニュメント top
ルネッサンス風のハルテンフェルス城は町一番の高所で、教会堂の尖塔がぐんと屹立し、どこからでも見える。
近づいてみると、かなりの高さだ。その横の小道を抜けると、視界がにわかに開けた。
エルベ川だった。対岸が田園地帯のせいか、たっぷりとした水量で気持ちよく流れている。
すぐ南に、見るからにスマートな新しい橋が東岸へ伸びているが、一見してのっぺらぼうで、面白みに欠ける。
こちら側の堤防上は、樹陰も涼しそうな遊歩道になっていた。
古城を背にした広場正面に、威風堂々たる碑があった。
高さ一〇メートルほどもある石造りで、それが「エルベの誓い」のモニュメントだった。
ああ、これがそうか。とうとう歴史の現場まできたか、という思いが胸にこみ上げてきた。
「一九四五年四月二五日、この地でソ連赤軍と米軍が邂逅す。ファシスト・ドイツに勝利した赤軍と、英雄的な連合軍の勝利のために」
と、刻まれている。ロシア語である、
戦後すぐにソ連によって建立されたものだそうで、碑の真上にはソ連国旗と星条旗を左右にして、何本かのたてかけた銃が浮き彫りにされている。
武器はもういらないと、不戦を象徴しているのだろう。
ベルリンの壁崩壊のあと、よくぞこんにちまで無事に残されたものだと思う。
モニュメントと向かいあう堤防の一部が水面に突出していて、ちょっとしたバルコニー風になっている。
子供が遊び、若いカップルが堤防の上に座って、のんびりとくつろいでいる。川面からの風はさわやかで、何とも平和そのものである。
「そこが、出会いの橋のあったところですよ。橋桁だけを記念に残して、その上を、こんなようにね」
と語るジェンナー氏の頬に、木漏れ日がちらついている。
「橋そのものを残そうという声もあったんですね。平和と友好のしるしに」
「そうそう。何度か補修して持ちこたえてきたんだが、人が通るのがやっと、車はダメでした。
それじゃどうしようもないとあって、新しい橋ができると、もう用ずみってわけですな」
「前の橋は、たしか鉄橋式のアーチ型では……。
なかなか風格があったんじゃないですか」
「その通りです。よく知っている。その中ほどが爆破されたわけで、ほら、これを見てください」
4 “やらせ”の写真だった top
樹陰の下に、記念の案内板があって、破壊された旧橋の写真入りになっている。
こちら西側から写されたもので、よほど強力な爆薬が仕掛けられたものか、梏骨がぐにゃぐにゃに変型し、その一部が水面に没している。
対岸は森林地帯で、建物らしいものはない。
現在と変わりない眺めなのだが、ソ連側が高射砲陣地をかまえていた地点である。
モスクワのゴルリンスキー氏も、あの森のどこかに息をひそめていたのだろう。
「出会いの有名な写真は、橋桁の上で写されたんですね」 念のために、私はたずねた。 |

ナチによって爆破されたトルガウにかかるエルベ河の橋
|
「公式には、四月二五日、握手の瞬問にパチリということになっている。
ところが、あれは次の日に写されたものでしてね」
「え、そうなんですか」
「ま、いうなればやらせですが、戦争中だから、仕方ありませんな」
|

エルベの誓い。米ソ両兵士が握手。
左から2人目がフィルポット氏(1945年)
|

サンフランシスコでお会いしたフィルポットさん夫妻(2001年)
|
はっははは……と笑い、ウルリケさんに持たせてきた資料から、出会いの写真を手に広げて見せながら、
「実は、この背の高い真ん中の米兵は、デルバート・フィルポットといいます。
彼はね、壁崩壊後にトルガウヘやってきた。そして、これは自分だという。
ご冗談でしょうといったら、サインしてくれました」
「へえ? そうだったんですか」
「彼は当時二二歳でした。いろいろ話してくれましたよ。以来、親交が続いていますが、今はカリフォルニアに住んでいる」
「ああ、それで写された日がわかった、と」
「そうそう。それからね、最初の出会いは橋桁の上じゃないんです。
ここから南へ三〇キロばかりの地点でした。トップを切った米兵は通称ジョー。
ジョセフ・ポロウスキーといって、ほら、この人ですよ」
またまた広げたページの写真を、指で示した。
「やっぱり……」と、私は目を見張った。
現地まできただけのことはある。こんな貴重な写真があったのだ。
見たいもの知りたいことばかりで、私の声は無意識にはずんだにちがいない。
「この人が、そうなんてすか。ポロウスキーは、なんでまた、ソ連兵と一番に握手を?」
「中隊で、彼だけがドイツ語に通じていた。だから、偵察隊の先陣になったわけですな」
「そのポロウスキーこと、ジョーのお墓もあるとか」
「ええ、後でご案内するつもりですがね。彼の名前のついた学校もあります」
「学校? こちらではそんなに知られているんですね。なぜ彼けトルガウに慕が?」
たたみ込むような質問に、氏はちょっとたじろいだようだったが、何もそうあわてなくてもといわんばかりに苦笑した。
横でウルリケさんも、うふふっと白い歯をのぞかせている。
ジョーこと、ポロウスキーについては資料不足で、わからないことばかりだった。
だから、なおさらに知りたくもなるのだ。しかし、それには半世紀余をさかのぼらなければならないようである。
以下、ジェンナー氏の説明に、氏から提供を受けた『Yanks treffenn Rote』なとがら、ジョーの足跡をたどってみよう。
|

米ソ双方の兵士が何回か入れかわって写真を撮ったという
(一つ左上の写真と違っていることに注意)
|
5 ライラックの花盛り top
一九四五年四月、ナチス・ドイツ軍は終末期で、もはや完全に浮足立っていた。
ドイツ国内でかれらを南北に二分すべく、エルべ川に向けて米ソ両軍が迫っていたトルガウでは、四月一三日、ドイツ軍が住民に対し避難命令を出している。
ヒトラー指令ではあくまでも徹底抗戦の構えだったが、弾薬も補給も尽きていたから、戦う術(すべ)はなかったのだ。
二三日、ほとんど無人と化した町に、ソ連ウクライナ第一師団による砲弾数発が炸裂。
ソ連軍急接近にあわてふためいたドイツ軍は、エルベ川にかかる橋を爆破して、われ先にと退却した。
ソ連軍は、東岸で米軍の到着を待つことにした。
二四日、第六九師団第二七三歩兵連隊第一陣、A・コツビュー中尉ほか二八名が、トレプセン市からエルベ川に向けて出発した。
その中にドイツ語のわかるジョーこと、ポロウスキー二等兵もいた。
二五日、コツビュー隊は途中のキューレンからさらに前進し、一方、並行してロバートソン少尉の一隊がトルガウヘと向かう。ここまでは前述のとおりである。
さて、そのあとだが、エルベ川までたどりついたジョーが目にしたのは、快晴の陽光をあびて「いたるところに咲き乱れるライラックの花」盛りだった。
薄い紫色のリラの花のことだが、それはよほど印象的だったのにちがいない。
「生きることの感動で、最高に胸がときめいた」と、彼は書いている。
エルベ川は、流れも速く、雄大な眺めだった。
コツビュー中尉が緑色の発煙信号を二発を打上げた。対岸で、しきりと手を振る者がいる。ソ連兵だ。
こっちへ来いと手招きしているが、どうやって川を渡ったらよいのか。橋という橋はみな壊滅状態で、水面にわずかな残骸を出すだけだった。
しかし、よくよく見ると、こちら側に小舟がつながれている。
コツビュー中尉とジョーを含む六人が、それに乗り込んで、やっとのこと東岸へたどり着いた。
ところが、少し先で三人のソ連兵がうろうろと、何かためらっている様子。
さっきはもっと大勢いたはずなのに、何をしているのだろうか。以下は彼自身の回想記である。
6 ポロウスキーの手記 top
理由はすぐにわかった。川岸は五〇ヤード(一ヤードは約九一センチ)にもわたって、文字通り、死体で覆い尽くされていたのだった。
薪(まき)のように累々と折り重なっている女、年老いた男、そして子供たち。
一人の小さい女の子が片手に人形を握りしめていたのが、今でも目に焼きついて離れない。
五歳か、せいぜい六歳くらいであったろうこの少女は、もう一方の子が母親にしがみついているのだった。
一体何が起こったのか? 知っている者は誰もいなかった。
近くの橋は破壊されて、少なくとも二、三日は経っていた。ドイツ軍が撤退の際に爆破したのか、連合軍の爆撃によるものなのか。
しかし、川岸の惨劇は、おそらくソ連軍の遠隔砲撃によるものだろう。
こちら一帯は低地なので、ソ連軍からは、こんなにいた多くの一般市民は見えなかったにちがいない。つまり事故だったのだ。
この戦争中、何と多くの事故が起きて、罪もない人たちの命が奪われたことだろう。
一面に横たわっている死体は、我々のほうにこようとするソ連兵をひるませた。
そこで、死体の海の中でむごいショックに耐えねばならないのは、我々だけということになった。
信仰心の厚いコツビューは、かなり動揺していた。
中尉はいった。
「ジョー(ボロウスキーのこと)、犠牲となったこれら一般市民たちの前で、ロシア兵と確認しよう。
今日が、米ソ両国の歴史において犬切な一日であることを。
彼らにこのことを伝えてくれないか」
私の通訳で、ドイツ語のできるソ連兵が、他の仲間たちに、そのことを説明した。
二つの国が出会ったこの歴史的瞬間、そこに居合わせた両国の兵土たちが、皆おごそかに誓ったのだ。
このようなことが二度と地上に起らぬよう、各自が力をつくし、できる限りのことをしようと。
地上におけるすべての国の人たちが、平和に生きていくべきであり、それを単なる理想に終らせることなく実現しようではないか、と。
これが、我々の「エルベの誓い」である。
形式ばってこそいないが、しかし厳粛(げんしゅく)なひとときだった。
ほとんどの者は涙を浮かべていた。
将来、我々がこの時点で望んだようには、世界が順調に進むことはないだろうという予感が、それぞれの胸の内にあったかもしれない。
しかし、みな互いに抱き合い、このことは決して忘れまいと固く誓い合ったのだった。(前掲書)
|

エルベ河を渡った米兵を迎えるソ連女性兵士
|

喜びあう米ソ両軍兵士。
中央立ち上がっているのがポロウスキー(この本の主役)
|
7 反戦・反核の活動に top
そのあと、コツビュー中尉たちは、米軍司令部に連絡をとるべく一度無線機のあるジープまで戻ったが、またすぐソ連軍前線陣地へと合流した。
にわか造りのテントが張られて、先の誓いを繰返しながらの、乾杯また乾杯となった。ウオッカにドイツビールにワインに、みんなへべれけになる。
たちまち、友人となったソ連兵の奏でるアコーデオンやバラライカに合わせて、踊りがはじまった。
アメリカの曲だった。ロシア娘たちが踊った。
それは「あまりにも不思議な強烈な光景で、ずっと私の心をとらえてはなさない」と、ジョーは書いている。
ジョーは、「強烈な光景」と表現せざるをえないほどに感激したのだろう。
「涙をうかべて」ともあるから、彼の人生にとってこれほどまでに感激したことは、かってなかったのではないか。
その時、ジョーは二六歳だった。
植物学を専攻するシカゴ大学の学生だったが、戦争で学業を中断して、銃を持たねばならなかった。
彼は歩兵G中隊のライフル銃兵だった。
一九四四年六月のノルマンディー上陸作戦からアルデンヌの森の激戦を経て、たび重なる修羅場の闇をくぐり抜けてきた。
多くの戦友たちが、帰らぬ人となったにちがいない。
ライラックの花咲くエルベ河畔でのひとときは、死と闇のトンネルが終ったことを意味していた。
それは、夢にまで見た平和の到来だったといえる。
だからこそ、コツビュー中尉は通訳をしたジョーの功績をたたえて"ジョーがいなければ、話は何も通じなかった”、軍用地図を記念にプレゼントする。
銃も地図も、もう不要なのだった。
「さて、戦後のジョーは、どう生きたか。誓いの理想をどう活かしたか、ですが……」
と、ジェンナー氏は言葉を継いだが、次第に熱がこもってきたかのようだった。
「彼は、シカゴでタクシーの運転手をしながら、とぼしい収入をはたいて、冷戦への戦いを開始したのです。
それも、だった一人でね。
"エルベで誓い合った米退役軍人会”を組織し、元ソ連兵との交流の機会を作る一方で、自国の首脳や議員、マスコミや国連にと、何千通もの手紙を書き続けました」
「手紙をですか?」
何千通もとは、すごい数である。
「ええ、四月二五日を国際的な平和デーにせよ、とね」
「"エルベの誓い”を、あの不戦の誓いを忘れるなってわけですね」
「そうです。年ごとにエスカレートするばかりでしたからな、米ソの対決は。朝鮮戦争、ベトナム戦争と……。
彼はどうにもいただまれぬ心境だったのにちがいない。おれたちのあの誓いはどうなるのか、とね」
毎年四月二五日がくると、ジョーは反戦・反核のプラカードを掲げて、シカゴのミシガン通りの橋のたもとに立った。
ビラをまき、訴え続けたという。
あの日、ライラックの花咲くエルベ河畔で、米ソ両軍の間に交わされた誓いの原点に戻れ、「戦争はやめよ」「核の脅威を取り除け!」と。
しかし、通りすがりの人々には、おそらく風変わりな奇人、あるいは気がふれた男にしか見えなかったことだろう。
「あなたは何者か?」
と、問いかける人はそう多くはなかったが、すると、ジョーは四月二五日がどんな日だったかを、せつせつと語って聞かせる。
川岸を埋めつくした死体の山と、人形を手にした少女のことまで。
そんな活動を一〇年余も続けたが、ジョーの努力はついに実を結ぶことなく、終焉を迎えることになった。
ガンに侵されたのだ。手術を前にして遺言した。自分の亡骸はあのエルベ川の出会いの地に埋めてくれ、と。
一九八三年一〇月一七日、ジョーは死んだ。六六歳だった。
その枢は星条旗に包まれて空路東ドイツへと旅立ち、十一月二六日、トルガウ市郊外で水遠の眠りについたのだった。
top
****************************************
|