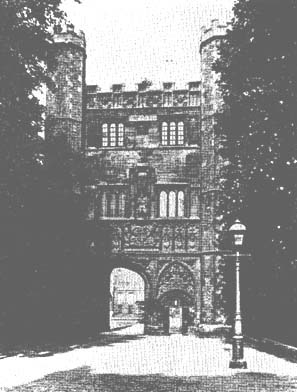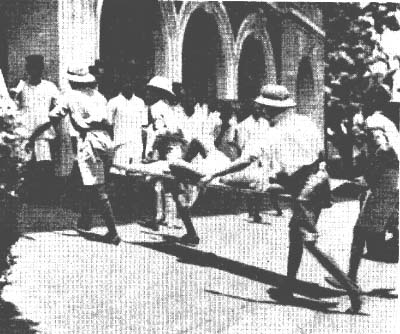|
****************************************
HOME 解説
中国 インド インドネシア フィリピン アラブ連合 イスラエル ガーナ
2 インド独立の父――ネール
1 ハスの花のちかい top
もし今、君たちが新聞記者とか評論家とか歴史家、そのほか世界情勢にくわしいといわれる人々をつかまえて、現代でもっともすぐれた話題の人を、十人あげてくれとたのんでみたまえ。
おそらくだれもがそのなかの一人に、インドの政治家パンディット・ジャワハルラル・ネールの名をあげないわけにはいくまい。
彼こそ二十世紀の生んだ偉大な指導者の一人なのだから――。
ネールがこれまでになしとげた大きな仕事は、かぞえあげればきりがない。
そのなかでももっとも大きな仕事といえば、次の三つであろう。
まず第一はマハトマ・ガンジーと一緒に歩んだ、インド独立への長い戦い。
第二は独立後のインドに民主主義をそだてるための苦難の道。
そして中立国の指導者として、世界平和のためにたゆみない努力を重ねてきたこと――この三つであろう。
アジア・アフリカに新しくおこった独立国の指導者といえば、ほとんどは貧しい家に生まれ、あるいはそれと同じような苦しい生活にもまれてきた人が多い。
それにくらべ、ネールの少年時代は、ひじょうにめぐまれていた。
ネールの家は、代々、インドでも特別ゆたかな、北インドのカシミール地方の学者の家だった。
インドには昔から、カースト制度といってきびしい階級制度のおきてがある。階級のちがった者とは、同じ職業についたり、結婚したりできないばかりか、食事も一緒にできない。
ネール家はこの階級制度のなかで、いちばん上のバラモンという階級にぞくしていた。
バラモンは代々、お坊さんや学者を職業にしている最上の階級である。
ネールのひいおじいさんの代になって、ネール家は、カシミールをはなれ、都のデリーにやってきた。
このひいおじいさんと、息子のおじいさんは、インド王につかえる役人だった。
一八八九年十一月十四日、ネール家には、男の子が生まれた。ジャワハルラルと名づけられた。
父はそのころ、デリーからさらに南のアラハバート市で弁護士をしていた。
インドは長いあいだイギリスに国をうばわれて、人々はたいへん苦しい生活をしていたが、政府の役人とか弁護士といった職業の人は、反対にたいへんゆたかな生活を送ることができた。
ネール少年の家も、たいへんな金持ちだった。
ネールが十才のとき、新しくたてた家には、ベランダのあるひろい芝生や、テュス・コートがあった。
そのころ、インドではまだめずらしい、電燈やプールまでついていた。
家には、毎日のように、イギリス人や、インド人の金持たちが集まり、人々は、この家を『幸福の家』と、よんでいた。
けれども、『幸福の家』に住んでいたからといって、ネールの子供のころが、幸福だったとは、かならずしもいえない。
なぜかといえば、ネールはいつも、一人ぽっちだったからである。
父は、朝から晩までおとずれる客の応待にいそがしかった。
書斎や客間から、父の大きな笑い声が聞こえてくれば、父は家にいるということになる。
広い家なので、一日、父と顔をあわさないという日も、すくなくなかった。
そこで、ネールは、小さいときは、ほとんど、母のそばでくらした。
母は小がらできゃしゃで、心のやさしいインド婦人だった。
父は、豪放な一面、気のみじかい人なので、家じゅうに、よく、かみなりがおとされた。
ネールは、父にしかられると、きまって、母のふところへとびこんだものである。
が、普通のときは女ばかりの母の部屋は、やんちゃな少年には、いつも退屈だった。
ネールが十一のとき、妹のスワラプが生まれた。
けれども、女の子だし、それに、あまりに年がはなれすぎていて、相手にならない。
小学校などというものはなかったので、家庭教師につけられ、学校友だちもなかった。
ずっとのちになって、二番めの妹のクリンチが、
「兄は、ひじょうに意志の強い人のように思われていますが、本当は、ひどく内気で、神経質でした。」
と、いっているのも、小さいときの、こんな環境のせいかもしれない。
ネールの家には、そのほか、おおぜいの従兄弟(いとこ)たちが、一緒に住んでいた。
インドでは、金持ちの家ほど、大家族でくらしているものなのである。
従兄弟たちは、みなもう大きくて、ネールの遊び相手にはならなかった。
けれどもネールは、ときどき、従兄弟たちのあいだにまじると、だまって話に耳をかたかけていた。
従兄弟たちの話ときたら、たいていきまっていた。イギリス人か、そのあいの子たちの悪口なのである。
「まったく、シャクにさわるったらありゃしない。
おふくろがイギリス人だというだけで、顔は僕たちとちっともかわらない。
そいつが、一等車にひとりでふんぞりかえっているんだ。
こっちは、ギュウギュウづめの立ちんぼ。おまけに、野菜やブタと一緒なんだ。」
汽車に乗って旅行をしてきた、いとこの一人が、ふんがいして、いきまいている。
「今日ね。あたし、かわいそうなおじいさんを見だの。ツエにすがって、やっと歩いていたわ。
そして、つかれたのね。道ばたにあったベンチに腰をおろしたら、インド人の警官がとんできて、『ここにすわっちゃいかん!』というの。
そして、おじいさんがぐずぐずしているといって、棒でぶったのよ。」
「そうだ。イギリス人がすわるベンチには、ぼくたちインド人はすわれないんだ。いったい、あいつらと僕たちと、どこがちがうっていうんだ。同じ人間じゃないか。」
「イギリス人なら、まだ、しかたないってこともあるけれど、がまんできないのは、その警官よ。おなじインド人が、なぜ、イギリス人のために、同胞を、棒でたたかなきゃたらないの?」
「それが、あの人たちの仕事なのさ。そうしなければ、今度は、あの人たちが、イギリス人の兵隊に、そうされるからね。イギリス人ならしかたがないなんて思っちゃいけない。やつらに、そんなひどいことをゆるしてはいけない!」 |
いとこたちの話を聞きながら、ネールの幼い胸はいっぱいになった。
ネールは、泣きながら、ムンシじいさんのところへとんでいった。
「どうしてなの? なぜ、イギリス人は、そんなにいばっているの? インド人が弱虫だから?いくじがないから?」
ネールが、幼い怒りをぶちまけるには、このムンシじいさんのところよりなかった。
ムンシじいさんは、ネールの父の、昔からの友だちだった。
もとはバートンというところで、ゆたかな暮らしをしていたのだそうだが、一八五七年、インドに反乱がおこったとき、イギリス軍のために、一家皆殺しになってしまったのだという。
その後一人さびしくくらしているわけだが、だれにでも親切で、ことに、子供たちにはやさしかった。
ネールは、なにか嫌なことや悲しいことがあると、かならずこのムンシじいさんの家をおとずれるのだった。
「インドが、弱い国だなんて、大まちがいだぞ、坊や。」
ムンシじいさんは、ネールの頭をなでながらいった。
「インドは、古い古い昔から、さかえだ国じゃった。そのころは、まだ、イギリスなんて国は、影も形もなかった。
いや、西洋の歴史がはじまる二〇〇〇年もまえに、わしらの祖先は母なるガンジス川、父なるインダス川のほとりに、偉大なインド文明を、きずきあげたのじゃ。
だが、あまりに長くさかえすぎた。
インド人たちは、祖先のはらった偉大な努力や、建国の若々しい精神をわすれ始めた。
インド人は、なまけ始めたのじゃ。
あまりにも偉大な文明をうけついでいくのに、つかれたといったらいいかな。
そこのところを、イギリス人なんて、ついさきごろ、できたばかりの若僧の国に、つけこまれたんじゃ。
人々は、インドを『老いたるライオン』などといって、わらいおる。
だが、インドはけっして老いたライオンではない。
『ねむれるライオン』なんじゃ。いつかは、ねむりから目ざめる。
目ざめたときこそ、イギリス人め、思いしるがいいのじゃ。」 |
ムンシじいさんは、ながいインドの歴史を、いく日もいく日もかかって、ネールに話してくれた。
お釈迦(シャカ)さまの始めた、偉大な教えの話もしてくれた。
ある日、ムンシじいさんは、大きな池のふちに、ネールをつれていった。
「それ、坊や、そこに咲いている花を知っているかな?」
「ハスでしょう?」
ネールは、あたりまえじゃないかといった顔つきで、ムンシじいさんを見あげた。
「そうじゃ、ハスじゃ。ハスの花は、お釈迦さまの花じゃ。インドの国花じゃ。
ドロ水の中にあって、あのような、清らかな花を咲かせる。
インドの花は、元々、あの花のように、清らかなのじゃ。
あまりにも清らかすぎて、イギリス人のような海賊どもに、だまされたともいえる。
だが、だまされて、やっつけられ、いじけてしまうようたのは、本当の清らかさてはない。
清らかとは、弱さではないんじゃ。
不正を憎む心、暴力や非道にたいしては、断固として戦う鉄のような意志こそ、本当の清らかさに通じるんじゃよ。
一八五七年の反乱のとき、インド軍の兵士たちは、このハスの花を合図に、いっせいに立ちあがった。
だれからも命令されたわけではない。相談があったわけでもない。
ある夜どこからか、だれからともなく一輪のハスの花が、兵士の手から手へと渡された。
そして、兵士たちの心はきまったのじゃ。
だが、知ってのとおり、この反乱は失敗した。
イギリス軍は、はるかによく訓練された軍隊と装備をもっていた。
そのため、インド軍の兵士はもちろん、罪のない女や子供まで、たくさんの人がころされたのじゃ。
わしの父や母、兄たちも殺された。わしは、まだ小さかったし、運よくにげのびることができたのじゃ……。
だが、あのとき、イギリス兵にみつかっていたら、父や母と同じ運命をたどっていたじゃろう。
あの反乱はイギリス人たちにも、大きなショックをあたえたはずじゃ。
インドが、けっして、眠りっぱなしのライオンではなかったことが、骨身にしみたはずじゃよ。」
ムンシじいさんは、手をのばして、ハスの花を一輪、手にとると、
「さ、おゆき。これを机の上にかざって、じっと見つめるのだ。ハスの花が、坊やに話しかけるだろう。
不正や暴力を、どんなに憎くまねばならないか、坊やに教えてくれるはずじゃよ。」 |
ムンシじいさんは、片手でハスの花をネールの手にもたせると、片手で小さな頭をなでながらいった。
「ウン。」
ネールは大きな目をクリクリさせながら、じっと手のなかのハスの花を見つめるのだった。
2 心のかて top
ネールに、古いインドの話をしてくれたのは、ムンシじいさんだけではなかった。
母やおばあさんも、大変な物知りだった。
カシミヤ地方にふるくからつたわるヒンズー教の伝説や、叙事詩のなかの英雄の話もしてくれた。
とくに、大おばさんは、ヒンズー教にかぎらず、インド文学について、よく知っていた。
『ヴェーダ』とか、『サンスクリット』とか、古典文学の話になると、おばさんはいつも時間をわすれるほどだった。
「おばあさんは、一生かかっても話しきれないほどの、神話や伝説を知っているんだな。」
ネールはそう思った。
十一才のとき、イギリス人の、新しい家庭教師がやってきた。フェルジナンド・ブルックス先生といって、ネールの勉強ぜんたいを見てもらうためだ。それまでも、ネールは、イギリス人の女の先生に英語をならっていた。
ネールの父は、インドの国を思う心では、他のインド人のだれにも負けない自信があった。だからといってイギリス人なら、だれもかれも悪く憎いというような、心のせまい人ではなかった。
イギリス人にも立派な人はいるし、インドはイギリスに学ばなくてはならないことが、たくさんあるということを、よく知っていた。
この父がえらんだブルックス先生は、人間として、先生として立派な人だった。ネールは少年時代、この先生からたくさんの影響をうけたのである。
ネールは、この先生のおかげで、まず、本にしたしむことをおぼえた。
『シャングル・ブック』『キム』『ドン・キホーテ』『ゼンダ城のとりこ』、そのほか、マーク・トウェーンの名作や、『シャーロック・ホームズ』の推理小説など、子供むきに書かれた英語の本が、ネールを夢中にさせた。
探検家ナンセンの北極ものがたりや、ウェルズの空想科学小説は、冒険のたのしさを、じゅうぶんに教えてくれた。
ブルックス先生は、さらに、ネールの勉強部屋に、小さな実験室をつくってくれた。ここには物理や化学の、ごく初歩の実験に必要な道具は、みんなそろっていた。この実験室は、ネールに自然科学にたいする興味の目をひらかせてくれた。
実験に夢中になると、ネールはまる一日、この部屋にとじこもって食事もわすれるほどだった。ブルックス先生は、たいへん知識のひろい人だった。
文学や科学ばかりではなく、哲学にも深い理解をもっていた。
ネールが、神知学という学問に心をひかれたのも、ブルックス先生の影響だった。神知学というのは、人間には神秘的な霊感があって、えらばれた者だけがこれを感知し、神の真理を知ることができるというので、インドではそのころ、たいへんはやっていた宗教哲学だった。 |

ネールはイギリス人の家庭教師に教育を受けた。
英国風の服装をした幼年時代のネール
|
ネールはブルックス先生につれられて、アニー・ベザント夫人の講演をよく聞きにいった。
ベザント夫人はイギリス人だったが、インドにながく住んでいて、神知学の大家だった。
ネールは、ベサン卜夫人の講演にすっかり心をうばわれてしまった。
そして、神知学協会の、熱心な会員になった。
そのとき、ネールは、まだ十三才だった。いつもえらばれた人――というほこりが、ネールに、ついてまわった。
そのため、ネールは、しぜん、自分の行ないや言葉に気をつけるようになっていた。
ブルックス先生は三年間で、ネールの家を去っていった。同時に、ネールの神知学にたいする興味もさめていった。
というのも、十五才になったとき、ネールは、イギリスの中学へ留学したからである。
一九〇五年の五月、ネール一家は、イギリスへ旅行した。父と母とネール、それに、まだ、赤ちゃんのスワラプの四人だった。クリシナは、まだ生まれていなかった。
一家がイギリスへ出発するまえ一九〇四年に、アジアでは、一つの戦争がはじまっていた。日露戦争である。
世界一大きな国で、世界一強さをほこる軍隊をもつロシア(いまのソビエト)。
それと戦うのが、ついこのあいだまで鎖国をしていて、やっと、世界の国々の仲間入りをしたばかりの日本。
勝負は、はじめから、きまっているようなものだ――と、だれもが考えていた。
ところが、対馬(つしま)沖の海戦で、日本艦隊は、ロシアがほこるバルチック艦隊を、めちゃくちゃにやっつけてしまった。いわゆる、日本海海戦である。
ネール一家は、このニュースを、ドーバーからロンドンヘむかう汽車のなかで知った。
「日本が勝ったって! 本当だろうか!」
あまり、ものにおどろかない、豪放な父が、びっくりしたような声をあげた。
ネールは父の手から新聞をひったくるようにうけとると、日本海海戦の記事に食いいるように見いった。読み終わったときのネールの目は、興奮でキラキラかがやいていた。 |

日本海海戦に勝利をおさめた日本艦隊司令長官東郷元帥
|
「日本が勝った! ぽんとうなのだ! あのちっぽけな日本が、ロシアをやっつけたんだ!
いままで、しいたげられてばかりいたアジアの国が、ヨーロッパの圧力を、自分の手ではらいのけたんだ。
なんて、すばらしいニュースだろう!」
ネールは、まるで、熱にうかされた人間のように、日露戦争の記事ののっている新聞を、かたっぱしから、買いあさった。
「いまにみろ。インドだって、おさえつけられてばかりはいないぞ。
よし! 僕はやる。イギリスで勉強するのは、イギリスのつくった政府のなかで、いい地位がほしいからではない。
勝つためには、相手をよく知らなければならないからだ」
ネールは、これからの勉強にも大きな張りがでてくるようだった。
日本が勝ったという記事に、大いに力づけられたのである。
3 イギリスでの生活 top
ネール少年がいれられたのは、イギリスでも、もっとも伝統の古いハロー中学だった。
父と母は、ネールがぶじにハロー中学に入学しだのを見とどけると、ヨーロッパ旅行をしながらインドへ帰ってしまった。
ハロー校といえば、イギリスの上流階級の子供ばかりあがる学校である。
ネールは、ここでは、よく勉強した。成績もよかった。
ハロー中学では、成績さえよければ、いつでも、どんどん、上級へあげてくれる。
ネールははじめ、ラテン語がよくできなかったので、下の学年にいれられたが、すぐ、上級にすすむことができた。
ネールはハロー校では外国人であり、しかもイギリスの植民地の人間である。
だからあまり友だちもできず、ここでもあいかわらず、一人ぽっち、そういうわけで、しぜん、勉強にも精がでた。
それにネールは、ただ、なんとはなしに学校にかよってくるイギリスの金持ちの生徒とはちがう、大きな目的をもっていっていた。
インドの独立という大望を、もっていたのである。
ネールは、本や新聞に、だれよりもたくさん、目をとおしていた。
だから常識は、他の生徒よりはるかにすぐれていた。
イギリスの政治の機構や、大臣の名前などになると、イギリス人の生徒などよりずっとよく知っていた。
といってネールは、けっして、ガリ勉ばかりする学生ではなかった。
フットボールや、サッカーなども好きだったし、得意だった。
さて一九〇六年から一九〇七年にかけて、インドの国内は、にわかに、さわがしくなった。『インドは、インド人の手で!』というスローガンをかかげて、ベンガル州、パンジャブ州、マハシトラ州といった、大きな州の人たちが、立ちあがったのだ。 |

ハロー枚時代のネール
|
|

英国官憲にさからってデモをするインドの婦人
|

“国産品を愛用しよう”というプラカードをかかげてデモするインドの人々
|
イギリスはインドから、原料をやすく買いあげて、それをイギリス本国で加工し、今度は高いお金で、インド人に売りつけるという政策をとっていた。
こうしておけば、イギリスの経済は発展するし、逆にインドはいつまでたっても発達せず、独立などというだいそれたことはできなくなる、という考えだった。
お茶、綿織物、砂糖、塩、みんなそうである。どれもインドで、原料はやすく手にはいる。だがそれを使ってできた製品を使おうとすると、高いお金をとられるというしくみである。
イギリスにかぎらず、ヨーロッパの国々は、植民地にたいして、みな、こういう政策をとってきたのだ。
これでは、インド人たちは、いつまでたっても、ひどい貧乏からぬけでることができない。
そこで、ベンガル州などの人々は、自分たちのものは、自分たちの手で、といって立ちあがったのだ。
国産品愛用運動である。
もちろん、イギリス政府は、この運動にたいして、すぐさま、弾圧にでた。
ライ、ジンク、チラットといった愛国運動家がとらえられ、国外に追放された。
が、こういったインド国内の不穏な動きは、イギリスの新聞には、あまりよくのらなかった。
ネールは気が気でない。
フランスやドイツの新聞をとりよせたり、最近インドからやってきた人の話を聞きにいったり、休みの日にはインド人の留学生や、いとこたちのいる家へいって、いろいろ話しあったりした。
ハロー校では、インド人の学生はすくなかったし、学校のなかでもめったに顔をあわせることもなかったので、そういったできごとを話しあう友だちがいなかったのである。
あるときネールは、成績のよいほうびに、学校から一冊の本をもらった。
それはイタリア統一の志士ガリバルジーの伝記だった。
一八六〇年ごろ、イタリアはオーストリアやフランスにはさまれて、国のなかは分割され、人々は苦しんでいた。
かつては、大ローマ帝国として世界に君臨したイタリアも、中世紀ごろから国が乱れ、小さないくつの国に分裂して、たがいにほろぼしあっていた。
そこのところを、まわりの大きな国々につけこまれたのだ。
ガリバルジーは北イタリアのニースに生まれた船乗りだったが、愛国の精神にあふれ、はじめ南アメリカにわたって、その国の自由の運動のために戦った。
が、祖国に統一運動がおこると、すぐそれに参加するためイタリアに帰り、わずか一千人の義勇兵をひきいて、シシリア島と南イタリアを統一してしまったのだ。
しかも統一された南イタリアを、国王の手にわたすと、自分はサッと田舎へ引退してしまった。
ガリバルジーのひきいる義勇兵は、みな赤シャツを着ていたので、赤シャツ隊といわれ、いまでも、イタリア人のほこりになっている。
ネールは、祖国イタリアの統一と自由のために、あらゆる苦難をたえぬいたガリバルジーの物語が、いつか他人事とは思われなくなってきていた。
はじめ、学校からもらったのは、ガリバルジーの伝記の一部だったが、ネールはさっそく残りりの二巻も、自分で買ってきて読んだ。
ネールの頭のなかでは、イタリアとインドがすっかり混同してしまい、興奮してなかなか、寝つかれなかった。
「そうだ! ぼくも、ガリバルジーのように、祖国インドの自由と独立のために戦おう!」ネールはそう決心すると、おちつかなくなった。
いつまでも、こんなのんびりした学校で勉強していたのでは、祖国の危急にまにあわない。一刻も早く学問をおさめ、その力を祖国インドのために、役だてなければ……。
ネールは父にねだって、ケンブリッジ大学に入学することにきめた。ハロー校にはわずか二年間いたばかりである。ケンブリッジ大学では、ネールは特に化学と地質学、植物学を勉強した。少年時代の実験室でのおもしろさが、ネールに、自然科学の科目をえらばせたのだった。
が、大学では学校で教わるよりも、自分で本を読んだり、友だちと研究しあったりして身につけた知識のほうが、はるかに役にたつことが多い。
ネールもハロー校とちがって、ここではたくさんの友だちをもつことができた。友だちのなかにまじって文学を論じたり、歴史を語ったり、政治について討論したりしながら、自分たちの考えをたかめていくのだ。
そのころイギリスでは、新しい思想家たちがあらわれてきた。
数学者であり、哲学者であるバートランド・ラッセル――この人の新しい自由の思想は、人々にふかい感銘をあたえた。
評論家であり、戯曲もつくるバーナード・ショーは、痛烈な皮肉をとはして、新しい批判精神を確立した。経済学者のケインズは、近代経済学という、新しい経済理論を発表して、人々をおどろかせた。
ネールたちは主に、こういう人たちの考えについて語りあい、議論をたたかわしたものだ。またネールは、夏休みにアイルランドに旅行した。
ここにはまた、アイルランドの独立のために戦った、シン・フェイン党の活躍がある。ネールは、自分の足で、この人たちの記録をしらべて歩いた。 |
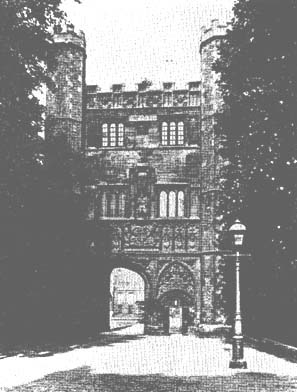
ケンブリッジ
|
一九一〇年、ネールはケンブリッジ大学を卒業した。そのあとの二年間、ロンドンで弁護士になる勉強をし、資格をとって彼は祖国インドへ帰ってきた。じつに七年間の長い留学生活だった。
4 ガンジーとの出会い top
インドにもどって二、三年のあいだ、ネールはアラハバードの高等裁判所へつとめた。
イギリスにいるとき、あれほど独立運動の血にもえていたネールだったが、この二、三年はなにか気のぬけたような気持だった。一時はインド全体をゆりうごかすほどだった独立運動も、指導者たちがとらえられて、すっかり鳴りをしずめてしまっていた。それにネール自身、七年間もの留学生活から帰ってみると、何もかもしっくりといかなかった。
まず英語をしゃべり、イギリスの歴史や文学をまなび、イギリス風の考えかたをすることにならされていたネールの行動や話は、いかにもインドの生活にはそぐわなかった。
そのくせネールはインド人であり、イギリスを批判しインドを愛した。
つまりインド人ともイギリス人ともつかぬ、中途半ばな存在になってしまったのだ。
ネールの考えはことごとく、国の人々と食い違っていたのだ。
ネールはどこへいっても、あまりおもしろくなかった。
弁護士会へいっても、話はいつもきまりきった商売のことである。
父にさそわれてはいった国民会議派の集会さえも、ネールには退屈だつた。国民会議派はインドの自治をもとめる運動をおこしていた。
自治というのは、植民地のまま、自分たちで政治をおこなうという制度である。イギリスからの独立をのぞむネールは、この会議派のなまぬるいやりかたに。あまり賛成できなかった。
「ものには、順序というものがある。あせって、さきをいそぎすぎると失敗する。我々は、まず、イギリス人を信じようではないか。」
イギリスで教育をうけた父はこういって、ネールをなだめた。 |

弁護士姿のネール(1912年)
|
父親にかぎらず会議派の人々は、イギリスで教育をうけた人が多く、みな英語をじょうずに話す上流社会の金持ちばかりだった。一般大衆の考えなどは、まったく知らず、また知ろうともしないし、政治運動などというものとは、およそ縁の遠い集りだった。上流階級の社交クラブぐらいに考えている人が、大部分だったといえよう。
一九一四年、第一次世界大戦がはじまった。
ドイツ、オーストリアの同盟軍が、イギリス・フランス・ロシアなどの連合軍と戦ったのである。
やがてアメリカや日本も連合国側に参加した。
が、戦いは長くはげしく、いつ終わるともしれなかった。
イギリス政府は、インドに、戦争に参加するようよびかけた。インド人たちは、イギリスのために戦うことを好まなかった。むしろ、ドイツが、イギリスをやっつけてくれればいいぐらいに考えている人が多かった。だが、けっきょくは支配者の権力には勝てない。多くのインド人と、多くの物資が、ヨーロッパ戦線へ送られていった。
その戦争のあいだ、一九一六年にネールは結婚した。
相手は、十七才のカマラで、あくる年、娘のインディラが生まれた。第一次大戦はますます、はげしくなっていった。
イギリスは、さらにインドに、戦争への協力を求めてきた。
そのかわりこの戦争に勝利をおさめたあかつきには、インドに自治をゆるしてもいいという。 |

フランスにおけるインド騎兵隊(1916年)
|
国民会議派をはじめ、多くの指導者たちは、イギリスのこの言葉を信じた。
そして新しいインド防衛軍を、ヨーロッパに送ることを考えた。
この防衛軍は、インドの中産階級の若者たちで組織されるはずだった。
ネールも、この新しい軍隊に加わる決心をした。
ネールはほかの人々のように、イギリスを信じたわけではなかった。
が、自分たち若者が、軍事教練をうけておけば、いざ独立戦争などというとき、役にたつと考えたのだ。
だがイギリスは、インド防衛軍ができただけでは満足しなかった。
もしこの非常時に、イギリスにそむくような者がいればたいへんである。
独立運動の指導者たちにたいする監視の目は、いっそうきびしくなった。
そして、全インド自治連盟のベンサンド夫人がとらえられた。
この事件はネールに、つよいショックをあたえた。
ベンサンド夫人といえば、少年のころ神知学の講演でふかい感銘をうけた人だった。
この人はイギリス人だったが、インド人の味方だった。
しかもすぐに独立をといったような、はげしい思想の持ち主ではない。
自治をあたえてくれという、隠健派なのだ。
ネールは怒って、新しい軍隊に参加することをやめてしまった。
「お父さん、ごらんなさい。これが、イギリスのやりかたなのです。
それでもあなたは、イギリスを信じろとおっしゃるのですか?」
「しかし、相手を信じなければ、とても自治なぞのぞめまい。」
「だから、私は完全独立をさけびたいのです。
ただお父さんが、時期を待てとおっしゃるから、その言葉にしたがったまでです。
でもお父さん、今度のヨーロッパ派兵の計画は、きっぱりやめてくださるでしょうね。
こちらが下手にでれば、やつらは、つけあがるばかりです。」
父親のモチラル氏は、新しいインド防衛軍の編成委員をしていたのだ。
「わしは、法にそむいた行動は、したくないのだ。
たとえ、自由のためとはいえ、つまらぬ血を流したくはない。
だが今度のことは、わしも態度をはっきりさせねばならぬ。ヨーロッパ派兵はとりやめにしよう。」
ネールは父の考えを完全に変えることはできなかった。
が、このときを区切りにして、父の考えかたが、だんだん変わってきたように、ネールには思えた。
息子の考えに、だんだん近づいてきたのである。
ネールが、カマラ夫人と結婚式をあげた年のクリスマスの日に、国民会議派は、ラクノウで大会を開いた。
|

ガンジー(前列中央の人。 1913年)
|

非暴力による抵抗運動をはじめたころのガンジー
|
ネールは、ここではじめて、マハトマ・ガンジーに会ったのである。
ガンジーこそは、長いあいだインドが待ちこがれていた偉大な指導者だった。
多数のインド人たちが、今やイギリスにむかって立ちあがろうと、心をかためていた。
しかし、その人たちは、いくつものグループにわかれ、それぞれ、勝手な方針で勝手に動きまわるばかりだった。
いまインド人に必要なのは、力づよい統卒力のあるリーダーだったのである。
ガンジーの名は、はやくからインド人のあいだに知られていた。
が、ガンジーは南アフリカにいったまま、インドには帰ってこなかった。
南アフリカに住むインド人たちの自由のために戦っていたのである。
人々は何度も、ガンジーをインドによびもどそうとした。
が、ガンジーは、政治問題にひっぱりこまれるのを、ひどくきらって、帰ろうとはしなかったのだ。
そのガンジーが、この会議に出席している――そう聞いただけで、ネールの胸はおどった。
ガンジーという人は、まるで、磁石のように、人をひきつける力をもっていた。
たくさんのインド人たちが、ガンジーを尊敬し、したっていた。
ネールもまた、ひと目でガンジーにひきつけられた。
どこから見ても、これがイギリスで法律を勉強したインテリとは思えない。
が、めがねの下にキラリとかがやく目は、つよい意志と何事も見とおさずにはおかない、理知の色をたたえていた。
一九一八年、第一次世界大戦は終わった。連合軍の大勝利だった。
しかし、この戦いで死んだ者は一千万人をかぞえ、負傷者やゆくえ不明の人間はかぞえきれなかった。
ヨーロッパに送られた、たくさんのインド人も死んだ。
インド人は、ヨーロッパの兵隊よりも悪い待遇で、しかも危険なところにばかりやらされていたので、犠牲者が多かった。
だが我慢しよう。これも、インドに自治をゆるされるための、貴い犠牲なのだから……指導者たちは、そう考えた。
ところがである。
戦いが終わってみるとイギリスはインドの自治などということは、ケロリと、忘れたような顔をしている。
そればかりではない。ローラット法というひどい法律をつくって、インド人を苦しめようとしたのだ。
ローラット法とはあやしいとみたら、逮捕状もなしに逮捕し、裁判にかけることができるという法律である。
これにはさすがおとなしいインド人たちも、すっかり怒ってしまった。
「お父さん、いかがですか? これが、イギリスの正体なのですよ。
これでもあなたは、イギリス人を信じろというのですか?」
ネールは、父親につめよった。
「ウーム。」
さすが穏健派の父親も、うなるばかりだった。
「ひどい。あまりにひどい……。しかしそれなら、どうすればいいのかな?
すぐにでも独立戦争をおこすかね?
だが一体、いく人の人が独立戦争についてくるだろう。人々は今度の戦争だけでも、もう血を見るのはたくさんだと思っているよ。」
そういわれてみると、ネールにもこれといってよい考えはうかばない。
どうやってこの怒りをイギリス人に見せてやったらいいだろう? 思いしらせてやったらいいだろう?
ネールはまよった。そのとき、ガンジーが立ちあがったのだ。
「インド人よ、イギリス人とあらそうな。イギリス人に反抗するな。
けれども、イギリス人の命令にしたがうことはない。イギリス人のつくった法律をまもる必要はない。」 |
こうして、サチャグラハ運動――不服従運動がはじまったのである。
もしローラット法が適用されたときは、全インドはストライキにはいり、労働者は仕事をやめ商店は店を閉じよというのである。
ネールはすぐさまこの運動に共鳴した。目のまえが急にひらけてきたように思われたのだ。
「私のいくべき道がみつかった!」
ネールは弁護士の仕事などそっちのけで、各地で演説したり新聞や雑誌にうつたえたりした。 |

ネール(左)とその父
|
だが、父のモチラル氏は、なおも慎重だった。
「この運動は、とりもなおさず刑務所いきを意味する。
自分から、ローレット法にふれて、監獄を志望するようなものではないか‥…」
モチラル氏は息子がこの運動に夢中なのが、心配でならなかった。
自分の息子がいっときでも、刑務所のなかですごすなどということは、たえられなかったのだ。
モチラル氏は何度か冷たいコンクリートの上で夜をすごしては、獄舎の冷たさをあじわってみたうえで、
「いけない、いけない。私の息子に、こんな生活は、たえられないだろう。たちまち、死んでしまうかもしれない。」
けれどもネールは、そんな父の心などすこしも知らなかった。そして父の考えのあまさが、歯がゆくてならなかった。
ふだんは仲のよい親子であったが、この政治的な考えをはさんで、二人の心がだんだんはなれていくように、ネールには思えるのだった。
父も同じことを心配したのかもしれない。
ある日父はガンジーをアラハバードにまねいて、サチャグラハ運動について話しあった。
ネールはガンジーが父を説得してくれることを、心ひそかに期待していた。
そしてソワソワしながら、ガンジーと父の話しあいが終わるのを待っていた。
ところが、父との会話を終えて、外へでてきたガンジーは、ネールをみつけると、
「ジャワハルラル君、あせってはいけないよ。なにごとも、しんぼうづよく、気長にやりとげることだ。
それに、何はともあれ、お父さんをこまらせるようなことをしてはいけない。
お父さんは、君のことを、ずいぶん気にかけていらっしゃるからね。」
ネールは、ぼうぜんとしてしまった。ガンジーから、父と同じこのような言葉を聞こうとは、夢にも思っていなかった。
〈ああ、ガンジーも、また、私の指導者ではなかったのか……。〉
いままでのガンジーにたいする尊敬の心が、だんだんうすれていくようにネールには感じられてならなかった。
5 独立へのけわしい道 top
ネールのこんな不安とはよそに、無抵抗・不服従の運動は、すこしずつインド全体にひろがっていった。
この不気味な闘争に、イギリス側は、神経をとがらせた。
そのやさき一九一九年の四月十三日、北インドのパンジャブ地方では、たいへんなさわぎがおこった。
その日の夕方、アムリツァーという町の小さな公園で、会議派の講演会があった。集まった人々はおよそ二千人。なかには夕涼みの老人や女、子供たちもまじっていた。
講演はなかばをすぎ、人々は講演を聞くでもなく聞かないでもなく、のんびりと夕風に吹かれていた。
と、そのときである。ダ、ダ、ダ、ダ、ダ……。
とつぜん公園の一角の小高いところから、機関銃の雨がふってきたのだ。
「キャーッ!」人々は、にげまどった。
この公園は三方を高い家にかこまれていて、出口がひとつしかない。そこには、一メートル半ほどの壁がたっていて、そのむこうが道になっている。人々はその壁を乗りこえて、外へにげようと壁にむかって殺到した。
そこをねらって機関銃が、きちがいのようになりひびいた。
たちまち、壁のまえは死体の山。かよわい女子供が多かった。このおそろしい事件は、パンジャブ地方の人々を恐怖におとしいれた。
人々はおそれおののき、各地に不穏な空気がただよった。
これを見てイギリス政府は、パンジャブ地方に、戒厳令をしいた。
パンジャブ州に住む人は夜間の外出をゆるされず、昼間買いものにいくにもいちいち監視がつく。
もちろん、州の外からは、だれもはいれなかった。
イギリスはこの事件に関するいっさいのニュースを、禁止した。
けれども戒厳令がとかれると、人々は救援のため、パンジャブ州におしかけた。
会議派は事件調査のために、のりこんだ。ネールも、その調査団にくわわった。
にげる人たちが殺到したという壁のあたりは、無数の弾丸のあとで、当時のひどさを物語っていた。
しかもその事件のあとアムリツァーでは、インド人がイギリス人のそばをとおるときは、腹ばいにならなければいけない、という規則までだされていたのだ。
「やつらにとって、我々インド人は、虫けらのようなものか!」
ネールの腹のなかは、にえくりかえるようだった。
そのうえアムリツァー事件の責任者であり指揮者でもあったダイヤー将軍は、一応軍事裁判にかけられたものの、なんのとがめもうけなかった。 |
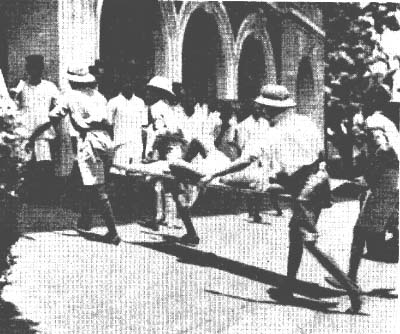
デモで傷ついた人が病院に運ばれる

デモに参加した女性の手から旗をとりあげるイギリス官憲
|
集まった群衆をストライキのための集会とまちがえた――つまり過失であるというのである。
そればかりではない。
当のダイヤー将軍はこのことを反省するどころか、まるで手柄話のようにトクトクと友だちに話しているのを、ネールは偶然同じ汽車にのりあわせて聞いてしまった。
汽車がデリーにつくと、ダイヤー将軍はこともあろうに派手なパジャマ姿のまま、ゆうゆうと駅の中を歩きまわっている。
インド人を人間とも思っていない、無礼なふるまいというほかはない。
この事件は、インドじゅうをゆすりにゆすった。
さすが穏健派のネールの父のモチラル氏も、こんどという今度は、かんにんぶくろの緒がきれた。
「イギリス人に、法律や常識がつうじると考えたのは、私の大きなあやまちだった。」
モチラル氏は息子と手をにぎって、ガンジーの運動をおしすすめることをちかった。
いままで運動の成り行きを見まもっていた、インドのイスラム教徒たちも、すすんでこの運動に参加することをちかった。
ここで初めてインドのヒンズー教徒とイスラム教徒が、手をにぎったのである。
ヒンズー教徒とイスラム教徒のにらみあいは、インドの歴史のなかで長いあいだつづき、このことがインドを弱い国にした、
一つの大きな原因になっていたのだ。
「チャルカをまわして、自分たちの手で糸をつむごう。」
ガンジーの、イギリス品非買運動がおこされた。チャルカはインドの手まわしの糸つむぎ機であるが、イギリスの安い綿布がはいりだしてからは、だれもそれを使わなくなっていた。
それをひっぱりだして糸をつむぎ、イギリス品を買わないようにしようというのである。
この運動の一周年記念日には、イギリス品の焼きはらいがおこなわれた。
町々のかどに、きものや家具やおもちゃなど、イギリス品が山とつまれ、それに火がつけられた。
一九二〇年、およそ二〇〇人の農民がパルタブガルという奥地から一〇〇キロ歩いて、アラハバー卜までやってきた。自分たちの苦しい生活を、町の政治家たちに知ってもらいたいとい、うのである。ネールはぐうぜん、アラハバートにいっていて、この農民たちと会うことができた。
農民問題はつねに、ガンジーの主張するところだった。
農民を大事にしなければいけない、農民を我々の味方につけなければと、主張していたのである。
だがネールは、不服従運動の仕事にいそがしくて、いままで農民と会う機会がなかった。
二〇〇人の農民たちは、ひどいぼろを着て、やせこけ、こじきよりひどいかっこうだった。
農民たちを苦しめているのは、イギリス人ではなく、同じインド人の地主や役人たちなのである。
農民たちのうつたえを聞いたネールは、さっそく、パルタブガル地方へいってみた。 |

インドの農村風景
|
人々はまるで神のすくいでもおとずれたように、ネールをしたい、口々に自分たちの苦しさをうつたえる。
ネールは胸のつぶれる思いだった。
じつのところネールはインドの上流社会に育って、こういう貧しい生活をしている人々のことは、なにも知らなかった。
一日の食事も満足に口にできず、ただ家畜のように、こきつかわれている農民たち。
「そうだ、この人たちをのけものにしてなんの独立だろう。
この人だもの苦しみをのぞいてやらないで、どんな国民運動が、おしすすめられるというのだろう……。」
ネールはできるだけ、人々のうつたえをきいてやった。
自分の力でできることなら、なんでも、力をかしてやった。
けれども、この貧しさは、一人二人の力では、どうすることもできない。
イギリスの力をはらいのけ、自分たちで、自分たちのための、いい政治をしなければならないのだ。
ネールはそのりくつを、よくわかるまで人々に話してきかせた。
そして自分たちの運動を、遠い農村までおしひろげる努力をかさねた。
一九二一年の暮れ、イギリスの皇太子が、インドをおとずれることになった。
それにたいして、ガンジーは、ボイコット運動を命令した。
この運動を知ったイギリス側は、皇太子がくる四、五日まえ、会議派の人々のいっせい逮捕をおこたった。
ネールの父もとらえられた。ネール自身も、とらえられた。
ただ、ガンジーだけは、ぶじだった。
ガンジーをつかまえることは、あまりに影響が大きすぎて、かえって危険だと考えられたからだろう。
だが指導者たちの逮捕は、かえってボイコット運動に味方したような結果になった。
アラハバードやカルカッタなど主な都市の機能はとまり、皇太子はストライキのおこなわれている、からっぽの大通りをすすまなければならなかった。
このためイギリスのインド政府は、きちがいのように運動をしている主な人々を逮捕した。
一九二二年、刑務所のなかにいたネールは、おどろくべきことを耳にした。
ガンジーが不服従運動の闘争を停止したというのである。
原因はチャウリ・チャウラという村で、村民たもの過激な人たちが、ひどい弾圧のしかえしに、警察を焼きうちにして、警官五、六人を焼きころしたというのである。
「それだからといって、いま、ここまでもりあがった運動を、にぎりつぶすということがあるもんか!」
「一地方におこった小さな事件を、いちいち気にしていたら、きりがない。」
獄舎のなかの人々は、いきりたった。ネールもすっかり、ガンジーのやりかたに失望した。
しかしガンジーは、他の人々より、もっとふかく、そのときの情勢を見きわめていたのだ。
たとえ小さな事件にしろ、焼き打ちをするなどということは、不抵抗をとなえる不服従運動の精神に反する。
こんなことになるのも、運動の正しい精神が、すみずみまで、よく伝わっていないからである。
そんなことでは、いつかこの運動そのものが、まちがった方向へむかってしまうかわからない。
それに運動の主な指導者は、みんなつかまってしまっている。
運動はいま、糸をきられたタコみたいに宙にういてしまっている。
一時の熱にうかされた民衆だけでは、どうひっくりかえるかもわからない。
それよりも、時期を待とう。みんなが獄舎からでてきて、もう一度じっくりと、運動の方針をたてなおそう――というのが、ガンジーの考えだったのだ。
だがネールは、長いあいだ、このガンジーの考えを理解することができなかった。
というのもネールたちとはいれちがいに、ガンジーが刑務所に送られてしまったからである。
不抵抗不服従運動は、しばらく活動をとめてしまった。
6 貴い犠牲 top
一九二三年、獄舎をでたネールは、アラハバートの市長選挙に立候補して当選した。
だがイギリスは、なにかにつけてこの新市長の仕事のじゃまをするのだった。
市の予算も事業もイギリスの許可がなければ、思うようにつかえない。
予算がとれなくては市長として失格というほかはない。
しかも当時、ネールは、会議派の書記長もしていたので、一日、目のまわるようないそがしさだった。
一日十五時間、はたらきずくめで食事をとるひまもないありさまである。
このためネールは、市長という職の無意味さと、自分の健康を考えあわせ、会議派の仕事にだけ専念することを決心した。
在任わずか二年間の市長だった。
一九二六年、ネールは一家をつれて、ヨーロッパへでかけた。
夫の入獄、収入がすくなくなったための家計のやりくりなどで、元々からだのあまりじょうぶでなかったカマラ夫人の健康が、ひどくわるくなったので、静養をかねての旅行だった。
この旅行中、ネールは、ベルリンで、被圧迫民族会議の人々と話しあう機会があった。
南アメリカ、ジャワ、フランス領インドシナ、パレスチナ、シリア、エジプト、北アフリカといった植民地の国々の人々が、ベルギーのブリュッセルに集まって、反帝国主義の会議をひらいていたのである。
そのなかには、アインシュタイン、孫文夫人、ロマン・ロラン、ホー・チミンといった、有名な人々もいた。
それを知ったネールは、インド会議派の代表としてブリュッセル会議に出席したのである。
この会議に出席してネールは、はじめて自由というものを、世界的なつながりのなかで見つめることを知った。
ひとつひとつの国の力は小さいけれど、おたがいに手をむすべば、征服者の大きな力をはねかえすこともできるのだ――という自信と、力づよさを感じたのである。
一九二八年、インドに帰ったネールは、あくる年、インド国民会議派の議長にえらばれた。
はじめ、ガンジーが議長におされたのだったが、ガンジーは、辞退して、かわりにネールを推薦したのである。
年をとっているということと、これからのインドをひきいていく人は、世界の動きにあかるくなくてはいけないというのが、その理由だった。
インドに自治をあたえよ、という運動は、そのころ、すでに、インド全体に、火のようにひろがっていた。
あちこちで、イギリス軍とインド側の、小さな小ぜりあいがつづいていた。ガンジーはふたたび、チャンスがおとずれたことを見てとった。
ガンジーはイギリス製の洋服をつかわずに、自分たちの手でつくった布で服をつくるよう、もう一度、運動をおこした。この運動に参加した人々は、自分たちの手で織った、ホームスパンの小さな白い帽子をかぶることにした。
しかしイギリス軍の騎兵隊が、群衆のなかにあばれこんだり、警官の竹のむちがふりまわされたりするなかで、この不服従運動をおしすすめることは容易なことではない。
ときには軍隊の行進する道に横だわって、不服従を示すという戦術さえとられた。
銃よりも精神的圧迫のほうが、より強力な武器である、との考えからだった。 |

みずから糸をつむぐガンジー
|
|

モチラル・ネール逮捕に抗議する学生たち
|

ネールがいれられた獄舎
|
一九二九年の会議派の大会で、自治ではなくインドの完全独立を要求する決議がおこなわれた。
そしてあくる三〇年の一月、インドの自由を求める大行進がおこなわれた。
一月六日、ガンジーはいく人かの人々と一緒に、アラビア海岸のダンデイにむかった。
「我々の塩は、我々の手で……。」
そう叫びながら、人々は行進した。
塩は政府の専売品で、一般の人々は、塩をつくることができない。しかもその塩には法外な税金がかけられていた。
そのため塩のねだんは高く、貧しいインド人は生きるためにいちばん必要な塩すら、なかなか手にいれることができないのだ。
ガンジーのひきいるこの行進には、あとからあとからと人々がくわわった。はじめ八十人たらずの行進が、ダンデイにつくころには、数千人の数になっていた。
人々はガンジーとともに海水で体をきよめ、塩づくりにとりかかった。
これはイギリスにたいする、大きな反逆である。イギリスのつくった法律を、はっきりとおかしたのだから。
ガンジーとネール親子はたちまちとらえられ、刑務所へいれられた。他の多くの人々もつかまった。
が、今度の運動は一九二〇年のころとは、まるっきりちがっていた。
各地の労働者は立ちあがり、ストライキやデモが、インドのあちらこちらに、ひきおこされた。
いままで政治向きのことには、まったくタッチしなかった女たちも立ちあがった。イギリス製品のボイコット運動は、こうした目ざめた女性たちの手で、ひろがっていったのだ。
ネールの母も、カマラ夫人も、この運動の先頭に立ってはたらいた。
そのため警察につかまったことも、しばしばだった。
こののち、一九四七年、独立が達成できるまで、ネールは、刑務所をでたりはいったりした。
数えてみるとザッと十年間、刑務所のなかで生活していたことになる。
そのあいだネールは、同室の者たちと未来を語り、計画をねり、研究しあった。独房にいれられたときは、できるだけ本をとりよせて、読むようにした。長いあいだ、いそがしい生活がつづいて、ろくに本を読むひまがなかったのである。
だがいちばん気にかかるのは、娘のインディラのことだった。
父親は長いこと獄舎にあって、勉強をみてやることもできない。
家のなかはつねに官憲にあらされ、母もまた夫の仕事をたすけることにいそがしかった。
そこでネールは、娘に長い長い手紙を書いた。そのなかには、世界の歴史が、わかりやすく書かれていた。
これは、のちになって、一つにまとめられ、『父が子に語る世界歴史』として出版された。
このあいだネール家にとっては、悲しいことがうちつづいた。
まず、一九三一年、父親のモチラル・ネールが死んだ。 |

娘のインディラとネ一ル夫妻(1918年)
|
長い刑務所生活が、モチラル氏の健康をそこねたのだったが、それにもまして出所後のはげしい運動が、病気を悪化させたものにちがいない。
ガンジーや息子のネール、その他ほとんどの指導者たちが刑務所にいるあいだ、会議派の重要な仕事を、ほとんど一人でひきうけていたのだ。モチラル氏の死ぬちょっとまえに、ガンジーもネールも、釈放されていた。
「ガンジーさん。」
モチラル氏は、枕元にかけつけだガンジーにいった。
「私は、まもなくお召しをうけます。私はインドの独立を見ることはできないでしょう。だが、かならずあなたが、独立を勝ち取るであろうことを信じています。」
父の死からいくらもたたない一九三六年、今度はネールの妻のカマラが死んだ。ついで、二年あとの一九三八年には、ネールの母親がなくなった。
この二人の婦人は、全インド女性の母だった。
家にひっこみがちのインドの女たちを立ちあがらせ、大きな組織にもっていけたのは、この人たちのたゆまぬ努力があったからである。だがその仕事が、このきゃしゃな元々体のあまりじょうぶでない、二人の命をちぢめたともいえる。
カマラが死んだ日、だれかがネールの服に、赤いバラをつけておいた。それいらいずっと、ネールはどこへいくにも赤いバラを胸につけては、亡きカマラ夫人を思い出すのだった。 |

非合法の塩つくりをする
ネールの妻カマラ(左)と母(カマラの向かって右どなり)
|
7 独立の旗のもとに top
一九三九年、第二次世界大戦がおこった。
が、今度はインドも前のような、遠い戦争といった、呑気な構(かま)えはしていられなかった。
真珠湾でアメリカ艦隊をやっつけた日本軍は、たちまちのうちに、南方諸島のオランダ軍をうちやぶり、ビルマ、インドへとせまったからである。
インドはただちに、連合軍にくみいれられた。インド人たちの考えなど問題ではなかった。
ロンドンからの命令一つで、そうきめられたのである。国民会議派はイギリスの命令を拒否した。
もうそのころ国民会議派の力はインドの全体をにぎり、市や町の議員たちも、どんどん会議派の人たちで、しめられていった。そのあいだも戦争は、ますます連合軍側に不利になっていく。
イギリスはまたもや戦争に協力してもらうかわりに、インドの自治をゆるすと申入れてきた。
が、今度はもうその手にはのらなかった。
一九四二年、会議派の大会はインドの完全独立をイギリスに要求した。
そしてすばらしく大きな反英運動を展開したのだった。
ふたたび、多くの人々がとらえられ、一万人以上もの人が殺された。ガンジーもネールもとらえられた。
ガンジーはこの乱暴なおこないに抗議するため、二十一日間の断食を宣言した。
またネールは、獄中で『インドの発見』の著作にせいをだした。
しかしインド独立ののろしは、こういう指導者たちをうしなっても、もう、おとろえることがなかった。
各地でストライキや衝突や流血さわぎがおこった。
そしてそのさわぎは、まるで枯れ草にもえうつる火のように、たちまちインド全土にひろがったのだった。
一九四五年五月、ドイツが連合国に降伏した。
同じ日、イギリスではチャーチル内閣がたおれ、アトリーのひきいる労働党が内閣をとった。
アトリーは、「インドに自治をあたええよ。そして、インド人自身のことは、インド人がのぞむところの政府によって、決定されるべきである。」と、いった。
そして六月、ネールをはじめ会議派の人々は、釈放された。その年の八月、日本が連合国に無条件降伏を申入れた。だが、日本がアジアの植民地各国にまいた爆弾は、連合国側にとって、けっして、小さいものではなかった。
また、終戦と同時に終わるものでもなかった。
八月十六日、ベトナムがフランスから独立した。
十七日には、インドネシアがオランダにたいし、独立を宣言した。一九四六年には、フィリピンがアメリカから、マレー半島がイギリスから、それぞれ独立した。
もう、イギリスには、インドをおさえる力はなかった。
一九四七年八月十五日、ついに、インドは独立した。
ネールは、新しいインド共和国の首相にえらばれた。
「ついにきた! 真夜中の時計が鳴るとき、世界の人々は眠り、インドは目ざめるのだ。我々の生命と、自由にむかって……。」
十五日の朝をまえにして、ネールは声高らかに叫んだ。 |

インド独立の日。よろこびをわがちあいに集まった群衆
|
十二時の鐘が鳴り終わると、ホラ貝の音が空になりひびいた。
新しいインド共和国の国旗が、スルスルとポールをのぼった。
国歌がはずむように、人々の口からほとばしりでた。
聞いているネールの目から、ひとすじ、ふたすじ、白いものがほおをつたっておちた。
「ああ、お父さん! お母さん! カマラー見てください。ついに、インドは、独立したのです。
あなたがたの努力が、いま、実をむすんだのです……。」
インドに独立をあたえたイギリスは、最後まで卑劣な手段をとった。
インドをパキスタンとインドのふたつにわけて、それぞれ独立国にしたのである。
パキスタンには、イスラム教徒がたくさんいる。そして、インドにはヒンズー教徒が多い。
インド独立のため、このふたつの教徒は力をあわせたが、元々まるでイヌとネコのように仲が悪い。
そこで喧嘩をしないようにというのが、イギリスのいい分である。
が、しかしその仲のわるさを利用して、いつまでもインド国内に、ゴタゴタをおこさせようというのが、本当の考えだったのだ。
ガンジーは、このことをたいへん心配した。
せっかく独立しても、国のなかにゴタゴタがあっては、いつまでたっても国が発展しない。
同じインド人なのだ。両方とも、手をむすぶべきだ――そう考えたガンジーは、表むきの政治のことはネールにまかせ、もっぱら地方を歩いて、このふたつの教徒の主だった人たちを説得して歩いた。
ガンジーの努力も、どうやら実をむすぼうというときだった。
ガンジーは自分と同じヒンズー教徒の、頑固な考えの持ち主に殺されたのだった。このため二つの教徒はついに分裂し、独立後も、長いあらそいをつづけることになった。
しかし、ネールはいつまでもガンジーや肉身の死に、悲しんではいられなかった。明日のインドの建設がある。
長いあいだの植民地政治と独立への戦いのために、インドはいま、まったくつかれきっている。
職もなく家もない貧しい人が、村にも町にも、道路にも、みちあふれている。まずこの人たちに食物をあたえ、家をあたえ、職をあたえなければならない。
そして教育をひろめ、字も読めないような文盲(文字のよめない人)を、なくさなければならない。
それには、まず、国の経済をたてなおすことが第一だ。
ネール首相は、経済五ヵ年計画というのをたてて、インド経済の五年先の目標までつくり。 |

ガンジーは暴徒の手にかかって倒されてしまった(1848年)
|
それを実行にうつしている。最初の五ヵ年計画ができたらさらにその先と、ドンドン計画も発展させていくのだ。
ネール首相がてがけた仕事は、そういう国内のことばかりではない。
戦後世界は東と西にわかれて、おたがいに軍事競争をしながらにらみあっている。
なるべく多くの国を味方につけ、すこしでも相手より強くなろうと、たいへんな競争をしているのだ。
そのなかでネール首相は、西にも東にもつかないで中立をとなえた。
中立国は西にも東にも味方しない。だからどちらの国とも貿易ができる。
また、どちらの国から経済的援助をうけても、すこしもかまわない。
新しくおこったまだ力のない国は、この中立をとったほうが得なのである。
このネール首相のとった中立政策は、アジア・アフリカのだくさんの新興国にみとめられ、中立国の仲間入りをする国が、どんどんふえるようになった。
国の数がふえると、しぜん国連などで発言する力が強くなる。
それはともすると、自分たちの力にたよりそうになる、東や西の国々の考えに反対できる、第三の大きな勢力ができたことにもなるのである。
ネール首相の中立外交が、どんなに世界の平和の役にたったか、その例は数えきれないくらいである。
「ガンジーがインドの魂であるなら、ネールはインドの知恵であり意志である。」と、ある学者はいっている。
また、ある人は、
「ネールは、東と西がであったところの屋根である。ネールのなかには、ふたつの文明のエキスがとけあっている。それは、未来の姿であり、人間の姿でもあるのだ。」
と、いっている。
ネール首相は、こうして祖国インドのために、たゆまぬ努力と前進をつづけてきたのだった。
しかし、その偉大な指導者ネールも病気にはかてない。
インドなしにネールは考えられるが、ネールなしにインドは考えられないとまでうたわれたネールだったが、一九六四年五月二十七日、心臓病で七十四年の一生をおえたのである。
文字どおり、独立と平和にささげた一生だったといえよう。
top
**************************************** |