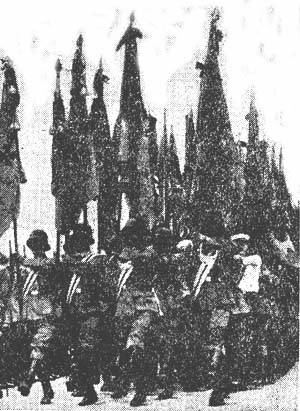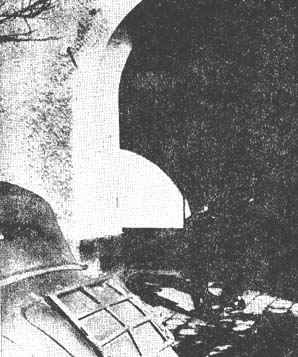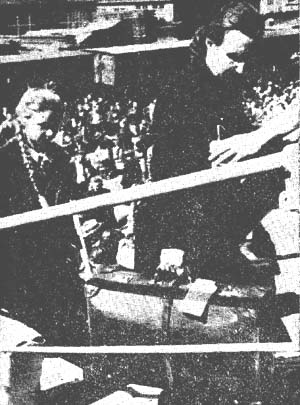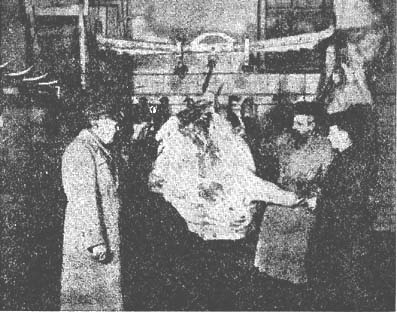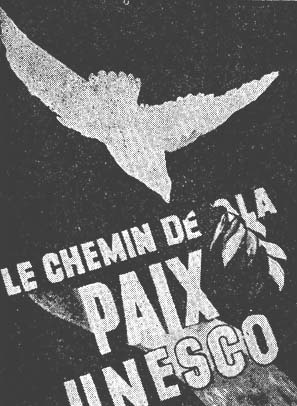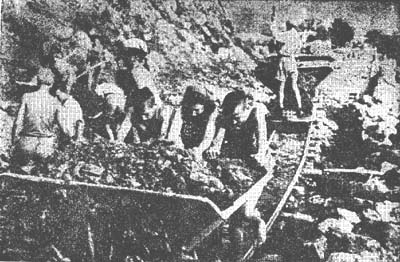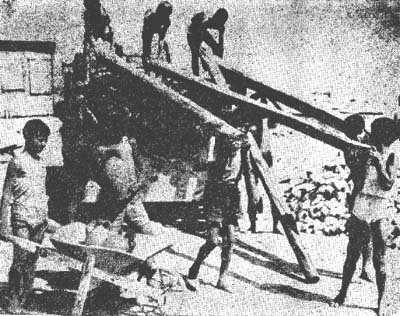|
****************************************
HOME チャーチル ルーズベルト ウォーレス 国際連合 ユニセフ 世界平和の戦士 エリノア 明石康
Ⅰ 大戦終決直後の国際連合(ユニセフ)の活躍
(少年少女20世紀の記録 p10-132)
原著者紹介
エリノア・ルーズペルト (Eleanor Roosevelt)は、第二次大戦時にアメリカ大統領だった故フランクリン・ルーズベルトの夫人です。1884年にニューヨークのハドソン川のほとりの旧家に生まれました。
八才のとき母に死に別れ、十才のときには父をなくし、二人の弟ともに孤児になってしまいました。
十五才のときイギリスに渡って、そこで教育をうけ、やがて1908年にフランクリン・ルーズベルトと結婚しました。
五人の母となりましたが、社会改良事業に努力し、また、各種の婦人団体の指導者になりました。
日本に来たこともあります。
また第二次大戦後、ニューヨークに国際連盟に代わる国際連合が創設された時そのアメリカ代表となり、国際連合の発展に尽しました。
本書は編集者であり児童文学者であるヘレン・フェリス女史の助力を得て書かれたものです。 |
1 少年少女たちへの誓い top
世界の少年少女たちは、国際連合では大切な存在なのである。
一九四五年の六月二十六日、アメリカのサンフランシスコに集った五十ヵ国の代表が、『国際連合憲章』に署名したとき、彼らは憲章の前文で、次のように少年少女たちに誓ったのである。
| 「我々、国際連合の人々は、我々の時代に二度までも、言葉でいいあらわせないほどの不幸を人類にもたらした戦争のわざわいから、次の時代をになう少年少女を救うことを決意した。」 |
少年少女のために、よりよい世界をきずこうというのが、国連の重要な仕事の一つなのである。
国連の人たちは、世界中の国々へいって、そこの政府と力をあわせ、少年少女たちがすこやかに生活ができ、もっと学校をふやし、もっと楽しく暮らせるように、努力しようと決心した。
そしてどこの国の少年少女も国連の協力者になり、国連の主催でひらかれる世界中の少年少女たちの集りに出席し、そこで一緒になった新しい友たちと仲良くなり、お互いに理解しあうようにとねがったのである。
しかし、一九四五年の六月のあの記念すべき日、サンフランシスコに集った五十ヵ国の代表者たちは、まず、さし当って、国連がしなければならない少年少女のための大問題が、すぐ目の前によこたわっていることに気がついていたのだった。
第二次世界大戦のわざわいをうけた国々には、何百万という少年少女や幼児たちが、食べ物もなく衣服もなく薬もなく家もなく、ほったらかしになっていたのである。
戦争で家をおいだされた、たくさんの子供たちは、洞穴に住み、こわれた家のあとに住み、焼けた貨車に住んで、雨や雪をさけていた。
たくさんの少年少女や幼児たちは、両親と別れ別れになったり、殺されたりした。誕生したばかりの国連は、まずこういう少年少女や幼児を救うために、立ち上がったのである。
では、その話からはじめよう。 |

家もなく、親もうしなった戦争孤児
|
2 帰ってきた少女 top
しかし捜索班の人たちは、それくらいのことではあきらめなかった。
捜索班の人たちは、すぐにフランクフルト市へ向かった。
電報をよこしたその本人にあって、よく話を聞こうと思ったのである。
ところがフランクフルト市の戦争裁判所についてみると、そんな名前の人は、どこをさがしてもいなかったのである。
それでも捜索班の人たちは、あきらめなかった。
その人たちは、新聞社をとおしたり、集りにでたり、あらゆる機関を利用し、あらゆる方法を使って、電報を厚生大臣におくった相手をさがし続けた。
ある日、ついに捜索班の一人が、その人なら知っているという婦人に出会うことができた。
「ええ、知っています。その名前の人なら、ここから八十キロほど離れた村にいますわ。」
その婦人は、そういってその村を教えてくれた。
捜索班の人たちは、またもや、ジープにとび乗ると、その村にいそいだ。しかし、その村についてみると今度も、たずねる人はいなかった。
ところが、その村の役場につとめている、ある人が、その村に住んでいる、もとナチスの役人の未亡人が八つぐらいのもらい子を育てている、とおしえてくれたのである。
「この子ですがね――。」
役場につとめているその人は、戸籍簿を見せてくれた。
捜索班の人たちは、熱心にのぞきこんだ。そこには、ハンナ・スポッ卜という名前が、書いてあった。
「名前はかわっているが、この子にちがいなさそうだ――。」
しかし、捜索班の人たちは、すぐにそのナチスの元役人の未亡人の家へいくことはしなかった。一度、フランクフルト市へひきかえすと、そのことをいって、陸軍省から、パンチの転出許可書を発行してもらったのである。
あくる日、捜索班の人たちは、許可書をもつと、その未亡人の家ヘジープを乗りつけた。
捜索班の人たちは、誰でも心のなかで、パンチがドイツの子供ではなく、チェコの子供だとつげられたとき、はたして何というだろうかと、思うのだった。
「そんなことは嘘にきまっているわ。私は、この家の子なのだから、この家から動かないわ。」
そういうかもしれない。げんにいままで、探しあてた子供のなかで、こういった子供が何人かいたのである。
玄関にあらわれた未亡人は、しきりにその女の子が、自分の本当の子供に間違いないと、いいはった。しかし、捜索班の人たちは、それくらいでは、ひきさがらなかった。
「それでは、その子供を、ここへ連れてきてください。」
そういわれて、未亡人は仕方なしに、ハンナを奥からつれてきた。
捜索班の人たちは、ハンナを一目見るなり、すっかり疑いがはれた。みんなの目の前にあらわれた少女は、五年まえの写真にそっくりだったからである。
捜索班の一人が、その少女にやさしい声で、よくわかるようにドイツ語で、それまでのいきさつを話してやった。そして、ここにいるのは、おまえの本当のお母さんではないのだと、教えててやった。
「おまえの本当のお母さんは、チェコで一日もはやくあいたいと、おまえを待っているんだよ。」
ハンナはだまってじっと聞いていたが、捜索班の人の話がおわると、クルッと振り返って、未亡人にいった。
「私の荷物をもってきてください。」
未亡人が、おずおずと、ハンナの持ち物を運んでくると、
「これでみんなですね?」
そういって確かめると、ハンナは捜索班の人たちのジープに乗りこんだ。ジープが走りだすと、ハンナは、あとからあとからと、本当の自分の母親のことを、捜索班の人たちにたずねるのだった。
そしてチェコの言葉で、「お母さん、私は、帰ってきました。」という文句を教えてもらって、一生懸命におぼえ始めた。
ハンナは、自分の国の言葉を、すっかり忘れてしまっていたのである。
ジープはひとまず、フランクフルト市についた。
ここには、国際連合の手で設けられた、国際難民救済所があって、ハンナは、そこへひとまずあずけられた。
この救済所へは、捜索班の手で探し出された、チェロの子供たちは、誰でもひとまず、入れられることになっていたのである。
七十六名のチェコの子供たちが、そこで一緒になると、陸軍省ではプラハまでの特別車両を二台、列車にとりつけてくれた。七十六名の少年少女は、こうして、プラハまで、運んでもらうと、そこからそれぞれの親元へちっていくことになっていた。ハンナの母親はプラハの駅で、ハンナの到着するのを、今か今かと待っていた。
子供たちを乗せた列車が、ホームについた。
「あっ、パンナ!」
目ざとくハンナをみつけた母親は、ハンナをしっかりだきしめた。二人はものもいえず、しばらくは抱き合ったままだった。親と子のこのうれしい再会の様子をながめた人たちは、その胸うつ光景を、一生忘れることはないだろう。
3 気のどくな子供たち top
|

難民救済本部
|

アンラ(連合国救済復興軌間)からの食料をもらった難民の親子
|
チェコの少女、ハンナを探し出した捜索班の人たち――ドイツのエスリングンの製粉工場の建物でハンナの記録を、熱心に調べた人たちは、国際連合のなかに設けられた国際難民救済本部に属する人たちだった。
その本部は、まだ、自分の家にもどれない難民たち(戦争の犠牲になった人たち)百万人以上にたっする人たちの熱心なうったえにこたえて一九四六年に、国際連合がつくったものである。
一九四五年五月に第二次世界大戦はおわったが、その当時ヨーロッパで家をなくし、住むところのない人たちは、八百万人以上もいたのだった。
そのなかの何百万人かは、ドイツとハンガリーにあったナチスの捕虜収容所に収容されていて、一刻もはやく故郷に帰りたがっていた。
進駐してきた連合軍の兵士たちや、赤十字社の人たちは、さっそくそういう人たちの救済を始めた。
当時、国際連合憲章に、参加国はまだ調印をすましてはいなかった。
が、どこの国も力をあわせ、連合国復興救済機関UNRRA(アンラ)をつくって、そういう困っている人たちの救済にあたったのである。
連合国復興救済機関(アンラ)は、国際連合が発足すると、そこに引継がれた。
戦争中、ナチス・ドイツ軍が使っていた校舎をはじめ、ホテル、体育館、そのほか、公共の建物は、すべて難民のための収容施設にあてられた。
しかし、それだけではたりないので、応急の建物が、あとからあとからとたてられて、その人たちの宿舎にあてられた。
なにしろ、大変な数の難民たちである。食料が、じゅうぶんいきわたるというわけにはいかない。
誰もかれも、生きていけるだけの食料をあたえられるのが、せいいっぱいだった。
しかしとにかく、雨露をしのげる場所と、生きていくのに必要な、食べ物が、あたえられたのである。
つづいて、連合国復興救済機関(アンラ)の人たちは、根気よい調べをはじめた。
それは八百万の難民たちのなかのいく人が、故郷へ帰りたがっているか、という調べだった。
二度と故郷へ帰りたがらない人たちも、大勢いたのである。
六百五十万の人たちは、故郷へ帰りたいという希望をしめした。が、鉄道がまだ破壊されたままで、復旧していなかったし、それに、たくさんの橋がこわされたままだった。走れる状態のトラックだって、そうおおいわけではない。
しかし、その人たちを故郷へかえす仕事は、さっそく、始められた。本当に大変な仕事だった。
が、それでも、一九四六年の十二月までには、六百五十万人の大部分の人たちが、故郷へかえることができた。
あとにのこった百万人以上の人たちは、戦火でやけて、何一つ残っていない故郷へ帰ってもしかたがないといって、かえることをのぞまなかった。
一九四五年(昭和二十年)四月にはじめて、国際連合をつくろう、という会議が、アメリカのサンフランシスコで開かれた。
そして、その年の六月に、国際連合憲章をまもる加入国の調印式が行われ、こうして、十月に国際連合は、正式に誕生したのだった。
そのはじめての会議で、アンラからひきついだ、それらの人たち――帰る家をどこにももたない難民たちのことが、特別の議題になった。
一体誰がそれらの人たちのために新しい住み場所をつくる仕事をやったらいいのだろうか。
一体誰が今度の戦争で行方不明になったまま、消息のわからない人たちをさがしだす仕事をしたらいいのだろうか。
また、誰が行方不明の子供たちをさがしだす役目にあたったらいいのか? そして、難民たちへ食料や衣服や、そのほか、いろいろな、必要品をあたえる仕事は一体、誰がしたらいいのだろうか。
それらにこたえて、国際連合ではすぐに国際難民救済機関をつくることを、総会の席上できめ、次のような重大なとりきめをしたのである。
| それは年齢をとわず、年寄りでも子供でも、男でも女でも誰一人として、自分のいきたくない国へ、むりに送られるようなことは、けっしてしないということだった。そしてその仕事を行うために、加入国は二年以内に割当られた費用を、それぞれだすことに総会できめられたのである。 |
国際難民救済機関(アンラ)の長官には、有能なアメリカ人の技師であって、また行政官という役にあった、ウイリアム・ハラム・タックという人が、任命された。
さて、故郷にかえることを希望しない難民たちを取り扱う仕事には、すでにアンラの何百人という男女が当っていたが、国連に新しい機関ができたので、今度は、いっそうたくさんの人たちが、その仕事にくわわった。
そして、それからの三年間に、その難民たちをのこらず処理しようという目標をたてて、国際難民救済機関は、実にめざましい働きを始めたのである。
まず彼らのために、収容所があとからあとからと建設され、その数は七百にもたっした。
食料をはじめ、必要品が、五つの大陸にまたがる国連加入の二十七の国々から、ぞくぞく送られてきた。
熟練したうでをもつ健康管理の衛生官、医師、看護婦たちが、熱心に活動をしてくれたおかげて、どの収容所にも悪い病気ははやらなかった。
難民救済機関では難民のため、遠い国々に新しい土地をみつけだしてやった。
そして、その人たちを送りだすために、たくさんの船を集めなければならなかった。
戦争のときをのぞけば、そんなにたくさんの船が、ひとところに集められたことは、まずなかったといってもいいだろう。
このむずかしい仕事をやりぬくために国際難民救済機関の本部をはじめ、支部には、世界中の四十の国から、いろいろな人たちが応援にあつまった。
その人たちは、それぞれ、ちがった言葉で話しあいながらも、どの人も仲良くうちとけ、本当に熱心に働いてくれたのである。
難民たちのほうも、ただ、うでぐみをしていないで、熱心に協力を申し出た。難民救済機関の係の人たちに相談して、自分たちの手て町をつくり、その町には、自分たちのあいだから町長をえらびだした。
また、警備のためには、警備員をつくり、そのほか、いろいろな役目を設けて、自分たちの町を立派におさめていった。
難民のなかには医者がいたが、その医者は、みずからすすんで医療にあたり、病人をみてまわったり一、新しく建てられた病院の勤務についたりした。
もと大工だった人たちは、新しい建築があると、すぐに手伝った。料理人だった屠は、調理場でねっしんに働き、衣服の仕立職人は、衣服をつくったし、靴屋だった者はせっせと靴づくりにはげんだ。
また、もと教師だった人たちは、その方面のしごとをてつだわしてもらいたいと、申し出た。はじめは、学校といっても名ばかりの、おそまつなもので、教科書一つなければ、道具なども何一つなかった。
その人たちは、夜おそくまで起きて、あくる日の教材をせっせとつくった。やがて、ちゃんとした学校が設けられるようになり、いろいろな学課が、きちんと教えられるようになった。職業教育も始められるようになった。
両親を失った子供たちは、四千人ほどもいたが、それらの子供たちには、特別な施設が設けられた。
その施設に、はじめて連れて来られた子供たちのなかには、ひどくめんくらう子供がよくあった。なにしろ、収容所で、それまで親切にされたということがないので、これから一体、何をされるのだろうかと、不安でたまらなかったのだ。
ある施設に連れて来られた、そういう少年少女の一団があった。年齢は十才から十二才までの子供たちだったが、どの子も、長いことナチスの捕虜収容所に入れられていて、人間らしいあつかいをうけたことがないので、いつも、人をうたがい、おこりっぽかった。
難民救済機関の女の係官が、その子供たちのリーダーにいった。
「ここではどんなことをして遊んでもいいのよ。」
リーダーの少年は、さもふしぎだという顔をして聞いていたが、仲間たちのところへ戻って、なにか相談すると、また戻ってきていった。
「本当に、僕たちの好きなことをやってあそんでもいいのですか?」
「いいんです。ただ、お互いに迷惑をかけてはいけませんがね。」
ものの数秒としないうちに、ものすごい大さわぎが始った。
子供たちは、大声をはりあげ、さけび声をあげて、まるで、気でも狂ったように、そのへんを駆け回った。
あくる日も、その大さわぎが続いたが。係官は、すこしも、とめようとしなかった。とうとう、その大さわぎも一人でにおさまったが、子供たらは、はじめて、この場所が、いままでと、まるっきりちがうこと、そして、もう、自分たちは、敵のなかにいるのではないことを、知ったのである。
収容所や施設の少年少女たちは、自分たちより小さい子供たちの面倒をよくみてやった。
また、調理場の手伝いをしたり、病院の手伝いをしたりするのだった。
Y・M・C・AやY・W・C・A、ボーイースカウトやガールースカウトなどの国際的な青少年の団体は、自分たちの会員を難民救済施設に送って、ねつしんに協力してくれた。
難民の少年少女のあいだにも、新しくボーイ・スカウトや、ガール・スカウトの組織が生まれでた。
そして、その団員たちは、熱心な活動をしてくれたのである。
難民の少年少女が集ると、そのなかには、かならずといっていいくらい、チェコの少女ハンナをみつけだした捜索班の人たちと同じように、さがしだすことに、特別な才能をもった子供たちがいたものである。
そういう子供たちの一人に、十三才になる、ポーランドの少女がいた。
その少女は、西ドイツのハイデルベルクの近くにあった国際難民救済機関の建物に収容されていて、救済部の人たちからは、「だんまり屋さん」というあだなをつけられていたくらい、ひどく無口な子だった。
ある日、その少女のすがたが、ふっと見えなくなった。べつに、どこへいくともいっていない。すこしすると、少女は、自分の大おばさんだというおばあさんをつれて、施設に戻ってきた。
「一体どこで、みつけだしたんだね?」
係官が、少女に聞いても、少女は、ひとこともこたえない。しかし、そのおばあさんは、たしかに少女の大おばさんにちがいなかった。
これがはじまりで、その少女は、その後もちょいちょいすがたをけしては、そのたびに、家族の誰かをつれて戻ってきた。
こうして、その少女は、どういう方法でさがしだすのかわからないが、自分の家族を七人まで探し出してきたのだった。
第二次大戦で行方不明になった人たちの搜索本部は、ドイツのアロルセンというところに設けられてあって、国際捜索事業部というのが、正式の名称である。
そこには、六百万人をこえる行方不明者についての、くわしい調査が記入されてあるカードが、それこそ、山のように保管されてある。
まえにお話しした、ドイツのエスリングン町にあった児童捜索班は、その国際捜索事業部に属していて、主として、小さい子供たちの行方不明者の捜索に当っていたわけである。
この児童捜索班の人たちくらい、知恵をしぼり、工夫をこらして、ホンのわずかな手がかりをもとに、活躍した人たちもあるまい。それこそ、どんなすばらしい探偵小説の名探偵でも、かなわないことだろうと思う。
それでは、その捜索班の活躍を、一つご紹介するとしよう。
ある収容所に、一人の女の子がいたが、自分の名前が、なんというのか、また、どこに住んでいたものやら、すこしもわからない子がいた。これには、収容所の係りの人も、ほとほと困ってしまった。
児童捜索班の人たちは何とかして、この子の身元を知りたいと思った。そこでさっそく、活動が、始ったのである。
まず、新聞にその子の写真をのせたら、家族の誰かが、ひょっとして目にとめ、なにか、連絡でもありはしないかと思った。そこで、さっそく、近くの、いくつかの町で発行されていた新聞にのせてみた。
すると、いくらもたたないうちに、縄を作っているという、ある人から手紙が届いて、
「どうも、行方不明になった、うちの子のドルーシーににているようですが――。」
と、いってきたのである。
縄を作る商売-そうすると、その少女は、父親が縄を作るところを、それまでにいくどか見たことがあるにちがいない。
捜索班の人たちは、そう考えると、さっそく、近所の縄作りの人にきてもらった。
その人は、わらを運んでくると、収容所の子供たちがあそんでいる近くにすわりこんで、さっそく、縄を作り始めた。
子供たらはあそびをやめると、その人のところへとんでいって、めずらしそうに、縄作りを見物し始めた。
すると、身元の知れないその少女も、すぐにとんできたが、それを見るなり、
「私の父ちゃんも、ああいうことができるわ!」
と、大声でいったのだ。
この一言で、その少女が、縄作りの娘のドルーシーであることがわかり、無事に両親のもとに帰ることができた。
次はスイスであったことだが、捜索班の人たちは、フランスからにげてきた子供たちがたくさんいるスイス村で、アドルフ・ラシドという、これも身元のまったくわからぬ幼児を発見した。
服はボロボロで靴はすっかり底がへっていた。
それっきりで、身元を調べる手がかりになりそうなものは、ほかには、何一つない。
ただ、首に名前を書いた厚紙をぶらさげていて、それには生まれた年月日と、「アドルフ・ラシド」と、名前が書いてあるだけだった。
その子と一緒にいる子供たちは、それぞれ自分たちが、どこの生まれで何という名前なのか知っていたが、その子だけは、何を聞いても、だれに聞いてもわからなかった。
「さあて、この子はどこで僕たちと一緒になったけな……。気がついたら、一緒になっていたんだ。」
誰もがそういうだけだった。
ご本人のアドルフに聞いてみても、両親の名前も知らなければ、どこに家があったものやら、何一つ覚えていない。
捜索班の人たちは、ふと思いついた。
それは、ラシドという名前があんまりありふれた名前でないことだった。
「ひょっとすると、生まれた村か町の名をとって、つけられたのかもしれない。」
そこで捜索班の人たちは、さっそくヨーロッパ中の地図や、市町村案内などを熱心にしらべたが、どこにも、ラシドなどという地名はなかった。
ある日、一緒にいた子供たちが、船の話をしはじめると、アドルフは、さっそく自慢するようにいった。
「僕のお父さんとお母さんは、僕と一緒に船に乗っていたんだよ。」
それを耳にしたとたん、捜索班の人たちは、ひょつとすると、それが、大切な手がかりになるかもしれないと思った。
赤ん坊が船で生まれたとき、よく、その船の名をとって、わが子に名をつける両親がいるからである。
そこで、捜索班の人たちは、さっそく、船の記録をかたっぱしから調べ始めた。
根気よく調べた結果、ラシド号というイギリスの汽船が、戦争まえに地中海を往復していたことがわかった。
そこで、スイスにあるイギリス領事館にた飲んで、ラシド号の航海日誌を調ベてもらった。
すると、どうだろう――そのなかに、アドルフ少年の生まれたことが、ちゃんと記入されてあったのだ。
そして、生年月日もピッタリあっていたではないか!
彼の両親の名もわかった。
捜索班の人たちが、このことをアドルフに話してやると、アドルフはとてもうれしそうな顔をした。
はじめて心からの笑顔をみせたのである。
それからというものアドルフは、前と違ってほかの子供たちと同じように振舞うようになった。
自分にも、ちゃんと両親があるんだ、という誇りをもつことができたからである。
イギリス船の上で生まれたのだから、イギリスの法律にもとづいて、アドルフは立派にイギリスの国籍をもつわけである。
アルドフの両親の行方はいまだにわからないが、彼は今はイギリスのある家庭に引取られて、幸せに暮らしている。
4 難民救済機関の活躍 top
現地の捜索班がわずかの手がかりをもとに、熱心な活動を続けている一方、国際難民救済本部の何百人という人たちは、ほかの仕事に熱心に当っていた。
それも一種の捜索の仕事といえばいえるが、おいては人間ではなくて、難民たちの希望する落着き先――世界中にちらばる、いろんな国の落着き先だった。
まず、国際難民救済本部では、世界中の国々の政府へあてて、手紙をだした。
難民のなかには、教師、医師、技師、画家、作家をはじめ、大工、農夫、織物の職人などがいることを知らせ、それらの職業のくわしいリストをつくって送ったのである。
それにこたえて、いろんな国から、どういう職業の人がほしいかをいってきた。
家族ぐるみきてもらいたい、という申し込みもあった。また、団体できてもらいたいと、熱心にいってきた国もあった。
それは、オーストラリア、カナダ、イギリスなどの国だった。
すると、そのことを知ったほかの国々も、ぞくぞく、団体を希望するといってきた。
ベルギーでは、鉱山に関係したことのある人たち二万人にきてもらいたいと、いってきた。
そして、三ヵ月ほどすると、その家族の人たちも、ペルギーにわたっていった。
また現在、ブラジルのゴイアスというところには二百家族をこえる、かつて難民だった人たちが一緒に暮らしている。
みんな、自分たちの家をもち、畑をもって、楽しい生活をおくっている。
ところで難民のなかの子供たらは、一体どうだったろうか。
最初は、年のいかない子供たちを引取りたいと、申し込む人たちが多かった。
というのは、養子にするのなら、年のいかない子供がいいと思うのが、人情だからであろう。
「これではいけない……。」
そう思った難民救済本部の主だった人たちは、その考えをかえさせようと思って、難民の子供たちのなかには、実にすぐれた少年少女がおおいことを書いて、世界中の国々にうったえた。
するといろんな国から、続々とそういう少年少女たちにきてもらいたい、という申し込みがおしよせた。
オーストラリアからは、五百人の少年少女にきてもらいたいといってきたし、アメリカ合衆国、スウェーデン、ニュージーランドからも、たくさんの申し込みがあった。
ほかの国からも、続々といってきた。
難民救済本部では、この申し込みをよく調べたうえで、少年少女たちの調査カードともくらべあわせ、彼らが一番幸福になれそうなところへ割当た。
こうして少年少女たちは、いろいろな国へ連れられていったが、彼らは誰もかれも、難民救済本部の人たちの獣身的な努力に、心から感謝した。
九人からなる、ある少年たちのグループは、アメリカ合衆国にわたることになった。
その少年たちは世話になった難民救済本部の人たちに、寄せ書きを送ったが、その中にはこんなことが書いてあった。
「いよいよ明日、アメリカへ出発できると知って、僕らは、みんな楽しくてしかたがありません。
このことも、あなたがたのおかげがなかったらできなかったことを、僕らはよく知っています。
僕らは、どんなに感謝していることでしょう。
どのようにして、この感謝の気持をあらわしたらいいものでしょう。
僕らは、みんな話しあいました。そして、その感謝をあらわす方法として、次のようにすることを申し合せました。
かならず実行することをちかいます。
一 僕らは、僕らのいく新しい国で、どんなときでも最善をつくそう。
一 僕らは、いつでもよい市民になるようにつとめよう。
一 僕らは、いつでもよいアメリカ人になるようにはげもう。
以上のことを、かたく誓います。」 |
アメリカ合衆国では、難民の少年少女に、新しい家庭をみつけてやることや、彼らが到着したときの取扱いや、そのほか、引取ってくれる家庭へ運んでやることなどを、ヨーロッパ児童救護委員会が一手に引受けた。
この委員会で働いてくれた人たちは、カトリック、ユダヤ、プロテスタントなどの宗教団体から送られてきた人たちだった。
救護委員会の人たちは、ニューヨーク市のブロンクスに、子供たちの歓迎センターをつくった。
そしてヨーロッパから送られてきた少年少女たちは、三週間ほどアメリカの環境になれるあいだ、そこにおかれた。
そのセンターは、楽しい雰囲気にみちていた。
娯楽設備がいろいろあるうえに、自由に歌もうたえれば、ゲームもできるようにたっていた。
こうしてこの国の空気になれたうえで、新しいアメリカ人になった彼らは、自信をもってそれぞれの土地へ、それぞれの家庭へ運ばれていった。
歓迎センターで働いた人たちは、いまでも、ふかい愛情とともに思いださずにはいられない少年少女たちを、たくさん知っている。
リジナという十四才の少女は、センターで発行していたガリ版ずりの『新しい生活』という新聞に、アメリカにきてから覚えた英語で、次のように寄稿した。
「私は、小さいころから、お医者になろうと思つていました。
その理由は、お医者は、なんでもよく知っている、えらい人だと思ったからです。
お医者は、いつも白衣を着て、とてもすてきに見えます。
そういうわけで、私は、お医者になろうと思いました。
私のいたドイツの収容所で、私は赤ちゃんばかり入院する、小さな病院の手伝いをしました。
私はそこで、女のお医者が働くのをいつも見ていましたし、いつもすばらしいと思っていました。
私はお医者になれたら、そのときの女の先生のように、一生懸命働くつもりです。
いまも、私の希望にかわりはありません。
私は誰でも、病気になった人は、たいへん不幸なことを知っています。
病気になれば、働けなくなります。
そうなれば、毎日必要な食べ物をはじめ、何一つ買うことができません。
お医者は、そういう不幸な人を助けてあげられるのです。」
リジナを引取ったアメリカの養父母たちは、リジナの希望を知って、こう約束してくれた。
「君が高等学校を卒業しても、なお、医者になりたいという希望だったら、かならず大学の医学部か、医科大学へあげてあげよう。」
ベルギーから送られてきたジョージ少年は、十八才になっていたので、大学へ入学したくて仕方がなかった。
彼を引取ったアメリカの養父母は、希望どおり彼を大学へあげた。
ジョージは熱心に勉強し、優等で大学を卒業したので、養父母はたいそう得意でだれにも自慢するのだった。
ジョージは大学に入学したときから、ゆくゆくは国語の先生になろうと、決心したのだ。
大学を優等で卒業した彼は、今は、研究科に残って、博士の学位をとるため勉強を続けている。
また講師として、その学校で教えてもいる。
ハンガリーからやってきたイムレという少年は、お百姓になるのが希望だった。
救済委員会では、イムレ少年を、アイオワ州の農家に引取ってもらった。
イムレは中学へあげてもらったが、学校からもどってからと学校の休暇には、農場の手伝いをして楽しく暮らしている。
彼のお百姓になる希望にはかわりがないので、イムレは高等学校をでたら、農業学校へすすむはずである。
しかし、一方、少年少女の、ある者のためには、特別な計画が必要だった。
それは、たくさんの少年少女のなかには、個人の家へ引取られて、家族の人たちと一緒に暮らすことをこわがる者がいたからである。
長いあいだ、収容所で集団生活を続けたために、そういう集団生活のほうを好むようになったのである。
すばらしい音楽の才能のあるアニカという少女が、そうだった。
委員会では、そういうアニカのために、アメリカープロテスタントーホームをせわしてやった。
そこでアユカは、大好きなピアノに親しみ、今は音楽の先生になって、幸福な生活をおくっている。
しかし、また、ジャックのような少年もいるのだった。
ジャックは、学校へはあがりたがらず、すぐに働きたいというのが希望だった。
ジャックは、ちゃんとした自分の計画をもっていた。彼は、料理人になりたかったのである。
ジャックは、アメリカのニューイングランドのある家に引取られたが、そこの養父母は、彼の希望を入れて、ボストンの大きなホテルに住みこませ、彼の人生の道を開いてやった。
彼は、まず、そこで、調理場のつかい走りとして働くことになった。
ジャックは、一生懸命働いたので、じきに引上げられて、今は、料理人見習いになっている。
ところで、難民の少年少女たちにとって、引取られた国の新しい風習や、いろいろなやりかたになれることは、けっして、らくではなかったにちがいない。
また、一方、彼らを引取った養父母のほうだって、けっして楽だったとはいえなかったろうと思う。
しかし、双方に、お互いを理解しあおうという熱心な気持があるかぎり、やがては理解しあえるものだということが、よくわかるのだった。
5 片足のないフランキー少年 top
こうして、しだいにヨーロッパの収容所にのこった難民の数はへっていった。
難民の数がへるにしたがって、収容所は次々と、とざされていった。
しかしまだ、たくさんの難民たちが残っていた。
その人たちは、いわゆる難物で、どこからもきてくれという申し込みがなかったのである。
そういう人たちのなかには、高い教育をうけ、特別な才能をもった専門家たちが、いく人もいた。
そういう人たちは、頭を使う仕事に向く人たちなので、労働力のほしい国からは、いつも敬遠されてしまった。
また、老人やメクラの人たちや、不具者たちもそうだった。
どこの国でも不具者をひきとることには、ためらった。
やがて、引取った国の負担になることが、はっきりとわかっていたからである。
国際難民救済本部の主だった人たちは、こんども、活躍した。
その人たちは、世界中の国々に、そういう引取り手のない難民たちのことを、強くうったえた。
すると、どうだろう。いろいろな国から、すぐに反響があった。
そして、いままでどこからも申し込みのなかった専門家たちに、きてもらいたいという手紙が、続々と来始めのである。
不具の人たちにも、きてもらいたいという申し込みがあった。
ノルウェーは、国際難民救済本部と力をあわせて、自分の国にメクラの人たちのためのホームをつくった。
そして、たくさんのメクラの人たちを引取ってくれた。 |

心からあたたかく迎えられて
|
ベルギーは年寄りたちを引取って、自分の国の老人ホームに入れてくれた。
ほかの国もそれぞれ、いろいろなやりかたで引取ってくれた。
アメリカ合衆国のニュージャージー州のロジにある、カトリック・ホームの親切な尼さんたちは、ポーランドで片足のないフランキー少年と、彼の七人の兄弟たちを、引取ってくれた。
その兄弟たちは、戦争で両親を失い、長いことヨーロッパの収容所で暮らしていたのである。
アメリカのロジのカトリックーホームで暮らすようになった彼らは、いかにも幸福そうだった。
なかでも、フランキー少年は、誰からも愛された。
彼はとても快活で、明るくて何をやるにも熱心だったせいである。
すこしすると、松葉づえをついたフランキーは、野球のゲームにくわえてもらい、グランドを愉快そうにとびまわった。
「僕は、ローラ・スケートだってできるよ。」
フランキー少年は、うれしそうにいうのだった。
本当に、フランキーはローラ・スケートができるようになった。
そして、じきに上手になったので、町の人たちは、彼のことを自慢するようにさえなった。
ある日、一人の医者が、フランキーのローラ・スケートぶりを見て、すっかり感心してしまった。
「きみ、すまないけれど、僕と一緒に、このそばにある病院にいってもらえまいか。」
それは陸軍病院で、そこには今度の戦争で腕を失くしたり、足を失くしたりした兵隊たちがたくさん収容されていたのだった。
その医者は、片足のないフランキーが、こんなに上手にローラ・スケートで走りまわれるのを、その患者たちに見せてやったら、どんなに彼らが元気づけられるだろうと、思ったのである。
フランキー少年は、すぐにうなずいて、その医者と一緒に病院にいった。
そして、みんなのまえで、ローラ・スケートのすばらしいうでまえをみせてやった。
兵隊たちは、すっかり感心したし、また、元気づけられもした。一人の兵隊は、こういった。
「子供にだってできるんだからな。大人の俺たちにできないはずはないさ。」
フランキー少年は、それからはニュージャージーの陸軍病院を、かたっぱしから慰問してまわった。
どこの病院の患者たちも、けなげなフランキー少年のおかげで、すっかり元気づけられた。
フランキー少年くらい、負傷した兵隊たちを元気づけてくれた者は、ほかにはいないというのが、傷病兵たちの一致した意見だった。
フランキー少年は、片足のないことなんか、ちっとも苦にしていなかったのである。
6 少女マルージャのよろこび top
|

アメリカの家庭へよろこんでいく少女
|

こんな小さな子が難民……
|
国際連合の計画にしたがえば、国際難民救済本部(IRO)の仕事は、一九五〇年いっぱいで、打ち切りということになっていた。
そういうわけでその時期が近づくにつれて、救済本部の主だった人たちは、まだ身の振り方のきまっていない残りの難民たち――二万五千の人たちを、なんとかしようと、懸命の努力を続けた。
一方、国際捜索機関(ITS)のたくさんの記録類は、ドイツを管理する最高機関に引継がれた。
今度の戦争で、消息をたった男や女や、子供たちの行方を探し出すのは、ほとんど、望みのない仕事のようにみえた。
が、それでもひょっとすると遠いところから手紙がきたりして、再会のよろこびにひたれることがないわけでもない。
少女のマルージャの場合が、そうだった。
マルージャはスペインの少女で、どこにも身よりがないので、アメリカのミズーリ州のある家庭に引取られていった。
マルージャがほかのスペインの子供たちと一緒に、戦火を逃れたときはまだ十一才だった。
マルージャたちは、浸水しかけたボロ船で、大西洋をただよっていたのをすくわれて、アメリカヘ連れて来られたのである。マルージャはこうしてミズーリ州のある家庭に引取られ、学校にかよわせてもらい、学校のいろいろなクラブにも入って、活動した。
やがてマルージャは、高等学校へあがったが、そこでは応援団のリーダーにえらばれた。
マルージャはアメリカの養父母を心から愛し、学校の友だちたちとは仲がよくて、楽しい生活を送っていた。
が、いつも心の底には、きっといつかは本当の両親にあえるという夢と望みを、忘れたことはなかった。
こうして、月日はだか、マルージャがアメリカにきてから五年の月日がすぎた。六年目のある日のことである。
彼女が、いつも夢にまでいだき続けていたことが、とうとう、実現したのだった。国際難民救済本部の捜索班から一通の手紙がとどいて、彼女の両親がイギリスにいるということを知らせてきたのである。
マルージャのよろこびは、一体どんなだったろう!
このようにして、国際難民救済本部が三年間になしとげた仕事は実にめざましいもので、その記録は本当にすばらしいものだったといえよう。
一九五〇年までに、難民救済本部は、百四十九万九千人をこえる難民をすくった。
そして、七十万九千三百九十八人という難民に、新しい家をみつけだしてやったのである。
国際捜索本部は、七万二百五十三人の行方不明者をさがしあてた。
そしてそのうちの二千九百七十五人は少年少女や幼児たちで、それらは児童捜索班の手によって発見されたのであった。
なんというすばらしい働きであろう。
7 かわいそうな少女テレーズの話 top
その少女は、真っ暗なジトジトした穴倉の中にひそんでいた。
ナチス・ドイツ軍によって、メチャメチャに爆撃されたフランスの片田舎のある農家の穴倉の、ガラクタのあいだに隠れていたのを発見されたのである。
発見したのは児童捜索班の人たちで、その人たちはその少女を、はじめは十才くらいだと思った。
あとになって十四才だということがわかったが、なにしろひどく痩せこけてチビだったので、そう思ったのも無理はなかった。
その少女は、何を聞かれてもだまっていた。
捜索班の人たちは、しかたがないので、その少女をジェニーと呼ぶことにした。
ジェニーはその人たちにつれられて、町へいくのが嫌いなようだった。
町の親切な人たちは、ドイツ軍の爆撃をまぬがれた一軒の建物を救護センターにあて、親や家を失った子供たちの面倒をみてくれていた。
ジェニーは連れて行かれるのが嫌だといって、泣いたり、わめいたり、ひっかいたりして暴れまわった。
でも、やっとのことで、自動車に乗せられ、町へ連れて来られた。
センターの人たちは、少女の着ているボロをぬがせ風呂にいれ、こざっぱりした服にかえさせてやったが、少女はすこしもうれしそうな顔をしない。
長いあいだ、食べ物は盗んでくる習慣だったとみえて、ジェニーは、小さな子供たちが食べ物をもっているのを見ると、いきなりひったくった。
ジェニーの話す言葉のなまりから、センターの人たちは、ジェニーは多分、ひそんでいた穴倉のある地方の子供にちがいないと、誰も思った。
しかし家はどこで、どうして穴倉にかくれていたのか? と、いくらたずねても、ジェニーは、こたえようとしない。
センターの人のなかには、すべてのことに疑ぐり深くたっているからだろうと、考えた人がいた。
またある人は、あの恐ろしい戦争で何もかも忘れてしまって、一つも思いだせないのではなかろうか、と思った。
町の教会の片隅に設けられてある小さな診療所で、その少女を診察した医者は、肝油をあたえたあとで、
「あの子に、いろいろたずねることは、しばらくやめたほうがいいですね。」
と、センターの人にいった。
まず、食べ物をどんどんあたえて、栄養をとらせることが第一で、体さえ回復すれば、記憶のほうも戻ってくるにちがいないと、その医者は思ったのである。
ある日、センターへの配給の食料をどっさりつんだトラックに乗って、一人の女性がセンターへやってきた。
そして、センターの人たちに、収容されている子供たちの様子をたずねては、手帖に書きこんだ。
それがすむと、その婦人は、収容されている子供たちを集めてもらって、一緒に歌をうたった。
古いフランスの歌もうたわれた。
ジェニーははじめ、その仲間にくわわらなかったが、やがてなつかしいフランスの古い歌のメロディーがながれだすと、体をまえにつきだし、両手をかたくにぎりしめて、何かしきりに思いだそうとした。
歌のはじめの一節がおわったとたんに、ジェニーは、いきなり跳び上って、戸口のところに駆け出していった。
そして、そこにいたセンターの人にだきつくと、大声で自分の村の名をつげたのだ。
それは十キロ以上も、離れたところにある村だった。
ジェニーは、とうとう、自分の村の名を思いだしたのである。
一度思いだすと、ジェニーは、あとからあとからと、いろいろなことを言い出した。
センターの人たちは、熱心にジェニーのいうことに耳をかたむけた。
すると、次のようなことがわかった。
少女はテレーズという名前で、家には両親と兄のピエールがいて四人で暮らしていた。
しかし自分の姓がなんというのか、それだけは、どうしても思いだせないようだった。
でも、それだけでじゅうぶんだった。本人の名と兄の名、そして、村の名がわかったからである。
あくる日、センターの自動車にテレーズを乗せると、センターの人たちは、さっそく、その村へ向かった。
自動車がその村に近づくと、テレーズは、もううれしくてたまらないらしかった。
そして、村にはいうたとたんにおこったできごとは、まず、奇跡といってもよかったろう――。
村の入り口の一軒の小さな店から、チンバの男がでてきた。その男を見るなり、テレーズは大声でさけんだ。
「おじちゃん!」
テレーズは、自動車から。とびおりるようにして、その人のところに駆け寄った。
「ジャックおじちゃん!」
「おお、テレーズじゃないか!」
その人は、両手でしっかりテレーズをだきしめた。涙が、両ほおをポロポロとこぼれおちた。
テレーズのおじさんだったのである。
その人のうしろには、顔色の青いはだしの少年が立っていたが、その少年も両手を拡げてテレーズにだきついた。
兄のピエールだったのだ!
ジャックおじさんが、センターの人たちに話したことは、悲しい物語だった。
もっともそれは、戦争でメチャメチャに荒されたフランスの村では、ありふれたことかもしれなかったが……。
テレーズのお父さんは、戦争にとられて、それつきり帰ってこなかった。
お母さんのほうは、ナチス・ドイツの兵士が、牛を徴発にきたのに応じなかったので、その場で銃殺されてしまった。
敵の兵士は、おまけに。ピエールを連れて行ってしまった。
小さなテレーズは、たった一人で、森のなかへかくれてしまったのだ。
それからというもの、村の人は誰も、テレーズのすがたを見たことはなかった。
ジャックおじさんも戦争にとられたが、負傷して戻された。
戻ってみると、妻のジョルジエがいるだけで、兄の一家は一人残らず、いなくなってしまっていたのである。
しばらくするとピエールが、ドイツから帰ったきた。
ドイツ軍はピエールをつれていくと、毎日、工場で長い時間働かせた。
戦争がおわると、ピエールはたった一人でドイツをさまよいでた。
なんとかしてフランスの生まれ故郷へ、歩いてかえろうと思ったのである。
ピエールは、途中で親切な人に出会い、その人はピエールを難民たちが収容されている収容所へ連れて行ってくれた。
やがて交通機関もしだいに回復して、収容所の難民たちは、それぞれ故郷へ帰れることになたった。
こうして、ピエールは、フランスの生まれ故郷へ、無事に戻れたわけだった。
そこへ、小さなテレーズも無事に戻ってきたのである。なんといううれしいことだったろう。
ジャックおじさんの家は、村から一キロほど離れたところにあった。
とても小さい農家で、三人くらしていくのがせいいっぱいのようだった。
そこへ一人増えることになるのだから、けっして楽なことではなかろう……。
ドイツ軍は、農具を一つあまさずうばっていってしまい、おまけに台所の鍋や釜まで、あらいざらいもっていってしまったのだ。
それに、一頭いた牝牛は、とうの昔に殺されてしまっていた。
ジャックおじさんが、去年の春に畑にまいた種は、育ちがとても悪かったし、おまけに日照りときている。
人生はつらいものだ。しかし、なんとしても、生きていかなければならないし、テレーズにも食べさせなければならない。
ジョルジェおばさんもテレーズを見て、涙を流してよろこんだ。
さて、そのうれしい再会がすむと、一緒についてきたセンターの人が、ジャックおじさんにたずねた。
「村の子供たちは、どうして食べているんですか? ほかの畑の様子は、どうなのです?
村の食べ物は、じゅうぶんなのでしょうか?」
ジャックおじさんとジョルジエおばさんは、首か左右にふって、いうのだった。
「いまでさえ、じゅうぶんな食料がないのですから、冬になったら、一体どうなるのかとあんじられてなりません……。」
センターの人たちは、うなずいた。かえりがけに、センターの人はいった。
「また、きます。じきに、またくるつもりですが、そのときは、きっと、いい知らせももってこられると思います。」
そして、センターの人は、約束をまもったのである。
次の週になると、センターの人たちは、フランス政府の有力な人たちを自動車に乗せて、つれてきた。
その人たちは、ジャックおじさんの家へいくまえに、村長の家へいくと、長いこと話しあった。
それから、ジャックおじさんの農家へ向かうと、でてきたおじさん夫婦、テレーズ、ピエールたちにうれしい知らせをもたらした。
「じきに食料がきますよ。幼児や少年少女たちに食料がくるんです。
牛乳とパン、それに力をつける肉。そして野菜もとどきます。元気をだしてください。食料は、じきにきますからね。」 |
その日、ジャックおじさんたちにつげられたうれしい言葉が、同じように戦争でメチャメチャゃにされた、ヨーロッパのほかの国々の少年少女たちにも伝えられたのである。
またその同じ言葉が、それからの三年のあいだに、世界中の何百万という飢えに苦しみ、必要品に苦しんでいる少年少女たちに伝えられ、実行されたのだった。
国際連合のなかに設けられた、国際児童救済基金(ユニセフ)の働きで、食料をはじめ、衣服や医薬品などが、続々と送られてきたのである。
8 ユニセフのおいたち top
一九四六年十二月十一日。
この日ひらかれた国連総会の席上で、ニューヨーク市長であり、。国連の経済社会理事会の委員長をつとめるフィオレロ・ラグアルディア氏が、一つの提案をした。
それは、第二次世界大戦の犠牲者――家を失い親を失った子供たちを救うために、国際児童救済基金を至急設けたいというもので、それには各国の政府によびかけ、基金をあおぎたいという提案だった。
この提案は、出席した全員の賛成のもとに、すぐに取上げられて、次のような意味の声明がだされた。
「世界中の十八才未満の少年少女は、人種、宗教、国籍のちがいなどは、いっさいかまわず、必要の度合いに応じて、国際児童救済基金から救助をうけることができる。」
総会の出席国の代表者たちは、その日すぐに、それぞれ自分の国に、そのことを報告した。
するとどの国の政府も、折り返して返事をよこし、よろこんで基金を分担したいと、申し出たのである。
また、ノルウェーの代表者であるオーディン氏の提案で、その基金には各国の政府ばかりでなく、団体でも個人でも、寄付できるということがきめられた。
このことが一度発表されると、世界中の人たちから、また、各種団体、学校、教会から、続々と、寄付金が送られてきた。
こうして、基金は集ったが、さて。一体だれをその実行委員に任命したらいいだろうか。
とにかく、ぐずぐずはしていられない。
何百万という子供たちが、一刻もはやく、食料、衣料、医薬品を待っているのである。
そういうわけで、国際児童救済基金――United Nation's International Children's Emergency Fund――の頭文字をとって、ユニセフ(UNICEF)と、よばれることになり、その組織は、各国からの代表者たちのなかからえらばれた二十六名の実行委員たちの手で、運営されることになったのである。
委員長には、長い経験をかわれて、アメリカの名高い実業家、モーリス・ペート氏が任命されたのだった。
9 イタリアの山奥の村で top
さて、ここに、イタリアの山奥の村である。
十四才のアルチュロ少年は、学校へつづく道を、元気にトットと歩いていく。
今日は、もう、すこしも足がおもくない。
昨日までは、学校へいくのが嫌で嫌で、途中で、どこかへ逃げ出したくてしかたがなかった。だが今朝はちがう。
〈今日は学校へいっても友だちが笑ったら、あのことをいってやるんだ。
そうすれば、いっぺんに、笑い声はきえてしまうだろう……。
また昨日みたいに、僕のおばあさんが、おいぼれて、なに一つ物を知らないといったら、あのことをいってやろう。
そしたら誰も、あいた口がふさがらないだろうなあ……。〉 |
アルチュロは、そう思いながら、元気いっぱい学校への道をいそいだ。
彼がみんなから馬鹿にされ始めたのは、つい、おとといからだった。
そして、それが彼一人だけなのだから、しまつが悪いのである。
こんど、アルチュロのかよっている学校に、スープとミルクの学校給食が始められることになった。
まったく、すばらしいことである!
それなのに、彼の悩みの原因が、そのミルクにあったのだ。
そのことを学校の老先生が、直接アルチュロのおばあさんに話してくれさえしたら、おばあさんもわかってくれたろうに――。
二週間ほどまえのことである。一人の見知らぬ人が自動車で学校へやってきた。
そして、老先生と長いこと話しあって帰っていくと、先生は、さつそく、村の家を一軒一軒、まわり始めた。
「食料が送られてくるぞ。このさき、ずうっと送ってくれるそうだ。ありかたいこっちゃ。
これで子供たちは、もう飢える心配がなくなった。」
老先生は、こういって、村の家をまわって歩いたのだ。
その子供たちの食料は、遠い国に住む。親切な人たちからの贈物だということだった。
そして、村の母親たちには、交替で学校へきてもらい、給食の世話をしてもらいたいと、老先生がたのんで歩いたのである。
ところで、このびつくりする知らせをもってまわったのが、みんながいつも信用している老先生だからよかったものの、もし、ほかの人だったら、村の人たちは驚いてしまい、あたまから信じようとはしなかったろうと思う。
老先生は、村の誰からも尊敬されていた。
それというのも、戦争がおわり誰一人、先生なんかになり手がないままに、子供たちが野ばなしになっていたとき、なんとしても学校をはじめなければ、といいたしたのが、老先生だったからである。
もちろん、それまであった校舎は、爆弾でメチャメチャにされていた。
それに老先生は、そのよび名のとおり、かなりの年寄りで無理はできない。
それなのにその老先生が、自分から教えると言い出したのである。
しかし、校舎はどうしたらいいものだろう。
すると老先生のおくさんが、自分たちの家を教室に使ったらどうかしらと、言い出した。
老先生の家は、小さい家だった。
が、生徒を下級生と上級生の二つにわけ、下級生は、週に二日、上級生は週に三日かよってくるということにすれば、どうやらやっていけそうだった。
「よし、そうしよう。」
老先生はすぐにそうきめると、さっそく自分の家を教室にして、学校をひらいたのである。
「なに、やろうという気さえあれば、かならず道はひらけるものだぞ。」
老先生は、生徒たちにいつもそういって教えていた。
まったく、そのとおりだった。
老先生は、本らしいものといえば、たった一冊しかもっていなかった。
手あかがついて、やぶれかけている地理の本一冊。
しかし、老先生は、本なんかなくても、たいそう物知りで、いろいろなことを教えてくれる。
アルチュロたち生徒は、毎日が楽しくて待ちどおしいくらいだった。
生徒たちは誰一人、鉛筆一本もっていなければ紙一枚もっていなかった。
しかしそこはよくしたもの、老先生の家の裏手がたいらで、やわらかい地面になっていたので、そこを利用して雨さえふらなければ、棒の先をとがらしたもので地面に字を書いては、勉強するのだった。
まったく老先生のいうとおり、やろうという気えあれば、どんなことでもけっこう、できるものである。
ところで老先生のいった食料が、とうとう学校に到着した。
ゆげのたっているスープを、最初にごくんと飲んだときのおいしかったこと!
そして、ミルクをゴクゴクと飲んだときのあのうれしさ! アルチュロは、一生わすれられないだろうと思った。
生徒たちは、誰もかれもうれしそうだったが、なかでも、ミルクがいちばんの人気だった。
それというのも、見たこともない粉ミルクだったからで、給食当番にあたった村の女の人が、お湯にとかしてくれるのである。
生徒たちばかりではない。
村の人だって誰一人、粉ミルクをいままで見た者はなかったし、そんなものがあることも知らなかった。
はじめての給食があった日、アルチュロは、学校がおわって家に戻ると、さっそく、おばあさんにそのことを話した。
アルチュロは、おばあさんと二人きりで暮らしていたのである。
「とてもおいしかったよ。これからも、ずっと飲ませてくれるんだって――。」
おばあさんは、うれしそうな孫の顔を見て、涙を流してよろこんだ。
「ミルクは、とてもおいしいよ。粉をとかして、ミルクにするんだよ、おばあさん。」
アルチュロがとくいになっていうと、おばあさんは、きゅうにまゆをしかめた。
「なんだって? もう一度いってごらん。粉でミルクをつくるといったね?」
おばあさんは、きつい声で聞き加えした。
そこでアルチュロは、くわしく説明した。
するとおばあさんは、いっそうきびしい顔になって、最後にアルチュロにこういったのだ。
「おまえは、そんなものを飲んではいけない!
わしらをだまそうとしているんだからの。見も知らずの人間が、わしらをだまそうとかかっているんだぞ。
それは、毒にちがいない。毒の粉じや!」
アルチュロは、一生懸命、そうではないといいはったが、なんのやくにもたたなかった。
おばあさんは、自分の考えが正しいと思った。あくまで、正しいと思ったのである。
ほかの子供たちがそれを飲んで病気になり、死ぬのはしかたがないが、たった一人の孫のアルチュロだけは、なんとしても、そんな目にあわせたくない。
なにしろ小さいとき両親を失くした孫を、これまでずうっと手塩にかけて育ててきたのだから、おばあさんにしてみれば、無理もない話だったろう。
戦争の最中、どんなに苦労して、孫のために食料を集めたことだったろう。
その孫を、見知らぬ人間から送られてきた、毒の粉なんかで、死なせてたまるもんか……。
「おまえが何といったって、そんなものは飲ませない。さあ、私にちゃんと約束するんだよ。
その毒のミルクには、手もふれないとな!」
アルチュロはしかたがないのでそうしますと、おばあさんに約束したのだった。
あくる日は、下級生だけの授業のある日だったが、上級生たちもお昼には、学校へやってきた。
老先生が、上級生にも給食をするから、登校するようにいったからである。
アルチュロは学校につくと、給食の手伝いにきていた女の人たちの自分を見る目つきから、すぐに察した。
〈ハハア、おばあさんが村の人たちに、粉ミルクが毒だということを、しゃべってしまったんだな。〉
アルチュロは、困ったなあと思った。
ミルクが飲めないことは、我慢できる。
また村の女の人たちが、そのことを知っているのも、しかたがないとあきらめることができよう。
が、どうしても、我慢ができないのは、友だちにそのことがわかってしまうことである。
しかし、もうわかっているにちがいない……。
そのとおり、生徒たちはみんな、そのことを知っていたのだ。
休み時間になると、友だちは、待ってましたとばかり、
「アルチュロは、ミルクを飲めないんだってさ。アルチュロの弱虫め!」
友だちたちは、つづいて、アルチュロのおばあさんの悪くちをいい始めた。
まぬけで、何一つものを知らない脳なしだと、はやしたてたのである。
しかし。友だちは心得たもので、老先生がそばにいると、知らん顔をするのだった。
老先生はそのミルクが、体にとてもいいと信じていた。それなのに、おばあさんは毒だといいはる。
アルチュロは、ただ、なさけなかった。
こうして二日間というもの、アルチュロはじっと我慢を続けた。
昨日の午後のことである。
アルチュロがみんなにワイワイからかわれていると、とつぜん、老先生があらわれたのだ。
みんなは、ぴたりと口をつぐんだが、先生はもう、耳にしてしまっていた。
先生はそのときは気がつかないふりをして、みんなのところを通りぬけていったが、授業がすむと先生は、アルチュロにあとに残るようにいった。
「アルチュロ、みんなに何をいわれていたんだね?
何を苦しんでいるんだね? おまえは、気がつかなかったろうが、私は、はじめから気がついていたよ。
おまえは、ここ二日も苦しんでいるじゃないか。」
アルチュロは、うなずいた。が、一言もいわずにだまっていた。
「アルチュロ、いうんだ。私はおまえが、なんで苦しんでいるか知りたいんだ。」
先生の声は、きびしかった。
「ミルクです。給食のミルクは、こなからつくるので、うちのおばあさんが、飲んではいけないといったんです。」
先生は、それを聞くと、めんくらったように、いった。
「でもおまえは、ミルクがきらいだといったじゃないか。」
「嘘なんです。僕、はじめの日に飲んで、とてもおいしかったんです。
それなのに、うちのおばあさんは、毒だといいます。
おばあさんは、そんなミルクを飲むと、病気になって死ぬというんです。
おばあさんは、けっして飲まないことを僕に約束させたんです。そして……。」
アルチュロは、悲しそうな顔をしていった。
「わかった。わかった。
おまえのおばあさんは、そのことを村の人たち残らずにいったのだが、私と私の家内にはいわなかったんだよ。
誰か、私にいってさえくれればよかったのになあ。
アルチュロ、おまえも黙っていたりしないで、なぜ、早くいってくれなかったんだ?」
「でも、先生は、ミルクは、とても体にいいものだと、おっしゃったので……。」
「わかったよ。おまえは私の気持をそこねまいとしたんだね。さあ、一緒に、おまえのおばあさんのところへいこう。」
老先生はアルチュロをつれて、彼の家へ向かった。
するとおばあさんは、家のまえにしげっている大きな木の下に座って、じっと遠くのほうを眺めていた。
おばあさんは、老先生にあいさつしたが、ちっともうれしそうではなかった。
老先生は、話しだした。おばあさんは口唇をかたくむすんで、そっぽをむいた。
先生は、そんなことにはおかまいなしに、話し続けた。
「あの食料を送ってくれたのは、本当に子供のためを思ってくれる、親切な人たちなんだよ。」
そうはいったものの、その親切な人たちが、どういうわけで、そういうことをしてくれるのか、どうしてこんなイタリアの、山の奥の子供たちが、食料に困っているのを知っているのか――
そのときはまだ、老先生もハッキリそのわけを知っていなかった。
それでも老先生は、知ってるかぎりのことを、おばあさんに話した。
アルチュロのおばあさんの、きぴしい表情がだんだんゆるんできて、とうとう、先生と顔を向きあわせた。
しかし、先生の話が、ミルクをつくる粉のことになると、おばあさんはまた、表情をけわしくした。
「いいえ、私はアルチュロに、それだけはけっして飲ませません。」
しかし老先生は、あいかわらず、やさしい口調でいい続けた。
「おばあさん。私はけっして、あれは毒じゃないといったろう。
けっして毒なんかじゃない。私が保証する。
あれをはるばる、遠い国からおくってくれた親切な人たちは、なんてえらい人たちだろう。
もう三日も、子供たちは粉からつくったミルクを飲んでいるんだ。
しかし、一人も、病気なんかになっていないのが、なによりの証拠じゃないかね。
病気になるどころか、顔色がすっかりよくなってきたぞ。
それに、食料を送られたのは、この村ばかりじゃない。
イタリアの残らずの町と村の子供たちに、送られてきたんだ。
そしてどこの子供も、よろこんで飲んでいる。飲んだために死んだという話は、一度も聞いたことがないぞ。」 |
おばあさんは節くれだった指で、みすぼらしい前掛けのはしをいじったまま、一言もいわなかった。
「この体によいものを、やはりアルチュロに飲ませない気かね?
あの粉はミルクをかわかして、粉にしたものなんだ。
どうして、そんなことができるか、私にもよくわがらぬがな。
しかし、けっして毒でないことは、私がいくらでも保証するから、アルチュロに飲むようにさせてくれまいか……。」 |
小さいアルチュロは、大きな木の下にこしをおろして、老先生のいうことをじっと聞いていた。
そしておばあさんが、なんというだろうかと、熱心におばあさんの顔を見まもった。
それなのにいつまでたっても、おばあさんは口をひらかない。
しかしとうとう、おばあさんは目にいっぱい涙をため、手をふるわせながら言い出した。
「うちのアルチュロも、粉からつくったミルクを飲んでいいです。」
老先生は、手をおばあさんの肩にやさしくおくと、
「よくいってくれた。ところで、おばあさんにたのみたいことがあるんだよ。
ミルクとスープの元を運んできてくれた人たちが、二、三日のうちに、今度はパンの材料の粉をもつてきてくれることになっているんだ。
村の女の人たちに、それで、子供たちのお昼のパンをつくってもらうことにしようと思っている。
おばあさん、あんたは村で一番、パンづくりがうまいといわれてきた人だ。
どうだね、一つ、そのパンづくりの監督をしてくれまいかね?」 |
「とても、そんなことはできません……。」
「おばあさん、村の子供たちのためだ。
おばあさんにみてもらって、おいしいパンができたら、子供たちはもっと、元気になれるんだからな。」
おばあさんは、ふしくれだった指で、またも、まえかけをいじりながら、しばらくだまっていた。 |
が、とうとう、ふるえ声でいった。
「よろしいです。村の子供たちのためにやりましょう。」
さあ、これで、この章のはじめに書いたように、アルチュロが、元気いっぱい学校へいそいでいくわけが、みなさんにもおわかりになったことだろうと思う。
老先生がたくさんいる村の女の人のなかから、パンをやく仕事の監督に、特別にえらんだのは、一体誰だったろう?
友だち残らずが、もうろくばあさんだとか、能なしだとかよんだ、僕のおばあさんではないか?
もう二度と、そんな口をきかせるもんか!
小さいアルチュロは、胸をとどろかせ、ほっぺたを真赤にしながら、元気いっぱい学校へ走っていくのだった。
10 ユニセフの活躍 top
|

国際児童救済基金(ユニセフ)のマーク
|

国連食糧農業機関(FAO)のマーク
|

世界保健機関(WHO)のマーク
|
|

送られてきたジャムをたべるブルガリアの少女たち
|

道ばたにつくられた食料配給所(ギリシア)
|
アルチュロたちの住むイタリアの山奥の少年少女や、幼い子供たちに配給されたスキムミルクの粉は、ユニセフの人たちがまず第一番に着手した仕事の一つだったのである。
ユニセフ・国際児童救済基金はできたが、さて、どういうふうにとりかかったらいいか?
これがまた、よういなことでなかった。
戦災にあった何百万という少年少女や幼児たちに必要なものは、いろいろあった。
医薬品も大いそぎでいるし、衣服もいるし、住む場所もいる……。
しかし、なんといっても、食料が一番さきに必要ではないか。
まず食料を送ろう。ユニセフの本部では、そうきめた。
ところで、まず最初に、どこへ送ればいいのだろう?
食料がたりなくて困っているのは、ヨーロッパの戦災地の人たちだけではない。
アジアの人たちだってそうだし、太平洋の島々の人たちだってそうだ。
まず最初に送るところを、どこにしよう?
本部では、いろいろ相談した結果、運送の便の一番いいヨーロッパということにきめたのだった。
第二の問題は、どんな食料を送るかということだった。
栄養に富んでいなければならないのはもちろんだが、手軽に船に積込むことができて、楽にに陸上げできるものでなければいけない。
それに、ユニセフの資金で、大量に買いつけることのできるものでなければならないし、大量に買うわけだから、できるだけ安価なものでなければいけないわけである。
ユニセフではこの問題を解決してもらうために、国連食糧農業機関(FAO)と、世界保健機関(WHO)の、それぞれ栄養問題の専門家たちにたのんだ。
すぐに青少年のための栄養問題委員会が、十二ヵ国の権威者を集めてつくられた。
カナダ、中国、キューバ、チェコ、フランス、イギリス、ギリシア、ハンガリー、イタリア、ノルウェー、ポーランド、アメリカの国々である。
それらの委員たちは、熱心な討議を続けて、次のようなものを送るのが、一番よろしいと決定した。
スキムミルク、チーズ、肝油、脂肪、食肉と魚肉、ココア、ダイス類、ジャムと砂糖、ピーナツ・バター。
ところで、それらの品物を、どこの国から買いつけたらいいだろう?
買いつけるにしても、時間がかかってはだめだ。すぐに買える国でなければならない。
ユニセフの本部は、すぐに世界中の国へ電話、電信、航空便などで問いあわせた。
すると返事が、ぞくぞく届いた。値段も予想していたより安かった。
ユニセフ本部では、さっそく大量買いつけの注文をだした。びつくりするほどの量だった。
それからの三年間に、ユニセフがアメリカ合衆国一国から買ったスキムミルクの粉だけでも、二十四億五千万ポンドを上回っている。
国際連合は、いろいろな計画をたて、それを実行したが、いつでも、一つの条件があった。
それは、国連のどんな計画でも、あいての国の人たちが、その国の政府をとおして、国連の専門家たちにきてもらい、よく話しあったうえでなければ、着手されないたてまえになっていることである。
それは、ユニセフの場合も同じである。
そういうわけで、ユニセフの本部ではまず、ヨーロッパの戦災地から、仕事をはじめようときめたので、さっそく、ヨーロッパの戦災国の政府へ、そのことを知らせることになった。
「あなたの国へ、ユニセフの本部の者たちがいってもよろしいか?」
ユニセフ本部から、それらの国へそういう電報がうたれた。
すると折り返して、「すぐきてもらいたい。」という返事が届いた。
アルバニア、オーストリア、ブルガリア、チェコ、フィンランド、ギリシア、ハンガリー、イタリア、ポーランド、ルーマニア、ユーゴースラビアの各国からだった。
一九四七年になると、ひどい日照りが続いたので、フランスもそのなかにくわえてもらった。
ポーランドは、こんな電報をうってきた。
「まず第一番に食料がほしい。」
それらの国へ、どのくらい食料をつみだせばいいのか調査するため、ユニセフ本部では、当時、合衆国児童局の副部長をしていたマルサ・エリオッ卜女史を、ヨーロッパへ派遣した。
エリオット女史は、それらの国へわたって栄養の不足している少年少女や、幼児の実数を調査し、その国で供給できる食料の量、そして、不足量がどれくらいかを、本部に報告した。
こうして、ユニセフの活動が始ったのである。
これは、月日がたつにしたがって、どんなに大事なことかが、よくわかった。
まもなく、ユニセフの仕事に協力しようという人たちが、いろんな国に続々とあらわれた。
もちろん、このむずかしい仕事が、ユニセフだけの力でできようはずはない。
教師や医者たちの団体、P・T・Aの人たち、それに各家庭の人たちが、すすんで協力を申し出たのだ。
そのほか、国際赤十字社、ボーイースカウト国際局、ガールースカウト世界連盟、国際ライオン・ロータリ・クラブ、国際Y・M・C・A(キリスト教青年会)、Y・W・C・A(キリスト教女子青年会)、世界カトリック団体、ユダヤ団体、新教団体、国際労働組合などである。
食料の輸送は、迅速に行われた。
食料はまずそれらの国の首都に送られ、そこでユニセフの係員が立ちあって、大都市と地方の少年少女・幼児への分配の仕事にあたる。
まだ、鉄道はこわされたままで、復旧していなかったし、橋はおちたままだったし、トラックは不足していた。
そのようなときに、よくもまあ山奥の村にまで、食料が輸送されたものだと、驚くしかない。
しかしそれは、やろうという決心一つにかかっていたのだ。
そして、そのかたい決心が、どんな困難にも打ち勝ったのである。
つづいてまず給食の設備が、学校、孤児収容所、病院、教会、そのほか、公民館などに設けられた。
そういうところを利用できない人たちのためには、畑や道ばたに間に合わせの小屋がつくられた。
なにしろ、戦災地のことである。
ストーブ一つ、ミルクをわかす釜一つさがすのにも、大変な苦労だった。
それに燃料が、簡単に手にはいらないときている。が、とにかくミルクの供給所は、こうして開かれたのである。
そういう供給所に協力して働いたある婦人が、本部にこう報告してきている。
「朝の七時三十分に、私たちは、ミルクをとかしたり、ほかの仕事の準備をするために、供給所につきました。
私たちは子供たちに、パンをあたえることもできない母親たちのために、かなりの量のパンをしたくしました。
七時四十五分に、子供たちは、きはじめました。
本当に小さい幼児ばかりで、母親とか、父親とか、兄さんや、姉さんに連れてきてもらっていました。
幼児たちは行列をつくり、暖かいミルクをついでもらおうと、どの子もコップを高くかざしてみせました。
暖かいミルクをコップについでもらうと、子供たちはうしろへさがって、地面にそっと座りました。
気候が寒いときなので、子供たちは、かじかんだ小さな手で、暖かなコップをしっかりにぎって、まず自分の手を暖めるのでした。
子供たちはどの子もオズオズと、ミルクをもらいにきました。
私たちは、したくしてきたパンを、子供たちの手に渡してやりました。そのときのうれしそうな子供たちの顔。
一緒にきた父親のなかには、あとに残って、私たちの仕事のあとかたづけを、手伝ってくれた人もたくさんいました。」 |
それがどんなによろこばれたか、目に見えるようではないか。
最初の年の冬のあいだに、これらの供給所は、ヨーロッパ中に三万ほどつくられ、そこでは毎日、三百五十万食を供給した。
もちろんこれは、たくさんの人たちの協力がなければ、とてもできる仕事ではなかった。
家庭の主婦たちは、すすんでパンづくりに手をかしてくれたし、大きい少女たちは、学校の料理の時間を利用して、ユニセフの仕事にかせいしてくれた。
また大きい少年たちは、野菜づくりにはげみ、それを供給本部に運んでくれた。
ユニセフ本部の事務局の人たちは、つぎにはどんな食料を積みだそうかと、しょっちゅう頭を使っていた。サメの肝臓からとれる油が、タラの肝臓の油よりも三十三倍もききめのあることがわかると、さっそく、ニュージーランドでとれるサメの肝臓をカナダで加工させ、すぐに、海をこえてヨーロッパに送った。
フィリピンでとれるヤシ油は、チェコで加工されて、ヨーロッパの戦災地に送られ、パンにぬってたべると、とてもおいしいと、子供たちのあいだに、たいそうよろこばれた。
こうして、ヨーロッパのいろいろな国の港に陸上げされるユニセフからの食料の量は、どんどんふえて、三年目のすえには、ヨーロッパ十二ヵ国の少年少女や幼児に供給された食事の数は、一日六百万食にまではねあがった。
食料ばかりではない。
そのほか、衣料や靴、医薬品や、せっけんなどが、同じようにユニセフの手でどんどん送られてきて配給された。
また、四年間にユニセフの送った皮、羊毛、もめん類は、五百万ドルにたっした。それらの皮から、子供たちの靴が百万足以上つくられたし、また羊毛や木綿(もめん)からは、百万組の毛布と百万人分の服がつくられたのである。
それでもエルゼさんは、一生懸命、書き始めた。書くにしたがって、彼女の顔には、微笑がわいてきた。
〈ああ、あの少年や少女たち、そして、小さい子供たち! あの子たちは、本当にいい子たちだったわ……。〉 |

ユニセフ配給の皮でくつをつくるギリシアの子
|
11 エルゼ看護婦の報告 top
一九四七年の、ま冬のある日のことである。
その日は、寒さがとてもきびしく、長いかがい一日だった。看護婦のエルゼ・アンドリアさんは、もう疲れきっていた。
なにしろ、朝からひっきりなしに働きづめだったからである。その長い一日も、やっとおわった。
エルゼさんは、やれやれと息をついたが、今日の一日の報告を書いて、デンマークの都コペンハーゲンの本部に送る仕事がまだ残っていた。
エルゼさんは便箋をとりだすと、薄暗いカンテラの灯影で、報告書を書き始めた。
エルゼさんの手はひどく冷たくて、鉛筆をにぎっていても、にぎっているという感じがすこしもない。
「――ここは、チェコのストライボの近くの小さい町です。
ルンド博士とフンバルスカ医師とわたし、それにチェコの手伝ってくださる方の四人は小さな町の郊外にある、ある学校へ自動車を向けました。
ルンド博士が、車のハンドルをとりました。道はどこもここも、大変な雪です。
すこしすると、とつぜん自動車は横にすべって、溝におちこんでしまいました。
私たち四人は自動車を溝から引上げようと、一生懸命やってみましたが、私たちではとても手におえないことが、じきにわかりました。
私たちはすぐに町へ引き返して、手伝ってくれる人を探すことになりました。
さいわい農家の人たちが、いく人もきてくれ、自動車を溝から引上げてくれました。
そのなかの一人のかたが親切にも、その学校へ道案内してくださると、いうことでした。
ところがしばらくいくと、大変な雪で、もう一歩もすすめません。
でもそこからは、もうあまり遠くないというので、私たちは車からおりると、大事な道具類や薬品をもって、雪の道をあるきだしました。
一時間ほどあるくと、めざす学校に着くことができました。
小さな学校で、先生は一人でした。
その女の先生と生徒たちは、教室に集って、私たちを待っていてくれました。
女の先生は私たちを見るととんできて、すぐに調理場へつれていきました。
そして真赤にもえているストーブで、服をかわかすようにいってくれました。
それから、熱い紅茶とケーキをだして、もてなしてくれました。
私たちは、それからすぐに仕事にかかりました。
残らずの生徒にBCGの接種をおわって、ホッとしたところへ一人の人がとびこんできました。
そして、よその学校の百人ほどの生徒が、どうしてもこの学校にまでこられたいで、途中の宿屋で待っているというのです。
その生徒たちもこの学校へ集って、一緒にBCGの接種をすることになっていたのです。
それが大雪のために、どうしてもここまで来ることができなくなったのです。
『そんなわけですから、ごむりでしょうが、その宿屋までおいでになっていただきたいのです。』
その人は、いくども私たちにたのみます。
私たちにどうしてことわれましょう。私たちは、そこへいくことにしました。
その学校の女の先生は、私たちのために、二頭だての馬ぞりを用意させてくれました。
私たちはそれに乗っていきました。
毛布一つないそりでした。それに、途中の道はけわしく、おまけに大変な雪です。
それこそ、体がこおってしまったかと思いました。
やっと、私たちはその場所について、無事にBCGの接種を残らずの生徒に行うことができました。」 |
看護婦のエルゼさんは、一番おしまいに、自分の名前を署名するとホッとして、鉛筆を下においた。
エルゼさんは、いま報告書に書いたように、ルンド博士、フンバルスカ医師と三人で、BCG(結核予防ワクチン)巡回班を編成して、チェコの国をまわっていたのである。
もちろん、この巡回班は、エルゼさんたちばかりではない。
ほかにも、何百という人たちが。それぞれ班をつくって、戦争ですっかりあれはてなヨーロッパの国々を、巡回していたのである。
この結核予防の大きな運動は、スカンジナビア諸国(デンマーク、ノルウェー、スウェーデン)の赤十字社とユニセフ、それにWHO(世界保健機関)の手で、始められた仕事だった。 |

BCG接種のため、遠くの田舎の村へまでも、泥の道をいく
|
12 ヨーロッパの結核予防運動 top
|

コペンハーゲンから、ヨーロッパ各地へ送られる結核予防医薬品
|

世界各地で結核予防運動が。(インドでのツベルクリン反応テスト)
|
その巡回班は、BCGの巡回班とよばれていた。
BCGというのは、みなさんも知っているように、結核予防のワクチンのことである。
BCGは、二人のフランスの人の医学者たち――カルメット博士とグーラン博士によって、第一次大戦中から戦後にかけての長いあいだ実験され、つくられたものである。
そして、オランダとノルウェーの二国が、自分の国の青少年や幼児に使用して、効果をあげていた。
第二次世界大戦後、ヨーロッパの国々の少年少女や、幼児にふえた結核をふせぐために、BCGをつかっからどうかと、国際連合に提案したのが、オランダとノルウェーだった。
その提案は医師と看護婦で巡回班を編成し、少年少女や幼児にツベルクリンの注射をして歩いたらどうだろうということだった。
ツベルクリンというのはみなさんも知っているように、名高いドイツの細菌学者ロベルト・コーホ博士によって、発見されたもので、結核菌を培養してつくったワクチンのことである。
結核菌が、体に入ったかどうかの診断には、なくてはならたいものである。
このツベルクリンを注射して、反応が陰性だったら、BCGを接種する。
そうすれば、結核菌が入り込んで感染しても、体が抵抗できるようになり、発病しないですむのである。
反応が陽性だった場合は、レントゲンやそのほかの検査をして、進行性だと認められると、病院や療養所に送られるのである。
デンマークの首都コペンハーゲンや、ノルウェーの首都オスロにある研究所では、ツベルクリンとBCGワクチンの製造に全力をあげた。
そして、医者や看護婦たちは、熱心にそれらの薬品を少年少女や幼児たちに使ってみた。
その結果、彼らの努力は、じゅうぶんむくいられた。
それらふたつの国の少年少女や幼児の結核発病率は、その予防運動がはじまってからというもの、ぐんと少なくなったのである。
さて、第二次世界大戦がすんですこしすると、それらの二国をのぞいたほかのヨーロッパの国々の、多くの少年少女や幼児は、結核にかかったのである。
そしてその死亡率が、とても高いということがわかったのである。
さあ、そのことを聞いて、デンマークの人たちはそれは大変と立ち上った。
デンマークの人たちは、自分の国の赤十字社、国立血清研究所、国立保健協会などによびかけると、さっそくBCG地方巡回班というものをつくり、一九四六年の九月には、ユーゴスラビアヘいって、仕事を始めた。
すこしすると、その結核予防運動に、スウェーデンの赤十字社と、ノルウェーのヨーロッパ救済連盟がくわわった。
こうして、一九四七年のすえまでに、スカンジナビア連合BCG巡回班は、オーストリア、チェコ、ドイツ、ハンガリー、イタリア、ギリシア、ポーランドというたくさんの国々をめぐって、仕事を続けたその費用は、スカンジナビアの国々の国民たちが、負担したのである。
それらの巡回班の活動は、本当にめざましいものだった。
しかし、じきにその人たちだけの力では、どんなに努力をしても、まにあわないということがわかった。
それほど、結核でたおれる少年少女や幼児の数が、多かったのである。
そこで、その人たちは、国際連合のなかにあるユニセフとWHOによびかけたのである。
「私たちの運動にくわわってはもらえないでしょうか?」と。
すでに、WHOは、結核の予防と、撲滅の問題に立ち上っていたのだった。
国連にWHOがもうけられて、最初の仕事の一つは世界の結核の専門家たちに委員になってもらい、世界中の国々の政府に、結核がどんなに恐ろしい病気であるかを、いろいろな方面から説明し、それの予防と治療の方法について知らせることだった。
ちょうどその時、スカンジナビア諸国の考えついたBCG巡回班の計画が、WHOに提案されたのである。
WHOの人たちは、すぐにその計画に賛成した。
それは、戦災にあった少年少女や幼児を救うばかりではなく、BCGというものを研究し進歩させるにも、このうえない、よいチャンスでもあったからである。
ユニセフも、その計画に賛成した。
そして都合のよいことに、ユニセフは、その仕事を行うことのできる基金を、たくさんもっていたのだ。
そこで、さっそく、大規模な結核予防運動が、始められたのである。
こうして、WHOは、自分のところから専門家をだして、スカンジナビア諸国の巡回班を後援することになり、ユニセフのほうは、各国の政府と共同して、器具をはじめ、いろいろな経費を分担することになった。
結核予防運動の総指揮者には、デンマーク赤十字社のアムンゼン博士が任命された。
アムンゼン博士は婦人で、その博士の指導のもとに、BCG巡回班の医師や看護婦たちは、まずスカンジナビアで編成され、それから、ヨーロッパのいろいろな国へ出張していった。
はじめ、巡回班の準備は、ごく簡単なものであったが、そのうちに、大都市などをまわる自動車には、レントゲン装置をはじめ、いろいろな道具類がそなえられるようになった。
BCGワクチンは、研究所でつくられたあと、わりあい短い期間に使われないと、効果がなくなる。
そこでそのため、飛行機が使用されることになった。
BCGワクチンが、コペンハーゲンのオランダ血清研究所でつくられると、飛行機がすぐにつんで定期的にワルソー、プラーグ、ブダペスト、ベルグラードへと運んだ。
飛行機はまたBCGワクチンぽかりでなく、ペニシリンやストレプトマイシンをはじめ、注射器などの器具や自動車のタイヤまで運んだ。
こうしてBCG巡回班は、ヨーロッパの都市や町や山奥のさびしい村にまでいって、子供たちの結核の予防と治療に、めざましい活動をしたのだった。
13 BCG巡回班の活躍 top
|

手に手にカードをもって、注射をまつポーランドの子
|
BCGの注射については、こんなことがあった。
ある学校の下級生のなかで、とてもツベルクリンの注射をされることの好きな男の子がいた。
その男の子は、ツベルクリンの注射をうけたが、もう一度してもらいたくてしかたがない。
そこで友だちにこんな嘘をついて、頼んだ。
「きみ、その注射をうけるカードを僕にかしてくれたいか。そのかわり、僕、きみにとってもいいものあげるから。」
その友だちは、注射がきらいだったので、大よろこびで、自分のカードをわたした。
すると男の子は、そのカードをもっていって、またツペルクリンの注射をしてもらい、大得意で戻ってきたのである。
その男の子は、もう一人のまだ注射をしてもらっていない友たちのところへいくと、また、うまいことをいって、カードをかしてもらった。
男の子は、カードをもって、またまた、お医者さんのところへいった。ところが今度は、ばれてしまったのである。
またある学校では、ツベルクリン検査の結果にしたがって、生徒たちにピンク色のカードと青い色のカードをそれぞれわけてあたえた。
すると、どうだろう――
生徒たちはこれは都合がいいぞとばかり、さっそくピンク組と青組に別れて、フットボールの試合を始めてしまった。
お医者はグランドを見て、「これは、これは……。」と、驚くばかりだったという。 |

ストレプトマイシンで結核を治療するイタリアの少女

セルビアの子どもの結核療養所
|
次は、ユーゴスラビアのノバグラディスカという町の近くにある学校で、生徒たちのツベルクリン検査をしたときの愉快な話である。
カーレンさんという看護婦が、小さい子供たちを一列にならべると、一人一人、自分の膝(ひざ)の上にのせて、注射をしてやっていた。
すると列のうしろのほうで、この様子をジッと見ていた十七才のずうたいの大きな少年が、自分の番になると、どうだろう。
こわそうな顔をして、小さい子と同じように、カーレンさんの膝の上にのってしまった。
これには看護婦のカーレンさんも、目を白黒させて驚いたということである。
毎日毎日、くる日もくる日も、BCG巡回班はやすまずに働いた。
どの巡回班も、長い時間、やすまずに働いた。
大都市をうけもった巡回班になると、一日に千回もワクチン注射をしなければならなかった。
巡回班が一体何をしにきたのか、わからない人がたくさんあったが、それをわからせるのは、その国の赤十字社の人たちとか、そのほか、いろいろな人たちが、すばらしいやりかたで協力してくれた。
しかしそれにもかかわらず、ツベルクリンやBCGというものがよくわからないために、いろいろ、面倒なことがおこることがあった。
なかには、通訳なんかのいうことをきかないで、巡回班の人たちに直接きこうとする。
そのため、巡回班の人たちは、やっと覚えた片言(かたこと)の、その国の言葉で応待しなければならないことも、めずらしくなかった。
次のことは、ポーランドのある小学校であったことだが、ある日、デンマークの巡回班の看護婦が、生徒たちがぞろぞろ教室に集ると、片言のポーランド語でこういった。
「みなさん、これから、はじめますから、めいめい頭の上にのってください。」
生徒たちは、どっと笑いだした。
そのオランダの看護婦さんは、こういうつもりだったのである。
「みなさん、さあ、はじめますから、一列にならんでください。」
最初のころ、おおいに活動したデンマークのBCG巡回班の一人で、ジョン・ブンツェン医師は、ユニセフの本部へ、次のように報告している。
「私たちは、ユーゴスラビアへ到着して、あちらこちらの市や町や村を巡回して歩いた。
いく先々で、私たちの見たものは、戦争による災害と破壊のあとだった。
しかし、私たちの驚いたのは、復旧事業が、すでにはじまっていたことである。
どこでもここでも、みんなが、力をあわせて、復旧事業につとめていた。
あるところでは、十三才から十六才までの少年たちの一団が、とても熱心に、こわされた鉄道の復旧にはげんでいた。
大抵の大きな市は、爆撃されてメチャメチャになり、ガランとしていた。
市とは思えず、まるで、さぴしい村といってよかった。
お百姓たちは夜になると、町のなかに家畜を連れてきて囲い、明るくなると野原につれていく。
だから、夕方になると、町のなかは、そういう家畜や車などで、ごったがえすのだった。
へんぴな田舎へいくと、読んだり書いたりすることのできない人たちが、たくさんいる。
だから、私たちが、何をしにきたかということを知らせるには、口で伝えるしかない。
検査や注射をする場所や、時刻を知らせるには、たいこをたたいてふれまわることにした。
それでもあつまらないときは、赤十字社の支部の人たちが、一軒一軒回って連れ出してこなければならない始末だった。
しかしそのかいがあって、私たちは、とてもよい成績をおさめることができた。
少年少女や幼児たちがきてくれた率は、実に九十パーセントというすばらしい成績たった。
母親や父親は、子供たちを何キロという離れたところから連れてきてくれた。
なかには真夜中に家をでてきたという人たちもあった。
そうしなければ明るいうちに、巡回班のいる町に着くことができないからである。
なにしろ遠いところからくるので、家じゅうみんなが馬車に乗り、焚き木から食料にいたるまで、すっかりしたくしてきた一家もよくあった。
そういう人たちは、レントゲンをかけてもらうとどんな病気でもなおると、かたく思いこんでいたからである。
ユーゴでは、もともと結核が一番死亡率の高い病気の一つだった。
それが戦後は、いっそう高くなり、十万人について三百人をこえる死亡率になっていたのである。」 |
このようにして、ヨーロッパのBCG結核予防運動が始められてから、二年間に、九つの国の合計千四百万人の少年少女と幼児が、ツベルクリン検査をうけ、そのうち七百五十万人がBCGワクチンの注射をうけた。
BCG巡回班は、ヨーロッパのいたるところで、みんなから歓迎された。
夏には、巡回班のジープやトラックは、どれもうつくしい花でかざられ、歓迎の歌でむかえられた。
かわいい孫が、ワクチンを注射しもらったといって、そのお礼に遠いところから、わざわざ卵一つを大切そうにもってきて、看護婦さんにくれたおばあさんもあった。
ツベルクリン反応が陽性で、結核におかされていると診断された何万という少年少女や幼児は、すぐに病院や療養所に入れられた。
ユニセフは、全力をあげて、BCG巡回班の仕事に協力した。
レントゲン装置をいく千台とかく送り、また、必要な医薬品をいくトンとかく送ったのである。
そのなかには、アメリカのワクスマン博士の発見した新薬、ストレプトマイシンもふくまれていた。
わずかな日数のあいだにユニセフでは、十ヵ国の三十の病院に大量のストレプトマイシンを送り届けたのだった。
14 ほかの大陸へも top
|

ワクチンの注射をするパキスタンの農夫
|

チュニジアの遊牧民の検査
|
ヨーロッパのBCG巡回班の仕事が軌道にのると、WHO(世界保健機関)とユニセフとは、その結核予防運動を、ほかの大陸にまで、おしすすめる計画をたてた。
北アフリカが次の施行地域にきまると、アルジェリア、モロッコ、チュニジアなど、北アフリカの医師たちがえらばれてヨーロッパに渡り、BCG巡回班の活動を見学し、また実地に訓練をうけることになったのである。
のちには、そのなかにエジプト、タンジェール、イスラエル、レバノン、シリアなどの医師もくわわった。
こうしてそれらの地域にも、BCG巡回班の活動が始められたのである。
その状況について、モロッコからマクスペレー博士が、次のような報告をよこしている。
「私は、BCGの巡回を、まず、サルタン(王さま)の王宮、市場、回教の寺院などで行いました。
どこでも大変な数の人が集りました。まったく、びつくりするような人の群れでした。
私の一番困ったのは、集った少年少女のせいでもなければ、幼児たちのせいでもありません。風なのです。
消毒用のアルコールランプはふきとばされるし、書類や記録を書いた紙は、空にまいあがるし、いやもうサンザンでした。
砂漠をふいてくる風のおかげで、目の中にしょっ中ほこりは入るし、器具類はすぐに砂だらけになってしまうのでした。」
「BCG巡回班がきたから、みんな検査をしてもらうように。」
というサルタン(王さま)の命令は、まるで電波のように、ひろいひろい砂漠を伝わっていく。
BCG巡回班の医者や看護婦たちは、そのサルタンの言葉の伝わり方があまりに早いので、誰もかれも驚いてしまった。
クラウド・サイモン医師は、モロッコの国の一番はしの地域を受持っていたが、そこへいってみると、どこのオアシスでも、部落民や子供たちが、サルタンからいわれたといって、ちゃんと待っていてくれるのだった。
アフリカではどのBCG巡回班も、BCGワクチンのききめがなくならないように冷却器とか、魔法びんに入れて運ばなければならなかった。
それにアフリカでは、医療器具のほかに、どこでも野営できるようにキャンプ用具を車に積込まなければならなかった。
いつ、どんなところで、野営しなければならなくなるかわからないのである。
ジーン・ミレー女医の巡回班は、ミレー女医のほかに、看護婦二人、アラビア人の助手二人、それに運転手の六人から編成されていた。が、その報告書には、こんなことが書いてあった。
「モロッコで、私たちの最初の三ヵ月のあいだ、一番大きい障害といえば、それは雨がふるとすぐに洪水がおこって道がなくなってしまうことでした。
そのために私たちは、よく目的地へつくのに、百キロも二百キロも遠回りをしなければなりませんでしたし、そのうえ途中で、いくども道を自分たちの手でなおして進まなければならなかったのです。
それにもかかわらず、私たちは、タラダン、チズニット、イネズガン地方を、一日に五十キロから百キロにわたって、巡回することができました。」
15 カイロの町で起ったこと top
|

WHOのかつやく(ポスター)
エジプトでコレラが発生したが、WHOの活躍で
未然に流行するのを防ぐことができた。
|

健康管理のため、婦人たちは話しあう(エジプトこて)
|
ここは、エジプトのカイロの町。
アビドとナシルはエジプトの少年たちで、いつも学校がおわると、遠まわりして家に帰ることにしていた。
二人は、カイロの町の、にぎやかな区域へ足をむけるのである。
高いビルと、商店のならぶ通りをいそいでとおりぬけ、市場に集る人々のあいだをかきわけて、最後に外国人の観光客の集る場所にやってくるのだった。
そこにいきさえすればいつだって、ピラミッドを見物にいってきた外国人たちが、自動車からおりるのを見ることができたからである。
〈外国人って、なんて、おかしな人たちだろうなあ!〉
二人は、いつでもそう思った。
外国人の見物客を、自動車に乗せていってきたエジプト人の運転手は、どの運転手も、きっと、外国人のかわった話をする。
ある外国人は、ぜひピラミッドに登ってみたいといって、石の壁をはって、頂上に登った。
せっかく登ったのだから、頂上でゆっくり見物するのかと思うと、ろくにまわりの景色を見ようともしないで、また、すぐに降りてきたという。
そうかと思うと、ラクダのうえに自分が座っている写真を、わざわざお金までだして、大よろこびでとってもらっている。
外国人というのは、お金を使うことを、ちっとも気にかけていないようだ。
そして、見物から戻ってくると、いつだって大よろこびで、はしゃいでいる。
アビドとナシルはそういう外国人を見ていると、いつでも、あきるということがなかった。
ところが、どうしたことだろう。
一九四七年の十月のある日のことであるが、二人がいつものように、学校の帰りにそこへいってみると、まるで様子がかわっていたのである。
車から降りるどの外国人も、笑い顔一つしなければ、うれしそうな声一つたてないのだ。
なかには青い顔をして、足早にサッサといってしまう人もいた。
自動車からおりても外国人たちは、びっくりしたような声で話しあっている。
「一体なにが、おこったんだろう?」
アビドとナシルの二人は、自動車の運転席で、お金を数えていた顔見知りのカシムのところへ走っていった。
「なんかあったの? 誰か、ピラミッドからおちて、大けがでもしたの?」
アビドが心配そうにたずねた。ナシルのほうは、アビドが、とっぴょうしもないことをきいたので、ゲラゲラ笑った。
すると、運転手のカシムは、数えていた手をやめて、顔をあげると恐い顔をした。
「笑いごとじゃないぞ。おまえたちだって、じきに死ぬんだからな。
俺だってそうだ。みんな、死んでしまうんだぞ。」
少年たちはギョッとした。いつも運転手仲間で一番陽気なカシムではないか!
それが、こんなことをいうなんて!
「おじさん、い、いったい、それ何のこと?」 アビドが、どもりどもりたずねた。
「何って? あいつが、また、おそってきたんだ。
ギゼの町で、よそからきた運転手に聞いたんだが、コレラなんだ――
俺のおじいさんも、コレラの恐ろしさについては、いくどとなくいってたな。
今から、十年ほどまえにはやったことがあるんだ。
そのときのはやりかたの恐ろしいことといったらな――いいか、一人残らず死んでしまったんだぞ。
俺のおじいさんは、それをちゃんと見たんだからな。」 |
運転手のカシムは、お金を数えおわると、車からおりてきて、二人にいった。
「逃げるんだ! とにかく、遠いところへ逃げるしかないんだ。」
アビドとナシルはそれを聞くと、夢中で家へ向かって駆け出した。
人にぶつかったり、自動車をスレスレによけながら、家に駆け戻った。
アビドは、家のそばの角をまがったとたん、嫌っというほど、一人の青年にぶつかった。
青年は、もっていた何冊もの本を、地面にまきちらした。
「こらっ!」
青年は、大声でどなったが、すぐに、
「や、アビドじゃないか! おい、とまれ! そして、すぐ、僕の本をひろうんだ!」
青年は、アビドの兄のオーラだったのだ。
オーラは、カイロの町にあるアメリカの大学にかよって、法律を勉強していた。
お父さんが、弁護士をしているので、ゆくゆくは、お父さんのあとをつぐつもりなのである。
アビドは兄さんの腕をつかんでいった。
「僕たち、死ななきゃならないんだって――。兄さんも、お母さんも、お父さんも――みんなだよ。」
兄さんのオーラは顔をしかめた。
「おまえ、頭がどうかしたんじゃないのか?」
「コレラなんだ。コレラがこの町にもやってくるんだって。
ギゼの町であったどこかの人が、運転手のカシムにいったんだよ。」
「いきずりの人に聞いただけで、信じてしまうなんて、カシムもどうかしているんじゃないか。」
「本当なんだ。僕、知ってるんだよ。サア、逃げださなくちゃ。
コレラはまるで、野火みたいに拡がるんだってさ、カシムが、そういったんだ。」
「おちつけ、おちつけ!」
と、兄さんは、まじめな顔をして、アビドにいった。
「まず、おちている本をひろってくれ。それから、家に戻って、電話をかけて確かめてみよう。
病院のアリーにかけてみれば、だれに聞くよりか、いちばん確かだからな。」
アリーというのは、二人のいとこで、カイロの町で一番大きい病院のインターンをしていた。
「カシムは、どういうわけで、一人残らず死ぬといったんだろうな?」
兄さんのオーラは、家へ向かって駆け出しながら、アビドにきいた。
「カシムのおじいさんが、まえにはやったとき見たんだって。一人残らず死んだってよ――
一人も、生きられなかったんだって。」
オーラは、それを聞いて笑いだした。
「じゃ、カシムのおじいさんだけは、どうして、生きていられたんだい? おかしいじゃないか。」
「うん、そうだね……。」
アビドは、返事ができなかった。
二人は家に戻ると、さっそく病院に電話をかけた。
病院の交換手は、オーラの電話をうけると、ぶっきらぼうな声でいった。
「アリーさんは、電話にでられません。あなたはどなたです。どこからかけているんです?」
「僕は、アリーのいとこで、自分の家から電話をしているんです。」
「じゃ、家からでてはいけません。いまラジオで放送するはずですが、コレラがはやり始めたのです。」
16 二十世紀の偉業――WHO top
夜にならないうちに、エジプト政府は、エジプトの残らずの市場、商店、人の集る場所などをとじてしまった。
国境の要所要所には、きびしい見はりがついて、通行人がとおるのを禁止した。
役人をのぞくと誰一人、エジプトの国へ出入りすることができなくなった。
医者、看護婦、赤十字社の人たちが、コレラの発生した場所へ駆けつけた。
カイロ市の人たちは、どこへもいかないで、コレラ予防のワクチン注射をうけるようにと、ラジオが伝えた。
運転手のカシムのいったことは、本当だったのだ。
コレラという病気は、本当に野火のように、アッというまに伝染するのである。
十九世紀にはヨーロッパに五回、コレラの大流行があった。三回は大西洋をこえて、北アメリカにまで流行したのだった。
その日―― 一九四七年の十月のある日、エジプト政府が国民に警告をだすまえに、コレラが発生したという知らせは、カイロからスイスのジェノバにある国連WHOのなかにある流行病対策本部に届いていた。
ジェノバの流行病対策本部から、警告は、すぐに、ヨーロッパ中に伝えられた。同時にアメリカヘ、インド洋をこえてアジアへ、アフリカへ、中東へ、また地中海方面へと、伝えられたのである。
たちまち各国の港や空港では、検疫官が緊張して待機した。すぐに、世界中の人たちが活動を始めた。
エジプト人全員の分の血清を、大至急で送らなければならない。
エジプトの人口は、九百万人である。世界中の国々の血清を集めても、はたしてたりるだろうか。
アメリカ合衆国では、全部のワクチン製造工場が、ほかの仕事を一時やめて、コレラ予防の血清の製造に全力をあげた。
伝染病の専門家たちが招集されて、四十八時間もたたないうちに、もう、エジプトに向かってとんでいた。
その人たちの乗っている飛行機には、積めるだけのコレラ予防の血清が、積んであった。
アフガニスタン、オーストラリア、ベルギーの国々からも、飛行機が血清を積んでとびたった。
ブラジル、中国、イタリア、オランダ、スペイン、トルコ、ソビエト、日本、韓国からも、血清を積んだ飛行機が、エジプトに向かってとびたった。
それらを合計すると、コレラ予防のワクチンは、三十二トンにのぼり、そのほか、血漿、緊急用品が運ばれた。
五週間にわたってコレラは、エジプト中にひろがった。
ところが十二月にはいっての最初の週のうちに、見事にコレラの流行が食い止められてしまったのだ。
なんという見事さだったろう。
あのように大きくひろがった流行病が、こんなに短い期間に、ピタリと食い止められたのは、人間の歴史はじまってはじめてだったということである。
そしてまた、その死亡率はどうだったろう?
あの運転手カシムのおじいさんが見たという、昔のコレラの大流行のときは、八十五パーセントの死亡率だったのが、今度は、四十八ハーセントにとどまったのである。こんなふうに、世界中の人たちがびつくりするほど短い期間に協力できたのは、WHO(世界保健機関)が活躍したからである。
WHOが、一九四六年に設立されたとき、まず最初の事業計画の一つは、ひろく流行病をコントロールする組織をつくることだった。
WHOのなかには、さっそく専門家たちの委員会がもうけられ、世界中の国々のために、コレラばかりでなく、天然痘、ペスト、チフス、黄熱病をはじめ、そのほかいろいろな伝染病についての予防法と、一番新しい治療法をまとめあげたのだった。
現在、スイスのジェノバにあるWHOの本部では、一日に二回近くにある、いくつもの強力な送信所から世界中にむけて、各地から集る報告を電波にのせて、送っている。
「アフガニスタンにチフス発生。」
電波はそう伝えると同時に、一方、飛行機はすぐに必要な医薬品を積んで、現地に向かってとびたつ。
そしてじきに、「チフスの発生はとまった」と、電波は伝えるのである。 |

WHOとユネセフの共同による保健活動(マラリア対策)
|
「ボリビアに黄熱病発生。」 電波はそう伝える。
と同時にWHOは、パン・アメリカン衛生局をとおして、活動をはじめ、すぐに黄熱病を食い止めるのである。
WHO(世界保健機関)は、いままでもそのようにして数々の活動を続けてきたし、これからもいつそう活動をつづけることであろう。
WHOの活動は、医学に関係している人たちからは、実に二十世紀の偉業とたたえられているのである。
17 ギリシアの少女キリアの場合 top
|

人はだれしも、恐れから自由になる権利をもっているが、しかし……
|

人は、教育をうける権利をもつ(イタリアにて)
|
ここは、ギリシアの片田舎。
十六才の少女キリアは、やぶかげにひそんで、子供たちがワイワイいいながら遊んでいるのをジッと、のぞいていた。
子供たちは、あちこちこわれている倉庫のそばで遊んでいるのだが、その倉庫は今は子供たちの学校になっていたのだ。
〈馬鹿な子供たちだわ。あんな古レンガを運んできて小屋をつくろうなんて……。〉
キリアは、そう思うのだった。
〈本当に、馬鹿な子供たちだわ。あの子たちばかりじゃないわ。
ケーディだって、だれだってみんな馬鹿だわ……。〉
ケーディというのは、戦争前まではキリアと仲良しの少女だった。
戦争前までは、キリアと仲の良かった少女たちは、今はみんな、かわってしまった……。
〈へえーッ、あんなこわれた倉庫が学校だって! あんなところへいってやるもんか。〉
戦争の被害をこうむったこの小さな村では、教科書といえば、先生が何冊かもっているきりだった。
だから生徒たちは、学校がおわると、せっせとその本をうつし、あくる日はそれを勉強するのだった。
〈あんなものをうつして、午後の時間をむだにするなんて、なんて馬鹿だろう。第一もったいないわ……。〉
少女キリアは、いつもそう思うのだった。
戦争中はこんなことは、まるっきりなかった。
キリアは敵の野営しているところへこっそりしのびこむと、敵が見はっているのもかまわず、品物でも食料でも手あたりしだい、かっさらってきた。
キリアはまた、地下のゲリラ隊の大事なルポ(連絡係)をつとめ、秘密の文書をたずさえては、しょっちゅう味方のあいだを連絡して歩いた。
敵につかまると、いつもオシの真似をしてはうまく逃れた。
「まったく、キリアは、すばらしい子だ。」
誰もかれも、そういってほめない者はなかった。
戦争がおわると、キリアは一躍、子供たちの人気の的(まと)になった。
どんな子も、キリアには一目置いたものである。
それが、どうだろう!
今は、まるっきり違ってしまい、誰一人、キリアをほめる者はいない。
キリアの母親は、キリアが、まえのように学校へいかないといっては叱る。
でも学校といったって、机もなければ、黒板一つ、地図一つない。
あれじゃ、学校なんてものじゃないと、キリアは、思うのだった。
〈まったく、あんなの、学校なんていえないわ。〉
木箱をもっているものは、それをもっていって、椅子のかわりにする。
もっていない者は、つめたい床に、そのまま、すわらなければならなかった。
それは、キリアにはまだ、我慢ができた。
キリアだって、はじめ二日ほどは、学校へいってみたのである。
ところが、先生がキリアを算数の時間に、ずっと小さな子供たちの仲間に入れてしまったのである。
キリアはまえから、算数はひどく苦手で、ちっともできなかった。
それはキリアが勉強しなかったせいでもあるが、そんなことは別として、いま彼女はまえよりもはるか下の組に入れられてしまったのである。
キリアと同じ年ごろの少女たちは、ドイツに占領されていた期間もこっそりひらかれていた授業に出席して、勉強を続けていたのだった。
キリアはそのころは、勉強どころではなかった。
味方の秘密のゲリラ隊のルポをつとめて、あっちこっちと、毎日とぴまわっていたのだ。
だから今、算数ができないといわれたって、当り前じゃないだろうか――。
〈本当に不公平だわ。〉
キリアは、不満でいっぱいだった。そういうわけで、学校へもいかなくなってしまったのである。
さて、はじめに戻って、キリアはやぶかげから子供たちが遊んでいるのを、ジッと見まもっていた。
子供たちはこわれたレンガを運んできて、高さ一メートルくらいの壁を、まわりにグルッとつくると中を二つに仕切った。
部屋を二つ、つくるつもりらしい。
子供たちは、すこし離れたところにある、こわれた建物のあとに積んである、古レンガの山へ走っていった。
あとを続けて、運んでくるつもりなのである。
キリアはすばやくあたりを見まわした。
それから体をかがめて、そっと、やぶかげから走りでると、子供たちが積みあげたレンガの壁のところへ近づいた。
キリアは次の瞬間、せっかく子供たちが積みあげたレンガの壁を、足でけとばしてしまったのである。
残らずくずしてしまうと、キリアはいそいで元のやぶかげに引き返した。
〈これで、せいせいしたわ!〉
子供たちは、めいめい、もてるだけのレンガをかかえて、戻ってきた。
が、戻ってみると、このありさまではないか!
「だれだ、こわしたのは!」
子供たちは、誰もかれも、大声をあげて、どなりちらした。どの子も、カンカンに腹をたてた。
何人かが、校舎にしている倉庫に走っていって、この事件を知らせた。
先生と高学年の生徙たちがゾロゾロと出てきた。
みんなくずされたレンガを見るなり、ひどいことする者もいるもんだと、腹をたてない者はなかった。
〈うまくいったわ。いいきみ、いいきみ……。〉
キリアは心のなかでそういうと、クスクスと低い声で笑った。
〈もっとしてやるわ……もっと、もっと。〉
18 一冊のパンフレット top
翌日、キリアはまた、昨日のやぶかげにひそんでいた。
下級生の子供たちは、昨日こわされたレンガを、もう一度積みなおそうとしていた。
しかし、もう誰一人身を入れてやる者はいない。
すきかってに古レンガを積んだりしている。
そのうちの一人の男の子は、何もしないで、ボンヤリしていた。
みんなから離れたところにションボリ座って、みんなのすることを、ボンヤリ眺めているだけだった。
コスタという名の子だった。母親の妹と、二人っきりで暮らしている子である。
父親は戦争で死に、母親の方は、行方がわからない。
キリアは、熱心にコスタの母親の行方をさがしまわった。
何キロも何キロも歩き回って、いろんな人に消息をたずねてみたが、誰からも手がかりが得られなかった。
キリアが、やぶかげからソッとのぞいていると、そのコスタがいかにも悲しそうに泣きだしたのだ。
だが、声をだすまいとして、一生懸命、我慢しているのがよくわかる。
キリアはハッと思いだした。コスタは昨日、だれよりも熱心にレンガ運びをやっていたのだ。
彼がまあ、どんなにうれしそうに、小屋づくりに熱中していたことだったろう……。
キリアは悪かったと思うと、夢中でコスタのそばへとんでいった。
泣いていたコスタは、誰かがやさしく自分を抱いてくれたことに気がついた。
泣いている顔をあげてみると、キリアが自分の顔をのぞきこんでくれていた。
「あっ、キリア!」コスタは低い声でいった。
キリアは敵に村を占領されていたころは、一番村のためにつくしてくれた少女だった。
そして、コスタは、その話を村の大人の人たちから、いつも聞かされていたのである。勇ましいキリア。
「コスタ、がっかりしてはいけないわ。私が、この小屋を上手につくるやりかたを教えてあげるから。
壁がけっしてくずれないようにしてあげるからね。」
キリアは、やさしくコスタにいった。
ほかの子供たちが、二人のところへとんできた。キリアは、子供たちにいった。
「ねえ、みんな、あの学校の建物の壁を利用するのよ。
あの壁を利用して、両側にレンガを積めば、それだけ手間もはぶけるし、丈夫なおうちができてよ。
さあ、レンガを運んできて!」
子供たちは大よろこびで、レンガのかけらをせっせと運び始めた。
「ねえ、どうして、この建物の中を二つに仕切ろうというの?」
キリアが子供たちにたずねた。するとステリオという、元気そうな子が、こたえた。
「僕たち、幼稚園をつくろうとしているんだよ。
一つの部屋は僕たちので、もう一つはお医者の先生のだよ。」
ステリオが先生といったのは、その村から二つほどよその村をこしたさきに住んでいる、今年七十六才になるお医者のことだった。
そのお医者は、ここらの子供たちから、たいそう慕われていたのである。
ステリオは、なお続けていった。
「ねえキリア、それに僕たち、誰にでもわかるように『幼稚園』と『先生の部屋』と書いてはっておきたいんだよ。」
それを聞くとキリアは、きゅうに困ったような顔をした。
この村のどこをさがしても、満足な紙一枚なければ、インキ一瓶なかったのである。
ちゃんとしたペンー本どこにもなかった。キリアが困っていると、きゅうにうしろで声がした。
「私が手をかしてあげるわ。」
キリアは驚いて、振り返ってみた。
「あっ、先生!」
先生が、いつのまにか立っていたのだ。キリアは、ハッとして逃げ出そうとした。
おもわず、やぶかげのほうを見た。が、先生には別におこっている様子なんかは、どこにも見られなかった。
「これは、本当にいい考えだわ! 学校の建物の壁を利用するなんて、よく考えたものね。
さあ、みんな、ちょっと待っててね。すぐに戻ってくるわ。」 |
女の先生はそういうと、いそいで校舎にひっかえしていった。
先生はニコニコしながらすぐに戻ってきた。
「いま調べてきたんだけど、ちょうど紙が一枚残っていたわ。
何か、特別な用のために私がとっておいたのよ。
そしてそれが今、やくにたったわ。あなたがたがつくったこの建物は、本当に大切なものですからね。
キリア、この午後、ススが集められるでしょう?
水をまぜて、インキをつくれますよ。みんなは、鳥の羽をみつけてきてちょうだい。ペンをつくるんだから。」 |
こうして、子供たちの幼稚園の建物はできあがった。
しかし、どこから見ても、家らしくはなかった。
屋根もなければ、戸というものが一つもなかったのだ。
しかし、子供たちは、自分たちの教室ができて大よろこびだった。
もう一つの部屋――年とったお医者さんのためにつくった部屋も、そのお医者さんがわざわざ見にきてくれて、気にいったといってくれたのである。
看板は学校の建物の壁にはりつけてあったが、通る人はみんな読んでくれた。
もっとも字のほうは、ひどくたどたどしく書いてあったのだが――。
その幼稚園の建物ができあがってから三日間というもの、キリアはいつも休み時間には、かならずいってみた。
四日目めことだった。
子供たちが休み時間になって外にでようとしたとき、雨がザーッとふってきた。
子供たちはいそいで看板がわりのはり紙を大切そうにはがすと、キリアにいった。
「キリア、学校へはいろう。ねえ、雨にぬれてしまうから。ねえ、はいろう。」
どの子もキリアのまわりに集ると、キリアを雨にぬらしては大変だというふうに、学校の建物のところに引張っていくと、中におしこんだ。 |

小さな小屋――それでも、うれしいのだ
|
キリアはオズオズと教室の中を見まわした。
もうずっと学校へきていない自分を、誰かが、笑いはしないだろうか、と思ったのだ。
キリアは、きっと誰かが、自分を馬鹿にして笑うだろうと思った。それなのに誰一人笑う者はいない。
みんな自分たちの勉強を熱心に続けている。
先生は、ちょっとキリアに手をふっただけで、授業を続けた。そこでキリアは、そのまま教室に残っていた。
あくる日、小さな子供たちは新しいプランを考えついた。
それはキリアに幼稚園の先生になってもらって、教えてもらったら、というプランだった。
先生にそのことをいうと、すぐに賛成してくれた。
「そりゃ、いい考えだわ。みんなは、字の書いてあるカードをもっているでしょう。
それをもっていって、教えてもらいなさい。」
子供たちがキリアにそのことをいうと、キリアはしばらく考えていたが、
「ええ、やってみるわ。」と、子供たちにこたえた。
あくる日からキリアは、小さい子供たちに字を教え始めた。子供たちは熱心に字を覚えた。
するとすこしして、先生がキリアにこんなことを言い出したのだ。
「キリア、あんた字を教えるのは、とても上手ね。どう、算数も教えてみないこと?
私は大きい子供たちを教えるだけでいっぱいで、とても、小さい子供たちまで手がまわらないのよ。」
とたんにキリアは、真赤になった。自分の不得意な算数を教えるなんて!
そればかりは――とてもとても……。
すると、それを見て、先生がいった。
「これから、毎日、学校がはじまるすこしまえにきてみない。
そしたら私たち二人で、教えることのおさらいができてよ。」
キリアは、きゅうにうれしくなった。
そうだわ、そうしよう! そして、なんでも教えてみよう。
いままで、自分を馬鹿にしてきたみんなに、自分だってできることをみせてやるんだわ……。
できないはずがあるもんか。
キリアは、さっそく、そのあくる日から先生のいうとおり、学校がはじまるまえにいって、先生からいろいろ教わった。
雨ふりの日は、屋根のない幼稚園は休みなので、学校でみんなと一緒に勉強した。
数ヵ月して、生從たちがみんな帰ってしまったあとで、キリアは先生と二人だけ、学校に残っていた。
学校はもう前のようではなかった。黒板もあれば、黒板ふきもあったし、チョークもあった。
鉛筆もあれば、紙もあった。地図も壁にかけてあった。教科書も十冊ほど、そなえつけられていた。
そして、近いうちに机もくることになっていた。
キリアは、先生にいった。
「先生、私は心の底から、先生にお礼をいいたいと思います。」
先生は成績表を開いて、キリアが一番なのだと、いましがた、キリアに教えたのである。
小さい子供たちのなかの一番ではなく、キリアと同じ年ごろの生徒たちのなかでの一番なのである。
「キリア、私にお礼をいうことはないわ。これはみんな、あなたが自分で努力してなったものなんだから。」
「先生、いつか小さい子供たちが、一番はじめに幼稚園の建物をつくろうとしていたとき、あれをこわしたのは、私だったんです……。」
キリアは、長いこと心の重荷になっていた、あのときのことを先生にかくさずにうちあけた。
「私もそうだと思っていたわ。」
「あのころ私は、誰もかれも憎らしく思っていました。お母さんも、友だちも、先生も、みんなをです……。」
「でもあなたは、小さい子供たちだけは、憎んでいなかったのよ。」
先生はそういうと、そばの机がわりの木箱から、一冊のパンフレットを取上げた。
英語で書いてあるパンフレットだった。 先生は、パラパラと、ページをめくると、
「キリア、聞いててね。あんただけじゃないわ。ここにも同じことが書いてあるのよ……。」
先生はそういうと、それをキリアたちが使っている言葉――ギリシア語になおしながら、読み始めた。
「この戰争で、たくさんの少年少女が、大事な役割をつとめたことは、誰でも知っている。
その少年少女たちは、忍耐づよく、工夫をこらし、知恵を働かせ、また大胆に勇気をもって行動した。
行方のわからなくなった親や兄弟を苦心して探し出し、食料を苦心して手にいれ、地下のゲリラ隊の人たちのために、一生懸命働いた。
現在の世界は、そういう少年少女たちのことを、すこしもかまわなくなってしまったようである……。」
キリアは、身うごきもしないで聞いていた。先生は、なおも読みつづける。
「誰も、いまでは、反抗することが当り前のことだと思っている。
人に失礼なことをするのを、なんとも思わなくなり、自尊心とごうまんとが同居している。
多くの場合それらは若い人たちであって、彼らは戦争中、占領軍の命令はどんな命令でもまもらないように教えこまれたのである。
彼らは、反抗するように教えこまれた。
仕事をなまけ、命令にしたがわないことが良いことだといわれ、ほめられたのだ。
彼らは、そのように教えこまれたのである。」
キリアは目に涙を浮かべて、じっと聞いていたが、息をつまらせていった。
「本当にそうでした。私もそのとおりだったのです。
私はしょっちゅう、嘘をつきましたし、物もぬすみました。そして――。」
「ええ、それは、みんな、戦争のせいなのよ、キリア。
でもあなたが、いつも子供たちをかわいがっていたということは、けっして忘れてはいけないわ。」
「先生は、そんな私が今度、先生になりたいというのを助けてくださっているのです。
私は本当に、先生になりたいと思います。先生のような立派な先生には、到底なれないと思いますが――。」
「私なんかより、ずっといい先生になれますとも。」
先生は目をうるましてこたえた。やがて二人は、手をとりあって、学校から帰っていった。
二人が立ち去って誰もいなくなった教室の、机がわりの木箱のうえには、先生がさっき読んでくれたパンフレットがおいてあった。
パンフレットの表紙には、少年少女たちの写真がのっていて、その下には、次のような字が印刷されてあった。
「――ユネスコ発行。」
|

せまくるしく、ぎゅうぎゅうづめの教室でも勉強したい
|

爆撃で教室をなくしたハンガリアの子たちは、青空教室で勉強
|
19 ユネスコの活躍 top
キリアのような少女をはじめ、そのほか何百万という、戦災にあった国の少年少女や幼児や、学校の先生たちを助けることが、ユネスコの緊急な仕事の一つだったのである。
ユネスコは、一九四六年に国際連合の専門機関として発足したもので、ギリシアの少女キリアとその先生にとって、とても重大な意味をもっだあのパンフレットは、ユネスコが最初にだした出版物だったわけである。
たいして厚くもない、簡単なパンフレットだったが、それがそれからのユネスコの仕事のシンボルのような役目をつとめたのである。
ユネスコ――正しくいうと、国際連合教育科学文化機関(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)というのであるが、そのユネスコは、発足すると、すぐに世界中の国々から、教育者、科学者、作家、音楽家などにあつまってもらい、それらの人たちの知識や経験などをいろいろ話しあってもらった。
ユネスコの本部はパリにあるが、その本部からは、使節たちが、世界中の国へ派遣されて、その国の政府の人たちとあって、もっともっと学校や図書館や科学の研究所などをふやすことを、話しあうことにしたのである。
ユネスコの仕事は、実にたくさんの種類に別れている。
というのは、五十九ヵ国の委員たちによって調印されたユネスコの憲章には、こううたってあるからである。
「世界の平和と幸福につくすために、教育、科学、文化などをとおして、世界中の国民の共同研究をすすめること。
それは正義を貴ぶことであり、世界中の人々の人権と基本的自由を護るためでもある。」
そしてその憲章は、有名な次のような文句でむすばれている。
「人種、男女の別、言語、宗教などには、いっさい関係しない。」 |
最初のユネスコの大会は、名高いイギリスの学者で、ユネスコ本部の委員でもあったジュリアン・ハクスレー氏の司会のもとに行われ、事業計画が、いくつも討議されたが、FAO(国際食糧農業機関)やWHO(世界保健機関)の場合と同じように、まず、今度の大戦の戦災国をまっさきに取上げようということが、きめられたのである。 |
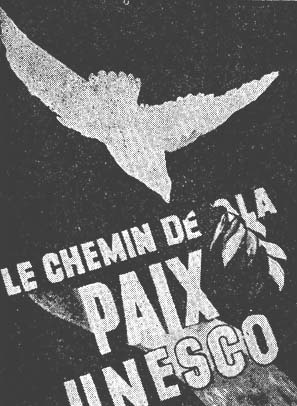
国際コンクールで入賞したユネスコのためのポスター
|
戦災国の政府は、すでに自力で自分たちの国の教育の復興に着手していたところが、多かった。
戦争がすんでからばかりでなく、すでに戦争のさなかの一九四二年ごろからはじまっていた国もあった。
ナチス・ドイツ軍の爆弾が、さかんにふってきている最中、イギリスの都ロンドンでは、連合国がわの文部大臣たちが集って、いろいろ、教育の問題について相談しあっていた。
どんな場合でも、少年少女や児童の教育は、ゆるがせにできない大問題だからである。
戦争がおわると、この問題は、いっそう緊急なものになり、どこの国でも、教育の問題にはすっかり困ってしまった。
ユネスコでは、この問題にすぐのりだし、委員たちをすぐに、次のような国々に派遣することにした。
それらは、オーストリア、ベルギー、ビルマ、中国、チェコ、エチオピア、フランス、ギリシア、イラン、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、フィリピン、ポーランド、ユーゴスラビア、ハンガリー、インド、マルタ、シンガポール、北ボルネオ、サラワクーの合計二十一ヵ国である。
そして、派遣された委員たちは、その国の文部省の役人たちや、学校の先生や職員だちと話しあい、何か目下のところ、一番必要とされているかを、くわしく調査してくるということにきまったのである。
こうして、それらの委員たちのもってきた調査報告をまとめて、ユネスコでは広くその結果を世界中に知らせることになっていた。
しかし、ユネスコの委員の人たちが、戦災国をたずねて調査してからというのでは、遅すぎはしないだろうか。
なにしろ、いまの急場に間に合うものがほしいのである。
ギリシアの片田舎にある少女キリアの学校のように、満足なものは何一つそなわっていない学校もあるのだ。
黒板、チョーク、紙、鉛筆そういうものが送られるまえに、そういう学校で教えている先生たちの心の支えになるものが心要なのではあるまいか。
はげましが心要なのではあるまいか。
その先生たちは、またそういう環境で、自分たちは、こうこういう工夫をして教えているが、ほかの人たちはどうだろうか、――そういうことをお互いに知りたいと、熱望しているにちがいない。
しかしそれは、個人の力などでは、到底できることでない。
そこで、ユネスコは、世界中の先生たちのために、実際に教えている先生たちの、いろいろな意見を集めた本をだすことにしたのである。
それにはまず、材料になるものを集めなければならない。 |

爆撃でこわされた校舎のまえで体操をするギリシアの子たち
|
誰かを、大至急、ある国に送ってその国の先生がたの意見を聞き、またどういう授業をしているのかを調べ、また生徒たちの実状を知らなければならない。
なにしろ、急を要することである。
調べてみると、ギリシアがなかでも一番ひどい戦災をこうむっているし、物も一番不足しているようである。
そこでユネスコでは、ギリシアへさっそく委員を派遣することにした。
その委員には、アメリカの教育者であり、ユネスコの事務局員でもあったレオナード・ケンワーシイ氏が任命された。
ケンワーシイ氏は、ギリシアのアテネに飛行機でとぶと、そこでギリシア人の通訳の人と一緒になり、三週間にわたって、大きな町や村や、山奥まで歩き回って、先生たちと話しあった。
ケンワーシイ氏はどこへいっても、子供たちが学校へいきたがっているのに気がついた。
先生たちはいろいろ工夫して、間に合わせの材料で子供たちを教えていた。
ケンワーシイ氏は、それらのことをくわしくノートにとった。
また、どうしたら、戦災にあった子供たちを、もっと上手に導いていけるだろうかと、彼は会う先生ごとに尋ねられたが、それらのこともくわしくノートに書きつけた。
20 誇りをもって top
ケンワーシイ氏は、パリのユネスコの本部に戻ると、さっそく、本の執筆にかかった。
ユネスコの事務局員たち――教育問題に長い経験のある人たちが、ケンワーシイ氏に協力した。
こうしてその本はできあがり、戦争国の児童たちの実状、そしてその児童たちをどう扱ったらいいか、という問題など、いろいろ取上げられてあった。
その本は「戦災国の教師と戦後の子供」という題がつけられ、記録的といってもいいくらいの短時間で印刷されると、世界中の政府へ送られた。
そして各国の政府から、今度は、の国ののこらずの学校、教師の組合などに配布された。
まえに書いたギリシアの片田舎の女の先生が、少女のキリアに読んで聞かせたのは、そのパンフレットだったのである。
多くの先生たちはこれを読んで、ほかの先生たちの考えがわかり意を強くした。 |

パリのユネスコ本部の建物
|
また、自分の当面している問題が、自分一人の問題でないこともわかって、新しく勇気づけられた。
そのパンフレットには、また、それらにたいして、一つ一つ具体的に解決の方法がのべられてあって、ずいぶん役にたった。
いまでは、戦災にあったヨーロッパの街路にもたくさんの樹木が茂り、人の目を楽しませくれているが、ひと頃はあらかた切って薪(まき)にされ、もやされてしまっていた。
が、そのパンフレットに書かれていたオランダの少年少女たちの話のおかげで、また植えられるようになったのである。
パンフレットには、こう書かれてあった。
「理由の一つは燃料が不足していたことと、それになんでも破壊したい気持のせいで、オランダの建物はあらかたこわされ、バラバラにされ、たきものにされてしまった。
オランダのパーク市をはじめいろいろな町では、学校の生徒たちが先にたって、公園をはじめ街路に木を植える運動を始めた。
子供たちは誰一人、その木にいたずらをして、ひっこぬいたり荒したりはしなかった。
子供たちは、自分たちの手で始めたその運動に、大きな誇りをもっていたからである。」 |
まったく、戦災国の少年少女の働きには、めざましいものがあった。
ユーゴスラビアでは、青少年連盟の会員たちが、道路をなおし運河をつくる仕事に力をつくした。
熟練した技術者たちの指導のもとに働き、彼らは、仕事をすることによって、いろいろ、実地に学ぶことが多かった。
ユーゴの東ボスニア地方にある、二つの炭坑をむすぶ鉄道を建設したときなど、六万二千人のユーゴの青少年たちが、熱心に二ヵ月間働いた。
自分たちの手でつくった小屋に寝泊りし、炊事から洗濯から残らず自分たちの手でやって、彼らは六ヵ月かかってその鉄道を完成したのである。
同時に、鉄道建設につきものの鉄橋を二十二ヵ所にかけ、二千百本の電信・電話線の柱をたてたのである。 |
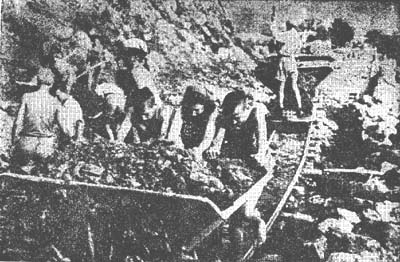
鉄道建設にはたらくユーゴスラビアの十代の少年少女
|
ハンガリーでは同じように、青少年連盟の会員たちが、学校の建設に働いた。
彼らは授業がおわったあとと、週末の休みにかけて、なれた大工さんの指導で、せっせと働いた。
ハンガリーの都ブダペストだけで、そういう青少年のグループは二十四もあり、地方には四百以上もあった。
その連盟にくわわっている少女たちは、学校の道具類をつくった。
少女たちは、通学カバンを一万個、インキ入れを、四千個もつくったのである。
21 イタリアの「少年の村」 top
一九四五年の十二月二十四日――クリスマス・イブの日だった。
小柄なお坊さんのドン・ギド・ビセンダスさんは、イタリアのランチアーノ地方にある、小さな村に着いた。
その村には、戦争で親を失い家を失くした子供たちが、政府の手で集められ、閉じ込められていた。
ほうっておこうものなら、かっぱらいをしたり、盗みをしたり、手のつけられない少年たちばかりだったからである。
背の低いお坊さんのビセンダスさんは、役人たちに向かって、 「私はそういう少年たちを、なんとか助けてやりたいのです。」
そう熱心にいって、少年たちの収容されているサンタ・キアラの、元兵舎だった建物にいって、そこの厩(うまや)の鍵を受取った。ビセンダスさんは、その鍵で厩の戸をあけた。
するととたんに、中にいた少年たちは、「わあっ!」と、いっせいにさわぎたてた。
どの子もボロ服をまとい、体をモソモソさせながら、石の床にふるえながらねころんでいた。彼らは口々に、ビセンダスさんの悪口をいっては、ドッと笑った。 |
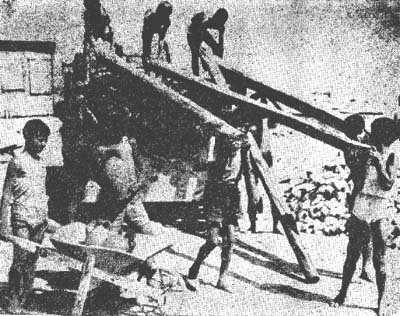
自分たちの村を建設するイタリアの少年たち
|
ドン・ビセンダスさんは、さわぎたてる少年たちをなだめて、一緒に暮らすことにした。
はじめ少年たちは、ビセンダスさんが食べ物や服などをもってきてわけてやっても、あいかわらず馬鹿にすることをやめなかった。
ビセンダスさんが、厩の中の掃除をはじめても、誰一人手伝おうとする者もなかった。
だがビセンダスさんが、こわれた壁を修理し始めたときは、二、三人の少年たちが手伝ってくれた。
でも、ピセンダスさんが、壁を塗替えようと、きれいな色のペンキをもって戻ってきたときは、どの少年も「わあーッ!」と、よろこびの声をはりあげた。
厩はたちまち、少年たちの手できれいに塗替えられ、あちらこちらの壁には、美しい花までが少年たちの手で描かれた。
「おい、ここを俺らの村とよぼうぜ。」
誰かがいいだすと、たちまち、残らずの少年が賛成した。
その「俺らの村」のうわさは、すぐにランチアーノ地方の家のない孤児の少年たちから少年たちへと、伝わっていった。
「俺らも入れてもらおうぜ。」
五つから十八才までの少年・八十名が、その村に入れてくれといって、やってきた。
もちろん、入れてもらうことができた。
こうなると厩だけでは、とても残らず少年たちを収容することはできない。
役所に話して、もと兵舎だった建物のほうも貸してもらわなければならなくなった。
それらの新しい少年たちがくわわったので、たちまち、重大な問題がおこった。
夜になると、近所の家の食料が盗まれるようになったのである。
新しい少年たちに食料を補給してやろうという、善意からでたものかもしれないが、盗むことは何といったって悪いことである。
「せっかくよくなったと思ったのに、また、わるさをはじめやがった。」
町の人たちや村の人たちは、少年たちを悪くいい始めた。
ドン・ビセンダスさんは、さっそく、少年たちを集めていった。
「私は諸君が何をしようと、かれこれいわないつもりだ。
しかしこれからは、諸君はここで起ることについて、何によらず責任をとってもらわなければならない。」
少年たちはそういわれるとすぐに集って、自分たちで掟(おきて)をつくり、法廷をつくった。
そして、自分たちの村の村長をえらびだした。
それからというもの、そういう事件はもう、一つもおこらなくなった。
なにしろ、百人をこえる少年たちの面倒をみなければならないのだから、大変である。
食料だけでも、やりくりするのが、むずかしい。
そこで、困ってしまったドン・ビセンダスさんは、何とかその若境を打開しようと、努力を始めた。
ビセンダスさんのイタリアの友人たちや、ドン・スイシーなどの宗教団体が援助してくれたが、それだけではとてもやっていけない。
そこでビセンダスさんは、「少年の村」の十五才の村長をつれてスイスへいき、「少年の村」の話をして援助をあおぐことにしたのである。
ビセンダスさんが少年たちにそのことを話して、しばらく留守にすることをいうと、すぐに少年たちは会議を開いて、留守のあいだの村長を、選挙できめることにした。
すると、えらばれた少年は、みんなにこう言い出した。
「僕は間違いをいくつもしでかすような気がするので、とても引受けられない。」
それを聞いた少年たちは相談しあって、次のような文句を全員一致でとりきめたのである。
「我々は君が、間違いをしでかしてもいい、ということを認める。」
その少年は、留守のあいだの代理村長の役目を引受け、ドン・ビセンダスさんと少年村長は、スイスに向けて出発した。
ドン・ビセンダスさんと少年の村長のスイス訪問は、大成功だった。
二人が帰ってこないうちに、食料や衣料が、続々と送られてきたのである。
こうしてその助けと、イタリア政府からの援助、それにいろいろな団体からの寄付で、ドン・ピセッダスさんは「少年の村」を続けていくことができた。
ドン・ビセンダスさんは、『少年の村』に学校をつくり、そこでは大工や洋服屋、靴作りなどの職業教育が行われた。
22 「少年の村」から「少年の町」ヘ top
ー九四八年の三月、その「少年の村」に、悪い知らせが届いた。
少年たちが住んでいた兵舎がほかの目的に使われることになり、みんなは立ち退かなければならないことになったのだ。
「さあ、困ったことになったぞ。」
少年たちががっかりしていると、政府ではこのことを知って、彼らに近くの丘の上の土地を提供しようと、いってきた。
そこは青いアドリア海を目の下にした、ながめのよい場所だった。
少年たちの代表者は、その場所を調べてきて、そこに移ることにきめた。
彼らは、そこに新しい家をつくって、今度は「少年の町」とよぶことにしようと、相談しあった。
たくさんの応援者があらわれて、新しい少年の町の建設に寄付をしてくれた。
ドン・スイシー宗教団体は、五むねの組立式の建築材料をおくってくれた。
あるフランス人の建築家は、無料奉仕を申し出た。
ユニセフは、イタリア政府と共同で、余分の食料を補給してくれた。
少年たちは、新しい建物を自分たちの手でつくりあげるのに、懸命だった。
みんな戸外に毛布一枚をしいて、野宿しながら仕事にはげんだ。
彼らはまた、そこの土地を開墾して、ひろい野菜畑をつくった。
とうとう、少年の町はできあがって、彼らはそこへ引き移った。
電灯がひけてなかったが、そんなことは構うことでない。
飲料水も遠くから運んでこなければならないのだったが、それも苦にならなかった。
彼らはふたたび、自分たちの町をもつことができたのである。
23 ユネスコの働き top
ヨーロッパの各国をはじめ、またビルマ、インド、マラヤなどの善意の人々は、今度の戦争で親や家を失くした少年少女たちを集めて、面倒をみてくれていた。
やりかたこそ違っていても、それらの少年少女たちの集りをできるだけ、親身なものにしてやるために、衛生や教育に、じゅうぶんに注意し、また、めいめいが責任をもって行動するように、ということだった。
このような青少年の共同団体は、けっして、新しいものではない。
五十年以上まえにアメリカ人のウイリアム・ジョージという人が、ニューヨークのフリーヴィルというところで始めたもので、それは「ジョージ・少年共和国」というものだった。
戦後、それと同じ計画のもとに、幾人もの人たちの努力のおかげでヨーロッパの各地に、戦災で親を失った子供たちのためのホームができた。
ハンガリーのブダペストやフランスのブリタニーやモーリンヴィユなどに、名高い少年の家がいくつもできたのである。
それらの少年の家や町でくらしている、親に別れた少年少女たちは一つところに集って、お互いの経験を語り、お互いの問題を話しあいたいという希望をいだくようになった。
ユネスコはさっそく、その希望をかなえさせてあげようと、一九四八年の夏、それらの青少年の団体の代表者たちに、スイスのトローゲンにある、ペスタロッチ村に集ってもらうことにしたのだった。
ペスタロッチ村というのは、戦後にできた家のない青少年たちの共同社会で、そこで暮らしている少年少女は、めいめいの国籍にしたがって、別々にグループをつくって生活している。
つまりフランス村というのは家を失くしたフランスの少年少女たちが住み、ドイツ村というのはドイツの少年少女たちが住むといったぐあいである。
これは最初、スイスのチューリヒの教育者ワルテル・コルチ氏が考えついたもので、それがスイスの青少年連盟に取上げられたのだった。
「ペスタロッチ村をつくろう! そして戦争の犠牲者である、家を失い親を失った少年少女たちにきてもらおう!」
青少年連盟のよびかけは、スイス中の人たちの心をゆすぶった。
寄付金が、あとからあとからと送られてきた。
青少年連盟ではその集ったお金で、さっそくペスタロッチ村をつくる土地をさがした。 |

スイスのペスタロッチ少年村
|
その結果、ながめのすばらしくよい、トローゲンという土地が選ばれたのである。
こうしてペスタロッチ村ができたのであるが、ペスタロッチというのは、十八世紀に生まれたスイスの名高い教育者で、その名をとって命名されたわけである。
一九四六年の夏に、ペスタロッチ村には、フランス、ポーランド、オーストリア、ハンガリー、ドイツなどの戦災孤児百十二人がうつってきた。
そしてそれぞれの国籍にしたがって、グループをつくって暮らすようになったのである。
彼らの暮らす建物こそ、別々になっていたが、仕事は共同でやり、娯楽の時間も一緒だった。
お互いの言葉がわからなくても、彼らは、じきに仲良くなり、お互いの国の歌をうたいあうのだった。
また、ペスタロッチ村には、学校もあって、職業教育も行われている。
ところでユネスコが、そのペスタロッチ村で各国の「少年の家」や「少年の町」の代表者たちの集りをひらく、という通知をだすと、六ヵ国の十四人の代表者たちから、出席したいという返事が届いた。
それらの青少年の代表者たちは、いろいろな国から出席した教育者たちと話しあい、すべての国にこういう施設を、もっともっとつくることをすすめようということだった。
そして、このときの集りがきっかけになり、各国の「少年の家」や「少年の町」の青少年たちのあいだに、手紙やプレゼントの心暖まる交歓が行われるようになったのである。
ユネスコはこのように、
① 戦後みだれた数育をやりなおすこと、
② お互いに力をあわせ、助けあっていくこと、
③ 新しい発明をどしどしするようにつとめること、
④ 物の考えかたをお互いに知らせあうこと、 |
などを目標に、世界的な計画をいろいろたてて、熱心に仕事をすすめている。
世界のどこかに災害があると、ユネスコではさっそく物資を送ったり、お金を送ったりして助ける。
また文化の遅れている国には技術者を派遣して、その国の科学や文化の進歩を助けているのである。 |

ユネスコのマーク
|
top
**************************************** |