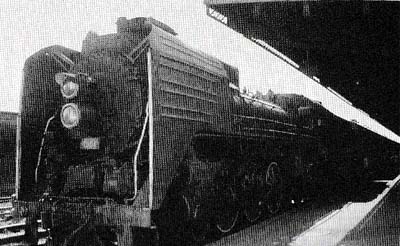|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章
四章 長春行き列車からの手紙
|
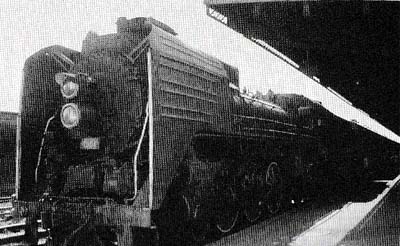
ハルビン→長春行き列車
中国の列車は、軟座(なんざ)車と硬座(こうざ)車とで編成されています。
読んで字のごとしで、ほんの二両ほど連結された軟座車は、日本のグリーン車といったところでしょうか。
常に超満員の硬座車と比べ、座席も広くゆったりしているのですが、駅の待合室までが双方の客用に分かれているのには驚きました。
ハルビン駅の一般待合室は、ばかでかい倉庫を思わせる空間で、ぎっしりとひしめいた人で座る場所もないばかりの混雑ぶりに加え、何ともいえない臭気が鼻につきます。 |

東北烈士記念館、2階入口の烈士像と案内人
|
その奥の貴賓室めいた待合室は、椅子もソファーで、少々うしろめいた感じでしたが、それはどの待ち時間もなく、通訳氏の案内でホームに出ました。
ホームもまた、大変な雑踏です。
かって満州時代には、このあたりに大勢の苦力(クリー)が日本人監督の元にこき使われていたのだろうと、暇があると当時の本を読んでいるせいか、そんな想像が胸をかすめます。
苦力とは、日本人が称しか中国人労務者のことで、荷の上げおろしとか、貨物の詰めかえなどの重労慟にたずさわっていたはず。
苦力の文字同様に、いつも苦しい力をしぼられていたのにちがいありません。
幻の満州国とともに遠い昔のこととなりましたが、ホームで見かける機関車は、黒々とした巨人のようなSLで、その風景自体は、当時とあまり大差ないように思われます。
ハルビンを後に、私はこれから長春へ向かうのです。
「SLを見ると、なんだか少年の日に戻ったような、ノスタルジックな感じになりましてね」
列車の窓から外を見ながら、私は通訳氏にそういいました。先生は機関車がお好きですね、と彼が声をかけてくれたからです。
旅の全行程についてくれる彼は、いかにも人のよさそうな国際旅行社の青年です。
「こちらでは、まだSLが主力です。もっとも、私たちの列車はディーゼルですけど、少し残念ですか?」
「いえ、乗っている分には、同じですから」
「これでハルビンともお別れですが、いかがでしたか、印象は……」
「そうですね。いろいろ考えることがたくさんあって、まだ、ちゃんと整理ができていないのです。
ただ、これまで思いこんできたこととは、ずいぶんちがうんだと……」
「どういうことですか?」
「中国の東北部、わけてもハルビンというと、すぐ連想されるのはやはり戦争末期の、あのソ連の参戦、それから肉親探しに来日するいわゆる残留孤児(ざんりゅうこじ)の悲劇……などが主力になってしまうんですね。
でも、それは、こちらの人にとっては、おそらく不本意なことなんですよね。
だって、悲劇が前面に出てしまって、日本のしでかした加害面がかすんでしまう。
いま、そんなことを考えていたのです」
列車が動き出すと、赤い頬をした若い女性の服務員さんが、かいがいしく熱いお茶のサービスにまわります。
大きな、たっぷりとした蓋つきの湯飲みは、いつまでたってもお茶がさめず、表面に浮いている葉茶をふーふーと吹きながら飲むのは、何とも落着いた感じ。悪くありません。
「七三一部隊は、私もショックでした……」
お茶を飲みながら、向い合った席で、通訳氏が、正直な感想を口にしました。
「あすこを訪ねたのは、はじめてでしたから」
「え? はじめてなのですか」
「はい、先生のおかげで、いい勉強をさせてもらいました」
駅頭で別れた現地のママさん通訳さんは、さすがに年齢のせいか、七三一部隊の輪郭をよくガイドしてくれましたが、平房初訪問の彼は私同様の、いや、それ以上の衝撃を受けたかのようです。
それから少し、七三一部隊をめぐっての、お互いの意見の交換となりました。
「部隊の幹部は軍医とはいうものの、医学者とか医者とか、つまり人命救助の責任を持つ優秀な科学者ですよね。
そういう方たちが、なぜ、人殺しのための細菌兵器なんかを開発したのか。考えれば考えるほど、頭が痛くなります」
というのが、彼の最大の疑問点。
「ぼくも、あれからずっと考えていて、まだよくまとまらないのですが、ただね、あなたの疑問は平和時の発想ではないのかな。 平和を土台にしてなら、ほとんどの方が人間らしいものの考え方をするものですよ」
「はあ、そういうものですか……」
「ところが、戦争ともなれば、そうはいかない。
だって、敵を一人でも多く殺傷しようという目的が、大前提にありますものね。
しかもその本質は、日本の場合、よその国をぶん取ろうという侵略戦争でした。
元々人間的であろうはずなんかありません」
「戦争を仕掛けた側に、人間らしさを求めるほうが無理なんだ、ということですか」
「そう思いますね。ですから、彼らも軍医として、自分も功績を上げ、お国のためにつくそうと考えたんじゃないかと思う」
「しかし、七三一部隊がやったところの生体実験は、正直いって、私たちの想像をはるかに超えるものがありました。ただただ、オドロきです」
「いや、それは、ぼくも同じだな。ずいぶん本では読んできたつもりだけど、やはり、こたえましたよ」
「ですからね、その場合、医師としての矛盾を感じなかったのか、どうか……です」
「矛盾はなかったはずはないけれど、世はすべて戦争美化の情報だらけで、やがてだんだんと慣れて、矛盾に不感症になっていったんじゃないでしょうか。
生体実験の捕虜たちに対しても、どうせ死んでいく運命なんだから、細菌戦のためにふるに役立ってもらおう、と」
「それも、みな、お国のために……の大前提ですか」
「ええ。だから、より人間的になろうというよりも、時代の要請を先取りする科学者のほうにひかれていったんじゃないのかな」
「すると、慣れって、いいことばかりじゃないんですね、先生」
「そうだと思う。人間って、慣れてしまっては悪いことにまで慣らされていっちゃうんですよね。
日本人の場合、長いものには巻かれろ式に、特にそうした面が強いんじゃないかと、これは、ぼく自身への反省というか警告ですがね」
「なるほど、なるほど……」
『それにしても、七三一部隊といえば、これまたすぐに思いうかぶのは、話に出たところの生体実験の数々で、日本人の中には、ともすると残酷モノ的な見方をしていた人も、少なくなかったように思います。
今度の取材で、ぼくが驚いたのは、部隊による被害はその時だけのものではなかった、ということ。
後遺症も実に深刻なものですよね」
「あ、証言者のなかの靖さん。ペストで、家族一二人を亡くしてしまった……」
「ええ。とても、つらいお話でした。いとしい身内を一人亡くしただけでも、大変なことだというのに」
「周辺地区で、一〇〇人以上のペストの犠牲者を出してしまった、と、韓館長さんのお話でしたね」
「あれは、部隊にもっとも近かったという三つの村にかぎっての死者数ではないんでしょうか。
私が鞄に入れてきたた中国の資料によれば、ハルビン地区でペストにより、二万三〇〇〇人の死者が――と」
「え? そんな数字がありますか。わが国の図書で?」
湯飲みをスタンド式のテーブルに押しやった通訳氏が、大きく目を見張り、身を乗り出してきました。
七三一部隊の関連資料は、彼にも見てもらう必要があるかもしれません。
お国柄はちがうとはいえ、やはり、戦争を知らない世代の一人なのですから。
劉恵吾(りゅうけいご)、劉学照(りゅうがくしょう)・主編『中国から見た日本近代史』(横山宏章訳、早稲田大学出版部)は、日本の中国侵略を直接的に体験してない中国青年に向けてまとめられた日本史テキストだそうですが、七三一部隊について、次のようにしるされています。
「日本の細菌工場で“試験”のため惨めにも殺害された中国人は毎年六〇〇余人に達し、一九四〇年から一九四五年の五年間に、こうして殺された人は三〇〇〇人を数える。
また一九四五年、日本が降伏したときには、犯罪証拠を消滅するため、ハルビンの平房では、生きていた数百の中国人を全員殺害し、屍体を焼き捨てた。
日本軍がこの細菌工場を爆破したときには、多数のペスト菌をもったネズミが逃げ出したため、ハルビン地区にはペストがはびこり、二万三〇〇〇人の死亡者が出た。
こうした東北四省における日本の犯罪行為は、筆舌に尽くしがたい」 |
通訳氏はこれまでになく真剣な表情で、その数字を手帳にメモしていましたが、残念ながらこの本の記述に関するかぎり、ペストによる死亡者二万三〇〇〇人の根拠は、明らかではありません。
陳列館の韓館長に質問して、確かめてくればよかったのですが、あとの祭りで、大事なことは後になってから気がつくものです。
それにもう一つ、同書の記述では、七一三部隊の撤去の際に多量のペスト鼠が「逃げ出した」とあって、直接の体験者や韓館長の説明とのくいちがいがあります。
鼠が自発的に逃げ出したのか、それとも逃げ出すようにしむけられたものなのか……。
結果としてハルビン地区で、二万人を上まわる犠牲者が出たとは、読み捨てにできないくだりです。
これから行く長春でも、同じような後遺症がありました。
七三一の姉妹部隊ともいうべき関東軍軍馬防疫廠第一〇〇部隊で、こちらは主として馬や牛、羊などの家畜用細菌兵器の開発でしたが、やはりコレラ菌によって、多くの犠牲者が出たといわれています。
「飛ぶ鳥あとをにごさず」、ではなくて、「あとは野となれ山となれ」の置き土産も、またメモする必要がありましょう。
しかし、ハルビンでは、そうした日本の侵略に決して頭を垂れることなく、勇敢にたたかった人たちがいたのを確認できました。
そして、その人たちに対する日本側の通称は匪賊だった、と私は遅ればせながら気づいたのです。
賊というと、少年の日のイメージで、つい山賊とか海賊、盗賊などとなり、それに準じた匪賊が私の心に色濃く焼きついたのは、いつ頃からだったか。
一つのきっかけは、どうやらあの歌「討匪行」(とうひこう)からです。
どこまでつづく ぬかるみぞ
三日二夜を 食もなく
雨ふりしぶく 鉄兜(てつかぶと) |
テナー歌手藤原義江のヒット作「討匪行」は、そこはかとない悲壮感が売りもので、私の兄たちの世代によく歌われていました。
おかげで、満州には馬賊や盗賊が付きもののように思いこみ、私のなかでもそれが長く尾を引いていました。
もちろん、一部には本物の盗賊もいたのでしょうが、しかし匪賊たち暴徒たちのほとんどが、実は「政治匪」「共匪」といわれる反満抗日の愛国者たちであったとは……!
いかなる困難な状況にも、決して慣らされることなく、長いものに巻かれなかった人たちのことも、この手紙にしるしておくべきかもしれません。
|

日本軍とたたかった英雄たちの展示はつづく
ハルビンの東北烈士(れっし=英雄)記念館は、市街の中心地ともいうべき一曼街(いちまんがい)三号にあります。
七三一部隊の平房を訪ねたあと、私はめったになく疲労困憊(こんぱい)していましたが、それこそわが身をムチ打つような気持で足を向けました。 |

東北烈士記念館正面。
旧関東軍特務機関の本拠となっていた
|
この記念館は、はるかな昔、市の「万国図書館」でしたが、やがて日本軍のハルビン占領からは、関東軍特務機関の本拠となり、数多くの反満抗日ゲリラの戦士たちが連行されて、残虐な拷問で殺されていったところ。
それらの烈士たちをしのぶ展示の内容は、二つのパートになっていました。
東北地方での抗日戦争関係と、その後の解放戦争(蒋介石軍との戦い)とで、計二二九名の烈士たちの足跡(そくせき)が、約千点からの写真や遺品で展示されているのです。
七三一部隊の跡も、日本人として見るのはいたたまれぬものがあったけれど、烈士記念館もまた圧倒される感じです。
かって日本が掲げた「五族協和」「王道楽土」の満州国がどのようなものであったのかが、中国側からの視点で妥協の余地なくきびしく告発されているからです。
ふだんは、自分が日本人だなどと意識することは皆無といっていいのに、今度の旅は、何度そのことを考えさせられるのだろう。
しかも、やりきれぬ痛恨とともに。
私は、ここにその悲劇的な足跡をとどめた人たちのことを、一人ひとり、深く心に残さなければいけないのだ、と思いながら見て行きました。
楊靖宇(ようせいう)――東北抗日連軍第一軍長。濠江県保安村で日本軍討伐隊に包囲され、たった一人となって激戦の末に戦死。
討伐隊によって解剖された彼の胃からは、一粒の穀類もなく、草と木の皮しかなかったという。
一九四〇年二月二三日没、三五歳。
八女投江――東北抗日連軍五軍婦女団の女性八名。五常県内の鳥斯浦河(牡丹江支流)で、日本軍討伐隊と激戦。
すべての弾丸を打ちつくして、捕虜になるよりはと激流に身を投じて死んだ。
八女とは冷雲、楊貴珍、安順福、胡秀芝、郭桂琴、黄桂清、王恵民、李鳳善、一九三八年一一月のこと。
緑川英子――長谷川テルのこと。
エスペランチストとして、抗日の戦列に参加、一九三八年武漢で、さらに重慶で、対日広報活動をおこなう。
日本軍兵士に対して、「あなた達はなぜ無駄な血を流すのですか。あなた達の敵は、海を越えたこちら側にはいないのです」と。
烈士のなかの、ただ一人の日本女性。
重苦しい空気の室内で、まさか、日本女性にお目にかかるうとは思いませんでした。
しかし、なかには、涙なしには到底、立ち去ることのできない烈士もいました。
「抗日女英雄」趙一憂(ちょういちまん)が、その人です。
「一九〇五年、彼女は四川省の地主の娘として生まれました……」
ガイドさんの説明を聞きながら、私はその人を見つめました。
一歳くらいの坊やを抱いた女性は、背もたれの大きな藤椅子に座っています。
やや細面で、目鼻立ちのととのった表情は、彼女の恵まれた生いたちと生活を裏づけているかのよう。
一九三一年、関東軍の謀略による九・一八事変(満州事変)のあと、趙一憂は東北入りをし、反満抗日ゲリラ部隊に加わりました。
そして、すぐに東北人民革命軍(後の東北抗日連軍)第三軍第二師団の政治委員になったとのことで、女性にもかかわらず、遊撃戦でも相当な能力があったものと思われます。
戦闘中、重傷の身で捕えられ、おそろしい拷問を受けたが、一言も口を割ることなく、病院に移されたとのこと。
しかし、入院中に看護婦を味方にして、脱走。またまた捕えられて、ついに銃殺刑に。
一九三六年八月二日、三一歳の短い生涯を閉じた――とは、ガイドさんの説明によるものです。
「ジャオ・イーマン(趙一憂=中国音で)が、処刑前に、最後の手紙を、わが子あてに書きました。ごらんください」
女性のガイドさんは、このコーナーではいつもそうなのか、涙にむせんだ声で、母子の写真に添えられた横書きの文書を示しました。
それが、趙一憂の遺書なのです。
「何と書いてあるのですか。ゆっくりと、読んでくださいませんか」
「はい、そうします。では……」
私は、かなり正確に、遺書の全文をメモにうつしとりました。 |

「抗日女英雄」超一曼の胸像
|
寧(ねい)ちゃんへ。
お母さんは、あなたの教育上のお世話ができないのを、とても心苦しく思います。
お母さんはね、命をかけて反満抗日の戦いに力をつくしてきましたが、悲しいことにまもなく処刑されようとしています。
お母さんは、もう二度と、あなたに会うことはできません。
私のいとしい寧ちゃん――すくすくと、成長してくださいね。私はあの世から、両手を合わせてお祈りしています。
私の、何よりも愛する息子よ。
お母さんは、たくさんの言葉で、あなたを教えることはできなかったけれど、私の生きてきた道筋そのものが、あなたへのささやかな贈りものなのですよ。
そして大きくなってからも、母親が祖国のために命を捧げたことを、忘れないでちょうだいね。
一九三六年八月二日 |
メモを開いて読み返すたびごとに、胸の底から込み上げてくるものを抑えることがきません。
趙一憂は、まだいたいげな幼児の母親なのです。
しかも、地主の娘として特に不自由することのない生活が保障されていたのですから、できることなら、わが子と一緒におだやかな日々を過したかったことでしょう。
にもかかわらず、一人っ子を留守家庭に残してまで、あえて危険な道に踏みこまなければならなかったのは、なぜか?
ガイドさんの説明から、そこまでは理解できませんでしたが、単に個人的な勇気というよりも、彼女の目から見て、日本軍の侵略が黙認できぬばかりに残虐だったからではないのでしょうか。
趙一憂の人柄は、わが子に寄せた遺書の短な文面に、あますところなく伝えられています。
烈士というよりも、母親のあふれんばかりの愛情がたっぷりとにじんだ文章は、最後に、大きくなっても私のことを忘れないでの一行で結ばれています。
いまわの際の、せつない心情が読みとれるかのようです。
あとで通訳氏から聞きましたが、東北烈士記念館前の大通りは、趙一憂にちなんで、一憂街(イーマンチェ)と名づけられ、その北側の通りは、胃袋に草と木の皮だけを残して死んだ楊靖宇にちなんで、靖宇街(チンユーチェ)と呼ばれているとのこと。
そうと知ったら、どちらの通りも、もう少しゆっくりと歩いてみるべきでした。
しかし、烈士記念館には、背筋がうそ寒くなるようなものも展示してありました。
七三一部隊の遺留品です。
細菌用の陶製爆弾だけがやや大きめのほかは、どれも廃品回収にでも出そうなものばかりで、細菌を倍養する寒天容器とか、ペストノミを繁殖させるための籠、大小の乳鉢とか、金属性のへこんだフラスコとか、何とも薄汚なく、見すぼらしいものばかり。
七三一部隊で、細菌兵器の研究開発に従事していた幹部たちは、若い通訳氏にいわせるならば「人命救助の責任を持つ優秀な科学者」であったわけですが、趙一憂が母親ながら選んだ生きかたとは、ずいぶん大きなちがいがあります。に生同時代きた人間同士でありながら。……
双方の人生の極端な距離は、一体どこにあったのだろう。
侵略する側と、される側と、二股の道は左右に無限大といっていいばかりに開いていったのではないのでしょうか。
前者の道に押し流されていった人たちの言いわけに、上官の命令はすなわち朕(天皇)の命令だったのだから仕方なかったという声があります。
むろん、それはわからないわけではないけれど、しかし、いかなる状況にも屈せず、流されず、自分の信じる道をひたむきに切り開いていった人もいるのです。
たとえば、エスペランチストの烈士、長谷川テルのように。――
列車は休みなく走り続けて、車窓の風景は、さっきからずっと広大な平原ばかり。
どこまで走っても、そしていつ見ても、ほとんど大差のない緑の風景で、それがはるかな地平線までつらなっているのは、いかにも大陸の感じです。
ハルビンから長春までの移動は、私にとって、考えることのみ多かりきの旅となりました。
top
**************************************** |