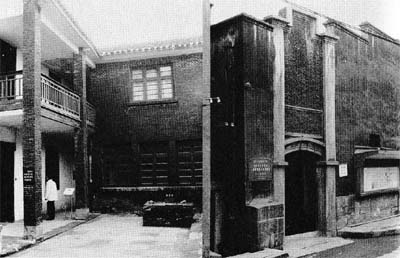|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章
三章 霧の街での手紙
「川面(かわも)に、白く濛々と霧がはっていたが、彼女は、霧かいつ深くなったのかも気づかなかった。
いまや霧のにおいがする、あの、窒息させ、肺腑を腐らすようなにおいが。
夜は白味を帯びはじめ、霧はひろがって岸へあがってきた。
霧が彼女をつつむ。彼女には、彼のほかだれもみえなかった。
あの一組の若い男女は、とっくに霧にのまれてしまっていた……」
なんと、ロマンチックな描写であることか。これは抗戦末期の重慶を舞台にした小説 『寒夜』(かんや=常石茂訳、平凡社)で、作家巴金(はきん)の代表作です。
それぞれの恋人たちが、まことに都合よくたちまちにしてミルク色のベールに包まれてしまう霧の街・重慶に、私はやっとのことたどりつきました。
東京を発って、上海、成都を経由し、乗りつぎの時間に少しは町を散策したものの、なんと三日を要したことになります。
ついに来た……という実感がありました。
飛行機も飛ばぬこんな時期に、春過ぎからの三峡下り(重慶から武漢への長江遊覧)のほか観光地とはいえない重慶へ、はるばるやってくる客はいないのか、大ホテルはがらがらで、商用の日本人と西洋人が計四、五人ほど。
町へ出ると、全くといっていいほど外国人の姿がありません。
中国の大都市は、どこでも金をふんだんに使う日本人観光客で溢れているというのに、重慶はなんと不思議な街でしょうか。
しかし、重慶は、実は大都市なのです。
市の人口は千四〇〇万人(市内三〇〇万人、郊外は一千万余り)で、北京市の九四〇万人、あれほど人が多すぎると舌を巻いた上海市千二〇〇万人を抜いて、中国一の超過密都市です。
ということは、都市人口では世界のトップ・レベルに入ります。
そんなにたくさんの人たちが、たがいに肩を寄せ合い、ひしめき合っている町の一月一日の風情はどんな具合なのでしょうか。
まさか、着いたとたんから戦争関係の取材というわけにもいかず、私は食事のあと、一休みしてすぐ町へ出発です。
こちらではたった一日だけの休日という元旦は、幸いにして雨はまぬがれたものの、うわさにたがわず町全体がどんよりと曇りがちで、太陽はどとこにあるのか、ちらっとも見ることができません。
老眼鏡をかけたまま歩くのと同じで、手元はよく見えるけれど、ほんの少し先は、ぼうっとかすんでしまう。
「ですからね、この町は、女の人たちにとても喜ばれるのです」
とは、ガイドの通訳さんの話。
出かけていく町ごとに、男性やら女性やら、いろいろなタイプの案内役がついてくれます。
「え? それは、なぜ」と、ききますと、
「だって、アラが見えませんから」
「あ、なるほど……」
私は笑いながら、霧の中にそれぞれの力ツプルが消えていくという小説『寒夜』を、改(あらた)めて思い出したことでした。
一年のうちの三分の一は深い霧におおわれる重慶は、長江と嘉陵江の二大河川が合流するところに、さながら恐竜が首をもたげたような形で位置する山あいの都市です。
ガイドブックによれば、市の西側のもっとも高い場所は海抜三八〇メートル、一番低いところは東のはずれ、埠頭(ふとう)のある朝天(ちょうてん)門で一六〇メートル。
従って、その落差は二〇〇メートル以上、当然ながら半島形の町は、中心地の高所から南北の二大河川に向かって、だんだん畠以上の急傾斜になっています。
「霧都」が、「山城」と呼ばれるゆえんなのでしょう。
町に入ってみて気がついたことですが、ここは中国の都市のなかで、独特の風情があります。
どこの町でもおなじみの風物だったあの自転車の波を、全く見ることができません。
坂と階段ばかりの町では、自転車はなんの役にも立たず、必要なのはバイクですが、人力ならぬ動力となったらまだまだぜいたく品らしく、町の中心地に入るにつれて、籠(かご)やら天秤棒(てんびんぼう)を持った人が多くなりました。
荷物は籠に入れて肩にしょっていくのが、もっとも手っ取り早く、天秤棒も、きわめて素朴なテコ原理の日常化です。
港や駅のみならず急坂と階段には、佐々木小次郎の長刀みたいに天秤棒を背にした男が群らがっていましたが、要するにポーター役。
大荷物持参の客を待っているらしい。
いつか、きっと仕事にありつけるだろうと、みんなくわえ煙草で話し合いながら、いかにものんびりした感じ。
旧市街は丘陵にへばりついたように入りくみ、あちこちに、ややこしく古びた石段がくねっています。
通りから一歩人って、石段を降りたら、どこからどこへ通じるのやら、通路の上にありあわせの屋根をつけたような家もあって、両側に軒をつらね合わせた家並が、びっしりと。
かって私か幼い日を過した東京下町のトウモロコシ長屋に似て、ありあわせの材料で囲ったみたいな家が、なんと多いことでしょうか。
屋根材なんかも、トタンより、ルーフィングめいたものが見られよしたが、下町の家屋とちがうのは、お国柄で竹がふんだんに使用されていることです。
もちろん新しい集合住宅群が丘の上のつんのめりそうな空間に屹立(きつりつ)していたり、また建設中のもあったけれど、丘陵にかさぶたみたいにしがみついた住宅群は、木と竹と土による住宅がほとんどで、おそらく抗戦中と大差ないように思われます。
これでは、日本軍機の熾烈(しれつ)をきわめた猛爆に、ひとたまりもなかったにちがいない。
消防設備はせいぜい手押しポンプくらいで、それさえも急坂や階段では動きがとれぬはず。
しかも水道管が破壊されれば、かんじんの水は思うにまかせず、あちこちに火の手が上がると、迷路みたいな小路に逃げ場所さえありません。
年寄りや幼児は、火煙の渦巻く燃えやすい家や、石段で、どんな運命をたどったのだろう……などと考えながら、古い家並の間の路地をたどって行きますと、通りすがりにちらと目に入るだけでも、家のなかはすべて丸見えです。
ということは、どの家も、ほとんど奥行きがないからで、ペット一つに、小さな食卓と椅子くらいなもの。
家族がどれだけいても、みな寄り添って一つペットで休むのでしょうか。
上海の一人当りの住宅面積がわずか六平方メートルとききましたが、ここはもっとひどく、私はなんだか四十余年もの戦後の歳月をタイム・スリップして、日本軍による爆撃直後の町にさまよいこんだような錯覚に、頭がおかしくなるのでした。
|

民家の屋根越しに見える長江(揚子江)
|

朝天門から長江上流をのぞむ
|
かって東京の下町も、B29によって一望見渡すかぎりの焦土と化し、戦後しばらくの間、焼跡にトタン張りのバラックや壕舎に住む人がいたものですが、いまとなっては、そんな住居は皆無といえましょう。
なのに、重慶の庶民の中には、まだ当時と大差ない暮らしがつづいている。
これを、どう考えたらよいのだろう。
そんな思いをめぐらしながら歩いているうち、いつのまにか古い家並を抜けて、長江と嘉陵江の交差する市街地の突端へ来てしまいました。
「朝天門埠頭です」と、通訳さんの説明です。
小高い丘の見晴台に立つと、右に長江が、左に嘉陵江がたっぶりとした水量で交錯し、眼の中にまでひたひたと迫ってくるかのよう。
さすが水運の要衝だけのことはあります。
大小無数の船がひっきりなしに出入りし、桟橋(さんばし)には三峡下り用かと思える大型観光船が横付けになって、汽笛が鳴ったり、歓送迎の爆竹がはじけたり、とてもにぎやかです。
埠頭からの石段は例の籠や天秤棒による荷物運び人の往来も激しく、見晴台につづく広場は自由市場です。
水上輸送で運ばれてきた品物を始めとして、おりとあらゆるものが、雑踏の中にごった返しています。
よく一杯飲屋に正体不明のごった煮があるけれど、少々怪しげなものが入っていてもそれもまた庶民の味で、市場に群らがる人たちの活気といったら、すさまじいばかり。フーテンの寅さんよろしく、品物の口上をまくし立てるのもいれば、それを値切るのもいて、ささいな買物一つでも、熱気と活気でむんむんするような人いきれ。
戦時中の中国は、食物に胡麻をまいたようにハエがたかったものだときいたことがありますが、それは昔の語り草です。
いまでは考えられません。
しかし、ぼんやり突っ立っていると、はじきとばされそうで、私はいつのまにか戦後の燒跡につづく闇市を思い出していました。
やっとのこと平和を手にしたものの、あの頃は、みんな生きることに目の色を変えていました。
生きるためには食わねばならず、その食物を手に入れるのが一苦労で、おのずと生活や労働との人間の直接的なふれ合いが生じ、そこから戦後の道を出発したはずだったのに、一体どこで道を踏みちがえてしまったのか、と考えさせられること、しきり……。
町の中心地は、恐竜がぐいと首をもたげたような地形の、ちょうど目玉あたりに位置する人民解放碑のある交差点。
解放碑を基点にして北東へ延びる民族路、南西へ向かう民権路、その大通りに交わる鄒容(すうよう)路あたりが、もっともにぎやかな繁華街です。
休日とあって、郊外や地方からのおのぼりさんや買物客も相当数いるにちがいなく、それでなくてさえ人口密度の過密な町が、ものすごい人波でいまにも押しつぶされそうな大にぎわい。
交差点に重慶百貨商店をはじめ、軍林市場にありとあらゆる商店、レストラン、飲食店、みな黒山の人だかりで、身動きもつかぬ喧騒です。
|
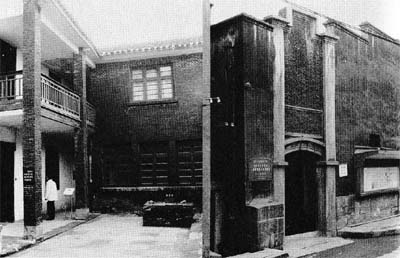
「周公館」の中庭(左)と玄門(右)。
|

その中庭には爆撃をさけるための防空壕がつくられていた。
防空壕の入口で著者(左)。周恩来の執務室(右)
|
いまにももみくちやにされそうで、これはとてもたまらんわいと繁華街から抜け出し、町の北西にあたる中山四路の革命遺跡を訪ねてみました。
曽家岩(そががん)五〇号という妙な名の記念館は、別名「周公館」で知られています。
後に総理となった周恩来(しゅうおんらい)の住居だったところ。
重慶は国民政府の臨時首都でしたが、抗日民族統一戦線のための国共合作の町でもありました。
様々ないきさつはあったものの、国民党と共産党とがここで名目上は手を握って、日本とたたかっていたわけです。
ために共産党も重慶に代表部をかまえ、それが中国共産党中央南方局と八路軍(はちろぐん)重慶事務所で、周恩来をはじめとして、董必武(とうひっぶ)、郵穎超(とぅてんちょう)らの幹部が駐在していました。
国民党と共産党は、抗日戦争のためさしあたりは手を結んでいたものの、その以前も抗日戦争後も仇敵になるわけですから(このあたりはほかの本にゆずりますが)、周恩来らにとっては敵本陣に乗りこんできた交渉団と同じです。
監視はもちろんのこと、スパイやテロリストの暗躍にも注意をはらわねばならず、気の休まる時はなかったにちがいない。
その上、さらに日本軍機による連続波状的な集中爆撃があるわけで、「周公館」の中庭に掘られた防空壕は、さながらピアノ線のように張りつめた緊張の日々を、静かに物語っているかのようでした。
当時の共産党代表部と八路軍の合同事務所は、「周公館」から車で三〇分ばかり、嘉陵江畔の紅岩(こうがん)村一三号にあって、木造三階建ての建物とその周辺が「紅岩革命記念館」となっています。
ここにもまた庭の片隅に木製扉つきの防空壕が保存されていて、どこへ行ってもついてまわる、と苦笑せざるをえません。
日本軍の無差別爆撃は、それほどまでに罪深い犯罪行為だったといえましょう。
しかし、防空壕といえば、それまで見たのと格段にちがってコンクリート製の通路から室内まで、きわめて堅固に作られ、ためにおそらく戦後取り壊すこともできずに、こんにちにまで残された壕がありました。
ほぽ原型のままの、蒋介石の専用壕です。
国民政府の主席だった蒋介石は、重慶にくるとすぐ日本軍の猛爆と夏の猛暑を逃れて、長江南岸に面した南山に、作戦本部を移しました。
いま、南山公園となっているところ。
海抜四〇〇~七〇〇メートルにおよぶ五つの峰から成り立つ丘陵で、その峰の一つの黄山に、当時の蒋主席の別荘がありました。
市内から長江大橋をわたって南岸区に入り、小高い山を登っていった先です。
車を捨てて、さらに小道をまわっていきますと、苔の生えた石の段がうねうねとつづく山頂に、二階建ての古めかしい建物がありました。
いかにも風格のある造作です。「雲岫亭」(うんしゅてい)と呼ばれ、蒋介石の居室ならびに作戦本部だったところ。
作戦本部がある以上、森林のあちこちに国民党高官の住居や、連合国を代表するアメリカ、イギリス、オランダ、ベルギーなどの大使住居がありました。
けれども、いまは全く人々の関心の外にあるらしく、「雲岫亭」は国のものとなって、民間の三家族に貸しているとか。
あたりは、ひっそりと静まりかえっています。
雑草の茂るにまかせたままの樹海の先に、アメリカ特吏マーシャルのいたという別荘の屋根がちらと見えたけれど、狂犬が住みついているので、近寄らぬほうがいいとの話。
蒋介石のいた住居の台所には、いざというときのために、地下の防空壕への抜け道ができていて、もう抜け道はふさいでしまっだけれど、壕はいまも残されているという。
|

道路のいたるところに、防空壕の入口をみることができた
|

防空壕の入口
|
山の中腹にまわって、雑草をかきわけながらたどりついた防空壕は、これは壕という単純なものではなく、迷路のように通路が入りくんだ奥行きある防空洞でしたが、懐中電燈の照明に浮かび上ったコンクリートの肌は冷たく、あちこちに蜘蛛の巣だらけ。
強者どもの夢のあとがしのばれて、半世紀ほどの歳月が、一瞬の風となって通り過ぎたかのようでした。
話を少し元に戻しますが、蒋介石が初重慶入りをしたのは、一九三八年十二月のこと。
日本軍によって首都・南京が陥落したのは前年の十二月十三日で、それより早く蒋介石と国民政府は長江沿いに武漢へ逃れ、武漢がさらに危なくなって重慶へと移ったのです。
こうして、重慶が国民政府の「陪都」(ばいと)と定められました。臨時の首都ということです。
南京が陥落すれば、まちがいなく白旗を上げてくるとばかり信じた日本軍の思惑ははずれ、なんとしても蒋政権と同時に国民の戦意をつぶさなければ……と、日本軍は武漢三鎮(武昌=ぶしよう・漢口=かんこう・漢陽=かんようの三都市)攻略に乗り出し、甚大な犠牲と引きかえに一九三八年十月、武漢を落としました。
しかし、蒋介石と国民政府が遷都(せんと)した重慶は、その武漢から長江沿いにさらに八〇〇キロも奥地にありました。
さすがの日本軍も、重慶攻略はできない相談です。
四川省の標高三千メートルものけわしい山岳地帯が大きな障害となり、それでは長江沿いに攻めのぽろうとすれば、いわゆる三峡の極端に狭くなる水域と激流にはばまれてしまう。
大船団による侵攻作戦は、これまた不可能なのです。
陸路水路どちらも重大な壁に直面した日本軍にとって、抗戦の根拠地重慶をたたくには、その壁を乗り越えて行ける空路しかなく、こうして一九三八(昭和十三)年の十二月から、漢口を基地とした日本軍機による重慶爆撃の火ぶたが切って落とされましたが、年が開けて一九三九年になると、爆撃は都市部に向けていよいよ本格的に。
では、次に日本軍機による重慶爆撃のおおよその規模と輪郭とを、先にしるしておこうと思います。
ただし、その資料ですが、重慶で入手できた被害トータルはそれぞれまちまちで、数字の算定は当時の国民政府発表にたよらざるをえなかったため、日本の大本営発表と同様にかならずしも正確とはいえません。
資料によって若干の盖があり、さらに日本側資料と照合しますと、出撃機数よりも、中国側の来襲機数が多がったりします。
これはむしろ当然のことで、爆撃機にいちいちナンバーが書いてあるわけではありませんから、同じ爆撃機が反転してきた場合には、一機でも二機と数えられる場合もありましょう。
しかし、被害数字はもちろん加害者側にわかろうはずはなく、その基礎データーを、『重慶抗戦紀事(きじ)』中国人民政治協商会議四川省重慶市委員会文史資料研究会編)によることにしました。
同書には、まえがきとして、当時中国共産党四川省委員会秘書長だった魏伝統(ぎでんとう)が、長文の詩を寄せています。
恵みある四川の地
八年の抗戦を経て
山城・重慶ここに
ありとあらゆる災難にたえる
忘れがたい日本軍の大爆撃
その限りない悲しみと苦しみと
あるいは防空洞の窒息と
まさに千年に一度の暴虐のかぎり |
詩はさらにつづいて、「あの極悪のトリオ、東条英機、ヒトラー、ムッソリーニ……」などの行もありますが、同書の「重慶大爆撃と日本軍の中国侵略戦略」の章に各年度ごとの爆撃統計が出ています。
一九三八年、爆撃開始の年の被害はそう大きなものではなかったらしく、はぶかれていますが、さてその次の年から本格的になります。
一九三九年度の年間統計は、日本機による重慶空襲が三四回、延べ八六五機が来襲して、投下した爆弾千八九七個、破壊された家屋四千七五七棟、死亡者五千二四七人、負傷者四千一九六人。
一九四〇年度、日本機による重慶空襲は八〇回、延べ計四千七二二機が来襲して、投下した爆弾一万五八七個、破壊された家屋六千九五二棟、死亡者四千一四九人、負傷者五千四一一人。
一九四一年度、日本機による重慶空襲は八一回、延べ計三千四九五機が来襲して、投下した爆弾八千八九三個、破壊された家屋五千七九三棟、死亡者二千四四八人、負傷者四千四四八人。
ただし、この年の六月五日、市内の大防空洞で、日本機の波状攻撃下に悲惨な事故が発生し、「一万人近くの市民が洞内で窒息死した」と記録されています。
その一万人は、年度統計の死亡者数には加えられていません。
以上の三年間が、もっとも深刻な被害を出した年で、一九四一(昭和十六)年十二月八日の太平洋戦争勃発のあと、戦争の主要舞台は太平洋に移り、日本機による重慶空襲は散発的なものとなったが、それでも一九四三年八月二十三日まで、まる五年近くにもおよび、この間の総合統計は次の通り。
日本機による重慶空襲は合計二一八回、延べ九千五一三機が来襲して、投下した爆弾二万一千五九三個、破壊された家屋一万七千六〇八棟、死亡者一万一千八八九人、負傷者一万四千一〇〇名、市内の商工業関係の直接損失だけで五〇〇万ドルに達した、と。
そして、その結論は次の一行でむすばれています。
「日本軍国主義者が、重慶で犯した数々の犯罪を、重慶市民はいつまでも忘れることはないし、忘れることはできないであろう……」
今日の手紙は、ここまでにしておきます。
top
**************************************** |