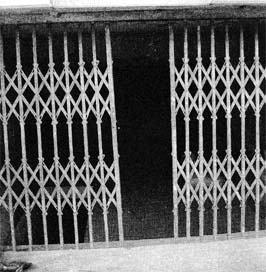|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章
第五章 証言だけの手紙
|

南区公園下の防空壕
陳栄安(ちんえいあん)さんの体験
私は、いま六六歳になります。
あれから、何と四七年も過ぎてしまいましたが、六月五日のことはよく覚えていますとも。
忘れろといっても、決して忘れることなんかできませんよ。
当時私は十九歳で、草薬街の小さな鍛冶屋で働いていました。
両親は田舎にいて、一人身でしたから、戦争がはげしくなっても、わりと呑気にかまえていられたのです。
その日私は、敵機がやってくるという最初のサイレンを聞いてすぐ、店の奥さんと若い連中三、四人と、あわてて地下洞へ避難しました。 |

当時の状況を証言する陳栄安さん

証言者陳栄安さん(中央)を取材する著者(右)と通訳の範さん(左)

二号防空壕の入口(写真下)
|
夕方でした。まだ、じっとりと汗ばむような熱気が残ってましたよ。
洞内は、最初の間しばらくはみな落着いていて、秩序といいましょうか、それが保たれていたと覚えています。
ただ、それこそラッシュ並の状態でして、両側に長椅子があるのですが、とうてい坐れるようなものじゃありませんでした。
いつもは、短時間でしたから、辛抱できたのでしょうな。
じっと耐えていた時間は、どれくらいだったでしょうか。
何とか保たれていた秩序が、突然に破れたのは、
「毒ガス弾が……」という声を、聞いた時からです。
毒ガス弾が落ちたのではないかの声が、落とされたらしいになり、それがどこからかまたたくまにひろがって、みな目の色を変えました。
しかし、なにしろ洞内はせまくて、おまけに身動きできぬような雑踏ですから、気はあせるばかりで、足は一向に前へなんか進みません。
つまづいた人は気の毒に下敷きになってしまい、その上を乗りこえていく人がまた倒れたりで、あちこちに悲鳴と絶叫ばかり。 そうこうするうち、私は、店の奥さんとも、同僚ともはぐれてしまいました。
空気がだんだんと薄くなってくるのか、それで倒れる人も出てきましたが、私は若かったから反応も早く、落ちつけ落ちつけ、と自分にいいきかせました。
騷げばその分だけ体力を消耗するし、入口に近づけば近くだけ、大混乱に巻きこまれるにちがいない、と。
そこで私は、壁にぴたりと身をよせて、石の上に腰掛けていました。
壁の隙間にほんの少しの空気がたまっているような気がして、口を押しつけて吸っていたのです。
すると、天井のランプがあちこちで消えはじめて、その心細かったことといったら、何ともたとえようがありませんな。
私は、いつのまにか、気を失ってしまったらしい。
目がさめたら、不思議なことにまわりに誰もいません。
洞内はひっそりと、静まりかえっています。
それから、入口へと向かいましたが、ええ、これは這いずっていくより仕方ありませんでした。
というのは、地面はほとんど足がつかないくらいぬめぬめと死体だらけなのです。
その死体の上を這い登って、小さな隙間からまた次の隙間へ出るといった感じ。
けれど、私も体力の限界だったのでしょう。
入口の防衛団のさしのべてくれた手にすがって、やっとのこと外に出られたものの、ほっと一息ついたとたん、またまた気を失ってしまって、何もかもわからなくなってしまってね。
お店の奥さんと同僚とは、それっきり、もう二度と会うことはありませんでした。
全体で一万人くらい死んだと、聞いています。
|

「死体が通路をふさいで………」と劉さん
劉潔玉(りゅうけつぎょく)さんの体験
当時、私は二二歳の主婦で、草薬街一一号にいました。
ですから、陳栄安さんのいた鍛冶屋と、そんなに離れていません。
私は一六歳からそこに住んでましたが、まだ戦争ははじまっていませんで、暮らしは決して楽ではなかったけれど、狭いところにみんな助け合って生活し、活気もありました。
日本軍の爆撃で、何もかも焼かれてしまいましたよ。
あの日、私が飛びこんだ地下洞は一八梯のすぐ横の紙煙草同業組合の管理する防空洞でした。
入場料を払って入りました。 |

証言する劉潔玉さん
|
入場料?
ええ、そういう防空洞もあったのです。
いろいろな企業が、自分たちの従業員家族用に作ったのは、その人たちだけしか入れませんし、また一年契約で入洞証を手にした者だけしか入れないところもありました。
それが、とても高い金額でしてね。ひどいものよね。
市民は誰でも避難用の鞄を用意してたけれど、私も貴重品だけを入れた鞄を持ち、それに懐中電灯です。
私の入った洞は、となりの一八梯とつながってましてね、つなぎ目のところは木の柵で仕切られてました。
柵の先に懐中電灯を照らしてみましたら、なにか、いつもとちがう感じ。
洞内の熱気はすごいものでしたけれど、むわっとばかりに水蒸気が立ちこめていて、水滴が、ぽたり、ぽたり、と。 |
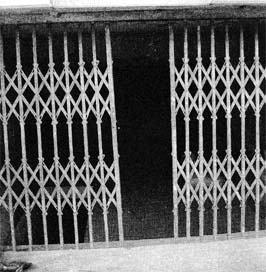
大随道(防空壕)の入口
|

磁器街防空壕入口
|
その息苦しさに耐えかねたというよりも、なんだか妙な胸騒ぎがして、私はすぐ外へ飛び出してしまいました。それで、命拾いしたのです。
いったん家にかえりましたが、おかげで、私は近所の人たちがたくさん死んだのを見ましたよ。
防空洞からかき出される死体は最初のうちこそ簡単な棺桶に入れてたけれど、あとからあとからひっきりなしで、もう、とても間に合いません。
ですから、顔と頭にほんの少しの石灰をふりかけて消毒(にもなりませんが)しただけで、トラックに山積みにして郊外へと運んだのです。
洞の入口あたりは、特にひどくて、たくさんの死体の山でした。死体が通路をふさいでしまうものですから、中からやっとの思いで脱出してきた人たちは、死の一歩手前みたいな状態で、うめいたり、もがいたり。
知り合いの奥さんと息子さんは、洞に入るときにはちゃんとした衣類でしたが、出てきたときには、血で真っ赤になっていました。
ええ、もちろん死体で……。
近所のリュウさんも、洞内で発見されたときには、まだ息をしていたそうですが、死体の下積みになってしまっていて、どうやってみても這い出してこれないんですよね。
自分の力ではとても無理で、手を引っぱったくらいでも、駄目なんです。
それで、腰に繩を結んで何人かで力まかせに引きましたら、骨がはずれてしまったとか。
骨がはずれるくらいですから、本人も、よっぽど痛かったのでしょう。
「やめてくれ、やめてくれっ!」
と、さけんで、それ以上やるのは酷だと手加減しましたら、急に静かになってしまったそうです。
しばらくして、入口付近から死体が片づけられていって、やっとリュウさんの番がきたときには、もう手遅れになっていました。
死体が身につけていた衣類や、鞄などの持ち物は、何日かの間、現在の労働映画館の横に置いてあって、遺族たちがむらかっていました。
いまでも、そこを通るたびに思い出しますよね。
被服街から掘り出された、不発弾のあの硫黄のにおいと一緒に。
|

1941年6月6日、大随道(防空壕)惨事の犠牲者

死体が積重ねたようになっていた。
|

1939年の爆撃にあった大平門海関港付近
|
|

一八梯防空壕からかき出された死体の山から身内をさがす
|
|

証言する楊澤釣さん
楊澤釣(ようたくきん)さんの体験
この中では、わしが一番最年長ということになりますかな。
けれど、当時はまだ若かったのです。三二歳でした。
わしは紙煙草同業組会に勤めてまして、劉さんのお話でおわかりのように、会社は一八梯近くに独自の防空洞を持っていました。 |

一八梯の長くつづく階段
|
一八梯は一般市民用で無料で、そのかわりに超満員なのに対し、こちらは有料なだけに多少のゆとりがあって、設備も心もちととのっていました。
わしらの洞は一八梯とつながってましたから、行き来はできなかったものの、となりの様子はわかり、話していることなんかも聞こえてきました。
ですから、あの日の大混乱は、かなりの程度までわかりました。 |

一八梯を取材する著者
|

楊澤釣さん
|
一万人もの人たちが犠牲になったのは、直接的にいって一八梯の管理や設備のミスにあったのは確かだが、しかし、その元をたどっていけば、日本軍機のたえまない不法な市民爆撃にあったのです。
このことは、はっきりさせておきたい。
洞内では空襲の正確な情報がわからないから、一体敵機がどこまできているのかいないのか、外の様子がどんな具合なのか全く不明で、かといって外には出るに出られず、不安と恐怖のあまり、小さなうわさから大惨事となったのですな。
全く、えらいことでした。 恐怖の夜があけて、朝がきたときの一八梯付近は、もうお話のほかでしたよ。
おびただしい死体は、洞内から篭に乗せて外に出しまして、トラックで次々と運んで行く。二度と、思い出したくない地獄のありさまで、何とも溜息が出ます。 |
|

|

|
|
陸橋の上にもにも下にも階段状に家が立ちならぶ。爆撃からまぬがれて、当時の古い家並が残っていた |
わしは磁器街に生まれ育って、根っからの重慶っ子でした。
ですから、ここが、わしの故郷ということになりますか。しかし、その故郷も、日本軍機のひっきりなしの爆撃で、みじめなことになりおった。
一体、何回爆撃されたことか、何回やったら気がすむのか。……
おかげで、わしの家は何度もこわされてはまた建てなおし、建てなおしてはこわされて、そのたびごとに貧乏になり、家族をかかえて、路頭をさまよったあの忘れられない日々……。
わしだけじゃなかった。重慶に住む人たちが、みんなそんな目に会ったのですな。
もっともっと話したいことが山ほどありますが、このくらいにしておきましょう。
|

証言する白素芳さん
白素芳(はくそほう)さんの体験
私は、当時二七歳でした。主婦でした。
警報が鳴るとすぐ、赤ん坊を抱いて飛びこんだところがその一八梯でした。
空襲警報が鳴ると、電柱に高くするすると大きな赤いランタンが掲げられます。ですから目で見て、耳で聞いてわかるわけ。
それから、たいてい小一時間ばかりで日本機がやってきますと、ランタンの明りが消えて緊急警報です。 |

重慶の特徴的な旧住宅街(上下とも)
しかし、この頃から中国の経済成長がはじまり、
今は都市交通や高層ビルの近代的な街に生まれ変わっている。

|
これで、防空洞の扉が、ぴたりと閉じられます。
私は子持ちでしたから、ぐずぐずしてはいられません。
おわかりでしょうけれど、母親は自分の命もさることながら、わが子の生命も守らなければならないからです。
長女は、生まれて、十一ヵ月になろうとしていました。
一八梯の防空洞のなかは、すでにお話がありましたように、息もできないばかりのこみかたでしたね。
身動きさえつかないのです。
おまけに熱くて熱くて……人いきれというんでしょうか。壁や天井に蒸留水がいっぱい。
どの人もどの人も、みなじっとりと汗をかき、私もいつのまにかびしょびしょになっていました。 |

一八梯の頂上入口
|

南紀門防空壕入口
|
とても気持ちが悪くて、頭がぼうっとかすんでくるんですよね。
もう、空気がかなり薄くなっていたんでしょう。
夢だが現実だかもわからなくなって、抱いている赤ん坊を落としちゃうんですね。
はっと気がついて、また拾って抱きしめるのですが、赤ん坊はまたぐったりして、お乳をあてがっても吸う力もありません。
空気は、もうかなり薄くなっていました。
洞内の奥のほうから、なにか悲鳴じみた騒ぎが起きたのは、洞に入ってから一時間以上過ぎたときでしょうか。ですから、夜も八時すぎですね。
悲鳴とともに、奥のほうから、どっとばかりに人波がくずれてきました。
「助けてくれ、出してくれっ!」
みんな、口々にさけんで、それはもうお尻に火がついたような感じでした。 |

死体を坊空壕から運び出す(1941年6月)
|
火がついたのではなく、酸素がなくなったわけですが、どっちにしても結果は同じです。
私もこのままでは死んでしまうと思い、赤ん坊を抱きしめて入口へ向かいましたが、赤ん坊で手をふさがれていますから、思うようになりません。
それに、足の下は、下敷きになった人ばかり。
倒れた人たちが、次々と押しよせてくる群衆に身を起こすこともできず、這いずる自由さえ失って、両手で必死にしがみつくんですね。
誰かの手が、私の足にからみついて、靴を取られてしまいました。
おまけに、右足の親指をかみつかれて……。
中国のことわざに、「人にかじられたらつけるクスリはない」というのがあるけれど、本当です。
肉がそげてしまって、それから何ヵ月も治りませんでしたものね。
やっと、出入口まできました。かすかに明りらしいものが見えて、暗闇の中でもわかったのです。
ところが、そのあたりがどうにもならないばかりの死体の山なのです。死体のなかを掻き分けていくより仕方ありません。
死にもの狂いで、ほんの少しの隙間を押しひろげていくうち、ふと見たら両手がからっぽ。全身が総毛立つような気がしました。
赤ん坊が、いない! それで、また引き返しました。
あの子を殺して、おめおめと生きちゃいられない、と。
ええ、どうせ死ぬなら娘と一緒に……と思いました。
母親の一念というのでしょうか。わが子を見つけることができました。
手さぐりで、這いずっていったのに、ちゃんと赤ん坊を拾ったのです。
人の子じゃありません。ええ、わが子ですとも。
それも、踏みつぶされることもなく!。
でも、また死体の山を越えて、ほんのわずかな隙間からこちらに伸びているたくさんの手のひとつにすがって、やっとのこと外に出られた途端、気を失ってしまいました。
失神しても、抱きかかえた赤ん坊だけは離さなかったのです。
気がついたとき、私は娘と一緒に、草薬街三〇号の家に寝かされていました。
近所中は、泣き声だらけ。
大抵どこの家でも、誰かが犠牲になって、みんな声をふるわせ、身をよじって、泣き叫んでましたよ。
私は死体がこわくて、一八梯洞のそばには近づきませんでした。
ようやく命拾いはしたものの、後遺症が残って、娘も私も病気になってしまい、実家の田舎に帰りました。
top
**************************************** |