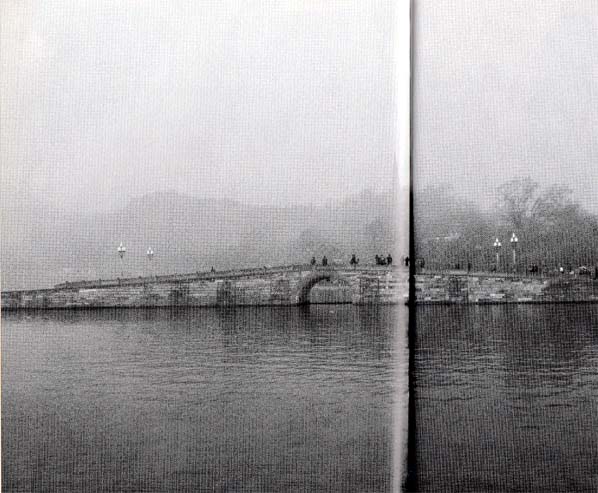|
****************************************
Index 第一部(Ⅰ Ⅱ Ⅲ) 第二部(Ⅳ Ⅴ) 第三部(Ⅵ) 第四部(Ⅶ)
二部 日本軍による戦争被害者 Ⅳ 杭州で高熊飛さんと再会 早乙女勝元
1 南京から特急列車で杭州へ top

編者夫妻と高さん夫妻
南京取材を終えたあと、列車で抗州へと移動する。
上海経由で、五時間あまりだ。二階建ての特急列車だが、軟座(なんざ)席はミニテーブルをはさんで、二人ずつ向かい合うように固定されている。 短時間ならいざ知らず、ずっと顔を付き合わせているわけだから、一人で読書をしたり、調べ物などするには不自由このうえもない。 |
 |
でも、それは「仕事の虫」たる日本的発想かもしれない、と考えなおす。
せっかく特別列車に乗ったからには、旅の風情と、コミュニケーションを大事にしろということか。
列車が動き出すと同時に、お茶のサービスだ。
赤ベレーをかぶった女性服務員が、大きなヤカンを持ってくる。
蓋つきの湯飲みに、たっぷりと汗がれるお茶は猛烈に熱く、表面に浮いている葉っぱをふうふうとよけながら飲む。
お茶飲み話に花が咲くのはいいが、さてトイレとなると、各車両に一つしかないので、すぐ行列だ。
そのトイレは水洗ではない。昔なじみの、穴があいていて、車外へ落ちる素朴な仕組みである。
従って駅の近くなると使用禁止で、鍵をかけられてしまう。停車中はもちろんのこと。発車してまた少しすると、赤ベレー嬢がポケットから取出した合鍵で、うやうやしく扉を開けてくれる。
「さあ、どうぞ」
てなわけだが、謝謝というのもバツが悪い。
市場経済の導入によって、沿海大都市の外観はすべてきらびやかになったものの、列車のトイレ事情は一昔前のまま。
そこまではまだ手が回らないということか。
一車両に一人ずついる赤ベレー嬢も、日本式の車掌ではない。彼女たちの仕事といったら、お茶のサービスと、トイレの開け閉めといったら失礼だが、時には詰まったトイレを、バケツの水でざんぶりと隴すくらいのものだ。
その水が、一階の座席通路にまでちょろちょろと流れてきて、列車の震動に、行ったりきたり。
何とものどかな感じで、合理性一本ヤリの新幹線に乗り慣れた者にとっては、見ているだにもの珍しく、微笑ましい。
お茶は、何杯でもおかわりすることができる。
いや、やっと飲んだと思えば、またすぐに注ぎにくるのは、過剰サービスというべきだろう。
賑やかだった対面の客が、やっと寝込んでくれた。おかげで、これから行く町についての資料を開くことにする。
|
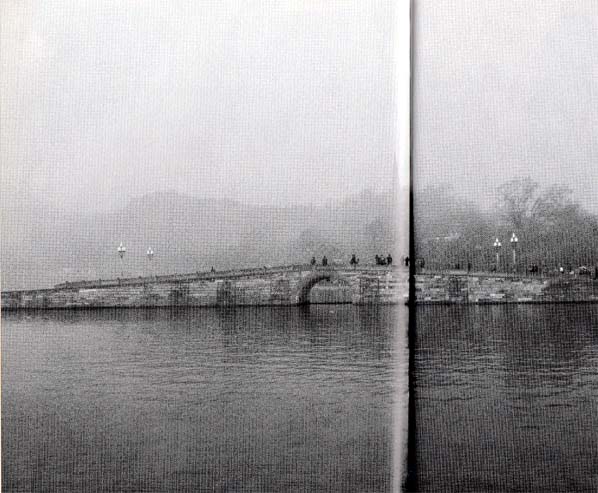
風光明媚な西湖。観光客で賑わう
|
|

野外ステージでの京劇
淅江(せっこう)省の省都、杭州は、古くから貿易港として栄えてきた。中国六大古都の一つ。
私には未知なる町だが、特に美しい西湖と、絹織物の特産品で知られている。
上海から近いこともあって、内外の観光客が多いとある。
最近は日本の修学旅行の生徒たちも、どっと押し寄せるらしい。 しかし、昭和史をさかのぼれば、杭州は上海とともに激戦地だった。 |

杭州で有名な六角塔
|
一九三七年秋、日本軍が中国の首都・南京を攻略すべく、侵略の第一歩を踏出した華中の重要拠点である。
陸軍の大規模な上陸作戦に先立って、海軍航空隊による渡洋爆撃も頻繁に行われていた。
現在は、かっての戦場だった面影はないとのことだが、私が訪ねる目的は、戦跡調べではない。
戦跡を、生きてあるかぎり、わが心身に残した方と会うためである。
2 高さんの珍しい名刺 top
高熊飛(こうゆうび)さんが、その人である。
熊が飛ぶなんておかしな名前だが、先にいただいた名刺には、漸江省教育学院の「数学、副教授」の肩書がついている。
本当は熊さんと呼びたいところだが、助教授ともなれば、そうはいかない。
その名刺だが、またまた風変わりだ。二つ折りになっていて、広げた内側が、ご自身のメッセージになっている。
列車内で通訳のS女史に訳してもらうと、次のような内容だった。
「中国国民である戦争被害者が、日本政府に“被害賠償”を要求するのは、正義と道理にかなったものであり、中華民族の尊厳を維持するためです。
それはまた、わが中華(中国)を愛し、中日友好を深めることと同時に、もっとも基本的な人権を、保障することにほかなりません。
さらには世界平和のかけ橋となるもので、従って、世界の平和を愛する人々の支持が得られるはず。
民間の対日賠償要求は、決して被害者の私事ではないのです。
なぜなら、私たちは侵略され、略奪され、はかりしれない犠牲と苦難を強いられたのだから。
それ故に、正義と道理を追求するのは、私たち中華民族のやむにやまれぬ声であり、当然の要求といえましょう。
私たちと真の友好を願っている日本の友人たちも、それを望んでおり、何人も妨げることのできない平和と友好の潮流なのです。
日本政府は国際法に従って、それぞれの戦争破害者に、謝罪と賠償をすべきです。
賠償なしの謝りはいつわりのものであり、謝りのない賠償は道義に反するものと、言わねばなりません……
そして、最後に「政府と自治体の役人たちは、中華民族の立場を守って、このことをよく理解してほしいと思います」と、結ばれている。
二つ折りの表は、勤務する学院名と自宅のアドレスに電話などで、その裏面は自説を立証する政府首脳の談話である。
すなわち一九九五年三月、銭其琛(せんきしん)外交部長(副首相兼外相)のコメントで、「一九七二年、中国と日本とが国交を開復した際に放棄したのは国家賠償であって、個人のそれではない。
従って、中国国民が賠償を要求するのは、個人の権利である。政府はこれを干渉するものではない」
なるほどと思った。訳してもらってわかったことだが、要するに戦争賠償には二通りあるというわけである。
国家における損害賠償と民間の被害賠償とで、中国政府は後者まで放棄してはいないということ。
従って、九五年以降は個人の日本政府や企業に対しての訴訟に規制はしない、と受けとれる。
市場経済にともなう開放政策のせいか、政府高官が、個人の権利を認めたのは一歩前進だった。
が、しかし、一歩だけでは、かゆいところにまでは手が届かない。個人の非力な被害者が、日本政府に対して、一体何ができるというのだろう。
その要求を積極的に支持するとか、援助するとかではないのだから、見方によってはそっけなく、やるならご勝手に、といわんばかりである。
3 日本軍の侵略のせいで top
だからこそ高さんは、一人でも多くの支持者をと、ユニークな名刺を作らざるを得なかったのだと思う。
そして、周辺に少なからず「規制」の動きがあったから、わざわざ政府筋の公式発言まで引用して、自分とかかわる人たちの理解を求めたのにちがいない。
南京事件の李秀英さんではないけれど、中国の要人ではない一庶民が自力で日本政府を訴えるのは、これに共鳴・支援する強力な「日本の友人」でもいないかぎり、ほとんど不可能に近いことなのだ。この国の現状では……。
私が、高さんに初めて会ったのは、一九九八年七月の東京・大塚での集会だった。
「日本軍の無差別爆撃の被害者、高熊飛さんの証言を聞く会」だったが、事前に集いのビラを手にした時、行こうとハラを決めた。
これだけははずすわけにはいかない、と思ったものだ。
なぜかというなら、都市無差別爆撃の歴史は、米軍機による東京大空襲に始まったのではない。
元はといえば、日中戦争特に中国の諸都市に向けて、日本軍がいちはやく先鞭をつけたのである。
それがどんどんエスカレートしていった結果が、未曾有の大量殺戮ともいうべき三月一〇日の「炎の夜」であり、広島・長崎への原爆だった。
と考えるならば、高さんは、東京大空襲の惨禍を総合的に追いつづける私と、直接にかかかる方であろう。
会場の受付には、たまたま近所に住む知人がいて、すぐ控室へと案内された。紹介されたのは、何人かの弁護士さんだった。
ああ、こういう人たちが手弁当て、中国人戦争被害者の要求を支えているのかと、頭が下がった。
そして、お会いした高さんは、意外に明るくて、さっぱりした方だった。
大学の先生という気むずかしさはなく、それこそ熊さんというにふさわしい。
明るいと感じたのは、私が会った戦争体験者は、国の内外を問わず、みなかなりの高齢だったからだ。
戦後半世紀余ともなれば、無理もない話だが、日本軍機による爆撃で、お母さんともども右腕を失った高さんは、まだ四歳だった。
被爆は、一九四三年十一月四日、福建(ふっけん)省の永安(えいあん)市だという。
従って、今も五〇代の後半だ。しかも気楽に話のできる楽天的な庶民性がプラスして、この人を年齢よりもずっと若くしているように思えた。
「ぜひ、わが家に遊びにきてください」
と、初対面なのに、白い歯並みを覗かせていう。
「はい。いつの日か、きっと」
私も笑って答えたが、そのYシャツの右袖がたらんとしているのが、何とも痛ましかった。
目立たぬように腕の左右をまくっていたが、右腕は肩の付け根から切断されてしまったのだ。
被災時は幼かったので、記憶はとぼしいが、その後、左手だけの母とともにどう生きたかというお話は、思わず吐息が出るほど苦難に満ちたものだった。
「私には、人並みな少年時代はありませんでした。
当時の中国は、その日食うものにも事欠くような生活でしたが、ことに私はそれこそ言いつくせないばどの、みじめな思いばかりでした。
様々な差別と、いじめと、ひどい貧しさと。
母は何度か自殺を考え、一度ならず橋から飛び降りて、助けられたこともあります。
大病院の婦長だった母は、片手では働き口もなく、不幸な子供を抱えて、生きる意欲さえ失ったのです。
私自身も、さらに進学や結婚で、どんなに悩み苦しんだかわかりません。私は三度恋愛しましたが、三度とも受入れてもらえませんでした。
私たちの、被害事実は明らかです。すべては日本の侵略のせいです。
日本政府に対し、謝罪と賠償を要求するのは、わが家の五〇年来の強い願望でした。
私は多くの被害者の一人にすぎませんが、人類社会の正義と平和と、人間の尊厳のために、皆さん方のご支援と、日本の裁判所が公正な判決を下されることを希望しています」
時々高ぶる感情に声を震わせながら、そう訴えて深く一礼した姿が、私の脳裏にあざやかである。
4 ジャンパー姿の高さん top

抗州市中心街 |

証言する高さん |
特急列車は、いつのまにか杭州駅に着いた。駅から車でひと走り、ホテルのロビーで、高さんと無事に再会できた。
中国語で別れの挨拶は「ツァイヂェン」(再見)だが、集いのあった夏の日から、まだ半年たらず。
季節は冬に変ったものの、高さんはあの日と同じ屈託のない笑顔で、お元気そうだった。すでに先に来ていて、
「やあ、やあ!」と、私たちを迎えてくれたのである。
「また、お会いしましたね」
「ご縁があるんですよ。はるばるとご苦労さまです」
セータァを二枚重ね着した上にジャンパーをはおった高さんは、近代的なホテルにはちょっと不釣合いだ。
そのジャンパーの右腕の先を、右のポケットに突っ込んでいる。
ラフな感じだが、背広だとポケットの位置が低いので、右袖がぶらぶらするのかもしれない。
しかし、当然あるべき両手の一方がないのだから、こちらに歩いてくるのにも、鞄から何かを取出すのにも、やはりどこか不自然で、不安がある。
そういえば、子供の頃にはバランスがとれず、よく転んだという。転んでも右手の支えがないので、顔面への怪我が多かった。
また片腕を失ったことで血液の流れが悪くなり、右の肩と肺機能に影響が出た。
気温が低下すると右肩から冷え出して、切断されたはずの腕に、今でも鈍痛が感じられるという。
その夜は、高さんご夫妻と一緒の夕食会となったが、隣席に座ったせいか、ああ、これは大変なんだなと気付くことがいろいろあった。
左手だけでは、箸しか持てない。小皿なり茶碗を持って、食べることができないのだ。
横から、奥さんがさりげなく世話をしていたが、毎日のことともなれば、どんなに不自由なことか。
両手がなければ、物をしぼることもできないし、何か重いものを持ちかえることも不可能ならば、雨の日に傘をさすこともできない。
もっとも、こちらでも、ジャンプ式の傘が出回っていることだろうが……。
中国は今も開発途上国にランクされているが、高さんの幼少年時代や青春期は、もっともっと貧しかった。
それこそ食うや食わすのどん底生活だっただろう。
身体障害者となった高さんが、同じように右腕を奪われて就職口もない母の保護の元に何とか進学し、大学の助教授になるまでには、どんなに多くのハードルを越えてきたことか。
「障害者に、教育を受けさせるゆとりはない。それは浪費だ」
と、面と向かって、言われたことさえある。
しかし、高さんはくじけなかった。同じ人間なのに、何が浪費か。好きで障害者になっだのではない。
日本軍の空爆でやられたんだ、と詰め寄り、新聞の読者便りにまで投稿した。それが採用されて、多くの人たちの関心と話題を呼んだ。
まだまだ閉鎖的だった進学の扉を、次々とこじ開けて、得意の理数系で自分なりの道を切開いてきたのは、それこそ血のにじむような努力と、前向きな気迫によるものだったといえよう。
しかし、その生活状態は、現在どのようなものなのか。次の日、私は高さんのお宅を訪問することにした。

自宅台所で高夫人
5 お宅は2K、書斎もなく top
中心地のホテルから、市内北西に向けて、車で二〇分ばかり。
信号もなくやたらと人々の行き交う通りの途中で、降ろされた。 路上には、食べ物の屋台が並んで、みな威勢のいい声を張り上げている。
雑踏と喧騒の続きで、お世辞にも静かとはいえないようなところの、集合住宅だった。
見かけは、わが家近くの都営団地と変わらない。
エレベーターはなくて、ざらついたコンクリートの石段を上がっていった四階が、高さんのお宅である。 |

高さんの自宅アパート |
玄関を入った先が狭いキッチンで、その左側に、殺風景な小部屋が二つだけ。
いわゆる2Kだが、これが大学助教授の住居かと驚く。
「さあ、どうぞどうぞ」
と、奥の一間に通された。
奥といっても、その鼻先はすぐベランダになっている。
室内をきょろきょろするのも失礼だとは思いながら、取材者たるもの、目にしたものを素早く脳裏に記録しなければならない。 それでおのずと生活程度がわかろうというものだ。
ドアのすぐ右側、璧ぎわに古びたソファ、その並びが本棚で、正面のベランダと向き合って、資料類が雑然と積まれたデスク。
左の壁の前には、大型テレビが独占している。天井には、これまたばかでかい四枚羽根の扇風機だ。
「このテレビは、先頃、香港で働いている娘が買ってくれたんですよ。私たちの月給じゃ、なかなか……」
高さんは、メモ帳を手にしている私に気づいてか、声高に笑いながらいう。
ちなみに、その値段を聞くと六〇〇〇元、これに対して、高さんの月給は一〇一〇元、人民元へのレートは現在、一元が日本円で一五円ほどだ。
ということは、日本円で約一万五〇〇〇円の月給で、テレビは何と、その約六倍ということになる。
奥さんは保母さんで、五○〇元の月収とのことだった。
テレビの高額なのには仰天したが、それよりも、ご夫妻の収入が安過ぎるのではないのか。
二人合わせても、二万円ちょっとで、特に障害者への年金とか手当とかはない。
物価の基準がちがうから、日本と比べることはできないものの、一見して、これほど物の少ない住居も珍しい。
研究者だというのに、書斎はなく、それは居間と兼用で、デスクに電気スタンドもない。隣室はペッドに、小さな洋服ダンス一つ。
衣類もそうだが、書籍などこれで足りるのかと思えるようなミニ書棚だった。
「これでも、まあ、中国では中流どころですよ。
ただ、テレビはなかなか手が届かなくて、旅行なんかはとてもとても……」
と、高さんは、苦笑まじりにいう。
「娘さんは、景気いいんですね」
「香港へ嫁にいったのです。夫婦で、不動産屋と文具店に働いています」
「お子さんは、一人だけ?」
「ええ、そういう決まりなの」
と、奥さんが、横から口を添えた。
ああ、そうか、中国は一人っ子政策なんだとうなずきながら、私は思ったものだ。
夫妻にとって、よき協力者だったであろう娘を、嫁がせるのは、どんなにか痛手で寂しかったことだろう、と。
娘もそれを承知しているからこそ、高価なプレゼントをはずんだのにちがいない。
6 奥さんの涙の告白 top
高さんは、三度恋愛してすべて失恋に終ったと、先の集いでうち明けている。
それでは、現在の奥さんとは、どのように結ばれたのだろうか。
奥さんの名前は、黄玉英(こうぎょくえい)さん(中国では結婚しても姓は変わらない)。
一九四七年生まれで、二三歳で高青年と結婚したという。文化大革命の嵐の吹き荒れていた頃で、下放政策により農村へ追いやられていた。
都市部の知識人と結婚すれば、町へ戻ることができる。そんな気持ちも少しはあって、九歳上の教職にある高青年の求愛に応じたのだという。
しかし、高さんが障害者ということでの、周囲の反対はすごかった。
当時の中国では、女性が障害者と結婚したら、世間から白い目で見られ、あれこれと噂の的になって、蔑まれるという風潮が強かった。
高さんが熱を上げた女性たちは、その社会的な圧力に耐えられなかったのだろう。
「でも、この人は、誰かが助けてあげないかぎりは、生きていけないのです。いい教育者になれる人なのです。
そう思って、ありとあらゆる反対を押しきったのは、やはり若さだったかもしれません。結婚してから、何度別れようと思ったことか……」
と、玉英さんは、感慨深けに語り出した。
「今でも、後悔の気持ちが、時々胸をかすめるの。同僚たちにもずっと内緒にしてきて、決して家に呼ぶこともありません」
「……」
「そんなプレッシャーに加えて、私は、二人分苦労してきたと思う。だって、この人が左手だけでできることといったら、限度があります。
私は病気になることもできない。たとえ具合悪くて寝こんでも、起き上がって、食事をつくらなくちゃいけないの」
「……」
「この人は五九歳、あと半年たらずで、定年です。そして私は、心臓が弱いんです。
こちらでは介護者がいなければ、入院もできませんから、この先、どうしたらいいか。考えれば苦労ばっかり。
今までは何とか若さで乗切ってきたけれど、もうそういうわけにはいかないの……。
こんなこと、私、しゃべったの、はじめて。中国人だってわかってもらえないんだから、日本人には、なかなか……」
突然に玉英さんは、おろおろと涙声になり、通訳のS女史に両手ですがって泣き出した。
私は、目のやり場に困った。
初めてとはいいながら、これまで胸にうつうつとしていたものを一気にさらけ出した感じだった。
しかも、夫のいる前でである。夫にも聞いてもらいたかったのか。
客の私は、何とも身の置きどころもなかった。
そもそもの原因はといえば、日本軍機の無差別爆撃によってもたらされたのだ。
と考えれば、なおさらのこといたたまれぬ思いである。
「でも、この人は、とてもやさしい人で、積極的ないい人です。だから、私は尊敬しているんです」
と、かすれ声で一語をつけ加えた。
高さんはとみれば、ソファの端に座ったまま、身じろぎもせずに涙ぐんでいる。
私は、ほっと胸をなでおろした。その胸が熱くなった。
もしかすると高さんは、到底、言葉にできないほどの彼女の胸の内を十分に察していればこそ、その分まで含めて、日本政府を訴えたのかもしれないと思う。
提訴の決断は、そのくらい深いものではなかったのか。
7 死んでも娘が受けつぐ top
ようやく落着きを取戻したのか、玉英さんの話は続く。
高さんの勤務する学院は、この家から自転車で約三〇分ほど。いつも、片手運転で往復するのだそうだ。
ところが、悪天候の日もある。みぞれまじりの雪や、道路の凍りついている日など、危険このうえもない。
雨が降れば徒歩で一時間以上、もちろん傘をさしていくわけだが、たとえ滑って転んでも支える手はない。
だから無事に帰宅するまでは、気掛かりでならないという。
「元気な顔を見るまでは、とにかく心配で、心配で……」
と、玉英さんは、繰返した。
さもありなんとうなずきながら、そこで、私はふと気づくことがあった。
高さんも玉英さんも、さっきからずっと外出着姿である。
中国の家は床が土間で、靴をはいたままなのは承知していたが、高さんはホテルのロビーに現れた時と同じに、セータァを二枚重ね着して、ジャンパー姿だ。
奥さんは、赤い襟つきのアノラックだ。
「あのう、部屋の暖房はどうしてるんですか」
と、聞くに、
「たくさん着るだけですよ、上に上にと」
高さんは、片手だけのゼスチュアで、笑いながら答えた。
天井に扇風機がついているのだからエアコンがないのはわかるが、しかし電気からの暖房は可能だろうに、と聞けば、
「電気代が高くついて、ね」驚きだった。
杭州は東京よりもずっと冷えこむのに、冬は暖房なしで過ごすんですか、という声を私はおさえて、話題を変えた。
「春がくると、先生は定年なんですね。どうされますか」
「いずれは、娘のいる香港へ移住したいのです。
さっきの入院話ではないけれど、娘がいてくれれば何かと心強いから。ただ、香港への移住はそう簡単にはいかない」
「この夏の東京には、娘さんもご一緒されたんですね」
「そう。娘の分は自前でね。支える会の皆さんには、あまり負担はかけられませんから」
「裁判の成り行きですが、さてさて、どんなふうになると考えますか」
「先は長いと思います。この何十年間にわたって、日本人で私らを心配してくれた人は一人もいなかった。
日本大使館にも何度か手紙を書いたが、中国の弁護士同様に、みんな知らん顔だった。
もちろん上からの圧力でですよ。提訴した当初は学校からも煙たく見られ、何かにつけてブレーキをかけられたけれど、でも、教え子たちが支持してくれました。
また、日本にも支える会ほか、皆さんのような友人ができたのが、何よりもうれしい、ほんとに……」
と、高さんは、声を震わせる。メガネの奥の目がうるんでいる。さらに続けて、
「その日本にも、アメリカ軍の空爆で大被害を受けた人たちがいるのを、私は知っている。なんの補償もないとか。
でも、これは区別してほしいと思います。なぜなら、中国は日本に侵略されたんですから。
日本の空襲被害者や遺族は、政府とアメリカに謝罪と賠償を要求すべきであって、そういう運動なら私は支持できる」
「なるほど、日本の空襲犠牲者も黙っているべきではない、と」
「そうです。だから、人々のため平和のため未来のために、どんなに長くかかるうとも、絶対に引くわけにはいかない。
私どもが死んでも、娘が受けつぐ。裁判を通じて、日本人にも過去の事実をきちんと知ってほしいと思います」
奥さんが、横でうなずいた。
多くの苦難と試練を越えて、夫を信頼している妻の、あたたかい目差しが感じられた一瞬だった。
最後に、並んで座ったご夫妻にカメラを向けたが、その笑顔は最高で、しかも玉英さんの両手は、高さんの左手としっかり結ばれていた。
top
****************************************
|