|
****************************************
Index 第一部(Ⅰ Ⅱ Ⅲ) 第二部(Ⅳ Ⅴ) 第三部(Ⅵ) 第四部(Ⅶ)
二部 日本軍による戦争被害者 Ⅴ 日本軍の無差別爆撃による被害者 大谷猛夫

1953年、中学校卒業時の高さん |

1945年11月、左手だけの母と2人の妹と弟。右端が高さん |
1 高さんの生まれた頃 top
高熊飛(こうゆうひ)さんは、杭州のホテルで私たちを迎えてくれました。
一九九八年七月に東京地裁で本人尋問で来日した時以来の再会です。
高さんは、大学で数学を教えています。
教え子は淅江(せっこう)省各地で教師になり、校長先生になっている人もたくさんいます。
私たちが杭州に高さんにお会いした時、三人の中学の校長先生がおみえになっていました。
高熊飛さんが話してくださった苦難のおいたちは次のようなものです。
高熊飛さんは、一九三九年二月に中国淅江省金華市で生まれました。
一九三七年廬溝橋事件の後、日本は中国各地の海岸線から中国の各地に侵略の軍隊をすすめていきました。
夏には、上海から当時の首都であった南京にむけて日本軍がすすんでいました。
この年の一二月には有名な南京大虐殺がおこります。高さんの生まれる一年半ほど前になります。
高さんの両親の家は杭州市にありましたが、杭州は上海から日本軍の進路に近く危険だったので、父母は親戚を頼って金華市に移っていたのです。
高熊飛さんの父、高文達さんは「大風出版社」という出版社で編集の仕事をしていました。
主に雑誌の編集出版の仕事をしていました。
その雑誌が「左翼系」だということで当時の中華民国の政府から強制的に廃刊させられ、出版社も閉鎖され、お父さんは失業してしまいました。
お母さんは病院の看護婦をしていました。金華市では福音病院の婦長をしていました。
一九四〇年二月には上の妹・高雲瘟(こううんおん)が生まれました。
一九四一年九月、お父さんは福建省政府の職員として招かれ、福建にいくことになりましたが、お母さんは金華での仕事の都合で母子は残ることになりました。
ここも空襲がはげしくなったので、またすぐ母子は、淅江省衢州市に移らざるをえませんでした。
一九四二年六月、日本軍は衢州市に侵入し、占領しました。
高さんはお母さんと一緒に、衢州市から二〇キロほど離れた山深い石屏郷(せきびょうごう)に避難しました。
母親は農家のかたわらにある牛小屋で二番目の妹(高雲屏)を出産しました。
四人は野草を食べて生きのびていました。町に戻った人の多くは日本軍に殺されたそうです。
同年八月下旬、日本軍は衢州市をひきあげはじめました。
日本軍は引き揚げる時に細菌をまいたということも聞きました。
家は爆弾でこわされ、住むことができなかったし、日本軍がまた攻めてくるのがこわかったので、たくさんの逃げる人について、そこから二〇〇キロ離れた福建省の浦城(ほじょう)まで歩いて逃げることにしました。
その数は二〇万人もいました。
この地域は北と西と東と三方、日本軍に包囲される形になっていたので、南の方に逃げるしかなかったのです。
昼は日本軍の攻撃があったので、朝と夜だけ歩きました。一日に二キロほどしか移動できませんでした。
日本軍の機銃掃射でたくさんの人が亡くなったのを見ました。そうやっておよそ一〇〇日かかって浦城につきました。
ここにお父さんが迎えにきてくれて、そこからは車で移動しました。
一九四三年春、当時の福建省の戦時省都・永安市にたどりつき、東門街の一民家を借りて住むようになりました。
2 永安市で空襲にあう top
一九四三年十一月四日午後一時頃、永安市は、日本軍の一六機の飛行機の来襲を受けました。
二〇〇発余の爆弾が投下されたのです。高さん兄弟とお母さんはその時、家で昼食を食べていました。
日本軍の飛行機がやってきて、高さんとお母さん二人とも右腕を失いました。
その時、お父さんは一〇〇キロほど離れた同じ福建省南平市に出張していて留守でした。
お母さんが一人で小さな子供(二歳、三歳、四歳)を守っていました。子供たちを食卓の下にいれました。
二人の妹は床に伏せ、ふとんがかけられました。高さんとお母さんは椅子の下にうずくまって、ふとんの端をひっぱっていました。 |

1941年、中国の臨時首都だった重慶は、
日本機の反復する爆撃目標となった。遺体処理作業
|
家の中庭に落ちた一発は高さんたちから六~七メートルのところに落ちました。
一瞬のうちに右腕を失い、気を失ってしまいました。
高さんの右腕はどこかにとんでいってわからなくなっていました。どこにいったか今でもわかりません。
お母さんは皮一枚で腕がつながっていました。その時、天井も床もいたるところ血だらけになっていました。
母子とも気を失ってしまったのです。近所の人たちが高さんたちを見つけ、傷口を麻縄でしばり、戸板にのせ、救急所へ運びました。
救急所に着いたのは午後二時頃です。そこには数十人の人が長い列をつくっていました。
二時半ごろに医者が高さんたちをみてくれました。
医者はつれてきた人に「ここでは治療は無理なので、すぐに病院に運べ」と話しました。
その場で高さんとお母さんに強心剤を注射してくれました。
そこで近所の人たちは、高さん親子をまた戸板にのせ、被爆して燃えさかっている町をぬけ、北門を出て、燕江(えんこう)をわたり、福建省立医院往院部に着いたのは、すでに夕暮れになっていました。
病院の前にも重傷の人が待っていました。
かついできた人たちは、高さんが死んでしまったと思い、畑の方にほったらかしにしていました。
医者はまず最初にみてくれました。まわりの人は「死んでいるから助けなくていい」と医者に言っていました。
院長さんは「本当に死んでいるか、自分で見てから判断する」と言いました。足で蹴ってみると反応があったそうです。
それぞれの人の、目の瞳孔が開いていないのを見て、人道主義に基づいてまず、子供と女の人を見るといいました。
このことが幸運だったのです。お母さんの手術は八時半ぐらいまで三時間ほどかかりました。
病院の中には薬もなく、輸血の感染を防ぐため、四センチ多めに(高さんは七センチほど)切られました。
高さんは手術の間合計四回気を失ったのです。
当時着ていた服は病院の玄関においてありましたが、衛生員が持っていってしまいました。
お母さんはこの手術した時に、体からでてきた弾片を一九五六年まで保管していました。
次の日になって、昼ごろお父さんが南平から帰ってきました。
近所の人から母子が病院に行っていることを知らされました。
まだ死んでいるか生きているかもお父さんはわかりませんでした。
お父さんが病院に着いた時、すでに手術は終っていました。
腕は切断され、意識を取戻すことはありませんでした。三日目になってやっと意識が戻ってきました。
近所の家も燃えて灰になっていました。
高さんの家の親しい友人の何人も、日本軍の爆弾の犠牲になって命を落としていました。
道路はほとんど壊され、壁には血や皮膚が張り付いていたりしました。
当時三万人の永安市で一万人の人が罹災し、百貨店が一軒、飲食店が一軒残っているだけでした。
もっともにぎやかな所は焼きつくされていました。物質的損失は四億元になるといわれていました。
3 それまでの永安市における空襲 top
永安市はそれまでに十一回、日本軍の空襲がありました。
一九三八年六月三日に第一回目の空襲があり、一九四三年十一月四日の高さんが遭遇した十一回目の空襲まで、のベー七〇機の日本軍の飛行機が永安市に飛来しました。
そのなかでもっとも被害が大きかったのが、この永安大空襲です。
一六機の飛行機が五〇〇ポンド以上の爆弾を投下したという記録が中国の新聞に掲載されています。
焼夷弾を投下し、三平方マイルのところにある九七八棟の家屋を焼きつくしました。
まず焼夷弾を投下し、大火事をおこし、逃げてくる人々を機関銃でねらいうちしました。
大火事は三日三晩続き、半月後にはいたるところに新しい墓がつくられました。
警察によればそれでも引取りにこない遺体が五〇〇体以上あったといいます。
当時、食糧難もひどいものでした。政府の布告は三日分の食糧を提供するというものでした。
それ以上は各自で調達しろというものでした。永安市は生気のない静寂につつまれていました。
たくさんの人たちがよその土地へ避難していきました。
日本軍の中国無差別爆撃というと「重慶爆撃」が有名です。
四川省の重慶は当時中華民国の臨時首都がおかれていたので、日本軍が爆撃したのです。
しかし、永安市は軍事施設もないし、軍隊もいないといういわゆる「無防備都市」です。
ここに対しても日本軍は爆撃を続けたのです。
この高熊飛さんの右腕を奪った飛行機が、どこから飛び立ったどの所属の飛行機だったかの確たる証拠はまだみつかっていません。
しかし防衛庁の資料には、この時期海軍の飛行機が、台湾の飛行場からひんぱんに福建省の各地を爆撃していた記録が残っています。
アメリカなどの連合軍が、中国の飛行場を使って日本軍を脅かすのを防ごう、という作戦が続けられていました。
この中のどれかが、一九四三年十一月四日の永安爆撃を行ったのではないでしょうか。
4 お母さんのつらい体験 top
お母さんは看護婦をしていましたが、右腕を失ってからは当然仕事をすることはできません。
衢州にいる時までは、小さい子供の世話や家事は、お手伝いさんを雇っていましたが、当然そんなことはできなくなりました。
お母さんは被爆した時三〇歳でしたが、片腕で何もかもこなさなければなりませんでした。
お母さんは自分でご飯を食べるのも大変なことでした。片腕なのですから。
子供たちにご飯を食べさせなければなりませんでした。
お母さんは退院した後も一九四四年春に二回も病院にかつぎこまれました。体が衰弱していたのです。
戦争が終り、日本軍が中国からいなくなり、一九四七年、お爺さんがいる実家に帰りました。
92-48
しかし、お爺さんからは大変な差別を受けました。
働きもせず、食べるだけで身なりもきたなくて物乞いみたいだというのです。
お母さんは何度も自殺を考えました。一九四八年春、お爺さんからののしられ、橋から飛び降り自殺をはかりました。
冷たい初春の川に身を投げたのです。
三番目のおじさんに川から救いだされました。お母さんは、村中に聞こえるような大声で叫びました。
「こんなにつらい思いをするのは日本人のせい。家族に被害をもたらして、どうしようもない」。
村の人たちは母親をはげましました。
「自殺してはいけない。子供たちをおいていってはいけない。日本政府にきっと償わせる」と。
5 高さんの小さい時 top
高さんは四歳の時に被爆して、右腕を失い、体の平衡感覚か弱くなってしまいました。
よくころんだりしました。身体の発育にも大きな影響かありました。
腕がなくなって血の流れが悪くなっていたのです。骨格の成長にも影響がありました。
右肩と右肺の発育か弱く、病気がちになっていました。
気温が低い時にはなくなった右腕のところに鈍痛が走りました。
障害のためたくさんの差別をうけました。
数少ないわけのわからない子供たちが高さんのことをあざ笑いました。
同じぐらいの年の子から髪の毛を引っ張られたり、襟口から泥をそそぎこまれたり、口の中に泥をおしこまれたりしたこともあります。
高さんは小さいころ、よくいじめられて、泣いて家に帰ってきました。わけもなくピンタをはられたこともあります。
それでも抵抗しないのを見て大声で笑ったりするのです。
知らない土地に行くと「オーイかたわが来たぞ」とみせしめにされたこともあります。
お父さんとお母さんが一緒でもことは同じでした。小さい時、どうしてこんな目にあうのかわかりませんでした。
また空襲の時の思いが強く、一九四七年までは飛行機の音を聞くだけでこわくなって気絶してしまったのです。
中国は一九四九年に共産党政権の社会主義の国、中華人民共和国になっていました。
そして高さんは一九五三年八月に中学を卒業しました(中国は九月が新学年の始まり)。
皆と同じように高校進学できると思いました。そのころ公立と私立二種類の学校がありました。
公立高校は国が創設した学校で教師のレベルも高く学費も安いのです。
まず公立高校が生徒募集をします。合格発表のあとに不合格者は私立高校に願書を出しに行くことができます。
卒業と同時に高校入試の出願をしようとしました。
省立瑳州(さしゅう)高等中学校へ友だちと一緒に願書を出しに行きました。
他の同級生は受けつけてもらえたのですが、高さんだけは願書を受けつけてもらえないのです。
その時はその学校だけが受けつけてもらえないと思いました。
翌日瑳州師範学校に願書を出しに行きました。将来卒業したら教師になりたいと思っていました。
しかし、そこでも受付を拒否されました。
「右腕がないので、体型的に見掛けが悪い。教師になるには顔だちが整い、立派な体型をもつという基本的な条件が必要」というのです。
「国は障害者の教育をするひまがあったら、健常者を教育する」とも言いました。
理由を確かめに市の文教局(日本でいえば市の教育委員会)に行きました。
そこの役人は「上級からの指示で、決まりもそうなっている」というだけでした。
帰ってすぐ文を書き、近くにあった地方の新聞社(当代日報社)を訪ね、自分の不幸な境遇を訴えて、障害者差別の不当を主張しました。
新聞社の編集の人たちは大変同情してくれて、八月一三日付けの『当代日報』読者便りコーナーに載せてくれました。一四歳の時のことです。
この記事は大きな反響を呼びました。町で知合いに会うとはげましてくれました。
一五日午後になって教育長が会うという連絡をうけました。
翌日、文教部の建物にはいり、教育長に会いました。よく話を聞いてくれました。
「そのネッカチーフも自分で結んだのか。靴ひもはどうか」と聞きました。
高さんはその場でネッカチーフをほどき、まき直しました。靴ひもも自分で結び直して見せました。
教育長は高さんに「私の願い」という作文も書くように指示しました。
その時の思いを大体次のように書きました。
「……たしかに私は障害者です。身体的な障害はありますが、志は健全です。
私は親に養われ、社会に救済される人になりたくはありません。
おまけに母も障害者ですのでなおさらです。私の願いは他の人に頼らず自分で働いて生活することです。
そしてさらに国の建設に参加し、国に貢献できる人間となるように知識を身につけたいと思います。
そのために学習のできる機会を得たいのです。
私は中学校で水泳・自転車・卓球や片手でバスケットボールをシュートすることなどのスポーツを身につけました。
私は一人で釣瓶(つるべ)を持って井戸から水を汲むことができます。
自分で洗濯をすることができます。また自分で手の爪を切ることもできます。
私はまだ一四歳にすぎませんから、仕事はまだできませんが、学習の機会を与えてもらいたいのです。
私の人生の道のりはまだ長いです。
いろいろな困難が待っているでしょうが、自信と気力をもって私なりに困難を乗越える方法をあみだせると思います。
私は必ず与えられた学習の機会を大切にし、一生懸命勉強したいと思います。……」
そして力を認めてくれたのです。
教育長は「今はもう公立高校の募集は終り、まもなく私立高校の募集が始まります。
『樹範(じゅはん)高校』への出願を認めてくれるよう校長先生に連絡をとってみましょう」と言ってくれました。
この教育長は喋仲武(きんちゅうぶ)といいました。一九九三年に高さんは、この元教育長喋仲武さんを訪ねあてました。
再会して当時のことをあらためて伺いました。「当時高さんのようなケースはたくさんありました。
できるだけ学生の意思を生かす方向での処理をしました」と話していました。
こうして高校に合格できましたが、合否判定の会議は相当にもめたということです。
少数の教師は「障害者の教育」に疑問をもっていたようです。
まだ障害者も国に役立つ人間に育てられるということを信じていない人が、ずいぶんいたというわけです。
大学進学の時も困難がありました。当時の規定では、身体障害のある人は理科系に進学することができず、中国文学・政治・歴史などしかできませんでした。
高さんは数学が好きで得意でしたので、数学系の大学に進学を希望していました。
国の建設のためということで、最後は認めてくれました。そして上海の復旦(ふったん)大学の数学部に進学しました。
6 卒業してからも top
|

1970年、結婚前の2人
就職の道も、けっして平坦な道ではありませんでした。
多くの人は高さんが就職してもきっとまわりの人に迷惑をかけたり、国の建設にも役立たない、と考えていたようです。
社会主義中国でもこういう状況でした。いくつかの就職先もあれこれの理由で断られてしまいました。
やっと一九六二年、江西省教育学院教師として就職することができました。
結婚などの家庭を持つことなどにも大きな苦労がありました。 |

1984年旧正月で奥さん一家と高さん(右端)
|
高さんは三度恋愛をしましたが、三回とも高さんが身体障害者だということでわかれました。
恋愛相手が断ったこともありますし、社会習慣の圧力に耐えられず、高さんを受入れてくれないケースもありました。
女性が身体障害者と結婚したら、世間のうわさの的になり、さげすまれ精神的なプレッシャーが大きいというのが多くの中国人の考え方でした。
結婚して高さんは妻のプレッシャーを軽くするために三ヵ月かかって何度も上海に通い、やっと義肢をつけました。
7 自分で証拠を集める top
大学に勤めるようになってから、高さんは自分をこんな目に遭わせた事実について確認したいと思いました。
なにしろ高さんが爆撃で右腕を失ったのはわずか四歳の時のことです。記憶も確かではありません。
だれでもそうですが、四歳の時のできごとを、何十年もあとになって再現するなど不可能なことです。
八〇年代にはいって、高さんはまず新聞広告をだしました。
永安市の空襲の事実を知っている人を搜そうとしたのです。
もっと早くからやろうとしましたが、中国の国のなかは文化大革命などがあって、戦争中のことをふりかえる余裕はありませんでした。
新聞広告の反響はありました。永安爆撃の当時の住民の中にも高さんのことを覚えている人がいました。
それらの人たちを訪ね、高さんは親子を運んでくれた人、病院の先生などを搜す努力を続けました。
高さんを手術した病院の先生は亡くなっていましたが、その家族に会うことができました。
高さんはお礼をいいながら、当時のようすを訊ねました。こうやって少しずつ証拠を集めていきました。
爆撃のようすを報道した新聞も手にいれることができました。
こうして一九四三年十一月四日という日時が特定できました。
爆撃からしばらくして永安市に住む画家であった薩一佛(さついちふつ)さんが「永安大災難」についての一〇〇枚余りのスケッチを書いたこともわかりました。
永安・南平・沙県などで展覧会をしたこともわかりました。
当時まだ日本軍の侵略が続いていたなかで、多くの人々に日本軍の暴行への怒りをわきおこしたということです。
現在この絵の行方はよくわかりません。
高さんはついに永安空襲の生き証人をみつけることができました。
自分よりも、もっとはっきりこの日のことを記憶している年配の方と遭遇することができました。
施財亮(せざいりょう)さんです。
この方は、この日の惨劇を目の当たりにした方です。その証言です。
「一九四三年十一月四日、私は朝から鍬をかついで東門街の野菜畑で作業をしていました。
十一時ごろ警報が聞こえて東門の上に赤い風船があげられ、敵の飛行機が近づいているのが知らされました。
私も急いで近くの川の淵に身を隠しました。
三〇分ぐらい混乱の状況がありましたが、敵の動きも特にはっきりしませんでした。
敵の飛行機は東から西へ飛んでいっておよそ一〇分後に消えました。みんなはほっとしていました。
しかし一時少し前だったと思いますが、敵の飛行機が突然現れて西北から東南にかけて猛烈に射撃し始めました。
爆弾は風雨のように落ちて人々を襲いました。
私はどうしたらいいかわからなくて、頭を抱えて山の麓に隠れていました。
しばらくたってから空は少しずつ明るくなって敵の飛行機は東の空へ消えていきました。
目の前の畑は砂・石・土に覆われて作物はすべてなくなっていました。
私は日本軍の暴行のひどさに涙があふれて仕方がありませんでした。
私は東門街に住んでいましたが、近くに大けがをした人がいました。
邵鋳華(しょうちゅか)さんとその息子の高熊飛さんです。
大同路は燃やされて家はすべてなくなりました。
李さんの家ではちょうど婚礼の式典が行われていましたが、警報にもかかわらず逃げ遅れた一三人がなくなりました」 |
と証言されています。
また、薩一佛さんの絵に詩を書いた賈子豪(かしごう)さんの作品が残されています。
「今夜ほどこの家に宿るか」
ここは猛烈な煙あり、 そこは火がある。
我々は今夜どこの家に宿るか。
鳥はもう巣に帰って、 日はもう暮れた。
我々は今夜どこの家に宿るか。
母は倒れそう、子供は疲れ果てた。
我々は今夜どこの家に宿るか。 |
|
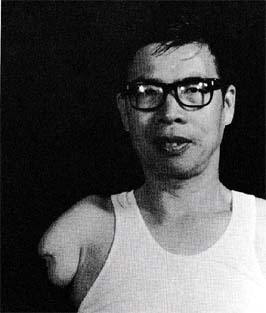
日本軍の無差別爆撃で右手を失った
|

一九九六年二月、父母と高さん(右端)
|
8 日本政府を訴える top
高さんは、こうして調べていくうちに、自分にこのような被害を与えた日本の軍隊、そしてその戦争をすすめた日本政府に責任を求めたいと思うようになりました。
一九九四年に日本から弁護士さんが来ました。
中国人戦争被害法律家調査団です。
尾山宏弁護土、小野寺利孝弁護土たちです。
高さんは、弁護土さんたちに自分の体験を話し、高さん自身が集めた資料を見せました。
高さんは日本人の中にも正義のために活動している人たちがいることを知りました。
高さんは、この弁護土さんたちを通じて、日本政府を訴える決意をしました。
一九九五年四月、この弁護土さんたちは、日本政府に対して高さんたちの声を代弁し、「中華人民共和国国民の日本政府に対する戦争被害損害賠償要求書」を提出しました。
この年の八月、日本の弁護士さんや法律冢たちが主催した「戦後補償国際フォーラム九五」に高さんは参加するため東京へきました。
そこで、高さんは自らの体験を語り、日本政府への謝罪と補償を求めました。
そのあとの十一月二九日、高さんは弁護士さんたちの援助で東京地方裁判所に提訴したのです。
高さんは中国にいて、東京の裁判所にはなかなかこれません。
日本の弁護士さんだちと連絡をとりながら、陳述書などをつくりました。
日本国内では、弁護上さんや良心的な人たちが中国人戦争被害者の要求を支持して運動を開始していました。
一九九五年五月二〇日に「中国人戦争被害者の要求を支える会」が結成されました。
代表委員には家永三郎、大田尭、中坊公平、藤原彰、本多勝一、森村誠一、松井やより、池辺晋一郎、寿岳章子、浅井基文氏らが就任しています。
この「支える会」は日本国民の中に、中国人戦争被害者の被害の事実を広げ、署名や集会、裁判を見守るなどの活動を続けています。
日本国内におよそ三〇〇〇人以上の会員がいて、中国の被害者を支えています。
機関紙「すおぺい『索賠』(中国語で賠償請求という意味)」を発行して、裁判のゆくえ、運動の広がりを伝えています。
高さんは、一九九八年七月、本人尋問のため日本にやってきました。
裁判所では、悲劇の体験を淡々と述べました。
裁判官の心にひびくような高さんの証言に裁判所は緊張につつまれました。
この来日の際、東京都内で証言を聞く集会をしました。
この集会には、東京大空襲で家族を失った金田茉莉(まり)さんもみえ、アメリカ軍による東京大空襲の悲劇のようすも証言しました。
無差別空襲ということでは、その被害に遭うのは、罪のないふつうの庶民であり、全くいわれのない悲劇です。東京でも中国でもそうです。
しかもこの戦争がなぜおきたかということでいえば、日本の軍隊が中国への無謀な侵略を開始したことから始まったわけです。
高さんの訴えは「無差別爆撃の被害にあったから、その責任をとって日本政府は謝罪と補償をしろ」というものです。
日本政府は高さんの訴えを受けて、裁判所ではどう主張しているのでしょうか。
普通の裁判では、訴える証拠になったものを原告が示し、被告がそれは本当のことかとうかを確認します。
事実の認否です。この場合、原告の高さんはたくさんの資料を基に日本軍の飛行機が爆弾を落とし、自分の右腕が失われたことを示しました。
ところが、日本政府は「事実の認否」を拒否しています。
日本軍による無差別爆撃は日本国内はもとより、世界中に明らかになっています。
歴史的な事件になっているわけです。
しかし被告の日本政府は、この事実を認めようとしません。
この事実を否定することもできないので、「事実認否拒否」という姿勢を続けているのです。
被告の事実認否なしでも裁判はすすみます。
その過程で日本政府の主張はふたつです。
第一は「古いことだ。もう解決ずみのこと」というのです。
日本政府は戦後、戦場になった各国に対して個別に交渉をすすめ、賠償協定などを締結しました。
中国とは一九七二年の日中共同声明で「中国政府は対日賠償請求権を放棄する」と書かれたことを盾にしています。
また民事訴訟では「時効」(除斥)というのがあり、一定期間たつと訴えの権利がなくなるというものです。
しかし「国と国の間の話合い」はついたとしても、個人の被害への補償という問題は未解決であり、しかも戦争責任には時効はないというのが国際的にも認められた議論になっています。
日本と同じくファシズムが支配したドイツでは戦争責任を明確にし、その個人の被害については永久に補償するということをはっきりさせています。
また国連の人権委員会で九六年には「慰安婦問題で日本政府は責任がある」(クマラスワミ報告)、九八年には「責任者の処罰」(マクドゥガル報告)が出され、日本政府の戦争責任を国際的に明らかにしています。
第二は「戦前は『国家無答責』という考えがあり、民間人は国家を訴えられない」というのです。
これこそ時代錯誤の考えです。天皇が絶対的な権力をもっていた戦前は、役人や兵隊の不始末があっても「国家の責任」を問えないという“法律”があったというのです。
だから、この場合も国家の責任はないというわけです。
これこそ誰の支持もえられない議論だと思います。
天皇は絶対に正しいから「悪」は行わない、という議論ですが、百歩譲っても「国家無答責」は明治憲法下の日本政府と日本国民との関係をいうのであって、中国人である高さんに適用することなどできるはずもないことは明白です。
9 社長が変わっても会社の借金は残る
top
高さんは、今回杭州のホテルで私たちの前で、その悲劇の体験を語りました。
杭州は風光明媚な町で、町の中心には三国史の時代からの遺跡や美しい西湖もあります。
上海からも列車で数時間というところにあります。
最近の中国の発展で大きなビルディングも立ち並んでいます。
杭州駅は目下改修中で、臨時の杭州東駅は人でごったがえしていました。
夜の屋台は奥地から出稼ぎに出てきた人たちが露店を構えていたりと、中国が大きな変動の中にいることも実感するような町です。
私たちが話を聞いたホテルも、最新の設備のそろった近代的なホテルでした。
ここで高さんは語ったわけですが、日本国内の「戦争礼賛、責任回避の動き」などにもふれ、日本の次の世代にこの事実をしっかり伝えてほしいことを強調しました。
また「悪いのは日本の軍国主義であり、これからの日中人民の友好が第一」という「現在の日本政府の責任をなしにしよう」という一部の考えにもきっぱりと「社長が変っても会社の借金はなくならない」とし、日本政府の責任を求め、謝罪と補償を要求していくこともあらためで明言していました。
top
****************************************
|