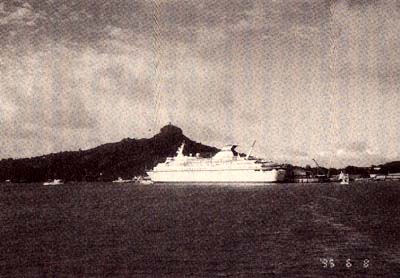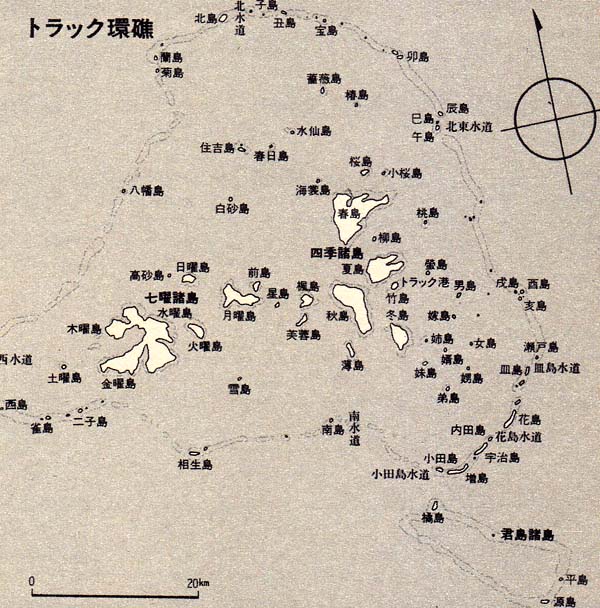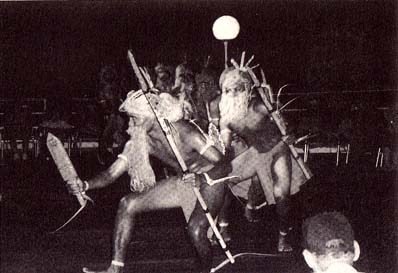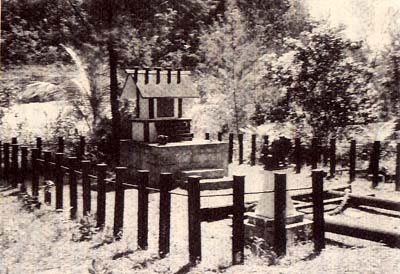|
1�@�����m�̔e��������������m�Q��
top
1.1 �A�����A�E�C���n�[�g�̖�
���㎵�N�܌������A�u�����V���v�[���̈�ʂɃJ���[�ʐ^����ŁA���̋L�����f����ꂽ�B
�@�@�@�@�@���͈����p����
�@�@�@�@�@�@�@60�N�O�Ɠ��^�@�����@�o���@�Ő��E���
�@�@�@�@�@�@�@�Ă̏������Ɖ�
�@�s���T���[���X28���g�c�O�V�t60�N�O��1937�N�ɑo���@�ɂ�鐢�E�����s�̓r���A�����m�ōs���s���ɂȂ��������ȕč��l�����p�C���b�g�A�A�����A�E�C���n�[�g����̖��̎�����ڎw���Ă����č��l�������ƉƂ�28���A�o���n�̃T���t�����V�X�R�x�O�̃I�[�N�����h���ۋ�`�ɒ����A�P�Ɛ��E�����B�������B
�@�e�L�T�X�B�̃����_�E�t�B���`�����i46�j�ŁA�C���n�[�g����̈�u���p�����߁A�����Ɠ��^�̃��b�L�[�h�А��o���v���y���@�u�G���N�g���v���4��6000���~�����ĕ����B3��17���A�I�[�N�����h��`���ї������B
�@�t�B���`����͓����ɃC���n�[�g����Ƃقړ����R�[�X�����ǂ�A�ԓ��߂���5�嗤18�������o�R���A���v��4��1600�L�����s�B
�@�C���n�[�g���s���s���ɂȂ����쑾���m���͒Ǔ��̉ԑ��𓊂����낵���Ƃ����B�i�����j
�@�t�B���`�����3���̕�e�B�e�L�T�X�B�암�̃T���A���g�j�I�s�ŗ×{�����o�c���Ă���B |
�@���̐����k�ɂ͌���k������A���т����т��q���C�����A���̌o�c����×{���̕s����E������A�h���̋A�����܂��ē��ǂɌ������ꂽ�Ƃ����̂ł��邪�A���̋L���̓A�����A�E�C���n�[�g�v�l�̔ߌ����߂���A�����̃A�����J�����̑����Ɉꌾ���ӂ�Ă��Ȃ��B
�@���O���N�Z���A�A�����J�̏�����s�ƂƂ��Đ��E�I�ɗL���������A�����A�E�C���n�[�g�v�l���A���b�L�[�h�u�G���N�g���v�o���@�𑀏c���āA�}�C�A�~��s��𗣗����A�v�G���g���R�A�u���W���̃i�^�[���A���A�t���J�̃_�J�[���A�V���K�|�[���A�W�������̃o���h���Ȃǂ��ւāA�z�m�����A�J���t�H���j�A�o�R�Ńj���[���[�N�ɂ����鐢�E�����s�ɔ�ї������B
�@���łɁA�N�ɏ����p�C���b�g�Ƃ��Ă͂��߂Ă̑吼�m���f��s�A�O�Z�N�ɂ͎j��͂��߂Ẵn���C����A�����J�{�y�ւ̒P�Ɣ�s�ɐ������Ă���A�ޏ��̖����͍��������B���̃C���n�[�g�@���A���悢�搢�E����̍ŏI�R�[�X�̓����Ƃ������ׂ��z�m�������߂����āA��������ɓ��j���[�M�j�A�̃��G�𗣗����āA���G�ƃz�m�����̒��ԂɈʒu����n�E�����h���i�L���o�X�����Őԓ��̂����k�j�Ɍ��������܂܍s���s���ƂȂ����B
�@�܂��Ȃ�����������ḍa��������������A�����푈���u�����������̎����ł���A�A�����������̔���������܂�A�C���n�[�g�@�͓��{�����������m�Q���̏��ŁA���{�R�̌R�������̔閧����邽�߂Ɍ��Ă��ꂽ�̂ł͂Ȃ����A�Ƃ̋^�f���捹�����ꂽ�B
�@�E�H���^�[�E�}�N�h�D�[�K���w�����m���E�x���́A�u�A�����J�����܂��A���{���閧�̂Ƃ�̗��ŃT�C�p���A���b�v�A�g���b�N�A�e�j�A���̏�����v�lj����Ă���̂ł͂Ȃ����Ƌ^�����肾�����B
�@���O���N�ɃA�����A�E�C�A�n�[�g�́w���b�L�[�h�E�G���N�g���x���n�E�����h���߂��i���{�ϔC�����̂̂͂邩����j�ŏ������ƁA�A�����J�l�̑����͓��{�̔w�M���^�������̂ł���v�Ə����Ă���B
�@�C���n�[�g�@�s���s���ɂ܂��č����̑����������āA��ܔN�Ԃɂ킽���m�Q�����߂�����ăX�p�C�����ɖ������낳�ꂽ�B
�@���̔N�A���V���g���C�R�R�k��������ē��Č��͋������ĊJ����A���{�͒����ւ̖{�i�I�N���푈���J�n���A�����m�̌R�������͌��R�̂��̂ƂȂ�A���ď��푈�����I�ɂ�荂�x�̎����ɓ˓���������ł���B
1.2 �C�����G���[�g���Z�̃X�p�C
�@�C���n�[�g�@�s���s����������ܔN�O�̈����N�āA�Z�[���X�}���Ǝ��̂��ė��������A���R�[�����ł̃A�����J�l���A���l�̃A�����J�C�R�a�@�Ɏ��e���ꂽ�B
�@�ނ̓A�����J�C�����̃A�[���E�g�E�G���X�����Ɛg���𖾂����A�a�@��E�����čs���s���ƂȂ����B
�@���{���݂̃A�����J�C�R�����͂��̒j�̑{������{�̓��ǂɈ˗������B
�@���炭�̂��A�j���d�a�̊�ď�ԂŃp���I�̃R���[�����Ŕ������ꂽ�|�̒ʒm�����{�̊C�R�Ȃ��炠��A�A�����J���l�C�R�a�@����Ō�l���h�����ꂽ���A�j�͂��łɎ��S���Ă���A�⍜�ƂȂ��ē����ɖ߂��ė����B
�@�⍜�������A�����Ō�l���ɓx�ɐ��サ�Ă����̂œ��@�������A�܂��Ȃ��֓���k�Ђœ|�ꂽ�����̉��~���ɂȂ�A���������B
�@�G���X�́A���Z���o�ĊC�����̉��m���ɂȂ������A���їD�G�œ�����N��ɏ��тƂȂ�A�j���[�|�[�g�̊C�R��w�Ɋw�̂������Ƃ��đ�ꎟ���ɏ]�R�����B
�@���A�C�����̊�{�I�C���͑O�i�w�n�̒D��ɂ���ƍl���A�����_���u�~�N���l�V�A�ɂ�����O�i��n���v�������A���ꂪ���N�����Ɂu���v�掵���c�v�Ƃ��Đ����ɏ��F���ꂽ�B
�@���́u���v�掵���c�v�́A�C�����̔C���𐅗����p����i���̊T�O�݂������̂��G���X�����ł������j�ƋK�肵�A����Ȍ�̑��킩�猻�݂ɂ�����܂ł́A���E�ɓƓ��̃A�����J�C�����̐헪���_��ł����Ă��B
�@�T�a�ɂ��������G���X�̓A���R�[���Ȃ��ɐ����ł��Ȃ��Ȃ�A����̌R�l�Ƃ��Ă̐E�ƓI�����������Ȃ��Ɗo�債�A���̑O�ɁA�������p���̑z����ł�����{�̓�m�Q���̖h�������n�Ɏ����̖ڂŊm�F���Ă��������ƍl���A�݂�����X�p�C�ƂȂ��ē�m�Q���ɐ��������̂ł������B
�@�A�����J�C�����̐������p��헝�_�̑n�n�҂ł���G���[�g���Z�̃G���X�������A�݂�����X�p�C��ړI�Ƃ��ē�m�Q���ɐ������ĕa�������̂ŁA���̎����ɂ��ăA�����J���Z�̂������œ��{�ɂ��d�E�Ƃ̉\�����������A���̉\���͂Ȃ��B
�@�l�C�T���E�~���[�w�X�p�C����푈�x�́A
�@�u�G���X�͎��R�������Ǝv���邵�A�i�����j����Ȃ��ƂɁA����E���œ�����̂���Ă݂�ƁA����Z�N��ɓ��{���B�����Ƃ��Ă����閧�Ƃ́A�R���͂���������Ă������Ƃł͂Ȃ��A���ꂪ�n�ゾ�������Ƃ����炩�ɂ��ꂽ�B
�@���O�ܔN�ȑO�ɒz���ꂽ�v�ǂ͂Ȃ��A���̂قƂ�ǂ͈��l��N�Ȍ�ɑ���ꂽ���̂������̂��v
�@�Əq�ׂĂ���B
�@���{�͈ϔC�����̂⑾���m�̏����̌R���֎~���߂��x���T�C�����ƃ��V���g�����𐽎��Ɏ��A��m�Q���ɂ��������R�������Ȃ������B
�@�������A�A�����J��擪�Ƃ��āA���E�͂����M�p���Ȃ������B
�@�h�q���w��j�p���x�́A�u��m�Q���̌R���ɑ���̋^�f�͂��Ȃ荪�[�����̂��������B
�@���ɓ��{�̃��V���g����c�p���O��͂��̒��_�ł������B
�@�C�R�͂��̊ԁA�I�n���d�Ȕ閧��`�������ėՂ݁A�O���͑D�̈�̊�q��f�ŋ��ۂ��A�܂������������������Ď����I�ɂ͊O���l�̓������s��s�\�ɂ������v�ƋL���Ă���A���{�C�R�̔閧��`�����p�̋^�f���Ƃ�F�߂Ă���B
1.3 �h�C�c�̃I�Z�A�j�A
�@�A�����J�̗��嗤�ƃA�����[�V�����A���A�W�A�̓��{�E����A�W�A�̃t�B���s�������E�C���h�l�V�A�̓��C���h�����A�I�[�X�g�����A�嗤�ɂ͂��܂ꂽ�L��ȑ����m�ɑ����̓��X���_�݂���B
�@�����̓��X�́A�n��I�Ƀ|���l�V�A�E�����l�V�A�E�~�N���l�V�A�̎O�n��ɕ������Ă���B
�@���̕��A�n���C��k�[�Ƃ��A�C�[�X�^�[���𓌓�[�Ƃ��A�j���[�W�[�����h�𐼓�[�Ƃ����O�p�`���������Â���n����|���l�V�A�Ɩ��Â��A�����萼�̒n��Ńj���[�M�j�A�����܂ސԓ��ȓ�̒n��������l�V�A�A�ԓ��Ȗk�̒n����~�N���l�V�A�ƌĂ�ł���B
�@�����m�̑��݂����E�̋��ʔF���ɑg�݂��܂ꂽ�̂́A�����m�̖��Â��e�ł���|���g�K���l�}�[�����i�}�K�������C�X�j�̐��E����q�C�Ȍ�ł��邪�A�}���A�i�����͈�ܓ��N�ɐ��E����r��̃}�[�����ɂ���Ă��̑��݂��m��ꂽ�B
�@�J�����������ɂ͈�ܓN�Ƀ|���g�K���l�f�B�A�S�E�_�E���V�����A�}�[�V���������ɂ͂��Ȃ��N�ɃX�y�C���l�T�A�x�h�������B�����B
�@�����~�N���l�V�A�̏�������Z���Z�N�ɃX�y�C�����̓y�ɕғ��������A�X�y�C���̂̒���Ăƃt�B���s�������Ԓ��p�n�Ƃ��ăO�A�����̊m�ۂɗ͂𒍂����ق��ɂ́A�X�y�C���͌Q�����̑��̓��ɂ��܂萭���I�ȊS�������Ȃ������B
�@�ꔪ����N�Ƀh�C�c�鍑�̓�������������h�C�c���x����ɐA���n�l���ɏ��o�������A�ꔪ���l�N�Ƀj���[�M�j�A�̃J�C�U�[�E�r���w�����E�����g�A�r�X�}�[�N�����A���ڂ����̃X�y�C���̂̃}�[�V���������A�ꔪ�����N�Ƀi�E�����̗̗L��錾�����B
�@����Ƀh�C�c�͈ꔪ���ܔN�Ƀj���[�M�j�A���������̖k�j���[�M�j�A���̂��A����ɂ������ăC�M���X�̓j���[�M�j�A���������̓�j���[�M�j�A�i�p�v�A�j�������ی�̂Ɛ錾���A�j���[�M�j�A���͐������̃I�����_�̂ƎO�����ꂽ�B
�@�h�C�c�̓J�����������ɂ���������X�y�C���ƕ������N�����A���[�}�@�����̒���ɂ��X�y�C���̗̗L�����F�߂�ꂽ���A�X�y�C���͈ꔪ�㔪�N�̕Đ��푈�ɔs��ăt�B���s���ƃO�A�������A�����J�Ɋ������A�O�A�����������}���A�i�E�J�������̓����h�C�c�����������B
�@�ꔪ���N�ɃT���A���A�����J�ƕ������Đ��T���A���A���Z�Z�N�Ƀ\�����������ɂ�����C�M���X�Ƃ̋��E���߁A�u�[�Q���r�����Ȗk���h�C�c�̂ƂȂ����B
�@�������āA��㐢�I���ɁA�h�C�c�̃I�Z�A�j�A�̗̈悪�A�\�����������̃u�[�Q���r�����Ȗk�E�k���j���[�M�j�A�E�r�X�}�[�N�����E�}�[�V���������E�J�����������E�O�A�����������}���A�i�����E�i�E�����E���T���A�Ɋm�肵���B
�@�Ȃ����Z�O�N�Ƀp�v�A�̓C�M���X�����̂���I�[�X�g�����A�̂ɕύX���ꂽ���A���̎�s�|�[�g�E�����X�r�[�́A�X��C�̊C�㌠�𐧂��A�I�[�X�g�����A���C�݂ɋ��Ђ��������邽�߂̌R���I�v�ՂƂȂ����B
�@�h�C�c�̃I�Z�A�j�A�̎�s�Ƃ��Č��݂��ꂽ�̂��A�j���[�u���e�����̓��k�[�̃J���f���p���`�Ƃ��A�X�H���R�Ƌ�悳�ꂽ�h�C�c���̐A���s�s���o�E���ł������B
�@�h�C�c�̃~�N���l�V�A�̐����͓��J�����������̃|�i�y���ɂ����ꂽ���A�|�i�y���̓h�C�c�̃~�N���l�V�A�ő�̓��ŁA��������v�ȓ��̒��Ńh�C�c�̃I�Z�A�j�A�A���n�̎�s���o�E������ł��߂������ɂ������B
�@���͑���Ńg���b�N�����o����n�Ƃ������{�R���쑾���m�̐��Ƃ������X�́A�C�M���X�̂ł������\�����������ƃM���o�[�g�����i�L���o�X�j�������ẮA���h�C�c�̃I�Z�A�j�A�A���n�ɑ������n��ł���A���̒��S�s�s�����{�R�ɂ���ăg���b�N���̑O�i��n�Ƃ��ꂽ���o�E���ł������B
1.4 ���{�C�R�̓�m�Q�����
�@����l�N�����ɑ�ꎟ��킪�͂��܂�ƁA���{�͓��p�����𗝗R�ɉ����t���̍Ō�ʒ��������ăh�C�c�ƍ��������ĊJ�킵�A���R���h�C�c�̃A�W�A�ɂ�����R�����_�ł��钆���R���Ȃ̐��i�`���^�I���P�B�p�j���U������ƂƂ��ɁA�C�R�͑��쌭�}������ё��쌭�}����Ґ����A�h�C�c���m�͑��̏��m�͑���ǐՂ���ƂƂ��ɁA�㌎�����̃����[�g����̂���n�߂Ɉ�Z����l���̃T�C�p������̂������āA�h�C�c�̃~�N���l�V�A�̎�v�ȏ����̐�̂��I�������B
�@���[���b�p�̎�v�ȏ����������ꂩ�̑��ŎQ�킵�ă��[���b�p�̐��ɗ͂��X�����A�����m���ʂ�������݂�]�T���Ȃ��Ȃ����@��ɕ֏悵�����{�̃����[�g����̂ɂ������A���̂���܂��������ł������A�����J�Ŕ������_���N��������A�������C�M���X���܂����O���������̂ŁA���{�C�R�͐ԓ��ȓ�̃h�C�c�̃I�Z�A�j�A�̊C����s���͈͂��珜�����B
�@�ԓ��ȓ�ł͐��T���A���j���[�W�[�����h�R�A���k�j���[�M�j�A�E�r�X�}�[�N�����E�u�[�Q���r�����Ȗk�ƃi�E�������I�[�X�g�����A�R����̂����B
�@�ŏ��O���Ȃ͑ΕĊW���l�����ē�m�Q�����̂����A���G����уh�C�c�R����{�݂̔j��Ȃǂ��I����Η��ォ��P�ނ�����j�ŁA�C�R�R�ߕ��������͑��쌭�}���i�ߊ��ւ̊o���Ɂu����ɉ䂪������g�����邱�Ɓv�ƋL���Ă������A���n�͑����狭�d�ӌ����o����A�C�R��b�ƌR�ߕ��������c�̌��ʁA�o������u�O�L�̑[�u���I�肽���͑��ɗ�����P�ނ��ׂ��v�̕������폜���A��̌p���̕��j�ɓ]�����B
�@�I�[�X�g�����A��C�M���X���ԓ��ȓ�̃h�C�c�̂̉i�v��̂���}���Ă����̂ŁA���p�Ԃ̔閧���������Ȃ��A�h�C�c�̂t�{�[�g�ɑR���邽�߂ɓ��{���쒀�͑������[���b�p�ɔh�����邱�Ƃ������ɗ��҂̑Ë����������A��l�N��Z�������A���{�̉��������O����
�@�u�ԓ��Ȗk�̓Ɨ̏����̉i�v��̂��咣����͓��R�v
�@�u���ړI���ѓO���邱�ƂɏA�āA�p�����{�̉�����M�����v
�@�Ɛ������A�̂��̍u�a���ɂ����ē��{�ɂ���m�Q���̗̗L���C�M���X���x�����閧�����������Ƃ����������B
�@�Ƃ���ŁA��m�Q���̉i�v��̂ɂ��āA���n�i�ߊ��͂ǂ̂悤�ɕ]�����Ă������B
�@�������Y���쌭�}���i�ߊ��͏H�R�^�V�i���˂Ȃ�j�C�R�ȌR���ǒ����Ă̏��ȂŁA
�@�u�R����̉��l�Ƃ��Ă͉������Ȃ鉿�l�Ȃ��A�������ɐ�ߒu����Ă͍��̐i�s���s�@���i�ӂɂ傢�j�̂��Ƃ���䂦�Ɖ]���ʂ��ւ̎R�ɂāA�i�����j
�@�̂ɉ���̓��ł��X�����ґ�ɍl���Đ������̓�A�O�ǂ���u���i���炢�j�Ȃ����i��j�B
�@�V�ɔ����ď�����ɂĂ͑�W����A�R���䂪��m�f�Ղ̐U�킴��ꌴ���͕t�߂ɋ��_��L�������i����j��v |
�@���Ƃɂ���Əq�ׂĂ���B
�@�܂�C�R�ɂƂ��Đ헪��̉��l�͔F�߂��������A���{�o�ςɂƂ��Ẳ��l���傫���Ƃ����]���ł������B
�@�܂��q��@�����B���Ă��Ȃ����������A�����m��ɐ�݂���~�N���l�V�A�̏����Q�̂����A�A�����J�̂̃O�A�������ő�̓��ň�㐢�I������ߌ~�D��n�Ƃ��Ďg��ꂽ���т������A���̓��ɌR����n�Ƃ��Ẳ��l��F�߂������Ƃ����̂͊m���ł��낤�B
�@�A�����J�ɂ��Ă��A�����̓n���C�ƃt�B���s�������Ԓ��Y�E���Y�̒��p��n�Ƃ��Ă̖������O�A�����Ɋ��҂����ɂ������A�~�b�h�E�F�[���̌R���I���l���F�߂Ă��Ȃ������B
�@�u�������ɐ�ߒu����Ă͍��̐i�s���s�@�ӂ̂��Ƃ���v�Ƃ������A���͓��ĊW��A��m�Q���𒆗������̗L���Ă����������{�ɂƂ��čD�s���ł������Ƃ�������B
2�@���{�̓�i��n�g���b�N�����߂�����
top
2.1 �쑾���m�ւ̃N���[�W���O
�@����ܔN�Z���O���ߑO��ꎞ�߂��A�������v�w�͓����`���C�i�͂�݁j�q�D�u���ŏ�D�̃`�F�b�N�C�������A���炩���ߑ�z�ւő����Ă������ו������A�o���葱���I���Ĉ�O���߂��ɏ�D�����B
�@���蓖�Ă�ꂽ�D���͑��f�b�L�����t�ߍ����̑����Ђ낢�c�C���E���[���ł���B
�@�����ɓ���ƍ��������b�J�[�l�l���A�E�����V�����[�E�g�C���b�g�E���[���A�����ʂɃe�[�u��������A�����ɓ�i�x�b�h�ŁA�Ǎۂɗ��ĂĂ����i�̃x�b�h�����낹�Ύl�l�����ɂ��Ȃ邪�A�ʏ�͉��i�̃\�t�@�[�E�x�b�h�������g���c�C�����[���Ƃ��Ďg���Ă���B
�@�E���x�b�h�ƃV�����[���̂������ɂ͑傫�ȋ��̉��ϑ䂪���Ă���A�����͂܂��z�e�����݂ł���B
�@�傫�ȑ����琅�����܂Ō��킽���A���H�ł͍����̂��̕�������A����Ă���A�Q�Ȃ���ɂ��Đ���������̓��̏o�����邱�Ƃ��ł���B
�@�������͈���ܔN�́u�q�[�X�{�[�g�쑾���m�̑D���v�ɎQ�������B
�@�Z���O���ɓ����`�o�`�A
�@�������~�N���l�V�A�A�M�̃g���b�N�����`�A���̓��̖�o�`�A
�@�����[���\�������������K�_���J�i�����̃z�j�A���`���`�A
�@�������[���o�`�A
�@��l�����߃p�v�A�j���[�M�j�A���̃��o�E���`���`�A
�@����ܓ��ߌ�o�`�A
�@�ꔪ���[���p���I���a���̃R���[���`���`�A
�@�������[�����`�o�`�A
�@�����ĉ����I���܁Z���N�����̘Z����O�����ɓߔe�`�ɓ��`���ė[���ɏo�`�A
�@��ܓ����߂��ɑ�k�Ђ��甼�N��̐_�ˍ`�ɓ��`���ė[���ɏo�`�A
�@��Z���[���ɓ����`�ɋA�`���D�Ƃ�����l���Ԃɂ킽�闷���ł���B
�@���̃N���[�W���O�́A���{�̓�i��n�Ƃ��Ē��������m�ɂ�����A���͑��̒��j��n�Ƃ��ꂽ�g���b�N���A
�@�����m�푈�ɂ�����쑾���m�̑O����n�ł���Â������o�E���A
�@�����m�푈�œ��Ă̍U��̗��ꂪ�t�]���A���{�̔ߎS�Ȕs��̍ŏ��̈���ƂȂ�쓇�i���Ƃ��j�ƌĂ��ɂ��������K�_���J�i�����A�����āA���{�̐A���n��m�Q���̍s�������ł������R���[������A���̏Z�ވ�錧�̋��y�A���A���˂̕������A�����E��ꓬ�̂����S�ł������A���̕���Ԃ���̓G�A�����J�掵�͑��̋��P�g���͖͂̊��ɂ̂����y�������[���i�A�����J�C�����������m�̐������p���ɋ�킵���^�����A�y�������[�A�C�I�[�W�}�A�I�L�i���̓������A�g���͖͂̊��ɂ̂����ꂽ�j�̂���p���I��K�₷�闷�ł���B
2.2 �E�N���C�i�D�J�����A��
�@�N���[�W���O�Ƀ`���[�^�[�����D�̓E�N���C�i�D���i�I�f�b�T�`�j�̃J�����A���i�ꖜ�܁Z�Z�ܑ��g���j�A���D�̓t�B�������h�A�w���V���L�̃����`�����D���A�D����N�A���q���x�ꎵ�m�b�g�A�ō����m�b�g�A��q������Z�B
�@�N���[�̓E�N���C�i�l�����A�^�q��Ђ̓V�h�j�[�ɖ{�Ђ�����b�s�b�N���[�Y�E���C���B
�@���C�E�G�[�Q�C�N���[�W���O�p�̋q�D���`���[�^�[�����̂ł��낤�B
�@���̃I�[�X�g�����A�؍݂��o�����A�����ɂ��傴���ςȃI�[�X�g�����A�����j���[�̐H������m�鎄�����ɂƂ��āA���̑D�̐H���Ɋ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A������Ƌꂵ���B
�@��D��A��O�����ɒ��H�A�o�C�L���O�E�e�[�u�������������������Ōy���ς܂������A�ʂɃ����`�E���j���[�̗������������̂��ƁA���Ƃŕ������ꂽ�B
�@��l���o�`�A�J�͗l�̊C�͑����r��Ă���B�Ƃ��ɓ����p���o�����ƁA�{�B��݂ɒ����v���~�J�O���߂����ċ����앗���������ނ��߁A���Ȃ�g���r���B���̂��ɑD���h��Ȃ��B
�@�Ƃ��Ƀ��[�����O���قƂ�ǂȂ��B
�@�D�ɂ����X�^�r���C�U�[�̌��ʂ�����Ȃɑ傫���ƒm��A���㑢�D�Z�p�̔��W�̐��ʂ��͂��߂Čo�����邱�Ƃ��ł����B
�@�ꔪ�����Ƀf�B�i�[�A�\�������Ƃ���H�ނ̑I�肪�m���i������j�ŁA�����͂��܂��Ȃ��B
�@�R�[�q�[���g�����~���N���������B�H�O�Ƀ��C���𗊂�A�n�[�t�{�g���̃e�[�u�����C���͂Ȃ��Ƃ����B
�@�O���X����Ȃ炠��Ƃ������A���߂ă��C�������͂��܂��I�[�X�g�����A�E���C�����ς�ł���ƁA�v�����Ƃ�����B
�@�����ɋA���ĂЂƖ��肵���B
�@��ꎞ�����ɖڂ��o�܂��ăo�[�ɍs���B
�@���{���̊ʃr�[������E���h���A���C��̑D�ŖƐł̂͂������A������ƍ�������B
�@������͎萔���Ƃ��ň�h�����Z�~�ŗ��ւ��Ă���̂��B
�@��h���D�ŕ����ƁA�d�݂̂��ނ肪�Ȃ��Ƃ����ē�{�ŘZ�h�����ꂽ�B
�@�����Ƃ��A���̌��́A���Ɋ���Ă���ɂ��������ė����ł��A���������������悤�ɂȂ������A�����������~���h�������}�i�s���A��ܔN�O���ɋ�Z�~������h���̈ב֑���͎l���ɂ͔��܉~���A�������̗��s���Ɉꎞ�I�Ɏ��Z�~��ɂ܂ŗ�����Ƃ����ُ펖�Ԃ��������B
�@�h���̌��Ђ��S�����Ă��������Ƃ��ŁA�o�[�̎x�����Ȃǃh�����~������Ƃ킩��A�~�ŕ����悤�ɂȂ��Ă���ɂ킩�ɐe�ɂȂ������A���i�����Ȃ芄���ɂȂ����B
�@�������đD�̒��ł́A�����Ă��̂��Ƃ͉~�ŊԂɍ����悤�ɂȂ����B
�@���{�ɋA�q���邱�̑D�̏ꍇ�A�~��������������Ȃ̂��B
�@�q�C����ڂ̘Z���l�����A������{�B��ɉ������~�J�O���̉���˂���A�O���ɐ������ޓ앗���܂Ƃ��ɎĂ̍q�C�ł���B
�@�J�_���Ⴍ���ꂱ�ߕ����悭�g���r�����A�D�̓��h�͂��قǂł��Ȃ��B
�@���Z���ɋN���A�V�����[�𗁂сA�J�V�Ȃ̂Ń~���[�W�b�N�E�T�����ł����Ȃ�ꂽ���W�I�̑��ɎQ�����A�I����ď�b�̃o�[�Œ��̂����B
�@�e�B�[�����̂ނƁA�J�b�v�̃e�B�E�o�b�O�ɓ��ƃ~���N�𒍂��ł��ꂽ���A���͗Β��ł���B
�@�Β��Ƀ~���N�͂͂��߂Ă����A���̌��ɍ���Ȃ��B
�@��������̓R�[�q�[�ɂ��邱�Ƃɂ����B
�@���H�́A���j���[�ɋL�ڂ̗m��H���A�o�C�L���O�����̘a�H���ŁA��������X�[�v�݂͂��`�A�����ɔ[���̘a�H�����݂����A�тɂǂ��̕Ă��g���Ă���̂��A���������I�[�X�g�����A�ŐH�ׂĂ����I�[�X�g�����A�Y�Ă��܂����B
�@����ɒ���čq�C���A��x�ƒ��̘a�H�͌��ɂ��Ȃ������B
2.3 �N���[�U�[�̑���Ǝd�g��
�@�ߑO���ɑD�̒����ЂƂƂ���T�������B
�@�ŏ�̃u���b�W�E�f�b�L�̑D���̂������ɓǝꎺ������A���K�̃{�[�g�E�f�b�L�̑O���ɃX�C�[�g�E���[����������уf���b�N�X�E���[���Z���A�f�b�L�̂��������Ƀv�[���ƃJ�E���^�[���̃l�v�`���[���E�o�[�A�����ăf�b�L�̍��E������O��Ɋђʂ���L�����A�C���ɂ�����Ȃ���Ǐ������蒋�Q�����肷��̂ɓs�����悢�f�b�L�E�`�F�A�̍s��ł���A�U���f�b�L�ł�����B
�@��b�͑O���Ƀ~���[�W�b�N�E�T�����Ƃ������̑�W��A���ʼnE�Ƀ��[�j���O�E�e�B�[��������͎����o�����l���̍��k�ɓK���������ȃh�j�F�v���E�o�[�A���͑�H���A���̌���͒��H���ŁA���̌��ɑD���ł�����傫���_���X�E�t���A������T�h�R�i �j�E�o�[������B �j�E�o�[������B
�@�Z�J���h�E�f�b�L�ƃT�[�h�E�f�b�L���D���ŁA�Z�J���h�E�f�b�L�̌������̃��[�����傫�ȑ��t���̃c�C���E���[���ł���B |
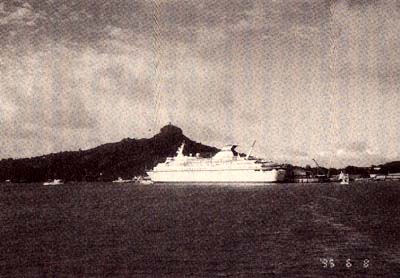
�g���b�N�����̃��G�����i�t���j�ɒ��݂����J�����A��
|
�@�t�H�[�X�E�f�b�L�̒������ɉf�掺�Ƃ��ׂ̗ɖ锼�߂��܂ŊJ���Ă���~���[�E�o�[�����邪�A�~���[�E�o�[�ׂ̗����x�̍q�C�ł͊J���Ă��Ȃ��J�W�m�ŁA���̃o�[�͂���J�W�m��p�o�[�ł���B
�@�D�͍����ɏ�����ĊC�������f���炵���A���̓��̌ߑO���ɔ��䓇�t�߂�ʉ߂����炵���B
�@�܂��ē����������A�C�̐F�͂�����ł��邪�A�C���͂悭����ł��āA�D��������Ă��Ă��g�̌��̍q�Ղ͂��ꂢ�ȕɐF�ł���B
�@�������A���Ȃ�͂��������˂�̊C�ʂ͍����F�ł���B
�@���ꂪ�����̐F�Ȃ̂��ȂƎv���B
�@�N���[�W���O���������邩�ǂ����̔����͐H���A�̂���̔����͒����D�����q�ɖO�������Ȃ����߂́A�D���ł̂��܂��܂ȍs���̊�掟��ł���B
�@����̃N���[�W���O�͓쑾���m�̐�Ղ̗��������ł��邩��A���Ă̎��������̐���K�˂�쑾���m�̐��A��̋��R�����̘V�l���������Ȃ����Ă���B
�@�����ł܂��A�l����O��������A�u�Q���ґ̌��k�E�݂�ȏW���A�쑾���m�ɂ����閲�\�\�v���o�Ɍ��푈�v�̉�J���ꂽ�B
�@���̌�����͐��X�����̌�����邪�A�����̐푈�̌��̋q�ϓI�Ȉʒu�t����������Ƃ��Ă��Ȃ��̂ŁA����͕ʂƂ��āA�푈�ɂ�������{���I�ȏȎ@���Ȃ��A���ǂ͐��̌��̎����b�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�Ƃ��ɍ���̐푈�̌���D�҂܂���̐����c��̑����́A���͍őO���łȂ��A�O���ւ̕�⋊�n�ɂ����Ȃ��������o�E������̐��Ҏ҂������B
�@����k�ڂ̒n�}���d�˂��킹�Ă݂�킩�邪�A���o�E���𓌋��ɏd�ˁA���{�����̊C��ɉ������Ă݂�ƁA�p�v�A�j���[�M�j�A�̃|�[�g�E�����X�r�[���k�C���̏��O���ɏd�Ȃ�A�u�i�͏H�c���\�㉫�A���G�E�T�����A�n��͋{�Â��甪�˂ɂ����闤���C�ݖk���A�_���s�[���C�������Εt�߁A�K�_���J�i�����̓��[���Δn�̖k�[���A�j���[�W���[�W�A�����������̏��]���ӁA�u�[�Q���r��������[�i�_�C���j���O��{�Â�����A�����k�[�����É��ɑ�������B
�@���o�E���𒆐S�Ƃ�����͂��̂悤�ɍL�傾�����̂��B
�@���o�E���ɂ��āA�K�_���J�i������u�[�Q���r�����̗���̉��A�j���[�M�j�A�̐��̔ߎS���������ł��܂��B
�@�������A�����̉�Ȑ�ꂩ��͂ǂ�قǂ̐l�������҂��Ȃ��������A�܂��Ă��̑D�ɂ͂���琶�Ҏ҂͏�荇�킹�Ă��Ȃ��B
�@�Ⴂ�l�����ɕ������������������������̂́A�{���͂��������N����������Ȃ��b�Ȃ̂��B
�@�l���ꔪ���l�ܕ�����A�D����ẪE�F���J���E�p�[�e�B�[�B
�@�~���[�W�b�N�E�T�����ł̃J�N�e���E�p�[�e�B�[�A�D���ȉ��̃N���[�����̏Љ�Ɗ��t�̂̂��A�H���ɐȂ��ڂ��ăf�B�i�[�A���̌�܂��~���[�W�b�N�E�T�����ɖ߂��āA�D���E�E�F�[�g���X�E�X�e���A�[�f�X�����ɂ�郍�V�A���w�Ɩ������x�̉�A���̑D�ɂ́A��^�N���[�U�[�ł���ȏ㓖�R�ł��邪�A�ꑮ�̊y�c������Ă��Ă��̃o���h�}�X�^�[�������œT�^�I�ȃ��V�A���l�ł���B�������̗��͖�̊w�K������A�ޏ��̏o�Ԃ����Ȃ������̂͋C�̓łł������B
2.4 �������z����ΊC�͍���
�@�Z���ܓ��̑����ɖڂ��o�܂��A�L���r���̑�������̏o�������B
�@�D���~�J�O���̓쑤�ɂʂ��o�āA���̐������̉_�C�͂悢���_��ɓ����p���������͎̂l���l�ܕ��A�D�͂قړ��o��ܓ�x�̃g���b�N���Ɍ������Ă���̂ŁA�D�̌��݈ʒu�͓�����肩�Ȃ蓌�ɂ�����A�Ď����߂����̋G�߂̓��̏o���Ԃ͓��{���ԂŌv����Ȃ葁���B
�@�C�̐F�́A�����̍����F���率���ւƕς���Ă���B
�@�Z���O�Z���A�u���b�W�E�f�b�L�̃R�[�g�Ń��W�I�̑��B
�@���̋�͒��̃X�R�[���ŁA�݂��Ƃȓ������������琅�����܂ł�������Ɣ��~�`���������Ă��������B
�@�V�C���悭�Ȃ����̂ŁA�ߑO���̓ԂقǁA�f�b�L�ŊC���ɂ�����Ȃ���Ǐ����y���B
�@�����ߑO���̓ԂقǁA�����̑|����x�b�h�E���[�N�̂��߁A���Ȃ炸�������˂Ȃ�Ȃ��B
�@�ߌ�͌������w�����i���w�j�̉͌���j����Ɛ푈�F���ɂ��Ĉӌ��̌�����������ȂǁA�q�[�X�{�[�g�̌����͂��߂ĂłȂ��͌�����́A����̍q�C���Ɏ�����Ńe���r����^�悵�������m�푈�L�^�r�f�I�̏�f����l���Ă���Ƃ̂��ƁA���傤�ǎ����ڂ����N�\���쐬���Ă����b�������̂ŁA������e�L�X�g�ɉ�����邱�Ƃɂ����B
�@���o��O��x�܁Z���̓����`���瓌�o��ܓ�x�̃g���b�N���Ɍ����A�D�͂�Ⓦ���̐j�H���Ƃ�Ȃ����H�쉺���Â����B
�@�g���b�N���̎�v�ȓ��X�́A�k���x���玵�x�l�Z���ɂ����ē_�݂��Ă���̂ŁA�D�͘Z���̍����A�k��A�����z���ĔM�т̊C��ɂ͂���͂��ł���B
�@�C�̐F����⎇�����������Ƃ������A�����ȐF�ɕς�����B��������̑����m�̐F�͌��Ǎ��ɂł͂Ȃ������B
�@�����D���R���Ă锒�g�̖A�������č��̊C�ɖ߂�ߒ��œ������̂悢���ɂ̐�����������Č������牓�������Ă����B
�@�l���Ă݂���A�푈���ɓ����p�ƃg���b�N�������Ԓ��s�q�H�𑖂����͑D�́A�g���b�N�����A���͑��̊�n�ł����������ł������A�ǂꂭ�炢���������낤���B
�@�����̊͒��͌���⋋�E�C���E�x�{��n�Ƃ��A���˓��C����L�㐅�����o�āA�T�C�p�����܂��̓}�j�����o�R���A�ꍇ�ɂ���Ă̓p���I�����ւăg���b�N���ɐi�o���Ă����B
�@�ɓ���������ɂ����̂��͓��e��������A������Ȃ������m�̂ǂ܂�Ȃ����A�Ђ�����ŒZ�����Ńg���b�N���Ɍ������q�H�͂Ȃ�Ƃ������ȋC���ł���B
3�@���N�l�Ԉ��w�Ɠ��{�l���l����������������
top
3.1 �Ȃ��R�p���z��Ȃ̂�
�@�Z���Z���ߌ�A�~���[�W�b�N�E�T�����ŃV���|�W�E���u�Ԉ��w��肩�猩�����⏞�v���������̂ŎQ�������B
�@���_�̍Ō�Ɏ������˂Ă���̎��_���q�ׂ��B�������e���̓��L������p���Ă������B
�@�]�R�Ԉ��w�Ƃ������t�͎g���Ăق����Ȃ��B
�@�Ȃ��Ȃ�A�ޏ������͐펞���ۖ@�ł���p�[�N����@�K�ɋK�肷��]�R�҂łȂ��A���������ăW���l�[�u���Ō��҂ɏ�����ҋ����߂��̓K�p��F�߂��Ȃ����炾�B
�@�ޏ������͗A���D�ɏ悹��ɂ��R���i�Ƃ��ĕ��i�������ꂽ���A�l�i�Ȃ��z��Ƃ��Ă����ҋ�����Ȃ������B
�@�l�i�Ȃ����┵�ɂ������ď]�R�ł͂Ȃ��R�p�Ƃ������̂����������Ă������i�R�n�������ɂ͌R�p�n�C�ł���j�A�܂��������̈Ӗ����炷��Δޏ������̈����͌R�p���z��ɂق��Ȃ�Ȃ������B
�@���ɁA���ݖ��ɂȂ��Ă��鋭���A�s�Ԉ��w�����A�j���̐����ʈ�ʂ̖��┄�t���Ƃ��Ȃ������̖��Ƃ��ċc�_����͔̂����Ă������������B
�@���̖��͂���Ȃ�Љ���ł����ʖ��ł��Ȃ��A���Ƃ̌R�����x�̖��ł���B
�@���̂��Ƃ�F�����Ă������������B |
�@�Ñ�ȗ��A���E���̌R���̉����ɔ��t�w�̐��s���t�����̂ł������B
�@�������A�Ȃ��A�����̑��ŁA�L�͂Ȓn��̐��ɂقƂ�ǂ��܂Ȃ��A�����A�s�Ԉ��w�ɂ��u����Ԉ����v�Ȃ�O�㖢���̌R���{�݂��A���{�R�ɂ����J�݂��ꂽ�̂ł��낤���B
�@���{�ł����I�푈�̌��I�L�^�E�R��̕E�����̓��L��莆�ɁA��n�ɐi�o���A�R�����ڂɂ��̉c�ƂƐ��a�\�h�q�����Ǘ��������t�Ƃ̘b�������Ώo�Ă���B
�@�������A����́A��n�ɐi�o���Ă������t�Ƃ��R�I���I�ƌR�q���̈ێ��E��̒n�R���̗��ꂩ��Ǘ������̂ł���A���t�Ƃ̌R���{�݉��ł͂Ȃ������B
�@���m�����̎莆����L������ƁA��n���t�̒l�i���������Ĉ�ʕ��m�̑��������������Ɩ����̑��݂ƌ��Ă����悤�ł���B
�@���{�R��Z�Z���̑�R���n�ɑ��������I�푈����푈�ł��������A���[���b�p�̂��ׂĂ̑卑�A�̂��ɂ̓A�����J���Q�킵�A���ׂĂ̍����������������̗p���đ啺�͂����ɑ���A�Λ����Č݂��ɏ���Ȃ�������ƂȂ����̂���ꎟ���ł������B
�@������P�����A���m�����͚͍������Ɍ��݁A���Ӗ��Ȏ������������A�}��C�����Ђ낪�����B
�@�e���̑O�������ɔ������N���������A�킯�Ă�����Z�N�̃t�����X�R�ɋN�����������͊낤���t�����X�R�̑S����̕�����������˂Ȃ������B
�@�����قǑ����̕��m���R�@��c�ɂ������A����畺�m�ɂ��������ʏ��Y�������Ȃ�ꂽ���A���Ԃ͉������Ȃ������B
�@���m�����̕s�����������邱�Ƃ��挈�Ƃ��ꂽ�B
�@�������đ����Ζ��̕��m�����ɂ���������Ζ��ɂ��x�ɐ��x���������ꂽ�B
�@���̐��x�́A����ɂ�����A�����J�R�⒩�N�푈�E�x�g�i���푈�ɂ�����A�����J�R�ɂ������p���ꂽ�B
�@���N�푈�̂Ƃ������̗����n���ӂ��ČR�ړ��Ă̔��t�X�Ɖ����A�x�g�i���푈���̉���̉Î�[��n���ʂ̃R�U�i����s�j��掵�͑��̊�n�̉��{�ꂪ�ČR�̈����Ɣ��t�̒��ƂȂ����̂��A���̌��Ζ��ɂ����A��̋x�ɕ��m�����̋C�U���̏�Ƃ��ꂽ����ł���B
�@��㔪���N�Ɏ����V�h�j�[�ɍs�����Ƃ��A�����܂���̏��X�c�Ƃ�������Ă��Ȃ������I�[�X�g�����A�̗�O�I�Ȗ�̔ɉ؊X�A�L���O�Y�N���X���ӂ̃r�W�l�X�E�r���X�̈Â���̊p���ƂɊX���������Ă���̂��A�^�N�V�[���猩�����ċ������B
�@�����Δޏ������̓e���E�_���[�E�K�[���ƌĂ�Ă��邻�������A���̌ꌹ�̓x�g�i���푈���̋x�ɕĕ�����̔��t�w�����̕t�߂ɏW�܂�A���̔��t���ꂪ��Z�h���ł��������Ƃɔ�����Ƃ����B
�@�I�[�X�g�����A�̓x�g�i���푈�Q�퍑�ł���A�x�g�i������C�^�̋����������{�̉���ɂ���ׂāA�V�h�j�[�͕ĕ������났�₷���x�ɒn�ł������Ǝv����B
3.2 ���{�ŗL�̌R���{�݁E�Ԉ���
�@��ꎟ���ȍ~�́A�啺�͂ɂ�钥�����R���������Ă��钷����ɂ����āA�������m�̌��Ζ��ɂ��x�ɐ��x�͕s���̐��x�ƂȂ����B
�@�������A���̐��x�����Ȃ������̂����{�̌R���ł������B
�@�]�E�o���E�V��@����ȂǂŌ���̓s�s����n�Ɖ�������@����鏫�Z�Ƃ������A�����Ζ��������ɂ킽��x�ɐ��x���Ȃ����{�̕��m�����́A���̓��̂��ƂƂ��킩��ʖ����̏��W�����݂邾���ŁA���������m��ʐ����̊댯�ɋ��₩�������X�𑗂�˂Ȃ�Ȃ��������A���̐��_�I�ْ�����̑��̊Ԃ̉���̋x�ɂ����^�����Ȃ������B
�@���m�����̋C���͍r�i�����j�݁A�Փ��I�ŗ��J�I�ȋ������������������B
�@���O�ܔN���̒��������Ō��Ƃ��Ē��W����O�Z�N�ꌎ��Z���ɓ��c�����O���N���̓�N�������́A���̔N�̎�����Z���ɏ����A�x����\��ł������B
�@����������ḍa���������N����Ɣ�����A���R�����R��b�͋��s�Ȑ��̎t�c�̏����̉����𖽂����B
�@�ނ�͂����炭�����R���Ȃǂ̕Ԕ[�葱���I���Ă���A����͑��ʍs���ŕ��A��Z���̌ߑO���ɂ͕����ɒ������ĕ��c�̖���o��\����A����O�ɓˑR��������A�t�ɐ��ւƋ��o�����H�ڂɂȂ����B
�@���s�Ȑ��̌����t�c�ŁA��̓싞�U���ɉ�����������ɁA�F�{�̑�Z�t�c�A���s�̑��Z�t�c�ƁA�l���̑���t�c�̈ꕔ���������B
�@�싞�s�E�����ōł��������Ƃǂ납�����̂����s�̑��Z�t�c�ł������B
�@�F�{�̑�Z�t�c�̕]�����悭�Ȃ��B
�@���Z�t�c�͎t�c�����헪�P�ʂ̕��c�����邾���̐l�i�E��ʂ̎���łȂ������Ƃ������Ƃ��w�E����Ă��邪�A���{�������Ɛ푈���͂��߂Ȃ���A���N�O�ɌR����E���Ō̋��ŕ��a�ɉƋƂɏ]�����Ă����͂��̕��m�������A�������O�Ɍ�������������Đ�n�ɑ����A�����̐�F�����̐펀�ɓ��h���Đ��_�̕��t�������A�S���r��ŁA�����E�s�E�E���D�̎�l���ƂȂ����̂��̂Ȃ��Ƃ��Ȃ��B
�@�������鋭�������ɓ���ɂ߂����R��]���l�������̂��A���m�����Ɍ��ŋx�ɂ�^���đO���̕��͂�����������͂�ቺ�����邱�Ƃ�����邽�߁A�R���g�D�I�ɔ��t�w����ɑ��荞��őO�����m�����̗~���s������������Ƃ����A��͓I�ȃ��X���������A�������ȕ������B
�@�������āA���E�ɓƓ��̌R���{�݂Ƃ��Ắu����Ԉ����v���R�ɂ���Čv�悳��A�J�݂��ꂽ�B
�@�R���{�݂Ƃ��Ȃ�Ό��͂ɂ�鋭�����\�ƂȂ�B
�@���n�̐N�j�q�ɋ����������ɂ�镺���̋`��������ȏ�A�A���n�̎�N���q�ɈԈ��w�Ζ��̋`�����ۂ����Ă����R�Ƃ����A���̘͂_�������̔w��ɂ�����Ă���B
�@�Ȃ��A�A���n�̎�N���q�Ȃ̂��B�����A���n�o�g�̕��m�����̍ȂƂȂ�A�����̕��m�̕�ƂȂ�ׂ����n�̎�N���q�������Ԉ��w�Ƃ��邱�Ƃ́A���ڂɕ��m�����̎m�C�𗎂����ʂƂȂ�B
�@����Ƃ����āA�E�ƓI���t�w�����������ĈԈ������J�݂��邱�Ƃ́A�l�����s�����A�R���̐�͂ɉe������Ƃ��낪�傫�����a�����Ђ낭�R�����Ɏ������ފ댯���B
�@������A�A���n�̎�N���q�̈Ԉ��w���K�v�������̂��B
�@�Ԉ��w���]��������ꂽ�̂͂���Ȃ鋭���J���ł͂Ȃ��A����Ȃ锄�t�ł��Ȃ��B
�@����͖̋����ł͂��������A���̖��̂��̂������Ǒ��ɔ�����s�ׂł���A���̍s�ׂ̋����ɘJ���̑Ή��⏤�s�ׂ̊T�O��K�p���邱�Ƃ͌���Ă���B
�@�̑㏞�Ƃ��ČX�̕��m����������Ƃ����咣�́A�����Ȏ咣�Ƃ��Đ��������Ȃ��B
�@�ނ�͈Ԉ����Ɏx��������������Ȃ����A�Ԉ��w�ɒ��ڂɎx�������킯�ł͂Ȃ����낤���A�܂��Ďx�������㏞���R�[�ł���A����͓��{���Ƃɂ���Ă���ꂽ��Z�D�ł����Ȃ������B
�@����͂͂����茾���č��Ƃɂ��ƍߍs�ׂł���B
�@���������āA�⏞�ƎӍ߂͍��Ƃ̐ӔC�ɂ����āA���Ƃ��璼�ڂɔ�Q�����X�l�ɂ������āA���ڂɂ����Ȃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���ꂩ��s���A�g���b�N����o�E���ɁA���̎�̌R���{�݂͑������������A���̖��͐[���ɍl����������Ȃ��Ȃ�B
3.3 �g���b�N���̈Ԉ���
�@��Ƃ̌E�c���Ɂw�g���b�N�������x�Ƃ�����i������B
�@�����Ƃł��钘�҂͂�����u�����v�Ƃ��ď��������A���Ȃ��̌�����i�������̂��́w���l���ɂāx�ɂ���ׂ�ƁA�͂邩�Ƀt�B�N�V�����̕��������Ȃ��A���Ҏ��g���푈���̐����Ƃ̎�Y�҂̈�l�Ƃ��Čo�����������������Â�����i�ł���B�@���̂Ȃ��ɂ��Ȃ��D�Ńg���b�N���ɑ����钩�N�l�Ԉ��w�̓��g���E�̘b���o�Ă���B
�@�g���b�N��̈Ԉ����앗���̏��Z��p�̓��{�l�Ԉ��w�ƂƂ��ɓ��S������Y�҂̘b������A��Y�҂͕߂���ꂽ���A���{�l�Ԉ��w�͎��E�����B
�@���{�l�Ԉ��w���������āA�D���D��ňԈ��w�ɂȂ����킯�ł͂Ȃ������B
�@�܂��ċ\�i�����ށj����đD�ɏ悹��ꂽ���N�l�Ԉ��w�̓��g���E�ɂ��āA�w�g���b�N�������x�͎��̂悤�ɏ����Ă���B
�@�D����ɂ����ނɂ��������A�D�q�̂Ȃ��̏����͂܂��܂��Ђǂ��Ȃ��Ă����B
�@����ɃT�C�p�������������邱�납��A�g���r�炭�Ȃ��Ă����B
�@����Ȃ�����A�������̈�l���C�ɓ��g���E�������B
�@�������̂������l���́A���ꂩ�瑗���Ă䂭����̓��ł̂ق�Ƃ��̎d���̓��e��m�炳�ꂸ�A���܂���Ă�Ă���ꂽ�̂��Ƃ������Ƃ������B
�@���g���E�̌��������̂��ƂƊW���������悤�ł���B
�@����͂�������A�u�݂ǂ肪���v�Ƃ����ӂ��ɁA�D�q�̎������ɂ�����Ă������A���͍̂��̂䂩���𒅂��N��̏��̂ق��������B���łɗ[�H�̂���ŁA��ɂ͂����Ă��炾�����B
�@�u���݂̂ǂ�Ƃ������A���N�l���Ƃ�v
�@�z�H���ԂŐH��ɍb�ɏo�Ă����A�����A���Ă��āA�b�������Ă����B
�@�u�ȂB���N�s�[���v�i�����̃}�}�j
�@�u�݂ǂ�Ƃ����̂͏����p�̌��������A�{���͗��p���Ƃ����B
�@�����͖{���̎o�ŁA�݂ǂ肪�A�C�S�A�A�C�S�Ɛ��������āA�b�ŋ����Ă����c�c�v
�@�݂ǂ�A����A���p���̎o�̎��E�̘b�͂����ɑD�q���イ�ɍL�������B
�@���̂����̔��������s�[�X�݂̂ǂ�̕��łȂ��A�Ȃ��N��̎o�̂ق��ł������̂��\�\�B
�@�i�����j
�@���̖k�[�Ɉʒu���Ă��邱�̗����n����A����ɖk���̕����ցA�C�݂����̓���������Ƃ܂���āA���傤�ǃR�u�R�̗����ɂȂ錳�����������b�`�f�[���ɂ́A�w�앗���x�Ƃ����C�R�̈Ԉ������ł��Ă����B
�@�s�����̊Ŏ炽���ɂ��A��]�҂ɂ͓앗���o�������s����Ă��āA�x��Ŏ�̏o���ԍ��́A���傤�Lj�Z�Z�Ԃ������̂��B
�@�u���j���ɂ����Ƃ����ւB�݂�ȁA�ǂ̎��̂܂��ɂ��s�Ă��ĂȁB
�@������̂��̂��w�͂₭��ꂦ�b�I�x�Ƃ����āA�ǂȂ�B��������������@����˂���v
�@�x��Ŏ�͂���Ȃӂ��ɂ����āA��������߁A���i�F�̎��l���𒅂����j�������킹���B
�@�x��Ŏ�̘b�ł́A�앗���ɂ͓�\�l���܂�̏���������Ƃ������Ƃ������B
�@���̂����̔����ȏオ���m�ۂŁA�������Ƃ�������ɑ���ꂽ�����������ł���B�i�����j
�@�������������́A����ȕx��Ŏ�̘b���������тɁA����ɂ���r���̕��m�ۂ̂Ȃ��ł̂ł����Ƃ��v�������Ă����B
�@��̍b�ňÂ��C���݂߂āA�A�C�S�A�A�C�S�Ɛ��������ċ����Ă������������s�[�X�݂̂ǂ�Ƃ������̏����\�\���p���̂��Ƃ��v��������Ă���̂ł������B
�@�u�܂��\���A���̂��ǂ����������ȁv
�@�u���݂̂ǂ�̎��̂܂��ɂ��s�Â��̂����B
�@�ǂ���������ł���ȓ��ɑ����Ă����̂�����Ȃ����A�ނ����b���ȁv |
�@��Y�҂���������ɑ����Ċ�n�݉c���s�ꌚ�݂Ȃǂ̋����J���ɏ]��������ꂽ�����͂��܂�m���Ă��Ȃ����A�g���b�N���́A�����̎��l�����Ƌ����A�s���ꂽ�R�p�Ԉ��w�����Ƃ��A���Ȃ����œ��{�C�R�ő�̑O����n�̏��������ɕ�d���邽�߂̖��������ꂽ�A������̓��ł������B
�@���ꂪ�푈���̃g���b�N���̂�����̊�ł������B
3.4 ��m�Q���ɑ���ꂽ���l����
�@���O���N�̖����ɂȂ�Ɠ��{�͓�m�Q���̌R�����}���͂��߂��B
�@���[���b�p�ő���̊�@�����܂������O���N�A�A�����J�̓��[���b�p�ƃA�W�A�ł̑����Ԑ푈��z�肵�A����܂ł̈ꍑ����̐F�ʍ��v������ă��C���{�[�E�v�������v�悵���B
�@�����̓��{�̓�m�Q���̌R���͐���@����ї���@�̔�s�ꌚ�݂���̂ŁA���l��N��̑ΕĊJ�펞�Ɏg�p�\�ȗ����s��́A�}���A�i�����p�K���A�T�C�p���̃A�X���[�g�A�e�j�A���̃n�S�C�A�J�����������g���b�N�̒|���A�|�i�y�̃i���{�}���A�p���I�̃y�������[�A�}�[�V���������N�F�[�����̃��I�b�g�A�}���G���b�v�̃N���A�A�E�H�b�[�ł������B
�@���݂̘J���͂��s�����A�܂��O��N�ɁA�e�j�A���ƃE�H�b�[�̔�s�ꌚ�݂ɁA���l�Y��������̎��l�J�����������ꂽ�B
�@�Ԑ����Ɩ��t����ꂽ���l�����́A�e�j�A�����ɑ���ꂽ��Y�҈�Z���i���S��Z���j�A�E�H�b�[���ɑ���ꂽ��Y�҈��Z���i���S�O�Z���j�ŁA��������J��O�ɍH�����������Ă��̑��������n�ɋA�����B
�@�Ƃ��낪�A�g���b�N���Ɏ��l�����𑗂�o�������ؗ��s�Y�ǒ����������������w�펞�s�Y���^�x�ɂ��h�q���́w��j�p���x�ɂ��A�e�j�A������E�H�b�[���̎��l�����̂��Ƃ͏����Ă��邪�A�g���b�N���̎��l�����̏͏�����Ă��Ȃ��Ƃ����B
�@�����̎��l�����̑啔���͊J��O�ɋA���ł������A�g���b�N���̎��l�����͑������J���ɓ��ɑ����A�A���R�̐���̔w��Ɏ��̂�����ċQ���ɋꂵ�ޔߎS�Ȑ������������A�����̋]���҂��o�����B
�@�E�c���ɂ��A�l��N��Z���Ƀe�j�A�������Y�ҋ㔪�����ɕ����ăg���b�N���ɓ]�p����A�S����l�Z�̌Y�������牡�l�Y�����ɏW�߂�ꂽ��Y�҂ŁA��O����O�Z�Z���A��l����l�Z�Z���A����܁Z�Z���]�̎��l�����̐}������Ґ�����A�l��N����l���ɂ����ăg���b�N�̏t���̗���@�̔�s��Ɛ���@�̔�s��̌��݂̘J���͂Ƃ��đ��荞�܂ꂽ�B
�@�����n�͎l�O�N�ꌎ�ɊT���A�����n�͎l��N�i���s���j�ɊT�����ߕ�����鎞���ɒB������Y�҂����҂��ꂽ�B
�@�l�l�N�l���̓�x�ڂ̃g���b�N�����P��A�g���b�N���Ɩ{�y�Ƃ̑D�ւ͐₦�����A���̂Ƃ����Ɏc�����Ă�����Y�҂͌l�㖼�A���̌㌻�n�Ŏߕ�����ČR�v�ɕғ����ꂽ���̂����Z���A�푈�I�����̐����҂͎��l���A�l�l�N��Z���Ȍ�ɎO�ܔ����̎�Y�҂����B
�@��P�ɂ�鎀�҂͈ꖼ�ŁA���͂��ׂĉ쎀�ł���B
�@��Z���̊Ŏ�̂������҂͎O���i�����ꖼ�͔����j�ɉ߂��Ȃ������B
�@�O���N�Ȍ�ɋ}�݂��ꂽ��s��ȊO�̌R���{�݂͕n�ゾ�����B
�@�`�p�ł̓T�C�p���A�g���b�N�A�p���I�A�A���K�E���A�|�i�y�A�����[�g���J�`��ƒ�߁A���V���g�����̐����ɂ����Ă����ԍ`�Ƃ��ċD�D�p�̕u���̌��݂������Ȃ�ꂽ�B
�@�������A�ꖜ�g�����ȏ�̑�^�D���ڊ݂ł���u���̓T�C�p���`�ƃp���I�`�����ł������B
�@�C��Ȃǂ̖h���{�݂̌��v��͂��Ƃɗ����x��A���݂ɂ͓��䓹�H���g���A���̕~�n�ɂ͓���~�n�𗘗p����Ƃ����A���悻��p�I�ϓ_���ɂ����X��`�I�ȑ㕨�ł������B
4�@�u�I�����W�v��v�ƃ��V���g���̐�
top
4.1 ���b�h�����A�I�����W�͑��
�@���I�푈��A���B�̗����J�������߂����ē��{���푈���̌����j�����̂ŁA���I�u�a�����������A�����J�̑Γ�����͗�p���A����ɃA�����J�����ɂ�������{�l�ږ��r�˖�肪�N�����ē��ĊW���ɓx�Ɉ������A���Đ푈�̊�@�����ꂽ���Ƃ��������B
�@���I�푈��̈��Z�Z�N�������l�N�ɂ����āA�A�����J�C�R�͑����m��Ƃ���Γ��푈�ɂ�����헪�v��𗧈Ă����B
�@���̌v��Ă����Z�Z�N�Ɂu�I�����W�v��v�Ɩ��t�����A���{�ł́A����Ȍ�A�����J�̑Γ��푈�v�挤�����p������Â����ƏЉ��Ă���B
�@�������A�u�I�����W�v��v�Ɋւ�����{�ł̂��̂悤�ȗ����͐������Ȃ��B
�@���ɁA���{�����I�푈��̈��Z���N�Ɂu�鍑���h���j�v�����肵�A�C�R�̑z��G���̑��ɃA�����J�������A�Ȍ�A���{�C�R�͑ΕĐ푈������ڕW�Ɍ��݁E�P�����Ă����̂ŁA�A�����J���I�����W�v���Nj����Â����Ƃ��Ă��A�����s���Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@���ɁA�Ȃ��I�����W�Ȃ̂��A�Ƃ������̂̈Ӗ��𗝉����ׂ��ł���B���E���ʂ̌R���펯�Ƃ��āA���R�E�C�R���킸�A�n�}��C�}��ɓG�����̔z�u���L���ꍇ�A�G�����b�h�A�������u���[�ŋL������̂�����ł������B
�@��{�̔������ԁA�������Ƃ����F���M�����邪�A����͏��Z�����̐}���p�p�ɍl�Ă��ꂽ�R�p�F���M�ł������Ƃ����B
�@���{�C�R���ނ��瑽�����w�C�R�헪���_�ƃA���t���b�h�E�}�n�����w����Ƃ���Z�I�h�A�E���[�Y�y���g�哝�̂́A�A�����J���C�R���Ɉ�Ă����悤�Ƃ����B
�����̃A�����J�̊C�R�헪�̑�ꐳ�ʂ͑吼�m���ʂł������B���������āA���[���b�p���̊C�R���C�M���X��R�R�i���b�h�j�ɂ���Ƒz�肵�A�������ʂ̑����m�ŃC�M���X�̓������ł�����{���u���b�h�v�ɂ��R�R�Ƒz�肵�āu�I�����W�v�Ɩ��t���A�A�����J�̐��͌��i�u���[�j���̑��L�V�R���v����u�O���[���v�Ɩ��t�����B
�@������A�d�_�̒u�����ł́A���b�h�i�C�M���X�j���u���[�i�����j�ɑΉ����A�I�����W�i���{�j�̓O���[���i���L�V�R�j�ɑΉ����郌�x���̌R���v��ł������B
�u�I�����W�v��v�Ƃ������̎��̂��A���{�𐳖ʂ���G�Ƃ���헪�v��łȂ����������������Ă���B
�@�����A�����J�͑��̎�͂��吼�m�݂̃A�����J�����̌R�`�ɂ���A�����m�ɉ�q����ɂ͓�Ẵ}�[�����C�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��������Ƃ��A���Đ푈������ɂ��Ă����B�����̌R�͂͐ΒY�����C�D���i�{�C���[�j�Ń��V�v���E�G���W�������V�X�e���ł���A�R�͗p�̗ǎ��̖����Y�̓A�����J�����̃A�p���`�A�n��ł����Y�o�����A��͑��������߂̒��Y��E���Y��𒆌p��n�Ƃ��ē�Ċe���ɂ����Ƃ��K�v�ł������B
�@���Z���`����N�ɂ����ẴA�����J�̃O���[�g�E�z���C�g�E�t���[�g�i���F��͑��j�̐��E����q�C�́A�����̃n���v�g���E���[�Y���o�`���A��Ċe�n�ŋ��Y���Ȃ���}�[�����C�����ւăT���t�����V�X�R�ցA�n���C�̃I�A�t���A�ė̓��T���A�o�R�ŁA�j���[�W�[�����h�̃I�[�N�����h�A�I�[�X�g�����A�̃V�h�j�[�E�����{�����E�p�[�X�o�R�ŃC���h�l�V�A�̃o�������̃����{�N�C���A�{���l�I�i�J���}���^���j���ƃZ���x�X�i�X���E�F�V�j���̂������̃}�J�b�T���C�����ăt�B���s���̃}�j���ɓ������A���ꂩ����{�̓����Ɂu�e�P�K��v���͂������B
�@�������A���̊͑��͐�͂Ƒ��b���m�݂͂̂ŁA�퓬�ɂ͕s�����������q�C�Ɋ����Ȃ��쒀�͂Ȃǂ̏��^�͒��𐏔����Ă��Ȃ������B
�@�����̑�͑��̑�q�C�ɂ́u�e�P�K��v�̎�|���܂܂�A����䂦�ɓ씼�����I�āA�j���[�W�[�����h�A�I�[�X�g�����A�̓Ɋ�����Ƃ������Ƃ��ł��邪�A���{�ւ̐펞�U���H�̊J����l�������ꍇ�A���̍q�H�̊J��͓���������݂đR��ׂ����̂ł������B
�@�Ȃ��Ȃ�A�u����l�N�ȑO�A�T�d�h�́A�n���C�ƃt�B���s���̊Ԃɂ���Ǎ`�͒������ɂ���ď��L����Ă���Ƃ��������s�\�̖����ɒ��ʂ��Ă����B
�@��ꎟ���E���ɍۂ����{���h�C�c����~�N���l�V�A������D�����Ƃ��A�͖�������A���̔h�̋F��͂��Ȃ���ꂽ�̂������v�i�w�I�����W�v��x�j�Ƃ�������������������ł���B
�@�u�T�d�h�v�Ƃ����ł����̂́A�h�C�c�̃~�N���l�V�A�̑��݂���Q�ƌ��Ȃ��h�ł������B
�@�A�����J�C�R�̒��ɂ�����������́u�ːi�h�v�́A�h�C�c�̃~�N���l�V�A�̑�ʂ̂������ɒ��Y��E���Y���ݒu���邱�Ƃ��l���Ă����B�ނ�́A�h�C�c���h�G�C�M���X�̓��������{�������v���Ă��Ȃ����낤����A���{�U���̂��߂̃A�����J�͑��ɒ��Y��E���Y������\��������ƍl�����̂������B
�@�������A����͒��̂悷���鎩������ȍl�����ł���A�h�C�c�������̎R�������ɂ�������̗�������{�ɒD����댯��`���Ă܂ŁA�A�����J�Ɍ����ꂵ�Č���������j��Ƃ͎v���Ȃ������B
4.2 �u�I�����W�v��v�Ɏ����\�ȏ���
�@��ꎟ����A�����m�����܂��R�������傫���ω������B
�@�A�����J�̓p�i�}�^�͂��J�ʂ����A�吼�m�̊͑���͂��m�ɒZ���Ԃʼn�q�ł���悤�ɂȂ����B
�@�R�͂̋@�ւ̓��V�v���E�G���W��������C�[�|�r���ɑւ���ĔR����サ�A����ɔR�����ΒY����d���ɐ�ւ����A�A�����J�����̃J���t�H���j�A�����E�L���̐Ζ��Y�n�Ƃ��ēo�ꂵ���B
�@������̍ő�̕ω��́A���������m�ɗ����͂�����h�C�c�̎p�����������Ƃ������B
�@�u�A�����J�̐헪�Ƃ����́A�I�����W�E�v�����ɂƂ��ē��{�̋L�O�i�����w�ō��̏d�v���x���悭�������Ă����B
�@�T�d�h�́A�������r��Ő_��������������H���ƍl�����B
�@��ѐΐi�U���ɂ͐�Εs���ȁw�펞��̂��Ďg�����m���Ԃɂ����A�̍`�x�͍��R�Ƃ��ċ�̉������B�i�����j
�@�������C�R��w���̓ːi�h�ɂƂ��ẮA���{�̓����͍Г�ȊO�̉����ł��Ȃ������B�i�����j
�@����́A�������{���A�O�A������уt�B���s���ւ̕ČR�̕⋋�����ׂ��悤�Ȋ��D�ŗ��Ƃ���A�A�����J�������Ɋ댯�ȏɂ��炳��邩�ɂ��Čx��������̂ł������v�i�w�I�����W�v��x�j�B
�@���Ԃ͓ːi�h�ɂƂ��Ă��L���ɉ��������B�����N����̃x���T�C���u�a���ŁA���h�C�c�C�O�̂̐폟���ɂ��̗L��F�߂��A���ۘA���̈ϔC�����̂Ƃ����`���ŕ��z���邱�Ƃɂ��A�ϔC�����̂̓�m�Q���ɂ��Ă͍��ۘA���K��Łu�z�閔�͗��C�R�����n�̌��y�x�@���͒n��h�q�ȊO�ׂ̈ɂ���y���̌R�����������i�����֎~�j���ׂ����Ɓv����߂�ꂽ����ł���B
�@�Ȃ��A��ꎟ���ŃI�[�X�g�����A����̂��A���풆�ɓ��{����̂��邱�ƂɂȂ�`�N�����́A�C�M���X�{���̈ϔC�����̂Ƃ��ꂽ�B
�@��ꎟ����܂ł͌��z�Ƃ��Ă������݂����Ȃ������u�I�����W�v��v�́A����ɂ���Ƌ�̓I�v�搫�������Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B
�@��ꎟ���ɑ吼�m����у��[���b�p�̐��ŘA���R�̈���Ƃ��Đ퓬�ɎQ�������A�����J�ɂƂ��āA�C�M���X�͂��͂�u���b�h�E�v�����v�̑Ώۂł͂Ȃ��Ȃ������A�V���̃h�C�c�鍑�C�R�i�u���b�N�j����ł����B
�@�A�����J�̐헪�����̑ΏۂƂ��Đ����̂������̂́A�u�I�����W�v��v�����ɂȂ����B
�@�������u�I�����W�v��v��̉��̏�������������B�p�i�}�^�͂̊J�ʁA�͑��@�ւ̏d����ĉ��ƃJ���t�H���j�A�̐Ζ���Y�n���A�R���⋋�ɕK�v�ȃ^���J�[�̐����A��ꎟ��풆�̃��[���b�p�ւ̐Ζ��A���̎��т��ؖ������悤�ɁA���E�̐Ζ��s����قۓƐ肷��A�����J�̃X�^���O�[�g�Ќn�̏��L�^���J�[�����ŏ\���ł������B
�@�ł��d�v�ȏ����̕ω��́A��O���ɔz�����邱�ƂȂ��ɁA�͑����n���C���璆�������m�i���铹���J�������Ƃł���B
�@�����N�́u�I�����W�v��v�ŁA�����i�K�Ńn���C�̐^��p�Ɋ͑����W�����A���i�K�Ő^��p����}�[�V���������̃G�j�E�F�g�N�ʂɐi�o���A����ɓ��J�����������̃g���b�N�ʂ��̂���Ƃ����A���������m�̓ːi�v��ƂȂ����B
�@��O�i�K�͂��̂Ƃ��̐���̏�Ԃɂ��s�m��ł��邪�A�g���b�N������n�Ƃ��āA���{�ɐ�̂��ꂽ�O�A�����D��Ɍ��������A��͂��̂��ꂽ���\�����̃}�j���D��̂��߃V�u�����C���ʂɌ��������A�p���I���ւ邩�ւȂ����͖���Ƃ��ē�V�i�C�ɖʂ����p���������̃}�����o���p�i�̂��~���_�i�I���̃_�}���L���X�p�ɕύX�j�Ɍ��������A���邢�͒��ڂɓ��{�̉�����Ղ����A�������̑I�������l����ꂽ�B
�@������ɂ���A�u�ő�̌���ꂪ���������ƂȂ邱�Ƃ́A�헪�Ƃ����̈ӌ��̈�v����Ƃ��낾�����B�i�����j
�@���Z�Z�N����l�ܔN�̍Ō�̐퓬�Ɏ���܂ŁA���������̍U���͕č��헪�̎�v�e�[�}�ł������v�i�w�I�����W�v��x�j�Ƃ����B
4.3 ���p��O��������ĉp�����O����
�@���������������������Ĉ���Z�N��͂��߂̈����N�ɁA���V���g����c���J���ꂽ�B
�@���{���S���͊C�R��b�̉����F�O�Y�E�M���@�c�����ݓ���ƒB�E���đ�g�̕�����d�Y�ł������B
�@���{�C�C��̂Ƃ��̘A���͑��Q�d���Ƃ��Đ�p�Ƃ̖��������������ƁA�����O���̑㖼���Ƃ������镼���A��l���O���̕���Ƃ������V���g����c�̌��ʂƂ��Đ����������V���g���̐��́A���{�ɂƂ��ėL���ł��������A�s���ł��������B
�@��ꎟ���ɏ��������卑�͊C�R�̌��͋����ɓ˓����A�e���Ƃ��ɉߑ�ȍ������S�ɋꂵ�ނ��ƂɂȂ����B
�@���V���g����c�̖ړI�͓��A�W�A�E�����m�ɂ�������̐��Â���ɂ���A���̈�Ƃ��āA�C�R�̌R�����������߂鐢�E�I���_�̂��ƂŁA�C�R�R�k��c���J���ꂽ�B���V���g���̐��Ƃ��Đ��������̂́A�����m�̕��a�ƍ��ے����ێ��Ɋւ�����E�āE�p�E���Ԃ̎l��������i����ɂ���ē��p�����͔p�~�j�A�����̎匠�E�̓y�ۑS������і�ˊJ���E�@��ϓ��̌������m�F�����フ������i�O�L�l���̂ق������E�x���M�[�E�C�^���A�E�I�����_�E�|���g�K���������j����т���ƊW������{�̒����ւ̋��h�C�c�̎R�������Ԋ҂Ɋւ�����؏��A�C�R�̌R�������Ɋւ�����Ȃǂł������B
�@����܂Łu���{�O���̊�v�ł��������p�����̔p���ŁA���{�̊O��H���͎��I�]�������܂�ꂽ���A���V�A�鍑�����ł��A�C�M���X���J�i�_�̖h�q��S�ʓI�ɃA�����J�Ƃ̗F�D�W�ێ��Ɉˑ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�����̂��ƂŁA���p�����͂��̑����̈Ӌ`���������B
�@�l�������ɂ̓C���h�V�i��̗L����t�����X��������ꂽ���A���͓̂��ĉp�O���̊����m�������ł������B
�@�܂��A���I�푈��̖��B�����̔閧����̑���ł��������V�A�鍑�����āA���{�̒����ɂ����鐨�͌��Ɨ����̊g�吭�p�[�g�i�[�������ČǗ������ȏ�A�����̌���ێ����߂��フ�������܂��K�R�ł������B
�@����͌��݂ł����A���̏I���ɂ��A���Ĉ��ۑ̐�����Ƃ�����{�O�����A���Ē����̊����m�������̐��ɓ]������قǂ̑�]���ł������B���������O���͐V�������ۓI�����ւ̑Ή��ł��������A��ꎟ��킪�����炵�����E�V�X�e���̘g�g�݂̕ω���F���ł��Ȃ��������{�̑����̐����Ƃ�R���́A�����O������O�����Ƃ��Ĕ����B
�@����Ɍ�̎���̍����ɂ������ɗ�������Ȃ������̂́A���V���g���C�R�R�k���̒����ł������B
�@���̏��͓��E�āE�p�E���E�ɂ̌܃����ԂŎ�͊��i��r���ʈꖜ�g�������a���C���`����C������R�͂ŁA�q���͂������j�ۗ̕L�ʂ𐧌�������Ƃ��Ē������ꂽ�B
�@���_�Ƃ��Ď�͊͂ۗ̕L�ʂ͕āE�p�̊e�܂ɂ��������{���O�A���E�ɂ��e��E�Z���̔䗦�ɒ�߂�ꂽ�B
�@�Ƃ���œ��I�푈��̓��{�C�R�ɑ�����͊͑ΕĎ�����ۗL����Ƃ����͑��g���\�z�����������B����͑����m���z���Đi�U���Ă���A�����J�͑����}��������v��������{�́A�A�����J�͑��̐�͂̎��������ĂΌ����ĕ����Ȃ��Ƃ����v�Z����l���o���ꂽ���̂ŁA�A���t���b�h�E�}�n���̒�q�ł���A�C�R�ɂ����鍑�h���̑�ƂƂ����鍲���S���Y�i�̂������j���咣�����Ƃ�����B
�@���V���g���R�k��c�ł́A���炩���߃A�����J�ƃC�M���X�����c���A�����͑Γ��A���{�͗����ɂ������Z���Ƃ����䗦�����߂Ă����B
�@���{���ΕĘZ�����̂ނ��A�ΕĎ����ɌŎ����ĉ�c�������邩�́A�C�R���\����S�������F�O�Y�̌��S�ɂ������Ă����B
�@�����N�u�吳�\��N�x�ȍ~�̊C�R����i�����j�A�����ɂ͍��Ɨ\�Z�͑S�̂ň�l������ꔪ���~�𐄈ڂ��Ă���A���̒����疈�N�܉��~�߂��z���C�R��Ɋ������Ƃɂ͑���̍���������ƍl������v��Ԃɂ������i�w���{�C�R�j�x��O���j�B
�@����͓��{�̍����̎���s�\�ɑ������B
�@���ĕs��_��M���Ƃ��A���h�͌R�l�̐�L���ɂ��炸�Ƃ̐M�O�̎���ł����������S���́A�����m�̖h��������ێ��Ƃ�������̂��ƂɁA�ΕĘZ�������������B
�@�A�����J�ł͓ːi�h���O�A�����v�lj��_���咣���ăn���C����t�B���s���ւ́u�ʂ��ؕ��v����ɓ��ꂽ�����Ă����B
�@���{�C�R�̐헪�\�z���炷��A��͕͊ۗL�䗦�̈ꊄ�����ɌŎ�������A�O�A���E�t�B���s���E���`�̌R��������j�~���A�A�����J�̊C�R��n���n���C�Ȑ��A�C�M���X�̊C�R��n���V���K�|�[���Ȗk�ɐi�o�����Ȃ������d�v�Ɣ��f�����̂ł������B
4.4 �헪�ƁE�����F�O�Y�̉p�f
�@�w���{�C�R�j�x��O���͉����̔��f�ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�����C���́A���Ȃ�ȑO����A
�@�@����̃p���[�E�o�����X���傫���ς��A���ɂ���͑����m�E�ɓ����ʂɂ����Č����ł���A
�@�A���u�[������������̍����E�o�ς̕N���͐r�������A�Ƃ�킯�C�R��̑啝�ȏk����}��K�v������A
�@�B�č��Ƃ̊C�R�͋������s�������Ƃ���͖����ł���A���炩�̌`�ŕč��Ƃ̍��ӂɒB���Ȃ�����Ƃ̑O�r���낤���A
�@�Ɛ؎��ɔF�����Ă����B
�@�������Ȃ���A���{�́A���O�Ƃ��ɌR�����������o���ɂ͂Ȃ������B
�@���܂��ܓ����ꋫ�ɂ������ł����p����������d�|�����̂ł���A�䂪���́A�u��҂̓C�M���X�A�n�Ԃ̓A�����J�v�Ƃ�����I���ȉp�O�𐭍�ɏ�����ꂽ�킯�ł���B
�@�����͋A����A��������Ɠ��{�͉p�ĂɈ������ꂽ�ƕΌ�������Ă���҂�����Ƃ̂��Ƃ����A
�@�u�e�����Ղɓ��肽��\�͎z�l�Ȃ邱�ƌ����Ė����肵��f����������̂Ȃ�v
�@�Əq���i�O�f���{�O���w���V���g����c�E���x��Ê��}�ӎ`��A�A�Z�܋�y�[�W�j�A�C�R�R���������͑�Ǐ�̍��h�Ɋӂݏ��Ë��������ʂł���A
�@�u�鍑�̗�����V������Ό���C�R���͂Ƒ����m�h�������Ƃ��ȂĂ��č��h�����x�Ⴗ�鏊�����v
�@�Ǝ��M�������ĕ\�������̂ł������i�O�f�w�����@�R���x�j�B |
�@�������āA���{�͓�m�Q���̖��h���A�瓇�E���}���E�쐼�����E��p�E�O�Ώ����̖h���̌���ێ��i�O�Γ��̔n�����C�R�v�`�A�O�Γ��E��p�̊�E���Y�͗v�ǁj�A�A�����J�̃t�B���s���i�}�j���p���̃R���q�h�[�����͗v�ǁj�A�O�A�����A�E�F�[�N���A�~�b�h�E�F�[���A�A�����[�V�����̖h���̌���ێ��A�C�M���X�̍��`�i�v�ǁj�̖h���̌���ێ������肵���B
�@����͓��{�̌R�k�O���̐����ł������B
�@�������A�����̐헪���_�̌p���҂����͏��a���̊C�R�����̐����̌��ʁA���d�h�ɂ���Č�������r������Ă��܂����B
�@���̌��ʁA���O�l�N�ɓ��{�̓��V���g�����̔p����ʍ����čĂуA�����J�Ƃ̌��͋����ɓ˓����A�������̉ʂĂ͐^��p��P�U���ɐ������Ȃ���A�┑���̐�͂�Z���ԂɈ��g���C���\�Ȑp���ɝ����i�������j������ɂƂǂ܂����B
�@�d���^���N�j��Ȃǂɂ��C�R��n�̋@�\��j�āA�ꎞ�I�ɃA�����J�̊C�R��n��嗤���C�݂܂Ō�ނ����������헪�I�ɗL���ł���Ƃ�������F�O�Y���̐헪�I���z�͑S���Y����A�n���C�̊�n���̂܂܂ɕ��u���ċ@���������A������Ƃ��������������Ȃ����̂ł������B
5�@�g���b�N���A���\�Ƃ��Ắu���{�̐^��p�v
top
|
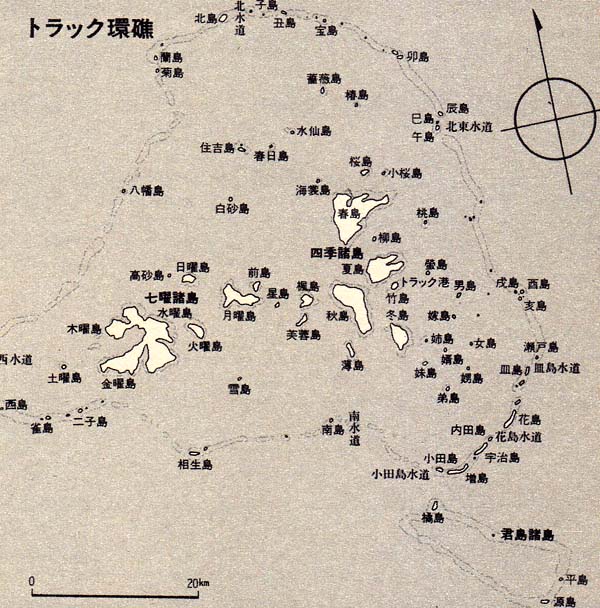
�t�ďH�~�̎l�G�����A���j����y�j�܂ł̎��j�����Ȃǂ��������B
|
5.1 ���E�ő�Ƃ�������
�@�Z���������A�ڂ��o�߂đ��̊O������ƁA�ȊO�ɋ߂��Ƃ���ɓ����������B
�@�₪�ē��̑O�ʂɔ������������т������Ă��āA���̔��������߂Â��Ƃ���ɏ㑤�ɃG�������h�E�O���[���̐��ʂ��L����͂��߂��B
�@�������͊ʂɂ�������g�ł���A���̏㑤�̃G�������h�E�O���[���̓��O�[���i�ʌj�̐����̐F�ł������B
�@�D�����O�[���̒��ɓ���A���ɋ߂Â��ɂ�A������D�O�@�t���̑����̏��M���D�����͂�Ŕ������͂��߂��B
�@���}�Ȃ̂ł��낤�B
�@��������A�D�Ƀ����`�����t���ɂȂ�A�����R�������D�ɏ��ڂ����B
�@�����葱�Ƃ����Ă��A��l���Ԉȓ��̃g�����V�b�g�葱�Ȃ̂ł������ĊȒP�ŁA�����ǂ��쐬�z�z�����r�U�p�ʐ^�\�t�̂h�c�J�[�h�ł����Ȃ��A�{�l�̗����K�v�Ƃ��Ȃ��Ƃ����B
�@���H���ɁA�D�̓`���b�N�i�g���b�N�j�ʃ��G�����i�t���j�̍`�̊ݕǂɉ��t���ƂȂ����B
�@�S���̓����R�����I���A��Z���ɏ㗤�J�n�ƂȂ����B
�@�g���b�N���̓~�N���l�V�A�̓��J�����������̎哇�Ƃ������ׂ��n�ʂ��߁A�قۓ��o��܈�x�O�Z�������ܓ�x�܂ŁA�k���x���玵�x�l�Z���܂łɂ܂����钼�a�Z�܃L�����[�g���́A���E�ő�Ƃ��������i�����ɂ͚Əʁj�Ɉ͂܂ꂽ��܁Z�̓����琬��ΎR���Q�ŁA���n�ʐς͍��v���Z�Z�����L���A��v�ȏ����́A���{��������̖��̂ŏt���i���G�����j�E�ē��i�f���v�������j�E�H���i�t�F�t�F�����j�E�~���i�E�[�}�����j�𒆐S�Ƃ���l�G�����A���j���i�E�h�b�g���j�E�Ηj���i�t�@���y�Q�b�g���j�E���j���i�g�[�����j�E�ؗj���i�p�^���j�E���j���i�|�����j�E�y�j���i�I�i���G���j�E���j���i���}�k�����j�Ȃǂ��琬�鎵�j�����ł���B
�@���{����̋����́A�w�ϔC�����̓�m�Q���x�f�ڂ̍q�H�}�ɂ��A�����`�T�C�p���Ԃ���܊\�A�T�C�p���`�g���b�N�Ԃ��Z�Z�Z�\�ŁA���������ē����`�g���b�N�Ԃ̒��������͖���Z�Z�\�A���Ȃ킿��O�܁Z�Z�L���ł���B���{��������̓�m�Q���́A�k�ɏ��}����������Â��ē�k�ɗ��������Â���}���A�i�����i�哇�͏�����[�ɋ߂��T�C�p���j�A���̓�ɁA�ԓ��ɕ��s�ɓ�����Z�Z�\�̊C�ʂɓW�J����}�[�V���������i�哇�̓����[�g�A�g���b�N�܂Ŗ���Z�Z�\�j�E���J�����������i�哇�̓g���b�N�j�E���J�����������i�哇�̓p���I�A�g���b�N�܂ň��l�Z�\�j���琬��A�����t�s�F�^�̔z�u���������Â����m�Q���S�̂̌�_�Ɉʒu����̂��g���b�N�ł������B
�@���O�[�����ɐi������ɂ͊ʂ̐�ڂł������̂��܂�������ʉ߂��˂Ȃ炸�A��ʃg���b�N�̃��O�[���������̔g�Â��ȓ����̊C�́A�����͂̐N���U��������A�ʊO����͖̊C�ˌ���������S�ł������B
�@����烉�O�[�����ł�����Ɏl�G�����͓��X�̔z�u���悭�A���̂������Â����d�̓��C�́A�g�Q��\����h���ɂ��D�s���ŁA�͑D�ɐ�D�̕d�n����Ă����B
�@�����������Ƃ���A�l�G���������̉ē��͑��풆�ɓ��{�C�R�̊�n�Ƃ���A�����m�푈���J�n�����ƘA���͑��i�ߕ��������ɐi�o���A�u���{�̐^��p�v�ȂǂƌĂ��悤�ɂȂ����B
�@���{�̐A���n��m�Q���̗��j�͌�ɂ��āA��肠�����A���{�C�R�̓������n�̐Ղł���ē���������悤�B
�@���D���Ă܂��~�N���l�V�A�A�M�̃g���b�N�B���{�̊��}�s���A���A�i�B���璷�ƏB�m���㗝�̍��Z���j�ƋF��Ɨx��Ɉꎞ�ԁA���A�̂Ȃ��R���N���[�g�̊ݕǂł̂��̍s���́A�����Ȃ�M�т̒n�ɏ㗤��������̎��ɂ͂��������炩�����B
�@���̌�A�s���悲�Ƃ̔ǂɕ�����čs�����J�n�����B�������̂`�ǂ͎O�ǂ̑D�ɕ��悵�ăf���v�������i�ē��j�Ɍ��������B
�@���݂́A���G�����ɂ���ςȊݕǂ̂���`���ł��Ă��邪�A���{��������̓g���b�N�`�̏��ݒn�Ƃ����Ήē��ł������B
�@�ē��܂ňꎞ�Ԃقǂ�����B
5.2 �g���b�N�ɑ�l�͑��i�ߕ���ݒu
�@��ꎟ����A�����m�̋��h�C�c�̂̂����A�ԓ��Ȗk�̓�m�Q�������ۘA���̈ϔC�����̂Ƃ��ē��{�̎{�����ɂ͂��������A���{�͓�m�Q���ɂ��������R�������Ȃ������B
�@���O�O�N�ɓ��{�͍��ۘA����E�ނ������A��m�Q�����x�z���Â��A���O�l�N�Ƀ��V���g�����̔p����ʍ����ĎO�Z�N�ɏ��������ƁA�C�R�͓�m�Q���̍q���n�̐����ɒ��肵���B
�@���O��N��ꌎ��ܓ��A��m���ʂ�����n��Ƃ����l�͑���Ґ����A��v��n���p���I�ɒu�����B
�@�����͒��͐���@��́E�~�݊́E�@���~�ݐ����͂Ȃǂ́A��Ƃ��ČQ���Ɍ��ݒ��̍q���n����̂Ƃ�����̕⏕�I�ȔC�����͒��݂̂ŁA�͑��Ƃ����ɂ͂��܂�ɕn��ł������B
�@�l��N�����ܓ��A��l�͑����m�풓�Ƃ��A�͑��i�ߕ����g���b�N�ɂ������ƂƂȂ����B
�@�͑��i�ߒ����Ɉ�㐬���i�����悵�j�������C����ꂽ�B
�@�g���b�N�����{�C�R�̊�n�Ƃ��Ă̒n�ʂ����߂͂��߂��̂͂��̂Ƃ�����ł������B
�@�����Ƀg���b�N�ɊC�R�����n�����u����A��Z�����ɁA����U���@�O�Z�A�퓬�@�ꔪ�A��s����l�ŕҐ����ꂽ���l�q��������l�͑��ɕғ�����A���̎i�ߕ����g���b�N�ɐi�o�����B
�@�l��N���Z���A�����m�푈�J�풼��̑�l�͑��̕Ґ��́A���͎����i���K���m�́j�A��ꔪ����i�y���V���E���c�j�A�������i�~�ݟB�����E��ցE�Ìy�j�A��Z��������i�y���[���E29�A30��������j�A�掵��������i������͐v�~�E26�A27�A33��������j�E���l�q�����i��q����E���l�q����E����@��͐_�Ёj�A��O�i�p���I�j�E��l�i�g���b�N�j�E����i�}���A�i�j�E��Z�i�N�F�[�����j�����n���ł������B
�@���͎����͈��l�Z�N�v�H�̐V�B�ł��������A����Q����\�肵�Ă��Ȃ����߁A�D�̂̍��i�Ȃǂ͏��D���݁A��C�������ŁA�퓬�͂Ƃ��Ă̔\�͂͂Ȃ��������A�����A�m���P����p�̗��K�B�ł��邽�߁A�i�ߕ��@�\�ƕt������₻�̑��̋@�B���̐��\�͂悩�����B
�@�y���V���E���c�͌����ŋ����̌y���o���́A�[���̓����h�����ɂ�錚�͐����̂��ߋ}篌v���ύX���ĎO�Z�Z�Z�g�����̏��^�y���Ƃ��Ď��삳�ꂽ�B�Ő����g�ގo���B���Ȃ��A��������̕�͂Ƃ��Ă̂ݎg��ꂽ�B
�@��������̋쒀�͂������A�����͂͏��^�̘C���^����A�q�����̗���U���@���퓬�@����Z���Ƃ����A�����̎O���͑��ł������B
�@�J�풼��A��l�͑��̓E�F�[�N���U���𖽂���ꂽ�B
���O�̍q��U���ŃE�F�[�N���̕ČR�퓬�@������S�ł������ƍl���ď㗤�����J�n������Z��������́A�܂�����̖C�䂩��̖C���𗁂сA�쒀�͎�������e���A�����E�����̗U���ɂ�蒾�v�A�Â��Ďc�����Ă����l�@�̃O���}���e4�e�퓬�@�̍U�����ċ쒀�͔@�������v�A���^�͖퐶�����������B
�@�q���͂̒Z����Z���퓬�@���͑�������ł����A�͑�������C�͗[���̔��Z���`���p�C��傾���ŁA�ČR�̋����퓬�@�̍q��U���ɂ������Ă܂��������h���ł������B
�@���w�ŁA�q���͂̉��삪�Ȃ��͑��͂ǂ�ȏ����̓G�q���̍U���ɂ����ĂȂ��Ƃ�����ɂ����P���A�g���b�N���̑�l�͑��͊w���ꂽ�B
�@���ǁA�n���C�^��p�U���̋A�r�ɂ�������ꕔ���̉�����Ĉ��Z���ɍēx�̏㗤���������Ȃ��A�E�F�[�N���̐�̂ɐ��������B
�@�l��N�ꌎ��l���A���@�������͎������ɂ��Ȃ��ăg���b�N�ɓ��`�A�����ɑ��q�����i��q��j�E���q�����i��q��j�̋��l�ǂ���m�͑��ɕғ�����A��܍q�����i�܍q��j�̋���ǂ͓��n�ɋA��A�@�������̓I�[�X�g�����A�̃|�[�g�E�_�[�E�B����P�A����ɗ��R�̃W�������㗤���ɋ��͂��A���ŃC���h�m�@���U�����������Ȃ����B
5.3 �X��C�E�~�b�h�E�F�[�C��̔s�k
�@���̌�A��q���i����E�ԏ�j�E��q���i�����E�j�͓��n�ɋA��A������Č܍q���i���߁E�Ē߁j���g���b�N�ɐi�o�����B
�@���̌�ւ̓|�[�g�E�����X�r�[�U������i�܍q��j����у~�b�h�E�F�[�U������i��q��E��q��j�̏����̂��߂ł������B
�@�l��N�܌�����A�|�[�g�E�����X�r�[�U�����̂��ߌ܍q��̓g���b�N���o�`�������A�܌����`�����A�ĊC�R�@�������ƎX��C�Ő��E�ŏ��̋��͑����m�̊C��������Ȃ����B
�@��͋�ꂪ���{�̌܍q��̓�ǂɂ������A�Ď�͋������L�V���g���A���[�N�^�E���̓�ǁA�ق��ɓ��{�ɏ㗤�D�c��q�̏��^�������˖P�����������A�C��̌��ʂ́A���{�̏��^�������˖P���v�E�Ēߑ����A�ČR�̓��L�V���g�����v�E���[�N�^�E�������ŁA��p�I�ɂ͂킸���ɓ��{��ꕔ���̏����ł������B
�@�������A���̊C��̂��ߓ��{�R�̓|�[�g�E�����X�r�[�㗤����f�O����������Ȃ��Ȃ�A�헪�I�ɂ͓��{�R�̎�ɂ��s�k�ƂȂ����B
�@�������A�|�[�g�E�����X�r�[�㗤��편�s�̌��ʁA�j���[�M�j�A���k���C�݂���I�[�G���X�N�����[�R�����z���ė��H�|�[�g�E�����X�r�[�U�����߂����Ƃ������d�ȍ��ɕ��j����ւ����āA���j���[�M�j�A�ɂ�����n��킪�͂��܂�A���Ɉ�]�̓��{�R���͂��Q���ƃ}�����A�ɋꂵ�݁A�j���[�M�j�A�̖��т̒��ɂ��̐����߂�[���ƂȂ����̂ł���B
�@����ɒv���I�������̂́A���������Ē߂̏C���ƁA���߂̑��Ղ����q��@�Ƃ��̓�����̕�[�̂��߁A�܍q�킪���n�܂ŋA��Ȃ���Ȃ�Ȃ��������Ƃł���B
�@���̌��ʁA�Z���ܓ��̃~�b�h�E�F�[�C��ɎQ���ł��Ȃ������B
�@�����A�傫�ȑ����������[�N�^�E���̓n���C�ɖ߂�A�����Œ��錓�s�̏C���H���Ǝ������q��@�Ɠ�����̕⋋�E��[�̂̂��A���炭���~�b�h�E�F�[�C��ɊԂɂ����A�ċ��z�[�l�b�g�A�G���^�[�v���C�Y�ɂ��O�ǖڂ̋��Ƃ��Ďl�ǂ̓��{��ꕔ���Ƒΐ킵���B
�@�l�Γ�Ȃ��ɕċ�ꕔ���ɏ����ڂ͂Ȃ������B�������A�l�ΎO�Ȃ�ċ�ꕔ���̕��ɏ����ڂ��������B
�@�Ȃ��Ȃ�A���{�̋�ꕔ���̓~�b�h�E�F�[���U����ړI�ɂ��Ă���A�O�ǂ̕ċ��ɐ旧���āA�~�b�h�E�F�[���Ƃ����s��������n�Ƃ���A�����J�̊�n�q���Ɛ��˂Ȃ�Ȃ���������ł���B
�@�~�b�h�E�F�[�C��̌��ʂ������A�O�ǂ̕ċ�ꂩ�甭�i���������@�̐�ʂ̓[���A�z�[�l�b�g�̔������͓��{�͑����ł����A�R����Ń~�b�h�E�F�[���ɒ����A�G���^�[�v���C�Y�̔����������낤���Đԏ�Ɖ���̔����ɐ��������B
�@���[�N�^�E���̎Q�����Ȃ���A���{�̋��̔�Q�͈�q��̋���ǂ����ōς݁A�����̓�q��̑����Ɣ���U���͂��قƂ�ǎ������ċ���ǂ��m���Ɏd���߂��ł��낤�B
�@�������A��O�̕ċ�ꃈ�[�N�^�E�������ɋ삯���A���̔������������̔����ɐ��������B
�@�c����z�[�l�b�g�ɋt�P�����������A�G���^�[�v���C�Y�ƃ��[�N�^�E���͎c�������@�ō�����������Ґ����ĔɍU���������A���{�̋�ꕔ���l�ǂ�S�ł������̂ł������B
�@�~�b�h�E�F�[�C��̌��ʂ̂��̂������́A�ĊC�R���n���C�ɑ�^�͑D�̏C���@�\���܂߂āA���Q�l���̕�[�A���ڋ@�̕⋋�A�͒�����̌��ȂǍ��x�̊�n�@�\���������Ă������ƁA���{�̏ꍇ�A�����͂̏C���͂������A�͍ڋ@�₻�̓�����̕⋋�E��[�̂��߂ɂ����{�ꂩ���܂ŋA��Ȃ���Ȃ�Ȃ��������ƁA�̑���ɂ������Ƃ����悤�B
5.4 ��n�@�\�F���́u���{�̐^��p�v
�@�~�b�h�E�F�[�C��ɂ�������{�̔s�����ČR�ɂ����{�C�R�̈Í��̉�ǂɂ������Ƃ���咣��A���{��ꕔ���̑�ꎟ�U�������~�b�h�E�F�[���̍q���n���U�������̂��A��U�����̔��i�̌ܕ��x�ꂪ�v���I�������Ƃ̎咣�����邪�A��������}�t���߂̋c�_�ł���B
�@�傫�ȑ���́A�n���C�͊���������C�R��n�ł��������A�u���{�̐^��p�v�Ə̂����g���b�N�́A�C�R��n�Ƃ��Ă̐�͑����@�\�炵�����̂��A���������Ă��Ȃ��������Ƃł���B
�@�l��N�������A�A���͑��i�ߕ��i�i�ߒ����R�{�\�Z�叫�j���g���b�N�ɐi�o���Ĉȗ��A�l�l�N��Z���ɎR�{�����펀��̌�C�i�ߒ����É����叫�����͕����ƂƂ��Ƀg���b�N������܂ŁA�A���͑��i�ߕ��̓g���b�N�ɂ���Â����B
�@�������A���̊�n�Ƃ��Ă̎��Ԃ͒����┑���\�ȑ�d�n�Ƃ�������x�̂��̂ŁA�R���E�e��E�H�Ƃ̕⋋�A���K�͂Ȑl���̕�[�E���A�㗤�x�{�A�H��͂Ȃǂɂ�鏬�K�͂ȕ�C���\�ł��������x�̂��̂ł������B
�@���̒��x�̋@�\�����Ȃ��g���b�N�ɃR���p�X�̒��S��u���čs�����a���������A���o�E����O�i��n�Ƃ��Ă���ɍs�����a�̉��L��}��Ƃ����A�����̓��{�C�R�̔��z�ɂ����ő�̖�肪�������Ƃ����悤�B
�@�g���b�N��n�̒��S�ł������ē���������Ă݂āA���Â��Ƃ�������������ꂽ�B
�@�ē��ɏ㗤���āA�܂��������ꂽ�̂́A�ݕǂɓ����̏��^�g���b�N���W�����Ă������Ƃł���B���^�g���b�N�A�s�b�N�A�b�v�A���^�g���b�N�̉ב�ɖؐ��x���`�����t�������̂���A���^�_���v�J�[�܂Ő��������Ă���B
���ꂪ���̗B��̌�ʋ@�ւŁA�S������グ�A���̎Ԃɂ݂�Ȃ����悵�ē������̂��Ƃ����B�g���b�N�����g���b�N�ɏ���Ĉ�������Ƃ����Ή���ȑʂ����ɂ����Ȃ�Ȃ����A�{���Ȃ̂ł���B
�@���̊ݕǂɁu������905�v�Ə�����A�ܐ��g�����f�������D���┑���A���X�H�ꂩ��X��ςݍ���ł����B
�@�����̋��D�����������m�܂ʼn��m���Ƃɏo������Ȃǂ����ߔN�̌��ۂ��Ƃ������A�D���u���B�v�Ƃ������̋��D�����{����w���������ÑD�炵���B
�@���ꂩ��}�O�����Ƃɏo�����邻�������A���{�̐��Y�Ǝ҂ƌ_���������D�Ǝv����B
�@���^�g���b�N�ɕ��悵����s�͍����ɉē������͂��߂��B
�@�܂����̏W��ɘA��Ă�����āA���H�ɓ��{�̖��̓����̃p�b�N�ٓ����z��ꂽ�B
�@�W��̓R���N���[�g���ŏ��Ƀr�j�^�C�����\���Ă���A�₽���ė������B
�@�����Ƀ��V�̎������ׂĂ���A���h�����Ƃ����B
�@���i�Ȃ��j�̂悤�ȎR���Ŏ��̏������Č����J���Ă���B
�@�������������Ĉ����A�₽�����悢�Â��łȂ��Ȃ��|���B
�@�H��̉ʕ��̃o�i�i�̓����L�[�o�i�i�̂悤�ɏ��^�ł��邪�A�ʎ��ɂȂ����܂ܐ��n�����̂ŁA���肪�悭�����Z���B
�@���̗����▯�Ƃ̎��ӂ̐A�͂ɂ̓R�R�i�b�c�A�o�i�i�A�p���̖������A��n�ɂ̓^���C�����A���Ă���B
�@�����ɂ܂����āA�}���S�[�A�p�p�C���A���k�ނ̃i�C�r�X�Ȃǂ����邱�Ƃ��ł���B
�@�N�����ԏ�Ő������Ă������A��l�ɂ��R�R�i�b�c���ܖ{�A�o�i�i����{�A�p���̖���{����A�N���̐H�Ƃɍ���Ȃ��Ƃ����i�{�����ȁH�j�B
�@���܂̋G�߂͂܂������e��̉ʕ��̎��͐��A�ʕ��̖��o���y���ނɂ͋G�߂͂���ł������B
5.5 �j�s�����ꂽ��n�̐�
�@�ē�����̃g���b�N�̍s��h���C�u���͂��܂������A���l�l�N�ꎵ���E�ꔪ���̕ČR�@�������ɂ����P�ŁA���̊C�R�{�݂̑啔���͔j��A������H�̗����ɂ́A���C�R�̎{�݂̃R���N���[�g�̖和��K�i�A�s���e�B�[�����z�̓y��Ȃǂ�����ɂ������A���C�R�a�@�̌��������݂͊w�Z�̎{�݂ɓ]�p����Ă̂����Ă��邭�炢���Ƃ����B
�@�Â��S�����[�������{�����ɕ��ׂĒu���Ă���B�{�i�I�ȎO�Z�L�����[���i�����ꃁ�[�g���̏d�ʁA�W������Z���[�g���j�ł��邪�A���Ɏg�����̂��B
�@���߂���̏I�_�߂��A���H�̊C�ݑ��ɌÂ����ΐ��̔z�ǂ����тĂ���̂ɋC�t�����B�R���ɂ��e��ɂ��������Ղł��낤���B
�@�ܑ��Ȃ��A���^�Ԃ̂���Ⴂ������ƂƂ����A���̈�����H�͋��C�R���ォ�炻���������̂��낤���B
�@���̓��H�̏�Ԃł́A�R���E�e��Ȃǂ̕⋋�@�\�̒��x���������m�ꂽ���̂������낤�B
�@�R����n�Ƃ��ẴC���t�����n��������̂ɂ����������ꂽ�B
�@�u���{�̐^��p�v�Ƃ��u���m�̃W�u�����^���v�Ƃ��A�펞���̍����ɐ�`���Ă����A���̓��̕n���������炯�����Ă���悤�Ȃ��̂��B
�@���H�̊C���̓}���O���[�u�т��悭���B���A���������㗤�����ݕLjȊO�ɕ⋋�p�D���̐ڊݐݔ����������悤�ɂ������Ȃ������B
�@��P�̔�Q�����R�тɂǂ̒��x�̉e����^�������������������Ƃ��Ȃ����A�R���͔M�щJ�т̗l����悵�āA���悭���Ă����B
�@�����ܕ��ɍ`�ɋA�蒅���A�D��ǂ͂��܂��������ւ��Ă��Ί݂̒|�����A��ǂ͒��v�������{�̊͑D�Ȃǂ����邽�߂̃V���m�[�P�����O�w�B
�@�l�l�N�̃g���b�N���P�Œ┑���̊͑D�l�O�ǂ����߂���i�ق��Ɍܓ�Ǒ����j�A���O�[���̒�ɒ��ꂵ�A�܁Z�N���ւĎX�肪���炵�čD�K�Ȋ��̋��ʂ��������Â���A��D�̃_�C�r���O�E�X�|�b�g�ƂȂ�A�����͑D�̎c�[�������g���b�N�B���{�̊ό������̖ڋ��ƂȂ��Ă���B
�@�|���́A�̂��ɗ���U���@���������ł���悤�Ɋg�����ꂽ���A�퓬�@�p��s��̐��ł���B
�@�������A���̍��Ղ͊����H�ՂɌ����Ǝ��ӂ̍L��Ȃǂ̕��R���ɂ̂��邾���ŁA���͂��ׂĖ����������ɂ������Č��ʂ����������A��s��ł��������Ƃ����̂ڂ�����̂͂Ȃ��B
�@�킸���ɔg�~�ꂩ��݂�����A�C�ݐ��ɒ����ŕ��R�ȐΊ_���Â��Ă���A�����đ�������Ċ����H������ꂽ���Ƃ�m�邱�Ƃ��ł���B |

���|���̊����H�Ղ�����������̐Ί_
|
�@�l�l�N�̃g���b�N���P�̒��A�퓬�@����������͑O�邩��Ί݂̉ē��ɓn��A������Ԉ����ɔ��荞�݁A��P��m�����Ƃ��ɂ͂��łɒ|���ɋA�邱�Ƃ��ł����A�啔���̓��{�R�q��@�͒n��Ō��j���ꂽ�Ƃ����B
�@����Ԃ̍q��@�̑��Q�͓Z�@�ŁA�g���b�N�̊C�R�q�͉͂�ł��A�g���b�N�͌R����n�Ƃ��Ă̋@�\�����S�Ɏ������B
6�@���{�͂Ȃ��K�_���J�i���Ő�����̂�
top
6.1 �u�����}�s�v�̍q�H�����ǂ�
�@�Z������A�͂��߂ē�\�����������B�k�ɐ��̏��݂�m��w�j�ƂȂ�k�l������J�V�I�y�A���������ꂽ�ڂɂ́A�����Ȑ����ł����ւ��ɂ����B
�@�悭�씼���ɍs�����l�œ�\�����������Ƃ����l�����邪�A�{���Ɍ����̂��ǂ����^�킵���ꍇ�������Ƃ́A�����Ă��ꂽ���`�������i�@����w�̌��J�u�����a�w�̑n�ݎҁj�̘b�ł���B
�@���`����͐푈���A���R�q��m���w�Z�o�g�̍q��ʐM���Z�Ƃ��ăt�B���s���̑�l�q��R�i�ߕ��ŋΖ������o���̎���ŁA��������Ƃ������������ďڂ����B�������������Ă��ꂽ�B
�@��̋�̋�͒��ɕ���Ŗ��邭�P���P���^�E���X���̃����ƃ���������ł��̐������ǂ�Ɠ�\�������̏\���̏�[�̃����i���j������A���ꂩ��E���ɏ\���̍��[�̃����i�ꓙ���j�A�\���̉��[�̃����i�ꓙ���j�A�\���̉E�[�̃��i�O�����j������B
�@�����ƃ��������ԉ�������ɓ�ɂ�����̂ŁA�q�C�҂ɂƂ��ďd�v�Ȑ����Ƃ��ꂽ�B
�@��Z�����ɂ͐ԓ����z����Ƃ����B�D���ɋ������݂Ȃ���A���͐���ɐԓ��Ղ�����ƁA������Ă���B
�@������s�@�ł͂��łɐԓ������O�����������A�D�ł͂͂��߂ĂȂ̂ŁA���炽�߂Đԓ��Ղ̏K����A���̐̂����Ȃ�ꂽ�Ɠ`�����邢������̘b�Ȃǎv���o���B
�@�悭�����b�ɁA�o�ዾ�̑Ε������Y���ɐԂ��������ɒ���l�ɂ̂������Đԓ������������낤���x���b�����邪�A���̘b�͂ł���߂ł���B
�@�o�ዾ�̃����Y�̂����O�ɒ������Ԏ��͏œ_���ڂ₯�āA�o�ዾ�̎���S�̂��s���N�F�ɐ��߂�ɂ����Ȃ��̂��B���ڂ��o�߂āA�ԓ���ʉ߂����̂͌ߑO�l���l�ꕪ�������ƕ�������A�����Ă��Ēm��ʊԂɐԓ����z�����ƒm��A�C�������Ă��܂����B
�@�Z�������̒��Z���l�ܕ��ɍb�ɏo��ƁA�����ɒ��������������B
�@�u�[�Q���r�����̓쑤�̃u�[�Q���r���C������쓌�ɉ��т���̗��\�����������ŁA���̖k����͖k������`���C�Z�����E�C�T�x�����E�}���C�^���ƂÂ����A���̃C�T�x�����ł���B
�@�쓌��̓u�[�Q���r�����̓�̏����ȓ��ł���V���[�g�����h���ƃ��m���Ƃ̂������̊C���𐼂̃\�������C�ɔ����Ėk���Ɍ��������o�E���ł��邪�A���m������쓌�Ƀx�����y�����E�R�����o���J�����E�j���[�W���[�W�A���E���b�Z�����E�T�{���E�K�_���J�i�����E�T���N���X�g�o�����ƗÂ��B
�@���̓��̗ɂ͂��܂ꂽ�C���\�����������ł���A�����̓�[������A�K�_���J�i�����̂����k�Ƀt�����_��������B�t�����_���쑤�̏����̃c���M��������܂ł̉p�̃\�����������̐����̏��ݒn�ł������B
�@�D�͓�����C�T�x�����ɐڋ߂��A�E�ɓ]�j���}���C�^���Ƃ̂������̊C����쉺���A����ɉE�ɓ]�j���ăt�����_���������ɁA�T�{�����E���Ɍ��Ȃ���c���M�C���ɓ����Ă������B
�@�c���M�C���́A�l��N���������̑�ꎟ�\�������C��ȗ��A���x���C�킪�����Ȃ��Ĕމ�̊͒������݁A�܂����{�̗A���D�c�����߂��āA�C��͊͑D�̕��ƂȂ�A�C�A���{�g���i�S��j�C���ƌĂꂽ�C���ł���B
�@�������̑D�́A�A�H�Ƀ\���������������o�E���Ɍ������̂ŁA�l��N��Z����l���ɑI�肷�����������A���D�c���K�_���J�i���⋋�������s�����A������u�����}�s�v�̍q�H�Ƃ��Ȃ��q�H�����ǂ��Ă���B
6.2 �푈����s�z�j�A����
�@��Z����Z���Ƀ\�����������̎�s�̃z�j�A���`�ɓ��`�����B
�@�z�j�A���̔w��̎R�̓K�_���J�i�����̓��{�R�ɂƂ��ĖY��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��ꂵ�݂̎R�A�E�X�e���R�ł���B
�@���̎R�̔w��̖��тɁA���{�R�͍ŏ�����Ō�܂ŋꂵ�߂�ꂽ�̂ł������B
�@���܁A�z�j�A���̍`�ɋ߂Â�����D���猩����i�F�ł܂��������ꂽ�̂́A�A�E�X�e���R�ɖ��т��Ȃ��Ƃ��������ł������B
�@�����Ƃ��A�z�j�A���͐��Ɍ��݂��ꂽ�s�s�ŁA��풆�܂ł́A�}�^�j�J�E��̍��݂̊C�݂ɂ��������ȏW�����������悤�ł���B
�@���̐��ɏ����ȃN���c�����C�݂����яo���Ă������A���̖������̂܂ܕu���ɑ��������̂��z�j�A���`�ł���B
�@���A�\�������������p�����i�����j������Ƃ��p�A�M�ɑ�����Ɨ����ƂȂ�A��s���c���M������Ί݂̃K�_���J�i�����k�݂Ɍ��݂����V�s�s�z�j�A���Ɉڂ����B
�@���̌_�@�́A�푈���̎l��N�Z���ɓ��{�C�R���K�_���J�i�����ɐi�o���A���݂̃z�j�A���̓��A�����K��̉E�݂ɔ�s���i���Z�Z���[�g�������H�j�̌��݂��J�n���A�����ܓ��Ɋ����H���T���������Ƃł���B
�@�����҂��Ă������̂悤�ɁA���������ɃA�����J�C�������㗤���A�퓬�͂̂قƂ�ǂȂ��C�R���ݕ������R�U�炵�Ĕ�s����̂����B
�@�����m��A���o�E���ɂ��������{�̑攪�͑��i�d���ܐNJ�j�͔��������c���M�C���̕Ċ͑����P���A�č��͑��̏d���l�ǒ��v�E��Ǒ����A�䂪���̑��Q�͏d����ǒ��v�݂̂Ƃ������ʂ��������i��ꎟ�\�������C��j�B
�@�������A���{�C�R�̈����ȂŁA�ꌂ��ɃT�{����������邩�����Ŕ��]���A�����K���ɒ┑���̃A�����J�A���D�c��S���U�������ɁA�}����ނ��ċA�q�����B
�@�������ŕĊC�����͋���ɖ����㗤���������A���{���R�̔�����҂����܂��邱�Ƃ��ł����B
�@�ً}�A�����ꂽ���R�̈�؎x���i�掵�t�c������A���̖��Z�Z�Z���j�挭���́A�����ꔪ���Ƀ^�C�{���ɏ㗤�������A�����ɔ�s��̃e�i���͌��t�߂őS�ł��A�x�����̈�ؐ����卲�͌R�����Ă��Ď��������B
�@����Ȍ�A�l�O�N�����A��E�C�E���̐�͂��s�������{�R���K�_���J�i������������đދp����܂ŁA�����m�푈�̏��s�������㌈�����ߎS�Ȑ퓬�����̓��̔�s��̑��D���߂����Ă����Ȃ�ꂽ�B
�@��s��͕ČR�ɂ���Ċg�������i��O�Z�Z���[�g�������H�j�A���\�������������{�Ɉڊǂ���A�O�܁Z�Z���[�g�������H�������ۋ�`�ɔ��W�����B
�@�ꖜ�܁Z�Z�Z�g���ȏ�̑D�����ڂɒ��݂ł���u���ƁA�C�݉����ɓ��ɑ��铹�H��ʂ��ăA�N�Z�X�̂悢���ۋ�`�����A�V��s�z�j�A�������݂��ꂽ�̂ł���B
�@���Ă����u���œy�n�̐l�X�ɂ�����}�̖������x�������Ȃ�ꂽ�B
�@��̊���ʂ��������̑��ۂ̉������ǂ남�ǂ낵�����ɂ��݂�B
�@���ꂼ���n�̉��Ƃ��������ł���B�o�����Ǘ������D���ɏo�����ė��ă\�����������ւ̓����葱���ς܂��A���ւ��ς܂��A���łɂ�����o�����Ă����X�ǂ���y�Y�ɂ���؎���A�D�����B
�@�Z�������A���Z�����ɒ��H�A�������ɉ��D�B��ՖK��̂`�O���[�v�͎���̃}�C�N���o�X�ɕ��悵�Ĕ����ɍ`���o�����A�܂��z�j�A���x�O�̃A�E�X�e���R�Ɍ��������B |

�K�_���J�i�����ł̊��}�̗x��
|
6.3 ��p���������̓��{�R�̃K����
�@�K�_���J�i�����A������{�c���R���̍��Q�d�ł������̖���m��Ȃ��������̓����A�����m��̌����ɂȂ�Ƃ͒N���\�z���Ȃ������ł��낤�B
�@�ǂ����Ă����������ƂɂȂ����̂��B
�@�ő�̖��͎R�{�\�Z�A���͑��i�ߒ����̐헪�\�z�̍d�����ɂ������Ƃ����悤�B
�@�R�{���Z������헪��ł��o���A�J�활���ɐ^��p����P������p��́A�O��I�葱�܂Ȃ������J���P�ł������_�i����͊͑��̐ӔC�ł͂Ȃ��j�������A�����Ȃ��B
�@�^��p�U�����┑�͑��̍U���ɂƂǂ܂�A��n�j����ő�̖ړI�Ƃ��Ȃ������̂́A�A���͑��̐ӔC�Ȃ̂��U�������̐ӔC�Ȃ̂��A������ɂ��挻��̐ӔC�ɑ�����B
�@�R�{�ɑ�����ő�̐ӔC�́A�^��p�U����A���@�������ɌP���ƌ�p�җ{���̋�����Ԃ�^���Ȃ��������Ƃł���B
�@���@�������́A�p�C���b�g�̔�J��~�ς������x�𗎂����߂Ƃ��������悤���Ȃ��قǁA�|�[�g�E�_�[�E�B����P�A�C���h�m�@�����ƁA�K�v�͈͂��z�������ɍ��g����A�������̉ʂĂɃ~�b�h�E�F�[���ɋ��o���ꂽ�B
�@���̊��Ԃ��P���ƕ�[�v���{������ɏ[�Ă��Ȃ�A���{�̋��p�C���b�g�̗��x�͂���Ɍ��サ�A��������ɋ��͍ڋ@�̏n���p�C���b�g�̕�[��ɋꂵ�߂��邱�Ƃ��Ȃ������ł��낤�B
�@�^��p����~�b�h�E�F�[�܂ł̊��Ԃ̋���P�������낻���ɂ������߁A�~�b�h�E�F�[�Ő��s�̋���p�C���b�g���������Ƃ��A����p�C���b�g���[���鏀�����Ȃ������B
�@���̂��Ƃ���n�q�̖͂����ȑO�i�z���ւƊC�R����藧�Ă��B
�@���{�C�R�̊�{�헪�͑Ε�籌��i�悤�������}�����j���ł��������A�J��O�ɁA���̌���\��C�ʂ͓����̏��}������}���A�i�C��A�����ă}�[�V�����C��ɂ܂őO�i�����B
�@�����籌����̈���z�����N�U���ƂȂ����B�����ŘA���͑��d�n�Ƃ��Ẵg���b�N���̐헪�I�Ӌ`���傫���Ȃ�A�g���b�N�h�q�̑O�i��n�Ƃ��ă��o�E���̒n�ʂ����ڂ����悤�ɂȂ����B
�@���R�͂͂��߃��o�E���U���ɗ��R���͂��g�p���邱�Ƃɂ����������B
�@��⋗A���̂��ׂĂ��C�R�Ɉˑ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������m��̉��u�n�̓��ׂɁA���R������h�����邱�Ƃ̊댯���l��������ł���B
�@��p������A���̔��͐����������B
�@�Ȃ����R���K���D����ɂ����āA���̌������|�ɔ����Ȃ������̂��A���܂��ɗ����ɋꂵ�ށB
�@�A���͑��̓K���h���̗��R�����ւ̕⋋�ɐӔC�����Ɩ������A���̖������ۏ͂Ȃ������B
�@�����Ƃ��A�A��A���œ��{�R�̕s�s�_�b��M���Ă����A�����̎v���オ�������C�R�̍�퓖�ǂ́A���̂悤�Ȋ�{�I�Ȑ�p�����ȂǖY��Ă����̂ł��낤���B
�@�A�����J�͑����m��킪���㗤���ƂȂ邱�Ƃ�\�����āA�C�R���琶�ݏo���ꂽ�C�����𐅗����p�핔���Ƃ��Ĉ琬���A�C�����̐������p���̍ŏ��̕���ɃK����I���A���{���퓬������z�u���Ă��Ȃ������K���ł͐������p���̕K�v���Ȃ������B
�@��������Z�Z�Z�Z�L���A���{�R�őO���̃��o�E�����炳��Ɉ�Z�Z�Z�L���̃K���ɔ�s������݂��悤�Ȃǂƍl�����̂��C�R�̂ǂ̎Q�d�ł��������A���̖��͖��炩�ɂ���Ă��Ȃ��B
�@�ނɂ͂�������{�C�R���ւ�[����̍q���͂������Ă��Ă��A�r���̒��p��n�Ȃ��ɁA���o�E�������Z�Z�Z�L���u�Ă����ɁA�q���n���݂��ꋓ�ɐ��i���邱�Ƃ��A�ǂ�ȂɌ��������������ł��Ȃ������炵���B
�@����ɏd�v�Ȍ��������́A�푈�I���_���l�����Ȃ��������Ƃł���B��͍͂���̋����̓��ɔ���Ⴕ�Ē�������B
�@���{�̂Ƃڂ�����͂Ƃ��ɊC��A���͂������Ă���A���o�E�����قۑΓG��J�v���X�E�}�C�i�X�E�[���̌��E�_�ɂ���A������z����}�C�i�X��͂ɓ]����B
�@���̐푈�I���_�̎v�z������I�Ɍ������Ă����̂����{�C�R�̐�p�v�z�ł������B
�@���o�E���̑攪�͑��Q�d�߂Ă����Ƃ��̐_�d���i���݂����̂�j�Q�d���A
�@�u�K�_���J�i������������o�E���͎��Ȃ��A���o�E����������g���b�N�͎��Ȃ��A�g���b�N��������Γ��{�͎��Ȃ��v
�@�Ɓu�����v�i�����I�j��f�������������A����Ȏq�����݂��P���ȃh�~�m���_���C�R�����Œʗp���Ă����Ƃ���A�����͂��Ȃ��B
6.4 ��{�헪��Y�ꂽ���{���C�R
�@�܂��A���{�R���ڑO�̊�{�헪��Y��Ă��܂������Ƃ��w�E�����B���{�C�R�̗\�肵������C�ʂ͒��������m�ł������͂��ł���B
�@�ĊC�R���܂��Γ�����̏�𒆕������m�ɋ��߂Ă����B
�@�ĊC�R�̑Γ��헪�́A�}�[�V�����A�g���b�N�A�}���A�i�A�����i���邢�͑�p�j�̐N�U���C����ݒ肵�Ă����B
�@���ۂɂ͓��{����ăM���o�[�g�������̂����̂ŁA�A�����J�͑��̒��������m�N�U���͎l�O�N��ꌎ�̃}�L���E�^���������U���킩��͂��܂�A�}�[�V���������̃N�F�[�����E���I�b�g���U�������̂��A�g���b�N�ɂ����͑��d�n�Ƃ��ău���E���i�G�j�E�F�g�N�j�ʂ����p�ł��邱�Ƃ����������̂ŁA�v�lj����ꂽ�Ɛ��������g���b�N�U�����X�L�b�v���āA�}���A�i�Ɍ��������B
�@�}���A�i�Ɖ���̂������Ƀp���I�̃y�������[�E�A���K�E���ƃt�B���s���̍U���킪�}�����ꂽ�̂́A����Ŕs��ăt�B���s����E�o����ɂ�����A�u�A�C�@�V�����@���^�[���� I shall return! �v�̌��t���̂������Ƃ����A�쐼�����m���ʎi�ߊ��̃}�b�J�[�T�[�̖ʎq�����Ă邽�߂̍��ł���A���{�̑����������߂����ČR�ɂƂ��ĕK�v�s���̍��ł͂Ȃ������B
�@��v�Ȑ헪���ʂłȂ��A�I���ʂɉ߂��Ȃ��쐼�����m���ʂ̎琨���ɁA���{�͂Ȃ��S��͂𓊓����Ă��܂����̂��B���̕s�v�c�Ȑ헪���ʂ̓]���ɂ��āA�R�ߕ������Ȃ�A���͑��i�ߒ����Ȃ肪���m�Ȍ��f������������������̂��낤���B
�@�������邸��Ə�ɒǐ����A��Ȃ��̏��Ր�Ɉ������荞�܂�Ă������Ƃ����̂��^���ł��낤�B
�@�K���̔�s�ꂪ�T�����A�K���̊C�R�݉c�����퓬�@�̐i�o�����o�E���ɗv�����Ă����Ƃ��A���o�E���̗��C�R�i�ߕ��Ƃ��Ƀ|�[�g�E�����X�r�[���H�U�����̔����ɂ��A���̕��ɂ��ׂĂ̗͂��z���Ƃ��Ă����B
�@�K���ւ̐퓬�@�i�o�Ȃǂ��������Ƃ͂���܂��Ƃ����̂��A���o�E���̎i�ߕ��̔��f�������Ǝv����B
�@�܂�����s�ꂪ�g����悤�ɂȂ��������ɕČR���㗤���Ă���ȂǂƂ́A���z���ɂ��Ȃ��������낤�B
�@�������A�����Ƃ����͕̂ČR�ł���B
�@��ł����ΕČR�����{�R�̗\�z�����Ȃ��������ł����̂ɂ��������{�R�͂�����݂����ɂ��̐���邱�Ƃɖ����ɂȂ�S�ʂ̋ǖʂ�����ڂ��Ȃ����Ă��܂����B���ꂪ�K����ł������B
�@�Ֆʂ̋��ɑł����܂ꂽ�͂���Ȃ�̌��ʂ�����ł��낤���A���̐�����Ă���������Ƃ����đS�ʂ̋ǖʂւ̒v���I�ȉe���͂Ȃ��B
�@��ł����A�Ֆʂ̋��̍��i�R�E�j�����ɂ̂߂肱��ŏ��Ȃ��������Ԃ��g���͂����ĎS�s�����U����ł��ł���A�����ł����A�ˏo�������Ԃ������邽�߂ɔ�Ԋp�������܂ł����݉����𗇂ɂ��Ă��܂����悤�Ȃ��̂ł���B
�@���R�ɂ��Ă����A�q�͂̔h���Ȃ��A�헪�P���i�t�c�j���ӂ��܂��A���ꂼ������O�������Ƃ���W�߂̎x���O����͂Ƃ���ϑ��I�ȑ�ꎵ�R��g���A���̏������͂ŁA�t�����X�̃j���[�J���h�j�A�A�t�B�W�[�����A�T���A�����A�|�[�g�E�����X�r�[�܂ōL�͂ȓ쑾���m�̏������U�����悤�ƌv�悵���̂�����A����܂����C�̍����Ƃ͂����Ȃ��B
�@���̌��ʂ��A��������Ƃ����߂�ׂ����͂̒��������ƂȂ��Ă������B
�@�쑾���m���̌v��͕ČR�̃K���㗤�łԂ�A�����ɂ̓|�[�g�E�����X�r�[���H�U�����ƃK���D����Ƃ����s���Ă����Ȃ�ꂽ���A��ɂ��G�ꂽ�悤�ɁA�����ƃ��o�E���̈ʒu����v����悤�ɒn�}���d�˂�ƁA�|�[�g�E�����X�r�[�͒Ìy�C���̏��O���A�K���͑Δn�C���̐������i���N�C���j�ɑ�������B
�@���{�̖{�y���L�����ŁA�����͎t�c�ɂ�����Ȃ��A�R�Ƃ͖��݂̂̕��͂ō������s�����̂ł��邩��A�܂��������d�ȍ��ł���A�Q�d�{���̉��̉@�Ƃ���ꂽ��핔�̎Q�d�����̖��\�������Ă���B
�@�Q�d�Ƃ́u���d�A���\�A���\�̎O�ڂ��v�Ƃ͂悭�����������̂ł���B
�@�K���̐�Ղ߂���ŁA�A�E�X�e���R�A�G�f�B�\���E���b�W�i�����߂̋u�E�ނ��ō��n�j�A�e�i���A�w���_�[�\����s��̏����ɉ��A�z�j�A���Ɉ����Ԃ��ăz�j�A���E�z�e���Œ��H���A�ߌ�͊C�݂𐼂ɑ����ăR�J���{�i�����̑��t�c�㗤�n���Ȃ킿�ێR���i�}�����}�E�g���C���j�̋N�_��ʂ�A�푈�����قւƉ�����B
7�@�W�����O�����������K�_���J�i����
top
7.1 ���Ղ̃W�����O����������
�@�܂��������̂́A�D�ォ��]�������悤�ɁA���ĔM�щJ�т̖��тɂ������A���{�R�̍s�����������邵���j�Q���A�����̕��m�������Q���ƃ}�����A�ɓ|��āA�ނȂ�������ł������n��̖��т����S�ɔ��̂���A�����̑��R�Ɖ����Ă��邱�Ƃł������B
�@�A�E�X�e���R�Ƀ}�C�N���o�X�œo���Ƃ����̂��l����Εs�v�c�ł��邪�A�R�ォ��̌����炵�̗ǂ����q��ł͂Ȃ��B
�ꌩ�����Ƃ���A����͂܂�ŃS���t�ꂩ���q��ł͂Ȃ����B
�@���t�c�́A���ђ����I��@�����ē�ʂ����s����U�����邽�߂ɃA�E�X�e���R��[�ɏ��a���J���A���̏��a���t�c���̊ێR���j�����̐��ɂ��Ȃ�ŊێR���Ɩ��t�������A��j�p���w�쑾���m���R���q2�r�x�͊ێR���ɂ��Ď��̂悤�ɋL���Ă���B
�@���t�c��͂̑O�i�����ێR���́A��Օ���A���̔��̂�����k�������̒ʉ߂���Ƃ��Ė�܁Z�`�Z�Z�W���ɃW�����O�����J�������̂ŁA�}�s�ȍ⓹�������A�������f���ꂽ���я�Q�̏Ƃ͑S���l�����قȂ�A�s�R�͗e�ՂłȂ������B
�@���ɂ���Ē����I�ɒʘH���J�������߁A�}��ł͎v�������ʏs�₪���X�ɂ����āA�����̓W�����O���̖��i��j�ɂ�����Ȃ���o�����B
�@�e�����͏��Z�ȉ��������̗��a�Ǝ��Ă邾���̒e���w�����A�t�c�S������{������ʏc���őO�i�����B |
�@�l��l������ƈ��łƂ������x�ɁA���т̉��������Ђ炢���̂��ێR���ł������B
�@�A�E�X�e���R�̐������։I��ێR�����A���܂��A�E�X�e���R���猩���낷���Ƃ��ł���Ƃ������Ƃɂ����̌o�߂����������邪�A���̊ێR�������̎Ζʂ��͂����Ă���p�͉��Ƃ��Ԃ̔��������̂ɂ݂���B
�@�K����̍ŏI�ǖʂŁA���{�R�̓A�E�X�e���R�t�߂̒J�Ԃ̖��ђ��ɒǂ��߂��A��͂���A�̗͂��s�������m�����͎��X�Ɠ|��Ă������B
�@�Ȃ�����ȂƂ���ŁA����Ȃ������̕��m�������Q���ƕa�ɓ|���˂Ȃ�Ȃ������̂��B
�@�o�X�͊C�݉����ɓ��ɂ͂���A���ɕČR�A���D�c�̗g���n�ł����������K���n�����ă����K����킽��A���݂͍��ۋ�`�ƂȂ��Ă���w���_�[�\����s��̓��[�����A�����H�쑤�̍��n��o�����B
�@�ŏ��̓ˏo�������n���G�f�B�\���E���b�W�ł���B |

���{�R���̐ՁE�A�E�X�e���R��]��
|
�@�����̓��{�R���B�e�����q��ʐ^�ɂ��ƁA���n�̔����͊J�������n�ł��邪�A�Ζʂ��烋���K��̗��݂ɂ����Ă͂т�����Ɩ��тɂ������Ă���B
�@���܁A���������n���烋���K��̗��݂܂Ō��ʂ����悭�A���т͂Ȃ��A�����ɍ������d���̓S���������Ă���B
�@��؎x����Ō�ɁA�p���I�������x���i��������l�A����ܑ̌���j���K���ɑ��荞�܂�Ă�͂�^�C�{���ɏ㗤���A��s��̓��C�݂����̍��n�ɉI�ċ㌎�����ɔ�s��ɖ�P���������B
�@���̂Ƃ��ɂ́A����x���͂��̍��n��˔j���邱�Ƃ��ł��A���̔w��̑����ōU����j�~����đދp�����B
�@���ő��t�c���K���ɑ��荞�܂ꂽ�Ƃ��A�ČR�͂��̍��n�̐w�n���������Ă����B
�@��Z����ܓ��̑��t�c�̑��U���ɍۂ��A�E�������̐�����������͂��̎��������A���肩��h������Ă�����{�c���Q�d�̒Ґ��M�����ɉE����I��U�������������ł���Ɛi�����A�҂̗����������B
�@�������A�҂����̌����ێR�t�c���ɂǂ������̂��A���̒���ɐ���͓d�b�ʼnE���������Ƃ��ꂽ�B
�@�U���J�n���O�̎w������Ƃ͕����̎w�������������A�E�����̍s���͐ϋɐ����������B
�@���̍��n�̐��ʍU���Ɍ��������̂��������i��͕͂�������A���j�ł������B
�@�U���͊��S�Ɏ��s���A���������̓ߐ{�|�Y�����͐펀�A��������A�����Ë{�����Y�卲�͌R���ƂƂ��ɍs���s���A��������A�����L�����Y�卲���펀�Ƃ����S�W���錋�ʂɏI������B
�@�������̍��n�̈�p�ɑ��t�c�����x���̈ԗ�肪���Ă��Ă����B |

���J�f���n�̐���x���ԗ��
|
7.2 �J�J�I��A�o�A�`���R���[�g��A��
�@��s�ꐳ�ʂɂ��ǂ�ƁA���ʍL��ɃK���h���������ČR����������L�O�肪�����Ă���B
�@���̓K���ɏ㗤���ē��{�R�Ɛ�����̂͊C Second Marin Devisin �Ɩ��L���Ă���A���ݍ��܂�Ă�����͂��C�����t�c�̋J�͂ł������B
�@���̔�͒n�������Ă����̂炵���A�蕶�́u���E�͂��Ȃ������̂������ʼn�����ꂽ�v�Ƃ����^���ŏI����Ă���B
�@�A�����Ă��璲�ׂĂ݂�ƁA�l��N���������ɏ㗤�����̂͊C�����t�c�ł���A��ꌎ���{����C�����t�c�Ɨ��R�̃A�����J���t�c�̑������J�n����A�l���̑��Ղ��͂������i�啔���̓}�����A�j�A��͂��ቺ�����C�����t�c�͈�ꌎ���܂łɃK������P�ނ��A�l�O�N�ꌎ����܂łɊC�����t�c�E���R�̃A�����J���t�c�E���t�c���㗤�����������B
�@�K���ł����Ƃ��ꂵ���퓬�ɏ]�������̂͊C�����t�c�ł��������A���̖��͔�s�ꐳ�ʍL��̋L�O��ɏo�Ă��Ȃ��B
�@����ɂ��Ă��A����̍Œ��ł��A�����J�R�͐퓬�����̌�㐧�x���ێ����Â����̂ł���B
�@�̂̍q��ʐ^�����Ă��w���_�[�\����s��̑O�ʂ̕��n�̓R�R�i�b�c�̗тł���A�Ƃ������A���{�C�R�����R�ȃ��V���̂��Ċ����H���}�������̂ł��낤�B
�@�������A�����H�̔w��̃��J�f���n�ɂ����Ă͖��тł���B
�@���܁A���J�f���n�ɂ����铹�̗����͈�ʂɃR�R�i�b�c���A�͂���Ă���B
�@���̕t�߂̃��V���̃R�R�i�b�c�͊C�ݕ��ʂɂ���w�̍������V�Ƃ������A���������[�g�����炢�̍����ő����̎������Ă���B
�@�n�C�u���b�h�Ȃ̂��Ɛ������ꂽ�B
�@�Z�C�������Y�̃L���O���V����z�������̂ł��낤���B
�@��s�ꂩ��e�i���ɂ����铹�̗����ł̓J�J�I�͔̍|������ł���B
�@�J�J�I���͂悭����ꂳ��Ă���A�A�o�_�Y���Ƃ��ďd�v�Ȓn�ʂ����߂Ă��邱�Ƃ��킩��B
�@���̒m���l�ł���ē������͂����B
�@�u�J�J�I�͑�ʂɗA�o����Ă��܂��B�������A�A�o�����ʂ��͂邩�ɏ��Ȃ��ʂ����ɍ����l�i�ŗA������ē��ɂ��ǂ��Ă��܂��B�`���R���[�g�̌`�����Ăł��v
�@���̌��t�́A�ꎟ�Y�i�i�R�v���E�J�J�I�E�؍ށj�̗A�o�Ƌ��ƌ��i��Ƃ��ăJ�c�I�j�����Ɉˑ����Ă���A���̍��̌o�ς̔ߌ��I���i���ے����Ă���B
�@�z�j�A�����琼�ɐ푈�����ق������r���A�C�݂ɋ���Ȗ؍ޏW�Ϗꂪ�������B
�@���a�܁Z�Z���`�ȏ�̗ǎ��̖؍ނł���B�؍ނڂ����g���[���E�g���b�N�Ƃ������Ή�����B
�@�z�j�A���Ȑ��̂��̊C�݂ł́A���V���̂��ĊC�������A�G�r�̗{�B������Ă�����i�������������B
�@��p�⒆���A�C���h�l�V�A��^�C�ɍL���������{�����A�o���i�Ƃ��ẴG�r�̗{�B���A�Ƃ��Ƃ��\�����������̉ʂĂɂ܂ł���т���̂��B
�@�e�i���́A�ŏ��ɃK���D��ɔh�����ꂽ��؎x���̐挭�����㗤���X�ɑS�ł�����ꂽ�Ƃ���ł���B
�@���������ɃK���ɏ㗤�����ČR�͊C�����t�c�i���͖�j�ŋ���܂łɈꖜ�ȏ�̕��͂��㗤�����Ă����B
�@��؎x���̓~�b�h�E�F�[�U�����̂��߂ɖk�C���̑掵�t�c����Ґ����ꂽ���A�~�b�h�E�F�[�C��̔s��ɂ���킪���~����ăO�A��������A���̓r���A�}篌Ăт��ǂ���Ă��̑���c��Z�Z�����g���b�N����쒀�͂ŃK���ɒ��s�����B
�@�����ꔪ���ɔ�s��̃^�C�{���ɏ㗤�����x���挭���i���͋�Z�Z�j�͓��������ɊC�݉����ɔ�s��U�����J�n�������A�D���ȕČR�̔������A�펀�������A�����O�Z�A�܂�S�ŏ�ԂŐ퓬�͏I�������B
7.3 �푈���̏Z������
�@��؎x���S�ł̒n�ɋL�O�肪���Ă��Ă��邪�A�����͕ČR�̖��a�@�̐Ղł�����B
�@���݂́A���V�̒�����i�͂�j���قŊ����đg�݁A�|�ƃ��V�̗t�ŕǂƉ��������傫�ȏW������Ă��Ă���A�����Ő��̌��������Z���̘b�����B���{�R�ɒ��p���ꂽ�Z����l�A�A���n�@�卑�̉p���ɏ����Ƃ��Ē��p���ꂽ�Z����l�̘b�����B
�@�Z���̉p���ɂ��A���n�x�z�ւ̉��O�͋������A�č��ɂ������Ă͈�ۂ��������悤���B
�@�ČR�͏Z������@�卑�̉p���Ɉ�C�������炾�낤���B
�@�p�R�ɒ��p���ꂽ�Z���͖������������A�|�X�g�E�E�H�c�`���[�i���݊Ď����j�Ƃ��ăj���[�W���[�W�A���̃����_�ɔh�����ꂽ�Ƃ����B
�@���{�R�͌��n�̏Z����M�p�ł��Ȃ��ƍl���Ă���A�Z���ł�������������������̎�̊����ɁA�Z���̋��͂�Ƃ������z���Ȃ������B
�@�A�����J�Ɠ��{�ɂ��Ă̊��z���ƁA�����͊��ق��Ăق����Ƃ����B
�@���ݗ�������o�ω������Ă��闧�������Ȗ�肾����A�Ƃ̂��Ƃł���B
�@�ē������́A�X�y�C��������ƃ}�����A�𓇂ɂ����A�C�M���X������\�͓I�Ɏx�z���A���{�����ɐ푈���������A�Ɣ����������A��͂�A�����J�ɂ��Ă̓R�����g���Ȃ������B
�@�K���ł͓��Ă̌��킪����Ђ낰��ꂽ�B
�@�������A���̐��ƂȂ����y�n�́A���a��O���L���A�Z�a�l�܃L���̓����ɒ����ȉ~�`�Ɏ����K���́A�k�C�݉����l�܃L���ȓ��A�����w�ꁛ�L���ȓ��̈ꕔ�̓y�n�ł���A���������ďZ���̑����͐��O�ɔ��Đ푈��������Ƃ����B
�@�K���̐�͎l�O�N�����̓��{�R�P�ނł����܂������A���̊ԁA�㗤�������{�R���l���O����l�Z�Z���E�P�ވȑO�̗������ғ����l�Z���E��a������эs���s���Z�Z�����E���C�R�P�ސl���ꖜ�Z�ܓA�K���ɏ㗤���������̎O���̓A��Ƃ��ċQ���ƃ}�����A�ɂ��̗͏��ՂŃK���̖��т̓y�ƂȂ��Ďp���������̂������B
�@�z�j�A���Ƌ�`�̂������A�˂������H�����̃����K����C�z���̓��H���Ƃ��邽�тɁA����͓��{�̂n�c�`�����Ŏ{�H�͓��{�̂j�g�ł��Ɛ��������̂ɂ͂܂������B
�@�Ƃ����̂́A���{�̑��[�l�R���̂j�g�́A�I�[�X�g�����A�̌��ݍH���ɐi�o���āA�V�h�j�[�p��������g���l���̌��݂��Ă��Ď�����������A�X�L�[��̘[���璸��܂Ńg���l�����@���ĔN�ɎO���������^�s���Ȃ��o�R�n���S�𑖂点�����i���{�ɂ��Ȃ����̍��؎{�݂����X�L�[��͂܂��Ȃ��|�Y�����j�A���j�[�N�Ȏ��ƂŗL������������ł���B
�@���ꂪ�K���̏����ȋ��̉˂������H���܂Ő��������Ă���Ƃ́A�����܂����i�o�Ԃ�ł���B
�@�K������p���I�܂ŁA�K���̊����̐��ƂŌ������̃��[�[�X����D�����B
�@�Z���ꎵ���A���o�E������p���I�܂ł̑D�̒��ŁA���[�[�X�����������ރV���|�W�E�����J���ꂽ�B
�@���тł������͂��̃K�_���J�i���̎R�X�����̑��R�ɂȂ��Ă������ƂɁA�݂�ȃV���b�N���������炵���A���̖��Ɏ��₪�W�������B
�@�K�_���J�i���̃c�A�[�Ő�Ղ�K�˂�O���[�v�̂ق��ɁA�M�щJ�т̊ώ@�O���[�v�����������A���̃O���[�v�ɎQ��������l�����[�[�X����ɁA�ē����ꂽ���т��z���Ɗ|������ĂƂĂ������тƂ͎v���Ȃ����A�K�_���J�i���̌����т͂���Ȃ��̂��ƁA���₵���B
�@���[�[�X����͂�������ƁA���Ȃ������ē����ꂽ�̂͂��Ԃ��x���̂��ꂽ��̓тł��傤�A�Ɠ������B
�@�\�������̗A�o���i�͐�ɏ������悤�ɃR�v���E�J�J�I�E�؍ށE���Y�����炢�ł��邪�A�Γ��A�o���z�̂����؍ނ̐�߂�䗦�͈���Z�N�Ō܋�E�܁��ł������i�W�F�g���f�Վs��V���[�Y�w���E�쑾���m�����卑�x�j�B
�@�؍ނ̔��͎̂�Ƃ��Ċ؍��ƃ}���[�V�A�̋Ǝ҂������Ȃ��A���̗A�o��͘Z���܂ł����{���Ƃ����B
�@���{�͎����̎���������A�\�������ő�̊��j��҂ƂȂ��Ă���B
�}���[�V�A�̃T�����N�͓��{�ɂ��M�щJ�є��̂̔�Q�ŗL�������A���̃}���[�V�A�̋Ǝ҂����{�̂��߂Ƀ\�������̔M�щJ�т�܂����Ă����Ƃ͒m��Ȃ������B
�@�A�o�؍ނ̑����̓R���N���[�g�p�l���p���̑f�ނƂ���Ă���B
7.4 �n�c�`�Ńy�b�g�t�[�h���Y
�@�o�ω����̓\�������������ɂƂ��Č������Ƃ̂ł��Ȃ������ł��邪�A���Ƃ��c���M��j���[�W���[�W�A���m���n��̋��Ɗ�n�����Ɏx�o���ꂽ���{�̂n�c�`�́A������A�\�������������{�Ɠ��{�̑�m���Ɗ�����ЂƂ̍��َ��ƂƂ��Ĉ�㎵�O�N�ɐݗ����ꂽ�\�������E�^�C���[��Ђ̂��߂̐�p�{�݂ł���B
�@�\�������E�^�C���[�̓c���M�ƃm���ɗⓀ�q�ɂƉ��H�H��������Ă���B
�@�����A�N�Ԗ�l���g���O��̃}�O���E�J�c�I�̋��l�ʂ̂����A��ꖜ�g�����ʋl�Ƃ��Ē��ڃ��[���b�p�ɗA�o����A����ɗⓀ����r�u�V�ȊO�ɁA�^�C��t�B�W�[�o�R�Ńy�b�g�t�[�h�ʋl�ɉ��H����ē��{�ɗA�o����Ă���Ƃ����B
�@��㎵�O�N�Ƃ����Ύv���o�������A���̔N�Ɏ������ꌧ�{�Ó���K�˂��Ƃ��A�n���̐l�Ɉē�����Ē��H�Ƀ��X�g�����ɓ���ƁA�X���Ő��ꒅ�p�̎q����l�ƕ�e���A�����ɂ����̓��̂͂Ȃ₢�����͋C��������킹�Ȃ���H�������Ă����B
�@�n���̓��s�҂��u�K�_���J�i������̑������Ƃǂ����̂��ȁv�ƂԂ₢���B
�@�u���̕t�߂̋����̉҂���͂��܃K�_���J�i���̃J�c�I���ł��v�Ƃ����̂����s�҂̐����ł������B
�@������A���{�̃J�c�I���Ƃ��K�_���J�i���ɐi�o���Ă��鎖���͒m���Ă������A�����Ŋl�ꂽ�J�c�I���y�b�g�t�[�h�ɉ��H����ē��{�ɗA�o����Ă���Ƃ͒m��Ȃ������B
�@�n���̋��t�������̎�i�Ƃ��Ă����{�ނ�̋����A�J�c�I���̐����a�Ƃ��邽�߂ɑ�ʂɕߊl����A���邢�̓J�c�I���ԋ��̊��Y���Ƃ���āA�n���̋��t�̐������������Ă���B
�@���[�[�X����ɂ��A���{�̂n�c�`�ƍ��ي�Ƃ���Z�Z�Z�l�̎��Ǝ҂ݏo�����Ƃ����B
�@���n�̐��Ƃɂ���Ȑ[���Șb������ċA�������Ƃ���ɁA��ܔN�����O����t�u�����V���v�́u����n���s���@�D�K�_���J�i�����v�ɁA�u�F�D�I�ȑΓ��ς̓y��ɂ́A���n�l���l���ق��Ă��鍇�ي�ƃ\�������E�^�C���[�ɑ�\�������{�̐��Ȍo�ω�����Z�p���͂�����v�A�Ƃ����L�q������̂������B
�@���{�̂n�c�`�́A�����\�������ł̌ٗp�Ɋւ��邩����A���ǃ[���T���E�Q�[���ɉ߂��Ȃ������B
�@�����A���̋L���ɏЉ�ꂽ���n�̐��u���{�͐푈�ɂ͕��������A�o�ϓI�ɏ������v�Ƃ����̂́A���n�̐l�X�̎������낤�B
�@�Ȃɂ���A���{�R�����̐�����ۂݍ���œ��{��s��ɒǂ������̖��ьR���A���̌o�ϗ͂şr�ł��Ă��܂����̂�����B
�@���͑�̋��D���ł��邪�A��������ŐH�ׂ�}�O����J�c�I�͋ߊC���̂ł���B
�@�}�O���̃g���͍D�݂łȂ��̂ŁA�����ς�ߊC�}�O���̐Ԑg�̎h�g��H�ׂĂ���B
�@�J�c�I�́A���Ă̏��J�c�I���A�H���ɒn��̊C�Ŋl��鎉���̂����߂�J�c�I�����H�ׂȂ��B
�@������A�\�������̋���r���Ɏ��͂��܂�֗^���Ă��Ȃ��Ǝv�����A���������b���ƁA�L�⌢���y�b�g�t�[�h�Ŏ����Ă�����^���Ƃ⎩�R�ی�_�҂ȂǂƂ������݂��U�P�҂߂��Č�����B
�@���ĐX�ѕی�̂��߂Ɋ�������߂悤�Ƃ����A�Ԕ���K�v�Ƃ���X�ш琬�̂��߂ɂ��܂�Ӗ��̂Ȃ��^�������������A����������Ǝ����ی�̂��߁A�C�̐��Ԍn�ۑS�̂��߂Ƀy�b�g�t�[�h����߂悤�Ƃ����^���̕�����قǗL�Ӌ`���낤�B
�@�Ƃ���ŁA�K�_���J�i�����܂ރ����l�V�A�ɏZ�ރ����l�V�A�l�ƁA�~�N���l�V�A�ɏZ�ރ~�N���l�V�A�l�Ƃ͂ǂ��������̂��B
�@�����Œ��ׂĂ݂�ƁA�����l�V�A�l�͐l��I�ɂ̓I�[�X�g�����C�h�i���l�j�ƍ������������S���C�h�n�̐l�����ł���A�~�N���l�V�A�l�̓����S���C�h�ɑ�����Ƃ����B
�@��A�W�A����ŏ��ɑ����m�ւƐi�o�����ŌÂ̐l�킪�I�[�X�g�����C�h�ɑ�����I�[�X�g�����A���Z���i�A�{���W�j�j��p�v�A�l�ł���A���Ńj���[�M�j�A�o�R�Ń����l�V�A�̓��X�ɓn���������S���C�h���A�r���Ńp�v�A�l�Ȃǂƍ������ă����l�V�A�l�ƂȂ�A�Ō�ɐԓ��Ȗk�̓��X�ɓn���������S���C�h���~�N���l�V�A�l�ł��낤���B
�@�|���l�V�A�l�������S���C�h�ł���Ƃ������A������̓����l�V�A�̂ǂ�������T���A�ɓn��A�}���P�T�X�������ւē������m�̓��X�ɎU���Ă������炵���B
�@�K�_���J�i���̏Z���ɁA�����l�V�A�l�ł��邪�����������ɋ߂��l���������Ȃ��R����B
�@����͔��l�Ƃ̍����Ȃ̂��낤���B
8�@���ΎR��ł��ǂ������o�E���v��
top
8.1 �ΎR�D�ɖ����ꂽ�s�s���o�E��
�@�z�j�A����[���ɏo�`���A�T�{���Ƃ��̔ޕ��ɉ��ރK���̐��[�̃G�X�y�����X���ɖ��c���ɂ��݂Ȃ���A�D�̓\�������������u�[�Q���r�����ւƌ��������B
�@���A�ڂ��o�܂��đ��̊O������ƁA���O���ɉΎR���炵������������B
�@�n�}�Œ��ׂĂ݂�Ƃǂ����R�����o���J�����炵���B
�@������̓��̓j���[�W���[�W�A���Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�D�͂���Ƀ\�����������𐼖k�ɂ����݁A�E�Ƀ`���C�Z�����A���Ƀx�����x������]�݁A�E�̃V���[�g�����h���ƍ��̃��m���Ƃ̂��������ău�[�Q���r�����̐��C��ɏo���B
�@�����̓����͓��{���D���̃\���������Ր�Ɉ������荞�܂ꂽ�퓬�̐�j�ɂ��Ȃ��݂̓����ł���B
�@�V���[�g�����h���ƃ��m���܂ł��\�������������ɑ����A�V���[�g�����h���ƃu�[�Q���u�C�����Ƃ̂��������p�v�A�j���[�M�j�A���Ƃ̍��������͂����Ă���B
�@����Ɉ�閾�����Z����l�����A�E���ɋ߂��傫�ȓ��������B�q�s���Ԃƒn�}���Q�Ƃ��āA�j���[�A�C�������h���炵���ƌ����������B
�@���H��b�ɏo��ƁA�͂邩���O���ɓ��e�������A���̉E�[�ɏ��ΎR�̒[��Ȏp���������B
�@���̓j���[�u���e�����ŁA���̉ΎR�̘[�Ƀ��o�E���p������͂����B
�@�݂ȍb��ɏo�ċ߂Â����o�E����������B�e������ɖ����ł��������A�X�q�����Ԃ炸�ɍb�ɏo���l�������A���������Ȃ�ɂ�A�ԓ������̑��z��^�ォ�痁�тď������Ƃ��т��������A���X�ƑD���ɔ����B
�@�j���[�u���e�����͓��j���[�M�j�A����_���s�[���C�����u�Ăē����ɉ��т�O�����`�̓��ŁA�p�v�A�j���[�M�j�A�ł̓j���[�M�j�A���ɂ��ő傫�ȓ��ł���B
�@�h�C�c�̃I�Z�A�j�A�̐A���n����ꎟ����ɐԓ��ŕ�������A�k�̃~�N���l�V�A�����{�́A��̃����l�V�A���I�[�X�g�����A�̈ϔC�����̂ƂȂ����B
�@�j���[�M�j�A���̐������̓I�����_�̂ł��������A���܂̓C���h�l�V�A�̐��C���A���ł���B
�@�I�[�X�g�����A�̓j���[�M�j�A���̓������̓쑤�̃I�[�X�g�����A�̃p�v�A�Ɩk���̋��h�C�c�̂̈ϔC�����̂��A�����Ƀp�v�A�j���[�M�j�A�Ƃ��ēƗ��������B
�@���h�C�c�̃I�Z�A�j�A�̎�s�����o�E���ŁA���I�[�X�g�����A�̃p�v�A�̎�s���|�[�g�E�����X�r�[�ł��������A���݂̃p�v�A�j���[�M�j�A�̎�s�̓|�[�g�E�����X�r�[�ł���B
�@��ܔN���݁A���o�E���͔p�ЂƉ����ďZ�������Ȃ��B
����l�N�㌎�������A���o�E���`�̂���V���v�\���p����k���n�Ƃ���}�O�j�`���[�h�Z�E�O�̒n�k�����o�E���܁Z�Z�Z�l�̎s�����������A�Â��ĒÔg���s�X�n��A�Ō�ɓ��̘p���߂��ɐ���オ�����}�`���s�`���R�i�ԍ�R�j�Ƃ��̔w��̃J�C�u�R�i����R�j�A�p�݂̐�������p���ɓ˂��o���o���J���R�i����R�j�̏����ɔ������A�s�X�n�͍~��ς���ΎR�D�Ɍ����������Ė�����A�p�ЂƉ����Ă��܂����B
�@���Ƃ��ƃV���v�\���p�̓J���f���p�ł���B�p�̓쓌���ɂ���p������̌i�F�́A���̂��Ƃ��͂����苳���Ă����B
�@�p���̓쑤���琼�����ւĖk���ɂ�����n�`�͖��炩�ɃJ���f���̉Ό��ǂɓ��L�̒n�`���������Â����Ă���B
�@�p�̓��쑤�ʼnΌ��ǂ���ĊO�C�ɂȂ����Ă���B
�@�������A��k�ɒ����J���f���p�̂قڒ������ɃJ���f���̉Ό��ǂƗ��Â��Ő��̃o���J���R�A���̃}�`���s�`���R�Ȃǂ̒����Ό��u���p���ɂ��肾���A�J���f���p�̉��ɂ���ɓ��p�������Ă���B
8.2 ��D�̊C�R��n�V���v�\���p
�@�J�C�u�R������ΎR�D�̑͐ςŐ��܂ꂽ���R�n�Ƃ��̐�[�̏��������肾���A���R�n�̃��V�����Ђ炢����s��̊����H���}�`���s�`���R�Ɍ������ĉ��тĂ���B
�@���풆�̓���s��ł���B
�@�j���[�u���e�����͑傫�ȓ��ł��邪�A�k�����̃K�[�������ȊO�͊J�����i��ł����A�K�[�������̎�Ƃ��ăV���v�\���p���݂ɏZ���������B
�@�J���f���p�ł���V���v�\���p���`�Ƃ��čœK�̏���������Ă�������ł���A����ɘp���o���C�ʂ̓j���[�A�C�������h���Ƃ̂������̕������܂��ג����Z���g�W���[�W�C���ł���A���������n���I�����͊C�R��n�Ƃ��Ă���D�̏����ł������B
�@������̌��_�́A���̃J���f���p�����ΎR���������������Ă��邱�Ƃł������B
�@���O���N�Ƀo���J���R�E�}�`���s�`���R�������ă��o�E���s�X���قƂ�ǔj��A���̂Ƃ����o�E���̍s���I�@�\�𓌃j���[�M�j�A�̃T�����A�Ɉړ]�����邱�Ƃ��������ꂽ���A����̖u���ɂ��������Ȃ������B
�@���l��N�ꌎ��O���A�x��x���Y�����̎w�������C�x���i�������l�l�A����j�����o�E�����̂��A�Ȍケ�̒n�̓\�������E���j���[�M�j�A���ʂ̍��ɂ����闤�C�R�̋���ȑO����n�ɐ��������B
�@�l��N�l������ɊC�R�̑��܍q�������Ґ�����A���o�E����n�q����ƂȂ����B
�@�܌��ꔪ���ɗ��R�̑�ꎵ�R�i�i�ߊ��E�S�����g�����j�A�C�R�̑攪�͑��i�i�ߒ����E�O��R�ꒆ���j���Ґ�����A������������Ɏi�ߕ������o�E���ɐi�o�����B
�@�K���킪�͂��܂�������̔��������A�����C�R��n�q����̎��핔����ꉺ�ɒu���Ă�������q��͑��i�ߕ��i�����E�ˌ���l�O�i�ɂ������j�����j���}���A�i�̃e�j�A�������烉�o�E���ɐi�o�����B
�@�������ĕ��ΎR��œ��{�R�̃��o�E���v�ǂ����ǂ�͂��߂��B
�@�l��N��ꌎ��Z���A���R�͑攪���ʌR�i�i�ߊ��E�����ϒ����j�E�����j���[�M�j�A���S���̑�ꔪ�R�i�i�ߊ��E���B��\�O�i�͂������j�����j��Ґ����A��ꎵ�R���\���������ɐ�O������ƂƂ��ɁA�쐼�����m�̍����w������攪���ʌR�i�ߕ������o�E���ɐi�o�������B
�@���l���ɂ͊C�R���쓌���ʊ͑��i�����͒ˌ������ƌ�サ�������C�ꒆ�������C�j��V�݂��Ă��̕��ʂ̍���S���������B
�@�������A���̂���A���o�E����n�q����̑��Ղ͎O���@�ɒB���A��͂����łɂ������邵���ቺ���Ă����B
�@�������āA�l��N��O����A��O��c�ŃK�_���J�i�����P�ނ����肳�ꂽ�̂ł������B
�@���R�́A�K���ɑ��t�c�E��O���t�c�𒍂������A����ɑ�Z�t�c���u�[�Q���r�����̖h�q�ɓ�������ƂƂ��ɁA��ꔪ�R�S���̓��j���[�M�j�A�̊m�ۂɏd�_�������A���G�E�T�����A�n��ɑ�܈�t�c�A�E�F���N�ɑ��Z�t�c��h���A��l��t�c����ʌR�����i�̂��E�F���N���ʂɓ]�p�j�Ƃ��A����ɑ�Z��s�t�c�����o�E���ɐi�o�����i�̂��E�F���N�Ɉړ��j�A�m���s�̌P�����ւĂ��Ȃ����R�q�����m����ɓ��������B
�@����͓��{�̗��C�R�����͂������āA���̐�͂�쐼�����m���ʂɒ��������Ƃ��Ӗ�����B
�@�K�_���J�i���̎c�����͂̓P�ލ��͎l�O�N�܂łɂȂ����������A���̊ԁA���j���[�M�j�A�̃u�i���痤�H�|�[�g�E�����X�r�[�U���ɏo��������C�x������уu�i�m�ۂ̂��߂Ɏ���ɂ����������ꗷ�c�͑S�ł����B
�@�����āA���{�S�R���ӂ邦�オ�点���u�_���s�[���C���̔ߌ��v���l�O�N�O���O���ɋN�������B
�@���o�E�����瓌�j���[�M�j�A�̃��G�E�T�����A�n���i���łɐ挭�����㗤���Ă����j�ɐi�o���邽�߂ɁA��܈�t�c�̎�͂����ǂ̗A���D�ɏ��A���ǂ̋쒀�͂Ǝl��@�̒����퓬�@�̌�q�̂��ƂɃ_���s�[���C�������f���A�ČR�@�����P���A�킸���O�Z���ŗA���D�����i��ǂ͑O�����v�j�ƌ�q�̋쒀�͎l�ǂ���������A�쑗�D�c�͑S�ł����B
�@�ČR�@�̋}�~�������ɂ��Ȃ��č������ł������{�̐퓬�@���̋������āA�ČR�����@�͒����őD�c�ɓˌ����A��������̂Ƃ��Ȃ��v�̂Ŕ��e�𓊉������B
�@��瓊�����ꂽ���e�͐p�x�Ő��ʂƐڐG���Ē��˕Ԃ�A��Ⴍ���Ō����ɖ��������i�X�L�b�v�E�{���r���O�j�B
�@�����𑖂鋛�������Ԕ��e�̕��������ł���A���̕����̕����}�~���������ڕW�߂��ڋ߂ł��������������A�Z���ɂ�钾�v���e�Ղł���B
�@�_���s�[���C���̐��������A���o�E����n�q������͐s������u�ł������B
8.3 �R�{�A���͑������̐펀
�@�l���O���A��Ɋ�@�����������R�{�\�Z�A���͑��i�ߒ����́u���v���������A���O�Y��O�͑��i�ߒ����̎w��������ڍq�������o�E���ɐi�o�����A��n�q����Ƌ������������Ȃ킹���B
�@�C�R���L�̏���l���̕��Q�������ŁA�R�{�A���͑��i�ߒ������g�����o�E���ɐi�o�����B
�@�����쓌���ʊ͑��i�ߒ����Ə����O�͑��i�ߒ����͊C�R���w�Z�̓����ł��邪�A�n�����b�N�E�i���o�[�i���Ɛ��сj�͑����̕�����ʂł������B
�@���o�E���ɐi�o�������q����͐�C�̑��������̎w�����ɓ��邱�ƂɂȂ�A�w���n����A�ւ荂�����q�������n�q����̉����ɗ�������A���̎m�C�ɂ������Ƃ����̂ŁA�R�{���������o�E���ɐi�o���đ��w�������邱�ƂɂȂ����B
�u���v�����͐��ʂ��オ�炸�A���q����͈����g���邱�ƂɂȂ������A���̑O�ɎR�{�����͍őO����n�̃u�[�Q���r������K�₵�āA�C�R�̈˗��䂦�ɃK���ŋ�J������ꂽ���R�̑�ꎵ�R�i�ߕ����˂��炤���Ƃ����ӂ����B
�@�����A���͑��Q�d���ł������F�_�Z�i�܂Ƃ߁j�����̓��L�w�푔�^�x�ɂ��A�l���O���Ƀ��o�E���ɓ��������R�{�����́u��O�l�Z���z�[�����B�쓌���ʊ͑����ɂɓ���ꎞ�����������Ɍf�g���v�u���O�Z�R��̔��͑������h�ɂɓ��蔑���v�Ƃ���A���o�E���؍ݒ��̐퓬�i�ߏ���쓌���ʊ͑��i�ߕ��ɂ����A�攪�͑��i�ߒ����h�ɂ��h�ɂƂ����B
�@�l���ꔪ���ߑO�Z���ܕ��ɁA�R�{������A���͑��i�ߕ���]�͈ꎮ����U���@��@�ɕ��悵�A���o�E������s��𗣗����A�Z�@�̃[����̌�q�̂��ƂɃu�[�Q���r�����̃_�C����n�Ɍ��������B���{�C�R�̈Í�����ǂ��Ă����A�����J�R�͎R�{�����̎E�Q��ړI�ɓ��ʂɕҐ�������Z�@��P38�퓬�@�����u�C�����őҕ��������A���U��@�����Ă����B
�@����̖��тɒė�������ԋ@�̓���҂͎R�{�����ȉ��S���펀�A�C�߂��C���ɒė�������ԋ@�͉F�_�Q�d���ȉ��O�l�������A�Z�@�̌�q�퓬�@�͂��ׂĖ����ł������B
8.4 �ߗ����R�ƂȂ������o�E���̓��{�R
�@���Ƃ��ƈꎮ���U�͔�e����Ƃ���������̂ŁA���̗t���`�̓��̂��������āu�t�����C�^�[�v�ƌĂꂽ�قǖh��͂��ォ�����B
�@����A�o���o�����Ƃ����߂��炵���`��̂o38���C�g�j���O�퓬�@�̎c�[���K���̖�O�푈�����قŌ������A�o���퓬�@�̍������\�ɉ����āA�o���̌��ɓ��̂��L�т�o�����Ƃ������قȌ`�����v���ꂽ�̂́A���c�Ȃ̂��钆�����̂�C���Ƃ��A�j��͂��傫�����C�g��20�~���@�֖C��������邽�߂ł������B
�@���Ȃ�20�~���@�֖C�ł�����𗼗��ɑ��������[����̏ꍇ�A�����ɐ���ĖC�g���Z������A���̌��ʂƂ��ď������������˒����Z���A�e�����������̋Ȑ����������i�u����������v�j�̂ňЗ͂��������A����������邢�B
�@�u�t�����C�^�[�v�́A���̒��C�g��20�~���@�֖C��Ƃ���u�E�����v�̐퓬�@���C�g�j���O�̍D�a�ƂȂ����B
�@�l�O�N������l���A��{�c�͐���h�����A�瓇�E���}���E�}���A�i�E�g���b�N�E�����j���[�M�j�A�E���k�e�B���[������˂���ɐݒ肵���B
�@���O�̃��o�E�����i�ߕ��E��⋊�n�Ƃ���\�������E�����j���[�M�j�A�̐���͎��ԉ҂��̎̐ƈʒu�t����ꂽ�B
�@�l�O�N��ꌎ�����A�j�~�b�c��̎w������Ē��������m�R�̓M���o�[�g�����̃}�L���E�^���������ɏ㗤���������Ȃ��A�{���́u�I�����W�v��v�ɂ��ƂÂ����������m���ʂ̐i�U�����J�n�����B
�@�l�O�N���ܓ��A�ČR�̓j���[�u���e�����̃}�[�J�X���i�_���s�[���C���̓쓌�����j�ɏ㗤�A�l�l�N�ꌎ����ɕČR�̓_���s�[���C���̒��������m�ւ̏o���j���[�M�j�A���̃O���r���ɏ㗤���A�_���s�[���C�����˔j����Ď��ꂪ���������m�Ɉڂ����B
�@����Ƀ}�[�V���������̃N�F�[�����E���I�b�g���U�������ČR�́A���W�����ʂ���̂��č������@�������̕d�n�Ƃ����B
�@�����A�A�h�~�����e�B�����̃��X�l�O���X���ɕČR���㗤���ă��o�E���n��͐������Ɏ��c����A�����I�ɂ͕ČR���H�킹�Ȃ��čςދ���ȕߗ����e���Ɖ������B
�@�l�l�N�܂ł̂��̕��ʂɂ�������{�R�̑��Q�́A��v�Җ��O���A�͒��Z�ǁA�D�����ܐǁA�q��@�Z�Z�Z�@�ł������B
�@�����ȉ���Ǎ쐬�̎����i���Z�l�N�j�ɂ��A�l�ܔN������ܓ��̏I�퓖���A���o�E���𒆐S�Ƃ���r�X�}�[�N�����̐����Ґ��͗��C�R�����킹�Ė�㖜�Z�l�Z�Z���i�����I���̎��v�Җ�l�܁Z�Z���j�E�I��O�̎��v�Ґ��͖�Z�Z�Z�Z���A���v�Ҍv��O���܁Z�Z���ł������B
�@���o�E���̎w�����ɂ������\�����������ł̓������̐�����������ΐ����Ґ���܈�Z�Z���i�����I���̎��v�Җ�ꔪ�Z�Z���j�E�I��O�̎��v�Ґ����Z�l�Z�Z���A���v�Ҍv������Z�Z���ł������B
�@���Ȃ����j���[�M�j�A�ł̐����́A�����Ґ���O���O���Z�Z���i�����I���̎��v�Җ��܁Z�Z���j�E�I��O�̎��v�Ґ����܈�Z�Z���A���v�Ҍv�����Z�Z�Z���ƎZ�肳��Ă���B
�@�ȏ�̐���������ƁA���o�E���̗��C�R���ʎi�ߕ��̊NJ����ɂ��������ɑ��荞�܂ꂽ�����E�R���i�I��O�ɑ��̐��ɓ]�p���ꂽ�҂������j���́A��O�㖜�Z�Z���A�푈���̎��v�҂Ɛ��̕����܂ł̎��v�҂Ƃ̍��v�͖��l���Z�O�Z�Z���A�����ċA�����邱�Ƃ��ł����͖̂��l���Z�܁Z�Z���i�a�b����ƂƂ��ĕ��������҂��܂ށj�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@���̌���Ɏ��̂�����A��͂Ƃ��Ă܂����������l�ɂȂ��ĈȌ�A�a�ƋQ���䂦�ɂ����ɑ����̐���������ꂽ���A���̐������������Y�قɕ�����Ă���B
9�@���S�Ȕp�ЂƉ��������o�E��
top
9.1 �w�����猩�����o�E���̔p��
�@�D�����o�E���`�ɋ߂Â��ɂ�A��ʂ̌y���p���ɕ������Ă���̂��F�߂��A�ΎR���̕��o���̗ʂ̑����ɋ������ꂽ�B
�@�E��̃}�`���s�`���R�A����̃o���J���R�̂��������ē��p�̃��o�E���`�ɓ���̂ł��邪�A�}�`���s�`���R�͎R�����傫�������Ƃ����āA���̔�������C����]�ނ��Ƃ��ł���B
�@�o���J���R�͉Ό�����C�ʂ܂ʼnΎR�D�ɂ�����ꂽ���R�ƂȂ��Ă���B
�@�����炩�W���������J�C�u�R�̕��Ό��͊C�ォ��悭�����Ȃ��B
�@�D�͊C�ʂ��������s�����ĕ�������y�����������Ȃ��璅�݂����B
�@�u���̂����ׂɁA�|�S�D�̑D�̂߂ēy�荞��ŕu�������Ɏg���Ă���̂��ڂɂ����B
�@�����A���v�������{�D���q���̑D�̂𗘗p�����Ƃ̂��ƁB
�@�A����Ɂw���{���D���펞����j�x�Œ��ׂĂ݂�ƁA���l��N�l���ꔪ���̍��ɁA�u���q�ہA���ܓ�l���g���A���ۋD�D�A�A���o�E�����v�ƋL�ڂ���Ă����B
�@�n���̊��}�s���Ƃ��Ė������x�̃V���V�����ݕǂł���Ђ낰��ꂽ�B
�@���Ƃŕ������Ƃ���ł́A���݃��o�E���ɂ͏Z���͏Z��ł����A�����̐l�X�����o�E���̏Z���̔��n�ł�����Z�}�C�����ꂽ�R�|�|����A���}�s���̂��߂ɂ킴�킴����Ă����Ƃ����B
�@�ŏ��́A���{�̏㗤�M�������܂��Ɍܐǂ̂�����Ă���p�[�W�E�g���l���A��n�q����̗��U������n�ł���������s��ՁA�R�|�|��K�˂�c�A�[�ɎQ����\������ł��������A�D���Ń��o�E�������w���R�v�^�[�Ŕ�ԃI�v�V���i���E�c�A�[������ƕ����A������̕���\�����B |

94�N9���̕��ŎR����������}�`���s�`���R

�Œ��v�����u���q�ہv�̑D�̂𗘗p�����u��
|
�@���̊S�́A��ł������o�E���s�X�̏�����ŁA���̔�Q���王�@���邱�ƂɌ������B
�@�w���͍`�̂����e�̍L�ꂩ�甭������B�R�|�|�Ɍ�������s�̃o�X�������������ƁA�w������g��O�l�͌ܐl���w���ɐ\���ݏ��ɏ�荞�B
�@�������͎O�g�ڂŁA��l����Z���ɗ����B�����ł����w���̗������͂��т����������o�������グ�邪�A�~��ς������ΎR�D�̏�𗣒�������̂ŁA���̍��o�͂��̂������B
�@�w���̓��o�E���s�X�̏����r�߂�悤�ɔ�ԁB
�@�z����₵���Ђǂ��ЊQ�ŁA�Ђ̐Ղ͂Ȃ����A�������P����̍q��ʐ^���v�킹��B
�@�s�X�����S�ɏ��ł��Ă��܂����̂ł���B
�@�߂���ł����A��O�N���������̖k�C���쐼���n�k�i�l7�E8�j�ɂ�鉜�K���̐k�ЂƒÔg�̔�Q�ɁA��B�E�����̉_��E�����x�̕��ɂ����N�Z�������O�N�Z���ɂ����Ă̐��x�̑�ӗ��Ƒ�y�Η��̔�Q���A�����Ƃ���x�ɉ������ꍇ��z������悢�B
�@���O���N�̑啬�Ό�ɍČ����ꂽ�s�X���A����͍Č��s�\�̂悤�Ɏv��ꂽ�B
�@�p�v�A�j���[�M�j�A�̎�s�|�[�g�E�����X�r�[���烉�o�E���܂ŁA���傤�Ǔ������牜�K���܂ł��炢�̋����ł���B
�@��̓s�s�����Ԍ�ʐ��͊C�H���q��H�����Ȃ��B
�@�V���v�\���p�����t�߂̃R�|�|�̒����̂����āA�j���[�u���e�����ɂ͂ق��ɓs�s���Ȃ��B
�@���o�E����БO�̒��l�������܁Z�Z�ł������R�|�|�̒����A���o�E���܁Z�Z�Z�l�̔�Ў҂̂�����̎����n�ł���B
���o�E���͑S���Ǘ�������Вn�ƂȂ����B
�@�w���͎s�X�n�̏����ւăJ�C�u�R�̉Ό������сA�}�`���s�`���R�̏����������Ɛ��A���̂��̂�����������̉��܂Ō����Ă����B
�@����ɓ���s��̊����H���������߂ăJ���f���Ό��ǂ̓����ɏo�āA���̓��C�݉����ɔ�сA��ɐ��čĂјp�����ɏo�Ă������ƃo���J���R�̉Ό�������A�����A����s�ꊊ���H�̏����ւč`�̕u���̉�����������A��������ɒ��������B
�@�ΎR�D�ɖ����ꂽ�����H�̓��[�ɑo���̗��q�@����@�g���Ȃ��Ȃ��������H�ɗ������������܂ܕ��u����A�J�ɐ���ċ�F�ɋP���@�̂������ΎR�D�̍L����̂Ȃ��ɂ�������Ǝp�������яオ�点�Ă���̂���ۓI�ł������B
�@���̊ԁA�ꎵ���Ԃ̔�s�ł��������A�ړI�n�܂ł̉������Ԃ�v���Ȃ������̂Ō��\�������@���Ԃ������A���������B
9.2 ���n�E���̎s�X�n�Ղ܂ŕ���
�@�`�̉ΎR�D�̏������A�l�肪�Ȃ��������A�ݕǂɗ��g�����ꂽ�܂ܕ��u����Ă���^�V�������ݗp�d�@�ɓY�t���ꂽ�����Ȃ��i���@�卑�I�[�X�g�����A����̉����ł������j�������̂��A�D�ɋA��A�V�����[�𗁂тāA�r�[���ł̂ǂ̊��������邨�����B
�@���̓��o�E���ւ̋~�������Ƃ��ă{�����e�B�A���A�k�Вn�_�˂ő�ʂɎg�p���A�������������ĈȌ�s�v�ƂȂ������ݐ��p�̃|���E�^���N���ʂɂ��̑D�ɐςݍ���Ń��o�E���Ɏ��Q�����B
�@�Ȃ�Ƃ����Ă��A��Вn������̃R�|�|���A���ނɂ��ƌ����قǂ̋����s���ł���B
�@��̃o�[�ł̉�b�ŁA��Ղ�R�|�|��K�˂��l�����̘b�������A�t�ɁA��Ճc�A�[�ɎQ�������ɉ������Ă�����ł����Ǝ��₳��A�������Ă��܂����B
�@�u���o�E���܂ŗ��āA���Ƀ��o�E���q����������������v
�@���Z����ܓ��́A���������ɉ��D���Đ�Ճc�A�[�̈�s�ɍ������A�~�j�o�X�ɕ��悵�A���o�E���s�������w�����B
�@��s�̑O����R�|�|���痈���x�@�̃p�g�J�[����q���Ă����B
�@�܂����H���ΎR�D�ɖ����ꂽ�ꏊ�������A�댯���Ƃ��Ȃ����߂̐擱�Ȃ����ł���B
�@�����猩����Вn�������͒n�ォ�猩�邱�ƂɂȂ����B�͐ς����ΎR�D�̗ʂɂ��ǂ낭�B
�@���ɂ͈ꃁ�[�g���߂��͐ς�����B
�@���ꂾ�������ɐς����ΎR�D���X�R�[���̉J�����z�����߂A�����Ă��̌��z���͂Ԃ���Ă��܂��B
�@�������ē|�������������ɂ���B���̕����ɐ����|���ꂽ�悤�ɌX���A���Ȃǂ������Ă��錚���͔����ɂ���Q�Ȃ̂ł��낤���B
�@���X�ɂȂ��Ċ��I�Ɩ؍ނ̔j�Ђ̎R�Ɖ����Ă���c�[�͒n�k�ɂ����̂Ȃ̂��A�Ôg�ɂ����̂Ȃ̂��B
�@���H��L��E��Ȃǂ͉ΎR�D�ɖ����ꂽ�����A���̉ΎR�D���~�J�ŃZ�����g�̂悤�Ɍł߂��A���̓P����Ƃ͗e�ՂȂ��̂łȂ��B
�@�p�ЂƂȂ�����̕Ћ��ɐ����̂������A�����M�ѓ��L�̂����₩�ȍʂ�̉Ԃ��炩���Ă���̂�����Ɋ�������B
�@�ΎR�D�̔����q�����ɂ܂��オ��A�h�o�p�̃T���O���X�Ɩh�o�}�X�N���s���ł���B
�@�ΎR�D�͏Ă����z��̓���������B
�@�s�X�n�̔w��A�J�C�u�R�i����R�j�Ƃ��̖k�̃\�[�X�h�[�^�[�R�i�o�R�j�Ƃ̂������̓����z���ĊO�C�݂ɒʂ��铹������B
�@���̓��ɂ̂ڂ铹�̓r���A�s�X�n�������낷�Ζʂɓ��{�R��v�҂̈ԗ�肪�����Ă���B
�@������ΎR�D�ɖ�����Ă����̂�������������̂�m���Ēn���Ō@��o���A�ꉞ�̐��������Ă��ꂽ�̂��������B
�@���̈ԗ��͓쑾���m�̐��S�̂̐�v�҂̂��߂Ɍ��Ă��A���̏ꏊ�͊C�R�̑攪���a�@�̐Ղ��Ƃ������A���a�@�ł̎��v�҂̂��߂̈ԗ��͂܂������ΎR�D�ɖ��܂����܂܂ł���B
�@�C�Ɍ������ĂЂ炢���߂̉����̓����ɓ쑾���m�̓��X����������ɂ��ꂽ�n�}�������ĉ����̒����Ƀ��o�E��������A���o�E���̏ꏊ�Ɍ����������A���̉��ɑ嗝�̑䂪�������A�w��ɂ͑嗝�̂����Ă��������牺�����Ă���B
�@�q�˂Ă݂�ƁA���ΑO�ɂ͂��̌��ɐ��d�������āA���̑���Ƃ炵�o���Ă����̂������ł���B
9.3 ���o�E���C�R�q����̎c�[
�@����s����͂ރ��V���ɕ��u���ꂽ���{�R�̍q��@�̎c�[�����ɍs�����B
�@����s��͐�O���珬�^�@�i�퓬�@�j�p�̔�s��ł���A���{�R����̒��ɗ���U���@���������ł���悤�Ɋg�������B
�@���̓��o�E����`�Ƃ��Ďg�p����Ă������A����̕��ɂ���Ďg�p�s�\�ƂȂ����B
�@�����ɓ���������ɗ���U���@�p�̐���s�ꂪ�����������͍r�p���Ă���B
�@�R�|�|�̓��C�݂ɂ͓��s�ꂪ���݂��ꂽ���A���݂��̔�s�ꂪ���o�E����`�̑�֎{�݂Ƃ��Ďg���Ă���B
�@�����H�����铹�H�e�ŎԂ��~�߁A���V�т̒������Ȃ�̋��������ĖړI�̎c�[�ɓ��B�����B
�@���������@�̂̑O�����Ɨ����Ĕ��������ꂽ�G���W�����A�嗃�̌��Ƃ��̑O�ɗ����Ė����ꂽ�G���W�����ƁA���̌��Ɋ��S�ɗ��Ԃ��ɂȂ��Ĕ��������ꂽ�@�̂̌㔼���A�����̓�@�Ƌt�����������ĉΎR�D�̒�����킸���Ɏ嗃�̕t�����t�߂��@��o���Ă������P���@�̃G���W�����A���v�O�@�̋@�̂ƌ܊�̃G���W�����������B
�@���ӂ̂�����Ƃ���ɉ��̍��̓y����̐Ղ�����A���̈�ɂ͑o���@�̎c�[�������܂����܂܂ł���B
�@����������Ԃ��猩��A�����̎c�[�͕ČR�̋�P������ă��V���̒��ɑa�J�铽��������ďP���A�j�ꂽ���̂Ɛ��肳���B
�@�o���@�̂����@�̑O�������̂����Ă�����̂��ꎮ����U���@�ł��邱�Ƃ��킩�������A�����菬�^�̑o���@���������B |

��P�Ŕj�ꂽ���{�C�R�̈ꎮ����U���@
|
�@�Ō�܂Ń��o�E���ɂ������U�ȊO�̑o���@�Ƃ����A�C�R�̓����@�@���邢�͂��̋@�̂�]�p������Ԑ퓬�@�E�������A���R�q����攪���ʌR��������������Ƃ��ɕ��ʌR�ɂ̂�������Z�Z���i�ߕ���@�@�U�^���ł���B
�@�����A��Z�Z���i�ߕ���@�@�͐���s�����n�Ƃ��Ă����\�����悢�B
�@�ƂȂ�ƁA����s��߂��̃��V�����ɂ������̂͌����̎c�[�ł͂Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�����ɓ��ڂ����G���W���́A�����m�푈�\�ɂ����Ƃ������P���P���퓬�@�A�C�R�̃[����◤�R�̔��Ƃ��Ȃ�������s�@���́u�h21�^�v�i�n���܁A��⎮��^��l�C���j�G���W�����ł������B
�@��Z�Z���i��U�^�ɓ��ڂ����G���W���͎O�H�d�H�Ɛ��́u����21�^�v�i�n��Z��A��⎮��^��l�C���j�G���W�����ł������B
�@�����̃����ɂ́u�A�����Ē��ׂ�A���̐����͔������邾�낤�v�ƓۋC�Ȃ��Ƃ������Ă��邪�A�A����Ɍ���ŎB�e�����G���W���̎ʐ^�����Ȃ��當���ׂĂ��������Ȃ������B
�@�����ĉΎR�D�ɔ��Ζ��܂������V�̎�����A�܁Z�Z���`�قǂ̍����̃��V�̉肪������Ƃ���ŐL�тĂ���B
�@���V�т̍Đ��͒����ɐi�݂���悤�ł���B
9.4 �R�{�\�Z�Ō�̖�̏h
�@�s�X�n�ՂɈ����Ԃ��ē쐼���ʊ͑��i�ߕ��ՂɈē����ꂽ�B
�@�ΎR�D�ɔ��Ζ����ꂽ�S�R���N���[�g���̊��Ȓn�������̂����Ă���B
�@������������Ƃ����̂ŁA�ΎR�D�̒���������ȂLjꕔ���@��o���Ă��ꂽ�̂������ł���B
�@�R�{�A���͑��i�ߒ����̓��o�E���Ō�̖�����̒n�����ʼn߂����A�������ɓ���s����ї����Č��Ă���펀�����Ɛ������ꂽ�B����͎����Ȃ̂��B
�@�攪���ʌR�i�ߊ������ϒ����i�܌��ɑ叫�j�́w���L�E��R�l�Z�\�N�̈����x�̋L�q�ł́A�u�l���̏\�����A���o�E�����ʊ͑��i�ߕ��ɉ������Ă���R�{��������[�H�ɏ�����A�o���̎Q�d���F�_�C�R�����ƁA�����i�o���������j���R�����Ƃ����Ȃ����v�ƋL����A�R�{�����͕��ʊ͑��i�ߕ��ɉ����������ƂɂȂ��Ă���B
�@�����ƎR�{�́A���������p��������ɁA�R�{�����ĕ�������Ɋo�����u���b�W�̘r�����ŁA�R�{���C�R�����A���������R�����̂����i����l�N�j�ɁA���̃u���b�W�D���̕č��A��̗��R���Z�����ƁA���j���ƂɊe�ƒ뎝���܂��Ńu���b�W�ɋ��������ł��邩��A���̒�Ə��R�̊W�ł͂Ȃ������B
�@���̍Ō�̔ӎ`�̍ۂ��A�ɍ������K���P�ޕ��������������ߊC�R�̗��U�ɏ���ău�[�Q���r�����Ɍ��������Ƃ��A�Đ퓬�@�����̑ҕ����U���������A������ՓI�ɂ���ɕ����Ă������_�̒��ɓ������݉B��ď��������b���A�R�{�ɂ����Ƃ����B
�@�����͎R�{��@���Ă̕���A�u���قǂ܂��A���̏�@���G�̕ґ��ɏo�������Ƃ��Ɠ��������A�������̏��ŁA��͂�O�\�@�̓G�Əo���킵�A�喧�т̏�Ɍ��Ă���A���ɏ}�E���ꂽ�v�ƁA���̕s�v�c�������₵��ł������A���ɂȂ��ĈÍ�����ǂ���Ă����Ƌ������A���R����l�̉^���������Ƃ�m�����B
�@�������������ʌR�i�ߊ��́A�R�{�����ʊ͑��i�ߕ��̒��ɂɉ��������������m�F�����킯�ł͂���܂��B
�@���̍Ō�̔ӎ`�ɂ����������F�_�Q�d���́w�푔�^�x�́A���o�E���؍ݒ��̎R�{��̏h�ɂ��u�R��̔��͑������h�Ɂv�ł��邱�Ƃ��L���A��͂�l���ꎵ���́u���ɂɉ��ĔӐH���҂��v�Əq�ׂĂ���B
�@�������A���ꔪ�����́A
�@�u���܌܁Z�h�Ɍ��ւ��o���B�����̑�O��R���p�n�߂Č���B
�@�����Ɏ������������ꂴ��ׂ����f���ق�B��Ɏ���Ă͏��X�R���������͂悫�ς�Ȃ�B
�@���Z����s��ɒB���v
�@�Ƃ���A�i�ߕ����ɂł̔ӎ`�̌�R��̏h�ɂɋA��A�����E�Q�d�����Ԃœ��s���ē���s��ɍs�������ƂɂȂ��Ă���B
�@�R�̒����̊C�R�a�@�̐�ɁA���@�R�Ƃ������{�R�̕t�����n�����n�}�ɋL�ڂ���Ă���A���̕t�߂Ɋ͑������h�ɂ��������Ɛ��������B
�@����s��܂ŎԂň�Z��������Ώ\���ɓ����ł���B
�@�������̍s�������ɂ����F�_�Q�d���̎�L�̕����M�����������B
�@�w�푔�^�x�ʼnF�_�͎l���l���A
�@�u�R���~��đ攪���ʌR�i�ߕ���K�₵�A�����i�ߊ������Q�d���ɖʐڂ��B
�@���ɂ͋���\���R�i�ߕ��̂��̂Ɍ��đ���������̂Ȃ���A���藈�����̂͗��R��嫂����e���Ȃ�v
�@�ƁA���i�̕��ʊ͑��i�ߕ����ɂ̍��������ւ��Ă���B
�@����ȗ���̍������ʌR�i�ߊ����猩��A�C�R�����ȕ��ʊ͑��i�ߕ����ɂƕʂɁA�R�̏�ɒ����h�ɂ܂ł����Ă����Ƃ́A�l������Ȃ������̂�������Ȃ��B
�@�R���N���[�g���̒n�����������̂����i�ߕ��Ղ̌��w���Ō�ɑD�ɋA��A�D���炯�̈ߕ���E���A�s�V���c�𐅐��ăV�����[�𗁂сA���D��͈�H�̐������߂��A�����������̂ǂɃr�[���𗬂����B
�@�ԓ������ɋ߂���l�x�̔M�т̒n�ŁA���ŗ̎����قƂ�Ǐ����Ă��܂����ΎR�D�����̓����́A��͂肩�Ȃ肫�т������̂ł������B
10�@���E�ōł��V�����Ɨ����A�p���I���a��
top
10.1 �ԓ��ɂƂ��������̍s��
�@�Z���ꎵ����㎞�l�ꕪ�A�D�͍Ăіk�����ւƐԓ����z�����B
�@���ʂ̍s���̗\��͂Ȃ��������A���̏u�ԁA�D���D�J��炵���B
�@���̂Ƃ����͉E�����̃f�b�L�ɂ������A�����E�O���ɓ����������B
�@�ӂ肩�����č������A�܂肢�܉z��������̐ԓ��̕���������ƁA���Ȃ�߂��ɑD�Ƃقڕ��s�ɓ��̍s������邱�Ƃ��ł����B
�@�D���ɓ����āA
�@�u�ԓ��ɖ��肪���Ă��邼�v
�@�ƌ�������A�Ⴂ�A���܂ł��A
�@�u�{���H�v
�@�ƐM���Ȃ��B�ނ�������D�̐ԓ��z���ɂ܂�邢������̘b�������̂ŁA�M���Ȃ��̂������͂Ȃ����A
�@�u�{������A�b�ɏo�Ă����v
�@�Ƃ����ƁA��Q�Ăł݂�Ȍ��ɍs�����B�A���ė��āA
�@�u�{�����I�v
�@���傤�Ǔs���̗ǂ��Ƃ���Őԓ����z�������̂��B
�@�ڂ����C�}�ɂ͋L�ڂ���Ă���̂��낤���A���̗�͂��Ԃ�X��ʂ̈Ïʂ̍q�H�W�����������Ǝv����B
�@�ꔪ�����A�b�ɏo�Ă݂�ƁA�E���ɗ̓��X�̂�Ȃ肪������B
�@�D�͒m��Ȃ��������ɃA���K�E�����ƃy�������[���Ƃ̂������̊C�����Đj�H�����X�ɖk�Ɍ����������̂��B
�@�ʂ��������Â���X��ʂ̎��͂�傫���I�A�ʂɓ��钼�O�Ƀp�C���b�g����D�����B�p���I�`�ɓ��`�����^�D�����O�[���ɓ��邽�߂ɒʉ߂ł��鐅���͐����������Ȃ��B
�@���O�[���ɓ����Ă���̍q�H�̍q�s�͂��Ȃ�ނ������悤�ŁA�D�͑��x�𗎂Ƃ��Ă������Ɠ쉺���ꎞ�Ԃقǂ����ăp���I�`�ɓ��`�����B
�@����l�N��Z������ɓƗ����ʂ������̋��a���̖��͐����ɂ̓p���I�Ȃ̂��x���E�Ȃ̂��B
�@���{�̈ϔC�����̎���̌Ăі��̓p���I�ł���B
�@���n��ł̓x���E�ł���A�p���I�͂��̃X�y�C����Ȃ܂肾�Ƃ����A���}�Ёw��S�Ȏ��T�x�́u�p���I�v�ɂ��A�����ɃA�����J�̐M�������̂ƂȂ�A����N�ꌎ�ɓƗ���O��Ƃ��鎩�����{���������A�������̂��x���E���a���iRepublic of Belau)�ƒ�߂��A�Ƃ����B
�@���ݎ��̃p�X�|�[�g�ɂ����ꂽ�o�����R�����Republic of Palau�ƂȂ��Ă���B
�@�O�c�N�j�w��j�����m�@�픚�����m�x�Ɍf�ڂ���Ă����㔪��N�ꌎ���`����̗������{�n�ݎ��i�哝�̏A�C���j�@�ւ̒��҂��Ă̏��ҏ�ɂ́uREPUBLIC OF PALAU�v�ƋL�ڂ���Ă���B
�@�������A���͂��̌���������@��Ȃ��������A�V�n�v�}�w�x���E�̐��Ǝ��x�́A���Z�N�ɐ����������̍��̌��@�̕\���ɂ́uBELAU�v�Ɩ��L����Ă���Ƃ����B
�@�q�[�X�{�[�g�́w�쑾���m�̑D���K�C�h�u�b�N�x�ɂ́A�o�T���L���Ă��Ȃ����A�u���n��̐��������̓x���E�iBelau)�ł���A�w�x���E���a���x���w�x���E�x�̂Ȃ��Ɂw���a���x�̈ӂ��܂܂�邽�߁A�����ɂ͌��v�Ǝw�E���A��l�N�ɓƗ����͂������Ȍ�̌������L�ڂ̍������p���I���a���iRepublic of Palau�j�ɓ��ꂵ���Əq�ׂĂ���B
�@�����ł́A���̍��̌��@���x���E���@�ƌĂԂق��̓p���I�̖��̂œ��ꂵ�Ă����B
10.2 �u���R�A������v�Ń~�N���l�V�A��
�@�����ē��{�̈ϔC�����̂ł���������m�Q���́A���݁A
�@�@�@���Z�N�����́u����v�ɂ��ƂÂ��A�����J�̎匠���ɂ���u�����́v�i�Ƃ������ی�́j���߂��Ȃ��k�}���A�i�A�M�A�@
�@�A�@�����N����́u���R�A������v�ɂ��ƂÂ��A�����J�Ƃ́u���R�A���v�Ƃ��Ď���N�Ɏ������{�����������Z�N�ɓƗ������}�[�V�����������a���A
�@�B�@�p���I�������J�����������ō\�������~�N���l�V�A�A�M�A
�@�C�@����Ǝ����K�₵���������킸���������܂��ɓƗ���B����������̃p���I���a���A
�@�ƁA�l�̍��E�n��ɕ�������Ă���B
�@���̕����̓A�����J�̌R���I���v�ɂ��ƂÂ��Ă����Ȃ�ꂽ���̂ł������B
�@�}���A�i�����̒��̕ė̃O�A�����ɃA���_�[�\���헪��R��n�ƊC�R��n�A�v�������A�����J�ɂƂ��āA�O�A���̍T����n�Ƃ��āA���čL���E����ւ̌��������@�i�������Γ��푈�̐헪��R��n�e�j�A���A�^�i�p�O�`�����T�C�p���̌R���I���l�͑傫�������B
�@���̂��߁A�A�����J�͐M�������������I����Ă��}���A�i����������A�A�����J���u�O���Ɩh�q�Ɋւ��邷�ׂĂ̌����ƐӔC��L�v���A�u���h�ӔC�𐋍s���邽�߁A�e�j�A�����̖�O���̓�������G�[�J�[�j�A�t�@�������E�f�E���f�j�����S���i��Z�Z�G�[�J�[�j�A�T�C�p���̃^�i�p�O�`�i�ꎵ���G�[�J�[�j����������Z�Z�N�ԁA��G�[�J�[�����Z�Z�Z�h���i�N�Ԉ�Z�h���j�Ŏg�p����v�Ȃǂ́u����v��k�}���A�i�A�M�Ɍ������B
�@�����A�}�[�V���������͐��A�����J�̊j������Ƃ��ꂽ�B
�@���l�Z�N�Ƀ}�[�V�����̃r�L�j�ʂ��j������ɑI��A�l���N�ɂ͂���ɃG�j�E�F�g�N�ʂ��j������ɒlj�����A�܈�N�ɂ̓N�F�[���������j�����̎x����n�Ƃ���ďZ�������ނ��𖽂���ꂽ�B
�@�������Ĉ��l�N�O������A�r�L�j�Ŏj��ő�̐��������������Ȃ��A���{�̃}�N�����D��ܕ����ۂ��픚���A�����O���b�v�ʂ̕ČR�l�E�Z���A�E�g���b�N�ʂ̏Z�����픚���ċ~�o����A�����Ɏ��e���ꂽ�B
�@�r�L�j�ƃG�j�E�F�g�N�ł̊j�����͌ܔ��N�ɏI��������A�܋�N����N�F�[�����ʂ��~�T�C��������Ƃ��A�ʂ̈ꕔ�̓��X����Z���𑼓������ڏZ�������B
�@���̃~�T�C��������͎���Ɋg�傳��Ă������B
�@�����������Ƃ���A�u�A�����J�͕K�v�ȌR���{�݂Ƃ��̉^�c���������A�~�N���l�V�A�Ɋւ�����S�ۏႨ��іh�q�̑S�����ƐӔC��ۗL����v�u���R�A���v��Ă��A�����J��������o����A�~�N���l�V�A����~�T�C��������m�ۂ̂��߂Ƀ}�[�V���������A�ʂ̗��R����p���I�����������āA��������O�������A���ꂼ��Ɂu���R�A�����蒲��v�����܂�A�p���I�������J�������ƃ}�[�V�����́A���ꂼ�ꎩ�R�A������ɒ��A�p���I���ꑫ��ɓƗ����ʂ����B
�@�p���I�����ɂ͂��낢��Ȏv�f�����߂��Ă����B��㎵�Z�N��̔��A���ċ����̃p���I�J���E���p�̍\�z���ł��o���ꂽ�B
�@�\�z�̓A�����J���̃p���I����`�J���\�z�ł���A���{�́A�Ζ����~��n�i�b�s�r�j�\�z�Ɗj�ď����p�����̔p����Ȃǂ̌v��ł��̍\�z�ɏ��A�A�����J�͌R����n���̌v��ł��̍\�z�ɏ��A�����v���W�F�N�g���ւƓ����͂��߂��B
�@�������͂ӂ��ʂƌ����Ȃ�킵�Ă��邪�A���O�[�����ɓ�������p���I�͌����ɂ͚Əʂł���B�p���I�Əʂ̖k���Ƀp���I�Əʂ��甼�ΓƗ����Ă��邩�̂悤�ɃR�[�������E���[�t�ƃR�b�\���E���[�t�Ɉ͂܂ꂽ�R�b�\�������ƌĂ�铇�̂Ȃ����O�[���i�ʁj������A���̃��O�[��������`�Ƃ��ĊJ�����悤�Ƃ����̂ł������B
�@�����E��k�Ƃ��ɓ�Z�L���߂��ʂ̃��O�[���ߗ��ĂĔ��~�\�͌ܔ��Z���L�����b�g���̌��������^���N�A�ςݑւ��ݔ��A�������A���q�͔��d���A�����ɕK�v�ȍ`�p�ݔ������݂��悤�Ƃ����̂ł��邩��A���܍l����Ƃ܂�������펯�Ȋ��j��v��ł���B
�@����ɖ��́A���̍`�p���݂��A�A�����J�ɂƂ��ă~�T�C���̎˒����L�т��헪�j�����E�g���C�f���g�^���q�͐����͂̊�n�́A�^��p�E�O�A��������p���I�ւ̓쉺�A���{�ɂƂ��ă}���b�J�C���E�����{�N�C���o�R�̂�����V�[���[���h�q�̊�n�ݒ�A�Ƃ����Ӗ��������Ƃł������B
�@�������A���{�ɂƂ��ẴV�[���[���h�q��n�̐ݒ�́A�A�����J�����m�R���A�t���J���݂��璆���ւƓW�J���邽�߂́A�C���h�m�̉p�̃`���S�X�����f�B�G�S�[�K���V�A�ʂɐݒ肵�����O�W����n�ւƌ��ԑ哮���̒��p��n�ƂȂ�B
10.3 ��j���@�̃x���E���@����
�@��킪�I���A�A�����J���t�B���s���̃X�[�r�b�N�p�C�R��n�ƃN���[�N��R��n����P�ނ������݂ł́A���̂悤�Ȍv��͌������������A�����I�ɂ����藧���̂łȂ��Ȃ����B
�@���{�̒ʎY�Ȃ��b�s�r���v��ɂ��̌o�ϐ��]���̂��߂̗\�Z���������Ƃ�����A�ꎞ�͑����m�̊j��n���Ƃ��đ傫�Ȗ��ɂȂ������A���ۓI�ْ��̊ɘa�ɔ����A�v��͒��~���ꂽ�B
�@����������̂��ƂŔ�j���@�Ƃ�����x���E���@�����������B
�@����N�����ɔ�j�����荞�x���E���@�̏Z�����[�������Ȃ��A��Z���ȏ�̎^���ŏ��F���ꂽ���A�A�����J�̈��͂ɂ��@�I�ɖ����Ƃ��ꂽ�B
�@��Z���Ƀx���E�C�����@�i�A�����J�āj���Z�����[�ɂ�����ꂽ���A���Z���̔��Ŕی��A����ɔ��Z�N�����ɔ�j���@�̃x���E���@���O�x�ڂ̏Z�����[�Ŏ������̎^�������Đ��������B
�@���ꂪ���݂̃x���E���@�ŁA�j����ȂǂɌW�鍑�ۋ���ɂ́A�������[�Ŏl���̎O�ȏ�̎^����K�v�Ƃ��邱�Ƃ��߂Ă���B
�@���̔�j���@�́A�A�����J�Ɋj���܂߂đS�ʓI�ɌR���I�������䂾�˂�u���R�A������v�Ɛ�ɖ�������B
�@�A�����J�́u���R�A������v�ɂ��ƂÂ��Ȃ��x���E���@�̂��Ƃł̓Ɨ���F�߂Ȃ������B
�@�p���I���a���̓Ɨ����x�ꂽ�����͂����ɂ������B
�@���̊ԁA���{�̊j�p�����̊C�m�����v�悪���Z�N�ɃO�A�����ŏ�����A�O�A�������܂ރ~�N���l�V�A�n���i����m�Q���j�S�̂ɊC�m�������̉^�����N����A�₪�Ĕ��j�^�����I�Z�A�j�A�S��ɍL����A���Z�N�ɓƗ����������l�V�A�̃o�k�A�c���a���͔���N�ɁA�j�����ύڂ��Ă��Ȃ��Əؖ��ł��Ȃ��������`��F�߂Ȃ��ƁA�Ċ͂̊�`�v�������ۂ��A���O�N�ɂ͔�j���Ɛ錾������ō̑������B
�@���O�N��A�I�[�X�g�����A���h���͊j���퓋�ڂ𗝗R�ɉp���C���r���V�u���̊�`�����ۂ����Ɣ��\���A���ܔN�A�j���[�W�[�����h�̃����M�͊j�ύډ\�͂��ׂĂ̊�`���ۂ��A�����J�ɒʍ����A�����N�Z���Ƀj���[�W�[�����h��j�@������ŏ��F���ꂽ�B
�@�㎵�N�O�������ߑO�A��錧���C���̓��͘F�E�j�R���J�����ƒc�i���R�j�̎g�p�ς݊j�R���ď����H��ŁA��x�����ː��p���������̂��߂̃A�X�t�@���g�ʼn��H��ɉЂ��������A�₪�Ē���������ꂽ���A�����ߌ㔪���߂��ɓ��H��Ŕ������N����A���˔\���^�̌ʼn��{�݂̔��𐁂��Ƃ��A�����͂���Ɏ{�݂̌����̑���V���b�^�[��j�ĊO���ɗ��ꂽ�B
�@���̑厖�̂��N��������x�����ː��p���������̂��߂̃R���N���[�g�E�A�X�t�@���g�ʼn��Z�p�́A�C�m������ړI�Ƃ��ĊJ�����ꂽ�Z�p�ł������B
�@�������A����N�ɓ����p�̓쓌��Z�Z�L���̊C��Ŏ��������������Ȃ����Ƃ���A��x�����ː��p���������h�����ʂ��[�x�Z��Z�Z���[�g���ɒB��������ɔj��Ă��܂��A�C�m���������͎��s�����B���̌��ʁA��n�����n���ݏ����������p������j�ƂȂ����B
�@�u�����V���v���l�N��Z������t�L���́A���̊C���̕��p���j��ᔻ���āA
�@�u���{����x���p������쑾���m�ɓ������悤�ƌv�悵����A�����ǂ���ɊW�e�����瑍�X�J����H�����o�܂��L���ɐV�����B������ː��p�����́w�����������x�����ێЉ�̌����Ȃ̂��v
�@�Ə����Ă���B
�@����ł��A���{���{�͂�����߂��A�w���q�͔����@���a60�N�Łx�i��㔪�ܔN�j�́A
�@�u��x�����ː��p�����̏����́A���n�����ƊC�m�������čs�����j�ł���v
�Ɩ��L���A���́u���j�v�́A�w���q�͔����@�����S�N�Łx�i�����N�j�ł́A�u��x�����ː��p�����̏����́A���n�����y�ъC�m�������s�����Ƃ���{�I�ȕ��j�Ƃ��Ă���v�ƁA�ނ���u��{�I�ȕ��j�v�ɋ��߂��`�ŁA�ێ���������ꂽ�B
10.4 ���{�̌����̃g�C���ł͂Ȃ�
�@����O�N��ꌎ�A�����h���ŊC�m�����K�����������A����ɐ旧�O���Ƀ��V�A�̓��{�C�ւ̉t�̕��ː��p�����̓����������N����A���{���~�N���l�V�A�����Ƃ��Ȃ���Q���ɂȂ�댯�������������ƂƂ����܂��āA�悤�₭�u��x�����ː��p�����̏����̕��j�Ƃ��ĊC�m�����͑I�����Ƃ��Ȃ��|�̌��q�͈ψ������s�����v�i�w���q�͔����@����6�N�Łx�j�B
�@����ł��A�u������ł͏����A�����I�A�Љ�I�ȏ�����傫���ω������ꍇ�ɂ́A�{����̍Č������l������Ƃ��Ă���v�ƕt�������Ă���B�������āA�~�N���l�V�A���ӊC�悪���{�̌����̃g�C���ɂ����A�������܂����댯���͂ЂƂ܂�������ꂽ���A����珔�������{�̊j�̃S�~�̂ď�ƂȂ�댯������A�܂����S�ɂ͉������Ă��Ȃ��B
�@����̓��C���̍ď����H�ꔚ�����̂́A���{���܂��C�m�����̕��j��O��ɊJ�������A�X�t�@���g�ʼn��Z�p��������߂Ă��Ȃ��������Ƃ�\�I�������A���̎��̂ɂ���ē��{�̌��q�͐������������C�m�����ւ̎��O�͌���I�ȃ_���[�W�����̂ł���B
�@�������Ĕ�j���@����ɂ�葾���m�̔�j���̐擪���������p���I�ł��������A�A�����J�����̂䂦�ɓƗ���F�߂��A��j���@�̎������̂��߂̐����I���͂���߂��B
�@���@�N���ψ����ł���A�������{�̏���哝�̃n���I�E�������[�N�����ܔN�Z���[��Ɏ���O�ŏe������ÎE���ꂽ�B
�@���ڂ̃��U���X�E�T���[�哝�̂͐e�Ĕh�ł��������A�����N�����ɗ��R�s���̎��E���Ƃ����B
�@�T���[�哝�̎���ɁA�u���R�A������v�̎O�`�Z��ڂ̏Z�����[�������Ȃ������A���Ɍ������ɂ������Ă͕s���F�̏ꍇ�͋����s������ꎞ���قȂǂ̐����I���͂��������ɂ�������炸�A����������F�������Ȃ������B
�@�p���I�ő�̎�_�͍����I����������Ȃ��Ƃł���B
�@�A�����J�����{�̌o�ω����ɗ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���{�̈ϔC�����ƃA�����J�̐M��������ʂ��āA���̂悤�Ȍo�ύ\���ɂ��肩�����Ă��܂����̂ł���B
�@�O��ڂ́u����v���i�h�̃G�s�\���哝�̂̂��ƂŁA����N�܌��A�����J�͎������^�̑��z�ɉ����i�O�A�����Ӂj�A��Z�N�ɃO�A�����ӂƍ��킹�Ď���ڂ̓��[�������Ȃ�ꂽ���A�t�Ɏ^���[���ߋ��Œ�Ƃ����L�^���������B
�I�Z�A�j�A�̔�j�^���̑�g���p���I�ł����܂���݂����̂������B
�@��Z�N��Z���A�A�����J�̓p���I�ړ������ɒu���A���̎�������I�グ�����B�p���I�̍����͍s���l�܂�A��A�A�����J���쐬�����\�Z�𐭕{�E�c��Ƃ��Ɏ����ɂ��������B
�@�����Ŕ����N�ɏZ�����[�Ŕی����ꂽ���@�C���Ă����𐁂��Ԃ����B
�@�C���Ă̓��e�́A�u���R�A������v�̗L�����Ԓ��͂���Ɩ������錛�@�̏����́u����v�ɓK�p����Ȃ��A�Ƃ������̂ł������B
�@���̂悤�ȃA�����J�̐����I�E�o�ϓI���ߕt���̂��ƂŁA���N�����ɏZ�����[�Ō��@�C���Ă����F����A��O�N��ꌎ�̏Z�����[�Łu���R�A������v���������A��l�N��Z���A�p���I���a���͐��E�ň��Z�Ԗڂ̓Ɨ����ƂȂ����B
10.5 ���{���Ђ��Ȃ������̍c����
�@���{��������̍s�����ł����m���̓p���I�̃R���[�����ɒu����Ă����B
�@���{�̓�m�����͈ϔC�����Ƃ�������̂��߁A���̐A���n�����Ƃ����������i�������Ă����B
�@�ő�̂������́A��m�Q���̓��������{���Ђ������Ȃ��������Ƃł���B
�@�w�ϔC�����̓�m�Q���x�ɂ��A���{���{���獑�ۘA��������ɒ�o���ꂽ���O�l�N�x�ϔC�����N���i���{�̍��ۘA���E�ތ�A�ŏ��ɒ�o���ꂽ�N��j�ɁA�u�����n��̏Z���͔V�𓇖��i�gInhabitants of islands�h�j�Ə̂��A���{�鍑�b���Ƃ͑��̐g�����قɂ��A�����ċA���A���������̈ӎv�Ɉ˂�̊O���{�鍑�b������̐g�����擾���邱�ƂȂ��v�ƋL�ڂ���Ă���B
�@���̂��Ƃ͓�������ɂ��\��ꂽ�B�ŏ��A�C�R����m�Q�����̂���ƁA��m�Q�����w�Z�K�����߁A����E�Z�p�E���̂Ȃǂ̋��Ȃ����������A�K���̒��ɂ́u�C�g����̓���������v�ƁA�c��������̕��j�����荞�܂�Ă����B
�@���ꔪ�N�ɖ����Ɉڊǂ����ƁA��m�Q�������w�Z�K�������肳�ꂽ���A�����ɂ͂����Ɩ����Ɂu�c���������߂邱�Ƃ����Ƃ���v���j�����L����Ă����B
�@�������A�x���T�C�����ňϔC�����̂Ƃ����ƁA��m���w�Z�K�������肳��A�u���w�Z�ɂ����Ă͎����g�̂̔��B�ɗ��ӂ��ē�����{���A�����̌�����P�ɕK�{�Ȓm���Z�\�������邱�Ƃ�{�|�Ƃ���v�Ɖ��߂�ꂽ�B
�@���w�Z�͖����œ��w�A�A�w�N���O�N�A����ɕ�K�ȓ�N�ɐi�w���邱�Ƃ��ł��A���ȏ��Ƃ��Ă͓��Ɂw��m�Q������ǖ{�x��Ҏ[�����ق��A�C�g�E�Z�p�E�n���E���ȁE�_�ƉȁE��H�Ȃ͂��ꂼ�ꋳ���v�ڂ��߂ċ��������A���ʂȋ��ȏ��͕Ҏ[����Ȃ������B
�@�w��m�Q������ǖ{�x�Ƃ����A�쑺���w�C��n�������{��x�̖`���ɋL���ꂽ�����ւ̃G�s�\�[�h���v���o���B
�@���l��N�A�܂������̍���i�Ƃ������܂������̂Ȃ���Ǝu�]�ҁj�������O��̒����́A���Ɠ�̑��q���������A�Ƒ��𓌋��ɂ̂����ē�m���̍���ǖ{�̕ҏC���L�Ƃ��ăR���[���ɕ��C�����B
�@�������R���[�����瓌���̎q�ǂ������ɏ������莆��쑺�͒����̖`���ŏЉ�Ă���B
�@�����@�Ȃ₷�݂ł����ˁB������̍����w�Z�ɂ́@�Ȃ₷�݂��@�Ȃ���B
�@��N���イ�Ȃ�����@���������Ȃ��B������ɂ́@���ƂȂ̂����炢�̂ł�ł����邺�B
�@����傤�肵�Đl�����ׂ�Ƃ��B�킩���Ƃƃn���o���킷��Ȃ����ƁB�p���I�ɂ́@���݂����Ȃ��B |
�@�u����傤��v�́u�������v�A�u�킩���Ɓv�Ɓu���o�v�͓������s�̌��N�E���{��i���ł���B���̎莆���Љ�����ƁA�쑺�͒������e���̊w�Z�����@�����Ƃ��̊��z���Љ�āA����Ɏ����̊��z�����̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�q���ւ̗t���ɁA�u��N���イ�Ȃ�����@�Ȃ₷�݂��Ȃ��v���Ƃ������������ւ́A�����ł́u�I�I�N�j�k�V�m�~�R�g�v�Ƃ����A�ٖ����̐_�l�̖��O���g�����������h�ł��Ȃ��T�C�p�������̐��k�ɓ���I�ł���B
�@�u�Ȃ₷�݁v�̂Ȃ��ނ�Ɂu�Ȃ₷�݁v�̊y����������������������邱�Ƃ͖����ł���A�u���݁v�̂��Ȃ��p���I�Łu���ݍ̂�v�̊y������u���݂̐��v�̑��������������邱�Ƃ����v�ł���悤�ɁA�ٍ��̐_�l�̖��O�𐳊m�ɈÏ������邱�Ƃ́A���F�����ȗv���Ƃ��킴������Ȃ����낤�B
�@�����̓��{�ꋳ��ɂ����āA����Ǝ҂̐�����������O�i�͂��j�ꂽ�Ƃ���Ō��t�����̋�����s�Ȃ��̂͂���߂č���B���t�����̋���Ƃ������Ƃł���A�����Ɣނ�̐��������Ɋ�Â������ނ��H�v���邱�Ƃ͉\�Ȃ͂��Ȃ̂ł���B |
�@�Ƃ��낪�A�쑺�����p�����w��m�Q������ǖ{�x�̖ڎ��́A��N�p�Ɂu�����^���E�v�A��N�p�Ɂu�E���V�}�^���E�v�u�L���E�W���E�v�u�c���q�a���m�䐬���v�u�I�E�M�m�}�g�v�A�O�N�p�Ɂu���{�v�u���m�ʖm���v�u�m���V�c�v�u�ޗǁv�u�I���߁v������A�����̓��n�ł̗��j�I�����Â�����\�������Â����ɒ����������ŁA���ނ̓��e�͑S���̍c��������ł���B
�@�u���{�鍑�b���v�̍��Ђ��^�����Ă��Ȃ������ɍc����������قǂ������Ƃ̊��m���ɁA�w��m�Q������ǖ{�x�̕Ҏ[�҂������C�t���Ȃ������Ƃ���ɁA���̌Q���ł̓��{�ꋳ��̔ߌ�������A����������Ƃ����Ƃ���ɒ����̐�]���������B
�@�������̃G�s�\�[�h����ɋL�����Ă����̂́A�p���I�ɖ{���ɃZ�~�����Ȃ��̂��m���߂ė��悤�ƁA�����������Ă�������ł���B
�@�������ɃZ�~�����Ȃ������B
�@�Ƃ��낪�A�D���p���I���o�����Ƃ̑D���V���ɁA�u��Ղ��߂���ɏ����W�����O���ɐ�̐������y�������[�̓��v�Ƃ����Z�̂����e�f�ڂ���Ă����B
�@�y�������[�ł��A���܂��܂̒��̐������Ƃ͂ł������A�Z�~�̐��͂��ɕ����Ȃ������̂����B
11�@�䂪���̕��m�����́u�ʍӁv�̓��y�������[
top
11.1 ���{��̉̂ŗx�����p���I�̎q������
�@��A�p���I�̐l�����̊��}�̗x�肪�D�̌�b�A�v�[���̂���b�ł����Ȃ�ꂽ�B
�@�x��͎O�g�A���w�Z��w�N�̔N��̏��̎q����i�j�̎q����l�܂����Ă����j�O���[�v�A���w�Z���w�N�̔N��̏��̎q�̃O���[�v�A�����Đ��N�j�q�̐�m�̗x��ł���B
�@��w�N�g�̗x��̓t���_���X�Ɏ��Ă����B�I�Z�A�j�A�̗x��ɂ͗��̗x��ƊC�̗x��̓��ނ�����悤�ł���B
�@�C�̗x��͔g�ɗh����M������鋙���̃��Y���ƃ����f�B�[�ł���A�n���C�A��������ɑ�����Ƃ����悤�B
�@���̂��ƂɋC�Â����̂́A����N�ɓ����ŃI�[�X�g�����A��Z���̉̂Ɨx��������Ƃ��ł������B
�@�I�[�X�g�����A�̐�Z���ɂ͑嗤�ɏZ�ރA�{���W�j�ƃp�v�A�Ƃ̊Ԃ̃g�[���X�C���̏����ɏZ�ރA�C�����_�[�Y�����邪�A�A�C�����_�[�Y�̉̂Ɨx�肪�n���C�A�����Ȃ̂ł���B |
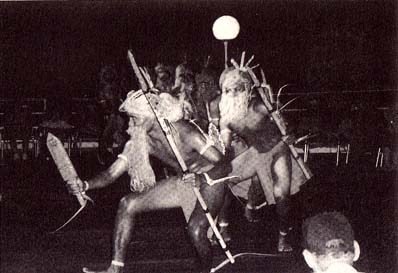
�p���I���̐�m�̗x��
|
�@�嗤�ɏZ�ރA�{���W�j�����Ƃ��Ƃǂ�ȃ��Y���ƃ����f�B�[�������Ă����̂����炩�łȂ����A�ނ炪�q�r��̖q���Ƃ��ē��������j�������̂ŁA��Ȃ��ƂɃE�F�X�^�����Ȃ̂ł���B
�@���܂�ɑΏƓI�Ȃ̂ł��̑���ɋC�t�����ꂽ�B
�@�������A�{���̗��̗x��̃��Y���ƃ����f�B�[�́A��������邢�͐�m�̂���ł���B
�@�j���[�W�[�����h�̃}�I�����̗x�肪�����ł��邵�A�K�_���J�i�����̗x��������ł������B
�@�Ƃ���Ńp���I�̗x��ł��邪�A��w�N�g�̃n���C�A�����ɑ����āA���w�N�g�͉����̂��Ȃ���x���Ă���B
�@���̗x����n���C�A�����Ƃ���͌�������Ȃ����A���{�̖~�x��Ƃ���������Ȃ��B
�@������ƕςȂ̂ł���B�̂Ɏ������܂��Ă��ăA�b�Ǝv�����B
�@�ޏ����������ɂ��Ă���̎��͂Ȃ�Ɠ��{��ł������B
�@�@�N������W������@�������̂ۂ�
�@�@���͂�@���͂�@�邪������
�@�����ɂ��A�����������}���邽�߂ɓ��̋��t�����ʂɍ�����̂��Ƃ̂��ƂŁA��O�́w��m�Q������ǖ{�x�Ƃ͊W���Ȃ��Ƃ̂��Ƃł������B
�@���l�j�q�̗x��͐�m�̗x��ł������B�p���I�̓`���I�x�z���x�ɂ��āA�w�ϔC�����̓�m�Q���x�́A�u�{�����̏U���K���́A�呺�U���A�������U���̓�K���ɋ�ʂ���Ă���B
�@��U���͓��Ĉ���A�C�o�h���Ƃ����ăR���[�����ɍ������A��̓A���N���C�Ƃ����ă}���L���N���ɍ������Ă���B
�@���̓��\���̓p���I��������Ċe���̈���x�z���A�e�U���͓��U���̔z���ɑ������B
�@���U���͌×�����e�X���̐��͊g���̂��߁A�����Α��������i������푈�j�������Ă������A�ߑ�ɂȂ��āA�悤�₭������~�߂��B
�@�������A�����Ȃ��A���҂̊W�͂�T������Ή~���������X��������v�ƋL���Ă���B
�@��m�̗x������������Љ�I�W���琶�܂�A���܂Ɍp�����ꂽ�̂ł��낤���B
�@���Z�������A�����Ȃ肻���ȑ�ςȍD�V�C�A�ʓ��̃��O�[���͖��𗬂����悤�ɓ₢�ł���B
�@�g���Ԃ��ɂʂ�Ă��A�X�R�[���ɂ����Ă��悢�悤�ɁA�h���̑���\���ɑӂ�Ȃ��A�Z���ɒ��H�̂̂����D���āA���z�ɋ�l�����M���z�ɕ��悵�A�y�������[�����߂����Ĕ��i�����B
�@���}�n�̈�l�Z�n�͑D�O�@����t�����v���X�`�b�N���͖җ�ȃX�s�[�h�Ő��ʂ���������B
�@�l�Z�m�b�g���炢�o�Ă���̂��낤���B���c�Ȃׂ̗ɂ�����Ă����̂ŃX�s�[�h���[�^�[��`���Ă݂���A���[�^�[�͎~�����܂܂ł������B
�@�����̃{�[�g�̂悤�ɑD�ɏオ���Ă���̂ŁA���c�Ȃ���O���������Ȃ��B
�@�����炭�ǂ������Ă���̂�����ŁA���̉��ɗ����Đj�H���w�����Ă���̂������ł��낤�B
�@�҃X�s�[�h�œ��X�̂��������삯�����A��܁Z���Ŋʍœ�[�̃y�������[���̖k�[�̃K���R���g�~��ɓ������㗤�����B�@�����ȓ��X�Ɉ͂܂�āA������܂肵���悢�`�ł���B
�@���肶��Ƃ���鑾�z�̉��Ńo�X��҂B
�@�g���b�N���ł��������������A���̕邵�͂̂�т肵�Ă��āA�S�����悹�邾���̎Ԃ��Ȃ��Ȃ������Ȃ��B
�@��ɒ����ĎԂɏ���Ă����l�����������ɕ����ĎԂ��~��Ė؉A�ɔ��A�Ԃ��؉A�Ɉړ����ėz�˂�������Ă���B
�@�₪�ă}�C�N���o�X���A�o���l�䂪���낢�A������̃c�A�[�J�n�B
�@�K�_���J�i�������l�A�Ԃɗ�[�͂Ȃ����A�����J�����ĂA�S�n�悢�C������������ł���B
11.2 �j���[�M�j�A�E�C���p�[���E�y�������[
�@�y�������[���A���̓��͎����Z�ޒ��o�g�̕��m�������������������ł���B
�@�܂萅�˂̕������A�����njR�������Đ��ɑS�ł������ł���A�����m�̓��א�ł́A�������E����ƕ���ŃA�����J�C��������킵�����ł���B
�@���̏Z�ޒ��́w�s�j�x�����ĕҎ[�����Ƃ��A���́w�s�j�x�̌��e�ɁA�y�������[���Ő�v�����s��o�g�̕��m�����̎�������l���A����ɍ��݂���悤�ɏ�������ł������B
�@�����̎s���i�꒬�j�o�g�̕��m���p���I�œ�ܐl��v���A���̂����y�������[���ł̐�v�ғ�Z�l�̐�v�N�����͈ꗥ�Ɂu���a�\��N�\�O�\����v�ƋL�^����Ă���B
�@�{���̐�v�����͕s���Ȃ̂ł���B
�@���́A���˂ŕҐ�����A�܂��͐��˘A�������[�n�Ƃ��������A���A���Ȃ킿���y�����́A������{�y���핺�c�̘A���������A
�@�@�@���{�ŌÂ̏�ݘA���̈�ł���������A���i���l�t�c�E�F�s�{�j�A�����푈�����ɓ��ݎt�c�Ƃ��ē�������A�싞�U����ȂǂɎQ�����A���O��N�㌎�ɕ������ĉ��U������ꎟ�̕������Z��A���i����l�t�c�E�F�s�{�j�A
�@�A�@������O�P�ʎt�c�V�݂ɂƂ��Ȃ����O���N�l���ɐV�݂���A���˘A�����Ґ��E��[�����Ƃ��������攪�l�A���i����t�c�E�F�s�{�j�A
�@�B�@���O��N�ɐ��̕�����l�A�����Ґ���S�����A���݂̑��Z��A���̕����ɂƂ��Ȃ��A���˘A���悪��[��S���������������A���i��O�O�t�c�j�A
�@�C�@���O��N�Z���ɒ��N���R�̕����掵��A�����Ґ���S�����A���l�Z�N�ꌎ�̕������A���̕����ɂƂ��Ȃ��A���˘A���悪��[�����ƂȂ����������O���A���i��l��t�c�j�A
�@�D�@���l�Z�N�����ɑ��l�t�c���������ĕ������A�������B�풓�t�c�ƂȂ������ƁA���˂ɑn�݂��ꂽ��̕������Z��A���i��܈�t�c�E�F�s�{�j�A����ł���A�ق��ɒ����x���̓Ɨ��������c�̂������̓Ɨ���������y�уA�h�~�����e�B�����Łu�ʍӁv�����Ɨ��������A���̕Ґ��E��[��S�������B
�@�ȏ�̕����A���͂��ׂĈ�x�͒�������ɏo���������̐��Ő���Ă���B
�@�������l�A���͏I�n��������Ő킢�A�푈�I�����͕����i�x�g�i���j�k���ɂ������B
�@���˘A���悪�Ґ��E��[��S�������A���̂������l�A�����������̎l�̕����A���́A������������m�푈�ɂ�����ł��ߎS�Ȑ��ɓ������ꂽ�B
�@����A���͒��������]�킵���̂��r���}����ɓ]�p����A���̃K������́u�쓇�v�ƕ��я̂����u�����X���v�̖��ߌ��I�Ȑ��̃C���p�[�����ɎQ�������B
�@���̏��������O�O�t�c�́A�r���}����ɎQ�����̕��͂���O��Z�A��v�҈ꖜ�܁Z���A�A�ҎҎ����l�ŁA�K���P�ޕ�����萶�������Ⴉ�����B
�@�A���̏o���ȗ��̐�v�Ґ��͒��������Z�Z���A�r���}����l�O�����A�v�l���㔪���ɒB�����B
�@�܈�t�c�̈�Z��A���́A�����t�c�ƂƂ��Ɉ��l��N�Z���̓ƃ\��J�n�ɂƂ��Ȃ��\�폀���̑哮���u�֓����v�Ŗ��B�ɔh������A���Œ�������̉ؓ�ɓ]�p����ē]��̂̂��A�l��N��ꌎ�A�����j���[�M�j�A����ւ̓]�p�����肳��A�t�c�̐挭�����Ƃ��āu�_���s�[���C���̔ߌ��v�ȑO�Ƀ��G�E�T�����A�n��ɏ㗤���A���n�悪��͂��ꂽ�̂��A�W���l�Z�Z�Z���[�g���̃T�����P�b�g�R�z���őދp����Ƃ����A�O�㖢���̎R�x�ދp��Ȃǂŕ��͂����Ղ��s�������B
�@�A���̕Ґ��l���O���l�A��[�l���ꎵ��l�A�v���ꔪ�A�A�ҁE�c�u�E�ґ��E�]�����Z��A��v�E�����s���E���ݕs���ҎO�Z�Z��A�����ҋ㎵���i�l�ܔN�������݁j�Ƃ����S�W����^�������ǂ����B
�@�O�A������������l��t�c�͕Ґ��Ɠ����ɒ����ؖk����ɏo�����A�l�O�N�ꌎ�ɑ�ꔪ�R�ɕғ�����ē����j���[�M�j�A�̃E�G���N�ɐi�o�����B
�@�Ȍ�A�}�_���E�A�C�^�y�ƃj���[�M�j�A����ŋ��𑱂��A�j���[�M�j�A�]�p�̍ۂ̕Ґ��l���l�Z�l�����A�ґ������i�A���r���ł̊C�v�҂��܂ށj�l��ꖼ�A�]���҈�Z�ꖼ�A��v�ҎO�l���㖼�A�A�ҕ����҂킸���Ɏl�Z���A���̘A���͌��t�̖{���̈Ӗ��őS�ł����̂ł������B
11.3 �������A���A�y�������[�������
�@�������A���́A���Ɠ�������E���t�c�ɑ��������ɐݒu����A���Ő�t�����q�Ɉړ]���A���̒�����͐�t���A��錧�ł������B
�@�����푈�ŗ����U�����ɎQ�����A�����Z���s�E�������N�������͎̂�Ƃ��Ă��̘A���ł������B
�@���I�푈�ł������U�����ɎQ���������`�E�s�X�n�ւ̓�����N�i�����j���鏼���R�Ɨۂ��U�������B
�@�����푈��̈ꔪ�㔪�N�ɁA���˘A�����i��錧�j���Ƃ��鋽�y�����ƂȂ�A���I�푈��A�V�݂̉F�s�{���l�t�c�̏����ƂȂ�A���˂̕��c�i��ꎵ�N�ɂ���Ԏ��̐E��ł��������E����w���˃L�����p�X�j�Ɉړ]�����B
�@���V�A�v�����푈�̃V�x���A�o���ɏo�����A�����̃j�R���G�t�X�N�ɌǗ������ΐ������S�ł�����`�i�ɂ����j�����i�O�́u�T�n�����v�Q�Ɓj�������N�������B���B���ρA�����푈�ɏo�������̂��A�l�Z�N�ꌎ�ɕ����A�����ɖ��B�풓�����ƂȂ������A�����m����̏���}������ɂƂ��Ȃ��A�֓��R���琸�s�t�c�𒊏o���ē���ɔh������������Ȃ��Ȃ�A�Ȑ܂��ւ��̂��A�l�l�N�O���A��l�t�c�͑�A���o�`���ăp���I�Ɍ��������B
11.4 �Đ������p�핔���̎v�������ʋ��
�@�ČR�͋㌎��ܓ��Ƀx�������[���ɁA�ꎵ���ɃA���K�E�����ɏ㗤���J�n�����B
�@�w�j�~�b�c�̑����m�C��j�x�́A�y�������[��ɂ��Ď��̂悤�ɋL���Ă���B
�@�쐼�����m��������ђ��������m�����ɂ��㌎���{�̂��̓����I�Ȑi�U���́A�ΏƓI�Ȉ�̌��������N�����B
�@�Ƃ����̂́A�C�l�̓V�R��Q���̊댯��W�Q�������A�����^�C��̂͑����m�푈�ł����Ƃ��y�Ȃ��̂̈�ł��������A����A�y�������[�̕��G����܂�h���ɑł����ɂ́A�č��̗��j�ɂ����鑼�̂ǂ�ȏ㗤���ɂ������Ȃ������ō��̐퓬���Q�䗦�i��l�Z�p�[�Z���g�j���ÎȂ���Ȃ�Ȃ���������ł���B�i�����j
�@�k�����Ɍ܁Z�Z�}�C������A�����^�C��肸���Ə����Ȓe�ۍ��q�̂悤�ȃy�������[�̐����́A�Ђǂ����̕����ł���B
�@���̒n��ł́A��܁A�Z�Z�Z���̎�����͂������Ă����p���I�{���i�o�y���X�A�v�j�͔�щz���邱�Ƃɂ��ꂽ�B
�@�������A�����l�}�C���̃y�������[�ɂ͐������l�t�c�̐퓬�����̖���Z�A�Z�Z�Z���ȏ�̓��{�R���z������Ă����B
�@���̏�A�y�������[������͍���̐V�h�q���j���߂���{�c�̎����w�߂ɖ����r���ď]�����̂ł������B
�@�]���͘A���R�̐������p�U���ɑΏ�������{�R���w�����ɏo����Ă������߂́g������͐��ۂɂ����čU���R���}���A��������ł���h�Ƃ������̂ł������B
�@�g�������������M���ɂ��C�݂ɉ^�ԕĎ��㗤�s����x�������ɑ��ẮA���̓��{�̐�@�͎���Ƃ���ő傫�ȑ��Q�����̂ł������B |

|
�@���{�R�̐V�v��͐T�d�Ɍv�Z���ꂽ�c�[�h��@���̗p�������̂ł������B
�@���ۂɂ�������Օ��͂͒P�ɕČR�̏㗤��x��������ړI�Ŕz������Ă���A���R���͊C�R�͖C�̔j��͂�������邽�߂����Ɠ����ɍ\�z����Ă����B
�@���̐��́A�����̒n�`�̕s�K���Ȃ����闘�_�𗘗p�����w�n�Ԃɂ���Ďx������邱�ƂɂȂ��Ă������A�l�q�̍l���y�Ԍ���̂������ނɂ���ē�U�s���Ȃ��̂Ƃ��č\�z����Ă����B
�@������͍͂D�@�����ɍۂ��Ĕ����̂��߂̗\���Ƃ��Ăł��邾�����������͂��ł������B
�@�����ł͂��͂△�v�ȃo���U�C�ˌ��͍s�Ȃ��ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ���A������̈�l��l�����̐������ł��邾���L���ɍ�������ɔ��킹�邱�ƂɂȂ��Ă����B
�@�y�������[�ɑ���O���Ԃ̖җ�Ȋ͖C�ˌ��́A����Ƃ����鐅�ۏ�Q���₻�̔w��̋u�ˏ�̌��������̖h��ݔ���Ռ`���Ȃ�����������B
�@���C���t�c���C�l�߂����ēːi�����Ƃ��A���̏㗤�p�M���̎����Q�⎀���̑啔���́A�k���ɂ̂т�Ő��𗘗p�����v�ǂ̔w��̌X�Ζʂɕz�w�����C���w�n����̖C�ɂ���Đ��������̂ł������B
�@���̎R�w����̘A���ˌ����h�������̈�A�̔����Ƃ������A�C�������͑f�����㗤���_���łߔ�s��ɐi�o�����B
�@�������A�k���̎R�w�ɓ˓������Ƃ��㗤�R�͐V������R���ɂԂ������B
�@�����œ��{�R������͌܁Z�Z��������l�H�܂��͎��R�̓����̖��H�̂Ȃ��ɗ����Ă����̂ł��邪�A���̑啔���͓�������ʂł���悤�ɂȂ��Ă��āA�S�������������̂܂ł���A�S�������ɂ���čI���ɋU������邩�B������Ă����B
�@���̂Ƃ��܂łɊC��\�����Ƃ��đҋ@���ł������攪������t�c�̘A���́A�אڂ̃A���K�E�����Ɖ����̃E���W�[�ʍU���̂��ߐi�����ł������B
�@�ČR�ɂƂ��čK���Ȃ��Ƃ́A�A���K�E���͖h�����͂������ł���A�E���W�[�̂ق��ɂ͎���������Ȃ��������Ƃł���B
�@�K�C�K�[���R�̓A���K�E����킩���A���������Ĉ������Ă����C�����̑����̂��߂Ƀy�������[�ɋ}���œn�点���B
�@�V�������{�R�̖h��Z�p�ɑ���R��Ƃ��āA�o�Y�[�J�C�A���j�p�Ζ�у^���N�ɂ̂����������Ή����ˋ@���������ꂽ�B�������A���{�R���y�������[�����|���邱�Ƃ͂��������ɂ͂��ǂ炸�A���Ɏ��̔N�̓܂ō����ȍ��𑱂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B |
11.5 �傫�������n��o�g���m�̋]��
�@�������y�������[��̂��ׂĂ�����Ă���B�����A�㌎��Z���ɂ͕ČR���^�@���y�������[��s������͂��߂Ă����B
�@�㌎���ɒ������������������Ă������͖͂�ꔪ�Z�Z���ł������B
�@���{�R���p���I�ɐS��D���Ă���Ƃ��A�ČR�̓E���W�[�ʂ���̂������A���̐�p�I�Ӗ��͑傫�������B
�@�E���W�[�ʂ͈Ȍ�̃��C�e���㗤��≫��㗤��ŁA�č������@�������̎�߂ȕd�n�Ƃ��ĕ⋋�⑹���͂̔�ޒn�ɗ��p���ꂽ�B
�@��Z�������A�A���K�E�����̎�������S�ł����B��Z����Z���A�ČR�����C�e���ɏ㗤�������A�y�������[���͂܂�����Ă����B
�@��ꌎ�ꔪ���A�����������̎蕺�͖��܁Z���Ɍ������A�����A�����������͓��{���R�ŌÂ̌R�����Ă��A�t�c����̔h���������䌠��Y�����ƂƂ��Ɏ������A�y�������[������̓��ȏ�ɂ���Ԗh�����A�g�D�I�Ȓ�R���I�����B�������A�����҂͂Ȃ��Q������𑱂��A����͗��N�܂ő������B
�@�����āA���A�Ȃ����Z�ȉ��O�l���̐����҂��p�����킵���̂ł������B
�@�l�ܔN��Z���A�p���I���ӏ�������̓��n���҂��J�n���ꂽ�Ƃ����݂̋]���Ґ��́A�y�������[���̐�v�҈ꖜ�Z�Z���A�A���K�E�����̐�v�҈��܁Z�A���̑��̃p���I�����ł̐펀�ҘZ�܁Z�E�a���Ҏl�ꔪ���A���b�v���̐펀�҈��Z�E�a���ҎO��l�A���v�ꖜ�Z�O�l���A�����҂͗��R�ꖜ���l��O�E�C�R�Z�l�Z�l�E��������m�������ȉ���㎵�܁Z�E�����O�܁Z�A���v�O�����㎵���ł������B
�@���߂Ď��̏Z�ޒ��ƃy�������[���Ȃǂ̐�v�҂Ƃ̊W���������Ă݂悤�B
�@���l�Z�N�̍��������ɂ��꒬�̐l�������Z�Z�Z�ł���A���傤�njR���H��������쏊�Ƃ��̎q��Г�������̑�H�ꂪ�i�o���Ă��Đl�������ӂ��ꂵ����A�l�O�N�ɂ͐l�����O���l�����B
�@�������A�����͖{�Вn��`�ł��邩��A���̏Z�ޒ��̐�v�҂{�Вn�l���͖�ł������Ɛ��肳���B
�@�{�Вn�l����̒����o�g�̐�v�Ґ����Z�l�A�����C�R�����ꖼ�ŁA��v�n�͊C�オ��������ł���B
�@���R�̐�v�Ҍܓ�ꖼ��n��ʂɌ���ƁA�ő�͂�͂��̋��y�A�����قۑS�ł����j���[�M�j�A�̈�Z�A�����t�B���s���̋�Z���A�O�ʂ����ׂĂ̋��y�A�����o��������������̔��Z���A�l�ʂ͓��O�A�����C���p�[�����ɓ������ꂽ�r���}�E�C���h�Ŏ��㖼�A�܈ʂ��y�������[�E�p���I�̓�ܖ��ł���B
�@����ɂ��Ă��{�Вn�l����A�j�q�l����ꖜ�̒�����Z�l���̐�v�҂��o�������̐푈�Ƃ͂����������������̂��A�u�ʍӁv�̌��n�ɗ��ĉ��߂čl��������ꂽ�B
12�@�Ă��s�����ꂽ���ɑh�i��݂��j��������
top
12.1 �Đ��������тɖ쒹�̌Q
�@���������㗤�����̂́A���̖k�[�̃K���R�t�g�~��ł���A��������l�X�������C�݉����ɓ��̓�[�܂ő����Ă���B
�@����������}�C�N���o�X�ɂ͓��{�ꂪ�ł��錻�n�̔N�z�̏���������Ĉē����Ă��ꂽ���A���{�R�̊����Ԃ��J�߂�����A�����������͂����������B
�@�ŏ��ɁA�����i�����������ʁj�����ČR�̐������p��Ԃ̎c�[�Ƃ��̔w��̓��{�R�̓��A�w�n�Ɉē����ꂽ�B
�@�ČR�������p��Ԃ͎v��������^�����A���̔��C�͎l���~���A���肪���{�R����������ʗp���������ł���B
�@����̂ڂ�Ɠ��A�w�n������A���A���ɓ�Z�Z���`�E�Z�J�m���C�����������Ă���B
�@�݃p���I�̊C�R�����n������Z�Z���`���˖C����E��܃Z���`���˖C����E���E���Z���`���˖C���E���Z���`���˖C���E���Z���`���p�C��Z����y�������[�Ɉڑ������̖h�������������ƋL�^����Ă��邩��A���̂����̈��ł��낤�B��Z�Z���`���˖C����͏d���E�t����ǂ̎�C�i���J�m���j�ɑ�������B
�@�܂��ŐV�̌y���E����싉�̓��ږC�͈�܃Z���`�C�Z��ł������B���p�C���p������������Ώ����̑傫�Ȓ��J�m���C�ɓ]�p�ł���B
�@���ꂾ���̐��̑���a�d�C�Ƃ��ɃJ�m���C�̉Η͂��v�lj����ꂽ���A�w�n�ɗ����Ă�A�j�~�b�c���Q�����悤�ɁA�㗤�����͎�ɂ��ڂɂ��킳�ꂽ�킯���B
�@�y�������[���́A���܂ł͔M�щJ�тɂ������A��Z���[�g����̓W�]�������Ȃ��B
�@�ČR����̂����̂��ɐ������ꂽ���H���c���ɑ���A�X��ʂ̐ΊD����Ђ炢�����H�ܑ͕����H�ƂقƂ�ǂ��Ȃ��ŁA�Ԃ̑���S�n���悭���K�ł���B
�@��̂����Ă��ՂɕČR���܂�����l�������[�ň���Ă��邪�A��l�����������т��͓̂��H�e�̈ꕔ�����ŁA����{���̓암��Ղ̂悤�ɋ�l���т��������Â���܂łɔɖ��Ă��Ȃ��B
�@���[�̃R�R�i�b�c���ƃo�i�i���A�W�����ӂ̃p���̖̗сA�J�����ꂽ�^���C�����Ƃ��̎��ӂɐA����ꂽ�}���S�[�̖������A���H�̗����͂��ׂğT������M�щJ�тł���B
�@�܁Z�N�O�̌���őS���̐X�т��Ă��ė��̓��ɂȂ����Ɛ�������A�A����Ɍ����ČR�B�e�̃y�������[��̂ǂ̎ʐ^���S�i���S���̗��R�ł��邪�A���݂̐X�т͓тƂ͂����A�����тƂقƂ�Ǖς��Ȃ��B
�@�ё��͖L���ő����̎����������A�l�̗������錄�Ԃ��Ȃ��B
�@���J�̔M�тŐ����������������A���łɋ��ɐ��������������B
�@�X�є����i�������j�ŗ��ɂ��ꂽ�K�_���J�i�����̔M�щJ�т̍Đ��͐�]�I�ł���B
�@�������A�Ă����y�������[���̔M�щJ�т݂͂��ƂɍĐ������B
�@�Ă����͏Ă��ۂ����肩��Ăщ肪�o�ĐL�сA���̗ё������邱�Ƃ��ł��邪�A�F���i���������j���ꂽ�X�т͉��߂ĐA�����Ȃ�������͐����Ȃ��Ƃ����A���̍����܂��܂��ƌ�����ꂽ�B
�@�����ɔM�щJ�т̐��ł͏Ĕ��_�Ƃ̂����ł͂Ȃ��A�F���̂����Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��悭�m�邱�Ƃ��ł����B
�@�X���L���ł���A����܂ŃK�_���J�i����o�E���ŕ������Ƃ̂Ȃ������쒹�̐������Ƃ��ł��A�C���R�̌Q�������p�����邱�Ƃ��ł����B
�@���ہA�����܂����قǂ̑����̎�ނ̖쒹�̐������Ƃ��ł����B
�@�������̐��̑��l�����������ɂ��A�Z�~�̐��͕����Ȃ������B
��͂�u�p���I�ɂ́@���݂����Ȃ��v�̂��B
�@���̖K���̓u���f�B�[�E���b�W�A�y�������[���ŖT�̐��ŁA�������L��ɕČR�̋L�O�肪�����Ă���B
�@���̍L��̔w��ɂ����藧�R�����{�R�u�ʍӁv�̒n�ŁA���{�R����R�Ɩ��t���Ă����R���������B
�@����Ɉԗ�肪����ƕ������̂œo�肽���������A�����̂ł��Ȃ薳�����Ƃ������ƂƁA���Ԃ��Ȃ��Ƃ������R�œ�������͂������Ƃ����B
�@���Ĉ�؈ꑐ���Ȃ��Ȃ������̍��n���猩���낵���M�щJ�т̎����i���ォ��j�̔g�����炵���B
12.2 �ČR�㗤�n�̔��������l
�@�p���I�̊ʂ̓g���b�N�قǑ傫���Ȃ����A�ʂ̖ʐς͎l���������L���A���̒n���I�����́A�k�k�������쐼�����ɍג����a����̊ʂ��ő啝��܁Z�L���E��������Z�L���ɂ킽���Ă��āA�ʂ̓�쓌���ʂɓ������сA�ʂ̖k�k�����ʂ���k�����ʂ̑S���ɂ킽��X��ʂ����œ����قƂ�ǂȂ����Ƃł���B
�@����珔���ւ̏㗤�K�n�ɐڋ߂���ɂ̓y�������[���쐼�[�������Ă͂���������O�[�����ɐi������ȊO�ɂȂ��A���O�[�����ւ̊͑D�i���H�͎������̑D���ʉ߂��������������ŁA�㗤�R���ɂ������邵���s���ł���B
�@�ʂ̓�쐼�[�Ɉʒu����y�������[���̓쐼�C�݂������O�m�ɐڂ��A���������₩�ȋȐ����������p���������Â��������l�ŁA�ʂ̖W�����Ȃ���D�̏㗤�n�ł���B
�@�㌎��ܓ��A�đ��C���t�c�͓��{�����l���A�k����z���C�g�E�r�[�`�[�E�U�i�C�����A���̏㗤�n�j�A�I�����W�E�r�[�`�[�E�U�i�C����ܘA���̏㗤�n�j�ƃR�[�h�l�[���ŋ敪���ď㗤���Ă����B
�@���傤�ǁA��s�ꊊ���H���S�����삪��n����̈�ܘA���O����̎���n��ŃI�����W�E�r�[�`�U�ɑ������A���̖k�����n����̓�A�������̎���n��Ńz���C�g�E�r�[�`�ƃI�����W�E�r�[�`�T�ɑ��������B
�@�ČR�̏㗤���ʂƂȂ����I�����W�E�r�[�`�T�̊C�݂̍��l����тɓ������Ƃ���ɍL�ꂪ�����A�đ��C���t�c����ё攪������t�c�̋L�O�肪���Ă��Ă���B
�@�y�������[���̖k���͍ג��������ɂȂ��Ă��邪�A���̕����͓Ɨ������O�l�Z����̎���n��ŁA���̖k�n����̓��[�_�[�̂������d�T��ɒǂ��l�߂��A��Z���l���ɑS�ł����B�㗤�R�͔�s��ɎE�����A�{���ƕ��f���ꂽ��n����͓��̓�[�A�씼���ɒǂ��l�߂��ċ㌎�ꔪ���ɑS�ł����B
�@���̗����̊C�݁E��p�́A�u���f�B�[�E�r�[�`�ƌĂꂽ�Ƃ����B�j�~�b�c�������悤�ɁA�đ��C���t�c�̑��Q�͂������邵���A��Z������Ƀy�������[������P�ނ��A�A���K�E�����̕����攪��t�c���y�������[��������p�����B
�@�y�������[��Ղ̗��́A�u�y�������[�_�Ёv�A�����H�߂��ɝ������Ă�����{�̋㎵������ԁA��s�ꊊ���H�A���ȃR���N���[�g�ǂƓS�������c�ɂ��Ŕj�ꂽ�C�R�i�ߕ������̔p�ЁA�[����̎c�[�A�ČR�@�̔p�@�@�̂̎̂ď�A�I�����W�E�r�[�`�Ƒ����āA����[�̊C�����u�ĂăA���K�E������]�ޓ얦�ցB
�@�얦�͌��݁A���ė������{�����݂����Ƃ����y�������[���a�L�O�����ɂȂ��Ă���B
�@�I�����W�E�r�[�`�͎X��̔����������̂сA���̐��g�Â��ȉ���̕l�ŁA��D�̊C������ł���B
�@�������㗤��̌���ꂾ�������Ƃ��M�����Ȃ��قǁA�l���������B
�@�얦�͊O�m�ɖʂ����r��ŁA�ł���g���܂肩���Ȃ������̌��Ԃ���C�����グ�鍋���Ȍi�F�������Ă����B
�@�C���̂��Ȃ��ɕ��R�Ȏp�̃A���K�E������������B
�@�K�C�h���̏����́A�㗤��ŕl�����ɐԂ����߂�ꂽ�̂ŃI�����W�E�r�[�`�Ɩ��t����ꂽ�A�Ɛ��������B
�@�V�n�w�x���E�̐��Ǝ��x�������^�ɎāA�u�I�����W�E�r�[�`�������B�ČR�̏㗤�n�_�ł���B
�@�����҂������A�C�͌��ɂ���ăI�����W�F��悵���Ƃ����v�Ə����Ă��邪�A����͎����Ƃ������B
�@�㗤�C�݂̃R�[�h�l�[���͏㗤�ɐ旧���āA���߂̕z�B�ȂǂɎg����n�}��̒n�_���Ƃ��ĉ��ɕt����ꂽ�����ł���A���̒n�_�̓��{�R�w�n�̃R�[�h�l�[���u�C���}�c�v�i�z���C�g�T�j�u�N���}�c�v�i�z���C�g�U�E�I�����W�T�j�u�A�����v�i�I�����W�U�j�́A�ČR���̃R�[�h�l�[���ƑΉ����Ă����B
�@���a�L�O�����Œ��H�B�ٓ��Ɨ₦���R�R�i�b�c�̎����z��ꂽ�B
�@���ɓ������ٓ��̒����́A����т���A�^�s�I�J�̓b���c�q���o�i�i�̗t�Ŋ����ď��������i���܂��j��A���V�I�̒܂̉����i������Łj�ŁA�Ԃ���̔��g�̋��̐�g�̎ϕt���A�T���_�A���̖�������̂��������̂悢��̘a�����A�f�U�[�g�ɂ悭�n�����}���S�[�ƃo�i�i�Ƃ����A���n�F�L���Ŕ����Ȓ��H�ł������B
�@�����ł̓A�_���̎����Ԃ������Ă����B
12.3 �s�v�c�Ȏ{�݁u�y�������[�_�Ёv
�@���̓��ň�a�����o�����̂́u�y�������[�_�Ёv�Ȃ���̂̑��݂ł������B
�@���ɁA�D���V���ł��A�푈�����ɐ��܂��l�̐����L���ɂȂ��Ă����B
�@���Ă̌���n�y�������[�����̐�Ղ߂���A�����R�̓��e�̒��ňٍʂ�������̂��u�y�������[�_�Ђł������v�ƒ��삳��͌����B
�@�u���̗���ʂ��Đ_�Ђ͏��߂Č����B���̐�Ղ͎����������Ƃ��Ď������̂����_�Ђ͈Ⴄ�v
�@���{�͂��Ă��̒n�ɓ�������������Ă����B
�@�u������_�Ђ͐��ɓ��{�R�N���̃V���{���B
�@������Č����펀�҂��p��Ƃ��čՂ�̂́A�푈�Ȃ��Ă�����ł��Ȃ��͂����v |
�@�_�Ђ̑��݂͏�Ⴂ�Ȋ����Ȃ̂ł���B
�@�������n�Ō���܂Łu�y�������[�_�Ёv�Ȃ鑶�݂ɂ��ĕ������o�����Ȃ������B
�@�A����A�Ă����ǂ��Ē��ׂĂ�������B
�@�y�������[����v�҂̈⑰�c�̂̂��ƂȂ炱�̐l�ɕ����킩��A�Ƃ����l�̘b�ɂ��A�ӊO�Ȃ��ƂɃy�������[����v�҂̈⑰�c�̂Ɛ_�Ђ͑S���W���Ȃ��Ƃ����B
�@�u����́A����_���W�̒c�̂����Ă����̂ŁA���܂܂œ�x���킳�ꂽ�ƕ����Ă��܂����A�܂������Ă��܂����H�v�@�Ƃ̂��Ƃł���B
�@���������A�K�i�ق���j�͐V�������A���ʂ̒�������������܂�ē|��Ă����B
�@�����̊m�F�̂��悤�͂Ȃ����A�����A
�@�u�����K�i�ق���j�̂Ȃ��ɐ�v�҂̈⍜���[�߂��Ă���̂ł���B�������͂��̈⍜��Ԃ��ƌ����Ă���̂ł����A�Ԃ��Ă���܂���v�@�Ƃ����B |
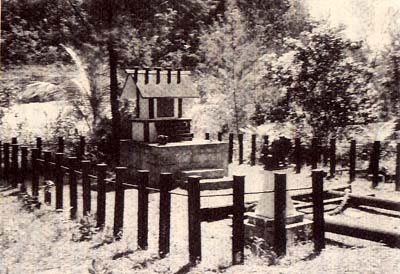
�x�������[�_�Ёi�����͓|��A�[�����͂��̍��Ղ��Ȃ�
|
�@���́A���̏@���c�̂����s���Ă��锪���N�����s�̋@�֎����������A���̌�A�L���̌Ï��X����w�y�������[�_�Е�^��ݗ���ӏ��x�Ȃ���q����ɓ���邱�Ƃ��ł����B
�@�@���c�̂̎�Ɏ҂ł��邱�̍��q�̒��҂́A�u�_�E�Ȃ邪�R�ɁA���쑾���m��̊e���ɂ��������_�Ђ��Č����Ă����ɉp��̌䍰���������Ĉԗ삷�邽�߂ɁA���̈ꐶ������悤�Ƃ����ł����ӂ�������v�Ƃ����B
�@�@�֎��ɂ��A��㔪��N�Ɂu�y�������[�_�Ёv�A���O�N�Ɂu�A���K�E���_�Ёv�A���Z�N�Ɂu��m�_�Ёv���������A���N�_�E�ƈ⑰��̐l�X���e���ɓn����Ղ��s�Ȃ��Ă���B
�@��㔪���N�x�́u�A���K�E���_�З��Ձv�A�u��m�_�З��Ձv�A�u�y�������[�_�ЎQ�q�v�Ɓu�e���ԗ쏄�q�v���A�������蓯�������̗����ł����Ȃ��A�_�E�A�⑰��̐l�X��ܖ����Q�������B
�@��ꌎ�ɂ́A�u��m�_�Ёv�u�A���K�E���_�Ёv�ɍ�����V���Ɍ������A�܂����a�ɐI�܂ꂽ�u�A���K�E���_�Ёv�̎Гa�̐ΐ��̎Гa�ւ̌��đւ������̓ɏI�������B
�@����̏��q�ɂ����ẮA�u�y�������[�_�Ёv�ɂ����������������A�ƁB
�@����A�y�������[��v�҂̈⑰�c�̂́A��㎵�Z�N�Ƀy�������[���̏U�����K�����č����h�쑍����b��\�h�K�₵���ۂɁA�扑�Ȃǂ̗v�����Ď����t���ꂽ�ꖜ�h���i�ژ^�j���A�u���������ĖK�����A�U���ɓn���ƂƂ��ɊW���铇�̗L�u����ђn�傽���ɍ������āA�[���ԗ��̌�������т��̕~�n�A�扑�ɂ��Ă̗����A����ɂ����̉i�v�Ǘ��i�����j�Ɋւ��Ă����ӂɒB���Ċo�����������A�����ɓ����̈ԗ쎖�Ƃ̊�Ղ��m�肵���B�i�����j
�@���a�l�\���N�i��㎵��N�j�y�������[���݂��܉�͏�����W�߂āA�y�������[���扑�Ɉԗ쓃�w�݂��܁x���[�������݁������������v
�@�����A�@���c�̑��́A����N�Ƀy�������[���A�V���X���̑����ő����̃C���V�A�X�E�E�V�A�X�ƁA����̃y�������[����v�҂̂��߂Ɂu�W���p�j�Y�E�^�C�v�E�I�u�E�e���v���i���{���̎��@�j�v�i�_�Ё��V�����C���ł͂Ȃ��j�����݂���ړI�ł��̕~�n�g�p�Ɋւ���_������B
�@���̌_��̑O��Ƃ��Č��n�̊W�҂Ɏ��O�ɑ��t���ꂽ�u���{���̎��@�v�̐v�}�ʂ́A�_�Ђƒ���Ё��[�����Ƃ̓�̕����{�݂ł������B
12.4 ���W�����⍜�͂ǂ��ցH
�@�Ƃ��낪�A�_���̏@����֑��̉��߂ł�
�@�u�w�o�����x�ɂ���܂��悤�ɁA�w���{���̎��x�Ƃ͐_�Ђ̌����̂��Ƃł���܂��āA���̎Ђɂ͐�v�҂̌䍰�����J���g�y�������[�_�Ёh�Ɩ��t���܂��B
�@���ɂ���܂��w���ӓ��e�x�Ƃ����ו��Ɋւ��錏�́A���������p��̈⍜�����u����A��[�����̌����ƁA������K�₷��W�҂̂��߂ɏh������V�݂��Ăق����Ƃ������̏Z���̗v�]���܂܂�Ă��܂��v
�@�ƁA�_��ɖ��L���ꂽ�Ώۂ́u�_�Ёv�����ł���A�u�[�����v�̌��݂́u����̋��c�v�ɂ䂾�˂�ꂽ�u�_��̏������v�i�זځj�ɑ�����Ƃ����B
�@�����A�����s�����Ƃ��A�}�ʂł͒n��ꃁ�[�g���̍����̐Ί_�̊�b�̏�Ɍ������ꂽ�͂��́A�u�[�����v�炵�����z���̎p�͂������A���̍��Ղ������܂�����������Ȃ������B
�@�������A���ۂɔ���N�܌��A���̒c�̂̎�Â���u�N�_�E��m�ԗ쏄�q�c�v�̓y�������[���ɍs���A�������瑗�������ނ�g�ݗ��Ăăy�������[�_�Ђ���������ƂƂ��ɁA�⍜��܁Z�̂����W�����Ƃ����B
�@���q�Ɏ��^���ꂽ�n�����́u���͂炫�v�Z������t�L���́A
�@�u�⍜�͊��삳��炪�����Ȃ̔F�������W�c�łȂ����ߓ��{�Ɏ����A�ꂸ�A�������_�Ђ킫�̔[�����ɔ[�߂��v�A
�@���Ȃ��n�����́u��z�V���v�́u���̑唼�́A�_�ЂƂ��킹���������[�����ɔ[�߂Ă����Ƃ����v�ƕ��B
�@�ق��ɂ��A�u�ǔ��V���v���ł́u�_�ЂƂƂ��Ɍ��������[�����ɔ[�߂��v�A
�@�T���P�C�V�����ł́u�_�Ђ킫�[�����Ɉ��u�v�ƕĂ���B
�@�������A�����̋L���͋L�҂��������n�Ŏ�ނ������̂ł͂Ȃ��B
�@�������n�Ŕ[�����炵���{�݂�ڂɂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ������悤�ɁA����N�܌��Ɂu���q�c�v���y�������[���Ő_�Ђ���������Ƃ��A�������猚���ɕK�v�Ȏ��ނ��������𑗂��Ă���A���q�ɓ]�ڂ��ꂽ�����̑D�ς݉ו��̖����ɂ́A�_�Ќ����ɕK�v�Ȏ��ނ͏ڍׂɋL������Ă��邪�A�[�������ݎ��ނ͂��������L�ڂ���Ă��Ȃ��B
�@�����̓����҂����̂Ƃ��[���������݂����Ƃ͏����Ă��Ȃ��B
�@�܂�A�e�V�����������ɂ́u�_�ЂƂƂ��Ɍ��������[�����v��u�_�Ђ킫�[�����v�͑��݂��Ȃ��������A���݂����݂��Ȃ��B
�@����ɁA�u�y�������[�_�Е�^���v�́u�ړI�v�ɂ��u���Ɓv�ɂ��A�⍜�̎��W�Ƃ��̋��{�i���悤������͕����p��j�ɑ�������_���I�@���V���s���ɂ��đS�������G����Ă��Ȃ��B
�@�����l����ƁA���������A���̒c�̂����W�����Ƃ����⍜�́A�ǂ��ɔ[�߂��A�ǂ̂悤�ȏ@���V��̑ΏۂƂ���Ă���̂ł��낤���B
�@���̈⍜�͂�͂�⑰�c�̂����݂����扑�̔[���{�݂ɔ[�߂��đR��ׂ��ł͂Ȃ����낤���B
�@���H��̋x�e�̌�A�ԂŃK���R���g�~��Ɉ����Ԃ��A�{�[�g�ɏ���ăR���[���ɖ߂����B
�@�O���͂�����Ƃ���͂������X�R�[���ł���B�G��邱�Ƃ��o�債�����A�{�[�g�͍I�݂ɃX�R�[��������A�J�����ق�̃|�c�|�c�Ɠ����������x�ŁA��l���O�Z���Ƀp���I�`�ɒ������B
�@����A�D�ɂ�����A��ꂽ�̂Œ��Q�����Ă�����A�D�͂��̊Ԃɂ��o�`���Ă����B
�@�\��ł͈ꎵ���o�`�̂͂����������A��Z���ɏo�`�����Ƃ̂��ƁB�[���������Ń��O�[�����̍q�s������ɂȂ邽�ߎ��Ԃ𑁂߂Ă̏o�`�������Ƃ����B
�@�����Ƃ��A�A�D���Ԃ͈���ƒ�߂��Ă����̂ŁA��D�҂Ɏx��͂Ȃ��͂��������B
�@�Z����Z���[���A�C�ׂ͂���A���𗬂����悤�ł���B
�@���̊C�ʂ̂Ƃ���ǂ���ɁA���g���������ʂ̐F���ς�萅������オ���Ă���B
�@���ԂQ�A�J�c�I�̌Q�ꂾ�낤�B
�@����\����̌ߌ�ɓ����Ă��炤�˂肪�����Ȃ����B
�@�D�͂��������̗���ɏ�����͂��ł���B
�@���Ď����}�̉����Ńe���r�̕��f���~�ɒǂ����܂ꂽ�u�x�g�i���C�������L�v���A�B�e�҂̐ΐ앶�m����̉���Ō����B
�@��x���Ȃ��Ă���A����ׂ��̐ΐ삳��ƈ��݂͂��߂āA�锼�ɂ��������B
13�@�p���I�̉���l
top
13.1 ���ꂩ��̓�m�o�҂�
�@�Z����O���A�����I���܁Z���N�̓����ɓߔe�V�`�ɓ��`���A�ߔe�œ����葱�����ď㗤�����B
�@���N�Ԃ�̉���K��ł���B�암��ՂɐV�������Ă�ꂽ�u���a�̑b�v�ƓW���̓��e���V�����Ȃ������a�L�O�قɍs�������������A���̓��̓암��Ղł̋L�O�s���ƌ�ʎ���̂��Ƃ��l����ƁA�A�D���ԂɊԂɍ������ǂ�������Ԃ܂ꂽ�̂ŁA�܂����Ă��Ȃ��������ꂽ��̌��w�ɍs�����B
�@���x������ɒʂ������A�����ł̓n�Õ~�i�Ƃ������j���Z���̂�����W�c���������̐����c��̑��Ǎ�ƒm�荇���A���̗U�����Ĕ����N�ɓn�Õ~���ɓn�����B
�@�����c��Ƃ������A�W�c�������������A��邳��͂܂���ɂ������A���g�A�i���͂��j�ɏZ�ޔނ̈�Ƃ͔ނ������Ă݂ȏW�c�����Ŏ��v���A�������܂�����ꂽ�ނ́A�R���畜�����������̈�Ƃɂ���Ĉ�Ă�ꂽ�B
�@�����ē�����āA�n�Õ~�̐l�X�������p���I�Ŏ����Ƃ�m�����B
�@�����p���I���ӎ������̂́A���̏Z�ޒ��o�g�̐�v�҂Ƃ̊ւ�肩�炾���ł͂Ȃ��A������A���ꌧ�̓n�Õ~����ʂ��Ă̔F�����������B
�@�w�n�Õ~���j�@�����ҁx�̉���́A
�@�u�n�Õ~����{�y�ւ̏o�҂��͂���߂ď��Ȃ������Ƃ����悤�B�i�����j
�@�n�Õ~����Ԗ��i���܂݁j��n�����i�ƂȂ��j�́A��������ȗ������Ƃ�����ł������̂ŁA�j���͋��t�ƂȂ菗�����i���߁j������œ����Đ������Ă����B
�@���Ȃ킿�A�L�������������Ƃłǂ��ɂ���炵�Ă������Ƃ��ł����̂ŁA�{�y�ւ͏o�҂��ɍs���Ȃ������̂ł��낤�B
�@�Ƃ��낪�A���O�Z�N�i���a�܁j���ɂȂ�ƕs�������ƂȂ�A�O������ĉƌv����肭�肷��悤�ɂȂ����悤���B�i�����j
�@���傤�ǂ��̍��A��m�̈ϔC�����̂ł́A���ꌧ�o�g�������}���ɑ������������v
�@�ƁA�������Ă���B
�@���O�ܔN�����A��m�ɂ������ꌧ�o�g�҂͈ꖜ�O�l����l�A�����n�Õ~�o�g�҂���l�O�l�i�j�ꔪ�Z�l�E�����l�j�ł���A�����̓n�Õ~���̐l���͈�O�Z�l�ł���������A���l���̈�܁E�����̑傪��m�Q���ɏo�҂��ɍs���Ă������ƂɂȂ�B
�@�n�Õ~����{�y�ɏo�҂��ɍs���Ă����l�̐��͂킸����ܐl�i�j��l�E���Z�l�j�ɉ߂��Ȃ������B
�@���l���ɂ��������m�o�҂��l���̔䗦�́A�n����̓��E�l���i��Z�Z�l�A�{�y�ւ̏o�҂��ܔ��l�j�A���Ԗ��̈�Z�E�l���i����l�A�{�y�ւ̏o�҂��O��l�j�ɂ��ō����B
�@��m�Q���̓��{�l�i���N�l�E��p�l���܂ށj�l���́A���v�̔������邩����ŏI�I�ɋ㖜�Z�Z���Z�l�A���{���Ђ�L���Ȃ������l���͌ܖ����㎵�l�ł��邪�A���{�l�l���̏o�g�n�ʂ��������Ă���̂́A���O��N�ł���B�����̓�m�ݏZ���{�l�l���͎���������l�ŁA�������ꌧ�o�g�҂��l�����Z��l�A���{�l�l���̌܋�E���߂Ă���B
�@���ꌧ�ɂ��̂������{�o�g�҂̎l�l���l�l�A���ŕ������o�g�҂̎O�Z���l�l�A���������o�g�҂̓�܈ꎵ�l�A���N�l�̈��Z���l�A�R�`���o�g�҂̈��܋�l�A�k�C���o�g�҂̈�O��l�Ƒ����B
�@��m�Q���̓��{�l�l���̖�Z�������ꌧ�o�g�҂���߂Ă����B
�@���ꌧ�o�g�҂̓�m�Q���e�x���ʍݏZ�l�����킩��Ō�͈��O���N�A���̔N�̓�m�Q���ݏZ���{�l�l���Z���O��Z�ܐl���A���ꌧ�o�g�Ґl�����O���l��O���l�A���ꌧ�o�g�҂̊e�x���ʍݏZ�l���́A�T�C�p����������l�A�p���I���l�����l�A�g���b�N��������l�A�|�i�y�����l�ܐl�A���b�v����l�l�l�A�����[�g���l���l�ƂȂ��Ă���B
�@�u�吳�\��N�i�����N�j�ɂ͂��߂đ厑�{�ɂ���m����������Ђ��ݗ�����v�i�w�ϔC�����̓�m�Q���x�j�A�u��m����������Ђ̍ŏ��̎d���͊���͔|�ɂ�铜�Ƃ���̂ł������̂ŁA�O��Ђ̎��s�Ɋӂ݁A�M�ѐ��C��ɏ������A�������M�ђn�̍�ƂɊ���A����͔|�ɏK�n���鉫�ꌧ�l�𑽗ʂɓ������邱�Ƃł������B
�@���Ȃ킿�A�����N�i�吳�\��j�ɖ��Z�Z�Z�l�̉��ꌧ�l��n�q�����߁A�J���E�_�k���ɏ]���������B���̌��ʂ͔��ɂ悩�����B
�@�܂��A���ꌧ�����m�Q���ւ̈ڏZ�҂̂��߁A�ߔe�`�T�C�p���Ԃɒ��q�̉q�D��z�u�����v�i�w���ꌧ�j7�@�ږ��x�j�Ƃ����B
�@�����̔_�ƈږ��̓n�q��́A�T�C�p�����E�e�j�A���������S�ł������B
13.2 ���ꋙ���ɂ��J�c�I����
�@�����A�u�����Ƃ͏��a��N�i���N�j������p���I�y�уg���b�N�𒆐S�ɑn�n����A���l�������߂Ƃ��ėe�Ղɏ�������邱�ƂƁA��r�I�����{�Ŏ��Ƃ��n�ߓ��邽�߁A���̌�e�n�Ɋ�Ƃ�����悤�ɂȂ�A���ɌQ���ɂ����鐅�Y�Ƃ̑�\�I�n�ʂɂ��܂łɔ��W����ɂ��������B�i�����j
�@��m�����ɂ����銏�����Ƃ̐��́A�吳�\��N�i�����j�̈ꌏ�ɑ��ď��a��N�i�j�ɂ͈�A����N�i�O�l�j�ɂ͔��l���A���\��N�i�O���j�ɂ͈�܌܌����Z����قǂ̑����ɒB�����v�i�w�ϔC�����̓�m�Q���x�j�Ƃ�������A����͔|�̔_�ƒ��S�̃T�C�p���E�e�j�A���ɂ������A�J�c�I���ƒ��S�̃p���I�E�g���b�N�Ƃ����}���ɂȂ�B
�@�����Ƃ��A���̐}���́A��m���������O�O�N�ɐ��Y�����Ɨ������ē싻���Y������Ђ�ݗ����A�u���ꌧ���ǂɉ��ꋙ�v�O�S�]�����W�ٗb���A���^���D�\���ǂ����ꈽ�͓��{�{�y����Q���ɒ��q�����߂Ĉȗ��N�X�D���т����߂��v�i�w�n�Õ~���j�@�����ҁx�j�Ƃ��邩��A�K�����������ɑ������킯�ł͂Ȃ��B
�@���l��N�ɂ������m�Q���̉��ꌧ�l���Y�ƎҐ��́A���{�l���Y�ƎҐ��̋���߈��|�I�ł��邪�A���̊e�x���ʐ����́A�g���b�N��㔪��l�A�p���I��Z����l�A�T�C�p����Z�Z��l�łقڝh�R���i���̑��̎O�x���v����Z�l�j�A���̏��L���D�i�o�^�D�j�̓g���b�N�O�ܐǁA�p���I�O�O�ǁA�T�C�p���ǁA���̑��̎O�x���v��O�ǁA�Ƃ��낪���g���z�ɂ���ƁA�p���I�Z���~�]�A�g���b�N�܁Z���~�]�A�T�C�p���O�㖜�~�]�A���̑��̎O�x���v��Z���~�]�ƁA�f�R�p���I�ɏW�����Ă���B
�@����̓J�c�I���ƂɂƂǂ܂炸�A�p���I���A���t���C�̔����L�̎拙�Ƃ̊�n�ƂȂ������ƂȂǂɂ����̂ƍl���Ă悢�B
�@�p���I����m�Q�����Ƃ̍����v�̒��S�������̂ł���B
�@�n�Õ~�����m�Q���ɏo�҂��ɍs�����l�����̏،��L�^����A�܂��g���b�N���ɃJ�c�I���Ƃ̏o�҂��ɍs������R�C�Y�i�I�펞�O�܍j�̘b���Љ�悤�B
�@�������A���a���N�ɂȂ�ƕs���������A���̊z������ɑ傫���Ȃ����B
�@���̂܂܂ł͐������ꂵ���Ȃ����ł���������A�������̑g���ł͌����ۂ蕥���đg�����Ɠ�m�ɏo�҂��ɍs�����ƂɂȂ����B���O��N�i���a�Z�j�A������Z�̎��̂��Ƃł���B�i�����j
�@�g���̓����̔�p�͓ߔe�̃}���\�E�Ƃ������ߖ≮����肽�B
�@��m�Ő����������߂͑S�ă}���\�E�Ɉϑ�����Ƃ����̂��؋��̏����ł������B
�@�������́A�g���b�N���̓~���ɒ����Ƃ����ɑD��H�̈����ԂƂ����l�ɗ���őD���Ă�������B
�@�D����������Ƌ@�B�����t���đ������Ƃ��J�n�����B
�@�����͓n�Õ~�̏o�g�҂����ŏo�����Ă������A���N���߂��������玟��ɑ��̒����̏o�g�҂��������̑g���ɉ������ė���悤�ɂȂ����B
�@�ł����������͖̂{�����o�g�ł������B
�@���ꂩ���A�O�N�͑務�������A��N�Ԃŏ\�����~���ׂ������Ƃ�����B
�@�����A�g���b�N���ɂ͓n�Õ~�̏o�g�҂����������B
�@���t�̂Ȃ��ɂ͓n�Õ~�ƃg���b�N���s�����藈���肷��҂��������A������������������Ȏq���Ăъ�҂������B
�@�����g���b�N�ɒ����ē�N�ڂɍȎq���Ăъ��B
�@���̂܂ܑ務���������������肷�邾�낤�Ǝv���Ă������A���O�l�N�i���a��j�ɂȂ�ƕs���������A�ׂ��������ȉ��ɂȂ����B
�@�����Ă�ނ��g�������U���āA�������͓싻���Y�̑D�œ������ƂɂȂ����B
�@��Ђ��D����āA�z���͉�Ђ��Z�A���������l�Ƃ��������ł������B
�@�������A���͌��Lj�N�Ԃœ싻���Y��ސE�����B |
13.3 �A���K�E���̉���J���҂̃X�g
�@�A���K�E�����̗Ӎz�̌@�́A��せ��N�Ƀh�C�c��m�Ӎz��Ђ��̍z���͂��߂��̂��A�����N�ɓ��{���{���������ē�m���̊NJ��Ɉڂ��Ċ��c���ƂƂ��A���O�Z�N�ɍ����Ђ̓�m��B��������i���j��ݗ����Ă��̌o�c�Ɉڂ����B
�@�����Ђł������ɃA���K�E���Ӎz�ʼn��ꌧ�o�g�J���҂̃X�g���C�L���w�������I���r�v�i�I�펞�O�Z�j��������b�ł���B
�@�����A�p���I�̃A���K�E�����ɓ�m��B��ЂƂ����̂������ėӍz���̌@���Ă������A�����ɉ���o�g�̍z�v����܁Z�Z�������Ă����B
�@���O�Z�N�i���a�\��j�Ɏ��́A�i���{�����m�o�R�Ń��i�h�ݏZ�̓��{�l�Ɂj���A���邽�߂ɏ������Ă������m����J�����߂ɂ����֍s�����B
�@�m��������Ă��邤���ɁA���̓m��Ȍo�c�ƍz�v��݂̂��߂ȕ�炵�����Ƃ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���悤�ɂȂ����B
�@�����̍z�v�̓����́A��~��Z�K�`��~�l�Z�K���炢�ł������B
�@���ꂾ���ł͂ƂĂ������ł��Ȃ�����ƁA�z�v�������W�܂��ĉ�ЂɌ����Ă��A�g���ɘr�����ň���ɚ��������Ȃ��l�q�ł������B
�@�܂��A����o�g�̍z�v�͖��O���Ă��ɁA���Ƃ��u�I�̈�ԁv�Ƃ��u�I�̓�ԁv�Ƃ����ӂ��ɔԍ��ŌĂ�Ă����B
�@�����͐����u���Ă��邭���ɁA�Ă��l�オ�肵���Ƃ���������Ȃ����ȂǂƂ����ĐH���ނ�グ�Ă����B
�@���͓�������ŘJ���^�������Ă��Ă�������A���̍z�v�����̖����ꏏ�ɉ������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƌ��S�����B
�@���傤�ǂ��̎��A���̉�Ђ���p���I�ɍz�v�̕�W�ɂ����̂ŁA���͘a�c�Ƃ����U���ł���ɉ��債�A�J���Ǘ��̔ǒ��Ƃ��č̗p���ꂽ�B
�@�Ɛg�̍z�v�͔я�Ő������Ă����̂ŁA�܂����F��⌧�l��Ȃǂ�P�ʂɑg�D�����B
�@�Ζ��N���̒����z�v�͂قƂ�ljƑ������ŁA�я�ɂ���킯�ł͂Ȃ������̂őg���ɓ��낤�Ƃ��Ȃ������B
�@�펞���Ƃ�������������ł���������A���R�Ƒg���𖼏�邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
�@�r�����ꖇ�����炸�A�؋����c���Ȃ��悤�ɗp�S�����B
�@�܂��A�����̑��c�ɂȂ�ł��낤���Ƃ�\�z���āA��Z�Z�܂̕Ă�я�Ɋm�ۂ��Ă������B
�@�����ď������[�ƂƂ̂����Ƃ���ŃX�g���C�L�����s�����B�i�����j
�@�X�g�ɓ˓����Ă���Z�������߂���ƁA��Б����ł肾�����B�z�v�����́A�����狺������Ă��X�g���������Ƃ͂��Ȃ������B
�@�d�������Ă���Ɖ�Б����痊�ݍ��܂��ƁA�ꉞ����ɍs���ɂ͍s�������X�R�b�v��˂����ĂďI���T�{�^�[�W�������B
�@���Ƃ��o���Ă��A�D�ɐςݍ��ނ��߂̃x���g�R���x�A�Ɉ�l�ň���ɃX�R�b�v��t���̍z���̂��邾���ł������B
�@��l���Ԃ�����Ώ\���ςݍ��ނ��Ƃ��ł������A����Ȓ��q�ł����������Z���������Ă��ςݍ��݂͊������Ȃ������B
�@�����ʼn�Б��̓X�g���������߂Ƀ��[�_�[�����悤�Ɗ�Ă��B
�@������A�����A���Ɖ�Ђ���ٓ������炢�̑傫���̕�݂��͂����Ă����J���Ă݂�Ƃ���͎D���ł������B
�@���͕��������Ďd�����Ȃ������̂ŁA���̋��������ĉ�Ђɍs���A
�@�u�B�v�ɂ͌܁Z�K�̋����o���Ȃ��̂ɁA����ȑ���Ŕ����H�������Ƃ͉����Ƃ��v�Ɠ{�荞�B
�@�����ĎВ��̑O�ɂ��̋��𓊂������B
�@�я�ɋA���Ă��炭����ƁA�����܂ތܖ��̃��[�_�[�ɉ�Ђ���o�����߂������B
�@�������͈ꏏ�ɂł��������A������A���ɗp��������Ƃ������Ƃň�l�����c���ꂽ�B
�@���̕����̂Ȃ��ɂ͎Q������x�@�������͂��߁A��Ђ̏d���⏄���炪�\�l�A�ܖ��W�܂��Ă����B
�@���͂��炭�������킸�ɖق��Ă������A�ǂ��ɂ����̒������܂炸�A����ɓ{�肪�����Ă����̂ŁA�����Ȃ�e�[�u���̏�ɍ����āu�ς�Ȃ�Ă��Ȃ�D���Ȃ悤�ɂ�����ǂ����v�ƚV�������B
�@��Б��́A�����\�ꂽ��ߕ߂��čS�����Ă��炨���ƍl���Ă����炵�����A�v�f���O��Ă��܂����悤���B
�@���炭����ƁA�u������������A��v�Ƃ����̂ŁA���͗��قɖ߂����B�i�����j
�@�X�g�̌��ʁA�z�v��̓����͈�~�܁Z�K�ɏオ�����B
�@���͉�Ђ���߁A��Б����В����ސw���A�u�ږ��W�v�̉ے��ƌW�������J�Ƃ������ƂɂȂ����B |
13.4 �p���I�����ѓ��̋Q�쐶��
�@�p���I�Œ��p����A�Q�쐶���̒��Ŕs����ނ������V�_�q���i�I�펞�j�́A�p���I�ł̔ߎS�Ȑ푈�̌�������Ă���B���̘b�̂����̕������Љ�悤�B
�@���l�O�N�i���a�\���j�ɂȂ�ƁA���z���ł�������s�ꂪ��P�ɂ���Ĕj�ꂽ�B
�@�V���K�|�[�����玝���Ă������̃u���h�[�U���g�p����O�ɉ�Ă��܂����B
�@�y�������[������̍U�����₦�ԂȂ��J��Ԃ��ꂽ�̂ŁA�������͕����ƈꏏ�ɎR�ɓ������݁A����Ƃ̎v���ŃK�X�p���W�����O���ɂ��ǂ�����B
�@�����ɂ͓��{�R�̒e��ɁE����q�ɂȂǂ����������A��ܐ�l�̕��m�Ƃ���Ƃقۓ����̖��Ԑl�������B
�@���Ԑl�̖��͉���o�g�ł������B���̎莝���̐H���͊Ԃ��Ȃ�������A�Ђǂ��H�Ɠ�������B
�@�������q�̎����H�ׂ������B���{�R�͒�����ɔ�����ȂǂƂ����Ĕz���Ă̗ʂ�����܁��O�����ɐ������Ă����B
�@���ꂾ���ł͂ƂĂ��������Ȃ��̂ŁA���͟F�P���̐V���H�ׂ���A�l�⏬�����Ȃǂ�H�ׂċQ���𗽂����B
�@���̓A�I�_�C�V���E��H�ׂ����Ƃ����邪�A�R�E���������͂ǂ����Ă��H�ׂ邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
�@��P�̍��ԂɁA������҂͑S���^�s�I�J��A���t���邽�߂ɋ��o���ꂽ�B
�@�܂��A�������́A�R�n�ɐH�킹��≖��H�ׂĂ������A������Ȃ��Ȃ�ƊC��������ł��ĐH�����������B
�@���̂悤�ȋQ��̂Ȃ��Ől�X�͑������Ŏ���ł������B�l�Έȉ��̗c���͉h�{�����Ŗw�ǖS���Ȃ����B
�@���тł̔��������N�����������A�������͕ČR���T�����r���ɂ���Ĕs��̎�����m�����B
�@�����ĊԂ��Ȃ����т��o�ĕČR�Ɏ��e���ꂽ�B |
�@�g���b�N���ŃJ�c�I���D�Ɗ��߉��H����o�c����g���ɑ����Ă��������E���i�I�펞�O��j�̏ꍇ�́A�푈���͂��܂�ƃJ�c�I���D�͌R�ɒ��p����ė��a�^���D�Ƃ���Č�Ɍ�������A�₪�Ė{�l�͌��n���W����ĕ��m�ƂȂ�A�g���b�N�ɌĂъĂ������ȂƎO�l�̎q����n�Õ~�ɋA�����߂ɏ悹���D����P�ɂ���Č�������čȎq�l�l�����v�����B
�@���̓������،����Ă���B
�@���g�A�i���͂��j�ł͂قƂ�ǂ̉Ƒ����]���ɂȂ�A����������m��������g���Ă����̂ɒN�������c���Ă��Ȃ��Ƃ����P�[�X�����������B
�@��鑾�Y�����Ƃ̏ꍇ�́A�{�l���g���b�N���ŏ��W����Đ펀�A�Ƒ��͓n�Õ~�i�Ƃ������j�őS�ł������A���g�A�ł͂��̂悤�Ȉ�ƑS�ł̎���͕K���������炵���Ȃ��B |
�@���ꂩ��܁Z�N�A���|���̂����ł͕��a�������ǂ����ߔe�̒��͓�����Ă����B
�@���ăp���I��g���b�N�ɏo�҂��ɍs���Ă�������̃J�c�I���������́A���K�_���J�i�����܂ŏo�����Ă���B
�@�ߔe�̌��ݎs��̑N���X�Ő������ɐ��G�r���A�X�̐l�Ɏs��̓�K�ɂ���ΐ앶�m����s�����̐H���̖��������ƁA�S�[���E�`�����v���[����Ƀr�[����Z��ł��邤���ɁA�ɐ��G�r���h�g�ɂ��Ă����ė��Ă��ꂽ�B
�@�T�[�r�X�Ƃ��ă^�C�̑���܂œY���Ă������B
�@�H���ŃG�r�̓����݂��`�ɂ��Ă���������A�A����ŏ��̘a�H�������ł������B�����̏K���ł��邪�A�s�̂̌Ӟ��Ƃ������ē��h�q�̕��������ĂȂ��̂Őh�����������N�V���~���o�Ȃ����A����̗ǂ����Y�̔��d�R�q�o�[�`�i�V�R�Ӟ��j�����B
�@��Z���O�Z�����A�D�̖���ŁA�ꔪ���ɏo�`�B
�@��ܓ����߁A�_�˓��`�A�k�Јȗ��͂��߂Ă̑�^�q�D�̓��`���Ƃ̂��ƂŁA���h�����ؗ�Ȋ��}�����������Č}���Ă��ꂽ�B
�@�㗤���Ē��؊X�Œ��H���A�܂�������Ƃ���ɂ̂���k�Д�Q�̏��Ղ������܌����̂��A��Z���o�`�A��Z���[���A���������`�ɓ��`���ē�l���Ԃ̑D�����I�����B
top
��������������������������������������������������������������������������������
|
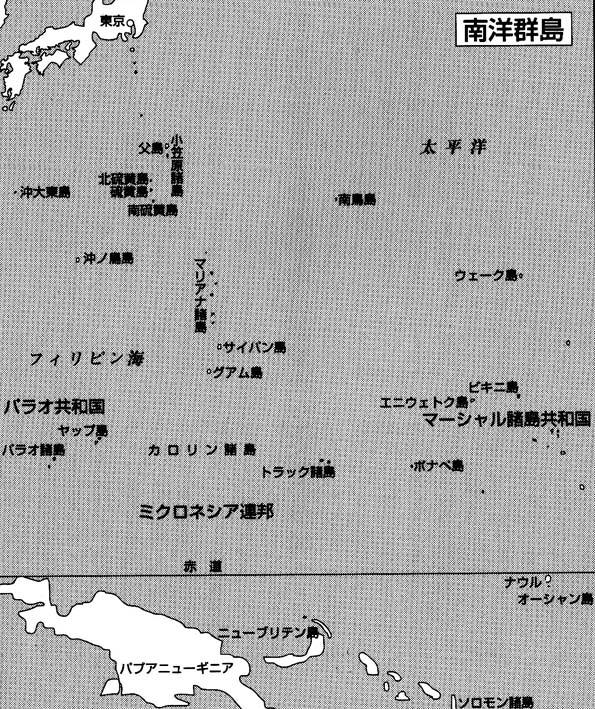
 �j�E�o�[������B
�j�E�o�[������B