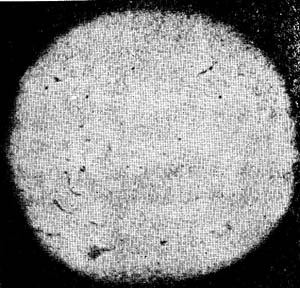|
****************************************
Home 概要 インスリン 太陽 X線とラジウム 薬剤師 微生物 20世紀の奇蹟
Ⅱ 昔からの医師――太陽
1 光りの探求者フィンセン
top
光りのエネルギーは、死の最大の敵であることをニールス・フィンセンが発見したとき、彼はすでに死に跡をつけられていました。
フィンセンは、日光の力で死と闘うことをはじめて組織した人で、また同時に機械医術の創始者でもありました。
彼はデンマークの医師でしたが、デンマーク中の医師たちにあざわらわれながら、コペンハーゲンの電灯研究所で、皮膚結核の最初の治療を行いました。
彼は普通の人とは、だいぶ変っていました。
臨終の床で、ふくみ笑いをしながら、彼は周りの人にいいました。
「自分の体の解剖を見られないのが、残念だよ。」
少年時代フィンセンは「能力も気力も乏しい」という理由で、大学予備校から退学させられました。
フィンセンの父はアイスランド人で、息子に「文明国」で教育をうけさせるため、彼をデンマークの大学予備校に入れたのです。
しかしアイスランド人に流れる昔の海賊の血は、つめこみ教育で人真似のオウムになることでは、我慢できませんでした。
フィンセンがコペンハーゲンの医科大学に学んだのは、一八八〇年代です。
その頃、医科大学では教授も学生も、パスツールとコッホによって始められた細菌の追究に熱中していました。
一人フィンセンだけは、それにひきいれられずに、自分の思うとおりのことをしていました。
ある日フィンセンがぼんやり窓から外を眺めていると、一頭の猫がものうげに屋根に座っているのが見えました。
猫は病気で貧血し、悪寒にふるえているようです。
猫は平らな屋根のうえで、日の当るところに移動しては、うずくまっています。
幾日かたつと猫は、健康を取戻したように思えました。
それでもなお、いままでいたところが日影になると、日当りを求めて移っていきます。
フィンセンの頭には、猫が本能的に知っているこの治療の方法が、こびりついて離れませんでした。 |
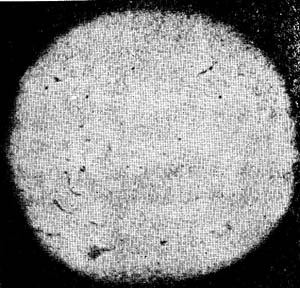
太陽の表面の写真

紅炎を吹き出し、赤々とかがやく太陽
|
大学の勉強をそっちのけにして、彼はデンマーク、ドイツ、イギリスの医学書を読みあさり、このことに関係のある知識を求めました。
ところが医学書に書いてあったのは、日光が炎症をおこさせることや、日焼けさせて害があるという事ばかりでした。
その頃フィンセンは、歩くとすぐに胸がいたくなって、余り遠くまでは歩けないという状態でした。
ある日、スロッツホルメン運河にかかっている橋にもたれ、胸の痛みをやわらげようとしていました。
ふと見ると、アメンボウのような虫が一匹、水流にはこばれていきます。
虫は、橋のかげにはいると、にわかにすべるような動きで流れをさかのぼり、日向(ひなた)にでます。
何度も何度も、虫は同じことをくりかえしています。
フィンセンの目には大きな書物には書かれていない教えが、ここにあるように感じられました。
彼は、自分の考えたいろいろな実験を思いだしていました。
それらはまだ、実際にやってみてはいなかったのですが、まもなくその機会があるだろうと思っていました。
彼は非常に器用な人で、有名な外科医であったキービッツが、彼を有能な外科医に育てあげようと望んだくらいですから、実験をしてみたいと思っていたのです。
一八九二年のことでした。
いまフィンセンは、恋人のイングボルク・バルスレフ嬢と庭にいます。
甘い言葉は、たまに一言、二言いうだけです。
フィンセンは昨日、三時間ほど自分の腕を真夏の日光にさらしたまま座っていて、イングポルク嬢を困らせました。
今日の様子は、昨日とは少し違っています。やがて彼は、恋人であることは忘れてしまったような調子で、彼女にいいました。
「どう、墨(すみ)を塗ったところのほかは、どこもかも日に焼けてしまったでしょう。」 そしてフィンセンは彼女に、この墨が太陽からくる「化学光線」を遮るので、皮膚が日に焼けるのは、その化学光線のためなのだと説明しました。
フィンセンにとっては、そういう説明が求愛の言葉のつもりだったのかもしれません。
今日も三時間、彼は同じ腕を日光にあてて焼かせています。墨はぬぐいとってあります。
次の日に腕を見ると、墨が塗ってあって白かった皮膚だけが、火ぶくれのようになっています。
そのほかの部分はいっそう焼けて、とび色になっていますが、火ぶくれをおこしたりしてはいません。
こんなことは、船員なら誰でも知っていることで、わざわざ実験するほどの必要はなさそうです。
しかしフィンセンは、それによって、日光はいつも悪いのではないこと、また日光で傷付くのは、日焼けしていない皮膚だけであることを確かめました。 |

フィンセン
|
大きな医学書をこえてすすむ土台は、こうして築かれたのです。
一八九三年の春、フィンセンはイングボルク・バルスレフ嬢と結婚して、新婚旅行にでかけました。
その旅先でフィンセンは、若い妻の耳たぶを、二枚のガラス板の間にはさみました。
こうすれば、耳たぶを通る血の量がへるでしょう。
彼はこうして、白くなってしまった耳たぷを通る日光は、血のゆたかに通っているパラ色の耳たぶを通る日光より、写真の乾板に強く感光することを、妻に見せてやりました。
イングボルクは辛抱強い女性で、それほどうるさがりもせず、夫のするままにさせておきました。
コペンハーゲンに戻ってからも、同じような実験が、つづけられました。
実験室もなく実験動物にたくさんお金をかけることもできなかったので、フィンセンが使った実験動物といえば、イングボルク夫人のほかは蛙のオタマジャクシでした。
フィンセンは自宅の一室で、顕微鏡の下に横たえたオタマジャクシの尾に、レンズで日光をあてています。
尾が熱くなりすぎないように、たえず一方の手で、オタマジャクシの尾に水をかけてやっています。
オタマジャクシの尾の毛細血管を、無数の赤血球が流れていきます。
そのうち白血球が現れ数をまし、たちまち何百万という多数になります。
それらは血管の中を流れていかなくなり、血管の壁をアメーバーのように通り抜け、尾の組織の中に入っていきます。
これこそ炎症です。皮膚が日光でやけるという、ごく普通の出来事のもとには、この現象があるのです。
メチュコフは有害な細菌が体に入ったとき、白血球が血管から出ていって細菌を飲込んでしまうことを、明らかにしました。
フィンセンは、メチュコフのその発見を知っています。
だが今、彼が見ているのは、細菌が入ってきていないのに無数の白血球が血管から出ていくという、そのような種類の炎症なのです。
光りが生命を救うということを、オタマジャクシで証明しかけていたその年に、フィンセンはそれとは全く反対に思える意見をのべて、コペンハーゲンのブレダム病院の医長と議論していました。
彼は天然痘の病人には、少しの日光もあててはならないという、まるで空想のような意見を主張していました。
天然痘の水疱(すいほう)ができ始めた病人は、水疱が炎症をおこさぬように、そして感染をまぬがれるようにするために、全く日光にあたらせないでおかねばならない、というのです。
そうしておけば病人は、敗血症で命を失わないですむという主張です。
医長はデンマーク人らしいもの柔らかな態度で、フィンセンの思いつきを笑いました。
だがフィンセンは、ひるみませんでした。
「天然痘にかかった病人には、水疱はどこからでき始めますか? 体中です。
だがどこの水疱が膿(う)んで傷跡になりますか? 手と顔、つまり光りが当るところです。」
フィンセンは熱弁をふるいました。彼は天然痘の病人は、厚い赤いカーテンをおろした部屋にとじこめ、化学光線、すなわち、青や紫の光線および紫外線にあたらせてはならないと、強調しました。
コペンハーゲンでは、フィンセンはうるさい奴ぐらいに思われて、誰も彼の意見をいれてくれませんでしたが、ノルウェーのベルゲンまでは、彼の悪い噂は届きませんでした。
ペルゲンの二人の医師、リンドホルムとスウェンセンは、フィンセンの書いた論文を読み、彼のいうとおりにやってみて、よい結果をえました。
スウェーデンのゴーテンブルク市の医師からも、フィンセンの方法で重症の天然痘の患者を救ったという報告がありました。 フィンセンはにわかに、世界的に有名な学者になりました。
しかしフィンセンの本当の望みは、日光が有益なものであることの証明です。
彼は天然痘の治療についての説が、成功したことは忘れたかのように、学界の隅で暮らしていました。 |

天然痘のあとが顏にのこっている
|
きまった職業はなく、イングポルクとの二人の生活費をどうやってえていたのか、わかりません。
方々の大学に勤めさせてくれるように頼みにいきましたが、無駄でした。
フィンセンは理想家でした。詩人の気質をあわせもつ、博物学者でもありました。
彼は少年の頃、野原にあおむけにねそべっては、草や木が日光にいきいきと輝くのを、印象ふかく眺めていました。
日光の不思議な力――それは彼にとって、忘れられないものでした。
一八九四年のある日、フィンセンは書斎の隅で水をいれた皿の中を、のぞきこんでいました。
三匹の小さなサンショウウオが、なかでじっとしています。彼は小さい凹面鏡を取り出し、窓からはいる光りを集めて、一匹のサンショウウオにあててみました。
数秒間は反応がありません。しかしそのうち、サンショウウオはスイと泳ぎました。
三匹のサンショウウオで、同じことを何度もくりかえして起させることができました。まるで機械仕掛のようです。
フィンセンは光りをあてることによって、動物の体内に何か化学作用がおこり、エネルギーがだされるにちがいないと考えました。 |

サンショウウオ
|
次に彼はオタマジャクシで、青色の光線は赤色の光線よりずっと有効であることを観察し、またサンショウウオの餌にするイトミミズが、死にかけているのを、日光にあてて生きかえらせました。
「光りは炎症もおこさせる。要するに光りは刺激する。これが根本だ。」
「ところが日光という自然の力は、医学ではちっとも注目されていない。」
フィンセンの胸はおどりました。何とかして日光の力を、病人の治療に利用せねばなりません。
技師モゲンセンはもう八年間も、顔面の皮膚結核に悩まされていました。
その症状は尋常性ろうそうといって、炎症がすすんで潰瘍(かいよう)ができ、その跡が醜く残ります。
フィンセンは、日光で皮膚結核を治すことを考えていました。医師たちはまたも、彼を笑いました。
だって炎症に日光が悪い影響を及ぼすといったのは、ほかならぬフィンセンだったのです。
それにフィンセンが、この治療を考えたのは十一月でした。デンマークでは、十一月には強い日光はえられません。
「フィンセンはどうやって、日光をえるつもりか」という陰口も、ささやかれました。
彼は、電灯工場の技師長をしていたウィシフェルド・ハンセンを訪ねて、街灯に使われているのより少し強力な炭素アーク灯をつくってもらいたいと、頼みました。
それは日焼けと同様に、炎症をおこさせることができなければなりません。
フィンセンはすでに、日光をレンズで集めれば、普通の日光の場合にくらべて、十五分の一の時間で細菌を殺すことができることを、明らかにしていました。
皮膚結核では、結核菌が皮膚の表面ちかくにいるから、日光で殺しやすいでしょう。
そして皮膚結核は、不治の病気とされてきたものですから、これを治せばほかの病気も治せることを、人々が信じてくれるでしょう。
これがフィンセンの考えたことです。
ハンセンは医師ではないので、医師仲間でのフィンセンの評判などは知りませんでした。
それで彼は、フィンセンが日光のかわりの光線をえるつもりで頼んだ炭素アーク灯をつくり、また友人のモゲンセンを患者として、フィンセンに紹介しました。
モゲンセンは一八九五年の十一月から翌年の三月まで、毎日二時間ずつジッと動かずに、アーク灯の青い光りを顔にあてられました。
初めの一ヵ月では、何の効果もないようでした。
しかしまもなく、モゲンセンの顔の皮膚に変化が、おこり始めました。
醜いろうそうがとれてきて、その下から健康な皮膚が見えてきました。
他人に顔を見られるのが嫌で全く外出しなかったモゲンセンが、今は昔とかわらぬ顔で、外出できるようになりました。
フィンセンはモゲンセンから、一円のお礼ももらおうとしませんでしたが、モゲンセンの顔が治ったということは、コベンハーゲン中に知れわたって、評判になりました。
ヨルゲンセンおよびハーゲマンという二人の事業家は、フィンセン研究所を創立するお金をだし、大学教授も四人、その指導者としてくわわることになりました。
フィンセンはようやく、学界の尊敬をうける身になりました。
フィンセン研究所には、さっそく多数の病人が、各地から集ってきました。
だが全部の病人を、完全に治すというわけにはいきませんでした。モゲンセンの場合は幸運でした。
光線の強さやそのほか治療の方法に、いろいろの改良がくわえられねばなりませんでした。
そのあいだには、怒って帰ってしまった病人も、大勢おりました。
しかもフィンセン自身、体のなかで病気が進行して、もはや長くは生きられないのではないかと、感じられてきました。
それで人々も、フィンセン研究所の建設をいそぎ、仕事は一階だての仮小屋で始められていました。
フィンセンはしだいに弱り、おなかに水がたまるので、乾燥した食品だけを食べるようにするなど、苦しい生活をしなければならなくなりました。
一九〇二年の冬には、おなかに六回も針をさして、水をとりました。
フィンセンは車椅子に座り、あるいはベッドに寝たままでいろいろの指導をしました。
こうして、フィンセンの太陽灯が、完成されていきました。
一九〇三年度のノーベル医学生理学賞は、フィンセンにあたえられたのですが、そのとき彼の死期は、まぢかにせまっていました。
一九〇四年の秋、彼は妻イングボルクにみとられながら、静かに死んでいきました。
2 太陽の医師ロリエ top
丘の頂上に向かって日光の中を、素裸の少年たちが、ならんで歩いていきました。
昔は青白く、ひ弱だったこの少年たちが、いまは日焼けして、とび色の皮膚をしています。
彼らは日に照らされながら楽しげに笑い、彼らの体に細菌がまた侵入することなどは、とても考えられません。
少年たちは、気管から気管支への入り口を結核菌におかされ、青ざめた顔色でこの丘にやってきました。
そして今、太陽の夢想者オーギュスト・ロリエのこの学校にいるのです。
変り者のスイスの外科医ロリエは、一九〇三年に外科医としてのその名声をさらりと捨ててしまいました。
この太陽の医師が夢みていたのは、医師のメスも血清も新発見の長たらしい名前のついた薬も、昔からの医師である太陽の、安価で簡単な光線に較べれば、とるにたらないものだということでした。
その光線で、結核をおさえることができるだろうというのです。
ロリエは体が大きく、顔はあさ黒く、そして声のやさしい人でした。
彼は三十年以上も辛抱強く、不治の病いを宣告されてこの山腹にやってきた何千人もの病人の体に、太陽エネルギーがおこす不思議な作用を見守ってきました。
その太陽エネルギーは、未知の神秘的な化学作用で、細菌をやっつけてしまうのです。
彼のこの辛抱強さこそ、科学の最大の知能が哀れにも失敗しつづけてきたことを、完成させました。
これは、死と闘う科学の一種の革命でした。
ロリエの太陽崇拝が始ったのは、彼がまだ少年の時代、一八八〇年代のことです。
彼はニューシャテル湖のほとりに住み、父は、いつも本ばかり読んでいる大学の先生でした。
学校には日焼けした農家の子がたくさんいて、ロリエは力では彼らにはかないませんでした。
それで彼は、裸になって日向ぼっこをはじめ、体をインド人のように黒く焼きました。
ロリエのあとばかりついてくる、一人の子がいました。その子の背中には、腫物(はれもの)ができていました。
将来は医者になろうと夢みていたロリエは、腫物を切開して丁寧(ていねい)に包帯をまいてやりました。
ところがその子は、何度包帯してもすぐにむしりとってしまいます。
ある日、ロリエはこのいうことをきかない子を寝かせ、傷口を日光にあてることを、思いつきました。
毎日それをつづけると、傷は完全に良くなりました。 |

黒くたくましくなりたいと思いました
|
ロリエは有名な外科医コッヒエルのもとで学ぶつもりで、勉強していました。
その頃は外科はまだ野暮な技術だった時代で、コッヒエルは甲状腺の部分的な切除をした最初の医師として、外科学の進歩に一つの道しるべをうちたてた人でした。
ロリエのある級友の運命は、コッヒエルのような有能な外科医の手によってさえ、冷たいメスは治療とともに死をもたらすことがあるということを、彼におしえました。
その級友は体操場の階段からおちて尻をうち、腰部結核をおこし安静療法で治そうとしましたが、だめでした。
それで彼は、偉大なコッヒエルにみてもらうために、ペルヌにつれていかれて、腰の関節の切除手術をうけました。
手術は見事に行われ、腰の関節の結核にかかった部分は、のこりなく切り取られました。
少年は青白い顔をして、びっこをひきながら、学校に戻ってきました。
それでも、病気の部分をすっかりとりさってしまったことで、陽気な気分になっていました。
だがまもなく、ひざが結核におかされ、またコッヒエルの手術をうけました。
さて今や、ロリエはコッヒエルの片腕ともいうべき、有能な助手になっていました。
コッヒエルが以前にひざを手術した元の級友が、土色の顔をして、またみてもらいにきました。
ロリエにとって彼の偉大な先生が、青年の肩の関節を切り取っていくのを見ているのは、ひどく苦痛でした。
青年にとってはこれが五度目の手術で、すでに片方の足と一本の指も手術をうけていたのです。
青年は、コッヒエルとロリエに丁寧にお礼をいって、退院していきました。
しかしまもなく、自殺してしまいました。
コッヒエルは、手術のあいだ、細菌を患者にちかづけないようにすることに、すぐれた技術をもっていて、危険の大きい甲状腺の手術でさえ、百人のうち死ぬ者は四人より多くはありませんでした。
ところが骨を結核におかされた場合は、べつです。
ロリエが、コッヒエルの助手をしていたあいだに、手術をうけた者百人について五十人は、命がたすかりませんでした。
コッヒエルのような人さえ、すっかり見通すことはできないのだと、ロリエは思いました。
骨と関節の結核は、腫瘍のように切りとってしまうことはできないものなのです。
あちらを切りとればこちらに現れ、百人のうち五十人は絶望でした。
たまたまロリエの恋人が、重い肺結核にかかりました。
彼女は、安静と新鮮な空気で治療するため、山の南面を一・五キロ余りのぼったレサンにいきました。
そこからは万年雪をいただくダン・デュ・ミディの峰々が見渡されます。
彼らは、山を山羊のようにのぼっていく牛の首につけられた、教会の鐘のようにかんだかい鈴の音を聞きながら、「いつか、よくなって、ロリエと結婚できるかしら。」などと、考えていました。
ロリエは肩にかかっていた名医の未来を投げ下ろし、恋人のあとを追っていきました。
彼はレサンで、田舎医者としてあらたに出発することを、決心しました。
いくつもの丘を登ったり降りたりして、貧しい農家を回って歩くのが、彼の仕事になりました。
しかも、外科医、小児科医から産婆がわりのことまで、何でもやらねばなりませんでした。 |

甲状腺
|
必要な手術は、納屋とつづいた汚い部屋ででも、かまわずにやるつもりでした。
ところがおどろいたことには、ひどくうんだ傷や敗血症の患者には、全く出会いませんでした。
ここでは傷はうまず、細菌の感染もないのです。
「どうしてだろうか?」 彼は考えにふけりながら、恋人のもとにかえっていきます。
ニューシャテル湖のほとりにいたときの元気な日焼けした級友たち、背中を切開し日光にあてて治してやった少年、そして、コッヒエルの手術をうけて自殺した不幸な青年などの記憶が、胸に浮んできます。
シャンペンのようにここちよく刺激する澄んだ空気の中を、日光をあぴて帰宅するロリエの胸に、突然、解決がうかびあがりました。
だがもしもそれが彼一人の思いつきだったら、すぐ実行に移すことをためらったでしょう。
ちょうどそのとき、山の向こうのエンガディンのサマデンにいる老医ベルンハルトから、一つのニュースがもたらされました。
ベルンハルトは自分のにがい経験で、外科手術にいろんな疑問をもつようになっていました。
また彼は、無知な住民の患者たちが、食物を日光にさらし、それが細菌をおいはらうただ一つの方法になっていることを、見てきました。
住民たちは何の健康法もとってはいないのに、みな非常に長生きで、「日光の入る家には、医者はいらぬ」という格言を、いつも口にしています。
そのベルンハルトが、フィンセンの論文を読み、ろうそうに太陽灯をあてて治療したことを、知りました。
ベルンハルトは、ただちに高原のスイスの日光を、大きく口をあけた傷の治療に、利用してみました。
ロリエは、ベルンハルトのそのニュースを聞いたのです。
ロリエの恋人は日光のおかげで良くなり、二人は結婚して幸福を取戻しました。
ところで今や奇妙な行列が、エーグルからレサンのロリエのもとへ、山道をたどってき始めました。
それは小さな老人にも見える、びっこの少年たちの陰気な一隊です。
一歩あるくのも苦しそうで、ギプスをはめられ担架でかつがれている者もあります。
この子供たちは皆、医師からみはなされ、「ロリエのところにでもいってみたら」と、ほんの慰めをあたえられて、おくられてきたのです。
ロリエは、彼らに日光浴をさせました。
まだ、どんな医学書にも書かれていない、新しい方法が試みられました。
ロリエはこの哀れな者たちを、気をつけて静かに静かに、山地の強力な、そして危険な日光の中に押し出していきました。 初めの幾日かは、ドアを開け放して、通風をよくした部屋に寝かせておくだけです。 |

空気がシャンペンのように感じられる高原
|
次には少しもゆれないように、大きな車をつけたベッドに子供を寝かせ、南むきのバルコニーにつれていきます。
しかし、ベッドは日影において、日光は直射させません。それを、何日もつづけます。
おとろえた手足をつつんでいた包帯や、ギプスを静かにとりさり、傷口を空気にさらします。まだ、日にはあてません。
そののち、よく晴れた朝をえらんで、足のさきを五分ずつ三回、日光にあてます。
次の日は、十分ずつ三回にして、また五分間、日光をひざまであてます。
こうしてだんだんに、全身に日光浴をさせるようにします。
ロリエはいつも病人たちのそばに立っていて、何かあぶない徴候が現れはしないかと、用心ぶかく見守っています。
病人たちの全身の皮膚は、日に焼けて黒くなりましたが、水ぷくれや赤いはん点は、全く生じていません。
皮膚がとび色になってくるにしたがって、痛みがうすらいできます。
皮膚がさらに焼けて赤銅色になるころには、顔に微笑が浮んできます。
それは、何週間も何ヵ月もかけて行われます。
しかしそんなことは、何でもありません。
病人たちは、体に力が湧いてくるのを、感じとっているのです。
ロリエは、自然には時間が必要であるのを知っています。
どんなに重い病人でも、ロリエがあきらめるということはありませんでした。
たとえば、R・Rという頭文字で記録されている、一人の少年がありました。
ウィーンの総合病院の医師たちから、完全に見放された者で、その症状をきけば誰でも絶望だと、思わないわけにはいきませんでした。
彼がロリエのところにきたときは五歳で、体重は十キログラムしかありませんでした。
顔は灰色でくちびるには色がなく、ひたいに、静脈が青すじになって現れていました。
体中にぐりぐりができ、手足は痩せ、左の肺はひどくおかされていました。
治療をうけ始めたのは、一九〇八年七月です。
一九〇九年六月には、すでにとび色に日焼けした、丈夫そうな少年になっています。
そして三年後には、日光のなかのロリエ学校の生徒として、雪の上を裸のままスキーですべっています。
さらに二十年たった頃、彼はふしくれだった右手をした植木屋として、働いています。
初めの何年間かは、いろいろの苦しいことがありました。
彼の仕事の最初の発表は、一九〇五年にパリで開かれた、物理療法学会の会議においてでした。
そのときは多くの人たちが、彼に見むきませんでした。
しかし、やがてヨーロッパ中から、医師に見捨てられた者たちが、病気を直して働けるようになるために、ロリエのもとに集ってきました。 |

丈夫な体
|
「病人が歩けるようになり、働くことができるようになっただけでは、充分な科学的証明にはならない。」
といって、ロリエを信用しない医師たちがあります。
彼らを信用させる科学的証明が、えられるでしょうか。
それは、わけのないことです。骨のX線写真を見せればよいのです。
ロリエが日光療法の宣伝をひかえていたのは、実際の仕事が余りに簡単だったからです。
特別の器具も、複雑な装置も、いりません。
注意して、皮膚を日焼けさせるだけのことです。
日光は、皮膚からふかくはいることはできないから、内部の骨の結核を治せるはずはないという者も、大勢いました。
いや、当時の医学の研究者たちは皆、そういう考えでした。
しかし、ロリエのもとには、実際に治った病人たちが、たくさんいるのです。
この事実をみて、それでもなお、疑うことができるでしょうか。
ついにドイツのケルンの、有名な外科医バーデンボイエルが、レサンのロリエを訪ねてくるまでになりました。
何年もの間に、レサンにやってきた一六一名の病人のなかで、死んだのは五名だけでした。
百人のうち九十人ちかくがすっかり治って、仕事につけるようになりました。
肺結核の病人に日光浴をさせることについては、ロリエは不思議なほど慎重でした。
彼はそれを、けっして大規模にやろうとはしませんでした。
アルプスの日光が、強すぎるためなのでしょうか?
それとも、日光のスペクトルのどちらかの端に、肺結核には有害な波長の光線が含まれていると考えたためでしょうか?
そういうことも、ないとはいえません。
だがニューヨークのペリスパークで、病人たち自身が肺結核にたいする日光の治療作用を、ホーレス・ロ・グロッソ博士の目の前で証明しました。
アダム記念病院では数年間、ロリエの方法にしたがって、骨と関節の日光療法が、行われていました。
しかしそれを受持っていたロ・グロッソ博士は、肺結核の病人に日光療法を用いることは、控え目にしていました。
日光療法は、肺結核の病人に発熱させ、出血させるといわれていたからです。
もっとも、ゆっくり日光療法を行った肺結核の病人に、そういうことがおこったという例はみられませんでした。
この病院には、新鮮な空気と、安静とで治療されている肺結核の病人たちがいました。
その中には、充分な手当をうけているのに、病気が悪くなっていく者たちがありました。
その者たちは日影にねかされているとき、隣で日焼けして健康そうになっていく病人たちを、うらやましそうに見ていました。 |

裸でスキーをするほど強く、たくましく……
|
何人かの者が、ロ・グロッソ博士や看護婦たちの目をぬすんで、日光浴をしていました。
家のかげや草むらにかくれて、こっそりやったのです。
胸だけ日光にあてた者もあれば、丸裸で日光浴をした者もあります。
一度に七時間も日光をあぴた者もいました。
発熱した者も出血した者もありました。
しかしそれは少数で、これらの者の多くは、だんだん良くなっていきました。
この結果をみてロ・グロッソ博士は、肺結核の病人にも日光浴をさせることを、始めました。
その方法で大事なのは、胸には日光をあてないことです。
それから発熱で病人が苦しむ昼間ではなく、まだ草の葉に露が光っている早朝に日光をあびさせ、午後遅くなってから、もう一度日光にあたらせることです。
この方法で病気が悪くなった者は、一人もありませんでした。
アメリカのそのほかの土地でも、肺結核の治療に日光療法を利用する医師たちが現れ、ヨーロッパの諸国やそのほかの国でも、同じような療法が用いられるようになりました。
3 機械の日光をおしすすめたストランドベルク
top
フィンセンは、炭素アーク灯で皮膚結核の治療を行いましたが、機械の日光の利用をおしすすめたのは、気性のおだやかなアクセル・ラインと、気性の強いオーブ・ストランドペルクでした。
フィンセンは死の床で妻のイングボルクに、皮膚の病気の場所だけに光線をかけるより、全身にあてた方がもっと強力であろうと語りました。
フィンセンの後継者であったラインは、フィンセンの言い残したことを、大抵はまもっていました。
しかし、全身の光線浴は、なかなか実行しませんでした。
フィンセンの用いた部分浴で、百人のうち四十人は治らなかったことが、ラインをためらわせていたのかもしれません。
レサンでロリエが、全身の日光浴を用い大きな効果をあげているという事実が、コペンハーゲンに伝えられてきました。
そのことがラインを、全身浴にふみきらせる動機になりました。
フィンセン研究所では今、八人の者が裸になって、二台の大きな炭素アーク灯の下に座っています。
目を強い光りから守るために皆、電灯の傘のようなものを、かぶせられています。
時々、体のむきをかえて、方々に光りが当るようにします。
青い光りと人間の影とが、奇妙な形になって壁にうつっています。
初めは三十分、次は一時間、その次は二時間というように、だんだん時間をふやしながら、光線浴は毎日つづけられます。
一ヵ月たつと病人たちは、結核につきもののだるさを感じなくなりました。
それどころか、新しい力が体の中に湧いてくるような気がしました。
フィンセンの局所療法では、こういう効果はうまれませんでした。
その上で顔のろうそうに光線をあてると、それは速やかに消えていきました。
ラインの助手であったエルンストは、さらにめざましい結果をえました。
全身の光線浴で、腰や背柱やそのほかの骨の結核症が、良くなってくるというのです。
ロリエの用いた、山地の日光にもおとらない結果です。
では肺結核ではどうでしょうか?
それにたいしては、ロリエの日光も、一時は無力のように思われました。
ところがストランドベルクは、重態どころか絶望となっている肺結核の患者に、光線の全身浴を試みました。
ラインが炭素アーク灯の治療を始め出したころ、ストランドベルクはただの耳鼻咽喉科の医師でした。
しかし彼は実行力に富んだ医師でした。
彼はラインやそのほかコペンハーゲンの結赧専門医たちに、肺結核の病人に光線の全身浴をさせてくれという頼みをして、困らせ始めました。
一九〇八年に、インターンとして大病院で訓練をうけていたとき、喉の結核患者が全く絶望であることが、ストランドベルクの心を痛ませました。
インターンをおえてからつとめた地方の大病院では、「肺および喉頭(こうとう)結核」という科がありましたが、これは、喉頭、つまり喉の結核が肺結核の末期であるとみられていたためです。
喉の結核の病人たちは、全く絶望の状態におかれていました。 |

裸のまま雪中でスキーをする健康な子たち
|
ストランドペルクは夜遅くまで医学書をひもといて調べましたが、喉の結核の治療に役立つようなことは、何も書いてありませんでした。
耳鼻咽喉科の専門医になったストランドペルクは、ついにフィンセン研究所の所員になりました。
彼の仕事は、口や耳や鼻の結核あるいはほかの病気の場合に手術をして、そのあとフィンセン式炭素アーク灯を、局所的にかけることでした。
肺結核の患者にたいしては、彼はあれこれといろいろの方法を用いてみましたが駄目でした。
その方面の権威者であったスウェーデンのアーノルドセンの書物には、手術によって百人のうち、わずか四人が治るにすぎないと、書いてありました。
ラインついでエルンストが、皮膚結核の患者に光線の全身浴を用いてよい結果をあげたのは、ちょうどその頃でした。
ストランドペルタは肺結核の患者、しかも病気がすすんで喉をひどくおかされている者にまで、全身浴をさせることを、主張しました。
だが肺と喉の結核の場合は、皮膚や鼻の結核とは違っていると、ほかの医師たちは強く主張しました。
「ロリエだって肺結核の場合には、日光浴をひかえさせたではないか。」というのです。
ストランドペルクの主張はいれられず、肺結核の病人に全身浴を試みさせることは、なかなか許されませんでした。
貧しくて、医師の命令するような栄養のとれない喉頭結核の病人が二人、ストランドペルクのところにやってきました。
この二人が、ストランドペルクによって、炭素アーク灯の全身浴をさせられました。
彼らは栄養をとって、病気を良くすることができないので、そのほかのことを何でもやってみるより、仕方がなかったのです。
次には病気のもっとすすんだ者、その次にはさらにひどくなってしまった者が、炭素アーク灯の青黄色の光りのもとに座りました。
それは、一九一四年のことでした。
ストランドベルクのこの実験は、いわば貧乏が仕方なしにやらせたものだと、いえるでしょう。
結果からみれば恩恵でしたが、動機は悲惨なことだったのです。
一九二二年までに、六十一人の病人が、ストランドベルクの手で、光線の全身浴をうけさせられました。
みな、声もでないようになってしまった重症の者でしたが、三十一人はほとんど完全に良くなり、ほかの者たちも多くは、フィンセン研究所まで、自分で歩いてこられるようになりました。
新聞売りをしていた、貧しい一人の主婦は、ストランドペルクでさえ、もうむずかしいと思ったほどの病状でしたが、自分から無理に頼んで、光線浴をさせてもらいました。
ストランドベルクは、初めは彼女の病状に気をつけていましたが、少しずつ良くなるにつれて、忙しさの余り彼女のことを忘れていました。
ある日、旅行から帰ってきたストランドペルタは、町で大声をあげて新聞売りをしている婦人をみつけ、ふと気がつくとそれが、あの重症の患者だった貧しい主婦でした。
「とんでもないことをしている。」とストランドペルクは、彼女のそばにより、すぐ病院にくるようにといいました。
だが彼女を診察してみると、ストランドペルク自身がおどろかずにはいられなかったほど、病気は良くなっていました。
機械の日光は太陽灯と呼ばれ、あるいは、そのほかの名前で呼ばれて、どんどん普及していきました。
改良も、あいついでなされました。
いつでもどこでも、望みの強さの光線がえられることなど、自然の日光より便利な点も、たくさんあります。
いまでは結核との闘いには、ストレプトマイシンのような抗生物質、またパスのような薬があります。
しかし、機械の日光は結核症だけではなく、いろいろな病気の治療に、今日でもなお、大事な役割を演じています。
top
**************************************** |