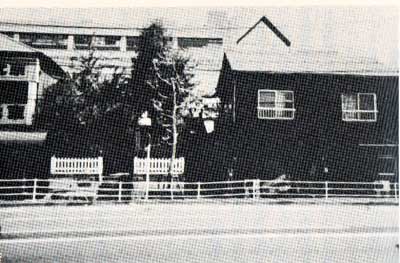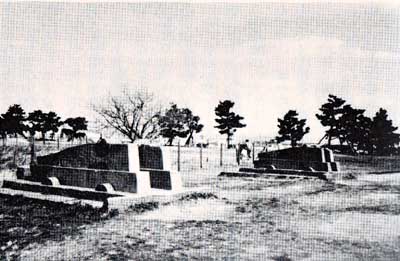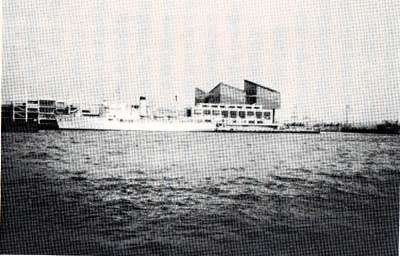|
*************************************
間宮林蔵 松浦武四郎 阿部正弘 長井雅楽 川路聖謨 小笠原長行 小栗忠順 HOME
開国の騎手・小笠原長行(ながみち)
(岩井弘融著 新人物往来社 1992年刊 抜粋)
1 イギリスが 攻めてくる、皆んな逃げろ top
文久三年(一八六三)の五月八日は、日本の歴史が息をつめた瞬間――。
江戸は大騒ぎになっていた。
高縄(現、港区高輪)あたりの大名や旗本屋敷では、奥方や用人が家具や什器をこっそり売り払っている。
町では荷車に家財をつんだり、背中に荷をおぶい子供の手をひいた男や女でごった返している。
北の奥地の村々の方に、列が続々と続く。
”品川”ここは東海道五十三次の親宿で、はじめて日本に来たシーボルトが“村の両側に娼家が並ぶ”と書いたところ。
「求愛者は、自分の履物を、女の名前の木札に、選んだ印として結びつける」と珍しそうに書いていたが、これらの見世も、客は来ないし、まるで火が消えたようであった。
すでに三月頃から、なんとなく落ちつかなかった。
例年なら三月三日の大干潮時には、一立斎広重の描く“品川潮干狩之図”のように、裾をからげて貝籠をもった女達や、蟹を手にしてはしゃぐ干供たちで溢れるのだが、今年はまるで人出がなかった。 |
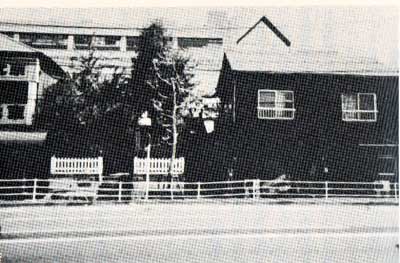
生麦事件現場(現横浜市鶴見区生麦一丁目信号付近)
|
品川の旅篭屋は、北品川、南品川、徒行新宿(かちしんじゅく)あわせて百軒前後、遊女は五百人以上といわれた。
大見世のお女郎は、銀十匁の相場で、はるか西の博多ドンタクの尻取り囃子歌にまで“坊んち可愛やねんねしな、品川女郎衆は十匁……”と唄われている。
実際は、銀五匁、四匁の食売女までいたが、これらを抱える廓(くるわ)内の主だった主人たちが、三月の末に額を集め、女達の万一の避難所を相談した。
そしてまず、御殿山下の神社に近い小泉長屋にある北品川の旅篭屋・岩槻の別宅に女たちを集合させ、それから目黒川沿いに西に大崎村の細道を通って、目黒不動前の内田屋他十軒へ疎開することにした。
文久三聚葵年三月廓内申合
若年寄外国奉行横浜表へまかり越し懸合の向き模様にて、外敵打払相い成るや否やを確め、いよいよ打払の場合は食
売女並に小女共は一旦小泉長屋岩槻別荘へ立ち退き、同所に一同揃いたる上、目黒不動前内田屋外十軒へ立ち退く事。 |
南品川猟師町、大井御林猟師町の漁師たちも将軍家への御看献上の旬のサヨリ等を捕りに、沖に出ることもできなくなってきた。
いよいよ五月になって、不安は最高潮に達した。
海岸近くの住民はパニック状態で、その中には家まで売り払って避難する者さえもいた。
それというのも幕府から江戸湾岸の住民に対し“婦女と老人、子供を避難すべし”とのお布令(ふれ)が出されたからだ。
もっとも宿場の駕龍屋のように、血相変えた役人を急ぎ駕龍に乗せたり、老人、病人を田舎に運んだり、大忙しで稼いでいる者もいた。
このほか「船頭や日雇夫の賃銀も急上昇した」と『武江年表』は記している。
この騒ぎは浦賀や横浜では、既に三月中旬にさらに激しく起こっていた。
三月十六日に神奈川奉行から避難命令が出た。
浦賀ではパニックが発生し、住民は持運びの出来る家財を残らず持って、保土ヶ谷へ移動した。
横浜では家の戸をしめ、家財道具を荷造りし、商人は商品を値段もかまわずに処分した。
住民の四分の三が、家財と共に近郊に退去した。
「十八日には横浜の外国人居留地の雇われ日本人達が、スプーン、フォーク、そして飯の残りまで食卓布に包んで、みんな逃げた」とサトウは書いている(アーネスト・サトウ著『外交官の見た明治維新』)。
なぜ、こんなことが起こったか――いきさつはこうだ。
その年の二月六日、二隻のイギリス軍艦が横浜港に入ってきた。
続いて九日、また一隻の軍艦が入ってきた。
イギリス海軍が、横浜港に集結しはじめたのである。
十九日になって、砲艦ハヴォックに乗った日本係書記官ユースデンが、イギリス代理公使ニール大佐の要求書をもって江戸に入った。
本国からの訓令にもとづき、東禅寺で、幕府の外国奉行、阿部正外(まさとう)に渡した。
その内容は、昨年(文久二年八月)の生麦(なまむぎ)事件に関するもので、
――下手人の処罰
――幕府の十万ポンドの償金
――薩摩に、遺族扶助金、一万ポンドを出させよ
と、いうものであった。
“生麦事件”というのは、東海道の生麦村で、薩摩藩士が島津久光の供先を切ったリチャードソンを斬殺し、二名重傷、香港のボロデール夫人のみ逃げのびた事件である。
しかも、「二十日以内」、の回答の期限付きであった。
その生麦村では、前年、事件の三日後の八月二十四日に、定廻りの三橋敬助か村にやってきて、事件を目撃した松原徳次郎女房と甚五郎女房を桐屋によびよせ、質問をして帰って行った。
もちろん村としては、偶然、事件の現場になったにすぎないのだから、それ以上の関係はない。
今年はこの三月十七日に、戸部役所から生麦村に疎開命令が伝達された。
名主の関口家では、翌十八日に衣類、古金類等を戸塚宿の親戚にあずけ、翌十九目、村内でも東海道筋から離れた岸の知人の家を借り、母たえと祖母とくを、避難させた。(『名主日記が語る幕末』)
昨年、事件が起こった時は、イギリス軍艦は一隻しかいなかった。
キュパー提督が、旗艦ユーリアラス号、砲艦リングダヴ号を率いて来たが、その後、引き揚げていた。
今度は、ちがう。
三月七日までに、ユーリアラス号、パール号、エンカウンター号、ラットラー号、アーガス号、セントーア号、その他を含めて十二隻が横浜に集まってきた。
しかも五月八日になると、それらが一斉に石炭をくべ、蒸気をあげへさきを江戸に向け出していた。
そのうちの二隻はすでに江戸湾近くに進入していた。
のみならず、これに応援する各国軍艦も含め総勢十七隻、商船六隻が横浜から品川沖に待機の姿勢をとった。
その頃京都では、朝廷が上洛した将軍に攘夷をせまり、その結果「攘夷の決行日が五月十日と決まった」のである。
将軍家茂が三月四日に京都に到着し、すったもんだの末に、公武合体派の有力諸侯が退き、勇ましい攘夷論が勝った。
将軍後見の慶喜以下、いやいやながらもそれに従ったのである。事態は、のっぴきならなくなった。
江戸城では御三家の尾張、水戸の両藩主はじめ、江戸留守居役の閣老たちが、頭を抱え込んでしまった。
無謀な攘夷の命令と、現実の戦争の不可能との板挟みである。
赤坂の松平石見守の宅に呼び出され、イギリス公使の公文書を杉田玄端、高畠五郎と徹夜で邦訳したのは、例の福沢諭吉である。
彼によると幕府はいろいろ口実を設けて、二十日、十日と引き延ばしを計ったが、もうどうにもならなくなった。
幕府の評議はなかなか決しない。
ついには、閣老は病気と称して出仕しなくなり「ただ役人達が小田原評定をする」だけになっていた。
この時の状況を田辺太一は、その『幕末外交談』の中で「幕府の狼狽、実にこの時よりも甚だしきぱ無し」と述べている。 それも無理はなかった。
確かにそれは「日本の運命にとっても、重大な危機の瞬間であった」のである。
ところは江戸。瘠せても枯れても当時の幕府は、日本を代表する中央政府である。
幕府が戦端を開くことはすなわち日本の開戦であり、万一の敗北は国の存立をも危うくするものであった。
二の足を踏めば踏むほど騒ぎは大きくなる。
福地源一郎は、市中の混乱ぶりを「さながら火事場のようであった」と伝えている。
人々は縁故を求めて、遠きは十里、近きは二、三里のところに妻子を立ち退かせた。
それもできぬ者は、王子、染井などに疎開の家を借りたりした。
彼自身は家が小石川にあって比較的安全だったにもかかわらず、万一をおもんぱかって、大久保村の農家に逃れる手配をした。
福沢の家では米三十俵と仙台味噌一樽を買って危急に備えた。
ところがいざとなると「俵や味噌樽をかついで走れるものではない」とわかり、騒動の真っ盛りに大笑いしたという。
結局、金を数人の書生に頭割りにして、腰に巻かせ逃げ支度をしたと『福翁自伝』に書いている。
だがここに幸いなことが起こった。福沢は続いてこう述べている。
もう掛け値なしでこれ以上は延ばせぬ、明日か明後日はいよいよ戦争の始る外に道はない」と覚悟したところが――
ここに幸な事がある、と云うのは、其時に唐津の殿様で小笠原壱岐守と云う閣老がある。
それから横浜に浅野備前守と云う奉行がある。
それ等の人が極秘密に云い合わせた事と見えて、五月の初旬十日前後と思いますが、いよいよ今日と云う日に、前日まで大病だと云って寝ていた小笠原壱岐守がヒョイとその朝起きて、日本の軍艦に乗って品川沖を出て行く。
するとイギリスの砲艦が壱岐守の船の尾に尾(つ)いて走るということが起こった。 |
福沢は十日前後と書いているが、これが起こったのは実際は五月八日のことである。
「“砲艦が追尾する”と云うのは、壱岐守は上方に行くと云って品川湾を出発したから、若し本当にその方針を取って本牧(ほんもく)の鼻を廻れば英人は後から砲撃する筈であったと云う。
所が壱岐守は本牧を廻らずに横浜の方へ這入って、自分の独断で即刻に償金を払って仕舞った。
十万ポンドを時の相場にすればメキシコ弗で四十万になる其正金を、英公使セント・ジョン・ニールに渡して先づ一段落を終わりました」と、述べている。
昨日まで“大病だ”といって寝ていた殿様が、ヒョイと朝起きて軍艦に乗っていく、ところがおもしろい。
しかも、泡を食って跡を追っていく英艦を尻目に、横浜港に入って自分の独断でサッサと金を払ってしまった、というところが意表をついて痛快である。いささか、人を食ったところがある。
この唐津の殿様とは、一体どんな人物であったか。
2 唐津の殿様・小笠原長行、廃人から幕閣へ top
唐津は海の見える城下町である。
この町の東側の平地にボツンと立っている姿のよい“鏡山”からは、玄海の水路が一望に見渡せる。
よく晴れた日には、沖の島々はおろか壱岐まで見ることが出来る。
朝には紺に薄緑に、濃淡の水脈がゆったりと息づき、夕べにはさざなみに真紅の落日がくだけて映じる。
まっ白な砂浜と、長く尾をひいてたなびく緑の松原の対照は美しい。そして入江の中央には突出した城山がある。
これをいわば頭部にし、白い砂浜をふちどりに、虹の松原と奥の松原とがあたかも東西に翼を拡げたようであるところから、“舞鶴城”と呼ばれた。
鶴は正に遠い外洋に向かって、大きく飛翔する勢いを示している。
小笠原長行(ながみち)は、文政五年(一八二二)五月十一日この城の中で生まれた。
城といっても藩主一家の住居そのものは、城山の直下の御住居曲輪(くるわ:現、唐津東高校敷地)にあり、長行はその西御住居で育った。
唐津の殿様といったが、長行は実は藩主ではない。
彼は“世子”つまり、藩士の後継者扱いで、その一生のうち一度も藩主そのものになったことはない。
国許の藩士たちは“若殿様”と呼んでいた。
当主の「大殿様」は小笠原長国、しかも「大殿様が若殿様よりも二歳年下」という奇妙な関係である。 |

肥前唐津・舞鶴城
|
彼の生い立ちを述べる前に、唐津藩小笠原家についてふれておこう。
唐津小笠原家は小藩の譜代大名で僅か六万石。
周りは筑前黒田、肥前鍋島、肥後細川といった数十万石の大藩の外様大名に囲まれている。
しかし、天正以来の徳川の譜代ということで、長重(ながしげ)、長尭(ながたか)などが幕府の閣老等の要職に就き、中央政府に直結する“誇り”をもっていた。
譜代の小藩の常として転勤が多い。
文政元年、唐津に来るまでは奥州棚倉(福島県)、その前は遠州掛川(静岡県)である。
掛川城主時代に、例の白浪五人男の盗賊・日本左衛門こと、浜島庄兵衛の事件が起こった。
彼は領内を荒らし回ってなかなかつかまらなかった。
しかも最後は京都まで行って自首したから、藩の面目丸つぶれである。
藩主の長恭は、当時、土丸といって僅かに三歳であったが、気の毒にもその“召捕不行届”ということで、棚倉に左遷されてしまった。
棚倉は生産力が低い上に、近江にも分封(一分石)があり、表面は六万石だが実質四万石で収入は少ない。
ここで二十三万両の借財を抱えながら、今度はさらに遥か九州肥前唐津にお国替えになった。
藩士の妻女、娘たちが唐津に入った時、町人たちは「奥州の大女が来た」と噂した。
昔ここを領していた寺沢家の家臣には、優男の美男子が多かったらしく、“寺沢の雛侍(ひなさむらい)”といって、これに較べたものである。
小笠原の前任は水野家である。水野忠邦は野心家である。
長崎警護の大役をもつ唐津藩では、幕閣につらなりえないので猛運動をし、財政不利を承知で五万石の遠州浜松城に移った。
彼自身は老中に出世して有名な天保の大改革をおこなったのだが、転封に際し、幕府への忠義立てに唐津領のうち一万六千九百二十五石を上納した。
かわって唐津に入った小笠原主殿頭長昌は、思わぬ大減収で大迷惑した。
藩財政は慢性赤字で、藩士の俸禄は極めて零細である。
百石以上は一割もなく、最高級の家老でも五百石取りは二名しかいなかった。
壱岐守の幼名は行若(みちわか)、また長若(ながよし)といった時もある。元服して敬七郎といった。
父親の主殿頭長昌の妾腹の子である。嫡母は前の領主の水野織部正忠光(ただあきら)の次女お連(れん)の方(蓮寿院)であり、生母は松倉の姓であった。
父の長昌が江戸桜田の藩邸で死んだとき行若は僅か二歳であった。
当時の幕府の制度として、幼主であれば長崎巡視の職務執行ができないので転封させることになる。
藩としては棚倉で借金があり、転封にも費用がかかり、しかも僅か数年でまたお国替えでは、金がかかってたまったものではない。
そこで重臣たちは行若の出生を幕府に届ず、周辺には“ろうあの廃人”ということにして、養子政策をとることにした。
ところが、こうして庄内藩の酒井家から長泰(天休公)を養子に迎えたが病弱。
次は、長昌の外甥の長会(ながお)を養子にし、さらに長会の急死で大和郡山藩柳沢家から長和(ながよし)を末期養子に、そして最後には長和の二十歳の急逝で信州松本藩の戸田家から、戸田光庸の次男の長国(信州公または中書公)を迎えた。
松本は信濃守護職小笠原氏の故地で、始祖秀政の墓もここにある。
僅か十七年間に病弱、若死で、四代も続いて藩主に養子を迎えるという、あわただしくも珍しい家柄であった。
目は切れ長だが、やや小柄で、やせっぽちの行若は、藩士の小川正直がお育て役であった。
行若は、なかなかのいたずらでもあった。
あるとき、正直が南蛮渡りの遠眼鏡で沖を眺めていると、目の前が突然、見えなくなった。
「おかしい」と思って外してみると、小さな行若が浜にころがっていた大根を棒の先につきさして、背伸しながら遠眼鏡の先をふさごうとしている。
そして「正直、どうじゃ見えるか」といい、「見えませぬ」と答えると、「ふさいでいるから見えぬのじゃ。こう取れば見える」といった。
彼が十二歳のときに、ちょっとしたチャンスがあった。
酒井家から来ていた長泰が病気になった時、長昌の弟で長行の叔父にあたる長光や家老の百束が、長行をその跡継ぎにしょうと考えた。
そして、長行を連れ江戸に出て老中の水野忠邦に会い、その後押しを願った。
しかし、忠邦は、いい顔をしなかった。
「姻戚をひくのは、非難を招く」といって断わった。
「正室たる自分の妹の生んだ子でない」といった感情もあったのかもしれぬ。
一年ほどして国元に帰ったが、それから再び江戸に上がってくるまで、九年ほど。
朝六時に起きて、一日置きに藩の学者の村瀬文輔や大野肯堂から、四書、小学から易経、詩経、書経、そして史記、漢書などを学んだ。
武術の稽古もひと通りやったし、城内西の門に近い御見馬場で馬にも乗った。
後年乗馬にかけては「諸侯中及ぶ者なし」といわれた素地はここで培われた。とくに騎射は得意であった。
彼は、二十一歳になったとき、唐津から江戸に出た。深川高橋(たかばし)の下屋敷の中にある背山亭に住んだ。
小笠原の上屋敷は虎の御門内、外桜田にあった。約四千八百坪で、本邸が五百余坪、藩士の長屋が四百八十余坪。
東隣りは朽木近江守(福知山藩)、南隣りは北条美濃守(狭山藩)、道を隔てて西の向いは久世大和守(関宿藩)、同じく道を隔てた北のお城寄りは松平大膳(長州藩)のいずれも上屋敷である。
今の日比谷公園の、大音楽堂のあたりである。なお、日比谷公園は、毛利、鍋島、丹羽等の諸侯の屋敷のあったところ。
明治になって練兵場になり、明治三十六年に公園になった。
中屋敷は本郷御弓町(享保の大火で焼失、幡ヶ谷へ移転)、そして深川高橋の下屋敷は、現在の江東区の高橋に近い森下三丁目あたりである。 |

現在の森下3丁目(江東区)
唐津藩の高橋屋敷はここから右手に広がっていた
|
元、酒井左衛門尉の下屋敷で元禄十年(一六九七)、小笠原長重が拝領してその下屋敷となったもので、屋敷地内に木立があったところから、森下町の名が生まれた。
当時は同じ深川の霊岸寺(現、白河一丁目)をはじめ、現在でも白河、三好、平野の一帯に三十数ヶ寺ある寺町から、高橋を渡って北の森下に出ると、西側には少し町屋があって、その先は井上河内守や松平遠江守の邸である。
新大橋は、ほど近い。小笠原屋敷の南側は太田摂津守(掛川藩)の下屋敷である。
太田屋敷と並んで、小名木川沿いの東側には御徒組二軒、そして御三卿・田安殿の屋敷(ここは今でも地元で知っている人もいる)や土浦藩九万五千石の土屋采女正の屋敷が並ぶ。
その先の小名木川と菊川が交差するところには、当時の新高橋、猿江橋、扇橋がかたまっていた。
小笠原邸の北は森下町、三間町であった。
現在でも小名木川は護岸が改修されて舟が通っており、高橋の河原には江東区水上バスの高橋乗船揚がある。
小笠原屋敷はその北の森下三丁目児童造園や東京消防庁森下京の道を挟んだ向いあたりで、今はもうすっかり家、店、ビルが建ち混んでいる。
この高橋屋敷は約一万坪。その中には、藩の茶道方・山田宗偏が作った名庭“合江園”があった。
宗偏は吉良義央の紹介で最初に小笠原に仕官した豊橋にも、臨済寺庭園や茶の流派を今に残している。
彼はここで藤田東湖、羽倉簡堂、塩谷宕蔭(とういん)、安井息軒、藤森大雅らの碩学に師事し、また松田迂仙、朝川善庵らにも親しく学んだ。
彼の文人的才能は、開花した。
“明山公子”とも呼ばれたが、明山というのは故郷の鏡山からとったものであり、鏡は明るく“明”に通じたからである。 彼には政治指向の性格と、隠者風の矛盾した性格がある。それはもっぱらここで養われた。
ここでちょっと一言すれば……この時代の教養というのは、今とは違っている。
まず基礎としては中国の古典の四書五経を学び、『十八史略』、『史記』の中国史を覚える。
学習法としては声を出して読む素読とゼミナール的な会読講義がある。
そして技能としての書道と漢詩作成が上手でなければならぬ。
長行の青年期は、かなりの時間がこうした学習に割かれたことと思われる。
政治論が好きで、北条政子や徳川家康が珍重した『貞親政要』などはよく読んだようである。
彼が親しく接した“松田迂仙”は、菘盧(そうろ)ともいって、高崎藩の儒臣であった。
幼い時から書が得意だったが、母親から「お前は技能だけで世に出ようとするのか」といわれて奮起して、学問の道に入った男である。
昌平学問所の古賀精里(せいり)に師事し、『芸林蒙求(もうきゅう)六巻』の著書もある。 |

若き日の長行(小笠原記念館蔵)
|
藩では寺社奉行や祐筆をやり、後に江戸で藩主大河内氏の世子の侍読として、朝夕、指導を行なった。
世子が封をついだので国元に行き、藩主の藩政改革にたいする意見具申を行なった。
しかし重臣にうとまれ、藩主が死んだ後は閉居して不遇な生活をおくっていた。
それだけに彼は不遇な秀才の長行にとりわけ肩入れし、一日でも顔を見せないと使いを出すほどであった。
迂仙の末女・美和はやさしく柔順な娘であったが、父が亡くなった十七歳になってから、長行の側に侍(はべ)るような関係になった。
嘉永六年(一八五三)六月、ペリーが浦賀に来てにわかに騒がしくなった。
長行は、じっとしておれず、時勢に対する自分の意見を幕府への建白書として、藤田東湖のラインから、当時天下一の人物と考えられていた水戸のご隠居様、徳川斉昭(なりあき)に提出した。
時機を見て、自分の売り込みを計ったところもみられる。なかなか、積極的である。
既に三十歳を越えた彼には、明敏な才を抱きながらも日蔭の道を歩いて来たため、鬱積した覇気がある。
冷や飯食いの部屋住みでは自分を生かすことができない。
時代の急激な推移とともに、藩の外でも内でも、彼を日の当たる大道に出して、その才幹を十分に羽ばたかせたい、とする空気が生まれてきた。
彼と親しく接した塩谷や安井などの儒学者は、方々の大名屋敷に出入りする。そのたび、長行の優秀さを吹聴した。
安井などは「背山亭の公子を廃人というのなら、俺も廃人になりたいものだ」とまで極言した。
「まず藩の世子にして閣老への道を開こう」と考えた西脇勝善、尾崎嘉右衛門などの藩の老臣たちは、近習の村瀬や長谷川を使いながら、徳島の阿波侯・蜂須賀斉裕(なりひろ)に働きかけた。
ややぶっきら棒だが上品な風貌の斉裕は、江戸城中で藩主の小笠原長国に「長行を養子とするよう」口説いた。
ここに困ったことは、先にも述べたように“当の長国が長行よりも年下”ということである。
自分より年上の者を我が子とするのはおかしい。
しかし老臣たち、なかでもお留守居役の役目柄、他藩との付き合いの多い尾崎が苦心して先例をさがしだしてきた。
そして長行を、小笠原茂手記の二男・小笠原敬七郎ということにして幕府に届け出をし、一門に引き直すことに成功した。 安政四年九月、長行が三十六歳のときである。
こんなこともあった。
長行を推す家臣は土佐の儒者・安岡を介して、老候・山内容堂にも働きかけていた。
容堂は、長行の器量を見ようと思ってその邸に招いた。
しかし長行は、何かとかこつけて腰をあげようとしない。再三呼んでも来ない。
業をにやしていたところ……やっと足を運んできた。
容堂は当時三十三歳で大藩の藩主、長行は三十五歳だが小藩の世子にすぎない。
背が高く、あばた顔で、やや早口にしゃべる傾向のある容堂は、自負心が強い。
また“鯨海酔候:げいかいすいこう”とか、”酔狼君:すいろうくん”と呼ばれたような大酒家である。
宴たけなわになったころ、容堂はにわかに
「この幕府危急の時に、貴公のような譜代の者は朝夕を問わず我々藩主を訪ねて、主家救済の途を教わるべきだ。
しかるに貴公は尊大に構えて、使いをやってもこないのはどういうことだ」
とののしり、杯を投げ捨てて奥に入ってしまった。
土佐の家来たちは主君の行動に愕然として長行に謝まり「酔余のことなのでお許し下さい。後日、無礼を謝しますから、どうかお引き取りを」と頼んだ。
長行は泰然として「こんな些細なことで気にすることもない。自分も酔ったし膳部を用意しているのなら、一箸つけさせていただこう」と、ゆっくり食べて帰った。
佐々木味津三はこの一件を評し、容堂が長行の人物を測ったこの四ッ相撲で「終始自若、天下名物の土佐の隠居を鮮やかに、土俵の外に押し出した」(佐々木味津三『小説集・小笠原壱岐守』)といっている。
“長行は策士”と悪評する人もあるが、これは当らない。
彼は、容堂が豪放ではあるが酒癖の悪いことは、十分承知していたであろうし、それに「事を大きくして、相手の家臣を傷つけたくない」と沈着、冷静に思ったからであろう。
「容堂は気性は激しいが、やはり大名育ちで、どこかポッキリ折れるところがある」ということも、また、見抜いていたのだろう。
その通りに翌日、容堂は陳謝の意を表す手紙をおくり、また“見所あり”として、長行の閣老人りに推薦の努力をした。
長行は、藩世子となって半年後の安政五年(一八五八)二月、長国の名代として唐津に帰り“藩政”を執ることになる。
所領の村々では不時の水害・虫害などで収穫の少ない時、農民が減税を願い出る。
これがあると藩の役人は“検見”と称して実地調査に行く。
ところが従来は、この検見に大勢の役人がぞろぞろと行き、村の方ではその接待が大変である。
どうかすると税を減らしてもらっても引き合わぬほど、金がかかることがある。おまけに、賄賂や不正もあった。
長行は久里村の柏崎にたまたま家臣を連れていって、この実情を知った。
ただちに改革を行なった結果、金もかからず賄賂もなくなり、農民たちは大いに喜んだ。
さらに、不正摘発の「目安箱」の設置も行なった。
締めつける方ばかりでなく、従来、藩士を苦しめていた俸禄の二割引きを廃止し、役米・役金・勤金などを支払って働きやすくした。
藩財政窮乏のため内職に覆面をして山で畑仕事をしたり、賃銭とりの米突き内職をやっていた唐津藩の下級武士にとっては「大変有り難い」ことであった。
長行は長崎にも毎年一回出掛けた。
所領を南下して幕領の駒鳴峠、大川野を経て、嬉野そして長崎街道の彼杵(そのぎ)通りを通り、さらに大村から目見峠を越えて長崎へ、片道二十五里十二丁、四日の旅である。
最初は安政五年の二月十九日舞鶴城を発し、二十二日に長崎着。朝、奉行所目付並高木作右衛門を訪問、帰ると長崎在住で藩出入りの者が十数人やって来て、夜には海軍伝習所の勝麟太郎(海舟)が来て、酒肴を出し歓談となった。
翌日は稲佐(いなさ)陣屋を訪れ、次に会所謂役の案内で製鉄所を見学。
それから勝の案内で蒸気船に乗り、さらに伊沢謹吾に伴われてオランダ総督ハルデス・スクーネルを訪問した。
最後に唐館で清国の商人三人と会い、清国の事情を聞き、能書家の消息を訊ね最近の法書を見たりした。
彼は書も能くし、横山健堂によれば徳川三百年の大名中、二人だけしかいない名筆であった。
現在の“唐津くんち”の七番山笠、新町の曳子の法被(はっぴ)“飛龍”の文字は、彼の筆蹟である。
翌安政六年は、十一月に、長崎奉行の岡部長常及び目付の高木と会った。
この年、イギリス・スコットランドの貿易商グラバーが長崎にやってきたのである。
その次は、文久三年(一八六三)の三月であった。約一週間の旅であった。
この長崎の旅で得たものは、大きかった。
家臣達は、赤・黄・紫などの美しい五色のギヤマン、扇子の柄を覗くとふくよかなオランダ美人のヌードが見えるような、珍しい品を買って喜んでいたが、長行にとってはそこで得られる“外国事情”が一番大きな土産であった。
様子を知るほどに「攘夷などということは、全く馬鹿げたこと」としか思われなかった。
長行にとって惜しまれたことは、この“長崎の舞台裏”で、薩長はじめ各藩がどのような新しい動きを開始しようとしていたか、小藩のしかも周りに凡庸な家臣しかいない悲しさで、その情報をつかめなかったことである。
外桜田の藩邸にいた長国は、文久二年(一八六二)三月、暇を得て国元に帰った。
これと交替に今度は長行が江戸に出て来た。六月に、長行は父・長国に代わり将軍に謁見した。
そして七月二十一日に抜擢されて奏者番(そうしゃばん)となった。
奏者番というのは年始、五節句、参勤交代、その他の機会に大名、旗本、公家衆などの将軍への謁見の取り次ぎ役である。
姓名を言上、進物を披露し、将軍より下賜の物を伝達する役目である。
いずれも一万石以上の大名で、言語怜俐(れいり)、英邁(えいまい)の人が二十名から三十名えらばれ、当番・非番・助番の各交代で芙蓉の間に詰める。
そしてこの奏者番の中で優秀な者は閣老にえらばれるという、いわば“閣老候補者”でもある。
また寺社奉行は必ずこの職から兼担した。
幕府は虚礼の府である。奏者番は老中へは会釈するが、若年寄、用人にはしなくてよいとか、進物毎にいちいち出し引きを指図し、進物献上の相手の格式によって披露場が異なるというように、うるさかった。
名前などなかなか覚えられぬので、“御奏者番の手札”といって、氏名・官位等を小さな紙に書き、指の間に挟み、手をついた時に紙を見ながらそれを読み上げた。
時には、掌の内に細字で書き込むこともあった。
派手なのは御能の時で、舞台の真っ先へ出て投者たちが畏まっているところに、進物番が広蓋に唐織等の時服をのせて、うやうやしく奏者番のところに来て、側に置く。
奏者番はその襟をとり、右の膝をおし立て役者の肩に投げる、同時に役者はこれに手を添え肩に打ち掛けて……御礼をした。
子母沢寛は『花と奔流』の中で、この時代の長行のある逸話を書いている。
長行はやや脚気の気味があった。
八月十八日の当番日は、越後高田の榊原政敬(まさたか)の謁見日。長行は、諸役が威儀を正して並ぶ中を、高田侯献上の目録を三宝にのせ、長袴の裾をひいて進んだ。
ところが、突然、途中でくたくたと片膝折って、三宝の上の目録が散乱した。満座の中のことである。不始末というので、老中の間へ呼び出された。
当然、叱られたが、じっと然していた長行が反論しだした。
「拙者は、身体の具合が悪いので、これまで引き龍りの願書を出したが、お聴き届けなかった。病体を強いて勤めれば、かくの如きは当然である。」
そういった上で、懐中から、
奏者番の悪弊十三箇条の奉書を、水野和泉守の前へ差し出した。
「これは、病気はそれほど悪くはなかったが、思い切って火をつけたのである」と子母沢はいう。『花と奔流』は、長行の子、小笠原鉄桜(長生)翁談「昔ばなし」が、素材になっている。
奉書の指摘するところは、たとえば奏者番の勤め方には“何々流”、“某々流”というのまであって、厄介である。
扇の取り方からお辞儀の仕方、箸の上げ下ろしにいたるまで手数が多く、複雑でまるで鋳型に入ったように形式に縛られている。
これでは「人材が萎縮して、思い切ったことや、適材適所の活用ができぬ」というような趣旨である。
当時の柳営の形式主義は奏者番のことばかりでなく、大変なものであったらしい。
たとえば将軍がトイレに行くのにも、数十人のお供がついたという。
「たとえば、将軍の厠(かわや)に赴かるるにも、数十人お供し、一人は水を取り、一人は手水を持ち、一人は手拭を捧ぐというがごとき有様」(『昔夢会筆記』)であったという。
これは文久二年の改革で改まったが、文久三年、老中・諏訪因幡、若年寄・坂井飛騨らが衣服の制を元に戻した結果、「厠のお供が百人にもなりたり」というのだからあきれる。
ともあれ長行の体当たり戦術が成功して、まもなく奏者番は廃止された。
幕府の中枢に入った彼は、将軍後見職・一橋慶喜の補佐でもあった。
慶喜が将事後見職になったのは、この年の六月、京都から公武合体論の島津久光の薩摩藩兵を護衛として、勅使・大原重徳(しげのり)が江戸にやってきて、幕閣人事の改革と攘夷を迫ったからである。
朝廷が幕府の人事に介入する“異例な事態”であったが、幕府は屈し、慶喜の後見職と同時に越前の松平春嶽が政事総裁職に任ぜられた。
朝廷と幕府の力関係は、この時、大きく逆転しだしていた。
さらに続いて十月、土佐藩兵に守られた勅使・三条実美(さねよし)が江戸に到着し、朝廷の攘夷の意志を伝え幕府に実行を迫った。
この間、長行は八月十九日に若年寄、九月十一日に老中格に進み、そして十月一日には外国御用掛に任ぜられていた。
攘夷の問題は幕閣内の混乱のあげく、十二月五日にとうとう、将軍家茂が
「勅諚(ちょくじょう)の趣(おもむき)、畏(かしこ)まり奉(たてまつ)り侯」
と天皇の意思を奉承したとの答書を出した。
そして、せいぜい「策略等の儀は、衆議をつくした上で上洛し、委細申し上げる」と言わざるをえない羽目に追い込まれてしまった。
3 小笠原長行の信念、日本開国 top |

絵入りロンドンニュースにのった小笠原、板倉、水野の3老中
|
長行は攘夷に大反対であった。彼の非凡な先覚性はその積極的な開国論にあった。
たとえば、文久二年(一八六二)の十一月、彼は老中板倉勝静に宛てた書簡で、京都朝廷からもたらされた攘夷論を、真っ向から否定している。
この五十年来、世界万国の形勢が大いに変わり、ことにこの十年は、また一変しました。
“独立鎖国などの攘夷論”では国は保てませぬ。“万国通行の大公平の議論”をもって立国しなければなりません。理由もない攘夷鎖国などはとても出来るものではなく、国家のためになりませぬ。
開港こそ肝要で“開港は天下のおん為”であります。 |
と、開港不可避論をもって直言した。“万国通行の大公平の議論”、“開港は天下のおん為”というのが、その主張である。しかし勇気を欠いた幕閣の容れるところとはならなかった。
その年も押し迫った十二月十六日、長行はライモン丸で品川湾から西に向かい、二十二日に大坂に到着、宿舎の東本願寺に入った。
慶喜は一日遅れで江戸を出発し、陸路、京都に向かった。
長行がすぐに京都に行かず、大坂にとどまったのは、大坂湾の台場の構築を命じられたからである。
彼は早速、順動丸で兵庫の和田ヶ崎の現場を下見してまわった。
そこは勝麟太郎が見込んでいた場所で、福沢諭吉が江戸品川の“海鼠(なまこ)台場”に対して、“七輪みたいな丸い白い台場”と、からかった場所である。
年を越した文久三年の正月十三日、長行は京都に入って慶喜に合流した。
上洛早々、血生ぐさい事件が起った。
二十八日の夜、千草家の雑掌(ざっしょう)・賀川肇が斬殺され、その首級を慶喜の宿舎、東本願寺の大鼓楼の前に置いた。
「小笠原図書頭、大目付岡部駿河守、目付沢勘七郎の三氏にあてた一書」(『京都守護職始末』)がそれに添えられていた。
「攘夷の勅を遵奉せず、開港通商を欲するのはけしからん、攘夷の血祭にする」というのが、その趣旨であった。
三月四日になって、将軍家茂が上洛してきた。
京都には、一橋慶喜、松平慶永(よしなが:春嶽)、島津久光、山内豊信(容堂)、毛判定広、伊達宗成らが集まったが、公武合体派の勢力回復は成らなかった。
朝廷からの攘夷の要求は、ますます厳しい。
三月九日、利口な松平春嶽はいち早くさじを投げて政事総裁職の辞去を出し、二十一日に国元の越前に帰国した。
「攘夷などはとうてい不可能なことである。不可能と知りながら攘夷の命を拝するのは、上をあざむくものである」というのが、その言い分であった。
一橋慶喜はその時のことを、あれは「夜逃げしたんだ。届けっ放しで発ってしまった」と評している。
大佛次郎の『天皇の世紀』では、この時の集まりで慶喜が帰った後に、老中格小笠原図書守が後に残って本多飛騨と話して
「せめて生麦事件の示談だけでもご尽力願いたいと繰り返して説いた。図書守も条約拒絶、攘夷のことは到底実際には行われ得ない、と信じている開明的な考え方の人物であった」
と、述べている。
しかしこの長行の要請も空しく、春嶽はきびすを返して、さっさと自分の穴の中に引っ込んでしまったのである。
三月十九日、幕府は、朝廷から攘夷開始の期日をはっきりすることを要求され、さきに述べたように、しぶしぶ五月十日と答えた。
これに対し長行は、この攘夷政策を“もってのほかの御失策”と怖れずに真っ向から批判した。
そして堂々たる一篇の“開国論”を将軍に呈した。
これは彼のすぐれた識見、視野の広さを示す“正論”であり、当時の熱に浮かされたような攘夷ばやりの渦の中で、冷静で勇気のある一頭地を抜く見解であった。
しかしその前に、当時の“攘夷論”について、ちょっとふれておこう。
今から考えれば無邪気なものだが、白色人種は夷狄(いてき)、つまり「外国人などは畜生に近いもの」(『旧事諮問録』)というのが一般の人々の考え方であった。
攘夷の命令を出した天皇自身が、
外国の事情や何か一向ご承知ない。
昔からあれは禽獣だとか何とかいうようなことが、ただお耳に入っているから、どうもそういう者のはいってくるのは厭だとおっしゃる。
煎じつめた話しが犬猫と一緒にいるのは厭だとおっしゃるのだ。(『昔夢会筆記』) |
という素朴、無知な状態である。
攘夷の大本山教主、水戸の老公徳川斉昭も、
「攘夷(ばんい)はよだれをたらして神国、日本をとろうとしている犬猫」とみなしていた。
「攘夷は一匹も残らず召捕り、打殺し、切殺せ、分捕った船と品物は手丁柄により分けよ」といった勇ましさである。
文久二年、老中・安藤対馬守襲撃の斬奸状に、
「安藤は外国人と骨肉同様に親睦しているが、これでは我国が“外夷同様禽獣の群”とあいなる」
と大橋訥庵(とつあん)は書いていた。まったく無茶苦茶な話である。
文久頃というのは福沢流に言えば、日本国中攘夷の真っ盛りで、外国の話をしたというだけで、刀を技いて追いかけられる、という始末であった。
開国などと言おうものなら、生命がいくつあっても足りはしなかった。
さて元に戻ると長行はその進言書の中で、開国貿易は“富国利民(ふこくりみん)の道”であると断じている。
“交易”の義は“天地生済の理”に基ずくものであり、互いに有無相通じて、生民その処を得さしめる“公済之道”であるという。
もともと我国は開国していたのであって、鎖国は三代将軍の時代からの僅々二百年にすぎず、日本の歴史におけるいわば、“一個の新令”と論じている。
固陋な攘夷論に対しては、無体に打ち払うなどもってのほかの暴挙で「聖賢仁義の道にもとる」という。
まして、これまで友好関係にあったオランダまで断つというのは、理由もなく、筋が通らず、信義に反した“不直”というものではないか。
また、これまでの鎖国の中にもこの裏口を残してあったのは“知彼の御深算”、すなわちそれが世界情勢を知る情報源の役割があったからである。
これを断っては、全くの目隠しになるともいう。自ら目を塞いでいては世界は見えない。
このことは奇しくも、オールコックの観方と暗合している。
彼によるとヨーロッパの諸強国が強力な艦隊をもって、その門戸の開放を求めて、アジア諸国を乱打した。
中国は抵抗し、北京まで占領された。日本はすばやい適応性をもって、賢明に対処した。
それには、
「彼らが、オランダ人との関係を保っていたことにもよるところが、大」
と、彼は、解釈している(オールコック『大君の都』)。
長行は無体な打ち払いは、“滅国の基”となると憂えている。
「恐れながら天朝御一念の御誤り」から攘夷を行えば、世界各国を相手とし到底勝てない戦争をすることになり、その災禍で幾万の民衆が塗炭の苦しみを受けることになる。
従って、たとえ天皇のいわれることであっても、それが民衆を苦しめるようになるものなら、そのあやまりを傍観していてはならない。
「勅命にさえ侯えば、利害得失をも計らせられず、ひたすら御遵奉なさるというのは、真に一国をになう為政者の執るべき道では断じてない」という極めて勇気のある、正当な立論である。
薩摩の大久保一蔵(利通)が、「外人といえば唾を吐くようなコチコチの攘夷家」(市来三郎談)であり、長州の伊藤俊輔(博文)、志道聞多(井上馨)が品川御殿山のイギリス公使館を焼き打ちしていた時に、長行は「開港は天下のおん為」、開国貿易は「富国利民の道」、との確固とした信念をもって主張していた。
大久保や伊藤、井上が、権力を握ると百八十度転向して開国論になり、昔からこうでござった、と口をぬぐっていたのとは、違っていた。
単純な排外主義は、無知のなすところであり、その結果を考えない暴論である。
隣の中国では、アヘン戦争で、軍艦二十五隻、その他の船舶二十三隻、陸兵一万のイギリス軍に敗れ、上海を占領され、香港を失っていた。
さらに長行がこの文を書いた三年前には、約一万七千のイギリス・フランス連合軍が、大沽、天津を経、北京郊外の円明院を焼いた。
このことは、オールコックによって幕府にも知らされてした。
この戦争の結果、中国は、関税、裁判権を奪われ、租界まで造られていた。
もしも日本がこの時、尊王攘夷論者の意見に従って行動していたとしたら、今日の日本はありえなかったであろう。
いつの時代も、戦火に苦しむのは、無辜(むこ)の民衆である。
長行がいつも、“民衆の生活”に重点を置いていたことは、他の人とは少し違った点てある。
彼は文久二年六月、将軍に出した建言書でも、日光御参詣平和宮御下向に際し、「道筋の百姓どもを残らず人足に駆り出し、仕事を止めさせ、田畑を荒れさせるのは、なげかわしい」と述べ、こうしたことをやめるように直言していた。
そして、困窮が極まれば乱を思うほかなく、「四海困窮せば天禄永く終えん(人民がみな困窮すれば、天の与えた王位も永久に失われる)の警語、恐るべき事に侯」とも言った。
佐々木味津三は、この文言が大塩平八郎の檄文と同じであったことを、重視さえした。
こうした考え方は、彼がその生い立ちにおいて、長く生活の苦労をしたせいでもあろうか。
藩政時代には、高齢の老人に身分の別なく衣類を贈ったり、病気の老農婦の家に足を運んで、自分の手で彼女愛用のキセルに火をつけてのませてやる、といったこともやっている。
それは、格別気どったことではなかった。
この点は勝海舟の場合とは少し違っている。勝は確かに西郷隆盛との会見で、江戸を戦火から免れさせた。
しかし、談判がうまくいかないで、
「彼暴挙を以て我に対せんには、我もまた彼が進むに先んじ、市街を焼きて、その進軍を妨げ、一戦焦土を期せずんば有るべからず」(『海舟日記』)
と、市民を無視した焦土作戦を内心では考えていた。
長行にあっては、民衆の生活、生命を救い、国の存続を保つということが、彼の考え方の基本になっていたのである。
大佛次郎は、彼のことを決断、確信があり、勇気のある態度をもった「開明的な紳士」と評している。
彼はまた、一種の合理主義者でもあった。
彼の陣羽織は、表は派手な緋や白で、裏は黒ラシャであった。理由を聞かれて
「進む時は緋か白、しりぞく時は黒にする。
そうでないと、派手な陣羽織をめがけて功名手柄に奮い立つ者がおしよせ、生命も危うくなる。無駄な命は捨てたくないからな」
と、笑って言ったという。
また、征長の際に用いた兜は、三階菱の定紋入りで、立物が二尺ほどもある桐材に黒漆のものであった。
「折れたりする心配はないか」と言われて、
「兜の立物などは所詮、こけおどしにすぎん。
進撃の時とか、陣中でそっくり返っている時には、強そうに偉そうに見えるが、一旦負け戦さとなると自分の刀剣さえ邪魔になるものだ。
ポキリと折って逃げるにしかずだ」
と答えたという。(子母沢寛『幕末奇談』、尾崎秀樹『文学の中の明山侯』)
この兜は、今も唐津の近松寺のに残っている。
肩ひじ張った武士の、臆病者といわれるのがいやな時代に、こんなことを平然と言ってのけた。
彼は多少の変人で飄逸(ひょういつ)でもあったが、根は合理主義者であった。 |

長行の征長兜(小笠原記念館蔵)
|
長行の願いも空しく、京都では三月十一日に、攘夷祈願のために加茂神社行幸が行われた。
イギリスが償金を要求したことは、既に京都にも伝わっていた。
江戸の空気は、京都にはわからない。
そこで「過激の堂上らは償金拒絶を主張し、しばしば鷹司殿下に迫った」(『京都守復職始末』)ということも、起こった。
こうした中で幕府は、三月三日に徳川慶篤(よしあつ:水戸藩主)、伊達慶邦(よしくに:仙台藩主)を京都から関東へ
帰らせた。
そして三月二十三日、長行に対し幕府から、「慶喜より一足先に江戸に帰り、償金と開港拒絶の対英折衝に当たれ」との命が出された。
彼はもちろん「拙者には出来申さぬ」と蹴ったが、なかなか聞き容れられなかった。すなわち
老中小笠原図書頭長行朝臣に命じ、東下して、償金拒絶のことに当たらせた。長行朝臣は、ことが不可能に近いことを論じて辞退したが、後見職はこれを聴き入れず、再三強いられて、やむなく命を拝し、翌日、京都を発った。すでに意のうちでは何か期するところがあったらしく、はたして後日、一大物議を惹き起こすこととなった。
(『京都守復職始末』) |
と山川浩は書いている。その一大物議とは、さてどんなことであったろうか。
4 苦肉の対応、独断でのイギリスへの賞金支払 top
ここで、この本の冒頭に戻らねばならない。
償金支払いで福沢は「小笠原閣老と神奈川奉行・浅野が、極秘裏に打合わせしたらしい」と言っているが、もちろん、政治には複雑な真の流れというものがある。
今度はこの経過の実態について、くわしく見てみよう。
文久三年二月十九日、イギリス代理公使の要末書が来た時に、江戸にいた留守居の閣老は、松平豊前守信義(丹波亀山藩主)と井上河内守正直(浜松藩主)であった。
将軍家茂はこれも福沢の言葉を借りると「危急存亡の大事を眼前に見ながら其を捨てて置いて上洛」の途についていた。
二人は早速、連絡のための急使を出した。
大目付で外国奉行の竹本甲斐守が、一行の跡を追い、掛川で追いついて報告した。
将軍は例によって例のごとく「しばらく回答を引き延ばすように交渉せよ」と言っておいて、西上した。
イギリス側の回答要求は、二十日以内で、三月九日は、その期眼日である。
閣老側は、もう三十日待ってもらうようにニール大佐に頼んだが、ニールは「さばを読んだに違いない」と踏んで「もう十五日間だけ猶予する」と答えた。
その猶予期限が来ない前の三月十四日、閣老はニールにさらに十五日間の日延べを求めた。
そしてまた三月十七日と十八日には、イギリスとフランスの代表者と提督が、外国奉行の竹本甲斐守と竹本隼人正と会談した。
長時間の会談の末「将軍が江戸に帰る予定の四月六日まで、期限を延長する」ということになった。
この頃「イギリスは、東洋において動員出来る全兵力を、横浜に集結するよう命令した」との噂が流れた。
事実、ニール大佐は、上海のブラウン司令官に二千名の兵の派遣を要請したが、まだ中国に太平天国の抵抗などがある状況下で、余力はなく、すげなく拒絶されていた。
三月二十五日に長行は京都を出発した。
桑名に出て、そこから現在は記念碑も建っている“七里の渡し”を渡って、宮(熱田)に上陸し、ほどなく浜名湖という二川宿(今も本陣の遺構が残る)まで来た時、「一万俵の加俸を与えよう」との将軍からの使者が来た。
苦労をひかえての飴玉というわけだが、彼は丁寧に断わった。
幕府からの答えを待っているニールのところへ、三月二十九日に江戸の閣老から、「ある事情が起こって、将軍の江戸帰着が何日とも定められなくなった」との書面が届いた。
確かに、そのとき二条城にいた将軍は、江戸に帰る許可を得られず、「攘夷期日を決めろ」とさんざん痛めつけられ、帰るにも帰れなかったのである。
長行が江戸に帰府したのが、四月六日。
二日後の四月八日に、イギリス、フランスの外交及び海軍の当局と、外国奉行の竹本甲斐守、新任の柴田貞太郎とが再会談をした。
「目立たぬように、賠償金を分割して払うのはどうだろう」と申し出たが、「詳談はまたの機会」ということになった。
時代の針を逆転しているような京都では、四月十一日に、石清水行幸が強行された。
家茂は風邪を理由に随行せず、代理の慶喜は随行したが「急に腹痛が起こった」として、結局「攘夷の節刀」を受けなかった。
他方、江戸城では、四月二十一日に会議が聞かれた。
尾張侯(慶勝)、水戸侯(慶篤)が列座し、閣老以下の議論が行われたが、大勢は償金を支払うことに傾いた。
ところが、満座の中で長行と沢勘七郎のみは、償金支払いに反対論を主張した。
これは長行の作戦で「故意に反対の立場をとって、老中たちの気持ちを反対の方向にもっていかせよう」としたものであった。
尾張侯は途中で機嫌を損ねて「勘七郎、出て行け」とどなる一幕もあった。
結局、償金を渡すことに評決。渡す日の相談もあって、五月三日に支払うことになった。
尾張侯と水戸侯は共に、「償金を支払うとの証書を、三閣老より英国公使に与えよ」と、長行に迫った。
長行も最終的には、江戸の老中たちの決定に従った。
四月二十七日、外国奉行、菊池伊予守隆吉、同並柴田貞」太郎剛中が、老中の命で横浜に向かった。
翌二十八日、両名は「五月三日から十一万ポンドを、七回に分割して、六週間以内に支払う」との意をニールに伝えた。
ところが、大目付からは「攘夷を近日中にはじめる」との書付けがきた。
また、二十一日の決定を知った各藩の留守居の間では「長行の失策である」という声もあがってきた。
長行の膝元の唐津藩の江戸詰めの藩士内にさえ、動揺があった。
江戸家老の多賀長兵衛などは、自分たちに何も明かさぬ公用人の「尾崎嘉右衛門を討って、長行の登城を諌止し、その前で腹を切ろう」と、言い出したこともあった。
田辺太一(やすかず)は、こうした難局の中で「小笠原、阿部、松前の閣老は開国の主義を固持し、外交の外交たる所以を知っていた」と言い、しかしながら「これを輔翼すべぎ幕吏によく天下の大勢に通じた士がなく、その藩臣にさえ鎖攘を説く者があった」と述べている。
そして事情がこのようであったので、「真に卓識があり、真に胆略があり、名を借しまず、謗(そし)りを避けず、身を捨てて国に尽くすの精神がなければ、この盤根錯節(ばんこんさくせつ)の時局を料理出来るものでぱなかった」(『幕末外交談』)と長行らの苦衷を察し、その手腕を称賛した。
一橋慶喜は、四月二十一日、小御所に参内し、翌二十二日、京都を出発し、ゆっくりと江戸に向かった。
“ゆっくり”というのは、これから五月八日の江戸到着まで百二十里を「川止めだ、何んだかんだ――」といいながら、かれこれ十七日も、かかっているからである。
江戸の方では……償金支払い、と決めたので、四月二十六日、目付、宮内(くない)利孟が東下中の慶喜のところに、連絡に行った。
慶喜は近江、土山から鈴鹿峠を越え、桑名から船で尾張に出て、ちょうど熱田に夕刻着いたが、夜分、宮内に会って、「攘夷の命令を受けてきたので、中止せよ、自分が帰ってから話すから」と、言った。
そして、「もしそれにても異存を申すにおいては手討ちにでも」という“ひどい御書面”(『昔夢会筆記』)を、江戸表の老中宛に送り、また、熱田から水戸の家老のコチコチの攘夷家、武田耕雲斎を先発させた。
宮内の報告と慶喜の書面を受けた江戸城では、早速、会議が開かれた。
先にニールに渡した証書では、五月三日が償金交付日であったが、長行は、「ニールに延期を申し出て、慶喜到着後に開港拒絶の談判を開始しよう」と考えた。
そして、この件を、外国奉行をして掛け合わせるように計った。
しかし、閣老も、役人も、賛成せず、外国奉行も誰一人、これをかってでるものがなかった。
松平、井上は連署を断り登城しなくなった。
長行は、「五月七日まで延期する」との書簡をおくることを、決意した。沢勘七郎が水戸家に連絡、水戸侯も同意した。
ちょうどそのころ、熱田を出た武田耕雪斎が江戸に到着、慶喜が「借金を渡すな」と言っていることを水戸侯に伝えた。
水戸侯は、前に賞金を与える通牒を英国公使に発することに同意していたので、夜も寝られなくなった。
もっともこの殿様は水戸でも「よかろう様」といわれたくらい、何でも受けいれる定見の無い人物であった。
五月二日の夜に、長行の家来が早打ちで、「長行が発病したので、三日間延期してほしい」ということと、「一両日中に病気直り次第、長行がこの伴でイギリス代理公使と相談したい」との書簡を神奈川奉行、浅野氏祐(うじすけ)に渡し、三日の朝、帰ってきた。
ところが間もなく、その神奈川奉行が騎馬でお城に駆けつけその旨を伝えたら、ニールが激昂し長行と会わぬはもちろん、「約束の今夕六時までに償金を届けないなら、艦隊行動をとる」と言っていると注進した。
五月四日の朝の評定には、水戸侯はじめ、同藩の老臣、大場一真斎、武田耕雲斎なども加わった。
議論は出るが、なかなか決まらぬ。過半の者は、神奈川奉行の報告を間いて、内心、戦争を危惧している。
そうしているところへ、慶喜の家来が「償金を渡すな、拒絶の交渉をやれ」といった内容の長行宛の書簡をもって、浜松から急行してきた。
長行は、「自分は先に拒絶談判の委任を受けて来たことだし、慶喜公も“払うな”と言われることだから、すぐさま拙者が英艦に出向いて、断わりの談判を仕まつろう」と切り出した。
これに対し武田耕雲斎が、「もし閣老がおいでになって、防禦もできないのに談判破裂になり、敵艦隊が京都に近い大坂湾に入れば大変なことになる。ここは、慶喜様が帰られるまで、待っては如何」と提案した。
同じ日、フランスもイギリスに同調の意向を伝えてきた。
公使・ベレクールが、福沢の言葉を借りると、“大層な手紙”を以て「英国と共々に軍艦を以て品川沖を暴れ回ると、乱暴なことを言うて来た」(『福翁自伝』)のである。
幕府では期日が切迫するに連れて「沿岸防備をどうするか、百万の市民をどこに立ち退かせるか」等の小田原評定に時を移していた。
江戸港の防備となれば、芝浦冲に品川台場(海上砲台)がある。
これは、以前、嘉永六年にアメリカのペリーが浦賀に、軍艦四艘を率いてきた時のものである。
ペリーは、「五ヶ月以内に、またくる」と言って帰ったので、急遽、和船で相模や駿河の安山岩、下総の砂岩、そして対岸の御殿山や、高輪台地の土を据り崩して運び、築いたものである。
嘉永六年の八月に着工し、翌年四月までの僅か九ヶ月で、予定十一ヶ所のうち、五ヶ所を完成した。
海岸と平行して並んで、約百八十メートルの間隔で、品川近くから第一、第五、第二、第六、第三の順にちどり型に配置された、同じような形の、低い小さい島々である。
海面より約五メートルの高さの正方形や五角形の島に、沖に向かって大砲を据え付け、内部は窪地にして陣屋や、横穴式の弾薬庫を設けていた。
砲台から打ち出す砲弾は、実際は百八十メートルくらいしか飛ばなかった。
現在では、僅かに第三台場、第六合場だけが残っており(第二台場が灯台であった時期もあり、また、工事半ばで中止された第四台場は明治初期、緒明(おあき)造船所たったこともある)、第三台場は、有明ふ頭の陸続きのお台場海浜公園になっている。
休日などには、そのリクリエーション水域で、若い人たちの美しい、色とりどりのボードセーリングが見られる。 |
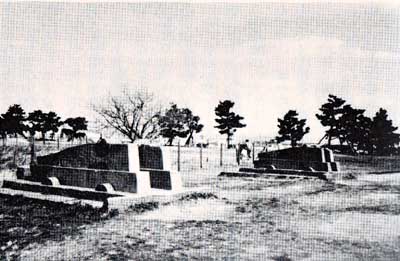
江戸湾防備のため造られた第三台場の砲台跡
|
近くの第六台場だけが、海上にある。これは今の話である。
オールコックは、はじめてこの湾にはいったときの印象を「海岸から二マイルほど沖合いに、花崗岩でがっちり作り、高潮点から数フィートの高さしかない、一連の砲台があった」と述べている。
幕府では、いざとなれば浜御殿から火矢をあげる手ぱずにした。
そして各大名、旗本に「火箭十発相放し侯はば、非常と相心得て、銘々小具足差込、火事具等勝手次第着用、詰場詰場へ出張致さるべく侯(火矢十発撃ち挙げたら全員持ち場に行け)」との布令(ふれ)を出した。
浜御殿というのは、溜池方面から流れる川が、湾に注ぐ出口の両側にある将軍の広壮な屋敷である。
万一城中に火災が起こった場合には、将軍は家族と共に、ここに避難することになっていた。
現在は、浜離官公園になっているところである。
五月五日、横浜ではフランス海兵隊が上陸した。フランス海兵隊はその後数年間、そのまま横浜に駐留した。
五月六日にはイギリス海軍司令官が、各国公使ならびにイギリス居留民に軍事行動に出る意向を示した。
この五日も六日も、処置に窮した閣老たちは、総引っ込みで登城しなかった。幕府の狼狽ぶりは最高に達していた。
五月七日、この日になって水戸侯はじめ、井上以下の老中、若年寄、各奉行達が、みな登城してきた。
尾張侯はすでに五月三日に「償金を与えざるを得ないことを、京都に行って上奏する」といって、江戸を去っていた。
しかし尾張侯は途中、居城の名古屋城にとどまり再び動かなかった。
五月八日朝、長行は急に品川沖から水野癡雲(ちうん)らを率いて幡龍艦に乗船し「京都に行く」と称して西に向かった。 水戸の慶篤は武田耕雲斎に命じ、品川沖まで長行を追わせ引き返しを命じたが、長行は艦を一時止めただけで相手にしなかった。
有馬遠江守が井上河内守の書簡を以て引き留めたが、これも取り合わず横浜に向かった。
城中の役人は互いに「小笠原侯は何の御用で行かれたか」と聞かれてもわからず、閣老たちも「知らぬ」と言っていた。
長行は横浜港に入り、イギリスの艦長に面会を求めたが拒絶された。
そこでフランスの代理公使と司令官に調停を依頼したが、司令官は断わって「イギリスの要求に応ぜよ」といった。
のみならず「横浜の防禦を自分たちの海兵隊に任せよ」と迫った。
慶喜は、この朝八時頃、神奈川宿に着いた。神奈川は東海道筋の宿駅である。
横浜はここからやや離れている。ここですれ違い劇が演じられた。
慶喜は神奈川宿に神奈川奉行の浅野伊賀守氏祐、山口信濃守直毅(なおたけ)を呼び出して経過を聞き、午後四時頃、急拠、馬を飛ばして川崎を乗り切り、午後十時頃江戸に着いた。
入れ代わって長行は横浜港に入り、奉行たちと会い、独断で「償金を支払う」と告げたということになっている。
しかし、翌朝には大量の現金が運びこまれたのであり、その準備が僅か数時間で出来るものではなく、“かなり前から打合わせがあり、用意されていた”と見るのが、至当だろう。
五月九日午前一時、長行はニール大佐に通知書をおくり「償金を支払うので、受領の時刻を知らせてほしい」といった。
“即日”という相手の要求で、同日の朝早くからイギリス公使館へ、荷馬車二十二、三台で各二千ドル入りの箱を運んだ。 この時の状況はつぶさにサトウが書いている。
総額が十一万ポンド(東禅寺事件償金一万ポンドを含む)で、メキシコドル銀貨四十四万ドルに当たり、当時の邦貨で二十六万九千六十六両二分二朱余であった。
あらかじめ江戸の御金蔵から日本橋本町の町役所、ここから両替商、三井組の手によって、神奈川運上所(税関、現神奈川県庁角)に運ばれていた銀貨を、本町通りを通って、海岸通り二十番地の公使館に運んだのである。
長行のこの処置については、当然のことながら攘夷派はもとより幕府の内からさえも、激しい非難が浴びせられた。
京都では、死罪にすべし、との声が上がった。しかし、こんなことは、彼の信念からすれば、覚悟の上のことである。
そうでなくては、困難を乗り切れるものではない。
当時、京都にいた老中首座・板倉勝静の命を受け、秘かに探索に従事していた川田剛は、その『探索書』のなかでこの長行の心境について、
| 専断の罪はご自分にて引受けなされ、万一お申し開き相立たず候時は、一命お捨て成され候お覚悟と察し奉り候 |
と切腹覚悟の行動であったと書き送っている。それは、まことに適切な観察であった。
慶喜のこの間の行動に関して疑問をもつ向きは、彼がことさらに旅行に日を費やした点を責める。
その身、重大の責任を負い国家存亡の機を決すべき時に「旅行に日を費やし、このような大事を閣老以下の役人に任せて処分させようとし、この困難をなるべく避けようとした」と非難した。
そして、償金交付が終わったのを見て「皆が自分の攘夷の命を聞かぬので任にたえず」と辞表を出すという攘夷回避の名演技で、責任逃れをしたというのである。
川田は、慶喜・長行の“事前合意説”を取っている。
償金支払いに関しては、「閣老方も内々お申し合わせの事に相違ない。外見はともかく、慶喜公も着府以前にこのように取りはからったに違いない」と推測する。
何故かといえばその後本来ならおとがめがあるはずなのに一向にそれがなく、小笠原侯もこれまで通り登城している。
「詰(つ)まり侯処、一橋公も御同意なされ候筋に御座侯」と、言っている。
子母沢寛は、長行が
「慶喜さんと相談し、こうなったら払うより法はないが、後でその責任をやかましくいうに相違ない。
その時は万事お任せなさい」
と言ったんだろうとしている。(『花と奔流』)
これは、おそらく真相に近いと思われる。
さて、そうこうしているうちに、長行は突如、意表を衝いて、幕閣や朝廷を愕然とさせるような行動に出たのである。
5 幕府兵力を率い上方へ top
長行は自分の一身に責任を引き受けさっさと償金を払ったら、何思ったか大坂に向かって動き出した。
しかも、大勢の兵を率き連れてである。
彼に従ったのは、外国奉行・井上信濃守清直、目付・向山栄五郎一履、同・土屋民部正直、元勘定奉行・水野忠徳(癡雲)をはじめ、四百以上の洋式の鞍やピストルを携行した騎兵奉行及び騎兵方約百五十人、歩兵奉行並びに歩兵方約百人、歩兵千二百人、外国御用出役約百五十人の総計、約千六百人である。
これらを幕府の軍艦・幡龍、朝陽、鯉魚門(ライモン丸)及び借り入れた英国汽船エルギン号とラージャー号の二隻に乗船させ、五月二十六日、横浜を出港した。
翌、二十七日に紀州の由良港に到着。ここで二隻の英船に乗ってきた兵員を、大坂から迎えにきた幕艦の順勤および鯉魚門、朝陽に、二日間かかって移乗させた。
そして長行以下の有司の乗った幡龍丸を先導とし、二十九日には兵庫沖、さらに天保山沖に至り、遥かに高灯龍(たかどうろう)を望んでいたが、六月一日午後四時前に大坂に上陸した。
そして僅か一休みしてから徹夜で歩き、朝、枚方に到着した。
この時、京都から驚いた閣老たちの命を受けた若年寄・稲葉兵部正巳(館山藩主)が馬で駆けつけ、入京の差し止めを伝えた。
六月二日、長行はかまわずに橋本まで北上すると、今度は使番の松平甲太郎が朝廷の現況を伝え「しばらくそこに止まるように」と説(さと)した。
しかし橋本では泊まれもしないので、長行は諸部隊を一里北の淀まで進め、ここで兵を商家、農家に分宿させた。
六月四日には老中の水野和泉守忠精(ただきよ:山形藩主)が尾張の家老・成瀬隼人正(はやとのしょう)、京部守護職の家臣、会津藩の小野権之丞(後年、函館戦争の際、高松凌雲の病院の事務長役をし苦難を賞めた)、秋月胤永(かずひさ)らを連れて淀に来て、勅命、台命による入京禁止を説いた。
彼らが長行にその来意を問うたのに対し
「そのことなれば、親しく将軍家に言上する、その後にたとえ死を賜うとも、敢えて辞さない。しかし、それまでは申し上げられぬ」
と、口を閉ざした。
『七年史』では、その「決心の精神、顔色を動かしけり」と書いている。
次の五日は使番の能勢金之丞が将軍の親筆を持ってきたので、長行はもはやどうすることも、できなくなった。 |

淀城の石垣(京都・淀競馬場の近くにある)
|
翌六日には、板倉周防守勝静(かつきよ:備中松山藩主、現高梁市)が御三家の家臣、永野彦三郎(尾張)、伊達五郎(紀州)、原市之進(水戸)と共にやってきて、長行の慰撫、説得に勤めた。
六月七日になって長らく京都に足止めをくっていた将軍、家茂が、いよいよ江戸に帰ることになった。
そして九日に京都、二条誠を出発し、大坂に向かうと布告した。
これは将軍がいると、長行の部隊が入京してきて、危険と感じたからでもあった。
長行の挙は、将軍を解放する役割は果したわけである。
翌九日、家茂が大坂誠に入った。
次の十日朝、ただちに朝命をもって、長行は官位を停止され、身柄を大坂城代に預け置きにされた。
「朝命により、重立った者は切腹を命じられるだろう」
という噂はすぐに広がったので、彼が死を覚悟したことはいうまでもない。
将軍は六月十三日、大坂から長行らの乗ってきた船に乗り、六隻の船に護衛されて海路、江戸に帰った。
長行はほぼ一ヶ月、大坂にとどまっていた。
それから七月十日になって、幕府は「長行を江戸へ差し出せ」との命令を下し、大坂城代はただちに彼を東下させた。
順動艦に乗った長行は十四日に品川着、ただちに桜田の藩邸に入った。
長行は、どうしてこういう行動に出たのだろうか。世にいう小笠原クーデターの目的は何であったのか。
それには、彼自身の言葉を聞くのが一番よい。
将軍からの尋問書に対し、彼が六月十日付で、在京の閣老を経て将軍宛に出した『答弁書』の中でこう言っている。
前略、一橋殿(慶喜)が江戸に到着されて、お目通りを仰せ付けられ、いろいろお話している時に“上京して償金を渡した次第(理由や経過)を申し上げろ”と、たびたび仰せ聞かされました。
これは、私だけでなく、他の役々の者へも仰せ聞かされました。
もっとも一橋殿も上京なさるといっておられましたので、私もその節お付き添いして上京いたすつもりでございました。
その後、一橋殿はご病気ということで、出発もお延ばしになり、しかも御辞職(後見職を)のお願いも出されたとのこと、こういうことであまり遅くなって時機を失してはと思い、早々に出発することにいたしました。
なお、“一橋殿へも、一刻も早く御上京なさるよう、おすすめ申し上げてほしい”と、松平豊前守殿、井上河内守殿、その他の方々にも話し、そして上京のお達しもありましたので、上京をお請けしました。
出発に当たり時間がないので、使者もやってお暇乞いをいたしました。
浅野伊賀守らを乗り組ませるため、金川(神奈川)へ参っておりましたところ、一橋殿より、また、上京の主意のお訊ねがありましたので、くわしく申し上げたところ、ついに御会得になり、「勝手次第に、上京仕り侯よう仰せ聞かされ」ましたので、金川を出船いたしました。
償金の事を申し上げるついでに、攘夷問題についても将軍様に、少しく私の意見を言上するつもりでありましたが、御所(朝廷)に対して、かれこれ建白がましいことをするつもりは、全くございませんでした。 |
つまり「償金交付の始末を説明し、あわせて外交問題についての意見を、将軍様に申し上げるのが、自分の意図であった」との弁明である。
また「なぜ多人数を率き連れたか」との訊ねに対しては
世間に色々の風聞があって、今回率き連れてきた者たちは、かねがね将軍の身の上を案じ、二条城や海岸の御警護の御命令があるのを待っていましたが、お差し留めになっていました。
ところが、このたび私が京都に出るについて、“ぜひ連れていってくれ”と言い、止めても止めきれないので、やむをえず、海陸に分け、海路の方を召し連れました。 |
と答えた。
この時期、慶喜に上京の意志があったかどうかについて『昔夢会筆記』に、藤井甚五郎が質問し、慶喜がこれに答えたところがある。
藤井が「小笠原がまだ横浜におりますうちに、御前が御上京ということに決ったということを聞いておりますが」と訊ねたのに対し、慶喜自身は、「それはない。小笠原の方へは一向関係がない」と答えている。
この点の食い違いについて、大佛次郎は
「上京軍の進発の直前まで、一橋慶喜がこの行に加わるものと、外国人の間である程度知らされていた。
慶喜の乗船する手筈のライモン丸を品川まで回航させながら、慶喜は出帆の間際に、病気となって出発延期」
となったという。そしてこの“慶喜の正体不明の動静”については、“いざとなってから行動に出る決断を失くしたもの”と解している。
さて、長行が西上するにおいて、彼自身「本当にどこまでやるつもりであったか」はわからない。
彼と同行した水野癡雲は、福地源一郎に「小笠原閣老がこの大切なる機会に至りて、押して上京するの断なかりしは残念なり」と言っている。
水野の腹は、この機会における武力による京都の鎖攘論の一洗(いっせん)にあったようである。
田辺太一は、こう推測する。
そもそも、小笠原閣老がこの一挙に及んだのは、この見兵(げんぺい:現役の兵隊)を率いて上京すれば、公卿たちはあわて惑(まど)って、力と頼む浮浪の輩と相謀り、力ずくでこれを拒(ふせ)ごうとするだろう。
これはもとより期するところであるから、わが勁旅(けいりょ:強力な部隊)を駆って直ちにこれを打ち破り、この機会に京師にある鎖攘論の根本を抜き、かくして幕府の誠意を中途で阻格(そかく:さえぎる)するものを除き、朝廷の真意を発揮して、公武の合体をはかろうとするものであったろう。 |
つまり、攘夷派の浪士たちを挑発してこれを武力で抑え、長州派の公卿へ圧力をかけ、朝廷に政策の転換を求めて、鎖国攘夷の放棄、公武合体へ向かわせようとしたと見ている。
そして、当時の状態にあって、死中に生を求めるには、ただこの方策が一つあるだけだったとしている。
長行が、真に武力行使を意図していたかどうかは、前に述べたように、疑問である。
彼が、六月一日に上陸したとき、姉小路公知(きんとも)の暗殺を知り、「大失望、大失望」と思わず洩らして、水野らは、その意が皆目わからなかった、という。
長行と公知は、姻戚の縁があり、大変親しい間柄であって、内外呼応して改革を行おうとする密計が、両人のうちに熟していたことを、田辺は「後になって聞いた」(『幕末外交談』)と、言っている。
出発の時はともかく、この時には、「一種のデモンストレーションを以て威圧を加えれば、最小の目的は達せられる」と考えたのでは、なかろうか。
慶喜は後に、京都の反対勢力の駆逐には兵力不足であった。
すなわち、「その目的、京都を清掃するにありせば、かばかりの兵力にては仕果すべくもあらず」と、言っている。
しかし、当時の御親兵は多くて千二百程度で、また長州藩も藩主が攘夷のため在国し、世子・毛利定広も兵を率いて帰国していた。
従って長行の兵に、守護職の会津藩、所司代の淀藩、それに桑名藩、江戸からの将軍随行兵などを加えれば、形勢を変えるのは、易々たるものであった。
結局は京都にいた幕府首脳の出方が問題であって、東西の老中の意思の不統一が、会津、桑名、淀等のため異議を生み、将軍の命令となって、長行の挙を失敗に導いた。
もっとも失敗といっても「将軍家の手勢の少ないのを危ぶんで守りにきた」というような口実は、前にも述べたように、体のいい軟禁状態の将軍を、救出する効果があったわけである。
また、これがあったればこそ、朝廷からの厳科の要求に対し、幕府は〈差控:さしひかえ〉という軽い処分に終わらせたのであろう。
田辺は長行に同情し、
「一身を両截(りょうせつ)して中外に対し、幕府の犠牲となったのは、もとより覚悟の上ではあったろうが、同情にたえないものがある」(『幕末外交談』)
と、言っている。
外国人には、朝・幕の意見を代弁して鎖国論者ととられ、国内では憎むべき開港論者ととられる。
自己を犠牲にして、一切の重荷を背負ったのである。
攘夷論者にとっては、長行はまさに巨悪であった。当時の攘夷派が作った誹膀の詩に、
出没明山瞑色遥、 前途目落更蕭条、
平岡十里癡雲合、 望新注内第一橋
というのがあるが、明山は長行、平岡は平岡円四郎、癡雲は水野忠徳、第一橋は慶喜である。
翌、元治元年(一八六四)の九月十七日、長行は謹慎を解かれ、諸大夫に命じられた。四十四歳の秋である。
翌日、図書頭(ずしょのかみ)を、壱岐守(いきのかみ)と改めた。
幕府からの一通りの申し立てで、長行の勅勘(ちょっかん:帝のとがめ)が宥免(ゆうめん:許す)されたのは、同年七月の蛤御門(はまぐりごもん)の変のあとで、長州系の攘夷論者が京都にいなかったからであった。
6 公武合体派の長州追い落とし top
江戸で謹慎を命じられていた一年三ヶ月の間には、いろいろなことが起こった。
藩邸に帰って間もなく、文久三年(一八六三)八月十八日には、京都で、会津・薩摩両藩の密議による公武合体系のクーデターが行われた。
長州は突然、堺町門守衛を免ぜられ、過激派の堂上方の“七卿落ち”となった。
翌元治元年六月には、“池田屋騒動”が起こった。まさに新選組活躍の最盛期である。
七月に入ると、長州藩の益田、福原、国司の三家老や、来島又兵衛、久坂玄瑞らに率いられた諸隊が東上し、会、桑、薩の禁門護衛の兵と交戦した。
平成の今でも、京都の御所の蛤御門にはそのときの弾痕が残っているが、ここでの戦闘は最も激しかった。
この禁門の変で長州兵は敗退した。
瀬戸内海の大島あたりでは六月半ば過ぎに、三田尻・富海(とのみ)・上関に集結し、白地に一文字三星の船じるしをつけた長州藩の舟六百余艘が大挙して、鼻繰瀬戸(はなぐりのせと)を東にのぼるのが見られた。
そして七月の末には、今度は遂に大三島の沖を西へ千艘あまりが、櫛の歯をひくように逃げていくのを見たという。
それから間もなく下関海峡を事実上、長州藩によって封鎖されていたイギリス・フランス・オランダ・アメリカの四ヵ国は、連合艦隊十七隻をもって、八月五日、長州砲台の攻撃を行った。
長州藩はこの戦闘で、諸外国との間に大きな差のあることを悟った。それは前年の薩英戦争の経験でもあった。
当時の諸藩の砲台の大砲はオランダ製の前装式滑腔砲が多い。
円形弾で発射速度は五分から七分に一発、しかも射程距離が短いから敵艦にとどかず、水柱をあげるだけである。
ところが相手力は後装砲である。
射撃速度が早く、射程距離は長く、長型弾の貫微力はその比ではなかった。
長州は無条件降服。
分捕られた長州砲は各国の土産物にされ、そのうち二門は今もフランスの軍事博物館の庭に陳列されている。
下関戦争の尻ぬぐいは、またもや、幕府に押付られた。
幕府は九月二十二日、若年寄、酒井忠舛(ただます)をして横浜で四ヶ国使臣と会見させ、『下関事件取決書』の約定をした。
その間に戦った同士の長州藩とイギリスとが接近し、その応援によって幕府を倒す武器購入などを行っていたのだから、おかしなものである。
長崎と言えば、石畳を上がった山手の一角に港を見渡すグラバー邸がある。
古びた木造洋館と洋式庭園が、アメリカ士官ピンカートンとの愛の物語『お蝶夫人』の舞台などとされているが、この邸の主人のトーマス・グラバーこそが、イギリス公使パータスの片腕ともいわれた武器商人であった。
アメリカで南北戦争が一八六五年に終わり、そこでいらなくなった小銃などを安く大量に買い、倒幕軍に売って大儲けしたのである。
慶応元年(一八六五)に薩摩藩が外国から買った軍艦、武器の購入額は三十八万ドルであったが、そのうち二十万ドルがグラバーに支払われている。
美しいオペラの世界とは裏腹の現実的な取引と致富の世界がそこにはあった。
もっとも、後には代金焦げ付きで倒産の憂き目も見ている。
禁門の変に対する長州藩追討の朝議が決定し、禁裏御守衛総督・一橋慶喜を通して幕府に伝えられ、幕府は八月十三日、中国・四国・九州の二十一藩に出兵命令を出した。
唐津では大平に慣れた土民が、にわかの出兵の沙汰で混乱した。とくに、時期が悪い。
長行の在唐の叔父である長光(ながてる)は、謹慎が解けて復帰していた長行に宛てた書簡の中で、持夫・中間等のいわゆる郷夫の件について、
「秋熟農務専一の時節、郷の壮を尽くし侯姿に而者、後日の疲弊甚以御案申上侯」と書いている。
つまり、「秋の農繁期にかんじんの農村の働き手を召集動員しては、後日の疲弊が生じる」と心配している。
また出兵のための財政困難も述べている。
武士同士の戦争に農民が田畑から駆り立てられて行くのは迷惑至極なことで、長光の主張は当然のことであった。
長光は長堯の十三男で、江戸に生まれ、その後、兄長昌と共に文政元年(一八一八)に棚倉から移って来た。
文政十一年には禄高千石で別家し朱門公と呼ばれ、通称では“お住居(すまい)さま”とも言われた。
短期の歴代藩主の長泰・長会・長和・長国に、執政として仕えた藩の実権者である。
江戸藩邸の執政の時、甥の敬七郎(長行)を世に出すために努力したことも、前に述べた通りである。
藩主・長国は十一月十三日、士卒二千四十三人、船大小三十艘を率いて唐津を出馬し、十五日小倉に着き、金田方面に陣した。
その半分以上が、軍夫として動員された百姓、船頭たちであった。
幕軍の総攻撃は十一月十八日の予定であったが、その前に長州は三家老の切腹、四参謀の斬首等の措置により、伏罪した。
本心では兵を動かすことを好まない諸藩は安心した。
十二月に入って撤兵令が出て長国は翌年になって小倉を発し、一月七日に唐津に帰城した。
だが、実はそれから半年とたたないうちに、長行にとっては、一生を左右する重大な事件が、次々と起こった。
それは……。
7 黒船大阪湾に現れ、兵庫・大坂の開港要求 top
二時頃、遠くの方で太鼓の音が聞こえた。やがて間もなく、将軍の親衛隊の前衛が見えてきた。
二人の鼓手が前に進み、その後に歩兵の司令官が乗馬ですぐ続いた。
それから約六百人の一連隊が来た。四列で、エンフィールド銃と銃剣で武装していた。
服装は、日本風と洋風の奇妙な混合であった。
騎馬隊の終わりに、約二十人の豪華に着飾った兵隊が続いたが、彼らはみんな高位の人々であった。
その真ん中に、将軍が乗馬でいた。彼は、この華々しい集団の中心にいる人物の若者である。
その陣羽織は、金の縫い取りがあり、その背中には、大きな紋章がついていた。(『ヤング・ジャパン』) |
これは将軍の長州再征の行列を見た、英人ブラックの記述である。
当日、横浜にいた外国人たちは、ピクニックのような気分で、東海道近くの丘の上で、神奈川通過の行列を見物していた。
慶応元年(一八六五)四月、長州・防州の形勢鎮静せず、激徒再発して「容易ならざる企てあり」ということで、幕府は長州再征令を出した。
そして五月になって将軍親任を布告し、十六日に将軍家茂は江戸城を出発した。
関ヶ原の時の家康の古例にならって、七本骨の金扇、銀三日月の馬標を立てて威風堂々と進んだ。
ブラックが“若者”といった将軍家茂は、このとき二十歳だった。
一方大阪にいた老中は、阿部豊後守正外(まさと:白河藩主)・松前伊豆守崇弘(たかひろ:松前藩主)・松平周防守康直(後に松井康英、棚倉藩、川越藩主)・松平伯耆守宗秀(宮津藩主)である。
阿部は強硬派で一徹の人、松前は一部に嘱望されていたが何といっても僻遠の外様で力がなかった。
松平康直はやや気迫があるが時勢への見識がなく人形扱いされた面があり、松平(本荘)宗秀は温厚一遍の人であった。
こんな状況であったので幕府の諸有司の中から、
「今の閣老では頼りない。小笠原壱岐守を再び老中に補することが目下の急務である。」
という主張がおこってきた。
もっともこの間、長行の再任を計る動きもあった。
前年の十一月、若年寄・秋月左京亮種樹(たねたつ:日向高鍋藩)が、「鎖港交渉に、外国に行かないか」と言ってきた。
一役買わせて“再任させよう“という好意である。
だが「そんなことができるはずはない」と思っている長行は丁寧に断わった。
代って貧乏くじをひいたのが、池田筑後守長発である。
彼を正使とし、副使・河津三郎太郎、監察・河田貧之助(煕:ひろし)で、文久三年十二月にパリに向け出発した一行が、有名な“スフィンクスと三十四人のサムライ”である。
国外に出て初めて事の不可能を知った若い池田は、途中で気が狂ったようになって帰国し、馬を飛ばして江戸城に行き、幕府の処分を受けた。
河律や河田も同様であったが、その後、河津は幕府最後の長崎奉行となり、池田は江戸城開城での勅使迎えの役を演じさせられた。
今回の長行の再任では、既に板倉が罷免前の在職中に熱心に発案していた。
これに対し、慶喜が首を縦に振らなかったようである。
これにつき、『昔夢会筆記』で、江間政発(せいはつ)が、
「ひとり一橋慶喜殿が御承知にならぬとあるが、それは何故だったのか」
と、問うているが、慶喜は忘れてしまったようで答えず、江間が
「御前が御不賛成というのは、今小笠原を出して朝廷との調和を破ることがあってはならぬから、という御趣旨であったろう、と考えます」
と解釈を下している。江間がなおも
「とにかく小笠原という人は役に立つということは、およそ幕府の方の与論」だったと見えますが……」
というのに対して、慶喜は、
「なかなか役に立つ人であった。学問もできるしね。」
と、答えている。
将軍は六月二十二日に入京、参内し、二十四日に大坂城に帰った。
同月二十九日に、小笠原再任の議が出され、かねがね在坂の閣老に頼りなく思っていた松平容保は、これに賛成、老中たちを説得した。こうして、長行の再起用が決った。
七月二十六日に、「御用の筋もこれあり侯につき、早々上京いたさるべく侯。」との、達しが長行にあり、上坂を命じられた。上坂に当たり長行は、藩主長国の長女・満寿姫と婚礼の式を挙げた。
「長行と満寿姫をそのままで結婚させるのはおかしい」というので、長国の一族の息女として輿入れの形を取った。
子母沢寛の『花と奔流』では、長国は長行より二歳下で満寿はその娘なので、長行と彼女は三十歳近くも歳が違う。
「娘を相手にするようでどうにも閉口した」としている。
満寿姫はお侠(きゃん)で、我意が強くてお酒が大好きであった。
利口で目先もきくが、派手好きで相撲取りをひいきにしたり、遊芸の者も何人か知っていたという。
ただしこれは長行の妾のお美和の方の子・長生の話だから、割り引いて考える必要があろう。
彼女は絵を谷文晁の弟子の文賀女に学ぶといった才能もあり、明治になってから雲龍の墨絵を義子の長生と合作して残してもいる。ただ、明治十二年には彼女は離婚している。
長行は八月十六日に江戸を出発し、三十一日に大坂蔵屋敷に着いた。
着くとすぐ九月四日に老中格で再勤することになった。
長州再征については反対の声も多かった。
老中でも、諏訪因幡守忠誠(ただまさ:高島藩主、信濃諏訪)や牧野備前守忠恭(ただゆき:長岡藩主)は長征に反対して罷免され、尾張・福井などの親藩をはじめ、岡山・鳥取・広島・徳島・熊本・福岡なども、みな不賛成であった。
さらに長州問題でも難かしいところに、急に外から難問が降りかってきた。
欧米列国が共同歩調をとって、大坂にいる幕府に、要求を強硬に押付てきたのである。
かねて開港問題のらちのあかないのに、いらだっていたイギリス公使・パータスが、
「大坂へ押しかけ、ひざづめ談判しよう」
という提案に各国は同意した。
こうして、九月十六日、イギリス・オランダ・フランス・アメリカの連合艦隊は、プリンス・ロイヤル号を先頭に一列に続き、兵庫和田岬に入り投錨した。
大坂城には、十七日に兵庫の町役人から、昨日の十二時半頃艦隊が沖にあらわれ、今朝八時半頃そのうち二隻が大坂へ回ったと、通報があった。
まもなく、軍艦二隻が天保出陣にあらわれ、そのうちの一隻、フランスの通報艦キンシャン号が安治川口に入った。
イギリス砲艦・ハウンサー号の方は、蒸気を起こせずに遅れたと、サトウは侮しがっている。
河口は艦載ボートしか入れず、フランス人のカション、イギリス人のシーボルト達は、これに乗って河口の保塁に上陸してきた。
町奉行組支配の役人が来意を訊ねると「奉行に会いたい」と言った。 |
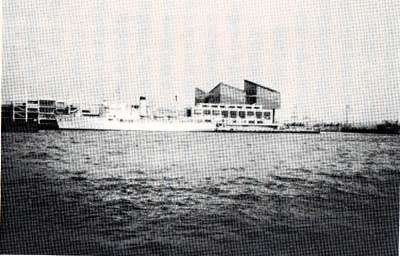
大阪・天保山、築港によって往時のおもかげはない
|
そこで大坂町奉行・松平大隅守信敏、井上主水正義斐(もんどのかみよしあや)と目付・赤松左京範静が出向いて彼らに会った。 彼らは「老中に会ってお話したい」と言い、「阿部老中はいるか、松平周防守は……」と訊ねた。
「二人とも京都だ」と答えると、「それでは小笠原老中に会いたい」と言った。
町奉行は早速城に帰って復命し、長行と山口駿河守が天保山におもむき、河口にすぐ近い接侍所の建物で彼らと対面した。
彼らは入港の趣意書を渡したが、それは条約勅許・兵庫の期限前開港・関税率改訂を求めるもので、あわせて、“七日以内の回答”を求めてきた。そして、
「回答がないなら京都に行って直接、朝廷と談判する」
と警告した。長行は、
「自分は全権がないので回答できないが、将軍が目下京都にいるので、同じく京都にいる阿部豊後守が帰ってきたら、彼が全権委員として二十日に兵庫のイギリス旗艦で会おう」
と約束した。約束の二十一日には、阿部の都合で会見ができなかった。
二十三日の朝、阿部老中は山口駿河守、井上主水正を伴ない、大坂から日本の汽船・翔鶴丸で兵庫に向かった。
一行は、キング提督の旗艦・プリンセス・ロイヤル号上で、パークス及びアメリカ代表、オランダ代表と五時間近く会見した。
パータスは提案を説明し、考慮を強く促した。
阿部はそのあと、フランス艦・グェリエール号に移って、フランス代表ロッシュと会談した。
阿部は提案への決答は、“二十六日にする”と約束して二十四日大坂に帰った。
帰ったその夜、将軍に会って交渉の模様を話し、病気と言っていた松平康直も無理に呼んで評議を開いた。
翌二十五日も将軍の前で終日協議を行った。阿部の意見は、
「明日は回答日だから、何とか答えないと、彼らは上陸してくるだろう。
一方、会津藩の者などは“淀・鳥羽よりは一歩も踏ませぬ”などと言って続々やってくる。
両方が衝突したら、大変である。
ここは、外国人を上陸させぬために、開港を承諾する以外にないだろう。」
というのであった。
阿部の基本的な考えは、
「たとえ攘夷で一時勝っても、諸外国を相手に永久に防備はできない。
第一、その防備の軍艦、鉄砲さえも外国に頼らねばならぬ。
これに対し、もし負ければ、領土をとられ借金を要求されて開港させられる。
こうして無理に開港させられるのと、自ら進んで開港するのと、栄辱どちらであるかは明らかではないか」 |
と、いうのである。
松前もこれに同調し、結局、兵庫開港承認の回答を決定。パークスに伝えるため、松平周防守を兵庫にやることに決めた。
その前夜、将軍は急使を京都にやって慶喜を呼んだ。
慶喜は二十五日の夜中に京都を馬で出て二十六日の朝早く、まだ明けの明星がきらめいている頃大坂に着いた。
城に行ったが早くてまだ誰も登城していないので、阿部の宿舎に馬を走らせた。
阿部に会ってその経過を聞いた。阿部は、
「時間の余裕がないのでやむを得ない」
というのであるが、同時にその腹の中には
「幕府限りで決答すれば、外国もかえって幕府の威厳を認める」
と考えている節もうかがわれる。このことは、外国奉行の山口駿河守に、
「なあに、おれが腹を切れば済むから、決答する覚悟だ。」
と、前に言っていたことからも、知られる。
慶喜は、
「勅許を得ないで事を進めては、ハリスの時の安政の二の舞だ。諸藩も決して納得しまい、もう一度評議し直せ。」
と言い、阿部もゆずらず、意見が一致しない。
そのうち、登城の時間がせまったので、連れ立って登城した。
やがて松前その他の老中や有志も集まり会議が開かれた。
慶喜と阿部、松前らの間で激論が交わされ、間に挟まった若い将軍がはらはらと涙をこぼす一幕もあった。
将軍は正直で、純情な人であった。結局、慶喜の主張が通り、
「まず勅許の奏請をする。それまでは何とでもして外国側に期日をのばしてもらう」
という線になった。
そこで、既に兵庫に向け開港の回答をもって出た松平周防を、急遽呼び戻しにやった。
他方、長行と若年寄・立花種恭(たねやす:下手渡藩主、現、福島県伊達郡月岡町)を新たに兵庫にやり、外国側と“期間延長”の折衝をやらせることにした。
長行は、病の故で辞退した。恐らく心中はこれに反対であったのだろう。
結局、立花と大目付・田沢対馬守政治、大坂町奉行・井上主水正の使者たちが、英艦上でパークス及びアメリカ、オランダの公使と会見した。
「阿部が病気で来られなくなった」
と詫びたあと、大坂での閣老や将軍の会議では条約勅許を不可欠としたが、朝廷との交渉に時間がかかるので、
「十五日間、延期してほしい」
と申し出た。パータスは怒って、
「閣老に勅許を得る力もなく熱意もないなら、直接、京都に出て天皇に掛け合う。」
とおどし、例によって暴言も吐いた。
立花も刀の束に手がかかりかけたが、押し殺して交渉を続けるうちに、
「十日間なら賛成しよう」
ということになった。立花は、フランス艦にも行ってロッシュの承諾も得た。
これまではもっぱら慶喜の側で、『徳川慶喜公伝』や『昔夢会筆記』によって見てきたが、慶喜がはたして一貫した態度をもっていたのか、あやしい点もある。
たとえば、当時の将軍、家茂の御側御用取次であった竹本要斎が、後に旧事諮問会の質問に答えた記録がある。
これによると、「自分が役目の上を越えてやったことが、一回だけある」と言っている。
それは、この時の大坂城での会議の席であった。
牡丹の間に将軍が出座し、慶喜公が京都から駆けつけた大評議であったが、その時、慶喜公は、
「どうしても、今までの順序がこうなって、こういうことで、ここに至ったものであるから、今般の攘夷のことはどうしても、しかるべからざることは目前は見えているが、勅諭なれば御受けなすって履行なさらなければならぬ」
と主張された。
自分(竹本)は、本来なら評議に加わる立場ではないし、これまでも国家の一大事というには聞き飽きてきたが、しかし、“これこそ真の一大事”と思って、
慶喜公の御論もだんだん順を逐って、いよいよ今度は履行せねばならぬという御論は一応御尤(もっとも)のように存じますが、なるほど順序を押したには違いないが、今日までは曲がり屈った道を踏んだので、それを今日誤ったと思ったら、過ちを改むるに憚ることもなく、どうも悪いが、仕方がないからというのはおかしい。
と反論し、役外のことをしてしまった、というのである。
そして、こうした議論の結果、
「将軍もいかさま自分もそう思う。どこまでも、勅諭の御思召が違うだろうということを御諌め申すことにしよう、ということになりました」 |
と述べている。
これで見ると、慶喜ははじめ勅諭だからと攘夷を主張し、竹本が、
「たとえ勅諭でも間違ったことを受けるべきでなく、勅掟を変えていただくのが筋だ」
と反論している。
「しかるべからざることは目前は見えているが……」
などというところは、いかにも慶喜らしい。
慶喜は京都では朝廷や会津の攘夷鎖港論にあおられ、大坂に来ては、だんだん条約勅許を得るという方に向かっていったように見える。
勝海舟も後年、
「慶喜公などは開国派のようでもあり、攘夷派のようでもある。開国派に対しては開国、攘夷党には攘夷さ」
(『海舟余波』)
と、その態度のあいまいさを皮肉っている。
ともかく条約勅許を得ようという将軍の結論だから、慶喜は
「将軍様が上洛なされて、勅許のことを朝廷へ申し上げる手続きをしたらよかろう」
と言って、二十七日に京都に帰った。
大坂の閣老側からいわせれば、慶喜は幕議の穏やかならざるを察し
「余は幕議に計らず、京都にて開港勅許を謀らん」
と言って、さっさと引き上げたということになる。
大坂では将軍の上洛に先立ち、尾張侯と長行を先行させ、期限猶予の事情を上奏させようと京都に向かわせた。
ところが意見がまた変わり、二人を呼び戻すことになり、目付・新見河内守正興が馬で一行を追い掛けていって、枚方で追いつき命を伝えた。
幕議の動揺を苦々しく感じていた両人は、「枚方で将軍の上洛を待つ」と言った。
『天皇の世紀』ではここのところを
小笠原壱岐守は、問題の解決に積極的で強硬な意志を抱いている人物で、事毎に幕議が動揺するのを苦々しく感じている。
尾張大納言もまた、大坂へ引返すのを不承知とし、将軍の上京をここで待つと答えた。
将軍を上京させ京都で諸藩の勢力に包囲され、苦境に立つのを怖れる空気が、老中などの間にあった。
将軍を軍艦で江戸に帰らせ、上洛を避けしめようと企てている。
幕府がその退嬰的な方針に出るのを小笠原壱岐守も尾張大納言も嫌って、枚方に停って将軍の上京を待つと述べたのだが……。 |
と書いている。新見は
「むしろ帰坂されて将軍の上洛を促されては」
と進め、結局大坂に引き返した。
大坂城では連日協議を重ねていたが、将軍が上洛しないで書面で開港勅許を奏請してはどうか等々、なかなかまとまらないでいた。
一方、京都のほうでは薩摩などは、
「阿部、松前が折衝して開港を決め、将軍が上京してこのことを報告に来るらしい」
との情報を得て、
「奇貨おくべし」
と喜んだ。早速、朝廷に書を呈して、
「摂海(大阪湾)に夷狭が来たのは良い機会で、向こうが手を出せば打ち払おう、当藩が先鋒を致す。」
などと心にもない攘夷論で幕府を攻めにかかった。
当時、攘夷が困難なことを最もよく知っていたのは、既に外国艦隊との交戦を経験していた薩・長である。
にもかかわらず無知な朝臣と組んで攘夷を唱えだのは、それが幕府をつぶす有力な武器だったからである。
当時、兵庫港には一隻の薩摩の汽船が停泊していて、船長の有川弥九郎以下がイギリス旗艦にサトウを表敬訪問している。
「彼らは幕府の役人たちよりはるかに愛想よく、兄弟のようだった」
と、サトウは述べている。また、細川の家臣なども、秘かに来艦している。
フランス公使ロセスが十九日に閣老に送った意見書では、
イギリスは将軍に誠意がなく、鎖港を考えていると思っていた。
ところが、薩摩、長州の大名が秘かにイギリス側に使者を出して、二ヵ国は開港する意志があることを明らかにした。
それでイギリスは、諸大名とは友好できるのに、幕府だけが鎖攘を考えていると見るにいたった。 |
と伝えている。
二十七日に慶喜が京都にもどって、事情を奏上したが、将軍はなかなか上洛してこない。
大坂からの連絡では、
「阿部、松前の両閣老の意見で、評議がまた変わった」
という。慶喜は会津侯と桑名侯をつれて参内、二条関白にこのことを伝えた。二条は
「阿部、松前へ厳刑を加えれば、うまくいくのではないか。」
と言い、早速、朝議を開いた。朝議においては、
「両名が幕議のみで勅許を得ずに開港を承諾しょうとしたこと、回答期間の猶予を取り付け得なかったことで罰する」
という案が出された。公郷たちは、誰一人の反対者もなかった。
九月二十九日、大坂城の老中、松平周防守宮に、京都伝奏より、
「叡慮を以て阿部豊後守、松前伊豆守の官職を召放ち、国許に謹慎せしむべし。」
との来書があった。
“禁中から老中の免職が申し出される”という未曽有の事態である。
「朝廷が直接、幕府の役人をやめさせよ、との命を出すとは何事か」
と大騒ぎになり、早速、会議が招集された。
尾張侯・紀州侯・閣老・参政・大小監察・諸奉行を含めての大評定である。
評議はとうとう徹夜となった。そして最後に、長行・山口駿河守・向山栄五郎らの主張、すなわち
閣老はそもそも将軍の任免する臣下であり、その賞罰は将軍の権限である。
しかるにこのような朝命は、将軍の職務を制し、職権を奪うものである。
このようなことでは職責を果たせぬから、将軍は速やかに職を辞して江戸に帰るべきだ。 |
という意見が、大勢を占めた。将軍も、
「自分は若くて大任を受けたが、いろいろ制肘を受けることが多い。
しかも股肱と頼む重臣を奪われるのでは、とうてい将軍の座にいられない」
と言った。そして、
「将軍職は一橋慶喜に継がせるよう、阿部、松前には登城を差し止め閉居させよ」
と命じて奥に入った。
このとき“満座嗚咽(おえつ)して仰ぎ見る者なし”というのが、大坂方の表現である。
興奮は、城中に満ち溢れた。
松前崇弘は憤慨して将軍へ上書を出し帰国した。
帰国後、月代も剃らず謹慎していたが、慶応二年(一八六六)四月、急性腹膜炎で死んだ。
将軍の辞職の表は向山栄五郎が書き、十月一目、尾張侯と長行を京都にやって、二条関白に提出させることになった。
その日、尾張大納言は伏見まで出たが、急を聞いた松平容保(守護職、会津藩主)が、京都から馬で駆けつけ午後四時頃到着、続いて慶喜、松平定敬(さだあき:所司代、桑名藩主)も来着した。
『徳川慶喜公伝』では、大納言が上京の目的について堅く口を閉ざしていたので、慶喜が、「これだろう」といって、将軍職を譲ることと江戸に帰ることを書いた布告を、大納言に示したとしている。
大納言は驚き、「誰にも言うな、と言ったのに、自分はたばかられた」と怒った。
慶喜は、これをなだめて、
「貴卿はともかく上洛されて、関白殿下に申し上げよ。さすれば、使命を果たされたことになるではないか」
といった、としている。 |
しかし、これは少しあやしい。『京都守護職始末』では、大納言が何も答えないので、慶喜は憤然として座を立ち、定敬と共に京都に帰った、としている。容保も、
「将軍職の辞退のような大事を、自分に諮詢もしないとは――」
と、あとで慨然としたのであった。
この日、長行は尾張侯より一日遅れて、晩方に伏見に入っている。
会津の家臣が、いろいろ探り出しにきたが、何も語らなかったのである。
十月三日、将軍は大坂を朝早く発し、伏見に向かい、東帰の途についた。この朝、大坂に行ったシーボルトは、町中が興奮し、川を移動する武装船を見、将軍がかなりの人数を率いて伏見に向かったことを知った。
また、この混乱で、山口駿河守がシーボルト、カションのところに来るのが遅れた。
山口は、二人に託された連合国側の伝言を受け取るはずであった。
翌日になって、山口と他の役人の三名がパークス及びオランダ、アメリカの代表者と艦上で会い、
「阿部、松前の罷免の事を告げるよう、閣老たちから命じられて来た」
と語った。
将軍は松平周防守を供とし、伏見まで来て伏見奉行の役宅に入った。
そこへ、京都から慶喜、容保、定敬が駆け付けてきて、目通りし、強く江戸帰還を引きとめた。
“慶喜が将軍を追いつめた”とする空気が、まわりにみなぎっていたので、慶喜は驚き、
「勅許は自分が必死に努力するから、将軍は江戸に向かわず、二条城に入るように」
と説得した。
将軍は結局、これに従ったが、夕方、二条城に入ってから、病と称して参内はしなかった。
十月四日、慶喜、容保、定敬、長行は、大坂町奉行、井上生水正、大目付、駒井相模守、目付、向山栄五郎、同、松浦越中守をひきつれて参内し、次の“上書”を奉ると共に、勅許の会議の開催を要求した。
上書の文章を今風にすればこうである。
このたび外国人が兵庫港にやってき、条約の勅許をしていただぎたい、と申し入れております。
そしてもし幕府であつかいかねるなら、天皇のところに参ってじきじき申し上げる、と言っております。
いろいろ交渉しましたが、七日までは待つけれども、お許しがなければ、艦隊を引き上げない、と申しております。
無理に戦争をしても、必勝の確信はありません。
たとえ、一時は勝っても、西洋万国を敵に引受けては、幕府はおろか、天皇の地位も危うく、万民が塗炭の苦しみを受けることになるでありましょう。
まことに容易ならざることで、万民を慈しみ結う御仁徳にも反し、国民生活に責任をもつ者として、どんな命令でもお受けする、というわけには、いかなくなっております。
このことがらをよくお考え下さって、速やかに勅許を下しおかれますよう。
そうなれば全力をつくして、外国船を退航させるようにいたします。 |
という内容で、小笠原壱岐守、松平越中守(定敬)、松平肥後守(容保)、一橋中納言(慶喜)の連署の下に、十月五日付で伝奏の飛鳥井中納言、野々宮中納言宛になっている。
その文章から察して、長行の書いたものと思われる。
四日の夕刻から聞かれた小御所の朝議で、廷臣は相変わらず、頑迷であった。朝議は
「大原三位に剣、馬、金を授けて、兵庫に行かせて応接させる。
薩摩の岩下佐次右衛門、大久保一蔵がこれを護衛する」
ということに傾いていたが、慶喜はこれに反対し、さらに長行も猛反対した。
こうして”壱岐守大いに弁論せられければ:『七年史』”結局、議は決定しなかった。
会議の途中で、関白以下が打ち切って退散しようとした。慶喜は、色をなして、
「それがし不肖ながら、多少の人数を有せり。
かかる国家の大事を余処(よそ)に見て、退散せらるるが如きことあらば、この侭には済ませ申すまじ。」
と、詰め寄った。長行は、
「公等がもしあくまで固執されるならば、日本は今に清国のように成るのは必定」
と言い、必死になって声を励まし、
「このように申し上げてもおわかりない上は、お国のために御所を一歩も退かず、ここで一同割腹して天座を汚し奉る。」
とまで、言った。だが、朝議は決しなかった。
その間、裏では薩摩の画策も行われた。
結局、その日は徹夜となり翌五日の午前三時、十五藩の代表にも諮問することとなった。
早速、列藩の三十余名の土を会し、長行が議長となって討論、五日の夜に及ぶ大激論となった。
場所は虎の間、議奏、伝奏は右側に、慶喜、容保、定敬、長行は左側に列しての論議であった。
薩藩は例によって、できもしない攘夷論を主張した。
すなわち、
「唯薩藩の大久保一蔵のみは退帆せしむべき」
を主張し、しかも
「薩藩の見込を尋ぬるに、是亦何の奇策もなし」(『朝彦親王日記』)
であった。大久保には、備前の花房太郎が同調した。
長行が開国についての一貫した定見をもっていたのに対し、大久保は、極めて現実的な謀略政治家ではあっても、外交上の定見は無かった。
後年、新政府の高官となった大久保は、前にも述べたように、あれほど嫌った米欧各国への使節となり、帰国しては、諸外国に比すべくもないわが国力の弱小を説いて、征韓論に反対する。
もしこの頃、長行に面したとしたら、かつての御所列座での自らの主張を、どう弁明したであろうか。
それはともかく、長行の主張は上書にあるように、
「ここでお許しがないと、外国勢は退航しない。だからといって、無理に兵力を出しても、必勝の目算はない。
また一時勝ったとしても西洋各国を敵にまわせば、幕府はともあれ国の存亡にかかわり、万民の塗炭の苦しみを招く。
そんなことをしてはならない。条約勅許は不可欠だ」
という正論である。そして、さらに進んで、
「諸君の議、一々感服せり。
今ことごとく外人の言を拒むも、彼必ず承諾すまじければ、三港を彼の請に任せ、兵庫を許さざるの決心を以て応接せば、彼頑然たるも承諾せざるの理なし。
たとへば鳥を追うに石を投げんとするの状を示せど、鳥必ずしも逃げざるも、実に石を持ちて鳥に向へば逃るが如し」(『七年史』) |
と、述べた。彼の筋の通った主張に、列座の者も次第に賛成に傾いていった。
また、これよりさき、長行は秘かに容保と共に、朝彦親王(尹宮:いんのみや)にも働きかけており、これらも功を奏した。 朝彦親王は、“応接は幕府にお任せあれ”との長行の説に賛成し、天皇のところに行って奏聞した。
「もし開港をお許しなくば、戦争となり、摂海、京師はもとより、ひいて伊勢の大廟もそのままではすまなくなります。
どうか御英断下さい」
と申し上げた。
結局、頑固な攘夷論者であった孝明天皇以下も折れて、条約勅許を得ることができた。
ただし、兵庫開港は許されなかった。
四日の夕刻から一昼夜に及ぶ激論で、長行は五日の午後十時になってやっと御所を退出した。
『ヤング・ジャパン』は、このときのことを、
| 老中の一員、小笠原壱岐守は十一月二十二日(西暦)の夜を通して、三十六人の大名の代表者と条約勅許について議論した。彼は説得することに成功した。 |
と報じている。
この会議の行われている間、大坂では、どうなったかと思って手に汗を握り、徹夜の騒ぎであった。
竹本要斎は、京都の会議の模様をあとで聞いて、
朝廷では御承諾がないものですから、慶喜公も一時、匙を投げたそうです。
小笠原は御随従ですが、なかなか剛情な人ですから、そんなことではいかぬといって励ましたそうです。
あの人は学力もあり、なかなか豪胆の人だったそうです。
それで結局、攘夷鎖港の御取り消しという勅諚を握って、慶喜様が大坂へ御出になったというような訳で……。『旧事諮問録』 |
と、述べている。
慶喜が匙を投げそうになることは、その性格からありうることで、長行がそんなことでは駄目だと尻をたたいた。
長行の豪胆、剛情がよくこの危機を救ったということができる。
一方、交渉の現場ではどうであったかというと、回答期限の間近い十月六日になって、外国奉行の山口駿河守はじりじりしていた。
日限が切迫してたまりかね、京都に様子を見に行こうと淀川船に乗って行った。
途中向こうから、目付の松浦越中守がやってくるのに、出会った。
彼は、前夜(五日)に決定された勅諭の写しを持って、大坂城へ行くところであった。
そこで、二人は川岸の茅屋に入って、その写しを見ると
「兵庫、大坂は許さぬ」
としている。
「それでは駄目だ」
ということで、そんな問答をしているうちに、夜が明けてきたので、大坂に帰った。
それから山口は和船に乗って、天保出陣に出てシーボルトのいる英艦バウンサー号に乗り移った。シーボルトが
「御老中は誰が来るか」
というので
「小笠原壱岐殿だろう」
と答えた。しばらくすると赤い船に槍を押し立てて老中の船が来る。
「小笠原が来ればよいが」
と思って望遠鏡で見ると、松平伯耆守(本荘宗秀、宮津藩主)であったから、
「しまった、何であんな人を出したのだろう」
といったが、仕方がない。こちらの船へ乗り移ってきてから
「小笠原はどうした」
というと、
「不快で出られぬから、拙者に出ろ、といわれたのです」
といった。この人は、温厚一遍の人であるが、慶喜がこれを評して、
「露骨に言うは心苦しいけれど、事に当たり決して意見を吐かず、ただ往けと言えば往き、せよと言えばそうするというふうの人」
といった人物であった。
仕方がなく、それから両名でプリンセス・ロイヤル号に行き、そこでパータスと会った。十月七日、午後のことである。 パータスは勅許の写しを見て怒って、松平に投げつけた。
山口らはそこはそのままにして、次にフランス船に行って、公使のロッシュに会った。彼は、とりなしてくれて
「老中の連印で、兵庫も大坂も後日必ず開くということを書いてくれ、これをもって取り計らうから」
と言った。
老中連はその場にいないので、無断で謀判するか、戦争になるか、二つに一つである。
「重罪を披ってもよいから謀判しよう」
ということで、小笠原壱岐守、松平伯嗇守、松平周防守の名を書き、伯州随行の御祐筆のもっていた老中方の花押の写しを使ってサインした。
そして山口はロッシュと共にプリンセス・ロイヤル号に再び行った。もう、日没になっていた。
談判の結果は、
「条約勅許の確認、兵庫開港の延期(慶応三年十二月七日まで)、関税率の改訂、賠償金の残余の支払」
ということになった。
山口は談判を終えて上陸し兵庫の広島本陣で見ていると、艦船は一斉に煙をあげて出港して行った。
「大坂は危険だ」というので彼はそこから唐(から)街道を通り、山崎の方に抜け九日の夕方京都に入った。
翌日、二条城に行って御用部屋に入ると、小笠原が
「お手前は、登城差し止めになっている。勅淀を書き改めたということで、大罪に処すことになっている」
と言った。そこで、事情を説明したら、
難局においては、こういう決断は道理至極である。だが、なにしろここにいては剣呑だ。
どんな間違いがあるかもしれぬから、早く江戸に帰れ。江戸で閉居して皆の噂が消えるのを待て。 |
と、言われた。
そこで早速、書き付けをもらって、東海道は危ないので木曽路を通り中仙道を飛ぶように帰った。
藤村の『夜明け前』には大津経由で木曽街道を下って、馬籠本陣に宿泊する山口駿河の姿が劇的に描かれている。
その客人“山口駿河”は、半蔵に対して話す。
「御主人はまだお聞きになりますまいが、いよいよ条約も朝廷からお許しが出ましたよ。
長い間の条約の大争いも一段落を告げる時が来ました。
井伊大老や岩瀬肥後などの骨折も、決して無駄にはならなかった。
そう思って、わたしたちは自分を慰めますよ。
やかましい攘夷の問題も今に全くなくなりましょう。
この国を開く日の来るのも、もうそんなに遅いことでもありますまい」
そう言いながら両手を後ろに組んで、あたかもそこの壁や柱に向かって話しかけるように部屋の中を静かに歩く。
あとで、用を済まして、何気なく客人の部屋に近づくと“思いがけなくも、彼はその隠れた部屋の中に、激しく啜り泣く客人を見つけた”のであった。 |
十月七日、将軍は辞意を撤回した。また同九日、長行は老中格から老中になった。
翌月十一月三日、将軍は二条城から、大坂城に戻った。
長行の歴史上の積極的な役割は、ここで終わったと言ってよいであろう。
しかし変転するその個人の運命は、引き続き我々の別の大きな興味である。
8 幕府崩壊の始まり、長行の広島出立 top
「一八六六年の日本歴史の舞台は、主として西国の端・長州である」
英人・ディキンズは、こう書いている。
徳川幕府の崩壊劇が今や開始されようとしている。
そして、その幕開けの引綱を握っていたのが……いや、握らされたのが、長行である。
長行の息子、長生(ながなり)は後年、その父について、
「多少、調子に乗るところがあった」
と言っている。さすがに、よく見ている。
生麦事件の解決、開港問題の決着と重大な幕府の危機を救ったので、長行に対する信望が集まってきたことは、彼にとってはいささか、不幸であった。
慶応元年(一八六五)十月二十九日、長行は軍事御用取扱いを命ぜられた。
十一月には、いよいよ紀伊侯を総督とし、井伊、榊原を先鋒とすることが決まった。
その月の二十一日には、大目付、永井主水正らの監察が、広島にいたって“八ヶ条の糾問書”を突きつけ、回答を求めたが、宍戸備後助(実は山県半蔵)、小田村素太郎が申し開きをした答は、人を食ったものであった。
たとえば、
「山口城をなぜ再築しているのか」と詰問すれば、「草木を切ったら、自然と城跡が出てきました」
と答える。 また、
「蒸気船を売って、武器を購入したこと」を責めると、
「売ってはおりませぬ。蒸気釜が壊れましたから、ほっておいて、どうなったか知りません。
大小砲など、夷人から買った者は、当藩には一人もおりません」
といった具合である。
この不得要領の答弁を持って、十二月の暮、のこのこと帰坂してきた。
長行は慶応二年正月二十三日に、京都から大坂に移ってきた。将軍から芸州への発向を命じられたからである。
しかし、彼は、「この将軍の命令を受けるべきかどうか」内心、深く迷っていた。
彼は元来、迷いや弱気やへんな妥協は嫌いであった。
また、なかなかの策士でもあったが、根本には筋を通す頑固さがあった。
だが、彼の一生のうちで、“この時ほど”迷ったことはない。
このとき、国元の唐津藩から家老の西脇勝善(東左衛門)が藩兵を率いてきており、江戸家老の多賀高寧(長兵衛)も大阪にやってきていた。
長行はこの二人の重臣を呼んで
「今回将軍様から芸州に行けと命じられたが、お前たちはどう思うか」
と訊ねた。こんな事は、これまで一度もなかったことである。両名は、口を揃えて、
「いかに将軍様の仰出でも今度だけはおやめなさい、お断りなさいませ」
と答えた。長行は
「そうだな」
とうなずいた。
翌日登城して閣老部屋に入り、御側御用取次を介して辞職を申し出た。
二、三日すると、再び将軍からお召しがあった。
将軍は閣老首座の板倉と相談したらしく、
「壱岐守、今度のことは是非引き受けてくれ。お前一人で安心出来ないのなら補佐の副役をもう一人添えてやるから」
と、言った。そして、
「これをお前につかわす」
と、自分の短刀を脱して長行に与えようとした。
長行は、かねがねこの将軍が好きであった。
癖の多い勝海舟でさえも、家茂のことを語るときは涙を浮かべたほどの、珠のような人柄である。
彼はこの時、意を決した。彼は将軍のいじらしさに打たれてしまった。
「この若い将軍の、いたいたしいまでの純情と信頼を、裏切るわけにはいかない」
彼は、そう思った。
「副役も、お刀も拝辞します。そんなご心配はいりませぬ」
ときっぱり答えた。
後の事であるが、家茂が死んでからの長行は、人が変わったように議論をしなくなり、淡々として事務を処理した(徳永真一郎『幕末閣僚伝』)といわれている。
長行は、邸に帰ると、また、重臣たちを呼び出した。
そして、いきさつを語ると、
「どうしたらよいと思うか」
と訊ねた。重臣たちは、もう長行の気持ちがわかっていた。
「こうなっては仕様がありません。お受けなさいませ」
と泣いた。
そうと決まると道は一直線であった。彼には徳川恩顧の譜代大名の世子としての誇りと意地があった。
「前途は暗く、けわしい。しかし、やるしかない」
と、考えた。
「総力を結集すれば、なんとかなる」
とも、思った。
だが時勢の流れに逆らうことはできない。この才物にもその情勢判断には、過去にとらわれた甘さがあった。
とくに長州の武力に対する誤算と、諸藩の動きに対する読みの浅さがあった。
前回の長征のとき、彼の国元の唐津藩さえ尻込みした出兵による財政圧迫を、諸藩が肯(がえ)んじようとしないのは、むしろ当然のことであった。
二十六日“芸州広島表へ出立せよ”との命令が、正式に下った。
二月四日、長行は幕府代表として室賀伊予守、木下大内記らと共に紀州藩の軍艦で出発した。
そして七日に広島に着き、宿舎の大手筋一丁目の丸内買屋敷(御年寄居屋敷)に入った。
現在の大手町一丁目、元安川の東側の原爆ドームのある一帯であろう。
二月二十二日には広島藩の重臣を召し出して、徳山、長府、清末の三支藩主と国老三名を広島に呼び出すように命じた。
しかし彼らは病気と称し、書面を差し出し出頭はしなかった。
この頃、在坂の板倉閣老らの間で
「勝安房守を長藩との交渉に用いてはどうか」
との意見が出たことがある。
このことを長行に連絡したところ、長行はこれを断った。
「勝はかねがね寛大論だし、これ以上、寛大論をやられては閉口である。
それに、この人については、少し考えるところがある」
という趣意である。
お互いに個性が強くて、相容れなかったのであろう。
あとでこの長州再征の後始末をした勝は、この時のこともあってか長行を酷評したし、長行もまた幕府が倒れても新政府の要職についた勝を、後年ひどく軽蔑していた。
さてしびれを切らした長行は、四月二日に毛利父子以下四支藩主に広島への出頭を命じ
名代を出しても差し支えないが、その期日は四月二十一日であること。
これに応じないならば、直ちに征討の軍をすすめる。 |
と警告した。
これより先、取り次ぎ役をしていた広島藩は、愛想をつかして、その役を辞退していた。
藩主出頭期限前の四月十一日に、長州から伝達役であり藩主名代であった宍戸備後助が、またのこのこと出てきたが、事態は一向に進展しない。
五月一日に長行は図案寺で長州の使者を引見し、「領土十万石の削封、藩主父子の整居」等の幕命を伝え、請書を出すように命じた。
また、別に高杉晋作、桂小五郎、小田村文助、山県半蔵、波多野金吾(広沢真臣)、佐世八十郎(前原一誠)、太田市之進(直方)、等十二名に広島本陣への出頭を命じた。
そして五月五日には数千の兵を率い、土気鼓舞のため本営から北東、二キロ余の二葉山の東照宮廟(現在、東区二葉の里)の参拝を行った。
なお、図泰寺(曹洞宗)は当時、現在の小町、中町の全日空ホテルのあたりに所在した。
寺域は広く、現国泰寺町にわたっていた(現在、国泰寺は西区己斐上町に移っている)。
長州藩の応接役の宍戸(山県)と小田村を呼んだが今度は来もしない。
そこで五月九日、持小筒組二小隊、歩兵一大隊、唐津藩士六人をやってこれを捕え、広島藩に拘禁させた。
また広島藩から取り次ぎに出ていた家老の辻将曹らにも、謹慎を命じた。
これらの措置は、広島藩士をも恐らせ、数百人が藩の学校に集まって会議するという騒ぎも起こった。
ただ広島には大勢の人が集まったので、四月頃から藩内本街道宿駅の人馬賃銀は六割増になって潤っていた。
五月二十九日、長州藩はついに「幕府の裁許に従えない」と返答してきた。
長行は折り返し大坂へ急報し、幕府は“往長の軍”を進発した。広島藩は出兵を辞退した。
副総督の松平伯耆守は二十八日に広島に到着しており、総督の紀州、徳川茂承はこれに遅れて広島に入った。
長行は、自ら買って出て、九州表討手指揮となった。
9 小倉での幕府対長州の戦い top
長行は、六月二日、“九州方面の監軍”のため宇品港を軍艦、翔鶴丸で出発し、翌日、豊前沓尾(くつお)に上陸、郡代、杉生募らの出迎えを受け、小倉入りした。
長行の総督本営は、馬借町の開善寺(約五千坪、後に焼失)に設けられた。
長行が小倉に移ったことについて、勝海舟は
「広島に札が立って“唐津の奸物を戮せむ”とあったので、これから逃げるために口実を設け小倉へ行ったのだ」
と、言っている。しかし、これは考えられない。
生麦事件の跡始末の時、兵を率いての西上の際など、切腹や暗殺は覚悟していたし、また実際にありえたことで、既にいくども一身を賭してきている。
九州方面の責任を引受たのは、何分とも彼自身の藩のあるホーム・グラウンドだし、宗家の小倉小笠原家が先鋒となっており、熊本藩もまた姻戚であったからである。戦うからには、当然のことであった。
長行は、小倉に着くと、数日経って、イギリス及びフランスの両公使に、“長州の罪状十四ヶ条”を記した文書も送った。その中には、
長州は幕命に背いて攘夷を唱えて外国船を砲撃しながら、外国軍艦が領海に来て撃破されると、脆くも自判の降伏を投じ、しかも、幕府の命令で余儀なく発砲したなどと偽り、自分の罪を朝廷や幕府になすりつけた。
そして蔭でこっそり交親を結び、往来を通じている。 |
といったことも、書かれている。
表で排外主義の看板をかけ倒幕の道具としながら、裏では、秘かにその外国の援助を得て、武力の伸長を図る卑劣な態度は、長行の倫理観の許せなかったところである。
六月七日の幕艦による周防国大島郡の砲撃は、この戦争の開始であった。
長行は諸隊を門司から小倉にかけて配置したが、譜代の小倉藩を除き九州の外様の諸藩の態度は極めて消極的であった。
前回の七藩、約三万の兵が集まったのとは、全く異なっている。
ただ、熊本、久留米、柳川が、少数の兵を出しているだけである。
肥後熊本藩・細川は長州の強敵であるが、藩主はもともと長州再征に不同意で、先に藩主・細川慶順はこの挙に反対の意見を幕府に表明していた。
筑後の久留米藩・有馬は、大目付・塚原昌義らが広島の監察に報告しているように、
「久留米は五百人程出しているが、これまた尊王攘夷の兵隊である」
という状態であった。
福岡藩は厄介物の五卿を抱えて内紛中で出兵どころではなく、五卿警固を口実に出兵せず、後に自領防禦のため若松、黒崎、芦屋方面に約九百名を出し、肥前佐賀藩は、兵四、五百人を筑前木屋瀬まで出しているにすぎない。
薩摩にいたっては、論外である。
小倉藩の各陣営の配置は、島村志津摩隊(小倉藩一番手)は東の旧・田の浦、小笠原級衛隊(小倉藩六番手)は西の新・田の浦、渋田見新隊(小倉藤三番手)は門司浦の梶ケ鼻・和布刈海岸、小笠原近江守貞正(支藩小倉新田一万石、篠崎侯)は楠原村(現在、東門司・老松町)に陣し、後方本営は長浜千畳敷、小笠原侍従真手(幸松丸、藩生息幹の実子、播州穴粟郡安志一万石)は庄司(現、門司区庄司町)を守り、本営は藩主の下屋敷。
小倉本城を中心としては、紫川の河口、東台場は渋田見舎人隊(小倉藩二番手)、西台場は鹿島刑部隊(小倉藩五番手)、城下は藩校の思永館を中心に中野一学隊(小倉藩四番手)が守った。
小倉藩の編成は、六備二小隊。一備は、千百七十人、小隊は三十二人であった。
さらに、各藩は柳川藩・立花の兵は家老・十時十左衛門、侍大将の矢島、小野らが各組の兵士と足軽八組を率いて城野村、片野村方面に入った。
久留米は、渡辺盛人が率いて初めは紺屋町、島町(現、魚町一〜四丁目)、後には北鋳物師町から中原方面、そして南の清水、さらに後方の高橋村、熊野村に移った。
肥後熊本藩は六月十七日から西山大衡、柏原新兵衛、長岡監物、溝口蔵人の諸部隊が小倉周辺に到着、七月二日までに約七千人になった。
足立山麓の広寿山福聚寺を本営、蒲生の大興禅寺(専教寺ともいう)を後営とし、足立村から蒲生村一帯の農家に駐屯した。
小倉側の記録によると、諸藩の部隊は赤坂、鳥越以西の小倉城下から筑前境、南は企牧郡の社寺、農家、商家に宿陣し、「一兵も大里から門司方面の前線には姿を現していない」としている。
『小笠原壱岐守長行』や『東松浦郡史』には、「唐津藩兵は白木崎」とあるが、唐津藩兵は本営の間着寺と、その北の且過(旦過橋付近)にいた。
白木崎というのは、現在の門司区、西海岸である。幕府の八王子千人銃隊の八小隊、二百二十余名は、鳥町の西連寺、西教寺、古法寺に分宿していた。
六月十七日、早朝、長州軍は下関の、阿弥陀寺(現、赤間神宮)に集合した。
対岸の門司、田の浦に上陸し、海に沿って西に行き、南下して小倉城を陥す作戦である。
主力は奇兵隊、これに長府の報国隊、山内家の正名団が合した。
この日、関門海峡は濃霧であった。午前四時、丙寅(へいいん)丸は癸亥(きがい)丸、丙辰丸を率いて田の浦へ、乙丑(いっちゅう)丸は庚申丸を率いて門司浦に向かい、砲撃の火ぶたを切った。
乙丑光はグラバーから薩摩を経て購入した、中古の木造蒸気船ユニオン号である。
薩摩では桜島丸といっていたもので、当時、土佐の坂本龍馬が海援隊士とこれを回航してきており、参謀の高杉晋作にすすめられて、彼らもこの日、参戦した。
龍馬は士官・菅野に命じて高杉の指揮を受けさせた。伊吹周平がその砲手をつとめた。 |

下関、赤間神宮−長州軍はここから出陣した
|
龍馬自身は阿弥陀寺の民家の屋上から、対岸の戦況を眺めた。丙寅丸には土佐藩士では田中顕助なども乗り組んだ。龍馬はこの日の戦争について、後日、実兄の権平に送った手紙の中で
| 簡単な絵図を書き、下関側のここの山より船の戦を助けるモルチールを用い、大小数十発なりしに、敵上にて快く発したるは心地よかりきとか、門司浦の台場の所にはこの日この浦を焼きつくす、また右の方には敵の破れたる兵卒これより引取る、同方向の海上では、ここに小倉肥後藩の蒸気船など出たり引込んだりして居れども、何故にや救いに来らざりきなどと書き記している。 |
長州側からの砲撃に対して、はじめは小倉側はほとんど応戦しなかった。
十時少し前から準備ができて、少しばかり大砲で反撃をはじめた。
長州側は、海峡最短の壇の浦台場からも砲撃を加えた。
長州軍は三部隊に分かれ、まず第一部隊として奇兵隊の第一小隊、第六小隊、第七小隊、一番砲隊、報国隊四個小隊が砲撃に続いて上陸した。
これには軍監の山県狂介(有朋)、参謀の会田春輔も加わっていた。
報国隊一小隊が田の浦の東に進み、他は全軍その西から上陸した。
海岸の防塁を破った長州兵は、二個小隊を田の浦と門司の間の新開地に置き、他は全部隊が山上の砲台、そして島村の本営を攻め各営に火を放った。
また、田の浦にあった小倉の渡海用の和船数百艘も焼いた。
第二部隊として奇兵隊の第二小隊、第三小隊、二番砲隊、報国隊一小隊、正名団が、早鞆の東岸の古城山の麓に上陸、門司と田の浦の双方に分れて進んだ。
田の浦方向に向かった部隊は、この方面の戦局が既に決まっていたので、山越えで楠原村に出てここを占拠、門司村方面の敗兵を挟撃する態勢に出た。
さらに第三部隊として奇兵隊総督の山内梅三郎も、奇兵隊第四小隊、第五小隊、三番砲隊、四番砲隊、正名団二小隊を率いて上陸してきた。
長州軍は、門司、楠原、庄司の各陣所を焼いた。
苦戦の最中、小倉から長行の使騎がきて大里への退陣を命じたので、小倉の前線各部隊は大里まで退いた。
大里沖には幕艦の順動丸、飛竜丸が停泊していた。
また前日小倉に着いたばかりの熊本藩の兵千六百も、大里に応援に進出してきた。長州側は、夕方になり、下関に引揚げた。
翌十八日、高杉は“長藩先鋒士官”の名で、熊本、佐賀、福岡、久留米、柳川の五藩の軍事役に書簡を送り、
「これは余儀なく仕向けられた戦争で、小倉藩以外とは戦争の意志がない」
と伝えた。部分的には
「我藩のことを小倉藩が一族の小笠原閣老に誹膀したのだ」
とも書いている。
十九日に島村志津摩らは集まって彦島に渡る作戦をたてた。
しかし長行はこれを容れなかった。
「武器がまだ十分でないし、諸藩の兵もまだ足りない」
というのがその理由であった。
しかし何よりも、最も有力な熊本軍が最初からこうした作戦に気乗り薄であることを承知していたし、他藩もこれを支える気持ちがなく見えたからである。
長行は武器が十分でないと言ったが、これはこの戦局の決定的な点でもあった。
十七日の長州軍の侵入の翌日、その戦況を広島の監察に伝えた塚原昌義、木下謹吉、平山謙治郎の報告では、
| 味方には機械乏しく、大砲はボードウィスル多く、小銃も火縄銃が多い。甲冑、小具足、弓などではらちがあかない。僅か二、三百の奇兵隊に破られた。 |
と正直に書いている。
小倉側が大時代な甲冑を着用して動作もにぶく、刀や弓で戦おうとしているとき、相手は士気の高い兵隊が軽装で、洋式銃をもち散開戦法で激しく攻めてくるのである。
長州藩は慶応元年の三月には、村田蔵六(大村益次郎)が上海に行って、壬戌丸を売りゲベール銃を買い入れてきている。
また、七月には井上聞多(薫)、伊藤俊輔(博文)が長崎でグラバーと会い、薩摩の了解を得て薩摩名儀でミニエー銃四千三百挺、ゲベール銃三千挺、計七千三百挺を薩藩の胡蝶丸、海門丸に積んで三田尻に陸揚げしていた。
さらに幕府の長征の噂が聞こえてから、長州は急濾、ミニエー銃千八百挺、剣銃二千挺を買いこんだ。
従ってその購入総量は、小銃だけで一万一千挺といわれている。
ゲベール銃はオランダ製で前装滑腔式、フランスのミニエー錠は前装管打火施条銃で、後者の方が性能が優れている。
従って、村田などはこちらを買うことに力を入れだしていた。
いずれにせよディケンズの言葉を借りると、
長州軍は主としてマスケット銃で装備し訓練も見事で、あらゆる点で佐幕諸藩の軍隊よりも、装備と組織が勝れていた。
そしてこれは、長州藩が一八六四年の戦争で多くの経験を得ていたからである。
すなわち禁門の変や、連合艦隊との交戦、激しい内戦などの経験が生かされていた。
幕府が何も生かせなかったのに対し、西国諸藩は攘夷を唱え外国人と戦端を開いたが、転んでもただでは起きなかったことが、大きな差を生んでいた。 |
西洋銃に対する刀、槍や火縄和筒という戦力の差は勝敗を左右した。
これは、長州側の本の『防長四境之役』なども指摘するところである。
長州の武器購入の便宜を計ってやっていた薩摩では、この九州北端での戦争の最中に、同じ九州の南端の鹿児島港で、昨日の敵のイギリス艦隊と、なごやかな友好親善を行っていた。
上陸したパークス公使、キング提督と島津公は平和な交歓の盃を挙げていたのである。
再び、関門の戦争にもどろう。
七月三日、長州側は彦島の弟子待砲台から大里(だいり)を砲撃、兵を門司に上陸させて大里の背後を襲った。
とくにこの日の戦法で成功したのは、和船に大砲を積み、幕府の富士山丸に近寄り、三発で蒸気釜を砕いて動けなくし、打ち手は海を泳ぎ帰ったことである。
長州方の軍艦は自由に動き、陸地を砲撃し、奇兵隊、報国隊の上陸を援護した。
この時の小倉方の布陣は、五番手の鹿島刑部隊が小森江から矢筈山方面、四番手の中野一学隊が大里、篠崎侯・安志侯の隊は大里柳(現、柳町)の静泰寺を本陣とし、観音山に主力を置き、鹿喰(かじき)峠、奥田越・二十丁越方面に哨兵を出し、二番手の渋田見舎人隊が新町、住吉原の数段構えで前線を形成した。
小倉城の守りは、三番手の渋田見新隊と六番手の小笠原織衛隊が紫川河口の東西の台場、一番手の島村志津摩隊は思永館を本拠とし小倉全町を警備した。
長州藩の上陸部隊は、まず小森江口を破り、続いて福間松原で中野隊を破った。
鹿島隊、中野隊は退いて、住吉原の渋田見隊に合流した。
また、からめ手の鹿喰、奥田の守備隊も逃げて住吉原に流れこんだ。
このとき、小倉にいた小笠原近江守は、住吉原の救援に進出してきた。
さらに、そのうしろには他藩の兵が控えていた。
小倉兵は奮戦して、一番橋付近で長州兵の進撃をくいとめた。
正午過ぎになって長州軍は攻撃を断念し、小森江へ引揚げた。
七月二十六日夜、長州兵約一千五百人が大里付近に上陸。交戦は、翌二十七日の夕方に及んだ。
長州兵は新町村、藤松、馬寄村を攻略、前線の小倉軍を破って、鳥越を径て、赤坂に迫ってきた。
小倉軍の背後にあって、長浜から赤坂の延命寺山、弾正山、そして大谷池から足立にいたる南北のラインに布陣していた熊本軍は、一番手備頭・溝口蔵人、二番手備頭・長岡監物の指揮下にこれに反撃した。
長州側は、死傷者約二百名を出す敗戦となった。熊本側も、死傷者を出した。
これらの地域は、現在の北九州市の門司区(西新町)、小倉北区(赤坂、手向山公園、富野)に属する町々となっているところである。
この直後、射撃戦の重要性をあらためて知って熊本軍の長岡監物は、藩に鉄砲二百挺を軍卒に持たせ、十挺に一人の隊長をつけて、支援に送るようにと要請している。
出兵はするが、戦わずに傍観するという方針をとっていた熊本側にいわせると、これは小倉藩の策略に引っ掛かって、やむをえず戦ったまでであるという。
そして、それ以後は、戦争に参加しなかった。
小倉戦争を詳しく調べている原田茂安は、その『愁風小倉城』の中で、長行の軍事作戦能力の欠如を酷評している。
確かにその通りで、彼は文人型の政治家ではあったが、武人型ではなく、軍事には明るくなかった。
だが同時にその根本的な戦略の失敗は、予定した九州諸藩の支持を得られなかったことにもよっている。
彼の言葉によれば「一和の基これなく、必勝の目算相見えず」というわけである。
熊本藩以下の従軍諸藩は形式的に出陣しているだけで、戦意が全くなかった。
佐賀藩は七月十六日、秘かに中野数馬を熊本藩の陣営に送って、肥後の藩論を確かめ、その結果がわが藩の論と符合する、といって戦争に加わらなかった。
熊本藩は出てきてはいたが、すでに述べたように、もともと今回の征長には消極的で、藩主慶順(韶邦:よしくに)の名前で小倉の長行に、
「長州問題には朝幕共に問題があるから、この際、国政の根本を立て直すのが先決だ」
との意見もよこした。
熊本軍の総指揮官の家老・長岡監物(米田是容)は十七日に長行に対し
「大坂に諸侯を集会させ人材登用を計れ」
とあらためて言い出し、長行が
「世間に名も知られたお前が、何を今更子供のようなことをいうか」
と怒るということもあった。
監物はまた、京都に在る同藩の小笠原一学に手紙を送り
「閣老はしきりに成功を急いで紀州公、慶喜公、春嶽公の進征を主唱しているが、事態は然るべからざるものがあるから、軽々しくこれに同ずべきでない」
といい、これを知った長行は激怒し、他の熊本藩士がとりなすということもあった。
以前から監物と意見が合わなかった長行は、十七日に藩主に対し、至急その弟の一人(できれば良之肋、後の護美、長岡監物を襲名)と溝口孤雲(蔵人、家老、小笠原秀政の九男が溝口家養子であった)をよこし軍を督してほしいと頼み、藩主がこれを断るということさえ起こっていた。
なお、その後、七月二十六日に、長岡と溝口が小倉から藩の重役にあてた書簡では、
「将軍家の存亡も、もはや旦夕に止まる」
とも書き送っている。
長行と監物の衝突は戦闘方針においても、長行はひたすら進撃諭を主張し、
「貴藩は、海を渡って彦島を占領すべし」
と要求し、監物は、
「彦島をとるのはやさしいが、そのあと山口まで攻める方略があるか」
と反諭し、激論数時間にも及んだ。
とくに二十七日の戦闘では、不本意な戦闘にまきこまれ、長行の指揮に対する監物の不満が一挙に爆発した。
彼が本国の重役たちにあてた書簡では、
「応援のための指揮が一定せず、予備隊の備えもゆきとどかず、すべての処置ひとつぴとつが不安のことばかりだ」
と言い、
「このままでは作戦が立たず、部隊の士気にもさしさわる。
この機会を失しては大勢の人間が死地に陥るから、軍を引揚げる」
と書き送っている。
監物らは二十九日に広寿山で軍議し、三十日朝に赤坂から撤退することを決め、さらに同夜、小倉からの総引揚げを決定した。
三十日に長行の本営に溝口、長岡が出向き
「暑い中やって来てこの数日は雨露にさらされて闘い、兵も疲れ、また根本的に備えも手薄で今後の見当もつかないから、我々は国に引揚げる。いかに仰せられても御無用である」
と溝口、長岡の連名で目付・平山に届書を出し、他に対しては陣変えと称しサッサと退いた。
これを知るや久留米、柳川もただちに引揚げた。これで九州の諸大名の援兵は全くなくなった。
小倉藩は、独力で戦わねばならなかった。
肥後の撤兵について『土佐藩勤王史』では、将軍の喪が早くも陣中に聞こえたので兵を引揚げたとしている。
将軍死亡とのニュースは、既に京都から二十一日に井口呈助か熊本藩に送った探索書に、
「同日(二十日)暁将軍様御大切、実は御他界の由云々」
とあり、あながち監物らに伝わらなかったともいえない。
小倉軍だけで赤坂の守りにつくことは、士気にも影響する。
そこで、同じ赤坂村に布陣していた幕府直轄の千人隊に対して、かねての打ち合わせにより出動を促した。
千人隊も最初はこれを快諾した。ところが城内から急使が来て城内に引揚げた。
同じく赤坂にいた唐津藩兵にも延命寺山に出兵を誘ったが、これも千人隊に続いて引揚げた。
長行は最初「幕府千人隊と唐津藩兵隊を出動させる」と小倉の使者に伝えていた。
そしてその後、千人隊長・長坂血槍九郎(本国三河、千石)と唐津藩の隊長を呼んで
「明早朝より小倉軍と協力して赤坂の守備につくよう」
との命令を発していたのである。これが、急に変わってしまった。
裏の事情は、こうであった。
二十九日の夕方、タ食が終わった頃……目付役・平山謙治郎が長行のところに来て
「板倉伊賀守様のところより、安藤金太郎が火急の密使として到着した」と告げた。
「何事であろう」と安藤に会うと、“将車様御他界”というので愕然とした。
将軍家茂は心臓脚気で、長崎からオランダ軍医、ボードウィンを招いたが、一日遅れで間に合わなかった。
安藤はさらに板倉からの伝言として「早速に御世継ぎの問題があり、主君としては一橋様より他ないと言っている。しかし、閣老中には異心の者もあり、貴殿にはただちに御上阪され、一橋様御世継の説得を願いたい。」と伝えた。
長行の頭の中には才人らしい戦況不利の読みと、何よりもここで後継問題が紛糾すると“幕府がたちまち空中分解し破滅する”という重大な危機感があった。
“勝敗は兵家の常”、ここで少し負けたぐらいは取り戻せるが、根本が壊れてはお仕舞だと考えた。
“どんなことがあっても、部下と生死をともにする”といった武人型の人物ではなかった。
この二十九日夜から三十日にかけて、彼は脱出計画を練った。
三十日の正午頃、長行は家老の西脇、多賀を呼んで、事情を話し
「大坂表で急用につき、自分は今晩、乗艦し出発する。多賀は江戸から連れてきた家臣を率いて長埼にまわれ。
西脇は夜、唐津の兵を率いて帰れ」と命じた。
三十日の薄暮、午後七時近く、開善寺の裏口から小舟が一艘、紫川にすべり出た。
小倉藩ではそうとも知らず、執政・小宮民部の指図で田中孫兵衛が援兵を頼みに総督・長行の陣に行ったが、騒然として、取り次ぎもしてくれない。
そこで、目付・平山謙次郎を訊ねると「形勢がこの状態では、貴藩は開城するしかない」と言った。
再び長行の営に行ったところ肥後の長岡らが来ていたが、誰も長行に会っていない。
孫兵衛、保高直衛、富永潤之助は、総督の部屋まで踏み込んだが、長行はいなかった。
既に夜半であった。岡出衛と孫兵衛が幕兵組頭・多田靭負に会ってはじめて将軍の死去、それ故、長行が急遽立ち去ったことを知った。
小倉藩の記録では、「総督小笠原長行は密かに脱出して大坂に逃亡」とある。小倉藩こそ、いい迷惑であった。
| 「小倉藩に何一つ事情も理由も説明せず、善後策も示さずに戦線を離脱したのであるから、こんな酷い話はない」(『愁風小倉城』) |
と怒るのも、もっともである。この点、長行に弁解の余地はない。
小倉藩では戦線を後退し、八月一日、城に火を放って、支藩・香春藩の田川郡香春(かわら)に退いた。
城主・小笠原左京大夫忠幹は既に前年、病没していたが、田川郡上野の興国寺で療養中として、その喪を秘していた。
彼の柩と奥方、ならびに四歳の幼主・豊千代丸を奉じて、香春へ移ったのである。
その後、藩主の死を公表したのは、豊千代丸が六歳になった慶応三年(一八六七)六月のことである。
小倉ではこの八月一日の自焼、退陣の時のことを、“御変動”と呼び、その前と後を御変動前、御変動後といった。
長州では、芸州口、石州口、大島口、小倉の戦争を“四境戦争”と呼んでいる。
なお小倉城は現在では復旧され、正月になると巨大な鏡餅が天守閣の一階に飾られるのが恒例となっている。
富士山丸に乗って小倉港を出た長行は、玄海灘を通って八月二日、長崎に着いた。
そして同六日に再び長崎港を出発し、鹿児島をまわって、二十一日に大坂に着いた。
大坂に着くと直ちに江戸への帰府を命じられ、二十九日、軍艦で大阪を発し、十月五日に江戸到着。翌六日に征長失敗の責で、御役御免となった。
10 最後の将軍・慶喜(よしのぶ)の就任 top
将軍がなくしては、幕府は成り立たない。
しかも今は、その後継者を決めるのが容易でない。
家茂が遺言としてその名をあげた田安亀之助は、わずか三歳の幼児でこの非常の事態では無理である。
当然、慶喜ということになるが彼には敵が多かった。
親藩の尾張も、紀伊も、そして出身の水戸藩においても、必ずしも彼を推す声ばかりではない。
大奥にいたっては、総反対である。
「御謀叛のお家柄の烈公(水戸黄門)の御子で、将軍の座を狙う野心家」と信じていたので、老女たちは老中首座の板倉に密書を送って、「田安殿を座につけよ」と迫りさえした。 ニス
老中有司はと言えば、先の阿部、松前の解任問題で慶喜への風当たりが強く
「されば公の意見を賛してこれを扶翼せんとする者は、唯公の推挙によりて再任せる老中板倉伊賀守、小笠原壱岐守あるのみ」(『徳川慶喜久伝』)
であった。
板倉は禁門の変の後、攘夷派とみられて罷免されていたのを、昨年十月、慶喜の支援で再任した。
こうした関係から板倉は心中強く慶喜を推し、長行も「この困難な時には、慶喜しかあるまい」と考えていた。
孤立的な板倉が長行を戦陣の中から急遽呼び出したのも、こんな事情があったからである。
いろいろともめ、慶喜自身もごねて“酒呑みのねじあげ”(松平春嶽の表現)をやったりしたが、結局この年の十二月、慶喜が将軍職についた。
長行はというと既に十一月に老中に返り咲いていたが、それから一年有余、淡々とした態度で外交関係の処理にのみ専念した。
彼には、既に徳川の将来が見えてきていた。
「私は最近、鬱(うつ)の気がありますから、何時でも辞めさせて下さい」というような手紙も書いた。
しかし慶喜の信任は厚く、十一月二十九日、外国御用掛ならびに御勝手入用掛を命じられた。
御勝手入用掛は、通常、首席閣老が担当する役目でもあった。
年の瀬の十二月二十九日、孝明天皇が亡くなり、翌慶応三年(一八六七)一月九日、新天皇の即位が行われた。
早いもので、かねて五ヶ年の延長を求めていた兵庫開港の期限切れが、いよいよ迫ってきた。
長行はこの件について横浜で折衝を続けていたが、新将軍の外国代表との会見の準備の都合もあり、一月二十五日、船で江戸から京都に向かった。
慶喜は、三月五日に、“兵庫開港の勅許”を奏請した。二十二日にも、再度、勅許を願い出た。
一方、将軍職に就いたのを機会に、大阪城において、“諸外国使臣との公式会見”を行った。
三月二十八日に、イギリスのパークスらが謁見した時の状況を、ブラックはこう書いている。
公使団が城に着くと、外国事務総裁の長行がこれを迎え、そして将軍のところへ導いた。
公式会見の揚は、日本風の装飾で、床には畳を敷き、天井には紋章や花の彫刻や飾りがあった。
そして将軍についての印象を、サトウと同じように、
「将軍は中背で、気持ちの良い、非常に知的な顔をしていた。眼はよく輝き、声は非常にやさしかった。
物腰には屈託がなく洗練されていた」と、述べている。
彼は、また、こうも書いている。
「この記事を読めば、現在、日本高官と外国人との気持ちの良い交際が、ほかならぬ将軍自身によって始められたことがわかるであろう。私は、このことを特に読者に強調したい」
ここで、“現在”というのは、明治維新後のことで「日本人の国際的な社交が既に将軍によって開かれていた」ということを、指摘したものである。
さらに、語をついで「事実を知らないで、現制度(明治政府)が創始したと思い込んで、今日の進歩を賞めるだけで、旧制度の支配者の悪口をいう人たちの誤った考えを訂正したいのである」(『ヤング・ジャパン』)と述べている。 |
そして、このような意見を持たせるにいたった背景には、長行が苦心して将軍を助け敷設した路線があったわけである。
ところで条約を履行し兵庫を開港するためには、前年得られなかった勅許が必要である。
他方討幕派としては、これを妨害しながら、幕権を奪って雄藩連合会議、列藩会盟に移そうという考えがある。
薩摩の小松帯刀、西郷吉之助、大久保一蔵らは薩摩、土佐、宇和島、越前の藩主による“四侯会議”を画策した。
四侯会議は、五月十四日からはじまったが、しかし、会議はもっぱら慶喜の提出した長州処分、兵庫開港の問題の諮問に、応ずる形となった。
長州への寛大な措置ということでは、全員がほぼ一致したが、島津久光は長州問題の先議と兵庫問題のあと廻しを主張し、慶喜は「兵庫問題は緊急で、徒らに日を費やすわけにゆかぬ」とつっぱね、松平春嶽は二件を同時にやる案を出すといった具合であった。結局、四侯会議は解散となった。
慶喜は、五月二十三日にこの二案件を朝議に提出し、“兵庫開港”と“長州藩への寛大な措置”の勅許を要請した。
午後八時からはじまった会議は、徹夜となっても決まらなかった。
そこで二十四日には、公卿の総参内を求めて、会議が続行され、ようやく午後八時頃になって、慶喜の強腰の押し切りによって、“寛(寛大)と開(開港)”の二つの御沙汰書が、降りることになった。
この兵庫開港の勅許は、長行にとっては、あれほど激しく争った慶応元年九月の条約勅許問題いらい、積年の懸案となっていた問題である。
この問題がかたづくと長行は、京都において外国事務総裁を命ぜられた。
今日の言葉で言えば、さしあたり外務大臣といったところである。
この年の政局の変転は、急激であった。
倒壊する徳川幕府を支えきれなくなった慶喜は、土佐藩の意見を容れて十月十四日、“大政奉還”を上表した。
しかし討幕派は岩倉、大久保等の謀議で、玉松が起草し、正親町三条・中御門の書いた“討幕の密勅”(宸裁を得たかどうか、疑わしいとの説がある)を、中山忠能(天皇の外祖父)に代わって、岩倉が同早朝、薩摩及び長州に授けて、先手を打った。
ただしその密勅の実行については、二十一日に「しばらくこれを延期せよ」との沙汰書も出た。
福地源一郎の言葉を借りれば、幕府の運命はまさに、「朽索(くさったなわ)を以て六馬を繋げるがごとき有様」であった。
事態は暮に向かって急転して行く。
十二月九日、岩倉、大久保らのクーデター計画は成功し、“王政復古”の宣言、小御所会議での慶喜に対する“辞官納地”の決定となった。
十二月十三日、慶喜は、京都の二条城を出て大阪城に移った。
長行は兵庫から帰って江戸にいたが、この頃、横浜の居留地問題でひとつの明るいできごとがあった。
過去神奈川開港にともない、街道筋に外国人が出ると事件が起こるので、横浜に区域を画して、外国人居留地と称した。
そして、道路、競馬場などその区域内の施設の工事費を、彼らに負担させた。
そのため自治的となり、警察も外人にゆだね、自治区域になっていた。
ところが、イギリス公使が長行に書を送って来て、居留地の件に関し、「朝比奈甲斐守・昌弘を担当奉行として交渉したい」と、言ってきた。長行は、喜んで応じた。
結局、居留地取締役を神奈川奉行の管轄下に帰属させ、その命令を奉じて、検察逮捕の役をさせることとなった。
そして、英仏米蘭の四国公使と議定、調印した。
11 江戸薩摩藩邸焼打から鳥羽・伏見の戦いへ top
十二月二十五日、薩摩の挑発に乗った幕府は、庄内藩に命じて江戸薩摩藩邸を焼き打ちした。
この報は早速、大坂に飛び、慶喜も在坂の老中も興奮し、年を越した慶応四年(一八六八)正月一日の“討薩の表”となり、西郷の策にうまうまとひっかかってしまった。
そして、三日には、鳥羽・伏見の戦争に突入、「鳥羽一発の砲声は百万の味方」と西郷を喜ばせてしまった。
長行はこれよりさき、京都の形勢が急変してきた二十三日、江戸城に譜代諸藩の重役を集めて、稲葉美濃守と共に、「各の忠勤を尺くすべきは正に今日に在り」(『徳川慶喜公伝』)と激励したが、開戦に関しては、反対を唱えていた。
後年、陸軍奉行並・松平太郎は、上野東照宮において開かれた談話会の席上で、このことを次のように語っている。
「伏見の戦争は、初めから戦争をする考えはなく、色々評議の御座りました時にも、周の武王の処置を烈敷非難する人もありまして、老中の板倉、小笠原または松平豊前などと申す方々にも開戦に大反対で、永井、塚原も同じく反対でした」
しかし開戦反対論者も、長行を除くと主戦論者の勢いの前にだんだん開戦論に転じていった。
「小笠原さんは非戦説でしたが、会、桑、竹中、戸田五助(肥後守又は設楽備中)、滝川播磨も主戦論でした。
大河内(あの時分には松平豊前守でした)も主戦論になって総督でした。永井も初めは非戦でした。
板倉は中を取って論じました。何分会津桑と新選組などが戦争を主張しました」(『旧幕府』) |
会津、桑名、新選組、若年寄並兼陸軍奉行の竹中丹後守重固(しげかた)、陸軍奉行並の戸田肥後守勝強、大目付の滝川播磨守具挙(ともたか)、目付の設楽備中守能棟、等は皆、主戦論であった。
鳥羽・伏見戦の総督になった老中格・松平豊前守(上総大多喜藩主)も主戦論、若年寄の永井玄蕃頭は、非職から開戦に転じた。
長行の“非戦論”の発言に対しては、主職論者たちは露骨に反感を示した。
「長州再征の敗軍の将が、今さら何をいうか」といった態度であった。長行の経験は、全く顧みられなかった。
天下分け目の鳥羽・伏見の戦いは、小枝橋で三日にはじまり、六日には幕府軍の敗走となった。
音に聞こえた主戦論者の滝川播磨は、鳥羽街道での戦争開始と同時に、薩卒の大砲の砲弾の作裂に驚いた馬に真っ先に振り落とされてしまった。
四日の伏見の戦争では、歩兵奉行並・佐久間近江守、歩兵頭・窪田備前守が戦死した。
佐久間近江守は敗走する兵を止めようとしたが成らず、自ら敵に向かって馬を進め従者沢田の小銃を取って敵を撃った。
しかし、竹林からこの隊長目掛けて乱射され、重傷を負って馬から落ちた。
佐久間の出陣の時から、馬側に供をした沢田鍍大(変名)は実は長州の間諜であった。
にもかかわらず佐久間が死ぬまでよく介抱し、頭髪を切り死骸を懇切に埋めて、いずれかへ去った。
維新後、かれは佐久間家を訪れその頭髪を遺族へ届けた。 |

鳥羽・伏見の戦いの戦端の京都鴨川の小枝橋
|
ひとつには佐久間の人柄によったのであろうが、間諜にはめずらしい行動と評された。
幕軍と薩長では、武器にも戦術にも大きな差があった。
前者が古風な関ヶ原戦法であれば、後者は近代的な戦法である。
片一方が「具足を着込んで、旗差物を押し立てて、笛や太鼓でヒュードンドンと噺し立てて進んで行った」のに対し、他方は、「尻を端折って身軽にいでたち、紙屑拾いか何ぞのような風で」(勝海舟『米川詩話』)鉄砲を担いでやってくる。
もっとも“紙屑拾い”というのは言いすぎで、その時のたとえば長州藩の軍装を例に取れば、兵士は黒木綿の詰襟服・黒木綿のズボン・革バンド・銃剣鞘付で、左肩から右脇へは革製弾薬盒(こう)の胴乱、右肩から左脇に紐で刀を吊った。
これに対し幕軍は、野袴・脛巾・足袋・草鞋・陣笠、そして鎖帷子に額鉄付鉢巻をしめた。
隊長には見廻組の佐々木唯三郎のように、直垂・烏帽子に陣羽織の者もいた。
ただフランス式訓練を受けだしたばかりのごく少数の部隊は筒袖・陣股引・韮山頭巾に、刀を腰に、小銃を手にした。
薩摩兵は紺または黒の筒袖に、ズボン、時に藍色の脚半をつけ、紺と白の帯に刀をさし、ミニエール銃をもち、韮山のトンキョ笠を変形した鉢振り笠をかぶった。
戦闘では幕軍の、鉄砲を持つのを潔しとしない刀信仰の勇士たちが、狭い道をしゃにむに、刀を振るって突撃していくと、正面からは六ポンド銃だの臼砲だの大砲の砲火を浴びせ、左右に隠れた小銃隊は物陰に伏せ、あるいは膝撃ち、立撃ちの多段構えで側面や斜め方向から雨あられと打ちまくる。
たちまちその銃火の餌食となり、ばたばたと倒れ、勇敢な連中が死んでしまう。
いまさら「飛び道具とは卑怯なり」といってみたところで、はじまらない。
この決定的な差はその後の戦争にも続いていく。
彰義隊攻撃、会津若松城の攻略、等で威力を発揮したのは、肥前佐賀藩の例のアームストロング砲であった。
鍋島家は先見の明があって、早くから洋式武器を取り入れていた。幕府はこの点、遅れていた。
長崎のグラバーに武器の購入を申し出ても、代金支払いで遅れたりした。
この戦いの時も板倉閣老の督促でアームストロング砲五門を、やっと大坂向けの船積みにしたのは慶応四年一月九日で、鳥羽・伏見の戦場には間に合わなかった。
大坂城で慶喜は、会津藩の神保修理から総くずれの敗戦を聞き東帰をすすめられた。
慶喜はこれをよいことに江戸に帰ることを内心で決めた。
慶喜は大坂城の大広間に諸役職、隊長たちを集めて「たとえ千騎没して一騎となるといえども退くべからず」と大見得を切った。
一同は将軍のこの勇ましい命令に踊躍して、持場持場に退いた。
その隙に慶喜は六日の夜十時頃、松平容保、松平定敬、酒井雅楽頭、板倉伊賀守、外国奉行・山口駿河守、御目付・榎本対馬守、奥医師並・戸塚文海、外国奉行支配組頭・高畠五郎、等をひきつれ、御小姓組の交替をよそおって城を抜け出た。
そして八軒家から、あらかじめ御側用人が心斎橋近くの舟小屋から手に入れていた苫舟に乗って、川を下り海に出た。
開陽艦に乗るつもりだったが、供の者は誰も開陽艦を見たことがなく、しかも当夜は闇夜であった。
天保山沖には英仏等の軍艦がいたが、そのうちで最も岸に近かったアメリカのガンボートのイロクォイス号に行った。
翌日、開陽艦に乗り移った。幕艦五隻は西宮近傍に停泊していた。
四艦は慶喜と共に八日朝、大坂湾を出港、十一日浦賀に到着、ここから小舟で浜御殿に入り、馬を飛ばして午前十時頃、江戸城に帰った。
開陽艦長の榎本釜次郎は、大坂に上陸していて、すっかりおいてけぼりをくってしまった。
慶喜が江戸に逃げ帰ってから、彼と長行の間はだんだん、疎遠なものになっていった。
慶喜は既に恭順に意を固めており、これに対する主戦論者の小栗上野介を、十五日に自ら罷免していた。
フランスの公使ロッシュが十九日にやってきて、慶喜に再挙を進めた時、慶喜ははじめ陪席していた長行を退席させた。
そして通訳だけを残して対談し、再挙を断った。
長行を遠ざけたのは、彼の口からその内容が他へ通れるのをおそれたからである。
長行にすれば、もうこうした将軍に用はなかった。二月七日に辞表を出し、十日に老中職を免職となった。
藩の方でも火の粉がぶりかかるのを恐れて、藩主・小笠原長国の名義をもって長行の“病気廃嫡”(はいちゃく)を申し出た。
九州には大小の藩がある。
唐津藩は福岡・佐賀・熊本・薩摩などの大藩に囲まれ、しかもこれらの西南諸藩は、程度の差こそあれ朝廷方である。
小さい藩がその中にあって、藩の運命と藩士の生活の不安をかかえながら、その存立を続けていくには、それなりの苦労があった。
小笠原長国は、予想のつかぬ混沌の中でもっぱら形勢観望に出ていた。
これは官軍の主力の一部とされた土佐山内や肥前鍋島の場合も、はじめは同じであった。
薩長が徳川に“関ヶ原の復讐戦を挑んでいる”と見ていた頃には、山内容堂は「これからは群雄割拠の時代で、正に手に唾すべき秋」と考えた。
従っていずれにもつかず、そのため薩長からは“土佐はいつも筒井順慶”とさえいわれた。
また鍋島閑叟(かんそう)は“二股膏薬さん”などと陰口をきかれながら、ひたすら中立を守って、内部の武力の充実、蓄積につとめてきた。
しかし、鳥羽・伏見の戦いで、時勢の流れが見え出してきた。土佐も、肥前も、芸州も、ようやく動き出した。
西郷隆盛は、このような情勢について、「土、芸等も、皆腹もすわり、大いに相変じ、ただ今にては勤王の士と見え侯」と、皮肉を言っている。
まして小藩の場合は、事態の急変に大あわてで、大垣藩、小浜藩のように、「東夷征伐の先鋒を願い出て許しを乞う」というのが、続出した。
徳川最大の親藩・尾張藩でさえも、青松葉殿と呼ばれた重臣・渡辺新左衛門以下十数名をスケープ・ゴートとして上意討ちにしたいわゆる“青松葉事件”によって、その態度を転じた。
宮津藩などは殿様の首を差し出すから、どうか藩を滅ぼさないでくれと、秘かに願い出て、さしもの西郷もあきれかえったほどである。
あの人の良い殿様、伯耆守は、全く気の毒なことであった。
鳥羽・伏見の勝敗が明らかになり、薩摩や、鍋島にも脅される状況になってきて、それまで日和見を決めこんでいた長国も、慶応四年正月二十一日、全藩士を招集して藩論の一致をはかった。
大勢順応派と抵抗を主張する馬廻、表詰の血気さかんな連中との対立があったが、執政の長光がこれを押えた。
そして取った道は、他の小藩と同じ恭順の道であった。
長国は早速、佐賀の鍋島に家老の大八木義住以下五名の家臣を派遣して、閑叟に“朝廷はじめ諸藩への執り成し”を乞うた。 はじめはすげなく断られた。しかし、繰り返しての懇願が、やがて閑叟の同情をひいた。
また二月初めには長崎会議所に家老の高畠勘解由、中旬には中老・福田喜大夫が嘆願を行なった。
二月二十二日、鍋島閑叟が上洛のため、伊万里の楠久(くすく)で電流丸に乗船、供船の皐月(さつき)丸を従え、呼子(よぶこ)港に寄港した。
そこで、長国に「同行しないか」という呼び掛けがあり、長国は“この機を逃しては”とばかり、取るものもとりあえず、大八木以下、徒士十五人をかき集め、皐月丸に乗せてもらって、閑叟に同行した。
閑叟自身も遅い上洛だったので、手土産代りの気だったかもしれぬ。
長国は、二月二十七日の昼、兵庫着。裁判所総督・醍醐忠順に「大坂で閉居して、命令をお待ちする」との書簡を先手組頭、山田勘右衛門の名で差し出した。
そして醍醐の命令で三月五日に京都に入り、天趣寺に謹慎して養子長行の廃嫡届を出し、朝議を待った。
朝廷では「長行を西上させ、罪を闕下(かっか:朝廷)にまたせよ」との強硬な態度であった。
長国は、家臣の長谷川清兵衛(久誠)を江戸に派遣して、長行を連れ帰るよう命じた。
長国はまた他の諸藩と同じく「徳川氏御征伐の先鋒を命じてほしい」と願い、三月十二日、市橋卯左衛門をして百数十人を率いさせ、唐津より迂回して中津に出、内海を航して上洛させた。
一部の藩兵は京都警備に残り、他は東山道第二軍への従軍を命じられた。
しかし、実際には長岡、越後には行かなかったようで、佐賀藩に付属、東海道を下り江戸に入っている。
そして、筑後藩と交代で新大橋、永代橋、次に津藩兵と交代で小田原三枚橋の関門警備、さらに一部は脱走幕艦を追って下田港へも派遣された。
『防長回天史』にいう唐津兵「大田原」出張は「小田原」の誤りであろう。
いまや、長国、長行の父子は、“敵対関係”に入ったことになる。
米沢藩の雲井龍雄が、慶応四年六月十一日、加茂の陣営において書いた『奥羽北越同盟軍政総督府の討薩檄』には、
井伊、藤堂、榊原、本多等は徳川の勲臣なり、臣をしてその君を伐たしむ。
尾張、越前は徳川氏の親族なり、親族をしてその兄を伐たしむ。
小笠原佐渡守は壱岐守の父なり、父をして其の子を伐たしむ。
これは五倫を滅し、三綱を破り、今上の初政をして保元の板蕩に越えしか。
その罪、何ぞ問わざるを得んや。 |
という趣旨のことがある。
「小笠原佐渡守は壱岐守の父なり、父をして其の子を伐たしむ」とは、正にその通りであった。
とはいえ、こうしたことは、どの藩においても、多かれ少なかれ、同じであった。
桑名藩にも本国の恭順派と、藩主と一緒に柏崎にのがれた抗戦派があった。
両端を持す小藩は郡上藩などを含め、いくつもあったことはいうまでもない。
小笠原長国は、一方で鍋島閑叟に頼ると同時に、朝廷にも働きかけた。
今城、嵯峨、中御門の各公卿が、長国の実家・信州戸田家と姻戚関係にあるので、この方面にも運動した。
また五百万斤の石炭の献上を、朝廷に申し出た。
各戦線への海上輸送は勝敗をも決し、ことに北越戦線では薩長の艦船が越後に向かおうとしても、石炭が間に合わず、京都の命令を待たずに福岡藩に直談判し、大鵬丸で石炭を輸送させるといった状況であった。
従って、石炭献上の効果は大であった。
いろいろな涙ぐましい努力の結果、長国は敦賀、延岡、宮津の各藩主と共に帰国を許され、八月二十六日、無事に帰藩した。
一説によると、長国は六月初旬、京都を発し、ほぼ三ヶ月大坂に滞在、オランダ船で八月二十三日、唐津港に到着した、ともいう。
いずれにしても、やっと安堵(あんど)の胸をなでおろしたというわけである。
長行は忽然(こつぜん)として江戸から姿を消した。誰もわからぬ謎であった。
蝦夷地箱館からアメリカ船に乗り、海外へ渡ったとの噂もあった。
以下中略(p129-275)
12 小笠原長行の余生 top
長行の帰路については、はっきりしないことも多い。
一応は、アメリカ船で横浜に着き、近くの安宿風のところに一泊し、翌日横浜から品川に出てここでも粗末な宿に泊り、それから東京に潜行した、ということになっている。
しかし、箱館から越後に行き、ここでは百姓家のまぐさの中に一月も寝ていた、といった話もあり、あいまいな点が多い。
もちろん、下手に話しては他人に迷惑をかける懼れもあったろうし、自分としても地下に潜るようなことをしていたのを、あまり話したくもなかったろう。
大野右仲の縁続きで、長行の旧い漢学の友である新発田藩士で、工部小丞であった大野誠(賢次郎)の家にしばらくかくまわれたり、本所の古本屋・和泉屋金右衛門のところに潜伏したりしていたらしい。
和泉屋は、むかし藩邸へ出入りしていて、本好きの長行に親しかった。
金右衛門が亡くなってから、その後をやっていた後家さんが中々のしっかりした気性で、長行を縁の下の穴蔵にかくまった
そしてその家の女中さえも知らぬほどだったという。
そこに一番長く居たらしいとは、子息の小笠原長生の話である。これらのことは子母沢寛『花と奔流』にくわしい。
その後、大野の庇護で湯島妻恋に一戸を借りて潜伏した。
御家人の隠居が世を捨てて住んでいた小さな荒れ屋敷で、家は三、四間、庭は五百坪くらいだったという。
神明社に近いところである。
小女を雇い太田俊介(または俊助)がその厄介人風にして、二階に住んでいたといわれる。
太田は、小倉戦争で長行が富士山丸で脱出した時の従者でもある。本名は太田唆太郎かと思うが明確ではない。
潜伏している間、米渓と尾崎は「公はアメリカヘ逃げた」としていた。
そして口の堅い東京の藩邸の勘定役が、時々為替を横浜在留のアメリカ人に振りこんだ。
その金をアメリカ人が太田にそっと渡す。太田はそれを受け取って妻恋へ持参するという方法をとっていた。
東北から箱館まで同じように脱走の行を共にした人々でも、松平定数や板倉勝静は箱館から引き揚げてすぐに名乗り出て、新政府に恭順の意を表している。
長行がこのような手段をとらず、あえて潜伏したのは「まず死は免れない」と考えたからであろう。
何といっても彼は長州処分の最高責任者であり、長州再征軍の指揮者であった。
当時、因備二侯の建白書でさえも、長・防に一挙に討ち入ったのは「小笠原壱岐守の私意より出たもので、重大の件を軽々しく取計らった」と非難しているほどである。
長州人の多い新政府が、小栗上野介以上に彼の罪を重く視るのは必至であった。世の中も次第に落ち着き、明治政府もその統一を達成したので、これまでの処分者に寛大な処置を取り始めた。
大野右仲は但馬豊岡の役人となっていたが、米渓、尾崎たちと相談して、大野誠、川田剛、平岡庄七、等の他藩者の支援も得て長行の赦免運動をはじめた。
大隈重信や鍋島閑叟などにも働きかけたという噂もあるが、ともかく要路に当たってその罪を追求しないことを、確かめた。 旧桜田の上屋敷は新政府に取り上げられ、一番町、後に下二番町といったところに藩邸を移した。
唐津にいた長国は廃藩置県で上京し、ここに住むようになった。
その長国の名義で、明治五年の七月に東京府知事・大久保一翁宛に届書を出した。それは、
「長行儀、戊辰之年、奥州へ脱出、其後函館ヨリ洋船二乗込、折柄風浪悪敷、竟二海外へ漂泊……」(『小笠原長国記』)
(長行は、函館から帰京の途中、風浪で海外に漂流、今般帰朝いたしましたので御届けします)
という簡単なものであった。
「謹慎して命を待て」ということであったが、一ヶ月ほどして謹慎が解かれ自由になった。 |

晩年の小笠原長行
|
家臣で『函館戦記』を書いた大野右仲は、青森では明誓寺、弘前では薬王院に収容され、再び青森の蓮華寺に移された後、東京の芝増上寺に護送、しばらくして放免となった。
そして釈放後、どんな道筋を経たかはわからないが、明治四年に豊岡県の役人となった。
おそらく父親が因幡の出身であったことや、新政府の太政官大書記官であった大野賢次郎の斡旋でもあったのであろう。
但馬豊岡の豊岡藩は京極飛騨守一万五千石で、佐幕色の強いところでもあった。明治六年に彼はここの権参事となった。
この年の官職改正で、初代県令は小松彰、幕臣出でかつて佐渡奉行や外国方を勤めたこともある田中光儀が参事の職についた。
ここの県令は小松のあと、林茂平(土佐)、桂久武(薩摩)であったが、桂は病気で赴任せず、田中が三年間職務を代行した。田中は文久三年末の幕府第二回遺欧使節、随員の経歴ももっている。
ところで、明治八年八月二十日、田中は突如、免官され、二十三日に鳥取県令、三吉周亮が県令に移動してきた。
そして、大野以下三名を除く七十数名を免官、そのうち十七名を再任、鳥取県から三十数名を引き抜いてくる、という大移動を行った。
田中参事免官と県庁人事の大刷新をめぐっては『豊岡市史』での大野の評判はあまり芳しくない。
検稲一件で田中をざん訴したというのである。だが、大蔵省からの拝借金の浮貸しと焦げつき、工事関係をめぐる使途不明金等で、田中が官吏懲戒令により官位返上をしたところをみると、はたして真実がどこにあったかは、わからない。
大野はその後、数県の警部長、東松浦郡長等を経て東京で死んだ。
榎本武揚は大鳥圭介たちよりも三ヶ月遅くはあったが、同年三月に特旨を以て罪を許されている。
彼の解放に福沢諭吉が奔走したことも、よく知られている。
そして、その福沢には勝や榎本を批判した“痩我慢の説”がある。
福沢は、勝と榎本の功績的な点を認めないわけではない。
しかし、どちらも「武士の節を保持する痩我慢に欠けている」とみなす。
勝は敵に対しただ和を講じ、哀れみを乞い、しかもその主家没落後、得々として敵の士人と並び立って名利の地位にいる。 榎本は最後まで戦ったのは天晴れだが、万骨枯れて将一人残り、敵の走狗に甘んじて高地位を得ている。
「彼の命令で死んだ者は、浮かばれまい」というのである。
もちろん、勝にも榎本にも言い分はある。
勝は、福沢が「遠慮なく意見を言ってくれ」と出した手紙に対し、
「いにしえより当路者、古今一世の人物にあらざれば、衆賢の批評に当たる者あらず……行動は我に存す、毀誉は他人の主張、我に与らず、我に関せずと存じ候」と、さらりと体をかわしている。
「世の中に批判を受けない人間なんて、いるものではない。俺は俺の信念に基づいて行動したまでだ。これをあれこれ批評するのは、他人の自由。俺の関することではない」というわけである。
福沢と勝は、このやりとりを離れてもあまり仲がよいとはいえない。
福沢は、かつて渡米の咸臨丸で勝に同行したが、艦長の勝が船に弱くて部屋の外に出ることも出来ず、また不平を言って八つ当たりばかりし、あげくは太平洋の真ん中で「俺はこれから帰るからボートを降ろせ」と水夫に命じた、と勝のことを書いている。
他方、勝は座談で、福沢のことを本所あたりに隠れておった弱い男とか、相場などして金儲けの好きな男とか評している。
榎本は、福沢に偏見を持っていたようである。
獄中で姉を介して貸してもらったイギリスの化学書がつまらなかったというので「福沢は不見識」とか「もっと学問があると思った」とか「あの程度の学者のくせにこうまんちき」とか、姉への手紙に書いている。
福沢の専門は経済学であり、化学ではないのだから性急な判断である。
福沢からの手紙に関しては「昨今、別して多忙につき、いずれそのうち意見も申しのぶべく侯」と書いたが、実際は何もしなかった。
福沢が、榎本に対して怒ったのは、駿河清見寺の境内の咸臨丸上で惨殺された春山弁蔵らの石碑の背面に、“人の食(しょく)を食(は)む者人之事に死す”と大書し、従二位榎本武揚、などとしていたからでもあった。
「人の食を食みながら、人の事に死せずして、敵の食を食む従二位公」に、腹を立てたのであった。
榎本も、福沢の痩我慢の節を読んで「真っ赤になって怒った」と伝えられている。
この二人と違って痩せ我慢の説を、まるで絵にかいたように実行していたのが長行であった。
小気味の良いほど“徹底したやせがまん”である。
長行は、湯島妻恋から、駒込動坂の薮下に移った。
ここではまるで百姓か植木屋のような生活で、地元の老良たちと話する以外は、一切の親戚故旧との面会を謝絶した。
その変人ぶりは、いくつかの行動にあらわれている。
文久三年の大阪出兵以来、会津若松での滞在まで長い間の知り合いであった会津の松平容保が、三度も訪ねてきたが、もう一度もあわなかった。
越前の松平春嶽も長行を世に出そうと、足を運んで来た。
息子の長生の語るところによると、長行は、家の裏に逃げて、茶畑にひそんだ。
春嶽の方も追っては行かず、悠々として座って待っていた。長行は隠れたままである。
ほとんど日暮れ近くまでそうしていたが、春嶽は、とうとうあきらめて、帰って行った。
もっとも春嶽は、かつて京都での長行の必死の頼みに逃げたのだから、「オアイコ」というところだろう。
長行は前にも述べたように開明家であり合理主義者であったが、同時にその性格は剛情であった。
その剛情さは彼の長所でもあり、また欠点でもあった。
春獄に会おうとしないのも、また終始一貫、日本の国の立場から開港貿易を主張し、非難を満身に浴びても節を曲げず一直線に行動してきたのもこれである。
彼は頑固といっていいほど、変節、無節操を嫌った。長州や薩摩を憎んだのもそれであった。
しかしその剛情さは、長州再征の失敗にもつながった。
理屈を通す潔癖さと直線的な行動が、政事、軍事の大局判断を見誤らせた。
彼の内面には、いくつかの気置が交錯していた。
たとえば、因循を好まず瓢然活発を好んで突拍子もないことをやる傾向があった。
また彼自ら言っているように、決断力と勇気、すなわち「奮然、勇断決定し不順疾雷不掩耳」(雷の音が突然起こって耳を覆う間もないのを顧みず突進する)の闘士型の側面があった。
かと思うと自分が片づけたものは暗闇でも取り出せるほどキチンとせずにはいられない、いささか病的な潔癖病の傾向もあった。
こうした内面の矛盾は、時々彼自身をも悩ませたようである。
ともかく彼にとっては、自分の筋目を通すことがその信念であった。「勝負は時の運、負けたら引っ込め」である。
どんなにおだてられようと、昨日の敵に餌を見せられた犬のように、尾を振って仕える気には全くなれない。
敵にせよ味方にせよ、表も裏も見てきて、ばかばかしくなってもいたのだろう。
同じ元の老中でも、板倉の場合は少し違っていた。側用人も愛想がつきるほど愚痴をこぼしたり、負けおしみを言ったり、許されて上野東照官の副祠官となった時などは大喜びしたらしい。
これも人間らしいが、長行は板倉のように愚痴ばかりこぼすのもいさぎよくないと思っている。これも、武士らしい態度ではない。
自分の失敗も苦々しい。自分の不明も間違いも認めよう。それはそれで全力を尽しただけ致し方ないことだ。
しかし人に会って話すとなれば、とかく自己弁明になり愚痴にもなる。
今更そんなことを言って何になる。人に会わざるに如かずである。
彼の徹底拒否の姿勢は、旧家臣の大野右仲に答えた書簡の中にも見られる。
お訊ねの生麦の借金高とか、兵庫開港とか古い反古をひっかきまわしてみたがなんにも見当たらない。
ご承知の通り勤務中は忙しくて日記をつける暇もなかったし、役向きのものはみな幕府に納めた。
記憶は健忘症で、年をとるにつれて酷い。何を考えても思い出せない。
折角お出でになっても、ひとつもわからぬ。どうか悪しからず。 |
“なんにも見あたらぬ”、“健忘症”、“ひとつもわからぬ”というすっとぼけぶりである。
この手紙が書かれたのは、明治十年三月十六日である。
明治革命の時代の流れは、大きく二つに分けられよう。
その第一は、ペリーの黒船来航から函館戦争までの徳川幕藩体制の崩壊の時期、第二は、それから西南戦争にいたる士族身分解体の時期である。
そしてこの手紙を書いた明治十年三月中旬は、正にわが国内戦史上、最大の激闘・田原坂の血戦が最高潮に連していた時期である。
長行たちを賊軍と呼んだかつての官軍・薩摩は、今度は第二の賊軍になっている。時代の転変は激しい。
しかし、その西南の砲煙弾雨も、長行にとってはすでに“我れ関せず”であった。
晩年の長行は、風流人であった。植木を愛し、
芳香盆栽の歌
梅素馨石解セイテラ茉莉木犀文殊蘭 なご蘭茶蘭茶梅蝋梅
などと、変な旋頭歌を詠んだりしている。
月の美しい夜など手作りの須磨琴を弾き、自作の今様歌をシンガー・ソングライターのように歌って楽しんだりした。
また久しぶりに故郷に帰り、舞鶴城址に立ったときには、
荒れたりな草のみ八重にはびこりて いづこ昔の名残なるらん
と、いささか懐旧の情に浸ったりもした。
彼が心魂を傾けて押し開いた開国がもたらしたものは、画期的な文明開化である。
彼は日常生活では、そうした開化の品々にも親しんだようである。
外出携帯品
烟草入煙管がま口財布手拭ハンケチ 時計に扇手さし襟まき
死んだのは明治二十四年一月、その死顔は安らかで微笑を浮かべていた。正に帝国議会開院の翌年である。
新しい時代が、すでに歩み出していた。
13 筆者あとがき 岩井弘融 一九九二年 top
有名な天文学のガリレイは、世の中がこぞって彼の地動説を非難し宗教裁判にかけられた中で、“それでも地球は動いている”と、つぶやきました。
今日考えると何でもないようなことでも、その当時にあっては口にするのも生命賭けの勇気がいることがあるものです。
これを日本の幕末において実行したのが、小笠原壱岐守長行であります。
彼はその困難な時代において外国との折衝に当たり、封建時代の長く閉ざされてきた日本を開国に導いた偉大な恩人であります。
そのすぐれた判断と強い意志により、外国の武力による植民地化から日本を免れさせました。
彼はいわば開国という目標に、若駒の日本を黎明の空高くいななかせ疾駆させていった最高の騎手でした。
もちろん彼のやったことがすべて正しかったとか、成功したとかいうわけではありません。
それは、ひいきの引き倒しです。
失敗もあります。時代の波に翻弄されて幕府丸は転覆しました。
その転覆させた舵取り役が、ある意味で長州再征に失敗した長行であったといえるかもしれません。
しかし恐らく誰が舵取り役になっても同じだったでしょう。
船の構造そのものが、すでに新しい流れを乗り越えるに適しなくなっていたのですから。
長行の子、小笠原長生によると「人間が世に処して行くには種々必要なものがあるが、果断という事はその最も大切なものの一つである」と繰り返し教えられたといいます。
長行が幕府末期の老中に登用され、諸閣老が去ってもなお、最後に自ら辞するまで残されたのも、外圧・内反の苦悩、動揺の中で果敢な行動をとれる人物とされたからにほかなりません。
彼はまた「世の中で本当に立派な行いというものは、忠なり義なりのもう一つ奥にある真心だね」と幼い長生に寝物語りに語ったとのことです。
当時の支配的な道徳に包まれながら、彼自身はこれを超えたところにその心を置いていたのであります。
それは自我の覚醒、現代風にいえば、アイデンティティの問題をその時の言葉で語ったものと申せましょう。
そうした意味でも、すぐれていました。
長生はその父を評して「在来の英雄とか豪傑とかいうものの型にはまらぬ一種不思議な人物でありました」といっています。 英気溌刺とユーモア、粘着心と淡泊、負けじ魂と気弱、これらが複雑に併存していたともいいます。
病蹟学的にいうと、彼のやや繰うつ的な性向、すなわち気分が高揚すると着想が豊かで、活動的、現実的で決断力があるが、うつ状態に転ずると気弱く大きな失策もするといった気質の両極の動揺が、そういう印象を生んだかとも思われます。
大きな変革の時代は一つの曼陀羅図と私は思います。
その時代を荷う諸仏はそれぞれ一瞬の光茫をひらめかせながら、個々の位置に布置されて動く全体像を創りあげます。
西郷隆盛も大久保利通も木戸孝尤も勝海舟も坂本龍馬も、その一仏であります。
長行もそうでありしかも見のがせぬ一仏です。
歴史が勝者の側に立ってのみ有利に書かれるとすれば、それは真実ではありません。
長行は自分の記録を残すことに消極的で、本文にも書いたように、むしろ抹消しようとさえしました。
したがって今にして新しい資料を得ることは、まずできないと思います。
しかし『京都守護職始末』『徳川慶喜公伝』『昔夢会筆記』『幕末外交談』等々、そのほか彼を語る外的な資料は多々あります。
ただその生涯に関しては、祖父や私が学生時代に一時、世話になったことのある久敬社関係の『小笠原壱岐守長行』が唯一で、これ以上のものは望むべくもありません。
とはいえその原文は“たり””べけんや”の古い漢語調で、今の若い人には到底読めないものです。
この本ではこれをいわば底本とし口語化しながら、これ以外にも他の資料を多く加え、内容的にも自己流の解釈を行なったつもりであります。
引用に当たっては、土筆社主、吉倉伸氏の温かい御快諾、御芳情をいただきました。
吉倉氏は長行と行を共にした吉倉郁太郎、冕三郎兄弟の御一族であります。
ここに厚くお礼を申し上げたいと思います。
私は、歴史の専門家ではありません。専門家だったら、恐らく十枚と書けなかったかもしれないと思います。
フィクションでもないし、ノン・フィクションともいえぬし、セミ・フィクションとでも言ったらよいでしょうか。
もちろん思いがけぬ誤りも色々あろうと存じますし、読者の方々が補正していただければ大変有難いと思います。
この本の出版に当たっては旧制高校以来の畏友の高橋昌郎教授、また法政大学の村上直教授の一方ならぬお力添えをいただきました。心から感謝します。
最後に上梓に直接の尽力をしていただいた新人物性来社の牧野洋氏に、深くお礼の言葉を申し上げたいと思います。
14 参考文献 top
一
『小笠原壱岐守長行』小笠原壱岐守長行編纂会 1943 1984(復刻版)土筆社
『天皇の世紀』(1)〜(17) 大佛次郎 1978 朝日新聞社
『旧幕府』(雑誌・合本7冊)1897 戸川安宅編 1971(復刻版)原書房。第1・3・6号に田辺松波「小笠原明山公御事蹟」
『福翁自伝』福沢論古 岩波文庫 1978 岩波書店
『品川宿遊里三代』秋谷勝三 1983 青蛙房
『武江年表』(2巻)斉藤月岑 東洋文庫 1968 平凡社
『鉄翁随筆』小笠原長生 1926 実業之日本社
『小笠原長生と其随筆』原清編 1956 小笠原長生公90歳祝賀記念刊行会(非売品)
『小説集・小笠原壱岐守』佐々本床津三 1932 柳書房
『花と奔流』子母沢寛 1932 中央公論社
『幕末奇談』子母沢寛 1989 文巻文庫
『流離の譜』滝口康彦 1984 講談社
『幕末閣僚伝』徳永真一郎 1989 PHP文庫
『名主日記が語る幕末』横浜開港資料館編 1986 横浜開港資料館
『佐賀県史』(中巻)佐賀県史編纂委員会 1968 佐賀県史料刊行会
『東松浦郡史』久敬社 1973 名著出版
『豊橋市史』豊橋市史編集委員会 1975 豊橋市
『棚倉町史』棚倉町教育委員会 1980 棚倉町
『昔夢会筆記』東洋文庫 1966 平凡社
『徳川慶喜公伝』(全円巻)東洋文庫 1968 平凡社
『最後の将軍』司馬遼太郎 1974 文春文庫
『幕末外交談』(全2巻)田辺太一 東洋文庫 1966 平凡社
『幕末衰亡論』 福地源一郎 東洋文庫 1967 平凡社
『京都守護職始末』(全2巻) 山川浩 東洋文庫 1966 平凡社
『一外交官の見た明治維新』アーネスト・サトウ 岩波文庫 1960 岩波書店
『ヤング・ジャパン』(1〜3)J・R・ブラック 東洋文庫 1970 平凡社
『水戸学精髄』菊池謙二郎校閲・関山延編 1941 誠文堂散光社
二
『旧事諮問録』(上・下)旧事諮開会編 岩波文庫 1986 岩波書店
『懐旧九十年』石黒思惑 岩波文庫 1983 岩波書店
『大君の都』(上・中・下)オールコック 岩波文庫 196二 岩波書店
『木村芥舟とその資料−旧幕臣の記録」1988 横浜開港資料館
『木村摂津守喜毅日記』木村芥舟 1977 塙書房
『幕府オランダ留学生』宮永孝 東書選書 1982 東京書籍
『定本・江戸城大奥』永島今四郎・太田貸雄編 1968 人物往来社
『指田日記』(抜葦)指田摂津藤詮 1954 村山郷土史編纂委員会
『増訂・明治維新の国際的環境』石井孝 1966 吉川弘文館
『徳川昭武滞欧記録』(1・2・3)日本史籍協会叢書 1932(復刻)1973 東京大学出版会
『花と霜−グラバー家の人々』ブライアン・バークガフニ 1988 長崎文献社
『日本の歴史・23・開国』芝原拓自 1975 小学館
『防長回天史』(2冊)末松謙澄 1980 柏書房
『増訂・戊辰戦役史』(上・下)大山柏 1968 時事通信社
『維新土佐勤王史』瑞山会 1977 日本図書センター
『肥後藩國事資料』(巻6)細川家編纂所 1932 図書刊行会
『改訂・愁風小倉城』原田茂安 1987 臨川書店
『防長四境之役』大塚武松・江木千之 1926 騰写代用
『戊辰戦争従軍日記−武広遜』武広武雄編 1978 ビッグフォアー出版
『維新の礎−小倉落と戊辰戦争』宇都宮泰長 1978 鵬和出版
『駆落志』(第22巻)橋本集約・川合鱗三綱 1978 文献出版
『江戸幕末滞在記』E・スウェンソン 1989 新人物性来社
三
『戊辰物語』東京日日新聞社会部編 岩波文庫 1983 岩波書店
『海舟全集、第九巻・海舟日記』海舟全集刊行会 1928〜29 改造社
『氷川清話』勝海舟 1974 講談社
『海舟座談』巌本善治編 岩波文庫 1983 岩波書店
『パークス伝』E・V・ディキンズ 東洋文庫 1984 平凡社
『小栗上野介の生涯』坂本藤良 1987 講談社
『図鑑・日本の軍装』(上・下)笹間良彦 1970 雄山間
『武家戦陣作法集成』笹間良彦 一丸六八 雄山閣
『薩藩海軍史』(上・中・下)島律宗編集所 1928〜29 薩藩海軍史刊行会
『鹿児島県史料・忠義公史料』鹿児島県史料編纂所 1976 鹿児島県
『佐賀藩戊辰戦史』宮田幸太郎 1976 佐賀藩戊辰戦史刊行会
『佐賀藩銃砲沿革史』秀島成忠編 1934 肥前史談会 |
『能久親王事蹟』1908 常陸会編「能久親王事蹟」(『鴎外全集・著作編11』森鴎外 1953 岩波書店)
『経商スネルと戊辰新潟攻防戦』阿達義雄 1985 鳥星野出版
『幕末諸藩の銃砲』所荘吉 『歴史読本』 1972年7月号 新人物往来社
『図解古鉄事典』所荘吉 1987 維山閣
『幕末実戦史』(幕末維新史料叢書9)大鳥圭介 1969 新人物往来社(付録として「衝鋒隊戦史」及び「麦叢録」を採録)
『新撰組始末記』子母沢寛 196七 中央公論社
『続・新選組隊士列伝』新人物往来社編 1974 新人物往来社(「島田魁日記」を採録)
『新選組再掘記』灼然 1972 新人物往来社(中島登の覚書を採録)
『新選組のすべて』新人物性来社編 1981 新人物往来社
『土方歳三を歩く』野田雅子・久松奈都子 1988 新人物性来社
『試衛館道場の日々』小島政孝『歴史と旅J 1979年7月号 秋田書店
『会津戊辰戦史』会津戊辰戦史編纂会 1841 井田書店
『七年史』(1〜4)北原雅長 日本史籍協会纒 1979 東京大学出版会
『谷干城遺稿』(上・下)島内登志衛編 1912 靖献社
『山内家資料・幕末維新』第8編=1986 第10編=1987 山内家資料刊行委員会
『片岡健吉日記』1974 立志社創立百年記念出版委員会
『片岡健吉先生伝』川田瑞穂 1978 湖北社
『幕末変動期の会津藩家老・西郷頼母近悳の生涯』西郷頼母研究会 1977 牧野出版
『尾張徳川家明治維新内紛秘史考説』水谷盛光 1970 非売品
『戊辰戦争論』石井孝 1984 吉川弘文館
『戊辰東北戦争』坂本守正 1988 新人物往来社
『戊辰落日』(上・下)綱淵謙錠 文春文庫 1984 文駱春秋
『ある明治人の記録−会津人柴五郎の遺書』石光真人編著 中公新書 1971 中央公論社
『戊辰戦↑敗者の明治維新』佐々木克中公新書 1977 中央公論社
『新修大垣市史』(通史編)1968 大垣市
『長岡市史』長岡市役所 1973 名著出版
『榎本武揚』加茂儀一 中公文庫 1960(初)1988 中央公論社
『幕末軍艦咸臨丸』文意平次郎 1969 名著刊行会
『軍艦開陽丸物語』脇哲 1990 新人物往来社
『日本の海軍』(上)池田清 1987 朝日ソノラマ
『長崎日記・下田日記』川路聖謨 東洋文庫 1968 平凡社
『プチャーチン来航・戸田村における露艦建造』戸田村教育委員会 1989
『ペテルブルグからの黒船』大南勝彦 角川選書 1979 角川書店
『北から来た黒船』(1・2)ニコラザドルノフ著・西本昭治訳 1977 朝日新聞社
『柳川藩史料集』永井新 1981 青潮社
四
『復古記』(全15冊)太政官編纂 東京帝国太 学蔵版 1930 内外書籍
『麦叢録』(乾・坤)小杉雅三 1874 尾州 名古屋・片野乗四郎、東京・北畠茂兵衛以下24発行書肆
『雨窓紀聞』(全2冊)(小杉雅之進・竹陰隠士校) 1873(初版)青黎閣(復刻版)1968 函館碧血会
「蝦夷之夢」今井信郎『歴史と人物』 1972年11月号 中央公論社
『鹿児島県史料集』(9) 鹿児島県史料刊行委員会 1968 鹿児島県立図書館
『薩摩出軍戦状』(第1・第2二)大塚武松 1932 日本史籍協会
『七飯町史』1976 北海道七飯町
『福山市史』(中)福山市史編纂会編 1968 福山市史編纂会
『川村純義・中牟田倉之助伝』田村栄一郎 1944 日本軍事図書株式会社
『高松凌雲翁経歴談・函館戦争史料』高原美恵編修(統日本史籍協会叢書)1979 東京大学出版会
『箱館戦争のすべて』須藤隆仙編 1984 新人物往来社
『埋もれていた箱館戦争』脇哲 1981 みやま書房
『箱館戦争』武田八洲満 1988 毎日新聞社
『幕末維新全殉難者名鑑』(全4巻) 明田鉄夫編 198六 新人物往来社
『新聞雑誌に現れた明治時代文化記録集成』(前)石田文四郎編 1935 時代文化研究会
『日本の名著33・福沢諭吉』1969 中央公諭社
『豊岡市史』(下)豊岡市編集委員会 1987 豊岡市
『戊辰の挽歌−桑名藩士情熱の奮戦録』鈴木芳雄 1987 新日本法規出版 |
top
**************************************** |