|
****************************************
間宮林蔵 松浦武四郎 阿部正弘 長井雅楽 川路聖謨 小笠原長行 小栗忠順 HOME
|
その1 長州藩家臣・長井雅楽の冤罪による切腹
(『もう一つの維新』 奈良本辰也著 昭和49年刊 p7-26 全
p296)
|
その2 その3 |
長州藩家臣・長井雅楽(うた)は「開国か、攘夷か」で揺れる幕末に、「航海遠略策」の開国論で藩論をまとめ、朝廷も幕府もそれに賛同し、藩主・毛利敬親が江戸幕府に出仕するまでになっていた。しかし老中・安藤信正が水戸藩の過激派に襲われ手傷を負い、毛利藩主の江戸出立がのびのびになった。
長州藩の松下村塾の若い志士連中は攘夷の過激派で、当時は長州藩の少数派でしかなかったが、その中の久坂玄瑞(くさかげんずい)は、長井を弾劾(だんがい)すること、まるで仇敵のようであった。そして過激派の公家が「航海遠略策」に不敬の言葉があると洩らしたのを聞き出した久坂は、それを追求して長井を切腹に追い込んで、藩論を攘夷に塗り替えた。
それから二年間長州藩は、英公使館焼討、下関戦争、蛤(はまぐり)御門の変と攘夷の過激行動を繰返したが、久坂は蛤御門の変で討ち死にした。
蛤御門の変をうけ幕府は第一次長州征伐を行い、藩主親子、三家老、高杉晋作に謹慎を命じた。三家老はその後切腹を命ぜられたが、高杉晋作は脱藩して生き延び、第二次長州征伐の小倉戦争と鳥羽伏見の戦いを薩長の勝利に導いた。しかし高杉は結核に冒されていたので、維新の大業を見ることなく亡くなった。 |

|
一
君恩に報ぜんと欲して業、未だ央(なか)ば
自ら四十五年の狂を愧(は)づ
即今の成仏は吾が意に非ず
願くは天魔と作(な)りて国光を輔(たす)けん
文久三年(一八六三)の二月六日、萩城下土原(ひじはら)の自宅において、四十五年の生涯を自刃によって終えた長井雅楽(うた)の辞世の詩句である。彼にはこのとき、
君が為 死する命は惜しからず 只思はるる 国の行末
という句も残しているが、しかし、私には、「欲報君恩業未央、云々」の冒頭にかかげた詩の方がはるかに彼の心事をよく伝えているように思う。
和歌の方では、どうしても言葉が月並になってくる。
漢詩の語彙(ごい)の豊富さにはどうしても及ばないところがあるのであろう。
私は、あの詩をみていると、何か心にじーんとくるものがあるのだ。
「君恩に報ぜんと欲して業、未だ央(なか)ば」はそれでよいとしても、「自ら四十五年の狂を愧(は)づ」という言葉である。
長井雅楽(うた)といえば、長州藩はいうに及ばず、当時、諸藩の人をして「智弁第一」と言われたほどの人物であり、その行動も論議も、冷静そのものであったように思われる。
私は、吉田松陰や高杉晋作などが自らを狂と呼んだことをいささかも不審とは思わない。
しかし、何故この理性の固(かたま)りであったような人が自らを狂というのか。
そして、狂と愧(は)じながら自らの腹に刃をつき立てなければならなかったのか。
しかしながら、次の句はまことによく分る。
それは彼が、「このまま成仏するものか」といっている言葉だ。
自分は今ここで、こと志と違って屠腹(とふく:切腹)して果つるのだが、見よ、自分をここに追い込んだ者たちには、天魔となってでも思いのたけを知らしてやろう。
それが君侯に報ゆることにもなるに違いない。
言外にふくまれている意味は、もっと複雑なものもあるだろう。
私は、この人が長井雅楽という人物であるがために、色々のことを考える。
そして、明治維新とは何であったかというようなことにも自然に考えが及んでゆくのであった。
ところでさて、ここでその長井雅楽の最期をもう少し、その姿においてとらえてみよう。
人には、それぞれ最期の姿というものがある。
昔の武士というものは、その最期を如何に美しく飾るかということが平常の心掛けとなっていた。
源平の戦に斎藤別当実盛(さねもり)が、とくに願って錦の直垂(ひたたれ)を着し、白髪を染めて出陣、最期のいくさをして討死したのもそれであったし、梶原源太景季(かげすえ)が一の谷の戦に梅花一枝をえびらにかざして馳せたのも、その平常の心掛けであった。
武士道の心得を説いた『葉隠(はがくれ)』には、戦国の武士は朝起きるとまず行水をして身体を清め、下着を替え、爪を切ってこれの角を軽石ですり落し、ほたる草の乾したものでこれを磨いてつやを出し、月代を剃って、髪に香油をつけるならわしであったと記している。
つまり、それは何時死んでも、身だしなみを忘れなかったという誇りなのだ。
いや、それだけでなく『葉隠』は、毎朝冷水で顔を洗うことをすすめ、頬紅もつねに用意すべきことを説いていた。
冷水で顔を洗えば、首を討たれたときに顔色が変じないことを言い、頬紅は気分のすぐれない時にこれをつけて青ざめた顔を人に知られないためなのだ。
死にのぞんでもいささかの後れをみせないというのが武士の心得なのである。
もちろん、このようなことが言われるのは、その反対の事実も多かったということであろう。
死にのぞんでは恐怖を感ずるのが人情というものである。
戦場において、いざ進撃の命令が下り、敵の姿を真向いに発見したときには、誰も目の前が暗闇のように閉ざされるということが昔の軍記物にも記されている。
加藤清正のような槍の達人でさえ、その槍が手に重く感じられたという。
戦国の武将にでもそれがあったとすれば、戦争がなくなって、平和の時代を生きてきた武士たちが、死にのぞんで取り乱すのは当然のことであろう。
彼らは、島原の乱以来、甲(かぶと)も鎧(よろい)も櫃(ひつ:箱)に入れたままなのである。
武器をとることよりも、筆や硯(すずり)に向うことが普通の生活に入っていた俸給生活者なのである。
しかし、武士が武士である理由は、今日の俸給生活者のように時間の単位でその労力や知識を提供しているのとは違っていた。
彼らは、その全生命を主君にあずけているのである。
そして、武士としての使命感というものが、その生活を支えていた。いや、いなければならなかった。
それは山鹿素行も言っているように、武士には、他の農民や工匠、あるいは商人等と違って、衣・食・住に関する仕事が免除されているのである。
もっと簡単に言うならば、彼らは労働というものをしないで生活できる特権をもっているのだ。
そのことは、他の何者にもまさって立派に生きなければならないということにもなる。
つまり他の身分の人々が、日常の生活に追われて、忘れ勝ちになる道徳や人間の生き方の根本を常に心掛けていなければならないということなのだ。
私は、そうした武士の教育というものはかなり徹底していたように思っている。
都会の武士には、いわゆるサラリーマン化した武士も多かったが、地方に行けば気骨のある武士が少なくなかったとみてよいであろう。
ところで、私が言おうとしているのは、そうした武士や、それから大きな影響をうけた庶民の生き方であり、同時に死に方であった。
何も、立派な生き方や死に方をしたのは、武士だけではないのである。
百姓一揆の指導者たちのなかには、武士にまさるとも劣らないほど立派な最期を遂げたものがあったことは、多くの物語などで知られているだろう。
もちろん、一揆の指導者だけではない。
伊予の百姓で作兵衛という人は、飢饉の年に一村すべで餓死したなかで、やはり同じように餓死してしまったが、彼が枕にしていたのは籾(もみ)の袋であった。
それは、何も彼も食いつくされたあとに、やがてくるであろう種まきの時節に、一袋の籾も残っていないというのでは残された百姓が困るであろうという耕作者の責任感があえてそれをなさしめたのである。
米をつくるのは誰でもない、それは百姓なのだ。
その責任をあくまでも守るという自立の精神がなかったならば、死を前にしてそのようなことはできなかったに違いない。
それはそれとして、長井雅楽の最期というものをこれから述べてみたい。
私が、長井雅楽という人物に大きな興味を待ったのは、あの最初にかかげた詩もさることながら、彼のいかにも武士らしい最期なのである。
このような感動的な最期をみせることのできる人を、単純な俗論派という一つの色彩で塗りつぶしてよいかということであった。
二
吉田松陰の高弟で、高杉晋作と並び称せられた久坂玄瑞(くさかげんずい)は、この長井雅楽を弾劾(だんがい)することまるで仇敵のようであった。
そして、長井を自刃にまで追いつめたのは、あらゆる手段を弄して、執拗にくいさがっていった久坂の執念といってよいものがある。
その久坂の数えあげた罪案をみると、長井の罪は次のようなものであった。
一、安政五年の歳、一藩の士気が大いに盛りあがって、長州落の勤王の志が確乎としたものになる機会があったが、そのとき脆弁を弄して、主君の厚い志から出た御直書を骨抜きにしてしまったこと。
一、吉田松陰という本当に尽忠報国の心の深い人物を、狼のような幕府の役人に売り渡したこと。これは、長井ほどの重要なポストにいたならば何とか防げたはずだ。その努力もしないで、幕府の意のままにそれを萩に伝える役目を引きうけたのはけしからぬことだ。
一、安政の大獄で、青蓮院宮(しょうれんいんみや)・近衛関白・尾張侯・水戸侯・一橋卿、それに越前・土佐・宇和島などの藩主がすべて幕府から処罰をうけているというのに、その弾圧の張本人である大老に媚(こび)をつかって、藩主の昇進をうけていること。
一、この度の藩主の参勤(さんきん)交代に際して、藩主が病気であるにもかかわらず、それを何か起るか分らないような政争の地にお連れしたこと。これは、たとえ藩主の意志であろうと、臣下としてはとめるべきだ。それをしないという情をわきまえない処置。
一、安政五年以来、朝廷では攘夷のお考えであったのに、公武一和を名として、その実外国との貿易を許すという勅状を下されるように仕向けたこと。 |
というようなことになっている。
この罪案が、ことごとく長井の責任であるというならば、あるいは彼は俗論派と称せられるものの代表といってもよいかも知れぬ。
俗論派というのは、思想的には吉田松陰の流れをくんで、やがて幕府との対決に入ってゆく尊王攘夷派に対立した一派なのだが、別な言葉でいえば、幕府支配の体側に順応してゆく一派といってもよいであろう。
しかし、私はここで今、長井にかわって、久坂の罪案の一々が当っているかどうかを明らかにするつもりはない。
ただ、長井はこのような形で、久坂らから徹底的に憎まれ、また追及をうけていたということである。
ただ、そのような追及があるにもかかわらず、彼がなかなか処罰をうけなかったのは、藩主父子の大きな信頼があったからだ。
そしてまた、重臣たちにも本来ならば、自分たちの役目を長井に押しつけてきた責任というものがある。
長井は百五十石の大組の士でしかなかったのだ。
その一藩の政治ということを考えれば、長井にすべての責任を転嫁して、彼一人を始末すればそれですむという気持にはならないのである。
文久二年の七月四日にその職を解かれ、二十二日に親類預かりになって以来、十一月の末頃まで決断がつかなかったのもそれであった。
十ー月の末に、切腹の決裁が下ったとしても、なおそれは正式に長井家に伝えられたものではなかった。
年を越して翌年の二月になってようやく決行ということになったのである。
長井はその間においていろいろと身の廻りの整理をしていたであろう。
辞世の句などというものも、その間に練っていたものに相違ない。
それは、同時に彼の死に直面したときの心の落着きということにも通ずるのである。
もちろん、この長井に対する裁決を不当とする人々も多かった。
彼が公武一和の航海遠略策をもって、京都と江戸の間を往復したのは決して私の心から出たことではない。
それはすべて藩の正式な機関の手続きを経てきめられたものである。
ただ、彼以上によくそのことを処理する者がいなかったため彼がその任にあてられただけのことなのだ。
責任があるとすれば、それは藩の全体であり、最後は藩主ということになる。
その責任を彼一人にとらせてよいものかということであった。
そして、彼一人の責任ということで考えるならば、彼が航海遠略策を正親町(おおぎまち)三条実愛(さねなる)に説明したとき、それを文書で出すように言われて草した文章の中に不敬の言葉があったということである。
しかし、その不敬の言葉というのも「謗詞似寄」(ぼうじにより)の言葉という表現で示されたもので、「不敬の言葉と思われるような」言葉なのだ。
だが、そのような言葉のために、久坂らは鬼の首でもとったように喜び、ついに藩主にせまって、これを処罰させた。
しかし、その言葉が、どこに一人の重臣を死に追いやるまでの意味をもっていたか。
これは、のちに毛利登人(のりと)や北条瀬兵衛などが直接に、その出所である中山忠能(ただやす)や正親町三条にただしたところでは、まことに曖昧模糊(あいまいもこ)たるものであった。
中山忠能は、海外との交易の個所を問題にしながら、
「さよう、本朝が隆盛であった時代の交易と、今の時代の蛮夷が非礼横行をきわめておる場合の交易とを一緒くたにしやって、朝廷が貿易を許されないのは分らぬなどと申すことがのう」
ということであり、正親町三条は、
「どこが謗詞かと申されるようじゃがの、あの文章のどの部分ちゅうことはない。まあ、しいて言えば全体にわたっていえることかのう」
という調子なのである。
「そのために雅楽めは、きびしい処罰を申しわたされたのでござりまするが、もう少し、御説明いただきとうござります」
と追及すると、
「何分、朝議でそのようなことに決ったもので、それ以上くわしくお聞きなさると、かえって不敬にあたりまするぞ」
と答えるような始末であった。
そこで、両人が両公家の口裏から察したところによると、
「朝議、朝議といって、さも大変なことのように言って廻っているが、これは大したことはござらぬの」
という結論なのである。
これは六月六日頃のことであるが、七月半ばには、学習院で、議奏、伝奏の両大納言と、中山・三条・坊城・野宮(ののみや)等、有力な諸公卿列席の上、
「長井雅楽申し出侯書き取りの内、膀詞似寄(ぼうじにより)の議は、一件委細演説に及び侯通りの叡慮(えいりょ)にあらせられ、右思召しの趣旨、伺ひ方相違の段は、固く御遠察御氷解の御事にて、御選意あらせられず侯間、以来とても必ず掛念なきやうとの御沙汰あらせられ侯こと」
という書付が長州藩に下されているのであった。
「膀詞似寄」などということ自体にすでに謀略があったのだが、そのことについては今はふれまい。
ともかく、その冤罪(えんざい)は消えているということである。
げんに、長井断罪の決裁をもって萩に帰ってきた毛利伊勢(いせ)は、長井の無罪を主張する老臣たちに散々に罵(ののし)られて、ついに病気にかこつけて城内に出仕することをやめてしまったくらいであった。
萩の城内には、長井の断罪を否とする者が圧倒的に多いのである。
そしていま長井をここまで迫いやった一派のことが、さらに彼らの助命運動を盛んにした。
萩の城中を自由に閲歩(かっぽ)できる人々は、久坂らの一派を「軽輩の分際で」と苦々しく思っていた。
あの連中が長州藩を代表したような形で他藩と交渉を持つことにも、それ以上の我慢のできないものを感じていた。
ここで、長井を助けなければ、彼らの面子は丸つぶれなのである。
老臣毛利隠岐(おき)は、城中の意見に賛成して、長井の処罰をできるだけ延ばそうとしていた。
やがて藩主が帰国する。藩主は、すでに一月二十二日に京都を出発して一路、藩地に向っているはずだ。
遅くとも二月の初めには萩に帰ってこられるであろう。そのときこそ、一同で嘆願すれば、長井の助命は困難ではない。
藩主自身が、誰よりも長井の助命を念願しているはずである。
そうした動きのなかで、長井雅楽がどのように考えていたか。
彼も、恐らく藩主の帰りを待ちわびていたに違いない。
ながい間、その側近に仕えて、何も彼も分ってくれているはずの藩主だった。
自分を助けることができない状態であるとしても、その意のあるところだけは心に収めて死にたいと思っていたであろう。 いや、その藩主がこの地にあるという安心感の上に立って腹を切りたいというのが、彼の本音であったかも知れない。
しかし、その藩主の帰国を恐れる人々もいた。
そして萩の城中にある人々の動ぎきが、なおもそうした人々の不安をかきたてた。
このままの情勢で押し移って行くならば、長井の罪は減ぜられるであろうという予測は当然に立つのである。
長井を生かしておいては、これからの運動に大きな障害となるだろう。
いまのうちに、つまり、藩主が藩内に足を踏み入れない前に既定の方針通り自刃させなければならない、というのが彼らの考え方であった。
藩主は、二月七日に岩国領に入る。
そこで支藩の吉川監物(きちかわけんもつ)に逢うことになっている。
長井はそれまでに処分してしまわなければならない。
もしそれを過ぎるようなことがあれば、これまでの画策はすべて無に帰するのだ。
何が何でも、長井を消さなければならないとする陰謀が、ついに二月の六日をその処分決行の日と決めたのである。
その前日、家老の福原越後は特に許して、彼を親類の家から自宅に帰らせた。
家族の者に、別れを告げさせるためである。
福原は、のちに蛤御門(はまぐりごもん)の戦に出兵の責任をとって自刃を命ぜられる三家老の一人であるが、それだけに長州藩を代表する老臣の一人でもあった。
彼は、毛利伊勢が病気として引っ込んでしまったあとの処理をまかさせるために十二月になって萩に帰されていたのだ。
福原としても、長井の罪状が死に値するものかどうか判断がつかないわけはなかった。
しかし、彼は京都における大勢が大きく変り、天下の輿論がただひたすらに攘夷の方向に突っ走っていることを目のあたりに見ていた。
幕府さえも安政の条約を破棄して、攘夷の実行に踏み切ることを誓わなければならない情勢に追い込まれようとしている。
長州藩は変節したのだ。そして、いまはその攘夷運動の第一線に立って進んでいる。
昨日までの航海遠略策はどうしたのだ。
あまりにもそれは手の平をかえすような態度ではないかとなじられたとき、藩としてそれに答える返辞があるだろうか。
あるとすれば、それはすべての責任を誰かに負わせることである。
もちろん、それには相当な人物が必要だ。長井雅楽という人物は、誰知らぬ者はない。
いやしくも政治を語るほどの者であれば、彼がどれほどの力量を有していたかは語らずして十分である。
藩論をまとめ、幕府を動かし、朝廷さえもその意見には引き込まれたことがあったではないか。
止むを得ぬ大きな犠牲である。福原越後はそう思ったに違いない。
しかも、それはすでに祭壇の前まで持ち運ばれた犠牲だった。
それを今更、ひっ込めることは世間の目をだましたことになるかも知れない。
越後の心のなかにも、藩主が帰国して事が面倒にならないうちに、これを始末しておこうという考えがないではなかった。
三
二月五日の夕べ、長井雅楽は自宅に引きとっていった。
長井の家は父祖の代までは三百石の知行で馬廻役であったが、雅楽四歳のとき病死したため、未成年相続の規定によって百五十石に減らされ、家も城下から少し離れた松本川に近いところにあった。
長井家が禄高を減らされたのは、後嗣が未成年者であったためである。
長井の家の近くには、前原一哉や周布(すふ)政之助の屋敷があった。
しかし城下から少しく離れてあるというところは禄高の低い者達が多く住んだところである。
私は、その長井の屋敷跡を訪れたことがあるが、街のはずれのようなところで、周囲は畑が多く、そこに余り大きくない門がぽつりと一つ立っていた。
もちろん、家はこわれてなく、門の中はただ畑があるのみであったが、私にはその家のたたずまいも分るような気がした。
一世に名なとどろかせた人にしては質素な住居だったようである。
ついでにいうと、彼の家から少し川寄りのところに吉田松陰門下で松陰に最も忠実であった入江九一(きゅういち)の家があり、そこから川の向うが松下村塾のあった松木村である。
品川弥二郎の家もその川を渡ったところにあった。
その辺りは、萩藩でも下級武士や足軽の多く住んだところで、それらが松下村塾に通って時代の鮮烈な息吹きを吸ったものなのだ。
だから、長井の邸は川を隔てては松下村塾の教えをうけた者たちが居り、付近も、周布・前原・入江というような反対派のなかに、ぽつんと一軒立っていたという恰好だった。
長井が親類の者に送られて自宅に帰った夜、その家の周辺には何か異常な空気がはりつめたようにあったという。
もちろん、デマを流されていた。
長井の助命嘆願運動をやっている小笠原弥右衛門らの数十人が、彼を奪って萩藩のこれまでのやり方を一挙にひっくり返す行動に出るかも知れないというような類いである。
そして、それはある人々にとっては、またそのようになって欲しいと願う心であった。
もちろん、長井雅楽がそのようなことを望むはずはない。
もし、彼がそれを望んでいたとしたら、小笠原弥右衛門をたのむ必要はないのである。
は、意を決して城中に登ってゆけばよかった。
そこは、圧倒的に彼を支持する者たちで占められているはずである。
長井が不意の登城をして、決死の覚悟で事情を説明し、公武合体派の奮起を促すならば、彼の智弁のほとばしるところ、何人といえどもその前に立ちはだかる者はないのだ。
尊王攘夷などといって駆け廻っている少数者は、忽ち萩城から放逐されるであろう。
そして、その上にかつがれて、さも世の中が分ったような顔をしている一、二の老臣も、なす術(すべ)もなく長井の意見に従わざるを得ないことになる。
そこには、厳然たる意志をもった一大勢力ができ上るのだ。
しかも、それは城郭をもって藩地にある。京都や江戸のようた出先機関ではないのだ。兵も、正規軍がある。
そこに藩主が帰ってくれば、藩主は此方の側に迎えるとする。
そして、がっちりとこの藩を固めれば、江戸や京都で走り廻っている連中は、糸の切れた凧のようなものだ。
長井雅楽の頭の中にそのくらいの考えが浮ばなかったはずはない。
これが立場を代えて高杉晋作だったら、あるいはそれをやったかも知れぬ。
いや、あの下関の蜂起などをみていると、きっとやったに違いないと思う。
しかし、長井にはそのことはできなかったのだ。
彼は自らを狂としながらも、それは高杉のような狂ではなかった。
高杉の狂は、そのとぎすまされたような智謀が、すぐに間髪を入れず行動となってほとばしるところにあったが、長井の狂はつねに頭脳の中で反転していた。
すべてが自己に反ってくるのである。
それがいよいよ彼の頭脳の冴えをみせるのだが、しかしそれだけにまたそのことが、行動に枷(かせ)をはめた。
いや、それよりも、そうして起る内戦にも似た藩内の党争が怖かったのである。
たしかに今、自分は勝つことができる。
しかし、この勝利を永久のものにすることができるかどうか。
敗北を認めた者たちが、このまま引込むと考えるのは余りにも考えが甘いということになる。
とすれば、一ばん困るのは誰か。それは藩主ではないか。
自分をあれほどまでに信頼し、またあれほどまでに重用してくれた恩人である。
この大恩ある藩主を窮地に陥れたくはない。
ここのところは、自分自身を犠牲にすることで、そのことを避けるべきだ。
長井は、そのように決心し、覚悟を決めていたのである。
しかし、その心は悟りの境地などというものとは凡そ遠くはなれていた。
すべてを己れ一身の不徳にして、何も彼も許して死ぬのではないのである。
いや、それどころか憤りを以て憤死してやるつもりであった。
彼の帰った晩に、その周辺の空気が異常な緊張をみせたというのも、そうした長井の気持の反映であったかも知れない。
もっとも、藩の当局でも、助命派の動きを警戒して、町の辻々に警備の者を配置したりしていた。
長井家の周りにも、監視の限を光らせていたという。長井は、家に帰ると早速に仏間に通った。
彼が頭のなかには、四歳のときに失った父の面影があり、そして毛利家の盛衰と共にその運命を共にしてきた祖先の語り草があった。
この家を今、自分の代で滅びさせようとしている。
彼は、まずそのことを父祖の霊に詫びたいと思ったのだ。
彼の後ろには、妻と嫡子の与之助が坐っていた。
妻に対して、断罪書は「女性の儀は御構いなく差し置かれ侯こと」と書いてある。
これは何とかして生活してやってゆけるであろう。
しかし、嫡子与之助は「父の科(とが)逃れ難く国退き仰せつけらるべきところ十五歳以下につき、先づ親類へ預け置かれ侯こと」という処置なのだ。
親を失い、その罪を負うて親類預けになる子供の不憫(ふびん)さが思わず長井の目をうるましたが、しかし彼には、これから済ませておかなければならない仕事が重なっていた。
親戚の者が、ひっそりと別れの挨拶にきては退っていった。
そうした親戚の者たちのなかで、長井はとくに福原又四郎という青年を選んだ。
又四郎は古田松陰の門をもくぐったことのある青年で、松陰から、「外見はやさしく見えるけれども、才知があってこれを補っている。そして一度正しいと思ったことは絶対にゆずらない」というように評されていた。
その人物に長井もほれ込んでいたのだ。
ときに又四郎二十一歳である。即ち、その又四郎に介錯として自分の最期を見届けて欲しいというのだ。
もちろん、又四郎もこの頼みを拒みはしなかった。
長井は多くの書籍や文書の中から、これだけは残して置きたいというものを選りわけていった。
そして、それを二、三の文庫や櫃に納めると、夫人をふり返って、
「後のものはそなたの心にまかせるが、これだけは残しておいてくれ、長井の家とわし自身じゃと思うての」
といった。
「はい、きっと守らせていただきます。それにしても、長いあいだの御忠勤、ごくろうさまでございました。
また私のようなものをここまで……」
夫人は妻として、かねて夫に伝えなければならない心を、このようにも整理していわなければならないと思いながら、あとの方は声にならなかった。
「それにしても殿様は……」という声が咽喉のところまで出てくるのだが、それは未練というものだろう。
未練は、この場においては最も禁物であり、そして武士の妻の口に出すべき言葉ではなかった。
折角のお気持に傷をつけてはならない。彼女は必死にこらえていた。
そしてその夜、彼女は親子三人の膳に福原又四郎を加えて、おそい夕食を用意したのである。
座の空気はとかくしめり勝ちであった。しかし、口にこそ出さないが
「私は、明日は立派に死んでみせるぞ」
という気持が、彼の顔に凛然たる色をみせて、一つの救いとなっていたようだ。
文四郎も、そうした叔父の顔を仰ぎみながら、武士として生きるものの厳しさを改めて思い知らされるような気がしていた。
酒も用意されていた。どのくらいそれがまわったのか私は知らない。
しかし、ほどよいところで又四郎は与之助を連れて別間に下っていった。
四十五歳という男ざかりで、この世にいとまを告げようとする長井に、心ゆくまで夫婦の別れをさせてやりたいというのが又四郎の気持であったろう。
私はここで、三島由紀夫の『憂国』という小説を思い出す。
しかし、私は世に言うところの作家ではないので、長井雅楽の最後の夜がどのようであったかというところまで筆を進めることはできない。
二月といえば、まだ裏目本の風は北から吹く。その季節作風が松本川に茂る葦の葉をゆるがせながら、長井の家の雨戸をもたたいて過ぎただろう。
その内側に、明日の死をみつめながら長井とその妻が枕を並べていたというように記すのが、歴史家というものの限界だということにしておこう。
四
あくれば、いよいよ六日であった。
長井はまず行水を使って下着をかえ、髪を整えて鬢(びん)にはたっぷりと香油をふくませた。
もちろん爪の手人れにもぬかりはない。軽い朝餉をとったのち自室にかえっていった。
そこには、このことのために用意した死の装束が置いてあるのだ。
彼は、静かにそれを膝の上に置いてみた。
立派に死んでやろうとする心の底に、あの憤りがふつふつとたぎっているのである。
天魔になる男の死に衣装だ、見てくれ!
そして彼は、一本の刀をとり出した。
「又四郎、又四郎」
声に応じて、福原又四郎がその前にいざりよった。
「この刀が、今日、お前が介錯に使う刀じゃ。長井家伝来の刀でよく切れるわ。
わしは独りで最後まで果すつもりじゃが、しかし思わぬ不覚をとることがあるかも知れぬ、そのときは頼んだぞ。
叔父とても容赦はいらぬ。存分にこれを揮ってくれい」
といいながら、傍らにあった夫人にも、最後の別れを告げた。
私のこのあたりの描写は、もっぱら、得能晩山の『幕末防長勤王史談』によっている。
というのは、この著者は当時まだ在世していた福原又四郎、のちに改めて今田又市翁からその場の状景を、くわしく語って貰ったというから、最も確かな史料であろう。
いまの私には、それ以上にその場の状景を知る手段はない。
しばらくするうちに検使の役人が到着した。福原又四郎がこれを迎えて、表八畳の間に通した。
正使は国司信濃(くにししなの)、副使は目付上席糸賀外衛(とのえ)で、それに目付役が十七名もつくという仰々しさであった。
もちろん、八畳の部屋にこの人々をすべて収容するわけにはゆかない。彼らは、次の間から式台にまで居並んだ。
長井は、そこに出て下座から挨拶をした。
それに対して、正使が荘重な口ぶりで断罪書をよみあげる。
断罪の理由は、あくまでも膀詞似寄(ぼうじにより)の言葉にかかっているのである。
中山忠能が語ったという、朝威が盛んなときの開国と、現在の夷狭(いてき)が横行しているときの開国とを一緒にして、幕府の開国を認めるといったことが怪しからぬとする一点なのだ。
そして、それに付加えて、「重大の御用筋を容易に相心得、我意を主張し、朝議を軽蔑し、御旨意を取失い、叡慮に相叶(かな)はず、かどかどの恣(ほしいまま)の所勤不屈(ふとどき)至極」というような文章も長井の耳に入ってきた。
百五十石の直(じき)目付が、この時代に、これほど大きな、自由自在の言動が許されていたのか。
長井は、罪案というものはどのようにでも書けるのだと憤りをこえた奇妙な感情にさえおそわれるのであった。
読み終った正使は、それを長井に渡して、長井はそれを型通りに見、再び正使のもとにかえした。
正使の国司信濃は、このとき二十二歳の青年で、攘夷派の家老であったが、長井の落着き払った態度にはすっかり感心してしまっている。
長井は、ここで一たん退席したが、すぐに衣服を改めてその場に戻ってきたという。
これは、公式の立場を離れて、一言いい残したいことがあったのだ。
それは、福原によれば、自分は頑迷な保守派の連中とは関係がないということであったらしい。
しかし、この弁明は、副使糸賀によって、にべもなくはねつけられた。
そのようなことを今更言って何になるというのが糸賀の考えであり、彼はまた、このような緊張から早く逃れたいという気持が動いていたのであろう。
長井と糸賀のあいだに、気まずい感情が流れて、二言、三言はげしい言葉のやりとりがあった。
争って無駄なことをしたと思った長井は、つと立上って奥の間に退いた。
切腹の場所をしつらえるためである。
正面床の前に、四枚の畳が持ち込まれ、それが二枚ずつ裏返しにして並べられた。
その上を白い布でおおい、白布の台の中央にあたるところで、白羽二重の座布団が置かれるのである。
そこで、正使と副使の二人は、席を正面から横の方に移した。
そこに長井が、水色無紋の衣服、それに水色の裃(かみしも)姿で現われてくる。
彼は、落着き払った姿で席についた。そこへ、福原又四郎が白木の三方に土盃をのせて進みより、酒三献を汲んだ。
そして、それが後へひかれると、次には、いよいよ短刀をのせた三方が出される。
その短刀の下には、半分に折りたたんで白紙が一帖。
長井が、次の動作に移ろうとしたとき、この悠揚せまらざる姿で死に着こうとしている偉丈夫の姿に感激したのか、国司信濃が正使の席をはずして、すべるようにして前に出た。
そして、長井の耳に近く、今このようなことになったが貴方の誠心はすべての人が知っていることだ。
安心して死んでゆかれよ、私も立派な武人の最期をみせて貰って光栄であるというような意味のことを述べた。
のちに、蛤御門の戦の責任をとって、長井と同じような方法で自決する運命にあった国司信濃だが、何か虫が知らせたとでもいうのであろうか。
この国司の言葉で、長井も武士の情けというものが知ることができた。
感謝の言葉を述べたあと、「お許しあれ」というと、彼のロから朗々たる謡曲の一節が流れはじめたのであった。
「弓矢八幡、箱根の権現も照覧あれ、それがしは存ぜず侯。
さてみづからが親の敵(かたき)をば、たれと申すべき。
いや、敵とは夏川(なつがわ)の糸、筋なき人の言ひごとを、かまひて用ゐ給ふなよ」
『調伏曾我(ちょうふくそが)』の一節であるが、しかし、この言葉の一くぎりにこそ、彼の訴えたい真実があったのだろう。
慶長十二年に、若狭国で起った強訴の罪を一身にひきうけて磔(はりつけ)の刑に処せられた松木長操(ながもち)も、捕吏を前にして悠々と謡曲『田村』の一節をうたったというが、何か日本人の心のなかにはそのような心情の型があるのであろうか。
その謡曲の一くぎりがすむと、長井は静かに肩衣を脱ぎ、三方を引きよせ、白紙を指先に巻いで首と腹をぬぐったという。
そして、残りの白紙で短刀をつつむようにして持ち、刃先一寸を余して右手にかまえ、左の手で三方を背後にまわした。
こうした儀式の進行と型は、長州藩において後の模範になったようである。
それから、長井は帯を下げて腹部をくつろげ、ゆっくりとそれを撫でおろすようにして、左の脇腹をさぐり、その手を右手の拳の上に置くと、一気にそこに突き立てた。
そして右の方に向ってきりりと一直線に刃を走らせたのである。
そこで、切先をかえして上方に抜き、そのまま頚動脈に持ってゆくのだ。
ところが、長井は、あまりにも深く刃を突き立て過ぎたようだ。
気性の激しい人物には、往々にしてこのことがあるようである。
そのために、思いもかけないほど多量の血液がながれ出てきた。
長井は、その腹部を左手でかばったまま、右手だけで咽喉をはねようとしたのだ。
しかし、腹部の重傷が彼の右手を狂わせた。刃は急所をはずれたようである。
介錯なしに自決したいという一念は、それほどの痛手にも屈せず左手を腹部から右の拳に戻すと、いま一度と血糊のふき出している咽喉首に突き立てた。そ
して、その刃をはねるようにして抜くと、その短刀を畳の上に突き、ゆらりとゆるいで前方に伏せた。
型の通りにいったのである。
ところが、このときも急所を外れていたようだ。
長井は、ぐっと首をあげ、最後の力をふりしぼるようにして身体を起した。
正坐にかえったのである。そしてじっと局囲を見廻したという。
また目が正使から副使の糸賀に向けられたとき、糸賀は背筋を走るような悪寒におそわれて、頭をあげることができなかったという話も残っている。
又四郎は、ここで介錯の役目を果すときがきたと思った。彼はすぐにその側に進みよった。
そして左の小脇に長井の身体を抱き、右手にその短刀を持たせて、これを助けながら一気に咽喉をはねさせようとしたのである。
しかし、長井は左の手を振った。一人で死ねる、まだよいという意志表示なのだ。
又四郎は手を放した。長井の意志とは反対に、もう身体が動かないのである。手が徒らに宙に舞っている。
又四郎は、長井から渡された刀を抜こうとした。
しかし、あくまでも自分の手で死のうと最後の力をふりしぼっている叔父の心を思うと、ここで首を打ち落すことがためらわれた。
彼はもう一度、叔父の身体にかぶさるようにして坐り、そしてその短刀を咽喉首に向けてあてがってやった。
そのとき、長井はまだそれだけの力が残っていたかと思われるほどの勢で、自分の気管を絶ち切ったのである。
彼の呼吸はそこで絶えた。しかし、身体はまだ坐ったままであったという。
又四郎が、その身体を静かに横にして、両手を合掌させた。切腹の作法が型の通りに終ったのである。
そして、「智弁第一」とうたわれた長井雅楽の一生もそこで終りを告げたのである。
長井が死んだあと、多くの人々は「惜しい人物を殺した」といい、また彼の反対派の中にも、「あれほどの人物を何故、自分たちは死に追いやったのだろうか」と反省する人々がいた。
しかし、誰がどのように言おうとも、長井雅楽は再び生きて帰ることはなかった。
いや、長井が心配して高杉小忠太に依頼したようなことも現実におこっている。
即ち、長井は永年の友人であった高杉に、最後の手紙を書いた。死の直前のものである。
その中に次のような一節があった。
「去五月、小生出府仰せ付けられ候より、逐々(おひおひ)御注進申し上げ候書状、先達て江戸に於て造酒(みき=内藤)より政之助(周布)譲蔵(兼重)間へ御記録相調べ候に付、入用との事にて貨渡仕候由に候、
左候へば今以て御用所に之れあるべく存じ奉り候、
尤(もっと)も小生かやう仰せ付けられ候次第に付、邪魔にも相なるべく候故、頓(とみ)に反古(ほご)に仕り候はんも計り難く存じ奉り候へども、相成るべくは何卒御役座へ御取返し置きつかはされ、御間隙の節、御一覧つかはされ候はば大慶之に過ぎず、
左候はば御建白の御初発(おこり)、京都・関東に於て小生御不奉公の次第一通りは相分り申すべく尚又(なおまた)、 右書面せめて御役座へ残し置かれつかはされ候はば本懐これに過ぎず存じ奉り候、云々」
という言葉であった。
長井は、彼の報告書や記録の類いが抹殺されることを恐れていたのである。
これまでの歴史は、つねに勝者の歴史であった。
敗れた者はそれにどれほどの理屈があろうと、またその事が正しい理由を持ったとしても、すべて抹殺されてゆくのである。 その人間を抹殺するだけではなくて、一切の記録も、公式の文書までもふくめて消し去られてゆくのが歴史というものの常道であったようだ。
この手紙を読んで、あの几帳面すぎるくらいの高杉小忠太(高杉晋作の父)が一体、どんな気持を抱いたであろうか。
恐らく高杉小忠太は、心の千切れるような思いでこれを読み、そして屹度(きっと)、この友のために役に立ちたいと奮い立ったであろう。
しかし、周布や兼重といったような老獪(ろうかい)な政治家を相手にして、この老人にはそのことは不可能のことだったであろう。
私は、この長井雅楽の悲願を思うて、今日あえて筆をとってみたい。
(以下長井の誕生から栄進、失脚までの長文となるので省略)
****************************************
その2 週刊ポスト 2012/3/2
top
no1

no2 top

no3 top

no4 top
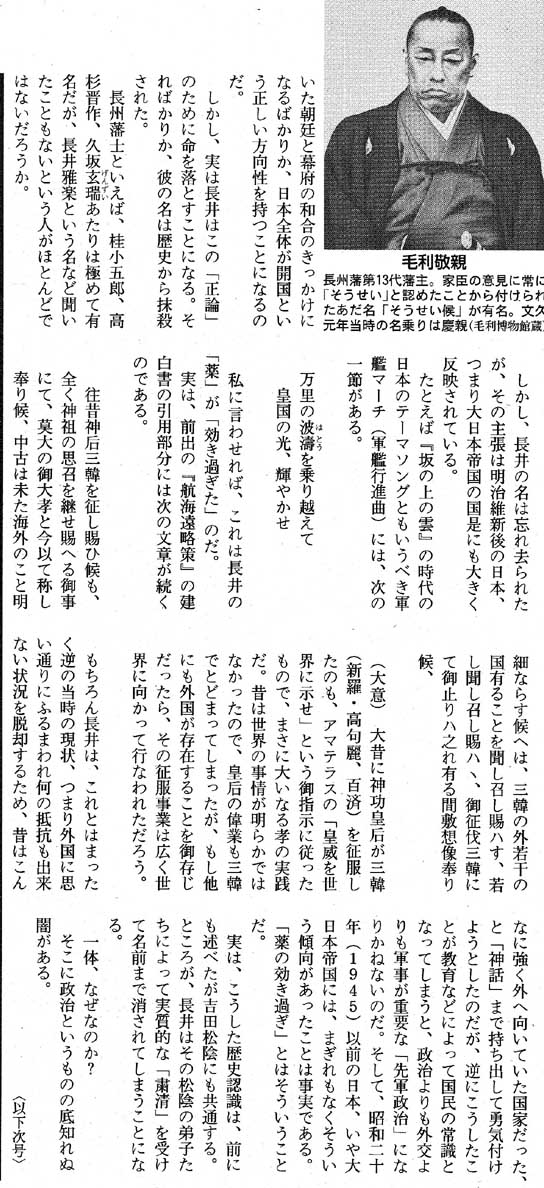
****************************************
その3 週刊ポスト 2012/5/25
top
no1

no2 top

no3 top

no4 top

top
****************************************
|