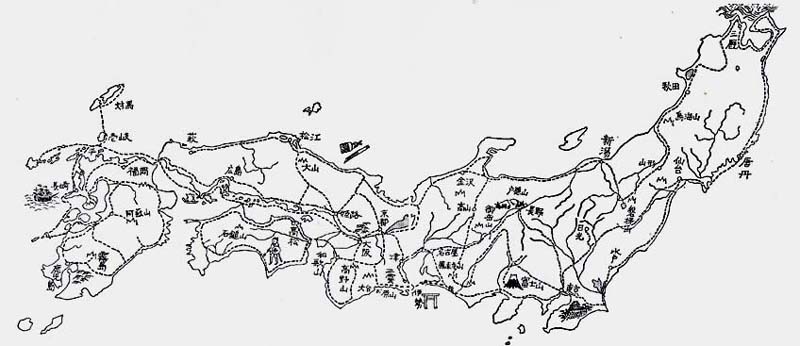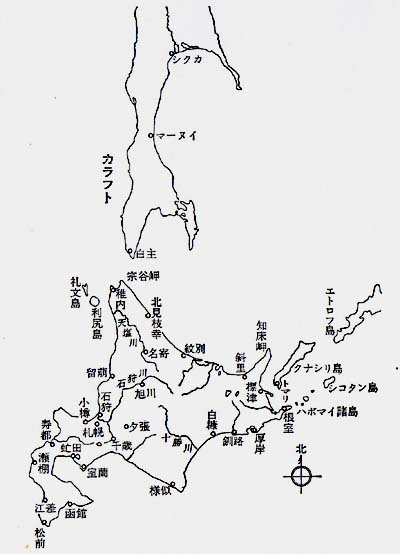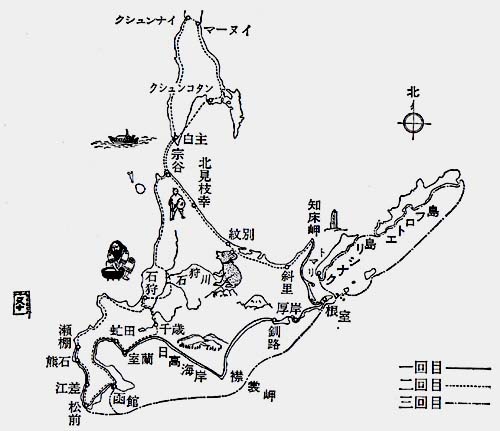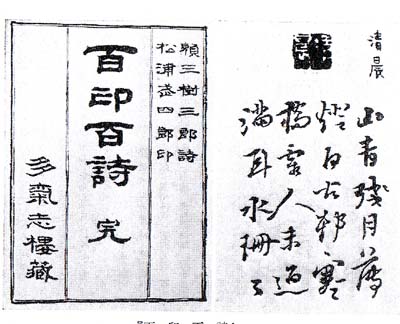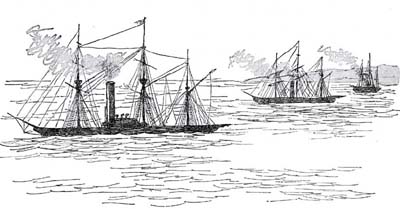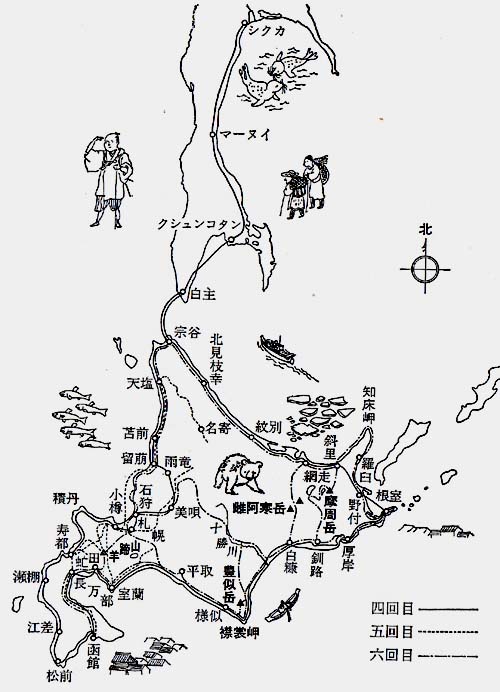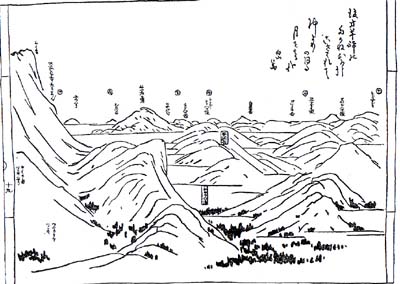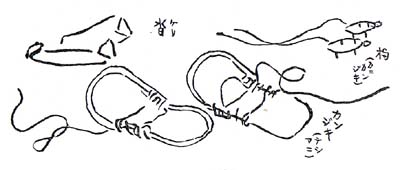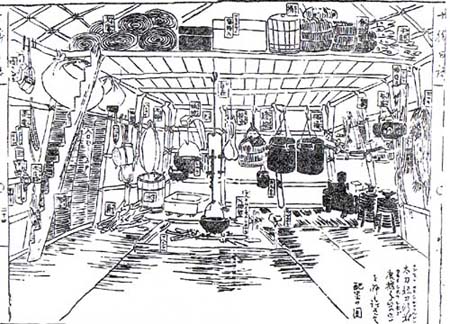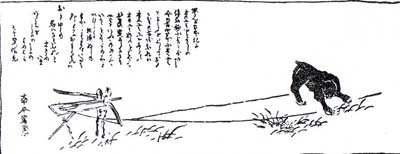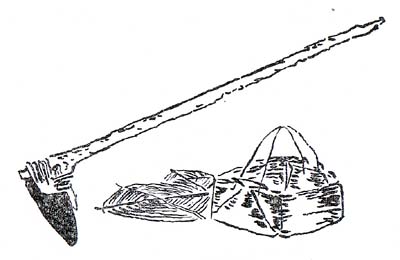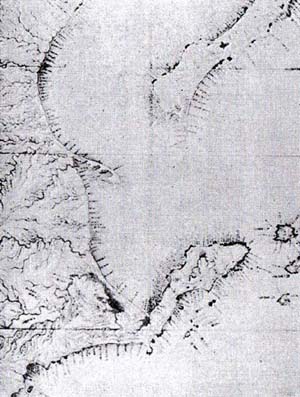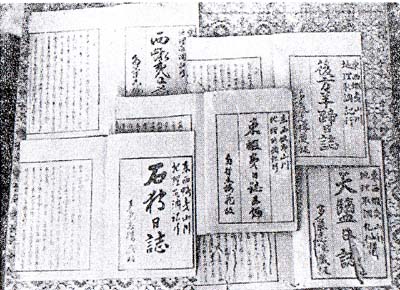|
****************************************
間宮林蔵 松浦武四郎 阿部正弘 長井雅楽 川路聖謨 小笠原長行 小栗忠順 HOME
北海道の名づけ親・松浦武四郎
(『白い大地』吉田武三著 日本史の目9 さ・え・ら書房 昭和48(1973)年刊)
あとがき 吉田武三 ――自然を愛し、人を愛し――
top
北海道という呼び方は、いまの私たちからみれば、ごく自然に親しまれていて、ずっと昔からそう呼び習わされていたように感じられます。
けれども北海道という地名がきまったのは、明治二年(一八六九)のことで、まだ百年とちょっとしかたっていないのです。
北海道はずっと長い間、えぞ地とよばれていました。
そのえぞ地に、北海道という名前をあたえたのが、この本の主人公、松浦武四郎なのです、
けれども、武四郎の功績は、それだけにとどまるものではありません。
本文でもしるしましたように、大変広い分野にわたって、すぐれた仕事を残しています。
普通の人の何人ぶんもの業績を、たったひとりで七十一年の人生につめこんだといっても、いいすぎではないでしょう。
これだけの人物でありながら、世間にはあまり知られていません。
かんじんの北海道でさえ松浦武四郎に関心がよせられるようにだったのはごく近年、ここ十年ぐらい前からのことなのです。
どうしてこんなことになったのでしょうか。
それには、いくつかの理由が考えられますが、ひとつには武四郎は、明治三年に開拓判官をやめて、それからというもの、なんの官職にもつかず、全くの自由人として一生をおわっだことがあげられます。
明治維新がおわって新しい政府が発足すると、新天地北海道は多くの人の注目するところとなりました。
屯田兵制度をもうけたり、幕府の遺臣たちの開拓村をもうけたり、また、札幌農学校のような西欧の文明を取入れた新しい学校もできました。
開拓のつち音が高く北海道にこだまするようになったそのころはもう、武四郎は北海道から手をひいていたのです。
いまの札幌から千歳にかけての一帯を、“白い大陸北海道の主都圈としたらいい”という考えを、はじめに主張した人が武四郎でした。
けれども、新しい行政府には名をつらねていないため、武四郎の名は、しだいに忘れられていきました。
また、武四郎は地位や名誉、財産といったようなものに、すこしもこだわりませんでした。
煎り豆が大すきだったということを本文にもしるしましたが、ふだんの自分の生活は、大変質素なものでした。
つつましい日々の暮らしをあがない、旅に出ては帰ってくるとその記録を出版する、それに充分な費用をえられれば、それ以上の欲をかかなかったのです。
このようなことも、武四郎を世間の記憶から忘れさせてしまった原因と考えられましょう。
私が松浦武四郎の研究を手がけるようになってから、すでに十五年をすぎてしまいました。
けれどもこの年月はまだ“十五年”といったほうがよいかもしれません。
日本国じゅうをくまなく歩き、北海道から樺太にかけては、六回も足をふみいれました。
それらの旅の記録をはじめ、広い範囲にわたるたくさんの著述を残しているのですから、そのあとをたどり、武四郎が何を考え、何を感じたかをこまかく知るのには十五年の年月も、けっして充分なものとはいえないと思います。
松浦武四郎というひとりの人物にこころひかれるままに、私は十五年をすごしてしまいました。
武四郎のどこに、そんなにひかれるのかときかれても、簡単にはいえません。
ひとつには、大変自然を愛した武四郎の人がらにあると思います。
今日、自然保護だとか環境改善だとかがさかんにさけばれるようになりましたが、私たちの祖先のすぐれた人たちは皆、自然を愛し、自然としたしみ、自然に従うことを生きるよろこびとし、日々のこころがけとしてきたのです。
しかも自然を愛し自然と親しむこころがけは少年時代から身につけることが、もっとものぞましいことなのです。
科学や経済の発展はもとより大切にはちがいありませんが、自然の貴さを忘れさった科学や経済は、けっして人間を幸福にするものではありません。
武四郎のこの考えは、ひろく人間そのもののことにもおよぼされていきます。
そのあらわれがアイヌへの態度といえましょう。
アイヌはシャモ(日本人)の自分勝手のために、長いあいだ苦しめられつづけました。
アイヌ語をおぼえて、アイヌの多くと直接に話しあった武四郎は、これまでのやりかたが、いかに人の道からはずれたものであるかを、はっきりと知りました。
アイヌもシャモも同じ人間であるという、当然のことを、武四郎は堂々と主張したのです。
いまなら当然のことも、その当時では、大変勇気のいることでした。
武四郎にしてみれば、日本人たちにいじめられるアイヌは、もちろん気のどくに思いました。
けれども、実際に北海道の奥地に足をふみ入れてみると、気のどくなどといった自分は安全な立場にいるということの上に立った気持ちではなくなったものと思います。
本州では想像もつかないようなきびしい気候風土のなかで旅をつづけるには、アイヌから多くの知恵をさずけられないかぎり、武四郎の生命はつねに危険にさらされていたことでしょう。
武四郎自身、アイヌから多くを学び、アイスもまた武四郎から、薬草のことなど教えられ、もちつもたれつの面があったことと思われます。
北海道に前から住んでいるアイヌたちが安心してすえ長く住める土地にしたいという武四郎の考えは地名を決めるときにもよくあらわれています。
あとからはいっていく者は先住者の呼び習わしている地名に従うのがあたりまえだと思ったのです。
「金もいらず、名もいらず、命もいらないような人間でなければ、本当にすぐれた大仕事はできないものだ。」
武四郎は、このような意味のことをいっています。
この自分の欲をすてた考えかたと、人間愛とがバッチリむすびあったのが、武四郎の一生でした。
これもまた幕末から明治の動乱期を生きた、一つのタイプだったのです。
1 大旅行家のたまご top
「ああ、すがすがしい朝だなあ――。」
十七歳の青年、松浦武四郎はわが家の門をくぐりぬけて街道にでると、さわやかな初秋の空気を胸いっぱいすいこみました。
それは天保五年(一八三四)九月九日のことです。
(旅に出るのはこれで二度め、すこしも心配することなどないぞ。)
武四郎は自分で自分に言いきかせるように心の中でつぶやくと、しっかりした足どりで、街道を北にむかって、歩き始めました。
背中には小さな包みをななめにゆわえつけ、着物のすそは、高々と尻」からげ、足には草鞋をつけただけという、かろやかないでたちでした。
伊勢の雲出川の流れを見ながら、武四郎は街道をすすんでいきます。
街道ぞいにたっているわが家は、だんだん小さくなっていきます。でも、武四郎は、ふりかえろうとしません。
(お父さんや、お母さんには気のどくだけれど、私はどうしても旅に出たい。
末っ子のせいか、お父さんもお母さんも、私には特別目をかけてくださったようだ。
でも庄屋とはいっても、四男坊では、ゆくすえどうというあてもないからなあ。
広い世の中へでて、自分のちからでどれだけのことができるか、私は自分で自分をためしてみたいのだ。
お父さん、お母さん、お許しください――。)
心の中で両親にわびると、武四郎は、思いきり背すじをシャンとのばして、いっそう足を早めるのでした。
(さあ、もうめそめそしてなどいられないぞ。武四郎.元気をだせ!)
松浦武四郎は文政元年(一八一八)の二月六日に、伊勢の国一志郡須川村の庄屋の家に生まれました。
いまの三重県一志郡三雲村(現松阪市)大字小野江で、そこには、いまも松浦家の子孫が立派に農器具商をいとなんでおられます。
松浦家の遠い先祖は肥前の国(長崎県)平戸の松浦党といわれ、伊勢に郷士(ごうし)として住みついたのは南北朝のころと伝えられています。
郷士というのは、身分のひくいさむらいで、ふだんは田畑をたがやし、ひとたびいくさとなると、武器をとって戦う人たちのことです。
領地の争いのはげしかった時代には、郷土の働きは、大変重要なものでした。
地方によっては、田んぼではたらいているときも、田のあぜに、よろいや刀をそろえておいて、
「いくさだぞお!」
と声がかかるやいなや、田んぼからはいずりあかって、すぐさまよろいを身につけ、戦場にかけつけたとさえいわれています。
けれども徳川家康が天下をとって、しだいに世の中が平和になってくると、郷士のさむらいとしての働きは、たいして意味がなくなりました。
そして有力な郷士は、庄屋となって、村々を治める役わりをになうようになったのです。
経済的にもゆとりができ、高い教養をおさめた庄屋さんが多くなりました。
武四郎のお父さんも、そういった庄屋さんの一人でした。
伊勢といえば有名な国学者、本居宣長のいたところとしてよく知られています。
武四郎のお父さんは、その本居宣長について学びました。それだけに、神をうやまう心の厚い人でした。
武四郎がものごころのついたときには、お父さんはすでに家を長男にフかせて、楽隠居の身分になっていました。
俳諧をよんだり、茶の湯をたてたり気が向くと近所の川や沼につり糸をたれて半日すごしたり………という、まことにのんびりした暮らしでした。
武四郎は、よくお父さんの相手をさせられました。
“末っ子はとりわけかわいい”と世間でいいますが、確かにそれもあったでしょう。
けれども、武四郎は、“親の欲目”ばかりではなく、生まれつき利口な子供だったようです。
七つのときから近くのお寺の和尚さんについて手習いをはじめると、めきめき上達していきました。
そして、ひまさえあると名所図会(めいしょずえ)などをひろげて熱心に読みふけったり、お父さんの書だながら日本各地の歴史や、産業などについてしるされている地誌を、次々とひっぱりだして読んだりしました。
十歳のときには、お父さんの真似をして、俳句をよんだとも伝えられています。
お父さんにしてみればますますもって、“目の中へ入れても痛くない”子供といったところです。
(この子にはもっと学問をさせてやりたいな。さあ、どの先生につけようか?)
でも、それはたいして考えるまでもないことでした。
(うむ、平松楽斎(らくさい)先生の塾に入れよう。あの先生につけるのが一番だ。)
平松楽斎というのはその頃伊勢の津に城をかまえていた藤堂(とうどう)藩につかえる儒者とよばれた学者でした。
当時三十九歳という働きざかりで、殿さまの信頼もあつく、重くもちいられているのでした。
十三歳で平松塾にはいった武四郎は、初めて漢学を学びました。
漢学というのは中国のむかしの書物を読んで、人間としての考え方、生き方をじっくり学ばせるという学問で、まず「四書」「五経」をたたきこまれます。 |
 |
「四書」というのは論語(ろんご)、孟子(もうし)、大学、中庸(ちゅうよう)の四冊、「五経」というのは易経(えききょう)、書経、詩経、礼記(らいき)、春秋の五冊、いずれも中国に昔から伝わる、宗教、哲学、文学、歴史などにかかわる書物です。
みなさんもテレビの時代劇などで、さむらいの子が勉強している場面を見たことがあるでしょう。
きちんとすわって、本をひろげ、
「シ、ノクマワク………。」と、声をはりあげて読んでいくのです。
でも、もしみなさんがその子の前にひろげられている本を実際に見たら、びっくりぎょうてんしてしまうでしょう。
むずかしい漢字ばかりがギッシリとならんでいるのです。
ひらがなも、カタカナもありません。ふりがななども、一つもついてしません。
「シ、ノタマワク」というのも、
「子曰」と書かれているだけです。
「子曰」を「シ、ノタマワク」と読んで、「孔子は、つぎのようにおっしゃいました」という意味だと、覚えなげればならないのです。
「なぜ?」とか、「どうして?」とかいうことは、いっさい許されません。
とにかく、先生が読みあげるとおりに、おうむがえしのように声をはりあげてとなえ、これはこういう意味なのだと、先生が説明してくださることを、一度で覚えなければならないのです。
「読書百遍、意おのずから通ず。」
どんなにむずかしい本で九百回ちくりかえし読めば、自然にその本が何をいおうとしているのか、深い意味がくみとれるようになり、自分の血となり肉となるのだ。」
むかしの教育は、この考えが基本でした。
学問を心ざす人はすべてこの第一歩から積みあげていったのです。
とにかく、武四郎も、「シ、ノクマワク」から本格的な学問の第一歩をふみだしました。
その頃伊勢の津では文学がもっともさかんでした。ここでいう文学は、現代の意味でのそれではありません。
元々文学というのは文章経学といって、いまでいう文学のほかに、政治や経済の学問をもふくめた、広い意味をもっていました。
江戸時代も天保のころといえば、世の中のおもてむきは平和のようでも、その中身にはたくさんの問題をかかえている時代でした。
元々人間の“何かをほしい”と思う心は、政治権力などでおさえればおさえるほど、強くもちあがってくるものです。
長い鎖国政策は、かえってこっそり外国の品物を買い入れる密貿易をさかえさせました。
土・農・工・商と、キッチリとわけられた身分制度は、大変きゅうくつです。
そのうえ、社会での実際のちからは、いちばん下の階級の商人がにぎっていました。
何といってもお金のある人たちには、かないません。
いちばん上の階級のさむらいは、おもてむきはいばっていても、商人からお金を借りるのに苦労しているありさまでした。
さらに、社会がだんだん複雑になるにつれて、お米の値段ですべての経済の基本を組み立てていこうとすることが、なりになってきました。
こんな世の中を、何とかしなくてはいけないと考える学者たちが、一方ではしだいにふえてきました。
津藩は学問がさかんでしたから、つとめてすぐれた意見の学者たちをよんで、話を聞くようになりました。
武四郎の入門した平松塾には梁川星巌(やながわせいがん)、山口遇所(ぐうしょ)、大塩中斎(平八郎)といった人たちが講演によばれました。
そのような講演の席には、かならず武四郎の姿も見られました。
まだ十四、五歳の少年が頬をほてらせ、目をかがやかせて、すぐれた学者の話に聞きいっています。
講演がおわると、武四郎は、いつも思うのでした。
(きょうの先生のお話は私には、半分も理解できなかった。でも、いつまでもこのままではいないぞ。
もっともっと世の中のことを学んで、いつかはすべてがわかるような自分になってみせる。
いや、それよりも、あの先生のように、ひとにも自分の意見を堂々とのべられるような人間にならなくては――。」
それにつけても、伊勢の津にいるだけでは、すぐれた学者の意見を求めるにも不自由でした。
先方が訪れてくれるのを待つよりほかないのです。
(聞けば、幕府のおひざもとの江戸は、さすがは日本一のみやこ。
すぐれた学者も大勢あつまっているとのことだ。私も江戸にいってみたい、そうしてそこで、思いきり勉強したい。)
武四郎の“江戸へいきたい”と思う心は、日ましにつのっていきました。
そしてとうとう、天保四年(一八三三)、まもなく十六歳になろうという正月のことです。
突然、平松塾をやめた武四郎は家に帰って両親のまえにすわると、正月のあいさつもそこそこに、いいました。
[お父さん、お母さん、私を江戸にいかせてください。」
「江戸へ? やぶからぼうに、何をいいだすのだ。」
「まあ、おまえ、何をいうのです。江戸なんて、そんな遠いところへ、とんでもない。」
お父さんもお母さんも、あきれてしまいました。
二人でかわるがわる、なだめたり、すかしたりするのですが、武四郎はどうしても江戸へいきたいと言いはるばかりでした。
「どうしてもいくというのか。津にだって、立派な先生はいらっしゃるじゃないか。」
「そうですよ。それに庄屋の四男坊では津まで学問に出してもらうだけでも、幸せだと思わなければなりませんよ。」
「利口なたちのおまえを、こんな田舎の小野江でうずもれさすのもかわいそうだと思って、津まで出してやったのだが、どうやらこれは、火に油をそそいだことになったようだ。」
「まあ、お父さんまで、そんなあまい言いかたをなさっては、困ります。どうか武四郎を、ひきとめてください。」
「ふむ、でもこの子は、一度いいだしたら聞かないからなあ――。」
両親のこんなやりとりを、武四郎は、ふかく頭を下げたまま、じっと聞いていました。
そして、ひたすら祈るのでした。
(お父さん。お母さん。どうぞわがままをお許しください。)
とうとう両親も、こん負けがしてしまいました。
「しかたがない。とにかくいってみなさい、でも、江戸といえば百里もはなれている。
一人で、歩きとおしていけるのか?」
「はい、大事ょうぶです。」
百里といえば四百キロちかく。馬やかごといった乗物もありましたが、これはえらい人か病人のつかうもの、普通の人は急ぎの旅のほかは歩くのがあたりまえといった時代です。
二月一日、武四郎は初めての長い旅に出ました。
その頃は、江戸から京都へいくことを上るといい、その反対を下るといいました。
武四郎の旅はあの「東海道中膝栗毛」の弥次さん、喜多さんのとおった道を、逆に江戸へ下っていったのです。
武四郎にとっては、見るもの聞くもの、すべてが初めてで、新鮮なおどろきと、喜びの連続でした。
桑名からは尾張の宮(名古屋市熱田)まで、海上二十八キロほどを船で渡ります。
伊勢湾のまんなかに船がすすみでたとき、潮風にふかれながら武四郎は、(ああ、旅に出たんだなあ――。)と、いまさらのように思うのでした。
尾張の宮に上陸すると、これからいよいよ東海道の下り旅です。さすが東海道は日本一の街道です。
上る人、下る人、のんびりと旅をたのしんでいるらしい人、一生懸命先をいそいでいるような人、さまざまの階層の人たちがゆきかいます。
身なりもちがえば、ゆきずりにかわすあいさつの言葉も、下るにつれてかわっていきました。
しっとりとおちついたふるさとの暮らしにくらべると、何というちがいでしょう。
武四郎は一つ一つの体験を、大切に心の中にたたみこみながら、旅をつづけていきました。
駿河(静岡県)にはいって、富士山の姿を初めてあおぎました。
(これが日本一の富士山! すばらしいなあ。
うわさには聞いていたが、こんなに神々しい姿とは! あのお山に登れたらなあ。)
武四郎は、しばしの間、時のたつのも忘れて、見とれるのでした。
十日あまりの日数をかさねて、武四郎は、ようやく江戸にはいりました。
たよる人といえば、「神田お玉が池の山口遇所(ぐうしょ)先生」たった一人です。
平松塾で文学の講演を聞いたことのある先生です。
そのとき遇所先生は江戸ではてんこく家として有名だと聞いていました。
てんこく家というのは書や画におす印をきざむ人のことです。
神田お半か池。いまの岩本町二丁目のあたりに、ようやく山口遇所のすまいを訪ねあてた武四郎は、
「津の平松楽斎先生のもとにおりました松浦武四郎と申します。
津でうかがいましたご講演の感動が忘れられず、親しくお教えを頂たいものと念じて、はるばる津からお訪ねしたしました。
何とぞ、おひざもとにおいていただきとうぞんじます。」
山口遇所はびっくりしました。
「ここにおいてくれって? 住込みの弟子にはいろうというのかね。」
「はい、ふき掃除でもなんでもいたします。何とぞお願いいたします。」
遇所はなかばあきれながらも、武四郎のひたむきな心を、そっけなくつっぱねるのもかわいそうに思い、住込みを許しました。
武四郎の毎日は、忙しくなりました。仕事場の掃除もします。
ろう石に鉄筆(彫刻刀)で画家や書家の雅号をほりつけるてんこくの技も、教えてもらいました。
おりにふれ遇所の口にすることも、ひとことも聞きもらすまいと、心にとめていなければなりません。
(むこうみずな若者と思っていた武四郎は、なかなか見どころがあるらしい。)
山口遇所の武四郎を見る目もかわってきました。
そして、自分の蔵書なども、ひまなときには見てもよいと、許してくれるようになりました。
忙しい一日がおわって、夜、一人で遇所から借りた書物にむかっているときなど、武四郎は
「やっぱり江戸にでてきてよかった。」と、しみじみ思うのでした。
ところが、一ヵ月ほどたっかたたないうちに、金蔵という国元の家の使用人が、武四郎を迎えにきました。
「大旦那さまも、お家さまもたいそうご心配になっておられます。
手前がお供をいたしますから、どうぞお帰りになってください。」
父や母が心配しているからといわれては、これ以上わがままをつづけるわけにもいきません。
「しかたがない、一度帰るとしよう。」
「それがよろしゅうございます。春の東海道の旅は、またけっこうでございましょう。」
「いや、来たときと同じ道をとおることはよそう。名所図会などを見ると、中山道の景色もなかなかよいらしい。
それをわが目で確かめながら帰ろうではないか。」
中山道六十九次は江戸から、日本中部の山岳地帯をぬって、名古屋にでる街道です。
けわしい山坂も多いけれど、東海道とはまたことなる。人情風俗があって、あじわいふかい街道でした。
信濃(長野県)では、有名な善光寺にお参りをしました。
その夜、門前町に宿をとると、武四郎はいいました。
「金蔵、すまんがおまえはここから一足先に伊勢へ帰っておくれ。
そして父上や母上には、武四郎は、おっつけあとから戻りますので、ご安心くださいと申しあげてくれ。」
「へえ.それで、これからどうなさろうというので?」
「この信濃には、有名な山がたくさんある。そのどれかに、私は登ってみたいのだ。」
「あれまあ、山登りを! 一人で、おそろしくはございませんか。」
「何の、何の。山といっても、戸隠(とがくし)山、木曽の御岳(おんたけ)山など、いずれも信仰の山、善男善女がひとしくたどる山坂を、この若い私に、登れないことはなかろう。私は、高い山の頂に立ってみたいのだ。」
あくる朝、金蔵とわかれると、武四郎は喜びいさんで戸隠にむかいました。
東海道の下り旅をしてみて、自分の足の強さには自信をもっていました。
けれども、けわしい登り道がつづいて、はく息もせわしくなるにつれ、街道歩きで得た自信など、どこかへふきとんでしまいそうになりました。そのたびに、武四郎は、
「へこたれるな.この苦しさをのりきらなくては旅をつづけることなど、できやしないぞ!」
と、自分で自分に言いきかせて、進むのでした。
こうして汗水たらして、ようやく高い山の頂に立ったときのすがすがしさは、何にもたとえようもないものでした。
武四郎にとって、いままで知らなかった、全く新しい世界が、目の前に大きくひらけてきた思いがしたのです。
戸隠から、木曽の御岳山を回って、三月の中ごろに、ようやく父母の待つ伊勢へ帰りつきました。
お父さんもお母さんも、かわいい息子のぶじな姿を見て、大変よろこんでくれました。
けれども武四郎は日がたつにつれて、何かものたりない気持ちが強くなってきました。
(ふるさとは平和で、おだやかで、あたたかく私をつつんでくれる。
けれども、こういうなかで、のんびり暮らしていていいものだろうか。)
旅先では毎日毎日が新鮮なおどろきの連続でした。
そのなかでもまれながら、一歩一歩大人に成長してきた武四郎です。
そのうえ、江戸からの帰り道、生まれて初めて高い山に登りました。
山の頂で感じた身も心も洗い清められるようなさわやかな感動を、武四郎は、忘れることができません。
(旅に出たい!)
武四郎の心は騒ぎたちました。ついにこらえられなくなって、あくる年の九月、再び、両親のまえに頭をさげました。
「お願いです。旅にださせてください。」
「しばらく大人しくしていると思ったら、また悪い虫が騒ぎだしたな。」
「今度はどこヘいくつもりなの?」
「はい、京都へいってみとうございます。」
「まあ、みやこへは、一度いってみるのもいいだろう。」
両親は思いのほか、あっさりと許してくれました。それというのも、両親は簡単に考えていました。
(どうせこのまえのように、二〜三ヵ月もしたら帰ってくることだろう。)
そのためもあってか、お父さんは旅費として、一両のお金をわたしてくれただけでした。
そのころ一両といえば、青午か持ち歩くにはそれでもかなりの大金ですが、旅先ではそうながくはもちません。
こうして、この章の初めにしるしたように、天保五年の九月九日、武四郎は二度めの旅に出ることになったのです。
武四郎の家のまえの街道を南へ進むと、伊勢神宮へたどりつきます。
その頃は、一生に一度はお伊勢まいりをするのが、人々のねがいでした。
武四郎の旅だちの日は、まだ夜のあけきらぬうちから、伊勢参宮をめざす人たちが、南へ.南へと歩いていきました。
その人たちの列にさからうように、一人武四郎は京都をさして北へむかっていきます。
一両のお金をふところに、すたすたと歩いていく一人の青年――、すれちがう人たちも、べつに気にはとめませんでした。
けれども武四郎は、この日から、何と十年もの間、旅から旅の暮らしをつづけたのでした。
のちに大旅行家として名を残すことになった武四郎にとって、この日は、彼の本当の第一歩だったともいえましょう。
京都につくと、平松塾で講演を聞いたことのある学者の家を訪ねました。
江戸で山口遇所を訪ねたように、今度もそのような名高い先生のもとへいって、親しく教えをうけようと思ったのです。
ところが、今度は、そう簡単にはいきませんでした。
訪ねたさきが留守だったり、先生が病気だからと断わられたりしました。
そればかりかあるところでは、とりつぎの者がでてきて、
「あかへんえ。添え状をお持ちか。そうやないと、先生にはお会いでけへんえ。」
と、けんもホロロに断わられてしまったのです。添え状というのは、紹介状のことです。
つまり、だれの紹介もない、どこの馬の骨かわからない者には、会ってもやらないというわけです。
「これは厳しいぞ。さて、これからどうしようか。」
たいていの者ならばここでガックリきて、こそこそとふるさとへにげ帰ってしまうところです。
けれども武四郎は、ちょっとちがうようです。
「よし。それなら、これからは、自分のちからで、諸国を回ってみよう。
それにしても、お父さんからもらった一両のお金も、あと残りわずか。さて、どうしたものか?」
2 無銭旅行のあけ暮れ top
|
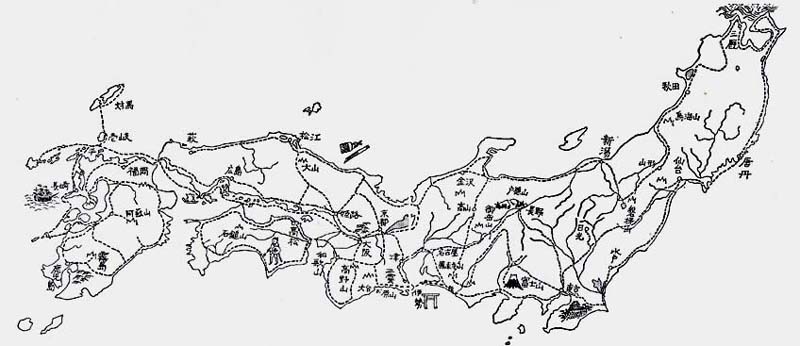
えぞへ渡るまでの武四郎の足取り。地名が書かれた場所が10年間に訪れた場所。日本全国に渡っている。
|
旅をしながら、暮らしをたてていくにはどうするか。武四郎は、いろいろ考えました。
(絵かきになろうか。いや、ひとさまに売るにしては自分はまだへたで、だめだ。俳句をひとに教えたりする俳諧師は?
これなら、まあまおできないことはないが、世の中にはまだ字も読めない人がたくさんいるから、やたらにどこへいっても弟子ができるというわけにもいくまい。
自分にできることで、お金をえて食べていくとすると、はて、何がいいか………。)
自分の身についた技をいろいろと思いめぐらしているうちに、はっと気がつきました。
「そうだ。てんこく(署名用の判子)がいい!」思わずさけんでしまいました。
江戸で山口遇所から手ほどきをうけたてんこくの技なら、もうすこし修業をすれば、それで身をたてていけそうに思えます。
そこで、師匠をさがすことにしました。けれども適当な人がなかなかみつかりません。
「よし、こうなったら、自分のちからで、やれるところまでやってみょう。
いろいろな印をおさめた印譜の書物一冊、それに鉄筆一本だけが、わたしのこれからの旅の道づれだ。」
こう決心した武四郎は印譜と鉄筆をふところにおさめると、大阪へ下っていきました。
大阪では天満に大塩中斎(ちゅうさい=平八郎)を訪ねました。
やはり平松塾の講演でその名を知った学者の一人です。
大塩は、東町奉行所の与力を隠退してから洗心洞という塾をひらいて、弟子をおしえていました。 |

てんこくで生活をしながらの無銭旅行
|
大塩の学問は陽明学といって、中国の儒教の学問のなかでも、王陽明(おうようめい)がとなえだしたものです。
学問を自分一人がおさめていればよいという考えかたをすてて、身につけた学問の知識を、ひろく人の世に役立てて、つねに実行にうつすことを大切にするものでした。
何事も自分の目で見てあるこうとしている武四郎の、積極的な生きかたに、大塩はたのもしさを感じたのでしょう。
大塩は武四郎にいいました。
「しばらくここに腰をおちつけてはどうかな。」
大塩は、この十七歳の青年に、自分の考えていることを、あますところなく伝えたかったのでしょう。
けれども武四郎は大塩にも心ひかれるものはありますが、まだまだ若いうちに、もっと諸国をめぐって、たくさんの学者にも会いたいと思うのでした。
「お言葉はありかたくぞんじますが、私はまた旅をつづけとうございます。」
こうして大塩のもとを去りました。
これはのちの話になりますが、大塩は三年後の天保八年二八三七)、大阪で反乱をおこしました。
その頃、日本全国がききんにおそわれて苦しんでいました。
「天保の飢饉」として、歴史にもしろされているもので、天保四年から、あしかけ四年にわたって、日本国中が不作になやまされていたのです。
わずかしかとれないお米は値段があがる一方で、ごくかぎられた人たちの口にしかはいりません。
村にも町にも、飢死にする人が、たくさんでました。
このありさまに、大塩は、だまっていることができなくなり、「困っている人々を救ってください」と大阪町奉行にねがいでました。
けれども、いっこうにききめがありません。
大塩は自分の大切にしている書物などをすべて売りはらってお金をこしらえ、飢えに苦しんでいる人たちを救っていきましたが、我慢にも限度があります。
とうとう天保八年の二月、怒りが爆発して、同志をつのると、暴動をおこしました。
それまでにも、飢饉に苦しむ人たちが.全国各地で、次々と一揆やうちこわしの騒ぎをおこしていました。けれども、今度は、いまは隠退したとはいえ、かっては町奉行与力までつとめた人物が、暴動の中心人物なので、幕府にあたえたショックは、大変なものでした。
結果としては大塩はやぶれて、自殺してしまいましたが、この反乱が全国にあたえた影響は、はかり知れないほど大きなものでした。
もし武四郎が.大塩のすすめにしたがって、洗心洞に長くとどまっていたら、あるいはこの乱にまきこまれて、彼の一生も違ったものになっていたかもしれません。
さて、大阪をあとにした武四郎は、中国地方にむかい、岡山から四国に渡って、また紀伊半島に戻り、天保六年(一八三五)の正月を迎えました。
それから天保十四年(一八四二)の夏、十年ぶりに伊勢に帰るまでの武四郎の足取りは、ほとんど日本全国に渡っています。
これはどの年月の間、武四郎はどんな暮らしをしていたのでしょうか。
とにかく旅といっても、それはすべて、わらじかけて歩くことです。自分の足だけがたよりです。
道ばたで手をふれば、親切なトラックの運転手が車をとめてひろってくれるなどというのとは、わけがちがいます。
また、年がら年中、お天気つづきというわけにはいきません。
雨の日もあれば、雪の日、風の日もあります。どんなにつらい日々も多かったことでしょう。
それだけでも、私たちには想像もつかないような大変な旅なのに、武四郎はそのうえに旅の道すから、これはと思う山があると、かならずといっていいほど、その頂に登りつめています。
なかには、加賀(石川県)の白山のように、あいにく雪のふかい季節で、登るのをあからめねばならない山もありましたけれど、夜は土地の旧家や、庄屋の家に泊めてもらいます。
そこで、てんこくの腕をふるって、印を彫らせてもらい、そのかわりにただで泊めてもらうのです。
長い年月の間には、いくら丈夫な体でも、病気にかかることもありました。
飛騨の高山(岐阜県)でのことです。たちのわるい出来物のために、動けなくなってしまったことがありました。
村役人の家にやっかいになっていたのですが、すこしよくなると、村の有志を集めて、平松塾で習い覚えた、四書や漢詩などの講義をしました。
そのお礼を、泊り賃と治療費にかえたのです。
四国では、八十八か所の霊場めぐりもしました。
生まれたところと名前をしるした笠をかぶり、おいずるという袖なし羽織のようなものを着て、首からはお札を入れた箱をぶらさげます。
そして、金剛づえをつき、鈴をならしながら、「なむ大師、へんじょうこんごう………」などととなえて、八十八ヵ所のお寺を、順番にお参りして回るのです。
いまの発達した乗物を使っても、十五日くらいかかるといわれる、千百キロあまりの道のりを、武四郎は、三ヵ月ほどで回りました。
もちろん.まわったのは霊場だけではありません。四国の有名な山には、すべて足をはこんでいます。
伊予(愛媛県)の石槌山に登ったときのことです。
天狗岳の頂に立って、目の下につらなる四国の山々、そして、そのむこうに瀬戸内海のきらめきを見たとき、武四郎は「何とすばらしいながめだろう。もう、思い残すことはない!」
と、感激のあまりさけんでしまったと、日記にしるしています。
このような四国の旅のようすについては、武四郎は、八年後の弘化元年(一八四四)に、「南海遍路日誌」という題名で、一冊の原稿にまとめています。そのなかには、自分でかいた写生図もたくさんはいっています。
武四郎は文や絵をかくことは、旅をすることや山に登ることと同じように、大好きでした。
“好きこそ、もののじょうず”といいますが、だれでも好きなことは、じょうずになれるものです。
のちに武四郎は北海道についての何冊もの書物をあらわすようになりますが、この「南海遍路日誌」は、そういった仕事の前ぶれのようなものといえましょう。
武四郎が歩き回っていたのは、ちょうど天保の飢饉の真最中にあたります。
大阪で門をたたいた大塩中斎(おおしおちゅうさい)が反乱をおこしてやぶれ去ったと聞いたのは、肥前(佐賀県)の大村にいるときでした。
自分に、もっとここにいるようにと、すすめてくれた先生の、悲しい最期を聞いて、武四郎は何を思ったことでしょうか。
その頃は、どこへいっても、飢饉の暗いできごとばかりでした。
旅から旅にあけくれる武四郎も、ずいぶん食べ物に苦しみました。
三日の間、一つぶのお米にもありつけず、とうきびばかり食べて、我慢したこともありました。
食べ物がたりなくて、人々の心もすさんでいました。肥後(熊本県)の都留(つる)では三人のおいはぎにおそわれました。
「おい、旅の若いの。酒手(さかて)をだせ!」
と、すごい目つきでおどされたのです。武四郎は、なけなしのお金をとられてしまいました。
でも、武四郎は、その人たちをうらむ気はしませんでした。
(気のどくに………飢饉でくるしんでいるからだろう。ものとりまでするなんて、どんなにかつらいことだろう。)
と、同情をよせています。
九州では薩摩(鹿児島県)へも足をのばしました。
薩摩は、島津の殿さまの領地で、昔から他国者を入れないことで知られていました。
「薩摩飛脚」という言葉がいまも残っています。
薩摩へむかっていった飛脚は身分がばれると、ころされてしまうのか。二度と帰ってこないのです。
だから、いったきり戻ってこないことをさして「薩摩飛脚」といいました。
島津藩では、これほどまでにして、藩の秘密が外にもれることをおそれていたのです。
(あたりまえの旅姿では、とても薩摩にはいることはできない。さて、どうしたものか。) 考えたすえ、武四郎はお坊さんの身なりをととのえました。 |

関所の厳しい薩摩には、雲水姿でもぐりこんだ
|
旅の雲水の僧だと、厳しい関所も、とおしてもらえるからです。
ようやく薩摩の領内にはいれました。けれども、とどまることを許されたのは、たったの三日間だけでした。
普通の人間ならば、知らない土地へいっての三日間では、ついうかうかとすごしてしまっておわりです。
けれども、武四郎は(これは、呑気にしてはいられないぞ。)と、思うよりもはやく、島津の城下町を歩き回り始めました。
うわさに聞いていた琉球人(沖縄の人)の町の商家の店さきなどで見かけました。
(島津藩では琉球との取引で、大変な金もうけをしているといううわさだが、とするとあの商家も、藩のご用商人か何かだろうか………。)
大変な“雲水の僧”もあったものです。そればかりではありません。
武四郎は、城下の見取り図までかいてしまったのです。
もしもこのことがばれたら、その場で武四郎は首をはねられていたことでしょう。
やがて天保も九年になりました。
武四郎が二十一歳になろうとする正月、長崎にはいったのですが、ここで思いもかけぬ大病にかかってしまいました。
長崎は外国の船もはいってくる土地です。
おそらく武四郎がやられたのは、そういった外国船がもちこんだ伝染病だったと思われます。
ひどい下痢と、熱になやまされて、禅林寺というお寺で病の床についてしまいました。
寺では和尚さんが、一生懸命、看病してくれました。
(ふらりと流れついた見ず知らずの男を、こんなに親切に介抱してくださるとはありがたいことだ。)
武四郎は、心のそこから感謝するのでした。
それにしてもお寺の一室で、毎日じっと天井をみつめて寝ていると、心がシーンとしずまって、物事がふかく考えられてきます。
十七玳の秋に家をててから四年というもの。ただひたすらに旆がしたくて、歩き回ってきた武四郎でした。
けれども、こうしてしずかに考えてみると、
「一体自分は、何のために旅をしてきたのだろうしという、大きな問題にぶ使ってしまいました。
確かに、いろいろな人に会いました。
いろいろな土地も、この目で見ました。けれども考えてみれば、それらのことは今のところ、武四郎一人のただそうしたいという欲望をかなえさせてくれただけで、自分は、まだそこから何も生みだしていない。
何かを生みだして、世のため、人のためになるようなことをしていない――このことに気がついたのです。
(旅をするにしても、何か人生の目的のようなものを思いさだめてするのでなければ、いけないのではないだろうか。
さて、それなら自分は何を……。)
あまりにも大きな問題で、武四郎には、すぐには答えがみつかりません。
そんな武四郎の心の迷いを見ぬいたのか、禅林寺の和尚さんはようやく床の上に起きなおれるようになった武四郎を見て、
「さしあたってゆく所もさだまっておらぬようなら、しばらくこの寺にとどまってはどうじゃな。」といってくれました。
「一つところにとどまって、苦労をしてみるのも、若いときには大事なことだと思うがの。」
「はい、」
「禅寺の雲水の修業というものは、厳しいつらいものじゃ。
けれども、それを一心につとめるうちに、日々生きてしるということに、すなおな喜びが見いたされもしようと思うのじゃ。」
「はい。一生懸命つとめてみます。何とぞよろしくお願いいたします。」
「それでは名は文桂と名づけてあげよう。まずお経を覚えてもらわねばならぬが、そなたが熱にうなされているあいだ、私がとなえてあげた般若心経(はんにゃしんきょう)は耳に残っているだろうか。」
「はい、もうすっかり、そらで覚えております。かんじざいぼさつ ぎょうしんはんにゃ はらみった じしょうけんご おんかいくうど いっさいくやく………。」
声高らかにとなえあげる武四郎を、和尚さんは、にこやかな顔で見まもってくれるのでした。
とうとう武四郎は頭をまるめて、黒い衣をまとい、一人のお坊さんとなりました。
そして、朝に夕に、般若心経をとなえ、それを大きな心のよりどころとする毎日が始りました。
3 えぞにいこう! top
武四郎が頭をまるめて文桂と名のり、禅寺の雲水となったのは天保九年三月二十八日のことです。
武四郎はくる日もくる日も雲水としての修業につとめるのでした。
あくる年には、一度“旅に出たい”という気がおこって、五島の島々をめぐり歩いたこともありました。
けれどもそのうちに、世話をしてくれる人があって、平戸の宝曲寺というお寺の住職になりました。
どんなに田舎のお寺でも、住職ともなれば責任があります。
朝夕のおつとめのほかに、おとむらいによばれたり、檀家交わりをしたり、そのうえ、寺の掃除やまきわりも、一人でしなくてはなりません。
思ったよりも忙しい毎日でした。
けれども、体はいそがしくても、心は大変おだやかな日々でした。
こうして、その一生を通じても、ほかに例もないほどの平和な三年あまりがたって、天保十三年(一八四二)、武四郎は二十五歳になりました。
この年やはり人の世話で、粉引村の手光寺というお寺の住職になりました。
粉引村は日本海に面した村で、千光寺には、昔千光国師という名僧が、唐(中国)からお茶の木を持ち帰って植えたと伝えられています。
海のかなたには遠く壱岐、対馬がのぞまれて、大変景色のよいところです。
朝に夕に、海のむこうの島をながめるうちに、武四郎の心は、また騒ぎ始めました。
「何とかして、あの壱岐、対馬へ渡れないものだろうか。」
その気になれば、手段は見つかるものです。対馬に渡るいか釣り船にのせてもらえることになりました。 |

平戸では本物の雲水になって、お寺の住職となる
|
そして九月、ついに壱岐(いき)に渡り、さらに対馬(つしま)にも足をのばしたのです。
ここで、大変なものを見ました。それは、水平線によこたわる大きな島影――朝鮮半島です。
「あれが朝鮮か――。」
この時が、いわば“僧文桂”との別れぎわとなりました。
またもや諸国をめぐり歩いて、ありとあらゆる高い山に登ってみたいという、旅行家武四郎に戻り始めたのです。
けれども、今度は壱岐や対馬に渡るように、簡単にはいきません。
なにしろその頃の日本は、厳しい鎖国政策をとっていたのです。
長崎の港に、中国と、オランダの船だけは出入りを許されていました。
けれども、そのほかの国は一歩もちかづくことができません。
また日本人も、国の外ヘー歩もでることができなかったのです。
ようやく自分をなだめるようにして、武四郎は平戸に戻りました。
そして僧文桂として寺の仕事にはげみながら、天保十四年を迎えました。
(伊勢を出てからはやくも十年め。旅から旅にあけくれて、国元に便りもしなかった。
あるいは、お父さんも、お母さんも、もうこの世におられないのではないか………。
とにかく、十年ぶりに便りを出してみょう。)
こう思った武四郎は、両親にあてて手紙を書きました。ところがその返事は、兄から送られてきました。
差出人が兄ということで、武四郎は、はっと胸をつかれました。そして、読み進むうちに、顔色が変りました。
「お父さんがなくなられたのは天保九年の三月二十八日。何と、これは私が出家したのと同じ日ではないか。
仏さまのおひきあわせだろうか………。
お母さんが、去年の二月になくなったとは、ああ、私は、何という不孝ものだろう………。」
武四郎は、衣のそでに顔をうずめて、はげしくむせびなきました。
旅でどんなつらいめにあっても、涙など見せたことのない武四郎でしたが、この時ばかりは、こらえることができませんでした。
「これはもう、こうしていることはできない。
すこしでもはやく伊勢へ帰って、ご両親さまの霊前に、不孝のおわびをしなければならない。」
こう決心すると、武四郎は、平戸を去るしたくにとりかかりました。
その時、武四郎の心をかりたてる、もう一つのことがもちあがりました。
七月のことです。武四郎は長崎で知りあった津川文作という老人に会いました。
津川老人は、当時本草学といった、いまでいう博物学のようなものに興味をもっていました。
その屋敷には、日本全国はもとより、遠く中国や南方の島の植物などが、標本になって、足のふみ場もないほどつみあげられていました。
武四郎は、この津川老人から、薬草についての知識など、ずいぶん教えられることが多かったのです。
そればかりではありません。津川老人は長崎酒屋町の名主をしていました。
その頃名主といえば、町でも指おりの知識人でしたから、奉行所へも出入りしますし、また漂流のあげく外国から送り返されてきた漁師などの報告書を書く仕事もうけもっていました。
しぜん、津川老人は外国のニュースにあかるく、武四郎はそれらを聞くのを楽しみにしていたのです。
武四郎は、津川老人に会うと、いいました。
「さきごろ、対馬にまいりました。そこで朝鮮を海のかなたにのぞみ、できることなら朝鮮へ渡りたいと思いましたが、何といっても、外国へ渡ることはきついご法度。残念ながら、かないませぬ。」
それを聞いて、津川老人は、はたと、ひざをうちながらこたえるのでした。
「いや、そのことじゃ。朝鮮へ渡られることなどは、おやめなされ。
それよりも、もっともっと大切な、ぜひともあなたのようなかたにいっていただかねばならぬ土地が、この日本のなかにござりますわい、」
「と申されますと?」
「えぞ地ですわい、」
「おお。大老!」
「さよう。このままあの土地をうちすてておいては、いまに赤えぞによって、すっかりうばいとられてしまいます。
そうたってから後悔しても始りませぬ。」
赤えぞというのは、ロシア人のことです。
その頃ロシアは、カムチャツカ半島から、千島列島をつたって、しだいに南へさがり、えぞ、いまの北海道へふみいろうとねらっていたのです。
そのことについては、武四郎は津川老人から初めて聞いたというわけではありません。
伊勢にいたころ大切にしていた本に、林子平の『三国通覧図説』というのがありました。
林子平というのはすでに五十年ほどまえになくなった寛政時代の人で、えぞ地へは行っていませんが、聞書(ききがき)ながらも、はやくから日本は、海のまもりをかためなければならないと説いていたのです。
| 親もなく 妻なく子なく 版木(はんぎ)なし 金もなければ 死にたくもなし |
このような辞世の歇を残して、幕府にとらえられたまま、獄の中で死にました。
『三国通覧図説』は朝鮮、琉球、えぞの地理、風俗、気候などを図示した本で、世の人ごとに、鎖国による太平の夢からさめることをよびかけたものでした。
武四郎はこの書物を読みながら、何かしら、自分の心のなかにうずくものを感じていたのです。
津川老人から、えぞ地のことを聞いたとたんに、林子平の辞世の歌がいなずまのように、武四郎の心の中をよぎりました。
「よし、これはぐずぐずしていられない。私は、そのえぞという北の果ての地へいこう。
えぞへいって、実際の姿をくわしく見て歩き、赤えぞの侵入を防ぐにはどうしたらよいかを考える――そのために、私はえぞに渡るのだ。」
武四郎にとっては生まれて初めて、はっきりと目的をさだめた旅を思いたったといえましょう。
一度心にきめると、すぐにそれを行動にうつす武四郎です。
さっそく世話になった光明寺の和尚さんのところへいって、自分の決心を伝えました。
「いかにも、それは、なみなみならぬご決心じゃ。男が一度心にきめたこと、ゆかれるがよかろう。」
「これまで文章、詩ばかりか、絵の道までおみちびきいただき、お礼の申しあげようもござりませぬ。
そのいずれの道もきわめぬままお別れするのは、おなごりおしうございます。」
「いや、いや、思いたたれたことはどこまでもやりとげなされよ。ただ、くれぐれもその身をいたわられるよう。」
「和尚さまにも、何とぞおすこやかにおいでくださいますよう。」
足かけ六年の平戸暮らしに別れをつげて、にわかに旅じたくをととのえると、天保十四年の八月、十年ぶりに武四郎はふるさとの伊勢にむかいました。
そしてあくる年、弘化元年(一八四四)二月に、父と母の法事をいとなむと、武四郎はそのままふるさとの家をあとにしました。
「もう、何も思い残すことはない。」
武四郎の足は、まず伊勢神宮に向いました。
武四郎は、衣をまとった僧の身なりで、伊勢神宮の外宮の神域にはいろうとしました。
「これ、待て、坊主。どこへまいる。」
突然うしろから、大きな声でよびとめられました。
びっくりしてふりかえると、外宮の役人が、おそろしい顔でにらみつけています。
武四郎は、はっとしましたが、知らん顔で答えました。
「はい、外宮さまにお参りさせていただきます。」
「だまれ、ここをどこと心得る。伊勢皇太神宮であるぞ。
坊主は、一歩もはいることまかりならぬ。とっとと帰りおれ!」
そうでした。昔から、そういうしきたりだったのです。
武四郎も知ってはいましたが、長い旅のまえにお伊勢まいりをと、心がせいていたので、ついうっかりしていたのです。
役人と喧嘩をしても始りません。
武四郎は、大人しくひきさがると、町でつけまげを買い求めで坊主頭にのせました。
着物は衣をきちんと着なおし、前でむすんでいた帯をうしろにまわしただけです。
そんななりでも、今度はとがめられずに外宮(げぐう)の鳥居をくぐることができました。
ぶじに内宮(ないぐう)もお参りをすませて、お伊勢さまをあとにしたのです。その時、武四郎は心にきめました。
「私は、今日限り坊主をやめよう。もとの松浦武四郎に戻って、これよりえぞ地のすみずみまでさぐる旅に出る。
そして、いつか国のために役立てるのだ。」
まず京都にでました。それから北陸路をとって日本海にでると、北へ。越後(新潟県)の新発田(しばた)から内陸へはいって会津若松(福島県)に、そこからは、ひたすら北をめざして、いまの山形県、秋田県をとおりぬけるのです。
夏の暑いさかりを歩きとおして、九月。陸奥の国(青森県)三厩(みんまや)につきました。
その頃、えぞ地の松前へ渡るには、この三厩から船にのるのです。
そのほか、大畑、佐井、大間などからも、えぞ地へ打けて船がでました。
それはえぞ地でも函館へいく船です。武四郎はまず松前へ渡りたかったので、三厩をえらびました。
船問屋へいって、たのみました。
「松前へ渡りたいのだ。气船をだしてもらえまいか。」
「それはなりません。」
どうしてと聞いても、どこでもはっきりした理由をいってくれません。
何軒めかの船問屋で、ようやくわけがわかりました。
「なにしろ、お上から人相書きがとどいておりまして、えぞへ渡る人のおあらためがきびしく、何かと面倒ですので、船をだしたくないのです。」
「なに、人相書? 一体だれの………。」
船宿の主が見せてくれた人相書に目をやって、武四郎は、はっとしました。主が、すばやくその顔色をよんで、
「もしや。あなたさまは、この人相書のぬしをごぞんじで?」
と、さぐるような目つきで、武四郎の顔をのぞきこみました。
「いや、いや、知らぬ。何やら、おそろしげな顔だな………」
と、言葉をにごしてしまいました。でも、武四郎は、ひと目でわかりました。
それは、かねてから尊敬していた高野長英だったのです。
高野長英は水沢(岩手県)の人ですが、長崎でドイツ人のシーボルトから西洋医学を学びました。
そして、西洋の文明を知るにつれて、幕府の鎖国政策があやまりであることをふかくさとり、幕府を批判する文書を書いたりするようになりました。
そのあげくついにとらえられて、牢屋に入れられたのです。
ところが、その牢屋が火事になりました。むかしは牢屋が火事になると、罪人を三日間だけときはなちます。
三日間のうちにもとの牢に戻ってくることが条件です。
もし、戻ってこなければ牢やぶりとして、全国に人相書をまわし草の根をわけてもさがしだして、きついおしおきをうけることになります。
長英は、この時決められた時間までに戻りませんでした。
すでに人相書も回っていることを思って、顔半分をわざとやけどさせて、人相を変え追手の目をのがれていたのです。
もちろん武四郎は長英が顔を焼けただらせてまで、にげるのに苦労していることは知りませんでした。
でも影ながら、
(何とかぶじに、役人に見つからずにおられるように………。)と、祈らずにはいられませんでした。
それにしても、せっかく決心してここまでやってきたのに、えぞに渡れないとは何とも残念です。
来年の春まで待てば、何とかなるかもしれないと、いってくれる人もありました。
けれども、武四郎は、じっとしていられませんでした。
あきらめきれないままに旅をつづけて、津軽半島の竜飛(たっぴ)崎まできてしまいました。
ここは、本州のいちばん北の端です。津軽の秋は早くも冬の初めを思わせるほどの寒さでした。
ドドーンと荒波がうちよせる岬の鼻に、武四郎は立ちました。
すると北の水平線に、見えるではありませんか。えぞが!
「おお、あれかえでの地だ………。」
からだのなかをはげしく血が流れます。心臓の音が自分でも聞こえるほどに思われました。
けれども、どんなにはげしく思いこがれても、いま、えぞに渡ることはできません。
「しかたがない。もうしばらく待って、何かてだてを考えよう。
さて、帰りには下北半島で、恐山にも登ってみょうか。」
新しいめあての土地をつくって、自分をなだめながら、太平洋岸ぞいに南へくだって、仙台のちかく、唐丹(とうに)村まで戻ってきました。もう、年の暮れでした。
ここで弘化二年の正月を迎えました。
その年は大変な大雪で、一か月、旅に出ることができずに、とじこめられてしまいました。
二月の初めになって、ようやく仙台へ魚をつんでゆく船をつかまえ、仙台に出ることができました。
仙台から、いったん江戸に帰ると、さっそく神田お玉ヶ池にとんでいって、山口遇所(ぐうしょ)を訪ねました。 |

津軽半島の竜飛崎から見えるえぞ地
|
「おお、そこもとは………」
「松浦武四郎でございます。先生、ずいぶんごぶさたをいたしました。」
「何とした。これは」
遇所は、ただおどろきの目を見はるばかりでした。
十二年さえ、まだ子供っぽさを残していた武四郎弌見ちがえるようにたくましく成人していたからです。
さらに武四郎が語る、十二年の旅の日々を聞いて、遇所は、あいた口がふさがらない思いをしました。
二十歳やそこらの青年が、自分がほんの手ほどきをしてやっただけのてんこくの技一つで、旅費をまかなって諸国を歩き回った、というのですから、遇所がおどろくのもあたりまえです。
そのあげくに武四郎は、さらにえぞへ渡るために、苦心しているといいます。
(赤えぞの侵入を日本がおそれていることは私も聞いている。
この武四郎が.一人でそのえぞ地を歩き回って、はたして身の安全をはがれるだろうか。
しかしこの男は、とめても聞くまい。一度、心にきめたことは、何としてもやりとげるたちだから。)
こう思った遇所は
「よろしかろう、ゆくがよい、そして思うままに見て回るのだ。」と、はげましてやるのでした。
三月二日。武四郎は、はやくも江戸をたって、奥州路をめざしました。
とぶような速さで北にむかい、四月の初めに、三厩(みんまや)につきました。
今度はうれしいたよりが待っていました。えぞへ渡れるというのです。
松前、江差の商人で斎藤佐八郎という人がいました。
その人の持ち船が松前へむかうので、斎藤の手代ということで、その船にのせてもらえることになりました。
“渡りに船”とは、まさにこのことです。武四郎がよろこんだことは、いうまでもありません。
4 地の果てに立つ top
いま北海道に渡るには青森から連絡船にのって四時間たらずで函館についてしまいます。
そのうちに津軽海峡に海底トンネルができれば、本州から列車にのったまま北海道に渡ってしまえます。
ところが武四郎のころは、そんなわけにはいきません。
十人ほどの舟子たちが、かじとりのかけごえにあわせて、ろをこぎながら小さな船で渡るのです。
なにしろ津軽海峡は、大変潮の流れの早いところです。
ごうごうとうねりをたてて、大波がたえず西からおそいかかってきます。
竜飛の鼻の潮、中の潮、白神の潮と名づげられた、三つの難所をもった、おそろしい海峡でした。
かじとりも、舟子たちも、みんな海草でこしらえた蓑(みの)を、頭からかぶっています。
腰にまわした太いつなで、ふなばたにはめこんだ環に一人一人、ゆわえつけています。
そうしないと、船の上をこす大波に、すくわれてしまうからです。
「そろうた、そろうた」
みんな大きな声で調子をとって、ろをこぎます。
「大波がきたぞ!」
かじとりがさけぶと、舟子たちのかけごえは、いっせいに変わります。
「船玉明神(ふなだまみょうじん)、たのむぞ、たのむぞ。」
船乗りもお客も、みんなが命がけでした。
こうして海の上をもまれること八時間ぐらい、ようやく船は松前の北、江差の浜につきました。
その頃の松前のあたりI帯汽大変にぎやかな土地でした。
松前藩ではえぞ地でとれた海や陸の産物を一手に買占め、それを内地に売って、大変にもうけていたのです。
江差につくと、武四郎汽船の持ちぬし、斎藤佐八郎の家にやっかいになりました。 |
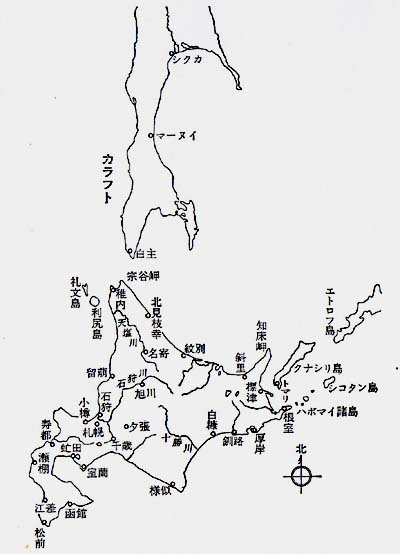
本文にでてくる北海道とカラフトの主な地名
|
佐八郎はぬけめのない商人で、土地のうわさを聞くと、あまり評判がよくないようです。
でも、その息子の作左衛門が、なかなか文学に明るい人で、武四郎とも話があうのです。
(とりあえず、ここを足だまりにさせてもらおう。)
武四郎は旅のつかれをいやす間ももどかしそうに、えぞ地を歩くためのしたくにとりかかりました。
当時えぞ地は、松前の城下を中心として、東のほうの海岸の函館、室蘭、厚岸(あっけし)、根室までを東えぞ、北の江差、石狩、留萌(るもい)、宗谷までを西えぞとよんでいました。
武四郎は、まず西えぞの入口だけでも歩いてみょうと思いました。
そこで江差から熊石、瀬田内(瀬棚)にむかいました。交通がひらけてきた今日でも、このあたりは、まだまだ不便なところです。
その頃は、道らしい道すらありません。人もわずかしか住んでいないのです。
けわしい、崖の岩はだにしがみつきながら一歩一歩進むようなところが、たくさんありました。
(こんなに道らしい道もないところで、しかも寒さに厳しい。
ここに住んでいる人たちの苦労はさぞかし大変なことだろう。)
武四郎は、一歩ふみはずせば、自分自身が、海へまっさかさまにころがり落もそうなところを歩きながらも、土地の人たちの暮らしのことを思うのでした。
(松前という、たったひとにぎりほどの広さのところだけが、江戸にもおとらないといわれるほどの繁盛ぶりをしめしている。一歩その松前をではずれると、もうこのありさまとは――。)
これから、この広いえぞを、くまなく歩いてみようとしている武四郎は、身も心もひきしまるようなものを覚えさせられました。
(でも、どんなに苦しい旅でも、自分は、えぞの奥地をふみわけなければならないのだ。)
これまでも寛政時代に、幕府はこのえぞ地へ.何人もの役人をつかわして、調べさせようとしました。
けれども、みんな海岸線にそった道を歩くだけで、だれ一人として、内陸ふかくわけいった者はいないのです。
(そのまねをしてはいけない。私は奥地にふみこんで、山脈や川筋のようすをつかみ、この土地に住行人の人情や、暮らしぶり、それに、どんな産物があるかをくわしくさぐって、国のために役立てようと、えぞ地へ渡ったのだ。)
このように決心はかためているものの、一つ困ったことがあります。
それは、旅人をかってに内陸に入れてくれないのです。
一つには、例の高野長英事件があって、旅人の通行取調べがきびしかったせいもあります。
もう一つは松前藩の政策でもあったのです。
なにしろ、えぞ地の産物を一手ににぎっているのですから、かってによその土地の者が出入りして、松前藩がどんなにもうけているか、見られては困るというわけです。
(どうしたら、自由にえぞ地を歩きまわれるか――。)
いろいろ考えたあげく、武四郎は自分の籍を江差の人別帳に入れました。
いまでいえば、住民登録をして、身分証明書をもらうことにあたります。
これで立派に江差の住人ということになりました。
これだけでも、どこの馬の骨かわからない旅人とはわけがちがいます。
そのうえ武四郎は大変、人との付き合いがじょうずで、どんな人からも親切にされるという、恵まれた人でした。
それで、どこへいっても、いく先々で、土地の有力者たちと親しくなり、何くれとなく世話をしてもらえたのです。
これだけの準備がととのうと、武四郎はいよいよ東えぞ地の探検に出発しました。
この時は函館の商人、白鳥新十郎という人が、大変ちからになってくれました。
方々の知合いにかけあって、武四郎のいく先々で、馬を一頭貸すように話をつけてくれたのです。 そればかりではありません。
和賀屋(わがや)という、やはり名高い商人の手代ということにしてくれました。
当時、松前藩は三万石の領地とされていました。 それはえぞ地でとれるお米が三万石、およそ、四千トンあまりと見積もって、それで家来をやしない、領地を治めるというわけです。 |

和賀屋の手代になってのえぞ地めぐりで、アイヌとの接触が始まる
|
ところが、その頃えぞ地では、お米はとれません。
そこで、海でとれる魚やこんぶ、川でとれるさけ、山で猟師にとらせる獣の皮、それらの産物すべてをお米に取替ていたわけです。
だから、松前藩の家来たらは扶持、いまでいう給料として、沿岸漁場を区切って、それぞれあたえられていました。
それを“場所”といっていました。
その場所には、それぞれ.松前や函館の大商人たちは冥加金(みょうがきん)、つまり権利金をはらって、勢力をのばしていました。
彼らは大ぜいのアイヌを使って漁をさせ、買いあげた産物を場所の主、つまり松前藩の家来たちにかわって、内地に高く売って、大もうけをしていたのです。
このような商人を“場所請負人”といいました。
武四郎を世話してくれた白鳥や、和賀屋なども、そうした請負人の一人でした。
請負人の機嫌をそこねると、産物を買いあげてもらうときにつらいめにあわされるので、どこでも、請負人というのは、大変な勢力をもっていたのです。
武四郎は白鳥の紹介状を見せれば、旅先でいろいろ便利なことを知りました。
また和賀屋の手代といえば、下にもおかないもてなしをしてくれました。
こうした経験をつみかさねるにつれて、請負人の実力のほどを、思い知らされるのでした。
けれども、一方では、
(私は、このような便利さに、ぬくぬくとおさまりこんでいて、いいのだろうか――。)
と、ふと考えてしまうこともありました。
とにかく、武四郎は夏から秋にかけて、東えぞの海岸をたんねんに歩きました。
いまの室蘭から日高海岸をとおって襟裳(えりも)岬をまわると、十勝、釧路、厚岸、根室、斜里と、たどっていったのです。 ここまできたのなら.ついでに知床も歩いておこうと思いました。
けれども、まだ日本人で知床を歩いた人のあることを聞いていません。そこでアイヌに道案内をたのみました。
アイヌは、ここをシレトクといいます。それは、“地の果て”という意味です。
いまの知識でいえば緯度だけから見ると宗谷岬のほうが、北海道の北の地の果てといえましょう。
けれどもオホーツク海に、くさびを打ちこんだように、細長くつき出た知床半島の突端に立てば、まさに“地の果て”という言葉が実感としてわきおこってきます。
アイヌさえも、シレトク、地の果てといって、わざわざいく必要もないところと思っているところへ.武四郎はむかいました。
半島の中央を走る山なみは、羅臼岳、硫黄山など、千五、六百メートルの高さをほこり、するどく海に落ちこんでいます。 波のおだやかな根室海峡のむこうには、はるかにクナシリ島がのぞめます。
けれども目を北にむけると、ただただ広いオホーツクの海。
どこまでもつづく水平線に、ぐるりととりかこまれて、思わず海にすいこまれそうな気分におそわれるのでした。
(日本人でここを訪れたのは私が初めてなのだ。)
それならばと、武四郎は岬の突端に柱をたて、腰にさした矢立をぬくと、墨黒々と柱に書きつけるのでした。
「勢州一志郡雲出松浦武四郎」
足元の断崖には、ウミネコの巣があるのでしょう。
ミャオ、ミャオーとさかんに鳴きさわいでいるのが聞こえます。空には、ワシがゆうゆうと舞っていました。
5 アイヌ語をものにする top
東えぞ地を知床まで歩いた武四郎はその年、弘化二年の十月には函館に帰り、ひとたび江戸へもどることにしました。 奥州路を南にむかいながら、武四郎は、(今度こそ、水戸へ寄っていこう。)と、心にきめました。
水戸にはぜひ会ってみたい人がいるのです。
その人の名は会沢正志斎(せいしさい)、水戸藩の名高い学者です。
水戸は昔から学問のさかんなところでした。黄門さまで知られる徳川光圀(みつくに)公は、『大日本史』を編さんさせたことは有名です。
そこでうちたてられた天皇家を国の中心にすえて、政治、文化のあらゆる面の考えかたに筋道をとおしていこうとする態度は、水戸学とよばれて、日本人の思想に深く根をおろすものとなりました。
徳川幕府が政治の実権をにぎっていることに、いろいろな不満をいだいている人の多くは、この水戸学にまず目をつけました。
のちに、明治維新をむかえるときに、この水戸学は、日本全国の尊王思想家の土台となったのです。
光圀公は徳川幕府をうちたてた徳川家康の孫にあたります。
その人がひらいた学問に心をよせる人たちが、幕府をたおす運動をしたことになります。
このような水戸学の学者、会沢正志斎は『新論』というすぐれた書物をあらわしていました。
武四郎はそれを読んで、正志斎を尊敬するようになり、一度会ってみたいと思っていたのです。
武四郎が訪ねたとき.正志斎はすでに六十歳にちかく、三十にもたりない武四郎は、おそらくふしおがむような気持ちで面会したことでしょう。
水戸は、ほかに大立原翠軒(すいけん)、藤田幽谷(ゆうこく)など、すぐれた学者を生みだした土地です。
水戸学が生まれた土地を自分の足でふみしめ、その空気をすってみる――それだけでも武四郎にとっては、大きな感動だったことと思われます。
江戸に帰ると武四郎は、今度のえぞ地の旅で、見たり聞いたりしたことを整理して、本にまとめる仕事にとりかかりました。
旅さきでしるしておいたメモをもとに、旅行記として文章にまとめるのです。
さらに、めずらしい風俗や風景のスケッチをまとめたり、見取り図のような地図をかいたりもします。
どれ一つをとっても、けわしい道を苦しみながら歩いた、ひとこまひとこまが思いだされて、武四郎は、
(この感動のなまなましいうちに、できるだけまとめて書いておくことだ。きっと、のちの役にたつにちがいない。)
と、心せわしく筆をすすめるのでした。
武四郎は、こののちも、何回もえぞ地探検にでかけます。
そのたびごとに、江戸へもどると、旅行記をまとめ、またでかけるということをくりかえしました。
武四郎のあらわしたたくさんの書物は、こうしてできあがったのです。
弘化二年の暮れもおしつまってきました。
「どうだ、みんなで忘年会をやろうじゃないか、」と、友だちに声をかけられ、両国橋のたもとの料亭に出かけました。
その席には、峯田楓江(ふうこう)という人もきていました。
この人はその当時、江戸ではえぞについてもっともよく知っている人とされていたのです。
しぜん、武四郎と、えぞについての話がさかんにとりかわされました。
しだいに熱が入ってきた武四郎は、
「一体、日本人は視野がせますぎる。
たとえていえば、江戸だけを見ても下町の者は、山の手について何にも知らない。
山の手の者が下町のことをよく知らないで平気でいる。
川崎からむこうへいくのでさえ、おっくうがっている。
だから、海といえば品川の海しか知らないし、川といえば、玉川がすべてだと思っているしまつ。
えぞなどといえば、聞いただけできもをつぶしてしまい、人間のいくところじゃないと思っているのか、役人でさえいきたがらないという、全くばかげた話だ。」
と、日ごろの心の不満をぶちまけるのでした。
なるほど、もうすでに本州、四国、九州のほとんどを歩きまわり、そのうえエゾにまで足をのばした武四郎にすれば、こんなこともいいたくなるでしょう。
世間の人たちの、自分のすでに知っている世界だけで、縮こまって暮らしているようなまねは、頼まれたって嫌だというところです。
たしかにその頃は旅にでるというのは、相当な決心がいるのでした。
旅だつまえには親兄弟と水さかずきをくみかわして――つまり、ふたたび会えなくなるかもしれないとまで決心して、わかれたものなのです。
それほど、旅は苦しく、困難なものだったわけです。
新幹線や飛行機をつかえば、日本国内いたるところ日帰り旅行ができる、今日からは想像もつかないことです。
弘化三年(一八四六)の正月がきました。
最初のえぞ地探検の記録整理もひときまりついた武四郎は、正月の二日、はやくも二回めのえぞ地探検をめざして、旅にてました。
江戸で親しくなった石井津香、それに峯田楓江の二人が、千住大橋まで見送りにきてくれました。
今度はまず江差の斎藤佐八郎の家に身をよせました。
さっそく出迎えた息子の作左衛門は、武四郎に会うなり、いいました。
「武四郎さん、今度はいい知らせがありますよ。」
「一体、それは?」
「あなたはこのまえ、カラフトヘ渡りたいとおっしゃっておいででしたね。それがかないそうなんてす。」
「それはありかたい。で、どうすればいいのです。」
「松前藩の医師。西川春庵先生は、今度カラフト詰のお役になりました。
あなたは春庵先生の召使いということにしてもらいましたから、先生と一緒にカラフトヘ渡って、思う存分歩いてきてください。」
武四郎はすっかりうれしくなってしまいました。
その頃は幕府の役人ででもないかぎり、カラフトヘ渡ることは、きびしくとめられていたのです。
もう一つ、うれしいことがかさなりました。カラフトヘの出発をまぢかにひかえた四月十日のことです。
いきなり、正月千住大橋でわかれた石井潭香(たんこう)が、訪ねてきました。潭香は、
「今度、石狩場所詰の役人になったのでね。ここでまたあなたに会えようとは、全く思いもかけなかった。」
と、いいました。
本当に思いがけないことでした。二人は、うれしさのあまり、一晩中、語りあかしました。 |
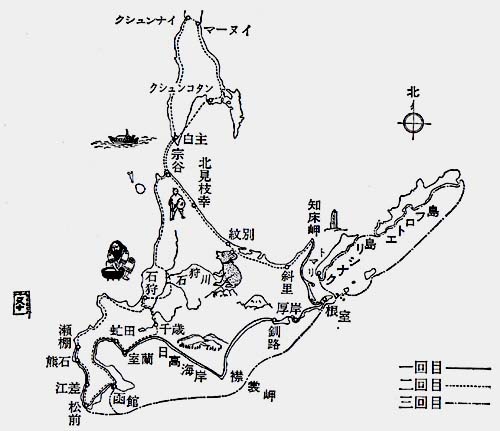
えぞ地探検、一・二・三回目(1845〜49年)のあと
|
潭香は、まもなく石狩にむかって出発していきました。
武四郎もあくる日、あとを追うようにして、カラフトにむかいました。
武四郎は、名を雲平とあらためています。かんばんとよぶはっぴを着て、なわの帯をしめた、ぞうりとりの姿です。
今度は、西えぞの海岸にそって北へのぼるコースです。
五月の中ごろ、宗谷につくまで、一ヵ月あまりの苦しい旅でした。
けれども、この“ぞうりとり雲平”は泣きごとをいうひまもありませんでした。
それは、アイヌ語を勉強し始めたからです。
(去年、知床まで足をのばしたときは、アイヌ語が全くわからないために、見たり聞いたりしたことの、半分も理解できなかった。こんなことでは、いくら奥地へ足をふみ入れても、何の役にもたちはしない。)
こう思った武四郎は、道案内や、荷はこびにやとったアイヌだちと、できるだけ多く、話をかわすようにしました。
手まねをまじえながら、一つ一つの言葉の意味を、お互いに確かめあっていくのです。
こうして覚えたアイヌ語を、武四郎は日本語とならべて、書きしるし、辞書の原稿のようなものをこしらえていきました。 ひとには見せませんでしたが、「蝦夷語(えぞご)」と名づけられた対訳辞書の草稿が、今日も残っています。
宗谷についた一行は海上は十二キロを船で渡って、カラフトの白主(しらぬし)へ上陸しました。
そこから二組にわかれて、東西両海岸を見てまわることになりました。
武四郎は東海岸の組になりました。
今はサハリンとよんで、ソ連領に入っていますが、この島はもともと日本人の方が早くはいりこんでいました。
イギリス、フランス、ロシアなどとあらそって探検隊をおくるようになったころ、間宮林蔵は、いまの間宮海峡を発見して、カラフトは、シベリア大陸からはなれた一つの島てあることを確かめました。
それは、武四郎が生まれるより久十年もまえのことでした。
けれども遠いため、政治の手が充分にのびずにいたのです。
幕府もいつまでもだまって見すごすわけにいかず、直接の統治下におくために、今度の調査旅行となったのでした。
実際の調査旅行となると、武四郎は身分こそぞうりとりの雲平(うんぺい)ですが、一行のなかでも、もっとも熱心な調査官となりました。
なにしろ、アイヌ語を覚えてかかろうとしているくらいですから、意気ごみがちがいます。
二ヵ月ちかくカラフトを歩いてまわり、七月の中ごろにようやく宗谷に戻りました。
そこから武四郎は一行とはなれて、一人でもうすこし東エゾを見てまわることにしました。
もうぞうりとりではありません。アイヌを一人やとって道案内につけ、宗谷から知床へむかったのです。
知床には去年、自分が来たしるしに、柱がたててあります。その地に、もう一度立ってみたいと思いました。
柱は、そのまま北海の風にさらされて立っていました。
柱の裏側に、あらためてその日の日付と、自分の生まれ故郷と名前をしるすと、武四郎はほっと、肩の荷が一つおりたような気分になりました。
根室海峡のむこうには、エトロフ、クナシリ、ハボマイ、シコタンなどの島々が見えます。
ちょうどさしのぼる朝日をうけて、海上にうかびあがって見えました。
武四郎は思わず一つの歌を高らかに歌いました。
| 玉ぼこの みちのく越えて 見まほしき えぞが千島の 雪のあけぼの |
これは水戸学で有名な藤田幽谷の子、藤田東湖のつくったものです。
藤田東湖もお父さんの名をけがさない立派な学者でした。
武四郎は自分より十二ほど年上の東湖を、かねてから尊敬の念でみつめていました。
学問的に尊王攘夷思想をつきつめていった東湖が、水戸で学の道にはげみながらも、外国船がしきりに近づいているえぞ地を心にかけているさまが、歌いこまれています。
武四郎は、この歌を朝日の中にうかぶ島々にむかって、歌いました。
こうして、東湖にかわって、自分がいまここに立っていることを知らせようとしたのでしょう。
八月の中ごろにはまた宗谷にもどり、今度は西えぞにまわって、石狩にでました。
石狩ではアイヌの舟で、千歳川をくだってみました。丸木舟です。屋形もなにもありません。
大きなフキの葉っぱを舟の胴なかにかぶせて、日よけや、雨よけにするのでした。
こうして千歳に出て、峠をこえて東海岸にくだり、江差に帰りついたのは九月の初めでした。
江差の斎藤の家に帰るとまもなく、一人のさむらいが訪ねてきました。
「頼(らい)三樹三郎(みきさぶろう)と申します。」
「おお、頼(らい)山陽(らいさんよう)どのの………。」
そうです。やはり水戸学の大だて者、頼山陽の三番めの子にあたります。
頼山陽はすでに文政十年(一八二七)、『日本外史』という歴史の書物をあらわして、ひろく世に知られていました。
けれども息子の三樹三郎は、文政八年(一八二五)生まれですから、武四郎よりも七つ若いことになります。
武四郎のように小柄で、ひきしまった体をしていました。
「この江差へは、いつおいでになりました。」
「まだ、ついたばかりのところです。とくに目的があってきたわけではありません。
こちらには、エゾ地にくわしいあなたがきておられると、土地できいたので、お訪ねしてみました。」
三樹三郎は自分の旅を、そんなふうにいいました。この出会いは実際に偶然のことでした。 |

アイヌの舟で千歳川を下る
|
弘化三年といえば、幕末の勤王運動丸相当はっきりした形のものになっていました。
三樹三郎は、すでに勤王の志士として、その名が知られていました。
それで、幕府が“要注意人物”として、目をつけていたのです。
その警戒のあみをくぐって、えぞ地までくるのは、大変なことでしたでしょう。
「よくこられました。私は奥地の旅から戻ったばかりです。」
武四郎は、三樹三郎を、暖かくむかえました。
二人の話はさっそく、えぞ地が今、どんなありさまなのか、ロシアがどんな手をうってきているか、といったようなくわしいことにまでたちいっていきました。
こうして、初めて会ったばかりというのに、この二人けを、まるでずっとまえからの知合いのように、親しみを感じる仲になってしまいました。
けれども、どうも武四郎のみるところ、三樹三郎は、すこし元気がありません。
それとなくたずねてみると、どうやらお金がとぼしいようです。
(遠い旅の空で、ふところがさびしいほど、つらいことはない。
なんとかしてあげたいが、私がありあまるほど持っているというわけではなし、どうしたものか………。)
武四郎はこまりはてて、斎藤作左衛門に相談してみました。
作左衛門は、しばらく考えていましたが、やがていいました。
「そうだ、いいことがある。
頼三樹三郎さんは学問で有名な頼家のご出身だから、定めし詩がよくおできになるでしょう。
それに武四郎さん。あなたは絵もうまいし、てんこくの技も身につけておられる。
一つ、書画会を開いてはどうですか。
松前のあたりには文学に親しむ人たちがたくさんいますから、きっと大勢あつまりますよ。
書画会によせられる賞金や、ご祝儀を三樹三郎さんにあげたらいいでしょう。」
武四郎も、手をうってこの案に賛成しました。
さっそくそのしたくにとりかかりました。
そして、十一月十四日、雲石楼というところで会を開くことにしました。
当日になると、作左衛門たちの宣伝もうまかったのでしょう。
たくさんの客があつまり、雲石楼の広い座敷は、人でいっぱいになりました。
そのころ江差は、千石場所といわれ、ニシンの漁場として、えぞでもっとも栄えた場所でした。 |
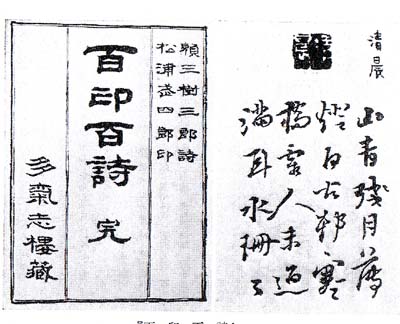
三樹三郎のために開いた百印百詩の会
|
それで、地元の大商人たちも、書画に親しむゆとりをもっていましたし、その栄えた土地をめざして、京都や江戸からも、たくさんの文人や、画家が渡ってきていました。
それらの人たちが、そろって雲石楼におしかけたのです。
このとき、三樹三郎と武四郎が演じた。「一日百印百詩の会」は、大変有名なものです。
それは朝八時から午後六時までかかって、会場の人からあたえられた題で三樹三郎が漢詩をつくり、武四郎がその題字をろう石にほりこんで印をつくる――これを百回もくりかえしたものです。
詩をつくるのと、印をけるのと、どちらが早くできるか、かけるわけです。
一つ一つできあがるごとに、勝つた負けたで、会場はわきたちました。
むずかしい字がでると、がぜん武四郎のほる手がてまどります。
なかには“しらみをひねりつぶす”といった意味の、おかしな題をだす客もあります。
そんなときは、三樹三郎のほうが、めんくらって、おそくなったりしました。
こうして、二人は、次々とだされる題に、夢中でとりくんでいきました。
そうして、とうとう百回めがおわったとき、武四郎のほうがすこしはやかったのでしたが、くたくたにつかれきった三樹三郎と武四郎は、思わずだきあってしまうのでした。
たくさんあつまったご祝儀や賞金は、全部三樹三郎にわたされました。
ただひとにあまえるだけでなく、自分の身につけた技で、困っている人を救ってあげられたわけです。
このとは、三樹三郎が漢詩を書いた色紙は、いまも何枚か、残っています。
けれども、武四郎のほった印はすべて散りぢりになってしまい、今はどこに残っているかわかりません。
でも、その色紙を見ると、詩も印もあわただしく即席につくったとは思えないほど、しっかりしたできばえになっています。
6 だまっていられるものか top
頼(らい)三樹三郎(みきさぶろう)と、“一日百印百詩”を行ってからあと、武四郎は弘化四年(一八四七)の五月まで江差にとどまりました。
それから江戸にもどり、またメモの整理にとりかかりました。
この仕事に、武四郎はあくる年。嘉永元年いっぱいをかけています。
あいだに、房総半島の旅にでかけたりもしましたが、探検の記録を整理するとなると、武四郎はまさに一刻もおしいかのような真剣さで、取組むのでした。
けれども、嘉永二年(一八四九)になると、もう武四郎はじっとしていられなくなりました。
その年の二月、三十三歳になった武四郎は、三度めのえぞ地探検にかかったのです。
今度の目的地は、エトロフ、クナシリです。
知床半島で海のかなたにながめたそれらの島に、どうしても渡ってみたかったのです。
二月十日に江戸をたって、四月七日に松前につくと、クナシリヘの船をさがしました。
今度は、クナシリ請負人の柏屋喜兵衛の持ち船にのせてもらえることになりました。
クナシリに渡ると、武四郎は足まめに歩きまわって、土地のアイヌだちからいろいろなはなしを聞きました。
もうこのころは武四郎のアイヌ語は、かなりうまくなっていて、日常の会話ぐらいは楽にやりとりできるようになっていたのです。
こうしていろいろ調べていくうちに、武四郎は、しだいに暗い気持ちにおそわれてきました。
それは、いままでもちょくちょく聞いてはいたのですが、場所請負人が大変あくどいやりかたで、アイヌたちを苦しめていることが、はっきりわかってきたからです。
まえに、カラフトの旅から帰ってきて、あくる年の五月まで江差にいたとき、武四郎はそれとなく、松前藩の内部のようすをさぐってみました。
場所請負人たちは藩の家老や重臣などと手をむすんで、うまくアイヌをだまして、大もうけをしているらしいということがわかりました。
それを武四郎は、江戸に帰ってから「秘めおくべし(かくしておくこと)」と題して記録しました。
けれどもこうして、クナシリという北の果ての地まできて、実際に場所請負人とアイヌたちとのやりとりを見ていると、それは思った以上にひどいものであることがよくわかるのでした。
クナシリ場所請負人柏屋は藤野喜兵衛といって、近江(滋賀県)の商人でした。
近江出身の商人は、江州者といって、とくに商売じょうずといわれていました。
この柏屋もその例で、松前藩の家老にとりいって、どんどん商売の手をひろげました。
柏屋の旗じるしは「又十」でした。
この旗じるしが、宗谷、利尻、礼文、北見枝幸、紋別、斜里、根室、クナシリなど、えぞ地の有利な場所を独り占めしていったのです。
その広さは、えぞ地の三分の一にもおよぶほどでした。
もうけることとなったら、どんなえらい人物にでも、手づるをつけてしまうのが柏屋でした。
のちに、安政六、七年のころは、時の大老井伊直弼にもねらいをつけ、幕府のご用商人となって、大もうけをしています。
それだけに、一方では弱い者にたいしては、情け容赦なくしぼりとることも平気でした。
えぞ地で柏凰のえじきとなったのは、もちろんアイヌたちです。
アイヌたちはすなおで、人がよいうえに、一般に学問がゆき渡っていませんでした。
内地からのりこんだ商人たちにとっては、もっともあつかいやすい相手だったわけです。
だましたり、おどしたりして、働かせるだけ働かせ、もうけはごっそりしぼりとるのも、朝めしまえでした。
請負人の考えかたがこれですから、その請負人の手足とたって働く者たちもアイヌを犬、猫のように見くだしていました。
さんざんいじめたり、いばりちらしたりして、わずかのほうびをあたえてごまかしていたのです。
「アイヌ勘定」という言葉がありました。
たちのわるい商人や役人たちが、アイヌから産物を買いあげるとき、数をごまかすやりかたをいったものです。
アイヌは川でとれたサケを持って場所の番屋へ持っていきます。
番人や下役人はそれを数えて、一ぴきいくらで買いあげるのですが、その数え方が問題です。
「それ、いいか、一つ。一つ。二つ。三つ。四つ。五つ。六つ。七つ。八つ。九つ。十。全部で十だ。いいな。」
アイヌは、目をパチクリしながら首をかしげます。
気の弱い者は、これでひきさがってしまいますが、なかには質問する者もいました。
「ニシパ(だんなさま)。それ、十でない。十と一つです。」
こんなことをいおうものなら、大変です。番人は、血相をかえてどなりつけます。
「ばかやろう、勘定も知らねえで、文句をつける気か。てめえは、そんなやつはひっこんでろ。
文句をいうやつは、金をはらってやらんぞ。さあ、そっちのクーチソコロ、持ってきたのを、ここへだしてみろ。」
もう一人のアイヌがおずおずと、サケをさしだします。 |

クナシリの請負人は悪徳商法でアイヌをいじめていた
|
「ようく見ていろ、いいか、一つ。一つ。二つ。二つ。三つ。四つ。五つ。六つ。七つ。八つ。九つ。十。ほら、十だろう、」
「ニシバ、それ、ちがう。十と二つだ。」
「わからねえやつたな。一つ、一つ、二つ、二つ。ほら、二つといったじゃねえか、わかったか。」
落語に「ときそば」というのがあります。屋台のそばやで、利口な客は、そばの代金を一文、二文と数える途中で“いま何どきだ”と聞いて、一文ネコババするのですが、それを見てまねをするばかな客が、時刻を知らずにやって、かえって損をするという話です。
アイヌたちは、みすみす目のまえで、一ぴは、二ひきと、サバをよまれて、ごまかされてしまうのです。
へんだなあと、指をおって数えなおし、首をかしげているあいだに、どんどん順番はつぎにまわされて、文句をいっても、とりあってくれません。へたをすると、
「てめえは、おれさまの勘定に、いいがかり、をつける気か!」
と、ぶんなぐられるのがオチでした。
でも、こんなのは、まだまだ罪のあさいほうです。
いってみれば、番人や下役人の、みみっちい小づかいかせぎでしかありません。武四郎が、
「これは、ゆるしておけない!」と、ふかいいきどおりを感じたのは、アイヌを使う人たちの考えかたそのものでした。
「アイヌだって、同じ人間なのだ。日本人は、アイヌが文字を知らないからと、ばかにする。
アイヌには、アイヌの立派な文化が伝えられているのだ。
それを知らずに、犬、猫のようにいじめつづけることは絶対に許せない。」
アイヌ語がはなせるようになって、アイヌだちといろいろ話をしてみるにつれて、武四郎はアイヌが立派な民族で、すぐれた文化をうけついできていることが、わかってきました。
そういうことを知らずにただばかにして、権力にまかせてのしかかるやりかたが、武四郎にはどうしても許せないのでした。
「よし、このようなアイヌの人たちをすくうためにも、自分はもっとえぞの奥地も調べあるき、正しいアイヌの姿を、本当のえぞ地の価値を無知な人たちに知らせよう。」
武四郎は、ますます決心をかためるのでした。
エトロフ、クナシリの旅をおえて江戸に戻った武四郎は、嘉永三年(一八五〇)から安政元年(一八五四)までの四年間。ひたすら探検記録のまとめにはげみました。
一回のえぞ探検ごとに、数十冊の記録にまとめるのです。
それらは『初航蝦夷日誌』『再航蝦夷日誌』『三航蝦夷日誌』などと名づけられて、今日も残っています。
行く先々で見たり聞いたりしたことを、くわしく文章にしるし、さし絵や、地図もたんねんに自分で書いてつけくわえてあります。
エゾの歴史を調べるのに、今日も役にたつ立派な書物となっています。
そのほかにももたくさんあらわしています。それらのなかに『蝦夷大概図』というのがあります。
これは、えぞ地の地図です。北海道の地図が世間に公表されたのは、こわが最初でした。
そのようなたくさんの著作のなかで、『蝦夷葉那志(ばなし)』というのをのぞいてみましょう。
これは、アイヌの伝説、風習、生活などをしるしたものです。中身は、十の話からなっています。
「起元」 (アイヌ民族のおこりについて)
「ウキクルミ・シャマイクルのこと」 (義経・弁慶について)
「ヤンカラブッテのこと」 (あいさつについて)
「サイモンのこと」 (まつりのとなえごとについて)
「イナヲのこと」 (神前にそなえるけずりかけについて)
「ヌシヤサンのこと」 (シカやクマの頭の骨への信仰について)
「イフミヌのこと」 (うらないについて)
「シフノサのこと」 (まじないについて)
「オムシャのこと」 (酒ふるまいについて)
「子供遊びのこと」
初めの「起元」について、およそをお話しましょう。
もともとアイヌ民族は文字というものをもっていません。これは世界の人類のなかでも、めずらしいことです。
文字がありませんから、アイヌの歴史や、伝説はすべて人の口からロヘ、語りつがれてきたものです。
長い年月のあいだに、それは節まわしのついた歌になりました。それが「ユーカラ」です。 |

アイヌの生活
|
アイヌたちは、お酒が大好きです。酒もりをよくやりました。
そして、お酒をのんで興がのってくると、ユーカラを歌いました。
炉辺をたたいて、拍子をとりながら、夜どおし歌いつづけるのです。
こうして子から孫へと歌いつぎ、かたりついで、自分たちの文化をまもりそだててきたのです。
口から口ヘと伝えるのですから、年月がたつにつれて、間違って伝えられたり、覚えちがいをおこしたりもしたことでしょう。
だから、ユーカラで伝えたことは、そのままアイヌの歴史であるとはいいきれません。
けれども、歴史を知る大切な手がかりになります。また、ユーカラの底に流れるアイヌ民族の、こうありたい、こうなりたいという願いや誇り、悲しみなどは、聞く人の心をうつものがあるのです。
そのユーカラの一つによると、アイヌ民族のおこりは男女二柱の神が、空からくだってきたことに始ります。
えぞ地のあたりも、大昔は一面の青海原でした。
それが、いつのころからか、海の底から大地がつき出してきて、日ましに大きくなり、ついに山の形となりました。
そこへ島つくりの神さまが天からおりてこられました。
つづいて女の神さまが、五色の雲にのっておりてこられ、二柱の神さまは、力をあわせて島づくりにとりかかりました。
女の神さまが、黒い雲をちぎって海に投げ入れると、みるみるうちに、大きな岩ができあがりました。
男の神さまと二人で、ちぎっては投げ.ちぎっては投げするうちに、あたり一面ゴツゴツの岩だらけとなりました。
と、今度は神さまたちは、黄色の雲をちぎって投げ始めました。 |

好きなお酒を飲んでユーカラを歌うアイヌ
|
なにができたと思いますか?土です。岩と岩のあいだをうすめて、土地ができていきました。
「これでは、いかにもすさまじいながめだ。」
そうつぶやいて、今度は青い雲をちぎって、地面に投げちらしました。
みるみるうちに、草木がおいしげり、住みごこちのよさそうな土地ができあがっていきました。
「海には、海の幸を!」そうとなえて、白い雲を海に投げ入れました。
と、白い雲は海のなかでサッと散って、たくさんの魚や、えびに変わり、にぎやかにおよぎ初めました。
「宝物も、ほしかろう。」最後は赤い雲です。
これは、神さまがなにやらとなえごとをなさると、たちまち金・銀などの、目もまばゆいほどの宝物となりました。
そこへ、どこからともかく、一つがいのフクロウが飛んできて、神さまのまえで、なかむつまじく遊んでいましたが、やがて、フクロウも二柱の神さまも、空高く舞いあがってゆき、やがて見えなくなりました。
それで、アイヌは、フクロウを神の鳥とあがめて、大切にしています。
みなさんは、この話を読んで、日本の神話にある、イザナギノミコト、イザナミノミコトの話を思いだしませんか。
民族はちがっていても、その発想にはどこか似かよったところのあることが、おもしろいと思います。
「子供遊びのこと」には武四郎が見つけたアイヌの子供たちの遊びが、いくつか紹介されています。
春になって、暖かい季節がおとずれると、アイヌの子供たらは浜辺ヘ出て、にぎやかに遊びたわむれます。
アカミチウという遊びは輪さしとでもいいましょうか、直径二、三十センチの輪を砂浜に埋め、子供たちは、一メートル半ぐらいの竹ざおを持って、砂浜をついて歩きます。
一つでも多く輪をつきあてた子が勝ちです。
竹で、おけのタガのような大きな輪をつくり、なわをぐるぐるとまきつけたものを、空高く投げあげる遊びもあります。
「そうら、いくぞお!」
みんなは、手に手に竹ざおを持って待ちかまえています。
大きな輪が空から落ちてくると、あらそって手にした竹ざおでその輪を受けとめようとするのです。
弓矢で、輪を射ぬいて、あらそうこともあります。
また、大きな輪に、縦、横十文宇になわをはり、これを地面に転がします。
子供たちは左右に弓矢を持ってならんでいて、ころがってきた輪に、すばやく矢を射こむのです。
このような遊びのどれを見ても、それはアイヌの狩りや漁の技につながるものばかりです。
小さいときから、遊びをとおして、きびしく技をみがいているのでしょう。
なお、武四郎は、「えぞ」という言葉に「蝦夷」という字をなぜあてはめたのかをしるしています。
アイヌは、おたがいをよびあうのに、「カイノー!」といいます。
その時、えびのように背をまるめます。
その姿を見た日本人が「蝦(えび)のように背をまるめた夷(えびす=野蛮人)」ということで「蝦夷(えみし)」の文字をあてはめたのだそうです。
旅にあけくれて、伊勢の家へ帰ることも忘れてしまったような武四郎は、江戸では宿なしみたいなものです。
たくさんの書物をつくることにうちこんでいた四年間、武四郎は、たびたび居どころを変えました。
武四郎のひたむきな心に声援をおくる親切な人たちを、つぎからつぎへとたよって、間借り暮らしをつづけていたのです。
もうその頃は、武四郎の名は、かなりひろく世間に知れ渡っていました。
普通の人なら二の足をふむ遠いえぞ地へ、三回も渡っているのですから、よっぽどの変わり者だと思っていた人も多かったでしょう。
でも、心ある人々は幕府の役人でもないのに、自分で苦労して旅費を工面してはえぞ地探検にでかける。
その心ざしを貴いものと思うのでした。
しだいに、武四郎のもとを訪ねて、えぞ地のことについて、武四郎から意見をもとめる人もふえてきました。
そこで、だまっていられなくなったのが松前藩です。
松前藩では武四郎がやってきても、はじめはべつに気にしていませんでした。
「たかが伊勢の郷士のせがれのことだ。ちょっとぐらいそこらを見て歩いても、何ほどのこともさぐれまい。」
と、たかをくくっていたのです。ところがだんだん.そうもいっていられなくなったわけです。
世間での名声はひろがる。えぞ地の地図は出版してしまうといったありさまで、このままほうっておいたら、松前藩がどんなに大もうけしているか、あばきたてられてしまうと、恐れ始めました。
実際まだ公表はしていませんが.武四郎は松前藩のやりかたについて、相当きびしい批判をくわえた書物を書いていました。それは弘化四年、第二回のえぞ探検をすましたあと、半年ほど江差にとどまったことがありました。そのあいだに、松前藩の内情をさぐって、しるしておいたものです。
それが前にもお話した「秘めおくべし」で、その名のとおり、武四郎は世間に公表はしませんでした。
松前藩の心配が、とりこし苦労とばかりはいえません。
「郷士のぶんざいで、ですぎたまねをする。けしからんやつだ。斬ってしまえ。」
と、恐ろしいことをいいだす者も、松前藩のなかにありました。
武四郎が有名になるにつれて、敵もふえました。その一人は幕府につかえる学者の最高責任者、林大学頭です。
武四郎はある日、町を歩いていて、とおりがかりの古本屋で、『婆心録』という、めずらしい本をみつけました。
これは寛政時代の老中。松平定信の書いた書物です。
松平定信は名高し“寛政の改革”をおこなった人で、幕府の政治そのものについて、ふかい考えをもっていました。
いつの世でも、はげしい改革をおこなう人に、反対者はつきものです。
寛政の改革も、きびしすぎて、さまざまな反対意見もありました。
けれども土台がゆるんでガタガタになった幕府の政治は、この寛政の改革によって、一度はシャンと腰をたてたのです。
松平定信は老中の座をしりぞいてから、自分のおこなった改革政治も反省しながら、
「政治のこと、世の中のことは、こんなふうに考えていかなくてはならないのではないか。
老婆心のようで、わかりきったことかもしれないが、自分の気持ちを世の人に知ってもらいたい。」
と、そんな意味でつづった文章をおさめた書物――それが『婆心録(ぼしんろく)』でした。
「これはよい書物がみつかった。このままうずもれさせてしまっては、もったいない。
世の中の人に、ひろく読ませたいものだ。」
武四郎は、こう思いました。思うと、すぐ行動にうつすのが、武四郎のつねです。
自分のお金で出版し、親しい人たちにくばりました。
これは、林大学頭をおこらせてしまったのです。
「定信公の書かれたものを、身分のひくい者がかってに出版するとはでしゃばりもはなはだしいしというわけです。
考えてみれば、おかしな話です。
それほど、定信公のことをうやまうならば、幕府の仕事としてするべきはずのものです。
それをおこたっていて、身分のひくい者がしたからといって、カーツと頭にきたというのですから、かえって林大学頭がボロをだしたかっこうです。
身分格式のある人たちに、ありがちな間違いともいえましょう。
そこへいくと、武四郎は気がらくでした。どこの藩につかえているわけでもありません。
水戸藩の同志からは旅費を工面してもらったり、いろいろ助けてもらっていました。
けれどもそれは、エゾ地にたいして関心をもっている水戸藩が、そのことについてくわしい学者に、もっとよい仕事をしてもらうために、援助の手をさしのべているだけで、藩士としてかかえているわけではありません。
だから武四郎は、思ったことを行動に移すにしても、誰かえらい人にお伺いをたててからというような、気兼ねはしなくていいのです。
その気楽さから、つい簡単に行動をおこしてしまう。
そのために思わぬ方向から、わざわいをまねいたことも、たびたびありました。
「このままでは、あなたの身の安全が心もとない。何とかして、まもってあげたい。」
と、武四郎のことを心配してくれる人もありました。けれども、武四郎は平気でした。
「反対する者があるからといって、自分の足で調べてまわったことを、こっそりかくしているわけにはいかない。」
と、せっせと著作の筆をすすめるのでした。
こうして三回めのえぞ探検の記録『三航蝦夷日誌』の原稿もできあがると、嘉永五年(一八五二)の正月、武四郎は、ひさしぶりに伊勢へ帰りました。
えぞ地を心ざしてふるさとをはなれてから、八年ぶりでした。
荷物のなかには、できあがったばかりの『三航蝦夷日誌』の原稿が大切におさめられていました。
伊勢につくと、まっさきに皇太神宮へおまいりして、日誌のできあがったことを奉告し、それから先祖の墓にもおまいりしました。
「さあ、今度は、なつかしい平松楽斎先生にお会いしよう、」
武四郎は、いそいそと津の平松塾をおとずれました。
ところが先生は、つい六日まえになくなられたとのこと、おりから、初七日の法事が行われている最中でした。
「ああ、先生………。」
武四郎は、言葉もなく、まあたらしい墓のまえにぬかづきました。
そして、声をあげて泣きくずれてしまうのでした。
旅にあけくれる者にとって、ふるさとはなにものにもかえがたい、暖かい思い出の土地です。
けれども伊勢の人たちにしてみれば、武四郎がなぜそんなに、遠いえぞ地に夢中になっているのか、理解できないことでした。
「庄屋の息子の道楽だろう、」
こんなささやきも聞かれました。
そのような雰囲気のなかで、平松楽斎先生だけは、武四郎の考えていることを、よく理解していてくれました。
だから、わざわざできあかった記録に目をとおしてもらいたくて、津まで戻ってきたのです。
「いくらくやんでもはじまらない。これからは、よりいっそう立派な仕事を残すよう、せいいっぱいつとめよう。」
武四郎は先生の墓のまえで、あらためて誓うのでした。
7 黒船がきた! top
年はあけて嘉永六年(一八五三)となりました。
嘉永六年といえば、アメリカのペリーが、四隻の軍艦をひきつれて、浦賀にやってきた年です。
日本国じゅうが天地をくつがえすような大騒動に見まわれました。このとき武四郎は、どうしていたのでしょう。
ひさしぶりにふるさとの土をふんで、嘉永五年の夏、武四郎は江戸に戻りました。
そして、嘉永六年の六月四日、武四郎は用があって日本橋のあたりにでかけました。
ふと見ると、河岸に見なれない舟が五、六艘つながれていて、何となくあたりがざわめいています。
「何かあったのですか、あの舟はなんでしょう。」と、そばにいた人に訪ねました。 |
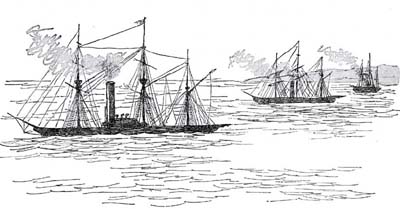
明治維新の始まり、黒船がやってきた!
|
「浦賀からきた早船だそうです。」
「早船? 何かできごとがあったのですか?」
「さよう、きのう、黒船が浦賀にやってきたということです。」
黒船といったのは、船体か黒くぬられていたためについたよび名です。
その頃日本で船といえば、手でこぐか、帆に風をうけて走る船しがありませんでした。
それなのに、浦賀にやってきたアメリカの船は、船体が大きく、帆もつけていますが、走るときはもくもくと煙をふきあげます。蒸気船だったのです。
えたいの知れない大きな船によせる恐ろしさも、黒船の“黒”という言葉にこめられていたのかもしれません。
早船の知らせは、いちはやく江戸の市中にもひろまりました。
けれども、それは人々の口から口へのうわさばなしにすぎず、くわしいことはさっぱりわかりません。
(もっとよく知りたいのだが――。)と、落着かない気持ちでいるところへ、かねてからつきあっていた宇和島藩のさむらいから、武四郎によびだしがかかりました。いってみると、
「大変なことになりました。宇和島藩ではこのさい、品川、御殿山をまもるようにと、幕府から命ぜられました。
ところが折悪くく、殿さま伊達宗城(だてむねなり)公は国おもてへお帰りになっておられまして、江戸の藩邸の人数だけではたりません。申しわげないが、あなたも、手伝ってくださらぬか。」ということです。
武四郎は、二つ返事で承知しました。
宇和島藩邸からの帰り道、武四郎は、神田に店をもつ友だちの質屋を訪ねました。
「革ばかまを貸してくだされ。」
そのつぎは古道具屋ののれんをくぐりましにた.
「陣笠ひとはり売ってくれ.紋はなんでもかまわぬ。」
こうして家に帰ると、メリヤスをカキのしぶでそめて、胴まきのようにこしらえました。身につけてみると、大変軽くて、動きやすい戦じたくとなりました。
「これでよし。いつ宇和島藩から出発の声がかかっても、大丈夫だぞ。」
この身なりで、大砲をそなえた軍艦と戦おうというのですか、いまから考えればマンガみたいなものです。
でも、その頃の日本のさむらいの、おおかたはこのていどの考えでした。その証拠には江戸市中の武具をあきなう店に、一度にどっとお客がおしよせました。
そしてあらそってよろい、刀、やりなどを買いあさり、武具の値段が、いっぺんにはねあがったといいます。
こんな騒ぎをよそに、黒船は立ち去ったという知らせは、また江戸市中にながれました。
(なんだ。から騒ぎでおわってしまったか。)
何となく、拍子ぬけしたような思いでいました。
そんなある日、武四郎のところへ、若いさむらいが訪ねてまいりました。
「てまえは、長州藩の吉田寅次郎と申す者です。」
長州藩(山口県)といえば、水戸藩とならんで、勤三思想の強いところです。
古田寅次郎というよりも、吉田松陰と号でよんだほうがみなさんにはわかりやすいでしょう。
その松陰は、長州藩にあって、勤王の志士としてさかんに活躍していました。
武四郎も、名前は聞いていました。
目のまえにいる松陰は顔色の青じろい、神経質そうな青年でした。 歳は、武四郎より十二下の二十四歳。二人が会うのは、これが初めてでした。 |

吉田松陰が武四郎を訪ねてきた。その後、松陰は黒船に乗り込んで
オメリカ行きを願ったが、ペリーに追い返され、幕府につかまった。
|
けれども、松陰のほうでも、武四郎のはたらきをよく知っていました。
「松浦武四郎どのは、水戸藩の方々ともした親しくおられ、われら勤王派の考えておりますところも、ご理解いただいておることとぞんじます。
黒船がもらわれて、日本国一大事のとき。
国のまもりをどうしたらよいか、ぜひあなたとお話がしたくて、まいったしだいです。
そのことについてはあなたの右にでる人はないと、うけたまわっております。
その体験をもとにして、どうぞご意見をお聞かせください。」
言葉ていねいに松陰にたのまれるまでもありません。
武四郎も、それはのぞむところでした。
二人は、さっそく、昔からの友だちのように、心をうちわって、熱心に話あうのでした。
松陰がきてからというもの、武四郎のもとへは、次々と長州の志士たちが訪ねてきました。
水戸藩士とのつきあいも、ひんぱんになりました。
武四郎の毎日、なにやら勤王の志士めいた、いそがしいものとなりました。
その頃日本国内は上を下への大騒ぎになっていました。
国の政治が安定して、みんなが多少の不満はあっても、何とかあすに希望をもてる暮らしであれば、国民の意見が極端に散りちりばらばらになってあらそうということはありません。
けれども、政治をとりしまる側に、大きな迷いがあって、やることがチグハグになってくると、国民一人一人が、不安でいたたまれなくなります。
そして、めいめいが自分の知識でわかる範囲のことを主張し始めこんがらかってくるものです。
この時代は、まさにそれでした。
幕府は寛永十六年(一六三九)にキリスト教を禁じ、オランダと中国をのぞく、すべての外国が日本に近づくことを禁止してしまいました。
それ以来二百年以上。ずっと鎖国政策をまもってきたのです。
けれども、そのあいだにヨーロッパでは産業革命がすすみ、航海術もどんどん発達しました。
こうなると、早く安くできる品物を売りさばく、取引さきをもとめて、アメリカを初めヨーロッパの国々が、アジアをめざして、次々と船をさしむけてきました。
ロシアも遅れをとるまいと、貿易と、領上への野心もふくめて、日本のまわりをうろうろするようになりました。
幕府は、いたたまれなくなって、文政八年(一八二五)に、日本に近よる外国船は、すべて打ち払えという命令を全国にだしました。
でも打ち払うといっても、何で打ち払うのでしょう。
相手は、海にうかぶ大きな船です。大砲も発達しています。
ところが、日本は小さな島の要所要所に、旧式の大砲をすえて、あとは昔ながらの一騎打ちしか知らないさむらいが、外国人が上陸してきたら斬ってやるぞと待ちかまえているといったしまつです。
時代にめざめたわずかの人たちは、何とかして外国の発達した文明を知ろうと、ただ一つ開かれた外国への窓オランダの書物をと対して、必死に勉強していました。
けれども残念なことに、オランダさえも遅れていたのです。
たしかに、幕府が鎖国を初めたころまではオランダ、ポルトガル、スペインなどは、ヨーロッパで大変な勢力をもっていました。
でもそののち、外国の勢力地図は大きくぬりかえられ、いまではイギリス、アメリカ、フランスなどが、文明のトップをきってあゆんでいるありさまです。
幕府のだした打ち払い令などは、それら文明のすすんだ国にとっては少しも恐いことはありません。
日本の近海には、年をおって外国船のくる回数がふえました。そして嘉永六年の黒船騒ぎとなりました。
アメリカは、ペリーを使節としておくりつけ、強い態度で幕府に開国をせまりました。
鎖国をやめて、アメリカと貿易しろというのです。
嫌なら大砲をぶちこんで、せめほろぼすぞといわんばかりのいきおいでした。
こらえきれなくなった幕府は二百年以上もちこたえてきた鎖国政策をすてて、安政元年(一八五四)、ついにアメリカと和親条約を結びました。
大雨のとき堤防にたった一つでも弱いところがあって、水がもれだすと、あっというまに大きくくずれ去り、大洪水をおこしてしまうでしょう。
これと同じように、アメリカと和親条約を結んだために、あとは外国の押せおせムードを支えることができなくなりました。
同じ年にイギリス、ロシアと、あいついで和親条約を結び、あけて安政二年には、フランスにも窓を開いてしまいました。
さあ、天下はおさまりません。やることなすこと、あぶなっかしくて、見ていられないというわけです。
明治維新の時代についてかたるとなると、すぐでてくるのが“尊王”とか、“攘夷”とかいう言葉です。これまで松浦武四郎についても、たびたび“勤王”という言葉をつかいました。勤王と、尊王は、同じ意味です。
徳川幕府が天下をとったとき、国をおさめるのに、権力の中心が二つあってはまずいので、政治の実際のことは幕府がやりますから、天皇はもっぱら文芸学間にはげまれて、国の文化を高めてくださいと、政治権力をいわば取上げてしまいました。
そういうやりかたは、やはり間違っていると主張したのが水戸学といえましょう。
そして、水戸学にそまった人たちが、もっと天皇をとうとぶべきだという考えから、幕府の政治にたいして批判をもつ――それが尊王派といわれる人々です。
また、一つの島国にとじこもって、ながく暮らしたため、すっかり外国人ぎらいになった人たちがたくさんいました。
はだの色、目の色がちがう外国人にたいする、おそれもありました。
そのおそれが、けがらわしいという思いに変わり、そんなけがらわしい人種に、日本の国土をふみあらされてたまるものかという考えになる。
こうして、攘夷思想もかたまってきました。
一方では、そんなことをいったって、日本では船といえば人間の力、風の力で走る船しかない。
ところが外国では、石炭をたいで湯をわかし、その蒸気の力で走る船、かできている。
そのほか.医学も発達しているし、ガラスや、毛織物など、日常の生活に便利なものが、どしどし作りだされている。
日本は、鎖国でねむっている間に、すっかり世界の文明にたち遅れてしまった。
一日もはやく外国と国交を開いて、この遅れを取戻さなければならないと考え、しきりに世間の人だちの目をさまさせようと努力する人たち――開国派が生まれました。
また、“そんなに幕府ばかりをせめないでくれ。幕府も、一生懸命なのだ。
何とかして、幕府の権威をもう一度建直して、外国にあなどられない、強い国にしようではないか。”
といった幕府を守りとおそうとする考え――佐幕派も、もちろん強力でした。
これらが入りみだれて、それぞれが意気にもえて同志をつのってはもみあっていたのです。
そのうえ、やっかいなことに、人の考えというものは、十人十色、みなちがうものです。
コチコチの尊王家や攘夷一点ばりの人がいるかと思うと、尊王・攘夷の両方の立場に立つ人、佐幕・攘夷をとなえる人、佐幕・開国をとなえる人といったように、複雑になる一方でした。
考えのちがうやつは邪魔だから斬ってしまえとか、権力をかりて牢にぶちこんでしまえとか、打ちつ打たれつでもみあいました。
そのあげく、もう、とにかく幕府を倒してしまうほか、この混乱をきり開く道はないと考える人たちがふえてきました。
この人たちが手を結びあって、なりたったのが明治維新ということになります。
話を、武四郎にもどしましょう。
苦心して仕上た『三航蝦夷日誌』三十五冊を、武四郎は水戸の徳川斉昭(なりあき)公に献上しました。
自分に目をかけてくれる殿さまに、探検の結果を報告したわけです。黒船騒ぎでわきたつ嘉永六年八月のことです。
その頃徳川斉昭は、幕政参与という資格で、幕府でうちだす政策に、強い発言権をもっていました。
もともと斉昭公は、思うことをズケズケと口にだす殿さまで、幕府でもことあるごとに、今度は何をいわれるかと、気にしていなければならない相手でした。
水戸学の親玉ですか、幕府にとっては、煙たい存在です。
けれども、黒船をおそれて、度を失っている幕府にとっては、斉昭公のように、決断力にすぐれた人の意見を聞かなければ、どうしていいかわからないありさまでもありました。
斉昭公の幕政参与で、よろこんだのは、藤田東湖(とうこ)を初めとする水戸藩の尊王攘夷を主張する人たちでした。
「幕府も、この六月に将軍家慶公がなくなり、あとつぎの家定公を、朝廷にみとめてもらわなくてはならない。
このさいあわせて、朝廷から攘夷をもっと強力にすすめろというご命令をいただくように、運動しようじゃないか。」
という意見がでてきました。
幕府は政治の実権はにぎっていますが、形式としては朝廷の命令で、すべてことを運ばねばなりません。
将軍をきめるにも“だれそれを征夷大将軍に任ずる”というご命令をいただいて、正式にきまるわけです。
その“征夷大将軍”という言葉が問題です。
昔、坂上田村麻呂がこれに任じられたときの“夷”は、東国に勢力をはる“えびす”、大和朝廷にしたがわない人々ということで、やはりひろい意味で日本人でした。
けれども、いまとなっては、日本は一つにまとまっています。
そのような時代に任じられる“征夷(せいい)”つまりえびすを征服するための大将軍といえば、そのえびすは、外国のこともふくめて考えていい、というのが、一応は筋がとおっています。
つまり東湖たちの考えは、
「朝廷から徳川家定を第十三代将軍に任命していただくときに、征夷大将軍なのだから、日本の国上を外国人にけがされないよう、努力しなさいと、あわせて命令していただこう。
そうすれば、攘夷は勅命、天皇のご命令ということで、だれはばかることかく実行できる。」
ということになります。
この勅命をいただくために、京都へいって、公家たちに働きかける仕事が、武四郎にふりあてられました。
武四郎は恩義のある水戸藩の人たちの役にたてばと、この役を引受け、嘉永六年の十一月に、この仕事も何とか責任をはたしています。
このあと、おかしなうわさか流れました。
武四郎が朝廷から院宣(いんぜん)と、錦の御旗をたまわったが、幕府にみつかりとらわれたというのです。
なになに院とよばれる太上(だじょう)天皇 * もおられず、錦の御旗なども、まだその頃は朝廷でも持っていません。
* 太上天皇 これは天皇がまだ幼い時などに代務を行う元天皇で、この時の孝明天皇は立派に勤めをはたせる成人で、太上天皇は不要だった。しかし維新の騒乱の中で、孝明天皇が突然36歳で崩御したので、明治天皇が15歳で即位した。
この時の経緯は『歴代天皇紀』肥後和男編に記載されている。
考えてみればこっけいなうわさでした。
けれども、朝廷がどの派につくかと、みんなが神経をピリピリさせていた時代の世相がしのばれます。
いまとなってみれば、武四郎のとった行動は時代の流れにさからうことともいえましょう。
このような朝廷をかつぎだす運動が、これからさき佐幕派、倒幕派、両方でおこったため、政治はますます混乱したのでした。
けれども、ロシアにおびやかされているえぞ地を、何とかまもりたい。
あわせて松前藩の無理なやりかたから、アイヌをまもってやりたいと思う、そればかりでえぞに首をつっこんでいる武四郎です。
それ以上に時のいきおいにめざめろと要求されても、無理だったことでしょう。
その点、吉田松陰となると、すこしようすがちがってきます。
はじめは尊王攘夷の考えでした。
けれども、日本とはくらべものにならないアメリカ軍艦の堂々とした姿を見ると、
「これはもっと外国のことをよく知らなければならない。」という考えにかわります。
外国のことをよく調べてから、日本はその外国にたいしてどういう態度をとったらよいか考えなくてはならないと思ったのです。
そして松陰は行動をおこしました。ベリーの軍艦にひそかにのせてもらって、アメリカへいこうとしたのです。
ペリーからはことわられました。松陰は幕府にとらわれてしまいました。
長州の萩で座敷牢に入れられた松陰は、やがて弟子をあつめて、松下村塾をひらきます。
そして、幕府のやりかたが、ことごとに後手にまわって、外国のいいなりに追いつめられていくと、あせりはじめました。
松陰は、幕府をたおす運動にふみきっていくのです。
ついには、井伊大老ににらまれて、安政六年(一八五三)、世にいう、安政の大獄“で死刑にされてしまいました。
すこしさきのことまでお話してしまいましたが、松陰はアメリカに渡りそこねて幕府にとらわれたその当時、武四郎にとっては、まだ幕府は必要なものでした。
尊王の思想はもっていても、幕府を倒そうとまでは思っていません。
それよりも、つぎの章でお話するように、えぞをもっと調べるためにも、幕府の権力を利用したいというところでした。
8 八方ふさがり top
「あわただしい一年だったな。」
武四郎は、江戸のわびずまいで、嘉永六年の暮れをむかえています。
えぞのことについては武四郎の右にでる人はないとまでいわれるようになっても、武四郎の暮らしは大変質素でした。
長屋の六畳一間を借りているだけです。
へやの中には、机が一つ、身のまわりの品や、大事な資料を入れた行李(こうり)が一つ、朝夕の食事は、たった一つの土鍋で、自分で煮たきするというありさまです。
三十七歳になっても、“ねぐら定めぬ渡り鳥”みたいに、旅に夢中になっていた武四郎はまだ独身です。
そのさむざむとしたへやへ、毎日のように、ひとが訪ねてきます。
それぞれ武四郎の、旅からえたゆたかな知識にあずかろうと、やってくるのです。
あけて年号は安政となりました。その正月、武四郎は、知合いの学者のところへ、年始のあいさつにいきました。
その学者が親切に教えてくれるところによると、近ごろ、松前藩ではしきりに武四郎の命をつけねらっているというのです。
その頃幕府ではさかんに南下してくるロシアの対策にくるしんでいました。
そして安政元年にはいると、どうしても、ロシアとの領土のさかいをはっきり定めなければならない事情に追いこまれてきました。 |

老後の武四郎の写真
|
幕府では、次々と役人を命じて、国境をどのように定めたらよいか、調べさせました。
けれども、誰もえぞや、カラフトについては、ほとんど知識がありません。
そこで、武四郎に応援をもとめてくることになります。
松前藩では武四郎のように、えぞ地にくわしい人間に、幕府の役人になられては、大変です。
一人“うまいしる”をすっているわけにいかなくなるからです。
そのようなことから、武四郎の命をねらっているなどという、ぶっそうなうわさも生まれたのでしょう。
殺さないまでも、何とかして武四郎を、幕府側にかかえこまれないように、さまざまな悪口を幕府の上のほうの人たちにふきこんで、邪魔だてをしました。
武四郎のまわりの人たちは心配して、安全なところへかくまおうともしました。
けれども武四郎は、べつに気にしていません。
「私は、なにもわるいことはしていない。見たとおりを、記録にとどめているだげだ。」
というところでしょう。
でも、この年も暮れちかくになったころ、一度、本当に“殺されるかな”と思ったことがありました。
家のまわりを、見なれないさむらいが、うろうろしているようたのです。
「ここにいてはあぶない………。」
さっそく身のまわりのわずかな荷物をまとめると、武四郎はさっさと引越してしまいました。
なにしろ武四郎は、刀も槍も全くけいこしたことがありません。
身をまもる武術ができないのですから、あぶないとなったら、逃げるよりほかに手がないのです。
これまで、刀をぬいたことといったら、函館の近くの峠で、いきなりクマとばったり出会ったときだけでした。
刺客のかげにおびえて武四郎が引越したさきは、何と馬小屋でした。
土間に四本の柱が立っているだけ、そのあいだに三枚の畳をしきたいのですが、そのままでは狭くてしけません。
畳の端を十五、六センチずつ切りおとして、やっと押し込むしまつです。
家財道具は、机と本箱、火鉢、土鍋、土瓶が一つずつ。茶わんと箸は、机のひきだしの中へしまえば、おしまい――といった、簡単な暮らしでした。
入口のところには、むしろが下げてあります。
どう見ても、乞食小屋といったところで、これでは刺客も、気がつくはずもありませんでした。
ある日、藤田東湖は、この馬小屋に武四郎を訪ねてきました。
むしろをはね上げて、馬小屋の中を見て東湖は、武四郎のやりかたがあまりにも極端なので、
「あっはっはっは………。」と、笑いころげてしまいました。そして、
「あとになったら、大笑いのタネになるだろう。」
といった意味の言葉を紙に書いて、武四郎にわたしました。
どんなにでもして、とにかく身の安全をはかっていてほしいという、東湖の暖かい友情です。
武四郎も、東湖の気持ちがわかっていさすから、この紙を馬小屋の壁にはって、朝夕ながめておりました。 |

松前藩の刺客に狙われるようになった武四郎は、
馬小屋を住いとした。そこを訪れる水戸の学者、藤田東湖。
|
すると、それからいく日かして、また一人の友達が訪ねてきました。
東湖の書いたものを見つけると、その男は、
「これではまだたらぬ。」といって筆をとると、「馬小屋の中での」という言葉を書きそえてしまいました。
今はひどいところにいるけれども、何とか頑張ってくれという気持ちなのです。
武四郎は、友だちの気持ちをありがたいと思いました。
何しろ、八方ふさがりのような毎日だったのです。
安效元年の初めには幕府から、さかんに声がかかりました。
けれども、ことごとく松前藩に邪魔されています。
松前藩のような現地の藩に邪魔をされたのでは武四郎としては、これ以上えぞ地へいくためにはどうしても幕府の“お雇い”というような形にしてもらわないかぎり、えぞへいっても、何にも仕事ができないことでしょう。
カラフトの境界線について、自分はどう考えるかというような意見書も幕府に出しました。
えぞ地の地図もつくってさし出しました。
また十月には、ロシアの船が伊豆の下田にきたので、幕府の役人の付人に加えてもらって、一緒に見にいきました。
その時の日記に、武四郎は、初めて見たロシア人の印象を、つぎのようにしるしています。
「一般にロシア人は、アメリカ人よりも背が高く、ふとっている。
人種としては五、六種あり、それぞれ服装がすこしずつちがう。
士官は、みな組糸のようなものをえりにまいている。大体の感じは、アメリカ人よりもすこしおろかのように見える。
すこし勇気もたりないようだ。でも、大変親しみやすい感じがする。
衣服は、アメリカ人よりそまつでラシャ(羊毛の服)を着ている者など、少ない。
アメリカ人は上陸して民家にもどんどん入っていっても、ロシア人はけっして入らない。
日本人のいうことは、アメリカ人よりも、よく守る。
アメリカ人はすぐ殺気だつが、ロシア人には、そんなようすはない。
いかにも、戦争をこのまないように見える。日本語の単語を知っている者も何人かいる。」
武四郎にしてみればえぞやカラフトで、きっとロシア人と交渉するようなことになる――その日のために、一生懸命ロシア人について観察をしておこうといった気持ちだったことでしょう。
このような努力も、安政元年のうちは、すべて実をむすばずにおわりました。
目のまえがひらけてきたのは、安政二年(一八五五)の春になってからです。
五月の初め、知合いの向山源太夫から、すぐ会いたいという使いがきました。
源太夫は、その頃はたいした役職にもつけないでいましたが、勉強熱心な人で、いつも外国関係の情報に心をくばっていました。
それで、えぞに夢中になっている武四郎にも、まえから目をかけてくれていました。
武四郎が訪ねると、源太夫はいいました。
「私は今度、函館奉行支配勤方(しはいつとめかた)という役をおおせっかることになった。」
「それはおめでとうございます。長い間ごしんぼうなさいましたかいがありました。」
「私のことを祝ってくれるよりも、そなたがひさしく願っていたこと、ようやくみのるであろう。」
「えっ! ………とおっしゃいますと………。」
「そなたを幕府のお雇いにするよう、私からもお上にお願いする。」
「はっ、かたじけなき幸せにぞんじます。」
武四郎はそれ以上、とっさのまに、お礼の言葉もうかばないほどでした。
源太夫の屋敷を出た武四郎は、本当に、足も地につかないようなうれしさでした。
もう、松前藩の邪魔をおそれることもなくなるでしょう。
「思う存分えぞ地を歩ける。
そして、アイヌのために、希望のもてる政治になるよう、意見を申したてることができる。」
武四郎は、明るい気持ちで、馬小屋のむしろをはねあげました。
そして、心のそこから、
「あっはっはっは………。」と、大笑いをするのでした。
9 カラフトの夏 top
「あけましておめでとうございます。」
安政三年(一八五六)の正月、武四郎は、堀織部正(ほりおりべのかみ)の屋敷へ、新年のあいさつにいきました。
主人の堀織部正はすでに函館奉行となって、えぞ地へおもむいてします。
武四郎の出発も、あと一ヵ月にひかえていました。
「今年は生きかえったような心持ちだ。」と、武四郎は、その日の日記にしるしています。
いよいよ二月の初め、えぞ地へ出発ということになりました。
今度は、にぎやかな旅立ちとなりました。水戸の徳川斉昭公を初め、ふるさと津の殿さま藤堂公や、そのほか方々から、せんべつももらいました。
千住の大橋までの見送り人八十五、六を数えるほどです。
これまでの、何のうしろだてもなく、自分一人の意志でえぞ地にむかった旅とくらべて、武四郎はうれしいような、ほろにがいような気分を味わうのでした。
三月の六日、武四郎は六年ぶりで、四度めのえぞ地に立ちました。
今度幕府の役人が大ぜいえぞ地にふみこんだのは、今まで松前藩にまかせていたえぞ地を幕府が直接管理することになったため、松前藩から領地の受渡しをするのが主なねらいでした。
国のまもりのひとつとして『北方の地域を幕府が大切なものに思うようになったからです。
そうなると、もっと交通が便利にならないと、いろいろな政治上の用事が手間どって大変です。
そこで武四郎は、西海岸に新しく道をきりひらくことを提案しました。
この提案はすぐうけいれられ、武四郎は西海岸に、どのように新道をきりひらくか、調べてまわることになりました。
これから武四郎の歩いたあとを、日記をもとにたどってみましょう。 |
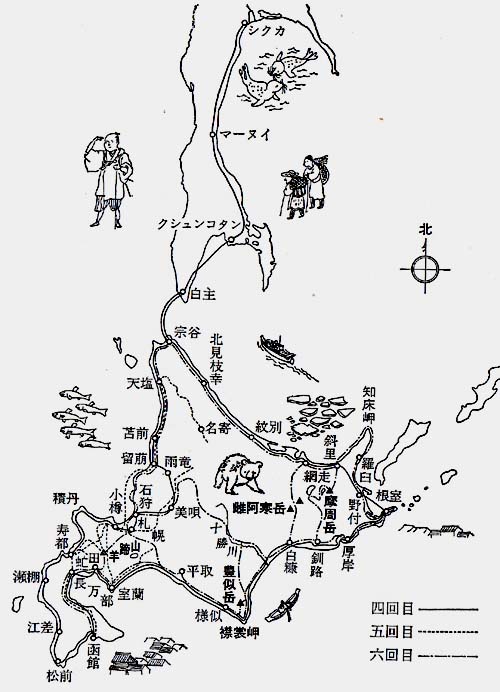
えぞ探検、四・五・六回目(1856〜58年)のあと。
|
三月二十九日
宿の庄吉が車じかけの船を工夫してくれた。
ふみ板を踏むと、車が水車のように回って船がすすむ。
庄吉たちは、“ふみ蒸気”といっていた。
これにのって、内澗町(うちままち)から当別(とうべつ)までゆく。
向山源太夫どのを、ここで待つことになる。
四月一日
いよいよ源太夫どの一行とともに出発。木古内村までくると、松前藩から役人が出迎えにきていた。
知内峠はまだ雪がふかい。
四月十二日
源太夫どの一行は汽船で海上を北にさかのぼり、私は案内人を一人つれて、陸路をゆくことになる。
いよいよ道はけわしくなる。
ホクシ、ホロホグシの断崖をこえてほっとしていたら、一人の僧にあった。
備前岡山の人で、たった一人で新道をきりひらこうと、ここにこもっているという。
小さなお堂か見えていた。
四月二十二日
寿都(すつつ)にさしかかると、アイヌが六人、道ばたにすわって、私を待っていたらしい。
いきなり口々にうったえはじめた。
「ニシバ、おねがいでございます。」
「シマコマキには八十年前には、家も五十軒からあり、人間も二百人も住んでおりました。
それが今では、人間は三十九人にへってしまったのです。」
「そのうち、男は二十六人、女はわずか十三人で、しかも子供を産めるような年頃の者は、六人しかおりません。」
「こんなにへってしまったのは、請負人のせいなんてございます。請負人たちは、私たちを情け容赦もなくこきつかい、働きざかりの者が、次々と死んでしまいました。
のこった年寄りや、子供ばかりでは冬のたきぎをとることも、充分にはできません。
冬じゅうこごえて暮らせば、春になるまでにはたいていが病にかかって死んでしまうでしょう。」
「せめてもう三人ほど、よそから元気な女子をこの村に入れて、一人者にめあわせ、子供を産ませて、私たちを根だやしにしないようにおとりはからいください。」
「いままでなんどもこのことを、支配人さんや、通訳のかたたちにうったえましたけれども、ききいれてはいただけませんでした。」
「そうです。
あなたさまのように、私たちアイヌの言葉もよくわかるかたがこられるのを、私たちは首を長くしてお待ち申しておりました。
どうぞ私たちの苦しみをお聞きとりください。」
六人のなかでも、かしららしい、立派な体格の、長いひげをはやした男が、ひとひざ前にのりだして、さらにつづけた。
「このぶんではもう十年もたてば、アイヌは根だやしになることでしょう。
どうぞおすくいください。もし、このことをだれがニシパに知らせたかと、あとになってニシパが問われるようなことがあったら、脇乙名(わきおとな)のリクニンリキがうったえたとお答えください。
あまりむごくこきつかわないこと、体の丈夫な女子をこれ以上うばわないこと、この二つのお願いをかなえていただけるのなら、この私の身は、どうなってもかまいませぬ。
場所じゅうの者の命にはかえられないのです。」
何とむごいことだろう。私はだまって見すごすわげにはいかない。きっと奉行にとりついでやろう、
このようなアイヌのうったえは、これから武四郎のゆく先々で、目の前にあらわれました。
江差で「秘めおくべし」にしるした松前藩の悪事にもおとらず、下役人や請負人はもっとひどいしうちを、アイヌにむかって行いつづけていたのです。
一日もはやく、こんなやりかたは、あらためなければならないと、武四郎は思うのでした。
五月六日
クマザサのやぶをこえていくと、札幌というところに出る。見渡すかぎりの大平原だ。
このあたりに、えぞ地の都をたてたらよいと思う。
石狩を大阪とし、対雁(ついしかり)を伏見とみなし、川筋を十二キロほどくだったここに都をさだめ、銭函や小樽を、尼が崎や西宮とすれば、やがては兵庫、神戸にも負けないようになるだろう。
ここから虻田(あぶた)、有珠(うす)に道をひらくことができれば、どれほど便利になることだろう。
武四郎のこの考えは、のちに開拓判官の島義勇(しまよしたけ)に取上げられ、今日の札幌の基礎をきずくことになりました。
五月十一日
トツクに着く。人家は五、六軒。アイヌは総出で歓迎してくれる。 |
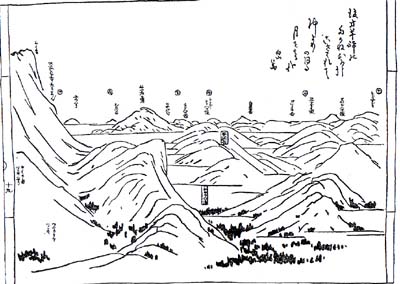
札幌を望む(『後方羊蹄日記』より)
|
アイヌのセッカウシは、すぐに毒矢をたずさえて、山にはいっていった。
子どもたちが川にかけだしていったと思ったら、まもなく大きなウグイを三びきほどとってきた。
女たちはそれをヤナギの枝にさして、焼いてくれる。
夕方になると、トミハセという男が雄ジカを一頭とってきた。
二人の女も、犬にとらせたといって、シカを一頭持ってきた。
男も女も総がかりで料理をこしらえ、やがて、にごり酒をくみかわしながらの、にぎやかな酒もりとなった。
私がアイヌ語がわかるということだけで、彼らはすっかり安心して無邪気によろこび楽しく酒によっている。
私も、じつに楽しい一夜だった。
五月十二日
面白内(おもしろない)でとまる。
アイヌがニレの木の皮をはいで、シトケリというわらじを作り、テシケユという、しょいこのようなものを作る。
あすからは、いよいよ険しい山にさしかかるから、ふだんは裸足で歩くアイヌも、このような身じたくをするらしい。
夜中に、エンリシウが中風の発作をおこす。持っていた薬をあたえた。
五月十四日
ヌプシヤの峠にたどりつく。 五月の中頃だというのに、山はだに雪がこおりつき、まさかりで打ちわって、足場をつくりながらでないと、一歩もすすめない。 |
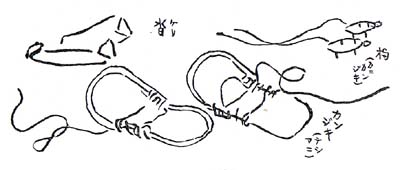
カンジキ、ケリ(『天塩日記』より)、アイヌの雪山の道具
|
何とも寒くてやりきれない。
またこのあたりは、野宿していると、夜中に、クマがさかんにあたりを歩きまわる。
大ぜいの人間がいるので、おそってはこないが、あまりいい気持ちはしない。
五月十六日
昨日あたりから、ようやく人里に近くなってきた。
今日は、苫前(とままえ)で日本人が畑をたがやしているのに出会った。
気候から考えて、ジャガイモと、陸稲(おかぼ)をつくることをすすめておいた。
この日本人は、場所詰合(つめあい)の役人の一人。役人にもこんな男もいたとはうれしい。
五月十八日
人間の住むところへくると、またもや役人や商人のひどいしうちが、いたるところで目につく。
彼らはえぞ地開拓のガンだ。彼らを追いはらわなければ、えぞ地の正しい開拓はのぞめない。
五月二十三日
宗谷から船で、カラフトの白主(しらぬし)にわたる。アイヌのヘンクカリに会う。
彼は、十年前にきたとき会ったキムラカイの孫だという。
私があたえたぬい針を、大切につかってしたなどと話てくれる。
ヘンクカリは、トレフというアイヌ料理でもてなしてくれた。
六月五日
源太夫どの一行もカラフトに着く。
これからさきの予定をうちあわせて、私はふたたびアイヌ五人をつれて内陸にはいる。
六月十三日
身の丈をこすほどのアシをかきわけながら、川筋をたどる。蚊とアブがひどく、目もあけられないありさまだ。
ようやくシララオロに着くと、十五、六人のオロッコ人が出迎えてくれる。
六月十四日
舟でトツソの岬をまわってみる。 |

カラフトに渡った武四郎一行(『北蝦夷余誌』より)
|
これまでの幕府さしむけの役人は、たいていこのトツソの岬でまわれ右している。
私の旅はそんなわけにはいかない。むしろ、これから先を確かめて歩かなければならないのだ。
それにしても寒い。
今日は晴れている日なのだが、この北の海の上では空はどんよりと冷たいなまり色に見える。
海岸にクジラの死がいが打ちよせらとていた。
オホーツク海で、氷山にぶつかって死んだクジラが、流されてきたものだという、
六月十五日
西洋のこよみでいえば、一八五六年七月十六日にあたる。
真夏だというのに、この寒さは、どうしたことだろう。
綿入れの着物など、なんの役にもたたない。
今日はあいにくの雨ふり、雨にぬれそぼり、笠もふきとばすような冷たい風にふきつけられては、たまったものではない。
だれの顔を見ても、死人のような色をしている。私もきっと同じことだろうと思う。
日本の内地でいえば、寒中のさなかでも、まだこれよりしのぎやすいだろうと思う。
六月二十四日
マーヌイに着く。三日ほど前に、源太夫どのの一行がとおったと聞く。
そして、米、みそ、煙草、筆、まき紙、ろうそく、大根づけなどが、私たちのために残されていた。
ひどい寒さにいためつけられ、フラフラになっていた私たちにとって、一つ一つか涙がこぼれるほど、ありかたいものばかりだった。
六月二十六日
ウタスで、ようやく源太夫どのに追いつく。
かなりつかれておられるようで、心にかかる。
七月四日
案じたとおり、源太夫どのは、ついに病にたおれてしまわれた。
はるか北の果ての旅先のこと、手当てが思うにまかせないのがくやしい。
ここで武四郎は、ずっと源太夫の看病にあたりました。
白主(しらぬし)まで医者をむかえに、部下を走らせましたが、医者がやってきたのは七月二十四日、すでに源太夫の病は重く、手のはとこしようもないありさまになっていました。
思いきって、函館に帰ることにきまりました。
源太夫をかごにのせ、心せわしい旅を重ねて、八月九日、ようやく宗谷まで戻ってきたのですが、源太夫はとうとう、あくる日十日に、なくなりました。
源太夫の遺骨をだいて、武四郎たちは十月十三日、六十四日ぶり、函館へ帰りついたのです。
ところが今度は、武四郎が病気になってしまいました。やはり、旅の無理がたたったのです。
武四郎も一度は、“もうこれまで”と覚悟をきめて、短冊に辞世の歌をしるしたほどでした。
| われ死なば 焼くなうずめな 新小田(にいおだ)に すててぞ秋のみのりをば見よ |
えぞ地の土となってこそ、自分の望みはかなえられるのだと、うたっているのです。
この短冊をねどこの下にしきこんで、死を待つ覚悟でいました。
武四郎が疫病神(やくびょうがみ)をふりはらって、再び旅に出られるような体に戻ったのは、あくる年、安政四年(一八五七)の早春のことでした。
10 子供をあげます top
安政四年の四月もすえちかく、武四郎には石狩地方をもっと調べるようにという命令がくだりました。
主なねらいは、えぞ地の開拓について、確かな意見がほしいということです。
四月の二十九日、犬塚という佐賀藩のささむらいをつれて、石狩にむかって旅立ちました。
それからの武四郎の足どりを、追ってみましょう。
五月二日
落部(おとすべ)から山越内(やくくしない)の会所前にくると、アイヌが四、五十人ばかり、旅じたくをしているのに出会った。
「おまえたちは、どうしたのだ。」
「私どもに、みな厚岸に出かせぎを申しわたされましたので、こうして荷づくりをしているのです。」
「どうぞかんべんしてくださいと、何度もお願いいしたのですが、えらいお役人さまのおいいつけとかで、聞きいれていただけませんでした。」
どうせ場所請負の商人と、役人かダルになっているにちがいない。アイヌは、なきながら旅立っていった。
何とも残酷な話で、私は、このことをそのままほうっておくわけにはいかない。
私自身、旅にでて幾日もたっていないが、犬塚を函館にかえして、奉行にこの事実を知らせよう。
私は、アイヌを雇えば旅をつづけることができるのだ。
五月二十五日
ナイにとまる。エゾシカをいたるところで見かけた。夜、しきりとないているのが聞こえる。
開拓のとき、気をつけないと、アイヌばかりか、このようなシカや、川の魚までが、ひどいめにあうことになるだろう。
五月二十七日
ペツバラに着く。乙名(おとな)エンリシウの家にとまる。でも、エンリシウは死んでしまっていた。
去年ヌプシヤ越えのとき案内してもらい、中風の発作でたおれたので、薬をあたえてかえしたのだ。
が、この春、死んでしまったという。
家のそばにアカザがあった。葉をつんで、みそあえにして食べた。
「ニシバ、この草は食べられるのですか。」
「そうだ。ゆでてあくをとれば、柔らかくておいしいものだ。おまえも食べてみなさい。」
おそるおそる口に入れたアイヌは、
「これはおいしい。さっそくみんなに教えてやります。」
きっとそのうちに、ここらのアカザは葉っぱをみんなつみとられてしまうことだろう。
五月二十八日
カモイコタン(神居古潭)へ出る。ここにしばらくとどまって、あたり一帯をよく調べることにしよう。
魚が、たくさん川をさかのぼってくる。マスが滝をのぼるのを見た。
体を折りまげて、しっぽで水をたたくようにしながら、高くはねあがり、滝を一段ずつとびこしていく。
見ていると、失敗するのがたくさんいる。
何度失敗してもあきらめずに、とびあがっては滝のいきおいにおし流され、またとびあがっては流されしていた。
コイの滝登りの絵などがあるがけっしてあんな姿では、コイは滝を登れない。
閏(うるう)五月七日
ビヤテキというアイヌの家にとまる。五十歳をこえたこのアイヌは、左腕がない。
クマにくわれたのだという、
ビヤテキは、狩りが大好きで、また大変上手だった。
くる日もくる日も、今日はヒダマを追って天塩(てしお)川までいったかと思うと、あくる日はシカを追って、十勝、夕張の山々をめぐるといったありさまだった。
雪ふかい山も、ビヤテキにとっては平地とかわりない。自由に走りまわることができた。
ビヤテキに足もとを見つけられたけものは、あわれであった。
なにしろ。足跡を見つけたとなったら、これまで一頭もしそんじたことがないという名人なのだから、道具といえば、弓矢と山刀しかない。
ところがある時、築別岳(ちくべつだけ)で、一頭のメスグマが、子グマとたわむれているのを見つけた。
「しめた!」
ビヤテキは、ブシという毒をぬった矢を弓につがえ、ねらいすましてヒョーと射はなった。
矢は、見事にメスダマにつきささった。でも、どうしたことか、メスダマは、たおれない。
傷ついたげものほど、おそろしいものはない。メスダマは死にものぐるいにあばれだした。
「しまった。毒のききめが弱かったかな。よし、二の矢を射こんで、今度こそしとめてやろう。」
ビヤテキは、弓をかまえた。と、その時うしろのほうで、けもののすさまじいうなり声が聞こえた。
ハッとしてふりかえると、大きなオスのヒグマが、ヌッとあらわれた。
と見るまに、ものすごいいきおいでとびかかってきた。
ビヤテキは、むが夢中で、矢をはなった。でも、矢はオスグマの背をかすめただけだった。
怒りくるったオスダマは、ビヤテキの左腕に、ガブリとくいついた。
大きなヒグマにかかっては、人間の力などなんの役にもたたない。
どんなにもがいても、クマをふりほどくことはできない。
覚悟をきめたビヤテキは、右手で山刀なをぬくと、歯をくいしばった。
(エイッ!) 山刀をふるって、自分で自分の左腕を切り落したのだ。
返す刀で、オスダマのあごを、力いっぱいついた。
つれてきた三びきの猟犬も、いっせいにオスダマのあと足にかみついた。 オスダマは、だまらなくなって、ビヤテギの左腕をくわえたまま逃げ出した。
「このまま逃がしてなるものか!」 |

アイヌのビヤテキとメスグマの一騎打ち。
この戦いでビヤテキは左腕をなくした。
|
ビヤテキは、自分の傷口をボロきれでしっかりゆわえると、あごから血をしたたらせながら逃げていったオスグマのあとを追った。
三百メートルほどいったところに、オスグマは倒れていた。
まだビヤテキには、やることか残っている。山刀をつかって、右手だけで皮をはいだ。
肉を切りとって、犬たちにわけてやった。
まずこれだけのことはしておかなければ、クマをしとめた意味がない。
こうしてビヤテキは、左腕をうしなった。けれども、けものを追うことをやめなかった。
弓をつかうときは弓のつるをひざにかけ、右手だけで引きしぼって、矢をはなつ。
これでも、ビヤテキがやると百発百中。だれにも負けないという。
一般にアイヌは、大自然のなかで暮らしていれば、大変勇気がある。
けれども、常にコタンとよぶ小さな部落単位で暮らしているために、大きな人間の集団のなかで暮らす知恵にはうとい。
えものをもとめて、すみかを変える。
遊牧生活のために、一ヵ所におちついて長耕をいとなみ、暮らしの幅をひろげていくことを知らないのだ。
その上コタンどうしの争いがたえず、お互いにいがみあっているのだ。
おまけに酒がすきときているから、外からはいってきた者たちにとっては、つけいるスキだらけの民族といえる。
六月六日
苫前(とままえ)にきてみると、去年教えておいたように、畑が見事に開墾され始めていた。
自分の意見が取入れられて、よい結果をうんでいるのを見るのは、うれしいものだ。
六月九日
去る閏(うるう)五月二十九日、小樽で奉行の一行と会って以来、十日間ほど一緒に歩いたが、今日からまた私は内陸にわけいり、奉行の一行は、船で宗谷へむかうことになる。
役人の一人が、今度は自分が内陸を見て歩く役にまわりたいと申しでたが、奉行は、
「なれない者が、けわしい山道にわけいったとて、なにほどの調べができるというのか。
松浦武四郎のように、経験ゆたかな者だからこそ、なしとげられる仕事なのだ。」
といって、その役人の願いをしりぞけられた。信頼されていると思うと、いっそう勇気がわいてくる。
ペカンペ沼を見る。ベカンペ――ひしの実を、アイヌは大切な食料にしていた。
でもこのあたりのペカンペ沼はすでに荒れ初めている。
六月十四日
先日から、天塩(てしお)のあたりを歩いているが、この一帯は、えぞ地でもとりわけ、アイヌの暮らしが貧しいところと聞いていた。なるほど、いく先々で、かなしい話を聞く。
今日おとずれた、ニカシテカニ一家も、あわれであった。
エカシテカニは目が見えず、すっかりおとろえていた。
妻のテケモンケも、どうしたわけか片目がつぶれ、年もすでに五十歳をすぎている。
子供はというと、おどろいたことに、二十六歳の息子をかしらに、すえは二歳まで、十人あるという。
なるほど見ると、五、六人の子供があそんでいるが、二十六歳などという者は見あたらない。
「大きな息子たちはどうしたのだ。」
「はい。娘二人はとつがせましたが、上の二人の息子は場所役人にとられてしまい、今頃はどこの漁場で働かされておりますやら………。」
妻のテケモンケは、日々の暮らし竃ボツボツとかたりだした。
朝起きると、まずるの火をかきおこす。十四になる子には、山へたきぎをとりにいかせる。
自分は四歳の子を背おい、二歳の子をふところにだいて、川へ魚をとりにいく、もりでつくのだ。
なれていなければ、なかなかとれるものではない。
山へいって、食べられる草の根や、くきなどをとってくることもある。
昔は主人のエカシテカニと一緒に働いたので、まずしくても、楽しいこともあった。
ところがエカシテカニの目が不自由になってからは、一家八人の暮らしがテケモンケ一人の腕にかかってきた。
そのうえテケモンケまで、木の切りかぶで目をついてしまったのだ。
「さぞかし大変な毎日であろう、まだ幼い子もたくさんいることだし。」
「いいえ、子供が大勢いることは少しもいといません。
ただ悲しいのは大きくなって、少しでも家の手助けになりそうな年頃になると、みんな場所役入に取上げられてしまうことなのです。」
私は、そのさきを聞くことにたえられなかった。
六月十五日
朝になると、テケモンケは昨日のかなしい話は他人ごとのように、子供だちと明るく声をかけあいながら、働いていた。
私の顔を見ると、テケモンケはいった。
「今はくるしい毎日ですけど、何といっても子供は宝、そのうちには、いいこともあるでしょう。
心配することは何もないんです。」
「それは何よりだ。私などは、もう四十になるというのに、まだ妻も子もない。」 |

木の皮でで織物をつくるアイヌ(『蝦夷漫画』より)
|
テケモンケは、よほどびっくりしたらしい。ポカンと口をあけて、穴のあくほど私をみつめていたが、やがて、
「それは、ニシペ 心もとないことでございましょう。」
「いいや、べつに、なにしろ、旅から旅にあげくれているので、家庭をもつひまもなかった。」
「して、ニシパは、どちらからおいでなのですかご
「私は江戸といって、松前からでも、三十日も旅をしなければつかない、遠いところからきたのだ。」
「ああ。」
テケモンケは、さも残念そうに溜息をもらした。
「それは、まことに残念なことでございます。
もし二、三日でいけるところでしたら、私どもの子供のうち、誰か一人を、ニシパの子供にさしあげてもよろしいのに。
ニシパは、このあたりにいつも回ってくるシャモ(日本人)たちとはちがって、たいそうよいお人柄と思います。
ニシパのように心のやさしいかたになら、子供をよろこんでさしあげますでしょう。
でも、三十日もかかるのでは、あまりに遠すぎて、さしあげるわけにもいかず、残念です。ほんとに残念です。」
テケモンケの顔には、真心があふれていた。
十人も子供がありながら、そのうちの一人でさえ、遠いところへは手離したくないという、母親の心とはありがたいものだ。
六月十五日
チノミにいたる。あるアイヌの家で、めずらしい光景を見た。
幼い子を、木の皮でこしらえた箱のようなものに入れ、両端に藤づるをつけて、木の枝に張りわたす。
子供がむずかると、親は木の皮の箱をゆすってやる。
さわやかな山の空気の中で、箱はゆらゆらとゆれ、子供は、またすやすやと眠ってしまった。
「これはいいことを考えついたね。」
「はい、こうして育てた子供は大きくなっても病気をしないといわれています。」 カラフトのオロッコ、タライカ、ニクブンなども、このような方法をとっていると聞いたことがある。
六月二十二日
ソウシペツ、テイネメンあたりの山中をふみ歩く。
密林がうっそうとおいしげり、大雨がふると川がすぐあふれる。 あふれた水は木をなぎたおし、たおれ重なった木が水の流れをさえぎる。
そのために、川筋は、しじゅうかわるらしい。かつて、間宮林蔵は、このあたりまでふみこんでいると聞いた。
七月九日
夕張の山中にはいる。タツコb8では八十三歳のアイヌの古老に会った。
昔からのならわしをいろいろ話てくれた。ユーカラもうたってくれた。
七月十四日
千歳の会所にたどりつく。すぐ出発しようとすると、アイヌがひきとめた。
「ニシバ、あしたは地蔵まつりです。ぜひともひと晩と言って、私たちと一緒に、地蔵まつりを楽しんでいってください。」 |

ゆりかごで幼児をあやすアイヌの古老
|
七月十五日
地蔵まつりのあと、千歳の弁天社におまいりして、アイヌのまねをして即興の経文をとなえてみた。
アイヌは、みんなニコニコして聞いていた。あとで、酒と赤飯をふるまい、大にぎわいの夜となった。
七月二十三日
有珠別(うすべつ)でアイヌのはシテヤキの家にゆく。
持ちあわせていた米で、おかゆをたき、アイヌたちにも食べてもらった。
そこへ七十歳あまりのアイヌの老人が、三十六、七歳の男に背おわれてはいってきた。
目が不自由らしい。うしろから、若い女が五つぐらいの男の子をつれ、赤ん坊を背負ってついてきた。
老人を背負っている男の妻のようだ。女は老人の腰をささえるようにして歩いてきた。
家の中にはいって、老人をすわらせると、男と女は老人の左右につきそい、きせるをとってたばこをつめてあげたり、おかゆがくばられると、熱すぎないかと、気をくばったりしていた。
二人とも、とてもよく老人のめんどうをみているのに感心した。
「あの人たちは、どういう人なのかね。」
かたわらの者にきくと、
「あの若い男は、サメモンといって、この有珠の場所内のコツチというところの者です。」 とこたえた。 |
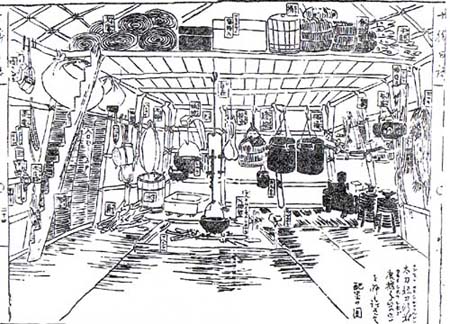
乙名(おとな)の家の内部(『十勝日誌』より)
|
それ以上よくわからないので、会所へ戻ったとき、会所の支配人にもう一度きいてみた。
「おお、お目にとまりましたか。あのサメモンは、この場所内でも、とりわけ心がけのよい者でございます。」
といって、くわしくサメモンのことを話てくれた。
「老アイヌは、名まえをシリウトクといって、若いころは、酒ずきで、働き者でした。
年とって今は、目も見えなくなり、歩くのも不自由になってしまいました。
妻もなくして、さびしい身のうえとなりましたが、よくしたもので、息子のサメモンが大変な親孝行者なのです。
サメモンは三十をすぎても結婚しようとしません。まわりの者が、妻をせわしようというと、
“私は、どのような女の人でもけっこうです。何よりも父の心にかなう女の人でなくてはなりません。”というのです。
そこで、会所の者も感心して、シュハッタという女をせわして、安心しました。
すると、サメモンは、まずはじめにシュハッタにいいました。
“親につくすということは、何にもかえられない、大切なことだと、私は思う。
もし親がなくなれば、もう、どのように大切にしようと思ったところで、取返しがつかない。
だから、私の妻となったからには何よりも、親を大切にしてもらいたい。”
すなおなシュハッタは、サメモンのいいつけをよく守って、あなたもごらんになったように、サメモンと力をあわせて、老人を大切に面倒をみているのです。」
サメモンたちはえらいと思う。しかしそれだけではない。
このような孝行息子のえらさをみとめて、妻のせわまでしてやる会所の支配人たちは、立派だと思う。
支配人や番人の心がけがよいと、場所内のアイヌもゆとりのある心で、自分たちの暮らしを守っていけるのだ。
七月二十七日
先日から、オサルベツの山中を歩いている。
今日はタツコブどまり、食事の用意をしようとして、いつも持ち歩いている鍋をまえのところに置き忘れてきたことに気がついた。
どうしようかと、途方にくれていると、アイヌの一人が、
「ニシバ、見ていてごらんなさい。こうすれば、鍋がなくても大丈夫です。」
といって、ふきの葉に米をくるんで、ご飯をたいてくれた。それがとてもおいしい。
鍋が無くてはと、うろたえた自分が、はずかしくなった。
八月十四日
利別に出る。
利別川の上流は、砂金の出るところとして知られていて、昔、掘りとったあとも、たくさん残っていた。
いまもきよらかな水が、音をたてて流れていた。
八月十五日
今夜は、イヌマカシというアイヌの家にとまる。
イヌマカシは六十七、八歳の体格のよい男で、たいした力もち。娘が五人あるという。
家には、クマを三頭のほか、キツネやワシのひなも飼っているという。
畑をひらいて、アワ、ヒエ、大根、きゅうり、いんげんまめ、だいずなどをつくっているが、なかでも見事なのは、カブ畑。 広いところ一面に、カブの葉が青々と夏の日をうけていた。
イヌマカシは“カブおやじ”とあだ名されているという。 |
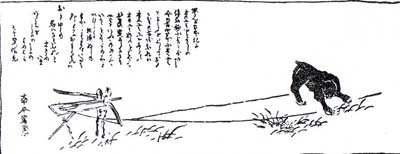
しかけわなで、くまを捕える(『天塩日誌』より)
|
「なんてまた、こんなにたくさんカブをつくるのかね。」
と、私がきくと、カブおやじは腰をかがめながら話しだした。
「はい。ここは、カブがよくできるところなのです。
それで私は、昔から、カブをたくさんつくっていました。
とれたカブは、太櫓(ふとろ)や瀬棚(せだな)へ持っていって、酒やたばこと取替ていました。
ところが、松前さまがおさめるようになってから、畑つくりが禁じられてしまいました。
太櫓や瀬棚の人たちは、冬のあいだ食べる野菜がなくて困っています。
見かねた私は、この山奥でつくって、こっそりはこびました。
みんなは私がいくのを待ちこがれるようになったのでいつしかカブおやじというあだ名がついてしまったのです。」
家の前の庭には小(お)ざさ、はぎ、かるかや、すすき、おみなえし、りんどう、くずなど秋の花が、いまをさかりとさきほこっている。
草むらの中から、スズムシ、クツワムシ、ウマオイなど秋虫の声が、まだ明るい昼日なかだというのに、さかんに聞こえてくる。 おりの中のクマは、わたしか近づくと、“ウォーッ!ウォーッ!”と、ほえたてる。
ワシのひなは、えさをくれというように、くちばしをカチカチうちあわせている。
カブおやじが日々の暮らしを楽しんでいるさまがわかって、うれしかった。
それにしても、八月のなかばというのに、もう秋風が肌にしみいる感じ。やはり北の国だなと思う。
八月十七日
黒岩にいたる。この地名のもとになっている。
黒い岩をこまかな粉にくだけば、茶わんを焼くときの上ぐすりに使えるだろう。
江戸へ帰ったら、専門家に調べてもらおうと思う。
八月二十日
ユウラップに着いて、川上をしらべにはいるための準備にかかる。
ユウラップの番人、宇之助は、親切な男で、私たちの山ゆきの食料を丹念に調べていたが、
「だんなさま、これで量は充分と思いますが、野菜をもっとお持ちになったほうがよろしいと思います。」
といって、大根を五本そえてくれた。
旅をつづけていると、肉や魚ばかりになって、どうしても野菜が不足してしまう。よく気のつく男だ。
そんなことをしているところへ、アイヌが一人、かけてきた。
「サケが五、六ぴき、のぼってきた!」という。
案内にやとったノサカというアイヌが、うれしそうに立ちあがった。
「よし、その五、六ぴきの内、三びきまでは、俺がとってみせる!」
いうがはやいか、ノサカはもりを手に、川岸に走っていった、
私もあとを追った。川岸では、すでにアイヌが何人も、もりを手にさわいでいた。
でも、まだだれもサケをしとめていない。
ノサカは、舟を二そう、つなぎあわせてのりこみ、三人の仲間にこがせて、川へのりだした。
ノサカは、舟の上から、身をのりだすようにして、もりをかまえた。
“エイッー”
と、つきおろすと見るまに、ノサカのもりの先には、サケが一ぴき、うろこをキラキラさせながら、のたうっていた。
つづいて、もう一ぴき、また一ぴき。あっというまに、三びきしとめてしまった。
ノサカは、このあたり一番のもりつかいという評判とのこと、評判どおりの、見事な腕前だった。
八月二十三日
雨が雪にかわった。村々はうす雪におおわれてしまう。駒が岳はすでに真っ白に雪化粧をしている。
こうして、冬のおとずれも近くなった八月二十七日、武四郎は、函館に戻ってきました。
奉行に旅の報告をして、第五回の探検旅行をおえた武四郎は、ほっと肩の荷をおろした気持ちになるのでした。
11 えぞ富士に骨を top
武四郎には休むまもなく、つぎの命令がくだりました。
今度は、東エゾをよく調べるようにということです。
出発はあくる年の正月すえの予定ときまりました。
それまでにしておかなければならないことが、たくさんあります。
幕府でも、ようやく本気でえぞの問題にのりだしているようです。
武四郎が尊敬している、堀織部正などの意見を取入れて、とくにあくどいやりかたでアイヌを苦しめている役人が、やめさせられたりしました。
また武四郎は、山川地理取調方という役をあたえられました。
伊能忠敬や間宮林蔵によって、えぞが島、つまり北海道の外まわりの形だけはあきらかなものにされました。
けれども、内陸のようすが、まだたしかにはわかってしません。
このまえの西えぞ探検でもわかるように、武四郎の探検は、これを足で確かめて歩いているものなのです。
武四郎はさっそく自分の歩いたところを、くわしい地図にこしらえる仕事にとりかかりました。
自分で地図をかき、色までぬって、一枚の図にこしらえあげていくのです。
安政四年の暮れまでには、探検旅行の日誌に、その地図をそえて、幕府に差出しています。
安政五年二八五八)の正月をむかえました。
第六回めの探検旅行の準備をすすめるかたわら、武四郎は上役の梨本弥五郎あてに、非常に長い手紙を書きました。
それは、第六回めの旅をはじめるにあたって、武四郎自身が、自分の覚悟のほどを確かめるために書かれたようなものです。
これまでにも、武四郎はそれぞれの場所で見たり聞いたりした、請負人、支配人、番人などのひどいやりかたを、手きびしく批判し、あばきたててきました。
これからの旅でも、その批判の目は、いっそうきびしく光ることでしょう。
それだけに、武四郎をにくむ人もたくさんいます。
「そのような人たちのじゃまだてのために、旅先で命をおとすかもしれない。
またきびしい寒さのために、もう四十歳をこした体が、たえられないことも考えられる。
もし私が死んだら、私の大好きなえぞ富士、後方羊蹄山のふもとに、その骨をうずめてほしい。」
と、その手紙にはのべられていました。
| みちのくの えぞが千島を開けとて 神もやわれをつくりだしけん |
そのころ武四郎がよんだ歌です。神がえぞ地をきりひらくために、私をこの世におくられたのかもしれないと、自分にあたえられた使命に、懸命にこたえようとしている心がよみとられます。
こうして、武四郎は、安政五年一月二十四日、東えぞへむけて旅立ちました。
二月四日
かねてからあこがれていた、後方羊蹄山(ようていざん)登りにとりかかる。
えぞ富士とさえよばれているように、富士山の姿に似た美しいこの山に、一度は登りたいと思っていた、その願いがようやくかなえられた。
激しい風と雪のなかをすすむのは大変な苦しみだった。
いただきに立っても、吹雪の中で、何も見えないかもしれない。でも、私は満足だ。
| 天津風(あまつかぜ) 胡沙(こさ)ふきはらえ しりべしの 千代ふる雪に照る日かげ見ん |
二月七日
今日もふかい山をわけすすむ。
大雪の中を、先にゆく者の足跡を見失わないようにたどらなけけばならない。
こんな雪山のなかで、一人迷子になったら――それは、死に結びついてしまう。
アイヌの家もなく、野宿をしなければならない。雪をふみかためて、木を切り倒してならべる。
凍りついた崖を切りくずして土をとり、木をならべたゆかの上にしいて、火どこにする。
この上で火をたくわけだ。
どうしても土がとれないときは、雪をふみかためた上で、じかに火をたくことになる。
これでは一晩中、火をたきつづけるのが大変むずかしい、
今夜は何とか火どこができた、夜どおし火をたきつづげる。
けれども、みなで体をよせあうようにしても、なお寒い。
二月八日
昨日と同じ身を切るような風と雪、今夜も野宿かと、なかばあきらめていたら、アイヌの一人が、クマのぬけ穴を見つけたので、そこにとまることにした。
これだけ何度もえぞ地を歩き回っているけれども、私はまだクマの肉を食べたことがない。
「一度、クマの肉を食べてみたいものだな。」
と、私がいうと、アイヌのトンネンハクが、ひげづらに笑みをうかべながらいった。
「ニシバ、それほどクマの肉をお望みならば、いずれとってさしあげましょう。」
トンネンハクは、虻田(あぶた)のアイヌで、クマとりの名人と聞いた。彼のいうとおりになるかもしれない。
二月十日
ものすごい吹雪で、昨日は一日、クマの穴にとじこめられてしまった。
今日、ようやく少しおさまってきたので、穴からはい出し、また登りはじめる。
五、六百メートルいくと、雪の上にクマの足跡が見つかった。
「クマだ、クマだ!」
アイヌたちは、大よろこびで、足もとをたどっていく。渓川におりていくようだ。
あった。大木の根かたに、大きな洞穴が見つかった。中にはクマがいるにちがいない。
私は五、六十メートル高いところにのぼって、見ていることにした。
アイヌたちは、洞穴の入口から棒をさしこんで、クマをさそい出そうとしている。
クマのうなり声が聞こえてきた。
つれてきた二ひきの大は、クマのうなり声に、狩りの興奮をおさえられなくなったのだろう。
しきりに尾をふって、私の手からのがれ、穴にむかってとんでいこうとしていた。
三、四本の毒矢が穴の中に射こまれた。 |

イナヲつくり(左)や、酒つくり(右)にはげむアイヌ。(『蝦夷漫画』より)
|
ひときわおそろしいうなり声をたてたと思ったとたん、一頭の大グマが、洞穴からおどり出てきた。
クマは、いきなりトンネンハクにとびかかった。
「なんじゃ、このヘウレホめ!」
トンネンハクは、クマの首をしっかりとかかえこむ。クマと人間の力くらべだ。
ヘウレホというのは小グマのことで、アイヌはどんな大きなクマでも、クマとたたかうときは「ヘウレホめ!」とさけぶ。
犬もくるったようにほえたてながら、クマにかみつく。
トンネンハクは、キューキューと、腕に力をこめていく。
そのうちに、矢じりにぬったブシの毒もきいてきたのだろう。クマは、しだいに力がおとろえてきた。
と見ると、トンネンハクは、すかさず山刀をぬいて、クマのわきの下から、グサリとつきたてた。
ドッと、地ひびきをたてて、大グマはたおれた。
「わあーっ! やった、やった!」
みんなのよろこびようといったらなかった。
それからがまた、大変だった。
まずはじめに、肉を切りとって、山と海の神にそなえる。
つぎに、皮と、肉の半分をゆうべとまった洞穴の中にしまう。
のこりの半分の肉は、ここで食べるのだという。
血のしたたる肉を切りとったまま、なまで食べる者もいる。
あぶって食べる者もいる。私も、おそるおそる手をたした。なかなかおいしい。
「おいしいね。」というと、
「ニシパ、おいしいですか。いったとおりになったでしょう。」
と、トンネンハクはうれしそうに笑った。
でも、その口やひげ、それに手までも、クマの血にまみれている。
まるで鬼のように見えて、私は思わずギョッとした。 |

アイヌの踊り(『蝦夷葉那志=えぞばなし』より)
|
二月十七日
札幌の川のほとりに出る。ここのところ毎晩、野宿を重ねている。
初めて野宿したのは私の十七の年だった。
天保五年、二度めに家をあとにして、京・大阪から西日本の旅に出たときだ。
四国から紀伊半島に戻って、あれは、印南谷(いなみだに)のいのしし小屋だったと思う。
年の暮れもせまった寒い夜、心細さと、負けてなるものかと、自分で自分をはげます心とが入りみだれ、しきりと寝返りをうつうちに、夜が白々とあけてきたことを思い出す。
あれから、私は一体、どれほど野宿を重ねてきたことだろうか。
二月十九日
石狩につく。アイヌたちは、ここでいままでの苦労をねぎらって、それぞれのふるさとへ返す。
これから、石狩の原野を開拓する方策を考えながら、ゆっくりとこのあたり一帯を歩くのだ。
二月二十五日
昨日まで、川は一面にこおりついていた。
それが今日は、われめができて、少しずつ流れてくる。春が近いのだ。
それはありがたいのだが、川を舟でいくには、この時期が一番あぶない。
小さな舟で、流れる氷の中を進むのは、かなり技術がいるものだ。
三月五日
ここは東西四十キロあまり、南北二十キロほどにわたる、大平原だ(いまの富良野のあたりです)。
広々と原野がつづき、見渡すかぎり、目をさえぎるものは何もない。
この平原だけで、ひとつのまとまりを見せている。日本の内地でいえば、立派に一ヵ国をなすことだろう。
そんなことを思いながら、ぼうぜんとながめていると、同行の役人の飯田という男は、一人つぶやいていた。
「これまで歩いてきた山地にくらべれば、あたたかで、とてもよい土地だ。
開墾すれば作物もよくできるだろうに、うちすてられている。
函館や、内地へ帰って、この土地のことを話ても、はたしてどれだけの人が信じてくれるだろうか。
えぞ地にも、こんなすばらしし土地があるということを………。」
三月二十二日
釧路にはいる。釧路川を越えて、東岸は会所まで、ずっと人家がつづいている。
七十二軒あって、まるで町のように見える。エゾ地の数ある場所のなかで、もっとも人家の多い場所である。
土地は西むきにひらけ、平山の中腹に位置しているので、見おろすと、白糠(しらぬか)のあたりまで見渡すことができる。 ここはやがて大きく発展して、すばらしい都市になることだろう。
三月二十五日
馬にのって道をゆくと、犬がさかんにほえたてる。なぜだろうと、アイヌにきくと、
「このあたりの犬は馬を見たことがないのでしょう。」という、
四月六日
稚内にたどりつく、雨がパラついた。一人のアイヌがつぶやいた。
「やっぱり雨になったな。
ここは、どのようなよい天気の日でも、シャモがくれば、かならず雨がふるといわれているけれど………。」
四月七日
アイヌ三人をつれて、摩周にのぼる。まだ雪がふかくて、大変くるしかった。
六月二十七日の阿寒の山もそうだったが、摩周もシャモとして足を踏み入れるのは、私が初めてなのだ。
これからさきの旅の食料を買い入れ、弟子屈(てしかが)にとどけるよう、五人のアイヌにいいつけておいた。
四月八日
弟子屈にいたる。食料はまだついていなかった。どうしたのだろうか。
もう手持ちの食料は、底をついてきた。
四月九日
屈斜路にはいる。まだ食料はとどかない、アイヌたちにたのんで、食料集めをさせた。
けれども、みんなの腹を満たすだけあつまらない。さて、どうしたものか。
四月十日
アイヌに刀のつばをあたえると、かわりにはした魚をくれた。
何とかそれを分けあって、ひもじさにたえたが………、
四月十一日
食料を運んでおくようにいいつけた五人のアイヌに、途中で会った。
彼らの顔が、食べ物に見えるような気持ちだった。
ところがおどろいたことに、彼らは、こわれかけた板蔵の前に、大まじめな顔ですわっている。
板蔵には、しっかりと錠がかけられていた。彼らは言う。
「ニシバ、一生懸命、番をしていました。」
さては? と思って錠をはずして、板蔵をあけてみた。
そこには四日間、待ちに待った食料が、きちんとつみあげられていたのだ。
なるほど、私は自分のいったことを思い出した。
「荷物は、めいめいで、しっかり番をしていておくれ。」
彼らは、いいつけを守ってくれたのだ。
つまり、私が命令するとき、ちょっと言葉がたりなかったというわけだ。
怒ってもはじまらない。 |

約束どおり待っていた!(『久摺日誌』より)
|
四月二十三日
花咲(はなさき)に出る。
四月二十五日
バボマイ、シコタンの島々を望みながら、納沙布(のさっぷ)岬の突端に立つ。
ここはえぞ地の東の果ての地で、一面に深いもやがたちこめ、激しい風が、かや野をふきわたる。
肌をつきとおすような寒さだ。
あまりにもやが深くて、何も見えない。
たまりかねて、かやに火をつけて、もやの晴れるのを待った。
わずかに、もやの切れめができた。海上をすかし見ると、クナシリ島が見える。
手前にあるはずのハボマイ、シコタンの島々は岬にうちつける波のしぶきにかすんで、よく見えなかったこれらの島々も、ちゃんとした計画のもとに開拓の手をのばさなければ、日本の領土でありながら、意味のないものになってしまうだろう。
沼口(トウシャム)で昼食にしようとしたが、水がない。
やっとのことで、岩のあいだから水がしたたっているのを見つけ、それでご飯をたいた。
ところが、一口食べたところ、何とも塩からくて、喉をとおらない。
あたりはすっかり霧につつまれ、大雨のなかにいるように、着物はぐしょぬれで、肌にべっとりとまつわりつく。
私たちは、大きなふきの葉をかさのようにかぶり、すかんぽの葉を腰にまとって、歩いていく。
まるで、ふきのおばけみたいだ。
昼めしにありつけなかったので、おなかがすいてたまらない。のどもカラカラだ。
ふと道ばたを見ると、いたどりの芽が出ている。
「しめた、これは食えるぞ!」
いたどりの芽をつんで、かむ、すっぱい汁が口のなかを満たす。
アイヌたちにも教え、みんなでむしっては口に入れた。少しは腹のたしになる、
夕方、やっと根室にたどりつく。えぞ第一のにぎやかな場所といわれているだけに、なかなかさかんだところだ。
私が幕府の役人だということで、会所のひとたちは、私のあっかいに気をつかっているようだ。
アイヌの酋長の家にとまる。彼は、アイヌでありながら、陳平という日本人名を名乗っていた。
あすからは知床へむかうためのしたくをととのえなければならない。
四月二十八日
陳平の家で、トコタン人のドンドンという男のえびす舞いを見た。
「見さいな、見さいな、えびす舞いを見さいな。」
と、はやしたてながら、身ぶり手ぶりもにぎやかにおどる。
私の羽織を貸してくれという。どうするのかと見ていると、羽織の両そでに足をとおし、はかまのように腰にまきつける。
かかえたほしざけは、タイのつもりだろう。
つりざおを肩にしながら、船をこぐかっこうをしたり、タイを釣るしぐさをしたり、釣りおとしたといっては地団太ふんだりと、そのゆかいなこと、みんなは旅の疲れもわすれて、笑いころげるのだった。
「ああ。おもしろかった。ドンドン。このえびす舞いはだれに教わったのだ?」
「はい。昔、日本人の船頭が教えてくれました。」
とすると、一体、どこの踊りがもとになっているのだろうか。
四月二十九日
知床にむけて、旅立つ。アイヌの供は四人。
五月三日
野付の会所の支配人、秋田屋伝蔵。アイヌ二人をともなって、朝、会所を出発。
オンネニクルでは、ムギやコムギがよく育っているので、おどろいた。
野付は、わらびのようなかっこうをした細長い半島で、風景は大変うつくしい。
けれども、いつもどんよりとした感じで、夏でも、ひややかな土地だから、ムギやコムギを育てるのは大変苦労なことだと思う。
「ほほう、よくもこんな土地で………。これはだれがつくっているのかな。」
伝蔵にきくと、彼は、いった。 |

陳平(アイヌ人)のえびす舞い。
これは日本人に教わったという。
|
「私が、アイヌに手伝ってもらってつくっているのでございます。」
「とてもよくできているではないか。大変だったろう。」
「このあたりは、貝がらの多い砂地ですので、このままでは畑作はだめだと思い、ほかから土を運んでまいりました。
今では、ムギのほか、ヒエやアワ、そのほか野菜など、あわせて二十七種ほどを育てております。」
「ご苦労なことだ。その手伝ってくれるアイヌというのは?」
「まことに感心な男でございましてな。
負うた子に教えられて浅瀬をわたるとか申しますが、全くそのとおりで、この畑を開く知恵も、そのアイヌに教わったのです。」
そのアイヌも、日本人名を名のり、茶右衛門とよばれているとのこと、もとはオチャシタエキといって、標津のちかくに住んでいた。
もう五十九歳にもなるが、妻も子供も親類もない、たった一人ぼっちの身の上だった。
えぞ地が、松前藩から幕府の管理にうつされると聞くと、オチャシタエキは、自分から日本ふうに髪をゆい、名さえも茶右衛門とあらためたことを、野付番屋の伝蔵のところへとどけてきた。
そして、
「これまで松前藩では、アイヌには作物をいっさいつくらさないというお達しでした。でも、私たちも同じ人間です。
幕府じきじきのご領地となりましたあかつきに、私たちにも鍬や、鎌を持つことをお許しいただけるようになるならば、見事に畑を開いてごらんにいれます。
私はもう年寄りですが、この年寄りが番屋て畑をつくるならば、あたりの若い者たちも、だんだんに、われがちに畑を開くようになることでございましょう。
そうなれば、私たちの暮らしもたち、えぞ地もひらけて、お国のためにもなることとぞんじます。」
と、熱心に申したてた。伝蔵も、
「なるほどもっともなことだ。幕府じきじきのご領地となれば、もはやおとがめもあるまい。
私も一緒に畑を開こうではないか。」ということになって、いまのような、立派な畑ができたのだという。 |
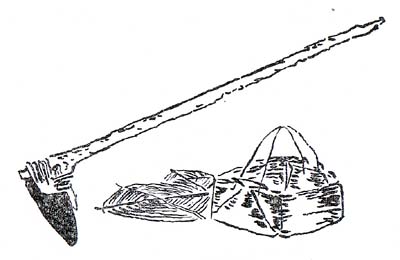
アイヌの道具(『石狩日誌』より)
|
五月四日
クナシリ島がひと目で見わたせるところへ出る。
ヨコマフという。舟で岩が切りたった、けわしい海岸を見あげながら、羅臼につく。番屋にとまるつもりだったが、残念なことに、こわれてしまっている。
しかたなく、その上のほうに大きな岩屋を見つけ、そこにもぐりこんでとまることにした。
岩には、いわすげがはえ、はまなずな、岩さくら草などが、赤や白の花をひらいている。
内地では明日は五月の節句だ。
ここでは、しわすげを、しょうぶと思って、節句を祝うしかない。
夜中に岩屋の外でで、バリバリという、ぶきみな音がする。
アイヌが、そっとようすを見てきて、いった。
「私たちがすてた、魚の骨などを、クマが食べているんです。」
(のちにこの岩屋は、天念記念物のヒカリゴケがはえていることで知られるようになりました。)
五月七日
斜里の砂浜を歩いていると、アイヌが数人、浜で貝をひろっていた。
このあたりは、ひき潮になると、ホッキ貝がたくさん打ちあげられる。彼らはそれをひろっているのだ。
だがよく見ると、彼らのようすがおかしい。
浜に見えるのは、腰のまがったおじいさんや、おばあさん、それに杖にすがってよろめき歩いている病人、あとは、小さい男の子や女の子ばかり、みんなぼろぼろの着物をまとい、というよりも、ぼろきれが肩にかかっているだけというようななりで、顔は青ざめ、土色をしていた。
あまりにもあわれなので、どういうわけかと近よっていくと、彼らも私に気がつき、そばへきて、へたへたとすわりこみ、代わるがわる頭をさげる。
「一体、どうしたのだ。」ときくと、彼らは、涙をうかべてうったえてきた。
「ニシバ、この斜里、網走のふたつの場所は、女の子が十六、七になると、クナシリ島につれていかれてしまいます。
男は、女房をめとるころになると、むりやりつれていかれ、夜昼のべつなくこきつかわれるのです。」
「そのために、若い働きざかりの年頃を、遠くはなれた島ですごしますので、ついに一生、女房をもたずに暮らさなければならない者もたくさんおります。
そればかりではなく、男も女も、さまざまな病気におかされ、どんなに体が弱っても、五年や十年はひきとめられ、帰ってくることも許されないのです。」
「また、すでに夫婦になっている者たちがクナシリ島につれていかれると、夫は遠い漁場へやられ、女房は会所か番屋で働かされます。
いつまでもへだてられていることに文句でもいおうものなら、それはもうひどいめにあわされますので、ただただ泣きあかして日をおくっているありさまです。」
「このようなひどい扱いをうけておりますため、昔は二千人もおりましたのに、今はもう、千人にもたりません。」
「今ここに残っているのは年寄り、子供、病人と、満足には働けない者ばかり。
毎日の食べ物を集めるにもことかくありさまで、できることといえば、潮のひいたすきに、浜へ出て貝をひろい、潮がみちてくると、山へはいって草の根をほって、やっと命をつないでいるのです。」
いま私にできることといえば、持ちあわせの米を、少しずつ分けてやるぐらいのことだ。
それがまた、いらだたしい。
五月二十三日
昨日、紋別に着き、今日はアイヌ四人とともに、舟で村々を見てまわる。
イチャスエというところにいくと、山から犬か一ぴき走りだしてきて、我々を見ると、はげしくほえたてた。
アイヌのなかの乙名、ヘイシュクは、犬を見て首をかしげながら、
「ふしぎじゃ。こんなところに人間が住んでる。」といっていた。
そこへ山のおくから、アイヌが一人出てきた。見ると、小人のように小さい。
舟を岸によせて上陸し、とにかく川原に小屋をこしらえさせ、その間に、私はその小人のようなアイヌと話をした。
「私は十勝の者で、シュツアイノと申します。」
と、その男は、自分のことを紹介した。そこへアイヌの女も出てきた。
「これは、私の妻です。」という、その女も、小柄だった。
「おまえたちはずっと山の中に暮らしておるのか。」
「はい。幼いときから山にいて、一度もコタン(部落)へ出たことはありません。」
「それでは、不自由なことも多いだろう。何かほしいものはないか。」
私がそういうと、二人はちょっと顔を見あわせていたが、シュツアイノが、決心したように口をひらいた。
「はい。鍋がもうひとつあれば………。」
「おお、そうか。それでは来年の春は、鍋を持ってきてやろう。」
とわたし、かいうと、がれらは、いかにもうれしそうに、あたまをさげるのだった。
ちょうど食事のしたくもできたので、彼らにも、おかゆをわけてやった。
前に、釧路のあたりでも、コロボックル(フキの下の神さま)とよばれる先住民族の小人の住んでいた家のあとを見たことがあるが、アイヌの小人に出会ったのは今日が初めてだ。
六月一日
宗谷に着く、向山源太夫の墓にもうでた。この人とは、もっと一緒に歩きたかった。
おしい友をなくしたと、しみじみ思う。
六月二十三日
シュルクの川筋をたどって、ウエンノキサフという山に登り、似湾の水源までいった。カニデ、カシワ、トネリコなどの大木が空もくらくなるほどしげりあい、道ばたには、愛らしい草花もさいている。
「なかなかよい道だな。」
「これは鵡川から山ごしにまいる道でございます。三十キロほどあるのですが、ここを夜をかけて往復しておる者がございます。」
「何と足の達者な! それは何者だ。」
「似湾(にわん)のシュクフウクルという者でございます。
三十八になりますが、二つ年下の妻と二人で、母親を大切にやしなっている孝行者です。」
「鵡川(むかわ)の浜へ漁に雇われていっていても、少しでもひまができれば、夜のうちに似湾へ帰って、母親をなぐさめるのです。
こんな深い山の中の道ですから、ヒグマに出会うこともあるとか。
それから、キツネもおりまして、きつね火を見たことがあると申しておりました。
そんなこわい思いをしても働いて、受取ったお米を母親にあたえたいばっかりに、夜ごと、山ごえをしているのでございます。」
「はじめのうちは、だれもそのことを知らなかったのですが、今ではもう、みんな知っています。
場所のお役人かたさえも、大目にみてくださっているようでございます。」
アイヌの案内人たちは、かわるがわる話してくれた、こういう人たちを、不幸におとしいれてはならないのだ。
武四郎の旅は、まだつづきます。
七月のはじめには、アイヌが昔から国の中心としている平取につきました。
ここで少し話が横道にそれますが、毘羅取(ひらとり)大明神のことについてしるしましょう。
高い岩がけの上に建つこの小さなやしろは、源義経をまつったものです。
みなさんも、義経が奥州の平泉で兄、源頼朝の計略にかかった藤原氏の軍にせめたてられ、えぞ地ににげて生きのび、やがて中国へ渡ってジンギスカンになったという言い伝えがあることを聞いていませんか。
アイヌの伝説では、つぎのように伝えられています。
その昔、源義経がえぞへ渡ってきて、この平取のコタンで、酋長の娘と結婚しました。
そして、子供も生まれました。
やがて義経は酋長が、兵法の秘伝をしるした巻物を大切にしまっていることを知って、ぜひそれを見せてほしいと、酋長にたのみました。
けれども酋長は、こればかりは絶対に見せられない、大切な宝物なのだといって、巻物のあるところさえ教えてくれません。
でも義経は、あきらめられません。じっとチャンスをねらっていました。
そして、ある時、ひとつの手を思いつきました。
義経は、ろばたで子供をだいていました。
それを、酋長に知られないようにわざと火の中におとし、あわててひろいあげ、
「おお これは大変なことになった。かわいそうに、やけどはしなかったかしら………。」
と、おろおろと、子供をなでさするのでした。
その義経のうろたえたようすを見ていた酋長は、
(これほどまでに、自分の子供に気をつかっているのだから、もしかしたら本当にこの家の婿になって、腰をおちつけてくれるかもしれない。) |

アイヌの社会では、義経がアイヌ娘と
結婚する話が伝わっていた。
|
と思い、ようやく義経に、その巻物を見せてくれました。
義経はやがてその巻物をすみからすみまで読み、すっかり兵法の秘伝を覚えてしまいました。
そして、ある夜、酋長のすきをねらって、浜べへ走り、小舟をぬすんで逃げ出しました。
気がついた酋長はあわてて義経のあとを追いました。けれども兵法の秘伝を覚えこんでしまった義経はすぐさま雲をよびおこし、その雲にのって満州へ渡ってしまいました。でも、義経の子は、その後も平取で元気にそだちました。ですから、平取のアイヌには、義経の血が流れているのです。
ざっと、こんなぐあいなのですが、これは、アイヌの本当の伝説ではありません。
武四郎が生まれるより二十年ほどまえ、寛政年間にえぞ地を探検した近藤重蔵という人が、こしらえあげたもののようです。
義経が、奥州で死んだことは確かな事実です。ただ。日本人の気持ちとして、血のつながった兄にさえせめたてられた、義経のあわれな立場に同情して、死なせたくないという思いから、さまざまな伝説を生んでいました。
近藤重蔵は、このことを思い出したのでしょう。それを利用して、義経をアイヌと結びつける話をこしらえあげ、アイヌに教えたらしいのです。
彼は、こうしてアイヌたちに、日本人に親しみをもたせようとしたと思われます。
武四郎が歩き回っていたころのアイヌは、まだ、義経をウキクルミとよび、あの衣川での立往生で有名な弁慶をシャマイクルとよんで、尊敬していたようです。
さあ。また武四郎の旅日記にもどりましょう。
七月十日
丸木舟で襟裳岬をまわり、沙流に着く。夕方、シマネズミを二ひきとらえた。アイヌ語ではカセクルクルという、体に縞があって、かわいらしい動物だが、大変すばしこく、とらえるのに大さわぎをした。
七月十四日
ビバイロ川の岸に野宿する。夜になると、大雨におそわれた。フキの葉で屋根をふいた小屋なので、何とも心もとなく、まんじりともできずに夜をあかす。
七月十五日
地面も、たきぎの枯れ枝もびしょぬれで、火がたけない。持っているシカの肉も焼くことができない。しかたなく、みそをぬりつけただけで食べた。
今日は、うらぼんえだというのに、ほとけの供養をするどころではない。おまけに、シカの肉を食べているなんて、ひとにも話せない。
七月二十一日
太陽暦では八月二十九日にあたる。
今日は、この夏一番の暑さだった。 |

北海道に住む動物、左よりテン、シマネズミ、シヤチリ
(『後方羊蹄日誌』より)。
|
それにもかかわらず、今日は、このあたり一番のけわしい山といわれる豊似岳(とよにだけ)に登った。
いただきには、カムイトウ(神の湖)があった。全く、ひさしぶりに、身も心も、あらわれるような思いをした。
八月七日
沙流(さる)でとまる。ゆうべから彗星があらわれている。
アイヌは彗星をシヌエフ・ノシウとよんで、この星が出ると、悪いことをみんなふきはらってくれると信じている。
だから、ゆうべから大変なよろこびようだ。
内地では彗星、ほうき星かあらわれると、悪いことの知らせだといって恐れるのに………と、おもしろく思った。
八月二十一日
ようやく二百四十日めに、出発点に戻ってきた。
えぞ地は広い。前後あわせて六回の旅をかさねても、なお回って見たいところがたくさん残っている。
こうして函館に戻った武四郎は、休むまもなく、さっそく『蝦夷山川地理取調日誌』の整理にとりかかっています。全く人間わざとは思えないほどの、意志のつよさです。
やがて十月五日、武四郎は、一度江戸へ帰ることにしました。
「その前に、小人のアイヌとの約束をはたしておかなければ………。」
あの鍋がほしいといった小人夫婦のことです。武四郎は約束をたがえぬよう、商人の柏屋喜兵衛にたのんで、鍋二つを送り届けています。
今度の江戸ゆきには武四郎は、アイヌの少年を一人つれていくことにしました。すでに以助という日本ふうの名前を名乗っている少年です。武四郎は市助に江戸のようすを実際に見せて、日本のことをもっとよく知らせてやろうと思ったのです。
道中は武四郎も幕府の役人の身分ですから、ていねいにもてなされました。おそらく、うれしいような、くすぐったいような気持ちだったことでしょう。
十月の二十九日に、一ノ戸でとまったとき、大変な情報を聞きました。江戸では、彦根藩主の井伊直弼が大老になり、勤王派の志土たちを、かたっぱしからきびしくとりしまっているというのです。いわゆる「安政の大獄」の嵐が、ふき初めていたのです。
「あわただしい時代になってきたな。」
武四郎は、夢からさめたような気分になりました。
「井伊大老は、徹底的に水戸藩にねらいをつけていると聞く。もし私が江戸にずっといたら、私も捕われていたかもしれなかったな。」
背筋の寒くなるような思いでした。
十一月二十二日、三年ちかく留守にした江戸に、ようやく帰りつきました。明くる日からさっそく方々へ、あいさつにまわりましたが、どうもようすがへんです。前には大変したしかった人たちが、なんだかよそよそしく、武四郎とつきあうことをさけているようたのです。おそらく、水戸藩と親しい武四郎とまじわると、井伊大老からにらまれやしないかと、恐れているのでしょう。
せっかくひさしぶりに帰ってきたというのに、何となくそらぞらしい気分で、安政五年の年の暮れをむかえねばなりませんでした。
けれども、旅日記の整理の筆は休めません。安政六年(一八五九)の四月末ちかくには、『蝦夷山川地理取調書』を書きあげ、堀織部正にさし出しました。
この年には、そのほかに右『何椰類も書きあげていますが、そのうちのひとつ、『近世蝦夷人物誌』について記しましょう。
九冊にまとめられたこの書物の内容はすべて、武四郎がしかに会ったり、アイヌから話てもらったりした、たくさんのアイヌの伝記を集めたものです。これまで、武四郎の四・五・六回のえぞ地探検のあとを、日記ふうにしてしるしたなかにも、そこから引用したものが数多くあります。
ところで、この書物の一番おわりにしるされた、あとがきにあたるもののあらましをご紹介しましょう。
「原稿を書きおえると、心身ともに疲れはて、筆をなげすてて、つい、体をつくえの上にうつぶしたまま、うとうとした――と思うと、いつのまにか、函館の港に近頃できたという、山の上町の大きな料理屋の三階にいるのだった。
大広間には、大勢の役人とともに、ご用達の商人、請負人、問屋、支配人、大工、棟梁、土方、船頭など、大勢の人たちが、山海の珍味をもりだくさんにならべたてて、大酒もりをしていた。 商人をはじめ、だれもかれも、役人たちにおせじをいい、おついしょうをならべたてている。芸者のうたと、おどり、三味線の音も高々と、全くのドンチャンさわぎをしていた。
すると、どこからか、スーツとなまぐさい風がふきこんできた――と思うと、みるみるうちに、木ざらにもりあげられたぜいたくな料理が、みんな生血のしたたるような人間の肉と骨と腹わたにかわり、さかずきになみなみとつがれた酒は、まっかな血しおになってしまった。そればかりか、大広間のまわりには、アイヌの亡霊がたくさんあらわれ、それらが一斉に、
“あーあ、うらめしや、うらめしや――………。”とよびかけるしまつ。 |
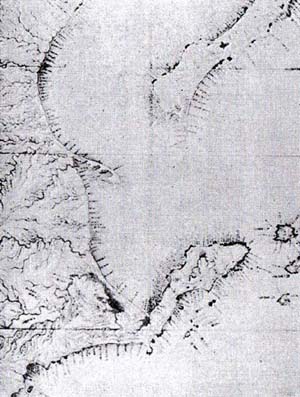
『蝦夷山川地理取調書』
(えぞさんせんちりとりしらべしょ)の一部
|
“あっ!”と思ったとたんに、私は目がさめた。
気がつくと、体じゅう、ぐっしょりと冷や汗をかいているのだった。」
これまで、どこへいっても、日本人の間違った政治のために、苦しめられているアイヌを、嫌というほど見つづけてきた武四郎の、政治にたいする激しい怒りのあらわれといえましょう。
このころ武四郎は自分の住んでいるところを、餐(ざん)ごう豆居(ずきょ)とよんでいました。
いりまめを食べながら暮らすへやという意味です。武四郎は、いりまめが大好きでした。
その好きないりまめをポリポリかじりながら、原稿を書く筆をすすめていた――すでに四十二歳の武四郎でした。
この年の秋には、福田トウという、幕臣の娘と結婚しました。
(旅にあけくれて、この年になって初めて妻をむかえるはめになってしまったが、あの十人の子持ちだったアイヌのテケモンケが聞いたら、どんなによろこんでくれるかしら。)
武四郎は、ふと、えぞ地の日々に思いをはせるのでした。
新婚の日々をたのしむまもなく、武四郎は、くる日もくる日も原稿を書いたり、書きあげたものの出版のために走りまわったりという、忙しさに追われていました。
それは、何かにとりつかれたかのようでした。
十月にはいって、安政の大獄の結果、したしかった頼三樹三郎、吉田松陰なども、次々に処刑されたことを知りました。
どんなにか、心をかきみだされたことでしょう。けれども、筆を休めません。
こうして書きあげたものをすべて堀織部正にさし出すと、十一月十二日、武四郎は、
「蝦夷地おやといの職を、やめさせてください。」という願書を出しました。
理由は、病気のためということになっています。けれども、それはうそでした。
「水戸ぎらいで有名な井伊直弼が大老として権力をにぎっているかぎりは、幕府は、私の出むく場所ではない。
これ以上、役人の席にとどまっても、おそらく、何も仕事はできないだろう。
そうとわかっていて、幕府の手当をもらっているわけにはいかない。」
おそらく、これが本心だったと思われます。
年の暮れに、武四郎は、つぎのような意味の漢詩をつくっています。
世間の人たちよ。笑ってくれるな。
住んでいるところは、ちっぽけな家だが、心の中は、えぞを思う気持ちがはりさけんばかりにつまっている。
幕府から手当をもらう身分も、年の瀬をしおに、きっぱりと捨ててしまった。
これからは、心もはればれと、頭上の青空をあおいで暮らすのだ。 |
12 歩かない者になにがわかる
top
安政六年(一八五九)の暮れ、自ら出したお役御免の願いが聞き届けられ、武四郎は、何の制約もない全く自由の身として、万延元年(一八六〇)の正月を迎えました。
これから明治元年二八六八)、今度は新しい政府からよびだされるまでのまる八年間.武四郎には何の肩書きもありません。
一人の中老の人として妻とともに、めだたない日々をおくっていました、
その間に.政治の世界では、明治維新の大づめを迎えて.めまぐるしい変動がつづきました。
万延元年の三月三日には井伊大老が桜田門外で、水戸の浪士を中心とする勤王派の人々におそわれ、命をおとしました。
これが導火線となって、勤王、佐幕、攘夷、開国、それぞれの意見をもつ人たちの動きが、いっそう激しいものとなりました。
外国人が殺されたり、イギリス公使館が焼き打ちのめにあったりするかと思うと、片方では意見のちがいから、日本人同士の殺し合いが、あちこちでおこります。
才能にめぐまれた多くの人たちも、この騒ぎのなかで、次々と命をおとしていきました。
武四郎にとってもっとも悲しかったのは、堀織部正(ほりおりべのかみ)切腹してはてたことでした。 万延元年の十一月のことです。
老中の一人と意見の衝突があって、そのためだと世間ではとりざたされましたが、本当のところはよくわかりませんでした。 |

幕府の役人を辞め、妻とひっそりと過ごす武四郎
しかし井伊大老が殺され、世は動乱の時代を迎える。
|
大変尊敬していた人を失った武四郎は、もうどんな役にもつきたくないと思うようになりました。
けれども国をあげての大騒動のときですから、武四郎のようにエゾ地については、この人の右に出るものはないというほどの名声をえた人を、捨てておくはずはありません。
いろいろな立場の人から、さまざまな誘いがかけられました。
武四郎は、これらをすべて断わりつづけました。引受けたのは、わずかに常陸(茨城県)の水利工事の下調べぐらいのものでした。
元治元年の春には、水戸藩士の一人加藤木(かとうぎ)賞三の家から、養子を打かえました。
妻のとうが、これまで二度も流産したため、養子をもらうことに踏み切ったのです。
ところがその年の十一月に女の子が生まれました。
四十七歳ではじめてわが子をだいた武四郎でした。
この娘は、おいしと名づけられました。武四郎のかわいがりようは、大変なものでした。
妻子とともに、平和な暮らしがつづきました。
書いたものを出版しているため、経済的にはいくらかゆとりができて、次々と旅の記録の整理をつづける傍ら、文人仲間との交わりをふかめていきました。
その間には、維新後に名をなした木戸孝允(きどたかよし)、その頃は桂小五郎といっていたのですが、その木戸にも会っています。
また、西郷隆盛とも知りあいになっています。
慶応四年(一八六八)の春.江戸城はついに官軍にあけわたされました。
江戸は、官軍の総攻撃からはまぬがれました。
けれどもも幕府に恩義を感じる武士たちが彰義隊を結成して、上野の山にたてこもってしまいました。
その頃、武四郎は、上野の山のちかくに住んでいました。
彰義隊と官軍のいくさになれば、ここも戦場になるかもしれないと、落着かない日々をおくっていたとき、ある夜、武四郎の家の戸を、どんどんどんとはげしくたたく音がしました。 |
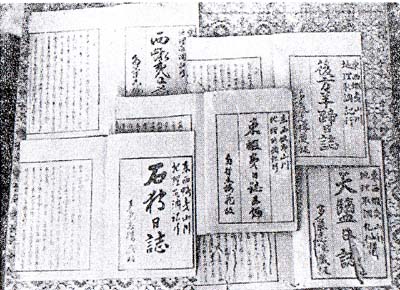
出版された『日誌』の数々。水戸藩の志士との関係から、
薩長の著名な志士とも、知合いになる。
|
「さては、軍用金を押し取りにきたか!
前に.釧路づめの役人の一人で、ひどく私をうらんでいる者があったが、そいつが彰義隊に入って、仲間をつれておそってきたのかもしれない。」
と、とっさの間に思いました。
けれども.いまさら逃げかくれするわけにもいきません。思いきって表の戸をあけました。
すると、そこに立っていたのは、何と官軍の身なりをした一人の兵士でした。
「松浦武四郎どのですか。」
「さようですが……。」
「これをごらん願います。」
状箱(手紙を入れるはこ)をさし出しました。
受取って開いてみると、大総督府参謀から、すぐにきてくれというよび出し状でした。
なんだかわけがわかりませんが、とにかくさっそく衣服をあらためると、武四郎は、その兵士についていまは官軍がはいっている江戸城にむかいました。
あいにくひどい雨降りの夜でした。ようやく夜中の十二時すぎに江戸城につくと、しばらく待たされたあげく、
「今夜はもうおそいから、あすの朝あらためてくるように。」
とのこと、なんだかあほらしいとも思いましたが、これが役人の仕事というものでしょう。
あくる日あらためて出向くと、朝廷から武四郎にいそいで京都にくるようにというご命令だと、伝えられました。
武四郎が江戸をあとに京へむかってたったのは、閏四月九日のことです。
おりから梅雨どきにあたり、毎日雨がふりやまず、川どめにあったりしながら、苦労のすえに京都にはいりました。
武四郎が朝廷からよばれたのは、新政府の役人としてとりたてられるためでした。
命じられた役名は「任徴士(にんちょうし)箱館府(はこだてふ)判事」(その頃はいまの函館を箱館と書いていたのです)さらに、従五位下(じゅごいのげ)という位をいただきました。
五月の二十五日には、これまでのえぞ地調査にたいして、朝廷からごほうびをいただきました。
そして帰り道には、東海道をよく調べていくようにという命令をうけました。
これにはわけがありました。
これまで幕府では東海道をさえぎって流れる馬入(ばにゅう)川、安倍川、大井川、天竜川などに橋をかけることを禁じていました。
西国の大名たちが、謀反をおこして江戸に攻めのぼるなどということが、容易(たやす)くできないようにするためです。
そのおかけで、旅びとは大変なんぎをしました。
天気がよければ、渡し舟にのったり、人足の肩にかつがれて渡るのですが、ひとたび大雨がふると、川の手前で雨がやむまで、いく日でも待たされたのです。
武四郎が今度京都へ上るときも、馬入川で川止めにあいました。
こんなことをつづけていたのでは、これからの国の政治は、やっていけない、と考えた武四郎は東海道に間道をもうけて、もっと川幅の狭い、上流をわたる道をつくったほうがよいと、新政府に意見書を出しておいたのです。
その意見が取入れられて、今度の命令となりました。
帰る道すがら、旅人の不便につけこむたちのわるい商人や、かごかき人足などの話をあれこれ聞くにつけ、武四郎は自分の出した意見に間違いはなかったと思うのでした。
江戸にもどると、秋、年号は明治とあらたまり、江戸も東京とよばれるようになりました。
天皇を京都からお迎えし、東京は日本の首都となったのですが、まだ名前ばかりで、火の消えたようなさびれかたでした。
武四郎は箱館府判事という肩書きはもらいましたけれど、実際にえぞ地へいくわけでもなし、何となく手持ちぶさたのようなかっこうでした。
彼のえぞ地の知識や体験が本当に生かされるようになるのは、明治二年になってからです。
新政府ではようやく、えぞ地をこのままほうっておくわけにはいかないと、本腰をいれはじめたのです。
それには、ロシアとの関係もありましたが、国内の事情もあったのです。
去年の秋、会津でたたかいがありました。それは何とかして幕府の権威をもりかえそうとする人たちが会津に追いつめられ、官軍にはげしくせめたてられてついに降伏した事件です。
それでもまだおさまりがついたわけではなく.かつて幕府の海軍にいた榎本武揚が、幕府の軍艦を持って函館にわたり、五稜郭にたてこもってしまいました。
明治二年の二月、官軍はやっとのことでこれを降伏させたのです。
えぞというまだ充分、開かれていない広い土地を、計画的に開拓しなければ、国のために大きな災いをのこすという意見が、新政府のなかで強くなりました。
これから、武四郎の舞台です。かれは明治二年の六月には、「えぞ開拓ご用がかり」という役をおおせつかりました。
ところかあいかわらず、とくにこれといった仕事も決まりません。
そこで武四郎はえぞ地に新道をどのようにきずくかという意見書にそえて、月給をお返ししたいのでそれを許してくれという願書を出しました。
おどろいたのは新政府です。
「どうして返したいといわれるのか。」という問いに、武四郎は次のように答えています。
「これまで、私は役職の任命をうけましたが、格別にこれというほどのことはいたしておりません。
そのうえ新政府もできあがってまもないことで、何かと物入りもかさみましょう。
そんなときに、ただ月給をいただくだけでは、心苦しくてたまりませんので、お返しいたします。」
この願いは、ゆるされませんでした。
それならと今度は、開拓ご用がかりを辞めさせてくれと言い出しました。
一本気な武四郎には、そうでもしなければいたたまれなかったのでしょう。
これは政府側の人たちからなだめられ、もみけされてしまいました。
そのうちにようやく開拓使というものがさだめられ、開拓のことも手がつけられはじめました。
新政府は武四郎のいったとおり、大変資金にくるしんでいました。
もともと、徳川家のように広い領国をもっているわけではなく、各藩の有志の寄合世帯みたいなかたちで、無一文
でうちたてた政府といったところでしたから、大変なわけです。
それに全く新しい政府のかたちを、いろはのいの字からきめて、組みたてていくのです。
必要な機関とわかっていても、すぐにはきめられないものもたくさんありました。
開拓使がそのひとつで、武四郎のように役にたつ人間は、早々とおさえておきましたが、どういう政治組織の下におくかが後からきまったわけです。
いまさら文句をいっても始りません。
武四郎はさっそく、えぞ地をこれから何とよんだらよいかという問題にたいして「道名の義につき意見書」というものを出しました。
そのなかには日高見道(ひだかみどう)、北加伊道(ほっかいどう)、海北道など、六つがしるされてしました。
政府でも相談のあげく北加伊道を取上げ、その加伊(かい)を海とあらためることにしました。
こうしてえぞ地は北海道とよばれることになりました。
武四郎は、えぞ地に足をふみいれるようになってから、ペンネームに北海道人という名を使った頃がありました。
思いがけなくも自分が愛してやまない土地の名が、自分のペンネームと同じになったのでした。
ひきつづき武四郎は、北海道のなかの国の名前と土地の名前を、どのようにきめたらよいかという問題にたいしても、意見書を出しました。
その意見が取上げられて、十一の国とその下の郡の名が、それぞれ決まりました。
まず武四郎の原案を見てみましょう.
渡島(おしま)国(六郡)
亀田・茅部(かやべ)・福島・津軽・檜山(ひやま)・爾志(にし)
後志(しりべし)国(十七郡)
久遠(くどお)・奥尻・太櫓(ふとろ)・瀬棚(せだな)・島牧・寿都(すつつ)・歌棄(うたすつ)・磯屋・岩内・古宇(ふるう)・積丹(しゃこたん)・美国(びくに)・古平・忍路(おしょろ)・高島・小樽・余市
石狩国(七郡)
石狩・札幌・夕張・樺戸(かばと)・空知・雨龍(うりゅう)・上川
天塩国(八郡)
厚田・浜益(はまます)・増毛(ましげ)・留萌(るもい)・苫前(とままえ)・天塩(てしお)・中川・上川
北見国(八郡)
宗谷・利尻・礼文・枝幸(えさし)・紋別・常呂(ところ)・網走・斜里(しゃり)
胆振(いぶり)国(八郡)
山越・虻田(あぶた)・有珠(うす)・室蘭・幌別・白老(しらおい)・勇払(ゆうふつ)・千歳(支笏=しこつ)
日高国(七郡)
沙流(さる)・新冠(にいかっぷ)・静内・三石・浦河・様似(しゃまに)・幌泉
十勝国(七郡)
広尾・当縁(とうぶち)・大津・下川・河東・河西・十勝
久摺国(八郡)
白糠(しらぬか)・足寄(あしょろ)・久摺(くすり)・善報(ぜんほう)・阿寒・網走・川上・厚岸(あっけし)
根室国(五郡)
花咲・根室・野付(のつけ)・標津(しべつ)・目梨(めなし)
千島国
国後(くなしり)・択捉(えとろふ) |
それにしても、まあ何とややこしい文字を使ったものでしょう。
これらはすべて、アイヌが呼び習わしていた地名に、日本の文宇をあてはめたものなのです。
いまの私たちの目からみれば、こんなむつかしい漢字をならべたり、無理な読み方をさせたりしないで、できなかったものだろうかとさえ思えます。
アイヌ語の地名の意味をとって、日本語の地名になおせば、日本人にわかりやすかったことは事実です。 |

各地のアイヌの呼び名を漢字にして地名が決まった北海道。
|
あるいは、カタカナのままでもよかったのではないかとも思います。
武四郎も旅の記録には、さかんにカタカナをつかっています。
この本で、日記のようにして旅の内容をご紹介した部分では、いまのみなさんにわかりやすいように、現在の地名で漢字でしるしましたが、武四郎はカタカナで書いているのです。
それはともかくこの原案のほとんどがそのまま認められ。北海道の内部の地名はきまってしまいました。
これも武四郎が名づけ親です。なかには政府側の人の意見で、いくつかは変えられました。
たとえば、いま千歳といっているところは、アイヌはシコツとよんでいました。
けれども、日本人の感覚では、シコツは死骨と間違えられ、縁起がわるいから、思いきって縁起のいいツルにちなんだ千歳にしようといった具合です。
武四郎は、このような変更をきらいました。
彼の考えは、北海道にもともと住んでいたアイヌの呼び名を守るべきだというのです。
アイヌに見なれない地名をおしつけて、あらたな苦労をあたえたくありませんでした。
それより後から入っていく日本人が、アイヌのいう地名を覚えて、そこで仲良く暮らすべきだという考えだったのです。
それはそれで、立派な考えでした。
ただ残念なことに、武四郎が幼い頃からうけた漢学の知識のために、一般の人にはピンとこないようなあて字がたくさんになってしまったわけです。
ついでにいまはソビエト領となっているサハリン、昔のカラフトに樺太の字をあてたのも武四郎です。
エゾが北海道となったので、北エゾといっていたカラフトにも新しい名前をつけることになり、武四郎の意見が取上げられたのです。
「カラフトには、樺(かば)の大樹がたくさんしげっているから、樺太とするのがよい。」と、武四郎はいっています。
さて、明治二年の八月には開拓判官を命じられました。
今日でいえば、国務大臣クラスの役にあたりましょうか。
月給は、当時のお金で二百円ですから、相当なものでした。
このごろは毎日、開拓使に朝からつとめる身分となりました。
開拓判官の仲間としては、北海道でもふれあった島義勇(しまよしたけ)も一緒でした。
けれども武四郎としては、何となく心楽しまない毎日となりました。
どうも役所の空気と、しっくりなじまないのです。
役所の事務をとるところは、広い座敷で、机がきちんとならび、まんなかの辺りに大きな銅の火ばちがすえてあります。
開拓使長官は、勤王派四公卿あがりの人でしたが、まだ三十九歳という若さ。
大変、几帳面性格で、役所へもきちんと毎目顔を見せ、部下の仕事ぶりを見てまわります。
しぜん、役所のなか全体が、極めて事務的な場所となりました。
それにもかかわらず武四郎は、広い座敷にはいると、自分の席になどつきません。若い役人たちが、
「松浦判官、おはようございます。」と、かしこまってあいさつするのを、
「おお、おはよう。」と、大きな声でうけこたえたまま、いきなりまんなかの大火鉢の脇に、どっかと腰をすえます。
そして、腰から、小さいなたまめぎせるをぬきとると、火の用心と言いた煙草入れの袋をとり出し、スッパ、スッパと、煙草をすいはしめます。
そばに島義勇がいると、あたりにはばからず、大声ではなしだすのでした。
「北海道四開拓。開拓といっても、もっと内地から、どしどし北海道へ出かけていって、実際のことを知るようでなけりやいかんな。」 |

東京での北海道の仕事では、仲間の島義勇との火鉢をはさんでの雑談だけで、武四郎にはなじめなかった。
|
「さよう、机の上で書物を読んだり、ひとの報告ばかり見ていたのでは、本当のことにわがらん。」
「百聞は一見にしかず、北海道の寒さがどのようたものかは、そこに暮らしてみたものでなけりゃ、わかるはずがない。
まずいってみることじゃ。」
「まことに、そうしてはじめて実際にあった、血のかよった命令を出すことができるというものさ。」
確かにもっともな意見です。
武四郎にしてみれば、開拓判官などと立派な名をもらっても、ぬくぬくと新都東京に居座っていることが、やりきれなかったのでしょう。
そして.北海道のホの字も知らないような大勢の役人が、毎日書類をいじくりまわしていることが、仕事を手間どらせている原因だと思うのです。
けれども聞くほうの側にしてみれば、これほど嫌味な言葉はありません。
しだいに、役人たちは武四郎や島義勇をさけるようになりました。
そして、判官の目をとおしてから長官に出す書類なども、武四郎や義勇には見せず、じかに長官にさし出されることが多くなりました。
また.函館から商人や請負人が陳情に上ってくると、武四郎たちには会わせないように、こっそりと用をすませてしまうらしいのです。
武四郎は、面白くありません。
「それほどまでにこの私が邪魔にされるのでは、これ以上お役大事に務めても始るまい。きっぱりと辞めよう。」
このような決心をかためたやさき、明治三年(一八七〇)二月末の夜のことです。
知人の一人が、あわただしく武四郎の家にかけこんできました。
「松浦の旦那、大変です。旦那のお命をねらっている人がいるてえことです。」
「何だって、この私を?」
「はい、松浦もいそいでかたづけるといっているのを聞いたと、ある芸者がいってました。
それですぐお知らせしなくてはと、とんできたのです。」
「はて、私はひとにねらわれるようなことをしたおぼえはないが………。」
ふしぎに思ってよく事情を聞くと、次のようなこととわかりました。
その芸者がある料亭へよばれていくと、ざしきには函館の商人だと名のる町人二人と、役人らしいさむらい二人が集っていました。
彼らが酒をくみかわしながら話ているのを、それとなく聞くと、役人たちは、
「もはや気づかいにはおよばぬ。松浦も急いでかたづけ申す。島判官のほうも.じきに追いはらうことができる。」
といいました。聞いて商人たちは、ぺこぺことあたまを下げ、
「かたじけのうぞんじます。これと申しますのも、みなお二人さまのおかげ、このお礼は、充分に……。」
などといっていた、というのです。
「ああ、それでは片付けるといっても、殺すというのではない。安らしなさい。」
そういって、知人を返しました。
つまり彼らは、武四郎を判官の役からひきずりおろそうと、運動しているのです。
「こうまでされて、おめおめと、職にいすわってなどいられるものか。」
心をきめた武四郎はさっそく、辞職願いを書きました。ただしそれはただの辞職願いではありません。
新政府の器にかわっても、あいかわらず中身は、商人と役人が利害で手をむすんで、くされきった内容であることを、自分にたいする嫌がらせを例にとって、あらいざらいばくろした、きわめて長い文章からなっていました。
同時に自分のまきぞえで、島義勇までやめさせてはわるいと思い、島義勇がどんなにまじめに仕事をしているかをたたえて書くことも忘れませんでした。
武四郎の決心を聞いて、島義勇はひきとめました。
「不愉快ではあるが、もう少しいまの地位にしんぼうしようではないか。
そうすれば、いずれはまた、北海道へ渡れる日もくることだろうに。」
武四郎も愛する北海道に渡りたいのはやまやまです。
げれどもいまさら出かけていって、昔どおりの役人の嫌らしさ、商人の悪どさを見せつけられるのは、ごめんだといった気持もありました。
「北海道もまずは外国にとられるようなことにならなくて、よかった。
これで、私のなすべきことは、すでに終ったのさ。」
こういって、はじめの決心をひるがえそうとはしないのでした。
長官にしても、この長文の辞職願いは自分のいたいところをつかれたものですから、面白くありません。
結局。武四郎の願いは聞き届けられ、明治三年の三月、武四郎は役職からしりぞきました。
ただし死ぬまで十五人扶持という給付かもらえ、東京府士族という身分が保証されました。
新政府のお召しとあって“この私でも役にたつならば”と、身をさしだした武四郎でした。
けれども、根が役人にはむいていなかったのでしょう。
「官に仕えるというのは、まことに窮屈なものだ。ちっとも面白いものではない。」
と、家族や友人にもらしたといいます。
再び自由の人となった武四郎には、またもや本を書いたり、文人と気ままな交わりをむすんだりという、楽しい日々が始りました。
その頃かれは、自分の号に「馬角斎(ばかくさい)」というのを使い始めました。
武四郎の住んでいたのが、右大臣岩倉具視のやしきのお長屋で、馬場先門の南の角にありました。
昔の方角のよびかたでいくと、南は午(うま)、つまり馬に通じるので「馬角斎」は住まいのある方角をあてていったものといえます。
げれども、それだけでしょうか。「馬角斎」と、口でとなえてごらんなさい。
バカクサイ――そうです“なあんだ、ばかくさい”のそれです。
「すったもんだと苦労しかあげく、人間の社会とは何とばかくさいものか。」
といった程度の多少諷刺(ふうし)をこめたしゃれが、この号を考えさせたものでしょう。
13 一生の仕事をもて top
「何とこれは広い平原であろう。これほどの高山のいただきに、このような大平原があるとは……。
日本じゅうをさがしても、紀州の高野山とここだけではないだろうか。
それに高野山もここも、水がゆたかで開こんすれば、きっとすばらしい天地ができあがることだろう。
私ももう、あと残り少ない命。老いの身をここにうずめて、開拓にちからをかすことができたら、幸せなのだが………。」
“ここ”というのは奈良と三重の県ざかいにそびえる、大台が原です。
千七百メートルちかい高さをほこる日出(ひで)が岳を中心に、南北二十キロにわたって、巨大な山塊を横たえている、紀伊半島でも指おりの険しい山地です。
そして.いまそのいただきに立って、じっと思いをこらしている一人の老人――それは、松浦武四郎でした。
もう七十歳に手のとどく年になっています。
うばそくも ひじりもいまだわけいらぬ
深山(みやま)のおくにわれは来にけり |
武四郎がうたったとおりでした。この大台が原は、わが国の登山の開祖といわれる役(えん)の行者も、行基菩薩も、弘法大師心登ったことのない深い山でした。
武四郎は、明治十八年(一八八五)の春、この大台が原に登ることを心にきめ、東京の家をあとにしました。
途中、京都で知合いの家によって、
「今度は、大台が原に登るためにやってきた。」というと、その人は、腰をぬかすほどおどろきました。
「め、めっそうもない。大台が原に登るなんて、おやめなされ。 |

紀伊半島の大台が原に登る武四郎。
山が深いため、当時は修験者も行かない山だった。
|
まだ、だれも登ったことのない深い深い山、大蛇やまむしがうようよいるときいてます。
もうその年で、そんな危ないところへいくなど、とんでもない話。悪いことはいわない。やめなされ、やめなされ。」
まごころこめて、心配してくれているのです。
武四郎は、ありがたいことだと思いました。
でも、かねてから心にきめていたことは、変えられません。
「ご厚意はかたじけないが、やめることはできません。
もしも山の中で大蛇ややまむしに出会ったら、山の神さまにお供えしますわい。」
武四郎があまりにきっぱりとした態度なので、とうとうその人もあきらめたのか、黙ってしまいました。
こうして武四郎は、大台が原に向いました。
険しい山坂を、あえぎあえぎ登りながらら、武四郎はいつしか、昔の思い出にひたっていくのでした。
(私もずいぶんいろいろなところを歩き回ったものだ。
若いころの全国をめぐる無銭旅行、そして北海道を六回も、ぐるぐるまわって歩いて………。)
全くそのとおりでした。せっせと歩き回っては、帰ってくると記録の整理をして、出版する――このくりかえしで六十年ちかくがたってしまったのです。
武四郎は、大変筆のはやい人でした。次のような言い伝えがあります。
昔は、はたごに宿をとると、まず上り口で、たらいの水で足をすすぎます。
武四郎は、そのすすぎ水をつかうまえに.立つたままで筆をとり、その日のうちに見たり聞いたりしたことを、すべて書きとめてしまうというのです。
武四郎の書いたものは、筆のはやいせいもあってか、大変、読みづらいことは確かです。
忘れないうちにと、サッサッと筆をとばして書きしるし、あとでまた思いだしたことを、小さい字で書きこむといった調子で、武四郎の文字を相当、読みなれた者にも、なかなか読み解くのがむずかしい場合すらあります。
武四郎は、これらの記録をもとに、一生の間にたくさんの書物を世に送り出したのです。
明治三年に、政府の役人をやめてからしばらくの間は筆をとったり、親しい人たちと交わったりしてすごしました。
明治十六年、六十六歳の年までは、あまり旅らしい旅はせずにすごしたのです。
それなのにその年の春、三井寺にいったことからまた旅に出る日が多くなりました。
三井寺へいったときにはえぞ地の探検で、いつも武四郎と一緒に旅の日々をすごした、記念の大小三つの鍋を、境内の天神山にうめました。
(あの三つの鍋は、私にとっては、いわば命の恩人。
もう北海道にわたることもなくなったので、鍋供養をしたというわけさ。
鍋を三つ埋めて、塚をたてた。
わけを知らない人から見れば、どこかのおいぼれ気違いのしわざと思うだろうなあ。)
それは鍋塚とよばれ、いまも残っています。
近江出身の小野湖山という武四郎の親友が書いた、この塚のいわれ書きが刻まれています。
この鍋供養でもわかるように、この頃から武四郎はそれまでの一生のしめくくりをつけようと意識し始めたふしが見られます。
各地の天満宮におまいりして回ったこと心その一つです。
役人をやめてからの一時期、武四郎は、まるで子供のように、いろいろな古いものを集めることに熱中しました。
むかしのお金、古い鏡、土器、石器、ふるびた仏像と、なんでも集めました。
ほしいと思った品が目につけば、その持主のところへ、何度でもおしかけてゆき、いつまでもいつまでも眺めています。
しまいには、持主のほうで根まげがして、
「それほどまでにこの品がお気にいりましたか。」と、つい声をかけてしまいます。
すると武四郎は、
「いかにも、気にいりました。できれば、これをゆずっていただきたいものです。」と頼み込み、ついに、
「それでは、おゆずりいたしましょう。」ということになってしまうのが常でした。
そのために。世間からは「乞食武四郎」とあだ名されたほどでした。
もちろん武四郎が集めるのは、いわゆるガラクタではありません。
若いときから諸国をあるいているだけに、いいものを見分ける目は、大変肥えていました。
それで、ひとに頼まれて、美術品が、本物か、偽物かを見おける鑑定を頼まれることもありました。
それによって受けるお礼も、彼の収入の道のひとつでした。
これを見てもわかるように、武四郎は収入の道をはかることも、なかかかしょうずでした。
ふつう探検家などというと、世間づきあいのへたな人がよくあるのですが、武四郎はちがいます。
若いときから、大変、人付き合いが上手でした。
そのために、友人もたくさんありましたし、いつでも何か収入の道が見つかるのでした。
そればかりではありません。もしその気になれば、武四郎は立派な大商人になっていたことでしょう。
明治六年に武四郎は五十六歳で、生まれてはじめて自分の家を建てました。
その時、自分の住いのほうはなるべく質素にまとめました。
そして、表どおりに面したほうには、貸し長屋を建てて、ひとに貸していたのです。
また、その長屋の一部には、店をこしらえて、妻のとうに商売をやらせています。
品物は、北海道の親しい友人たちから取り寄せたサケ、マス、ニシン、コンブなど、さまざまな産物です。
いまでいう北海道物産の直販売所といったところです。
なかなか.ぬけ目のないやりかたです。
ただ、利をかさばることにあくせくしていませんから、長屋も友人の困っている人たちに貸していますし、店のほうもめずらしい北海道の物産を、東京の町の人たちに少しでも安く、手に入れてもらえるようにという思いから始ったものでした。
(人間くふうをすれば、お金はつくれるもの。
若いときから苦労をした人間なら、誰だってこんなことはわかるうというのに、旗本のおさむらいなどといって威張っていた人たちの、何と気のどくなこと………。)
全くそのとおりでした。
その頃はまだ、旗本のご家人くずれの人たちが、食べるに困って、町をウロウロしていました。
彼らのなかには名の知れた人たちの家へいっては、無理やりにお金をせびってあるいたりする者もありました。
武四郎も、何度かそういう連中の訪問をうげています。
武四郎は、そういうときは、いつも、
「私が会うと面倒だから、いま留守だといってかえしなさい。」
と、お手伝いさんにいいながら、そっと、いくらかずつのお金をつつんで渡すのでした。
(どうやら世の中も落着いてきたし、妻のとうも、そろそろ隠居ぐらしを楽しませてやろうかな………。
それにしてもおいしは、かわいそうなことをした。
せっかく三回めにようやく無事この世に生まれてきた娘なのに。
やはり死んでしまって、もうはやいもので、今年は十三回忌か。
この大台が原の山登りがぶじに終ったら、娘の供養のために秩父に入って、秩父三十四か所の観音めぐりをしようかな。)
こんな思いを一足一足にこめながら、武四郎は、大台が原を登っていくのでした。
そしていただきに立って、ひさしぶりにすがすがしい山の空気を胸いっぱいに吸い込むと、もう武四郎にとって、犬台が原は、忘れることのできないものとなりました。
(この地に骨をうずめたい。)
この思いが、武四郎の心のなかに、しっかりと根をはってしまったようです。
はじめての大台が原の旅から帰って、秋には、予定どおり、秩父の観音めぐりもすませました。
この頃から、武四郎は、めっきりひととつきあわなくなりました。
書画の会などにも顔を見せなくなりましたし、大好きだった芝居見物も、プッツリとやめてしまいました。
ひたすら書斎にこもって、大台が原山行の記録のまとめにかかっていたのです。
書くことにつかれると、庭に出ていって、諸国から集めたたくさんの種類の草木の世話をします。
けれども、ひとしきりすると、また書斎にもどって、机にむかうという毎日でした。
おそらく。武四郎は自分の心のなかにどっかりとすわっている大台が原の山々と、語り合っていたのでしょう。
そうして、気力がみなぎってくると、年もかえりみずに大台が原へ出かけていきます。
武四郎は、明治十八年、十九年、二十年と、三年つづけて大台が原へ登りました。
そして、十九年に住まいのひとすみに建て増したたたみ一畳じきの書斎に座っては筆をとり、大台が原への思いをこらしていたのです。
このたたみ一畳じきの書斎というのについて、少し説明しましょう。
一畳じきといえば、大人三人も座ればいっぱいになるような狭さです。
武四郎はこれを建てるにあたって、日本全国の友人や知人から、それぞれいわれのある木ぎれを一つずつ寄進してもらいました。
それらを寄せ集めて、大工に頼んでこしらえさせたのです。
のちに武四郎は一枚一枚の木ぎれの寄贈者と、そのいわれを書いた小さな本をこしらえ、「木片勧進」と名づけて、寄贈してくれた人たちにくばっています。
この狭い書斎に、武四郎は建てた年の暮れ、その時の心境を一枚の紙に書いてはりつけました。そこには、
「自分の住まいすべてのたたみ数が、この書斎まで入れて十九畳半になる。
これは二十枚という数を満たさず、少したりないところで我慢しようという心持をあらわしたものだ。」
という意味のことが書かれています。そしておわりのほうに、
「私が死んだらこの書斎はこわして、ここにつかわれている木ぎれで私のなきがらを焼き、骨は大台が原にうめてくれればありがたい。」とも書いています。
三度めに大台が原に登ったときは、名古屋谷の牛石というところで、山岳宗教の行事に参加しています。
木を組みあげ、火をはなって、いわゆる護摩をたくのです。
ほのおが空をこがすなかで、集った六十三人の信者たちが、火のまわりを交わりながら、
「のうまくさんまんだ、のうまくさんまんだ。」と、経文をとなえます。
その声と、ジャラン.ジャランとならす錫杖(しゃくじょう)の音が、山々、谷々にこだまして、心はいよいよ澄みわたってくるのでした。
大台が原との三度めのふれあいをすませて東京に帰ってくると、武四郎は、ひさしぶりに富士山に登りたくなりました。
十九歳のとき、いちど登っています。それからかぞえると、もう五十一年めになります。
七十歳になっても、なお衰えをみせない武四郎でした。
このときのことで、面白い話が残っています。
頂上で、ご来光をおがんで、大宮口に下り知人の佐野寅吉という人の家に泊っていました。
そこへ警官がたずれてきて「何の気なしに宿帳を見ると、
「東京 士族 松浦武四郎 七十歳」と書いてあるのに目をとめました。
「七十歳? おい寅吉。これは何者だ。」
「はい。このお客さまは、さきほどお山をくだられて、いまお泊まりでございます。」
「嘘をつけ。これには、七十歳と書いてあるぞ。」
「いかにも、さようでございまして。」
「こらこら、私をばかにするのか?
七十の年寄りが、お山の頂上をきわめて、ここまでこれると思っておるのか。
嘘にきまっておる。あやしい者だから、取調べるぞ。」
警官がいきりたつのを寅吉は、一生懸命おさえました。
そして、武四郎という人が、どういう人物かをくわしく説明して、世聞なみの七十歳の老人とは、わけがちがうことを、やっとのみこんでもらったということです。
明治二十一年(一八八八)、武四郎は七十一歳の正月を迎えました。
二月四日、武四郎は下谷に友だちをたずねました。
それは鷲津毅堂(わしづきどう)といって、学者としても名の聞こえた人でした。
気ぐらいがたかく、人づきあいがうまくありませんでしたが、武四郎とは、ふしぎに気のあう間柄でした。
それは雪のふる日でした。
鵞津毅堂はよろこんで武四郎を迎えいれると、さっそく武四郎の好きな煎り豆などをさかなに、酒をくみかわしはじめました。
毅堂がいいました。
「あなたも、もう大台が原に三回いかれたそうだな。開拓場というのがあるそうだが、いまはどうなっているのだ。」
「大台の山中でも、もっとも地味の肥えたところでしてな。
明治三年に京都の人が何人かで登って、畑をひらき、アワ、ヒエ、ムギ、ダイス、アズキそのほか菜っぱや大根を栽培してみたそうな。
二年ほどつづいたが、それきりうっちゃってしまい、いまは、そのあとが残っているばかり。」
「なるほど、それで開拓場と申すのか。そういえば京都の画家、富岡鉄斎も、大台が原に登っているのであろう。」
「さよう。鉄斎の描いた大台が原の絵はすばらしいできばえだ。」
「うむ、鉄斎は本職だからな。なかなか風格のある絵だ。でも、あなたの絵も大変よくできているではないか。」
「何の何の。私の絵は、しろうとの手すさび、お笑い草さ。
若い時に平戸の寺で、和尚さんに手ほどきをしてもらったきり、あとは見よう見まねの自己流で、まことにおはずかしい。」
「そうはいってもあなたの数かずの書物にさし入れられた絵、あのアイヌの風俗を描いたものなど、なかなか面白いあじわいがあるではないか。」
「私のはただ見たままを、画法にはこだわらずに描いているだけじゃ。
本職の画家で、好きだと思う人もあるにはあるが、自分で描くときは、いつでもその好きな人の絵とは一味ちがった、この松浦武四郎独自の絵になるよう工夫している。」
「それだ!」
毅堂は、さけぶなり、ポンとひざをたたいて、乗出してきました。
「それが大切なことだ。なにごともひとよりも一歩ぬきんでられるかそれがかなわぬかは、すべてそこにかかっている。
他人にはできない、自分独自のことをしようとこころがける。それが大事なところだ。
これは絵の世界ばかりではない。学問、商売、すべて同じことさ。
だが世間には、つまらない人間が大勢いて、誰かが右といえば右、左といえば左と、サルまねをするばかりで、自分というものがない。」
毅堂は、すっかり自分の演説によってしまったようです。
武四郎はほほえみながら、毅堂の話を聞いていましたが、そのうちに武四郎は煙草がすいたくなりました。
使いなれたなたまめぎせるを腰からぬきとり、火の用心と書いた袋から煙草をつまんで、きせるにつめようとしました。
そのとたん、「うーん。」といったきり、武四郎は片手を枕にしたようなかっこうで、倒れてしまいました。
脳溢血におそわれたのです。
それから六日後、二月十日に武四郎は永遠の眠りにつきました。
途中で少し意識を取戻したとき、家人が、何か食べたいものがないかと聞くと、
「できることなら、煎り豆を腹いっぱい食べたいが、それももうだめかなあ。」
と、つぶやいたそうです。
自分の生活はあくまでも質素にすごしてきた武四郎の姿がよくあらわれています。
自分で心にきめたことを、ひたすら一生の仕事として歩みつづけてきた武四郎でした。
それは自分自身へのいましめでもあり、また、こころざしある者と思えば、熱心に教えさとしてもきたことでした。
いまはなき歌人、佐佐木信綱が、九十一歳のとき、次のようなことを知人に語りました。
「私は、十五歳のとき父にともなわれて、松浦武四郎翁にあった。明治十五年の春だった。
その時、翁はおりから病の床についておられたが、私たちは枕もとにとおされた。
父とひとしきり話をなさってから、私にむかって、
“私は十六のときに伊勢を出て、日本国じゅうをまわり、北海道をあまねく探検した。
茨のなかや、雪の上にも寝たりして、一生を北海道に捧げたといってもよい。
人間は、ひとつのことに一生を捧げるべきものだ。
おまえは一生を歌に捧げるつもりで勉強しないといかんぞ。
今日のこの言葉、よく覚えておくように”
といわれた。」
いま武四郎のたましいは大台が原にやどりながら、愛してやまなかった北海道のめざましい発展を、じっと見守っていることでしょう。
top
****************************************
|