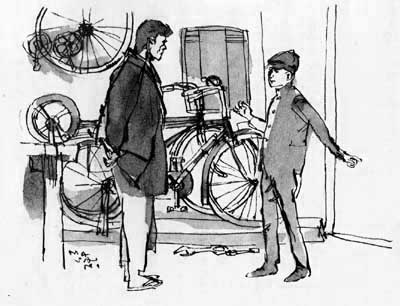|
****************************************
Index 1
2 3
4 5
6 7
2 商売を身につける少年
1 おいたち top
現代の電気王、松下幸之助は、少年時代は不遇でした。
この物語は、幸之助の一家をおそった不幸なできごとからはじまります。
松下幸之助は日清戦争が起った年の明治二十七年十一月二十七日、和歌山市の東の方の紀の川に近い小さな村に生まれました。
和歌山県海草郡和佐(わさ)村千旦の木(せんだんのき)というところです。
幸之助が生まれた屋敷あとには現在、「松下幸之助生誕の地」という記念碑がたっています。
この記念碑の文字は、同じ和歌山県生まれの湯川秀樹博士が書いたものです。
幸之助の家は、先祖からうけついだ屋敷がある地主でしたから、生活は楽な方でした。
お父さんの松下正楠は、村会議員になったり、村役場に勤めたりした人で、村の名士の一人でした。
幸之助は兄弟の中で末っ子でしたから、父や母には一番かわいがられ、なに一つ不自由なく育てられましたが、お父さんが米相場というものに失敗し、大きな損をしたことから、幸之助の運命が変わってしまう事になったのです。
その頃明治二十三年は、日清戦争も終わって、日本は工業がさかんになりはじめた頃です。
そして、たくさんの商品(米、生糸など)を売り買いする取引所が各地にできていました。
その頃お米の売り買いは、米穀取引所で行なわれていましたが、お米はその年の天候の具合によって、豊作になったり、不作になったりします。
豊作の年は、お米の値段が下がり、不作のときは値段が上がります。
この値段の上がり下がりを予想して、もうけをかせぐのを「投機」といいますが、お米の値段が上がると思って、たくさんのお米を買ったのが、下がったりすると、損をする事になります。
幸之助のお父さんは、予想がはずれて、大きな損をしてしまったのです。 |

幸之助の生まれ故郷――父は郷土の裕福な名士であったが
商品相場の投機に失敗し、幸之助は幼少の身でデッチ奉公に出された

同郷のノーベル賞を受賞した湯川秀樹博士の書いた記念碑
|
損をしたお金を払うために、先祖からうけついだ田畑や家を売らなければならない事になってしまったのです。
このとき、幸之助は四才でした。
一家は住みなれた家をはなれて、和歌山市内に引っ越し、下駄や草履(ぞうり)を売るはき物の商売を始めました。
しかし、なれない商売のことなので、うまくいかず、二年後には、店をやめてしまいました。
悪い事には、悪い事が重なるもので、幸之助の一家には、さらに不幸なできごとがつづきました。
その頃流行した悪いかぜのために、二人の兄さんと一番上の姉さんが死んでしまったのです。
生活の苦しさのうえに、三人の兄弟を失うというおそろしく不幸なできごとは、幸之助の幼い心を深く悲しませ、いつまでも忘れられないできごとでした。
こうしたなかで、幸之助は、明治三十四年四月和歌山市内の雄(おの)小学校に入学する事になりました。
商売に失敗したお父さんは、和歌山では仕事も収入の道もなく、職をさがして大阪へ出ました。
そこで盲亜学校に勤めました。
しかし、家族全員が大阪に移って、お父さんと一緒に暮らす事はできなかったのです。
幸之助らは、お父さんから送ってくるお金で細々と暮らしていました。
2 小学校四年で奉公に出る top
幸之助は、家の生活が苦しかったために、でっち奉公として、働きに出る事になりました。
幸之助が小学校の四年生になった年の秋、大阪のお父さんから一通の手紙がとどきました。
お母さんのとく枝が読みますと、
「大阪の八幡筋にある宮田という火鉢屋で小僧をさがしている。でっちとして住みこませたいから、幸之助を大阪によこすように……」という事が書かれてありました。
今日では中学校を出なければ、働きに出る事はできませんが、明治の時代には十一、二才で、でっち奉公に出る事は、それぼどめずらしい事ではありませんでした。
でっち奉公は、商店や職人の家に入って主人のお供、子守り、拭き掃除など、何でもしなければなりません。
でっち入りしてから二、三年だつと商売の走り使いをします。
でっちから、手代、番頭へと出世していくのですが、番頭になるには十数年もかかります。
それから何年も番頭をつとめて、“のれんわけ”といって、主人から屋号(店の名主え)をもらって、独立の商人にしてもらう事もありました。
小学校を途中でやめる事は、幸之助には大変心残りでした。
それに学校友だち、近所の遊び友だちと、もう楽しく遊べなくなり、それにもまして、お母さんの元をはなれて大阪まで行くのです。こんなつらい事はありません。
それでも、子供心にも毎日の生活の苦しさ、家族を残して一人で苦労しているお父さんの事を考えると、悲しんでばかりはおれない事がわかりました。
「大阪ってどんなところかなあ? 大阪にいるお父さんはどうしてるのかしら。」と考え、
「でっち奉公って、つらいんだろうなあ。
でも大阪の町って、商売でにぎあう大きな町だというし、それに大阪にはお父さんもいるんだ。」
と思うと、それほど嫌とは思いませんでした。
大阪の町は商業の中心都市としてさかえていて、地方から商人が集まってきていました。
したがって、幸之助が大阪にでっち奉公に行く事は、大阪商人の根性を身につける事になるのです。
でっち入りの話はすぐまとまって、十一月の終わり頃、大阪へたつ事になりました。
大阪へたつ日、お母さんが体の弱い、まだ子供の幸之助の大阪への一人旅を心配して、紀の川(南海線)の駅まで見送ってくれました。
駅までの道々、お母さんは幸之助に、行く先々の事をこまごまと、繰返し繰返し注意をしました。
「体に気をつけ、ご主人や、番頭さんや、みんなのいう事をよく聞いて、みんなからかわいがられるようにするんだよ。
どんなに苦しくてもつらくても、それが修業だと思ってじっと我慢をするんだよ。」
お母さんは、小さなわが子がこれからどんな苦労するかと思い、それにたえられるだろうかと考えると、繰返し繰返し言い聞かせないではおれなかったのです。
幸之助は、そんな母親の言葉を、先々の不安をおしかくして聞きいっていました。
二人が紀の川駅につき、幸之助が汽車に乗りこむと、大阪までいくという乗客に、
「まだ何も知らない子供です。大阪までいくのですが、途中よろしくおねがいいたします。」 |

紀ノ川駅までお母さんに見送られる幸之助
|
と、幸之助を一人で大阪へやる事が、不安でたまらず、何度も何度もたのみました。
幸之助は、もうすぐお母さんと別れ、これからは他人と一緒に暮らすのだと思うと淋しさで胸がいっぱいになりました。
長い汽笛をあとに残して、汽車が静かに動きだしました。
お母さんとの別れの言葉も、騒音に消され、小走りにあとを追うお母さんの姿もズンズン小さくなっていきました。
そして、その姿が見えなくなっても、窓から身をのりだしてお母さんを見つづけました。
汽車の窓から移り変わる沿線の風景をぼんやりながめながら、大阪でのこれからの事を考えていました。
淋しさと不安な気持ちをおさえる事で、となりの乗客の言葉もうわのそらでした。
大阪の難波の駅につくと、お父さんが出迎えてくれていました。
お父さんから、宮田火鉢店の話をこまごま聞くと、幸之助は肉身との別離の悲しさなどにひたっておれないと思いました。
宮田火鉢店の住見込みの小僧になった幸之助の仕事は、火鉢をみがく事でした。
初めは紙やすりでみがき、そのあとはトクサというかわいた草でみがきあげるのです。
上等の火鉢となると、一日中みがいて、やっと一つができあがるのです。
紙やすりやトクサをにぎる幸之助の手は、すりむけて、血がいつもにじんでいました。
それでも、朝晩の拭き掃除を休む事ができません。
水にぬれた手の傷がしみて、激しく痛む事もしばしばでしたが、そんな時でも、ただ顔をしかめてじっと我慢して働きつづけました。
一日の激しい仕事が終わって、一人寝床に入ると、思い出すのはお母さんの事でした。
昼の仕事がきびしければ厳しいほど、昼忘れていたお母さんの顔をありありと思いうかぺて、目に涙がにじむ事がしばしばありました。幸之助は少年時代、少々内気だったのでしょう。
その頃の商店や工場に働く人々にとって、毎月の一日と十五日は大変うれしい日でした。
給料をもらえる日でしたし、住込みの店員にごちそうをする商店もありました。
十二月十五日、幸之助は主人によぼれました。
「これがおまえの給料や、といって、主人は五銭の白銅貨を新しい小僧の幸之助にわたしました。
幸之助が和歌山のお母さんのもとにいたときは、あめ玉を買うぐらいのお金しかもらった事がなかったのですから、その頃の五銭は今のお金にすると五百円くらいにあたりますが、幸之助にとっては、初めて手にした大金だったのです。
手がすりむけるほど火鉢をみがいたり、掃除、子守りなど、つらい思いをしてえたわずかなお金ですが、幸之助は自分で働いてかせいだお金だと思うと、うれしさとほこりを感じて胸がいっぱいになるのでした。
宮田火鉢店でのでっちづとめは、三ヵ月ほどで終わりました。火鉢店の主人が転業する事になったからです。
宮田の主人は幸之助を、船場淡路町の自転車販売店の住見込み店員に世話しました。
自転車店の主人は五代音吉という人でした。
その頃の自転車は、イギリスやアメリカから輸入されていた高級な乗物で、東京の市電が四銭の時に、一台が百円もしたのですから、いまの高級乗用車なみの値段です。
自転車は金持ちの息子とか商店の主人が道楽で乗るくらいで、自転車を買えない人々は、時間いくらで借りて乗り心地を楽しんでいました。
その頃、こんな歌がありました。
チリリン チリリンと出てくるは
自転車乗りの時間借り
曲乗り上手となまいきに
両手はなしたシャレ男
あっちへ行っちやあぶないよ
こっちへ行っちやあぶないよ
ああ、あぶないといってる間に
それおっこちた |
自転車乗りがシャレ男だったその頃の様子がよくでている歌です。
自転車店の住込みの小僧になった幸之助の仕事は、朝、晩の掃除のほかは火鉢屋にいた頃とはずいぶん変わりました。 |

火鉢店の奉公は三か月で、直ぐに自転車店の
デッチ奉公になった。自転車店の五代夫人と幸之助
|
朝五時から起きて顔をあらうと、すぐ表戸をあけ、かど口を掃除して水をまきます。
それから一時間ほどかかって店内のふき掃除をすませてから、朝食になります。
朝食のおかずは、おこうこ(漬物)だけで、みそ汁もついていません。
食事がすむと、すぐ店に出て、自転車の修繕やチューブのはりかえなどの仕事にとりかかります。
手を休める暇もない一日になるのです。
夕食がすんでホッとするのば、夜の八時頃ですが、九時半か十時頃までは店は開いていました。
それまでは、店の番をしながらお客のこないときは、その頃の少年がよく読んでいた講談本を読みふけるのでした。
講談本はだれでも読めるように、ふりがながついていましたから、小学校の四年までしか行っていない幸之助にも、楽しく読む事ができました。
豊臣秀吉の一生を書いた太閣記、忍術の名人猿飛佐助の話、里見八犬伝などでした。
そこには、昔の人々の知恵の働かせ方や勇気、人情がえがかれていましたので、幸之助は知らず知らずのうちに、いろいろな事を勉強していったのです。
自転車の修理で機械を扱う仕事には、だんだん興味を覚えてきましたが、旋盤(工作機械)を手で回す仕事は一番つらい思いをしました。
先輩の職人たちは、幸之助が手で回す旋盤で仕事をするのですが、はじめの十分や二十分間は、勢いよく回すのですが、疲れてくるとつい回転がにぶってしまいます。
すると、先輩たちは、「もっと、しっかり回せ。」と、幸之助の頭をゴツンとやるのでした。
その頃のでっちや小僧たちは、先輩からそのように手荒く仕込まれたのです。
職人としての技術は理論で身につけるのでなく、体で覚えるのだと、その頃は考えられていたので、鋼鉄をきたえるように、なぐられて、厳しくきたえられたのです。
3 幸之助の学校 top
その頃の商店の主人は、小僧や少年店員を、手荒な方法で厳しくきたえたうえ、礼儀作法についても厳しくしつけました。
一通りの礼儀も知らない店員がいる事は、店の信用にかかわることだったのです。
あの店の小僧さんは礼儀が正しくて感じがよい――そういう評判は店の信用を高め、それが商売の繁盛するもとにもなったのです。
お得意さんや主人の知人のところへ使いに行く時には、もののいい方、挨拶のしかたまで細々と教えられました。
ただ、職人・商売人としての技能を身につけるだけでなく、伝統的にうけつがれていたその家の家風を守る事を厳しくしつけられたのです。
そうする事によって、一人前の社会人となっていったのです。
(先方に行ったら、最初はお天気の挨拶をする。それから用事をこういうふうに言うといって教えてくれた。
忘れるといけないから、それを復習していく。そういうしつけを十二才の時からやらされた。
私は学校の教育はうけなかったが、こういうしつけで社会人として訓練された。)
松下幸之助は、このように当時の事を振り返ってのべています。
五代自転車店には、番頭のほかに四、五人の小僧が働いていましたが、幸之助が一番年下でした。
主人は、小柄で利口な幸之助を自分の子供のようにかわいがっていましたが、しつけや仕事に厳しい人でしたから仕事をなまけるような事があると、幸之助のぽっぺたに主人の手のひらがとぶのです。
そのような日々の厳しい修業にたえる事によって、幸之助は日一日と社会人として育っていったのです。
幸之助が五代自転車店に住みこんでから三年ほどたったときの事です。
幸之助も得意先をまわる事も多くなり、商売というものがどういうものか、おぼろげながらわかるようになっていました。
「自分も一度、自転車を売ってみたい。」と、ひそかに考えていたのですが、一台が百円もするものですから、自分で売るという機会は中々ありませんでした。
ある日、番頭が用事で外出して、幸之助ら小僧だけで店番をしていたときでした。
「自転車を見たいから、すぐ持ってくるように。」という電話がありました。
主人は幸之助をよんで、自転車を注文先へとどけるようにいいつけました。日頃、願っていた、自分で売るという機会がおとずれたわけです。
先方に行った幸之助は、自転車についてできるだけくわしく説明し、買うようにすすめました。
すると問屋の主人は、かわいらしい小僧の熱心な商売ぶりに心を動かされたのでしょう。
「よし、買ってあげよう。だけど、一割まけなさい。」というのでした。
何とかして初めての商売を成功させたいと思っていましたし、「一割もまけたのではとても商売になりません。」といえば、買うのを断られそうだったので、そうはいえませんでした。
「店に帰って、主人にそういいます。」といってその値段で半ば引受けたような調子でぜひ一台買ってくれるように頼んで急いで店に帰り、その事を主人に伝えました。 |
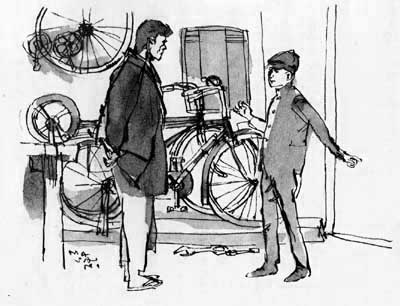
初めて自転車を売ったが、値引きが大きすぎたので
主人に注意される幸之助
自転車店には六年間、奉公した
|
ところが、「よく、売ってきた。」といわれると思ったのに、主人からは厳しい答えが返ってきました。
「幸吉、一割もまけてどうするのか。五分だけはまけますと、もう一度いってきなさい。」といいつけるのでした。
幸之助はその時、幸吉とよばれていました。
たとえ一割引きでも、商売ができたのだと心のなかでうれしく思っていたのですが、主人のこの言葉を聞いて、うれしさもふっとんでしまいました。
幸之助には、もう一度ひき返して、五分引きで売りますという勇気がありません。
何とか一割引きで売ってくれるように主人にたのみ、最後は泣きだすしまつでした。
これには主人もあきれて、
「幸吉、おまえは売る方の店員か、買う方の店員か、しつかりしなさい。」といいます。
こんな事で、注文主への返事がおくれていたところ、先方の番頭がやってきて、
「どうなっているのですか、値引きができないのですか。」とききました。
主人が事情をくわしく話しますと、番頭は帰っていきましたが、まもなく、五分の値引きでよいから買おう、という返事がありました。
使いの番頭から、主人と幸之助のあいだのやりとりをきいた注文主は、
「中々おもしろい小僧さんだ。今後も自転車を買う事があったら、あの小僧さんの店で買ってやろう。」といいました。
幸之助は初めての商売に成功しただけでなく、得意先を一軒ふやしたのです。
幸之助の主人五代音吉という人は、自転車の小売店から問屋や売店に品物を売る店にまで商売を拡げていった人でした。
品物の値引きについては、中々うるさい人でしたが、お客を大変大切にする人でした。
そして、いったん売った品物には、どこまでも責任をもち、お客に迷惑のかからないように心がける人でした。
それほど、店の商品に自信をもち、店の信用を大切にしたのです。
でっち奉公の小僧たちは、主人の商売の心得ややり方を働きながら身につけて、一人前の商人になっていったのです。
ですから小僧たちにとっては、店は学校でもあったわけです。
松下幸之助は、でっち時代の事を振り返って、「船場学校に学ぶ」という題でその頃の思い出を書いていますが、次の文章は、そのなかの一部です。
(船場の店に入って少年時代をすごしたのですから、行きたい学校には行けなかったけれども、その七年間をつうじて、学校ではえられない、非常に大きな教育をうけたように思います。
それは、商人としてもとになる知識や態度であり、もとになる商売のコツを覚える事です。
私が十三才のとき、今でいえば中学二年生の頃です。私一人で自転車を一台売りこんだ事があります。
これは現在では、自動車を一台売込むのと同じぐらいの仕事ではないかと思います。
しかし、あなた(読者)に私(松下幸之助)がいいたいのは、売ったその事ではありません。
それをとおして深く商売というものを学んだ事です。)
この文章から、松下幸之助が小僧時代に学んだ事をいまでも大切にし、それが世界の松下の第一歩になった事がわかると思います。
幸之助が自転車の修繕などで働いているとき、店にきたお客に、
「すまんが、煙草を買ってきてくれ。」とだのまれる事がよくありました。
そのたびに、幸之助は、油でよごれた手を洗ってから、煙草屋へかけださなければなりません。
そこで幸之助は考えたのです。
「自分の給料のうちから煙草を買っておいて、お客にたのまれたときその煙草を渡せばよい。
そうすれば、仕事ははかどるし、自分が煙草屋まで走る面倒ははぶけるのだ。」
こんな妙案はないと思って、煙草を買っておいて、お客にわたすようにしました。
その頃、二十個が一つになっているのを買うと、一つをただでくれるようになっていました。
煙草をたのむお客は、ひと月に五、六十人いましたから、五十個ぐらいは、幸吉の手から客にわたされました。
そのうちには、煙草屋からただでくれた分も入っていましたから、一個十銭として、ひと月に二十銭ほどが幸之助のもうけとなりました。
顔見知りのお客が、
「幸吉どん、煙草を買ってきてくれ。」というと、
「はい。」とすぐにさし出すので、驚いて、
「おまえは煙草をすわないのにどうして持っているのだ。」とききます。幸吉がそのわけを話しますと、
「それはうまい事を考えついたものだ。」とお客は感心するのでした。
半年ほどたつと、仲間の小僧たちのあいだから、
「あいつは、煙草で金もうけをしている。」という蔭口が出るようになりました。
幸之助は、もちろん、お客へのサービスと時間の無駄をはぶくためにしたので、金もうけを目当てに考えついたのではなかったのです。
しかし、店の小僧たちの不平を耳にした主人は、これをだまって見すごす事はできません。
店を統率していく主人にとって、店の者から出る不平、不満はほっておけなかったのです。
主人は幸之助をよんで、
「おまえのやっている事は悪い事ではないが、みんなが心よく思っていないから、止めてくれ。」
といいました。
そのようにいわれてみると仲間たちの事を忘れていた自分に気づき、主人の気持ちもよくわかって、さっそく止めました。
学校とか会社などの団体生活をするところでは、自分ではよいと思ってした事でも、それが全体にとって悪い結果になり、団体生活をするのにマイナスになる事があります。
人の上にたって人を使っていく場合、その事を考えて判断しなければならないのですが、この事をすでにその時から幸之助は学んだのです。
幸之助が五代商店に住みこんでから、五年ほどたったときの事です。
幸之助は古参の店員になっていましたが、店員の一人が店の商品をごまかして売り、その金をこずかいに使っている事が、ふとしたことから主人にわかりました。
店には七、八人の店員が働いていたので、この事はすぐみんなに知れわたりました。
主人がこの悪い事をした店員をどうするか、みんなが注目していました。
この店員はよく気がきく、働き者でしたから、主人は彼を手ばなしたくなかったでしょうし、一度だけだから許してやろうという気持ちだったのでしょう。いましめるだけで、そのまま働かせようとしました。
幸之助には、この主人のなまぬるい方法が納得できなかったのです。
「私は、悪い事をした人と一緒に働きたくありません。あの男を店においておかれるのなら、僕が辞めます。」
と店の主人に抗議しました。
主人の顔にはアリアリと、「困ったな。」という表情が見え、「あまりに厳しい考え方ではないか。」といって、幸之助をなだめたのですが、ついには幸之助の主張をいれて、その男を辞めさせてしまいました。
幸之助がいちずに不正を憎んだのは、他人への思いやりに欠けていたかもしれませんが、周りの事情などを気にせずに、良い事と悪い事のけじめをはっきりつけたところは、幸之助の純粋な気持ちがあったからでしょう。
|

明治四十三年、幸之助には忘れられない、電気との結び付きができた年となった。
街には路面電車が走り、家庭には電灯が灯る電気の時代が、日本で始ったのである。
|
4 電気の仕事に関係する top
幸之助は、明治三十八年から四十三年の六年間、五代商店に働きましたが、その間つらい事、苦しい事があるたびに思い出しだのは死んだ父、正楠(まさくす)の言葉でした。
父、正楠は三十九年の秋、ふとした病気から急にこの世の人ではなくなったのです。
米相場で財産を失った父が、家をたでなおすために、身を粉(こな)にして働いていた姿を思いうかべて、幸之助は一生けんめい働きました。今度は、幸之助白身が松下家をたてなおさなければならないと自分を励ましたのです。
幸之助がでっち奉公に出てからまもないころの事です。
母のとく枝が、小学校にもゆけず、大阪ででっち奉公している幸之助をかわいそうに思い、
「幸之助を貯金局の給仕にして、夜学で勉強させては。」と父にすすめた事がありました。
「奉公を続けて、商売で身をたてなさい。」と、父は、幸之助にいいました。
その頃の人々は、立派な商人や職人になるには、小さい時から、でっち奉公をして苦労するのが一番だと思っていたのです。
そのうえ若いときの苦労は、かならずむくいられると考えていました。
幸之助の父も同じような考えで、学校へ行くより一日も早く商売を覚えた方が、立派な商人になれると考えていました。
幸之助は父の言葉にしたがって、一日も早く一人前の商売人になりたいと思っていました。
彼は五代商店にはいったその日、高価な自転車を店の裏へ持ち出して、
「自転車屋の小僧なら、自転車に乗れなけりや。」と、ガチャン、ガチャン、自転車をたおしながら乗る練習をして、番頭さんにしかられた事もありました。
また、それから二、三年して、新車宣伝のため自転車レースがひらかれると、五代商店のためにと毎朝四時半から起きて練習をし、レースに勝って五代商店の名を高めました。
52
そして、堺のレースでは左肩甲骨(けんこうこつ)をおって、気を失ってしまった事もありました。
このように、幸之助は人より進んで物事をするように、いつも努力をおしまなかったのです。
明治四十三年、この年は松下幸之助にとって生涯忘れる事ができない年なのです。
それは、幸之助の一生の事業となった電気との結びつきができた年だからです。
明治三十七、八年の日露戦争に勝った日本は、東洋の日本から、世界に注目される日本になりました。
世界の各国とのつきあいが多くなり、外国の工業の技術がドンドン日本へ入ってきました。
電気機械の製造技術や電球の製造技術などは、外国から入ってきましたが、電力だけは日本でつくりださなければなりませんでした。
川の多い日本では、火力発電にくわえて、水力発電がさかんになりました。
電力が多くうみだされるようになると、日本の国民の生活は激しく変わる事になりました。
工場の機械は電気で動かすようになり、乗り合い馬車にかわって、電車が都会のおもな交通機関となりました。
家庭では、ローソク、ガス灯、石油ランプにかわって、電灯が夜の灯りになりました。
幸之助が働いていた自転車店は、自転車が便利な乗物として、急にいきわたりだしたので、店の仕事もいそがしくなっていきました。
幸之助は、ふと、こんな事を考えました。
「たくさんの人を乗せて走る電車がふえていくと、自転車は売れなくなるのではないだろうか。」
幸之助には、電気の事業の方が、将来、有望だと考えたのです。
一人で考えても、解決がつきそうもないので、幸之助は大阪市内に住んでいる姉さん夫婦をたずねて、電気に関係のある仕事をしたい事をうちあけました。
姉さんの婿さんは、知りあいがいる大阪電灯会社へ幸之助を世話しようと約束したのです。
しかし、幸之助には困った事があります。
何といって、五代商店を辞めたらよいかという事です。
幸之助は五代商店の主人に大変世話になっていましたし、主人や仕事に不満があって辞めたいと思うのではありません。
自分の行動が、身勝手な事のように思えるのでした。
幸之助の心のなかの悩みは、知らずに、そぷりや顔色にあらわれます。それに気づいた主人は、
「幸吉、この四、五日は落着きがないが、何か心配事でもあるのではないか。店を辞めたいと思っているのなら、正直にいいなさい。」
人を使っている主人の目には、十五才の少年の心にある悩みが何であるかを見ぬいていたのです。
そこまでいわれても幸之助は、「はい、じつは……」と正直にいえなかったのは、主人への申し訳ない気持ちを強く感じていたからです。
おいつめられた幸之助がとる手段として考えたのは、何もいわずに店をとびだす事でした。
ついに心をきめた幸之助は、心のなかで何度も「すみません。……」と繰返して、六年間働いた店を無断でとびだしてしまいました。
姉さん夫婦の家へ一時身をよせた幸之助は、すぐに五代の主人へ手紙を出して、無断で店をとびだした事を深くわびるとともに、「暇をもらいたい。辞めさせてもらいたい。」という事を伝えました。
その後、電灯会社で働くようになってからも、幸之助は、五代商店をなつかしく思い、時々おとずれては、仕事の手伝いをする事がありました。
五代の主人は、幸之助の顔を見るたびに、店に帰るようにすすめましたが、それが幸之助にとって、かえって気詰りだったのでしょう、五代商店からだんだん足が遠のいていきました。
五代商店をやめた事で、幸之助のでっち生活は終わりましたが、ここでの六年間は、幸之助の人生にとって貴重な事をたくさん学びました。
松下幸之助は、七年間の小僧時代を振り返って、こんな感想をのべています。
これは、彼がたくさん学んだ事のなかでの一つについてのべたものです。
(小僧時代に学んだありがたさはたくさんありますが、私(松下幸之助)の一生にとって大事だと思われるものは、物の値打というものが、ぼんやりとわかるような気がしてきたという事です。
紙一枚にしても、それを深く考えない人は、むぞうさに捨ててかえりみません。
しかし、たとえ紙一枚にしても、その裏にひそむその物の値打をじっくり考えるならば、中々平気で捨ててしまう事はできません。
“米一粒の恩”という事も、それと同じ事であるが、これを百万遍唱えてみたところで、それだけで米一粒の値打がわかるものではありません。
それが私には、どうやらわかるような気がしたのです。
それというのも、あの七年間の奉公時代があったからだと思うのです。
砂糖は甘く塩は辛い、それは誰でも知っています。
しかしそれは議論したり、考えたりしてわかるものではありません。
その甘さ、その辛さを知るには、まず、一口なめてみる事です。体験の貴さは、ここにあります。)
松下幸之助は、小僧時代の苦しい体験をとおして、物の値打を知るようになった事をのべているのです。
5 運の強い青年 top
五代商店を辞めてから、幸之助はほんのしばらくのつもりで、姉さん夫婦の家に身を上せたのでしたが、電灯会社の都合で、採用が伸びてしまいました。
「欠員ができるまでしばらく待ってほしい。」という事でした。
幸之助は就職できる日が、一ヵ月先か二ヵ月先かわからないまま、義兄の家にやっかいになっているのは心苦しい事でしたから、義兄の働いているセメント会社の臨時工として、一時働く事にしました。
セメント会社での仕事は、セメントをトロッコに積んで運ぶ事でした。
筋骨たくましい男たちにまじって、小柄で力仕事になれない十五才の幸之助が働くのですから、一人前に仕事をするのはつらい事でした。
幸之助の働きぶりを見かねた現場監督は、
「君は、こんなところでは働けるような体ではない。ほかの仕事にまわしてもらったらどうだ。」
と親切にいってくれました。
まもなく、幸之助は、セメントの分量をはかる機械の前に立って仕事をする計量係にまわされました。
この仕事は、トロッコをおす仕事にくらべると楽な仕事でしたが、機械のところで上げおろしされるセメントは、モウモウと煙のように舞い上がり、幸之助の体をつつんでしまうほどです。
一時間もすると幸之助の口の中はジャリジャリになり、セメントを吸いこんだ喉はヒリヒリ痛みます。
この仕事には一日でまいってしまい、もとの運搬工にもどってしまいました。
初めはあんなにつらかった運搬工の仕事がなれるにしたがって、楽になるのを、幸之助は感じるようになりました。
どんな仕事でも毎日繰返しているうちに、コツを覚えて楽になるのです。
幸之助がセメント工場へ通っていたある日の事です。
工場は大阪湾に近い埋立地にあって、幸之助は、朝夕渡し船に乗って、通っていました。
夕方の帰りの船に乗って、船べりに腰をかけ、一日のつかれた体を休めていました。
汗にまみれた幸之助の体には潮風がいっそう涼しく感じられました。
その時船ばたを歩いていた船員が、幸之助のそばで足をふみはずしたのでしょうか、アッと声をあげて幸之助をかかえるようにして海へおちました。
幸之助が海面へうかび上がったときは、渡し船はかなり離れたところに見えました。
「救けてくれー!」幸之助は、夢中で泳ぎました。
まもなく船は引返して、二人を救い上げました。
このとき、幸之助には水泳の心得があり、季節があたたかい夏であったので、彼は救われたのです。
あやうく生命を落としそうになったような体験は、中々忘れるものではありませんが、このような体験は自分自身の運命について考える事になります。 |

幸之助は渡し船から落っこちたが、助かった。
これから自分は運の強い人間だと思うようになった。
|
松下幸之助は、このできごとを振り返って、次のようにのべています。
(ここで、ああ助かったと思っただけならば、それだけの話です。
こんな目にあっても助かる自分は、非常に運が強いのだと思った事です。
これほど運が強ければ、中々死なないぞと思いました。
だから、どんな困難にあっても切り抜けられるぞ、と何となく考えました。)
松下幸之助は、このできごとから、「自分は運が強いのだ」という事を感じました。
この事は、いつの間にか彼の固い信念となって、これからの人生にぶつかっていくのです。
セメント工場のトロッコ押しの仕事は、三か月ほどで終わりました。
幸之助は、明治四十三年十月二十一日、あこがれの大阪電灯会社の内線工見習として採用されました。
このときの給料は、日給三十七銭でした。
top
****************************************
|