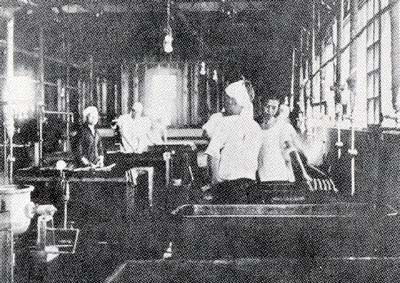|
****************************************
HOME 序章 一章 二章 三章 四章 五章 六章 付録
1 多摩の織物業 top
多摩の産業を振り返る時、織物の歩みが極めて重要な役割を果していたことがわかります。
現在でも、八王子、青梅(おうめ)、村山はその工場数や生産額は従来より著しく低下していますが、依然として地域のイメージとして織物の歴史が強く残っていることに気がつきます。
例えば八王子駅周辺の並木道は全国でも珍しい桑の木が植えられていますし、青梅や村山の織物会館などはその歴史を偲ばせます。
多摩の織物業は大正時代に一つの大きな発展を示しますが、もう少し時代を遡って振返り、そして現在の多摩の産業につながる意味にも触れていくことにしましょう。 |
 |
多摩の織物と産業革命
現在、関東周辺の織物 *
産地として知られているのは、結城(ゆうき)、足利、桐生(きりゅう)、佐野、伊勢崎、小川、所沢、飯能(はんのう)、秩父(ちちぶ)、青梅、村山、八王子、郡内などですが、それぞれの置かれた地理的、歴史的、社会的条件の違いにより、独特の内容を備えた織物産地を形づくり、相互に影響しあいながら全体として関東の織物地帯を形成していました。
* 織物=織物は大きく分けて染めてから織った先染織物と織りあげた布地に模様をつける後染織物がある。
絣(かすり)は糸をあらかじめ模様に合わせてくくって染めた絣糸を使う先染織物。
多摩を含む西関東の織物地帯をみると、西関東で中心的な役割を果した先染絹紋織物の八王子、西多摩地域の中心地として先染綿夜具地の青梅、先染絹緋織物の村山など、それぞれが置かれた条件の違いによって独特な織物産地を形成してきたのです。
しかも多摩全体でみれば八王子を中核とする織物地帯を構成し、相互に深く関連しあいながら長い歴史的な時間をずんできたのです。
ところで、すでに江戸時代に各織物産地の製品の違いをみることができますが、さらに明治末から大正時代にかけて進められた多摩織物産地の産業革命ともいうべき時代をくぐり抜けることによってはっきりとしたものになっていったのです。
そうした意味で、大正時代は多摩の織物業をみていく際に非常に重要な時期といえそうです。
多摩の織物業は関東山地に接する山麓一帯の農家の副業として歩んできました。
しかし明治後期から大正にかけて、特に八王子、青梅は動力織機化、工場組織化、電力を求めての市街地への集中という求心運動に巻きこまれていきます。
従来の山麓一帯に広く分散していた農家副業の織物地帯は、市街地に集中する織物都市に変っていったのです。
この点、例えば八王子について、次のように言われています(八王子市教育委員会編『八王子織物の百年』昭和四三年)。
明治末年に導入された力織機は、従来の手織機を急速に駆逐していった。
大正三年には力織機台数はわずか二九一台で、手織機は四四九三台と圧倒的な数を占めていたが、大正九年には、これが逆転して力織機台数四六八一台、手織機台数一五三九台と力織機の飛躍的成長を示した。
八王子織物は第一次大戦中に従来の家内工業的手工業から機械制工場工業の確立をみたのである。
(中略)従来農村にあった機業者は動力の得やすい八王子市中に集中し、織物生産地帯は農村から市中へと全く塗りかえられてしまった。
そして、八王子は西関東における最も生産力の豊かな織物産地として、当時の先端技術であるジャカード
*
を積極的に採入れ、紋織中心の先進的な織物産地を形成していきました。
そのことはその後の多摩および西関東織物地帯全体に重大な影響を与えることになったのです。
* ジャカード=紋織物製造に使用される経(たて)糸開口装置。フランス人ジャカールによって発明された。
ジャカード機は経糸に連絡した針を紋紙によって制御し、一本ごとの経糸を上下させ複雑な模様織りをする。
織物地帯の分化と新たな関係
この点、まず散在していた副業農家の有力なところが八王子市街地へ集中し、力織機化、工場組織化、高級紋織生産に踏みだし、そうした流れに乗切れなかった部分が独自に別の織物産地としてまとまりを見せはしめたことが注目されます。
つまり、多摩の織物地帯は明治から大正にかけての産業革命ともいうべき時期をくぐり抜けることにより、広く散在していた農家の副業織物地帯から織物都市八王子を形成し、さらに周辺の織物産地を分化させたということになります。
この時代以降、多摩の織物地帯はかっての関東山麓にベルト状に展開していた状況から、八王子、村山、山梨県郡内、青梅の四つの織物産地に分裂していくことになります。
それは圧倒的な生産力を形成した八王子に対して、周辺の地域はそれと競合しない範囲で独自な製品展開、産地形成を進めていったということを意味します。
現在、絹絣(きぬかすり)織物の「村山大島紬」で知られる村山は、従来は綿織物産地であった所沢の影響が強く、農家副業による綿絣(めんかすり)織物を生産していたのですが、大正年間に入り、村山貯水池の造成で所沢市場への交通路を断たれ、次第に八王子の影響下に組み込まれながら、当時、需要拡大が著しかった女物絹着尺の銘仙に活路を見出そうとしました。 |

村山大島紬(つむぎ)染色用絣(かすり)板製造(昭和20年頃)
|
その場合、力織機と工場生産によって生産力を高めていた八王子銘仙に対抗すべくもなく、農村手織機でも可能な特殊な板締絣(いたじめかすり)の技術を伊勢崎から導入し、新たに先染絹絣織物の「村山大島紬」として、八王子織物とは異なった製品分野で活路を見出していったのです。
現在でも、村山織物は家庭の婦人たちによる手織機を特色の一つにしていますが、それは大正時代以降、力織機と工場生産に展開した隣接する八王子産地と差別化して生残るための知恵であったといってよいでしょう。
青梅は先の村山とはかなり事情が異なります。
青梅自体、従来から八王子を中心とする先染絹織物地帯と所沢を中心とする先染綿織物地帯の交差点に位置し、絹綿交織に特色を示していたのですが、多摩における八王子の中心性には及ばないものの西多摩地域の政治経済の中心として、やはり大正年間に入ってから力織機化、工場組織化、生産者の市街地への集中という織物都市の形成を経験します。
ただし、生産力の豊かな織物都市化にあたって、八王子とは競合しない量産の先染綿の夜具地を生産していくことになりました。
この決して絹や広幅(ひろはば)ではなく、綿の小幅織物であったということは、おそらく次のような事情が横たわっていたのでしょう。
まず、零細生産者を主体にする織物都市化であったこと、もともと低付加価値の先染綿絨物を主力とすることから絹産地のような関連加工業者の成熟がみられなかったことなどが強く影響したと思われます。
例えば八王子の場合には関運加工業者として撚糸、張糸(糊付け)、糸染、紋意匠、紋編み、整理などの基本的な加工機能の専業者を大量に生み出しましたが、青梅の場合は糸染(哂し=さらし)以外に目立った専業者を生み出すこともなかったのでした。
こうした事情を背景に、西多摩地域で一定規模の生産力を備える織物都市を編成した青梅は、これ以後、先染綿夜具地という実用量産品こそ最も適切なものとして受け止めていくことになります。
また江戸時代に絹裏地の「甲斐絹」で知られた上野原から大月、富士吉田にいたる郡内地方は、農業生産力に乏しく、零細な農家副業による広大な織物地帯を編成していましたが、従来から八王子の後背地として位置づけられ、付加価値の低い絹裏地や、草深い太織、縞物などの生産地として歩まざるをえませんでした。
こうした性格は明治以降も継承され、先の多摩の産業革命の直接的な影響を受けることは少なかったのです。
むしろ明治から大正にかけての郡内地方は、散在しながら全体としては生産力に優れる農家副業のままで八王子を頂点とする多摩および西関東織物地帯の底辺を構成するものとして、高度な技術要請の少ない絹夜具地、絹裏地産地へと展開することになっていったのです。
このような中で、八王子が最も生産力の優れた、しかも紋織という高級織物に進んでいったことは、多摩織物産地の中での指導的立場をいっそう強め、生産技術的な面でも、流通構造上の位置でも際立ったものになり、あらゆる意味で中核性を強めていったのです。
例えば生産工程については先に指摘したように多様な専業者が成立し、また流通過程では関東の織物地帯に特有の買継商(産地の問屋的な商業資本)が八王子ばかりでなく周辺の産地をもカバーするものとして成熟するなど、八王子は多摩地域の経済活動の中心地として著しい繁栄を謳歌したのでした。
製品の展開については、八王子は江戸時代以来実に多様な織物を産出してきましたが、基本的な流れとしては男物着尺産地として歩んできました。
この点、大正時代は洋風化か著しく進んだ時期であり、男性の洋装化の中で男物着尺以外のところに産地発展の主導的なモメントを求めなければなりませんでした。 |
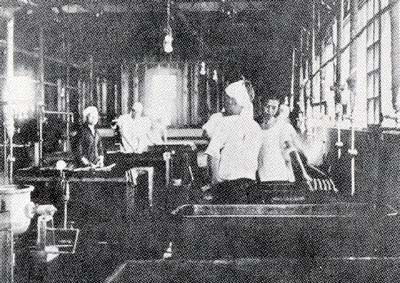
八王子絹織物工場染色場(昭和初期)
|
そして、こうした要請の中で、大正時代の八王子については幾多の努力が払われたことが語り継がれています。
例えば大正時代に大流行した女物実用着尺の銘仙目取り組み、北関東から解(ほぐ)し染枝術を導入し、全国の五大銘仙産地の一つといわれるまでに発展したこと、また女物高級着尺を創出するために伝統の紋織技術を多面的に駆使し、「多摩結城」の名で知られるお召織物を作りだしたこと、さらに袴地の技術を応用し、現在でも八王子の名産になっている織ネクタイ生地を開発したことなど、その後の八王子の織物産地としての発展を基礎づける主導的な製品が大正時代に形づくられたことに注目しておく必要がありそうです。
第二次大戦後、爆発的なブームを経験した八王子ウール着尺についても、多摩結城に結集し高められた紋織技術と、銘仙で確立された実用着尺の市場展開が交錯して実現されたものであることはいうまでもありません。
多摩の織物産地の大正時代
以上のように、産地別の特色、製品展開の方向の萌芽はすでに江戸後期にはみられたものの、関東山麓織物地帯の中でかなり同質的な内容を示していた多摩の織物産地は、明治末から大正時代にかけての産業革命の時代を経ることにより、その後の織物産地としての発展方向、製品展開を決定的なものにしていったのでした。
しかも、郡内を含む多摩の各織物産地のその後の生産構造、製品展開の方向をみる限り、八王子を中核とする全体としてバランスのとれた織物地域を編成していったことにも注目しておく必要がありそうです。
そして、各織物産地は自らの特異性を十分認識し、産地別の同業組合組織などに結集しながら、技術レベルの向上、相互の交流を深めていくことになったのです。
それは、同質的な織物地帯が産業革命を経ることによって分化し、産地間の差異を明確に意識させながら、反面、産地内の同質化をいっそう進めていく契機にもなっていったのでした。
紋織を基礎にしたお召、銘仙などの先染絹織物に展開した八王子、板締絣による手織りの大島紬に展開した村山、先染綿夜具地に展開した青梅、広範な零細農家副業による先染絹裏地、夜具地に展開した郡内など、その後の多摩の経済を象徴する各織物産地の発展方向は、この時期にほぼ確定されたものとみてよいでしょう。
実際、第二次大戦後の八王子の紋ウール着尺の爆発的なブーム、青梅のタオルケット、シーツへの転換など、多摩の戦後を彩るいくつかの局面は大正時代に基礎づけられた発展方向の延長上に位置するものであったのです。
2 デモクラシーと青年たち top
友愛会秋川分会の誕生
大正から昭和初めにかけて、時代は憲政擁護運動や普選運動、あるいは民本主義など、いわゆる「大正デモクラシー」が社会的思潮となりました。
しかし、農村地域にはそのままの形で入りこむことはできませんでした。
様々な媒介を通して、時間差も伴ってじわじわと浸透してきたともいえましょう。
この時期の多摩をこういう視点でながめてみると、いったい何がみえてくるでしょうか。
ひとつには社会運動があります。農民運動、水平運動、無産政党運動、労働運動、借家人組合運動、消費組合運動などの動きが際立ってみえてきます。
地域に即して一つひとつをみると「民主主義を発展させ定着させ、よりよき社会を概ざす試みが間断なく続けられた」ことが証明されます。
多摩の民衆運動はけっして輝きを失ってしまったわけではなく、「自由民権運動を造り出した創造的精神は枯れずにあった」ともいわれています(大串夏身編『三多摩社会運動史料集』昭和五六年)。
一つ例をあげてみましょう。
大正元年、鈴木文治らによって結成された友愛会は、共済・修養的な性格から次第に労働組合の性格を帯びて全国的組織となりましたが、五日市と八王子にはいち早く分会が設立されました。
大正四年、五日市にてきた秋川分会発会式に友愛会会長の鈴木が出席し、「労働者の覚醒と国家の隆興」と題して熱弁をふるいました。
また、鈴木はその時の印象を次のように語っています。
五日市の人々は、東京府下の人とは思はれない位に質朴で、しかも進取的気象に富んで居るのを見ます。
其の小学校は静粛に、其の旅館は飾り気なくして親切である。
(中略)この町の富豪土屋氏、馬場氏、松本氏、岸町長といふが如き方は、公共の事には率先して尽力せらるると云ふ事である。
(中略)此の小天地に、何かしら精神的な香ひ、澗ひのあるやうに思はるるのは、最も悦ばしき事と思ひます。 |
「進取的気象」といい、「公共の事には率先して尽力」といい、「何かしら精神的な香ひ、潤ひのある」というような印象を鈴木にもたせたのが、三〇年ほど前に自由民権運動の最大拠点だった西多摩郡五日市であることに、我々はすぐに気がつきます。
正会員四五名、婦人会員二〇名、賛助会員一〇名、計七五名の会員を擁する「友愛会秋川分会」は、八王子支部と共に『時代之青年』という機関誌を発行しました。
そこには初期大正デモクラシーの時代の影響を強くうけ、なおかつ自由民権の余風が残っている中で成長してきた地域の青年たちの姿をみることができます。
日本の労働組合運動の源流ともいえる友愛会と、五日市、八王子などの青年との接点にあるものが、多摩の社会運動の中にはいくつもみられます。
教員と青年が主役の文芸運動
もうひとつに、日露戦争前後から関東大震災、昭和初期の金融恐慌にかけて、多摩の農村青年や教員らを中心に盛上がった「地域文芸運動」とも呼ぶべき草の根文化運動があります。
この時期、多摩では小作人たちが小作料値下げを求めて地主と対決し、小作争議が各地で頻発しておこりました。
また、独自の青年団活動か活発に行われたところもありましたが、ここでとりあげる地域文芸運動はそれらとはまた別の担い手が主役となって活動した新しい運動です。
教員と地域青年はどっぷり地域社会につからずに割合さめた目で地域をながめ、様々な場面で旧態依然たる社会に出会い、それとぶつかり対立し、その結果、不満や不平を自らの心の中に内向させてきました。
自己覚醒した青年や教師には、それは苦しい選択でした。
そうした中から拙(つた)ないながらも自分の肉声で、自分の言葉で伝える動きがでてきたのです。
この時期に多摩の各地に続々と生れた文学、文芸作品がそれで、表現は詩、短歌、俳句、文芸など様々です。
また、美術、音楽、演劇、教育文化、児童文化など、表現は異なりますが、ペンを絵筆や楽器にかえ肉体を通しての表現も新しい動きが次々とでてきました。
それはまさに地域文化の洪水ともいえるほどの噴出ぶりでした。
八王子の大正デモクラシー文化
特に南多摩郡の八王子や町田などは、多様な地域文化が開花し結実しました。
文学や絵画からはじまり、その後児童文化、郷土史研究、音楽、社会問題研究、生活改善運動というような広まり方を示しました。
また、明治三〇年代後半から東京の文芸雑誌に積極的に投稿し始めたことが、八王子の近代短歌の先駆けとなり、大正期もその流れの中にありました。
そして「大正デモクラシーの高揚する時代世相の中で、八王子の文芸活動もその機運にのり、自分たちで編集し発行する同人誌を作る動きが、さらに盛んになってきた」といわれています(丹野美子『八王子の近代短歌と歌大たち』昭和六一年)。
まず大正二年、鈴木信太郎や若林牧春らによってグループ誌『蘭奢待』(らんじゃたい)が発行され、哲学、文学、美術などが語られ創作されました。
翌三年になると一三歳の早熟少年三人(大熊長次郎、大石亮三、小林登吉)が文芸グループを結成し、毛筆書き会誌『少年文林府』を発行しました。
「少年ほつぽみ也、青年は花にして老年は枯れ葉ならんか。
(中略)少年たる者、一寸の光陰も不可軽」と書いています。
少年たちは成長するにつれ、『青いぺージ』、『寂光』、『素焼』、『人間派』。
『燎原』と改題を重ねながら、回覧の短歌雑誌や文芸雑誌を発行し続けました。
こうした自己表現を積み重ねて精神的かつ思想的成長を遂げていったといえるでしょう。
『人間派』に結集した一〇代から二〇代の青年たちは、大正九年七月、桑都公会堂に一〇〇名を越える参加者を集め「思想問題講演会」を開きました。 |

『蘭奢待』(らんじゃたい)
|
その演題には「一労働者の世界観」、「マルクスの堕落」、「智の自縛と機械の圧迫」、「虐殺と国民性」、「傍観者の悲哀」などがならんでいます。
それらは、文芸創作活動の枠を越え、社会に目を向け始めた青年たちの姿を伝えるものです。
この時代をおおった大正デモクラシーは、このように地域の青年たちの純粋な心をも強くとらえたのです。
そして行動はさらにエスカレートし、武者小路実篤ら貴族たちの「新しい村」づくりに対抗して、騒音の中にこそユートピアを求めようとまず故郷を脱出し、東京小石川に共同生活兼印刷工場の拠点をつくります。
「俺達は庶民、しかも無名無資産の労働者だ。それだけ俺達の成功は困難であらう。苦痛が多いであらう」といいながら“理想郷”を目指して新しい生活に挑戦します(大熊長次郎「騒音の中のユートピア」『人間派』大正九年三月)。
この共同体は間もなく挫折してしまいますが、旧態依然たる村社会にじっとしていない新しいタイプの青年が続々と育ってきたとみることができます。
町田の文学学校と田園文化運動
同じ頃忠生村(現町田市)図師では、小学校の教員たちが文芸グループ「葭(よし)の笛社」を結成し、ガリ版刷りの同名の雑誌を創刊しました。
「新しい文芸に生き様としているものの集り」で、若い文学教員が「赤裸々な自分」や「心の叫び」を表現する場でした。
「絶えず動いていたい。動揺の波は、自分に進歩を与へるものである」と、弛緩(しかん)を脱却して、緊張と動揺の中で進歩していこうとしている真摯な青年教師の姿がうかんできます(小島うしほ「真実を求むる心より」同誌)。
そこには、「自分の心にふれたまま」を表現することで、古いしがらみや、伝統的社会的慣習から自分自身をとき放ちたいという強い意志を感じとることができます。
同人たちの巣まる「分校は、あたかも文学学校の観を呈し、寄り合うごとに作歌に、短歌づくりに、散文に、文学雑談し、夜を徹した有様であった」と、同人の一人若林昇は語っています。
この「葭の笛社」に同人として参加していたメンバーを中心に隣村の小山田(現町田市)で、『雜草みのる丘』や『紅潮』(こうちょう)が創刊されるのは、犬正一〇年のことです。
紅潮社は「単調な勤労生活を詩歌化して、特異な田園芸術を生長させる」ことを目的とし、活動は農閑期に「文芸に関する活動、映写並び講演会」を開くことでした。
主役は社会矛盾に目醒めた農村青年たちです。同人の一人の高森有吉は、早稲田大学で安部磯雄から農村問題を学び、労働運動家の中西伊之助からも強い影響をうけていました。
「青年達よ、貴男等はもっと高い処へ眼をおつけなさい。
(中略)どうぞ社会の地平線上に立って下さい。
(中略)速やかにお目醒め下さい。一刻も早くお目醒め下さい」と叫ぶのもまた同人です(薄井薫「豊かなる微笑み」)。
「美しく衣て、美しく住んで、美しく生活する人と、貧しく生きて、貧しく暮す人々の間の矛盾と疑ひが、常に私の心をくもらせた」と、階級的矛盾に論及する会員もあらわれはじめます(小沢日出雄「唯物観から脱れて」)。 |

『葭(よし)の笛』

『紅潮』
|
河上肇が『貧乏物語』を新聞連載し始めるのは、ちょうど同じ頃ですが、紅潮社に集う小山田の青年たちも「醜悪な現社会の空気」を敏感にかぎとっていました。
まず自分たちが道をひらいていくという気概にあふれ、「田園文化運動の先駆者」たらんと活動を展開しました。
大正一一年七月、「魂を村に投ぜよ」と呼びかけて映画の夕べを開き、講演会には渋谷定輔が主宰する農民自治会から中西伊之助や竹内悠児、橋本義夫らを迎えて、農民自治会忠生支部が発足しました。
「会員二十人、あたかも一村を占領したかの気炎」であったと、竹内は渋谷定輔に報告しています(渋谷定輔『農民哀史』大正一五年)。
中西はこの時、農民の汗と血のかたまりを奪って肥ってきた都会を批判し、
「農民がこき使われ、搾り取られて黙っているのか。決してそうあってはならぬ。
吾々農民も人間である。人間として生きなければならぬ」と、声高に力説します(堀江泰紹「小山田紅潮社と農民文学」『多摩のあゆみ』第四一号)。
小山田の青年たちはこの言葉を丸ごと受けとめられるところまで成長していました。
それはもはや単なる文芸グループという伜を越え、自己解放、自己変革を遂げ、地域社会を公平にみつめながら新しい地平にたてるところまできていました。
同人たちのための紅潮社倶楽部の建設や農場を借りて「労働デー」を実施し、一種の「理想郷」づくりを目指していたともいえるでしょう。
秋川に生れた巨人社
秋川沿いの西多摩郡東秋留村(現秋川市)に「巨人社」が発足し、『巨人』という名のガリ版刷り雑誌を発行し始めるのは、大正一五年三月です。
お前達は今の若さに何をしているのだ。退嬰的な現実は何だ! 若い躍動する血潮は、流れていないのか?…。
而しお前達の進もうとする路は決して易きたるものではないぞ。
(中略)だが、どんな苦しみが来たとて、最後まで堪え忍べ、そして若人の誇りを示せ。(『巨人』創刊号) |
これをうけて東秋留の一四人の同人たちは、「円形に手をつないだ。手から手へ、体から体へある何物かが流れた」といい、それが巨人社を生みだす源動力となりました。 |

『巨人』
|
新しい「郷土文芸の表現」を目指して、誌友の論説、創作、小品、詩、短歌、俳句、感想などが掲載されました。
拙ない表現ながら、そこには若い青年たちが日常生活の中で感じとったものが素直に表現されています。
汝の世界に干渉はない
汝等の世界には束縛もなければ
制裁もない
自由を得たる汝等よ
縦横無尽にはせ巡礼
無心の境を行く如く |
とあるのは、「怒涛」(藤野桂花)という詩の一節ですが、はげしく岸壁に打ちよせる波に仮託した青年たちの姿でもあるでしょう。 古くさい社会規範から自由になること、そこに原点をおいた生活を模索しようという表明です。
何が何でも実力だ
いくらデモクラシーを叫んでも
実力なければ駄目なんだ
世界はズンズン進み行く
人はわいわいさわぐ間に
世界は休まず進むのだ
若き血燃ゆる若人よ
実力作らん努力より |
会員の吉村亀太朗の「実力」という詩です。現実を見つめた時に見えてくるものを、飾らずに表現しています。
言葉だけが上すべりしている空念仏のデモクラシーでは駄目だといい、古い共同体意識に縛られた村落の中で青年たちが何を目指さなければならないのか、「実力」という言葉にこめられた「権力」に対抗する強い意志を読みとることができます。
“たまり”と地域青年文芸運動
戦後の地域文化運動でも、昭和四〇年代の「全国ふだん記運動」
* でも
、その指導者として登場する八王子の橋本義夫は、犬正期のそれは「本屋」が“たまり”だったといいます。
* 全国ふだん記運動=昭和四三年、橋本義夫によって始められた運動で、全国に二〇〇〇人以上の会員を擁した。
「文章は万人のもの」誰でも気軽に書ける文章をとの提唱で“ふだん記”と名付けられた。
多摩にはじめて本屋らしい本屋ができたのは、大正八年に八王子に開店した「可正堂」でした。
そこが若い地方青年の“たまり”になりました。
そして昭和に入ってからは、橋本自らが開いた「揺籃社」(ようらんしゃ)が“たまり”になりました。
“たまり”は「ホーム的なもの、指導的なもの、行動的なもの、友情」など、さますまな役割をはたしました。
社会を新しく発展させるには、「理論は割合に個人でもまとまるが、実際に行なう場合には同志的な人を要する。
その交流の場が“たまり”となる」と実践者・橋本はいっています(「たまり」『多摩のあゆみ』第四一号)。
ここでとりあげてきた大正デモクラシーを時代の背景とした多摩の「地域青年文芸運動」は、まさに橋本のいう“たまり”の役割をはたしたといえるでしょう。
それも文芸だけにとどまらず、文化活動全般にわたっての“たまり”が、多摩の農村のあちこちに生れました。
大きな“たまり”もあれば、道の片隅にできた水たまりのようなものもありました。
しかしたとえそれら一つひとつが小さなものであっても、多摩という大きな地図の上に広げてみると広い面になります。 |

揺籃社(昭和17年)
|
多摩の大正期の文化創造はみなこの“たまり”から生れました。
「人の集まる家、庶民の文化はここから巣立つ」といったのも橋本ですが、まさしく橋本個人の一生に凝縮、体現されたように、この“たまり”で身につけた実力は、のちに大きな力とかって結実しました。
『大菩薩峠』を書いたばかりの中里介山が八王子の高尾山の草庵に住みながら、一〇歳前後の少年少女を対象とした民間の児童教育機関「隣人学園」を開校させたのは、大正一三年のことです。
開校趣意書には「行く行くは各地に及ぼして青年以上の為にも、種々の機関を設けてお互に学んで行きたいつもりです。
これは教へる人も教はる人も、すべて無報酬で、各々が先生でありまた同時に生徒である心持てやって行きたい」とあります(桜沢一昭「高尾山妙音谷草庵」『多摩のあゆみ』第四一号)。
この隣人学圈はのち、郷里の羽村で「西隣村塾」に継承されますが、この平等な立場での知的交流を目指した在野の塾もまた“たまり”のひとつといえます。
この“たまり”を踏んだ者の中から、また新しい芽が育ったことは間違いありません。
このように、三〇年前の自由民権運動と、三〇年後の戦後地域文化運動との間に、大正期の“たまり”を置いてみた時、多摩という地域のもっている文化の源流とその潮流の行方が見えてくるでしょう。
3 私鉄と学園都市 top
現在、多摩は東京でも有数の住宅地です。
あるいは国立(くにたち)市のように、住宅地の真ん中に教育施設がしっかりと根を下ろし、整然と区画された学園都市のような街を想像する人がいるかも知れません。
いずれにしても多摩が住宅地として開けるようになるのは関東大震災後からです。
郊外生活は〈仕事〉と〈生活〉の場が分離していることを前提として成り立っています。
このような生活形態が定着するのは関東大震災以後のことで、サラリーマン層に住まいの場を提供しながら発展してきた多摩は、近代における住宅史を考える上で重要な役割を果しています。
田園都市への高まり
ところで緑豊かな自然を切り開き、そこに文化的な都市を造ろうという発想、これを田園都市と呼びます。
田園都市が日本に紹介されたのは、明治四〇年が最初です。
その導入に際し、当時すこぶる熱心であったのが内務省の役人や実業家たちでした。
明治四〇年と言えば日本が日露戦争に勝利した翌々年のことで、世界の「一等国」の仲間入りを意識し始めた頃です。
この頃から日本の関心は「西欧先進諸国に追い付け追い越せ」の殖産興業から、一等国としての自覚をどのように持つべきかに移っていきました。
ところで、東京を始めとした当時の都会に目をやると、惨状は目を覆うばかりでした。
道路ひとつ取っても穴ぼこだらけで、とても一等国と呼ぶにはほど遠い存在でした。
そのうえ大都会では都市人口が急増し、西欧諸国が経験したと同じような社会現象が現われ始めていました。
日本でも本格的に都市問題の解決に乗出さなければならない時期に差しかかっていたのです。
そうした中で当時とりわけ深刻であったのが、都会に住むサラリーマン層の住宅不足と生活難でした。
ちなみに内務省が大正一〇年に行った住宅調査によると、東京市の住宅不足数は一万七、七九五戸に及んでいます。
しかも東京では大正九年頃から無秩序な郊外化か進展し、居住環境の荒廃を生んでいきます。
絶対的な住宅不足は都市中間層に対して生活の圧迫を押し付けるばかりでなく、都会の荒廃をも生んでいたのです。
サラリーマンが日本を支える重要な労働力であることは、当時も変りありません。
その彼らが日常生活に苦しむということは、それはそのまま国力の低下につながることを意味しています。
当時において住宅問題に熱心であったのは、当事者の労働者階級よりも実業家や内務省の官僚たちでした。
その彼らの直接的な部下に当るのがサラリーマンです。
そのことを考えれば、当時の実業家からか住宅問題の解決に躍起となるのは当然のことでしょう。
日本の田園都市と言えば、まず経済界の大御所であった渋沢栄一が計画した田園調布を思い浮かべることができます。
こうした時代背景を考えれば、なぜこの頃、田園調布が計画されたのかも自然に受け止めることができます。
東京の西郊方面では、三井系の東京信託会社が明治四五年に最初の計画的住宅地「桜新町」の分譲を始めており、東京での郊外住宅地の開発と需要が高まるのはこの頃からです。
別荘の進出と交通網の整備
次に多摩の発展過程をみてみましょう。まず最初に進出してきたのは有爵者や高級官僚たちでした。
大正元年には雑誌『東洋経済新報』を主幹した矢野為之が、調布町布田に約一、一〇〇坪の別荘を構えました。
矢野為之は早稲田大学の総長や理事、早稲田実業学校の校長などを歴任した明治期の代表的な経済学者の一人です。
また大正九年頃には「日本の鉄道王」の今村清之助の嗣子である今村繁三が国分寺村花沢に約五、〇〇〇坪の別荘を構えました。
そのほか国分寺の殿ヶ谷戸公園、小金井の滄浪泉園(そうろうせんえん)なども、大正期における実業家の別荘を前身としています。
彼らの進出がそのまま中産階級の住宅地開発に直接つながるとは思われませんが、郊外生活を指向しその生活を文化的なイメージにまで高めていったのが彼らであることを考えると、その進出が多摩における宅地化促進への足掛かりを作ったといえましょう。
まず多摩は高級官僚たちの別荘地として発展してきたことを認識しておくべきです。
また多摩の宅地化の進展を知るうえで、交通の発達と電灯の普及も見逃せません。
一般に電灯・電力の普及は、地域に“明かり”を灯すだけの貢献しか果していないと受取られがちです。
しかし工業などの生産力の向上を考えてもわかるように、機織(はたお)り機械の工業化には絶対的に電力の普及が必要であり、経済活動の向上とは切っても切れない関係にあります。 |

滄浪(そうろう)泉園(小金井市)
国分寺の殿ヶ谷戸公園や日立中研の池なども
多摩川の河岸段丘の崖(ハケ)にある。
|
早くも明治二八年四月には八王子電灯会社が設立され、電化事業が始まりました。
しかし電力事業が飛躍的に延びるのは、大正時代に入ってからです。
大正二年には青梅に帝国瓦斯(ガス)力電灯が開設されます。
それ以後も、町田電灯(同三年)、氷川電気(同四年)、秋川水力電気(同五年)、村山電灯(同五年)など、小規模ながらも電力会社の設立が地元の有力者によって相次いでおり、確実にその数を増していきました。
これらの電力会社はその後電気鉄道会社に活動の中心を譲り主役から遠ざかっていきますが、都市生活者による郊外移住を前提として考えなければ成立ち得ないものでした。
都市機関の整備と発達は多摩における郊外化を知るうえで、もう一度見直してみる必要のある事柄です。
一方、鉄道などの交通網の発達も都心との経済的な結びつきを強める不可欠な要素です。
多摩では大正時代になって私鉄が相次いで開通し、鉄道網は著しく発展・拡大を遂げていきました。
これも多摩における郊外化と宅地化を比較的早くから促した要因と考えられます。
|

京王閣の案内(昭和初期)――中央線武蔵境駅から出ている西武線の終点で、今はモーターボートレース場だけが残っている。
|
まず最初に開通しだのは京王電気軌道でした。
もっとも私鉄と言っても最初は四四人乗りのポール式木製四輪車で、高速電車と呼ぶにはほど遠い存在でした。
大正二年に笹塚〜調布間か開通しました。
次いで大正四年に武蔵野鉄道(現西武)の池袋〜飯能(はんのう)間か開通し、また大正一四年に玉南電気鉄道(現京王)の府中〜東八王子間、昭和二年に小田原急行鉄道の新宿〜小田原開と西武鉄道の高田馬場〜東村山間、昭和三年には多摩湖鉄道(現西武)の国分寺〜小平間が開通しました。
改めて考えてみれば、西武・京王・小田急の三大私鉄とJR中央線の鉄道網整備はこの時すでに出来上がっています。
現在見られるような新宿駅のターミナル化と西郊方面における宅地化の進展は、この時すでに約束されていたようなものでした。
震災後の郊外移住と土地建物会社
東京近郊において一般向けの住宅地開発が最初に進むのは大正七、八年頃で、その契機となったのが第一次世界大戦後の日本経済のめざましい発展です。
折りからの好景気と都心への人口集中は「土地ブーム」をもたらし、社会の中に事業投資の気運が盛んになるにつれて、土地建物会社が次々と設立されていきました。
そうした中で代表的な土地建物会社が、箱根土地・日本信託・東京土地住宅などです。
これらの土地建物会社の活躍場所をみると、いずれも東京近郊の地域に集中していることがわかります。
そして都心が関東大震災で大被害を受けると、都市生活者による郊外移住はなお一層進むようになります。
震災による被害で都会生活が快適でないことを察知したのは、生活にゆとりがありながら過密な居住環境を強いられていた人々でした。
このような人々はこぞって郊外へ流れ出し、大正九年には旧東京市内に比べてその半分にも満たなかった郊外人口は、大正一四年には旧市内の総人口を追い越すまでとなります。
野や田畑はみるみる都市生活者のための住宅地へと生れ変っていきました。
武蔵野は田園風景を色濃く残しながら、色瓦や洋ペンキの文化住宅が立ち並び、新しい住宅街へと急激な変貌を遂げていくのでした。
箱根土地はそうした洒落た洋風住宅街を計画した代表的な土地建物会社で、大正九年四月に設立されました。
「土地ブーム」は大正九年に一つのピークを迎えており、箱根土地の設立時期をみても一つの時代背景が表わされています。
もっとも最初は住宅の供給だけを目的とした会社ではありませんでした。
会社の 「設立趣意書」に「吾人ハ今ヤ左ノ二大理由ニ依り帝都付近ニ於テ完全ナル大遊園地ノ必要ニ迫ラレツゝアリ」とあるように、西武園などの遊園地経営や軽井沢・箱根の別荘地の計画なども行っており、最初は観光会社としての性格が強かったのです。
こうして箱根土地が住宅地開発に手を染めるようになったのは、大正二年頃からです。
特に箱根土地が震災前にもっぱら計画したのは、富豪が所有している遊休地の宅地分譲でした。
たとえば当時の東京における土地所有の実態を見ると、一万坪以上を占める大地主が一〇八人もいました。
しかもそれらの大半は庭園空地の状態で放置されていて、なかには庭園とは名ばかりで田畑山林の名目で脱税を図る者までが現われる有様であったといいます。
つまり東京の宅地総面積の約四割が貴族・富豪による土地独占にまかされており、当然のことのようにサラリーマン層の絶対的な住宅不足の中で、富豪による土地独占は庶民から批判の対象にさらされるようになりました。
そうして開放された土地を一手に引受けて開発したのが箱根土地でした。
最初に箱根土地は大正一一年九月に柳原義光伯爵による払下げ地を桜田町分譲地の名前で売出しています。
また久世山、池田山、島津山など、旧家貴族の名前が付いた住宅地も箱根土地が開発しました。
箱根土地の住宅地には一つの特色があり、場所は高台で、ガス・土下水道・土地ケーブル式の電灯電話などの地下設備があって、良好な環境を維持しています。
山手地区の宅地化を促したのも箱根土地でした。
学園都市の建設
さて箱根土地のその後の活躍をみると、震災後は対象を西郊方面にまで広げるようになります。
これは山手線の外側がそれだけ土地投機の対象になってきたことを意味しています。
たとえばこの頃に開発した住宅地に大泉学園や小平学園、国立(くにたち)などがあげられます。
これらは今でも良好な環境を維持しており、大学・高校などのめぼしい学園を早くから郊外に移転させ、学校と一体となった街づくりを行っています。
そうした中で、箱根土地の経営者である堤康次郎が最も心血を注いだのが国立の学園都市の開発でした。
堤康次郎は震災後の翌年夏、谷保(やほ)村(現国立市)の西野寛治村長を訪れました。
目的は田園都市の構想を語って計画の内容を住民に理解してもらうためです。
話の内容は米作と養蚕を主体とする純農村地帯の山林地区約八〇万坪を切り開き、そこに戸数四五〇余、約三、〇〇〇人が住む田園都市を建設し、新しい住宅地に生れ変らせようとするものでした。
堤康次郎がイメージした田園都市とは、ドイツに計画された学園都市のゲッチンゲンをモデルとしたものだったのです。
箱根土地は土地の買入れに谷保村の人達を社員に雇い入れるなど、やや強引とも受取れる方法で買収を重ねました。
戦前の土地会社の分譲方式には買い入れ方式と分譲委託だけを引受ける受託方式の二つの方法がありました。
特に後者の場合は手付け金を最初に支払って残金を分譲後に支払うために、土地が売れないと地主も金が貰えないため、金銭をめぐるトラブルが絶えなかったといいます。
国立の場合をみると、戦前までは宅地の売上げがあまり伸びていません。
そうしたことから残金を貰えない地主からの不満が続出し、新住民と旧住民、あるいは地主との土地買収をめぐるトラブルで、戦後までシコリを残したといいます。
それはともあれ大正一五年に国立駅舎が完成し、昭和二年から宅地の分譲が始まりました。
まず国立の町を見て最初に驚くのは、住宅地の中央を突き抜ける二四間幅(約四四メートル)の大通りに象徴される画然と区画された街区計画と、大学が一緒になった街づくりです。
大学などを住宅地の中に取込む例はケンブリッジやオックスフォードを始めとして外国などではよくみられ、文化的な香りの高い住宅地を造るうえでは絶対的な条件とも言えるものです。
移転してきた東京商科大学(現一橋大学)ではかねてから移転計画を持っており、先に計画された「大泉学園」の時も予定を立てて交渉を重ね、昭和二年の学校誘致で初めて実現しました。
また大正一五年に東京高等音楽学院(現国立音楽大学)、昭和一五年に府立第十九学校(現都立国立高校)、一六年に府立第五商業学校(現都立第五商業高校)が開設され、学校移転については順調に計画が進められました。
また箱根土地では学園町にふさわしい雰囲気を創り出すために、駅前広場にペリカンやツルを飼う水禽舎をつくったり、事務所から絶えずきれいな音楽を流すなどの努力が続けられました。
ところで郊外に形成された住宅地をみて旧東京市内の住宅地と大きく違う点は、その開発規模の違いもありますが、サラリーマン層を対象とした新しいライフスタイルを作り出したことでしょう。すなわち、 |

東京高等音楽学院
|
(1) 高速度鉄道によって結ばれたオフィスと住居が分離した生活形態。
(2) 豊かな自然に囲まれた庭付き戸建の住宅。
(3) 町並み美観への配慮。
(4) 居住性・快適性を高める公園緑地の設置。
(5) 大学移転などの教育機関の建設。
などに象徴されるものです。これは江戸時代以来の都市構造を引き継いだ町内的な職住接近型を中心とした生活形態とはまったく違うもので、その手本はイギリスなどで発達した田園都市構想にあります。
国立の町を歩いてみると、当時における街づくりの精神やその雰囲気を良く味わうことができます。
都市計画に基づいた格子状の街区プラン、大通りの左右にある歩道の配置とその桜並木、住宅街と商業地域の明確な分離など、これらはいずれも当時の新しい都市計画理論や街路計画に冓づいて計画されました。
また一流の音楽家を招いてプロデュースした「音楽村」や、音楽堂を始めとする文化教養施設の配置などは、新しい生活に対するイメージを背景にしなければ生れてこなかったものでしょう。 |

国立(くにたち)大学町
音楽村の広告
|
これらの生活イメージは、今では当り前のものになっています。現代人が当時の国立の町並みを歩いて、違和感を持って帰る人は誰もいないかも知れません。
これは裏返して言えば、それだけ現代に近い感覚で当時の町並みが創られたことを意味しています。
武蔵野で生れた田園都市は戦後に受継がれて、現在の生活形態の原風景をしっかりと形づくっているといえましょう。
top
****************************************
|