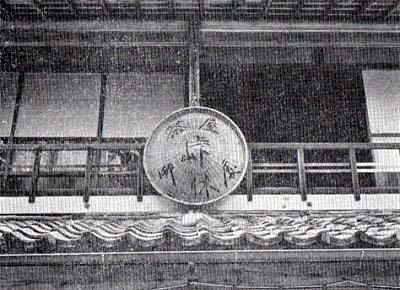|
****************************************
Index No1
No2 No3 No4
No5 No6 No7
No8
3 柳生(やぎゅう)街道
滝坂の道
春日原始林の中を縫う石畳の道が、ゆるやかな勾配をみせて続いている。
この道はある高名な作家が言ったように、日本最古のペーブメントであるとか、ローマ時代の軍道をおもわせる道であるというが、確かにそうした感じをうける道であるとも言えなくはない。
きれいに敷きつめられた幅二メートルばかりの石の舗道が、えんえんと原始林の中を走っているさまは、確かにある異様な印象を与える。
この道が奈良と柳生の里を結ぶ街道で、新しい自動車道路ができるまでは、唯一つの交通路であったのである。
薬師寺に近い破石から、古都の風情を今に残している高畑の道を歩きつめたところから、この道は始まるのである。
春日ドライブウェイと岐れるところから、やわらかな道になる。
その道に沿って小さな川が流れている。
行くほどにやがて原始林の生い茂った坂にさしかかる。
土地の人々はこの坂を滝坂と言ってきた。
道が次第に勾配を増すころになると、石畳が見えてくる。
その両側の草むらには名もない花が可憐に咲いている。
清らかな岩清水がせせらいでいる。
朽葉の匂いもあたり一面に漂っている。
上をみると数百年の樹令をもっただろう老杉や、常緑樹が、陽洩れもさせじと繁っている。
道は清閑そのものである。
石畳の道はやがて柳生につながって、いろいろな情景を連想させてくれる。
二階笠の紋所に、深編笠をかぶった武士たちが、大刀を腰に、大きな鉄扇を手に、のしのしと下ってくる。
物品交易のために、馬の背に生活物資を積んだ農民、天びん棒をかついた柳生の商人たちの姿もその中にある。
ではこの道は一体、どんな使命をもって開かれた道であったのだろう。
何かひどく由緒めいたものを持って来ないことには、観光宣伝にはならない。
そこで登場して来る人物は、奈良宝蔵院の槍の道場や、柳生道場をめざす剣豪たちである。
その中には荒木又右衛門があり、宮本武蔵がある、柳生一門の人たちを脚色した「春の坂道」は、はるばるとここにロケーションを行って、空前の好評を博し、そのお陰で柳生の村には数千の人たちが押しかけたが、それはもう語り草となって、柳生そばや、柳生うどんの店も今は閑古鳥が啼いている。
それはともあれ、この石畳の道を登りつめたところに、首斬り地蔵なる石仏が立っている。
首のところが切れているので首斬り地蔵というのだが、この無慈悲なる下手人は荒木又右衛門であり、一説には宮本武蔵である。
剣豪は、死してあの世でこの濡れ衣を、いかに憤慨しているであろうか。
この地蔵、八尺ゆたかな貫禄で、首の切れ目にはお賽銭が挾まれて、木洩陽に光っていたものである。
最近ではコンクリートで立派につがれている。
いつも真新しい赤いよだれ掛けを召し、野の花が供えられ、いくらかのお賽銭がおいてある。
ハイカーたちの程よい憩い場にもなって、仏と人はいつも睦やかだ。
この地蔵さままでの道の途中には、たくさんの磨崖仏がある。
それを麓の方からたずねると、最初に目につくのが寝仏と称する大日如来の像である。
もとこの上の崖に彫られていたものが、何かのはずみで欠けて転がり落ちて、丁度寝た恰好になっているから、寝仏というようになった。 |

首斬地蔵
|
この崖の中には、夕日観音とよばれる来迎の阿弥陀如来が彫られている。
大きな岩に彫られたもので、保存も立派である。
夕陽を受けると輝いてみえるところから、夕日観音となった。
このあたりは仏跡霊鷲山にたとえられていたので、大目、阿弥陀の両如来がこうして出現し給うたということであろうか。
暫らく登って行くと、今度は朝日観音という磨崖仏が深い木の間の岩石に高々と彫られている。
中央に釈迦如来、両脇に二体の地蔵が彫られているが、朝でないと鮮やかには拝めないところから、朝日観音とよんだ。
石仏といえば地蔵か観音が通念となってここでもお釈迦さまが観音さまにされてしまった。
文永二年(一二六五)の銘が残っているから、七百余年前のものだ。 |

夕日観音 |

地獄谷 |
そこでこの道の由来について、奈良の伝説は次のように伝えている。
滝坂につづく地獄谷は、昔奈良の庶民の死体の捨て場であった。
藤原の末期から鎌倉期、足利の初期にかけて、一般庶民は死んでも葬られる墓をつくることを許されなかった。
だから彼等は人生の最終の憩い場として、非情にも山野に捨てられ、風葬のうき目を見る他はなかった。
それは必ずしも奈良ばかりではなかった。
例えば京都でも、嵯峨野や鳥辺山は、風葬や火葬の場として、徒然草に描かれている。
それは今から考えると目を覆う酸鼻の世界であったにちがいない。
京都の化野が賽の河原とよばれたように、奈良の人々はこの谷を地獄谷とよんだ。 |

地獄谷磨崖仏
|
そう考えると、この道に沿う崖の仏たちは、このような無縁の霊をとむらい、欣求浄土の誓願にこたえる仏であったにちがいない。
そして人々は阿弥陀如来や釈迦如来、その他もろもろの仏たちの、この谷への出現を待ちのぞんだにちがいない。
この街道の村には忍辱山とか、鹿野園、あるいは誓多林といった、インド仏蹟に因んだ名のところが多い。
死後の理想世界に擬せられたこれらの名称に、非運の中に死んだ人たちへの、はなむけの心持がこめられたのであろう。
地獄谷に下って行くと、渓流によって深くえぐられた谷に、一人では恐くて通れないような幽気が立ちこめている。
落葉が積もって、やっと人一人が通れるほどの道は、うっかりすると足をすべらしてしまう位に小さくて心細い。
それでも所々に欠けた石仏が傾いていたり、奇怪な大石に花が供えてあったりする。
地獄谷をぬけると聖人窟がある。
毘盧舎那仏(るしゃなぶつ)に観音と薬師を配した線で、彩色を施されていることで有名。
今も僅かながら金箔と朱が残って、神秘な雰囲気がかもし出されている。
聖人窟は石材を切り出した後に仏をまつったものとも、あるいははじめから洞窟式仏龕(ぶつがん)としてつくられたものだとも言われているが、非常に格調高い磨崖仏で、藤原期にさかのぼるもの。
この聖人窟と並んで有名なのが、六仏と通称されている春日石窟で、春日山ドライブウェイに出た山の斜面にある。
仏体の多くは欠損していて、今日残ったものは十八体ほどである。
刻銘によれば、これは保元二年(一一五七)。
西側の窟には阿弥陀、不空成就、大日の各如来、東側の窟には地蔵菩薩その他の立像が彫り出されている。
さきの聖人窟と共に史蹟の指定を受けているから、柵の中に入ることはできない。

峠茶屋 |
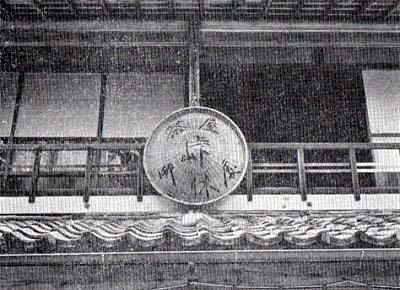
峠茶屋のかざり |
鬼哭啾々の地獄から、欣求浄土の仏たちを訪ねたら、あとはいよいよ峠道へとさしかかる。
坂道に疲れた身体を峠の茶屋で休ませよう。
この茶屋は昔の武芸者たちが腰を下して一服やったところで、いろいろな遺品がおいてある。
武具類から編笠などの日用品まで、それぞれにもったいつけたいわれ書がついている。
「春の坂道」以来どっとばかり押しかけた観光ブームの生み落した現象だ。
元々柳生村自体には、わざわざ出かけてみる程のものがあるわけではない。
家老屋敷や芳徳寺、そこにある柳生家墓地など、狭い村中にあるので一時間もかけると見られるのだが、NHKも罪なものでかっては二、三軒しかなかった茶店も、それ以来四十軒ばかりになって、忍者うどんとか、十兵衛そばが登場した。
土地にくわしい人の話によると、この村は元々そばなど栽培しないのである。
いやここばかりでなく、都会などでみかける信濃そばの看板など、いつわりもいいところ、日本人お互が好んで食べるそばの多くは、アフリカ輸入の原料を、日本で製粉するだけのものであるらしい。
しかし何れにしてもブームは去ること疑いなし、ちやほやされて浮かれた村の人たちにも、もうぼつぼつ虚脱が来はじめる頃だ。
村の高い丘の上に十兵衛石(一刀石)というのがある。
このあたり露出した岩石が多いが、何かのはずみで転がり落ちた大石が、丁度真中からバッチリと割れている。
これは柳生十兵衛が一刀の下に斬り割ったというもので、これがまた観光者たちの人気の的になり、一時は板囲いの中に入れて二十円の見料をとったというからすさまじい。
この程度のものなら罪のない話であるが、脱線のついでに言えば、小型で醜男であった義経が、あたりを払う美丈夫となったり、実在さえも疑わしい弁慶がたらいのように大きな鉄鉢で飯を食ったりする豪勇無比の男に化ける。
誇張や美化は物語につきものだが、嘘が真実にすり換えられては、これは困りものである。
さて余談はほどほどにして、柳生へと旧道を歩き出す。
私がはじめてこの道に足を入れたのは、春もすっかり老いて、山つつじの花が道ばたに淡紅の花をつける初夏の一日であった。 |

一刀石
|
柳生へ行こうという観光者たちは、奈良からバスで新道を行くので、旧道は極めて閑散だ。
歩くほどにやわらかな土の感触が快よい。
丘陵を利用した茶畑には手が行き届いて、株のうねりも美しい。
峠から忍辱山円成寺までの旧道およそ八キロ、この道は観て楽しむ道でなくて、歩いて楽しむ道である。
あたりの風物は心しなくとも眼に飛びこんでくる。
大和高原へと打続く山並は白い雲を浮かべて美しく起伏する。
道の両側には光る草があって人を迎えてくれる。
何も彼も忘れて歩かねば勿体ない気がする道だ。
禅に坐忘ということばがあるそうだが、私は今坐忘ならぬ歩忘の中にある。
捨てようとしても捨て得ぬ執着の多くを持った人間が、自然の愛撫を体一杯に受けて、ただひたすらに歩くことは、最高のよろこびの一つであろう。
歩きつつ私は忘れるために来たわけではないが、確かに歩忘の中にあった。
野の鳥を聴き、野の花と笑み交わし、野の仏に会釈して、やがて我にかえったのは、円成寺山門に辿りついた時であった。
そこには拝観、というよりも観光の群が、ぞろぞろと今しがたバスを降りたところであった。
|

土の匂い漂う古道
忍辱山円成寺
忍辱山という仏蹟そのままの名を冠したこの寺は、宗教的にも芸術的にも格調秀抜の寺院である。
奈良から柳生に至る街道中の最大のポイントをなすとも言うべき古刹で、小規模ながら完全なまでに統一されている。
街路に面する円成寺庭園は、平安時代の遺構、旧柳生街道はこの池の前を通っている。 |

柳生街道、円成寺境内の五輪塔
|
三間一戸の槍皮葺の楼門の見事さ(重文)、それをくぐると本堂(阿弥陀堂)がある。
その屋根の姿がまた美しい。変化の中にある均斉素晴らしい造型美だ。
本尊は弥陀如来坐像(藤原期の作で重文)その他運慶の作ったという大日如来の崇高な姿が心を引きつける。
境内の神殿は国宝の逸品であり、十三重塔にも、この寺の由緒が物語られている。
一山の管理が心憎いまでに行き届いていて、観光者たちのざわめきも自らしずまる。
柳生の村へ
円城寺から東南三キロで、大柳生村に着く。
ここに有名な夜支布(やぎう)山口神社というのがある。
延喜式の中に出て来る社で、昔から回り明神と称して村の長老たちが、一年交代で神を自分の家に迎え、家人とは暮しを別にして仕えた。
その古い祭祀の姿が今日も残っているという。
しかしこの大柳生は、柳生一家の住んだ村ではなく、その柳生にはここを通って暫らく歩かねばならない。
やがて十兵衛杉が見えてくる。
この杉には独眼流柳生十兵衛三厳が、諸国巡遊に出発するに際して植えたという伝説がある。
この杉の下に、江戸詰め家老広瀬小太夫等数名の碑が建っている。
明治維新の時、江戸詰めと国側か対立して、その犠牲となって小太夫等は切腹した。政変期の悲劇のモニュメントだ。
柳生という地名は、柳の巨木があったことでつけられたといわれ、古代から早く開けた土地で、古墳や古社も多い。
平安時代は藤原氏の荘園で、奈良春日神社の神領であったが、その後土豪の柳生氏が抬頭してきて、この地の領主になった。
南北朝での戦乱が起ると、柳生氏は南朝方に加担し、その後信長に協調してきたが、豊臣秀吉の文禄検地でその所領を失なったが、幸に石舟宗厳か徳川家康と結托したため、武道の家として家名をあげることになる。
剣豪としての石舟斎は、一世の剣聖上泉伊勢守に師事して、のち柳生神陰流を創めた人。
家康に強く兵法指南を乞われたが、老齢であることを理由に、五男の宗矩を家康に推した。
石舟斎創始の剣は、無刀どりといわれ、後年沢庵禅師によって、禅の哲学が加えられ、活人剣として柳生指南家の伝統をなした。
石舟斎は慶長十八年八十歳をもって没し、その墓は芳徳寺にある。
芳徳寺など

柳生の里、家老屋敷 |

ほうそう地蔵 |
柳生の里を見下す山の上に、柳生家菩提寺芳徳寺がある。
もとは柳生氏の居城だったところ、寺内に一族八十名の墓が並び、本堂に一族の遺品がたくさん残っている。
陣屋跡、家老屋敷、一刀石、ホウソウ地蔵などそれぞれその好むところによって訪ねるとすれば優に一日を費さなければなるまい。
この中に私の興味を惹いたのは、ホウソウ地蔵であった。
石仏そのものはとり立てて変ったものとは言えないが、地蔵を彫った石の一角に
「正長元年ヨリサキカンペ四カンコヲイメアルベガラス」と判読される刻銘のあることである。
これは山城、大和、河内を中心に起った徳政、つまり借金を棒引きにせよという一揆に際して刻まれたもので、正長元年以後、春日四郷(大柳生、小柳生、阪原、邑地)の人々の負債は棒引きだと、村人たちが気勢をあげた記念碑である。
柳生の里は昔近畿のかくれ里ともいうべきところで、自然も人情も美しい村であった。
また一万石の小大名である柳生家が、天下に鳴りひびいた剣と兵法のメッカでもあった。
早く変なブームを追い払って、汚れなき自然と、歴史の回顧ゆたかな村に帰ってほしい。
そう願いながら、私はまた歩忘の境を楽しみつつ奈良へ引返した。
top
****************************************
|