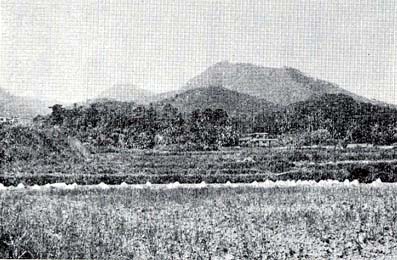|
****************************************
Index No1
No2 No3
No4 No5 No6
No7 No8
4 竹内街道
日本の道の原型
竹内という二上(にじょう)山麓の集落にある綿弓塚(俳聖芭蕉句碑)に立って、東の方を見渡すと大和平野が広々とひらけて、その展望の果に大和三山の姿が優美なシルエットを描いている。
三山の明日香から八木(やぎ)を通り、当麻の近くの長尾部落から竹内峠を越え、西へ真直に河内国堺に至る長々とのびる道、これが昔から竹内街道とよばれた道である。
この道は飛鳥時代に開かれた日本最古の公道として、大和、河内両国をつなぐ重要な道であった。
それは七世紀の初めの頃、第三十三代推古天皇の時つくられた道で、この道の開発のために百済から渡来したみちのこのたくみ(路子工)という役人が起用されたという。
これは恐らく日本最初の国道整備事業であっただろう。
この道は河内に入ると堺から北に折れて、今の大阪城南側法円坂にある難波宮址と推定されるあたりまで延びていた。
この道は、大和平野の西を限る生駒から金剛へと連なる峯の低く途切れるところを利用してつくられているが、古事記や日本書紀では二上山あたりの山越えの道を、大坂と呼んでいる。
別稿山辺の道で書いたように、倭述追日百襲姫命を葬る箸墓をつくるとき用いた石材は、ここ大坂山から運ばれた。
大坂山から墓所まで人々が並んで手送りに石を送り運んだというから、墓の主ヤマトトトヒモモソヒメはよほどの権勢者であったのであろう。 |

二上山麓の古い酒屋
今は“にじょうさん”と言うが、
万葉集では“ふたがみやま”と読む。
|
昼は人が働いたが、夜になると神がこれを作ったとも書いてあるので、物語が描くようにこの姫は神の妻の権威を持った女性であったにちがいない。
だからその女性こそ、邪馬台国の卑弥乎だとしても、決しておかしくはないとする人もある。
それはともかくとして、大坂山、即ち今日の二上山麓は、昔から石材の産地として有名なところであったことはこの物語でもわかるというもの。
さて竹内街道は日本最古の公道の名にふさわしく、今日でもこの道の左右には、曾我、忌部(いんべ)、雲梯(うなで)などという古代氏族の姓を伝える名の部落が残されている。
この道こそまさに古代史を縫う道であり、とぼとぼと歩くほどに、古代のもろもろの事件を実感させ、想像させてくれる楽しい道である。
しかもそのような実感と想像はまた民族的な思索をかき立ててくれる道でもある。
こうした意味でも、この道は東の山辺の道々、斑鳩の道と共に、日本の道の原型をとどめる道であるということができる。
坂道の竹内集落
当麻に隣接して南に長尾という部落がある。
この部落からだらだら坂を歩いて行くと、右手近くに美しい二上山が見える。
その麓に当麻寺がある。一キロばかりも歩くとすぐ竹内集落にさしかかる。
この集落は坂道に沿うた民家で構成され、道の両側には昔ながらの大和屋根の民家が残っており、変化のある風景をつくり出している。
椀をつけた屋根の棟には、松竹梅の造化が飾られ、鬼瓦の上には鳩や亀の焼物が、本物まがいに乗っていたりする。
大和ではこうしたところにも、花鳥の自然と心を通わしてきた風情を、いたるところに残してきた。
この頃では藁屋根の原料になる茅がなくなって、トタンとか安瓦に代ってきた。 住家にも実用性ばかりがはびこって、風土性を失なってきたのは残念なことである。
俳聖芭蕉は貞亨元年(一六八四)という年にこの里を訪れている。
竹内に千里という芭蕉の門人があったので招ぜられて興善庵という家に打ちくつろいだ。
芭蕉は当麻寺の諸仏を拝んだが、「よろづの尊さも伊麻を見るまでのことである」という手紙を友人に書き送った。 |

竹内部落
|
芭蕉のこの里への訪問は延宝、貞享、元禄にわたり前後五回、この間に「野ざらし紀行」にある次の句などを作っている。
綿弓や琵琶になぐさむ竹の奥
たのしさや麦田に凉む水の音
世ににほへ梅花一枝のみそざい
冬しらぬ宿や糘する音霰 |
芭蕉没後百十余年を経て文化六年、句碑がこの里に建てられ、綿弓の句に因んで「綿弓塚」とよばれた。
目近に葛城の連峯を仰ぎ、東に大和平野をみはるかす素晴らしい景勝を占めたところにこの塚は建っている。
芭蕉が当麻の仏よりも孝女伊麻を訪ねることを第一の目的としたという、その孝女の碑が忘れられたようにひっそりと集落の中はどの道傍に立っている。
鰻にまつわる孝女物語は、日本二十四孝の中に書き残されたもので、芭蕉はよぼどこの物語に感動を受けたものであろう。
碑の側に、今時には容易に読めそうもない変体仮名の説明板が、雨にさらされて判読し難くなっているし、村の人にその由来を尋ねても、返ってくる返答は瞹眛でたよりないものばかりであった。
この竹内集落をすぎるとすぐ峠にさしかかる。
峠まで約二キロ、それもきわめてゆるやかな坂道であり、めったに車にも会わぬ静かな道である。
杉や松の林が続いて、おそ鶯の声が林間によび交っている。
一服やるまでもない山路であるから、鶯の声に耳をすますと、そのほかにも野鳥の啼き声がにぎやかである。
ふと幽鳥弄真如ということばなどを想い出して、山の気に惹き込まれるような気持になって歩いていると、時折には自動車のエンジンの音に、その静寂を破られる。
山路のところどころに塵埃投棄禁止の立札が立っている。
夜間トラックなどでこの山に捨てに来るらしい。
スクラップ公害のとばっちりである。
竹内峠
竹内峠は大和と河内両国の国境で、昔はここに関所がおかれていた。
この峠の河内側にある孝徳天皇陵を「うぐいすのみささぎ」と呼んでいるのをみると、この一帯は昔からうぐいすの名所であったのであろう。
昔この峠には関所の外に一、二軒の茶店や宿屋まであったという。
中世以後八百年間はしだいに庶民生活と結びつき、そのために天皇や貴族たちの行列は少なくなり、大和、河内の両国を結ぶ産業道路的な役割を荷うようになった。
また明治中期に関西本線が開通する頃までは、茶店、めし屋、宿屋などがあり、天誅組の大和義挙に当って、危く逃げのびた主将中山忠光卿以下七名の武土たちは、文久三年九月にここに逃げ込み、峠の茶店で食事をとっていることが大和日記に記されており、また南朝の史蹟を訪ねてきた吉田松陰や松本圭堂などの幕末の志士たちも、ここで足を休めている。
この峠は標高わずかに三百メートル足らずのところであるが、眺望は杉の林に遮られて全く利かない。 |

竹内峠
|
鹿谷寺(ろくたんじ)のあと
峠を下り切ると右手に石の地蔵さんが立っている。
顔は磨滅して目鼻もさだかでないが、昔からこの峠を越える旅人たちを慰めはげました石仏であった。
この地蔵さんから細い山道を右手にとって登ること約五百メートルで、鹿谷寺址に着く。
雑木をおし分けて登る山路は難路で、夏ともなると山道を横ぎる蛇に足をすくまされることもある。
さてその寺址に辿りついてさらに驚くことは、飛鳥期に刻まれたという十三重塔と、如来三体を彫った石窟が、風化以外には損傷を受けず、見事に保存されていることである。
しかもその十三重塔は、地面生え抜きの塔で地盤の岩石がそのままに彫り残されているもので高さは五メートル余り、今も立派な均斉を見せている。
正に二上山の石の文化をシンボライズする遺物ということができよう。
寺境に累々と露出する岩塊をけづりとって開いたであるうその敷地は、さのみ広いとは言えないが、千三百年もの昔、この山中に営まれた伽藍、そこに朝夕の信仰の灯をともし続けた人たち、この寺は今日すでに幻の寺となってしまったが、それだけに大和に開花した仏教の源の深さが今更なからに胸に迫ってくる。
今は史跡として指定されている。時折に訪ねる人があるのであろう。
線香の燃えさしが雨にさらされているのを見かける。 |

鹿谷寺址十三重塔
|
十三重塔と如来の他にも、西側岩壁の岩塊に、東面して一体の仏像がある。
しかしこれは剥落がひどく、腹部の一部を残して、消え去っている。
また南の崖に高さ一メートル半ほどの方尖形の小塔が、これも同じく岩盤から掘り出されたもの。
これらを綜合してみると、極めて小規模ではあるが、印度や中国にみる石窟寺院の影響をみることができよう。
昔北周の武帝は、寺院をこぼち、仏像を焼いたが、この排仏に対抗するためには、焼けない寺や仏像を造る必要があった。
そのような焼けない寺院は、二上山のような石の多いところでは、容易に造られたので、そのような石窟寺院のうつしみたいなものがここに営まれたのかも知れない。
そこから少し下ったところに鹿谷寺の坊舎跡があり、土師器とか、和銅開珎なども発見されたという。
しかし記録の一切は失われて、縁起も分らなくなった。
文字通りまぼろしの寺である。それにしても開山の僧は誰であったのだろう。
そしてまた鎚の音をこの山中にひびかせながら、上求菩提下化衆生のいのりを刻みつけた人は誰であったろう。
大坂山の石
この寺址の背後はすぐ二上山の雄岳である。
二上山は地質学上では一千何百万年前に活動を始めたといわれる気の遠くなるような古い火山で、その活動を終ったのは百万年前だという。
地質学などという学問は、歴史や考古学とちがって、実証の学問であるから、まぎれもなく山の年令などを科学的に推定指摘できるのであろう。
この山には多種多様な火山岩が含まれており、この中でサヌカイトと称する黒っぽい石があり、縄文時代には、斧とか矢じりなどの原料につかわれたものである。
縄文期の頃は、大和、河内の両平野ともに低湿地か湖沼であったので水辺が後退するまでは、人々は二上山の中腹から山麓の高いところに住み、狩猟生活を営んでいた。
それが弥生期になると、人々の生活はだんだんと平地へと下りはじめ、はじめて米つくりがはじまることになる。
そうなると両平野の耕作地を支配した豪族が、祭政の支配者となり、降って古墳時代から飛鳥時代には諸豪族の上に立つ天皇家の基礎が確立することになるのである。
そしてやがて支配者の権勢を誇示するための巨大な墳墓が築かれるようになるのであるが、それら古墳の造築につかわれた石材は多く二上山から切り出されていたらしい。
今日両平野に残る古墳の石棺や石室の原料も、難波宮や四天王寺、法隆寺、東大寺など巨刹の用材も、その多くは二上山、即ち昔の大坂山から供給されたものであった。
大坂の砂で玉石を磨くことで功のあった斐太(ひふと)という人を良民とし、大友史(おおとものふひと)なる姓をたまわるという続日本紀の記事で想像されることは、玉や石の加工は一種の官営の仕事であったということである。
その大坂の砂と称した金剛砂をつくるザクロ石が、今もって産出していて、その露天掘が行なわれている。
この硬質の石は、やわらかな凝灰岩の切り出しには一番役に立ったものである。
二上山は別稿でも書くが、いろいろな意味で、古代と深くつながっている。
雄岳の頂上には、天武天皇第三皇子が、抗すべきもない運命を諦めて処刑に服し、遺骸は磐余から真西に当るこの山の頂上に葬られた。
うぐいすのみささぎ
鹿谷寺(ろくたんじ)址からもと来た道を引返して、地蔵の辻から西へ歩けば、やがて山田という部落に出る。
このあたりは古代は磯長とよばれたところで、推古天皇や孝徳天皇、用明天皇の御陵がある。
清少納言が枕草子の中で御陵の第一と推奨したのは孝徳天皇陵で、「うぐいすのみささぎ」という。
清少納言が御陵第一級の折紙をつけたほど、この御陵が気に入ったとみえるが、松や檜にとりかこまれたまことにすがすがしいここは今もうぐいすのこえに包まれる。
大化改新という大事業を完成された天皇を葬るにふさわしい御陵である。
この付近にはこの外に遣唐使をつとめた小野妹子の墓や飛鳥時代の貴族の二子塚などがある。
幸なことに車は村の入口から岐れているバイパスに集中して流れて行くので、この集落一帯は、なお古いさびを残す楽しいところだ。
孝徳天皇陵近くの民家には大和と同じ姿の民家が見られ、その昔近つ飛鳥とよばれた河内のおもかげは、遠つ飛鳥の大和と共通な民俗を残している。
ここに餅屋橋という名の橋があり、古い石の道標がある。
今はコンクリート造りの小さな橋になったが、この橋のたもとに、明治中頃まで一軒の餅屋があり、一日十円の売上げがあったという。
明治中頃といえば、米一升十銭にもならなかった時代、一日十円の売上げというのは大変な繁昌であったにちがいない。
大和、河内を往来する人たちは、名物の餅に舌鼓をうって、この峠道のつかれを慰めていたことであろう。
上(かみ)の太子
野にある百姓は耕すことをやめ、米を搗く女は杵を上げる力も出なかったという。
このことについて日本書紀は 「日月は光を失ひ、天地まさに崩れなん。今より後誰かを恃まんや」と記している。
太子の死の悲しみがぞくぞくと伝わって来る様である。
その御墓は世に三骨一廟といって、御母間人皇后と御妃膳夫人と共に合葬した珍らしいものである。
太子がこの磯長に墓所をきめられるについては、この地が天下無双の霊地、過去七仏転法翰の聖域と信ぜられたからであった。
太子御年四十七才のとき、御自ら役夫を督して築かせられたというが、このことについては、兼好法師はその徒然草に次のように書いている。
「わが身のやんごとなからんにも、まして数ならんにも、子といふものなくてありなん。
前中書王、九条太政大臣、花園左大臣みな族絶えんことをねがひ給へり。
染殿大臣も『子孫おわせぬぞよく侍る。末のおくれ給へるはわろきことなり』とぞ、世継の翁の物語には言へる。
聖徳太子の御墓をかねて築かせ給へる時も『ここをきれ、かしこを断て。子孫あらせじと思ふなり』と侍りけるとかや」 |
太子薨後は、御子山背王子は入鹿のために斑鳩宮で無抵抗の死をとげられ、太子の子孫は絶えた。
思うに太子は虚仮と断じた世間であればこそ、子孫あらせじと願われたのであろう。
そのためには、墓所のあちこちを切りけずって、自分のやがて眠る墓を縮められたのである。
その後二年を経て推古天皇の三十年二月二十二日太子は斑鳩の宮で薨ぜられたが、天皇は勅を下して太子の霊追福のために、方六町の地をおくられ、香華所としての叡福寺を開創された。
太子はかく日本最高の教主とも崇められる方であったため、以後宗派を超えて傾倒が篤い。
現在でも各宗管長が就任するに当っては、この御厠に参拝、管長就任を御報告申し上げるのが恒例になっている。
応神天皇陵
大阪府教育委員会が行った近つ飛鳥遺跡分布調査によれば、河内羽曳野(はびきの)、柏原、太子町一帯にある古墳の数はおよそ三百
* と報告されている。
大和明日香で高松塚古墳が発掘されて世間の耳目を聳動すると、暫らくして河内柏原市の玉手山では、馬に跨った人馬の珍らしい装飾古墳が発見された。
ここでおもい起すのは、東大名誉教授江上波夫氏の騎馬民族説である。
それによれば大陸から朝鮮を経て渡来した騎馬民族が、九州から河内に侵入して古代統一国家をつくった。
そしてその初代の大王が応神天皇であろうというのが、その学説の着想であった。
応神天皇陵が築造されたと推定される五世紀の初めの頃は、この学説によると日本にはこの頃から騎馬の習慣があったことになり、玉手山古墳の馬上の武人の謎も自ら解けることになる。 ともあれこの壮大な応神天皇陵を作るについては、この墳の主が勢威四方を圧した大王であったことに間違いはない。
その応神天皇陵は、堺にある仁徳陵につぐ前方後円の大墳で、歩いて一周すれば優に一時間もかかるという巨大なものである。 老松が年を経て古び立ち、森林に覆われて黙々と踞(うずく)まる姿は、古代の神秘と荘厳さをかもし出し、王者の風格をしのばせる。
古墳のすぐ側を通る大阪府道環状線の跨道橋の上に立って四顧すれば、あたりには宅地造成の波が押しよせて騒々しいが、遠近にある古墳群をながめていると、古代王朝の頃、このあたりに統一の業を進めた軍団の群が目に浮かんでくる。
仮りに応神天皇を以て騎馬民族の首領に擬すれば、このあたりこそその首領に率いられた軍団の根拠地であったといわれよう。
御陵の傍に応神天皇をまつる誉田八幡宮がある。 |

竹内街道、応神天皇陵
近鉄南大阪線古市駅が最寄り駅
|
天皇はいうまでもなく弓矢の神として後代に崇められる方で、その名ホンダワケスメラミコトの名に因んで、誉田八幡と称する。
「御陵さんの森から来る風で、このあたりは結構な涼しさでして……」
と物腰のやわらかな宮司夫人は、掃除の手を休めながら話して下さる。宮を守る人柄のしとやかさをたたえた面ざしが美しかった。
さてここで私は一度日本歴史の一駒をふり返ってみよう。
応神王朝説や騎馬民族征服王朝説の真偽はともかく、応神天皇の時代が一体いつのことであっただろうかということである。
当時中国の宋書によると、倭国には五王があって、その五王を讃、珍、済、興、武という名でよんでいた。
それが日本の帝記によると、丁度応神天皇から雄略天皇の頃に当るので、それをめぐって讃は応神か仁徳か、従ってそれ以後の四王を、履中、反正、允恭、雄略の何れの天皇に比定するかの論が起ってくる。
これは歴史学上のきわめてむづかしいこれからの問題であるが、この五王の時代は謎の世紀ともいわれている時代でもある。
五王の治世、そして謎の世紀の解明はむづかしいにしても、これら御陵を擁する古市の一帯は、そうした時代の王者たちの活躍舞台であったであろうということは想像される。
竹内街道に沿って、野というしゃれた名の部落がある。
そこから来し方を振返ると二上山の美しい双峯は、いつまでも私たちを見送ってくれている。
野中寺
野からおよそ二キロ、高速道路に沿い、野々上集落に野中寺がある。
聖徳太子創建四十六寺の一つで、上の太子叡福寺に対してここは中の太子とよばれて来た。 喧ましい往来から山門を一歩入ると、松林に包まれた寺域は静寂で心を休ませてくれる。
創建当時は法隆寺式伽藍配置の堂々とした寺であったが、戦火に罹ったりして一時廃寺となっていた。
それが江戸時代の寛文元年(一六六一)戒律道場として復活したという。
今日では当時の本堂を残すのみで寺は小さくなった。
が境内には創建当時を偲ばせる金堂の大きな礎石や、三重塔とおぼしき心礎が松林の中に、薄れ陽をうけて静まっている。 ここの本尊は金銅弥勒仏で白鳳期の作、天智天皇の五年(六六六)天皇の病気平癒をいのって造立されたという、像高三十センチ位の可燐な仏である(国宝)。 |

野中寺本堂 |

野中寺、中国渡来の石人 |
本堂左手にまつられる鎌倉期造立の木彫地蔵尊も国宝であり、信仰をあつめている。
朝鮮征討の物語に出る神功(じんぐう)皇后の夫、仲哀(ちゅうあい)天皇の御陵も近くにある。
この時代、朝鮮乃至中国との交渉を思わせる大陸風の石人が一つ土塀の前に立っている。
はるばる異郷から渡ったこの石人は、柔和な面相の中にも、何となく一抹の哀愁を境内に漂わせている。
柴籬(しばがき)の宮址

仲哀陵
近鉄南大阪線藤井寺駅が最寄り駅 |

反正天皇宮居・柴籬宮址 |
野中寺から南河内平野を真直に西へのびる道路、かっての竹内街道も今は自動車のひしめく高速道路に変ってしまった。
大和から西に伸びる竹内街道も、河内から東へ伸びた接点はどの辺であっただろう。
大和朝廷の開発より早く、河内王朝はその進出に伴なう道の開発をやっていたに違いない。
黒土、金田、遠野などの部落を過ぎて岡という部落につく。
仁徳天皇陵のある堺ももう六キロばかりに近ずいた。
この岡から真角に変る道を北へ歩くこと二十分ばかり、そこに柴籬宮址がある。
昔を偲ばせる老松の並木が残っていて、今は柴籬神社というさびしい神社があるばかりであるが、ここは倭の五王の一人に目される反正天皇が五年間宮居を置かれたところ、丹比柴籬宮地という。
その名の通り宮居の周囲に柴籬をめぐらしていたのであろう。
反正天皇は、履中天皇の弟君であるが、古事記によれば身長九尺二寸半、歯の長さ一寸、広さ二分、上下ひとしくととのい、珠を貫いているようである。
死の年は六十歳、墓は毛受野にありと記し、書紀は容姿美麗しとほめている。
その名「みずはわけのみこと」は瑞歯であり恐らくその容姿を讃えた美称であろう。
難波の都の南門から真直に大道をひらいて丹比の已に至る――と記された仁徳紀の記すように、日本歴史の上では謎の世紀といわれる時代の、大和王朝の活躍時代の舞台の一つが、この宮居を中心とした一帯であったにちがいない。
この付近から堺――大阪(難波)に至る今日の道は古墳以外にはもう古代の面影を残すものはなくなり、開発の喧騒がそれに取って代った。
しかし折角であるから、この道の起点である堺の仁徳陵をたづねよう。
戦前の日本歴史においては、その名のごとく仁慈の天皇として、困窮する民草のために三年の税を免じ給うた天皇として教えていた。
しかし宋書における倭の五王の讃と比定され、日本でも天皇制イデオロギーは、日本歴史上の一大課題であろう。
世界最大の墳墓である仁徳陵は全長四八六メートル、後円部の高さ三五・五メートルという宏壮な前方後円墳であり、前方部の領域にエジプト最大のピラミッドをその中にすっぽり入れるだけの広さをもっている。
ある考古学者の計算によると、一日千名を動員して四年はかかろうという大きな労働力を投入して築かれた。
しかしこれは単なる古墳だけの問題ではなくて古墳の衙築につかわれた土木技術は、治水、灌漑、築堤などの農業土木に直結する。
一方河内平野には、淀川と大和川があって、いつもそれが氾濫源であった。
しかし仁徳陵をつくリ得る労働力と技術は、河内平野の開拓にも充分駆使されたことであろう。
河内王朝の都高津宮址は、発掘の結果、大阪城に隣接する法円坂にあったことがわかった。
民の税を免じて三年「朕富めり」とよろこばれた仁徳天皇の物語は、後代のフィクションであろうが、都城が置かれたことは確かであり、後に難波を門戸として、中国の文化が移入してきたことも確かな史実である。
明日香とこの河内をつなぐ竹内街道、それに沿う古代の文化遺跡は、いつまでも日本民族の原郷として大切にして行きたいものである。
当麻(たいま)の道
近鉄吉野線の当麻という小駅に降りると当麻寺への参道が真直に西へ向ってのびている。
寺までおよそ一キロの道のりであるが、道の両側の民家には、日本文化の中心地であった大和らしい古代の色が濃く残っている。
大和古代の色をよく物語るものは、大和屋根である。
藁ぶきの屋根に藁の鰹木(けんぼく)をのせ、根がついたままの孟宗竹を棟木の代りにおき屋根をとめている。
その棟木の上には、松、竹、梅の飾りものがおかれ、瓦焼の鳰や亀などをとまらせている。まことにほほえましい風物である。
かって顕宗天皇は、新屋落成の日 |

大和屋根、梲(うだち)の飾り |

当麻けはや墓 |
「築き立つる柱は、この家長の御心の鎮めなり。取上ぐる棟梁はこの家長の御心の林なり。
取り置ける椽鏥は、この家長の御心のととのほりなり。
取り結べる繩葛はこの家長の御寿の堅めなり。
取葺ける草葉は、この家長の御富の余りなり。」 |
こう祝の言葉をうたわれたというが、屋根におかれたこれらの飾りものをみると、その意味がぴったりと理解されそうな気がする。
この参道の中ほどに、大同という年号を彫った大きな五輪塔があるが、これが相撲の開祖、当麻蹶速(けいそく)の塚である。
大同といえば五十一代平城天皇(八〇六−八〇九)、もちろんこの塔はそんな古代のものではなく、大同という彫文は後世の人のいたづらであろう。
この当麻町には、相撲開祖顕彰会という会がつくられていて町の観光宣伝に力を入れているということになるので、これは宣伝価値がある。
相撲開祖となると、当麻蹶速(けはや)と、これをうち負かした野見宿弥の二人ということになるが開祖顕彰会の宣伝文には、次のように書いてある。
「当麻蹶速は小股王の皇胤で、書紀のいうように、力をのみ侍む卑劣な人ではなかった。
只、東の野見宿弥との力闘に敗者となったため、千数百年来、路傍の石の如く顯みられなかったことは同情に堪えないところである。
しかし相撲が今日国技として尊ばれ受好され、而も隆々として繁栄の一途を辿っている時、われわれは同志相計って相撲開祖顕彰会を組織し……云々」 |
中々の力の入れようである。
こんなことだから、二上山登山口には当麻蹶速屋敷地というのがある。
勿論伝説であって相撲発祥の霊地というようなお国自慢はいささかオーバーであろう。
この「いさみこわきひと」については、日本書紀は次のように書いている。
垂仁天皇の御代、この「いさみこわさびと」は東(今の桜井市)の野見宿弥と天覧相撲の末一敗地にまみれたので、天皇は彼の領地を宿弥に与えたまう、と。
このことは東大和における天皇家の勢力が、西の葛城にあった部族国家を征服したことを物語る、一つの寓話であろう。
このいわば、天覧相撲の行われた場所は、垂仁大皇の宮居のあった桜井市で、そこに野見宿弥をまつる小さが神社がある。
伝説は今に生きて大相撲大阪場所の前には、横綱が必ずここに参拝して、奉納の土俵入りをする習わしとなった。
縁起の力というのは大きなものである。
当麻寺(たいまでら)
当麻寺といえば、蓮の糸で織ったという曼荼羅(まんだら)で有名なことは人の知るところ。
しかし蓮の糸が織物になるかどうか、今日それを詮索する人もあるが、蓮は浄土に咲く花であるとされるところから、こんな言い伝えが出来ても不思議ではない。
当麻寺が寺院としてのいかめしさよりも、優雅な寺であるとおもわせるのは、中将姫結縁の寺だからということにあるかも知れない。
足利時代、世阿弥のつくった謡曲「飛雀山」から、さらに後世歌舞伎に脚色された物語、心のやさしい不幸な尼僧が、蓮糸で曼荼羅を織ったという、哀れにも美しい物語にまつわる当麻曼荼羅、五月の頃におい咲き競うぼたんの花とともに、ぜひ一見すべきものであろう。 |

当麻寺ぼたん
|

二上山登山路の石仏
二上山(ふたがみやま)哀話
当麻に生れた恵心僧都は、往生要集で大いに浄土信仰を宣揚したことについてはあるいは当麻という風土が強く働いていたかもしれない。
というのは、当麻寺のすぐ西にそびえ立つ二上山で、この山は大和平野のどこからでも望まれる美しい容姿をもっている。 |

二上山頂より大和平野を望む |
朝夕にこの山をのぞむ大和人にとっては、ここは浄土へ行く入口であるとみられてきたのであった。
二上山については、本書の他のところでも度々触れるように、立地的にも物語的にも重要な山であるのだが、ここでは多少の重複にも拘らず飛鳥時代に遡る一つの哀話を書きとめておこう。
当麻寺から二上山への岩屋道とは、聖徳太子の開き給う古道といわれているが、やがて麓にかかろうという道に面して、傘堂という変った建物がある。
これは山の辺の道にある長岳寺の傘堂と同じ構造のもので、一本の角柱で支えられた建物である。
俗に左甚五郎の作といわれているが、単柱の上に宝珠露盤をのせた単層宝形造り瓦葺で、心柱の上部の厨子の扉をひらくと、さらに厨子を納めて、阿弥陀如来を安置してある。
この傘堂は土俗信仰の盛んになった鎌倉時代の頃から、死の苦しみを解くためにこの堂に三度祈願すれば、その苦から逃れて、安楽に死ねるという信仰がよせられたものであった。(大和名所図絵。西国名所図絵)
さて少し辛抱して二上山に登るとしよう。山は五百メートル足らずの、さして高い山とは言われないが、その眺望は大和河内の両国をみはるかして素晴らしい。
頂上に着くと大津皇子の墓がある。
| うつそみの、人にあるわれや、明日よりは 二上山を、弟世とわが見む |
言うまでもなく万葉集にある大来皇女(おおくのひめみこ)の歌である。
山上に葬られた大津皇子は、天武天皇の皇子、その皇子がどうして悲劇の主となったかについては、まづその系譜を一瞥してみなければならない。
皇子の父天武天皇には皇后の生んだ草壁皇子のほかに、次のようなたくさんな皇子、皇女があった。
皇后 鸕野皇女 (父は天智天皇)
妃 大田皇女 ( 〃 )
妃 大江皇女 ( 〃 )
妃 新田部皇女( 〃 )
夫人 氷上娘 (父は藤原鎌足)
夫人 五百重娘 ( 〃 )
夫人 犬融娘 (父は蘇我臣赤兄)
額王女 (父は鏡王)
尼子娘 (父は胸形君徳善)
徽媛娘 (父は宍人臣大麻呂)
|
草壁皇子
大伯皇女
大津皇子
長皇子
弓削皇子
舎人皇子
但馬皇女
新田部皇子
穂積皇子
紀皇女
田形皇女
十市皇女
高市皇子
忍壁皇子
磯城皇子
泊瀬部皇女
託基皇女 |
このような多数の皇后の他に妃、夫人があったのであるから、そこには当然のこととして皇位継承の問題が複雑にならざるを得ない。
そこで問題は皇后の腹に生れた草壁皇子と異母弟の大津皇子の間に生じた。
弟の大津皇子は、堂々たる偉丈夫で教養もすぐれて高く文武両道にわたり、天武天皇に非常に愛され、若冠十歳にして壬申の乱には父方としてその戦陣に加わった。
さて一方、草壁皇子は¥野讃良皇女の腹であるから、皇位を嗣ぐことになった揚合は当然優位に立つことになる。
しかし凡庸でおとなしい草壁皇子は、その才能においても臣下の信望においても大津皇子に劣っていた。
このようなことから父帝即位後八年を経ても皇太子はきまりかねていた。 |
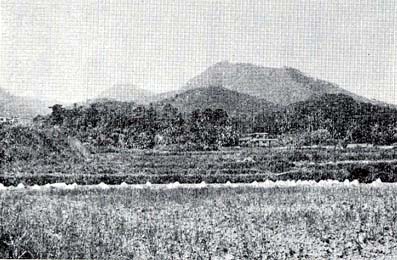
二上山
(右手雄岳の上に大津皇子の墓がある)
|
皇子六人のうち、草壁、大津、高市、忍壁の君皇子はみな腹ちがい、父は一人でもそれぞれの母としてみれば、自分の子の成功をいのらぬ筈はない。
しかも、皇后にとっては最大の競争相手である大津皇子が、すべての点において愛児を越えていることを知れば知るほど、大きなあせりを持ったにちがいない。
天武天皇はあるとき六人の皇子を伴なって、吉野に御幸したことがあった。
おそらく天皇は、自分の後継者をきめるに当って、トラブルを避けようという下心を持っていたからであろう。
| よき人のよしとよく見てよしといひし 吉野よく見よよき人よく見つ |
天皇はこう詠んで、皇子たちにお互に二心なきを盟わせると同時に皇后の生んだ長子に帝位を継がせる方が順当であり将来の紛争の種にもなるまいと思われたにちがいない。
そうした天皇夫妻の願いがかなって、やがて草壁皇子は無事立太子をとげ、ぼつぼつと朝政も見るようになったが、大津皇子の才幹も父天皇の心をいたく動かした。
このような日々の中に、美しく逞ましい青年と成長した両皇子の間には、石川郎女(いらつめ)をはさんで恋の鞘当がおこった。
郎女は当時の宮廷で、容姿と才能をもてはやされた才媛であったのである。
恋に胸を焦した草壁皇子は、郎女に次のうたをおくった。
| 大名児を彼方(おちかた)野辺に苅る草(かや)の 束の間もわれ忘れめや |
この皇子の切々のおもいをこめたうったえも彼女の黙殺に逢ってみのらない。
一方大津皇子の方は、
と呼びかけると、今度はうれしい答歌が来た。
| 吾を待つと君が沾れけむあしびきの 山の雫にならましものを |
正に触るれば散らん風情である。
恋はいつどんな場合にも理性を超えて乱離に人を導く。
大津皇子は虚心でも、皇子の身辺にはわざわいがしのびよっていた。
皇后は大津皇子の行動に細心の注意をはらいつつ、津守連通という陰陽道の大家に、スパイの役を命じていた。
一方天武天皇は側近の読経、礼拝の甲斐もなく五十六歳という働き盛りで病歿した。
しかもその没後一ヵ月も経たずして、大津皇子は謀反の罪を問われてあえなくも死刑に処せられればならなかった。
皇子はこの電光石火の処置に抗することもなく、初冬の風の冷たい夕ぐれの処刑の場に立った。
二十四歳の花盛りであった。
| 百伝ふ磐余の池に鳴く鴫(しぎ)を 今日のみ見てや雲隠りなむ |
あわれはかなき辞世と共に、才気縦横、多情多恨の皇子はあの世に旅立った。
后の山辺皇女は、この報せに髪ふりみだし、はだしのまま背の君のなきがらに縋(すが)りつき、あとを追って殉死してしまった。
そのとき皇子の姉君で、伊勢の斎宮をつとめていた大来皇女は、はるばると大和に上ってきた。
| 磯の上に生うる馬酔木を手折らめど 見すべき君がありといはなくに |
と詠って弟の死を悲しんだ。そしてさらに、
| うつそみの人なる吾や明日よりは 二上山をいろせと吾が見む |
と、はるかなる西の二上山を眺めやって慟哭するのであった。
今日も大和河内のどこからも望まれる山、四時に吹く嶺の風の音は、大津皇子の悲啾(ひしゅう)そのもののような気がする。
謀反があらわれて死を賜ったこの事件は古代史の謎である。
のちの持統天皇として藤原宮に君臨された女帝、万葉にみるような美しい歌をよんだ女性で、どうしてあんな処刑のむごたらしさを敢えてしたのであろう。
二上山頂からまた麓の道に引返すもよいし竹の内街道に下ってもよい。
山麓の里はいつもしづかなたたずまいを見せている。
野や道の辻には石の仏も微笑みかけ、木々の梢には四季の鳥のうたごえもにぎやかである。
top
****************************************
|