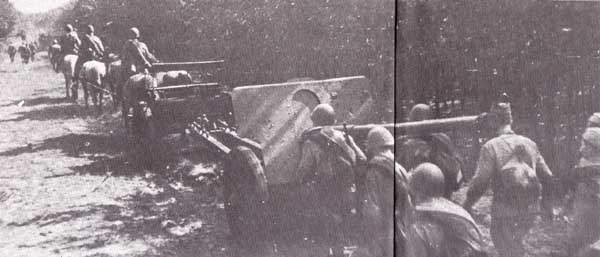|
****************************************
Index 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10
1 第二次大戦前夜の各国砲兵
新式の後装式加農砲〔弾丸を砲尾からこめる方式のカノン砲〕は、一八八〇年〔明治十三年〕頃から使われてきた。
液・気圧式駐退機〔後出〕、砲架装着照準具、金属製薬莢〔やっきょう〕、あるいは一般にいう速射性能などをもった野戦用砲架ができたのはさらにあとで、二十世紀にはいるころからである。
この種の火砲が初めて使われた大きな戦争は、一九一四〜一八年の第一次大戦であったが、著者が第二次世界大戦の火砲についてこの本を書き始めた理由は、この二つの戦争のあいだに横たわる根本的な違いを指摘するためである。
まず第一に、第一次大戦は砲兵が技術的にようやく“ゆりかご”から這い出し始めた時期で、戦術的用法においては「我が剣の指すところを撃て」というように、まだ極めて幼稚な時代だった。
また、先の見通しのきく砲術家の要求は、火砲メーカーの能力をはるかに越えてもいた。
|
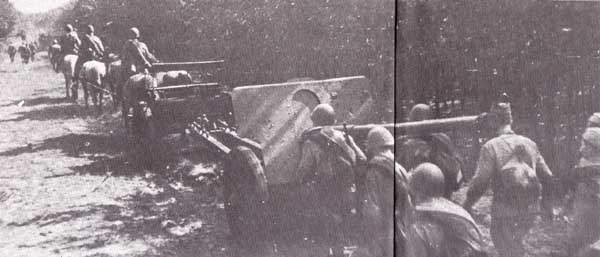
ソ連軍76ミリ加農砲:第二次大戦の初期にはおおくの国が馬にひかせた砲をつかっていた
|
1 砲兵の黄金時代、第二次大戦 top
第二次世界大戦中に、構造、戦術、操法、通信および一般的な専門技術が非常に進歩を遂げた。
その結果、第一次大戦は砲兵戦であったとよくいわれるが――事実、いくつかの大きな戦闘では、参戦した部隊の三分の一の兵力にもおよぶ多くの砲兵支援が行われた――
一方、第二次世界大戦では、実に各時代および各国の砲術家による六〇〇年にわたる研究の成果が、最高度に発揮されたのであった。
戦後、ミサイルや核弾頭の出現によって情況がかわったが、第二次世界大戦は、砲兵隊員にとっては黄金時代となった。
将来再びこのように、多種多様の火砲が使われることはないであろう。
また戦争で、このようにめざましい役割りを、砲兵が演じるこ伴いであろう。
さらに、一九四五年にいたる一〇年間ほど、砲兵の英智と技術がたよられるこ伴いであろう。
この理由だけでも、第二次大戦中の砲兵の改良および装備は、研究に値するものであり、我々は二度とそれに匹敵する研究テーマをみつけることはできないであろう。
最も、素人には、未来戦について何ができるかを予見したり、何が不足しているかを推し量ることは、むずかしいことではあるが、その素人から軍人は、過去の戦争にたいする訓練について、しばしば非難をうけることがある。
だが、正確に観察すれば、軍人は、最新の教訓にてらして、標準技法を常に改善しようと努力しているのである。
|

イタリア戦線で戦闘中の英軍25ポンド砲:
この砲は旧式のもので砲口制退器はついていない。後方にみえるのは弾薬車である
|
2 第一次大戦で貴重な教訓 top
第一次大戦は、砲兵にいくつかの新しい教訓をもたらした。
歩兵に近接して行われる弾幕射撃では、これまでの野砲が必要とした精度より、はるかに高い精度が要求された。その結果、射撃による砲身の磨耗や、弾丸の初速と命中精度との関係などが研究された。
しかし、風・気温・気圧・湿度など、各種の気象条件が弾道にあたえる影響は予知できなかった。
西部戦線においては、通信および射撃統制についてあらたな問題がおこり、まれなことであるが、砲からみえる目標にたいしては肉眼による直接照準射撃が行われた。
また、一方では射撃目標として、他方では観測の補助手段として利用できる航空機が出現した。
戦車も同様に射撃目標として戦場に現れ、同時に火砲に大きな機動力をあたえるようになった。
これらの諸問題は、戦時中から戦後にかけても研究されたが、多くの研究は戦争につきものの資金不足によって妨げられた。
さらに研究の難航に拍車をかけたのは、終戦による多くの設計チームの解散で、とくに一九一四年から一九一八年にかけて編成されていた「シンク・ファクトリー」〔考える工場〕の解散は決定的だった。
たとえば、対空射撃や射撃統制法の理論的解明にかんする多くの研究開発は、イギリスの大学から集められた数学者や物理学者たちと、そのときすでに軍人になっていた同程度の知識をもっている人たちとによって実施された。
戦争が終ると、軍人の多くは除隊し、教授連もそれぞれ平和的な研究をするため、再び大学にかえっていった。
少数の軍人が、あたえられた資金でベストをつくしていたものの、世界共通の傾向として一九二〇年代は、この種の研究は沈滞ぎみであった。
たとえば、二〇年代の末期、英戦車学校の校長は、戦車に搭載する重機関銃の実験を一年間行うため、わずか五〇ポンドの要求をする状態であった。
研究開発費が一〇〇万ドル単位のこんにちの情況からは、重要な問題にその程度の費用を割りあてたことは、信じがたいことであるが、当時はかろうじて研究がつづけられているという状態であったのだ。
3 米砲兵の基礎を造ったウ理論 top
ときたま、古い専門誌をひらいているとき、試験場や実験施設をおおっていた霧が、パッと晴れるように、じれったい思いをしていた将来へのひらめきがあたえられるものである。
こうして、一九三一年〔昭和六年〕に、アバディーン試験場〔米国〕は、完全自動制御四インチ〔約一〇センチ〕高射砲を発表した。
この砲は、兵員はできるだけ早く弾薬を薬室に投げ込むだけで、照準は中央射撃統制所から、リモート・コントロールされる動力駆動装置によって制御されるものであった。
この兵器が戦闘部隊の手にわたるまでには、さらに一三〜一四年かかった。
また一九二九年、イギリス陸軍は、実験的に編成した機甲部隊に自走砲を装備した。
これは、一九四〇年代に採用されたものよりも、その基本設計においてはすぐれたものであったが、この構想は研究費不足という理由で採用されなかった。
余り目だたないが、長い目でみてはるかに重要であったことは、気象学、音響距離測定法〔注〕、測量、射撃統制法、ラジオおよび既存の牽引車の牽引力などの諸問題の研究成果であった。
〔注=砲音のつたわる速度から敵の砲位置を求める方法=音源標定法〕
一九一八年に第一次大戦の戦火がおさまるまでに、各国は砲兵幕僚に第一次大戦の戦訓に基いて、次期火砲の仕様を研究作成させていた。
なかでも、最も徹底した研究は、おそらく米陸軍によって始められたものであろう。
これを担当したのは主宰者ウィリアム・ウェスターベルト准将の名前をとったウェスターベルト委員会であった。
この委員会は、何がよくて、何がわるいか、戦時装備品で何が不足しているか、また、将来装備したいものは何かなどについて、イギリス、フランス、およびアメリカの砲兵隊員に質問をした。
一九一九年、委員会はその結果を発表し、アメリカ陸軍の将来の砲兵について、口径や希望する特性などの勧告を行った。
これが、その後、三〇年間にわたって米軍砲兵の基本的な方針となった。
事実、ウェスターベルト理論は、最近二〇年間、NATO〔北大西洋条約機構〕の兵備理論に強い影響をあたえたのだった。
4 敗戦が幸い、ドイツの火砲開発 top
ドイツでは、火砲の設計や開発は、常に火砲メーカーにたよっており、軍は射距離、弾丸重量、火砲重量などについて要求するだけで、メーカーが要求条件の範囲内で、おもうように研究開発する体制をとっていた。
普通、仕様書は二、三社にだされ、試作されたいくつかの火砲をテストして、どれを採用するかをきめた。
第一次大戦後のドイツでは、ベルサイユ条約の各種の制約により、火砲の開発は困難であった。その第一は陸軍の兵力の制限、第二には火砲製造工場の制約であった。
たとえば、クルップ社〔ドイツの代表的な重工業会社〕は、口径一七センチ以上の火砲の製造を禁止され、もう一つの大きな火砲メーカーであるラインメタル社は、口径一七センチ以下の火砲さえ製造を禁止された。
両社は、これらの制限をごまかすため、外国の会社と秘密協約をむすんだり、あるいは外国に名義だけの会社を設立し、その社員としてドイツの技術者が外国にでかけて、火砲の製作にあたったりした。
だがある意味では、この制限はドイツによい転機をあたえた。
すなわち旧式となった莫大な武器や弾薬のストックをかかえて戦後をすごすかわりに、ドイツ陸軍や設計技術者たちは、事実上白紙の状態から出発できたからである。
火砲メーカーは、現実主義であったので、どこかで、いつかは戦争がおこるであろうということをよく知っていた。そして、メーカーの設計家たちは、設計・分析・評価およびこれまでのものを根底からくつがえし、設計しなおすなどの仕事のために温存された。これは多くの面で、見事な成果となって現れた方針であった。
そして一九三三年、ヒトラーが権力をにぎり、ドイツ精神の復興、とくにドイツ国軍の再建にふみきったとき、ドイツの火砲メーカーは、海外で研究をすすめていた枝術者たちをよび戻し、紙のうえの成果を鋼鉄にうつしだしたのである。
|

1944年1月、河川の氾濫で水ぴだしになった英軍180ミリ榴弾砲の砲列陣地
|
5 火砲生産もたつく米英 top
ソ連は、常に砲兵を重視してきた国で、第一次大戦中におこった革命 〔一九一七年〕により、多いにくるしんだが、ロシア軍の砲兵装備品の多くは使用可能な状熊でのこされた。
一九二五年〔昭和十四年〕に、ソ連の設計技術者は、最初の野戦砲を製造し、その後彼らは開発しつづけたが、国民の秘密保持観念がつ良かったため、この国から秘密かもれることは極めてすくなかった。
本書でもソ連の兵器にかんする部分が少ないのは、このためである。
ドイツが軍の再建に乗出すとまもなく、他のヨーロッパ諸国も、自国の兵器に注意をはらい始めたが、イギリスはそのころちょうど、新型野戦砲はどのようなものであるべきかを決定し、新型高射砲および対戦車砲の大綱を決定したところであった。
しかし、設計は承認されたが、部隊交付用として、まずいくつかの火砲をつくるのに、正式の手続きが何もきめられていなかったので、試作、テスト、改造にたっぷり一年かかり、それからさらに一年間のテストを行って、やっと量産用の設計書が承認され、メーカーが決定された。
戦雲がせまり、設計書は全力生産のため、製図室からまっすぐに工場におくられたが、最高生産量に達する前に、第二次大戦に突入してしまったのである。
アメリカは、一九一七〜一八年に、第一次大戦にまきこまれたが、火砲製造の経験のない会社で大量生産をはじめるという困難があったために、AEF〔米欧州派遣軍〕はイギリスおよびフランスの砲で装備した。
その後ウェスターベルト委員会は、一〇五ミリ榴弾砲を設計し、採用するよう勧告した。
設計はよくできており、さっそく、長期にわたる研究が行われた。
この一〇五ミリ榴弾砲は一九三八年、ついにテストにまでこぎつけ、一部改造をくわえて部隊の手にわたったのは、一九四○年であった。
ただちに量産が開始され、軌造にのったのち、ちょうど第二次大戦にまにあったのだった。
第一次大戦でAEFの砲兵司令官であったスノー少将が筆をとり、一九四○年に出版された本をみると面白い。
スノー少将はこのなかで、一九一七年における生産準備のおくれや、このことが陸軍装備品におよぼした結果などをのべ、とくに火砲の不足についてくわしくのべている。
もし彼がこの本を数ヵ月早く刊行していたならば、その教訓は、もっと大きな影響力をもったと思われる。
だがスノーの教訓は、かの有名な、チャーチルの戦時生産構想に生かされている。
つまり“最初の年はゼロ、二年目はチョロチョロ、三年目はほしいだけ全部”の名セリフである。
6 平時の基礎研究は“銀行預金” top
兵器の基礎研究と生産の関係は、銀行預金に似ているといわれている。
平和なとき、基本的研究として預金しておき、戦時には預金しておいたものを、火砲設計書の形でひきだすからである。不渡り小切手を書いて、破産においこまれるようなときでも、基礎預金があればすくわれるだろう。
戦争直前には、各国とも多くの預金をもっていたが、戦争中に多額がひきだされた。
交戦国はみな、その支払い能力のギリギリまでひきだした。
この例えを言い換えれば、次のようになる。
戦争の初期は、戦前に準備された兵器で戦われたので、この時期には研究こ孜術が、戦闘部隊の要求よりも先行していた。
これが預金にあたる。
しかし戦争が進行するにつれて、実戦部隊の要求が研究・技術においついて、その距離をちぢめていった。
つまり預金のくいつぶしである。
こうして第二次大戦が終ったとき米英両国とも、預金が底をついていたのである。
戦後、両国は研究計画を大幅に縮少し、勝利の原動力であった多量の兵器を廃棄した。
そして関係者は、再び基礎研究にもどった。
もう一度、預金をふやす努力を始めたのである。
こうした推移をたどったため、朝鮮戦争は、すべて第二次大戦の兵器で戦われた。
第二次大戦終結から朝鮮戦争までの六年間に、それらの兵器にかわるものがなにも生産されていなかったためであった。
そして朝鮮戦争の末期に近いころ、研究の成果の最初の現れを示す兵器が出現し始めた。
それいらい、研究の成果は、少しずつ現れつづけた。
一九三九年に第二次大戦が始まったとき各交戦国は、当面する戦争に一応適応した兵器を装備していた。
中には第一次大戦時代の砲もあったが、平均してみればけっしてわるいものではなかった。
その当時の対戦車砲は、軽量であったが、その時代の戦車の装甲にたいして十分な撃破力をもち、高射砲は、時速約三五〇キロ、戦闘高度約六〇〇〇メートルの性能をもつ当時の爆撃機に対抗できるものであった。
重砲は、一九三〇年代の中期および末期に、長距離爆撃機が重砲にかわる見こみがつ良かったので、低調であった。
7 ドイツ、砲兵機械化に先進 top
しかし、一九三九年の砲兵器材は、弾薬が改善された第一次大戦初期のものとくらべ、それほど大きな変化はみられなかった。
第一次大戦で使用された弾丸の大部分は、榴霰弾〔りゅうさんだん=中に鉛の震弾(弾子)が入っていて、時計信管により空中で爆破させ、人馬を殺傷する弾丸〕であった。
第一次大戦の経験から、当時行われていた塹壕〔ざんごう〕戦では、榴霰弾はよく訓練された敵には効果が少なく、榴弾〔鋼製弾体で、中にTNTなど高性能炸薬が入っており、破裂するとその破片で人馬、器材に損害をあたえる弾丸〕の方が、はるかに効果があることがわかった。
従って榴霰弾は、世界各国で一九三六年までについに廃止され、第二次大戦には、各国陸軍のほとんどは、榴弾をもって戦場にむかった。
例外は、ソ連であった。これは一九一七年の革命まで、東部戦線という他の戦線とややおもむきをことにした戦況で、戦っていたためと思われるが、ソ連軍はいぜんとして、榴霰弾を信頼していた。
さて、第二次大戦前の一九三〇年代の後半、火砲の牽引についてはどの程度近代化されていただろうか。
この時点でも、多くの国の砲兵は馬で火砲を牽引していた。
ただドイツ軍だけは、大部分を機械化していた。
ドイツ砲兵はクラウス・マッフェイ半装軌車〔ハーフ・トラック〕を使用していた。
この牽引車は野戦砲、対戦車砲、高射砲など各種火砲に使用されたが、数量は十分とはいえなかった。
英軍は野砲の牽引に「クワッド」〔牢獄〕とよばれる四輪車を使用していた。
これは砲班や弾薬を浴績する四輪駆動の特殊な外形のトラックである。
小火器にたいする防弾力があるといわれたが、実際はそれほどでもなく、また防弾性を意図して製作されたものでもなかった。
防弾性があると思われたのは、一見、装甲車のような外形のためである。
英米の重砲は、普通のトラックを改造した「マタドール」〔闘牛士〕トラックやスキャメル・トラックで牽引された。
米軍は野砲牽引用に二・五トンのGMC〔定員二〇人の軍用トラック〕を使用した。 |

英軍の野砲牽引車「クワッド」:
1944年4月マンチェスター市のパレード中の25ポンド砲
|
これは砲が配置されたあと、一般輸送車としてつかえる利点があったが、ときにはそれが欠点ともなった。
高級司令部などがほかの用事に使いすぎ、いざ砲を移動させようとするときに間に合わない、ということがおこりがちだったからだ。
それが、英軍砲兵が特殊な牽引車「クワッド」を使っていた一つの理由でもあった。
top
**************************************** |