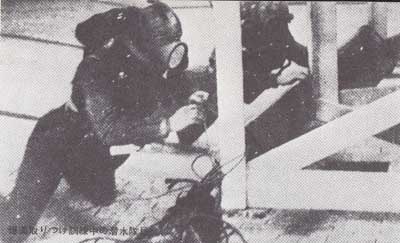|
****************************************
Index 1
2 3 4
5 6
7 8
3 独戦艦「ティルピッツ」を撃破
一九四二年六月、英海軍特別作戦本部(かねてから、イギリス本国より指令を発して、ヨーロッパ・レジスタンス運動を組織し、こっそりと秘密諜報員、武器、その他の資材を提供していた)に、潜水艦隊司令長官から申し入れがあった。
1 漁船に曳かれてノルウェーヘ top
それは、四万トンのドイツ戦艦「ティルピッツ」が、ノルウェーのトロンヘムス・フィヨルドに碇泊中なので、今のうちに攻撃を加えたいから手貨してくれ、というのであった。
本部は、あらゆる援助を惜しまないことを約束した。
まず、二隻の「チャリオット」を漁船で曳航して、シェトランド諸島のある港から出発させる計画が立てられた。
この漁船は「チャリオット」の乗組員や、その装備類を載せて、ノルウェー水域をドイツ軍管理の目をかすめて通り抜け、前もって示し合わせておいたフィヨルドの地点で、彼らを下船させ、攻撃を開始させる、という手筈を整えた。 |

「チャリオット」の最初の攻撃目標:
ノルウェー港内のドイツ艦隊「ティルピッツ」
|
ノルウェーの地下工作員だちとは、たえず秘密情報を交換し合っていたが、計画の実行は、延期につぐ延期で、ついに絶望にも近い気持ちに包まれるようになった。
ある報告によると、「ティルピッツ」はすでに出航したあとだ、ということだった。
天候は、悪化の一途をたどりつつあった。しかも、商一面に水のはりつめる冬は、刻々近づいてきている。
十月二十六日朝、ついに意を決した彼らは、シェトランドをあとに出航していった。
二隻の「チャリオット」を曳きながら、船が港を出て行くとき、桟橋の端に立って、強風にあおられながら、船に向かってさかんに手を振っている、“ちび公”フェル中佐のほっそりした姿も眺められた。
この漁船「アーサフ」は、ノルウェー海軍のレイフ・ラーセンが指揮をとっていた。
彼にとっては、これが占領下の、母国ノルウェーヘの初航海ではなかった。
彼は、有名なシェトランド乗合船”の船長をしていたこともある。
この船は、あちらこちらに秘密工作員を送り届けたり、いろいろな予備偵察をしたりして、かなりの旅を続けたものだった。
「アーサー」の乗組員たちも、全員ノルウェー人だった。
「チャリオット」の乗組員は、一隻がブルースター中尉とブラウン一等水兵、もう一隻は、クレイグ機関兵曹とエバンス一等水兵の予定だった。
テブとコーザー両一等水兵は、他の四人の助手をつとめ、いざというときの交替要員でもあった。
漁船の貨物室には、泥炭塊を山のように積み込んであった。
そして、万が ベドイツの巡視艇に見つかって停船を命じられた場合、イギリスの隊員たちが、身を隠すことができるように、その泥炭の山の中心部は、くりぬいてあった。
ノルウェー海域では、こうした検問は、まず間違いなく覚悟しておかなくてはならなかった。
そのため、乗組員たちは全員、たくみに偽造した身分証明書を持っていた。
「チャリオット」の乗組員たちは、「ティルピッツ」攻撃にそなえて、徹底的な予備演習を繰返していた。
そして最後には、イギリス戦艦「ロドニー」を仮想敵艦に見立てて攻撃を加えるという、実戦さながらの演習まで行なわれるようになった。
「ロドニー」が選ばれたのは、「ロドニー」の碇泊していた湾が、内側へ深く切れこんでいて、ちょうどノルウェーのフィヨルドによく似ていたからである。
もしこの攻撃を真剣にやっていたら、間違いなく「ロドニー」は撃沈されてしまっていたろう。
この訓練中に、「チャリオット」を、特別製の留め金で「アーサー」の船底にしっかりと固定しておけば、曳航するにも、目立たなくてすむことがわかった。しかし実行に移されないまま、ノルウェーヘ向けて出航することになったのである。
2 流された二隻の「チャリオット」 top
この作戦計画には、「チャリオット」の隊員たちが、攻撃を終えたあとの脱走経路まで含まれていた。
「アーサー」があらかじめ打ち合わせておいた地点に着くと、そこで隊員たちは下船することになっていた。
陸上にあがった隊員たちは、レジスタンスの工作員たちに出迎えられ、彼らが用意した車で、ノルウェー国境を突破して中立国スウェーデン領内に入り、ついで、イギリス本国へ送り帰される手筈になっていた。
だが現実には、そううまく、ことが運ぶものではなかった。
「アーサー」は、たえずすれちがう敵の巡視艇の検問を、なんとか切り抜けながら、やっとの思いで、ノルウェーの沿岸海域に入っていった。
目ざすトロンヘムス・フィヨルドの湾内に入っていったとき、「アーサー」にドイツ巡視艇の一隊が、乗り込んできた。
だが、イギリスの隊員たちは、泥炭の山の中の聖域に身を隠していたので、ことなきを得た。
ドイツ巡視隊員は、そのまま立ちさっていった。
彼らは、「チャリオット」が吊るしてある船底の部分まで調べる気など、さらさらなかった。
本当に危ないところだった。はるばる遠征してきた努力もこれで報われたというものである。
ところが、全く奇妙な話だが、ドイツの巡視員たちは、イギリス隊員発見のチャンスを、みすみす逃してしまったものの、実は知らず知らずのうちに、大きな手柄をたてていたことに、まるで気がつかなかったのである。
巡視隊一行の、船内検問が終わった直後、ドイツ海軍の一隻の軍艦が、「アーサー」のすぐかたわらを快速で通り技けていった。そのとき起きた横波をもろに受けて、「アーサー」の船体は、大揺れに揺れた。
そのあとに起こった悲劇的なできごとについて、ラーセンはこう報告している。
「本船が縦揺れを起こしたとき、船底に曳航している二隻の『チャリオット』が、ともにうしろへぐいと引かれるのが、手にとるように感じられた。
次の瞬間、そのうちの一隻が、本船のスクリューに激突した。本船が最初の横波をもろに受けて、船改が持ちあがったとき、二隻の『チャリオット』をつないでいた鋼索がぴんと張りつめ、ついで本船の船改が下がったときに、その鋼索がゆるみ、それからまた、ぴんと張りつめていったらしい。
つまり、本船が縦揺れ運動を繰返したために、ついに曳航索が切れ、その結果、『チャリオット』がどこかへ流されていってしまったことは、間違いないように思う」
3 戦艦の目前で攻撃を断念 top
「アーサー」は、そのまま航海を続け、安全な場所までやってきて止った。
そこでエバンス一等水兵が、様子を調べるために、船の底に潜ってみた。彼の報告によると、曳航索と留め環は、そっくりそのままの状態で残っていた。が、「チャリオット」の姿だけは、どこを探しても見当たらなかった。目標の敵艦を、指呼の間にとらえながら、どたん場にきて思わぬ不運に見舞われたばかりに、彼らはついに、敵にとどめの一撃を与えることができなくなってしまった。
「チャリオット」の乗組員たちは、なんとかして陸にあがり、そこでレジスタンスの工作員たちが用意してくれた車に乗り込みたいと考えていた。しかしラーセンにいわせると、この潮の流れの激しい荒海を突っ切って予定の上陸地点に到達するのは、とても無理だった。
そこで、結局は、別の地点を探し出して上陸したが、もちろんそこは、何の打ち合わせもしていない場所だったので、迎えの車がきているわけではなかった。隊員たちは、二組にわかれることにした。
二組とも、最後にはやっと、スウェーデンにたどりついたが、そこに達するまでには、何回となく危険な目にあった。なかでも不幸だったのはエバンスで、国境近くで敵と撃ち合って重傷を負い、ついには捕虜になってしまった。
あとでわかったことだが、彼は、壁に向かって立だされ、ヒトラーの命令により銃殺されたという。
残る三人は、スウェーデンでおもて向きは埋葬されたということにして、母国イギリスヘ帰還した。
|

訓練中の英潜水艦「ふとっちょの兄貴」
|
4 X艇による水中攻撃計画 top
この隊員たちの試みが、失敗したからといって、イギリスは決して、戦艦「ティルピッツ」の水中攻撃計画を、放棄したわけではなかった。
今度はX艇を用いて、この目標を攻撃する計画が立てられた。
しかし、「ティルピッツ」は、最も近いイギリスの基地からさえ、一六〇〇キロも離れた地点に碇泊したのである。
はるか遠く離れた作戦現場に、X艇を持ち込むために、艇を潜水させたまま、“ふとっちょの兄貴”と呼ばれる普通型の潜水艦が、曳航していった。
しかし、この輸送方法をとるためには、各X艇ごとに、別任務の二組の乗員を乗り組ませる必要があった。
一組は、“輸送員”と呼ばれるもので、曳航中もX艇に日夜乗り組んでいた。
彼らの仕事は、いざ発進というときに、いつでも“作戦員”に引き渡せるように、つねに艇を、最高の作動状態に整備しておくことだった。一端発進してしまえば、艇が自力で、目標めがけて突進してゆくばかりであった。
輸送員たちはまた、海上が大しけのときでも、あるいは真っ暗闇の水中でも、艇の曳航索に少しでもたるみがでないように、たえず気を配って、監視していなくてはならなかった。
そのほか、X艇の操縦、潜水、浮上などは、すべて母艦“ふとっちょの兄貴”と、調子をあわせなくてはならなかった。
母艦とX艇とのあいだは、もちろん交信手段はあったが、ある輸送員の指揮官は、こういっていた。
「我々は、いちいちそんなものに頼らずとも、ほとんど勘ですませましたよ。それがまたぴたりと当たったもんです」
5 戦艦「ティルピッツ」ついに脱落 top
今度の計画には、六隻のX艇が参加した。
すなわち、X5、6、7、8、9および10がそれであり、計画意図は壮大なものだった。
そのねらいは、戦艦「ティルピッツ」攻撃のみならず、二万六〇〇〇トンの「シャルンホルスト」、および一万二〇〇〇トンの「ルツォウ」まで、攻撃することにあった。
X5、6および7が「ティルピッツ」を、X8は「ルツォウ」、X9および10が「シャルンホルスト」を攻撃するよう、指令が見せられた。
X艇各一隻ずつを曳航した、六隻の潜水艦からなるこの特殊攻撃部隊は、八昼夜以上の航海を続けた。
この長い船旅のため、ただでさえ過重労働気味だった輸送部員たちの神経は、すっかり参ってしまった。
この果敢な攻撃作戦の戦果は、おそらくはヨーロッパ海域におけるX艇作戦のすべてを通じて、最も勇名をとどろかせた見事なもので、さすがのドイツの誇る戦艦「ティルピッツ」も、ついに、戦列から脱落してしまったのである。
当局からの感状や、攻撃隊員たちの非公式な手記は、当時の模様をいきいきと写し出している。
感状にはこう書いてある。
「イギリス国王は、一九四三年九月二十二日、北ノルウェーのカー・フィヨルドに碇泊中のドイツ戦艦『ティルピッツ』に果敢な攻撃を加え、これを撃破した、わが海軍特殊潜航艇X6、ならびにX7の指揮官ベージル・チャールズ・ゴドフレー・プレース大尉、および海軍予備隊員ドナルド・キャメロン大尉にたいし、その勇をたたえて、ここにビクトリア十字勲章を授与するものである。
敵の泊地に到着するまでには、機雷原を突破し、さらにフィヨルド内を、八〇キロの長さにわたって、航行していかなくてはならなかった。
周知のごとく、湾内は、敵の巡視が油断なく、またその周辺は防潜網、砲台、採音装置などによって防備されていた。この地点に到着するまで、わが基地より、じつに一六〇〇キロの長き航海を要したのである。
これらすべての障害物を排除し、敵艦隊泊地への潜入に成功した、キャメロンおよびプレース両大尉は、危険をもかえりみず、彼らの小艇を操って『ティルピッツ』の近くを取り巻く対潜、対魚雷網をくぐりぬけ、これらの防御網内の位置から、冷静にしてかつ果敢な攻撃を遂行した。
両名がまだ防御網内にあるうちに、敵は熾烈な反撃を展開してきた。このため、両名の脱出は不可能となった。
そこで、プレースおよびキャメロンの両大尉は、艇が敵の手中にわたることを恐れて、艇を放棄し、離脱した。
この挙に移る以前に、両大尉は、部下の艇員たちの安全を期するため、万全の策を講じた。しかしながら、艇員の大多数は、両大尉もろとも、ついに捕虜となった。
この攻撃作戦を通じて、これら小型舟艇は、その威力を遺憾なく発揮した。
その攻撃に際しては、かかる小型艇にとっては、避け得ざる危険にも幾たびか遭遇し、碇泊中の主力艦隊防衛のために、敵が人智をしぼって案出した、あらゆる障害物にも直面した。
この果敢にして成果をおさめた攻撃において、キャメロンおよびプレース両大尉が、敵の直前で示した勇気、忍耐力、さらに危険をかえりみぬ気概は、まさに最高殊勲に値するものである。
国王はまた、『ティルピッツ』攻撃を成功に導いた際の、勇気、熟練および果断を賞して、海軍義勇予備隊員ロバート・エイトキン中尉および海軍義勇予備隊員ハドン・ケンダル中尉にたいして殊勲章を、ならびに四級機関技士エドムンド・ゴダードにたいして顕功章を、それぞれ授与するものである」

ケンダル中尉 |

ロバート・エイトキン中尉 |

機関技士エドムンド・ゴダード |
|
6 殊勲の海軍士官二人 top
ドナルド・ギヤメロンとゴドフレー・ブレースは、ともに正規の海軍士官で、終戦当時までイギリス海軍に籍をおいていた。
不幸にも、キャメロンはその後、病気のために死んだが、プレースは、本書執筆中の現時点で海軍少将である。
当時の攻撃の模様をきかれたとき、プレースはもっと個人的な話をしてくれた。 |

1943年9月、「ティルピッツ」攻撃に成功したX6およびX7艇の指揮官たち:B・C・G・プレース大尉(左)とD・キャメロン大尉
|
「こうした特殊作戦の場合、無事に帰還できる確率は、他の作戦とくらべて大きかった。
というのは、訓練は長期にわたって、しかも徹底的に行なわれ、艇も攻撃後は、自力で走って帰れるように、設計されていたからだ。
しかし、今回のような、今まで例をみない全く新しい型の戦闘では、あらゆる事態に対処できる計画を、初めから立てることはむずかしかった。
我々が直面した難問の一つに、ちょっとした機械の故障があった。この故障の原因の一部は、作戦現場に着くまでぶっ通し一〇日間も航海を続け、その間、毎日二三時間も、水の中に潜っていたということにもある。
実際の攻撃は、白昼、ドイツ北方の、最も厳重に防御された、ノルウェー・フィヨルド内の碇泊地で行なわれた。
攻撃は、本質的にはいたって簡単なものだった。
問題はただ、『ティルピッツ』の艦底にもぐりこんで、時限信管つきの、強力な機雷を仕掛けてくることだけだ。
私自身にとって苦労の種だったのは、むしろ、いかにして防潜網を突破するかということのほうだった。
ここの防潜網は、我々がかつて予想していたよりは、けるかに複雑にできていた。
しかし、私はこの防潜網の下をかいくぐって、攻撃に移ることに決めた。
ところが、この網の下をくぐりぬけるのに、予想以上の時間かかかった。
実のところ、この隙間もなく張りめぐらされた防潜網に邪魔をされて、私は、攻撃後ついに脱出できなくなってしまったのである」 |
同じくこの攻撃に参加したドナルド・キャメロンも、彼の立場から、謙虚にもこう述べている。
「なんとも、ちぐはぐな気持ちだなあ――これが攻撃前夜、我々のうけた実感だった。
いま、我々は敵の水域のど真ん中にいて、明日は“でか野郎(あるいは女郎)”をやっつけようというのに、耳につけたイヤホンの片方では、BBC放送の番組を聴き、もう一方では、我々の頭上をうろつきまわっている舟の音に、耳をすましているのだ。
私が悩まされたのは、機械の故障の続出だった。艇の潜望鏡には水が入り、攻撃用爆薬もまた、水びたしになってしまった。
そのために、艇の平衡を取ることさえ難しくなり、船は一五度傾いてしまった。
それでも、我々はなんとかして、外側の防御網をくぐりぬけることができた。
しかし、それも的確な判断力や技量によったというよりは、むしろ、幸運にめぐまれた結果だった。
そのうち、いつのまにか、敵艦のまわりに張りめぐらしてある鋼線網の、すぐ傍までやってきていた。
幸いなことに、ごの厳重な防御網の一部が、小型舟艇の出入り用にあけてあった。
あとで知ったことだが、この通路は『ティピッツ』や、その護衛艦へ行き来する舟艇が通る三○分ほど前に開かれていた……」
7 除かれた連合軍輸送船団の脅威 top
「……我々は、この隙間からうまく中へ潜りこんだが、さていよいよ攻撃に取りかかろうというときになって、海図にも載っていない浅瀬に乗りあげ、ついに、敵に姿を発見されてしまった。
『ティルピッツ』艦上のめざとい歩哨は、早速当直将校のところへ飛んで行って大魚出現の報を注進するにおよんだ。
このため、『ティルピッツ』全艦に警報が発せられて、大騒ぎが持ちあがった。
実は、こんな特殊な軍港内に、大魚が住んでいるわけなど、絶対にありえないことはわかっていたので、この歩哨は、馬鹿もやすみやすみ言えと、そのときは叱られた。
だが、騒ぎはつぎからつぎへと広まって、やがて艦内は、異常な雰囲気に包まれていった。
浅瀬に乗りあげた瞬間、運転装置が作動しなくなってしまったので、我々は全く盲目も同然に、ただ防潜網の内側で、あがき続けるばかりだった。
もはや水面に浮上して、『ティルピッツ』に攻撃をかける以外に、手はなかった。
敵の弾幕のなかをかいくぐりながら、我々は五〇メートルの距離から、『ティルピッツ』に肉迫していった。
ついにその傍に、艇を横づけにすると、一時間の時限信管つき機雷数個を、海中へほうり込んだ。
機雷投下後、艇を捨てて脱出する方法をいろいろ考えてみたが、艇を敵の手に渡したくはなかったので、結局は、いま投下したばかりの機雷の上に、艇を沈めることに決めた。
我々がこの作業をし終えた瞬間、数隻のモーターボートがやってきて、我々を拾い上げ、『ティルピッツ』 の艦上に連れて行った。
私が『ティルピッツ』上で尋問を受けている最中に、機雷が爆発した」 |
かつてイタリア海軍のデ・ラ・ペンネが、イギリス戦艦を攻撃したときと同じ経験を、キャメロンはドイツ戦艦攻撃に際して味わったのだ。
デ・ラ・ペンネと同様、キャメロンもまた、真実の情報を提供することを拒否した。
もし、キャメロンが正直に告白していたら、「ティルピッツ」の艦長はすぐに出航を命じ、難を逃れることができたであろうからである。
キャメロンはまた、自分の仕掛けた機雷から、わずか数メートルしか離れていない場所に坐って、もし爆発が起きたら一体どうなることかと、様々な不安にかられたにちがいない。
「ティルピッツ」が戦列から脱落したことによって、イギリスや連合軍側の輸送船団にたいする、大きな脅威は取り除かれたのである。
8 挫折したX8艇 top
この困難をきわめた作戦の、他の攻撃部門を受けもった隊員たちは、残念ながら、思ったほどの戦果を収めることができなかった。
X8は、潜水艦「シーニンフ」に曳航されていた。
航行中、その艇首が突然、がっくり下がった。
明らかに、曳航索が解けたのだ。輸送指揮官のスマート大尉は、X8を全力で浮上させ、あわてて甲板に出てみた。
ところが、曳航母艦「シーニンフ」の姿がどこにも見当たらないのだ。
スマートは、どうにかして母艦に接触したいものと、時速三ノットという経済速度で、X艇を操縦していった。
もし、どうしても母艦を発見できなかった場合には、部下の輸送員たちと力を合わせて、目標の敵艦を探しだし、攻撃を加える覚悟をきめていた。
幸いにも、三六時間後に、彼らは「シーニンフ」の姿を発見した。
ただちに、新しい曳航索が取付けられ、彼らは再び、旅を続けていった。
ただ輸送員たちは、疲れきっていたので、オーストラリア海軍のB・マクファーレン大尉指揮下の作戦員たちが、その任務を代わって引受けた。
しかし、これで彼らの災難が終わったわけではなかった。
X8は、そのうち右舷へひどく傾きはじめ、そのために右舷に積んだ機雷が、水びたしになってしまった。
やむをえず、この機雷を海中に捨てることになり、機雷は安全の状態にセットされて、深海の底へ投下された。
ところが、全員が驚いたことには、投下後まだ間もないうちに、その機雷が船尾で爆発を起こしたのだ。
その後、左舷の機雷にも浸水していることがわかり、この機雷も水中投下された。
このときには、二時間の時限信管をセットしておいた。
しかし、この機雷も、X艇がいよいよ攻撃を開始するまで、あとわずか六・五キロという地点で、爆発したのである。
艇からの距離はずっと離れていたとはいいながら、このとても信じられないような水中異変によって、X8は艇内がめちゃめちゃにこわれ、ついに潜水もできなくなってしまった。
艇員たちはすべて「シーニンフ」に移され、X8は放棄された。 |

B・マクファーレン大尉
|
|

「シャルンホノしスト」の進水式に臨んだヒトラー総統(左端)。
この船の攻撃計画はX10の機械的欠陥のため放棄された
|
9 活躍した影の立役者 top
X9は、潜水艦「サーティス」に曳航されていた。
ところが航行中、「サーティス」の乗組員たちが、いつのまにか曳航索が切れていることを発見した。あわててそこらあたりの水面をくまなく探してみたが、ついにX9の姿は、どこにも見当たらなかった。かくて、艇はその乗員もろとも、消息を絶ってしまったのである。
X10は、オーストラリア海軍義勇予備隊員K・ハズペス大尉の指揮のもとに、潜水艦「セプター」に曳航されていた。
この艇は、九月二十日の午後八時に発進し、定められた目標艦めがけて突進していったが、潜水した途端に、いろいろな故障が起こりはしめた。
艇の平衡を保つことが難しくなった。潜望鏡が故障を起こした。
発動機とジャイロ・コンハスが動かなくなった。
ハズペスは海図を調べた上で、フィヨルドの奥まった人目につかぬ小さな入江に艇を移動させ、潜航して、緊急修理にとりかかった(夜は、浮上して魚を釣ったりした)。
ともかくも、一時しのぎの修理を終えた艇は、目標艦に向かって、発進していったが、またしても故障が起きた。そこで再び海底まで降りて、修理をはしめた。
そこは、「シャルンホルスト」の碇泊しているカーフィヨルドから、わずか数キロしか離れていない地点であった。
艇員たちの協力で、X10はなんとか使える程度にまで修復できたが、ハズペスは、他のX艇の活躍の邪魔になってはいけないと思い、X10による攻撃計画を、放棄することに決めた。
X10はおぼつかない船足で、よたよたしながらも公海へでて、そこで生存者救出のために待機しているはずの、潜水艦を探した。ほどなく、潜水艦「スタボーン」と出会った。
この艦は、さきにX7を送り届けてきたばかりだった。
X10の艇員たちは、艦上に迎え入れられた。
結果論になるが、実は「シャルンホルスト」は、当時すでに、こっそりと湾からでていったあとだったのだ。
だから、いずれにしてもX10の航海は、無駄骨だったということになる。
ここぞという場面で舞台に登場してくる作戦員の花やかさにくらべて、輸送員たちは役不足で、その存在はあまりめだたなかったが、その功績を、クロード・バリー大将も、心から褒めたたえてこう言っている。 |

X10の指揮官K・ハズペス大尉

X7上の戦闘員と輸送員。
後列左から、エイトキン、プレース、ホイッタム、フィリップ。前列左から、マジエニス、ラック、ホイットレー
|
「X艇の輸送員たちが、長い、骨の折れる航海によく耐えぬいてきたことは、偉大な賞賛に値する……。
彼らは、作戦を究極の勝利へ導くために、大きな役割を演じた。
かかる行為こそは、関係者一同にとって、海員魂と決断力を示す、またとないすぐれた手本である」 |
10 間違えて大型商船を撃沈 top
ノルウェー沿岸のあちこちに、迷路のように入りくんだ湾のなかに碇泊中の、ほかの数多くの船舶も、X艇から狙われた。海軍義勇予備員“マキシー”ことシーン大尉の指揮するX24は、ウェスト・パイフィヨルドに碇泊中の浮きドックを攻撃するよう、指令を受けた。
X24は、予定どおり攻撃水域まで到着したが、フィヨルド内は、船舶の往き来が過密状態だったので、衝突を避けるために、攻撃を断念せざるをえなかった。
潜望鏡を何度ものぞくことは、きわめて危険だったうえ、なんら価値ある情報も、手に入らなかった。
X艇の空気は急速に汚れはじめ、乗員の体にも、目に見えて悪影響が現われつつあった。
シーン大尉は、もはや“盲目操縦”する以外にはないと決断し、潜望鏡を最後にちらとのぞきこんで、攻撃に移った。
艇は、浮きドックの巨体に沿って、忍びやかに進んでいき、機雷を投下し終えると、あとは全速力で、その曳航潜水艦「セプター」へ帰投してきた。
のちに真相を知って、全員がっかりしたことだが、実は彼らは、浮きドックと間違えて、ドイツの大型商船「バレンフェルス」を撃沈していたのだった。
この船は攻撃目標ではなかったけれど、隊員たちは、転んでもただは起きなかったわけである。
X94の指揮官には、のちに殊勲章受賞者H・P・ウェストマコット大尉が就任した。
彼が、今度は本当に浮きドックを沈めたのである。
ウェストマコットは、当時の攻撃の模様を、気軽にこう語ってくれた。 |

X94の指揮官、H・P・ウェストマコット
大尉。この艇は最後にノルウェー湾の浮きドックを沈めた
|

シーン大尉
|
11 X24の攻撃 top
「このウェスト・パイフィヨルドの水域一帯は、機雷が一面に敷設されていたので、私は、まるで犬の川端歩きよろしく、あっちへよろよろ、こっちへよろよろしながら、艇を操っていった。
できることなら、きまった水路をそのまま進みたかったが、あたりは船の往き来でごったがえしていたので、いつのまにやら、予定のコースのはるか北方まで押しやられていた。
いろいろな理由から、私は潜望鏡の頭だけ水面にに出しておき、数秒おきに少しでも覗いてみるようにした。
とうとうブッデ・フィヨルドの湾口が、視界に広がって見えはじめた。
まず私たちは、監視所、寺院といったような、二、三の建物の確認にとりかかった。
午前九時、私は浮きドックを目撃した。私たちがそのドックの方へこっそりと近づいていくにつれて、水路はしだいにせまくなり、船舶の往来も混雑をきわめてきた。私は、潜望鏡をピストン運動のようにだしたりひっこめたりしながら、浮きドックのまわりをうろうろしていた。
まさにこの瞬間、まるで“いたずら株式会社”でも考えだしそうな、たちの悪い事件が突発したのである。あまり潜望鏡のだしいれが激しかったため、機械が熱をもち、ついに煙を吐きだしはじめたのだ。私たちは、あわてて修理した。
我々は、かなり浮きドックに近づいていた。見たところ、防潜網も目に入らなかった。だが、なんたることぞ、ドックの中はからっぽではないか。ただ、その傍に二隻の小型舟艇がいるだけだった。
浮きドックまであと一〇○メートルという地点まできたとき、ふと私の目に、『バレンフェルス』のマストがうつった。かつて“マキシー”・シーンが、その最後の攻撃で血祭りにあげた、あの商船だ。水面にでたそのマストには、“ Lansam Fahren ”という注意書きがあった。つまり、“徐行せよ”という意味だ。結構だとも。私は、わずか二・五ノットの速度で進んでいたのだから。
午前九時三十分頃、浮きドックの後部の下に潜水して、最初の爆薬を仕掛けた。そのあいだ私は、ドックが動かないように海底に固定させておいた。
それが終わると、今度はドックの下を通りぬけて前部へ向かい、そこでもう一つの爆薬を投下した。この作業が終わったのは、午前十時十五分だった。
いまや身軽になった艇を、一〇〇メートルほど走らせたところで、現在位置を確認し、艇首を下げて潜水、あとは競走馬よろしくウエスト・バイフィヨルドの湾口めがけて、まっしぐらに突っ走っていった」 |
|

水中戦用に採用された各種潜水服や装具をつけたイギリス海軍潜水隊員
|
13 たたえられる「X艇」二隻の乗組員 top
ラムゼー提督の報告には、この二隻のX艇の果たした役割が、次のように説明されている。
「S部隊とJ部隊に、海岸の上陸地点の位置を知らせるために、二隻のX艇を使うことにした。
というのは、S部隊は、あまり東の方へ寄りすぎないようにすることが重要だったし、また、J部隊の受けもち上陸海岸は、輪郭がはっきりしていなかったからである。
これら二隻のX艇は、すでに六月二日から三日にかけての夜出発し、途中まで母艦が曳航して運んだ。
ところが六月五日午前一時、両艇は『侵攻作戦八二四時間延期サレタリ』という通告を受けとった。
そのため、彼らはさかまく潮の流れのただなかにあって、潜水速度のにぶい小艇を、苦心惨憺〔さんたん〕して操りながら、六月六日の夜明けまで、敵地の海岸沖の地点にとどまり続けた。
そして、その日の明け方とともに、正確な位置から海の方へ向かって、懐中電燈の合図の灯を送った。
その光こそ、集結中の侵攻用舟艇にとって、唯一の道しるべとなった。
このX20、およびX23の乗組員たちの示した技術と忍耐力は、まさに偉大なものだったといえよう。
当時の行動について提出した彼らの報告書は、まことに謙虚に満ちた、すぐれた叙述といってもいいほどだが、それを読むと、とてもあの超小型で脆弱な潜航艇に乗り組んで、戦時中の危険きわまりない作戦を遂行した者の書いた航海日誌とは思えず、むしろ、平和時における、潜水艦の水上航海日誌を思わせるほど、淡々としたものであった」 |
真夜中近く、ケン・ハズペス大尉指揮下のX20とジョージ・オーナー大尉指揮下のX23は、指定された任務位置の近くにいた。
Dデイには、Hマイナス二○時から夜明けにかけて、両艇は、それぞれの指定地点から海の方ヘ向かって、色つきの光を点滅して送ることになっていた。
その地点は、敵地の沿岸から約五キロの沖合いだった。
戦車を運んできた先頭部隊は、戦車をおろす地点を時間通り通過し、X艇からの光信号によって、上陸地点は寸分の誤差もなく確認できた。
この侵攻作戦を通じて、あらゆる上陸用舟艇は、敵海岸を発見するのに、さしたる困難も感じなかった。
作戦時間七三時間のうち、じつに六四時間の長きにわたって、潜水したまま待機していた特殊潜航艇X20およびX23は、いまやDD戦車襲撃隊J1とS部隊の上陸用舟艇に向かって、それぞれ上陸地点の位置を知らせる合図を送りつつあった。
二隻のX艇からの誘導燈の光は、接近しつつある上陸用舟艇から、はっきりと見てとれた。
top
**************************************** |