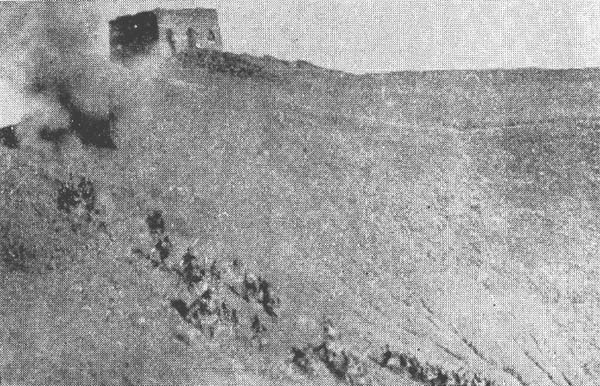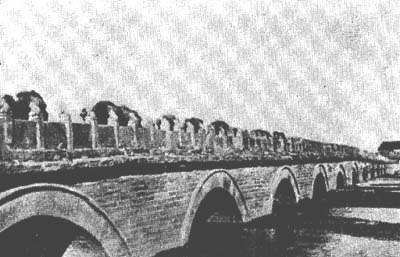|
****************************************
Index 1
2 3
4 5 6
7 8
4 日本との戦争
1 抗日(こうにち)民族統一戦線
top
|
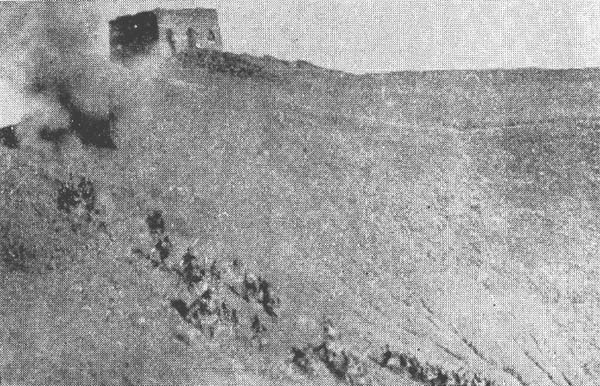
万里の長城をこえる日本軍
|
「満州国」をつくって東北を日本の植民地にしただけでは日本は満足しなかった。
一九三三年の一月に、日本軍は万里の長城をこえ、熱河(ねっか)省に侵入して省都の承徳(しょうとく)を占領した。
熱河省のすぐ南は北京(そのころは北平とよんだ)である。
日本軍は万里の長城をこえようとしたが、中国軍は守りをかたくして、長城の南には侵入をゆるさなかった。
日本は、そこで長城の南にも、「満州国」のように、日本のいいなりになる「政府」をつくろうとした。
そういう政府のことを「カイライ政府」という。
カイライとは糸であやつる人形のことで、人形をあやつるのが日本というわけだ。
毛主席が陝西(せんせい)北部ソピエト区についた一九三五年の十月に、日本は「河北省東部防共自治政府」というカイライ政府をつくらせた。
日本から金をもらった中国人の政治家がこのカイライ政府をつくったのだ。
日本は、「満州国」でアヘンという麻薬をたくさんつくって、これを中国にどんどん運んだ。
世界どこの国でもアヘンはつくることも輸入することも禁止している。
カイライ政府は日本から金をもらっていたから、アヘンの密輸入を禁止しなかった。
日本はさらに、中国人の政治家のなかのもっともくさった連中に金をやって中国北部の五つの省の「自治運動」をおこさせた。
五つの省を「独立」させて「満州国」のようなカイライ政府をつくろうというのだった。
中国の愛国的な人たちは、だまっていたわけではない。
「満州国」に反対して、東北の十四万の中国人が義勇軍をつくって日本軍に抵抗したし、一九三三年には日本軍の熱河(ねっか)侵入に反対して、馮玉祥(ふうぎょうしょう)将軍が共産党と手を結んで綏遠(すいえん)抗日同盟会をつくったし、上海で日本軍と勇敢に戦った十九路軍を中心に福建省に日本に抵抗する人民政府がつくられた。
しかし、蒋介石はまだ日本と戦う気がなかったので、大軍をさしむけて、綏遠抗日同盟軍も福建人民政府もつぶしてしまった。
だが、中国人民はこのような蒋介石のやりかたに強い疑問を持つようになった。
中国の国土が次々に日本軍に侵略されて植民地になってゆくのに、蒋介石政府はどうして中国人の仲間を殺す内戦ばかりやっているのだろうか?
一九三五年の末になると全国の学生や文化人は、蒋介石の政府にたいし、日本と戦うように要求しはじめた。
十二月九日の朝早くから、北京の学生は大デモ行進をおこなった。
「日本帝国主義打倒!」「すべての内戦をやめて、共同して敵にあたれ」「中国北部五省自治反対」と書いた旗やのぼりが冬の寒空にはためいた。
しかし蒋介石政府はデモ隊に消防ポンプで水をぷっかけ、警官は鞭(むち)と警棒でなぐりかかり、学生たちを北京の城門の外へおしだしてしまった。
北京の運動は全国にひろがった。
五四運動のときのように学生がまず立ち上り、新しい雑誌がたくさん発行された。
これらの抗日運動を指導したのが中国共産党だった。
一九三五年の八月一日に、モスクワにいた中国共産党の代表は、「抗日救国のため全国の同胞に告げる」という題の宣言を発表した。
それは、国民党の軍隊が赤軍への攻撃を止めさえすれば、赤軍はすぐ戦闘をやめ、ともに手を組んで日本とたたかおう。
全国のすべての愛国的な人々は、国を救うために立ち上ろう、とよびかけていた(八月一日に出たので、「八一(はちいち)宣言」という)。
毛主席も一九三五年十二月の瓦窰堡(がようほ)の会議で、日本帝国主義と戦うため、すべての中国人民が立ち上って抗日の統一戦線をつくろうとよびかけた。
統一戦線とは、立場や意見のちがう人や団体が、共通の目的のために手を組んで一緒に戦う組織のことである。
一九三六年の三月に、陝西北部ソビエト区の赤軍は、国民党軍の一部、張学良のひきいる東北軍と秘密の停戦協定を結んだ。
張学良は父の張作霖を日本軍に殺され、一九三一年に日本軍によって東北から追われた青年将軍であり、東北軍の兵士たちも、故郷の東北にカイライ政府「満州国」がつくられて、故郷にはかえれない人たちだったから、「内戦をやめて日本軍とたたかおう」という中国共産党のよびかけに耳をかたむけたのだ。
しかし、この協定はあくまで蒋介石には秘密だったから、東北軍は国民党政府の手先がいるところでは、赤軍と戦うふりをしていた。
陜西にいるもうひとつの国民党軍は楊虎城(ようこじょう)将軍のひきいる西北軍だったが、西北軍も五月には赤軍との戦いをやめた。
張学良(ちようがくりよう)と楊虎城(ようこじよう)とは、蒋介石にたいし、内戦をやめて日本と戦うよう要求した。
蒋介石は、東北軍と西北軍が、赤軍とたたかっていないことに腹をたで、張学良と楊虎城を叱るつもりで一九三六年十二月、みずから西安へやってきた。西安は毛主席のいる保安から南に約六百キロはなれたところにある、西北第一の大都会で、東北軍と西北軍の本部があった。
蒋介石をむかえた張学良と楊虎城は、内戦をやめるよう何度も話しあいをしたが、蒋介石はどうしてもきいてくれない。十二月十二日、張学良たちはついに最後の手段として、軍隊でもって蒋介石の宿舎をおそった。
蒋介石はねまきのままとびだして裏山へ逃げたが、岩の上でふるえているところをつかまってしまった。
政府の最高指導者が人質になってしまったのだから、世界じゅうの人がおどろいた。多くの人は、張学良が蒋介石を殺してしまうのではないかと考えた。
しかし張学良は飛行機を毛主席たちのいる保安に飛ばせて、相談した。
毛主席はすぐ会議をひらいて、蒋介石を殺してはいけない、蒋介石をよく説得して内戦をやめさせよう、という結論をだした。そして周恩来が張学良のよこした飛行機にのって西安に飛んだ。
周恩来は蒋介石と会い、蒋介石が赤軍との戦争をやめるのなら、共産党のほうでも蒋介石政府をたおす運動はやめる、ソビエト区やソビエト政府という名前もやめてよい、と説いた。蒋介石が納得したので周恩来は、張学良に蒋介石を南京にかえしてやるようすすめた。 |

西安事件で捕えられた蒋介石(右)とむかえにきた宋美麗(蒋夫人,中央)
|
張学良は蒋介石と一緒に南京行きの飛行機にのり、いさぎよく蒋介石を監禁(とじこめること)した罰をうける、といった。
(蒋介石はこのあと、日本との戦争中も、台湾へ逃げたときも張学良を監禁しつづけた。蒋介石の死後、張学良はアメリカに渡る)。
この事件を「西安(シーアン)事件」という。
こうして西安事件は中国共産党の努力で平和のうちに解決した。
蒋介石は周恩来との約束を守り、一九三七年になってから、すこしづつ内戦をやめる方向に政策をかえていった。
民間では、国民党と共産党を中心にした抗日民族統一戦線をのぞむ声がいちだんと大きくなった。
2 持久戦の見とおし top
一九三七年(昭和十二年)七月七日の夜、北京の郊外宛平(えんぺい)付近で演習していた日本軍は、一人の兵士がいなくなったという理由で、宛平にいる中国軍に町からでてゆくよう要求した。
中国軍はもちろんそのような不法な要求をことわった。
すると翌日の八日、日本軍は盧溝橋(ろこうきょう)という橋の近くでいきなり発砲し、これがきっかけになって、日本と中国の全面的な戦争が始まった。
中国共産党はその日のうちに「日本の盧溝橋進攻についての宣言」を発表して、全中国の人民に日本の侵略軍と戦うようよびかけた。
しかし、国民政府はまだ本気になって戦うという態度をしめさず、ようすをみていた。
しかし八月十三日に、日本軍が上海を大軍で攻撃してきたので、ようやく重い腰をあげて、全面抗戦(すべての力をあわせて抵抗すること、ただしここでは日本軍の侵略に抵抗するという意味)にふみきった。 |
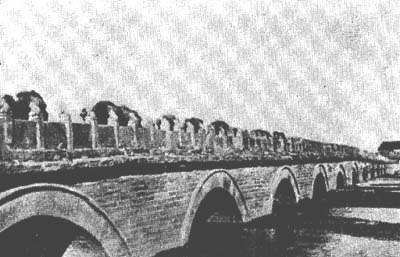
日中戦争が始まったところ、盧溝橋(ろこうきょう)
|
それと同時に、赤軍を国民政府軍隊に編入した。
赤軍の主力は八路軍(はちろぐん)と名をかえ、朱徳(しゅとく)が総司令に任命された。揚子江の下流地帯にいた赤軍の一部は新四軍と名を変え葉挺(ようてい=南昌蜂起のときの指導者)が軍長になった。
だが、赤軍は国民政府軍に編入されたといっても、あくまで独立の軍隊だった。将校も、もとからの赤軍の将校だけで、蒋介石軍の命令にはしたがわなかった。
これは北伐のときの四・一二クーデターのにがい思い出を忘れていなかったからだった。
九月には毛主席のいる陝西(せんせい)・甘粛(かんしゅく)・寧夏(ねいか)のソビエト政府が国民政府の地方政府として認められた。
こうして国民党と共産党はふたたび協力することになり、ともに手をたずさえて日本の侵略軍と戦うことになった。だが、準備のなかった国民政府軍は、北平(ペーピン=北京)・天津(テンチン)をあけわたし、十一月には激戦のすえ、上海が占領された。
|

日本軍の上海総攻撃
この勢いで南京も占領し、南京虐殺事件がおこった。
蒋介石は重慶に逃れ、重慶政府をつくった。
|
日本軍は中央政府のある首都南京さえ占領してしまえば蒋介石は降参するだろうと考え、上海を占領してからわずか一ヵ月で南京を三方面からとりかこんだ。
日本軍五万は食糧を運ぶ輸送部隊をつれていかなかったので、道々中国民衆から食糧を掠奪しながら進み、飢えた民衆は避難民となって、何十万も南京城内にとじこめられていた。
十二月十二日、日本軍は南京を占領すると、数万の捕虜をみな殺しにし、避難民や南京市民三十万以上を虐殺した。まわりを厚い城壁にかこまれて逃げるとともできなかった民衆は、揚子江の岸に立たされ、機関銃の一斉射撃で殺され、死体は揚子江になげこまれた。揚子江の水は真赤に染められた。生き埋めにされたものもいたし、ガソリンをかけて焼き殺されたものもいた。
そのころ南京にはイギリスやアメリカやドイツの宣教師や新聞記者もいたので、この南京大虐殺は世界中の人たちに知れわたり、日本軍の悪魔のようなしわざは全世界の人々から非難された。
知らないのは日本国民だけだった。
南京を占領すれば戦争は終わると思っていた日本のあてははずれた。同胞の中国人が殺されるのをまのあたりにみた中国の民衆のひとりひとりが、日本の侵略者とはどこまでも戦うという覚悟をきめたからだ。国民政府は首都を揚子江中流の武漢にうつして抗戦をつづけることになった。日本の近衛総理大臣は「蒋介石政府を相手にしない」と声明して、日本のいいなりになるカイライ政府をつくりはじめた。
翌年(一九三八年)の十月に日本軍は広州を占領し、さらに武漢を占領した。このころになると、国民党のなかには、とても日本にはかなわない。このまま戦争をつづけていると中国は亡(ほろ)びるといいだすものがあらわれた。 |

中国人の首をきろうとする日本軍将校
|
毛主席は、もともと日本軍と戦う気のない国民党の一部からこういう意見がでてくることを見通していた。
一八三八年の春、毛主席は延安の洞窟のなかで、日本との戦争の見とおしを長い論文にまとめた。
そのころ毛主席は昼は延安の学校で講義をし、夜は会議がつづき、原稿を書くのは夜中だった。
論文の題は「持久戦について」といった。持久戦とはながいあいだつづく戦争という意味だ。
あるときは二日二晩ねむらずに書いた。書きくたびれて眠くなると、警備の少年兵に水をくんでこさせて顔を洗うか、庭をひとまわりするか、ちょっとベッドに横になっては、また書きつづけた。
延安には電気はないのでローソクか石油ランプのあかりで書くのだ。
時には運ばれてきた食事に手もつけずに考えこんだ。あるときは書きながらうたたねをした。
ふと気がつくと洞窟のなかが煙くさい。
見ると火鉢の中で毛主席の靴が片方燃えているではないか!
もめんでぬった靴はくつひもも底もやけて、なかにつめた綿がはみだしていた。警備の少年兵はたまりかねて、
「主席、もうおやすみになる時間です。主席がいつまでもお休みにならないのでみんなひどく心配しています」といった。
「うん、わかった。お前たちは休んでいい。私もすぐねるから。」と毛主席は答えた。
だが、それは毛主席のくちぐせで、「すぐねる」ことはなかったのだ。
こうして「持久戦について」は完成したが、毛主席は原稿を劉少奇(りゅうしょうき)や康生(こうせい)など、共産党の指導者の仲間に読んでもらって意見をきき、文章をなおし、何度も手をいれてから印刷した。 |

「持久戦について」を書いている毛主席
|

延安棗園(そうえん)の毛主席の洞窟。毛主席はよく手前の亭で休んだ |
「持久戦について」には日本との戦争の見とおしが、つぎのように書かれている。
戦争はかならず持久戦になる。なぜかというと、日本は強い軍隊と経済力を持った帝国主義国(ほかの国を侵略して植民地を持つ国)だからだ。
しかし戦争は最後に中国が勝つ。なぜなら、日本は帝国主義国で、正義でない戦争をやっているからだ。
正義でないから外国の援助がえられない。日本は、軍隊や経済の力は強いが、国土もせまく人口も中国よりずっと少いから、長いあいだの戦争にはたえられない。
戦争が長びけば正義を愛する日本の人民が立ち上って日本の政府に反対するかもしれない。
これにたいして中国は、いまのところ力が弱いが、百年間、外国の侵略に反対する解放運動がつみかさなっている。
中国の日本との戦争はこの解放運動のつづきで、進歩のための戦争、正義の戦争である。
それに中国は大きな国で土地がひろく物産はゆたかで人口も兵力も多い。
正義の戦争だから国際的な援助をうけることができる。
戦争は三つの段階に分けられる。第一段階は、中国が日本を防ぐ「防禦」段階、つぎの段階が、日中双方の力がつりあってにらみあいの状態になる「対峙」段階、最後が中国の「反攻」段階である。 |
実際、日本との戦争は毛主席の見とおしのとおりになった。武漢が日本に占領されたあと、「対峙」段階になり、一九四五年までつづいた。そして一九四五年の夏、「反攻」段階が始まって、日本軍は負けたのだ。
しかし、毛主席の見とおしでひとつだけ、あたらなかったことがあった。それは日本の人民は、最後まで政府(軍部)にだまされつづけて、侵略戦争をやめさせるために立ち上らなかったことである。
3 二つの戦線 top
日本は「満州」でやったように、中国人のなかの裏切り者を集めてカイライ政府をつくった。
一九四〇年の三月に、国民党政府の有力者だった汪精衛(おうせいえい)をかしらとするカイライ政府がつくられ、「共産党に反対して日本との戦争をやめる」(反共和平)という旗をかかげた。
けれども中国の良心のある人々は、みな日本軍占領区からのがれて、どこまでも民族の自由のため、戦った。
たとえば「九四一年(昭和十六年)に、日本に占領されていた北京のある大学の卒業生のうち、七十パーセントが毛主席のいる解放区へゆき、二十パーセントが蒋介石の国民党支配地区へゆき、北京には十パーセントしか残っていなかったという。
このように、若い人たちの中では、日本の侵略と戦うためには、国民党地区へゆくよりも、解放区へ行こうという人のほうが多かったので、国民党は、このままでは共産党の力が強くなると思った。 そこで一九三九年の六月に、国民党政府は、法律をつくって、共産党の活動ができないようにし、国民党軍に命令して、八路軍や新四軍を攻撃させた。
一緒に日本の侵略軍とたたかっているはずの国民党軍から、いきなり鉄砲をうちかけられるのだからたまらない。八路軍と新四軍は日本軍と国民党軍の両方を警戒しなければならなくなった。 |

傀儡政府の主席となった汪精衛(おうせいえい)
|
毛主席は一九四〇年五月に、日本軍の占領区の内側でたたかっている新四軍に、国民党軍が攻撃してくる危険があるから、解放区の人民とよく結びついて、しっかり解放区をかためておくように、と指示した。
新四軍の第一部隊の隊長だった陳毅(ちんき=のちに中華人民共和国の外務大臣になる)はすぐにこの指示にしたがって、国民党軍の不意打ちにそなえ、民衆の生産をたすけたり、病気をなおしたりして、民衆の尊敬をうけ、民衆と一緒になって国民党軍の不意打ちを警戒した。
しかし新四軍の副軍長の項英は、国民党をあまくみていた。
一九四一年一月、国民党軍はとつぜん新四軍の本部をおそった。国民党軍は八万、新四軍は九千人。
新四軍は七日七晩はげしく戦ったが、弾丸も食糧もなくなり、軍長の葉挺(ようてい)は捕虜になり、項英は戦死し、ほとんどの兵士が殺され、包囲からのがれたのは千人だけだった。
日本軍とカイライ政府軍がこのチャンスを見のがすはずがない。すぐに新四軍にたいする大攻撃を始めた。
すると国民党軍はさらに二十万の大軍を動かして新四軍をはさみうちにした。
だが新四軍は亡(ほろ)びなかった。陳毅(ちんき)が新しい軍長になり、ゲリラ戦で日本軍とカイライ軍と国民党軍の三重の包囲をうちやぶり逆に解放区をひろげた。
4 生産運動と整風運動 top
解放区は大きくなったが、国民党軍はそのまわりをとりかこんで、食糧を運びこませないようにした。
毛主席はつぎのようにいっている。
「我々はほとんど着るものもなく、油もなく、紙もなく、おかずもない。
兵隊は靴や靴下もはけないし、政府で働くものには、冬でもふとんがない。
国民党は我々の軍隊の給料をはらわず、経済封鎖(物資や食糧を解放区に入れないようにすること)、をして我々を亡ぼそうとしている。」
毛主席は、解放区にいるすべての人間が生産をして、つまり畑仕事をしたり、糸をつむいだりして、この困難をきりぬけようとよびかけた。
農民に働いてもらうだけでなく、戦線からかえってきた軍人も、解放区政府の官吏も、毛主席も、働くことになった。
毛主席は自分の住んでいる洞窟のすぐ下の空地を毎日たがやした。
散歩をするときは、少年兵をつれてゆき、食べられる雑草や木の葉を教えた。
毛主席はむかし、井岡山(せいこうざん)や瑞金(ずいきん)で、いろいろなものを食べてみて、どの草が食べられるかわかっていたのだ。
毛主席は、自分の食事も、ふつうの農民と同じそまつなものにさせた。
よけいにおかずをつくって持ってゆくと、病人や老人にまわすように命じた。
服や靴がいくらボロになっても新しいものにとりかえさせなかった。
延安にはたくさんの学校があったが、教師と学生は一緒に鍬(くわ)をふるって自分たちの食糧をつくった。
軍隊では王震(おうしん)将軍の部隊が南泥湾(ナンニワン)というジャングル地帯をきりひらいた。
山の上から古い吊り鐘をおろしてきて、それを鋳なおして鍬をつくったりした。
こうして一年だつと、解放区では、だれもが腹いっぱい食べられるようになり、冬には暖かい綿入れの服を着られるようになった。
毛主席は、この生産運動をすすめる一方で、解放区の共産党員たちの心をきたえなおそうと考えた。
いまに全中国は解放される。そのときに共産党員たちは、新しい政府の官吏になって、政治をする。
新しい政府はいままでのように金持ちのためばかり考える政府ではなく、貧しい労働者や農民のためにしごとをする政府だ。そのためには官吏がひとりのこらず、労働者、農民の心がわかる、心から人民のために働く人間になっていなくてはならない。
いまは戦争中で、解放区は敵にとりかこまれているが、幸いはげしい戦いはおこっていない。
日本軍を追いだす「反攻」の時がくるまでに、党員たちの心を正しくする運動をおこなう。
毛主席は一九四二年二月に、「学風、党風、文風を正しくしよう」という題で講演をした。
学風というのは、勉強のしかたのことで、共産党員のなかには、自分の国のことより外国のことのほうをよく知つていたり、なんでも本に書いてあることを信用して、自分でしらべてみようとしない風(やりかた)があった。
それを、どんなことでも自分でよくしらべて、実際にやってみてから信じるようにしようというのだ。
党風というのは共産党のしごとのやりかたのことで、共産党のなかにも、派閥があって、なんでも自分のグループのことを第一に考えるという、よくない党風があった。それを、いつでも中国人民全体のことを考えるようにしようというのだ。
文風というのは、しゃべったり書いたりするときのクセのことで、よくない文風とは、むずかしい言葉や、文字をつかって、だれにもわからないことをしゃべったり書いたりすることだ。
毛主席は、大衆(ふつうの働いている人)の言葉を学び、外国語や昔の言葉からも学んで、美しい、わかりやすい中国語を使おう、とよびかけた。 |

延安幹部会で整風運動について講演する毛主席(鉛筆画)

延安・凰鳳(ほうおう)山のふもとにあった中国共産党中央委員会の建物
|
風(しごとのやりかた)を整える運動なので、これを整風運動とよぶ。
延安にいる共産党員たち、とくに文学をやっている人たちは、いい家のお坊ちゃんやお嬢さんだった人が多い。
だから生産をしたことがなかったし、働く人たちを軽蔑する人が多かった。
毛主席は、とくに文学をやる人たちを集めて話をすることにした。
毛主席が洞窟からでて、文学者たちの集まっているところへゆこうとしていたときに伝令がかけこんできた。
「毛主席、国民党軍が延安のほうへ近づいてくるそうです。」
そばにいた人たちは、
「きょうの会はのばしたほうがいいのではありませんか」といった。が、毛主席は、
「いや、整風運動のほうが大切だよ。もし国民党が延安に攻めこんできたら、我々は山のなかへいって、そこで整風運動をやろう。」
そういってさっさと会場へあるきだした。幸い、このときは国民党軍は攻めてこなかった。
会場には毛主席から招待された百人ばかりの文学者が待っていた。
毛主席は、心をかえるには、労働者や農民のなかにはいらなければだめだ、といって、つぎのように自分の経験を話した。
「私の感情がどのようにかわったかをお話しましょう。私は学生でした。学生の生活になれてしまって、自分の荷物をかつぐというようなちょっとした力仕事さえできませんでした。
大勢の仲間のまえでそんなことをするのは、かっこわるいと思っていました。
そのころ私は、世の中できれいな人間は知識人(上級学校をでた人)だけで、労働者や農民は、なんといっても知識人よりはきたないと思っていたのです。
私は、知識人の着るものならきれいだとおもい、よその人のものでも着られるのに、労働者や農民の着るものはきたないと考えて着る気になれませんでした。革命をやり、労働者、農民や革命軍の兵士たちと一緒になってから、私はだんだんに彼らをよく知るようになりました。
そのときから私は、ふるい学校で教えられた、あの金持ちのような感情をすっかり改めたのです。
そのときになって、知識人はきれいではなく、いちばんきれいなのは労働者、農民なのだ。
たとえ、彼らの手がまっくろで、足に牛のクソがついていても、やはり金持ち階級の知識人よりきれいなのだと思うようになりました。ひとつの階級からほかの階級にかわるというのは、こういうことなのだと思います。」 |
この話を聞いた延安の文学者たちは、それから仲間たちばかり集まっておしゃべりをするのではなく、労働者や農民のなかへはいって、一緒に働きながら、詩や小説を書くようになった。
|

手前の建物で解放区の議会がひらかれていた(延安)
|

毛主席が『愚公、山を移す』の講演をした講堂
|
そのころ八十万にふえていた共産党員は、毛主席の整風運動についての論文を読み、自分の考えかたや感情が、本当に労働者や農民の感情になっているかどうかをしらべあった。
自分の考えかたや感情を自分でしらべることを「自己批判」という。整風運動は自己批判の方法で、共産党員八十万の心を正しくし、いばらない、心から人民のために働く革命家をつくりだしたのだ。
一九四五年四月から六月にかけ、中国共産党の第七回大会が延安でひらかれた。
毛主席はこの大会で、共産党はまえよりもずっとよく団結するようになったが、それは党員が、団結しようという気持をもって自己批判をしたからだといった。
毛主席はこの大会でおこなわれた選挙で、最高点で中央委員に当選し、中央委員会の主席になった。
毛主席は閉会の言葉のなかで、中国の古い伝説を引いて、つぎのように話をした。
「中国には、『愚公(バカな老人という意味)、山を移す』というむかし話がある。
むかし愚公という老人がいた。老人の家の南には二つの大きい山があって道をふさいでいた。
愚公は息子たちをひきつれ、くわでこの二つの大きな山をほりくずそうと決心した。
智旻(ちそう=知恵のある老人という意味)という老人がこれを見てふきだし、こういった。
お前さんたち、そんなことをするのは、あまりにばかげているじゃないか。
お前さんたち親子数人で、こんな大きな山を二つもほりくずしてしまうなんて、とてもできゃあしないよ、と。
愚公は考えた。私が死んでも息子がいるし、息子が死んでも孫がいる。子孫がずっとつづくのだ。
この二つの山は高いけれども、これ以上高くなりはしない。
ほればほるほど減るのだから、いつかはほりくずせる、と。
愚公は少しも心をうごかさずに、毎日山をほりくずしつづけた。
神さまはこれを見て感心し、二人の家来の神を下界におくって二つの山を背負ってどけさせたというのである。
いま、中国人民の頭の上にも、やはり帝国主義(あきることなく自分の国の領土、勢力範囲を広げようとする侵略的なやり方。また、経済上、国際市場を独占しようとするやり方。ここでは日本とアメリカを指す)と、封建主義(支配勢力が一般人民を力でおさえて支配するやり方。ここでは蒋介石や地主階級を指す)という二つの大きな山がのしかかっている。
中国共産党は早くから、この二つの山をほりくずしてしまおうと決めている。
我々はかならずやりぬき、働きつづける。そうすれば、我々も神さまを感心させることができるだろう。
神さまとは全中国の人民のことだ。
全国の人民がいっせいに立ち上って、我々と一緒にこの二つの山をほるなら、きっとほりくずせるのだ。」 |
5 抗戦の勝利 top
|

日本軍に焼きはらわれた村
|
日本軍は一九四一年から、計画的に、中国の民衆を殺しはじめた。
ゲリラ戦争では、老人も子供も女の人も、侵略者と戦う。侵略者から見ると、平和に暮らしている農民がみな敵にみえる。
そこで日本軍は「三光」作戦ということをやった。
「三光」とは中国の言葉で、「みな殺せ、みな奪え、みな焼け」という意味である。
つまり、八路軍や新四軍のゲリラ部隊かいそうな村は、そこに住んでいる人をひとりのこらず皆殺しにし、役に立ちそうなものは皆とってしまい、家は皆、焼いてしまうというのだ。
一九四一年八月だけで、それも山西省とチャハル省と河北省のさかいの解放区だけで、十五万の家が焼かれ、一万頭の馬やブタがとられ、四五〇〇人の中国人か殺され、一万七千人あまりが「満州」につれていかれた。
日本にも五万人以上がつれてゆかれ、大勢の人が死んだ。
解放区のまわりに、日本軍はたくさんのトーチカをつくったが、その工事のために農民をかりたてて、いやがるものは鞭(むち)でなぐったり殺したりした。
だが八路軍や新四軍は、一九四四年の一年間に、二万回以上も日本軍やカイライ軍と戦い、敵二十二万を殺したり負傷させたりし、六万人を捕虜にした。
このころカイライ軍はぜったいに国民党軍とはたたかわず、八路軍や新四軍だけを攻撃していたのだ。
一九四五年のはじめには、日本はもう中国では新しい作戦ができなくなって、まもる一方になった。
毛主席が「持久戦について」で予言していた「反攻」の時が始まったのだ。
そのころ日本本土は、毎日のようにアメリカ空軍の爆撃をうけていたし、五月には日本と同盟を結んでいたドイツが降伏した。
八月六日にはアメリカが広島に原子爆弾を投下し、九日には長崎にも原爆が投下された。そして三十万もの人間が殺された。
八月九日にソ連軍が東北(「満州」)へはいってきた。
八月九日、毛主席は全中国の人民に、日本の侵略者への総反攻をよびかけた。
八路軍と新四軍は、いっせいに日本軍占領地区に進撃した。 |

延安揚家嶺(ようかれい)の農民と語る毛主席
|
八月十日、延安の山から山へ、洞窟から洞窟へ、風のように日本がついに降伏したというニュースが伝わった。
中国人民は、ついに勝ったのだ、と延安じゅうの人たちがたいまつを持って勝利をいわった。
だが、中国人民はまだ解放されなかった。
蒋介石がアメリカの助けをかりて、大きな内戦をたくらんでいたからである。
top
**************************************** |