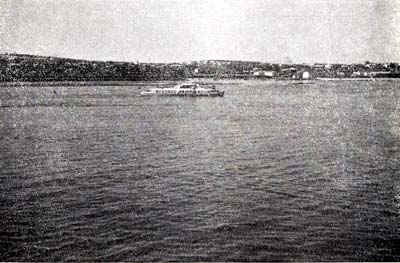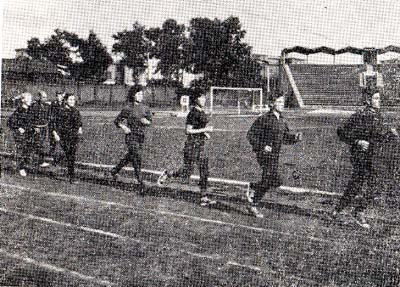|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章
一 シベリアの中のヨーロッパ、イルクーツク
1 ウラルを越えて top
TU104型ジェット旅客機の、若いスチュワーデスが、
「飛行機は、ウラル山脈を越え、シベリアにはいっています。」
と、アナウンスしてからまもなく、私たちNHKシベリア特別報道班を乗せた飛行機は、西シベリア平原の工業、農業の中心地オムスクの空港についた。
モスクワのドモデドボ空港を離陸して三時間たった一九六四年八月三十一日の午前二時十五分(モスクワ時間三十日午後十一時十五分)だった。
オムスクは外国人の立入禁止地帯であり、かつ、深夜のことでもあり、私たちは、空港待合室でかるくのどをうるおそうと、タラップをおりていくと、
「日本人のみなさんですね。ようこそいらっしゃいました。」
と、中年の婦人が一人、私たちのそばに近よってきた。
アエロフロート・ソビエト民間航空の婦人職員である。
「深夜の出迎え、どうもありがとう。」
と、私たちの、彼女のあとにしたがった。 |

TU104 型ジェット旅客機
|
真夜中だというのに、まだシベリアは思ったほど寒くない。
雨あがりのまんまるいお月さんが、空港ビルのまえの花壇をあかるく照らし、色とりどりの小さい花がいっぱい咲いているのが、私たちの目をうばった。
「これは、何という花ですか?」
と、おもわずきいた私たちに、婦人職員は、
「シベリアでは、乙女草といいます。」
と、こたえながら、
「ここは、シベリアです。ヨーロッパ・ロシアのモスクワから、アジアのシベリアに足を踏み入れた印象はどうですか?」
と、たずねかえしてきた。
ここは、もう、アジアなのだ。
ウラル山脈を越えて、東側はアジアであるとは、かねがね知っていたが、アジアの東京をたって西ヨーロッパを経由して、モスクワから再びアジアの土をふみしめた感慨は、ひとしおのものがある。 |

ウラル山脈を中心にしたシベリアの地図
|
モスクワと東京の時差は六時問だが、モスクワとオムスクの時差は三時間だ。
つまり、それだけ東京のほうへ近づいていることになる。
それにしても、外来の客にわざわざオムスクがシベリアであることを強調するのは、どういうわけであろうか。
シベリアという地名が、ロシア人の間にまだまだなにか特別の意味をもっているのであろうか。
それとも、流刑の地から生まれかわりつつあるシベリアを、誇りたい気持からだろうか。
このオムスクには七十万の人々が住み、シベリア第二の大都市である。
共産革命のまえは、シベリア最大の商業都市として栄えた。
文豪ドストエフスキーは、一八四九年から五三年まで、オムスクの監獄に収容されたが、彼の作品「死の家の記録」は、その頃の彼のみじめな生活をえがいたものである。
昔の商業都市オムスクは、今では大工業都市に生まれかわり、とくに、石油工業の発達はめざましい。
また、ここは教育文化の中心でもあって、自動車大学、鉄道大学など八つの大学のほかにテレビ局、劇場、美術館、それに市中には大小八十を数える公園もある。
また、オムスクの西のチャメン市は、一五八六年にひらかれたシベリアでは最も古い町で、ロシアのコサック、エルマークに征服されたタタール人の遺跡は、いまも市内に残っている。
最近、このあたりで大油田か発見され、シペリアにないものは石油だけだといわれていた伝説はくつがえされた。
このため、チュメン市は、石油の採掘をはじめ、製油工場、化学工場など、石油基地として急速に発展しようとしている。
さらにオムスクの東には、シベリア最大の都市ノボシビルスクがある。
人口は百万をこえており、シベリア開発の中心であるソビエト科学アカデミーのシベリア総本部があって、原子物理、地球物理、医学など十九の研究所をはじめ、大学、図書館などの研究機関が集っている。
この恵まれた環境のなかで研究にはげむ科学者は、二千五百人を数え、大がかりなシベリア開発の基礎的な調査研究は、すべてこのアカデミー・シベリア総本部で行われており、いわば、“シベリア開発の頭脳”の町といわれる。
また、ノボシビルスクには、シベリアでただ一つの本格的なオペラ・バレー劇場をはじめ、二つのドラマ劇場、人形劇場、美術館といった文化施設のほか、工作機械、発電機工場、食品工業も発達しソビエトでも有数の工業の中心になっている。 |

タタール人がのこした寺院
|
2 ネオンのある町 top
|

トーポリの並木と坂道のある風景(イルクーツク市内)
|

イルクーツク近くの略図
|
| 私たちはイルクーツクに、八月三十一日から九月二十六日まで一ヵ月ちかく滞在し、この間、ヤクーツクをはじめ、ブラーツク、ウラン・ウデヘ飛んだり、あるいは、シベリア鉄道を利用してチェレンホボ炭田の露天掘りを取材にでかけたりした。 |
この町は、ユーラシア大陸最大の淡水湖バイカル湖の近くにあり、人口三十三万五千、東シベリアの行政、経済、文化の中心地である。
私たちが泊ったホテルは、「ツェントラ・リナヤ」、英語でいえば「セントラル・ホテル」で、イルクーツクでただ一軒しかないホテルだ。
建物は五階建だが、エレベーターはなく、年老いたポーターが、私たちの荷物を三階まで運ぶのを手伝ってくれた。
私たちの、各自一個ずつのトランクをふくめて、防寒用具、防寒長靴、取材用具としてアリフレックス、フィルモ、フィルムの大箱、バッテリー、充電器、三脚、録音器、録音テープなど全部で二十個の荷物をモスクワからイルクーツクにもちこんだ。モスクワのドモデドボ空港で、二百五十キロ重量がオーバーしたので、超過運賃として二百三十ニルーブル五十カペーク(九万三千円、一ルーブル=四百円)をとられた私たちの荷物は、ホテルの狭い部屋に所せましとならべられた。
私たちの取材に協力するため、モスクワ・テレビ局から派遣された連絡係の職員とカメラマン、それにその助手の三人組は、ホテルにつくと、遠足にでもきたかのように、さっそく、ウォッカ(酒の一種)、ゆで卵、ソーセージ、フィンランド製のチーズ、キューバ製のコーヒーを出して、私たちに一緒に個食をとろうといった。
ホテルのレストランで食事をするものとばかり考えていた私たちの、意表をつかれたが、何事もつきあいが肝心と、私たちも東京から運んできたサケ缶、カニ缶、コーンビーフを取出した。
たちまち、平和共存の日ソ合同の食事会が盛大にひらかれ、ウォッカで乾杯して、最初の取材地についたことをおたがいに祝った。 |

帝政時代、貴族の子弟を教育したシベリアで
もっともふるい学校(現在イルクーツク大学)
|
私たちが、なぜホテルのレストランを利用しないのかときくと、彼らは口をそろえて、レストランの料理はうまくないし、第一、金がかかってこまる。自分の部屋で、こうして食べれば、出張旅費がうくからだ、とこたえて、私たちをわらわせる。 なかなか陽気な三人組だ。
イルクーツクは、今からおよそ三百年昔の一六五二年、ドン・コサックが、この地域に住んでいたブリヤト族を征服して、ロシアにしたがわせるため要塞をつくり、その後、一八〇三年には、シベリア総督府がおかれて、当時のペテルブルグ、今のレニングラードを型どってイルクーツクの町がつくられたといわれる。
市の中を、バイカル湖からながれでるただ一つの川であるアンガラ川の清流がながれ、菩提樹、トーポリ(ポプラの一種)、カラマツの多い、しっとりとおちついた美しい町である。
イルクーツクについた日の夕方、さっそく、私たちは、町を散歩した。一番にぎやかな力ール・マルクス通りには、しっかり手をにぎりあった若い男女の群れが、いったりきたり。
モスクワよりは何となくあかぬけした、きれいに着かざったおじょうさんたちや、はやくも冬すがたに着がえた老人たちが、通りいっぱいにいきつもどりつ、去りゆく秋の夕をたのしんでいる。
町全体は、中心部こそ石づくり、煉瓦づくりの建物で満たされているが、一歩裏通りにはいると、丸太をつみかされ、窓を半分地下にうずめたシベリアらしい木造の家戸建ちならび、そのコントラストがはっきりしている。
ソビエト人はだれでも、木造の家ははやくとりこわしてしまって、石づくりの家をつくるんだと、建設の意気ごみをみせるが、私たち旅行者の目には、かえって情緒があって、いかにもシベリアらしい雰囲気をもっている木造の家屋をとりこわすのは、おしいような気がする。
道路の舗装は、一九六〇年に市の中心部が終ったということだが、ちょっと町をはずれると、今でも舗装していない通りがつづいている。
三年前とくらべて目をひいたのは、まえには見られなかった螢光灯が比較的おおく見られ、街灯が通りをあかるく照らし、映画館や衣料品店などには、ネオンがかがやいていることである。 イルクーツクから北へ四百キロ、世界殼大の出力四百五十万キロワツトのブラーツク水力発電所がフル操業にちかづいており、電力の供給は、三年前とくらべると、格段の相違があるのであろう。
もっとも、日本の都市にくらべれば、問題なく町全体がくらく、ネオンの数にしても、ブラーツク発電所があるのに何とかならないのかなと、疑問をおこさせるほどの少なさである。
三年前よりは改善されているというものの、電力の消費量は、まだまだ重工業一点ばりのソビエトらしいつつましさである。 |
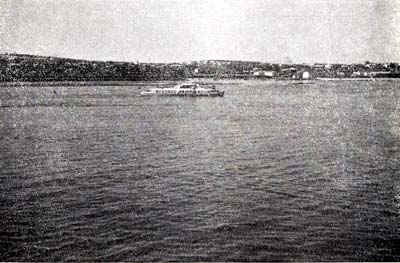
イルクーツク市内をながれるアンガラ川。
バイカル湖に向かう遊覧船も見える

木造の家がならんでいるイルクーツクの裏町のようす
|
3 食卓に日の丸の小旗 top
ホテルのレストランというと、すぐ日本の一流ホテルなどの高級なムードにあふれたレストランを思いだすが、ソビエトのレストラン、ことにシベリアのレストランにそういうものを求めてることは、全くのおかど違いである。
ちょっと気のきいた食堂、と思っていただければまず間違いあるまい。
レストランという言葉がわるいので、食堂といえばいいようなものだが、横文字で「レストラン」と書いてあるから、ついレストラン、レストランというようになってしまった。
ここ「ツェントラ・リナヤ」ホテルのレストランも例外ではなく、比較的大きな窓と明るい感じがするのが唯一のとりえだ。ドアをあけて、のこのこはいっていくと、年輩のウェイトレスがやってきて、
「インツーリスト(ここでは外国人旅行者のこと)ですか?」と、きく。
「ダー(そのとおり)。」 と、こたえると、右手のほうをゆびさして、あのドアの向うに外国人専用の部屋がありますと、いう。
いってみておどろいたが、そこには三年前にはなかった特別室がつくられていて、一つのテーブルの上には、大中小のグラスがおかれ、真中にフランスの国旗が立てられている。
どこにすわってもかまわないのだろうと、窓ぎわの明るいテーブルに席をしめると、ウェイトレスがきて、日の丸の小旗を真中に立ててくれた。
待つまもなく、さっきのウェイトレスが姿を現して注文をとっていった。
私たちは、まず、前菜にカニサラダと黒いイクラ(キャビア)を注文し、スープは夕食にはボルシチがでないので、かわりに卵入りプリオン(コンソメ)、セカンド料理としてバイカル湖特産のサケの一種オームリをえらんだ。 |

ホテルの前にかかげられたレストランの看板
|
ソビエトを旅行する外国人は、あらかじめ、「インツーリスト」と袮する外国人旅行案内公社で、クーポンを買わなければならない。
クーポンには、一人一日三十五ドル、十九ドル、十四ドル、十ドルの四種類があって、十ドル以外には朝食、昼食、茶、夕食と書かれた食券がついている。
十ドルには朝食しかついていない。
朝食は、一ルーブル十力ペーク(四百四十円)、昼食は、三ルーブル三十力ベーダ(千三百二十円)で最高、茶は三十力ベーダ(百二十円)、夕食は二ルドブル五十力ベーダ (千円)となっており、合計七ルーブル二十力ベーダ(二千八百八十円)が、一日の食費にあてられていた。
一週間や十日の短期間のソビエト旅行なら、どうにか食券を全部つかいこなすことができるが、元来、脂肪分のつよい食物をあまり好まない我々日本人は、一ヵ月、二ヵ月という長い期間のソビエト旅行になると、ついつい食欲がなくなり、したがって、食券が大量にあまるという結果になる。
4 入学式にシベリアの花 top
|

9月1日は入学式。花束を手にした小学生たち
|

マヤコフスキー小学校の入学式
(校旗を持つのは十年生の最優秀女子生徒)
|
ソビエトでは、九月一日に新学年がはじまる。
ようやく夜があけきった午前七時、私たちは、あらかじめ市役所から指定されたイルクーツク第十一マヤコフスキー普通・工業中学校の門をくぐった。
ここで、簡単にソビエトの学校制度について語らなければならない。
看板には中学校と書いてあるが、日本流にいえば、ここは小学校と中学校を併設してあるようなものだ。
つまり、七才で一年生に入学し、八年生で一応義務教育が終わる。 |
そのあとの九年生と十年生が中学生になるわけだ。
一九五八年当時のフルシチョフ首相は、それまでの七年生義務教育を八年制にあらため、八年制を卒業した者がさらに上級学校へ進学しようとする場合、生産教育をともなう教育年限三年の中等労働工業学校へ入学させることにした。
ここを卒業してはじめて、高等教育の学校へ進学できる資格を取得することになるわけである。
この第十一マヤコフスキー普通・工業中学校は、八年制義務教育とその後の生産教育を一緒にしたちのだが、どういうわけか、生産教育の期限が三年ではなく、二年になっている。
イルクーツクでは、中学校のほか、職業技術学校も取材したが、ここも教育年限は三年ではなく、九年生と十年生しかいなかった。
案内の人や、学校当局にも質問してみたが、答えはまちまちで、十年制と十一年制と両方あるということであり、これが、シベリアだけの現象なのかどうか、とうとうはっきりしなかった。
しかし、一九六六年になって、十年制に統一されることになったという。
それはそれとして、午前八時からの入学式を支えにして、学校の正門まえには、父親や母親につれられたかわいらしい新入学児童が、手に手にダリヤやキクの大きな花束をかかえて集ってくる。
男の子が、新しいランドセルを背負ってくるところは、日本の入学式風景と同じだが、女の子が、真っ白なエプロンをしている姿は、清潔そのものといった感じで、かかえている大きな花束とともに、何となくすがすがしい気分をあたえる。
一人の女の子にきいてみると、夏の間に九月一日の入学式にもっていく花を、自分の手で丹精してつくってきたということで、きいているだけでほほえましい美しい話だった。
石づくりの二階建ての校舎は、日本の学校ととくにかわったところはないが、玄関の所にレーニンの像がおかれているのが、いかにもソビエトらしい。
出迎えた婦人の教頭は、入学式がはじまるまでの間、私たちを教員室に案内し、卒業生の記念撮影アルバムを見せながら、
「この学校は、今年で五十周年をむかえました。
独ソ戦にはたくさんの卒業生が参加し、そのため本校は、国から『英雄』の称号を受けました。」
と、自慢そうにはなしていた。
この学校は、一年生から十年生まであわせて千二百五十人、一クラスに四十人の生徒を収容している。
やがて、新入生が上級生の演ずるブラスバンドにむかえられて、にぎやかに校庭にならんだ。
そのうしろに上級生がならび、父兄は校庭の隅にかたまって、心配そうにわが子を見つめている。
カメラを手にした父親が、一生懸命わが子を写している姿は、日本と同じで平和そのものだ。
入学式は、校長欠席のため、さきほど私たちを案内した婦人の教頭先生がかわってあいさつに立ち、校長の祝辞を代読したあと、新入生の男の子と女の子が、それぞれかわいい声で、はずがしそうに、
「毎日毎日、一生懸命、勉強することを詈います。」と、宣誓した。
そのあと、最上級で、まえの学年に一番いい成績をあげた女子生徒が二人、在校生を代表して歓迎の言葉をのべ、式は型どおりすすんだが、最上級生の最優秀生徒が二人とも女子生徒であったことは、最近の日本の傾向とにているようである。
式は三十分ぐらいで終わり、受持ちの先生につれられて、子供たちだけが教室にはいった。
日本なら子供たちと一緒に、父兄も教室にはいり、教室のうしろにならんで、先生のあいさつをきくのが習慣になっているが、ソビエトでは、小さいときから両親の手をはなれて、徼底した集団生活になれているせいか、子供たちだけが教室に入って、すぐさま授業がはじまった。 |

教室にはいった新入生たち
|

教室では、すぐ授業がはじまった
|
中年のふとった女の先生が、ロシア語の授業をはじめると、子供たちはべつに驚きもせず、右手のひじからさきだけを垂直にあげて、先生の質問にはきはきとこたえていた。
私たちが取材を終って、教室をでようとすると。数人の子供がはしりよってきて、私たち三人にめいめい花束を贈ってくれた。私たちが授業のじゃまをしたことをわびると、先生は、
「おたがいに平和でありますように、日本の子供によろしくつたえてください。」
と、いって、かたく私たちの手をにぎった。
私たちの、かかえきれないほどの花束をいっぱいもらって、何となく華やいだ気持になりかわいい子供たちの顔を思いうかべながらホテルにひきあげた。
この日、イルクーツクの町には、花束をだいじそうに胸にかかえた子供たちがあちこちに見られ、町全体が何となくおまつりのような活気にあふれていた。 |

真剣な目つきで授業をうける子供たち
|
5 生まれかわる古都イルクーツク top
入学式のあと、イルクーツク訪問のあいさつをするため、市役所にサラッキー市長を訪れた。
市役所の建物には、共産党市委員会、青年共産同盟、市議会の三つの機関が同居している。
サラッキー市長は、ソビエト人としてはほっそりした紳士で、終始微笑をうかべながら、私たちの質問にこたえてくれた。
市長の話の中から、ニュースをひろってみると、イルクーツクには地震があるので、四、五階の建物しかつくれない。
土地はいくらでもあるし、十二階もあるような高層建築をつくる必要はない。
アンガラ川の岸には、重工業のほか、食肉、食糧などの軽工業が発達し、市民の六十七パーセントは工業労働者である。 |

イルクーツクの町づくりは、ドンドンすすんでいる
|
また、イルクーツクは文化の中心地で、七つの高専と大学、二十三の職業技術学校、八十二の中学校(小学校をふくむ)があり、一方、ソビエト科学アカデミーの東シベリア支部もあって、東シベリアの地下資源の調査にあたっている。
いわば、イルクーツクは東シベリアの開発にあたる技術要員の訓練センターでもある。
イルクーツク州の七十五パーセントは森林が占め、このため、良質のカラマツを産し、ブラーツク市には、大規模な木材コンビナートがつくられている。
イルクーツク空港は、一九六四年つくりなおし、駅もシベリア鉄道の主要駅であるため、最近新しくつくりかえた。
教会を二つとりこわし、国民経済会議のビルと、「文化と休息のための公園」をつくり、アンガラ川のほとりには、市民の散歩道としてガガーリン通りをつくった。
また、いまのところ、ホテルが一つしかないので、一九六六年完成の予定で二番めのホテルを建設しており、さらに一九六七年には、ガガーリン通りに面して眺めのよい場所に、外国人専用のホテルをつくることにしている。
サラツキー市長の話はざっとこんなところだが、教会など由緒のある建物をこわし、民族の文化財を保存することには、あまり関心がないようで、いささか失望した。
現に町を歩いていると、とがった塔をもったポーランド教会が、東シベリア映画スタジオにかわっており、ギリシア正教会が、十字架をもぎとられてパン工場にかわっている。
ソビエト人は、ふるいものを保存するより、すぐとりこわして、新しいものにかえたがるが、シベリアのなかのヨーロッパともいえる歴史と文化と伝統の町イルクーツクのために、史跡が失われてゆく力をおしむものである。
6 「ミヤモトはどうしている?」 top
イルクーツクにも戦後多くの日本軍将兵が捕虜として抑留され、シベリア開発の基礎づくりをした。
私たちの取材のかたわら、日本人捕虜がどういう仕事をしていたかをいろいろな人にたずねた結果、断片的ではあるが、当時の日本人捕虜についての話をきくことができた。
イルクーツク放送局のプロデューサーの話によると、
「終戦翌年の一九四六年、毎日のように日本人捕虜の一団が、歌をうたいながら、朝はやくイルクーツクの町を出発し、夕方また歌をうたいながら帰ってきた。
これらの日本人捕虜が、どこで仕事をしていたのか知らないが、彼らの生活は、比較的自由であったように思えた。
その後偶然に、日本人捕虜が市内の競技場を建設しているのを見たことがあるが、この工事が終った一九四七年ごろ、日本人の姿は、イルクーツクの町から見えなくなった。」
また郊外の学園都市を取材中に乗ったタクシーの運転手にきいてみたら、
「一九四六年、私が目をわずらって入院していたとき、となりのべッドにいた日本軍の将校が、とても親切にしてくれた。 その人はミヤモトといっていたが、今どこに住んでいるか知らないか。私は、今でも日本人が好きだ。」
と、いかにもなつかしそうにいっていた。
しかし、このイルクーツクだけで四百六人の同胞が、命を失ったというのに、イルクーツクの町では、もう、日本人の話をしてくれる人はほとんどいない。
戦後二十年たった今、日本人のことなど念頭にないのかもしれないが、シベリア開発の捨石となった日本人のために、記念碑をたてることの好きなソビエト人が、このイルクーツクにも記念碑の一つぐらいつくってくれてもいいのではなかろうか。
私たちの、こんなことを考えながら、市役所の婦人係員の案内で日本人墓地を訪れた。
市の中心部をはなれて、舗装されていない、でこぼこ道を車にゆられて約十分、ゆるやかな丘の上の雑木林のところで車をおりた。
丘の上からは、イルクーツクの町が一望のもとにながめられ、なだらかな丘には、野ギクやバレイショの花が咲きみだれていた。
日本人墓地は、雑木林の奥にうららかな秋の日ざしをあびて、ひっそりとしずまりかえっていた。
墓地の入口には、木の扉がしまっていて、その上にロシア語で、
「一九四五〜四六年に死亡した元日本軍捕虜の墓」
と、書いた小さな札がさがっていた。
扉をあけて中にはいると、きれいな小石でふちどられた幅二メートルばかりの赤土の道が、二十メートルほどつづき、正面に高さ三メートルぐらいの純白の塔が立っていた。
この塔には、いっさい文字が書かれていないので、いつ、だれが建てたのか全く見当がつかないが、最近ここを訪れる日本人の数がふえてきたために、とくに建てられたのかもしれない。
この塔の左右に、長方形の白い墓石がずらりとならんでいて、墓石には全部番号がふってあった。
私たちは、さっそく、日本から持参した線香やタバコに火をつけて、それを一つ一つの墓石にそなえて、あるいた。 |

日本人捕虜がつくった競技場

日本人墓地に建てられた純白の塔
|
望郷の念むなしく、シベリアの土に骨をうめた四百六柱の御霊よ、故郷のかおりをかぎたまえ、と。
つぎの日、私たちの、日本人捕虜が建設に参加したという「トルード(労働)」 競技場をおとずれた。
鉄筋コンクリートの高い柱を四本真中に立てた入口はなかなかスマートで、中へ入ってみると、四百メートルのトラックがきれいにできており、女子学生たちが先生にひきつれられて、元気よく走っていた。
まもなく午後五時になって、イルクーツクの近くにある二つの町アンガルスク対ウソーリエの対抗サッカー試合がはしまったが、かれらはもちろん、この競技場が日本人捕虜の手でつくられたことは全く知らない。
シベリアでも戦後が終ったのだろう。
競技場の案内人の話によると、ここで練習していた二人の陸上選手が、オリンピック東京大会に参加することになったということで、日本人捕虜たちも、この競技場が平和な青年のつどいであるオリンピックにすこしでも役だったことを知れば、せめてものなぐさめとなるであろう。 |
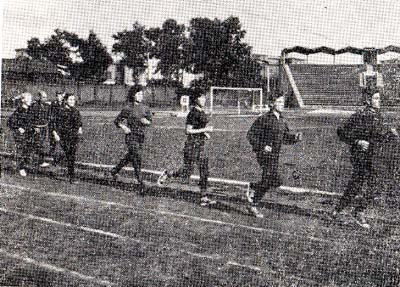
競技場のトラックをはしる学生たち
|
7 変わりゆくシベリアの市民生活 top
中心街のカール・マルクス通りは、昼も夜も、人の流れが絶えない。
映画館のまえをとおると、看板に西ドイツの記録映画 「カイロからケープタウンへ」と、フランスとイタリアの合作映画「鉄仮面」の広告がでている。
映画館の中へ入ってみると、すでに超満員の盛況だ。
スクリーンにビキニ姿のフランス美人や、ドイツ美人が現れると、観客は水をうったようにしずまりかえり、目をさらのようにしてスクリーンに見いっている。
ソビエトの上品な映画には、こういったシーンは皆無だから、観客が目を見はるのも無理はない。
私たちには、シベリアの町で西ヨーロッパの映画が公開されていることほうが、よほど興味をひいた。
オーバーな表現をつかえば、ヨーロッパ文化がシベリアに浸透しつつあるわけである。
帰りぎわにべつの映画館の前を通ったら、おどろいたことに、ピストルをもった女が男をねらっている看板が、大きくでている。
ポーランド映画 * だ。
* ポーランド映画 ポーランドはロシアと東隣りなので、昔から仲が悪い。第二次大戦は西隣のドイツのヒトラーがポーランドに侵入し、さらに東隣のスターリンまで攻めてきたのが始まりです。 |

緑ふかいカール・マルクス通り
|
映画が、共産主義の宣伝だけに使われていた時代は、すでに過ぎ去ったらしい。
中共のいう「現代修正主義」とは日常生活のうえでいえば、こんなところにも現れているのである。
イルクーツクの市民は、どのような衣食住の生活をしているのであろうか。
イルクーツク滞在中の一日、私たちの食料品店、コルホーズ自由市場、百貨店、スポーツ用具店、それに電気器具店を訪れた。
最初にいった食料品店は、四階建てのビルの一階を占め、店内はあかるく、比較的小ぎれいな店だった。
売り子もみんな白い四角い帽子をかぶり、白いエプロンを身につけて、食料品を取り扱う店としては、まあまあの感じだった。
入口をはいると、まっさきに目にはいるのは、正面の棚にならんでいる酒の類である。
酒好きなソビエト人らしい陳列のしかたである。
食品としては、太平洋産ニシンの酢づけが一キロ一ルーブル(四百円)、塩づけが一ルーブル三〇カベーダ(五百二十円)、燻製一ルーブル五十力ペーク(六百円)で、ケースに三段、山盛りになっていたが、だれ一人買う人はいなかった。 |

運動具、楽器など、レジャー用品の専門店
|
また、鳥肉が一キロ一ルーブル七十五カペーク(七百円)、むし鳥がニルーブル九十カベーダ(千百六十円)と、日本の鳥肉値段と同じような値段で売られていたが、なぜか、ここでも買う人を見かけなかった。
行列をつくっているところは、ロシア人が朝食にかならず食べる「スメタナ」という、ヨーグルトににた乳製品を売っている場所やパン売り場だった。
缶詰や瓶詰も、売れない商品の一つだ。
イワシやニシンの缶詰、キュウリのロシアづけの瓶詰、アンズの瓶詰などのほか、レッテルに漢字がかかれている中国製ミカンの缶詰が一個八十四力ベーダ(二百三十六円)で、山のように棚にならんでいたが、手にとって見ようとする客もいない。
このミカンの缶詰は、日本で五十円程度で売っている缶詰より一まわり大きいサイズだが、中味は袋ごとのミカンのつぶをサッカリンで煮つめてあり、食べられたものではない。
イルクーツクには、製茶工場がある関係で、この食料品店にも中国、インド、セイロン、グルジアの紅茶が数おおく売られていた。
原料を輸入してここで精製するせいか、豊富に出まわっている紅茶の味は、モスクワで飲む紅茶よりうまかった。
ただ、値段がたかいのが玉にきずで、五センチ立方ぐらいの紙袋にはいったセイロン・ティーが、一ルーブルニ十力ベーダ(四百八十円)もする。
8 豊富なレジャー用品 top
百貨店からちょっとはなれたところにあるスポーツ用具店と、電気器具店は、おいてある商品の種類がおおいことで私たちをおどろかせた。
はじめ私たちは、どうせたいしたちのはおいてないものと、たかをくくって店のドアをあけたところ、店内には意外にも多くの品物が陳列され、その質のよいことは、私たちの購買欲をそそったほどである。
ここは、さすが、シベリアのどまんなかだけあって、黒テンや銀ギツネのハンティングにつかう猟銃がずらりとならんでいて、十月一日の狩猟解禁日を待っていた。
また、バイカル湖に近いせいであろうか、釣竿などの魚つりの道具が一式、さらにボートまで売っていたのにはびっくりした。
猟銃は、二十二ルーブル(八千八百円)から九十五ルーブル(三万八千円)までさまざまな種類があり、釣竿も安いのは六十力ベーク(二百四十円)から十ルーブル(四千円)まで色とりどりである。 |

売場の楽器
|

猟銃、釣竿などがならんでいる売場
|
このほか、登山用品やフェンシングの面、弓、陸上競技用のスパイク、ラケット、ピンポン用具、スケートぐつなど、ほとんどあらゆるスポーツの用具やオートバイ、自転車、スクーターなどまでが、店内せましとばかりおかれてあった。
もっとも、実際に買っている客の姿はほとんど見かけず、子供たちがたくさん群がって見ているだけであった。
ちなみに、ラケットは十五ルーブル(六千円)、オートバイは三百ルーブル(十二万円)、スクーターは五百ルーブル(二十万円)の正札かぶらさがっていた。
店の一隅には楽器類もおかれていて、ピアノからロシアの民族楽器バヤン(二万八千円〜十五万円)、フルート(四万円〜十二万円)、バラライカ(二千四百円〜六千円)、ドンムラとよぶ楕円形の絃楽器(三千二百円〜四千八百円)、ギターなどこれまた美しい楽器類が、陳列だなをびっしりとうずめていた。
なかでも陳列だなの半分を占めていたのは、ロシア人も好んでつかうバヤンや、三角形のバラライカだった。
私たちが最後に訪れた電気器具店でも、ソビエトにきてはじめてみたトランジスタ・ラジオや、斬新なタイプのテレビ受像器が、店内いっぱいにならんでいた。
ここには、モスクワの百貨店でよく見る部厚い木のわくをはめたような、やぼったいテレビはほとんどない。
値段は日本よりも高く、大体、二百五十〜三百ルーブル(十万円〜十三万円)級のものが一番おおかった。
テレビはほかの物価にくらべればまだ安いほうである。
同行のモスクワ・テレビの職員は、モスクワでは買えないといって、バルト三国のリガでつくられた十石のトランジスタ・ラジオを買いもとめた。
値段は七十五ルーブル(三万円)とやや高いが昼間でもNHKの国際放送が完全にききとれるほど性能がよい。
私たち報道班がもっていった八石のトランジスタ・ラジオでは、とうてい、たちうちできない。
彼は日本製は小型で、なかなかスマートだと、おせじをいってくれたが、内心ほくほくのていであったことほ間違いない。 |

売場にならんだスクーター

イルクーツクで売られていたテレビ
|
トランジスタ王国といわれたわが日本のトランジスタが、しかも、NHK報道班がもっていったトランジスタが、ソビエト製よりおとるとあって、この勝負は完全に日本の負けとなった。
海外に商品をもっていくときには、最高のものをもっていかなければだめだ、というのが、体験をとおして得た私たちの実感であった。
9 宝くじもある自由市場 top
コルホーズ自由市場は、ソビエトのどこの町にいってもかならずある施設で、コルホーズ農民が、住宅のまわりに所有を認められている私有地でつくった作物を、統制価格ではなく自由な値段で客に売ることができる場所であり、農民にとっては大切な収入のみなもとでもある。
それだけに、売り子のあいそがいやによがったり、値段をまけても買ってもらおうとするなど、社会主義統制経済なかでは、自由主義経済の原則を認めた異質な存在である。 |

ニンジンやトマトをならべて
(自由市場)
|

コルホーズ自由市場では、宝くじも売っている
|
イルクーツク自由市場では、コルホーズ農民が、私有地の家庭菜園で丹精をこめてつくったトマト、バレイショ、ニンジン、キャベツ、ピーマン、ニンニクなどのほか、サクランボほどのリンゴ、ブドウ、イチゴ、ばかでかいスイカなどのくだもの類を自由価格で売っていた。
つづいて、イルクーツクに一つしかない百貨店へいってみた。
百貨店といっても、二階建の小さな店だが、商品は、婦人の綿製下着から冬の総毛皮のオーバー、カラクリ綿羊とよばれる毛皮用のヒツジの皮でつくったオーバー、合成繊維のオーバー、銀ギツネや黒テンのえりまきまで、一応そろっており、店員のサービスも、モスクワの百貨店「グム」や、「ツム」よりましな感じをうけた。
ここで売っていたオーバーのなかで、一番高かったのはミンクの婦人オーバーだった。
値段は何と八百九十六ルーブル(三十五万五千円)もし、カラクリ綿羊のオーバーも、六百五十五ルーブル(二十六万二千円)といういい値だった。
もちろん、一般市民が買えるはずはなく、大衆向きとしては、中共製のオーバーが百四十五ルーブル(五万八千円)で売られていたが、これとても、月給百ルーブルにならない若い娘さんたちにとっては、よほどの覚悟がなければ買える品物ではない。
10 女教師ポポワさん宅訪問 top
私たちの、豊富なレジャー用品や消費物資を売っているイルクーツクの市民が、どのような家庭生活をおくっているのかに関心をもち、市当局に家庭訪問を許可してほしいと、申しいれていた。
その許可が意外にもはやくおりて、女教師ポポワさんの家庭を訪れることができた。アンガラ川に沿ってつくられた新しいガガーリン通りから、ちょっとはいったところにあるアパートの三階に、夕方五時半ポポワさんを訪れると、ちょうどそこへ彼女の主人もかえってきて、夫婦そろって私たちを歓迎してくれた。
でっぷりと太った典型的なロシア婦人であるポポワさんは、ヨーロッパ・ロシアのスターリングラード、今のボルゴグラードで生まれ、独ソ戦争のさなか一九四一年に、イルクーツクに疎開し、イルクーツクの職業技術学校で先生をしている今の主人と結婚し、すでに十九才になる一人息子がいた。 |

ポポワさん夫妻
|
この家の月収は、夫婦あわせて三百ルーブル(十二万円)もあり、彼女は、住居費に十五ルーブル(六千円)しかかからないので、生活には不自由しないと、しょっちゅう、金歯をのぞかせながら二コニコ顔で語っていた。私たちが、
「それではお金があまってしかたがないでしょう。」
と、いうと、やや真顔になって、
「食費や衣料費をすこしはりこんだり、夏休みに遠くへでかけたりすると、みんななくなります。」
と、こたえていた。
主人のほうは、これからは、狩猟が唯一のたのしみだといって、猟銃を自慢げに私たちに見せ、息子と一緒に猟にでかけるのが待ちどおしいと、十月一日の開禁日を指折りかぞえて待っているようすだった。
イルクーツクから六十キロ北のほうへいくと、完全な密林があり、そこでは黒テン、銀ギツネ、リス、ウサギがいくらでもいるが、銀ギツネは年間二十匹以上とってはいけない規則があり、また、黒テンもかならず政府に供出しなければならないことになっている。
しかし、一匹あたり何万円という金をうけとることができるので、日曜日などは、臨時収入を得ようとするにわかじこみのバンターたちが、どっと密林にくりだすが、そう簡単に黒テンや銀ギツネがとれるはずはない。
主人は、それでもかなりの自信をもっていろようで、手にした猟銃をしきりにさすっていた。
私たちの、ボルブイフードにいろ彼女の父親からおくってきたというリンゴやビスケット、紅茶などをごちそうになり、夕食時のいそがしいなかを一時間もおじゃましてしまったが、夫婦ともすこしも気にかけず、フィルムに私たちがどんなぐあいに写っているのか、NHKの番組をぜひソビエトでも公開してほしいと、しきりにいっていた。
この家の部屋数は三間で、台所、ふろ、廊下をつぞいて四十三平方メートル、ここに夫婦と息子と主人の妹と、七十才のお婆さんの五人が住んでいる。
五人家族で三間というのはソビエトの標準でやや手狭な感じがしないでもないが、日本よりは恵まれた住宅条件である。
この家には、ピアノ、電気冷蔵庫、テレビ、ガスレンジと一応そろっており、市当局が訪問を許可しただけあって、かなりの文化生活をいとなんでいるようすだったが、ボポワさんの話からうけた印象では、収入の大部分を食費にさいているようであった。
帰りがけに台所をのぞいてみたら、黒パンとトマトが食卓の上においてあって、ガスレンジにかかっている鍋の中では、バレイショやキャベツが、ブツブツと音をたてて煮えていた。
夕食のおかずが一品だけではさびしいなと、よけいなことをいいながら、私たちの女教師ボポワさんの家を辞去した。
11 革命の闘士も教会へ top
九月二十日の日曜日、かなりまえから取材許可を願いでていたギリシア正教のフレストワズドゥビジェンスカヤ教会の取材が許可された。
私たちは、日曜の朝はやく、まだ、人通ののすくないイルクーツクの町を歩いて教会まででかけていった。
イルクーツクでは自動車を街頭でひろうことはまず不可能で、まえの晩から車を予約しておかなければ、歩くより手がない。
クレストワズドゥビジェンスカヤ教会は、今から二百十何年前の一七四七年につくられたもので、ほかの教会がとりこわされたり、パン工場にかえられたりしたたかで、この教会だけは存在を認められ、今でもギリシア正教の信仰の中心になっている。
礼拝は午前七時、十時、午後五時の三回にわたって行われており、私たちの二回めの礼拝を取材することになった。
午前九時五十分、教会の鐘がしずかに鳴りひびくと、杖をついたり、孫の手をひいた老人たちが、ぞくぞくと教会の門をくぐり、胸に十字を切っては建物の中に入っていく。
よく見ていると、老人のほとんどはお婆さんで、男はかぞえるほどしかいない。
若い人は、見学にきているような人をのぞいては、ほとんどいない。
私たちが、TVカメラをまわしたり、録音をとっていると、何人かのお婆さんがちかづいてきて、
「なぜ、写真をとるのか?」
「だれの許可を得て、なんのために音をとるのか。」と、つめよる。
私たちが、市役所と教会の両方から取材を許可されたと、いくら説明しても、けわしい顔つきでこぶしをふりあげんばかりにして、「なぜ」という言葉をくりかえす。
教会弾圧を身をもって体験した昔の恐怖心が、まだ消え去らぬためであろうか。
見知らぬ外来者を極度に警戒するお婆さんたちの気持は、考えてみれば、むしろ気の毒である。
定刻十時、キリストの像のかげで、普通のワンピースに白い毛糸であんだ肩かけを、頭からすっぽりかぶった中年の婦人が、教会スラブ語で書かれた聖書を声たかく読みはじめた。
お婆さんたちの、茶色のほそいローソクを手に手に、祭壇のまえまでちかより、キリストの像に口付けしたり、床にひざまずいて、口々に、
「おお、神よ!」と、いいながら、うやうやしく祈りをささげていた。
十時三十分、肩から黄色いケサをさげた僧正が、香をたきながら登壇し、ひときわたかい声で賛美歌をうたうと、聖歌隊とお婆さんたちがそれにあわせ、礼拝は最高潮に達した。
ローソクの光、壁にかかれた多くのキリストの像、香のにおい、荘重な賛美歌、これがシベリアだとは思えないような雰囲気だ。
集ったお婆さんたちの、百五十人もいたろうか、彼女たちのきびしい視線をあびて、私たちの、いつまでも取材をつづけることができないような気持になり、礼拝のなかばで教会の外にでた。
教会の庭のベンチにポツンとすわって、ハトとたわむれていた一人の老人に、いろいろと、話をきいてみた。
この老人は六十七才。一九一七年の共産主義革命のときには、先頭にたって党のためにたたかい、今度の大戦でもスターリンのために一命をなげうつ覚悟でドイツ軍と戦ったが、五十才をすぎると、どういうわけか、自分でもはっきりした動機はつかめたいが、いつとはなく教会に足を運ぶようになったという。
革命の闘士の生残りが、かつてみずから弾圧し、排撃した教会にこうして姿を見せるとはいかにも皮肉なめぐりあわせだが、いくらソビエト社会でも、マルクス・レーニン主義だけでは生きていけないことを、この老人の行動が、はっきり物語っている。
12 めざましい空の交通 top
私たちの、イルクーツクを根拠地にして、ヤクーツク、ブラーツク、ウラン・ウデヘ飛んだため何回もイルクーツク空港を利用した。
空港ビルは、できたばかりの、ガラスの大きい明るい建物で、カウンターで荷物の計量をすませてから、べつの建物の二階にある外国人専用の待合室で、待った。
この建物には一階に郵便局があり、私たちが東京へうつ電報をもっていくと、局員がローマ字を見て首をかしげ、あなたは中国人ではないようだが、これは一体、どこの文字ですか、ときくのがおもしろかった。
日本文をローマ字で書いてあるのだと、いくら説明しても彼らにはわからない。
日本文なら日本語で書けばいいという。
こちらが、日本語で書きたいけれども、それでは、ローマ字かロシア文字しかうてない機械で、どうして日本語がうてるのかときくと、それは不可能だと、はじめてわかったような顔をする。
しかし、やはり、よくわからないとみえて、引出の中から、国際電報のうちかたと書いてある本を取出して、一生懸命読んでいるが、読めば読むほどわからなくなるらしい。
本を机の上になげだして、ため息をついている。同僚がいるときはもっと大変だ。
二人で、ああでもない、こうでもないと、例によって大声で論争をたたかわす。
なにしろ、日本に電報をうつのははじめてだという局員が大部分なのだから、手がつけられない。
偶然、まえにひともんちゃくおこした局員がいあわせると、話ははやい。
先輩ぶって、それはそのままうてばいいのさと、ニヤニヤ笑いながら手ほどきする。
こうして、窓口で二、三十分ぐらい立ちんぼうでいると、やっと、難問は解決する。
空港ビルはできてまもないせいか、暖房の設備がいきとどいていないらしく、深夜になると九月でも外気が零度ちかくにさがるので、ビルの中は底びえがしてくる。
そうすると、直径二十センチぐらいのホースを二本つんだトラックがやってきて、ホースをドアのところからビル内にいれ、温風をおくりこんでくる。
はじめは、なにをしているつかと、ふしぎに思ったが、シベリアの人は寒さに対して、日本人などよりはるかに神経質になっていることがわかった。
なにしろ、冬は零下三十度から四十度という、想像もできないような酷寒のなかで生活しているのだから、寒さに対するたたかいでは、私たちよりはるかに敏感になっているわけだ。
よくソビエトを訪れた日本人のなかで、ソビエトのアパートに暖房設備がいきとどいていることを指摘し、むやみに感心する人がいるが、零下数十度のところと日本を一緒にして考えているのが、そもそもの誤りで、ソビエトの暖房設備は、日本でいえば水道設備と同じぐらいの意味しかもっていないのではなかろうか。
世界最大というだけあって、機内は二階になっており、一階はキチンと倉庫に使われている。
一九六六年の六月末か、七月はじめには、東京〜モスクワ間に直通航空路がひらかれ、このTU114が羽田空港にもおめみえするはずだが、この飛行機をふくめて、ソビエトの飛行機は振動がややはげしいのが欠点のように思われる。
TU114を設計したトッポレフ氏がやはり設計したジェット旅客機に、TU103双発ジェット機がある。
TU104ジェット饑は、七十〜百人乗りの中型旅客機で、舗装した滑走路もないような小さな空港でさえかならずといっていいほど一機や二機、姿を見かけ、その数のおおいことには、全くおどろかされた。
私たちの、パリからモスクワまでの国際線でもTU104に乗ったし、モスクワからイルクーツク、イルクーツクからハバロフスの国内線でもTU104に乗っかが、サービスはあまりよくない。
だが、ソビエトでは、やれ、サービスがどうの、スチュワーデスがどうのという段階ではないのかもしれない。
いってみれば、それほど飛行機が汽車や電車のように、大衆の乗りものになっているといえるのかもしれない。
TU104は、ジェット機だから、一万〜一万二千メートルの高度を、時速千キロで飛ぶことができる。
TU104はTU16中距離爆撃機を改良して、一九五六年以来、アエロフロートが使っているもので、これも元々旅客機として設計されたものではないので、スピードはでるが、快適性という面からいくと、どうしてもアメリカやヨーロッパの旅客機にくらべて見おとりがする。
ウクライナ人が設計した飛行機にアントーノフ10型四発ターボプロップ旅客機がある。
この飛行機は当初、キエフとかクリミヤとかウクライナ方面で、おもに使われていたが、今では、シベリアでもどんどん飛んでいて、私たちの、イルクーツク〜ヤクーツク往復にこの飛行機に乗った。
アントーノフ10A型機、翼が、ふとった胴体の上についていて、一見ユーモラスなかっこうをしている。
ふとったソビエトのお婆さんににているので、私たちの、「バーブシカ (お婆さん)」という愛称をあたえていた。
スピードはあまりでず、高度七、八千メートルでの巡航速度は、時速六百八十キロ程度である。
最大百三十人の乗客を乗せることができる。
ソビエトで、旅客機としてもっとも性能がいいのは、イリューシン18型四発ターボプロップ機だ。
この飛行機は、一九五九年四月からアエロフロートが使っており、当時第一副首相だったミコヤン氏を乗せて、羽田国際空港に飛んできたこともある。
どうも、この飛行機力機数はあまりおおくないらしく、私たちの、ハバロフスクからカラフトのユジノ・サハリンスクヘ飛んだときに乗っただけである。
この飛行機は、快適性からいっても、西側諸国の商業航空機にくらべて、けっして見おとりはしない。
私たちは、飛行機に乗るまえに何度もイリューシン18に乗りたいと希望してみたが、いつも私たちの希望はかなえられなかった。
最高速度は、時速七百五十キロだが、高度八千から九干メートルでの巡航速度は六百五十キロで、けっして速くはない。
乗客数は、八十四人から百十一人である。
ローカル線では、航空距離のみじかいイリューシン14型双発プロプラ機や、LI2型双発プロペラ機が、さかんに飛んでいる。
イリューシン18型は、二十八人から三十六人乗りのプロペラ機で、高度二千五百メートル程度のところを、時速三百キロぐらいで飛ぶので、下界のようすが手にとるようにわかっておもしろかった。
ジェット機とちがって、何となく気がるに乗れるし、スチュワーデスもひまができると、あいている座席にすわって、のんびり乗客と話をしたりしていた。
一度、こんなことがあった。
LI2型に乗って、ブラーツクからイルクーツクへ帰ったときのことである。
普通なら離陸して飛行機が一定の高度に達すると、スチュワーデスが機内に姿を現すのだが、この時は、どうしたことか、いつまでたってもスチュワーデスが姿をみせない。
そのうち、操縦席のほうから男の乗組員がやってきて、乗客に、
「どうも、スチュワーデスを、ブラーツク空港に忘れてきたらしいので、私がかわりにミネラル・ウォータをサービスします。」
と、いって、不器用な手つきで、ミネラル・ウォータのはいったびんから、乗客の一人一人に水を配って歩いていた。
離陸まえにスチュワーデスが、きゅうに体の具合でもわるくなったのではないかとも思われるが、いずれにしても、乗組員の口から冗談がでるほど、LI2型の空の旅はのんびりしたものだった。
また、ソビエトでは、飛行機の安全性にはとくに気を配っているようだ。
飛行機が定刻に飛びたつことはまれで、整備員は、納得のいくまで整備にはげんでおり、また、天候がおもわしくなくなると、なんのちゅうちょもなく空港を閉鎖する。
せっかちな日本人はいらいらするが、ロシア人はなれたもので、何時間、何十時間出発がおくれても、待合室でだまって飛行機を待っている。
top
**************************************** |