|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章
七 カラフトの一週間、トヨハラ(ユジノ・サハリンスク)
1 秋雨にぬれた日本家屋 top
ハバロフスクの目抜き通りの力−ル・マルクス街では、トーポリの黄葉がたえまなく散り、シベリアの秋はいよいよ終りをつげようとしている。
十月五日、私たちは、午後一時半発の飛行機で、外国人記者として戦後はじめて、カラフトのトヨハラ(ユジノ・サハリンスク)に入ることになり、午前中にすっかり出発準備を終った。
顔なじみになったレストランのウェイトレスから、
「こんないい天気の日に旅行するとは、あなたがたは、じつに運がいい。」
と、お愛想をいわれるほど、ハバロフスクは気持のいい秋晴れである。
ところが、いざ出発という正午頃になって、突然、天候不良のためトヨハラの空港が閉鎖され、出発は夜になるという連絡をうけた。
はりつめた気持がすっかりぬけてしまった。
私たちのトヨハラ行は、モスクワで一応承認されていたが、ハバロフスクにつくと、特別の許可書がなければはいれないことがわかった。
私たちは、インツーリストのお尻をたたいて、昨日やっとハバロフスクにあるソビエト内務省外人登録所で、トヨハラ行の許可書をとりつけたばかりである。 |

カラフト(サハリン)の地図
|
天候といい許可書の件といい、トヨハラ行は並大抵でないとぼやきながら、私たちはなかば気ばらしに、市内の取材にでかけた。
そして空港には、飛行機が出発する一時時前には連絡するよう、手配しておいた。
取材からかえっても、いっこうに空港から連絡がない。
なかば今夜の出発をあきらめていたところ、午後七時半すぎになって、突然、空港事務所から、二十分後に空港へくるようにという連絡があった。
私たちは、大急ぎでタクシーで空港にかけつけた。
空港入口のうすぐらい門のところには、婦人職員が待ちうけていて、荷物の計量はしなくていいから、すぐ飛行機へ急いでくれという。
タクシーは飛行場の中をつっぱしり、すでにエンジンをひびかせているイリューシン18の翼の下へすべりこんだ。
私たち一行五人が、息せききって乗りこむがはやいか、イリューシン18は、滑走路に向けて走りはじめた。
ホテルを出てから、まさに二十分間のできごとである。
しかし、この飛行機が、私たちを待つため、出発をおくらせたとは知らなかった。
荷物の計量もせず、飛行機の下までタクシーを乗りつけ、しかも、八十人の乗客をのせたまま、私たちを二十分間も待ってくれるというサービスは、ちょっと日本では考えられない。
規則ずくめのこの社会にも、こうした過剰サービスのあることを感謝するとともに興味をもった。
イリューシン18は四発ターボプロップの新鋭機で、TU104ジェット機とちがって、最初から旅客機として設計されたものだけに、乗心地はよく、悪天候にもかかわらず、あまりゆれなかった。
イリューシン18は一時間二十分後、午後九時三十五分トヨハラの空港についた。
さすがに国境の町だけに、すぐにはおりられず、民警が乗りこんできて、一人一人パスポートを検査した。
私たちは、真っ暗闇のなかを秋雨がふりしきるタラップをおり、二十年前まで日本の領土であったカラフトの地に第一歩をしるした。
闇につつまれて、飛行場の模様はわからない。
地元のテレビ局につとめる若いプロデューサーのほかに、労組委員長と称する中央アジアのカザフ人が、私たちを出迎えてくれ、テレビ局さしまわしの古びたバスに乗った。
バスは、デコボコ道をゆれながら飛行場の外にでた。
電灯のともった、日本式の低い軒の家が、夜の雨にぬれている。
また、狭軌で単線の踏切もわたった。
四十年間、日本人が住みついた体臭が、そこここにただよっているようだ。
十五分後、バスは、舗装された町の中心にはいった。
まもなく雨の夜空に、ロシア文字でユジノ・サハリンスクという緑色のネオンが輝く旧トヨハラ駅が目に入ってきた。
駅から百メートルぐらい手前でバスをおり、石づくりのホテル、ユジノ・サハリンスカヤの玄関に入った。
手にもったトランジスタ・ラジオから、日本の中波放送が勢いよくきこえてきた。
2 無表情な日本婦人 top
我々の部屋は三階六十六号室ときまったがその三階で思いがけない人に出あった。
それは、このホテルにつとめているという中年の日本婦人であった。
彼女は、私たちに会ったとき、一瞬はっとしたようだったが、あとは、全くの無表情であった。
カラフトに足をふみいれた夜、日本婦人にであうというのも、やはりカラフトである。
その婦人が、我々を部屋まで案内してくれた。
私たち一行は、さっそく、階下の食堂でおそい夕食をとった。 |

わたしたちが泊ったホテル
|
席には、私たちを出迎えてくれた地元テレビ局の若い人とカザフ人がいたが、このカザフ人はこの地区の共産党委員会の要職にもついているらしい。
片言の日本語がしゃべれる彼は、日本人からもらったというそまつなライターを得意そうにつかい、私たちに、
「ビールは、日本刀ものがおいしいですネ。
キリンビール、アサヒビール、サッポロビール、みな、飲んだことがあります。」
と、話していた。
私たちは、どういう経路で、彼が日本のビールを知っているのか興味をもったが、彼は時々日本の貨物船が、ホルムスク(真岡)やネベリスク(本斗)に入ったとき、日本の船員と接触する機会が多いからだという。
翌朝は、八時に目をさました。
カラフトは、北海道の北端からわずか数十キロしかはなれていないのに、日本とは二時間の時差があり、午前八時は日本の午前六時である。
窓の外は、まだ完全には朝になりきっていない。
駅のほうから、いききする蒸気機関車の汽笛が、しきりにきこえてくる。
日本時代のものと思われる駅の付属建物や、すすけた陸橋も見え、雨にぬれた駅前広場には、通勤労働者がいききしている。
ラジオをいれると、ききなれたNHKのラジオ体操の音楽がきかれる。
私たちは、日本の田舎の町にきたような錯覚におちいった。
しばらくすると、ドアをノックして、昨夜の日本婦人があらわれた。
彼女は、いくらか表情をやわらげ、はじめて日本語で。
「寒くありませんでしたか?」と、話しかけてきた。
彼女は、二つのとき、生まれ故郷の函館からカラフトにうつり住み、カラフトで終戦をむかえたあと、ロシア人と結婚し、現在、三人の子供の母親だという。
3 古い顔、新しい顔 top
ブロヒン市長の部屋には、共産党書記をはじめ、建設、経済、教育などの各局長がずらりと並んで、私たちをむかえてくれた。
ブロヒン市長は、さっそく、市の紹介をはじめた。
「ユジノ・サハリンスク(トヨクフ)は、ソビエトの最東端の町であるため、国家から本格的な投資がおくれて、町づくりをはじめたのは、一九六〇年以後である。
現在、市内には、古い木造住宅がまだ多く残っているが、一九七〇年までには、全部をとりこわして、新しい住宅街を建設する計画で、人口八万二千の町もその頃には、大体十五万人になる見込みだ。
現在、市内の電化は、五十五パーセントしかいきわたっていないし、上下水道や道路の改修が遅れているので、その方面に力をいれている。」
ブロヒン市長は、このようにのべ、市内の取材で疑問な点があれば、ここにいる局員連中になんでもきいてほしい。
また、あなたがたが同意するなら、市の責任者を案内役につけてもよい、と提案してきた。
私たちは、この国では案内役は監視役をかねることを知っているので、婉曲(えんきょく)に断った。
ところが市長訪問を終って、つぎの取材地にいくため、車に乗ろうとすると、市の建設局長のマコペツキー氏が、車に乗りこんできて、私たちの案内役を買ってきた。
人のよさそうなこの老建設局長は、おそらく、市長の指示によってきたのだろう。
私たちは、二台の車をつらねて力−ル・マルクス通のを東にすすみ、旭ヶ丘にのぼることになった。
車が山に入ると、周囲はうっそうとしたカラマツの林である。丘の中腹には、二階建てのヒュッテがある。
建設局長は、「戦前のものを改修したものだ。」と説明してくれたが、管理人は戦前建てたものだと、くいちがった説明をしていた。
この立派な建物は、昭和七年、世界スキー選手権大会の日本予選が、ここのスキー場で行われたときに建てたものであることはうたがいない。
この旭ヶ丘は、スキー場にはもってこいの地形で、現在、市では、旭ヶ丘をゴールヌイ・ウォーズドフ(山の空気)と、よんでいる。
それよりも、私たちをよろこばせてくれたのは、トヨハラの市街が、一望のもとに見渡せることである。
低い山脈にとりかこまれたスズヤ(鈴谷)平野の中にひろがっている市街、ところどころに白い鉄筋の新しい建物が見えるが、あちこちに日本式木造家屋も密集し、とくにトヨハラの駅の西側のほうは、昔の日本の町そっくりで、ほとんど手がつけられていないようだ。 |

旭ヶ丘のヒュッテ
昭和7(1932)年、スキー大会のとき建てられた。
|
私たちは、四十年の日本の統治時代の汗の蓄積を目のあたりに見るような気がした。
カメラをしだいに南のほうに向けて撮影していると、うしろから肩をポンとたたかれて、
「その方向には、飛行場があるからとらないでほしい。」と、注意された。
そのあと、音楽小学校と寄宿制小学校を訪ねた。
音楽小学校は、市の中心部に近いところにあって、一九五五年の創立、二部授業の小学生が、あき時間を利用してかよっているもので、ここでは普通教室のほかに二十一の小部屋があって個人指導も行っており、ソビエトに日本の家庭教師のような制度のあることに、ちょっとおどろいた。
寄宿制小学校は、近くに玉川が流れている市の東北部にある鉄筋三階建ての立派なもので、生徒数は三百八十人ということである。
案内してくれた校長の説明では、両親とも工場につとめて、昼間子供のめんどうを見れない家庭や、深夜作業の多い労働者の家庭の子供が勉強しているということである。
この校長は、朝鮮人系と思われる実直そうな人である。
私たちが、子供は家に帰りたがらないかときくと、校長は、
「もちろん、親と一緒にくらすほうがいいにきまっているが、ここは、第二の家庭だ。」と、答えた。
そこで、寄宿舎を見学した。
二十ぐらいのべッドをならべた、殺風景な部屋ばかりで、校長のいうような家庭的な雰囲気はない。
しかし子供たちは、廊下で会うと、かならず「ドラスチエ」(こんにちは)と、行儀のいいあいさつをして、表情は明るい。 |

寄宿制小学校
|
トヨハラでは、三十七の小学校で二万人の子供が勉強しているが、この寄宿制小学校は、市内ではただ一つ、三百七十人の子供は、いわゆる少数のめぐまれない子供かもしれない。
ソビエトの社会にも、音楽小学校にかよわせるような家庭もあれば、こうして寄宿舎にいれねばならない家庭もあることを、目のあたりに見せつけられた感じである。
旭ヶ丘の麓には、二つの保育所がある。
一つは新興住宅街の中にあって、数日中に開所するという近代的なもので、保母さんたちは開所準備に大わらわであった。
赤ちゃんから六歳までの就学前の子供を収容するもので、発育年齢ごとに教室がわかれていて、採光、設備とも満点である。
建物の設計は、モスクワにあるものをモデルにしたという。
そういえば、この保育所のある新興住宅街も、モスクワのマンモス住宅団地で有名なチェリョームシキの名をとって、サハリン・チェリョームシキとよんでいる。
モスクワ直輸入の町づくりである。
もう一つの保育所は、新興住宅街と道をへだてた白カバのなかにある。
この保育所は、旧カラフト庁長官官邸につくられたもので、林の奥に二階建ての白い洋館が見える。
庭ては、人工衛星をかたどったすべり台や砂場で、子供たちがが嬉々(きき)としてあそんでいる。
この官邸は、日本時代、市民から白カバ御殿とよばれたもので、建てられたのは明治四十一年というから、約六十年ほどまえの建物である。
ときうつり、世がかわるということをしみじみ感じないわけにはいかない。
4 お寺は映画館に top
私たちは、この日一日じゅう、市の建設局長の案内で、新しいトヨハラを、次々と見せられたので、翌日は日本時代の古い建物を撮彩することを考え、夜、同行のスタチェンコフ氏にそのむねをつたえた。
ところが、彼は、
「ここは、ごらんのとおりの国境地帯であることを忘れないでほしい。
市当局としては、一年後にとりこわすかもしれない古い日本の建物を、撮影することはゆるさないだろう。」と言う。
日本人に郷愁をおこさせるような、日本家屋などの撮影を、相手がよろこばないことは百も承知だが、日本人記者として残っている日本人家屋や施設を撮影しないで、おめおめ日本に帰れるわけはない。
私たちは、午前一時ごろまで議論し、翌朝、市当局と交渉するごとにしてわかれた。
翌日、市当局から、かぎられた地区でなら、古い建物を撮影することをみとめる、という返事があった。
私たちは一刻もはやく、日本時代の建物を撮影しようと思ったが、午前中は製粉工場の取材が組まれていた。
製粉工場は、市の北の郊外にあり、あと一週間もすれば操業するという。
トヨハラでは、昔の日本の工場施設をほとんど使っているだけに、新しく建てた工場は、ぜひ私たちに見せたかったのだろう。
5 親日的な朝鮮料理屋のおばさん top
私たちは、まえからトヨハラに朝鮮料理屋があるときいていたので、この日、同行のモスクワ放送の三人と一緒にでかけた。
駅の近くの朝鮮料理屋は、六十五平方メートルばかりの平屋建てで、私たちがドアをおすと、奥の調理場にいた朝鮮人のおばさんが、大声で、
「コンニチハ。」と、よびかけてきた。
一見して、日本人とわかったのだろう。
ひさしぶりにきく日本語はもちろんだが、親切にも、
「メニューにないものでも、すきなものがあったらつくりますよ。」
と、いってくれたのがことにうれしかった。
シペリアのロシア料理にあきあきしていただけに、私たちは、焼肉とウドンを注文した。
料理をはこんできたこのおばさんは、
「材料は内緒、口にあわんかも知れんヨ、味の素もないしネ。
ここの人(ロシア人)は、しつこい(油をたくさん使うこと)からネ。」
と、いいわけしていた。
代用品の醤油のようなものに、唐カランとニンニクをいれたものが案外おいしく、私たちは焼肉とウドンをかるくたいらげた。
戦前からここに住んでいた朝鮮人から、こんな親日的な扱いをうけたことにおどろいた。
帰りぎわにドアのところまでおくってきたおばさんは、
「本当によくカラフトまできましたネ、帰るまでにひまがあったら、またきてくださいヨ。」
と、わかれをおしんでいた。
ホテルに帰ると廊下の電話で、例の日本婦人が電話をかけていた。
ドアのすぐそばなので、話し声がつつぬけにきこえてくる。
話しのようすから、娘にかけていることがわかったが、話の切れ目では、
「ハラショー? (わかりましたか)」というロシア語を使っている以外は、全部日本語で話しているのにはおどろいた。
あとできいたのだが、こうした日本人を父や母にもっているロシア人の家庭では、日本語とロシア語をチャンポンで使っているところが多いということである。
町で会ったロシア人が、トヨハラでは片言でも日本語をしゃべる人が三十五パーセントいるといったのも、うなずけない話しではない。
市内に残っている日本時代の建物と同様に、日本語もトヨハラでは、今なお生きていることを知った。
6 増えているサケ top
|
 日露戦争当時の大砲(博物館の庭) 日露戦争当時の大砲(博物館の庭)
|

境界石(博物館玄関わき)
|
翌十九日、私たちは、午前中、博物館を取材した。
博物館の庭には、一九〇五年の日露戦争当時、旅順口の要塞にあった大きな要塞砲と、日本の砲二門がおかれ、ロシア人の女の子が無心にあそんでいた。
また玄関のそばには、日露戦争後一九〇六年に北緯五十度の日露国境におかれていた境界石があった。
片面には「大日本帝国」という文字と菊の紋章が刻まれており、反対側には、帝政ロシア時代の文字で、「ロシア 一九〇六年」と彫りこまれ、さらに横の面には、「明治三十九年天第三号」と、書かれてあった。
博物館のなかの歴史の部を見ると、サハリン島(カラフト)に最初に上陸したのは、一六四〇年、モスクビチンというロシア人であり、一七八七年にはフランス人のラペルーザが、また一八〇五年にはアメリカ、ロシアの合同探検隊が上陸したとあって、間宮林蔵のことについては、ひとこともふれていない。
また、一番新しい歴史の部屋には、一九四五年八月八日、ソビエトが日ソ不可侵条約を破棄して、南カラフトや千島に進攻したときの進攻図や写真がかかげられ、また棚には、旧日本軍の軽機、重機、てき弾筒、三八式歩兵銃などが並べてあった。
全体としては、対日戦争を比較的じみに扱っていて、陳列場所も、部屋の隅のようなところであった。
しかしこれらの陳列品のなかで、コトン(ボペジーノ)、ナイロ(ゴステラ)などで赤軍の勝利を祝った写真が目につき、国境近くでは、はげしい戦闘があったことを物語っていた。
また、南カラフト進攻図によると、最後の日本軍降伏の比が九月九日となっており、八月十五日以後、相当期間、カラフトの日本軍は、局地的な抵抗をしたことがわかった。
この日の午後、トヨハラの北、車で四十分のところにあるソーコリ村のサケの養魚場を訪ねた。
養魚場は幅三十メートルくらいの川を木の柵でしきり、そこで産卵にのぼってきたサケをせきとめており、木の柵付近は、サケであふれている。
最近、北海道の川をのぼるサケが減っているときいていただけに、おびただしいサケの群れにはどぎもをぬかれた。
所長のラマザノフ氏の説明によると、サケは木の柵の付近で深さ二メートルにわたって、ぎっしり川底までうまっているという。
文字どおり、サケの頭の上を歩いて、向こう岸にわたれるほどである。
この木の柵には、鉄の柵がとりつけられておい、すさまじい勢いでのぼってきたサケは、次々とハナを鉄の柵にぶつけていたが産卵のために、柵をやぶってでも上流へのぼろうとするサケの本能には、一種のすごみが感じられる。
ここですくいあげられたサケは、ペルト・コンベアで、別むねの作業場におくられ、そこでオスとメスによりわけられ、メスは、女作業員の器用な手さばきで、次々と腹をさかれ、洗面器のような器に真紅の卵(イクラ)が、どっと流しこまれる。
洗面器に半分くらいのイクラがたまると、べつな女作業員のところに運ばれ、今度はオスの腹から精子をしぼりだして、イクラの上にそそぐ。 |

ボリショイ・タフイ川を
さかのぼるサケの大群
|
精子をそそがれたイクラは混ぜられた上、べつの部屋に運ばれ、そこで三時間ばかり水で冷やされてから、孵化場へ運ばれるという。
ラマザノフ所長は、このサケの人工孵化施設は、ソビエトでもっともすすんでいると、自慢していた。
そして昔、この付近には日本人がつくった孵化場があったときいているが、くわしいことは知らないと、話していた。
私たちはそんなことよりも、日ソ漁業交渉の結果、毎年、日本でのサケの漁獲量は、資源保護という名目で減らされてきているので、実際にサケが減っているかどうか知りたいと思って、所長に、
「最近、日本の北海道では、サケが減っているが、ここではどうか?」と、訪ねてみた。
私たちは、所長は政治的な配慮から、カラフトでもサケは減っていると答えるかと思ったら、逆に、
「サケは、けっして減っていない。むしろ、我々の人工孵化で年々増えている。」という答えであった。
しかし、この養魚場を視察したことのある日本の漁業専門家によると、ソビエトではサケを海でとらないで、できるだけ川へのぼらせているということで、川にのぼるサケが多いからといって、オホーツク海のサケが増えているということにはならないそうだ。
この養魚場のある川を、ロシア人はボリショイ・タコイ川とよんでいたが、日本時代は単にタコイ川(多古恵川)と、よばれていた。
また、養魚場のあるソーコリ村は、日本時代何とよんでいたかわがらなかったが、川口まで四十キロくらいあるといっていたところから、おそらく「富岡」にちがいないと思う。
土地の人の話しでは、この付近に日本の旧軍用飛行場があったということであるが、現在、それがどうなっているかは、取材のしようがなかった。
私たちは、タコイ川の付近を歩いたが、しずかな林と日本時代の家屋の集落が見られた。
十月十日、トヨハラでの取材の最終日である。
私たちは、地元のサハリン・ラジオ・テレビ国家委員会の議員の紹待ということで、トヨハラの東、オホーツク海に面したトンナイ湖(富内湖)のほとりにある狩猟と魚つりの保養所を訪れた。
私たちは、オホーツク海の岸を見ることができると期待していたが、海岸までは六キロもあり、ついに海岸まででることができなかった。
トヨハラからトンナイ湖までの道路は、日本時代のものとみえ、沿道にはところどころに古い木造家屋が見られた。
私たちは、トンナイ湖を舟でわたって保養所についたが、低い丘や森にかこまれたトンナイ湖の神秘的なしずけさは、もう北海道でもあじわえないだろう。
マリモがとれるので有名なこのトンナイ湖を、土地の人々は、トンネンチャコとよんでいる。 |

トンナイ湖の船着場
|
私たちを案内してくれた保養所の管理人は、終戦後捕虜となった日本の将校と仲良しになり、この湖でよく釣をしてたのしんだと、片言の日本語で話してくれた。
保養所の近くを散歩すると、湖にそそぐ川のほとりに古い木造の小屋があった。
これは、日本時代につくられたもので、山火事の見張りや、休憩所につかわれたという。
なんでもない小屋にも、当時の日本人の生活がしみこんでいるようである。
私たちは、この日の夜十時の飛行機で、ハバロフスクに戻ることになっていたので、八時前トンナイ湖からトヨハラのホテルに帰った。
私たちは、飛行機が出発する一時時前の九時までに空港につけばよいと考えていたところ、突然、飛行機は九時に出発するという知らせをうけた。
一行は、大急ぎで空港にかけつけた。
もう出発十五分まえである。荷物の計量などの手続きのことを考えて、私たちはほとんどあきらめ、今夜はトヨハラに泊まる覚悟でいた。
一行がタクシーで飛行機のそばまでかけつけると、ハバロフスク行のアントーノフ10A型は、すでにエンジンをかけ、四つのプロペラは発進直前の勢いでまわっている。
パスポートの検査を終った民警も、車で空港事務所に引返そうとしていた。
ところが、すさまじい勢いで回転していたプロペラが急に弱まり、暗闇のなかからタラップが引出された。
だれがどのように手配したのか知らないが、これには私たちもおどろいた。
私たち一行は、一人一人タラップをあがった。
三人めに私が機内にはいったとたん、スチュワーデスがここまでと手で制して、すぐあとについてきた古成記者ら二人は席がないと、機内にいれてくれない。 |

トヨハラ市内
|
私たちは一行五人で、二人だけ別行動はとれないと説明していると、突然、機内の席にいた二人の軍人が席を立って、飛行機から出ていった。
私たちに席をゆずってくれたのである。
アントーノフ10A型は、まもなく発進し、ハバロフスクに向かった。
ハバロフスク空港からトヨハラに出発するときも特別な配慮をうけたが、今度のように発進直前の飛行機をとめ、しかも乗っていた客に席をゆずらせてまで乗せてくれるのは、一体、どういう理由なのだろうか。
木戸ごめんのサービスには、全く恐縮してしまった。
top
**************************************** |









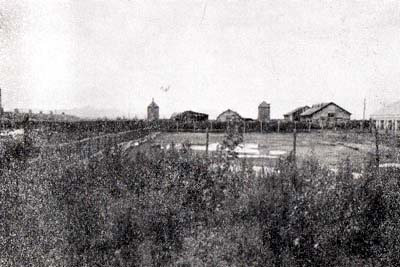
 日露戦争当時の大砲(博物館の庭)
日露戦争当時の大砲(博物館の庭)


