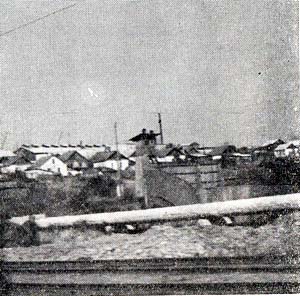|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章
八 アムール川のほとりで、ハバロフスク
1 アムール川にしずむ夕日
top
ハバロフスクといえば、アムール川(黒竜江)と切っても切れない関係にある。
市の西を流れるアムール川の川岸一帯は公園になっていて、見はらし台や、競技場があり、市民のいこいの場になっている。
風のつよい日は、大波が川岸にうちよせ、まるで、海のようである。
ハバロフスクは、人口四十万をこえる極東地方の政治・軍事・産業・文化の中心で、イルクーツクよりも活気にあふれている。
私たちは、ハバロフスクに帰ってきた翌日、ハバロフスク地方の河川局の好意で、観光船を一隻借りうけ、アムール川にのりだした。
市の付近の川幅は約一・五キロ、泥水のように黄色くにごった川で、川下のほうには今度の大戦後、日本軍捕虜が貨車におしこまれたまま、いよいよシベリア送りを観念したという鉄橋が、十九の橋げたの上にのっており、川上のほうは例の中ソ国境紛争があった中ノ島にさえぎられて、見とおしがきかない。
中ノ島はロシア語でタラバルスキー島、つまりおしゃべり島とよばれ、背の低い樹木と砂浜におおわれているが、島全体が水面からいくらも高くないので、大波がうちよそれは、水面下に没してしまうような感じだ。
一年間に何回もの国境紛争があったとは、とうてい信じられないくらいのしずけさだが、島に上陸してみなくては、本当のところは何もわからない。 |

ハバロフスク市を流れるアムール川。
岸べには、枯れ木などがうちよせられている

アムール川の上から見たハバロフスクの町
|
夜間、川岸から中国領のほうをのぞむと、かすかな灯が見えるが、これが中国の国境警備隊のものなのか、普通の民家のものなのか、あるいはソビエトの漁船のものなのか、確信をもっていうことはできない。
いずれにしても、アムール川をへだててすぐのところに、旧満洲、今の中国領があることだけは事実で、私たちは何となく、日本に近いところに来たなという印象をもち、一種のなつかしさを感じたものである。
中ノ島の裏側の川幅は、かなりせばまっているように見うけられたが、これに対しアムール川に合流しているウスリー江の川幅はかなり広い。
ハバロフスク市の付近は、アムール、ウスリー両河川の合流点になっており、石炭や石油をつんだ輸送船や、乗客を沿岸各地=コムソモルスク・ナ・アムーレ市、ニコラエフスク市などに運ぶ船舶がひんぱんに往来し、かなり活気がある。
また、川下のほうに船をはしらせると、アムール川の河川港があって、停泊中の中型輸送船、倉庫、工場、石油を運ぶ貨車の列などが手にとるように見え、アムール川が、ハバロフスク地方と、沿海地方の産業開発に重要な役割をはたしていることがわかる。
ここでは鉄橋をのぞいて、何を撮影してもかまわないという、同行のハバロフスク・テレビ局のプロデューサーの返事に、私たちは肩すかしをくったような気がした。
アムール川にしずむ夕日は、文句なく美しい。
十月十三日だったが、真赤な太陽が午後六時をすぎると、段々と卵型の長円形になっていき、平べったい鏡モチのようになって、午後六時十八分、完全に対岸の地平線に没した。
一瞬、空が真赤に焼けたようになり、徐々に暗黒の世界にうつりかわっていく。
日役寸前の太陽のまえを横切っていく船の姿にも美しさを感じるけど、アムール川の日没の光景は、私たち日本人の胸に、ジーンとせまるものがあった。
私たちは電線工場、サナトリューム、ホール木材コンビナートを取材するため、三回もウラジオストク街道を南下した。
これは昔、スターリン街道といったところで、ハバロフスク市をはずれるあたりの左側のほうに、望楼(ぼうろう=見張り塔)を四つ見た。
そのうち三つは朽ちはてたような感じのもので、一つだけは、夜間照明用の大きなライトが二個、望楼の下についていた。
このあたりは、想像するに、終戦後、日本捕虜を収容していたキャンプの跡らしい。
付近には、傾きかけた木造の小屋がずらりと並んでいて、何となく肌寒い感じをあたえる。
シベリアに抑留された日本軍将兵はもちろん、中央アジアや、モスクワ郊外のイワノボあたりに抑留された同胞も、みな一度に、ハバロフスクの収容所に入れられたといわれており、二十年前を思いおこして感無量のものがあった。
当局は、こういった古いものを撮影されることを心よしとせず、右側にずらりと並んでいる五階建てのアパート群の方に、私たちの関心をひこうとした。
きくところによると、これらアパート群も日本軍捕虜がつくったといわれており、このあたりには日本人の血と汗が流れているような感じだ。
市内から五、六分、べつの方角に車をとばすと、小高い丘があって、鉄柵にかこまれた大きなロシア人墓地がある。
この墓地を入っていって左側、東のはうに、日本軍将兵の墓地があった。
イルクーツクやウラン・ウデの日本人墓地と同じように、ここでもコンクリートの区画で一人一人の墓がつくられ、墓には番号がうってあった。
ただちがう点は一人一人の墓のほかにも、何人かの遺体を一緒に埋葬したのではないかと思われるような、かなり大きい墓が二つあったことだ。
ここの墓の一番大きい数字は七十六だったが、一ヵ所に複数の遺体が埋葬されていることになると、ここにほうむられている人の数は七十六人をかなり上回ることになるだろう。
ここにはすでに四年前、遺家族の墓参団が参拝しているし、政府関係者や実業界の人々も訪れているので、日本字で書かれた慰霊塔が立っており、それがせめてものなぐさめになった。
墓地の正面には、将官のものと思われる大きな墓標が、鉄の柵でかこまれていて、柵の中にはごく最近、だれかが捧げていったと思われる花束が備えてあった。
私たちが、日本人として戦後はじめて訪れたウラン・ウデの墓地とくらべると、ハバロフスクの墓地は、すでに多くの日本人が訪れて供養しており、憤(いきどお)りとも、悲しみともつかない気持にかられていた私たちも、その花束を見て、ホッと安堵の胸をなでおろしたものである。 |
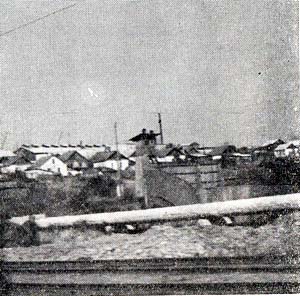
日本人収容所あとの望楼(監視塔)らしい

日本人墓地
|
ハバロフスクには、外国人旅行者が泊れるホテルが三つある。
私たちは九月二十六日、イルクーツクからハバロフスクにきてから、十月十八日、フルシチョフ首相解任にともなう情勢の急変により、モスクワにひきあげるまで、三週間以上を出たり入ったりしながらも、ハバロフスクですごした。
この間、「アムール」、「ダーリニイ・ウォストーク(極東の意)」、「ツェントラ・リナヤ(中央の意)」と、三つのホテルを転々とした。
極東の表玄関、ハバロフスクのホテル全部を泊まり歩いた日本人は、おそらく他にあるまいと思われるので、ホテルの品定めをしてみょうかと思う。
私たちが最初に泊まったホテルは、「アムール」だった。
はじめ、イルクーツクを出発するさい、インツーリストに、日本で評判のよい「ダーリニイ・ウォストーク」を予約するよう、たのんでおいたが、いざついてみると、「ダーリニイ・ウォストーク」は満員だから、「アムール」に泊まってくれといわれた。
その時の説明によると、どうも「ダーリニイ・ウォストーク」のほうが、「アムール」より一段格が上なため、「ダーリニイ・ウォストーク」を希望する観光客でいつも満員だということらしい。
私たちはしぶしぶ「アムール」におちついたが、古いホテルのわりには内部はきれいで、しかもレストランでは、シベリアのどこでも食べたことのないメロンヤマスカットをだしたり、料理もうまかったりして、ホテルのよしあしは何も古い新しいだけではきまらないのだな、ということを痛感した。
しかも、ここには、フロントのわきに電報局があり、寒い夜道をとことこ電報局までいく必要もなかった。
ナホトカから帰ってきて泊まったのは、はじめに希望していた、「ダーリニイ・ウォストーク」ホテルだった。
ここは、ハバロフスクの目抜き通り、カール・マルクス通りに面していて、夜はソビエトではまだまだめずらしい、グリーンやピンクのネオンが夜空にかがやく、何となく派手な雰囲気をもったホテルだった。
場所が場所だけに、午前一時の門限まで人の出入りがはげしく、かっぷくのいい空軍将校と腕を組んで、これまたヒップ一メートルもあろうかと思われるような女丈夫が、毛皮のシューバー(外套)に身をつつんで、ドッシドッシと入ってくる姿も、それほどめすらしくはなかった。
最後に泊まった「ツェントラ・リナヤ」ホテルはオリンピック東京犬会に参加する外国人選手や観光客が、ハバロフスク、ナホトカ経由で日本にいくというので、それを目当てにつくられたもので、私たちが泊まったときは、三週間前に店びらきしたばかりだった。 |

日曜日のカール・マルクス通り
|
従ってテーブルの上に電話器がおいてあっても、回線がつながっていなかったり、テレビがおいてあっても、テレビを見ることができないといった不手際が数多くあった。
しかし、それにもまして、建物のつくりが雑で、ドアがいくら閉めてもあきっぱなしになったり、トイレのパイプが上半分は壁の中にぬりこめられているのに、下半分が外に露出していたり、はやくも壁に大きなヒビが入っていたり、電気スタンドが二つおいてあるのに、差込は一つしかない、といったていたらくである。
ソビエトの建築技術の粋を集めたであろう「ツェントラ・リナヤ」ホテルの仕上を見て、いかに急いだかがわかった。
まだ、壁のにおいが残っているような新築のホテルに、すでに修理工が入っていて、大じかけの修理をしている。
天井が低くて、何となく寸づまりの感じがするのは、日本などでも新しいビルにはよくあることなので、文句はいわないが、「アムール」ホテルや「ダーリニイ・ウォストーク」ホテルの建物のほうがどっしりしていて、つくりもいいのは、一体、どうしたことだろう。
古い建物のはうがいいといわれては、「ツェントラ・リナヤ」をつくった建築技師や労働者はめんぼくあるまい。
またここには電報局がなくポストもないので、一々カール・マルクス通りの郵便局まで、でむかなければならなかった。 |

カール・マルクス通りの
郵便局と公衆電話
|
ポストくらいはすぐにもおけそうなものだが、ふしぎなものだ。
もっとも、フロントのわきに大きな机がおいてあって、「郵便局」と書いた札がぶらさがっているにはいたが、九日間の滞在中、ここに人が座っているのを見たのは、ただの一回だけだった。
「アムール」のように、夜八時になっても若い娘さんの局員が座っているところもあるのに、ここは、よくはずかしくもなく「郵便局」の札をぶらさげておれるものだ。
以上、三つのホテルに泊まってみて感じたことは、古いホテルのほうが、建物は一見うす汚れているように見えても、かえって設備もサービスもよく、料理もうまいということだ。
この三つのホテルに点数をつけるとすれば、「アムール」八十点、「ダーリニイ・ウォストーク」七十五点、「ツェントラーリナヤ」五十点ということになる。
「ツェントラ・リナヤ」には、「インツーリスト」の事務所があり、その点では、外国人に便利なのだが、長期滞在しようという方には、絶対にお勧めできないホテルである。
2 “客観的に報道してください” top
|

ハバロロスクの労働者
|

電車を待つハバロフスクの労働者
|
十月十二日、「アムール・カーペリ」とよぶ電線工場を取材した。
工場は、ハバロフスク市からウスリー江に沿って南下した市のはずれにあって、工場の敷地の端はウスリー江に面している。
この電線工場は、一九五六年にできたまだ歴史の新しい工場で、オートメ化のかなりすすんだ、しかも規模の大きい近代的工場だった。
技師長の話しによると、ここでは、長距離用通信線、電話線、高圧線、普通の電線など、およそ千種類の電線をつくっており、製品の大部分は、極東地方に供給している。
技師長の案内で工場内を見てまわると、二十歳くらいの若い女子工員がたくさん働いている姿が目についた。
きいてみると、二千人の労働者のうち半数が女子で、給料は性別に関係なく、熟練度によって八十ルーブルから最高二百ルーブル、平均百ハルーブルということだ。
電線を巻く機械のうち、外見もすっきりしていて性能がいい機械を見てみると、ドイツ語でベルリン製、ドレスデン製と書かれてあり、アルミニュームのくずが入っている袋にもケルン製と印刷されてある。
もちろん、レニングラード製と書いてある一見性能のいい機械もあるにはあったが、なにしろこの工場では、技師長の部屋にいるときから私たちには私服がつきっきりで、警戒が厳重をきわめていたため、おちついた取材ができず、工場のスケールなどはわからない。
技師長自身も、「外国人特派員は、事実を客観的に報道しない癖がある。」といって、撮影するさいには、すべて私の許可をとりつけること、工場全部を見せることはできないことなどを、しきりに強調していた。
私たちはこれまでの工場取材で、ここのような警戒的な態度をとられたことは一度もなく、まじめに取材しようとやってきた私たちにしてみれば、不愉快きわまる工場だった。
カラフトと同じように黒いソフトをかぶり黒い外套を着て、私たちに紹介されない人物が三人、いつも私たちのあとにつづき、私たちが電線にさわって見ていると、ツーッとそばまでやってきて、だまって私たちのしぐさを監視している。
カメラを向けると、普通のロシア人なら顔をそむけるところを、この三人は逆に顔をちかづけてくる。
スターリン時代のソビエトを思いおこさせるような、あとあじのわるい取材だった。
思うにまだまだソビエトには、スターリン時代の影響を強く残している人間や企業があり、そこでは革命後から、つい最近までつづいていた陰険な秘密主義をそのまま踏襲しているところがあるのだろう。
3 素朴なアムール漁民 top
|

アムール川の漁業コルホーズ
|

漁業コルホーズの議長
|
アムール川では、ばかでかい魚がとれる。
体長一メートルもあるサザン、アムール、トルストローブなどとよばれる、アムール特産のコイをはじめ、片手では重くて持上げられないタイメン、六十センチもあるアムール・カマス、ナマズ、ウグイ、フナ、それに、日本にはいない川魚ズメーゴーロフ、カキトカという魚など、いずれも気味が悪いほどばかでかい。
アムール産の川魚が、どうして、こうも大型ばかりなのか、理由はわからない。
私たちが訪れた漁業コルホーズは、ハバロフスクからアムール川をくだって二十五キロ、一九二九年に十二人で力をあわせて、協同組合をつくったのがそもそもはじまりで、戦前はそれはどの収入をあげることはできなかったが、戦後、とくに一九五三年(スターリンの死んだ年)から収入が飛躍的に増えたと、議長は話していた。
議長の説明によると、国家の投資が増えたこと、漁船の保有量が増えたこと、漁民の数が増えたこと、冷凍貯蔵庫が備えつけられたことがその理由で、工場労働者の中から漁業コルホーズにうつってきた人間が増えてきたため、今では、百六十四人のコルホーズ員をかかえている、ということだった。
冷凍貯蔵庫が備えつけられるまでは、魚を生のまま加工工場におくっていたため、たんに原料を供給するだけだったが、貯蔵庫ができてからは、冷凍魚をそのまま市場や食糧品店に売り渡すことができるようになり、その結果、収入が急速に増えたという。
ここの一九六三年の漁獲高は、六百五十五トン、収入は四十七万ルーブル(一億八千八百万円)である。
私たちは、問題のサケについて議長にきいてみた。
ロシア語で「ケタ」とよぶ白ザケは、一九六三年に四十トン、一九六四年は五十トンの水あげがあったが、サケの漁獲は一九五七年以来、日ソ漁業条約によって制限されているので、漁獲にも神経を使うとのことだった。
現に、漁船から魚を陸にあげているとき、私たちが偶然白ザケを発見したので「ケタ」だとさけぶと、漁民たちは何かわるいことでもしたかのように、もちあげた白ザケをまた船のなかにおろしてしまった。
また、「カルーガ」とよぶアムール産のチョウザメは、年々資源がへる一方なので、一九六〇年以降二十年間、漁獲を禁止しているということだった。
これは、ソビエト人が好んで食べるイビフ(キャビア)を、カスピ海産のチョウザメからとるだけでなく、この付近でも自給したい、というハバロフスク地方当局の考えによるものだ。
|

魚をいっぱいつんでかえってきた舟
|

よろこびいさんで獲物を水あげする漁師
|
このコルホーズには、小船が四十隻、中型の発動機船が二隻あり、議長の案内で見学中、偶然一隻の小船が漁獲を終えて川上から帰ってきた。
さっそくかけよってみると、長さ七メートルほどの小船から、耳覆いのついた毛皮の帽子をかぶり完全に冬じたくをととのえた漁師が二人、意気ようようと陸にあがってきた。
船内には、まえに書いたようなばかでかい魚がいっぱいつんであり、迎えに出た二人の妻たちも手伝って、さっそく水あげがはじまった。
なかには重くて片手ではもちあげられないような魚もまじっていたが、漁師が威勢がいいのはいずこも同じで、かけ声こそかけないが、四人の顔には豊漁のよろこびがあふれていた。
男たちにきいてみると、二日前にコルホーズを出発して、アムール川の上流、中ソ国境付近に向かい、二晩ほとんど一睡もしないで魚をとったという。
ソビエト人はふたことめには、一日七時間労働制を強調するので、それでは労働時間が長すぎやしないかと質問すると、
「ここはコルホーズだから、労働時間にはしばられない。
魚はいる時にとらなければならないので、労働時間などといってはおれない。
これで、二、三日は、家でゆっくりやすめる。」と話していた。
もっともそうはいっても、日曜だけはかならず家にいて、家族と休みをたのしむという話しだ。 |

漁師の妻も水あげを手伝って
|
北太平洋で操業している大型漁船の漁船員たちは、魚がいても七時間労働制を忠実にまもって、漁獲の途中でも仕事をやめるという話しをどこかで聞いたことがあるが、国営漁業とコルホーズ漁業の差が、こういうところにあらわれているのだろうか。
帰りぎわに議長は、一メートルもある大きいコイを四ひきみやげにつつんでくれた。
生魚をもらっても日本までもって帰れるわけでなし、それにあまりにも大きいので、見ただけで食欲はなくなっていたが、議長の好意はありがたくうけた。
市の西のはずれ、アムール川に面したところにハバロフスクの魚の加工工場がある。
大男の所長は、いかにも人のよさそうな男で、この工場は小さいし汚いので、お見せするようなものは何もないと、謙遜しながらも、私たち一行に白衣を着せて案内の先頭に立った。 |

アムール川のほとりの漁村
|
この魚加工工場は、アムール川沿いにある四十のコルホーズや、ウラジオストクから集ってくる魚を加工して、ハバロフスク市民の台所をまかなうことを第一の目標にしている。
アムール産の川魚は、ニコラエフスクやコムソモルスクなど、アムール川下流でとれる魚は多いということで、工場内には、白ザケ、コイ、ナマズ、アムールーカマスなどが山のように積まれ、みるみるうちに塩づけ、冷たい燃製、熱い燻製、フライに加工されていく。
ウラジオストクから運ばれてくる魚は、もちろん海の魚で、カレイとニシンが大部分を占めていた。
燻製に冷たい熱いの区別があるのはおもしろいので、製法をきいてみると、たとえば冷たい燻製をつくる場合、白ザケなら七十二時間、ニシンなら二十四時間、白ザケは約三十度、ニシンは約二十五度の煙でいぶす。
熱い燻製をつくる場合は、百七十度から二百度という高温の煙で、三時間あまりいぶすということで、カマの中には、いろいろな種類の魚が串ざしになって、いっぱいぶらさかっていた。
サケの目ざしとは豪勢なことである。
この工場は、ハバロフスク地方の同種企業では、最初に七ヵ年計画を一年もまえに達成した工場だということで、所長は得意そうであった。
取材を終って帰ろうとすると、所長がちょっと待ってくださいという。
何だろうと思っていると、魚のごちそうをするから食べていけ、という。
ごちそうのほうは、またの機会にしてください、といって腰をあげた。
所長は、秘書をよんでだいぶ長い間相談していたが、それではかわりにサケの煉製をもって帰ってくださいといい、私たちが手をふってそんな心配はご無用といっている間に、テーブルの上には紙につつんだ燻製のサケが、ずらりとならべられた。
私たちは、さあ一体、これをどうしたものかととまどいながらも、レストランで食べるサケの燻製がうまいのを思いだし、ありがたく頂戴することにした。
このみやげはモスクワへもって帰って、井上特派員の奥さんに焼いてもらったら、ちょうど新巻を焼いたのと同じような味になり、ほっぺたがおちそうになるほどうまかった。
ハバロフスクの魚関係者は、さきにいったコルホーズといい、ここといい、非常に純朴で、おみやげをもたして帰すところなどは、日本とよくにている。
電線工場の技師長などとは全くちがった、底ぬけに明るい好人物ばかりだった。
4 ハバロフスクのテレビ局 top
|

ハバロフスクのテレビ局
|

ハバロフスク・テレビ局の婦人局長
|
ハバロフスク滞在中、私たちの同業、テレビ局を見学した。
局長は五十歳くらいのロシア婦人で、NHKのことはよく知っているとみえて、丁重に私たちを局内くまなく案内してくれた。
この婦人局長の話しでおもしろいと思ったのは、マイクロ回線が、現在、ウラルのスベルドロフスクを経て、ノボシビルスク近郊まできており、ハバロフスクには、一九七〇年までにくることになっている、という話しだった。
従って、モスクワ・テレビ局の番組中継は、一九七〇年にならなければできないわけで、それまではフィルムを空輸して、放送することになる。
放送時間は、一日五時間、週三日は昼間宅放送しており、このうち一時間半が自主番組、残りは映画とモスクワから空輸されてくるフィルムでうずめている。
ちょうど私たちが訪れたとき、ロシアの詩人レールモントフの誕生日を記念する、子供向け番組のリハーサルが、一番大きなスタジオで行われていた。
まだうら若い女性が、プロデューサーのアシスタントとして、きびきびした動作で、出演者やカメラマンに注文をつけているのを見て、放送の世界は、どこでも同じなんだなという気持を強くした。
ここには、わずか四つのスタジオしかなく、職員も百二十人という少なさだ。
カメラは、ユジノ・サハリンスク・テレビ局でもそうだったが、ここでも全部ハンガリーのブダペスト製だった。
スタジオ見学ののち、試写室でハバロフスク・テレビ局製作の記録映画を三本見せてもらった。
そのうち一巻は、ニコラエフスクの近くにあるマゴ湖から木材を日本船に積込むところや、筏に組んだ木材が、間宮海峡(タタール海峡)をへて日本海に流れていく模様などを、あざやかにうつしていた。 |

子供向けテレビ放送のリハーサル風景
|
私たちのはじめの計画では、マゴ湖を訪れて、日本船に木材を積込むところを撮影することになっていたので、この記録映画は、私たちの関心を大いにそそった。
また私たちはハバロフスクで、極東地域やアムール川の経済開発の実状を知るため、ロシア共和国国家計画委員会に属する「極東経済地域計画委員会を訪れ、フィラートフ議長から極東地域の経済開発、アムール川の開発などについておよそ二時間、じっくりと話しをきいた。
それによると、一九五六年からはじまった中ソ合同調査は、中ソ関係が悪化している現在では、事実上、別々の調査になって、ソビエトはアムール川の支流ゼーヤ川に水力発電所を建設するなど、ゼーヤ川の開発に力をいれているのに対し、中国は、スンガリー江(松花江)の開発に重点をおいているということである。
ゼーヤ川では、すでに出力百万キロワットの水力発電所の建設がはじまっており、一九七〇年には、第一の発電機がまわりはじめるということである。
ゼーヤ州水力発電所の発電コストは、世界一をほこるブラーツク水力発電所の発電コストよりさらに安くなることははぼ確実だ。
次に極東地域の経済開発についていえば、最近もっとも著しい発展をとげているのは、林業、漁業、鉱山業の三部門である。
とくに林業は対日貿易との関連においても著しい発展をとげ、木材の生産は七ヵ年計画中に六十パーセント増えた。
これにつれて、木材加工工業、パルプ産業の発展は目ざましい。
対日貿易では、木材の輸送問題にやや難点があるが、日本が、沿海州の木材をはじめ、鉄鋼業、鉱業、建設産業に関心をもち、一方、ソビエトが、日本の消費産業と造船にとくに関心をもっている現在、両国の貿易上の利害は、完全に一致している。
従って日ソ貿易の将来は明るいと、話していた。
top
**************************************** |