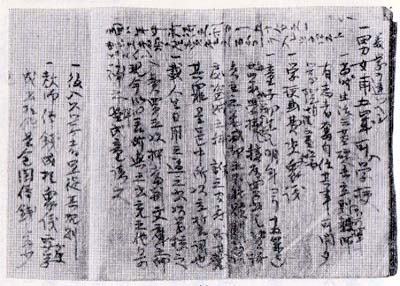|
****************************************
Index 序章 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 終章
二章 移民の共同体と土着
1 〈土着〉
いまは「開拓」という言葉は私たちには実態としてのイメージがうすれ、資源の「開発」というイメージの後景におしやられて霞んでしまっている。
土地の開拓を主に意味したこの言葉は、元々農耕文明をになう言葉だったのだ。
工業化の進展がそのイメージを後景におしやってしまったのだろう。
満蒙開拓から戦後の時期の未開地開拓あたりを最後にして、言葉の意味する実態は私たちから遠のいていった。
次に書く、移住者たちがこの土地でどんな共同体をつくり、どんなふうに土着していったかということは、その遠のいた開拓の初期の時代のことである。
しかし、日本人が北海道で何をし、何ができたかということを見直すのにはずすことのできない側面なのだと、私は思う。 |

新十津川町の獅子かぐら
|
自然の側からいえば、〈土着〉は人間とのかかわりで、自然の何かを掠奪して去ろうとする人間の移動をとどめ、土地に縛りつける関係でもある。
都市、鉱山、それに北海道の漁場(場所請負制は資本制工場に似ていて、漁民が土着できる仕組ではなかった。出稼ぎの労働力を使うことで、それは成りたったのである)などでは、人間は漂浪者であって、土着する人間ではない。
自然の側からは土着は人間を漂浪者としてではなく、土地に縛りつける関係である。
私はそういう意味での〈土着〉を考えるのだが、北海道での地縁共同体は、日本の古い共同体から孤独にぬけでたものの新開地での混住、またそういう人々が特別な集団に編成された屯田開拓、第三に古い共同体からの集団移住というかたちで、形成されていっている。
最後の例は、石狩川流域で当別と新十津川の開拓にみることができる。
当別を開拓したのは仙台支藩の封建家臣団であり、新十津川を開拓したのは奈良県十津川郷の自然災害によって移住した集団である。
2 当別移住者の「邑(むら)則」
top

伊達邦直肖像 |
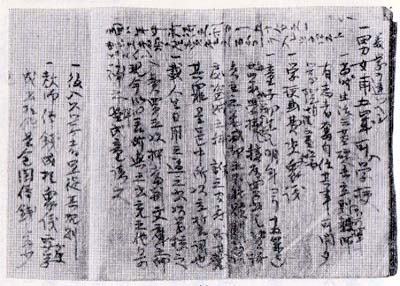
当別村邑則 |
当別を開拓したのは、東北の仙台支藩岩出山藩の家臣団で、藩主は伊達邦直、一万五〇〇〇石の藩だった。
支藩を含む仙台藩の封禄は六三力石だったが、明治維新の内戦で官軍に抵抗したため、二八万石に減封され、岩出山藩は領地が南部藩の支配下に入り、伊達邦直は六五石の扶持米をあたえられるだけの境涯におちた。
伊達邦直にそのとき、約七〇〇戸の家臣をかかえていた。
が、領地を奪われた彼は、六五石の扶持米だけを収入にする漂浪者に変ったもので、扶持米では家臣を養なうことかできなかった。
そういう条件で、彼は家臣団の北海道への移住をくわだてたのである。
東京の政府に移住を願いでたところ、空知のナエイからナイにいたる土地があたえられることになった。
しかし、ここはそれから二十年後に上川道路開削によって、ようやく開拓が可能になった石狩川中流の土地で、そのとき彼の家臣団は運輸の便がないことをまもなく知った。
伊達邦直は空知の支給地を返上して、石狩川河口への移住を交渉した。
開墾してそこで生活できるまでには、かなりの時間がかかるので、その間食いつなぐ手段を考え、開墾に取組なければならなかったからである。
河口は漁場だったので、賃稼ぎして食いつなぐ条忤かあった。
こうして、明治四年、伊達邦直は第一次の移住者五一戸一八〇名をつれて、海岸から二キロのシップに入植した。
しかし、シップが農耕の適地でないことがわかって、石狩川をさかのぼって、トウベツを探索し、開拓使庁に陳情して、翌年、そこに移動した。
この間の彼らの苦闘は、本庄陸男の「石狩川」に描かれている。
これは封建家臣団の移住で、この第一次の先発隊は、その後当別へ、二次三次の移住者を招いたが、しかし岩出山藩の家臣は全体がそっくり移住したわけではなかった。
家臣は北海道移住問題で分裂し、約六〇〇戸が岩出山に残った。
当別への移住にあたって、伊達邦直と元家老の吾妻謙は、〈第一条 邑中の事務一切衆議に決すべし〉から始まって四十九条から成る「邑則」を定めている。
衆議の方法は、五戸を単位にする〈伍〉から議長を選び、議長は全体から選んで、三分の二の多数決によってことを行う。
〈事務悉く公平に帰するを要す。必ず独断事を誤る勿れ。
自己の意見を飽迄主張し衆言を用ひざるものは不和を致すの本なり。然れども政体に昭準して採るべきものは断じて行うべきなり〉
生活の日課は、〈第十四条 毎日板木を叩いて操作の時を報ず。第一声朝六時朝起装束壮者は田畝に出て童子は学校に出づ。
第二声八時朝食を喫す。第三声十時田畝或は学校に出づ。第四声十二時午飯を喫す。第五声又其業に就く。第六声四時業を終る。
休業日之を打たず。只会議日に在りては集会の時を報ず〉とした。
教育については、五歳から学校に入れて読書習字数学を学ばせる。
〈若し期年に及んで入れざるものあらば其父母を厳譴すべし〉として、学校の日課も定めた。
さらに〈十五歳に及びて其才宇包撰み、本府大学校に入れて方今有用の学術を学ばしむべし〉とも規定した。
育児については、妊娠五ヵ月になると会議所に届ける。
〈第二十一条 育幼社を設け子生まるれば則若干余穀を与へて其撫育の資を助くるの法を立つべし〉とした。
飲食衣服、身体保護――つまり生活の仕方、農業・工業・商業の良法を見聞したら、かならず邑中にしらせる。
凶荒に備えるために穀倉を設けるなど、共同体の仕組と生活のしかたについて様々に規定し、それは邑の仲間を工匠にやとう場合の賃金、待遇までに及んでいる。
賃金は近隣諸邑の相揚で、食事はださなくてよい。酒を饗するのは二合五勺以内か、あるいは酒銭をだす。
この「邑則」は全員を平等とする観念で衆議によって共同体を維持することを根幹としながら、封建社会の共同体のもっていた相互扶助的要素もぎんみして取入られていて、廃藩置県でようやく封建体制の解体が始まったばかりの明治四、五年の状況を考えると、思想史的な意味でもユニークな共同体についてのイメージだったということができるのである。
3 「邑則」の思想 top
当別入植前にシップに入ったときの第一次移住者の五一戸には、下男、女中を含む家もあって、たとえば伊達邦直の家族は女中を一人含んでいたし、吾妻謙も下男を一人つれてきていた。
当別入植にあたっては、下男、次三男を分家させ、伊達邦直の女中もあとで養子をむかえて独立させた。移住者のなかには脱落して帰郷したものも五戸あったが、当別に移動するときはそういう分家の方法をとったので、戸数としては変らなかった。
封建家臣団であったが、旧家臣がごっそりまとまっていたわけではなくて、これは旧主の北海道移住に共鳴したグループとその家族だったのである。
伊達邦直はこの第一次の移住のさい、明治政府からの保護を全く受けず、家財、骨董を処分するなどして、移住費用をつくりだしたものだった。
この第一次移住の費用は、米価一石(一五〇キログラム)十円の当時、九一八一円になっている。
大部分は岩出山からはこぶ人員、貨物の輸送費で、米三〇〇石を買入れた二八五○円も含まれる。
第二次移住のさい、伊達邦直や吾妻謙が東京に行って陳情嘆願し、ようやく渡航に官船をあててもらうことができ、初めて官の保護を得ている。
第二次の移住者は四〇戸一六九人で、当別へはシップで挫折の一年を生活した第一次の先発組に第二次の移住者が合流して入植した。
「邑則」の思想は、維新の内戦で関西側の官軍に抵抗したため、「朝敵」とされ、仙台本藩からも犠牲を重くしょわされてから、辛酸の苦労をなめた二年あまりの歳月の間に、彼らの内部にそだっていた。
西洋の天賦人権論が日本の民主主義の起動力として働くのは、それよりあとで、これは自発した思索だった。
つまり、当別に入植したグループは、封建家臣団としての人間関係をひきずっていたが、内部に変革の契機をもつ集団だった。
「邑則」は国家として拡大されるなら、衆議で維持される「共和制」である。
4 共同体の小学教育自営 top

当別開拓絵図 |

明治39年に新築された当別庁舎 |
当別で彼らは、トウベツ川の支流パンケチベユナイ川に沿って、間口四〇間(七二メートル)奥行一〇〇間(一八〇メートル)ずつに土地を分割し、密集村落をつくった。
この区画割りは、彼らの誤算だったので、岩出山が開口二〇間の区画割りだったことから、その二倍とした。
この面積はわずか一・三三ヘクタールで、北海道では農業を維持できる条件ではなかった。
そのため、あとで彼らは農地をさらに遠くへもとめなければならないことになった。
北海道土地売貸規則および地所規則が制定され、一戸一万坪三・三三ヘクタール)を単位としたのは、彼らが入植してから半年後の明治五年九月である。
また、この年には、五月にはじめて開墾移民は、次のように米と塩噌料が三年間、給付されることになっていた。
〈十五歳以上米七合五勺、塩咐料二朱、七歳から十四歳米五合、塩膾料一分二朱、六歳以下米三合、塩咐料一分二朱〉米は一日分、塩噌料は月額である。
この集団は、前年シップの開墾に失敗して、開拓使から米一〇〇石を借りていた。
この明治五年の米と塩噌料の支給開始によって、ようやく開墾し、生きつなぐことが可能になったのだといえる。
彼らは前記の区画割りに、それぞれ堀立小屋を建てて、開墾をした。
開墾にとってもっとも困難だったのは、密林の伐木で、彼らの携行した鋸は、到底、大木を切断することのできない器具でしかなかった。
それで、鋸と斧で幹の周りを傷つけ、枯死を待つ方法をとった。
が、一年や二年で枯死しなかったので、次に根元に枯木を長時間燃やしつづけて焼きを入れてたおす方法をとった。
地中の樹根のほうは、火薬で爆破する手段もこうじてみたが成功せず、小さいものは掘りおこすことができたが、大きなものは自然腐朽を待って除かなければならなかった。
これは北海道での開墾に共通する苦労である。
彼らはこうした苦労をしながら、次のように開墾をすすめた。
明治五年三万四、六年五三・四、七年六五・四、八年七五・四、九年八三・四、十年八三・四、十一年一一八・二〇。(単位ヘクタール)
第三次移民五六戸二五〇人を旧岩出山藩家臣から招くことになったのは、明治十二年であった。
伊達邦直たちのグループがこうして当別で苦闘している一方で、明治七年、屯田兵例則が定められて、翌年、札幌近郊に屯田兵村加開村されていた。
条件のいい近郊の入植と違って、石狩川右岸の当別は札幌へは河口石狩にくだって、左岸をのぼらなければならず、右岸でポツンと原生林をひらいた孤立した辺地だった。
従って農作物を売るために、流木の障害があって舟の転覆の危険のある石狩川を、少量ずつ輸送している。
初期の作物は内国種大麦、小麦、小豆、大豆、粟、黍、燕麦、根菜類、外国種春播大麦、玉蜀黍などで、彼らはまた郷里から桃、桑、梨、桐などの苗木も移植した。
しかし、それらの苗木のなかで、梨と桑だけかようやく根づいている。
札幌周辺の屯田開拓にくらべるなら、離島のような辺地であったが、しかしこの集団は新知識の摂取になかなか熱心だった。
たとえば、「邑則」に十五歳以上の青年から選んで本府大学校におくって学術を学ばせると規定したが、それは将来そうしたいという願望をかかげだのではなく、当別に入植したとき六名の青年を西洋農法を学ばせる東京の青山官園におくり、官吏養成所として札幌に設立された資生館にも三名の青年を入学させていたのだ。
それで西洋種の大麦、玉蜀黍などの種子も、はやく入手していた。
明治八年に開拓使庁が西洋農具の実習生を募集したさいも、いちはやくこの二名をおくって、その後、再墾掣、馬具などの払い下げを受けている。
「邑則」は児童の教育を規定しているが、伊達邦直の家老のひとり鮎田如牛は、かって仙台藩校の教授でもあった。
当別の教育所は入植と同時に鮎田如牛塾として開かれた。それが明治十三年、小学校教則改正で官立当別小学校となった。
一九七二年の秋、当別をおとずれた私に人家の庭の萩の花が咲きそろっているのが、眼についた。
「ああ、仙台萩だな……」と私はおもった。
「学制百年記念」という大きなたれ幕を、町役場はかかげていた。
鮎田如牛塾が開かれた明治五年から、ちょうど百周年だったのである。

十津川郷を襲った豪雨の被害 |

新十津川開墾状況 |
5 十津川郷移住者の「移民誓約書」
top
奈良県十津川郷の災害の罹災者たちは、分村のかたちで北海道へ移住した。
明治二十二年八月十八日と十九日、台風による蒙雨が十津川渓谷の随所で山崩れを生じさせ、死者一六八名、負傷者二〇名、全壊・流失家屋四二六戸、半壊家屋一八四戸、村の水田の五〇%、畑の二〇%が埋没または崩壊して失われるという、大きな被害をもたらした。
災害後、県知事や十津川郷出身の東京在住者のあっせんで、北海道への移住が具体化して、罹災者の間から六〇〇戸二六九一人が移住保護措置の出願をした。
これは十津川郷の四分の一にあたる戸数だった。
そしてそれは分村の方針でまとまったもので、共有財産を災害前の戸主数で分割した。
その文書は冒頭で、〈今般郷人中北海道某地へ移住新村を造成するも十津川本郷と南北相応し永世其因縁を保ち由緒相続する事〉とうたっている。
政府も官費による輸送や移住後の特別な保護を認めて、移住者たちは一二梯団に編成されて、十月下旬から年末にかけて、神戸を出航した。北海道庁では彼らの入植地に石狩川中流右岸ドックを予定していて、屯田兵屋を建設中だった対岸の空知太へ輸送した。
小樽から市知来まで汽車、そこから空知太は徒歩のコースである。
空知太が滝川に改称され、屯田兵村として開村したのは翌年一月で、十津川郷移住者の先発組が着いたとき、四四〇戸建設予定の兵屋の一五〇戸が落成していた。
道庁は移住者たちをこの兵屋に、春まで収容し、対岸への入植の準備をさせることにした。
市来知で移住者たちは空知集治監の世話になった。新築の獄舎に宿泊することになって、食事も供された。
そして、囚人の列が先に立って踏みかためでくれた雪道を、空知太へ歩いた。空知太の屯田兵屋も囚人が建設したものだった。
ところでこの兵屋というのが、一七・五坪の規格のバラックで、一〇・五畳の畳の部分のほかは板間か土間なのだが、移住者たちは一軒に四家族ずつ、十五、六人から二十人の人数が収容された。
北海道の冬を兵屋の雑居生活ではじめて経験することになって、悪性の感冒がはやり、このとき十一月から翌年七月までに九名が死亡している。
最後の梯団が到着しかあとで、役員が「移民誓約書」を作成して、それに移住者の各戸主が連署した。
誓約書は七条から成って、第一条は次のようになっている。
〈吾ガ移住者ハ故郷ヲ去り遠ク絶海ニ移住セシモノナレバ将来一致団結互ニ扶持提携シ緩急相救ヒ患難相邸ミ偏ニ村ノ隆盛ヲ期シ勤王の御由緒相続ヲ計ル事〉
第二条は貸付地の五〇〇〇坪以上を開墾するまでは転業しないということで、旧郷から分割した資金などを新村の公共基金にすること、
第四条は生活の規制で、次のようになっている。
〈移住開拓創業ノ際ハ各自非常ノ節倹ヲ守ラサルベカラズ、依テ左ノ各項ヲ堅ク服膺スル事。
一、不急ノ器物ヲ購求セザル事。
二、家屋ノ構造ハ成可堅牢質素ヲ旨トシ荀クモ装飾ケ間敷事一切アルベカラズ。
三、家族の外二二人以上会席酒宴ヲ為スベカラズ。但シ開村ノ記念日大祭祝日ハ此限リニアラズ。
四、村内ニ於テ飲食店ヲ開カザル事。
五、衣服ハ成ルベク木綿ヲ用ユル事〉 |
第五条は児童教育、第六条は礼儀で、第七条は誓約違背の制裁になっている。
〈前各条ノ約ニ背クモノアルトキハ村長、五十組長又ハ村吏ニ於テ再応之レヲ訓戒シ到底改悛ノ見込ナキ者ハ、給与年間ニ在リテハ官に請フテ給与米金ノ幾部分ヲ減ズル事アルベシ。
又給与年限後ニ在リテハ村中隣保一切私交ヲ絶ツモノトス〉 |
6 旧共同体分村の想像力 top
伊達邦直たちの「邑則」にくらべてみると、共同体のイメージは抽象的なもので、具体的な部分は、第四条の生活節倹のところと、第七条だけである。
冒頭に〈勤皇由緒相続〉という言葉が出てくるのは、明治二十二年の時点としては異様だといわなければならないのだが、これは十津川郷の人が他の世界に誇る特別な心情だった。
「勤王」は十四世紀の南北朝時代、南朝の流亡者がこの地方に依拠して住民が親近したことに淵源する皇室への感情を表現する言葉だったのである。
約二十年前の当別の開拓者たちの「邑則」と、大きく違うのは、当別のグループは過去の共同体から流亡したが、十津川郷の罹災者たちばその共同体の分身としてそれを引継いでいたことである。
自然災害は物理的なもので、精神的に古い共同体を見直す契機をもたなかったことや、また明治初年代と違って明治の地方行政の仕組になじんで、どういう共同体をつくるかというようなことには自発的に想像力がはたらかなくなっていたという事情も、「邑則」と「移民誓約書」の違いの根底にあっただろう。
だが、誓約書を作成したのは役員で、移住者の内部には十津川郷・分村のイメージにだけとらえられていないものがあって、空知太で屯田兵に応募したものが九五戸でた。
移住者のほぼ六分の一の戸数である。それで、誓約書第三条の新村の公共基金にするという資金も、屯田兵応募者に分割して渡さなければならないことになった。
道庁では十津川郷からの移住者の受入地で、初めて区画制の方法をとった。
北海道の行政の仕組は、明治十五年に開拓使制から函館、札幌、根室の三県と農商務省北海道事業管理局に改編され、十九年、さらに北海道庁制に改編されるという経過をたどってきていたが、それまでの殖民事業は、おおよその面積を計算して未開地を処分して、開墾成功後に実地に面積を測定する方法であった。
区画制というのは、あらかじめ一定の規格で入植地を測定して区画割りに処分する方法で、アメリカ西部地方の開拓で行われた直角区画法を取入たものだった。
ドックでは、一戸の耕作面積を五ヘクタールとして、横一〇〇間、縦一五〇間の区画とされ、当然疎居制の村落がつくられることになった。
区画測量は移住者たちが空知太の屯旧兵屋で越冬をはじめた十一月に開始され、その後積雪のためいちじ中止して、翌年四月におわった。
さきに当別で伊達邦直たちがやはり区画割りをしたことを書いたが、それは横四○間、縦一〇〇間で、のちに農地をさらにべつな場所に広げなければならなくなっていた。
彼らは自発的に区画割をしたが、それは本州農村の密居性をなぞったイメージだった。
ドックがテストケースになった区画制について書いておくと、明治二十九年に「殖民地選定及区画施設規程」としてかためられ、この方法が北海道で一般化していった。
新十津川村が開村したのは、二十三年一月滝川村(旧名空知太)開村と同時で、屯田兵屋の移住事務所が戸長役場をも兼ねた。
地割りがすんだところから、道庁が業者に請負わせた家屋が建てられていったが、これは十二坪の堀立丸太組の小屋、しかし荒壁づくりだった。
十津川郷罹災者たちの受けた保護は、移住輸送費のほかに家屋、二年間の食料(米一日大人五合小人三合と塩咐料)、農具料、種子料、耕馬料(二戸に一頭)、道路、排水、用水、事務所、倉庫費などである。
7 混住とコミュニケーション top
この村の移民が神社をもったのは、開墾をはじめた翌年で、入植してまもなくそれをはかって、冬になって代表二名を母村に祭神の分霊受領に派遣した。
母村の郷社は玉置神社といい、翌年一月建立してあった分社にそれをむかえた。
神社とはべつに宗教とのかかわりでは、彼らは出雲大社教の信徒だった。
そして、移住者のなかにはその教派の教導職が何人もいた。 従って葬式は大社教のやりかたで行われ、教導職が執行した。
彼らの集団のなかには、災害前に小学校に就学していた児童が、三〇〇人ほどもいた。 |

新十津川神社(旧玉置神社)
|
それで、滝川屯田兵屋に越冬していた時期に、仮学校として児童をいくつかの私塾で教育していて、入植後は公立小学校二校のほかに、私設小学校も二ヵ所設けた。
私設小学校を設けたのは、区画制で散在して生活することになって、距離的に通学することが困難な地域ができたからだった。
この六〇〇戸の集団(滝川屯田兵に応募して分離した戸数は翌年十津川郷から補充された)は、教員経験者も含んでいたし、次に書く文武館で学んだものがいたので、それらが教育にたずさわったもので、内部に児童教育を行うことのできる力をもつ共同体として、移動してきていたのである。
文武館は十津川郷に幕末期につくられた私学校で、寺小屋より上級の青少年教育の場であって、生徒は選ばれ郷費で教育される方式だった。
移住者たちは、郷社玉置神社を分嗣しただけでなく、その私学校方式をも北海道の新村でこころみた。
入植五年後の明治二十七年、校舎建設をはじめて、翌年、私立新十津川文武館を道庁の許可を得て開校した。
当時の小学校制は尋常科高等科の二段階があって、文武館はいまの新制中学から高校にわたる教育の場になって、北海道の農村では当時それは異例のこころみだった。
新十津川文武館は、「日本外史」、「日本政記」、「国史略」、「小学」、「四書五経」などを、教科書にした。
しかし、明治二十年代後半の時点としては、これは旧慣習に執着するのにとどまっている感じである。
この私学校は、明治三十五年にこの村に高等小学校が設置されることになったとき、財政的に維持するのが困難になった事情もあって、廃止され消滅した。
この村が十津川郷移住者によってだけ形成され(トックに先住民の社会があったが、それについては後章で言う)たのは明治二十年代のうちで、三十年代になると一般混住移民が村に入ってきた。
その後、十津川の古い共同体をひきついだ生活慣習も、異なる風土の条件、また一般混住者との接触をつうじて、変っていった。
この集団は、生活慣習の一部の盆踊りなども、伊勢音頭、餅つき音頭など二十種ぐらいの踊りを新村にもらこんだのだが、大体、昭和期までに廃れ、画一的な「よされ節」の踊りに変ってしまったらしい。
「よされ節」は私も、流域の村で少年時代をすごしたので
「姉と妹に友禅(ゆうぜん)着せて、どれが姉やら妹やら……ヨサレ、ソーラヨイヤナ」
という歌詞の一節を覚えているが、画一化がどんなふうに進行したのかはわからない。
それはおそらく、一般混住移民の村の小学枚教育て、各地の方言、訛りがあまりにひどく違っていて、コミュニケーションが成りたたないような状況を、標準語をしつこくたたきこむことによって変えていったという、歴史の中のいとなみに関係かあるだろう。
コミュニケーションの広場を、十津川衆のような強固な共同体ももとめたもので、「よされ節」への調和がつくりだされたようだ。
この村には、いま、郷土芸能として、「獅子かぐら」が近隣に知られているけれども、これは明治三十年代に入植した富山県出身者が持込んだ芸能である。
そして、これは玉置神社の祭典に奉納されるのだが、玉置神社は十津川衆が郷土から移した産土神である。
が、産土神の由緒を問わず、コミュニケーションの広場がつくりだされ、移住者の社会が新しい共同体として一体化していったことを、それは物語っている。
しかし、十津川郷罹災者だけで村落がいとなまれた時期について、古い共同体のイメージを超えるひとつの努力として、私は信用組合のことをあげたい。
移住民のひとりで、村の郵便局長をやることになった池本楳吉は、明治二十八年、有志を糾合して信用組合をつくった。
それは、移民の金銭貸借の公的な場がなく、私的に高利の貸借が行われている状態を変えようとする、ひとつの試みだった。
池本楳吉が有志を募って、新十津川信用組合を組織したのは、明治二十八年である。
この時期、農民がやむを得ない事情から個人金融のルートで章足借りる場合、利子が月二分五厘ないし三分五厘の高利だった。 |

新十津川信用組合の建物、
現在は開拓記念館になっている
|
池本楳吉は村落共同体の内部で、貯蓄と金融の自立的な回路を成立させることを考えて、それを組織した。
その後、明治三十三年になって産業総合法が制定された。
池本の信用組合はその後、同法による組合に改組したが、新十津川村に生じていたそれは、官の奨励による産業組合運動にさきがけで始まった、
下からの自発的な努力だったのである。
この組合の明治四十年建築の石づくりの事務所が、現在も残っていて開拓記念館になっている。
8 屯田兵村 top
屯田兵村の場合は各地からの応募者で混成されたのだが、軍隊の一単位としての特異な共同体だった。
常備兵力の代用として、初期は要地防備が目的になって、屯田兵がまず札幌近傍の琴似、山鼻に配置された。
やがて、明治二十年代になって、上川道路が開鑿されて石狩川中流上流地帯の開拓が可能になった時点で、それまで士族から応募した方式から平民屯田への変更か行われた。
次に私の追尋してみる上流東旭川の兵村は、その平民屯田の村である。
ここに四〇〇戸の黽田兵とその家族が入植したのは明治二十五年で、彼らは屯田兵第三大隊の第三中隊と第四中隊であった。 |

屯田兵の描いた東旭川屯田開拓絵図
|
募集におうして合格した彼らは、指定された輸送船の寄港地に集結して、拾い集められるように乗船、小樽に上陸し、その年滝川まで鉄道が延長されていたので、小樽・滝川間は汽車輸送され、滝川から上流へ歩いた。
兵村にはすでに区画割りが行われ、兵屋が建っていて、彼らの入る地番はすでに抽籤で決まっていた。
この時の屯田兵の条件は、年齢が満十七螽から二十五歳までで、志願者のほかに農業に従事できる家族が二人以上いなければならなかったから、壮健な両親がいるか、また妻帯者の場合でも少なくとも労働できる片親がいなければならなかった。
東旭川に入ったこの集団は、輸送船のなかで子供が二人出生していた。
が、出産したのは二人とも屯田兵の妻ではなく、母親のほうだった。
屯田兵には一万五〇〇〇坪(五ヘクタール)の土地が支給されることになっていたが、兵屋の建っている区画は四五〇〇坪で、軍隊の一単位として密居制をとらなければならない事情からそうなったもので、このことはやがて開墾がすすむにつれて、とびはなれた土地の耕作にいかなければならない不便な条件に変った。
屯田兵の現役の期間は三ヶ年でその間、午前八時から午後四時までが軍務の時間で彼らは軍隊として集まって行動し、教育を受けた。
開墾の仕事は、農業に従事できるもの二名以上という応募条件の家族が、もっぱらすることになった。
彼らは五年間、扶助米と塩噌料を支給されたので、それは自費の一般移住者と全くちがった待遇であって、特別身分の移民だったといっていい。
しかし、北海道の開墾の最大の困難が、巨大な樹木のそびえる原生林の伐木と樹根の堀リおこしだったことを考えると、それがもっぱら家族労働にまかされたということは、大きな〈負〉の条件だったということができる。
東旭川で彼らが形成した共同体は、下士、一般兵の軍隊組織と、その家族で合成された社会で、干渉と統制は当然に共同体の生活全体におよんだ。
上からの巡察がしょっちゅう行われて、ときになにか感情の荒れている巡察者は、兵屋に踏みこんで鍋のフタまではぐって家族の食事をしらべたりした。
日常生活も開墾作業も屯田兵軍隊組織の統制下におかれていた。
この屯田兵制は、明治二十八年、現役期間が七年間に延長され、三十二年募集を中止し、三十六年兵制が廃止された。
その間に第七師団が設置され、屯田兵はその基幹兵力になったが、やがて駐屯地の軍隊以外のあいまいな農兵制が廃止されることになったのである。
屯田兵村の共同体は、従ってその後解体した。
この特異な兵制について付記しておくと、廃止時、次のような大隊編成になっている。
第一大隊本部・札幌(札幌、室蘭近郊の兵村)
第二大隊本部・滝川(石狩川中流の兵村)
第三大隊本部・永山(石狩川上流以北の兵村)
第四大隊本部・根室(道東地方の兵村)
9 流亡した屯田兵の一家 top
一九七二年の秋、私はかっての東旭川兵村の中央広場だった神社境内にある、開拓時の生活用具、書類などを保存した記念館で、一通の屯田兵子弟の書いた手紙に見入った。それはこう書いている。
〈チョーツトオタノミモーシマス 二十七日カラオカ(母)サンガネテをリマス
子供モ三人ネテオリマス オカサハセキガデテイキマセン 目ガモーテイキマセン
セキスルクピ左ノヂチノ下ノホネのナカイトウテオキラレマセン
ソレカラオイシヤサンニミテモライタイケンドゼニガノーテミテモライマセン
ドーシタラヨーゴザイマショウカ ドウゾコノコトヲテガミにカイテオトッサンノトコヘダシトイテクレルコトハデキマセンデスカ
オトサンガウカラ (家からの脱字だろう)
コズカイヲ一モンモモツテイキマセンカラ スコシをクテクダサイ
子供ハミチ四郎卜常吉上二人ネテオリマス ソノ子供ノナクノニコマツテオリマス
ヨンベカラオカサンハ左ノチチガハレテタイヘンウズキマス〉 |
これは明治三十七年九月、目露戦争に応召した屯田兵坪野源蔵の子供が、病気で寝こんだ一家の窮状を戸長にうったえた手紙である。
応召した坪野源蔵が家から金を一銭ももっていかなかったこと、そもそも一銭もない状態で応召したことを、手紙は語っている。 私はこの哀切な手紙に心を打たれ、この一家がどうなったか調べてみようとした。
坪野源蔵は富山県の出身で、明治二十五年八月、この兵村の地番三十一号に入植していた。
彼の現役期間は二十八年に終ることになっていたのだが、その年現役を七年とする条例改正があって、三十二年までそれは延長された。
その改正は日清戦争の影響だった。
七年間、開墾の仕事が家族まかせになっていたこと、現役延長にもかかわらず扶助米などの保護がうちきられた経過などを考えると、かろうじて自家でつくる作物で食いつないではいたが、それは崩壊の淵であやうい綱渡りをしていたような生活だったといえる。 |

日露戦争に召集された元屯田兵の子供の手紙
|
そこへ日露戦争が勃発し、坪野源蔵は一銭の蓄えもない状態で応召しなければならなかった。
東旭川の兵村四〇〇戸から、日露戦争に応召したのは三三三名だった。
その名簿を調べると、坪野源蔵は上等兵である。
そして、彼は戦死せずに帰還している。
だが、営農の中心の働き手を奪った戦争に、屯田兵土地給与規則などの廃止がかさなり、兵村は解体していった。
坪野源蔵の一家もこの土地から姿を消してしまったのである。
私は屯田兵の定着率が全体として二〇%ぐらいでしがないことを知らなければならなかった。
10 漂浪する移民 top
有島武郎の『カインの末裔』が描いているのは、農場制小作の世界である。
主人公仁右衛門はさきにこの農場へ小作にはいっている川森の縁者としてやってくるが、仁右衛門夫婦のもつ財産らしいものは、一頭の馬と馬に耿載できる荷物しかない。
いわゆる開墾小作ではなく、この農場は既耕地で、小作の一戸がたちのいたあとの耕地の小屋に入る。
畑のいちぶに秋蒔きの小麦を撒いたあと、まもなく冬がくる。
冬を食いつなぐ食糧のない彼は、馬を売りとばしてそれを買い、木樵をやったり錬場に出稼ぎしたりして金をつくり、翌年の春には馬やプラオ、バーロー、種子などを整える。
精悍な彼はそんなふうに生活の打開にがむしゃらに行動し、農場の規則など無視して、五分の一の面積に制限されている亜麻を畑の半分に作付したりする。
作者が〈ー人の自然から今掘り出されたばかりのような男〉と性格づけしているこの主人公は、農場の人々と調和できず、隣家の女房と密通し、また暴力で仲間をおびやかすなどして、無法者として、共同体から孤立する。
そして、冬がきて、小作料を納めない仁右衛門は、結局この農場から立ち去ることになる。
この農場にきたとき、彼は馬をもっていたのだが、出稼ぎの金で春にもとめなおした馬を事故で失い、一年の間に赤ん坊ち赤痢で死亡してしまっている。
農場に現れたときよりもっと惨めな漂浪者になって、夫婦は吹雪のなかにのみこまれて立ち去って、小説の世界は閉じられる。
私は北海道での土着と漂浪の問題を考える手がかりを『カインの末裔』から引出すことができると思うが、仁右衛門ほど鮮やかな漂浪者の貌をもたないけれども、この農場の人々もまた漂浪者の集団だったといえるだろう。
なぜなら小作農だったからで、それは根底のところで〈土着〉から疎外された存在だったのである。
北海道では未開地開墾に入植した自作農の場合でも、そのままそこに土着できずに、移動している人が多い。
たとえば、さきに書いた新十津川村の場合でも、割りあてられた土地に泥炭湿地があったりして条件が悪かったことから、数年後に、五〇戸ほどが村外に移住している。
屯田兵村が解体したのは明治三十年代未だが、定着率か約二〇%と推定されていることも、北海道で土着ということがなかなか困難だったことを証す材料であるだろう。
私は少年のころ、石狩川中流の村で生活したのだが、そこへ移住したのは大正十一年で、私の父はその十七年前に北海道へ移住していて、それまでに最初の入植地から三度土地を変っている。
私の父は『カインの未裔』の主人公と違って、おとなしい気性の勤勉な男だったのだが、入植した土地の条件が悪かったり、ひんぱんに冷害にみまわれて営農に失敗したりして、そんなふうな漂浪しなければならなかったものである。
十津川郷罹災民また屯田兵は入植地に家屋が建てられていて、扶助米などが支給されたが、それは特別に保護された集団だったのであって、一般的な移民はそうした保護を受けず、漂浪者として小屋掛けし、開墾に取組み、食いつないで、あるいはそこにおちつき、あるいは移動し漂浪した。
11 深層での〈内地〉 top
そういう一般混住む民の形成した開拓地の村落共同体は、どういうものだったろうか。
『カインの末裔』の主人公には、自然の野生児という作者のイメージが託されて、妻子と馬一頭をつれて登場するのだが、農場にあらわれるまでの過去は描かれていない。
しかし、移民はだれも〈内地〉の古い共同体からどういうかたちでか流離した過去を背負っていた。
当別とか新十津川の集団を別にして、一般移民は孤立して〈内地〉から流離し、漂浪者として開拓地に入ったのだった。
そういう孤立した一般移民の混住によって形成された共同体は、それぞれ生活の表層のところで新しい調和を見出したようである。
新十津川の罹災者集団のもつ盆踊り・伊勢音頭がよされ節に変るような(戦後になると「北海盆歌」に整合されるような)調整を、北海道の村落はそれぞれ見出していったとみていいだろう。
しかし、〈内地〉の伝統的共同体から持込んだものが、移民社会の形成する文明史の深層でどう働いたのかということを、あとであらためで追ってみたい。
top
****************************************
|