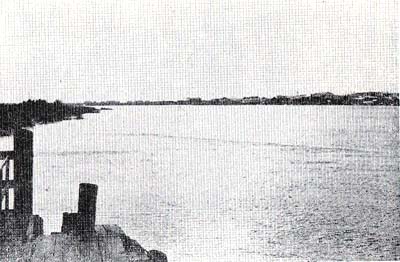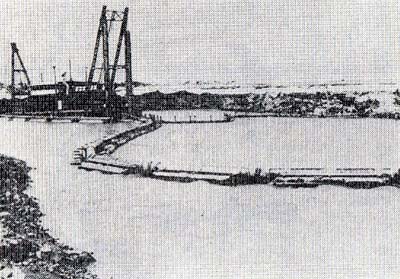|
****************************************
Index 序章 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 終章
終章 河口で
1 河口の街 top

石狩川河口 |
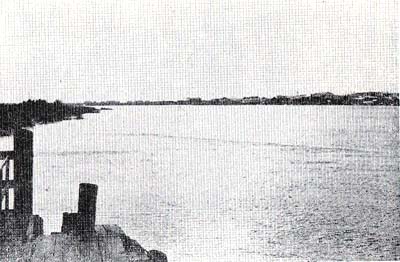
河口にちかい石狩川と石狩町 |
河口の街は今はひどくさびれていて、河岸の漁業関係の倉庫が廃屋になっているのが、眼につく。
灯台や町役場のある左岸でみつけた、一軒しか残っていないといわれる旅館に私は泊ることになったが、隣りに古びた大きな木造の倉庫風の建物があって、それはいぜん魚市場だったのだが、今は出入口を封鎖した廃屋に変っていた。
宿帳をみると、この旅館も副業としてかろうじて維持されている状態であることがわかった。
宿泊客は年間わずかに百数十人でしかなかった。
街の家並のとぎれたところから、砂浜が一キロほど二角州状に広がっていて、石狩川はたっぷりした川幅で流れて、海に注いでいる。
砂浜を河口まで歩いてみると、途中に灯台が一基建っているだけで、人気がなく、荒涼とした風景が広がるだけであって、私をとらえたのは、さいはての地にきたという感じだった。
このさいはての地の感じには、廃屋のめだつ、さびれた街の印象もはたらいていた。
この河口の街の漁業の歴史を閉じさせたのは、石狩湾新港を国が第三期北海道総合開発壮画の事業として、着手したためだった。
この計画は、太平洋側の苫小牧工業基地と一対の日本海側基地としてこの町を選んだもので、札幌、小樽に近いここは、加工工業と流通のセンターとされ、河口の五キロ西方から小樽市との境にいたる地域が新港地区に選定されていた。
つまりこの町は石狩湾新港の産業都市に生まれかねろうとしているのであって、一世紀以上も前、石狩場所の漁場の中心だった河口の街も、実は変身する昆虫のように今は蛹(さなぎ)に化している状態なのだといっていい。
この町の観光臨会示十年ほど前にだしたパンフレットをみると、十八世紀末の寛政年間、蝦夷地全体の鮭の漁獲高が三万六〇〇〇石で、石狩場所が一万二〇〇石、浜益、厚田、シコツを合わせると全体の半ばを占めたということや、明治十年代に鮭漁の時季になると札幌、小樽から娼妓が移動してきて三〇〇人にもなったことが、書いてある。
しかし、河口での漁獲は流域の内陸部の開拓か進むにつれて減少して、大正末期になると、明治十年代の三%ぐらいしか獲れなくなっている。
2 鮭の〈母なる川〉 top

千歳孵化場 |

石狩湾内の鮭漁網おこし(明治末期) |
十八世紀に蝦夷地の鮭の半ばが獲れたように、石狩川は昔から鮭の好んだ〈種川〉だったのであって、近代になって卵を孵化して稚魚を放流する方法も、まずこの川で行われた。
これは鮭鱒類が陸地の川で育って海にでて、やがて産卵に〈種川〉に回帰する習性を利用した、自然の資源をただ掠奪するだけでなく、資源を養殖しようとする、自然との一つのかかわり方だった。明治二十一年、千歳孵化場を開設して、石狩川をさかのぼる鮭鱒から採卵し、稚魚に育てて放流する仕事が始まった。
一九七二年の秋、実は、私は河口にくだるまでに、中流で廃止になった一つの孵化場をみていた。
それは私の田舎にあった、水産試験所千歳支場音江事業場で、静かな林の中にあるその小さな建物をたずねてみると、門札がかかっているが、窓に板が打ちつけられ、干あがった池には雑草が生えていた。
ここでの捕獲数は上流に産卵にさかのぼる数の目安になるのだが、すでに閉鎖されていたのだ。
私は中、上流での唯一の孵化場だったこの事業場の歴史を追跡したくなって、あとで札幌の中の島孵化揚でその記録を知った。
音江孵化場が開設されたのは昭和十九年で、その年の五二九八尾(雌雄合計)から始まって、二〇〇〇尾以上捕獲した年をあげると、次のようになる。
二十年八三一五、二十三年一二八八、二十四年二一四三、二十五年九九三〇、二十六年九〇一二、二十七年三〇一四、三十七年三〇二五、三十八年三一七七。
そして昭和四十年代になると、ひどく減っていっている。
この採卵孵化方式での石狩川本流支流の捕獲数の全体をみると、昭和二十年代前半までは、昭和九年の六万尾、十年三万尾台、十三年五万尾ちかく、十八年四万尾、二十年、二十五年の三万尾台と多い年もあるが、少ない年でも二万尾前後の状態が続いている。
昭和二十年代後半になると、二十九年の五万尾を例外にして、六〇〇〇尾から一万五〇〇〇尾前後になって、三十年代には一万尾以下に減少している。
三十年代で一万尾を超える捕獲をしたのは、三十三年、三十七年、三十八年の万年しかない。
四十年代は四十一年、四十六年の八〇〇〇尾のほか、五〇〇〇尾以下に減少する。
河口の街の鮭漁は湾内の定置網による魚獲だったが、採卵孵化方式の捕獲数の推移は、石狩川に回帰する鮭かどんなに少なくなったかということを語っているだろう。
次に書くのは新聞で読んだ知識でしかないのだが、アメリカのウィスコンシン大学のハスター教授の説では、鮭鱒類が自分の育った〈種川〉に産卵に帰ってくるのは、稚魚のさい育った川の独特な成分の香りを記憶していることにもとづく習性だという。
ハスター教授は鮭の鼻にセンをして河口で放す実験をかさねたのだが、鼻にセンをしないのは自分の育った支流の川に上ったが、センをされたのはその母なる川を感知できず、たださまようばかりだったそうだ。
前章で私は、パルプ廃液が川魚を異様な体臭に変えてしまったことを書いたが、調べてみると、その臭気はクラフト紙製造工程で出る有機硫黄の匂いなのである。
河川汚濁を測定する基準の一つに、BOD(生物化学的酸素要求量)がある。
しかし、ハスター教授の説のとおりだとすると、鮭鱒類が独特に感覚できる匂いの問題は現代科学が測定できる水質基準などとは異なる、自然の生態の霊妙な働きなのであって、そしてそういう意味で石狩川は全く変質してしまっているのだといっていい。
清流の孵化場で育った鮭鱒類は、石狩川の河口にはいっでも、母なる川をもとめえず、たださまようばかりなのかもしれない。
しかし、さまよいながらも産卵して生を終るために回帰したのだから、必死に清流を探し、やがて支流に入るだろうが、本流では鮭の母なる川はもう喪われてしまったのだといえる。
3 治水と洪水 top
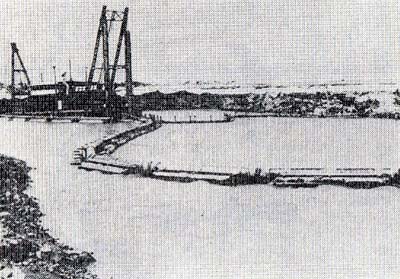
昭和十年頃の治水工事 |

昭和七年、深川市で水害に見舞われた筆者の郷家 |
石狩川の河流の長さは、国土地理院の測定でかっては三六五キロとされていたのだが、彎曲部の河道を直線状に切換える整形外科手術のような改造が行われて、現在では二六一・九キロに変っている。
これは約七十年間にわたって進められた改造で、最初の第一期工事は一九一〇年(明治四十三)に始まった。
一八九九年、政府が全国的な規模で河川治水に取組むことになって、石狩川治水事務所かその年発足して、調査研究と準備段階を経て、第一期工事の着工となったもので、河口近くの下流で大きく回流している河道の改造と、河口から対雁間の堤防築堤、旭川、深川、滝川の市街堤防築堤が、この第一期工事の規模だった。
これは二十三年後の昭和八年に完成。下流の彎曲部がこの工事で新水路に変った。
支流の江別川、千歳川、夕張川の治水工事も、この間に大正九年から着工、第二期工事は昭和九年から対雁、滝川間の本流と幌内川、美唄川で進められた。
第三期工事は月形から川にいたる低水路工事として、昭和十六年に計画されたが、これはほとんど実施されなかった。
戦後、この治水事業は北海道総合開発計画の中に引継がれて、二十八年から石狩川改修全体計画の事業として行われたのが第一段階、治山治水緊急措置法による昭和三十五年開始の治水事業十ヵ年計画の工事が第二段階となる。
捷水路工事といわれる、中流での河道改造のほとんどは戦後になって行われたもので、それは昭和四十四年に一段落している。
捷水路工事は河流を総計一〇三・一キロ縮めた整形手術だった。
洪水については、樺戸集治監が出現して中流の開拓が始まった頃からようやく記録が始まるのだが、その月形では明治期に二十四年、三十一年、三十七年、四十二年、大きな水害に見舞われている。三十一年のは市街地の大半が一週間、水につかり、三十七年のは農作物の収獲皆無の打撃をうけたという水害である。
沿岸はしばしば洪水に見舞われているか、広範囲に及んで被害甚大だった水害は、この明治三十一年、大正十一年、昭和七年、三十六年にあって、昭和七年は浸水九〇〇〇戸、五〇〇ヵ所の橋流失、三十六年は死者一一名、浸水二万三二八七戸である。
洪水は昭和三十七年にもあった。それから十三年後のことしの夏、大きな洪水に見舞われることになったが、そのことはあとで書く。
戦後の総合開発計画は洪水調節を一つの目的にする多目的ダム建設も含んでいて、石狩川水系では幾春別川に桂沢ダム、空知川に金山ダムが治水の一環としてつくられていたのだが、昭和三十六年、三十七年と続いた洪水は、治水計画の本支流の高水流量を再検討させることになった。
私が裏大雪の源流でみてきた大雪ダムは、そのうえで豊平川の豊平峡ダム、恵庭の漁川ダムとともに、あらたな洪水コントロール装置として計画された多目的ダムである。
多目的ダムは発電も行うが、北海道の水力発電は石狩川水系が五〇%を占め、火力発電所も大部分が中流河岸に集中している。
4 〈開発〉のもう一つの貌 top
全道の水田の八〇%を流域にもち、水力火力を合わせて電力の七〇%の発電量を水系で行うこの川は、北海道の産業経済の原動力として働いてきたし、北海道ではもっとも開発された河川だということができるだろう。
火力発電所が中流の河岸に集中したのは、原動機、蒸気タービンが大量の冷却用水を必要とすることと、近くに炭鉱地帯をもっという条件のためである。
戦後、電力事業再編成が行われた時、北海道電力の発電力は三一万キロワットだったそうだが、現在の河岸の江別新火力発電所の出力が三七万五〇〇〇キロワットで、それは終戦後の全道発電力をうわまわる能力である。
だが、開発がもう一つの貌をもつことを、私は前章で書いた。
鉱工業の排気廃液による環境破壊が問題になって、国が河川の汚濁防止を初めて法で規制しようとした一九五八年後、汚濁のすすんでいる水域からA、B、Cのランクに分けて、水質基準をさだめることになった時、Aの四二水域の一つが石狩川上流だった。
北海道の産業経済の原動力として働いた石狩川のもう一つの貌は、自然の生態系としての河川を改造され、下水道の役割を担わされた汚濁した川なのである。
5 台風十五号と高寒地造林法 top
石狩川の水源について、和人の探検者が現在の旭岳を石狩岳と誤認して、原住民社会に伝承される水源と和人の探検とがすれ違った二重の歴史があったことを、「水源行」で書いた。
そのことは実は、私にとっては、流域を歩きながら北海道の文明史を見直す思索の根のところに宿っていたのだといっていい。
自然の生態系についても、私は大雪山地で文明の側の次のような経験を知った。
その経験は、一九五四年に台風十五号か大雪山地を襲って原生林に大きな被害を生じたことから始まる。
大体、台風がこの日本列島の北の島にくるころ衰えている場合が多いのだが、その年九月二十六日北進してきた台風十五号は、風速が衰えず、函館で連絡船洞爺丸を転覆させて、一四〇〇余人を海に沈め、北海道を通過して宗谷海峡にぬけた。
この台風は北海道の屋根といわれる中央山脈を襲った時、風速三〇メートルないし三五メートルだったといわれ、大雪山地の原生林で多くの樹木を打ち倒した。
林業の歴史を通じてかって例のない大被害であることが、その後の調査で明らかになって、風倒木は材量二二二二万立方メートルとされた。
大雪山地の被害は全道被害数量の約五〇%にあたった。
私が車で入ることができた裏大雪の林道は、その後、風倒木を処理して造林するために開かれたもので、営林署、つまり近代の林業技術はそれまでこの原始の樹海に踏込もうとしていなかったのである。
風倒木の処理も、ここで日本の林業技術は機械化を大規模に試みることになったが、風倒木を処理したあとで林業技術が経験しなければならなかったのは人工造林だった。
日本の造林技術はその時、亜寒帯でのこうした高地の造林をした経験をもっていなかったので、初めてそれに取組むことになった。
農林省林業試験揚と大雪営林署の技術者たちが、研究と実験に取組んだ。
ここは気象の条件がきびしく、苗木を移植しても、霜害と凍害を免れる期間は、一年を通じて七月中旬から八月末までの四、五〇日にしか、わずかにない高寒地だった。
もちろん、ここで生きられる樹種は限られている。
裏大雪での天然の樹木の分布をみると、針葉樹のトドマツの上限が標高一三〇〇メートル、エゾマツが一二〇〇メートルから一四〇〇メートル、アカエゾマツが一四〇〇メートルから一五〇〇メートルである。
これは垂直分布で、アカエゾマツがグイマツの圈に接触するが、植生可能の針葉樹はそれが限度で、グイマツは植生不可能である。
広葉樹はダケカンバだけが、一四〇〇メートルから一五〇〇メートルにかけて分布するが、これも人工植生は不可能だった。
広葉樹のウダイカンバ、シラカンバ、ケヤマハンノキ、ドロノキなどの上限は、九〇〇メートルだった。
技術者たちは、標高九〇〇メートル以下の山地から、まず造林を計画した。
トドマツ、エゾマツ、アカエゾマツという、木材資源の中心樹種の造林が、まずはかられた。
だが、そもそも大雪山地では苗木を育てることができないので、苗園は気象条件の違う土地におかなければならなかった。
しかし、そこから大雪山に移植しても苗木は生命力を維持できないので、環境のちかい土地でしばらく自然条件に近接して生きなければならない。
それで、苗木はそうした段階を経て、霜害を免れえる一年の間のわずかな期間に移植された。
林業技術者たちは、実験と研究を数年かさねて、植生の保護手段を含めて、それを高寒地造林法と名づけた。
6 人工造林の考え方 top
台風十五号から一〇年後の昭和三十八年、大雪営林署のだしたパンフレット「高寒地造林法」は、「森林の位立て法について」という項目で、次のように書いている。
〈現在成林としている本道のトドマツ、エゾマツの天然林はどのようにしてできあがったかをみてみよう。
すでに知られている通り、ここで問題にする高寒地造林の対象地域に成林するこれらの天然林は、亜寒帯性針葉樹林で、トドマツ、エゾマツ、ダケカンバ、それに若干のナナカマドを構成要素としている。
しかしこの森林は最初からこれらの樹種によって優先されたものではなく、第一次の遷移過程では裸地から始まって、陽性の広葉樹の侵入(場合によってはエゾマツ、アカエゾマツの同時侵入)があり、いま我々が目的とする針葉樹類はやや遅れて侵入を始める。
従って先に侵入した陽性広葉樹により、林床は一時的に優生群落を形成する。
同時あるいはあとから侵入した針葉樹類は、この広葉樹類によって凍害霜害などの被害から保護され、かつこれら先駆広葉樹はその形態上から植生期問といえどもかなりの陽光を透過し、林床の針葉樹にとっては光合成上、それほど大きな支障もなく成長を続けることができる。
このようにして成育した針葉樹類は、先駆広葉樹の枯損によりやがて優性群落を作り、気候的極盛相群落へ発展していき、現在みられるような天然林ができあがる。
さらにまた、伐採、風倒などにより、このような極盛相群落が破壊されるとすれば(例十五号台風)、植生の連続は一次遷移の系列のある時点まで一時的に退行し、そこを起点にして二次遷移の発達が行われるが、現在高寒地において実行している造林行為も、この破壊後におこる二次遷移を人工的に進行させていることになる。
この二次遷移は出発の時点が一次遷移のある点に重なり、それ以後の発達過程は一次遷移と同じ経過をたどるものと考える。
そこで人工により森林を成立させる場合、特に気象その他の環境条件が悪い場合にはさらに一層、我々は伐採などによる植生の退行の時点を正しく把握し、それから自然状態で起るであろう二次遷移の過程を認識し、高寒地における人工林の造成を決定しなければならないのである。
このような亜寒帯性針葉樹林の発達の過程を考え、振返ってこれらの地域の人工造林地の多くの失敗例を反省するとき、凍害あるいは霜害を起し易い気象条件をもつこれらの地域では気象条件の温和な低海抜地の造林地にくらべ、かなり違った造林の方法がとられなければならない。
その一つの方法として前項では裸地造林をする場合の樹種配置計画を述べたのであるが、それにしても裸地の場合はほとんどの地域で相当の凍霜害を覚悟しなければならない。
そこでこのような環境下でもっとも安全確実の森林仕立て法として、凍霜害に強い陽性の先駆広葉樹の導入、あるいは林床の灌木類の積極的な利用を考えなければならない。
先駆広葉樹の導入は人工的な植栽、あるいは天然性のこれらの樹種の撫育により、とにかく林地へ被蔭を作り、その保護下に成林を期するのである。
林地に被覆物の存在するときは、その被蔭下に生ずる植物は凍害また特に霜害をほとんど完全に防ぐことができることは、以前から知られたとおりである。
高寒地造林では特に平坦地またはそれに近い地形では、まずシラカンバ、ウダイカンパ、ダケカンバ、オオバヤナギ、ドロノキ、ケヤマハンノキなどの導入をはかり、活着後三、四年後に針葉樹の植栽を行ない、一時的には針広混交林とし、やがて広葉樹を伐採し、次に針葉樹の伐採へと進んでいくことが望ましい。
しかし、前にも述べた通り、大部分の広葉樹の植栽限界は九〇〇メートル以下であるので、それ以上の高度では先駆としてダケカンバを採用することになるが、その導入は目下のところ人工植栽がきわめて困難であるので、主として天然性を期待するが、その方法は全刈かき起し、また可能の地域で特にササ型植生型のところは火入地拵による方法が得策と考えられる〉 |
7 自然の生態系のきびしさ top
これは初めて経験することになった亜寒帯での高寒地造林について、林業試験場の科学者たちとの集団研究にもとづく基本の考え方だった。
台風十五号による風害の跡地造林の試みは、昭和三十一年頃から始まって、このパンフレットをだす時点までには、風倒木処理の一方でかなりの面積に造林が試みられていた。
樹種としてはトドマツがもっとも多く、面積として一五万ヘクタールで、それは面積のほぼ半ばにあだった。
凍霜害は標高、地形によって、はなはだしい違いがあって、たとえばユニイシカリ沢の一つの斜面(傾斜度一八度、昭和三十三年造林試験)でも、河岸のちかくは凍霜害が五○%、河岸部から峰ちかい斜面でそれがなく、峰付近は九〇%の被害となり、ほとんど全滅している。
苗園と造林地の標高がちがい、造林地の気象条件がそれぞれ違うことから、裏大雪の人工造林は科学技術として多様な実験研究が続けられた。
実験に取組んでから十年後の一九六六年、大雪営林所は報告書「高寒地造林の進め方」で、次のような問題をあげなければならなかった。
〈低海抜造林の場合であると少々の実行上の問題(例えば苗木と苗畑との環境差等)があっても、良い環境条件に助けられて成育を行い得る状態にあるが、高寒地造林ではそれが難かしく、環境間の差がそのまま直接的あるいは間接的に苗木の生活様式に現れ、外観的、形態的に奇形成長を現出することもある。
このような奇形成長などといったことは、従来の造林では考えていなかった現象であり、その困難性については(略)
当営林署が新設されて以来、高寒地造林の難かしさとその環境の差を如何に克服するかが強くさけばれ、種々の手法を試みながら現在に至ったのである〉
造林には皆伐、漸伐、択伐の方式があって、皆伐は一定面積の樹木をすべて伐採して全面的に新しい森林を作り出す方式で、台風十五号の風害は大雪山地でそうした皆伐対象地を多く作り出していた。
北海道でも造林はほとんど皆伐方式で行われていたもので、高寒地造林法もそうした経験のうえでの発想だった。
だが、昭和四十年代に入って、大雪営林署は皆伐方式の人工造林をやめて、漸伐、択伐によって天然更新を保護する方法に転換したのである。
漸伐は年代的に段階のある二段林を古いほうから伐って、成長旺盛な森林とする方式、択伐はぬき伐りして森林を保護する方式で、それは自然の生態系というものがどんなにきびしい条件をもつかということを、高寒地造林の経験を通じて再認識したうえでの転換だった。
一応根づいたのに奇形成長をしめしたという事実は、第二の自然の生態系を作り出そうとした皆伐方式の人工造林技術の敗退を意味していた。
8 文明と自然の見直し top

1975年の月形町を襲った水害、月形大橋がみえる |

収穫期のタマネギの畑も水没した |
一九七五年八月下旬、石狩川は昭和三十七年から十三年ぶりに大きな水害をもたらし、さらに九月上旬の洪水がそれに続いた。
八月下旬の水害は、台風六号による流域一帯の豪雨の増水が、月形、江別などで本流の堤防を決壊させ、下流で札幌市内をながれる支流の伏籠川、創成川、茨戸川をおしかえして氾濫させた。
札幌北部の低地帯の新興住宅地は、それらの支流の氾濫で水びたしになった。
堤防の決壊した月形では、町の中心地である市街地に濁流が広がり、住民が高台に避難した。
九月上旬の水害も、台風による集中豪雨の被害で、上川、空知地方の支流が氾濫した。
この支流の氾濫も、たとえば新十津川町のワッカエンベツ川の場合は、流木で道営住宅三棟を全壊させるほどのものだった。
ニュースによると、八月水害の被害家屋は約一万四〇〇〇戸、田畑冠水一万六〇〇〇ヘクタール、九月水害の被害家屋は約三〇〇〇戸である。
ニュースは、また次のような問題を大きく浮び上らせた。
一つは泥炭地盤の堤防沈下の問題で、決壊箇所の月形町大曲右岸堤は一・六メートル、美唄達布堤は二・一メートル、それぞれ十年間に自然沈下していたのだった。
築堤時の堤防は今より高かったわけで、こうした自然沈下がなければ、今度の氾濫も防ぐことができたのである。
こうした自然沈下を防ぐ工法として、サンドパイル法という、砂の柱を打ちこみ、地中の水分を急速に地上に吸いだして早期に地盤固めをする方法が、すでに十年まえに開発されている。
この水域の提防を、建設省は昭和三十八年から四十年にかけて暫定工事として築いたのだが、本工事にこのサンドパイル工法をおこなう予定だった。
が、その後、本工事が行われず、十年間、仮堤防のまま放置されていた。
つまり、自然沈下を防ぐ方法があったのに放置されていたため、今度の災害は生じたもので、不可抗力の災害ではなく〈人災〉の性質をもつ災害だったことが、大きく浮び上ってきた。
また、それにつながるが、治水事業の軽視と支流の中小河川の治水の問題を知らされることになった。
月形地方で堤防沈下が放置されたのも、原因をたどってゆくと突きあたるのは治山治水を軽視する国の姿勢で、たとえば昭和五十年度の北海道開発事業費にしても、工業基地開発の道路整備費などは優先されるが、治水関係費はその三分の一ほどの配分でしかない。
そして治水工事費は国が広く薄く多くの河川に分配するので、割高な予算になるサンドパイル工事が、結局十年も見送られることになってきていた。
そうした治水行政の根本の姿勢から、中小河川の改修はなおざりになっている。
八月、九月の水害は、本流堤防の決壊のほかに、支流の氾濫と治水の問題を犬きく浮び上らせたのである。
国のエネルギー収策の転換は、石狩川流域で多くの炭鉱を閉山させたが、それは自然を荒らしたままの廃墟になって残っている。
また、かって豪雨のさい、遊水地の役割をもったところが、住宅地に変ったりして、流域の自然条件は最近十数年の間に変化してきているのであって、流程を一〇〇キロほども縮めた河川改造の整形外科手術を行ったものの、河川工学は〈開発〉の進展が変化させる石狩川水系全体の自然と、新しい緊張関係を自覚することによって、治水の問題を見直さなければならなくなっているといえる。
十三年ぶりの八月、九月の水害は、そうした問題を浮び上らせた。
北海道の近代の文明史を展いたのは、もちろん国の植民開拓の政策で、明治五年の開招使十ヵ年計画から現在の北海道総合開発紅画にいたる、拓殖・開発の企画と投資が動力になって、北海道の産業経済の活動と自然改造が進展してきている。
しかし、裏大雪で、私が日本人は北海道でなにができたかという問いにとらえられた時、石狩川水源地帯のダムと造林技術という自然と科学技術の問題と、単純に未開地だったのではなく文明圈を異にする先住民の社会を包容した北海道の近代化の独自な条件、また上からの近代化に応じただけではない民衆の内発的な文明経験と活動を見直してみたいという、三つの問題を私は考えさせられていた。
それぞれ短い時日ではあったが、流域を歩いた旅は、そうした視点から北海道の文明史というものを見直す旅になった。
先住民の社会と文明との近代化の関係についていうと、「近文保護地の六十三年」で言ったような経過を含んで、近代はその古代的な文明の世界を閉じさせた。
近代と絶ちぎれた形で、アイヌ文化研究が学問の世界で行われる一方で、〈北海道旧土人保護法〉が一種なまぐさい遺体として現存している。
〈全面的にシャモの人は内地の本島に帰ってもらいたい。
北海道島は全部アイヌだけのものにしてほしい、といいたいところだが……〉 |
これは一九七〇年、この法律の問題を扱ったテレビでの一人の老人の声だが、北海道の近代を衝撃しないではいない力が、この問題にはなまなましく呼吸(いき)づいているといえる。
私は上からの拓殖・開発におうじてだけ生きたわけではない。
民衆の生活の現場から生して文明に内から働いた活動を、もっぱら探索することになって、アカデミズムの世界での学者の仕事まではみないできてしまった。
また、科学技術についても、わずかに一九五四年の台風被災後の大雪山地の造林の苦闘にたちいってみるだけにとどまった。
だがわずかにふれることになったが、亜寒帯高寒地造林の経験は、自然の生態系のもつ重い意味を浮び上らせている。
それは私たちが生活環境の多くの様々な汚染と破壊に当面することによって、再認識することになった世界像なのである。
人間も自然の生態系の部分でしかないが、産業社会の自然改造と物質量産のメカニズムになれて、私たちはそのことを見失っていた。
いわゆる〈公害〉の顕著な環境汚染と破壊を経験して、自然の生態系のもつ重い意味を見直すことになったのだ。
大雪山系の樹海を襲ったのは自然の災害で、いわゆる人為の〈公害〉ではなかった。
が、ここでの造林経験―― 一般的な皆伐方式から天然の更新力に依拠する造林へ到達した苦闘は、自然の生態系のもつ重い意味を認識した科学技術と自然との新しいかかわりかたなのである。
拓殖・開発という、北海道の文明史を上から展いた政策は、私たちの産業社会が公害を生みだし、一種の〈壊疽〉を病んでいることを自覚するようになったのが、せいぜいこの十数年のことであることからいって、自然を資源としてしかみることのできない政策だったといっていい。
その考え方のサイクルでは、たとえばかって北海道の代表的産業だった石狩川流域の炭鉱などは、掠奪したまま、廃墟として棄て去られる。
そして、開拓移民にとっての文明史も、寒冷地の酷薄な自然との苦闘によって展かれてきた。
植物学者によると、〈内地〉からきた移民はエゾマツ、トドマツの亜寒帯針葉樹の黒々とした森林に畏怖を感じたらしい(北海道は渡島半島の黒松内低地帯以北が亜寒帯の植物圈だった)。
稲作と広葉樹になじんできた移民は、寒冷地の重苦しい針葉樹林を敵視するように、平地のそれを伐りたおしたという。
そういえば、『カインの末裔』の結びの次の描写は、そういう感覚のおののきを語る描写なのである。
〈椴(とど)松帯が向うに見えた。
総ての樹が裸になった中に、この樹だけは幽鬱(ゆううつ)な暗緑の葉色をあらためなかった。
真直な幹が見渡す限り天を衝いて、怒濤のような風の音を寵めていた。
二人の男女は蟻のように小さくその林に近づいて、やがてその中に呑み込まれてしまった〉 |
自然との緊張関係を核心にもって展かれた文明史は、今はしかし、自ら体内に病む〈壊疽〉(えそ)との緊張関係をもちながら、自然との新しいかかわりを展かなければならないところへきている。
北海道で日本人は何ができたかということも、資源の掠奪のイメージにかわって、何を育てているのかということを問いなおさなければならないところへきているといえる。
top
****************************************
|