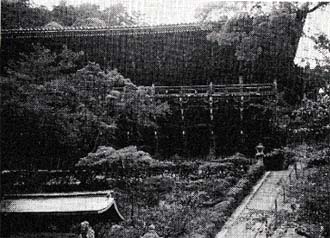|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章
二章 山名持豊(宗全)の前半生
1 持煕と持豊 top
細川勝元は永享二年(一四三〇)の生まれであるが、山名持豊(のちの入道宗全)は応永十一年(一四〇四)生まれで、勝元よりも二十六歳年長であり、この二人は丁度親子ほど年齢が隔たっているから、持豊の活動の方から見てゆくのが順序であろう。
持豊は『但馬村岡山名家譜』によれば、山名時熈の三男(『山名系図』によれば六男)で母は時熈の伯父師義の女(むすめ)であった。
持豊は応永十一年五月二十九日に誕生し、幼名を小次郎といった。
十歳になった応永二十年(一四一三)正月、将軍義持の御前で元服し、将軍の一字を賜わって持豊と名乗った。
応永二十九年(一四二二)持豊十九歳のとき長子教豊が生まれているから、それまでに妻を娶(めと)り、一人前の大人になっていたことがわかる。
しかし持豊は時熈の嫡子(後継ぎ)ではなく、少なくとも兄が二人おり、そのうち長兄の修理大夫(しゅりのだいぶ)満時は早世したと伝えられるが、次兄の刑部少輔(ぎょうぶのしょう)持熈(もちひろ)が健在で、この持熈が嫡子になっていた。
持熈は父時熈の入道した翌年の応永三十一年(一四二四)正月十五日には、山名家を代表して幕府に出仕し、将軍義量に椀飯(おうばん、饗宴)を献げている(花営三代記)。
その上に、第一に父時煕が入道後もなお四ヶ国守護として分国の政務を切り盛りしていただけでなく、幕府の宿老として義教から大いに尊敬され、幕府政治の相談おいてとなっていた。
だから持豊にはまだ表立った活動の余地が与えられておらず、当時の記録にもまだほとんど名が現れてこないのである。
したがって、『但馬村岡山名家譜』に応永三十年(一四二三)四月に時熈が職を辞し、持豊が将軍義持から司職(ししき)に列せられたとあるのは誤りに違いない。
なお「司職」は一般に四職と書くが、この家譜は所司の職というつもりでこう書いたのだろう。
正長元年(一四二八)、前将軍義持が亡くなり、その弟義教が六代将軍となっても、なおしばらく持豊の活動は見られない。
ところが兄持煕は、幕府への出仕を怠ったということで義教の機嫌を損ねた。
永享三年(一四三一)五月、義教は政治顧問の満済准后を通じ、時熙に命じて「持熈の振舞ははなはだよろしくない。
しかし山名入道は宿老だから、将軍が直接持熈を処罰しては入道に気の毒だ。
したがって持熈を元のように出仕させようとも、または遠国に下し置くとも、その処置は山名入道の判断に任せよう。」
と言った。
恐縮した時煕は、結局持熈を廃嫡し、持豊を家督にすることを決めたのである。
こうして持豊は山名宗家の嫡子と決まったが、父時熙は依然として幕政に参画し、六月には、時熙は畠山満家らとともに満済准后を通じて、義教の政治方針があまりに峻厳なことを批判し、より寛大な政治を望むという意見書を提出している。 |

山名宗全画像 江戸時代の版本より
|
翌永四享年(一四三二)九月、義教がその父義満の例にならって富士遊覧を行なうと称し、実は当時義教への敵対意識を燃やして将軍の地位をねらっていた鎌倉公方持氏を威圧するため駿河に赴いたとき、六十六歳の時熙も義教に随行して駿河まで往復しており、なかなか元気旺盛だった。
これよりさき、周防・長門の守護大内氏に内訌が起こり、守護大内持世(応永の乱で滅びた義弘の嫡子)の弟持盛が兄持世と家督を争って永享四年二月挙兵すると、時熙は義教の命令を受けて、山名の分国安芸・石見から援軍を出動させて持世に協力した。
そしてこれに力を得た持世が翌五年四月に弟持盛を攻め亡ぼすと、時熙はすぐさま持盛の代官であった大内(馬場)満世(持盛の甥)の京都の宿所に被官山口遠江守らを派して満世を殺した。
またその七月二十三日には、次に述べる延暦寺衆徒(しゅうと、本来は学問僧の集団だが、しばしば武力を行使した)の嗷訴(ごうそ)に乗じて、近江の坂本に蜂起した土一揆(つちいっき)が京都に侵入したのを、時煕はやはり軍勢を派遣し、大原辻で討ち破って鎮圧した。
このように時煕は老年ながら軍功をあげたが、それには持豊の協力があったものと思われる。
そして、時熈は、土一揆を鎮圧した五日後には、自邸に将軍義教を招いて歓待している。
時熈はかように矍鑠(かくしゃく)として活動していたが、既に六十七歳で、この時代としては余程の老齢なので、右のような軍功・勤功を潮時としていよいよ引退する気になり、同年八月九日に但馬・備後・安芸・伊賀の守護職と多くの所領を持豊に譲り渡すことを義教から承認された。
三十歳という壮年の域に入っていた持豊は、ここに宗家の家督と分国を譲り受け、独り立ちの活動をすることとなったのである。
なお分家の方は、そのころ持豊の弟熈高(時熈の養子か)が因幡守護、氏幸の孫教之が伯耆の守護、氏冬の孫熈貴(ひろたか)が石見の守護を継いでいる。
父から家督を譲られた永享五年、持豊には、早速軍事上の活動をする機会が到来した。
それは延暦寺の衆徒の嗷訴(ごうそ)事件が持ち上っていたからである。
北嶺の衆徒は南都興福寺の衆徒と並んで平安末期以来、その横暴ぶりが有名であるが、南北朝から室町中期にかけてもまだかなり勢力があり、寺領の問題とか僧侶の任免などをめぐってしばしば日吉の神輿を奉じて入洛し、朝廷や幕府を脅かしていた。
この年の六月にも神輿を奉じた叡山の衆徒が山門の寺務の猷秀法印と幕臣赤松満政・飯尾為種が結托して私腹をこやしていると言いたて、十二ヶ条の訴訟を要求して入洛を計った。
幕府は諸国の軍勢を至急京都に召集して神輿の入洛を防がせるとともに、閏七月、衆徒の要求を裁許する旨を発令して、ようやく入洛を思い止まらせた。
ところが山門(比叡山)の衆徒は、この嗷訴に園城寺(おんじょうじ=三井寺)の衆徒を誘ったのに同調しなかったといって、同年十一月園城寺に襲撃をかけ始めた。
山門と寺門(園城寺)は何百年来の犬猿の仲なので、山門衆徒は今回の勝利の余勢をかりて寺門を打倒しようとしたのである。
山徒への譲歩を腹に据えかねていた専制将軍義教は、管領細川持之らの諌めをきかず、二十七日、持豊に命じて山徒を攻撃して寺門を救うように命じ、さらに諸大名に出動を命じた。
持豊は軍勢を督励して叡山を包囲攻撃して山徒を追いまくっだので、彼らは降服を幕府に申し入れた。
義教は衆徒の首謀者円明院兼宗を捕えて禁錮刑にし、十二月十五日持豊以下の幕軍は凱歌をあげて帰京した。
大体衆徒の威力というのは、純粋の武力だけでなく、神罰仏罰を振りかぎして相手を脅迫するところにあったのだから、義教のように信仰心が薄く、幕府の権威回復を自分の使命と信じ込んでいる専制将軍には、とうてい敵対できなかったわけである。
そして義教の命令通りに叡山攻撃をやってのけて衆徒をたちまち降参させた持豊は、義教から大いにその勇猛を認められたのであった。
翌年十月、山徒が再び日吉の神輿を動座させて蜂起したときも、持豊は六角・京極・畠山・細川・赤松らの軍勢とともに坂本を攻撃して山徒を追い散らした。
|

山名持豊願文 出石(いずし)神社
|

出石神社 兵庫県出石町
|
父時熈は、家督といっさいの公務を譲った持豊が、山名宗家の当主にふさわしい果敢な活動をするのを見て安心したせいか、翌々年の永享七年(一四三五)七月四目、六十九歳の生涯を閉じた。
時煕の死を聞いた伏見宮貞成(さだふさ)親王は、その日記に「遺跡を兄弟相諭し、錯乱すべきかと云々」と、持熈・持豊兄弟の相続争いが勃発しそうなのを危ぶんだ。
持豊は父の建立した但馬国黒川荘の大明寺にその遺骨を葬った。
この大明寺は朝来(あさこ)郡の丹波境に近い山奥にあるが、翌永享八年(一四三六)八月に持豊はそれより北の出石(いずし)郡宮内の但馬一の宮出石神社に願文を掲げて決意をかためたことを、片岡秀樹氏が紹介されている(人物往来社歴史研究会「歴史研究」六二号)。
この願文は、まず山名家が数国の守護職を兼ねて栄耀も忠功も抜群であるとしたのち
「ここに持豊、末葉として父祖重代の蹤跡(しょうせき)を継ぎ、親族数輩の首領に備わる。
是れ則ち 神明擁護の然らしむる所なり。いよいよ崇め、ますます敬い奉らざるべからず」
と述べており(神床(かんどこ)文書)、兄持熈の叛乱を予測したとみられる持豊の並々ならない覚悟があらわれている。
この出石神社の傍らの此隅(このすみ)山には、持豊の祖父時義の築いたと伝えられる此隅城があり、このあたりに分国支配の中心となる守護所が置かれていたに違いない。
2 持豊の高野山領押領 top
永享九年(一四三七)七月、持豊は父時煕の三周忌の法要を京都で営んだが、果してその直後に兄持熈が備後で叛乱を起こした。
持熈は心を寄せる与党を集めて備後に侵入し、持豊の守護代の駐屯していた国府城を襲撃した。
持豊は分国の急を聞くと直ちに京都を進発して備後に攻め込み、持熈を攻めてたちまちこれを討ち取り、その首級を幕府に送り届けた。 兄持熈を亡ぼした持豊は、ここに山名一族被官を完全に統制下に入れ、分国内に対する勢力をますます伸ばしていった。
その一つの現れは高野山領備後国大田荘の押領事件である。
がんらいこの時代の守護大名は近世の大名と違って、その分国内を完全に領有していたのではない。
分国の中には幕府から承認された守護の直轄領や守護の管理下に入っている国衙(こくが)領などが存在してはいるが、公家領や寺社領の荘園もまだまだ多く残っていたので、守護大名やその被官たちは、しだいにそれらの荘園に圧力を加えて支配の手をのばしていったが、特に有力な公家・寺社の所領には幕府から守護使不入とか段銭国役免除などの特典が与えられていたから、守護やその被官の国人としても、そう簡単にこれらの荘園を押領してしまうわけにはいかなかった。
そこで案出されたのが、守護請(うけ)といって荘園の管理権を守護大名が請負い、現地には守護大名が代官を派遣して実質上の支配権を接収し、領家である公家や寺社にはあらかじめ契約した一定額の年貢を送り届けるという方法である。 |

高野山の奥の院へ至る参道
|
領家としては管理権を放棄するのはもとより好むところでないが、外部からの武力侵入や荘内の地頭荘官の押領などの際に、いくら幕府の保護命令を受けても、実際に荘園を守ってくれるのは守護大名以外にないのであるから、みすみす押領されるよりは一定の年貢だけでも確保できればという、半ばあきらめの気持から、守護請の申し出に応じるのが普通だった。
高野山領大田荘を守護請にしたのは山名時熙であり、契約を結んだのは応永九年(一四〇二)のことであった。
この大田荘が年貢だけでも千八百石に上る大荘であるところに目をつけた時熙は、幕府を動かして時の管領畠山基国から次の施行状(しぎょうじょう、実施命令)を発令して貰った。
高野領備後国大田庄并(なら)びに桑原地頭職・尾道倉敷以下の事、下地(したじ)に於いては知行を致し、年貢に至りては毎年千石寺納すべきの旨、山名右衛門佐入道常熙(時熙)に仰せられ畢(おわ)んぬ、早く存知すべきの由、仰せ下さるる所也、仍(よ)って執達件(くだん)の如し。
(管領畠山基国)
応永九年七月十九日 沙弥(花押)
(高野山金剛峯寺)
当寺衆徒中 (高野山文書・原和様漢文体) |
時熙は将軍の権威をかさに着てこの分国内の荘園を守護請として実質上接収し、しかも本来千八百石の年貢を千石に値切り倒したのだった。
だから少なくとも八百石の収益が時熙とその代官の手に入る計算だったが、そればかりでなく、時熙はこの毎年千石という契約額さえもその通りに実行しようとしなかった。
持豊か守護を継いでのちも、その状態はひどくこそなれ少しも改まらなかった。
永享十二年(一四四〇)になって、とうとうたまりかねた領家高野山は守護山名持豊を相手どって訴訟を起こし、
「この三十七年間に年貢米の末進(滞納)が積り積って二万八百余石に達しだから、大田荘の守護請を取消して高野山側の直務(じきむ、直接管理)に戻して貰いたい。」
と幕府に訴えた。
平均して年額子石のうち五百六十余石が未進で、納入した方が僅かに四百四十石弱であり、昔の直務の時代から見れば高野山の収入は四分の一に激減してしまった勘定である。
ところが高野山の訴えは少しも成功せず、持豊は大田荘を一向手放さなかったばかりか、かえって契約額自体を八百石に値切ってしまった。
しかも例えば文安二年(一四四五)分の年貢が、翌々年の文安四年三月までにやっと五百八十三石納入されるという状態であり、長禄・寛正年間(一四五七〜六五)になるとますますひどくなって、毎年二、三百石内外しか高野山に納めないのが恒例のようになった。
しかも寛正四年(一四六三)のごときは、高野山に納めるため泉州堺まで運んだ大田荘の年貢米を堺で売った代金の中から、十五貫文余りを持豊が自分の必要経費だといって取上げている。
このようにして持豊は父時熈以来の分国内荘園に対する管理権を強引に推し進め、ほとんど直轄領と同様の状態にして支配権力の基礎を固めていったのである。
3 持豊、侍所所司となる top
持豊は分国の支配権を充実するかたわら、将軍義教の意を迎えて、幕府の内に父時熈に劣らぬ勢力を張るように努めめ、永享十年(一四三八)三月には義教を招待して自邸で猿楽を催し、翌年正月には正四位下右衛門佐に叙任された。
また京都内外の治安維持のために活躍し、永享九年十二月には山名被官人である光台寺の僧が、船津西兵衛というものと組んで伏見不動堂の本尊を盗み出したので、その僧を捕えて寺を放逐した。
翌十年八月には、細川持常・斯波義郷(よしさと)らとともに、越智・箸尾らの籠もる大和多武峯(とうのみね)を攻めて陥れた。
こうして持豊は四職としての家柄にふさわしく、永享十二年(一四四〇)のころ赤松満祐(みつすけ)に代って侍所所司の職に任じられた。
そしてその年九月には、洛中洛外の米屋が春日社の神人(じにん)とか朝廷の四府駕輿丁(しふかよちょう)などという身分を言いたてて幕府の課役を納めようとしないのに対し、侍所所司としての職権によって督促を実施している。
持豊が侍所所司となったころの幕府には、色々と重大な事件が持ち上っており、なかでも大事件は永享十一年(一四三九)に起こった鎌倉公方(くぼう)持氏の叛乱すなわち永享の乱であった。
しかし翌年二月持氏が鎌倉で殺されて事変が幕府側の完勝に終ると、関東平定に自信を強めた義教は一層酷薄な性情を募(つの)らせ、少しでも命令に従わない諸将は悉く除こうとし、諸大名の粛清を実行に移した。
永享十二年三月には赤松満祐の弟義雅の所領を没収し、五月には大和の越智氏追討に出陣中の若狭守護一色義貫(よしつら)と伊勢守護土岐持頼を武田信栄・細川持常らに命じて殺させ、翌嘉吉(かきつ)元年(一四四一)正月には三管領の畠山持国を追放してその弟持永に畠山宗家を継がせ、さらに同年六月には加賀の守護富樫教家の所領を奪ってその弟泰高に与えるというすさまじさであった。 |

足利持氏血書願文 鎌倉市鶴岡八幡宮
|
4 嘉吉の乱 top
ここに至って、かねがね義教から亡ぼされる危険性を感じていた四職の赤松満祐は深刻な恐怖に陥った。
満祐はかつて応永の末年に将軍義持が本国播磨を没収して、寵愛する赤松持貞に与えたため叛乱を起こそうとしたことがあり、その時はたまたま持貞の罪状が露見して処刑されたので、満禰は危機を免れたということがあった。
満祐は義教には大いに優遇され、細川・畠山・山名等とならんで宿老として重要政務にあずかり、侍所所司にも任じられた。
しかし義教はやがて満祐の一族赤松貞村を寵愛し、永享九年(一四三七)二月に至り、満祐の分国のうち備前だけを残して播磨・美作を借り上げて幕府の直轄領にし、この両国を貞村に管理させようとした。
しかし満祐が承知せず、騒動が勃発しそうになると、義教は計画をとりやめ、みずから満祐の邸に出向いて和睦したのであった。
しかし義教の性格から判断すれば、この和睦は、鎌倉府との関係が差し迫っている矢先なので、止むなく満祐と妥協したのに過ぎなかったと思われ、関東平定後の諸大名排除の烈しさ、そしてとくに弟義雅の例から見て、満祐がいよいよ危険の切迫を感じたことは決して単なる杞憂ではなかった筈である。
そこで満祐は嘉吉元年六月二十四日、周知のように義教を自邸に招いて饗宴の最中、満祐の家来どもが突如義教めがけて切りかかり、ここに恐怖政治をしいた六代将軍はあっけない最期を遂げたのである。
居合せた諸将のうち山名熈貴(ひろたか)と京極加賀入道が義教とともに殺され、そのほか走衆(はしりしゅう)遠山・市の二人が討死しただけで、管領細川持之以下の諸大名は命からがら逃げ出してしまった。
伏見宮貞成(さだふさ)親王はその日の日記に、
「御前において腹切る人なし。赤松落行くを追懸けて討つ人なし。末練いうばかりなし。」と慨嘆し、
「所詮赤松討たるべき御企て露顕のあいだ、遮(さえぎ)って討ち申すと云々。
自業自得果して力なき事か。将軍かくのごとき夭死は、古来その例を聞かざる事なり。」と記している。 |
たしかにこの夭死といわれた義教の死は、足利将軍家の権威凋落の第一歩であり、これから応仁の乱へと続いてゆく室町幕府の大きな動揺の発端だったと言える。
義教を殺した満祐は、直ちに一族被官を率いて本国播磨に奔り、挑戦状を管領持之に送るとともに、木ノ山・白幡両城の防禦設備を厳重にし、国境の要所要所にも軍勢を配置して、幕府軍を迎え討つ準備を整えた。
一方、幕府は一時上を下への大混乱に陥ったが、管領細川持之は諸大名と会議して義教の嫡子千也茶丸(義勝)を次の将軍に決めるとともに、満祐追討の手筈をととのえ、七月十一日以来、軍勢を播磨に向かって続々と進発させた。
大手は細川持常・同頼久・同満儷・武田信賢・河野通宣・赤松貞村らが都合八万三千八百余騎といわれる大軍を率いて山陽道を攻め下り、二十五日から合戦が始まった。
搦手(からめて)は山名持豊か侍所の職を辞して主将となり、嫡子教豊、同族教清(義理の嫡孫)政清父子、教之(氏幸の嫡孫)以下、一族被官二万五千余騎といわれる軍勢で、二十八日に但馬口から播磨に攻め寄せた。 |

足利義勝像 京都市等持院
|
5 荒武者持豊 top
大手の軍勢は八月に入ってもはかばかしい進撃をせず、この間に赤松勢は分国美作・備前にも進出して、幕府軍に応じた美作の国人垪和(はが)や備前の国人松田らを追い払った。
その十九日に、細川持常以下はようやく播州塩屋の関を海陸から攻めて焼き払ったが、二十六日蟹坂で赤松勢の主力と戦ってかなりの損害を出した。
このように幕府軍の主力部隊の戦意があがらず、進撃が鈍かったのは主将細川持常が赤松満祐と親しかったからだともいわれるが、持常以下の諸将が義教の死にひと安堵し、満祐の立場にひそかな同情を抱いていたためであろう。
これにひきかえ、搦手の山名勢は大いに意気盛んで、但馬口から猛攻撃を行なって、播磨に進入するとともに、一族教清は美作に攻め込んで八月中旬のうちに美作一国の赤松方をことごとく追い払った。
この間に持豊の率いる本隊は赤松の一族龍門寺、被官上原備後守を討ち取って播州深く進入し、九月五日満祐の陣取る書写山(しょしゃざん)の坂本に達し、堀城を攻め落した。
山名勢の猛攻に力を得た大手の細川勢・武田勢なども、ようやく本腰を入れて攻撃を行なったので、満祐は全軍をまとめて木ノ山城に楯籠り、必死の防戦を試みた。
幕府軍は城を取り囲んで攻め立てたが、なかでも持豊以下山名勢の攻撃は一番目立っていた。
『嘉吉記』はその戦況を次のように描写する。 |
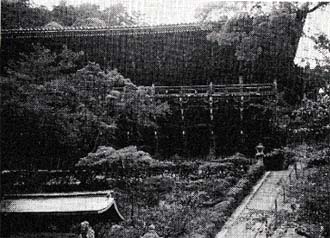
書写山円教寺
|
金吾(持豊)人ニ勝テ大功ヲタテント願フ人ナリ。其心操、驪龍領下(れいりゅうがんか)ノ玉ヲモ奪ハンホドノ機分ナレバ、ナジカハ少モ猶予スペキ。
大山口ヨリ国中へ切テ入(いり)、城ノムカヒ西福寺ノ上ニ、ハシサキ(端崎)河ヲ隔(へだて)テ陣ヲ取、修理大夫(教清)・相模守(教之)、因幡・伯耆勢ヲ卒シ搦手ヘマハリケレバ、金吾河ヲ渡シ城山ノ麓ニ陣ヲ取ル。
十重廿重ニ取巻キ、日夜息ヲモ不継(つがず)攻入、壁櫓引破リ城中アラハニ見透シ、其上兵粮モ尽ケレバ、九月十日大膳太夫満祐入道性具自害シヌ。
墟中兵、人ニ知ラルルホドノ者ハ腹ヲ切ル。其数ヲ不知(しらず)。
子息彦次郎教康イツノマニカ逐電シケン、アト知(しれ)ズニ成(なり)ケリ。
頸共京都へ上(のぼ)セ、軍(いくさ)ノ様(さま)ヲ申(もうし)ケリ。 |
この軍記に、「大手軍兵共ハ播磨路ヘ一足モ踏入レズ、勿論敵ノ旗ヲ不見(みず)帰陣シケリ。」とあるのは誇張に過ぎるが、それにしても持豊以下山名勢の働きが抜群で、ほとんど戦功を独り占めにした観があったことは間違いない。
満祐が白刃した直後、焼け落ちる城中に走り入って満祐の首を取り出したのは、山名の被官小鴨某であると伝えられ、但馬の住人出石(いずし)小次郎景則という者たったともいう。
持豊がこのように勇戦して大功を立てたのはなぜだろうか。
確かに『嘉吉記』にもいうように、彼が勇猛な荒武者であり、誰よりもすぐれた軍功をあげようと張り切ったからに違いない。 しかし彼には特に赤松勢との戦闘に勇み立つ理由があった。
それは、山名の分国但馬・因幡・伯耆は赤松の分国播磨・美作と境を接している上、美作は明徳の乱で赤松氏のものとなったもとの山名の分国だった。
このように勢力圏が噛み合っているせいもあり、また山名・赤松がいずれも四職の家柄として張り合っているためもあって、持豊は諸大名の中でも一番満祐と仲が悪かった。
『老人雑話』という逸話集には、持豊が満祐とならんで義教に出仕していたとき、ある日庭前に枯れた松のあるのを見た持豊が、
「あの赤松を断って捨て申そう」と義教の前で言い放った。
ところが満祐は歌学に達し、口の達者な男だったから、「山なをか」と言い返した。山名と庭の築山を掛けたのである。
これから二人の仲はいよいよ悪くなったとある。
この話は当てにならないとしても、二人がひどく対立していたことは事実で、永享九年(一四三七)十二月、持豊が満祐と争いを起こそうとし、義教が二人をなだめてやっと和睦させたほどだった。
しかも前述のように一族熈貴が今度義教とともに討たれたから、山名一族の満祐に対する恨みはますます大きくなったのであった。
山名一族が嘉吉の乱に殊勲をあらわした裏には、このような因縁があったのである。
6 山名氏の繁栄 top
満祐の首級は山名教清の嫡子政清が京都に送り届け、幕府では首実検の上、政清に太刀・腹巻・馬を、被官小鴨には太刀と刀を褒美として与えた。
閏九月に諸将は京都に凱旋し、幕府で赤松誅伐の論功行賞が行なわれた。
『但馬村岡山名家譜』によると、なかでも持豊は他家を交えず一族等を引具して将軍家の讎敵(しゅうてき)を亡ぼした功が莫大であるとして、翌年正月従三位に叙し、右衛門佐に任じ、白傘袋・毛氈鞍覆(もうせんのくらおおい)ならびに屋形号を許され、播磨・石見の両国を加賜され、修理大夫教清には美作、相模守教之には備前を賜わったとある。
事実、これ以来彼らのそれぞれの国の守護としての活動が文書・記録に見出され、これらの分国加賜が証明される。
このうち石見はこれまでも山名熈貴の分国であったが、他の三国は赤松の分国であった。
そこで結局山名一族は、今までの但馬・因幡・伯耆・石見・備後・安芸・伊賀に赤松氏の分国播磨・備前・美作をそっくり加えて合計十ヶ国、そのうち九ヶ国までが山陰・山陽両道にあるという、実に尨大な領域を併有し、持豊自身がこのうち七ヶ国までを独り占めして、かっての六分一家衆といわれた時代にまさるとも劣らない大変な勢威を振るうことになった。
この嘉吉の乱の大功は持豊三十八歳というまさに働き盛りのときだった。
その後、三、四年のうちに起こった赤松残党の蜂起に対しても、持豊は一手に鎮圧の功を収めた。
すなわち文安元年(一四四四)十月、赤松氏の一族播磨守満政というものが京都から本国に出奔し、赤松の牢人どもにかつがれて叛乱を起こしたが、持豊はみずから一族被官を率いて討伐に発向し、翌年三月摂津有馬郡で満政以下三百七十人ばかりを討ち取り、但馬国を経て引きあげた。
山名家再興の業をなしとげ、赤松氏鎮定の功を誇った持豊は、官途もやがて右衛門督に進み、勢いにまかせて傍若無人の行動に出て、人々に疎(うと)まれるようになった。
既に嘉吉元年(一四四一)七月赤松満祐追討のため軍勢が続々京都を出発し始めたころ、侍所所司の持豊は
「斯波氏の被官朝倉は赤松の被官と縁つづきだから、所領を没収する。」と言い出し、朝倉は
「もとは縁故があったが今は無関係だ」と反論し、騷動か起こりそうになったが、仲裁するものがあってようやく収まった。
また山名の家来どもは京都の混乱に乗じて、管領細川持之の召使う人夫の苅った草をむりやり銭三文で押買(おしかい=おどかして不当に安く買うこと)したり、洛中の土倉(質屋)に乱入して質草を強奪したり、目にあまる乱暴狼藉を働くので、持之は持豊に何回も使いを送って取締りを要求したが、持豊は部下の不法行為を放っておいて、一向禁止しない。
とうとう持之は山名の邸に攻め寄せる支度を始めたところ、やっと持豊は、不法な被官を処刑するといって詫びを入れたので、事なきを得た。
この有様を聞き伝えた公卿万里小路(までのこうじ)時房は、「近日の無道濫吹(らんすい)は、ただ山名にあるなり。」と評言している。
赤松氏を倒す前からこの有様だから、ましてその後の傍若無人ぶりは想像されよう。
管領持之が諸国の公家領・寺社領のうち武士の押領したものを返還させようとして国々の守護にその命を伝えさせたところ、持豊だけが命令を無視して分国に伝えなかったということも一例である。
嘉吉三年(一四四三)九月、南朝の子孫尊秀王がひそかに公卿日野有光と結び、与党を率い宮中に闖入して神璽(しんじ)宝剣を奪い、延暦寺の根本中堂にたてこもるという事件が起こったとき、伏見宮貞成(さだふさ)親王は、山名と細川も南朝の余党に同心しているそうだという噂を聞き、
「山名の野心、日ごろ風聞の間存(ぞん)の内なり。」といって、これは考えうることだと見ている。
実際は山名・細川がこの事件の一味というのは全くのデマであったが、それにしても常々持豊は大変な野心家という評判を立てられていたことがわかる。
さて持豊はこうした世間の評判をよそに、宝徳二年(一四五〇)四十七歳のとき、京都の南禅寺に塔頭(たっちゅう)真乗院を建立して香林和尚を開山とし、山城国深草郷を寄付して武運長久・子孫繁昌を祈らせ、権威づけのため将軍義政の執奏を経て、後花園天皇の綸旨をたまわってこの塔頭を勅願所とし、いかにも権勢家らしいところを見せた。
こうして禅道帰依をよそおった持豊は、同年嫡子教豊に家督を譲り、剃髪して宗峯と称した。
やがて法号を宗全と改める。ここに嘉吉の乱の際の活躍をピークとした持豊の前半生にはひと区切りが打たれ、続いて将軍義政の宿老山名金吾入道宗全としての後半生が始まるのである。
なお金吾とは衛門府の唐名であり、ここでは前右衛門督の宗全を意味する。 |

南禅寺三門
|
しかし宗全の後半生は、細川勝元との関係を主軸として展開されるのであり、私達はここにいよいよ室町幕府をめぐる歴史の舞台に勝元を登場させて、この二人がどのような事件をめぐって虚々実々のかけひきを演じるかを観察しよう。
top
**************************************** |