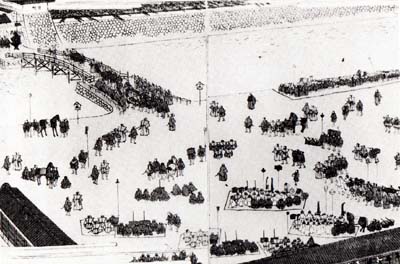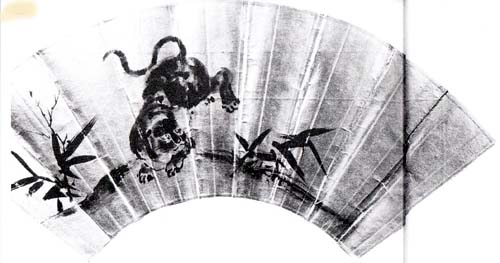|
****************************************
Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 図解コーナー
一 戦いのない時代のはじまり
幼い家綱が四代将軍になってから三ヵ月後、浪人たちを中心とする由比正雪(ゆいしょうせつ)の乱が発覚した。
もはや戦いのない時代となる、はたらき場所のない浪人たちが不満を高めていたのだ!
1 おさない将軍 top
江戸の町が初夏の風につつまれていた一六五一年(慶安四年)四月二十日、名君とあおがれていた三代将軍徳川家光が、四十八才で病死した。
そのことをしった江戸城大奥の女中たちは、大声をあげて泣き悲しみ、かけつけた老中松平信綱(のぶつな)にきつくしかられた。
「上さま(将軍家光)が亡くなられたことを秘密にしているのに、そう声高に泣いては外へもれてしまうではないか」
しかし江戸城中には、すでに数日前から家光の病状を心配した大名や旗本たちが集っていたので、家光の死を秘密のままにしておくことはできなかった。
彼らはその日の夜、正式に家光の死をしらされ、不安そうに顔をみあわせた。
家光の祖父家康は子の秀忠に、秀忠もまた子の家光に将軍職をゆずったのち、十年前後新将軍の後見
* (うしろだて)をしてからこの世を去った。
* 後見 政治をとる能力にかけた者や、年の若い者が将軍になったとき、政治の相談にのったり助言をあたえたりして、将軍を補佐する役め。
それにたいし、家光はまだ将軍の地位にあるうちに亡くなったのである。 しかも、世子(せし=跡継)の家綱は、やっと十一才になったばかりの少年であった。 |

徳川家光像 二代将軍秀忠の次男。三代将軍。
日光山輪王寺蔵
|
いずれも江戸幕府ができて以来、はじめてのことであり、だからこそ大名や旗本たちも、『なにか悪いことでもおこるのではないか』と、おさない将軍の誕生に不安の念をいだいたのである。
だが、その不安は、結局とりこし苦労におわった。
生前の家光に仕えていた重臣には、前に述べた松平信綱のほか、同じく老中の酒井忠勝(さかいただかつ)・阿部忠秋(あべただあき)らがいる。
それに家光の母ちがいの弟で、会津藩主となっていた保科正之(ほしなまさゆき)も、家光のよい協力者であった。
これらの人々が、
「家綱をたのむぞ、予(よ)にたいしてと同様、家綱にもかげひなたなく奉公いたせよ」 という家光の遺言を忠実に守り、かたく団結しておさない家綱を助けたからである。
また、家光の亡くたった直後、譜代大名(ふだいだいみょう=関ヶ原の戦い以前から徳川家に仕えていた大名)筆頭の井伊直政(いいなおまさ)が、もとめられもしないのにすすんで新将軍に忠誠をちかう誓紙(ちかいの書状)をさしだしたことも、うき足だった人々の心をしずめるのに役だった。
これがきっかけとなって、将軍の代がかわるごとに大名たちが誓紙をさしだすというならわしがさだまった。
新しい第四代将軍家綱は、一六四一年(寛永十八年)八月、江戸城中にうまれた。 母は側室お楽の方だが、家光の長男である。 |

江戸日本橋のにぎわい 日本橋は、1604年に諸街道の起点となった。
「江戸図屏風」より。国立歴史民俗博物館蔵
|
家綱は、体はあまり丈夫ではなかったようだが、大変気持ちのやさしい少年であった。
たとえば、父家光がまだ健在だったころの話である。家綱は家来から島流しの罪人のことをきき、
「生命を助けて流罪とするのであれば、どうして食べ物をあたえてやらないのか」
と、罪人たちの身のうえを心配した。
そのことを聞き伝えた家光は、
「なるほど、もっともなことじゃ。いわれてみれば、そのとおりだ」
と、家綱の慈悲心とかしこさに手をうってよろこび、さっそくかかりの役人に命じて流罪人に食料をあたえるようとりはからったという。 |

初音(はつね)の調度、黒棚飾
将軍家の娘が使用した、身のまわりのものをいれる豪華な家具。
徳川黎明会蔵
|
|

柳沢家で使用していた椀と膳
将軍綱吉の側近であった吉保の勢威がうかがえる。
恵林寺蔵
|
2 殉死(じゅんし)の禁止
top
武士の世界には古くから、殉死という習慣があった。
殉死とは仕えている主君が亡くなったとき、家来もまた自発的に切腹して主君のあとをおうことで、江戸初期はとりわけ殉死の慣習がさかんであった。
殉死流行のきっかけとなったのは、一六〇七年(慶長十二年)に徳川家康の第四子松平忠吉が亡くなったとき、四人の家来があいついで切腹したことだったといわれる。
それ以来、殉死は美しいものとされ、大名や将軍が亡くなるごとに何人かの恂死者が出て、世間から褒めたたえられた。
それについては家光死去のときも例外ではなく、老中の堀田正盛、阿部重次、それに御側出頭(おそばしゅっとう=将軍のそばに仕える人の第一人者)の内田正信らが追腹(おいばら=あとをおって切腹する)をきっている。
ところが、松平伊見守信綱 * は、家光にあつくもちいられていたのに、殉死しようとはしなかった。
* 松平伊豆守信綱 9才の時まだ赤ん坊だった家光に仕えて以来、家光の信頼が厚かった。 1638年には島原の乱を平定するなど、かずかずの手柄もたてた。
そのため、信綱も当然殉死するものとかんがえていた人たちは、信綱を卑怯者だといってわらいものにし、町じゅうにはつぎのような落首(批判や、からかいの意味をこめた歌)がはりだされた。
仕置(しおき)だてせずとも御代(みよ)はまつ(松)平
爰(ここ)にいず(伊豆)とも死出の供せよ |

徳川家綱像 江戸幕府四代将軍
11才で将軍になり、
父家光の重臣たちが補佐した。
|
松平伊豆守さん、あなたがいなくても世はちゃんと治まっているから、未練たらしく生きてないで、さっさと家光公に殉死しなさいよ、というわけである。
しかし、もちろん、信綱は死ぬのがこわくて家光のあとをおわなかったのではなかった。
信綱は合理的な殉死否定の考えのもちぬしであり、こう考えていたのだ。
「殉死がほめられるのは、『忠臣二君に仕えず』*
という武士道の美徳にあっているとみられるからである。
* 忠良二君に仕えず むかし、中国の燕という国が斉の国を破ったとき、燕王が斉の王蠋(おうしょく)というかしこい人を召しかかえようとしたが、王蠋は「忠臣二君に仕えず」といってことわった。
だが『二君に仕えず』とは、他姓の君(他の一族の主君)に仕えてはならないということであり、先君(家光)の幼君(家綱)に仕えることとは全く意味がちがう。
もし、家来がみな、自分一人の名誉をおもんじて殉死したなら、幼君のお世話をするつとめはどうなるのか。
先君の恩にむくいるには、幼君をもりたてることが一番の大事であり、それこそまことの忠義というものである」
信綱のこの考えは、心やさしく情け深い政治をこのむ家綱の気持ちともぴったり一致するものだった。
そこで、家綱は家光の死から十三年たち、殉死者たちへのなつかしさがうすれかかった一六六三年(寛文三年)五月、信綱らとはかって、つぎのような殉死禁止令をだした。。
「以前から殉死は無意味な習慣だといってきたが、法令をださなかったので、近頃も殉死するものが多い。
主君である者は、殉死がよくないことであることを、よくよく家来に説いてきかせよ。
もしこれから大名家などで、殉死者をだした場合は、死んだ主君の落度(罪)とし、跡目をついだ新しい主君の責任も追及することにする」
そして家綱と幕閣(ばっかく)は、それから五年後の一六六八年(寛文八年)、宇都宮藩(栃木県)一二万石の奥平(おくだいら)家に殉死者が出たことをしると、奥平家が家康の血をひく名門
* であるにもかかわらず、国替えのうえ減封(げんぷう)というきびしい処罰をくわえた。
* 家康の血をひく名門 戦国時代、奥平信昌が甲斐の武田氏と戦って手柄をたてたので、そのほうびに家康の娘を妻としてもらいうけた。
そのため、大名や旗本たちはすっかりおどろき、これをさかいとして恂死の慣習は武家社会から消えることになった。
3 由比正雪(ゆいしょうせつ)の乱
top
家綱政権ははじめにもふれたように、家光に仕えた重臣たちが家綱を助け、家光時代の政策をそのまま受継ぐかたちではじまった。
家光から家綱への代替わりも無事にすんだが、かといってすべてが順調にいったわけではない。
前の時代からの重臣にたいする批判の声は、はやい時期から一部にあった。
家光が亡くなってまのない一六五一年(慶安四年)七月、刈屋藩(かりやはん=愛知県)二万石の藩主松平定政(さだまさ)が突然上野寛永寺(かんえいじ)で出家し、江戸市中を托鉢(たくはつ)してまわるという事件がおこった。
定政はその直前、幕府に意見書を提出し、こう主張している。
「世のなかは太平(たいへい)のようにみえるが、まことは上下ともに困りはてている。
せめてのことに自分の領地をさしだすから、貧乏な旗本たちを救う資金にしてほしい」
幕府は、この事件の扱いに頭をいため、結局「狂気がさせたこと」であるとして、定政の身柄を兄の松山(愛媛県)藩主定行(さだゆき)に預けた。
大名が頭をまるめて托鉢に出るとは、いっけん奇妙な事件だが、実をいうと定政の真意は、身をもって幕府の重臣政治を批判することにあったのである。
定政のにわか出家から半月とたたない七月二十三日、今度は由比正雪の陰謀(たくらみ)が発覚した。
この陰謀もまた、幕府にたいする批判が原因となったものだった。正雪はいっている。
「私には、上さま(家綱)にはむかうつもりはすこしもない。
ただ、酒井忠勝ら重臣の政治のやりかたでは、人々の生活は苦しくなるばかりだと判断したので、政治のやりかたを正すために兵をあげようとしたのである」
正雪は、駿河の国(静岡県)出身の軍学者であった。
その計画は、同志の丸橋忠弥(まるはしちゅうや)らが風のはげしい夜を選んで江戸市中に放火し、小石川(こいしかわ)の火薬庫を爆破させるとともに、江戸城におしいって将軍家綱を人質にする。
一方、正雪じしんは駿府にいて忠弥らの決起をまち、ついで久能山(くのうざん=静岡市)を占領して諸国の浪人たちに協力をよびかける、というものだった。
だが、由比正雪の挙兵計画は、江戸の同志のなかから裏切者が出たため、結局失敗におわった。
しかし、正雪の乱はけっして偶然におこったものではなく、その背景には、正雪が協力を期待したように、関ヶ原の戦い以来四〇万人といわれる浪人たちの不満があった。
主君から俸給(ぼうきゅう)をもらうあてのない失業武士の浪人たちは、その日のくらしにも困るありさまで、正雪の乱の翌承応元年(一六五二年)にも、「承応事件」
* (じょうおうじけん)とよばれる浪人たちの反乱計画がもちあがっている。
おびただしい浪人 たち ** をこのまま苦しい生活のなかにほうっておいては、いつまた第二、第三の由比正雪が現れるか、わかったものではない。
* 承応(じょうおう)の反乱計画 別木庄左衛門、林戸右衛門、三宅平六らの浪人グループが、江戸の各所に放
火レその混乱のなかで芝の増上寺にある金銀をうばう計画をたてた。
** おびただしい浪人たち ある調べでは、1600年の関ヶ原の戦いから、由比正雪の事件がおこるまでの50年間に約40万人、つまり毎年平均8000人の武士が浪人になったという。
(注=明治維新では藩がなくなったので、これ以上の厖大な浪人が一時にでた。そのため発足当初の明治政府は混乱し、明治10年には維新の3傑もすべて姿を消した。)
|

役者絵にえがかれた由比正雪 正雪は浪人たちをあつめて、幕府をたおす計画をたてたが、同志のうらぎりにあい失敗におわった。

由井正雪の墓 駿府(静岡県)の宿屋で自殺。静岡市菩提樹院
|
そこで、幕府は浪人対策に取組まなくてはならなくなり、何度も会議を開いてこの問題を相談した。
「いっそのこと、浪人たちを江戸から追払ってしまえばどうか」
「いや、それでは根本的な解決とはならない。浪人をへらす方法を考えるべきだろう」
会議ではいくつかの意見が出たが、最後にきめられたのは、浪人べらしの工夫をするという意見だった。
幕府はそこで、浪人の発生原因となる大名のとりつぶしをできるだけすくなくし、また浪人たちに就職の世話をしてやることを心がけることにした。
家綱の仁政(じんせい=情けぶかい政治)ごのみは、ここでも発揮されたわけである。
4 明暦(めいれき)の大火
top
明暦三年(一六五七年)一月十八日、――この日、江戸の町には名物の西北の風がはげしくふきあれていた。
こんな日、江戸っ子たちは火の扱い *
に細心の注意をはらい、煮たきもできるだけつつしむことになっていた。
* 火の扱い 日本の家は木と紙とでできているからもえやすい。
また江戸時代は、消火のための水も不充分で、消防用具もととのっていなかったから、火事にはとくに注意した。
それなのにどうしたわけか、午後二時ごろになって、本郷五丁目裏の本妙寺から火の手があがった。
折からの強風にくわえ、去年からの日照り続きで空気がカラカラに乾いていたから、さあ大変である。
火はたちまち風下にもえうつり、本郷の台地をひとなめにして、下町にも燃えひろがった。
火のいきおいは、夜にはいってだいぶおとろえ、鎮火するかとみえたけれども、翌十九日の朝になって、小石川伝通院前から再び出火した。 |

明暦の大火 江戸本郷の本妙寺からあがった火は、
強風にあおられて下町方面にもえひろがった。
|
ついで、麹町(こうじまち)の方角からも焔がふきあげ、前日どうにか難をまぬがれた神田一帯から麹町界隈も一面の焼野原となった。
「振袖火事」 * ともよばれるこの大火によって、江戸の町がこうむった被害は、じつに巨大であった。
* 振袖火事 片思いの恋で死んだ女性がきていた振袖を、古着屋で買った娘たちが、あいついで死んだ。
この不吉な振袖を本妙寺でやいたところ、火の粉がとんで火事になったという。
やけた町数は四〇〇町、面積にして江戸市中の六〇パーセントにおよび、大名屋敷五〇〇あまり、旗本の屋敷七七〇あまり、神社仏閣およそ三五〇がもえた。
死者は、およそ一〇万七〇〇〇名にのぼったといい、大火の翌日、皮肉にも大雪が降ったため、焼け出された人々のなかには凍死する者もあった。
火はさらに、市中ばかりでなく、江戸城内にも侵入し、まず五層の大天守にとりついたかとおもうと、みるまに本丸、二の丸をなめつくした。
本丸は将軍のいるところであり、このとき、家綱は輿(こし)にのっていそぎ西の丸に避難した。
だが、そのうちに火は西の丸にも燃えうつりそうになり、つきしたがってきた酒井忠勝や松平信綱が口々に江戸城からの避難をすすめた。
「この火事さわぎにまぎれて、由比正雪のように幕府をたおそうとする者が現れるかもしれません。
ここはひとまず、私の下屋敷(郊外などにある別邸)におうつりなさいませ」
「酒井どのの下屋敷よりも、上野の寛永寺へ避難されるのがよいとおもわれますが――」
しかし、保科正之(ほしなまさゆき)や阿部忠秋(あべただあき)は、彼らの意見に反対をとなえた。
「火をさけるだけなら、城中のほうが広々として安全でございます。
また、よくない者どもがいるというのなら、いっそう城外に出ることは危険でございましょう」
家綱は、そのやりとりをきいていたが、
「中将(正之)と豊後守(忠秋)の申すとおりだ」
といって、ついにそのまま城内にとどまった。
その翌日、家綱は着の身着のままで逃れてきた者たちを救済するため、さっそく粥(かゆ)の炊き出しを行わせた。
ついで旗本たちにたいしても、禄高におうじて見舞いの金銀をあたえた。
さらにまた、松平信綱らに命じて、焼野原となった江戸の再建計画
* を検討させた。
* 都市再建計画 江戸城の周辺をあき地にするため、大蔵屋敷をうつしたり、寺や神社を町の周辺部に移転させたり、市民の家をこわして道幅をひろげ、松並木を植えたりした。 江戸の町は、この再建計画によって幕末(江戸幕府の末期)までつづく近世都市にうまれかわるが、焼け落ちた江戸城の天守閣は、防火上の見地からとうとう再建されなかった。 |

保科正之像 狩野探幽画。
三代将軍家光の母ちがいの弟。
将軍家綱の補佐役として、幕府政治に活躍した。土津(はじつ)神社蔵
|
5 下馬(げば)将軍まかりとおる
top
明暦の大火がおこったのと同じ年の七月四日、家綱は大目付(おおめつけ=老中に直属して大名の監視にあたる)を江戸城に召し、つぎのように命じた。
「予はこれまで、そなたたちから直接、物事をきくことはなかった。
だが、これからは、殿中にかぎらず、そのほかの出来事でも、かわったことがあったなら、じきじき予に申し出よ」
十一才で将軍の座についた家綱も、すでに十七才となっていた。
もう、おさない将軍ではない。家綱はそのことを自覚し、今後は自分がみずから政治をみると、一人だちを宣言したのであった。
そして、その六日後、家綱は伏見宮貞清親王の娘顕子(あきこ)と、江戸城西の丸において結婚の式をあげた。
それから五年後に幕閣(幕府の首脳)の人事異動があり、久世広之(くぜひろゆき)、土屋数直(つちやかずなお)
* が若年寄(老中のつぎにおもい役職。旗本の監視にあたる)に任命された。
* 久世広之(くぜひろゆき)、土屋数直(つちやかずなお) 久世は下総(しもふさ=茨城県)関宿藩主、土屋は常陸(ひたち=茨城県)土浦藩主の両人ともに誠実で聡明のきこえがたかかったが、性格的におとなしいのが欠点だった。
両人はともに家綱の側衆(将軍のとなりの部屋で仕える人)であり、彼らをもちいたのは、家綱が自立体制を強めるために行った人事だった。
なお、江戸幕府の特色である、老中、若年寄を中心とする仕組が確立したのは、このときである。
だが、家綱の自立への道は、おもいのほかけわしかった。
第一、幕府政治のありかたか父家光の代とはかわってきており、重臣たちの権限が強まったのにたいして、将軍が独裁的権力をふるえる余地は、大幅にせばまっていた。
重臣たちが決定したことを、将軍の名によって命令を出すという仕組が、できあがっていたのである。
それに、松平信綱・酒井忠勝ら前の代からの重臣があいついで亡くなったあと、酒井忠清(さかいただきよ)が幕閣の実力者にのしあがったことも、家綱の自立にとって大きな妨げとなった。
忠清は、上野(こうずけ=群馬県)前橋藩一五万石の大名である。
遠い先祖が将軍家と同じ * という名門だったので、一六五三年(承応二年)三十才で老中首座(第一人者)にすすみ、一六六六年(寛文六年)には大老(老中の上の役職)となって名実ともに幕閣のトップの座をしめた。
* 先祖が将軍家と同じ 酒井家の初代広親は、徳川蒋軍家の祖先親氏の子で、広親は母親の姓をとって酒井と名のった。広親は親氏に仕え、その後、酒井家は代だい徳川家に仕えてきた。
また忠清の屋敷は、江戸城大手門(正門)の外の下馬札(げばふだ=そこで馬をおりるきまりをしるした立札)のちかくにあったため、その権勢の大きさへのおどろきもこめ、人々から下馬(げば)将軍とよばれた。
ただし、世間の評判はあまりよくなく、大名のなかにも岡山藩主池田光政のように、忠清にたいして痛烈な批判をくわえた人物もいた。
忠清が亡くなったとき、江戸っ子は、 |
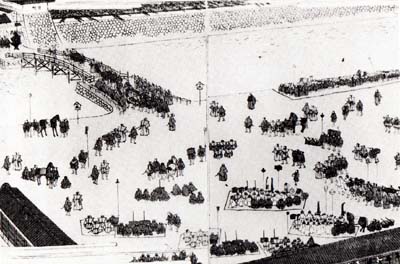
下馬札(げばふだ)ちかくの図
酒井忠清の屋敷は絵の下馬札ちかくにあったので、下馬将軍とよばれた
|
| 大著山(たいしゃざん)婬食寺(いんしょくじ)開基(かいき)文盲和尚 |
ぜいたくで、女性や食べ物にうるさく、教養のない者 |
というなんとも皮肉たっぷりの法名(ほうみょう)を勝手につけたが、このことにも忠清の不人気ぶりがわかる。
家綱は、この下馬将軍に頭をおさえられ、結局、本当の自立をはたすことができなかった。
忠清は、家綱に決定をあおぐとき、
「このことは、いかが取り計らいましょう?」 ではなく、
「このことは、このように取り計らうのがよろしいのでは――」 と、はじめから自分の意見を押付けてくる。
それにたいして、家綱は、
「さようにせい (そのようにしろ)」
と答えるほかになく、いつも同じ答えばかりするので、しまいには、“さようせいさま”と陰口をたたかれる始末たった。
6 家綱から綱吉へ top
一六八〇年(延宝八年)五月、家綱は四十才で病死した。
その生涯 *
は幼くして将軍の位につき、三十年間も人々にあおがれつづけたけれども、体が弱くて病気がちだったし、将軍らしい権力もふるえなかったから、あまり満ち足りたものだったとはいえないであろう。
* その生涯 11才で将軍の位についた家綱は、うまれたときから将軍になることがきまっていた。政治的な力にかけていたが、絵やおどり、音楽をこのむ風流な将軍であった。
それに、将軍の座を自分の子につたえることができなかったのも、家綱としては心残りだったにちがいない。
家綱は正夫人の顕子(あきこ)のほかに、お島の方、お振の方、お満流(まる)の方という三人の側室をおいたが、病弱のためか一人の実子ももうけることができなかったのだ。
一六七八年(延宝六年)、お満流の方がいちど身ごもったことがあり、家綱を大喜びさせたが、それも七ヵ月めに流産してしまい、一時の喜びにおわった。
一方、家綱が実子を残さずに亡くなったことは、幕府にとっても大きな問題であった。
徳川将軍はこれまで、家康→秀忠→家光→家綱と、すべて父から子へというかたちで受継がてきた。
将軍の跡継息子以外から、つぎの将軍をさがすということは、江戸幕府にとって、これがはじめてのことだったのである。
では、だれを五代将軍に選ぶべきなのか。
「ここはやはり、家綱公の弟君が最適任でありましょう」
「とすると、綱吉さまということになりますな。
名君家光(いえみつ)公のお子さまではあるし、お血筋からしても文句のつけようがございませんな」
重臣たちは、家綱が危篤におちいったころから、つぎの新将軍選びをはじめていた。
このとき、彼らがまっさきにおもいうかべたのは、家綱の兄弟であった。
つまり、三代家光の男の実子たちであるが、その実子は家綱を別にすると、次男綱重以下亀松・綱吉・鶴松と、計四人をかぞえる。
だが、亀松・鶴松は早死にし、綱重もまた一六七八年(延宝六年)に亡くなっていたから、家綱病死の時点で生き残っていたのは、四男の綱吉ただ一人であった。
綱告は幼名を徳松といい、産みの母は京都の町娘の出身で家光の側室とされたお玉の方
* (桂昌院=けいしょういん)である。
* お玉の方 京都の八百屋仁右衛門の娘。つとめさきの鷹司(たかつかさ)氏の娘が家光に嫁いりしたとき、ともに江戸城にはいったが、家光にみそめられ、その側室となった。
当時、綱吉は上野(こおづけ=群馬県)館林藩一五万石を支配し、館林(たてばやし)宰相とよばれていたが、血筋をおもんじるかぎり、だれも文句のつけようのない第一候補といえた。
ところが、おもわぬところから反対意見がおこった。
反対をとなえたのは、下馬将軍の酒井忠清である。
「かつて鎌倉幕府では、三代将軍源実朝で源氏の流れがたえると、京都の摂関家(藤原家)、宮家(天皇家)から新将軍をおむかえになった。
その先例 * にならい、このたびは京都より有栖川宮(ありすがわみや)幸仁(さきひと)親王においでいただき、新将軍になっていただくのが一番よい方法と考える」 |
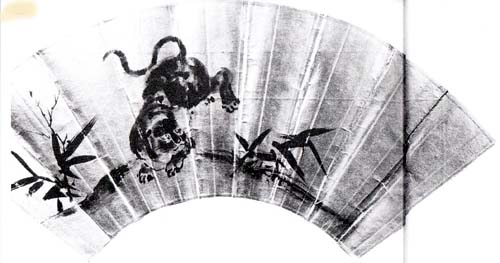
将軍綱吉のえがいたトラの絵
綱吉は上野(群馬県)館林藩主から兄家綱の養子となり、五代将軍の位についた。
|
* その先例 鎌倉幕府では、京都の宮家や藤原家から6人の将軍をむかえている。いずれも幼いうちに将軍となり、成人してからも政治的な力のない、ただ名だけの将軍だった。
忠清は、そう主張したのである。
権勢ならびない下馬将軍の主張だけに、いちじ重臣たちはそうすることにきめかかった。
しかし、老中堀田正俊が一人、忠清の主張にまっこうからかみついた。
「徳川将軍家の血統はたえてはおりません。
ふさわしい公達(きんだち=綱吉のこと)がちゃんとおられるではありませんか」
正俊の言い分は、筋がとおっている。
そのため、忠清も横から意見をおしつけることはできず、家綱の最期の枕元で、綱吉を五代将軍にたてることが正式に決定された。
それからまもなく、忠清は大老を辞めさせられてしまった。
top
****************************************
|